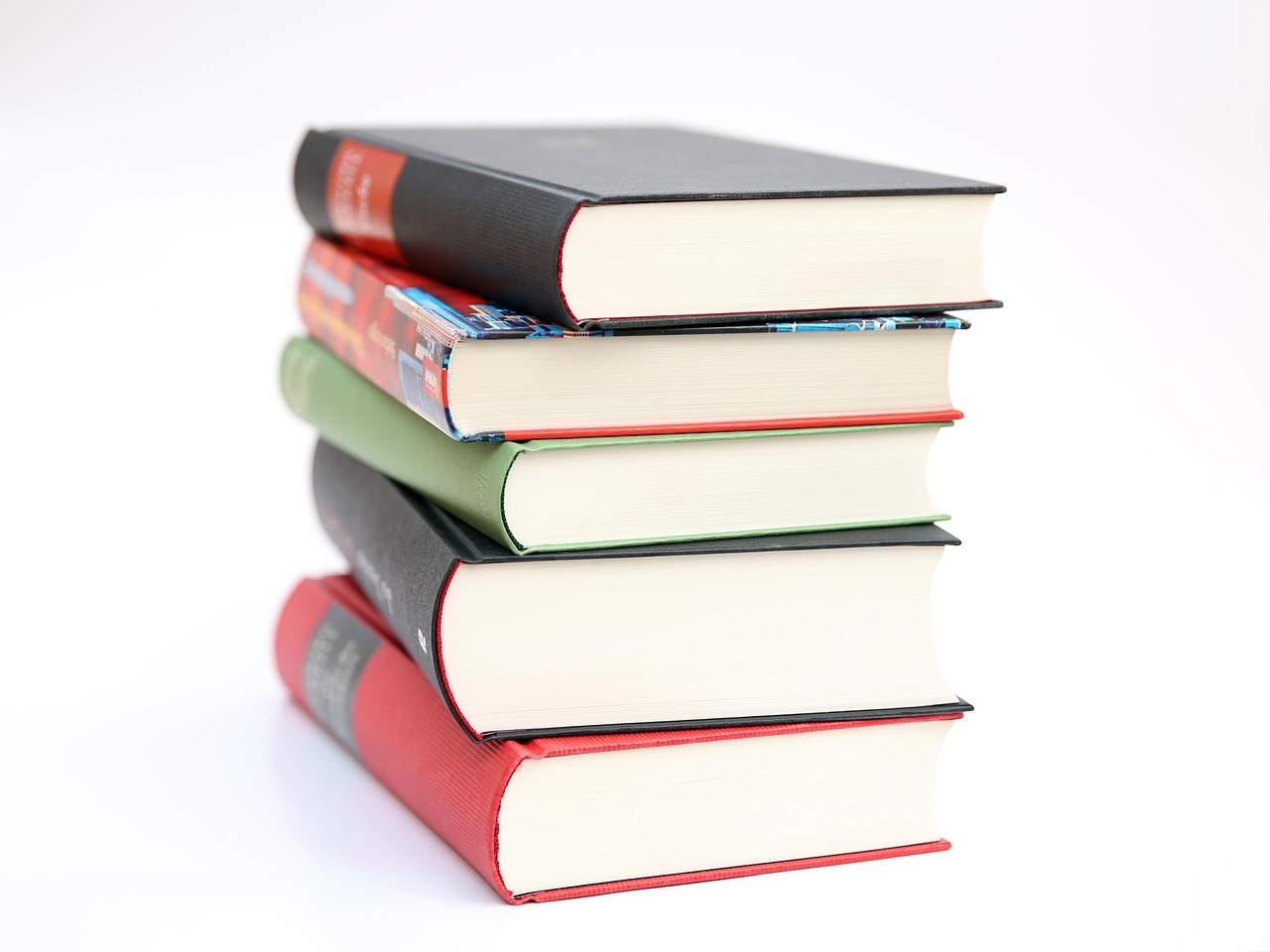医療事務の年収はどれくらい?平均月収と手取りを徹底解説【最新】
「医療事務の仕事って、実際どれくらいの年収がもらえるんだろう?」と気になっている人も多いのではないでしょうか。
病院やクリニックなど、医療現場を支える縁の下の力持ちとして活躍する医療事務は、安定した需要がある一方で、働き方や職場によって収入差が生じやすい職種でもあります。
また、正社員・派遣・パートといった雇用形態の違いや、資格の有無、勤続年数によっても年収が大きく変わります。
この記事では、医療事務の平均年収や月収・手取り額をはじめ、ボーナス・手当・年収アップの方法、さらに将来性まで最新データをもとに解説します。ぜひ今後のキャリア設計の参考にしてください。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
医療事務とは?

医療事務とは、病院やクリニックなどの医療機関で、診療報酬請求や会計処理などを通して医療現場を支える職種です。直接医療行為は行いませんが、サポートを通して患者さんの安心できる環境を提供します。
医療事務が他業界の事務と異なるのは、専門知識が必要となる点です。医療保険制度や診療報酬に関する知識が求められます。また、人と接する機会も多く、正確かつ丁寧な対応が求められるでしょう。
また、電子カルテなどのシステムが普及したことで、パソコン操作のスキルも重視されるようになっています。デジタル化が進む現代の医療現場では、ITに対する柔軟な対応力が強みになるでしょう。
資格は必須ではありませんが、医療事務管理士や医療事務認定実務者などの資格は、就職や転職時に役立ちます。学歴や経験問わず挑戦できる点も魅力で、結婚や就職後の再就職を目指す人にも人気です。
医療事務は安定した需要が見込まれる職種の一つであり、長く働ける仕事を探している人にとって、将来性の高い選択肢といえるでしょう。
医療事務の仕事内容

医療事務は、病院やクリニックの運営を支える大切な仕事です。事務職でありながら、医療の現場と密接に関わるため、専門的な知識と正確な事務処理の両方が求められます。
ここでは、医療事務の代表的な業務を6つに分けて紹介します。どの仕事も医療機関がスムーズに運営されるために欠かせない役割を持っています。
- 受付業務
- 会計業務
- レセプト業務
- 医療費請求業務
- 患者対応業務
- 医療事務全体の業務フロー
①受付業務
受付業務は、医療事務の中でも最も患者と接する機会が多く、病院の「顔」として重要な役割を担います。来院した患者を笑顔で迎え、診察券の受け取りや初診・再診の確認、問診票の記入案内などを行います。
予約状況の確認や診療科の案内、待ち時間の調整なども担当するため、常に周囲の状況を把握しながら臨機応変に対応する力が求められます。
患者が不安を抱えている場合には、穏やかな声かけで安心感を与えることも大切です。さらに、受付データを正確に入力する作業も発生するため、事務スキルと接客力の両方が必要となります。
小さな気配りの積み重ねが、病院全体の印象を大きく左右する仕事といえるでしょう。
②会計業務
会計業務は、診療後に発生する医療費を正確に計算し、スムーズに会計処理を行う仕事です。診療報酬の計算は保険制度に基づいて行われるため、医療点数の知識が欠かせません。
窓口での支払いだけでなく、領収書の発行や明細書の説明、電子カルテとの照合も行います。誤りがあると患者にも病院にも不利益が生じるため、慎重かつ迅速な処理能力が求められます。
また、混雑時には複数の患者を同時に対応することもあるため、冷静な判断力と優先順位をつけるスキルも重要です。
さらに、患者から支払いに関する質問を受けた際には、難しい制度や計算方法をやさしく説明する力も必要です。正確で丁寧な会計対応が、病院への信頼を高める大きな要素になります。
③レセプト業務
レセプト業務は、医療機関が診療報酬を保険者へ請求するために作成する「診療報酬明細書(レセプト)」を扱う仕事です。医療行為ごとに細かく点数を算定し、保険制度に基づいて請求書を作成します。
入力内容に少しでも誤りがあると返戻や減額の原因となり、病院の収入に直接影響します。そのため、医療用語や診療行為の知識、各種加算の仕組みなどを正確に理解しておくことが必要です。
また、月末から月初にかけては提出期限があるため、繁忙期にはチームで連携しながら迅速に処理を進めます。
電子レセプトの導入により効率化は進んでいますが、最終的な確認は人の手で行うため、注意力と集中力が欠かせません。
ミスを防ぐ仕組みを整え、的確な処理を行うことが、安定した経営を支える鍵となります。
④医療費請求業務
医療費請求業務は、レセプトをもとに診療報酬を保険者へ正式に請求する重要な工程です。医療機関の収入源に直結するため、正確性と期限厳守が何よりも大切です。
レセプト作成後、内容をチェックして支払基金や国保連合会に提出し、返戻があれば修正して再提出します。こうした一連の作業には保険制度の理解が欠かせず、法律改正にも常に注意を払う必要があります。
また、診療科によって請求内容が異なるため、業務に慣れるまでは細かなルールの把握に時間がかかるでしょう。経験を積むほどに効率的な処理ができるようになり、経営面でも大きな貢献が期待されます。
医療費請求業務は、単なる事務作業ではなく、医療機関の経済的基盤を支える専門職といえるのです。
⑤患者対応業務
患者対応業務は、医療事務の中でも特に人との関わりが深い仕事です。患者が来院したときの不安や疑問を軽減し、安心して診察を受けられるようサポートします。
受付や会計、電話応対など、あらゆる場面でのコミュニケーション能力が求められます。ときには体調が悪く、気持ちが不安定な患者への対応もあるため、相手の立場を理解した思いやりが大切です。
また、医師や看護師など他職種との情報共有も必要で、連携の正確さが業務の円滑さに直結します。クレームや問い合わせ対応では、冷静さと柔軟さを持って行動することが信頼構築につながります。
患者の声にしっかり耳を傾け、丁寧に説明することで、医療機関全体の印象を良くし、リピーターを増やす効果も期待できるでしょう。
⑥医療事務全体の業務フロー
医療事務全体の業務フローは、受付から診療、会計、請求までを一貫して管理する仕組みのことです。患者が来院した瞬間から、診療が終わり請求が完了するまで、医療事務はあらゆる段階で関与します。
受付では患者情報を確認し、診療内容を電子カルテに記録します。診療後は会計業務を行い、そのデータをもとにレセプトを作成し、保険者に請求する流れです。
こうした一連の業務がスムーズに進むことで、患者満足度の向上や経営の安定につながります。最近では、医療事務システムのデジタル化が進み、入力や集計作業の効率も上がっています。
しかし、人の判断が必要な部分も多く、細かな確認作業やチームワークが欠かせません。全体の流れを理解し、各段階で正確な対応を行うことが、信頼される医療機関を支える基盤となります。
医療事務の平均年収【最新データ】

医療事務の平均年収はおよそ400〜500万円です。これは正社員の場合、月給が20万円台前半で、ボーナスを含めた年間の総支給額として算出される数字です。
一般事務職と比べるとやや低めですが、医療事務は信頼性と正確性が求められるため患者数の変動に関わらず需要が安定しており、安心して長期的に働くことが可能です。
年収は経験や資格の有無でも差が生じます。例えば「診療報酬請求事務能力認定試験」の資格を取得すると、レセプト業務や請求管理など専門的な仕事を任され、給与アップにつながる場合もあります。
大規模な病院や大学病院では給与水準が比較的高く、個人クリニックでは年収が低めになる傾向が見られますが、その分残業が少なく、働きやすさを重視できる環境が多いのも特徴です。
結果として、医療事務は「安定した年収を得ながら無理なく働ける」職種であり、長期的なキャリア形成にも向いているといえるでしょう。
引用:
雇用形態別の医療事務の年収(正社員・派遣・パート)
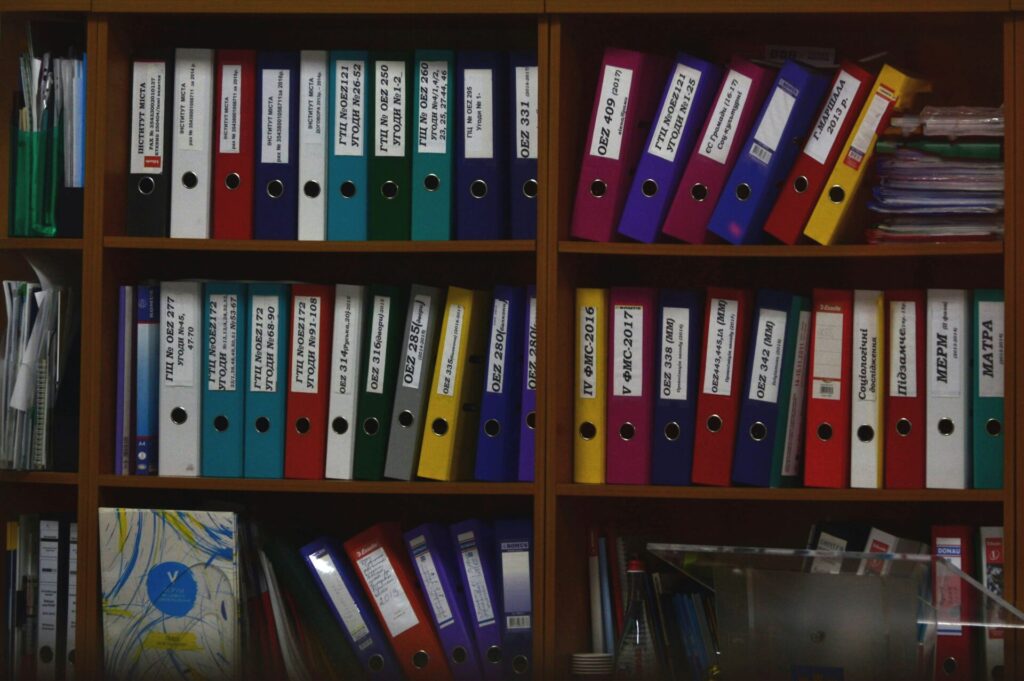
医療事務の年収は、雇用形態によって大きく異なります。安定を優先するか、柔軟な働き方を重視するかで、自分に合う選択が変わるでしょう。
ここでは、正社員・派遣・パートの特徴と年収目安を整理します。
- 正社員医療事務の年収
- 派遣医療事務の年収
- パート医療事務の時給・年収
①正社員医療事務の年収
正社員として医療事務を担当する場合、待遇や規模の大きな病院で働けば、給与や手当・賞与を含めた年収は比較的高めになります。
実際、OpenWork 上の医療法人では、正社員医療事務で「約 443 万円」という事例も報告されています(※医療法人財団康生会)
一方、小規模クリニックでは年収が抑えられ、300 万円前後という例も少なくありません。
未経験者や資格なしでの入社だと初任給は低めになることもありますが、資格取得や経験を積むことで昇給・転職に有利となります。安定性を重視しながら、スキルを磨き収入アップを目指せる働き方です。
②派遣医療事務の年収
派遣として医療事務を行うケースでは、時給制での勤務がほとんどで、月収や年収は勤務時間に大きく左右されます。医療事務の派遣時給の相場としては、1,200円台前半という報告もあります。
仮に時給1,250円、1日7時間×月20日勤務とすると、月収は約175,000円となり、年収換算でおよそ210万〜260万円程度になることもあります。
賞与なしの場合が多いため、その点を考慮する必要があります。派遣会社によって研修制度や資格支援が整っているところもあり、それらを活用してステップアップを目指す道も考えられます。
③パート医療事務の時給・年収
パート医療事務は、時給1,000円〜1,300円程度が相場とされます。週3〜4日勤務であれば、年収はおおよそ120万〜180万円前後が見込まれます。
ただし、賞与や昇給なしという条件が多く、長期間での収入増加は難しい可能性があります。
したがって、パートから経験を積み正社員登用を目指す、あるいは専門性を身につけて条件の良い職場に転職するという戦略が現実的です。
実際、OpenWork上には、中途入社6年目の医療事務で「350〜400万円」という報告も見られます(※日本調剤)
引用:
医療事務の賞与(ボーナス)・手当・福利厚生の実態

医療事務を目指す就活生の中には、「ボーナスはどれくらい?」「手当はある?」「福利厚生は実際どうか?」と疑問を抱く人も多いでしょう。
ここでは、公的統計や企業クチコミをもとに、ボーナスや手当、保険・休暇制度の実態を明らかにします。
- 医療事務の賞与(ボーナス)の平均支給額
- 医療事務に支給される主な手当の種類
- 医療事務の福利厚生制度とその内容
- 医療事務の社会保険・有給休暇の実情
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
①医療事務の賞与(ボーナス)の平均支給額
医療事務のボーナス(賞与)は、勤務先の規模や財政状況に左右されやすいです。公的統計によると、職業情報サイトのデータでは、年収の中央値にボーナスを含めた指標が示されています。
医療事務の年収相場はおおよそ478万円前後とされています。ただし、この数値には手当や賞与が含まれている場合があるため、実際の賞与額は勤務先ごとに異なります。
求人情報では「ボーナスなし」「年1回」「年2回」「業績連動」などさまざまで、小さなクリニックでは支給されないケースもあります。
応募時には、賞与の支給有無や金額、支給月数を確認しておくことが大切です。安定してボーナスを得たい場合は、法人経営で規模の大きい医療機関を選ぶとよいでしょう。
②医療事務に支給される主な手当の種類
医療事務には、基本給に加えてさまざまな手当が支給されることがあります。代表的なのは「通勤手当」「資格手当」「皆勤手当」「時間外手当」「夜勤手当」などです。
通勤手当は公共交通機関の利用費を全額または一部支給する形が一般的です。資格手当は、医療事務関連の資格を持つ人に支給されるもので、スキルアップの励みになります。
皆勤手当は欠勤がないことを評価する制度で、月ごとに一定額が支給される場合が多いです。夜勤や休日出勤がある医療機関では、夜勤手当や時間外手当が支給されます。
手当の内容や金額は職場によって異なるため、求人票を確認する際には細かくチェックしておくと安心です。
③医療事務の福利厚生制度とその内容
福利厚生制度は医療機関の経営体制や規模によって差がありますが、一般的には「健康診断・予防接種の補助」「退職金制度」「育児・介護休暇」「医療費補助」などが設けられています。
医療機関では、自院での診療費割引や従業員・家族対象の医療費補助など、職場特有の福利厚生も見られます。
また、研修制度や資格取得支援を導入している職場もあり、スキルアップを目指す人にとって魅力的です。一方で、休暇制度の運用や有給休暇の取得しやすさは職場によって大きく異なります。
求人情報や口コミを通じて、福利厚生の内容や実際の利用状況を確認しておくことが大切です。
④医療事務の社会保険・有給休暇の実情
医療事務として正社員で働く場合、多くの医療機関で社会保険が完備されています。健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険など、基本的な制度が整っているため安心して働ける環境です。
ただし、パートや短時間勤務の契約では加入条件を満たさない場合もあるため、事前確認が必要です。有給休暇は法律で定められた日数が付与されますが、実際の取得率は職場によって差があります。
人員配置が限られる職場では、繁忙期に休みを取りづらいこともあります。応募前に休暇制度の運用実績を確認し、長く続けられる職場かどうかを見極めることが重要です。
引用:
- 厚生労働省 職業情報提供サイト「jobtag」 医療事務(賃金・年収データ)
- 厚生労働省 賃金構造基本統計調査(医療・介護事務)
- OpenWork 社会保険診療報酬支払基金 クチコミ
- OpenWork 医療機関(病院)有給取得クチコミ
- OpenWork ワーク・ライフ・バランス クチコミ
- OpenWork 有休消化率ランキング(2025年版)
医療事務の年収を上げる方法
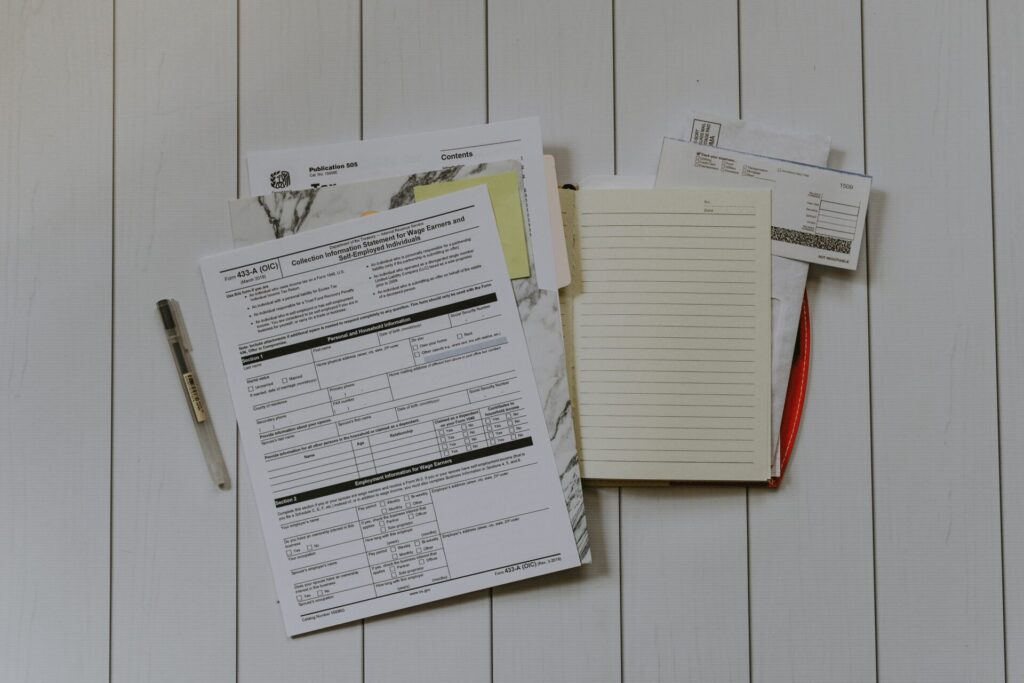
医療事務は安定した職業ですが、年収を上げるには計画的な努力が求められます。ここでは「資格取得」「キャリアアップ」「転職」「給与交渉」「兼務によるスキル拡張」といった具体的な手段を紹介します。
自分の強みを生かし、将来の収入アップにつなげていきましょう。
- 資格取得によるスキルアップ
- キャリアアップ・昇進による年収向上
- 高収入が期待できる職場への転職
- 給与交渉・評価制度の理解と活用
- 医療事務プラスα(経理・総務兼務など)のキャリア形成
①資格取得によるスキルアップ
医療事務の年収を上げたいと考えるなら、資格取得はもっとも効果的なステップといえるでしょう。資格を持つことで実務能力の高さを証明でき、採用時や昇給の場面で優位に立てます。
特に「医療事務管理士」や「診療報酬請求事務能力認定試験」は信頼性が高く、医療機関からの評価も上がります。
勉強を通じて医療制度や診療報酬の仕組みを深く理解できるため、日々の業務での正確さやスピードも向上します。
結果として、ミスが少なく業務効率の良い人材として周囲から信頼され、責任ある仕事を任される機会も増えるでしょう。また、資格を取得することで自信がつき、仕事へのモチベーションも高まります。
資格は単なる肩書きではなく、今後のキャリアを切り開く大切な「武器」になるのです。
②キャリアアップ・昇進による年収向上
医療事務で安定した収入を得たいなら、昇進を目指すことが欠かせません。経験を積み、リーダーや主任、事務長といった管理職を任されるようになると、給与は確実に上がります。
昇進を実現するためには、単に勤務年数を重ねるだけでなく、チームをまとめる力やコミュニケーション能力、柔軟な対応力を磨くことが大切です。
また、経営視点を持ち、業務改善やコスト削減の提案ができるようになると、上層部からの信頼も厚くなります。自分の仕事に誇りを持ち、職場全体の効率化に貢献する姿勢が評価につながるのです。
さらに、後輩の指導や育成に積極的に関わることで、組織内での存在感が増します。キャリアアップは時間がかかりますが、その分だけ安定と報酬を得られる道でもあります。
③高収入が期待できる職場への転職
医療事務の年収は、働く施設の規模や運営体制によって大きく異なります。現在の職場で昇給の余地が少ない場合は、転職を検討するのも有効です。
大学病院や総合病院、医療法人グループなどの大規模施設では、給与水準が比較的高く設定されている傾向があります。また、福利厚生や賞与も充実しており、安定した働き方を実現しやすいのが特徴です。
転職を成功させるためには、まず自分の強みを明確にし、資格や実績を具体的にアピールできる準備を整えましょう。
さらに、転職サイトやエージェントを活用し、条件交渉や情報収集を怠らないことが大切です。職場選びの際は給与だけでなく、職場環境や人間関係、将来的な成長の見込みも総合的に判断してください。
新たな環境への挑戦が、より高い年収とやりがいをもたらします。
④給与交渉・評価制度の理解と活用
医療事務の年収を上げるには、ただ努力するだけでなく、それをきちんと「見える化」することが重要です。多くの医療機関では評価制度が導入されており、成果や姿勢を数値で判断しています。
この仕組みを理解しておくと、どの時期にどのような成果を伝えるべきかが明確になります。
たとえば、定期面談の前に自分の実績を整理し、改善提案や患者対応での成果を具体的に伝えると好印象を与えやすいでしょう。
また、他院の給与水準や職種別の平均年収をリサーチしておくことで、現実的な交渉ラインを設定できます。自分の価値を理解し、根拠を持って交渉することが大切です。
遠慮せず、自分の努力を正当に評価してもらう姿勢が、結果的に年収アップへの近道になります。
⑤医療事務プラスα(経理・総務兼務など)のキャリア形成
医療事務のスキルに加えて、経理や総務などの知識を身につけると、仕事の幅がぐっと広がります。
特に中小規模のクリニックでは、複数の業務をこなせる人材が重宝されるため、給与が高く設定されるケースも少なくありません。
たとえば、請求処理と同時に経費管理や職員の勤怠管理を行うことで、経営全体の流れを理解できるようになります。これにより、事務職の枠を超えた「経営パートナー」としての立場を築けるでしょう。
さらに、PCスキルや会計ソフトの操作知識などを習得しておくと、どの職場でも通用する即戦力として評価されます。
医療事務にプラスαのスキルを加えることで、自分の市場価値が上がり、転職先の選択肢も広がります。長期的な視点でスキルを磨くことが、安定した高収入への確実な道です。
医療事務の将来性

医療事務の仕事は、医療現場を支える欠かせない職種です。医療制度の変化やテクノロジーの発展により、求められるスキルや働き方が大きく変化しています。
ここでは、医療事務の将来性をさまざまな視点から解説します。
- 医療業界の人材需要の変化
- 高齢化社会による医療事務需要の拡大
- 医療DX・電子カルテ普及の影響
- 業務自動化による仕事内容の変化
- キャリアパスとスキルアップの可能性
- 医療事務の将来の年収動向
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
①医療業界の人材需要の変化
医療業界では、少子高齢化にともなう人口構造の変化が進み、病院や診療所の経営環境も大きく様変わりしています。
その中で医療事務は、医療機関の運営を支える中核的な職種として安定した需要を維持しています。特に地方では医療従事者の不足が深刻化しており、医療事務の人材確保が課題となっています。
一方で、医療費の増加や診療報酬制度の見直しなどにより、経営の効率化が求められています。その結果、医療事務には単なる事務処理能力に加えて、経営的視点やデータ分析の力も必要とされています。
現場では、レセプト請求業務だけでなく、患者対応やスタッフ間の情報共有、在宅医療との連携など多面的な役割を担う機会が増えています。
こうした背景から、医療事務は「事務職の中でも成長し続ける仕事」として今後も価値を高めていくでしょう。
②高齢化社会による医療事務需要の拡大
日本の高齢化率はすでに30%に迫り、今後も上昇する見込みです。高齢者は慢性疾患の治療などで定期的な通院をしている場合が多く、このような社会構造の中で医療機関の利用者数は増え続けています。
患者数が増えるほど、保険証確認やレセプト請求、医療費管理といった業務も複雑化し、事務スタッフの重要性が高まっているのです。
さらに、医療と介護の連携が進むことで、医療事務が活躍するフィールドも広がっています。病院だけでなく、クリニック、介護施設、訪問診療所など、さまざまな場で需要が生まれています。
特に地域包括ケアシステムが整備されるにつれ、患者情報の共有や介護職との連携調整を行う医療事務の役割は一層重視されています。
人と人をつなぐ医療のハブとしての存在感を強めており、今後も安定した雇用と活躍の場が見込まれるでしょう。
③医療DX・電子カルテ普及の影響
医療DX(デジタルトランスフォーメーション)は、医療現場の働き方を大きく変える潮流です。例えば電子カルテの普及で、診療や会計情報がデジタルで管理されるようになり、業務効率が格段に向上しました。
これにより、医療事務の役割も「単なる入力作業」から「データを活用して医療を支える仕事」へと進化しています。
今後は、オンライン資格確認やAIによるレセプト自動チェックなど、DX化がさらに進むと予想されます。こうした変化に対応するためには、ITリテラシーやシステム理解力が欠かせません。
Excelや電子カルテの操作はもちろん、データ分析や報告資料の作成スキルがある人は職場で重宝されます。医療とテクノロジーの融合が進む中で、ITに強い医療事務は職場の中心的存在となるでしょう。
デジタル時代に適応できる人ほど、年収やキャリアの幅も広がります。
④業務自動化による仕事内容の変化
AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)などの自動化技術は、医療事務の現場でも導入が進んでいます。
これにより、レセプト点検やデータ入力といった定型業務は効率化され、人の手をかける部分が減少しています。しかし、業務自動化は「仕事が奪われる」ことを意味するわけではありません。
むしろ、人間にしかできないコミュニケーションや判断業務の価値が高まっているのです。
たとえば、患者への説明や問い合わせ対応、医師・看護師との情報共有などは、人の感情や思いやりを理解する力が求められます。また、トラブル対応や制度変更への柔軟な判断も自動化には難しい領域です。
自動化技術を上手に使いこなせる人ほど、現場では欠かせない存在になります。新しい技術に前向きに取り組む姿勢を持てば、業務の幅が広がり、キャリアの成長にもつながるでしょう。
⑤キャリアパスとスキルアップの可能性
医療事務は、経験を積むことで多様なキャリアを築ける魅力的な職種です。現場での実務経験を重ねれば、主任・係長・事務長といった管理職を目指すことができます。
また、医療秘書、診療情報管理士、医療クラークなどの専門資格を取得すれば、より専門的な分野で活躍できるでしょう。こうした資格はスキルの証明となり、転職時にも有利に働きます。
さらに、医療事務で培った知識やコミュニケーション能力は、保険会社や製薬会社、医療システム企業などでも評価されます。
医療現場から企業側へキャリアチェンジする道もあり、選択肢の幅は広いです。大切なのは、日々の業務で学んだことを活かし、常にスキルアップを意識することです。
新しい制度やシステムに対応できる柔軟性を持つ人は、将来にわたって求められ続けるでしょう。
⑥医療事務の将来の年収動向
医療事務の平均年収はおおよそ300万円前後といわれていますが、将来的にはスキルや勤務先によって大きな差が出るでしょう。
たとえば、電子カルテの管理や診療報酬請求、統計分析などの専門知識を持つ人は、昇給や転職の際に優遇されやすくなります。主任やリーダー職に昇進すれば、年収400万円〜500万円も十分に狙えます。
一方で、スキルアップを怠り、従来のやり方にとどまると収入が停滞する可能性もあります。今後は、医療機関の経営改善や業務効率化に貢献できる人材ほど高く評価される時代です。
つまり、学び続ける姿勢こそが安定した収入とキャリアの両立につながります。資格の取得やITスキルの習得に積極的に取り組むことで、将来的な収入アップのチャンスを確実に広げられるでしょう。
医療事務になるには?必要な資格・スキル・就職ステップ

医療事務は、医療機関を支える重要な仕事です。ここでは、医療事務になるために必要な資格やスキル、就職までの流れを詳しく紹介します。
就活生が抱きやすい「何から始めればいいのか」という不安を解消し、実際に行動へ移せるようなステップを整理して解説します。
- 医療事務の資格を取得する
- 医療事務の知識とスキルを身につける
- 医療事務講座や専門学校に通う
- 医療事務の求人を探す
- 医療機関へ応募・面接を受ける
- 医療事務として働きながら経験を積む
①医療事務の資格を取得する
医療事務に国家資格はありませんが、民間資格を持っていると採用時に有利になります。資格を持つことで、未経験でも医療現場の信頼を得やすく、就職活動の選択肢も広がるでしょう。
代表的なものには「医療事務管理士」や「診療報酬請求事務能力認定試験」などがあり、どちらも現場での基礎知識を身につけるうえで役立ちます。
ただし、資格取得だけに満足してしまうのは危険です。試験勉強を通して、医療保険制度の仕組みやレセプト業務の流れをしっかり理解することが大切です。
資格を取ることはゴールではなく、あくまでスタートラインです。学習の中で得た知識を実際の現場で活かす意識を持てば、面接時にも自信を持って話すことができます。
さらに、資格を複数取得しておくと、将来的に管理職や専門職を目指す際にも強みになります。
②医療事務の知識とスキルを身につける
医療事務の仕事は、受付対応や会計処理、レセプト作成、カルテ管理など多岐にわたります。そのため、正確さとスピードの両立が求められます。
加えて、患者さんとのコミュニケーションや医師・看護師との情報共有も多く発生するため、丁寧で柔軟な対応力が欠かせません。話を真摯に受け止め、相手に寄り添う姿勢が信頼関係を築く上で重要です。
また、現代の医療現場では電子カルテや会計ソフトの操作が日常的に行われるため、パソコンスキルも必須です。ExcelやWordの基本操作を習得しておくと、事務作業を効率よく進められます。
独学で学ぶことも可能ですが、専門の通信講座を活用すれば体系的に学べるでしょう。
学習を通じて医療事務の全体像をつかみ、自分の得意分野を把握しておくと、採用面接でも強みとしてアピールしやすくなります。
③医療事務講座や専門学校に通う
効率よくスキルを身につけたい人には、医療事務講座や専門学校への通学がおすすめです。
これらの学習機関では、資格試験対策はもちろん、実際の医療現場を想定した実習やロールプレイング形式の授業も行われています。
講師やクラスメイトと意見交換をしながら学ぶことで、知識の定着率が高まり、現場での対応力も身につきます。
ただし、講座や学校によって費用や受講期間が異なるため、事前に比較して選ぶことが重要です。短期間で学べる通信講座なら、大学生活やアルバイトと両立しながら資格取得を目指せます。
専門学校では、インターンシップ制度を活用して実際の医療機関で経験を積むことも可能です。現場を体験することで、仕事のやりがいや自分の適性をより深く理解でき、就職後にも役立つでしょう。
④医療事務の求人を探す
医療事務の求人は全国各地にあり、病院・クリニック・調剤薬局など多彩な職場が存在します。
求人を探す際は、勤務先の規模や雰囲気、通勤時間、給与形態など、働きやすさに関わる条件を整理しておくとよいでしょう。
求人サイトやハローワークのほか、医療事務専門の転職エージェントを利用すれば、自分に合った求人を紹介してもらいやすくなります。未経験可の求人も多く、資格を持つ人は積極的に挑戦できるでしょう。
その際、医療機関によって業務内容が大きく異なる点に注意が必要です。クリニックでは受付業務が中心になる一方、総合病院では診療科ごとのレセプト業務など専門性が求められる場合があります。
応募前に職場見学などを通して雰囲気を確認しておくと安心です。働く環境をしっかり見極めることが、長く安心して働けるキャリア形成につながるでしょう。
「自分らしく働ける会社が、実はあなたのすぐそばにあるかもしれない」
就活を続ける中で、求人票を見て「これ、ちょっと興味あるかも」と思うことはあっても、なかなかピンとくる企業は少ないものです。そんなときに知ってほしいのが、一般のサイトには載っていない「非公開求人」。
①あなたの強みを見極め企業をマッチング
②ES添削から面接対策まですべて支援
③限定求人なので、競争率が低い
「ただ応募するだけじゃなく、自分にフィットする会社でスタートを切りたい」そんなあなたにぴったりのサービスです。まずは非公開求人に登録して、あなたらしい一歩を踏み出しましょう!
⑤医療機関へ応募・面接を受ける
応募書類を準備したら、面接対策を念入りに行いましょう。医療事務の面接では、ビジネスマナーや清潔感、誠実な対応姿勢が重視されます。
志望動機では、「人の役に立ちたい」「医療チームの一員として貢献したい」など、経験と結び付けて具体的に語ることが大切です。医療現場はチームワークが大切なので協調性を意識すると良いでしょう。
また、面接では自分から質問する姿勢も大切です。仕事内容や教育体制、残業の有無などを確認しておくことで、入職後のミスマッチを防げます。
さらに、医療事務の仕事に対して「正確さ」や「気配り」を意識していることをアピールすると、採用担当者に安心感を与えられます。
緊張してもうまく話そうとするより、丁寧で落ち着いた態度を心がけてください。それが何よりの信頼につながります。
⑥医療事務として働きながら経験を積む
医療事務として採用されたら、現場での経験を重ねながらスキルを磨いていきます。受付や会計業務、レセプト処理、医師や看護師との連携など、学習では得られなかった実践力を身につける段階です。
最初は覚えることが多く、戸惑う場面もあるかもしれません。しかし、経験を積むほどに業務の流れが理解でき、自信を持って対応できるようになります。
経験を重ねることで、医療事務リーダーや医療クラークなど、より専門性の高いポジションを目指すことも可能です。
加えて、医療機関によってはスキルアップ研修や資格支援制度を設けている場合もあるため、積極的に活用すると良いでしょう。自分の得意分野を見つけて磨いていけば、キャリアの幅が広がります。
医療事務は安定性が高く、長く働ける職種です。日々の業務に真摯に向き合う姿勢が、信頼される医療事務員への近道といえるでしょう。
医療事務のキャリアと年収の展望
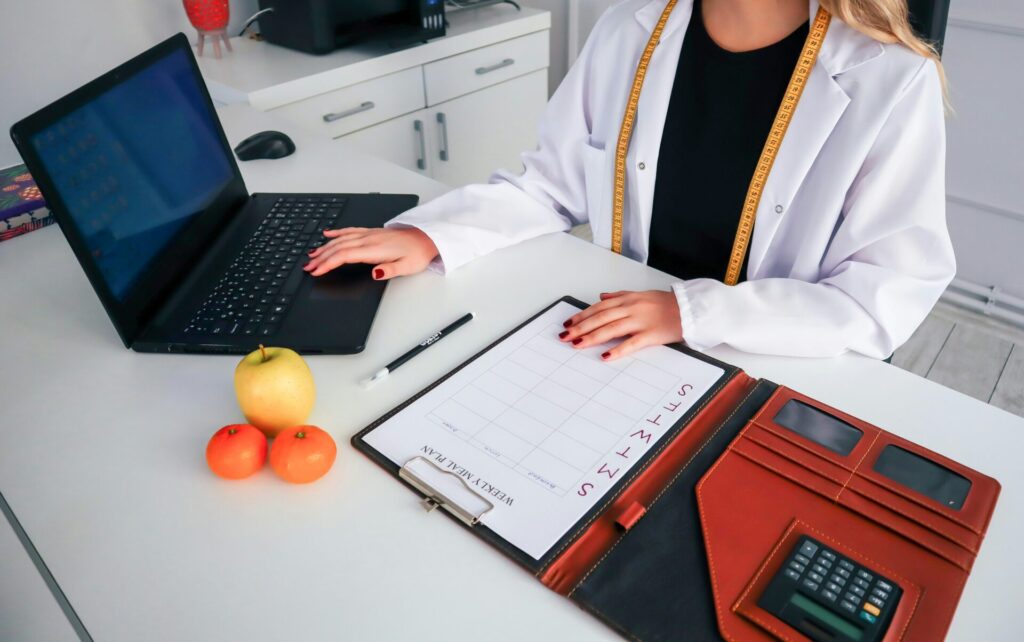
医療事務は、医療機関の円滑な運営を支える重要な職種であり、受付・会計・レセプト業務など多岐にわたる仕事を担います。
最新データによると、医療事務の平均年収は雇用形態や経験、資格の有無によって大きく異なりますが、安定した需要がある点が魅力です。
特に、資格取得やキャリアアップを通じて、年収アップを実現できる可能性があります。また、医療DXや電子カルテ普及の進展により、業務の効率化とともに新しいスキルが求められる時代へと変化しています。
今後も医療事務は高齢化社会の中で需要が拡大し、将来性のある職種として注目されるでしょう。安定した職場環境とキャリア成長を両立できる医療事務は、長期的に働きたい方にとって有望な選択肢です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。