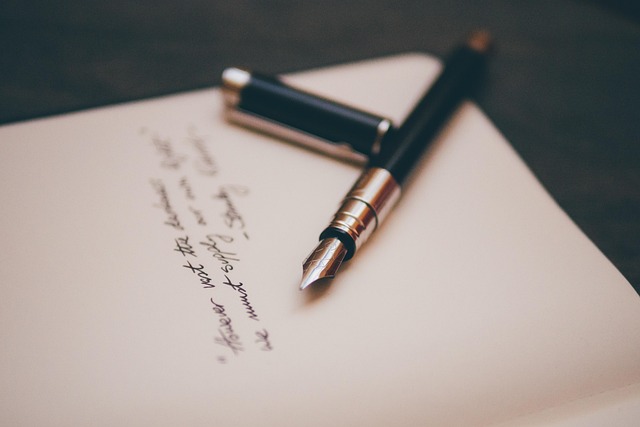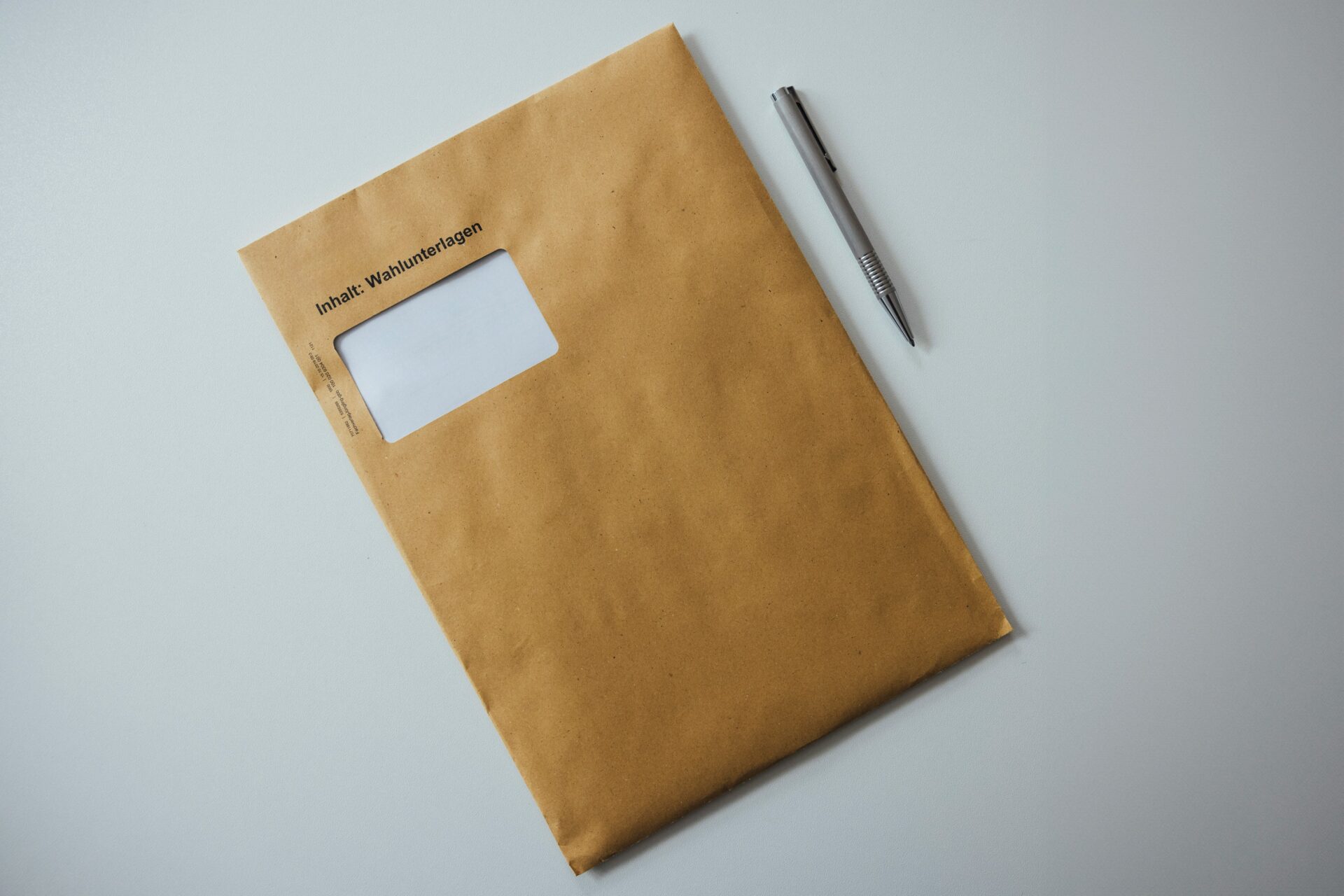御社・貴社を正しく使い分けるコツ|就活マナー完全ガイド
「『御社』と『貴社』って、結局どう違うの?」 就活の面接や書類作成で必ず出てくる表現ですが、実際に正しく使い分けられている人は意外と少ないものです。
そこで本記事では、それぞれの意味や使い方、就活の場での具体的な使用例、間違えた時の対処法まで徹底的に解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
御社と貴社の違いとは?就活で知っておきたい基本知識

就活の面接やメールで「御社」と「貴社」を使い分けるのは基本的なマナーです。しかし、言葉の違いや使い分け方を正しく理解していないと、知らずに失礼な印象を与える可能性もあります。
ここでは、就活生が迷いやすい御社・貴社の違いを解説し、安心して言葉を選べるように知識をまとめました。
- 話し言葉と書き言葉の違い
- 御社と貴社の意味と成り立ち
- 就活での使い分けの基本ルール
- 自社を示す表現との使い分け
- 敬語の種類と使い分けの関係
- 言葉遣いが面接官に与える印象
①話し言葉と書き言葉の違い
「御社」は話し言葉、「貴社」は書き言葉として使うのが一般的です。面接や電話など口頭のやり取りでは「御社」を使うのが自然で、丁寧な印象を与えられます。
一方、履歴書やエントリーシート、メールでは「貴社」が適切です。逆に使うと不自然に見られ、マナーに疎いと判断されるおそれも。
就活では言葉の選び方ひとつで評価が左右されるため、この違いは押さえておく必要があります。状況に応じた表現を正しく使えば、相手に配慮ができる学生という印象を持ってもらえるでしょう。
②御社と貴社の意味と成り立ち
「御社」は相手の会社を敬って呼ぶ表現で、「御」と「社」を組み合わせてできました。「貴社」は「貴い」という言葉を使い、同じく相手を敬う意味を持ちます。
どちらも相手企業に敬意を示す言葉ですが、口語と文語で使い分けが生まれました。背景を知ることで暗記ではなく自然に使えるようになります。
就活ではこうした基本知識を持つことが第一印象を左右するため、この違いを理解し意識して使いましょう。
③就活での使い分けの基本ルール
就活では、会話では「御社」、書類やメールでは「貴社」を使うのが基本です。面接では自然な会話を意識し、「御社」を使うことで応募先への敬意を示します。
逆に文書では「貴社」を選ぶとフォーマルな印象に。使い分けを誤るとマナー不足と見られる可能性があるため注意が必要です。
各場面に適した言葉遣いを心掛けることで、結果的に採用担当者からの評価も高まるでしょう。
④自社を示す表現との使い分け
「弊社」「当社」など自分の所属を表す言葉との区別も重要です。応募先には「御社」や「貴社」、自分の所属には「弊社」「当社」を使います。
アルバイト先や大学を指す場合は「当方」「当校」といった表現を使うとよいでしょう。適切な敬語の使い分けは社会人としての基本であり、採用担当者にも信頼感を与える要素です。
⑤敬語の種類と使い分けの関係
「御社」「貴社」は尊敬語にあたり、相手を立てる表現です。敬語には尊敬語・謙譲語・丁寧語の3種類があり、状況に応じて使い分ける必要があります。
自分の行動をへりくだるときは謙譲語を、相手やその組織を敬うときは尊敬語を使うのが基本です。このルールを理解すれば「御社」「貴社」以外の敬語も自然に使いこなせます。
言葉遣いは就活で評価される要素の1つなので、基礎を押さえておくと安心でしょう。
⑥言葉遣いが面接官に与える印象
言葉遣いは就活の印象を大きく左右します。「御社」「貴社」を正しく使える学生は社会人としての基本を理解していると評価されやすいです。
一方で誤りや迷いがあると、コミュニケーション能力やマナーへの意識に不安を持たれる可能性があります。事前に練習し、自信を持って話せるようにしておくことが大切です。
丁寧で自然な言葉遣いを心掛けることが、好印象を与える第一歩となります。
御社を使う場面と使用例

就活の面接や電話、会社説明会など、社会人とのやり取りで「御社」を正しく使えると好印象を与えられます。
ここでは使用シーンごとの例文を紹介します。
- 面接での受け答え
- 電話での会話
- 会社説明会での挨拶や質問
- OBOG訪問
- 職場見学やインターン
- 選考後のやり取り
①面接での受け答え
面接での受け答えでは「御社」を用いることで丁寧な印象を与えられます。例えば「御社の理念に共感しました」や「御社の取り組みに魅力を感じています」といった言い方です。
話し言葉では「貴社」よりも自然で、緊張した場面でも柔らかく伝わります。敬語に不安を感じる学生も多いですが、こうした定型表現を覚えておけば安心でしょう。
さらに企業情報を調べた上で具体的な内容を添えると、相手への関心や熱意が伝わります。ひと工夫で評価も上がりやすいため、積極的に取り入れてみてください。
②電話での会話
電話でも「御社」を使うのが基本です。「御社の○○様はいらっしゃいますか」といった言い方をすれば丁寧さが伝わります。声のトーンや話す速さにも気を配りましょう。
顔が見えない分、言葉遣いや声の印象が重要です。はっきり話すことを意識してください。メモを取りながら話すと要点を押さえたやり取りができ、信頼感を高められます。
細かい工夫の積み重ねが全体の印象を左右するため、繰り返し練習しましょう。
③会社説明会での挨拶や質問
会社説明会では「御社」を使った丁寧な質問が評価につながります。「御社の新規事業について詳しく伺いたいです」など、興味を具体的に表す表現を心掛けてください。
質問は公式サイトや資料を踏まえて準備しましょう。多くの学生が集まる場では、質問の仕方ひとつで印象が変わります。
自分のキャリアや志望理由に関連付けた質問を考えると、会話の流れも自然になり、採用担当者の記憶に残りやすいです。
④OBOG訪問
OBOG訪問では相手が先輩社員でも「御社」を使うのが一般的です。「御社で働くうえでやりがいを感じる点を教えてください」という質問が適切でしょう。
距離が近い雰囲気になりやすい場面でも丁寧な言葉遣いを意識すると好印象です。仕事内容やキャリアパスなど具体的な質問を選ぶと、より実りある訪問になります。
こうした対応は社会人マナーの習得にも役立ちます。
⑤職場見学やインターン
職場見学やインターンでも「御社」を使うことで礼儀を示せます。「御社の現場を拝見して働く環境を理解できました」と伝えるとよいでしょう。
体験を通じた気付きや学びを言葉にすることで、面接やエントリーシートに活かせます。会話の中で自然に「御社」を使えるようになると、自信もつきます。実践の場で丁寧な言葉を意識してください。
⑥選考後のやり取り
選考後のやり取りも「御社」を使うことが基本であり、「この度は御社の一次面接の機会をいただきありがとうございました」というメールが代表的です。結果連絡やお礼メールは印象を左右します。
感謝を丁寧に伝えながら簡潔で分かりやすい文章を意識してください。誤字や敬語の誤りがないか確認を重ね、信頼を築くやり取りを心掛けましょう。
貴社を使う場面と使用例

就活で「貴社」を正しく使えることは、文章力やマナーの印象を左右します。特に履歴書やメールなど書面でのやり取りでは、適切な表現を使えるかどうかが評価に直結するため注意が必要です。
ここでは、就活生が具体的に「貴社」をどの場面で使うのかを整理し、例文を交えながら詳しく解説します。
- 履歴書やES
- メールや手紙
- 送付状や書類提出時
- 志望動機や自己PR文中
- オンライン応募フォーム
- 内定承諾書や辞退連絡
①履歴書やES
履歴書やエントリーシートでは、志望先企業に敬意を示すため「貴社」を使います。「貴社」は書き言葉で使う表現であり、正式な文書には適切です。
例えば「貴社の理念に共感し志望いたしました」と書くことで、ビジネス文書としての体裁が整います。口頭では「御社」を使うのが一般的なので、書面と会話で使い分ける意識を持つことが大切です。
誤って「御社」と書いても意味は通じますが、形式面での印象は弱まるでしょう。
②メールや手紙
メールや手紙などの文章でも「貴社」が適しており、例えば「貴社の採用ご担当者様」と書くと、丁寧で落ち着いた印象を与えられます。
手紙では文章全体の敬語レベルが見られるため、細部まで注意が必要です。相手の名前がわかっている場合は「○○様」を使用し、会社全体に宛てるときは「貴社」と使い分けてください。
この区別ができると、社会人としてのマナーの高さを示せます。
③送付状や書類提出時
企業に履歴書や書類を送付するときも「貴社」を使います。「貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」といった定型表現を用いると、より丁寧な印象を与えられるでしょう。
封筒の宛名には「御中」を使うのが基本で、「貴社御中」と書く必要はありません。書類を送付する場面での正しい表現選びは、採用担当者に信頼感を与える第一歩です。
④志望動機や自己PR文中
志望動機や自己PRの文章でも「貴社」を使用します。「貴社の事業内容に感銘を受け」「貴社の成長戦略に共感し」と書くのは自然で、敬意を表す表現として適切です。
文章内で繰り返し使うことも多いため、違和感のない位置に挿入しましょう。正しい敬語表現を使える学生は評価が高まる傾向があり、文章の推敲も欠かせません。
⑤オンライン応募フォーム
オンライン応募フォームでも、書面と同じく「貴社」を使うのが基本です。入力欄が少なくても、敬語の基本を崩さない意識を持ちましょう。
「御社」と入力しても間違いではありませんが、書き言葉としては「貴社」の方が丁寧です。デジタルでもマナーを守る姿勢は好印象につながります。
⑥内定承諾書や辞退連絡
内定承諾や辞退の連絡を行う書類やメールでも「貴社」を使用します。「貴社より頂戴した内定を承諾いたします」など、感謝を伝える文章でも格式ある表現が求められますよ。
辞退の連絡時も「貴社のご期待に沿えず申し訳ございません」と書くことで誠意を示せます。重要なやり取りほど、慎重な言葉選びが評価を高めるでしょう。
御社と貴社を使わないケース

就活の場では「御社」「貴社」を多用しますが、必ずしも全ての相手に使うわけではありません。
特定の業種や組織形態に合わせた適切な敬称を知ることで、より自然で失礼のない言葉遣いを身につけられるでしょう。ここでは代表的なケースを解説します。
- 銀行や信用金庫など金融機関
- 病院・クリニック・介護施設
- 省庁・市役所・区役所
- 大学・専門学校・学校法人
- 財団法人・社団法人・協会
- 組合・NPO・その他団体
①銀行や信用金庫など金融機関
金融機関では「御行」「貴行」と表現するのが慣例です。企業向けの「御社」「貴社」ではなく、業界特有の呼称を使うことが求められます。
銀行や信用金庫は組織形態が株式会社であっても、伝統的に「行」を付けた呼称を使用するのが正式とされていますよ。特に履歴書やメールなどで誤用すると、業界研究不足と見なされる可能性が高いです。
面接時には「御行に入行したい」と述べるのが自然でしょう。こうした業界ならではの呼び方を理解することは、就活生の評価を左右する大切な要素です。
②病院・クリニック・介護施設
病院や医療法人には「御院」「貴院」、介護施設には「御施設」「貴施設」を使うのが適切です。
履歴書や志望動機で「御社」と書くと、事業内容や組織の理解が浅い印象を与える恐れがあります。面接では「御院での経験を積みたい」「貴施設の理念に共感した」という表現が好ましいでしょう。
医療や福祉の分野は使命感が重視されるため、言葉遣いひとつで誠意が伝わります。業界ごとの敬称を正しく使い分けることはマナーとして重要です。
③省庁・市役所・区役所
官公庁や役所には「御庁」「貴庁」という呼称を使います。国の省庁や自治体は企業ではないため、「御社」「貴社」を使うのは誤りです。公務員試験や行政関連の就活では特に注意が必要でしょう。
志望動機欄には「貴庁の施策に携わりたい」と書くのが正式で、面接でも「御庁の方針を理解しています」と述べるのが自然です。正しい敬称の使用は、応募者の配慮や知識を示すポイントになります。
④大学・専門学校・学校法人
教育機関には「御校」「貴校」という呼称が一般的です。
特に教職志望や事務職応募など教育分野の就活では、文書や面接での表現に注意が必要です。「御校で教育理念を実現したい」「貴校の特色に共感した」という表現が適切でしょう。
教育関連では丁寧な言葉遣いが評価されやすく、正しい敬称は誠意を示す重要な要素となります。
⑤財団法人・社団法人・協会
公益法人や協会には「御法人」「貴法人」という敬称を使うのが正しいです。これらは企業ではなく公益性を持つ団体であるため、「御社」では違和感を与える可能性があります。
応募書類や面接で適切な表現を選ぶことにより、団体の理念や活動への敬意が伝わるでしょう。例えば「貴法人の研究活動に参加したい」と述べるのが自然です。
法人格や組織形態を理解し、呼称を適切に使い分ける力は社会人としての基本的な素養を示すものです。
⑥組合・NPO・その他団体
組合やNPO法人などには「御組合」「貴組合」「御団体」「貴団体」という表現を使います。活動形態や法人格によって呼び方は変わりますが、「御社」をそのまま使用するのは誤りです。
NPOや市民団体は応募者が少ない場合もあり、丁寧な言葉遣いが評価されることが多いでしょう。面接時には「御団体の理念に賛同した」「貴組合の方針に共感した」と述べるのが適切です。
志望先の性格に合った敬称を選ぶことは、社会人としての基礎力を示す重要な要素です。
御社と貴社を間違えた時の対処法

就活での言葉遣いの誤りは避けたいものですが、万一「御社」と「貴社」を間違えてしまった場合でも、適切な対応をすれば印象を回復できます。
ここでは状況ごとの訂正方法や対応のコツ、ミスを減らすための工夫を解説します。
- 会話中に気付いた場合の訂正方法
- 面接時の訂正と謝罪方法
- 提出前の書類修正方法
- 提出後の書類訂正・謝罪方法
- メールやメッセージでの訂正方法
- 次回以降のミス防止策
①会話中に気付いた場合の訂正方法
話している最中に「御社」「貴社」の誤りに気付いたら、すぐに訂正しましょう。「先ほどは○○と申しましたが、正しくは△△です」と言い直すと誠実さが伝わります。
長く謝罪を続ける必要はなく、簡潔に対応すれば問題ありません。対応の速さと冷静さが評価される場面でもあるため、焦らず落ち着いて言葉を選ぶことが大切です。
日頃から練習しておくと、自然に訂正できるでしょう。
②面接時の訂正と謝罪方法
面接中の言い間違いは、会話の切れ目で「失礼いたしました。正しくは○○です」と一言添えて訂正してください。誠意を持った態度は面接官に好印象を与えます。
言い訳をせず、訂正した後はスムーズに話を進めることを意識しましょう。小さな言葉のミス自体は大きな問題にならないことが多く、むしろ対応の仕方を見られています。
丁寧で落ち着いた対応を心掛けることが重要です。
③提出前の書類修正方法
エントリーシートや履歴書などに誤りを見つけたら、必ず提出前に修正しましょう。オンライン提出の場合は正しい表現に書き換え、紙の書類なら新しく清書するのが基本です。
修正テープや訂正印は避け、誤字や言葉の誤用は注意不足と受け取られる恐れがあるため、印刷前に複数回チェックを行うと安心ですよ。家族や友人に確認を依頼するのも有効な方法です。
④提出後の書類訂正・謝罪方法
提出済みの書類に誤りがあったときは、できるだけ早くメールや電話で正しい内容を伝えてください。遅れても誠実な対応を心掛ければ印象回復のきっかけになります。
「このたびは大変失礼いたしました。提出済みの書類の中で○○と記載しましたが、正しくは△△です」と明確に伝えると良いでしょう。その後に修正版を送付すれば、迅速さと丁寧さが評価されます。
⑤メールやメッセージでの訂正方法
メールの文章で誤りに気付いたら、早めに訂正文を送るのが基本です。「先ほどのメールで○○と記載しましたが、正しくは△△です」と簡潔に訂正してください。
件名に「訂正のご連絡」と入れ、誤字や誤用を防ぐため複数回見直す習慣をつけましょう。
⑥次回以降のミス防止策
同じミスを繰り返さないためには、普段からの準備が重要です。「御社」「貴社」の使い分けを音読で練習し、書き言葉と話し言葉の違いを体で覚えると自然に使えるようになります。
面接や書類作成前に第三者のチェックを受けるのも効果的です。過去のミスを振り返り、似た状況での対応方法を考えておけば自信を持って臨めます。
日頃から丁寧な準備を習慣化することが、言葉遣いの精度を高める近道です。
御社と貴社を間違えた場合の影響

就活で御社と貴社を間違えると、採用担当者の印象や評価に影響を与える可能性があります。
ここでは評価やマナー、業界ごとの傾向まで詳しく解説します。
- 評価への影響の有無
- マナー面での印象低下
- 採用担当者視点の評価
- 業界による影響の差
- 面接と書類での影響の違い
- 言葉遣い評価の重要性
①評価への影響の有無
御社と貴社を間違えたからといって、必ずしも致命的な評価にはなりません。しかし、就活は細部にまで注意が求められる場面が多いため、小さなミスも印象に残る場合があります。
特に第一志望の企業や競争率が高い業界では、正確な表現が重視されるでしょう。事前に応募先での言葉遣いを確認し、面接練習の中で自然に使えるよう準備してください。
挨拶やメール文面なども丁寧に見直すことで、余計な減点を防ぐことができます。
②マナー面での印象低下
言葉遣いを誤ると、社会人マナーが十分でないと判断されることがあります。ビジネスの現場では、丁寧な言葉遣いは信頼関係の基本です。
面接官は話し方や文章の細部まで見ており、緊張による言い間違いは理解される場合もありますが、何度も繰り返すと準備不足と受け取られかねません。
誤りを減らすためには、模擬面接や第三者のチェックを受け、話し言葉と書き言葉の切り替えを習慣化しておくことが効果的です。
③採用担当者視点の評価
採用担当者は応募者の表現力や礼儀を見ています。そのため御社と貴社の誤用が多いと、指示理解や顧客対応力に不安を感じられる可能性も。
ただし、多くの企業では一度のミスで不合格になることは少なく、全体的な態度ややり取りの印象で評価されることがほとんどです。
間違えた際は落ち着いて訂正し、誠実さを示すことが信頼につながります。
④業界による影響の差
この言葉遣いの誤りに対する評価は、業界の文化によって異なります。金融や商社など顧客対応が多い業界では、敬語の正確さが重視されるので、ミスがないように気をつけましょう。
一方で、ITやクリエイティブ業界はスキルや柔軟な発想を優先することも多く、言葉遣いの影響はやや軽い場合があります。ただし、どの業界でも最低限のマナーは必須です。
応募先の文化を調べ、適切な表現を準備しておきましょう。
⑤面接と書類での影響の違い
面接では誤りをしてもその場で訂正できるため、深刻な影響は出にくいです。むしろ冷静に訂正できれば、誠実さが評価されることもあります。
一方、履歴書やESなどの書類は修正の機会がないため、誤りはそのまま印象に残ってしまいますよ。提出前には複数人でチェックし、誤字脱字や敬語の誤用を防ぐ体制を整えることが重要です。
場面ごとに求められる慎重さの違いを理解し、しっかり対策をしましょう。
⑥言葉遣い評価の重要性
言葉遣いの正確さは、社会人としての信頼性や注意力を示す要素です。御社と貴社を適切に使い分けることで、細部に気を配れる人物という印象を与えられます。
日常的に敬語を意識し、メールや会話で繰り返し練習することが自然な表現習得への近道です。こうした積み重ねは、内定後の職場での信頼構築にもつながるでしょう。
就活で押さえておきたい言葉遣いの基本

就職活動では第一印象を左右する言葉遣いが重要で、正しく使えないと誠意が伝わらない場合や社会人マナーを理解していないと見なされる恐れがあります。
ここでは、就活で頻繁に登場する敬語や表現を整理し、信頼される言葉遣いを身につけるための基本を解説します。
- 一人称の使い方
- 尊敬語と謙譲語の違い
- 二重敬語の避け方
- 「御中」と「様」の使い分け
- クッション言葉の正しい使い方
- 就活メール・電話で避ける表現
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
①一人称の使い方
面接やビジネスメールでは「私」を使うのが最も無難です。「僕」や「俺」は親しげな印象を与えるため、就活の場には適しません。
普段から使い慣れていないと、緊張した時に口をついて出てしまうこともあるでしょう。エントリーシートや履歴書でも「私」で統一することで文章が整います。
常に「私」を使うことを意識しておくと安心です。
②尊敬語と謙譲語の違い
尊敬語は相手を立てる表現で、謙譲語は自分をへりくだる言葉です。「申す」は謙譲語なので「申されます」は二重敬語となり不適切なので代わりに「おっしゃいます」を使うのが正しいでしょう。
就活では正しい言葉遣いが相手への敬意を表す行動となります。普段から適切な敬語表現を練習しておくと安心です。
③二重敬語の避け方
二重敬語は丁寧すぎる表現として不自然に聞こえるため避けましょう。「お伺いさせていただきます」や「お越しになられる」は代表的な例です。「伺います」「お越しになります」と言い換えると自然ですよ。
正しい表現を使えるかどうかは日本語力の指標にもなります。相手への敬意を示すためには適度な丁寧さが必要です。
④「御中」と「様」の使い分け
宛名では会社名や部署には「御中」、個人名には「様」を使います。「株式会社〇〇御中」は正しいですが「〇〇様御中」は誤りです。
採用担当者の氏名が分かる場合は「〇〇様」、部署宛の場合は「〇〇部御中」と記載します。正しい宛名の書き方は細部まで配慮できる印象を与え、マナーが身についていることを示します。
⑤クッション言葉の正しい使い方
クッション言葉はお願いや依頼を柔らかく伝えるために使います。「お手数ですが」「差し支えなければ」「恐れ入りますが」などが代表例です。使いすぎると文章が回りくどくなるので注意しましょう。
メールや電話で一言添えるだけで印象が変わります。状況に応じて自然に使えるよう練習すると良いでしょう。
⑥就活メール・電話で避ける表現
カジュアルな言い回しや学生同士の表現は避けた方が良いです。「すみません」は「申し訳ございません」、「了解しました」は「承知いたしました」に言い換えます。
電話で「もしもし」を使うのも不適切です。正しい表現を習慣づけることで、メールや電話でも丁寧な印象を与えられます。小さな積み重ねが評価を左右します。
就活で押さえるべき敬語表現の要点

御社と貴社の違いを理解することは、就活生にとって社会人としての基本マナーを身に付ける第一歩です。
御社は話し言葉、貴社は書き言葉として使い分けるのが一般的であり、状況や媒体によって適切な敬語を選ぶ姿勢が重要ですよ。
面接やメール、書類などで正しく使えると、企業に対して誠実さや丁寧さを印象付けられるでしょう。
金融機関や官公庁など、御社・貴社を使わないケースも理解しておく必要があります。さらに、誤用してしまった場合の訂正方法を知っておけば、焦らず冷静に対応できるでしょう。
就活で信頼を得るためには、基本的な言葉遣いの知識を押さえ、状況に応じた表現力を磨くことが不可欠です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。