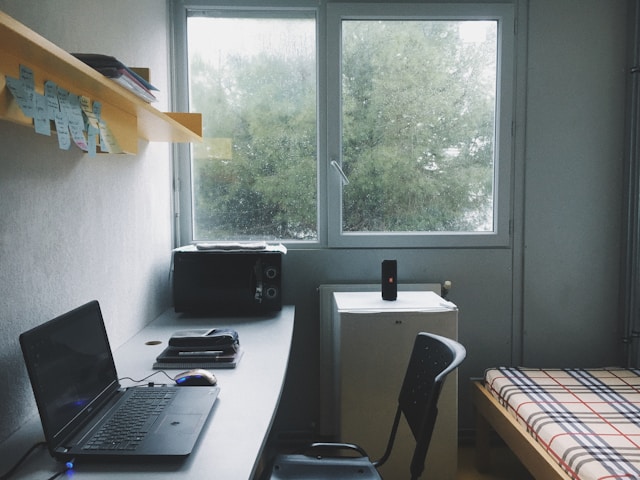休職中のボーナス(賞与)はどうなる?支給ルールと注意点を徹底解説
体調不良や育児、介護などで休職を検討するとき、賞与の扱いがどうなるのか不安に思う人は少なくありません。ボーナスは生活や家計に直結する大切な収入だからこそ、制度やルールを正しく理解しておきましょう。
この記事では、休職中のボーナス(賞与)の支給ルールと注意点をわかりやすく整理しました。疑問を解消して、安心して今後の働き方を考える参考にしてください。
高年収企業を狙うための必須アイテム
- 1高年収×ホワイト企業100選
- 最短3分で、年収トップクラスの企業リストをGETでき、ESを出すべき企業が明確になる
- 2ES自動作成ツール
- 志望動機・自己PRの「土台」を短時間で作成できる
- 3志望動機テンプレシート
- 年収トップクラス企業に評価される志望動機が、5つの質問に答えるだけで完成
- 4赤ペンESで志望動機を添削
- 年収上位企業が求める基準でプロが添削。あなたの志望動機を、高収入企業の人事が評価するレベルに引き上げます。
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 実際に高年収企業で問われた質問を100問厳選。深掘りされるポイントを先回りして把握し、年収上位の選考突破を手助けします。
▼60秒で診断ツール▼
| ⭐️適職診断 あなたの志向・価値観から、高年収企業の中で「どの職種・領域を狙うべきか」がわかる ⭐️強み診断 あなたの経験・思考特性をもとに、高年収企業で評価されやすい「強み」が言語化される。 |
休職制度とは?休職中のボーナスとの関係

就活生にとって「休職」という言葉はまだ先のことに感じるかもしれませんが、社会に出るとさまざまな理由で休職する可能性があります。
その際に「ボーナスはどうなるのか」と不安に思う人も多いでしょう。ここでは休職制度とボーナスの関係を整理し、将来の働き方やキャリアを考えるヒントにしてください。
- 私傷病(病気・けが・メンタル不調)による休職の場合
- 産休・育休・介護など家庭やライフイベントによる休職の場合
- 会社都合(業務都合・配置転換など)による休職の場合
- 懲戒・起訴・公職就任など公的理由による休職の場合
①私傷病(病気・けが・メンタル不調)による休職の場合
社会人になると心身の不調で長期的に働けなくなることがあります。
私傷病による休職では、多くの企業が就業規則で一定の条件を定めており、その期間は基本給やボーナスの算定に影響することが多いでしょう。
特に査定期間中に出勤日数が不足するとボーナスが減額されたり、支給対象外となる可能性もあります。
ただし短期間の休職であれば勤務実績に応じて一部支給される場合もあり、必ずしもゼロになるとは限りません。
早めに人事部門に確認しておくことで将来の見通しが立ちやすくなります。就活生は福利厚生や休職制度の有無を企業選びの指標にすると安心です。
②産休・育休・介護など家庭やライフイベントによる休職の場合
産休や育休、介護休暇など家庭やライフイベントに関わる休職は、労働基準法や育児・介護休業法により権利として保障されています。
このためボーナスの扱いも私傷病休職とは異なる規定になっていることが多く、特に公務員や大手企業では一定割合を支給する仕組みが整っています。
一方で査定期間との兼ね合いや勤務実績によって減額されることもあるため、取得前に確認しておくことが大切です。
将来的にライフイベントを迎える可能性のある就活生は、こうした制度が整備されているかを企業選びの重要なポイントにしてください。
③会社都合(業務都合・配置転換など)による休職の場合
会社の業務都合や配置転換、経営上の理由によって一時的に休職扱いとなるケースもあります。この場合、社員本人に責任がないため、ボーナスの算定でも一定の配慮がされることがあります。
ただし、会社規模や就業規則によって対応は大きく異なり、同じ「会社都合の休職」であっても支給の有無や金額に差が出ることがあります。
就活生は、労働契約書や就業規則で「会社都合の休職」や「休業補償」についてどのように定められているか確認する習慣を持っておくと後のトラブル防止につながります。
④懲戒・起訴・公職就任など公的理由による休職の場合
懲戒処分や起訴、公職就任など特別な事情による休職の場合は、ほとんどの企業でボーナス支給対象外とされています。
特に懲戒・起訴など本人責任のあるケースでは、就業規則により給与や賞与が大幅に制限されたり、停止されるのが一般的です。
一方、公職就任などの一時的な職務離脱の場合は、企業によっては復職を前提とした休職制度が整っており、一定条件のもとでボーナスが部分的に支給されることもあります。
休職中にボーナスが支給される基本ルール

就活生が入社後に意外と知らないのが「休職中のボーナスの扱い」です。休職中でもボーナスが支給されるかどうかは、雇用形態や就業規則によって大きく変わります。
ここでは民間企業・公務員・教員・非正規・派遣労働者といった立場別に、支給ルールの基本を解説し、将来の備えにしてください。
- 民間企業の場合
- 公務員(国家・地方)の場合
- 教員(公立・私立)の場合
- 非正規(契約社員・パート・アルバイト)の場合
- 派遣労働者の場合
①民間企業の場合
民間企業では、ボーナスの支給は法律上の義務ではなく、会社が任意で決定します。就業規則に「賞与あり」と明記されていれば、休職中でも一定条件を満たせば支給されることがあります。
たとえば査定期間の出勤率が規定以上ある、有給休暇で休職期間をカバーできるなどです。ただし長期休職では出勤日数が不足し、減額や不支給となることも珍しくありません。
就活生は企業説明会や採用ページで就業規則や福利厚生を確認し、休職時の賞与基準がどのように定められているか把握しておくと安心でしょう。
②公務員(国家・地方)の場合
公務員の場合、ボーナスは期末手当や勤勉手当として支給され、給与法や条例に基づいて決まります。産休・育休など法律で認められた休職期間中は一定割合が支給されることが多い一方、
私傷病や懲戒による休職では減額や不支給になることがあります。休職期間が長くなると査定への影響が出るため、復職のタイミングや勤勉手当の算定期間を意識して行動することが重要です。
就活生も、公務員志望であれば自治体や省庁ごとの休職制度や賞与支給の条件を調べておくと将来の働き方の選択に役立ちます。
③教員(公立・私立)の場合
教員の場合は、公立か私立かで制度が異なります。公立学校教員は地方公務員として扱われるため、期末手当や勤勉手当が基準となり、休職理由や期間によって支給額が変動します。
産休・育休中は一定割合が支給される場合が多い一方、私傷病休職や長期の欠勤では減額や支給停止になることもあります。
私立学校教員の場合は民間企業に近く、学校法人ごとの規程に従うことになります。就活生が教育業界を志望する際には、勤務先ごとの休職制度や賞与の取り扱いを事前に把握しておくと安心です。
④非正規(契約社員・パート・アルバイト)の場合
非正規雇用では、ボーナスの支給が必ずしもあるとは限りません。支給がある場合でも寸志レベルだったり、勤務実績や出勤率に応じて決定されるなど条件が厳しい傾向です。
ただし「同一労働同一賃金」の原則により、合理的な理由なく正社員だけに賞与を支給することは制限されるため、条件を満たせば受け取れる可能性があります。
休職中は査定期間や勤務日数が不足しやすく、支給対象から外れることも多いため、自身の雇用契約や就業規則を必ず確認してください。
⑤派遣労働者の場合
派遣労働者の場合、ボーナスの有無は派遣元(派遣会社)の就業規則や賃金規程によって決まります。派遣先から直接支払われるわけではなく、派遣元が賞与制度を持っているかどうかがポイントです。
正社員型派遣など一部では賞与制度が整備されている例もありますが、休職中は勤務実績が不足し不支給になるケースが多いです。
就活生は派遣という働き方を視野に入れる場合、派遣会社がどのような休職制度や賞与支給の基準を持っているか調べておくことが将来の安心につながります。
休職中でもボーナスがもらえるケース

休職中でもボーナスを受け取れるかどうかは、多くの就活生にとって気になるポイントです。実は会社のルールや勤務実績の扱いによっては支給される可能性があります。
ここでは就業規則、査定期間中の勤務実績、有給休暇の使い方など、ボーナスがもらえるケースを解説します。
- 就業規則で休職中のボーナス支給が明記されている場合
- ボーナス査定期間に勤務実績がある場合
- 有給休暇の利用で勤務期間に該当する場合
①就業規則で休職中のボーナス支給が明記されている場合
会社の就業規則に「休職中でも一定条件で賞与を支給する」と書かれていれば、その条件に当てはまる限りボーナスを受け取れる可能性があります。
たとえば短期の休職や、勤続年数・評価実績が十分にある場合などです。多くの人が休職すると自動的に不支給になると思いがちですが、実際は会社ごとの規程により扱いは異なります。
就活生は入社前に就業規則を確認し、休職時の賞与条件を把握しておくと安心でしょう。
②ボーナス査定期間に勤務実績がある場合
ボーナスは通常、一定の査定期間に基づいて計算されます。そのため休職中であっても、査定期間中に一定以上の勤務実績があれば支給されるケースがあります。
例えば4月から9月が査定期間なら、その間の勤務率や貢献度に応じてボーナスが算出される仕組みです。
勤務日数が多いほど支給額が維持されやすく、逆に勤務日数が少ないと減額や不支給になることもあります。就活生は、査定期間の考え方を理解しておくと将来のキャリア設計に役立つでしょう。
③有給休暇の利用で勤務期間に該当する場合
有給休暇を使うことで、休職していても「出勤扱い」となり勤務期間に含まれることがあります。この場合、ボーナスの査定期間に欠勤扱いが減るため、支給額を維持しやすくなるのが特徴です。
ただし、有給休暇の残日数や使い方には制限があるため、長期休職では十分にカバーできない場合があります。
就活生は、有給休暇がどのように査定に反映されるかを知っておくことで、将来の働き方の選択肢を広げられるでしょう。
休職中にボーナスがもらえないケース

休職中は必ずしもボーナスが支給されるわけではありません。期間や理由、会社の状況によっては減額や不支給になることがあります。
ここでは長期休職、無給休職、査定期間との重なり、そして会社業績の悪化といった、もらえないケースを整理して解説します。
- 長期休職の場合
- 無給休職の場合
- 休職が査定期間と重なる場合
- 会社業績が悪化している場合
①長期休職の場合
休職が長期に及ぶと、ボーナスの算定基準から外れることがあります。多くの会社では査定期間中に一定以上の勤務日数を求めており、長く休むことで出勤率が条件を満たさなくなるためです。
また、長期休職中は評価対象外となることも多く、支給されても大幅に減額される可能性があります。
就活生は、福利厚生欄だけでなく就業規則の細かい条件まで確認し、長期休職時にどう扱われるか把握しておくと安心でしょう。
②無給休職の場合
無給休職になると、給与だけでなくボーナスの支給資格も失うケースが多いです。
多くの企業では「賃金が支払われていない期間は賞与の対象外」と定めているため、無給であること自体が支給条件に抵触します。
ただし、一部の会社では勤続年数や過去の評価を考慮して、無給期間でも一部支給することもあります。就活生は、休職時に給与の有無がボーナスにどう影響するか確認しておくと後悔しにくいでしょう。
③休職が査定期間と重なる場合
ボーナスは通常、半年や1年など一定の査定期間で計算されます。休職期間がこの査定期間と重なると、出勤率や勤務実績が不足し支給額が減ったり、支給対象外になることがあります。
短期の休職であっても影響が出る場合があるため、査定期間の仕組みを理解しておくことが重要です。
就活生は、企業のボーナス支給ルールや査定期間を事前に知ることで将来の働き方を計画しやすくなるでしょう。
④会社業績が悪化している場合
会社の業績が悪化している場合、休職中かどうかにかかわらずボーナスが減額されることがあります。
特に賞与が「業績連動型」となっている企業では、業績が下がると全社員に影響が及ぶため注意が必要です。
また、休職中の社員は評価対象外として優先的に削減されることもあります。就活生は企業選びの際、過去数年の業績推移や賞与制度の安定性をチェックしておくと将来的な不安を減らせるでしょう。
休職中のボーナス支給と傷病手当金の扱い

休職中にボーナスが支給されると、傷病手当金に影響があるのか疑問に思う人も多いでしょう。
実は健康保険法上、通常のボーナスは「報酬」に含まれないため、原則として減額や支給停止にはなりません。
支給には「業務外の病気やけがであること」「労務不能であること」「3日以上連続で休業し4日目以降も働けないこと」「休業期間に給与が支払われていないこと」などの条件があります。
このうち、ボーナスは「3か月を超える期間ごとに支払われるもの」とされており、原則として報酬に含まれません。
そのため、年2回や年3回のボーナスであれば、休職中に受け取っても傷病手当金は減額されないのが一般的です。
就活生は、将来休職する可能性を見据え、会社の賞与制度や支給回数を確認しておくことで、安心して働ける環境を選びやすくなるでしょう。
休職中のボーナス支給と労働者災害補償保険の扱い

休職中にボーナスが支給された場合、労働者災害補償保険(労災保険)の給付に影響があるのか気になる人も多いでしょう。
労災保険は、労働者が業務上のけがや病気で働けなくなった場合に休業補償給付を支給します。
給付額は原則として「給付基礎日額(過去3か月の平均賃金)」をもとに計算されるため、休職中にボーナスが支給されても、すぐに給付が減額されることはありません。
ただし、労災保険の算定基準にはボーナスが含まれないため、休職中の賞与支給が給付額に上乗せされることもない仕組みです。
一方、休業補償給付を受けている間に会社が「休業補償金」や「給与の一部」を支払った場合は、給付との調整が行われる可能性があります。
就活生は、労災保険と会社の補償の違いを理解しておくことで、将来休職したときに混乱を避けられるでしょう。
休職中のボーナスに関するよくある質問

休職中やその前後は、ボーナスの支給がどうなるのか気になる人が多いでしょう。退職予定や復職直後など、状況によって扱いが異なります。
ここでは、就活生が将来の働き方を考えるうえで知っておきたい代表的な疑問を取り上げます。
- 退職予定の場合のボーナスはどうなる?
- 休職前に支給されたボーナスを返還する必要はある?
- 賞与の支給前に休職を開始した場合はどうなる?
- 休職中に転職活動してもボーナスはもらえる?
- 復職後の最初のボーナスはどうなる?
①退職予定の場合のボーナスはどうなる?
退職予定であっても、ボーナスの支給対象期間に在籍していたかどうかで扱いが決まります。
多くの会社では「支給日に在籍していること」を条件としており、その日まで在籍していれば受け取れることが多いです。
一方で、在籍要件がない会社では査定期間の実績で判断される場合もあります。内定先の規定を早めに確認しておくと安心でしょう。
②休職前に支給されたボーナスを返還する必要はある?
原則として、休職前に支給されたボーナスを返還する必要はありません。ボーナスは過去の勤務実績に対する評価として支払われるものだからです。
ただし、特別な契約や返還条項がある場合には例外となることもあります。支給時の条件をよく確認してください。
③賞与の支給前に休職を開始した場合はどうなる?
賞与の支給前に休職に入った場合、その期間が査定に影響することがあります。たとえば勤務日数や実績に応じて減額される、あるいは全額支給されないこともあります。
会社の就業規則や査定基準を把握しておくことが重要です。
④休職中に転職活動してもボーナスはもらえる?
休職中に転職活動をしても、ボーナスの支給条件を満たしていれば受け取れる可能性があります。ただし、転職活動そのものが問題になることもあるため、就業規則や会社の方針に注意してください。
⑤復職後の最初のボーナスはどうなる?
復職直後のボーナスは、休職期間中の勤務実績が少ないため減額されることが多いです。査定対象期間や評価方法により支給額が変動します。
復職を予定している人は、支給時期や算定期間を事前に確認しておくとよいでしょう。
休職中ボーナスの仕組みと注意点

休職中のボーナスは、制度や立場、在籍条件によって支給の可否が変わります。
まず、休職制度には私傷病や産休・育休、会社都合、公的理由など多様なパターンがあり、それぞれのケースで扱いが異なります。
さらに民間企業・公務員・教員・非正規・派遣など雇用形態によっても基準が分かれます。
就業規則に休職中のボーナス支給が明記されている、査定期間に勤務実績がある、有給休暇を使って勤務期間に該当する場合などは支給されやすいでしょう。
傷病手当金や労災保険への影響も踏まえ、自分の立場と規定を事前に確認しておくことが安心につながります。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。