公務員に有利な学部はある?学部ごとの公務員職との関係性も紹介
公務員を目指すなら、どの学部を選べばいいのだろう…」と迷っている人も多いのではないでしょうか。
行政事務職のように学部を問わず挑戦できる職種がある一方で、技術系や資格職は学部選びが合否や採用に直結します。
実際には「学部による有利不利」だけでなく、「どんな職種を目指すか」という視点を持つことが重要になってきます。
とはいえ、情報が断片的だと判断が難しく、結局どこから考えればいいのか分からなくなってしまいがちです。
そこで本記事では、公務員の職種ごとに有利とされる学部や、進学後の学びをどのように公務員試験へつなげるかを徹底的に解説していきます。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
公務員に学部は関係ある?基本的な考え方

「公務員に採用されにくい学部もあるのかな?」と不安に思う就活生も多いでしょう。結論から言えば、多くの公務員職では学部による制限はほとんどなく、どの学部からでも目指すことができます。
ただし、すべての職種がそうとは限りません。たとえば技術系の職種では、理系学部の専門知識が求められることがあります。
また、資格や免許が必要な仕事については、学部や履修内容が条件になるケースもあります。とはいえ、公務員試験では筆記や面接が評価の中心です。
つまり、学部よりも「どれだけ対策を積み重ねたか」「どれほど明確な志望動機を持っているか」が重要になるということです。
自分の興味がある分野や将来のイメージをもとに職種を選んで情報を集め、目標に向けて戦略的に動くことが大切です。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
公務員の職種とは?

就職先として安定した人気を誇る公務員ですが、その職種は多岐にわたります。
ここでは、学部による有利・不利が気になる就活生に向けて、代表的な職種の特徴を解説します。各分野の仕事内容や求められるスキルを知ることで、自分の学部との相性を判断しやすくなるでしょう。
- 行政事務系公務員
- 技術系公務員
- 公安系公務員
- 福祉・心理系公務員
- 資格・免許職
① 行政事務系公務員
行政事務系の公務員は、どの学部の出身でも目指せるオールラウンドな職種です。役所の窓口業務から政策立案まで、担当する業務の幅が広いのが特徴といえるでしょう。
学部による差が不安に感じられるかもしれませんが、採用試験の内容は共通しているため、努力次第で十分に合格を狙えます。
専攻の内容よりも、論理的な思考力や相手に合わせた対応力が問われる場面が多い職種です。人気が高く競争も激しいため、早い段階から試験対策を進めておくと安心です。
どの学部でも挑戦できる反面、準備不足では太刀打ちできない可能性があるため、油断は禁物です。
② 技術系公務員
技術系の公務員は、理系の知識や専門性を活かせる職種です。土木、建築、電気、機械、情報などの分野でそれぞれの専門に応じた採用が行われています。
たとえば土木職では道路や橋などの設計・維持管理、建築職では公共施設の耐震設計や保全業務を担います。これらは大学で学ぶ専門知識が、そのまま採用試験や実務に直結していることが多いです。
文系出身者では受験資格が得られない職種もあるため、理系の学生にとっては大きなアドバンテージになるでしょう。専門科目の勉強量は多くなりますが、行政職より競争率が低めな点は見逃せません。
③ 公安系公務員
公安系公務員には、警察官や消防士、自衛官などがあります。これらの職種は、学部よりも適性や体力、強い使命感が重視される点が特徴です。
試験では学力だけでなく体力試験や面接評価も大きな比重を占めており、受験準備の内容が他の職種とはやや異なります。体育会系の経験があれば、それが選考でプラスに働くこともあるでしょう。
文系・理系を問わず挑戦できますが、心理的負担の大きい業務が多いため、自分の適性をよく見極めて志望を決める必要があります。信頼性や人柄が重視されるため、学歴や学部による差はほとんどありません。
④ 福祉・心理系公務員
福祉・心理系の公務員は、社会福祉士や臨床心理士といった資格を活かせる専門職です。福祉事務所や児童相談所などで、生活に困る人々の相談支援にあたります。
この職種は学部との関連性が高く、福祉系や心理系の学部出身であることが受験資格の前提となる場合が多いです。大学で指定科目を履修しておかなければ、そもそも試験を受けられないケースもあります。
知識に加えて共感力や傾聴力が求められるため、人と接する仕事が得意かどうかも重要な判断材料になるでしょう。将来この職種を目指すなら、早めに必要な資格や履修科目を確認しておくことが大切です。
⑤ 資格・免許職
資格・免許職は、保健師・薬剤師・獣医師・栄養士・教員など、特定の国家資格を持つ人だけがなれる職種です。これらは大学の専門課程を修了していないと受験資格が与えられません。
たとえば薬剤師なら薬学部の6年制課程を修了し、国家試験に合格する必要があります。進路が早期に決まっている分、途中での方向転換が難しいという側面もあります。
ただし、その分野の専門性が高いため、職場での役割や待遇は非常に安定している傾向があります。
自分の学部で取得可能な資格があるかどうかを確認しておくことが、将来の選択肢を広げるカギになるでしょう。
行政事務職はどの学部でもなれる

行政事務職は、公務員の中でも多くの採用が行われる職種です。行政事務職は、特別な専門知識を必要とする職種ではなく、むしろ一般的な能力が重視されます。
たとえば、法律や経済学の知識よりも、コミュニケーション能力や問題解決力、事務処理能力が求められます。また、面接や筆記試験で学部が評価基準に影響することは、あまりありません。
そのため、学部によって大きな差がつくことはなく、どの学生でも十分に行政事務職を目指すことができます。
ただし、行政事務職は専門知識よりも実務能力が重要です。そのため、資格や専門知識よりも、実際の業務に対応できるスキルを磨くことが成功のカギとなります。
試験対策や面接準備においては、基本的な教養科目や時事問題に関する知識を深めておくことが大切です。
技術職の公務員に有利な学部とは
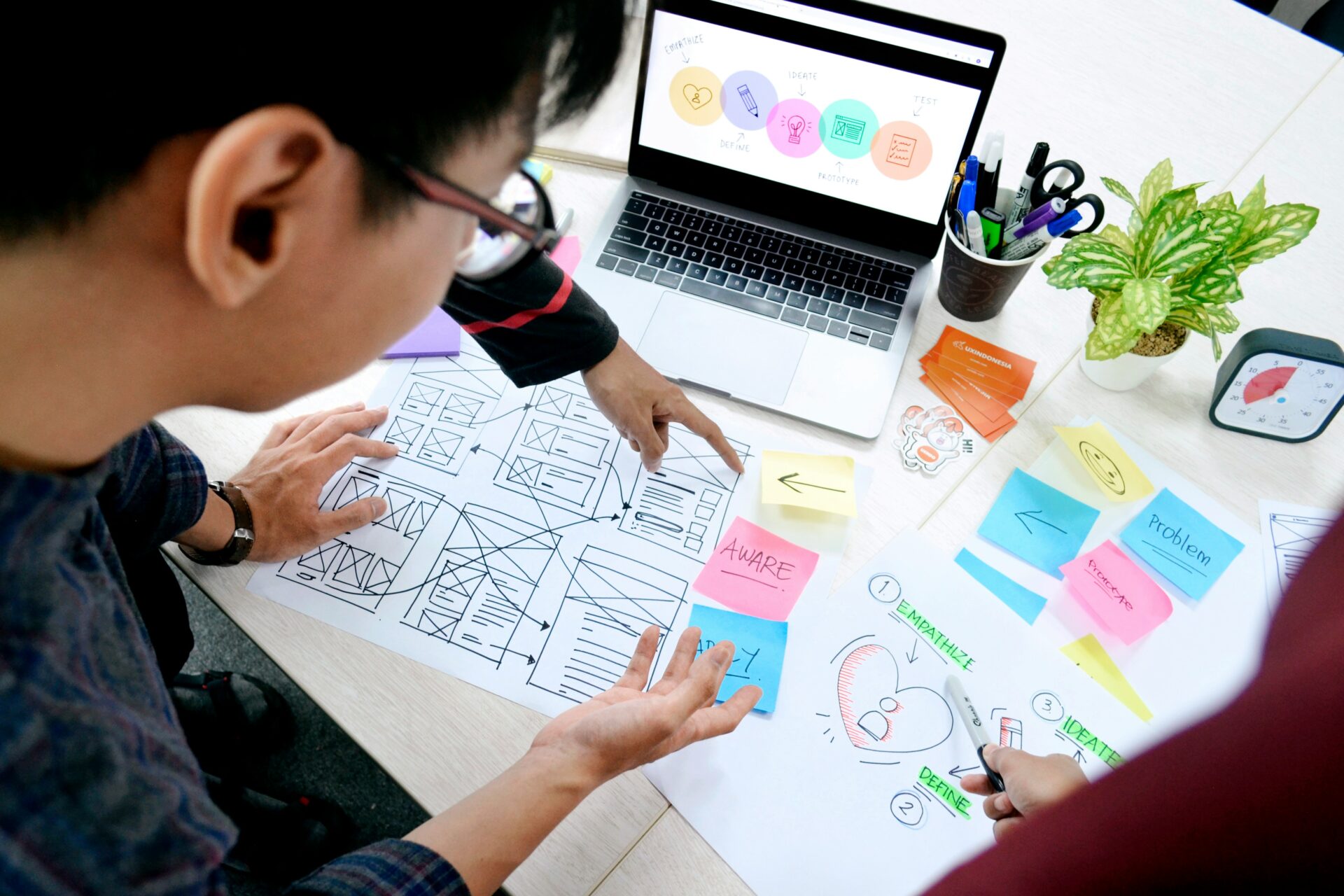
技術職の公務員を目指すうえで、学部の選択は合否や職種選びに大きく関わってきます。
行政職とは異なり、技術系の職種では理系学部出身者が求められることが多く、大学で学んだ知識が試験内容や実務と深く結びついています。
ここでは、どの学部がどのような技術職と相性が良いのかを紹介し、それぞれの特徴や注意点も解説していきます。
- 工学部
- 農学部
- 理学部
- 薬学部・医学部
① 工学部
技術系公務員の中でも、工学部は最も採用枠が多く、幅広い分野で活躍しやすい学部です。土木・建築・機械・電気などのインフラ系職種では、ほぼすべてが工学部出身者を対象としています。
大学で学んだ専門知識がそのまま試験や実務に直結するケースが多いため、有利に働くでしょう。
ただし、「理工系ならどれでもよい」と思い込んでしまうと、自分の専攻と職種とのミスマッチが生じる可能性があります。
たとえば化学系の専攻で土木職を目指すと、試験範囲のギャップに苦労するかもしれません。大学1〜2年のうちから志望職種に合った専攻を選んでおくことが重要です。
工学部出身者は専門性が強みになる一方で、志望動機や社会的視点の説明をおろそかにすると、面接などで印象が薄れてしまうため注意してください。
② 農学部
農学部は、あまり知られていませんが技術職の公務員として適性が高く、専門性を活かせる職種が数多くあります。
農業職・林業職・水産職といった分野では、農学部で学ぶ生態系や土壌、作物管理の知識が非常に役立ちます。自治体によっては獣医職や環境職も、農学部出身者が活躍する場として知られています。
一方で、農学部はカバーする分野が広いため、専攻によって受験可能な職種が変わってくる点には注意が必要です。
「農学部ならどの職種でも応募できる」と考えてしまうと、進路選択の幅が狭まる可能性もあります。大学入学後は、自治体の採用情報や受験要件を早い段階から確認する習慣を持っておくと安心です。
実務では現場に出る機会も多いため、体力や環境への適応力も求められるでしょう。
③ 理学部
理学部出身者は、化学職や物理職、環境分析職など「理科系」の専門職で公務員として活躍できます。
国家公務員試験や地方上級試験では、化学・物理・数学といった理学的知識が問われるため、大学で基礎をしっかり固めておくと試験対策にもなります。
ただし、理学部は理論重視の傾向があるため、実務とのギャップに戸惑う人も少なくありません。また、採用枠は工学部に比べて狭いため、希望の職種や自治体が限られることもあります。
理学部で学んだ知識を活かすには、「研究が好きだから」だけではなく、公務員としての使命感や社会貢献の意識を持って臨むことが大切です。
面接などでは、そうした視点を自分の言葉で語れるよう準備しておくとよいでしょう。
④ 薬学部・医学部
薬学部や医学部は、専門免許や国家資格を前提とした技術系公務員として重要な役割を担っています。
薬剤師免許を活かせる薬剤職、医師免許が必要な保健医療系公務員などが代表的で、保健所や厚生労働省、自治体の保健センターでの勤務が主な活躍の場です。
学業と国家試験、公務員試験を同時にこなす必要があるため、スケジュール管理と体力の両方が求められます。
また、医療系の進路では「民間病院に行くのが当たり前」といった風潮もあるため、公務員という選択をする理由や動機を明確にしておくことが大切です。
待遇面だけでなく、地域医療や保健行政への関心をしっかり持っていることが、合格への近道になるでしょう。
資格・免許が必要な公務員職と学部の関係

公務員として働くためには、いくつかの資格や免許が必要な職種があります。これらの職種において、どの学部を選んでいるかが影響する場合もあります。
特に、技術職や専門職など、学部が重要な要素となることが多くあります。しかし、すべての公務員職において学部が絶対に関係しているわけではありません。
ここでは、資格や免許が求められる公務員職種と、それに関連する学部選びについて解説します。
- 医師
- 看護師
- 薬剤師
- 教員
- 司法書士
- 公認会計士
- 社会福祉士
- 司法警察職
- 環境技術職
- 労働基準監督官
① 医師
医師は、医師免許が必要な職業であり、医師免許を取得するためには医学部に進学し、大学で必要な学びを積むことが求められます。
学部選びは非常に重要で、医学部以外の学部では医師になることはできません。
② 看護師
看護師も資格が必要な職種であり、看護学部などの専門的な学部を卒業することが求められます。
看護師免許を取得するためには、看護学部での学びが必要となり、他の学部から転職することは基本的には難しいです。
③ 薬剤師
薬剤師も薬学部に進学し、薬剤師免許を取得する必要があります。薬学部を卒業し、所定の試験に合格することで、薬剤師として働くことができます。薬剤師免許は他の学部から取得することはできません。
④ 教員
教育職も資格が必要な職業であり、教員免許を取得するためには、教育学部や教職課程を修了する必要があります。
特に小学校、中学校、高校の教員として働くためには、各学部において教員免許を取得するためのカリキュラムが組まれていることが多いです。
⑤ 司法書士
司法書士は法律系の職業であり、司法書士試験に合格することが求められます。司法書士になるために必須の学部はありませんが、法学部出身者が多いのは事実です。
法学部では法律の基礎から応用まで学ぶことができ、司法書士試験の勉強にも役立ちます。
⑥ 公認会計士
公認会計士になるためには、公認会計士試験に合格する必要があります。
公認会計士の試験は、必ずしも会計学部や経済学部を卒業している必要はありませんが、これらの学部から進んだ方が試験対策に有利です。
会計学部や経済学部では、試験に関連する知識を多く学ぶことができるため、合格率が高くなる傾向があります。
⑦ 社会福祉士
社会福祉士は、社会福祉士の資格を取得することが求められます。この職種では、社会福祉学部などの学部に進学することが基本となります。
他の学部から社会福祉士になることは基本的に難しく、専門的な知識と実習が求められるため、関連する学部を選ぶことが重要です。
⑧ 司法警察職
司法警察職は、警察官や捜査官などの職業を指します。これらの職業に就くためには、特別な資格が必要な場合がありますが、基本的には警察学校での訓練や試験に合格することが求められます。
学部選びについては、特に制約はありませんが、法律や犯罪学を学べる学部が有利に働くことがあります。
⑨ 環境技術職
環境技術職には、環境保護やエネルギー関連の技術職が含まれます。これらの職業に進むためには、環境学部や工学部などで専門知識を学んでおくことが有利です。
環境技術職には、理系の学部出身者が多く進んでいますが、必ずしも特定の学部が必要というわけではありません。
⑩ 労働基準監督官
労働基準監督官は、労働基準法に基づいて企業や労働者の適切な管理を行う職種です。
この職業に就くためには、特定の学部を卒業する必要はありませんが、法学部や社会学部で学んだ知識が役立つことがあります。法律や労働問題に関する知識を深めておくことが、業務に生かされるでしょう。
学部での学びをどう公務員試験に活かすか

公務員試験では、学部で学んだ内容が試験の合否にどのように影響するのか、気になる点だと思います。
実際、公務員試験は専門科目や論文試験、面接などさまざまな要素から成り立っていますが、学部での学びがどのように活かせるのかを理解することは非常に大切です。
ここでは、学部で学んだ知識がどのように公務員試験に生かせるか、また、どの職種に有利なのかを解説します。
- 法学部×法的知識
- 経済学部×データ分析力
- 理系学部×専門知識
①法学部×法的知識
法学部で学んだ知識は、特に行政事務職や司法関連の職種において非常に有利に働きます。公務員試験では、法律の知識が重要な場合が多く、行政書士や弁護士といった資格が求められる場面でも有効です。
例えば、法学部で学んだ憲法や民法、行政法などの基本的な知識は、公務員試験の行政職や法務職で重要な役割を果たします。
特に論文試験では、法律的な視点を持った問題解決能力が求められ、法学部での学びが直接的にアピールできるポイントとなります。
行政事務職や法律系の職種においては、実務に即した知識を活かすことが可能です。面接でも「なぜ法学部を選んだのか」といった質問に対し、具体的な法的思考を示すことができれば、説得力を増します。
また、法学部で身につけた論理的な思考能力や問題解決力は、公務員としても大いに活かすことができ、試験の選考過程でも強みとなるでしょう。
②経済学部×データ分析力
経済学部出身者は、政策立案や経済政策関連の職種において特に強みを発揮できます。
公務員試験では、経済に関する知識が必要とされる場面が多いため、経済学部で学んだ内容は直接的に試験対策に役立ちます。
経済学部で学んだマクロ経済学やミクロ経済学の知識は、論文試験での説得力を高めるだけでなく、政府の政策や財政問題を理解し、分析する力を養います。
業務においては、経済データを使って政策を立案したり、結果を分析して対策を考える能力が求められるため、経済学部で学んだ統計学やデータ分析の技術は非常に大きな強みとなるでしょう。
③理系学部×専門知識
理系学部で学んだ知識は、特に技術職や研究職での公務員試験に有利です。理系学部の学びを活かせる職種としては、技術系の職業や環境保護、都市計画などが挙げられます。
公務員試験では、理系分野の専門知識が重要な場面が多く、例えば、情報技術や建築学、環境学などの専門的な知識を活用できる機会が豊富です。
理系学部で学んだ内容は、公務員として求められる技術的な能力に直結するため、専門職の選考において有利に働きます。
また、面接時には、理系学部で培った問題解決能力や論理的思考力をアピールすることが求められます。理系学部の学生は、実験やデータ解析を通じて、課題を論理的に解決する能力を身につけています。
この能力は、公務員としての職務でも非常に重要です。学んだことを公務員としてどう活かすかを具体的に伝えることができれば、試験での強力なアピールポイントとなり、合格に近づく鍵となります。
大学生が公務員になるためのステップ
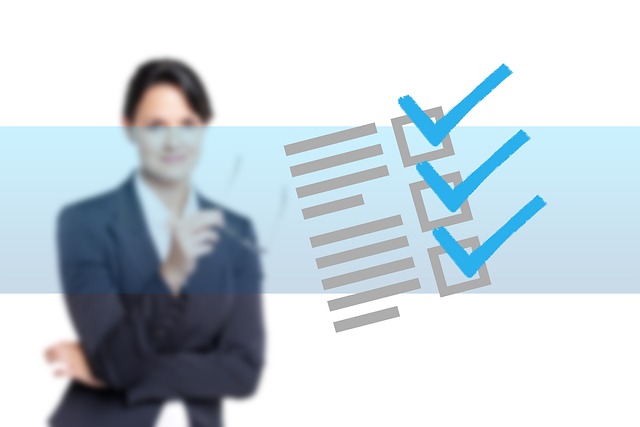
大学生が公務員になるためには、明確な目標設定と段階的な準備が不可欠です。就職活動とは異なり、公務員試験には特定のプロセスがあり、それに向けた戦略的な準備が必要です。
ここでは、公務員を目指す大学生が取るべきステップを、順を追って解説していきます。各ステップで重要なポイントを押さえることで、効率的に合格を目指すことができます。
- 目標設定と職種選定
- 公務員試験の理解
- 必要資格・スキルの確認
- インターンシップ参加
- 公務員試験の勉強開始
- 模試で実力確認
- 勉強スケジュールの作成
- 面接対策と自己PRの準備
- 本番の試験に向けた最終調整
① 目標設定と職種選定
公務員を目指す第一歩は、自分が目指す職種を明確にすることです。公務員と一口に言っても、行政職や技術職、資格・免許職などさまざまな種類があります。
それぞれの職種には求められる学部やスキルが異なるため、目標設定は非常に重要です。まず、自分の興味や強みを理解し、その上で目指すべき職種を選びましょう。
- 自分の興味や強みを把握
- 目指す職種を絞る
- 学部・学科ごとの特徴を理解
② 公務員試験の理解
公務員になるためには、必ずと言っていいほど公務員試験を受ける必要があります。試験内容は職種や採用する自治体によって異なりますが、大まかには一般知識試験、専門知識試験、面接が含まれます。
試験の形式や内容をしっかりと理解し、自分に合った勉強方法を見つけることが、効率的な試験対策につながります。
- 試験の科目と内容を把握
- 試験日程や応募条件をチェック
- 過去問で傾向を掴む
③ 必要資格・スキルの確認
公務員試験では、一般的に学歴や資格、スキルが問われます。特に専門職に関しては、特定の資格が必要な場合もあります。
自分が目指す職種に必要な資格やスキルを事前に確認し、計画的に取得することが大切です。早い段階で必要な資格を把握し、時間を有効に使いましょう。
- 必要な資格をリストアップ
- 資格取得に向けたスケジュール作成
- スキルアップを図る
④ インターンシップ参加
公務員になるために、実務経験やインターンシップが役立つこともあります。特に行政事務職などでは、インターンシップを通じて業務内容を理解し、就職後の適応力を高めることができます。
また、公務員試験では実務経験を重視する場合もあるため、積極的にインターンシップに参加しましょう。
- 実務経験を積む
- インターンシップの情報を集める
- 他の就活生と差別化を図る
⑤ 公務員試験の勉強開始
公務員試験の勉強を始めるには、早めに準備をすることが成功への近道です。試験の範囲は広いため、計画的に勉強を進める必要があります。
自分の得意分野と苦手分野を分析し、効率よく学習するための戦略を立てましょう。また、独学と予備校を組み合わせることで、より効果的に学習が進みます。
- 勉強開始時期を決める
- 自分の得意・苦手を把握
- 学習方法を選ぶ
⑥ 模試で実力確認
公務員試験の対策では、模試を活用することが重要です。模試を受けることで、自分の実力を確認でき、どの分野で弱点があるかが明確になります。
また、模試の結果をもとに、勉強計画を修正することもできます。定期的に模試を受けることで、試験本番に備えることができるため、積極的に活用しましょう。
- 定期的に模試を受ける
- 模試結果を分析して弱点を把握
- 実力を向上させるために修正点を洗い出す
⑦ 勉強スケジュールの作成
効率的に勉強を進めるためには、スケジュール管理が欠かせません。公務員試験は多岐にわたる科目を学ぶため、優先順位をつけて計画的に勉強することが必要です。
自分の生活リズムやモチベーションを考慮し、無理なく続けられるスケジュールを立てましょう。
- 目標に合わせたスケジュールを作成
- 無理なく続けられる学習計画を立てる
- 定期的に見直しを行う
⑧ 面接対策と自己PRの準備
公務員試験の最終ステップとして、面接があります。面接では、自己PRや志望動機をしっかり伝えることが求められます。
事前に面接の質問例を確認し、回答の準備をしておくことが重要です。また、面接時の態度や服装にも注意を払い、良い印象を与えるように心がけましょう。
- 面接の質問例を準備
- 自己PRを練習
- 服装や態度にも気を付ける
⑨ 本番の試験に向けた最終調整
試験前には、最終的な調整が必要です。特に試験直前の勉強では、これまでの学習内容を復習し、試験に向けて集中力を高めることが大切です。
余計な不安を抱かないように、しっかりと自分の準備に自信を持って本番に臨みましょう。
- 最後の復習を行う
- 集中力を高めて試験に臨む
- 不安を減らすために心を整える
【Q&A】公務員を目指す人のよくある質問
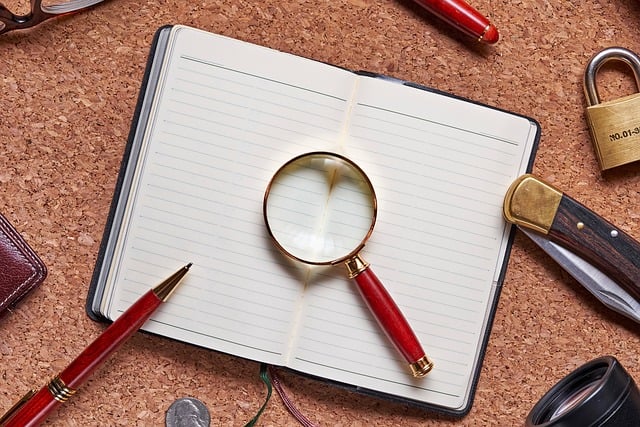
公務員を目指す就活生にとって、学歴や学部、試験の難易度など不安や疑問は尽きません。ここでは、よくある質問を10個紹介し、わかりやすく解説していきます。
- 大学中退でも公務員になれる?
- 大学と専門学校、どちらが有利?
- 公務員試験の合格率は?
- 公務員試験の難易度は?
- 公務員の年収は?
- 公務員の待遇は良い?
- 学部選びを間違えたらどうする?
- 民間企業との併願は可能?
- 文系・理系で有利不利はある?
- どの学年から準備すべき?
① 大学中退でも公務員になれる?
大学を中退していても、公務員になる道は十分にあります。実際、多くの自治体では「最終学歴が高卒以上」であれば受験資格を得られるケースが一般的です。
中退したからといって、諦める必要はありません。ただし、最終学歴によって応募できる試験区分や職種が異なるため、募集要項の確認は欠かせないでしょう。
中退者向けの採用枠も存在するため、正確な情報を集めることが大切です。経歴に不安がある場合でも、筆記試験や人物評価でしっかりと実力を示せば採用される可能性はあります。
② 大学と専門学校、どちらが有利?
公務員試験において、大学と専門学校のどちらが有利かは一概に言えません。大学卒業者は行政職や国家一般職など多様な職種に挑戦できる一方、専門学校は技術職や資格職など特定分野に強い特徴があります。
試験対策の面では、専門学校はカリキュラムが整っており効率よく学べますが、大学では幅広い知識や時間の使い方に柔軟性があります。
それぞれの違いを理解したうえで、自分に合った進路を選ぶことが大切です。目的に応じて最適な準備を進めることが、合格への近道になるでしょう。
③ 公務員試験の合格率は?
公務員試験の合格率は職種や自治体によって異なりますが、一般的には10~20%程度とされています。民間企業と比べても決して簡単とは言えません。
ただし、試験範囲や出題傾向が明確で、過去問などで対策しやすいため、努力次第で合格に近づくことは可能です。
採用人数が限られている一方で、毎年多くの受験者が集まるため、倍率は高くなる傾向があります。学力に自信がない場合でも、地道に準備すれば十分に合格を狙える試験といえるでしょう。
④ 公務員試験の難易度は?
公務員試験の難易度は、中程度から高めとされています。一般教養・専門科目・論文・面接など、複数の試験を突破しなければならないからです。
とくに独学で挑戦する場合、試験範囲の広さから長期間の対策が必要になります。ただし、出題傾向は安定しており、過去問を中心に学べば着実に力はつきます。
難しいと感じる原因の一つは、継続して学び続けるモチベーションの維持です。無理のない計画を立てて取り組んでみてください。
⑤ 公務員の年収は?
公務員の年収は安定しており、職種や年次によって段階的に上がっていきます。たとえば地方公務員であれば、20代後半で約400万円、30代で500~600万円に到達することもあります。
加えて、ボーナスや各種手当も充実しており、生活設計が立てやすいのも魅力です。昇進によって給与が上がる制度もあるため、将来の展望も描きやすいでしょう。
収入面だけでなく、年金や福利厚生なども手厚く、公務員の大きなメリットの一つです。
⑥ 公務員の待遇は良い?
公務員は待遇が良いといわれる理由に、安定した収入、充実した福利厚生、規則的な勤務時間などがあります。とくに女性の場合、産休・育休制度が整っており、復職支援もあるため安心です。
また、部署によっては転勤の頻度が少ないこともあり、家庭との両立を希望する人にとっても働きやすい環境といえるでしょう。
待遇を重視する就活生にとって、公務員という道は現実的かつ魅力的な選択肢ではないでしょうか。
⑦ 学部選びを間違えたらどうする?
「自分の学部で公務員を目指すのは不利かもしれない」と感じる人もいますが、行政職であれば基本的に学部を問わず受験可能です。実際、さまざまな分野から合格者が出ています。
ただし、技術職や資格職は特定の学部や資格が求められるため、あらかじめ要件を確認しておきましょう。もし学部が関連していなくても、独学や講座で知識を補うことで十分に対応できます。
大切なのは、学部よりも志望職種に合わせた対策を進めることです。
⑧ 民間企業との併願は可能?
民間企業との併願は可能で、実際に多くの学生が両方に挑戦しています。とくに地方公務員試験はスケジュールに余裕があり、民間との両立もしやすいです。
ただし、就活の負担が大きくなるため、スケジュール管理や優先順位の整理が欠かせません。併願する際は、それぞれの対策を明確に分けておくと効率的です。
視野を広げる意味でも、併願は自分に合った進路選択を見つける良い方法といえるでしょう。
⑨ 文系・理系で有利不利はある?
公務員試験では、職種によって文系・理系の違いが影響する場合があります。行政職であれば、学部を問わず受験でき、出題も一般教養が中心です。
一方で、技術職や研究職などは理系の専門知識が必要とされることが多いため、理系出身者に有利になるケースもあります。
ただし、どの職種であっても、努力次第でカバーできる範囲は広いです。学部にとらわれすぎず、自信を持って取り組んでみてください。
⑩ どの学年から準備すべき?
公務員を目指すなら、大学3年生の夏ごろから本格的に準備を始めるのが理想です。筆記試験の範囲が広く、独学には時間がかかるため、早めにスケジュールを組むことが重要です。
また、面接や論文対策にも十分な準備期間が必要です。4年生になってから焦ることがないよう、余裕を持って取り組んでください。
早い段階での情報収集と計画的な行動が、将来の進路を大きく左右するでしょう。
公務員試験では学部より職種に合った準備が重要

公務員を目指すうえで有利な学部を意識してしまうのはしかたのないことですが、行政事務系の職種であれば学部に大きな制限はありません。
とはいっても、技術系や資格・免許職など、専門性が求められる職種では学部の選択が重要になります。
公務員試験の対策はもちろん、学部での学びをどう活かすかも成功のカギです。自身の興味や将来のビジョンに合った学部選びと準備を進めることで、より有利に公務員を目指せるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












