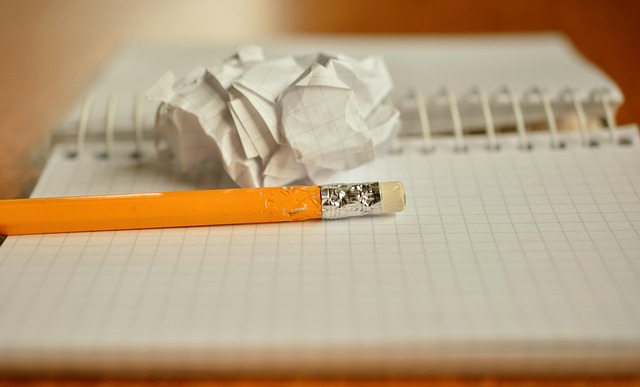SPI対策はいつから始める?必要時間と分野別の対策法まとめ
「SPI対策って、いつから始めれば間に合うんだろう…」
就活の筆記試験で最も多く採用されているSPIは、出題範囲が広く、短期間での詰め込みでは高得点が難しいテストです。そのため、効率よく準備するには開始時期の見極めが重要です。
そこで本記事では、SPI対策の開始時期の目安や分野別の必要勉強時間、スケジュール例までを詳しく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
SPI対策は余裕のあるスケジュールを立てよう

SPI対策は、時間に余裕のあるうちにスケジュールを立て、対策を始めておくことが、選考突破の近道になります。SPIの受検時期は企業によって異なりますが、多くは本選考と同時に実施されるのです。
しかし、就活が本格化する時期には、エントリーシートや面接準備などやることが一気に増え、SPIだけに集中するのは難しくなるでしょう。
そこで、早めに取り組んでおくと、苦手分野の克服にも時間を使えますし、学習ペースも安定します。スケジュールを立てるうえで、志望企業の選考時期を事前に把握しておくことも大切です。
特に大手企業ではSPIの点数が足切りラインとなる場合も多く、結果が合否を左右することもあるでしょう。試験直前に焦って問題集を始めても、思うように実力を発揮できません。
大学3年の後半からインターン選考が本格化することを考えると、できるだけ早いうちに準備を始めておきたいところです。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
SPIとは?

SPI(エスピーアイ)とは、就職活動における筆記試験の一つで、企業が新卒採用の選考時に使用する適性検査です。多くの学生にとって、エントリーシートや面接と同じくらい重要な評価項目となります。
SPIは大きく分けて「能力検査」と「性格検査」の2つに分類されます。能力検査は言語分野と非言語分野があり、それぞれ読解力や計算力など、基礎的な学力が求められるのです。
一方、性格検査では、応募者の価値観や行動傾向が企業の社風や業務に合っているかを確認されます。これらはいずれも企業が「入社後に活躍できるか」を見極めるための重要な判断材料です。
また、SPIにはテストセンター・Webテスト・自宅受験など複数の受験形式が存在し、それぞれ出題傾向や難易度に違いがある点にも注意が必要になります。
だからこそ、まずはこの試験の目的や構成を正確に把握して、自分に必要な準備をすることが大切です。
SPI対策はいつから始めるべき?開始時期の目安
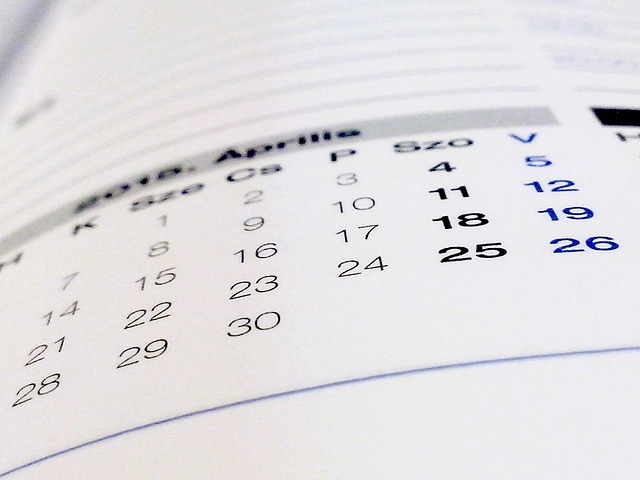
SPI対策は、本選考の約3カ月前を目安に取りかかると、ゆとりを持って勉強を進められるでしょう。特に大手企業やインターン参加を目指す学生は、SPIの受検時期が早いこともあります。
そのため、できるだけ早めに始めておくのがおすすめです。就活が本格化すると、エントリーシートの作成や面接準備などに追われ、SPI対策に十分な時間を取れなくなる場合があります。
大学3年の春頃から準備を始めておけば、夏のインターンや秋の本選考にも余裕を持って対応できるはずです。
SPIは一夜漬けで対応できるような内容ではないため、まずは自分の得意・不得意を把握することが重要です。そのうえで、試験日から逆算して学習スケジュールを組むようにしてください。
だからこそ、「いつ始めるか」を明確にし、できるだけ早く準備を始めておくことが、SPIを乗り越えるための第一歩です。
【分野別】SPI対策に必要な勉強時間

SPI対策を始めるうえで重要なのは、各分野にどれくらいの学習時間をかけるべきかを把握することです。分野ごとの目安時間を知っておくことで、効率よく準備が進められるでしょう。
ここでは、SPIの対策に必要な勉強時間を分野別にわかりやすく紹介します。
- 言語分野:10〜15時間程度
- 非言語分野:20時間程度
- 英語分野:10〜15時間程度
- 構造的把握力分野:10時間程度
- 性格検査:数時間程度
①言語分野:10〜15時間程度
言語分野の対策に必要な時間は、10〜15時間ほどが目安です。基本的な日本語力があれば、短期間でも十分に対応できるでしょう。
たとえば、1日1時間ずつ進めれば、2週間でおおよその範囲を網羅できます。
言語分野では、主に語彙や文の構成、論理的な読解力が求められます。出題内容は、文章の意味を正しく読み取れるかどうかや、適切な言い換え表現の選択などが中心です。
時間が取れない場合でも、スキマ時間を活用して少しずつ進めれば、着実に力はついていくはずです。ただし、正解を当てることだけに集中していると、応用問題への対応力が身につきにくくなります。
なぜその選択肢が正しいのか、どこで誤った判断をしたのかを必ず確認してください。焦らず丁寧に取り組む姿勢が、言語分野の得点アップにつながります。
②非言語分野:20時間程度
非言語分野に苦手意識を持つ就活生も少なくありません。学習時間の目安は約20時間です。最初は問題の意味がわかりづらく感じるかもしれませんが、パターンに慣れてしまえば、得点は安定していきます。
非言語分野では、数的処理や論理的思考力が問われます。たとえば、表やグラフの読み取り、割合や確率、損益計算など、数学的な問題が出題されるでしょう。
基礎を押さえてから応用に進むようなステップで学習を進めると、理解が深まります。おすすめなのは、時間を計って解く練習を取り入れることです。
本番では制限時間があるため、時間感覚をつかむことで実力を発揮しやすくなります。苦手だからと敬遠せず、むしろ重点的に時間をかけて取り組むことで、周囲と差をつけられる分野といえるでしょう。
③英語分野:10〜15時間程度
英語分野の対策の目安は10〜15時間程度です。英語に慣れている人なら、10時間未満でも十分な場合がありますが、苦手な人は15時間以上見ておいたほうが安心でしょう。
英語分野は、SPIの全企業で出題されるわけではありませんが、実施される場合には対策が不可欠になります。内容は、ビジネスシーンで使われる英語の文章読解や単語の意味の理解などが中心です。
市販のSPI英語対策問題集を一冊解き切ることを目標にすると、出題形式や時間配分にも慣れることができます。特に、問題文全体を読むよりも設問を先に確認し、効率的に読み進める練習が役立つでしょう。
英語は努力した分がそのまま結果に出やすい分野です。短期間でも集中して取り組んでおきましょう。
④構造的把握力分野:10時間程度
構造的把握力の学習時間の目安は10時間程度です。出題頻度はそれほど高くありませんが、出題された際に対応できるようにしておくと安心です。
構造的把握力の分野は、文章や情報の構造を整理し、因果関係や要点を正確に理解する力が問われます。グラフや図表、複雑な説明文の構造を把握する問題が中心です。
対策としては、問題集や過去問を使って形式に慣れておくのが効果的でしょう。情報を整理し、論理的に考えるクセをつけることで、自然と対応力が上がっていきます。
理系でない人にとっては少し難しく感じるかもしれませんが、逆にしっかり対策しておくと他の受験者と差がつきやすい分野でもあります。
⑤性格検査:数時間程度
性格検査の対策時間は、数時間もあれば十分です。まったく対策しないと、設問の意図がつかめず戸惑ってしまうことがあるため、数セットの模擬問題に目を通しておくと安心でしょう。
性格検査は、企業が応募者の価値観や考え方を知るために行うものです。正解・不正解はありませんが、回答に一貫性がないと「自己認識にブレがある」と判断されることもあります。
ポイントは、ありのままの自分を意識して答えることです。無理に「良く見せよう」と取り繕っても、全体のバランスが崩れてしまいます。
性格検査は軽視されがちですが、企業によっては選考の重要な判断材料になる場合もあるでしょう。短時間でもいいので、事前に準備しておくことをおすすめします。
SPI対策のスケジュール例
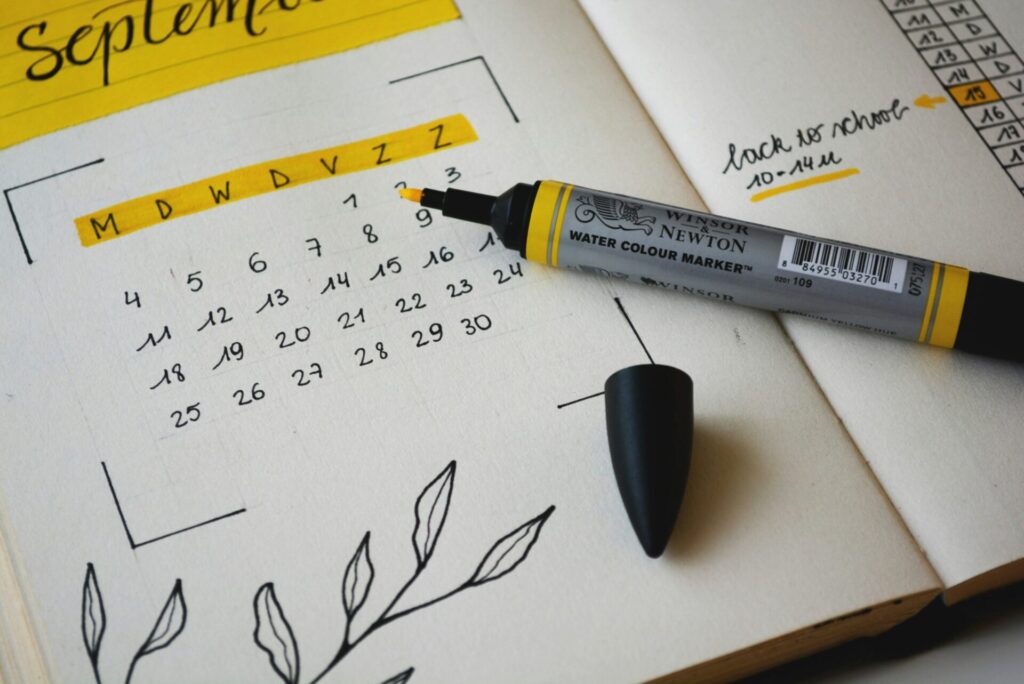
SPI対策を効率よく進めるには、いつ何をすべきかを明確にしておく必要があるのです。
ここでは、試験の3カ月前から1週間前までを5つのステップに分け、段階的に取り組めるスケジュール例を紹介します。
- 3カ月前:全体の試験構造と頻出問題を把握する
- 2カ月前:問題集を中心に基礎力を固める
- 1カ月前:苦手分野に重点を置いて反復学習
- 2週間前:模擬試験で本番形式に慣れる
- 1週間前:時間配分を意識して最終確認する
①3カ月前:全体の試験構造と頻出問題を把握する
SPI対策のスタートは、試験全体の構造を理解することから始めましょう。3カ月前の時点では、出題分野や形式、よく出る問題の傾向を把握することが大切です。
これにより、自分がどこから学習を始めればよいかが明確になります。SPIには、言語・非言語・英語・構造的把握・性格検査といった複数の分野があるのです。
受検企業によって出題内容が異なるため、まずは志望企業の傾向を確認してください。あわせて簡単な模擬テストを受けてみると、現状の理解度も把握しやすくなります。
最初に全体像をつかんでおけば、無駄な勉強を避けて効率的に学習が進められるでしょう。何となく勉強を始めるのではなく、計画的に進めるための準備期間として活用してください。
②2カ月前:問題集を中心に基礎力を固める
試験構造を理解したら、2カ月前には本格的な問題演習に入りましょう。各分野の基礎問題を繰り返し解くことで、出題形式に慣れて解答スピードも上がっていきます。
この時期は、1冊の問題集を選び、毎日少しずつ取り組むのがおすすめです。同じ問題を繰り返すことで知識が定着しやすくなり、効率よく実力が伸びるはず。
特に非言語分野は慣れが必要なので、焦らず丁寧に取り組んでください。時間を計って解く練習も、この段階から始めておくと良いでしょう。本番での焦りを防ぎ、落ち着いて対応できるようになります。
基礎をしっかり固めることで、このあとの苦手対策もスムーズに行えるでしょう。
③1カ月前:苦手分野に重点を置いて反復学習
1カ月前に入ったら、自分の苦手分野を重点的に復習するフェーズに移りましょう。模擬試験や過去の演習でミスが多かった部分を中心に、集中的に対策を進めてください。
すべての分野を均等に学ぶよりも、不得意なところを強化するほうがスコアアップにつながります。
たとえば、図表読み取りが苦手なら、同じ形式の問題を繰り返して出題パターンを体に覚えさせましょう。
この時期には、得意分野は軽く復習する程度にとどめ、苦手克服に時間をかけることを意識してください。自分の弱点に早めに向き合っておけば、本番での失点を防ぐことができるはずです。
④2週間前:模擬試験で本番形式に慣れる
試験が近づいてきた2週間前には、本番形式の模擬試験に取り組みましょう。時間制限のあるなかで解く練習をすることで、当日の緊張感や時間配分の感覚がつかめるようになります。
模擬試験は、Web、アプリ、紙などさまざまな形式がありますが、可能な限り本番に近い環境で行ってください。形式に慣れておくと、当日も落ち着いて問題に取り組めるでしょう。
模試の結果をもとに、再度苦手を洗い出して復習しておくことも大切です。最後の仕上げとして、実践に近いトレーニングを積んでおくと安心でしょう。
⑤1週間前:時間配分を意識して最終確認する
残り1週間を切ったら、これまで取り組んできた内容の総復習に入りましょう。ここでは特に「時間配分」を意識して、模試や問題演習を行ってください。
直前になると新しい教材に手を出したくなりますが、あえて使い慣れた問題集を見直すことが重要です。見落としていたポイントに気づけたり、ミスの傾向を再確認できたりします。
ミスした問題はそのままにせず、必ず原因を分析して再度解き直してください。最後の仕上げでしっかりと見直しができれば、本番でも落ち着いて実力を発揮できるでしょう。
SPI対策の計画を立てる際のポイント
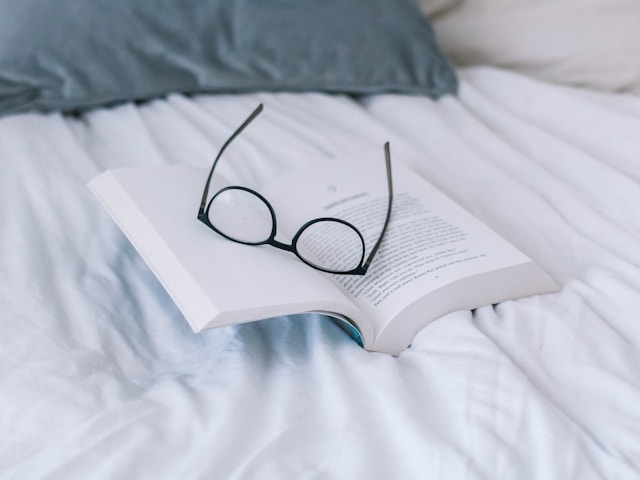
SPI対策は、ただ始めるだけでは効果が上がりません。限られた時間の中で効率よく進めるには、事前の計画が欠かせないでしょう。
ここでは、対策の質を高めるために押さえておきたい5つのポイントを紹介します。
- 志望企業のSPI受検時期を確認して対策開始時期を決める
- 本番から逆算して勉強スケジュールを立てる
- 毎日の勉強時間を確保しやすい習慣を整える
- 受検形式に合わせて対策する
- 模擬試験で実力を測り、必要な対策量を見極める
①志望企業のSPI受検時期を確認して対策開始時期を決める
SPIの対策は、受検日がいつになるかによって開始のタイミングが変わります。早めに志望企業のスケジュールを調べておくことで、無理のない準備が可能になるのです。
多くの企業では、エントリー後の初期段階でSPIを実施します。選考が始まってから対策を始めたのでは間に合わないかもしれません。
3月の本選考に合わせるなら、1〜2月にはSPIを受けることになるため、準備は3年の秋頃には始めておきたいところです。
また、夏のインターン選考でSPIが出題される企業もあるため、その場合はさらに早めの対策が必要になります。見落としていると、学習の機会を失いかねません。
早めに調べておくだけで、後々のスケジュールにゆとりが生まれます。
②本番から逆算して勉強スケジュールを立てる
勉強計画を立てる際は、「本番からの逆算」が基本です。目標とするSPI試験日がいつかを明確にし、そこから必要な学習量を見積もることで、無理なく進められるようになります。
たとえば、言語・非言語それぞれに10〜20時間が必要だとわかっていれば、週単位や日単位のスケジュールが組みやすくなるでしょう。
詰め込みすぎず、余裕を持たせたスケジュールにすることが、継続のコツです。うまく時間がとれない日もあるかもしれませんが、その分はほかの日でカバーすれば問題ありません。
大切なのは、学習ペースを乱さず、一定のリズムを保つことです。逆算して計画を立てることで、焦りを感じにくくなり、自信を持って本番を迎えられます。
③毎日の勉強時間を確保しやすい習慣を整える
どれだけ計画を立てても、実行できなければ意味がありません。そこで鍵になるのが、勉強を習慣化することです。日常生活の中で無理なく続けられる仕組みを作ることが大切になります。
たとえば、朝食後や寝る前に30分だけ取り組むようにしたり、通学時間を利用してスマホで問題を解いたりする工夫が効果的です。短時間でも継続すれば、確実に力はついていきます。
「今日は忙しいから休もう」と感じる日でも、5分だけでも勉強することでリズムを崩さずに済みます。ゼロにしない意識が、習慣化のポイントです。
毎日自然に勉強できる環境を整えることで、モチベーションも維持しやすくなります。
④受検形式に合わせて対策する
SPIの受検形式には、テストセンター・Webテスティング・自宅受験・紙のテストなど複数の種類があります。それぞれ操作方法や出題のされ方が異なるため、形式に応じた対策が欠かせません。
テストセンターではパソコン操作が必要なため、マウスの使い方や画面切り替えに慣れておくと安心です。Webテストでは、制限時間の管理やインターネット環境も重要になります。
企業によって受検形式は異なりますので、エントリー前に必ず確認しておきましょう。形式を把握しておかないと、試験当日に戸惑ってしまうかもしれません。
どの形式にも対応できるよう、模擬テストや体験版で実際の流れを体感しておくことをおすすめします。
⑤模擬試験で実力を測り、必要な対策量を見極める
計画を進めるうえで、自分の現在地を把握することはとても大切になります。そのために役立つのが模擬試験です。
SPIの模試を受けることで、得意な分野と苦手な分野が明確になり、対策すべきポイントも見えてきます。市販の模試や無料のオンラインテストを活用すれば、手軽に実力を確認できるのです。
実際に時間を計って解くことで、本番と近い感覚も得られるでしょう。得点が低かった分野は重点的に、すでにできている分野は復習中心に進めると、効率のよい学習が可能になります。
やみくもに時間をかけるよりも、必要な部分に集中した対策が結果につながるでしょう。模試を定期的に取り入れることで、成長を実感でき、やる気の維持にも役立ちます。
SPIの試験内容

SPIは大きく分けて「能力検査」と「性格検査」の2種類で構成されています。能力検査は複数の分野に分かれており、求められるスキルも異なるのです。
ここでは、各分野の特徴と出題内容についてわかりやすく整理しました。
- 言語分野
- 非言語分野
- 英語分野
- 構造的把握能力分野
- 性格検査
①言語分野
言語分野では、語彙力や読解力が問われます。設問には、同義語・反義語、語句の関係、文の並び替え、長文読解などが含まれています。
文章の構造を理解し、意味が通るように組み立てる力が求められるでしょう。特別な知識が必要なわけではありませんが、設問の表現に癖があるため、慣れておくことが大切です。
過去問や模試を活用して出題形式に触れておくと安心でしょう。読解問題は時間がかかる傾向があるため、設問の難易度や分量に応じて解く順番を調整するなど、時間配分にも気を配ってください。
②非言語分野
非言語分野では、計算力や論理的思考力が必要です。割合、損益計算、順列・組み合わせ、グラフや表の読み取りなど、中学〜高校レベルの数学力があれば対応できる問題が中心となっています。
この分野に苦手意識を持つ方も少なくありませんが、出題パターンがある程度決まっているため、繰り返し練習することで得点しやすくなるのです。
初めは難しく感じても、慣れることで得意分野に変わる可能性もあります。特に、文章が長くて混乱しやすい問題でも、数字や情報を丁寧に整理すれば解ける場合が多いです。
早めの対策を心がけておくとよいでしょう。
③英語分野
英語分野はすべての企業で実施されるわけではありませんが、出題される場合には基本的な英語力が求められます。内容は、語彙の意味選択、文法の穴埋め、短文・長文の読解などです。
TOEICスコアの提出を求めない代わりに、SPI英語を課す企業もあります。そのため、志望企業が英語出題の対象かどうかは事前に確認してください。苦手な方は、基礎単語や文法の復習から始めましょう。
大学受験レベルの知識があれば、十分に対応可能です。試験前に数回でも模擬問題を解いておけば、本番での落ち着きにもつながります。
④構造的把握能力分野
構造的把握能力分野では、図形や表の中にある法則性を見抜き、論理的に解答する力が求められます。すべての企業で実施されるわけではありませんが、一部の企業では評価項目として重視されているのです。
問題の例としては、図形の回転や展開、位置関係、図形の並び方の法則などがあります。知識よりも直感やひらめき、空間認識力といったスキルが問われる傾向にあるでしょう。
慣れないうちは難しく感じるかもしれませんが、類題を繰り返すことで徐々にコツがつかめてきます。答えを当てるだけでなく、なぜそうなるのかを説明できるよう意識しながら取り組んでください。
⑤性格検査
性格検査は、正解がある試験ではありません。質問に対して自分の価値観や行動傾向に沿って回答する形式で、自身の性格特性や仕事への適性を企業が判断するためのものです。
たとえば「協調性がある」「新しい環境にもすぐ慣れる」といった自己認識に関する設問が並びます。
自分をよく見せようと嘘を重ねると、回答に一貫性がなくなってしまい、評価が下がるおそれがあるでしょう。重要なのは、正直かつ自然な気持ちで回答することです。
回答に迷うときは、普段の行動や考え方を振り返ってみてください。その方が、企業とのマッチングも適切に判断されやすくなります。
【分野別】SPIの対策方法

SPIの問題は分野ごとに出題傾向や対策方法が異なります。効率よく得点を伸ばすには、それぞれの分野に合った学習法を取り入れることが大切です。
ここでは、各分野の効果的な対策方法を紹介します。
- 言語分野:問題集を反復する
- 非言語分野:計算力と論理的思考を鍛える
- 英語分野:頻出語彙と文法に絞る
- 構造的把握力分野:図形問題の練習をする
- 性格検査:正直に一貫性のある回答を意識する
①言語分野:問題集を反復する
言語分野では、文章の流れを読み取る力や論理的な思考力が求められます。対策としては、問題集を繰り返し解く方法が効果的です。
特に接続詞や指示語に注目しながら読むことで、設問の意図を正確に把握しやすくなります。間違えた問題はそのままにせず、「なぜ間違えたのか」を振り返って理解を深めてください。
同じ問題を何度も解くことで、パターンに慣れ、解答スピードも上がっていきます。新しい問題ばかりに手を出すのではなく、1冊の問題集を繰り返す方が記憶に残りやすいでしょう。
コツコツと基礎を固めることが、得点力アップへの近道です。焦らず丁寧に取り組む姿勢が、確かな自信につながります。
②非言語分野:計算力と論理的思考を鍛える
非言語分野は、割合や確率、損益計算などの数的処理が中心となります。この分野が苦手な人は多いですが、解き方のパターンを覚えて慣れることで得点を伸ばすことが可能です。
最初は解き方を理解するよりも、何度も問題に触れて慣れることを優先しましょう。パターンを覚えてから理解を深める流れが、効率よく実力を上げるポイントです。
また、時間を計って解く練習をすると、実戦感覚が身につきます。情報を図や表に整理する習慣も、正確な判断を助けてくれるでしょう。
完璧を目指す必要はありませんが、得意なタイプの問題を確実に取れるようにしておくと、全体の得点が安定しやすくなります。
③英語分野:頻出語彙と文法に絞る
英語分野では、長文ではなく短めの英文をもとにした設問が中心になります。幅広く学習するのではなく、頻出の単語や文法に的を絞ることが効率的です。
まずは問題集でよく出る単語や構文を確認してください。特に前置詞や助動詞など、基本だけど見落としやすいポイントは重点的に押さえておきましょう。
英語が苦手な場合でも、出題傾向を知り、設問に合わせたアプローチをするだけで十分に対応できます。
英文すべてを訳す必要はありません。設問や選択肢から文の構造をつかむコツを身につけると、解くスピードも上がるのです。短時間の対策でも成果が出やすいため、集中して取り組むことをおすすめします。
④構造的把握力分野:図形問題の練習をする
構造的把握力の分野の対策には、問題に慣れることが重要です。この分野では、複数の情報を整理しながら、正しい順序や関係性を読み取る力が必要になります。
また、図表や文章構造の把握が問われるため、普段の勉強ではあまり触れない形式に戸惑う人もいるかもしれません。
特に文章の並べ替えや図形・グラフを使った設問を繰り返し解くと、全体像をつかむ力が養われます。焦らず一つずつ情報を整理することを意識してください。
いきなり答えを出そうとせず、まずは要素を分解して整理することで、論理的に正しい選択がしやすくなります。出題頻度はそれほど高くありませんが、差をつけられるポイントでもあるのです。
対策しておくことで、安心して本番に臨めるでしょう。
⑤性格検査:正直に一貫性のある回答を意識する
性格検査の対策は、事前に模擬問題に目を通して設問の形式を知っておくことです。そのうえで、「自分らしい」回答をすることを意識しましょう。
性格検査では、企業が応募者の性格や価値観を見極めようとしています。正解がないため軽く見られがちですが、実は一貫性のある回答が評価の対象となることもあるでしょう。
良く見せようとして嘘の回答を続けると、全体のバランスが崩れて矛盾が生まれやすくなります。最終的に「この人は一貫性がない」と判断されてしまう可能性も。
自分を偽らず、自然体で回答することが、企業とのミスマッチを防ぐうえでも重要です。正直な回答こそが、結果的に自分に合った企業との出会いにつながります。
SPIに苦手意識がある人向けの対策方法

SPIに苦手意識を持つ就活生は多く見られます。焦って一気にすべてを克服しようとすると、かえって学習の効率が下がってしまうこともあるでしょう。
ここでは、無理なく取り組める具体的な対策法を5つ紹介します。
- 苦手分野は優先順位をつけて集中して対策する
- 問題集は自分に合ったレベルのものを選ぶ
- 解けなかった問題はすぐに解説を確認し理解する
- 時間配分に慣れるために模擬試験を活用する
- 友人や就活仲間と問題を出し合って学習効率を高める
①苦手分野は優先順位をつけて集中して対策する
すべての分野を同時に対策しようとすると、時間も労力も分散されてしまい、かえって非効率になります。まずは、自分が苦手と感じている分野を明確にし、そこから集中的に取り組むことが効果的です。
たとえば、非言語分野の割合や速さの計算が苦手な場合は、まずそこに絞って理解を深めていきましょう。優先順位をつけることで、学習に迷いがなくなり、集中力も高まりやすくなります。
不得意な分野を後回しにしてしまうと、直前になって焦りが生じるリスクもあるため、できるだけ早い段階で対策を始めることがポイントです。また、目標を具体的に立てると取り組みやすくなります。
たとえば「今週は非言語に5時間使う」といった計画を立てておけば、取り組むハードルも下がるでしょう。苦手を放置せず、順序立てて克服する意識が大切です。
②問題集は自分に合ったレベルのものを選ぶ
問題集を選ぶ際は、自分のレベルに合ったものを使うことが大切です。最初から難易度の高い問題集に取り組んでしまうと、理解が追いつかず、モチベーションの低下につながる可能性があります。
反対に、簡単すぎるものでは実力が伸びづらいため、基礎→応用と段階を踏んでレベルアップするのが理想的です。初学者であれば、解説が丁寧で図解が豊富な問題集を選ぶとよいでしょう。
視覚的に理解しやすくなり、苦手意識の緩和にもつながります。無理なく続けられることが、SPI対策において何より重要です。
問題集を選ぶときには、試しに数問解いてみて、解説のわかりやすさやボリュームを確認してから購入するのがおすすめです。
自分のペースに合った教材を使えば、継続もしやすくなり、学習の質も高まるでしょう。
③解けなかった問題はすぐに解説を確認し理解する
解けなかった問題は放置せず、その場でしっかり解説を確認し、理解するようにしてください。特に重要なのは「なぜ間違えたのか」を明確にすることです。
計算ミスなのか、設問の読み違いなのか、あるいは解法そのものを理解していなかったのかを見極めることで、次に同じミスを防げるようになります。
また、単に解説を読むだけでなく、自分の言葉で説明できるようにしてみましょう。誰かに教えるつもりで解説を言い直すことで、記憶への定着度がぐんと高まります。
間違えた問題をそのままにするのは非常にもったいないことです。SPIはパターン化された問題が多いため、同じタイプの問題が繰り返し出題されることも少なくありません。
解説を理解し、納得しながら進めることが得点力を伸ばす近道です。
④時間配分に慣れるために模擬試験を活用する
SPIは時間との勝負です。いくら知識があっても、制限時間内に解けなければ意味がありません。そこで、模擬試験を活用して実際の試験と同じような環境で練習することが大切です。
時間を計って取り組むことで、自分のペースや得意・不得意な問題の傾向をつかみやすくなるでしょう。特に非言語分野では、1問に時間がかかりすぎると他の問題を解く余裕がなくなってしまいます。
模擬試験で時間感覚を体に覚えさせることで、本番でも焦らず冷静に取り組めるようになるでしょう。
模試の結果を分析し、「どの問題に時間がかかったか」「どのタイミングで焦りが出たか」などを振り返る習慣をつけると、改善ポイントが明確になります。
繰り返し練習を積むことで、自信を持って本番に臨めるようになるのです。
⑤友人や就活仲間と問題を出し合って学習効率を高める
SPI対策は一人で進めるよりも、仲間と取り組んだほうが効果的なことがあります。特にモチベーションの維持や、理解の定着という面でグループ学習は大きな助けになるのです。
お互いに問題を出し合ったり、解き方を説明し合ったりすることで、理解がより深まるでしょう。人に教えることで、自分自身の理解がどこまで定着しているかを確認できます。
また、仲間の視点や解法から新しい発見があることも多く、視野が広がるのもメリットの一つです。さらに、定期的に一緒に学習する場を設けることで、自然と勉強のリズムも整いやすくなります。
SPIのように短期間で成果を求められる試験では、こうした仲間の存在が継続の大きな支えになるでしょう。孤独になりがちな就活対策において、学習を共有することで前向きに取り組めるようになります。
SPI対策の進め方で結果が変わる理由

SPI対策は、いつから始めるかによって成果が大きく左右されます。早めに取り組むことで、言語・非言語・英語など分野別に必要な勉強時間を確保しやすくなり、苦手な分野も計画的に克服できるでしょう。
また、受検形式や企業ごとの時期を考慮しながらスケジュールを組むことが、安定した準備につながります。実際に、3カ月前から段階的に対策を進めるスケジュールが有効です。
SPIとは何かを正しく理解し、適切な開始時期と計画を立てれば、本番で焦ることなく実力を発揮できるでしょう。SPI対策は「いつから始めるか」が合否を分ける第一歩です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。