公務員就活の流れと試験内容を徹底解説!スケジュールも紹介
「公務員になりたいけど、就活の流れや試験の種類が多くて不安…」
国家公務員や地方公務員など、職種の幅が広い公務員就活では、早い段階からの情報収集と計画的な対策がカギを握ります。特に筆記試験や面接の準備には時間がかかるため、スケジュール管理も重要です。
そこで本記事では、公務員の就活の全体像をつかみたい方に向けて、公務員の種類・民間との違い・メリット・試験の難易度・就活スケジュール・対策ポイントまで、体系的にわかりやすく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
公務員とは

公務員とは、国や地方自治体に雇用され、社会の仕組みを支える仕事に従事する人々のことです。国民の暮らしと密接に関わります。
「安定している」「社会貢献ができる」といった理由で人気がありますが、職種は幅広く、公務員の仕事に漠然とした印象を持つ人も少なくありません。
実際には、官僚や市役所職員、警察官、消防士など多様な職種があります。また、雇用形態によって国家公務員と地方公務員に分かれており、それぞれ異なる役割を担っています。
雇用の安定や福利厚生の整備、転勤の少なさなどが魅力ですが、年功序列や業務のルーティン化といった側面もあります。まずは全体像をつかみましょう。
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
公務員の主な種類

公務員と一口に言っても、その種類はさまざまで、それぞれ担う役割や仕事内容が異なります。自分に合った職種を見極めるためには、公務員の種類を知ることが大切です。
ここでは「国家公務員」と「地方公務員」の2つに分けて解説します。
- 国家公務員
- 地方公務員
①国家公務員
国家公務員とは、中央省庁や裁判所、税務署など国の機関で働き、政策の企画・実行などを通じて国全体の仕組みを支える職種です。
全国規模での勤務が前提となるため、地方勤務や転勤が発生しやすく、地域密着型の働き方を希望する人には不向きかもしれません。
一方で、法律や国の方針に関わる機会も多く、広い視野で物事を捉えたい人にとっては、大きなやりがいや成長を感じられる職場です。
国家公務員は「総合職」と「一般職」に分かれ、前者は政策の中枢を担い、後者は事務系中心。自分の適性に応じて進路を考えることが重要です。
②地方公務員
地方公務員は、都道府県や市区町村などの自治体に所属し、地域住民の生活に密接に関わる行政サービスを担う職種です。
福祉・教育・環境・地域振興など幅広い分野に携わり、市役所や県庁、消防署、教育委員会などが主な勤務先となります。
転勤は基本的に同じ自治体内で行われ、地元に根ざして働けるのが特徴です。地元貢献への思いがある人には適した働き方といえるでしょう。
事務・技術・福祉など職種も多岐にわたり、試験内容は自治体ごとに異なります。地域理解や人柄も重視されるため、自己分析と準備が重要です。
公務員と民間企業の違い

公務員と民間企業では、採用の流れや働き方など多くの点で違いがあります。就職活動を始める前にこの違いを知っておくことで、進路の選択がしやすくなるでしょう。
ここでは、6つの視点から両者を比べながらわかりやすく説明します。
- 採用プロセス
- 試験内容
- エントリー時期
- 仕事内容
- 給与
- 福利厚生
①採用プロセス
公務員と民間企業では、採用方法に大きな差があります。民間企業は、エントリーシートや面接を通じて人物を評価する選考が主流です。一方、公務員は筆記試験が中心で、知識や思考力が重視されます。
公務員の場合、まず筆記試験を受け、その合格者に対して面接が行われる流れです。民間企業は企業ごとに採用基準が異なるため、多様な方法で選考が進みます。
このように、公務員は試験重視、民間企業は人物重視の傾向があるでしょう。準備の内容がまったく異なるため、希望する進路に合わせた対策を早めに始めておくことが重要です。
違いを理解せずに就活を進めると、準備不足になりかねません。まずは採用の仕組みを知ることから始めてみてください。
②試験内容
試験の内容も、公務員と民間企業ではかなり異なります。特に公務員は、独自の試験対策が求められるのです。
公務員試験では、一般知能や一般知識、専門科目、論文などが問われるほか、面接や集団討論が行われることもあります。幅広い分野での理解と対策が必要です。
一方、民間企業の選考は、適性検査やグループディスカッション、面接などを通して、コミュニケーション能力や価値観が評価されることが多くなります。自己分析や企業研究が重要になってくるでしょう。
公務員試験は出題範囲が広く、長期間の計画的な勉強が不可欠です。民間と同時進行で受ける場合は、スケジュール管理に気をつけてください。
試験内容を理解していないと、学習の方向性を誤るおそれも。まずは出題傾向を確認することをおすすめします。
③エントリー時期
エントリーのタイミングにも、公務員と民間企業で差があります。スケジュールを把握しておくことで、効率的な準備が可能になるのです。
民間企業では、大学3年の夏頃からインターンシップが始まり、年明けには本格的なエントリーが進みます。企業によっては早期選考を実施するケースも多いため、早めの行動が求められるでしょう。
一方、公務員試験は年1回の試験日があり、それに合わせて募集やエントリーが始まります。たとえば、春に試験がある場合、前年の秋から情報収集や準備が必要になることもあるでしょう。
公務員と民間の選考が重なる時期もあるため、併願を考えている人はしっかりと計画を立てておく必要があります。就活の初期段階で全体の流れを把握しておきましょう。
④仕事内容
公務員と民間企業では、日々の業務内容や求められる姿勢が異なります。それぞれの特性を知ることで、自分に合った進路が見えてくるでしょう。
公務員の仕事は、法律や制度に基づき、住民サービスを安定的に提供することが主な役割です。たとえば、窓口対応や書類審査、災害対策などが日常業務に含まれます。
民間企業では、利益を上げることが目標となるため、営業や商品開発、マーケティングなどが主な業務です。
競争環境の中で成果を出すことが求められるため、やりがいも大きい反面、プレッシャーもあります。
どちらも社会に貢献する仕事であることに違いはありませんが、重視する価値観や働き方には差があるのです。自分がどのような環境で成長したいのか、よく考えてみてください。
⑤給与
給与についても、公務員と民間企業では仕組みや傾向が異なります。それぞれの特徴を知ることで、将来設計に役立てられるでしょう。
公務員の給与は「給与表」によって定められており、年齢や勤続年数に応じて安定的に上昇します。賞与も年2回支給されるなど、収入は安定しているでしょう。
一方、民間企業では業績や個人の成果に応じて給与が変動する場合があります。若いうちから実力で高収入を狙える一方で、成果が出せなければ昇給しにくい環境でもあるでしょう。
どちらが良いかは人によって異なりますが、安定を重視するなら公務員、実力で勝負したいなら民間が向いているかもしれません。将来の働き方や生活スタイルに合わせて選んでください。
⑥福利厚生
公務員の魅力のひとつが、充実した福利厚生制度です。働きやすさや生活の安定を求める人にとっては、大きなメリットになるでしょう。
公務員は共済組合に加入しており、医療費の補助や住宅手当、育児・介護休暇などの制度が整っています。こうした支援により、長く働き続けやすい環境が用意されているのです。
民間企業でも福利厚生に力を入れているところはありますが、内容は企業によって差があります。とくに中小企業では制度が最低限にとどまるケースも少なくありません。
給与だけで判断するのではなく、福利厚生の中身も含めて比較することが大切です。安心して働き続けるために、制度の内容にも注目してみてください。
公務員として働くメリット

公務員は就職先として人気がありますが、それには理由があります。収入や待遇の安定に加え、長く安心して働ける環境や社会的な意義も見逃せません。
ここでは、公務員として働くことで得られる主なメリットを5つに分けて紹介します。
- 安定した雇用が得られる
- ワークライフバランスを取りやすい
- 社会的信用が高い
- 地域・国家に貢献できるやりがいがある
- 職場環境が整備されている
①安定した雇用が得られる
公務員の大きな魅力は、雇用が安定していることです。景気の影響を受けにくく、民間企業に比べてリストラや倒産の心配が少ないため、将来に不安を感じにくいでしょう。
たとえば、経済情勢に左右されて業績が悪化する民間企業では、早期退職や希望退職を求められることもあります。一方で、公務員ではそのような事例はほとんど見られません。
長期的な雇用が見込めることは、就職後のライフイベントとも両立しやすい安心材料といえます。さらに、昇給やボーナスの制度も明確に決められており、給与に関する見通しが立てやすい点も魅力です。
安定した働き方を重視する方にとって、公務員は有力な選択肢となるでしょう。
②ワークライフバランスを取りやすい
公務員は私生活とのバランスを取りながら働きやすい職業のひとつです。多くの職場で定時退社が基本となっています。
有給休暇の取得もしやすく、育児や介護などの事情に対応した制度も整っているため、ライフステージが変化しても働き続けやすいでしょう。
実際に、育休からの復帰率が高いことや、フレックスタイム制度を導入している自治体も見られます。無理なく働ける仕組みがあることで、心身ともに安定した状態を保ちやすくなるのです。
仕事と生活をバランスよく両立させたいと考える方には、非常に適した環境といえるでしょう。
③社会的信用が高い
公務員は、社会からの信頼が高い職業です。安定した収入と職業としての信用が評価されやすいため、住宅ローンやクレジットカードなどの金融審査において、スムーズに進む場合が多くあります。
また、身近な人からの安心感も得やすく、家族や親戚から信頼される点も見逃せません。安定した職業に就いているという安心感は、自分自身の気持ちを支える力にもつながります。
このように、職業としての信頼性は、社会生活をスムーズに進める上で重要なポイントになるでしょう。
④地域・国家に貢献できるやりがいがある
公務員の仕事には、社会の仕組みや人々の暮らしを直接支えるという役割があります。住民サービスや政策の実行を通じて、地域や国に貢献することができるのです。
たとえば、災害対策、福祉、教育、インフラ整備など、生活に密着した分野での業務が多く、自分の仕事の成果を実感しやすい点も特長です。
「誰かの役に立ちたい」「社会の一員として貢献したい」という気持ちを持つ人にとっては、大きなやりがいを感じられるでしょう。
成果が目に見えにくい仕事も多いですが、そのぶん達成感や充実感も大きく、やる気を保ちやすい環境でもあります。
⑤職場環境が整備されている
公務員の職場では、働く人が安心して力を発揮できるように、さまざまな環境整備が進んでいるのです。たとえば、ハラスメント対策やメンタルヘルスへの配慮、労働時間の適切な管理などが挙げられます。
また、スキルアップのための研修制度も充実しており、新人研修だけでなく、キャリアに応じた学びの機会が提供されているのです。
専門知識を深めながら長く働ける体制が整っている点は、安心感につながります。
このように、制度面や教育面でも手厚いサポートがあることで、不安を感じにくく、安定した職業人生を歩みやすくなるでしょう。
【職種別】公務員試験の難易度

公務員試験の難易度は、職種によって大きく異なります。どの職種を目指すかによって、準備すべき内容や対策の方法も変わってくるでしょう。
ここでは代表的な6つの職種について、試験の特徴と難易度をわかりやすく解説します。
- 国家総合職
- 国家一般職
- 地方上級職
- 公安職
- 専門職
- 資格職
①国家総合職
国家総合職は、公務員試験の中でも最も難関とされています。各省庁の政策立案を担う将来の幹部候補として採用されるため、要求されるレベルが非常に高いです。
試験では、教養試験や専門試験に加えて政策論文や人物評価も実施され、幅広い能力が問われます。さらに、競争倍率も高く、合格までに数年かけて準備する受験生も少なくありません。
この職種を目指すなら、大学1~2年生のうちから計画的に勉強を始めるのが理想です。民間企業の就活との両立は難しくなるため、覚悟を持って進めてください。
国家総合職は、難易度こそ高いですが、政策に関わるダイナミックな仕事ができるという魅力があります。志のある人にふさわしい職種といえるでしょう。
②国家一般職
国家一般職は、中央省庁や出先機関で実務を支える役割を担います。国家総合職に比べて、業務はより現場寄りであり、実践的な内容が中心です。
試験の難易度は総合職よりもやや低めですが、教養・専門試験があるため、確実な学習が必要。過去問演習や頻出分野の復習を軸に対策を進めてください。
採用人数が多く、倍率が比較的低い職種もありますが、人物評価も重視されるため、面接対策も欠かせません。知識だけでなく、協調性や対応力も見られます。
安定した環境で実務を積み重ねたい人に向いています。専門性を身に付けるよりも広く行政に関わりたいと考えている人には、魅力のある選択肢になるでしょう。
③地方上級職
地方上級職は、都道府県や市区町村で地域行政を担う管理職候補です。地元に貢献したいと考える学生にとっては、特に人気があります。
試験内容は国家一般職と似ていますが、自治体ごとに出題傾向が異なるため、各自治体の過去問入手や情報収集が欠かせません。専門科目と教養試験の両方に対応できる準備が求められます。
応募者数や倍率は地域によって差があります。政令指定都市などでは倍率が高くなる傾向があるため、十分な対策が必要です。地域に根ざして働きたい人にはおすすめ。
志望自治体の特徴を理解し、地域に寄り添う姿勢を面接でしっかり伝えてください。
④公安職
公安職には、警察官・消防士・自衛官などが含まれます。国や地域の安全を守る使命感が求められる職種です。試験では教養科目のほかに、体力試験や面接が実施されます。
学力だけでなく、体力や責任感、コミュニケーション力も重要視される点が特徴です。教養試験の難易度はそれほど高くありませんが、体力試験の準備や志望動機の整理は欠かせません。
日常的な体力維持も大きなポイントになるでしょう。命を預かる現場で働く責任がある分、やりがいも非常に大きい仕事です。人を守ることに強い思いがある方には、適した職種といえます。
⑤専門職
専門職には、税務職員・裁判所職員・労働基準監督官などがあり、それぞれの分野で専門知識を生かして働くことになるでしょう。
たとえば、税務職員なら税法や会計、裁判所職員なら法律関連、労働基準監督官なら労働法規や労働安全衛生に関する知識が問われます。試験は教養と職種ごとの専門科目で構成されるのです。
職種によっては、出題範囲が明確なため、計画的な学習がしやすいという利点があります。ただし、深い理解が求められる分、表面的な知識では太刀打ちできません。
自分の得意分野や関心のある分野を明確にしておけば、対策も立てやすくなります。専門性を活かしたい人にとっては、非常に魅力のある選択肢といえるでしょう。
⑥資格職
資格職は、薬剤師・保健師・獣医師など、特定の国家資格を持つ人が対象となる公務員職です。資格に基づいて専門的な業務に従事します。
この職種では、一般的な公務員試験が実施されないことも多く、資格を前提とした選考になるのです。書類選考や面接が中心となる場合が多いでしょう。
選考それ自体というよりは、資格取得そのものに高いハードルがあります。そのため、すでに資格を持っている人にとっては比較的スムーズに進められることも。
自分の専門スキルを社会に役立てたいと考えている方にとっては、非常にやりがいのある職種です。安定性と専門性の両立を目指せます。
公務員就活のスケジュール
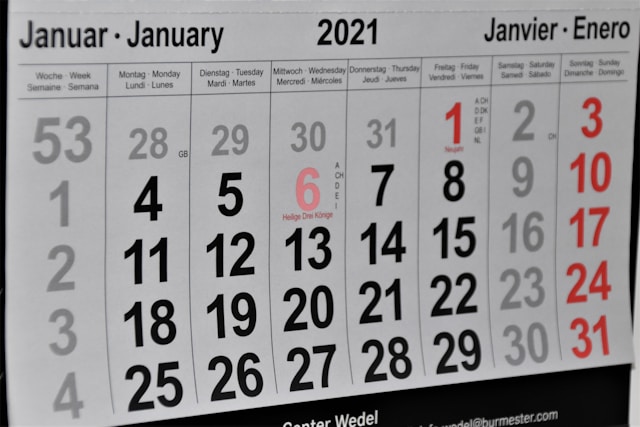
公務員を目指すうえで大切なのは、採用までのスケジュールを正しく把握することです。試験日やエントリー時期が決まっているため、民間企業の就活とは流れが異なります。
ここでは大学3年の春から4年の秋まで、時期ごとに行うべき準備を紹介しました。
- 大学3年春~夏:基礎知識の習得
- 大学3年夏~秋:インターンや説明会
- 大学3年冬~4年春:出願準備とエントリーシート
- 大学4年前半:一次試験・二次試験
- 大学4年夏~秋:最終合格後の内定手続き
①大学3年春~夏:基礎知識の習得
公務員を目指す就活は長期戦です。そのため、大学3年の春から夏にかけては、職種や試験制度などの基礎知識を早めに身につけておくことが重要。
国家公務員と地方公務員の違いや、各試験の内容、仕事内容などを理解しておくと、志望先を選びやすくなります。
漠然と「安定していそうだから」という理由ではなく、仕事内容をしっかり理解しておくことで、モチベーションも維持しやすくなるでしょう。
この時期から予備校やオンライン講座で勉強を始める人も増えてきます。出遅れると後で焦ることになりかねませんので、早めの行動がカギになるでしょう。
②大学3年夏~秋:インターンや説明会
夏から秋にかけては、自治体や官公庁が主催する説明会やインターンに参加する機会が増えてきます。数は多くありませんが、実際の業務を知るための貴重な場です。
特に地方自治体のインターンでは、地域に密着した仕事を体験でき、現場の雰囲気を肌で感じ取れます。
説明会では、採用担当者の話を直接聞くことで、試験の傾向や面接対策にもつながる情報が得られるでしょう。こうした経験は志望動機やエントリーシートの内容を深める助けにもなります。
予定が合えば、積極的に参加してみてください。
③大学3年冬~4年春:出願準備とエントリーシート
年末から春にかけては、出願に向けた準備が本格化します。各試験のエントリーや願書の提出、エントリーシートの作成が中心となるでしょう。
自治体によって提出時期が異なるため、複数併願する場合はスケジュール管理が不可欠です。提出漏れや記入ミスは選考対象外となることもあるため、慎重に進めてください。
エントリーシートには、志望動機や自己PRを具体的に記載します。自分の経験と職務内容を結びつけて表現できるよう、丁寧に準備することが大切です。
④大学4年前半:一次試験・二次試験
大学4年の春から初夏にかけては、公務員試験の本番です。多くの自治体や官庁では、6月から7月ごろに筆記の一次試験が行われます。その後、面接や集団討論などの二次試験が実施。
筆記試験は教養科目と専門科目の両方が対象で、十分な対策が必要です。ただし、筆記だけではなく、人物評価も重要なポイントになります。面接対策も並行して行っておくと安心です。
試験期間中は心身ともに負担が大きくなりがち。体調を崩さないように、生活リズムを整えておくことも忘れないでください。
⑤大学4年夏~秋:最終合格後の内定手続き
夏から秋にかけては、最終合格の発表が行われ、内定手続きが始まります。配属先の調整や提出書類の準備、場合によっては内定者向け研修などが予定されていることも。
この時期に得られる情報は、入庁後の準備にも役立ちます。仕事内容や組織の雰囲気を事前に知っておくことで、スムーズに職務へ移行しやすくなるでしょう。
一方で、残念ながら不合格となった場合でも、秋採用や民間企業の追加募集など、別の道は残されています。最後まであきらめずに行動する姿勢が大切です。
各時期に必要な対策を把握しておくことで、公務員就活はより計画的に進められます。焦らず、一歩ずつ前進してください。
公務員採用までの就活の流れ

公務員を目指す就職活動では、民間企業と異なる独自の流れがあります。各ステップに合わせて早めに準備しておくことで、落ち着いて試験に挑めるでしょう。
ここでは、公務員として採用されるまでの基本的な流れを7つの段階に分けて紹介します。
- 受験する公務員の職種・区分を決める
- 筆記試験対策を始める
- 書類を準備して出願する
- 一次試験(筆記試験)を受験する
- 二次試験(面接・適性検査など)を受験する
- 最終合格の通知を受け取る
- 採用面談・内定手続きに進む
①受験する公務員の職種・区分を決める
公務員試験を受けるには、まず志望する職種や区分を決める必要があります。国家公務員か地方公務員か、総合職か一般職かによって、仕事内容や試験内容は大きく変わるのです。
「地元で長く働きたい」なら地方公務員、「政策に関わる仕事をしたい」なら国家総合職が向いているかもしれません。
選択を誤るとモチベーションの維持が難しくなるため、仕事内容や勤務先、待遇などを事前によく調べてください。公務員講座のガイダンスや自治体の説明会を活用し、選択肢を広げることも大切です。
早い段階で自分の方向性を固めることが、その後の準備をスムーズに進めるコツといえるでしょう。
②筆記試験対策を始める
筆記試験は、公務員試験の中でも最も対策に時間がかかるパートです。教養試験に加え、職種によっては専門試験や論文試験が課されることもあります。
大学3年の春から夏に、対策を始める人が多いです。過去問や問題集を活用しながら、苦手分野を早めに見つけて克服してください。時間をかけて知識を積み上げることが、合格への近道になります。
予備校や通信講座を利用する場合も、自分のペースに合った教材を選ぶことが重要です。独学でも合格は可能ですが、効率よく進めるには計画的な学習スケジュールが不可欠。
早めに対策を始めておくことで、民間企業との併願も無理なく進められるようになります。
③書類を準備して出願する
筆記試験と並行して、出願に必要な書類の準備も進めておきましょう。申込書、写真、志望動機の記入など、細かい手続きが必要です。
募集要項に沿って、正確に準備することが大切。記入漏れや不備があると受験資格を失うこともあるため、必ず内容を見直してください。提出方法や期限も自治体や省庁によって異なるため、注意が必要です。
複数の試験を併願する場合は、スケジュール管理も欠かせません。出願の締切が重なることもあるため、カレンダーなどで管理しておくと安心です。丁寧な書類準備は、第一印象にもつながります。
余裕を持って取りかかりましょう。
④一次試験(筆記試験)を受験する
筆記試験は、最初の重要な関門です。教養・専門試験に加え、論文や記述式の問題が出されることも。出題形式や時間配分に慣れておくことが、合格の鍵を握ります。
模試や過去問で演習を重ねておくと、実践力が身につくでしょう。また、試験当日に焦らないためにも、会場や持ち物の確認は事前に済ませておくのが理想的です。
試験日は緊張する場面ですが、これまでの努力を信じて臨んでください。ミスを防ぐためには、心の余裕も大切です。ここでの結果が次の面接に直結するため、十分な準備を重ねておきましょう。
⑤二次試験(面接・適性検査など)を受験する
筆記試験に合格した後は、人物面が評価される二次試験に進みます。面接では、志望理由や自己PRに加えて、公務員としての資質が問われることが一般的です。
個人面接のほかに、集団面接や討論が行われることもあり、協調性やリーダーシップが見られます。模擬面接や自己分析を通して、自分の考えを的確に伝えられるようにしておきましょう。
また、身だしなみやマナー、言葉遣いにも注意が必要です。内容だけでなく、第一印象も評価に影響します。筆記で優秀でも、面接で落ちてしまうことは少なくありません。
自信を持って臨めるよう、練習を重ねてください。
⑥最終合格の通知を受け取る
二次試験が終わると、いよいよ最終合格の発表です。これは「内定」ではなく、「採用候補者」であることを示すものと考えておきましょう。通知は郵送やオンラインで届きます。
受験番号やログイン情報を忘れないよう、受験時の情報は必ず控えておいてください。合格しても、採用面談などの手続きを経て内定に進む必要があります。
複数の試験に合格している場合は、どこに進むかを決める時期でもあるのです。最終合格は大きな成果ですが、まだ気を緩めないようにしましょう。次に備えて、必要書類や日程確認を早めに進めてください。
⑦採用面談・内定手続きに進む
最終合格後は、具体的な配属先を決めるための採用面談や手続きが行われます。この面談で、勤務地や勤務条件についての確認がされることもあるでしょう。
内定手続きでは、健康診断や各種書類の提出が必要です。不備があると内定が取り消される可能性もあるため、丁寧に対応してください。また、この時点で内定を辞退する場合もあります。
その際は、連絡や書類提出のルールを守って対応しましょう。内定が確定すれば、安心して卒業や新生活の準備が始められます。最後まで気を抜かず、誠実に対応する姿勢が評価につながるでしょう。
公務員就活で押さえておきたいポイント

公務員試験は長期間にわたるうえ、職種や自治体ごとに流れが異なります。そのため、無理のない就活を進めるには、早めに準備し、重要なポイントを押さえておくことが欠かせません。
ここでは、公務員を目指す就活生が意識したい5つのポイントを紹介します。
- 志望動機を明確にする
- 試験日程・スケジュール管理を徹底する
- 筆記・面接の対策を行う
- 公務員試験の最新情報・傾向をリサーチする
- 併願先も視野に入れた就活戦略を立てる
①志望動機を明確にする
公務員を目指すなら、まず自分の志望動機をしっかり言語化しておくことが大切です。なぜその職種を選ぶのか、どのように貢献したいのかが明確になれば、書類や面接でも説得力が増します。
漠然と「安定していそう」という理由だけでは、選考での評価は得られにくくなるのです。業務内容を調べ、自分の経験や価値観とどのように結びつくかを深掘りしてください。
最近は人物重視の傾向が強まっており、志望理由の深さが選考結果に直結する場合もあります。早い段階で軸を固めておくと、その後の対策にもつながるでしょう。
②試験日程・スケジュール管理を徹底する
公務員試験は試験日や出願期間、合否発表などが職種や自治体によって異なります。そのため、情報を整理し、スケジュールをしっかり管理しておくことが重要です。
併願を考えている場合は、日程が重ならないか事前に確認しておくと安心。出願の締切を逃したり、準備不足のまま本番を迎えてしまったりすることがないよう、早めの行動を心がけてください。
スケジュール表やカレンダーを活用し、計画的に対策を進めていくことで、落ち着いて就活に取り組めるはずです。
③筆記・面接の対策を行う
公務員採用では、筆記試験と面接のどちらも重視されます。どちらか一方に偏った対策では、合格が難しくなるでしょう。
筆記では教養科目と専門科目が出題されるため、出題範囲の広さに対応できるよう、過去問や模試を活用しながら、効率的に知識を積み重ねてください。
一方、面接対策では自己分析や志望動機の整理が不可欠です。模擬面接などを通じて、自分の考えをわかりやすく伝える練習を積むことで、自信を持って本番に臨めるようになります。
④公務員試験の最新情報・傾向をリサーチする
公務員試験は、年度によって内容や重視されるポイントが変わる場合があります。たとえば、面接重視の傾向が強まったり、筆記の出題形式が変更されたりすることも珍しくありません。
そのため、公式サイトだけでなく、受験経験者の体験談や予備校の情報など、複数の情報源から最新の傾向を確認するようにしましょう。
情報を集めたあとは、自分の対策に活かせるよう、必要に応じて戦略を調整してください。常にアップデートされた情報をもとに準備を進める姿勢が大切です。
⑤併願先も視野に入れた就活戦略を立てる
1つの試験にすべてをかけるのはリスクが高いため、複数の併願先を検討することをおすすめします。倍率が高くなりがちな公務員試験では、選択肢を広げておくことが安心につながるのです。
ただし、やみくもに数を増やすのではなく、自分の関心やスキル、将来の働き方に合った職種や自治体を選ぶことが大切。
国家公務員と地方公務員では、業務内容や求められる資質も異なるため、よく比較して検討してください。併願を前提とした戦略を立てることで、結果的に自分に合った職場と出会える可能性が高まります。
公務員を目指す就活の進め方と成功へのポイント

公務員を目指す就職活動では、民間企業と異なる特徴を理解し、段階的に準備を進めることが成功への近道です。まず、公務員の仕事内容や種類を知ることで、自分に合った職種を選びやすくなります。
次に、公務員と民間企業の違いや、公務員ならではのメリットを理解することで、志望理由が明確になるでしょう。
さらに、各職種ごとの試験の難易度を把握し、スケジュールに沿って筆記・面接の対策を進めることが重要です。採用までの流れを把握し、計画的に行動することで、納得のいく内定獲得につながります。
公務員就活では、情報収集と自己分析、スケジュール管理の徹底が何より大切です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。











