テレビ業界の今後を徹底解説!構造・課題・将来性まとめ
「テレビ業界って今後どうなっていくの?伸び悩むのかな…?」
SNSやYouTubeなどの台頭により、若者を中心に「テレビ離れ」が進む中で、そんな疑問を持つ人も少なくありません。
しかし、依然として社会に大きな影響力を持つテレビ業界は、時代の変化に適応しながら進化を続けています。
本記事では、テレビ業界のビジネス構造や直面する課題、今後の展望までをわかりやすく解説します。テレビ業界の今とこれからを知りたい方は、ぜひ最後まで見てみて下さいね。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
テレビ業界とは?ビジネスモデルを解説

テレビ業界を志望するなら、まずはそのビジネスモデルの仕組みを正しく理解することが大切です。
とくに広告収入に頼った従来の構造と、近年注目されているサブスクリプション型の違いを知ることで、業界の強みや今後の課題が見えてくるはずですよ。
- 広告収入に頼ったビジネスモデル
- サブスクリプション型のビジネスモデル
① 広告収入に頼ったビジネスモデル
テレビ業界の基本的な収益源は、企業からのスポンサー収入です。番組の合間に流れるCMの枠が商品となり、視聴率が高い番組ほど広告の単価も上がります。
特にゴールデンタイムや大型特番では高額な広告枠が設定されており、そこから得られる収益が番組制作や人件費を支える構造です。
一方で、こうした広告モデルには課題もあります。インターネット広告が急成長した影響で、企業の広告予算がテレビから他の媒体へと分散しているのです。
広告に頼るだけでなく、多様な収益源を確保していくことが、今後の持続的な成長に向けて重要になるでしょう。
② サブスクリプション型のビジネスモデル
近年注目されているのが、サブスクリプション型のビジネスモデルです。
これは、月額などの定額料金を視聴者から直接受け取る仕組みで、NetflixやHulu、TVerといった動画配信サービスが代表例として挙げられます。
ただし、海外の競合サービスに比べると、オリジナルコンテンツやユーザーインターフェースの面で見劣りする部分も否めません。
サブスクリプション型への移行は、業界全体が抱える課題を解決する鍵となるでしょう。
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
テレビ業界の厳しい現状|直面する課題とは?
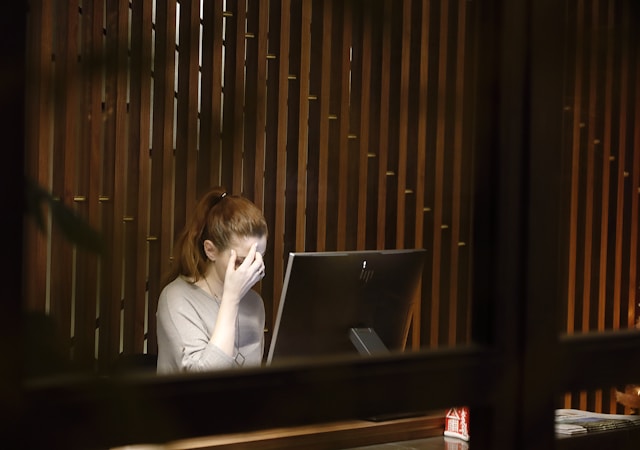
かつて「花形産業」と呼ばれたテレビ業界ですが、現在はさまざまな課題に直面しています。特にメディア環境の変化や働き方の問題など、構造的な課題が複雑に絡んでいます。
ここでは、現代のテレビ業界が抱える8つの主要な問題点を取り上げ、それぞれの現状と背景をわかりやすく解説します。
- 若い世代のテレビ離れ
- インターネット広告の台頭
- 視聴スタイルの多様化による競争激化
- 番組制作現場の過酷な労働環境
- 若手人材の確保と育成の難しさ
- デジタル化の遅れと業務効率の課題
- テレビ業界へのネガティブなイメージ
- コロナ禍による番組制作への影響
① 若い世代のテレビ離れ
テレビ離れは特に若者層で顕著です。スマホでYouTubeやTikTokを見る時間が増えた結果、テレビを見る機会が減っています。これは視聴率の低下に直結し、広告収入にも影響を与えています。
テレビ局はコンテンツや放送時間を見直し、SNS連携や見逃し配信を強化していますが、若者に刺さる企画づくりは容易ではありません。
単なる視聴習慣の問題ではなく、ライフスタイルの変化に合わせた新しい価値提供が求められているのです。
② インターネット広告の台頭
広告主がテレビから離れている背景には、インターネット広告の成長があります。
SNSや検索連動型広告は、ターゲットを絞って効果的に配信できるため、広告費の移行が加速しているのです。
その結果、テレビCMの出稿量が減少し、テレビ局の経営に直接打撃を与えています。
現在は配信サービスやSNSと連携した広告モデルの開発が進んでいますが、これまでの「視聴率=収益」という単純な構造では立ち行かなくなりつつあります。
③ 視聴スタイルの多様化による競争激化
視聴者は今、テレビだけでなくスマホ・PC・タブレットなど、さまざまな端末で映像コンテンツを楽しんでいます。
配信サービスの普及により、時間や場所に縛られない視聴スタイルが主流となり、地上波の競争相手はもはや同業他社だけではありません。
テレビ業界がこの変化に対応するには、マルチプラットフォームへの配信対応や、ニーズに合ったコンテンツ制作が不可欠です。
ただし、柔軟な発想とスピード感を持った組織体制がないと、変化についていけないおそれもあります。
④ 番組制作現場の過酷な労働環境
テレビ業界の制作現場は「激務」のイメージが強く、実際に労働時間の長さや休日の少なさが問題視されています。
とくにアシスタントディレクター(AD)は、深夜や早朝の撮影に対応しなければならず、心身ともに消耗しやすい状況です。
このような環境が原因で、若手の離職率が高いことも課題となっています。働き方改革が叫ばれる中、労働環境の改善は避けて通れません。
スケジュールの見直しや業務の分業化によって、徐々に変化が求められています。
⑤ 若手人材の確保と育成の難しさ
テレビ業界における若手人材の不足は深刻です。制作現場の過酷さや将来性への不安から、他業界へ流れる学生が増えています。
また、入社後も長期的に育成する仕組みが弱いため、人材の定着率が低く、現場のノウハウ継承にも支障をきたしています。
近年ではインターンシップや研修制度を整備する企業も増えてきましたが、魅力あるキャリアパスを示せなければ、優秀な人材を惹きつけることは難しいでしょう。
⑥ デジタル化の遅れと業務効率の課題
多くのテレビ局では、いまだに紙ベースの資料やFAXでのやりとりが残っており、業務の効率化が進んでいない現状があります。
コロナ禍を機にリモートワークやオンライン会議の導入が進みましたが、システム面の整備が不十分な企業も少なくありません。
業界全体として、映像データのクラウド管理や、進行表の電子化といった基本的なDX(デジタルトランスフォーメーション)の対応が遅れていることが課題です。
効率化と生産性の向上が、今後の競争力を左右するポイントになるでしょう。
⑦ テレビ業界へのネガティブなイメージ
テレビ業界は華やかなイメージがある一方で、「ブラック」「激務」「ハラスメントが多い」といったネガティブな印象も根強く残っています。
これは過去の報道や暴露本の影響もあり、就活生にとっては不安材料になりがちです。こうしたイメージを払拭するには、情報発信の透明性や社内コンプライアンスの徹底が求められます。
近年では、現場スタッフの声を紹介するSNS投稿や、若手社員のリアルな働き方を伝えるコンテンツも増えており、少しずつ変化が見え始めています。
⑧ コロナ禍による番組制作への影響
コロナ禍はテレビ業界の制作現場に大きな影響を与えました。ロケやスタジオ収録の制限により、番組の一時休止や再放送が相次ぎ、視聴者の満足度にも影響を与えました。
また、広告出稿も減少し、収益面でも苦しい状況に追い込まれました。しかし、この危機をきっかけに、少人数体制での制作やリモート収録など、新しい制作スタイルが生まれたのも事実です。
ピンチをチャンスに変える柔軟な姿勢が、今後の業界の生き残りを左右していくでしょう。
「業界分析」はこれ1冊だけ!業界分析大全を受け取ろう!
就活で志望業界を説得力高く語るには、「なぜこの業界なのか」をデータやトレンドで裏づける業界分析が欠かせません。とはいえ、IR資料やニュースを一から読み解くのは時間も手間もかかり、表面的な理解で面接に臨んでしまう学生も少なくありません。
そこで就活マガジン編集部では、主要20業界を網羅し「市場規模・最新トレンド・主要企業比較」まで1冊で整理した『業界分析大全』を無料提供しています。業界研究に迷ったら、まずはLINEを登録で特典をダウンロードして「面接で差がつく業界知識」を最短で手に入れてみましょう。
業界知識の深さは選考官が必ずチェックするポイントです。志望度の高さもアピールできるのでおすすめですよ。
テレビ業界の今後の動向|変化に対応するために必要な取り組み

変化の激しいメディア環境の中で、テレビ業界は多くの課題と向き合っています。視聴者の行動変化やテクノロジーの進化に応じて、各社は新たな取り組みを進めています。
ここでは、今後のテレビ業界が生き残るために重要とされる5つの対策についてご紹介します。
- 動画配信サービスへの参入
- 双方向コンテンツの開発
- ローカル局による地域密着型戦略の強化
- AIや視聴データを活用した番組企画
- 労働環境改善への取り組み
① 動画配信サービスへの参入
テレビ業界の未来を考えるうえで、動画配信サービスへの参入は欠かせません。
視聴者が「見たいときに見たいものを選べる」環境を求めるようになった今、リアルタイム放送だけではニーズを満たせなくなってきています。
そこで、各局はTVerやHuluなどの配信プラットフォームと連携し、自社コンテンツを配信する動きを強めています。
ただ、動画配信市場にはすでにNetflixやYouTubeといった巨大な競合が存在しており、差別化戦略が求められます。今後はオリジナルコンテンツの強化や使いやすいUI設計が鍵を握るでしょう。
② 双方向コンテンツの開発
これからのテレビ番組には、視聴者が参加できる仕組みがますます重要になります。SNSと連動した企画や、リアルタイムで視聴者の投票を反映させるような「双方向型コンテンツ」は、その代表例です。
こうした取り組みにより、視聴者の関与度が高まり、番組への愛着や視聴時間の増加が期待できます。
また、マーケティング的にも視聴者の反応をデータとして活用できるため、番組の質向上にもつながります。受け身の視聴から「参加型」へと転換することで、テレビの魅力を再定義できる可能性があります。
③ ローカル局による地域密着型戦略の強化
全国ネットの放送が中心だった時代から、今は各地域の特色に合わせた番組づくりが求められています。
とくにローカル局は、地域密着型の情報番組や地元企業とのタイアップ企画などを通じて、住民とのつながりを深めています。
このような取り組みは、視聴者との距離を縮めるだけでなく、地方経済の活性化にも貢献しています。
大都市圏以外のテレビ局が生き残っていくためには、地域との共創を軸にした事業展開が今後ますます重要になっていくでしょう。
④ AIや視聴データを活用した番組企画
AIや視聴データを活用することで、視聴者のニーズに即した番組づくりが可能になります。過去の視聴傾向やSNS上の反応データなどを分析すれば、どんな企画が求められているのかがより明確に見えてきます。
実際に一部のテレビ局では、AIを使って構成案やタイトルの候補を生成する試みも始まっています。経験や勘に頼りがちだった制作現場にも、データドリブンの発想が導入され始めているのです。
これにより、限られたリソースの中でも、より効率的で効果的なコンテンツ制作が期待されます。
⑤ 労働環境改善への取り組み
過酷な労働環境が問題視されてきたテレビ業界ですが、近年では働き方改革の動きが少しずつ進んでいます。
たとえば、スケジュールの見直しや業務分担の明確化により、長時間労働を減らす取り組みが行われています。
また、リモート収録やクラウド上での編集作業の導入も進み、柔軟な働き方が可能になりつつあります。
こうした改善は、若手人材の離職防止や、長く働ける職場づくりにもつながります。労働環境の整備は、人材確保だけでなく、番組の質や業界の信頼回復にも直結する重要なテーマです。
テレビ業界の企業の種類

テレビ業界とひとことで言っても、実際にはさまざまな種類の企業が関わっています。
就職を考える際には、それぞれの企業の役割や特徴を理解しておくことが大切です。
ここでは「テレビ局」「番組制作会社」「広告代理店」という代表的な3つの企業タイプについて紹介します。
- テレビ局
- 番組制作会社
- 広告代理店
① テレビ局
テレビ局は、番組を放送する中核的な存在です。ニュースやドラマ、バラエティなどを編成し、決まった時間に電波を通じて視聴者に届ける役割を担っています。
また、視聴率に応じて広告枠の価格が変動するため、どの番組をどの時間帯に放送するかという編成戦略が重要です。
キー局(例:フジテレビ、日本テレビ)と地方局では業務範囲が異なり、就職先としての特徴も異なります。公共性と影響力が高い一方で、安定志向の人にとって魅力的な職場と言えるでしょう。
② 番組制作会社
番組制作会社は、テレビ局から依頼を受けて実際の番組づくりを担当する企業です。ディレクターやAD、カメラマン、音声スタッフなど、現場を動かす人材が多数所属しています。
ドラマ、バラエティ、ドキュメンタリー、報道など、ジャンルに特化した会社も多く、企画から編集まで一貫して行う体制が整っていることも特徴です。
制作現場での実務経験を重ねながらスキルを磨けるため、現場志向の学生にとっては成長機会にあふれた環境と言えるでしょう。
ただし、ハードな勤務体系になるケースもあるため、覚悟が必要ですよ。
③ 広告代理店
広告代理店は、スポンサー(企業)とテレビ局の間をつなぐ役割を果たす存在です。クライアントの広告戦略を立案し、テレビCMの枠を買い付け、効果的な出稿方法を提案します。
さらに番組の内容に関与するケースもあり、タイアップ企画などを通じてブランディングに貢献することもあります。
広告主の意向と番組内容のバランスをとる力が求められるため、営業力や調整力が身につく仕事です。
華やかに見える反面、シビアな交渉が必要なこともあり、ビジネス志向の学生に適した職種だと言えるでしょう。
テレビ局の4つの種類

テレビ局と一口に言っても、実はその形態にはいくつかの種類があります。それぞれの特徴や役割を理解することで、就職活動における企業選びや志望動機づくりに役立ちます。
ここでは、「公共放送」「民放キー局」「準キー局」「地方局」の4つの分類を紹介します。
- 公共放送
- 民放キー局
- 準キー局
- 地方局
① 公共放送
公共放送とは、国民から集めた受信料をもとに運営されるテレビ局のことです。日本ではNHK(日本放送協会)がその代表で、営利を目的としない中立性が求められています。
報道や教育、災害情報の発信など公共性の高い役割を担っており、安定した財源と社会的使命感が特徴です。
民間企業の広告に依存しないぶん、視聴率への過度なプレッシャーが少ないのも利点といえるでしょう。
一方で、公的性格が強いために番組内容の自由度には一定の制約もあります。公共性を重視した働き方を志す方に向いている職場です。
② 民放キー局
民放キー局は、東京に本社を置き全国の系列局に番組を配信する中心的な存在です。具体的にはフジテレビ、日本テレビ、TBS、テレビ朝日、テレビ東京の5局がこれに該当します。
高視聴率番組を制作し、広告収入で成り立っているため、企画力とエンタメ性が重視される傾向にあります。
大規模なプロジェクトや著名人との仕事に携わる機会も多く、華やかな印象を持つ学生も多いでしょう。ただし、業務量が多く、スピード感のある働き方が求められるため、体力と対応力が必要とされます。
③ 準キー局
準キー局は、大阪や名古屋といった大都市圏に拠点を置き、一部番組を自社制作しながらキー局の番組も放送する中間的な存在です。
関西では朝日放送(ABC)や毎日放送(MBS)、中京圏では名古屋テレビ(メ〜テレ)などが代表的です。地域色を出しながらも、全国に影響力を持つコンテンツ制作に携われるのが魅力です。
キー局に比べると規模はやや小さいですが、その分若手が活躍しやすい土壌もあり、裁量の大きな仕事に早くから関われることもあります。地元志向かつコンテンツ制作に関心がある人に向いているでしょう。
④ 地方局
地方局は、各都道府県に根ざした放送を行うテレビ局です。キー局や準キー局の番組をネットワークで放送しつつ、地域ニュースや地元イベントの紹介など、地域密着型の情報発信に力を入れています。
視聴者との距離が近く、地元企業や自治体との連携が重要な役割を果たします。そのため、地域社会に貢献したいと考える就活生にとっては大きなやりがいを感じられる職場です。
一方で、制作予算や人員が限られているため、多くの業務を少人数でこなす柔軟さが求められます。
テレビ業界の代表的な職種

テレビ業界にはさまざまな職種があり、それぞれに異なる役割とやりがいがあります。自分に合った職種を見極めるためにも、具体的な業務内容や求められる能力を知っておくことが大切です。
ここでは代表的な4つの職種について紹介します。
- 番組制作
- 技術スタッフ
- アナウンサー
- 営業・事務
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
① 番組制作
番組制作は、企画・構成・撮影・編集まで一連の制作プロセスを担う中心的な職種です。
プロデューサーやディレクター、AD(アシスタントディレクター)など役割は細かく分かれており、現場では常にチームで連携しながら番組づくりを進めていきます。
やりがいは、自分が関わった番組が多くの視聴者に届き、反響を得られる点です。ただし、放送スケジュールに合わせて動くため、勤務時間が不規則になることも多く、体力と責任感が求められます。
柔軟な対応力とコミュニケーション能力も欠かせません。
② 技術スタッフ
技術スタッフは、番組の撮影や音声、照明などを担当する専門職です。
カメラマン、音声スタッフ、照明オペレーター、編集技師などが含まれ、現場での映像や音のクオリティを支える重要な役割を果たします。
番組のジャンルや現場の規模によって求められる技術も異なり、常に進化する機材への対応力も必要です。
裏方ではありますが、確かな技術力が番組全体の完成度を左右します。手に職をつけて、現場でスキルを磨きながら働きたい人に向いている職種です。
③ アナウンサー
アナウンサーは、ニュースや情報番組、バラエティなどで司会・進行を務める職種です。
原稿を読むだけでなく、時には取材や現場リポートも担当し、視聴者に情報を正確かつ分かりやすく伝えることが求められます。
テレビ局の“顔”として認識されるため、言葉遣いや表現力はもちろんのこと、信頼感や親しみやすさも重要な資質です。
また、生放送での対応力や、突発的なニュースにも臨機応変に対応できる冷静さも必要です。人前に出ることが好きで、情報発信に興味がある人に適しています。
④ 営業・事務
営業・事務職は、番組制作以外の業務全般を支える裏方の存在です。営業はスポンサー企業との広告枠の交渉や契約管理を行い、テレビ局の収益を支える要となります。
一方、事務職は人事・経理・編成など社内業務を円滑に進める役割を担っています。どちらも制作現場には直接関わらないものの、会社全体の運営にとって不可欠なポジションです。
安定した働き方を志す学生や、制作よりもビジネス寄りの業務に関心がある方におすすめの職種です。
テレビ業界で求められるスキルとは?

テレビ業界は多くの人々と関わる共同作業の連続であり、視聴者に「おもしろい」「見たい」と思わせるコンテンツを生み出すには、特有のスキルが欠かせません。
ここでは、業界で活躍するうえで求められる代表的な6つのスキルを紹介します。
- チームで働くためのコミュニケーション力
- 流行やトレンドをキャッチする力
- 突発的なトラブルに対応する柔軟性
- 不規則な勤務に耐える体力
- タイトな進行に対応するスケジュール管理力
- 視聴者を惹きつける企画力
① チームで働くためのコミュニケーション力
テレビ番組は一人で作るものではなく、多くの部署やスタッフとの連携が必須です。
そのため、相手の意見を聞きながら自分の意見を伝える力、そして関係を円滑に保つコミュニケーション力が求められます。
② 流行やトレンドをキャッチする力
番組は常に時代の空気を反映しています。
SNSやニュース、街の雰囲気などから敏感に流行をつかみ、それを企画に落とし込む力が求められます。
日常的にアンテナを張る習慣が重要ですね。
③ 突発的なトラブルに対応する柔軟性
撮影現場では、機材トラブルや出演者の急な変更など、予期せぬ出来事がよく起こります。
そんなとき、焦らず冷静に対応できる柔軟な発想力と判断力が信頼につながります。
④ 不規則な勤務に耐える体力
深夜の編集や早朝のロケなど、勤務時間が不規則になりがちな業界です。
体調を崩さず働き続けるには、日頃からの体調管理と基本的な体力が不可欠です。
健康意識も仕事の一部と考える必要がありますよ。
⑤ タイトな進行に対応するスケジュール管理力
限られた時間内に企画から放送までを仕上げるには、進行管理のスキルが求められます。
特にディレクターやADには、遅延が出ないよう各工程を見通してスムーズに進める力が重要です。
⑥ 視聴者を惹きつける企画力
最後に、もっとも重要なのは「見たい」と思わせる番組を生み出す企画力です。
発想力や視点のユニークさに加え、視聴者のニーズや感情に寄り添うことが求められます。
日常の気づきや好奇心が、魅力的な企画につながります。
テレビ業界で働くメリット

テレビ業界には「厳しい」「不安定」というイメージが先行しがちですが、それでも多くの人が憧れる理由があります。
ここでは、実際に働くからこそ得られる6つのメリットをご紹介します。自分に合う魅力があるか、ぜひチェックしてみてください。
- 多くの視聴者に影響を与える仕事ができる
- 情報の最前線にいられる
- 現場経験を通じて実践的に成長できる
- 専門分野のプロとして活躍できる
- 著名人やクリエイターと仕事ができる
- 仲間と一体になって番組を作り上げる充実感を得られる
① 多くの視聴者に影響を与える仕事ができる
テレビ番組は全国に発信され、何百万人という視聴者の心に届きます。
自分が関わった内容が社会の話題になったり、誰かの人生を変えるきっかけになることもあります。
この影響力の大きさは、テレビ業界ならではのやりがいです。
② 情報の最前線にいられる
日々、世の中の動きにアンテナを張り、ニュースやエンタメの最先端に触れられる点も魅力です。
常に時代の流れを感じながら働けるため、知的好奇心が刺激され続けます。
新しいことが好きな人にはぴったりの環境です。
③ 現場経験を通じて実践的に成長できる
テレビ業界では机上の学習よりも、現場での経験が重視されます。
失敗や試行錯誤を繰り返しながらも、実践の中でしか得られない力を身につけられるため、成長スピードが早いのも特徴です。
④ 専門分野のプロとして活躍できる
撮影、編集、音声、照明など、それぞれの分野でプロフェッショナルとしての技術や知識を深められます。
高い専門性が身につけば、将来フリーランスとしても活躍できるなど、キャリアの幅も広がります。
⑤ 著名人やクリエイターと仕事ができる
番組づくりでは芸能人や専門家、アーティストなど、多くの著名人と関わる機会があります。
間近で仕事ぶりを見られることで、刺激を受けたり、人脈を広げられたりします。
非日常の体験ができるのも魅力です。
⑥ 仲間と一体になって番組を作り上げる充実感を得られる
1本の番組を完成させるには、たくさんの人と協力が必要です。
チームでひとつのゴールを目指す過程には困難もありますが、それを乗り越えたときの達成感は格別ですよ。
仲間との強い絆が生まれるのがこの業界の特徴です。
テレビ業界の主要企業

テレビ業界にはそれぞれ異なる特徴や戦略を持つ大手局が存在しています。
ここでは、代表的な5つのテレビ局をピックアップし、それぞれの強みや取り組みの違いを見ていきましょう。
志望企業選びの参考にもなるはずですよ。
- フジテレビ
- 日本テレビ
- TBS
- テレビ朝日
- テレビ東京
① フジテレビ
フジテレビはバラエティ番組のパイオニアとして知られ、若年層を中心に強い支持を得てきました。
特に「トレンディドラマ」や「お笑い番組」のイメージが根強く、エンタメ色の強い編成が特徴です。
しかし、近年は視聴率の面で苦戦しており、動画配信サービス「FOD」の強化や、YouTubeチャンネル運営など、デジタル領域への転換を進めています。
これからのメディア環境に適応しようとする姿勢は、変化を楽しめる人材にとって魅力的なポイントです。
② 日本テレビ
日本テレビは視聴率三冠王を達成することも多く、民放キー局の中でも安定した実績があります。
特に「ドラマ」「情報番組」「スポーツ中継」のバランスが良く、幅広い層に支持されているのが特徴です。
また、Huluを運営する子会社を通じて動画配信事業にも早くから注力しており、マルチプラットフォーム戦略の先進性も見逃せません。
時代の変化を先読みし、実行できる力を持つ企業として評価されています。
③ TBS
TBSは「ドラマのTBS」と称されるほど、質の高い連続ドラマの制作に定評があります。
社会派からヒューマンまで、幅広いテーマを深く掘り下げる企画力が強みです。
加えて、TVerやParaviといった動画配信との連携を強め、コンテンツを多様な形で提供する動きも活発です。
企画や構成に興味のある学生にとって、自分の発想を活かせる環境が整っているといえるでしょう。
④ テレビ朝日
テレビ朝日はニュースと報道に強い局として、信頼性の高い情報を発信する姿勢が特徴です。
特に「報道ステーション」や「スーパーJチャンネル」は長年安定した人気を保っています。
一方で、アニメや刑事ドラマといった分野でも高い視聴率を記録し、エンタメとのバランスも重視しています。
真面目な姿勢で仕事に取り組みたいと考える人に向いている企業といえます。
⑤ テレビ東京
テレビ東京は「テレ東らしさ」とも言われる独自路線が最大の魅力です。
他局とは一線を画したマニアックで実験的な番組づくりを得意とし、深夜枠などでコアなファンを獲得しています。
また、経済番組やアニメ制作にも力を入れており、業界内でも存在感を放つ存在です。
少数精鋭の環境でチャレンジしたい学生にとっては、大きなやりがいを感じられるフィールドです。
テレビ業界各社の取り組み事例

近年のメディア環境の変化に対応するため、各テレビ局は独自の戦略を打ち出しています。
ここでは、日本テレビ・テレビ静岡・フジテレビの具体的な事例を取り上げ、業界がどのように変化に適応しているかを見ていきましょう。
- 日本テレビの「TVer」や「Hulu」連携によるネット配信強化
- テレビ静岡の地域密着型番組とイベント連携戦略
- フジテレビの海外向け番組販売とアジア展開の取り組み
① 日本テレビの「TVer」や「Hulu」連携によるネット配信強化
日本テレビは、視聴者のライフスタイルの変化に対応するため、ネット配信へのシフトを加速させています。代表的なのが「TVer」や「Hulu」との連携によるコンテンツの多角的な提供です。
特にHuluは日本テレビの子会社として機能しており、地上波放送で放映された番組の見逃し配信や、Hulu独自のコンテンツ制作にも注力しています。
このような動きは、従来のテレビという枠にとらわれず、視聴者がいつでもどこでも番組を楽しめる環境を整えることにつながっています。
若年層のテレビ離れが進む中、ネット配信の強化はテレビ局にとって重要な生き残り戦略となっています。
② テレビ静岡の地域密着型番組とイベント連携戦略
ローカル局であるテレビ静岡は、地元の人々との結びつきを強めることに力を入れています。
また、自治体や地元企業と連携したイベント開催やライブ配信を通じて、単なるテレビ放送にとどまらない地域貢献型のメディアとしての存在感を発揮しています。
このような活動は、広告主にとっても地元での信頼性や影響力を高める機会となり、ビジネス面でも有利に働きます。
ローカル局ならではの取り組みが、視聴者との距離を縮める好例と言えるでしょう。
③ フジテレビの海外向け番組販売とアジア展開の取り組み
フジテレビは、国内市場の縮小を見据えたうえで、海外市場への展開にも注力しています。
特にアジア諸国への番組販売や共同制作の推進を通じて、日本独自のコンテンツを国境を越えて届ける体制を強化しています。
韓国・台湾・タイなどでは、日本のドラマやバラエティ番組の人気が高く、ローカライズした放送も展開されています。
このような国際戦略は、フジテレビにとって新たな収益源の確保とブランド力向上に大きく貢献しており、今後の成長分野として期待が高まっています。
テレビ業界の志望動機に盛り込むべきポイント

就活で「なぜテレビ業界なのか」「なぜこの企業を選んだのか」を明確に伝えることは、他の応募者と差をつけるうえで重要です。
この章では、志望動機に含めるべき具体的な観点を4つに分けて解説します。
- なぜテレビ業界なのか
- なぜこの企業なのか
- 入社後にどう貢献できるか
- どのようなキャリアを目指すのか
① なぜテレビ業界なのか
テレビ業界を志望する理由は、自分の関心や経験と業界特性がどうつながっているかを示すことが鍵です。
たとえば「人の心を動かすコンテンツを届けたい」という想いが、番組制作の仕事に重なる場合は説得力が増します。
単に「エンタメが好き」といった漠然とした表現ではなく、どんな番組や出来事に感動し、その体験が将来にどうつながるかを伝えると良いでしょう。
過去の視聴体験や、自分なりの視点でテレビの魅力を語ることが、面接官の印象にも強く残ります。
② なぜこの企業なのか
志望企業の特徴をよく理解し、その上でなぜ他社ではなくそこなのかを述べることが大切です。
たとえば報道に強みを持つ局に対しては「真実を迅速かつ正確に伝える姿勢に共感した」、バラエティ制作に注力している局なら「多様な世代を楽しませる演出力に惹かれた」など、企業の特色と自身の価値観を結びつけて説明しましょう。
OB訪問や企業説明会で得た情報を引用することで、より具体性と信頼性のある動機づけが可能になります。
③ 入社後にどう貢献できるか
入社後に自分がどう活躍できるかを描くことで、採用担当者に将来のビジョンを示すことができます。
たとえば大学時代のプロジェクトで培ったスケジュール管理力を、制作現場の進行管理に活かしたいと伝えると、現場感覚を持った志望者として評価されやすくなります。
また、デジタルツールへの理解やSNS活用スキルなども、現代の放送業界では強みになります。
自分の持ち味を「業務にどう生かすか」まで結びつけて説明することがポイントです。
④ どのようなキャリアを目指すのか
キャリアの展望を語る際には、短期的な目標と長期的なビジョンの両方を意識すると効果的です。
たとえば「まずはADとして現場を支え、将来的には自ら企画立案し、社会的インパクトのある番組を制作したい」といった流れを描くと、成長意欲が伝わります。
加えて、業界の変化に対応する姿勢を示すことで、柔軟な人材としても印象づけられます。
将来像が曖昧なままでは説得力に欠けるため、自己理解を深めたうえで言語化しておきましょう。
テレビ業界への志望動機例文

テレビ業界を志望するにあたって、どのような志望動機を伝えればよいのか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
ここでは、志望する企業の種類ごとに分けて、具体的な例文を紹介します。
また、志望動機がそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの志望動機テンプレを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
志望動機が既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。
【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
① キー局を志望する場合
キー局を志望する就活生に向けて、テレビ業界への関心をうまく伝える例文を紹介します。多くの視聴者に影響を与えたいという想いと、自分自身の体験をうまく結びつけることがポイントです。
《例文》
| 小学生のころ、家族で毎週観ていたバラエティ番組が、家族の会話のきっかけとなり、私にとってテレビは日常を豊かにしてくれる存在でした。 大学では映像制作サークルに所属し、自分で企画から編集まで行う中で、映像が視聴者の感情を動かす力に魅了されました。 とくに貴社の番組は、情報とエンタメのバランスがよく、幅広い世代に届けられている点に感銘を受けました。 多くの人の心に届く番組を作る一員として、自らのアイデアや熱意を形にし、社会にポジティブな影響を与えられる存在になりたいと考えています。 |
《解説》
家族や大学での体験とテレビへの想いをつなげることで、志望動機に説得力を持たせています。自分の「原体験」と「企業の特徴」を一文でつなぐのがコツです。
② 地方局を志望する場合
地域に根ざした放送を行う地方局に興味を持つ学生に向けて、地元とのつながりや地域への貢献を軸にした志望動機の例文を紹介します。
《例文》
| 私の実家は地方都市にあり、子どものころから地元局の夕方ニュースを家族で見るのが日課でした。地域の話題を丁寧に伝えるその番組が、住民の安心や誇りにつながっていると感じていました。 大学では地域活性をテーマにしたゼミに所属し、地方の情報発信の重要性を学びました。そのなかで、地方局は単なる情報提供だけでなく、地元との強いつながりを持つ存在だと実感しました。 私は、自分が育ったまちの魅力を掘り起こし、視聴者に届ける番組づくりに携わることで、地域への恩返しをしていきたいと考えています。 |
《解説》
地元とのエピソードを具体的に語り、地方局で働く意義と結びつけています。視聴者目線の体験と大学での学びをセットにして書くと効果的です。
③ 番組制作会社を志望する場合
番組制作会社を目指す学生に向けて、自らの行動や体験を通じて番組づくりへの興味が芽生えたという流れを大切にした例文を紹介します。
《例文》
| 大学の文化祭で動画制作チームに参加し、企画から撮影、編集までを担当した経験があります。 見る人を楽しませるには、何を伝えたいのかを明確にし、そのための演出や構成を練ることが重要だと実感しました。 完成した映像が上映された際、観客の笑いや拍手を聞いた瞬間、自分の手で「伝える」ことの力強さに感動しました。 この経験を通じて、より多くの人に感動や気づきを届ける番組制作の仕事に携わりたいと強く思うようになりました。 御社では、現場での経験を重ねながら、自分にしかつくれない番組を世に送り出す力を身につけていきたいです。 |
《解説》
自ら手を動かした体験を軸に、番組制作に対する想いを伝えています。表面的な「番組が好き」ではなく、「なぜ好きか」を掘り下げて書くと説得力が増します。
テレビ業界の全体像を理解しておこう!

テレビ業界は、従来の広告収入に頼ったビジネスモデルから脱却し、動画配信やAI活用といった新たな方向へと大きく舵を切ろうとしています。
確かに、若年層のテレビ離れやネット広告の台頭など厳しい課題は多く存在しますが、それに対抗する動きも着実に進んでいます。
今後は、地域密着型戦略やインタラクティブな番組づくり、データ活用による番組開発など、変化に柔軟に対応できる企業や人材が求められます。
テレビ業界を志望する学生にとっては、業界の構造や職種の理解を深め、必要なスキルや強みを明確にすることが、自身のアピール力を高める鍵となるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。











