公務員と民間の併願を成功させる準備と対策ポイント
安定性が魅力の公務員と、成長環境や多様な選択肢がある民間企業。どちらも魅力的だからこそ、併願という選択肢が注目されています。
この記事では、公務員と民間の併願の可否や実際のケース別パターン、メリット・デメリット、成功のための準備と対策までを徹底的に解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ESをAIに丸投げ|LINEで完結
- 完全無料でESを簡単作成
- 2赤ペンESで添削依頼|無料
- 就活のプロが丁寧に添削してくれる
- 3志望動機テンプレシート|簡単作成
- カンタンに志望動機が書ける!
- 4自己PR自動作成|テンプレ
- あなたの自己PRを代わりに作成
- 5企業・業界分析シート|徹底分析
- 企業比較や選考管理もできる
公務員と民間企業の併願は可能?

公務員と民間企業の就職活動を同時に進められるのか、不安に感じる就活生も多いでしょう。結論としては、併願は可能です。
ただし、両者には採用スケジュールや選考方法の違いがあるため、明確な計画が求められます。
とはいえ、どちらか一方に絞らず幅広く可能性を探る姿勢は、自分に合った進路を見つけるうえで有効です。ただ、準備が不十分なまま進めると、どちらも納得のいく結果にならないおそれがあります。
そのため、併願を検討する場合は、最初に優先順位をはっきりさせたうえで計画的に動き、限られた時間をどう活用するかを意識して取り組んでください。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
公務員と民間企業の併願をするケース

就職活動において、公務員と民間企業の併願はめずらしくありません。ただし、選考時期や準備の進め方が大きく異なるため、両立を図るには注意が必要です。
準備が偏ると、どちらも中途半端な結果に終わるおそれがあります。ここでは、実際によくある併願のパターンを3つ紹介し、それぞれの特徴と注意点について解説します。
- 公務員が第一志望で保険として民間を受けるケース
- 公務員と民間企業どちらにも関心があるケース
- 民間企業が第一志望で念のため公務員も受けるケース
① 公務員が第一志望で保険として民間を受けるケース
公務員を本命にしているものの、採用に漏れるリスクを考慮して、民間企業の選考も受けておこうと考える人は多いです。
特に公務員試験は倍率が高く、一次の筆記を通過しても最終面接で不合格になる可能性もあるため、念のための併願は合理的といえるでしょう。ただし、このケースでは民間の準備が後手に回ることがよくあります。
エントリーや面接練習などの対策が十分にできず、結果として民間の選考で良い結果を得られないこともめずらしくありません。
そのため、民間企業に対しても「受けるからには内定を取りに行く」意識を持つことが必要です。特にスケジュールが早い業界や企業は前もって把握し、早期選考に備えましょう。
② 公務員と民間企業どちらにも関心があるケース
仕事の安定性を重視して公務員に惹かれつつ、民間企業の成長性にも魅力を感じている学生は、両者の違いを冷静に比較したうえで選びたいと考えることが多いです。
方向性が曖昧なまま進めてしまうと、説得力に欠ける印象を与えてしまい、採用担当者に「本気度が足りない」と受け取られるおそれがあります。
対策としては、まず自己分析を深めることが第一です。自分の価値観や将来像、働き方の志向を整理し、どちらの道が自分に合っているのかを言語化しましょう。
そのうえで、それぞれの志望理由を納得感のある形に整えることが重要です。単なる保険ではなく、自分の意志で両方を受けているという姿勢が伝わるようにしてください。
③ 民間企業が第一志望で念のため公務員も受けるケース
最初から民間企業でのキャリアを希望しており、選考対策にも力を入れてきた学生が、最終的な保険として公務員を受験するパターンもあります。
このケースで見落としがちなのが、公務員試験に必要な準備の重さです。一般的なSPIや面接対策とは異なり、数的処理や法律・経済といった専門科目の勉強には相応の時間がかかります。
また、公務員試験のスケジュールは民間よりも遅めではあるものの、自治体や省庁によって異なり、併願の調整が難しいこともあります。
公務員をもう一つの本命と捉えて臨む姿勢が大切です。そのためにも、就活全体のスケジュールを見通しながら、学習と選考準備を効率的に進めましょう。
公務員就職と民間就職の違い

公務員と民間企業、それぞれの就職先には明確な違いがあります。併願を考えている就活生にとって、それぞれの特性をしっかり理解しておくことは欠かせません。
まずは、仕事内容や選考、待遇などの観点から具体的に比較していきましょう。ここでは、公務員就職と民間就職の違いについて具体的に紹介します。
- 仕事内容の違い
- 選考フローの違い
- 待遇・キャリアパスの違い
- 求められる人物像の違い
- 働き方・ワークライフバランスの違い
① 仕事内容の違い
公務員と民間企業では、日々取り組む仕事の内容や目的が大きく異なります。
公務員は国や地域の安定と福祉を支えるため、法令や制度に基づいた公共サービスの提供が主な役割です。
一方、民間企業では利益の創出が大きな目標であり、そのために営業活動、商品開発、マーケティング、顧客対応など、多様な業務が展開されています。
どちらの仕事も社会にとって必要ですが、自分がどんな価値に共感し、どんな成果を出したいのかを明確にすることが、後悔のない進路選びにつながります。
② 選考フローの違い
就職活動の選考フローも、公務員と民間企業では大きな違いがあります。
公務員の場合、筆記試験が大きなウェイトを占めており、教養試験や専門試験、論文試験など複数の試験を経て面接に進むのが一般的です。
一方で、民間企業の選考は企業によって異なりますが、エントリーシートや履歴書を提出した後、Webテストや面接が数回行われるというのがよくある流れです。
また、公務員は一斉試験であるのに対し、民間は通年採用や早期選考などスケジュールがばらついているため、併願を希望するなら時期をしっかり把握しておく必要があります。
両方の試験対策を並行して行うには、優先順位をつけながら計画的に進める力が重要です。
③ 待遇・キャリアパスの違い
待遇面や将来のキャリアパスについても、公務員と民間企業では考え方に違いがあります。
公務員は、給与制度が統一されており、職種ごとの等級や勤続年数に応じて昇給していく仕組みです。定期昇給や安定した賞与、退職金制度などがあり、景気に左右されにくいのも魅力といえるでしょう。
一方、民間企業では企業ごとに給与制度が異なり、昇給スピードに個人差が出やすいのが特徴です。その反面、業績悪化などで待遇が下がるリスクも否定できません。
長期的な視点で、自分が目指す働き方や人生設計に合ったキャリアパスを考えてみてください。
④ 求められる人物像の違い
求められる人物像にも明確な違いが見られます。公務員は、法律や制度を守りながら多くの人と協力して業務を進める必要があるため、協調性や公平性、責任感のある人材が評価されやすいです。
民間企業では、これとは異なり、変化に柔軟に対応しながら新しい価値を生み出す力が重視されます。
また、公務員の面接では、地域社会への貢献意識や倫理観を問われることが多いのに対し、民間企業では業界への理解度や熱意、企業研究の深さなどが重視される傾向があります。
どちらの選考でも選考準備の段階で、自分の強みと弱みをしっかり言語化しておくと、対応しやすくなります。
⑤ 働き方・ワークライフバランスの違い
働き方やワークライフバランスにも大きな違いがあります。公務員は法律に基づく勤務形態が定められており、原則として土日祝日が休みで残業も比較的少ない傾向にあります。
一方、民間企業では業界や企業文化によって働き方が大きく異なります。繁忙期には残業が増えることもありますし、転勤や異動の可能性もあります。
どちらの働き方が自分に合っているのかは、生活スタイルや将来設計によって異なります。
自分にとって何を優先するのかを明確にすることで、後悔のない選択ができるようになります。
公務員×民間併願のメリット

公務員と民間企業の就職活動を同時に進めることには、ただの保険というだけではない、多くの利点があります。将来の選択肢が広がり、自分自身を見つめ直す機会にもなるため、併願は非常に有効です。
ここでは、公務員と民間企業を併願することで得られる主なメリットを5つ紹介します。
- 選択肢が広がり将来の視野が広くなる
- 公務員と民間就活で対策を相互に活かせる
- 全落ちのリスクを軽減できる
- 幅広い業界・職種への理解が深まる
- 公務員と民間を比較検討しながら進路選択できる
① 選択肢が広がり将来の視野が広くなる
将来の進路を考えるうえで、選択肢を持っておくことは大きな安心材料になります。公務員試験だけに絞ると、不合格の際に次の道をすぐに決めるのが難しくなるかもしれません。
また、複数の進路を並行して考えることで、「安定性を重視したいのか」「やりがいを求めたいのか」といった自分自身の価値観や働く上で重視したい判断軸が具体化されていくのです。
さらに、就職活動を通じて得た情報は、たとえ一方を選ばなかったとしても、今後のキャリア選択に役立つ知見となります。
広い視野で将来を見据えることで、後悔の少ない選択ができるでしょう。
② 公務員と民間就活で対策を相互に活かせる
公務員と民間の併願では、それぞれの準備が相乗効果を生みます。民間の面接練習で培った自己PRや論理的な話し方は、公務員の人物試験にも応用できます。
加えて、グループディスカッションや集団面接など、形式の異なる選考に触れることで、柔軟な対応力が身につきます。
どちらにも共通して求められるのは、「自分を客観的に理解し、それを伝える力」です。その点で、併願は準備の幅を広げ、自己成長のスピードを加速させてくれます。
結果として、一方に偏った準備よりも、全体として就活スキルがバランスよく高まるのではないでしょうか。
③ 全落ちのリスクを軽減できる
就活において最も避けたいのは、どちらにも受からず進路が決まらない状態です。公務員試験は倍率が高く、民間企業も選考基準が多様なため、どちらも油断できません。
1つの選択肢に絞って進めた結果、すべて不合格だったという事例も少なくないのが現実です。その点、併願をしておけば、どちらかが不調でももう一方でカバーできる可能性があります。
公務員試験が不合格でも民間企業から内定を得ていれば、無職の期間を作らずに済みますし、その逆も然りです。
安定した気持ちで取り組むことが、結果的に良いパフォーマンスにもつながるでしょう。自分の将来を守るためにも、併願は賢明な選択です。
④ 幅広い業界・職種への理解が深まる
併願によって、公務員だけでなく民間企業にも触れる機会が増えます。それぞれの業界で求められる役割や価値観を知ることで、自分に合った働き方を見つけやすくなるでしょう。
さらに、民間企業の多様なビジネスモデルや、成長戦略に直接触れることによって、視野が広がり、職業観にも深みが出てくるはずです。
一方、公務員試験を通しては、法律や行政の仕組みに関する知識が自然と身につき、社会への関心も高まっていきます。
結果として、選択肢に対する理解が深まり、自信を持って進路を決められるでしょう。
⑤ 公務員と民間を比較検討しながら進路選択できる
実際に両方の就活を経験することで、自分に本当に合う働き方や職場環境を見極めやすくなります。
公務員の安定性や使命感に魅力を感じる一方、民間企業のスピード感や成長環境に惹かれることもあるかもしれません。
それぞれの選考を体験する中で、仕事内容、福利厚生、ワークライフバランス、人間関係など、さまざまな要素を比較できます。
経験を通して得た実感に基づく選択は、将来への納得感にも直結します。どちらが正解ということではなく、自分に合った道を選ぶことが何より大切です。
そのためにも、併願という方法で複数の可能性を比べながら進路を決めていくのが効果的です。
公務員×民間併願のデメリット

公務員と民間企業の就職活動を同時に進めることには、一定のメリットがありますが、いくつかのデメリットも避けられません。
特にスケジュールや準備の両立、精神的な負荷などが問題になりやすいです。ここでは、併願によって起こりがちな代表的なデメリットを5つ紹介します。
- スケジュールや対策の両立が難しい
- どちらにも集中できず結果が中途半端になるリスクがある
- 精神的・体力的に負荷が大きい
- エントリーや試験対策にかかる費用が増える
- 内定・合格後の進路決定で迷いやすくなる
① スケジュールや対策の両立が難しい
公務員試験と民間企業の選考では、時期も進み方も大きく異なります。民間は3月以降にエントリーが始まり、早い企業では4月中に内定が出ることもあります。
一方、公務員は6月〜7月の筆記試験に向けて長期的な準備が必要で、さらに面接がその後に続くため、活動期間が長くなりやすいです。
また、公務員では数的処理や法律の理解が必要なのに対し、民間では企業研究やグループディスカッション対策などが重要です。
このような期間や準備内容の違いを同時並行で進めるには、かなりの計画性と自己管理が求められるでしょう。
② どちらにも集中できず結果が中途半端になるリスクがある
併願を進めていくと、1日の中で公務員と民間それぞれのタスクに取り組む必要が出てきます。
民間と公務員では求められる視点が異なるため、頻繁に志望理由や自己PRの内容を切り替える必要があります。それに慣れていないと、発言がぶれてしまい、一貫性を欠いた印象を与えてしまうでしょう。
こうしたリスクを回避するには、受ける業界や職種を明確に絞り込んだうえで、優先順位をつけて対策することが大切です。
③ 精神的・体力的に負荷が大きい
公務員と民間の両方を併願することは、心身に大きな負荷をかける行為です。
選考が重なる時期は特にハードで、スケジュールを詰め込めば詰め込むほど、体力だけでなく精神的な余裕も失われていきます。
毎週のように面接や試験が続く中で、準備や復習を行う余裕がなくなってしまうこともあるでしょう。
精神的・身体的な健康を守るためには、無理なスケジュールを立てず、休息の時間をしっかり確保することが必要です。
自分のコンディションに敏感になることが、長期的には成功への近道になるでしょう。
④ エントリーや試験対策にかかる費用が増える
併願を考える際に見落とされがちなのが、経済的な負担の増加です。まず、公務員対策では参考書や問題集の購入、さらに予備校に通う場合はその費用も必要になります。
講座の受講料は決して安くはなく、数万円〜数十万円になることもあります。
一方、民間企業の選考では、リクルートスーツや履歴書の写真撮影、企業説明会や面接の交通費、さらにはインターン参加時の出費など、確実に出費が増えていきます。
特に都市部の企業を受ける地方学生は、移動や宿泊にもお金がかかり、想像以上の負担となるケースが多いです。
必要な支出と削れる出費を整理し、無理のない範囲で計画を立てるよう心がけてください。
⑤ 内定・合格後の進路決定で迷いやすくなる
併願がうまくいって、公務員と民間の両方から内定や合格を得られた場合、最後に待ち構えるのが「どちらを選ぶか」という大きな選択です。
これは非常に難しい問題で、どちらも魅力がある場合には、簡単には答えが出ないでしょう。
このような迷いを減らすためには、併願を始める前の段階で「自分が何を大切にしたいのか」「将来どうなっていたいのか」といった価値観を整理しておくことが重要です。
その上で、情報収集や自己分析を繰り返し、自分なりの判断軸を持つことで、最終的な選択に自信を持てるようになります。
併願を成功させるための準備ポイント

公務員と民間企業の併願は十分に可能ですが、両立させるためには的確な準備が求められます。試験や選考の流れが大きく異なるため、それぞれに応じた対策を取る必要があります。
ここでは、併願を成功に導くために押さえておきたい準備ポイントを紹介します。
- 公務員と民間企業の試験内容と選考の流れを把握する
- 自己分析を通して就活の軸を明確にする
- 最新の就活・採用情報を収集する
- 併願する民間業界をあらかじめ絞り込む
① 公務員と民間企業の試験内容と選考の流れを把握する
併願を成功させるには、公務員と民間企業それぞれの選考フローや時期を正確に理解しておくことが欠かせません。
公務員試験では筆記試験に加え、人物評価も行われます。準備にかかる時間が長く、計画性が求められる点が特徴です。
一方で、民間企業の選考は近年はオンライン化が進み、選考スピードが速まる傾向にあります。
このように、両者は選考の方法もタイムラインも大きく異なるため、あらかじめ詳細を把握しておくことで、無理のない併願スケジュールを組むことが可能になります。
各選考の特徴と流れを把握し、事前に逆算して準備することが、両立成功への第一歩です。
② 自己分析を通して就活の軸を明確にする
公務員と民間企業では求められる人物像や役割が大きく異なるため、まずは自分自身の価値観や適性を理解することが重要です。
公務員には社会貢献への関心や公平な判断力、継続的な努力が求められるのに対し、民間企業では柔軟な対応力や利益への意識、スピード感が重視されることが一般的です。
そのため、どちらの選考にも対応できるようにするには、就活の軸を明確にし、自分がなぜその道を目指すのかを言語化する力が必要になります。
併願の成功には、他人に合わせた志望動機ではなく、自分らしい選択を貫く姿勢が大切です。
③ 最新の就活・採用情報を収集する
併願を成功させるうえで見落とされがちなのが、情報収集の重要性です。
就職活動では、毎年のように企業の採用方針や公務員試験の制度が変化しており、数年前の情報だけでは対応できないことが多くなっています。
情報源としては、自治体や省庁の公式サイト、企業の採用ページ、大学のキャリアセンター、就活エージェントなどがあります。
SNSや就活掲示板のような非公式情報も参考になりますが、信頼性の確認は怠らないようにしましょう。情報収集は早めに始めておくほど有利です。
情報戦を制することが、併願成功へのカギになります。
④ 併願する民間業界をあらかじめ絞り込む
民間企業との併願を考える際、あまりに多くの業界や企業に手を出してしまうと、情報収集や選考対策に時間がかかり、どちらの準備も中途半端になってしまう可能性があります。
そのため、併願する際は関心の高い業界を事前にいくつかに絞っておくことが有効です。企業研究の深度も上がり、エントリーシートの質や面接での受け答えに説得力を持たせることができます。
また、選考スケジュールも把握しやすくなり、試験日が重なるなどのリスクも抑えられます。
併願を成功させるためには、民間業界の選び方にも戦略が必要です。数ではなく、質で勝負する意識を持って取り組んでください。
公務員と民間併願を成功させるコツ
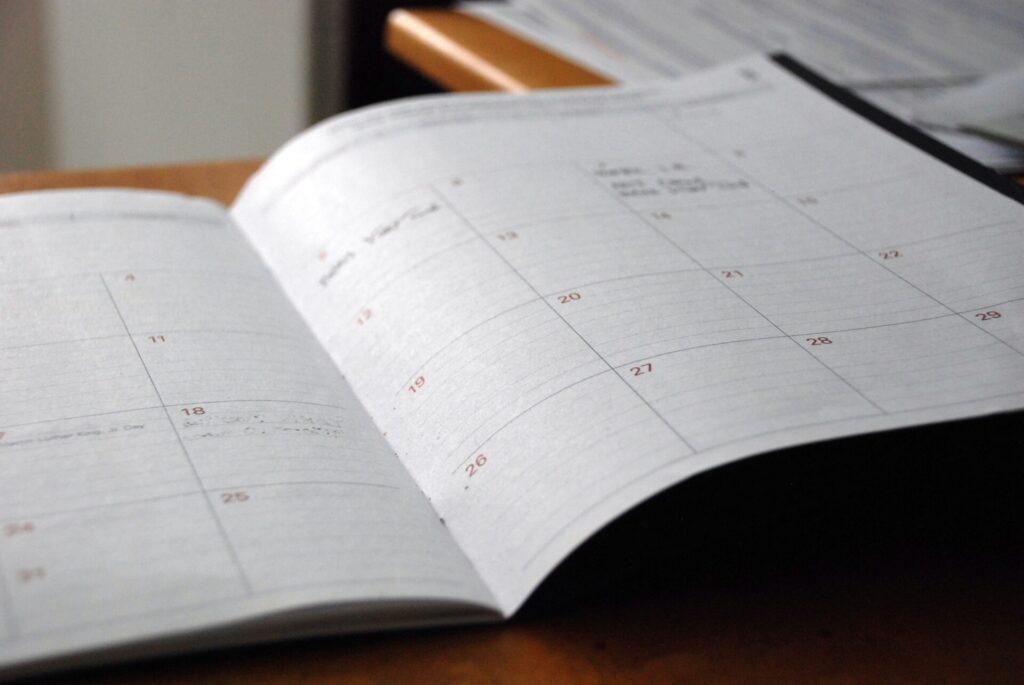
公務員試験と民間企業の就職活動を両立するのは難しく感じるかもしれませんが、実際には多くの学生がうまく併願を成功させています。
そのためには、計画的なスケジュール管理と、両者の共通点を活かす工夫が求められます。ここでは、公務員と民間企業の併願を成功に導くための方法を紹介します。
- 公務員試験と民間就活のスケジュールを可視化する
- 公務員試験対策を優先しながら民間も準備する
- SPIやES対策など共通項を意識して効率的に進める
- 併願先を選ぶ際は公務員と親和性のある業界を選ぶ
- 学内講座やキャリアセンター、予備校を活用する
- 早期に民間企業の選考を受けて経験を積む
- オンライン説明会やOB・OG訪問を活用する
- 自分の志望順位や就活の軸を明確にしておく
① 公務員試験と民間就活のスケジュールを可視化する
公務員と民間の就活では、選考時期の重なりが避けられません。特に、公務員試験は筆記・面接ともに時期が集中し、民間の最終面接ともバッティングしやすいです。
そのため、まず両者のスケジュールを早めに把握し、一元化して整理することが必要です。カレンダーやアプリを活用して、日付ごとにやるべきことを書き出すと、準備がしやすくなるでしょう。
特定の期間には公務員対策に集中し、空いた週には企業説明会や面接を入れるなど、戦略的に動くことも大切です。
さらに、大学の履修登録やアルバイトとの兼ね合いも考慮に入れることで、過度な負担を回避できます。無理のないスケジュール設計が、併願成功への第一歩といえるでしょう。
② 公務員試験対策を優先しながら民間も準備する
公務員を第一志望にしている場合でも、民間就活の準備をまったくしないのはリスクが高いです。
公務員試験には合格率の壁があり、結果が出るまでの期間も長く、不合格だった場合に備えて民間の内定を確保しておくことが、精神的な安定にもつながります。
試験勉強を日中中心に進め、夜の時間帯や週末には企業の研究やエントリーシート作成に充てると、両立しやすくなります。
万が一、公務員試験が不調だったとしても、民間での選択肢があることで焦らず行動できるでしょう。効率よく併願するには、時間の使い方と優先順位のバランスがカギになります。
③ SPIやES対策など共通項を意識して効率的に進める
公務員試験と民間就活の両方に対応するには、共通する準備ポイントを押さえて効率を高めることが求められます。
SPIのような適性検査は、公務員の教養試験にも通じる内容が多く、言語・非言語の練習をすることで両方に応用できます。
さらに、ESや履歴書で自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)を書く機会は共通しており、一度しっかりと構成を練っておけば、志望先ごとにカスタマイズするだけで済みます。
時間が限られているからこそ、こうした“重なる部分”を最大限に活かして進めることが重要でしょう。
④ 併願先を選ぶ際は公務員と親和性のある業界を選ぶ
民間企業を選ぶ際には、自分がなぜ公務員を目指しているのかという視点から考えてみてください。
例えば、「地域貢献をしたい」「安定した職場で長く働きたい」といった価値観を持っているなら、それに近い企業や業界を併願先として選ぶと、選考で話がブレにくくなります。
インフラ系や公的機関、金融、社会福祉、地域密着型の企業などは、公務員と似た使命感や安定性を重視する傾向があるため、違和感なくエントリーできます。
志望動機の一貫性が選考官に伝われば、併願であることが不利になることはほとんどありません。むしろ視野の広さや計画性が評価される可能性もあります。
⑤ 学内講座やキャリアセンター、予備校を活用する
就活や公務員試験の準備をすべて自力で行うと、情報が偏りやすく、対策の質に差が出ることもあります。そんなとき頼れるのが、大学内にある支援機関や民間の予備校です。
キャリアセンターではES添削や模擬面接、公務員対策講座を提供している場合が多く、学内講座は比較的費用も抑えやすいというメリットもあります。
一方で予備校は、出題傾向に特化したカリキュラムや講師の指導が受けられ、独学では得られない実践的なノウハウを学べます。
併願を考えるなら、これらのリソースを賢く使って負担を分散し、効率的な準備を心がけましょう。
⑥ 早期に民間企業の選考を受けて経験を積む
公務員一本で準備を進めていると、面接慣れや企業理解の面で遅れが出ることがあります。
特に、面接での受け答えやグループディスカッションは経験を重ねることで磨かれるため、民間企業の早期選考やインターンは実践の場として非常に有効です。
また、実際の企業選考を通じて、自分の強みや志望動機がどの程度通用するかを試すことで、公務員試験の面接にも応用できる発見があります。企業の人事と話す中で、自己分析が深まるケースもあるでしょう。
失敗を恐れず、積極的に挑戦していく姿勢が、結果的に併願全体の成功率を高めることにつながります。
⑦ オンライン説明会やOB・OG訪問を活用する
忙しい就活生にとって、オンラインでの情報収集は時間の節約だけでなく、行動範囲を広げるチャンスでもあります。
自宅にいながら参加できるオンライン説明会や座談会では、企業の担当者からリアルな話を聞くことができ、移動の負担もありません。
特に公務員を志望している先輩との交流は、試験対策や働き方に関する情報を得るうえで貴重です。
自分の志望と合っているかどうかを判断する材料として、早いうちから多くの機会を設けておくことをおすすめします。行動範囲を広げることが、選択肢の幅にもつながります。
⑧ 自分の志望順位や就活の軸を明確にしておく
併願を成功させるためには、まず「なぜ働くのか」「自分は何を重視しているのか」といった根本的な価値観を明確にすることが欠かせません。
給料・勤務地・働き方・安定性・やりがいなど、何を優先するかは人それぞれです。「地域に貢献したい」という想いが強ければ地方公務員や地域密着企業が候補になるでしょう。
志望順位を決めることで、選考が重なったときの判断軸がぶれませんし、面接でも一貫した説明ができるようになります。
また、自分の軸が定まっていれば、不合格や途中辞退といった場面にも柔軟に対応できます。選択に迷わないためにも、自分の中の“基準”を持っておくことが大切です。
公務員と民間、両立就活を戦略的に進めよう!

公務員と民間企業の併願は、就職活動における重要な選択肢のひとつです。
併願には「将来の選択肢を広げられる」「全落ちリスクを避けられる」などのメリットがある一方、「対策やスケジュール管理が難しい」といったデメリットも存在します。
例えば、公務員が第一志望で民間を保険とする人もいれば、逆のパターンもあります。それぞれの就職活動には選考フローや求められる人物像が異なるため、準備には戦略が求められます。
結論として、公務員と民間の併願は十分可能であり、自己分析と計画的な準備によって自分らしいキャリア選択を実現できます。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














