就活が大変だと感じる理由と乗り越え方|大変になる前に知るべき準備
この記事では、就活が大変だと感じる理由と乗り越え方を紹介しています。
就活は内定をもらうまでがかなり時間がかかり、どの就活生も大変さを感じる場面があります。実際に大変と感じる理由からどのように乗り越えるコツを紹介しているので、最後まで読んでみてくださいね。
就活が大変だと感じる理由を知って乗り越えよう

就活が大変だと感じるのは、決してあなただけではありません。多くの学生が同じように不安やプレッシャーを抱えています。
たとえば、学業やアルバイトと並行して就活を進めることは、想像以上に負担が大きいものです。
授業の課題をこなしながら、エントリーシートの準備や面接対策まで行うとなると、時間も気力も足りなくなってしまうでしょう。
さらに、不採用が続くことで自信を失いやすくなり、「自分は向いていないのでは」と思い込んでしまうこともあります。
金銭面でも、交通費やスーツ代などの出費がかさむと、経済的な不安が重なりやすいです。
そして何より、就活にはゴールが見えにくく、終わりがはっきりしないため、精神的に追い込まれてしまう人も少なくありません。
こうした背景を理解しておくことで、「自分が弱いからつらいのではない」と受け止められるようになります。完璧を求めすぎず、自分のペースで取り組んでいけば、気持ちにゆとりが生まれてくるでしょう。
就活のつらさを正しく認識することが、乗り越えるための第一歩です。
就活が大変だと感じる理由

就活は多くの学生にとって、初めて社会と向き合う経験です。期待と不安が入り混じる中で、時間・お金・精神面の負担が重なり、戸惑う場面も多いでしょう。
特に学業やアルバイトと並行して進める必要がある点は、就活を複雑にする大きな要因です。ここでは、就活が大変だと感じる主な理由を6つ挙げて解説します。
- 学業やアルバイトと両立する必要があるから
- ESや面接準備に多くの時間と労力が必要だから
- 不採用通知が続いて精神的に落ち込むから
- 交通費やスーツ代など金銭的な負担が大きいから
- 活動の終わりが見えずプレッシャーを感じるから
- 情報が多すぎて何を信じて動けばいいか迷うから
① 学業やアルバイトと両立する必要があるから
大学生活の中で就活を進めるには、限られた時間をやりくりする工夫が求められます。講義やゼミ、レポートに加え、生活費を稼ぐためにアルバイトを続ける学生も少なくありません。
選考と授業のスケジュールが重なれば、どちらを優先するか悩む場面も増えるでしょう。アルバイトを減らすと収入が不安定になり、精神的なプレッシャーも大きくなります。
こうした中で就活を進めるには、早めに予定を把握し、優先順位を整理して行動することが大切です。大学やバイト先と相談して調整することも、有効な対策の一つ。
また、スケジュール管理ツールなどを使いこなすことで、効率的に行動できるようになるでしょう。
② ESや面接準備に多くの時間と労力が必要だから
エントリーシート(ES)や面接対策には、思っている以上の時間と労力がかかります。企業ごとの内容に合わせてESを作成するには、自己分析と企業研究が不可欠です。
慣れないうちは、1社に数時間かかることも珍しくありませんし、添削や書き直しを繰り返すうちに気力が尽きてしまうこともあるでしょう。
面接準備も、質問への回答を考えるだけでなく、話し方や表情、マナーにも気を配る必要があります。これらの作業が重なることで、就活への疲れが積み重なるのは自然なことです。
過去のESを蓄積したり、模擬面接を活用したりして、効率的な準備を心がけてください。日頃から情報整理をしておくことも、時間短縮につながります。
③ 不採用通知が続いて精神的に落ち込むから
どれほど努力しても、不採用が続けば誰でも落ち込みます。「自分には価値がないのでは」と思い詰めてしまうと、次の行動に踏み出すのが難しくなってしまうでしょう。
特に友人の内定報告が耳に入ると、孤独感や焦りが強くなりがちです。ただし、採用は企業との相性にも大きく左右されます。不採用は能力の否定ではなく、「合わなかっただけ」と捉えることが大切です。
気持ちが落ち着かないときは、家族や信頼できる人と話してみるのも一つの方法。必要以上に自分を責めず、前向きな気持ちを少しずつ取り戻す工夫をしてみましょう。
たとえば、気分転換に好きなことをするのも効果的です。
④ 交通費やスーツ代など金銭的な負担が大きいから
就活は見えない出費が多くかかる時期です。面接や説明会での交通費、ビジネススーツや靴の購入、証明写真の撮影など、1件ごとの金額は少なくても、積み重なれば大きな金額になります。
経済的に余裕のない学生には、特につらい部分かもしれません。負担を減らすには、オンライン選考を選んだり、交通費支給がある企業を優先したりするのも一案です。
大学のキャリアセンターが提供する貸出スーツや支援金制度なども積極的に利用してください。加えて、事前に予算を立てて出費を見える化することで、経済的なストレスを軽減できるでしょう。
⑤ 活動の終わりが見えずプレッシャーを感じるから
就活には明確な「終わりの時期」がありません。友人が早く内定をもらうと、自分だけが遅れているように感じ、不安や焦りが増していくこともあるでしょう。
特に活動が長期化すると、先が見えず苦しさを感じやすくなります。そんなときは、短期目標を設定して少しずつ進むことが効果的です。
たとえば「今週中にESを1件出す」など、小さな達成を重ねることで、自分の前進を実感しやすくなります。周囲と比べすぎず、自分のペースを信じて取り組んでください。
気持ちのゆとりが生まれると、焦りもやわらいでくるでしょう。
⑥ 情報が多すぎて何を信じて動けばいいか迷うから
現代の就活は情報にあふれています。就活サイト、SNS、YouTube、就活イベントなどからさまざまな情報が手に入る一方で、内容にばらつきがあり、何を信じればよいのか分からなくなることもあるでしょう。
判断がつかず行動をためらうようになったときは、まず自分の価値観や目標を明確にすることが大切です。自分が本当に大事にしたいものを基準に、必要な情報だけを取捨選択してください。
大学のキャリアセンターや信頼できる先輩から話を聞くのも、正しい情報にたどり着く助けになるはず。情報に振り回されるのではなく、軸を持った判断を意識しましょう。
就活が大変だと感じる人の特徴

就活がつらく感じる背景には、単に外的な環境だけでなく、自分自身の考え方や行動パターンが影響している場合もあります。
特定の傾向を持つ人ほど、不安や負担を感じやすい傾向があるため、自分に当てはまる特徴を客観的に把握しておくことが大切です。ここでは、就活を特に大変だと感じやすい人の特徴を5つ紹介します。
- 判断に迷いやすく決断が遅れる人
- 悩みを相談できず一人で抱え込みやすい人
- 準備に時間をかけすぎてしまう人
- 物事をネガティブに捉えやすい人
- 自己分析が不十分な人
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
① 判断に迷いやすく決断が遅れる人
就活はスピードと決断力が問われる場面が多く、自分の意思でタイミングよく動くことが求められます。
判断に迷いやすい人は、情報を集めすぎてかえって混乱し、「本当にこの会社でいいのか」と不安を拭えず、なかなかエントリーに踏み出せません。
さらに複数の企業に同時に対応しなければならない中で、意思決定が遅れると、スケジュールが詰まり負担が倍増してしまうでしょう。就活には「絶対に正しい選択」があるわけではありません。
ある程度の納得感が得られたら、一歩踏み出す勇気も必要です。迷ったときは「やらない後悔」より「やってみた経験」を優先する視点に切り替えてください。
② 悩みを相談できず一人で抱え込みやすい人
就活中の不安や悩みは、多くの人が抱えるものです。しかし、それを周囲に打ち明けられず、一人で抱え込みすぎてしまう人は特にストレスを感じやすくなります。
ネガティブな感情をため込んでしまうと、考えが偏ったり、必要以上に自分を責めてしまったりすることもあるでしょう。
ときには「こんなこと聞いていいのかな」と遠慮する気持ちがあるかもしれませんが、相談された側はむしろ頼られることで力になりたいと思うものです。
友人、先輩、家族、キャリアセンターなど、頼れる人を見つけて話してみてください。言葉にするだけでも、心の負担は軽くなるはずです。
③ 準備に時間をかけすぎてしまう人
真面目で責任感が強い人ほど、準備に時間をかけすぎる傾向があります。
たとえば、エントリーシートの文章に納得がいかず何度も書き直したり、面接練習に完璧を求めすぎてなかなか応募に踏み切れなかったりするケースです。
その結果、締切ギリギリになって提出を諦める…という悪循環に陥ることもあるでしょう。もちろん丁寧な準備は必要ですが、就活は数をこなしていくことも重要です。
特に早期選考ではスピード感が重視されるため、ある程度の完成度で「まず提出する」ことを意識しましょう。質と量のバランスを取りながら、次に進む柔軟さが求められます。
④ 物事をネガティブに捉えやすい人
就活では思い通りにいかない場面も多く、失敗や不採用のたびに気持ちが落ち込みやすくなります。
とくに物事をネガティブに受け取りやすい人は、「自分に価値がないのでは」「もう受かる気がしない」といった思考に陥り、行動する力を失ってしまうことがあるでしょう。
しかし、就活の結果は個人の能力だけで決まるわけではありません。タイミングや企業との相性、募集枠の都合など、コントロールできない要素も多いものです。
結果に一喜一憂しすぎず、うまくいかなかったことから何を学べるかに目を向けてみてください。少しずつでも前を向く工夫が、心を軽くする第一歩になります。
⑤ 自己分析が不十分な人
自己分析が不十分なまま就活を進めてしまうと、自分に合った企業がわからず、軸のない就活になりがちです。
「どの業界に興味があるのか」「自分の強みは何か」といった基本的な問いに答えられないと、志望動機や自己PRもあいまいになり、選考通過の可能性も低くなってしまうでしょう。
企業にとって、応募者の意思や適性が見えることは非常に重要です。そのためにも、これまでの経験や価値観を丁寧に振り返り、自分自身が何に喜びややりがいを感じるのかを言葉にしておくことが大切。
「やりたいことが見つからない」と感じたら、まずは過去の体験の中からヒントを探すところから始めてみましょう。
就活が大変なときにやってはいけないNG思考

就活は精神的な負担が大きく、知らず知らずのうちにマイナス思考に陥ることがあります。こうした考え方に気づかず続けてしまうと、結果が出にくくなり、よりつらさを感じやすくなってしまうでしょう。
ここでは、避けるべき5つのNG思考を紹介します。
- 周囲と比べて自分を過小評価してしまう
- 不採用の原因を深く追いすぎてしまう
- 選択肢を狭めてしまう
- 経験不足のまま不向きと判断してしまう
- 完璧を求めすぎて行動を止めてしまう
① 周囲と比べて自分を過小評価してしまう
就活では、友人や同期の進捗がどうしても気になります。SNSで内定報告を見かけたり、就活状況を共有されたりすると、自分と比較して落ち込むことがあるでしょう。
しかし、就活の進み方は業界や職種、企業の選考スケジュールによって大きく異なります。誰かが早く内定をもらっているからといって、自分が劣っているというわけではありません。
他人と比較するのではなく、自分自身の成長や努力に目を向けてください。昨日の自分と比べて少しでも前に進んでいれば、それは大きな一歩です。周囲に左右されず、自分のペースを大切にしましょう。
② 不採用の原因を深く追いすぎてしまう
不採用通知が続くと、「自分に何が足りないのか」「どこで間違ったのか」と自問してしまうことは珍しくありません。反省すること自体は大切ですが、それが度を越すと自信喪失につながってしまうのです。
選考結果には運やタイミング、企業との相性といった、努力では変えられない要因も含まれています。
すべての結果に意味を見出そうとせず、改善点が思い当たる場合は1つか2つに絞って修正し、あとは気持ちを切り替えることが大切です。
引きずりすぎると、次のチャンスを逃してしまいます。反省は短く、行動は早めに。
③ 選択肢を狭めてしまう
「自分にはこの業界しか合わない」「この職種でなければ意味がない」といった強いこだわりがあると、選択肢が狭くなり、視野が固定されてしまいます。
確かに軸を持つことは重要ですが、それに縛られすぎると、ほかの魅力的な可能性に目を向ける余地がなくなります。
少しでも興味がある分野や企業があれば、柔軟な姿勢で調べてみるのが良いでしょう。知らなかった業界に思わぬ魅力を感じることもあります。
視野を広げることで、納得できる進路に出会える可能性も高まるはずです。
④ 経験不足のまま不向きと判断してしまう
「経験がないから無理だ」「向いていない気がする」と思い込み、最初から選択肢から外してしまうのは非常にもったいないことです。
やったことがないことに対して不安を抱くのは自然ですが、実際に経験してみないと向き不向きは判断できません。
とくに学生時代は情報も体験も限られているため、「向いていない」という判断が早すぎる可能性があります。少しでも興味を持ったなら、まずは行動してみることが大切です。
挑戦して初めて、自分の可能性や強みに気づくこともあるでしょう。
⑤ 完璧を求めすぎて行動を止めてしまう
就活において完璧を目指すあまり、「ESが完璧に書けないから出せない」「練習が不十分だから面接はまだ無理」と動けなくなる人もいます。
けれど、実際には行動することでしか得られない学びや成長があるのです。最初から完璧な人など存在しません。たとえ準備が万全でなくても、まずは一歩踏み出すことが重要です。
失敗したとしても、それは貴重な経験になります。完璧を目指す気持ちは悪いことではありませんが、それが足を止める理由になってしまうなら、少し力を抜いて進んでみてください。
就活が大変だと感じやすい時期

就活がつらくなりやすい時期には、いくつかの共通点があります。特に周囲の動きが気になったり、やるべきことが一気に増える時期には、不安や焦りが大きくなりがちです。
ここでは、多くの就活生が大変だと感じやすいタイミングについて説明します。就活が本格化する3月から6月頃は、多くの学生が「つらい」と感じやすい時期です。
この時期はエントリーシートの提出や説明会、面接などが重なり、やるべきことが一気に増えます。慣れない作業が続く中で、体力的にも精神的にも疲れてしまうでしょう。
また、まわりの内定情報が耳に入りやすいのもこの時期です。比較してしまうことで焦りが強まり、気持ちに余裕がなくなってしまうことも少なくありません。
さらに、大学の授業や卒論、アルバイトなどと並行して就活を進める必要がある学生にとっては、時間のやりくりそのものが大きなストレスになります。
すべてを完璧にこなそうとすると、かえって自分を追い詰めてしまうかもしれません。大切なのは、自分のペースを守りながら取り組むことです。
やるべきことに優先順位をつけ、無理のない計画を立てるようにしてください。
就活を乗り切るためのコツ
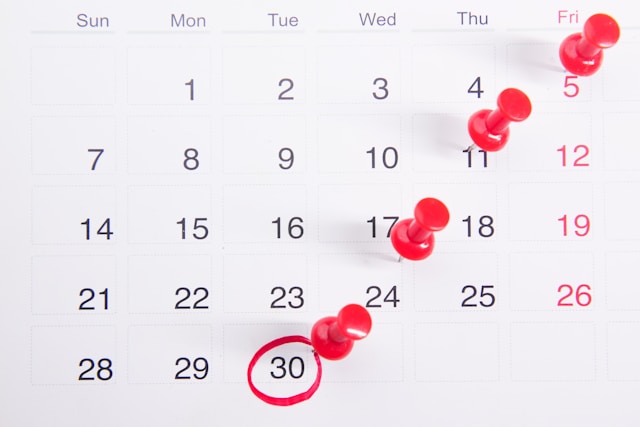
就活は長期間にわたることが多く、精神的にも体力的にも負担がかかります。だからこそ、無理なく進める工夫が必要です。ここでは、就活をうまく乗り切るためのポイントを5つにまとめました。
- 就活資金を早めに準備する
- スケジュールを立てて計画的に進める
- 周囲に流されず自分の軸を貫く
- 不採用を前向きに受け止める
- 定期的に休息を取りリフレッシュする
① 就活資金を早めに準備する
就活には意外と多くの費用がかかります。交通費やスーツ、靴、カバンの購入、証明写真代など、必要な出費がいくつも重なるため、経済的な準備が不十分だと精神的な余裕も失われがちです。
特に遠方の企業に出向く場合、移動や宿泊費が大きな負担になることもあるでしょう。だからこそ、就活が本格化する前にアルバイトなどでコツコツと資金を確保しておくことが大切です。
加えて、大学の就職支援制度や交通費を補助する企業の情報を早めにチェックしておくと、出費を抑えることが可能。お金の心配が少ないだけで、就活のストレスはかなり軽減されます。
② スケジュールを立てて計画的に進める
就活が始まると、エントリーや説明会、面接、適性検査など、複数の予定が同時に重なる場面が増えてきます。スケジュール管理を怠ると、準備不足や日程ミスにつながるおそれがあります。
そのため、自分なりの計画表を作成して行動することが重要です。月単位・週単位で目標ややるべきことを整理し、優先順位をつけて進めると混乱が少なくなります。
スマホのアプリや紙の手帳など、使いやすいツールを活用しましょう。しっかりと管理できていれば、面接の準備や自己分析にも集中しやすくなります。
③ 周囲に流されず自分の軸を貫く
友人や周囲の動向に振り回されがちな時期ですが、就活はあくまで自分のためのものです。
他人が内定を得た話を聞いて焦ることもあるかもしれませんが、人それぞれ目指す業界やペースが異なるため、比較することにあまり意味はありません。
むしろ、自分がどのような価値観を持ち、どんな働き方をしたいかを明確にすることのほうが重要です。
「自分は何を大切にしたいのか」「どんな職場ならやりがいを感じられるか」といった問いに答えられるようになると、選択にブレがなくなり、自信を持って行動できるようになります。
自分軸を持つことが、就活の不安を軽減する鍵になるでしょう。
④ 不採用を前向きに受け止める
不採用通知が続くと、自分を否定されたような気持ちになり、就活を続けることが苦しくなる場面もあるでしょう。
しかし、企業の選考は単に能力の優劣だけでなく、組織との相性やタイミングなど、さまざまな要素で決まっています。たまたま今はその企業と縁がなかっただけ、と考えることも一つの視点です。
必要以上に落ち込まず、改善点を冷静に振り返ったうえで、次に活かす姿勢が大切です。すべてを分析しようとすると疲れてしまうので、振り返りは1〜2点に絞るのがおすすめ。
就活は数をこなすことで成長していくものなので、1社の結果に振り回されすぎず、次に目を向けましょう。
⑤ 定期的に休息を取りリフレッシュする
就活に取り組むうちに、「休んでいる場合じゃない」と無理をし続けてしまうことがあります。しかし、疲れをため込んだままでは集中力や判断力が落ちてしまい、かえって効率が悪くなることも。
だからこそ、意識的に「休む日」を設けることが大切です。好きなことに没頭したり、友人と話したりすることで、気持ちがリセットされます。
短時間のリフレッシュでも、心が軽くなり、次の行動への活力が生まれるでしょう。就活はマラソンのようなもの。全力疾走ではなく、自分のペースで走りきる工夫が必要です。
就活本格化後すぐに取り組むべき対策

就活が本格的に始まったら、最初にやるべき対策を明確にし、優先順位をつけて進めることが大切。準備不足のまま選考が進んでしまうと、思わぬ失敗につながる恐れがあります。
ここでは、内定獲得に向けて早めに取り組みたい5つのポイントを紹介します。
- 自己分析を深めて強みを明確にする
- 企業研究を通して志望理由を具体化する
- 筆記試験の対策を早めに始める
- 面接練習で本番に備える
- エントリー先の管理や記録を行う
① 自己分析を深めて強みを明確にする
就活の土台となるのが自己分析です。自分がどんな価値観を持ち、どんな経験を通じて何を学んできたのかを振り返ることで、自己PRや志望動機の軸が明確になります。
たとえばアルバイトやサークル活動、学業での挑戦などを思い出し、そこでの行動や結果、感じたことを言語化してみてください。
また、他人の視点を取り入れることも効果的です。友人や家族から見た自分の印象を聞くと、新たな気づきが得られる場合があります。
最近は自己分析ツールも豊富にあるので、活用してみるのも良いでしょう。自分の強みや価値観が明確になると、企業選びやエントリーの判断にも迷いが少なくなります。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
② 企業研究を通して志望理由を具体化する
志望動機は、企業研究の深さに大きく左右されます。ホームページや求人情報を読むだけでなく、社員インタビューや説明会、口コミサイトなども参考にしながら、企業の姿を多角的に捉えましょう。
大切なのは「どこに共感したか」「自分の経験や価値観とどこが合うか」という視点で情報を読み解くことです。競合企業との違いを比較することで、その企業ならではの魅力が浮かび上がってきます。
また、OB・OG訪問で直接話を聞くことで、ネットだけでは分からない社風や働き方の実態も見えてきます。自分の言葉で語れる志望動機は、面接でも説得力を持つ大きな武器になるでしょう。
③ 筆記試験の対策を早めに始める
筆記試験は、就活初期に避けて通れないハードルです。とくにSPIや玉手箱などは、多くの企業で導入されており、事前準備なしで突破するのは困難。
試験形式に慣れておくことが重要なので、まずは簡単な模擬問題から始め、徐々に本番に近い問題へとレベルを上げていきましょう。苦手な分野を早期に把握し、重点的に復習することで効率が上がります。
時間配分にも注意が必要です。アプリや問題集を活用し、空き時間を有効に使って練習を続けてください。過去問や模試を繰り返すうちに、自信と安定感が身についてくるでしょう。
早めの対策で安心感を得ることができます。
④ 面接練習で本番に備える
面接は、企業との最初の直接的な対話の場であり、第一印象が結果を左右します。想定質問に対する答えを用意するだけでなく、話す順序や言い回しも意識して整理しておきましょう。
また、表情や姿勢、声のトーンなどの非言語的な印象も大切です。自分の話し方を録音・録画して見返すと、改善点が見つかりやすくなります。
可能であれば、大学のキャリアセンターや模擬面接会などを活用し、実践的な練習を積み重ねてください。集団面接やオンライン面接にも慣れておくと、本番での緊張をやわらげることができます。
準備に力を入れておけば、本番でも落ち着いて受け答えができるようになるはずです。
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
⑤ エントリー先の管理や記録を行う
就活が進むにつれて、応募企業の数が増え、スケジュール管理の負担も大きくなります。エントリーの日時、面接の予定、提出済みの書類などを手帳やアプリでしっかりと記録しておくことが重要です。
うっかりミスを防ぐだけでなく、後から振り返って改善点を見つける手がかりにもなります。また、同じ企業に再応募する際や、複数選考が並行する際にも、過去の記録があると対応しやすくなります。
企業ごとの印象や面接の内容をメモしておくと、志望動機のブラッシュアップにも役立ちます。自分に合った管理方法を確立し、常に最新の情報を把握しておくことが、スムーズな就活の鍵となるでしょう。
就活の大変さを乗り越え内定獲得獲得を目指そう!

就活が大変だと感じるのは、決してあなただけではありません。学業との両立や金銭的負担、精神的なプレッシャーなど、複数の要因が重なることで心身の負荷が増していきます。
さらに、就活がうまく進まないと、自分に自信を失い、間違った思考に陥ることもあるでしょう。こうした悪循環を断ち切るには、まず「大変さの正体」を知ることが大切です。
そして、計画的な準備と心のゆとりを意識することで、少しずつ前向きな気持ちを取り戻せます。
自分に合ったペースで就活に向き合いながら、必要な対策を早めに実行することで、就活の負担は軽減できるはずです。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










