インターンのグループワークの対策を徹底解説|目的や頻出なお題も紹介
この記事では、インターンのグループワークの対策を徹底解説しています。
実際のインターンでよくあるテーマ例や進行の流れ、役割の種類や内容まで詳しく紹介しています。インターンの面接が控えている場合は、グループワークの対策を事前に知っておき、他の就活生に差をつけましょう。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ESをAIに丸投げ|LINEで完結
- 完全無料でESを簡単作成
- 2赤ペンESで添削依頼|無料
- 就活のプロが丁寧に添削してくれる
- 3志望動機テンプレシート|簡単作成
- カンタンに志望動機が書ける!
- 4自己PR自動作成|テンプレ
- あなたの自己PRを代わりに作成
- 5企業・業界分析シート|徹底分析
- 企業比較や選考管理もできる

記事の監修者
記事の監修者
人事担当役員 小林
1989年新潟県生まれ。大学在学中に人材系ベンチャー企業でインターンを経験し、ビジネスのやりがいに魅力を感じて大学を1年で中退。その後、同社で採用や人材マネジメントなどを経験し、2011年に株式会社C-mindの創業期に参画。訪問営業やコールセンター事業の責任者を務めたのち、2016年に人事部の立ち上げ、2018年にはリクルートスーツの無料レンタルサービスでもある「カリクル」の立ち上げにも携わる。現在は人事担当役員として、グループ全体の採用、人事評価制度の設計、人事戦略に従事している。
詳しく見る
記事の監修者
記事の監修者
人事 鈴木
新卒でベンチャー企業で求人広告の新規営業を経験 入社半年でテレアポ獲得数社内1位。新卒売り上げ1位を獲得。 その後Cmind groupの人事部に入社し、新卒採用を担当。 現在は学生の面談だけではなく採用戦略や広報にも携わっている。
詳しく見るインターンのグループワーク成功の秘訣は対策

「インターンのグループワークって、何をすればいいんだろう」と不安に感じる方は多いはず。初対面の人たちとチームを組み、限られた時間で成果を出す場面では、戸惑いや緊張もつきものです。
しかし、実は事前に知っておくだけで、当日の動きやすさが大きく変わるポイントがいくつもあります。
どんなテーマが出やすいのか、どういった役割があるのかを知ることで、自分の立ち位置を明確にしやすくなるからです。グループワークで実力を発揮するために、事前の対策は惜しまないでください。
これから本番を迎える就活生に向けて、緊張せず自分らしく力を発揮できるヒントをお届けします。
「インターンの選考対策がよくわからない…」「何度も選考に落ちてしまう…」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるインターン選考対策ガイドを確認して必勝法を知っておきましょう。LINE登録だけで無料でダウンロードできますよ。
インターンのグループワークとは

インターンにおけるグループワークとは、学生が数人でチームを組み、企業から出される課題やテーマに対して話し合いながら答えを導き出す形式の活動です。
多くの場合、実際の業務やサービスに関係する内容が出題されるため、より実践的な対応力が求められるでしょう。
このワークでは、限られた時間内でチーム全体が意見を出し合い、最終的な結論や提案にまとめて発表する必要があります。
ただ結論を出すだけでなく、どのように議論を進め、意見を集約したかといった過程も評価の対象になるのです。
そのため、コミュニケーション能力や協調性、課題に対する理解力など、複合的な力が見られます。グループディスカッションと混同されがちですが、大きな違いは「アウトプットがあるかどうか」です。
ディスカッションは話し合いに重点がありますが、グループワークでは成果物の完成が求められます。事前に流れを理解し、基本的な役割を把握しておけば、本番でも落ち着いて対応できるはずです。
「メンバー間でどれだけ建設的な議論ができたか」「役割分担は機能していたか」が評価のポイントになります。最終的な提案の中身よりも、どう導いたかが見られているという点は意識しておくと良いですよ。
また、発言量よりも「聞く姿勢」や「他者の意見を整理する力」にも注目しています。チーム全体がスムーズに動けるよう工夫する姿勢が伝わると、印象に残りやすいですよ。
グループワークとグループディスカッションの違い

グループワークとグループディスカッションは似ているように見えて、目的や評価の基準が異なります。違いを理解せずに臨むと、場に合わない行動を取ってしまい、評価が下がるおそれもあるでしょう。
まず、グループディスカッションは、意見交換を通じて最終的な結論を導き出すことが目的です。一方、グループワークでは何かを作ったり、まとめたりする成果物が求められます。
そのため、単なる発言の多さだけでなく、チームと協力して結果を出す姿勢や行動力も評価されやすいのが特徴です。この違いを意識することで、自分に求められる動きがより明確になります。
準備の段階から、どのように立ち回れば良いのかを考えておくと安心です。どちらに参加する場合も、それぞれの目的を理解して行動してください。
インターンでグループワークを行う目的

インターンでグループワークが取り入れられているのは、企業が学生の能力を多面的に評価するためです。単なるお試し体験ではなく、採用にもつながる重要な要素といえるでしょう。
- 企業の業務理解を深めさせるため
- 協調性やコミュニケーション能力を評価するため
- 論理的思考力を見極めるため
- リーダーシップを発揮できるか確認するため
- ビジネスシーンでの柔軟な対応力を測るため
① 企業の業務理解を深めさせるため
グループワークでは、企業のサービスや業務に関連するテーマが出題されることが多く、実際のビジネスを学生が体感する機会となります。
たとえば「新しい顧客層へのプロモーション方法を考える」といった課題を通して、業界特有の価値観や仕組みを理解できます。
座学や会社説明では得られないリアルな視点に触れることで、働くイメージが具体化しやすくなる点も大きなメリットです。
インターン後の志望動機や業界研究にもつながるため、自発的な調査や関心の深さが問われる場面でもあります。
② 協調性やコミュニケーション能力を評価するため
企業がグループワークを重視する理由の一つが、協調性とコミュニケーション能力の見極めです。社会人として働くうえで、チームで成果を出す力は欠かせません。
意見を主張するだけでなく、他者の話に耳を傾ける姿勢や、適切なタイミングで発言するスキルも大切です。
たとえば、話し合いが偏ったときに「他の意見も聞いてみよう」と促す一言は、調整力として高く評価されることがあります。
誰かと対立した際にどう対処するかも重要で、空気を読みすぎず、率直さと配慮のバランスを取る必要があるでしょう。
③ 論理的思考力を見極めるため
グループワークでは、感覚や思いつきではなく、筋道を立てて考えられるかが重要です。
たとえば「○○だから△△すべき」という因果関係や、「過去のデータから見てこの方法が有効」という根拠のある意見が求められます。
さらに、他のメンバーの意見と自分の考えを比較しながら、どちらが論理的に優れているかを見極めて議論する場面も多くあるのです。
仮説を立て、根拠を示し、結論へと導く一連の思考プロセスが評価対象。意見の内容だけでなく、説明の分かりやすさもポイントとなります。
④ リーダーシップを発揮できるか確認するため
リーダーシップと聞くと「率先して引っ張る力」と思われがちですが、企業が見ているのは「チーム全体を前に進める力」です。
たとえば、進行が滞ったときに議論を整理したり、発言が少ない人に話を振ったりといった配慮も、立派なリーダーシップの一つ。状況を読み取り、必要なときに必要な働きかけができるかが問われます。
リーダー役に立候補しなくても、自然にチームを支えている姿勢が伝われば、評価は高くなるでしょう。目立つ言動より、安定感や信頼感のある行動が鍵になります。
⑤ ビジネスシーンでの柔軟な対応力を測るため
実際の仕事では、予定どおりに進まないことが多くあります。そうした中で冷静に状況を判断し、柔軟に対応する力があるかを、グループワークを通じて企業は見極めているのです。
たとえば、テーマの解釈がチームで食い違ったときに、それをうまく統合できる人は信頼されやすいでしょう。
想定外の意見やトラブルが起こっても、パニックにならず選択肢を出し、話し合いを前向きに進められるかどうかが評価のポイントになります。
自分の意見にこだわりすぎず、場の流れを見て柔軟に動く力が求められるでしょう。
インターンのグループワークの種類

グループワークには複数の形式があり、それぞれ目的や求められる力が異なります。あらかじめ種類を知っておくことで、自分がどう動けばよいかが見えてくるでしょう。
ここでは代表的な5つのタイプを紹介します。
- 作業型
- 課題解決型
- 選択型
- ビジネス型
- 討論型
①作業型
作業型は、全員で協力して一つの成果物を完成させる形式です。たとえば、紙やテープを使って高いタワーを作る課題などがよく出題されます。
このタイプでは、どれだけ発言するかよりも、チームでうまく協力できるかが評価されるポイントです。自分にできることを見極めて、必要な場面で動く姿勢が大切になります。
サポートに回ることも立派な貢献ですので、役割にこだわりすぎないようにしてください。
②課題解決型
課題解決型では、「売上を上げるにはどうすればよいか」など、実際のビジネスに近い問題を解決することが求められます。論理的に考える力と柔軟な発想力が必要です。
議論では、他の人の意見をうまく引き出したり、全体の流れを整理したりする役割も重視されます。自分の意見を伝えるだけでなく、周囲と一緒に建設的な議論をつくることを意識しましょう。
課題解決型のグループワークでは、発想力以上に「実際に企業が採用できそうな提案かどうか」が重要なんです。発想と論理のバランスが取れている案には、目が留まりやすいですね。
また、「全体を俯瞰して動けているか」「意見の対立を建設的にまとめられているか」などを細かく見ています。裏方のように見える動きも、評価されやすいポジションなんです。
③選択型
選択型は、複数の選択肢の中から一つを選び、その理由を話し合ってまとめていく形式です。「A案・B案・C案のうちどれを選ぶか」といったテーマがよく出されます。
この形式では、根拠を持って意見を伝えられるかが問われます。意見が分かれる場面も多いため、相手の考えに耳を傾けながら、冷静に説得していく力が求められるでしょう。
④ビジネス型
ビジネス型では、「大学生向けの新サービスを企画せよ」など、現実の仕事を想定したテーマに取り組みます。市場ニーズやターゲットを考えながらアイデアを形にする必要があり、最も実践的な形式です。
発表がセットになっていることも多く、資料作成や説明の順序にも気を配りましょう。自信がなくても、事前に似たテーマで練習しておくと落ち着いて臨めます。
⑤討論型
討論型は、賛成・反対の立場に分かれて意見を交わすスタイルです。ここでは正解のないテーマが中心になります。
意見を押しつけるのではなく、自分の立場をわかりやすく説明しつつ、相手の意見にも耳を傾ける姿勢が重要です。冷静なやり取りと、話の流れを理解してフォローに回る力も評価されるでしょう。
討論型のグループワークでは、意見の違いを越えて議論を前に進めるが試されています。単なる自己主張だけでなく、全体を見渡しながらバランスを取れる人に高く評価していますよ。
また、黙って聞いているだけのようでも、タイミングよく意見をまとめたり、緊張を緩和する一言を挟めると、場の空気を変えられる存在として印象に残りますよ。
インターンのグループワークでよく出題されるテーマ例
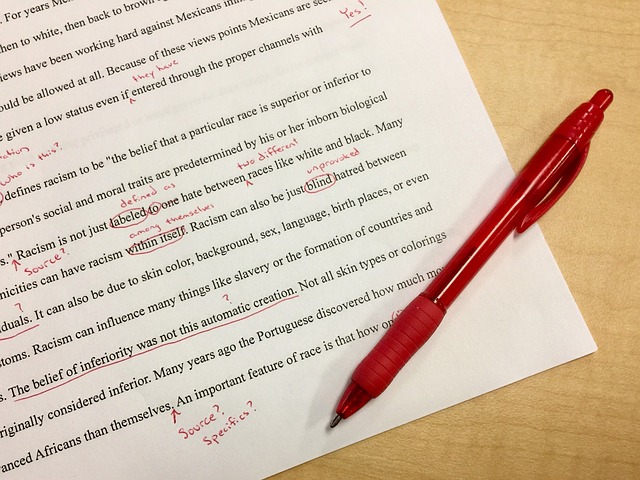
インターンのグループワークでは、企業によってさまざまなテーマが出題されます。内容や目的は異なりますが、事前にどのような形式があるのかを知っておくことで、当日の緊張を和らげやすくなります。
- 作業型のテーマ例
- 課題解決型のテーマ例
- 選択型のテーマ例
- ビジネス型のテーマ例
- 討論型のテーマ例
① 作業型のテーマ例
この形式では、決められた材料や条件のもとで、チームで何かを作り上げたり作業したりします。たとえば「紙コップでタワーを作る」など、協力して手を動かす内容が中心です。
評価されるのは、完成度ではなくチームでの動き方や分担、声かけなどです。目立つ発言をしなくても、周囲と連携しながら動ける姿勢が大切になります。
| ・紙とテープを使って、最も高いタワーを制限時間内に作成せよ ・限られた材料で一定の重さを支える橋を作れ ・ルールに従ってブロックを正確に並べる伝言作業を分担せよ |
② 課題解決型のテーマ例
企業が抱える問題に対し、学生がアイデアを出して解決策を考える形式です。「若者向けサービスの利用者をどう増やすか」といった実際のビジネス課題に近い内容が出されることも。
正解は決まっていませんが、筋の通った提案と明確な理由づけが求められます。突飛な案より、納得感のある説明の方が評価されやすいでしょう
| ・売上が落ちている書店の集客施策を提案せよ ・高齢化が進む地域での新サービスを考案せよ ・社内のコミュニケーションを活性化させるための制度を考えよ |
③ 選択型のテーマ例
複数の選択肢の中から、チームで1つを選び、その理由を説明します。「A商品の販売先をどこにするか」など、現実に近い判断を求められるのが特徴です。
多数決ではなく、情報を整理して話し合い、納得できる選択を導くプロセスが見られています。論理性だけでなく、他の意見に耳を傾ける姿勢も評価の対象になります。
| ・3つの広告プランの中から最も効果的な案を選び、その理由を説明せよ ・A社・B社・C社の中から就職先として最適な企業を選べ ・新卒採用において導入するべきツールを複数案から選定せよ |
④ ビジネス型のテーマ例
「新しいアプリを考える」「新規事業を提案する」といった自由度の高いテーマが出題されることがあります。企画力やマーケティングの視点、実現可能性が問われるため、発想力だけでは不十分です。
面白いだけでなく、現実的で説得力のある内容にまとめることがポイント。役割分担と進行の工夫も重要でしょう。
| ・大学生向けの新しいSNSアプリを企画・提案せよ ・5年後の市場を見据えた新規事業アイデアをプレゼンせよ ・環境に配慮した製品を開発し、販売戦略まで立案せよ |
⑤ 討論型のテーマ例
賛成・反対など立場を分けて議論を行う形式。「就職活動は早期化すべきか」など、学生にも身近なテーマが使われることが多いです。意見を押しつけるのではなく、根拠をもとに伝える力が必要でしょう。
また、相手の意見を受け止める姿勢や、冷静に対応できるかどうかも重視されます。結論よりも、議論の姿勢が評価される傾向です。
| ・終身雇用制度はこれからも必要か? ・大学の授業をすべてオンライン化すべきか? ・インターン選考におけるグループワークの有効性について |
インターンのグループワークの進め方

インターンのグループワークでは、チームで協力して成果を出す力が求められます。スムーズに進めるためには、全体の流れを理解し、どの場面でどう動くかを把握しておくことが大切です。
ここでは、基本的な進行を8つのステップに分けて紹介します。
- ステップ①:自己紹介をしてチームの雰囲気を作る
- ステップ②:時間配分とスケジュールを決める
- ステップ③:各メンバーの役割分担を決める
- ステップ④:テーマの理解と話し合いの方向性を確認する
- ステップ⑤:意見を出し合い、最終案をまとめる
- ステップ⑥:発表内容をブラッシュアップする
- ステップ⑦:プレゼンテーションを実施する
- ステップ⑧:フィードバックを受けて振り返る
ステップ①:自己紹介をしてチームの雰囲気を作る
グループワークの最初は、初対面のメンバー同士が打ち解けるための自己紹介から始まります。
形式的な名前や所属だけでなく、「今日はアイデア出しを頑張りたいです」など一言意気込みを添えると印象が柔らかくなるでしょう。
また、他の人の発言には笑顔やうなずきでリアクションを示すと、場の空気が和みやすくなります。自己紹介の雰囲気が良ければ、その後の議論も前向きに進むはずです。
緊張しているのはみんな同じです。お互いにリラックスできるような空気づくりを意識してみてください。
自己紹介の場面では、名前や所属だけでなく「その人の人柄やチーム内での立ち位置」が垣間見える一言があるかどうかを私たちも見ています。
また、うなずきや笑顔といった非言語のリアクションも、空気づくりに大きく影響します。場の雰囲気を読んで行動できる人は、その後の議論でも協調性が伝わってきますよ。
ステップ②:時間配分とスケジュールを決める
限られた時間内で成果を出すには、進行の段取りがとても重要です。まずは全体の所要時間を確認し、各フェーズ(議論、整理、発表準備など)にどれくらいの時間をかけるかをざっくり決めましょう。
タイムキーパー役を決め、こまめに時間の残りを伝えることで、チーム全体のペースが整いやすくなります。また、「残り10分になったら発表準備に入ろう」といった合意があると、焦らず進行できるでしょう。
時間のゆとりは心の余裕につながり、質の高い成果物にも反映されます。
タイムキーパーを任された人の段取り力や状況判断に加え、役割に関係なく時間を共有する姿勢があるかも、チームワークを図るうえでのチェックポイントになりますよ。
また、序盤から綿密に決めすぎると逆に柔軟性が欠けてしまうこともあります。途中で議論が長引く場合は、何を削るかの判断も求められますね。
ステップ③:各メンバーの役割分担を決める
チームワークを発揮するには、明確な役割分担が欠かせません。司会・書記・タイムキーパーといった基本的な役割を中心に、発言の整理役や発表担当なども含めて決めていきましょう。
自分の得意や性格に合った役割を選ぶと動きやすくなります。たとえば、人前で話すのが得意ならプレゼン担当、論点を整理するのが好きならまとめ役などが向いているでしょう。
ただし、役割に縛られすぎず、必要に応じて他のポジションをサポートする柔軟性も忘れないでください。
役割分担の精度が高いチームは、グループワーク全体の完成度も高い傾向があります。「誰が何をするか」だけでなく「なぜその人がその役割を担うのか」まで言語化しておきましょう。
さらにフォローし合える空気があるかどうかもポイントです。たとえば、司会が詰まったときに自然に他のメンバーが補足していたりすると、「このチームは柔軟性があるな」と感じます。
ステップ④:テーマの理解と話し合いの方向性を確認する
テーマが提示されたら、いきなり意見を出すのではなく、まずは全員で内容をしっかり読み込んで共通理解を図ることが大切です。
何を求められているのか、目的は何か、評価の観点はどこかなどを確認しないまま進めると、途中で「方向がずれていた」と気づいて手戻りが発生してしまいます。
議論の前に「要するにこういうことですよね?」と確認するひと声があると、ズレを防ぎやすくなるでしょう。共通認識を持った上で進めることで、議論がぶれずにまとまります。
テーマ理解の段階で「自分たちは何を解決すべきか」「どんな視点で評価されるのか」を明確にしておくと、その後の議論の質が格段に上がります。
また、この段階で曖昧な部分を放置してしまうと、後半で意見が食い違い、収拾がつかなくなるケースも珍しくありません。確認のひと声があるだけで、チームの進行がスムーズになりますよ。
ステップ⑤:意見を出し合い、最終案をまとめる
アイデア出しの段階では、発言の多さよりも安心して意見が言える雰囲気を作ることが重要です。
否定から入るのではなく、「それ面白いですね」「こういう方向もありますね」と前向きなリアクションを意識しましょう。
多様な視点を受け入れた上で、どのアイデアがテーマに最も適しているかを全員で整理し、納得できる形にまとめていきます。
意見が割れた場合も、論点を洗い出し、メリット・デメリットを比較して判断するとスムーズです。最終案に一体感があることが成功のカギになります。
意見を出し合う場面では、「他人のアイデアにどう反応したか」がよく見られています。誰の意見にも反応せず自分の主張だけした人は評価が伸びづらい印象ですね。
また、最終案をまとめる際に多数決で決める際も、メンバー間で納得感のあるプロセスを踏んだかどうか、判断の筋道を私たちも重視していますよ。
ステップ⑥:発表内容をブラッシュアップする
発表する内容が決まったら、それをどのように伝えるかを意識してブラッシュアップしていきましょう。
話す順番を整理したり、話が分かりにくくならないように言葉を簡潔にしたりするだけでも、聞き手の理解度は格段に上がります。また、図や事例を入れると説得力が高まるでしょう。
発表担当が話しやすいように原稿や流れを整理し、練習の時間を確保することも重要です。チーム全体で発表をサポートしながら、誰が聞いても伝わる内容に仕上げていきましょう。
発表内容のブラッシュアップでは、「誰が聞いても伝わる構成」にすることが非常に大切です。聞き手の理解を前提に構成する意識があるかどうかで、伝わり方が大きく変わりますよ。
また、図や事例を加える工夫は、チーム全体の論理性や現実的な視点を示すチャンスにもなります。聞く側の時間や集中力に配慮して構成を考えると、発表全体の完成度が一段上がるはずです。
ステップ⑦:プレゼンテーションを実施する
いよいよプレゼン本番です。緊張してしまうのは当然ですが、落ち着いてゆっくり話すことを意識すると、内容はしっかり伝わります。
ポイントは、事前に決めた構成を守ること、聞き手の顔を見ながら話すこと、そして堂々とした姿勢で臨むことです。
話す内容を丸暗記するのではなく、「伝えたいことを理解して話す」ことで、自然なプレゼンになります。1回でもリハーサルしておくと自信が持てるため、練習時間は必ず確保しておきましょう。
プレゼンで評価されるのは話のうまさよりも、「何を伝えようとしているのか」が明確であることです。特に、聞き手の理解度に目を配れるかどうかは評価に大きく影響します。
また、構成通りに進めることに集中しすぎて、棒読みになってしまうケースも多いですね。たとえ1回でも、声に出して練習するのとしないのとでは、表現力に差が出ますよ。
ステップ⑧:フィードバックを受けて振り返る
発表後のフィードバックは、グループワークの中でも特に成長につながる場面です。良かった点は素直に受け取り、自信につなげましょう。
同時に、改善点については防御的にならず、次回に活かす材料として受け止めることが大切です。自分では気づかなかった癖やクセのある話し方など、客観的な視点から得られる学びは多くあります。
また、自分自身でも「何がうまくいったか」「どこで戸惑ったか」をメモしておくと、次に活かしやすくなるでしょう。
フィードバックを「評価」ではなく「学びの機会」と捉えられるかが、伸びる人の特徴です。反省点を次回の行動に反映できる人は、成長スピードが段違いなんですよ。
加えて、言われたことを鵜呑みにするだけでなく、「なぜそう指摘されたのか」と自分の言動を振り返る姿勢も重要です。内省が深まると、短期間でも大きな変化が生まれますよね。
インターンのグループワークで求められる役割

グループワークを円滑に進めるには、各メンバーが自分の役割を理解し、状況に応じて柔軟に動くことが欠かせません。
役割の理解は、協力的な雰囲気づくりにもつながり、チーム全体のパフォーマンス向上に直結します。
- 司会(ファシリテーター)
- 書記
- タイムキーパー
- アイデア提供者
- まとめ役
① 司会(ファシリテーター)
司会は、グループの話し合いをスムーズに進行する役割を担います。議論が偏らないよう話を振り分けたり、発言が少ないメンバーにも声をかけたりすることで、全員が参加しやすい空気をつくるのが大切です。
テーマに関する知識や発言力よりも、空気を読みながら中立的に進行できることが求められます。また、話題が脱線した場合は本題に戻すなど、軌道修正する力も重要です。
周囲への気配りや配慮が自然にできる人が適任といえるでしょう。
② 書記
書記は、グループで話し合われた内容を記録する責任があります。単にすべてを書き起こすのではなく、ポイントを押さえながら、論点や意見の流れを整理して記録する力が必要です。
発表資料の作成に活用されることも多いため、書記の正確な記録がその後の成果物の質を左右します。
手書きでもパソコンでも構いませんが、記録に集中しすぎて議論に参加できなくならないよう注意してください。難しいときは「ここ確認していい?」と周囲に確認を取るのも一つの手です。
③ タイムキーパー
タイムキーパーは、グループワーク全体の進行を時間面からサポートします。各ステップに割り当てた時間を意識しながら、残り時間をメンバーに共有し、議論が滞っていると感じたら促しを入れる役割です。
「あと10分でまとめに入ろう」といった具体的な声かけが、全体の意識を整えます。
最終的な発表に間に合うよう逆算しながら動けるかが鍵で、単なる時計係ではなく、戦略的な時間管理能力が問われるポジションです。
④ アイデア提供者
アイデア提供者という役割に形式的な定義はありませんが、活発な議論を生み出すうえで非常に重要です。
斬新な視点やユニークな発想を積極的に出すことで、他のメンバーの思考を刺激し、チーム全体のアイデアの質を引き上げる効果があります。
突飛な発言が正解につながることもあり、自由な発想が歓迎される場面も少なくありません。
ただし、自分の意見にこだわりすぎず、他人の考えにも耳を傾けながら、チームとしての一体感を大切にする姿勢も忘れないでください。
⑤ まとめ役
まとめ役は、議論の収集点を見出し、出された意見を整理して最終的なアウトプットへ導く役目です。
発言が多く出た場合も、主旨を整理して論点を明確にし、矛盾や重複を取り除いて論理的な構成に整える必要があります。
発表資料の骨組みをつくる際には、全体の構造を理解しながら、伝えたいポイントを絞り込む判断力が求められます。全体を俯瞰する視点と、丁寧なコミュニケーションができる人に向いている役割です。
議論の中盤以降に自然とその役を担うことも多いでしょう。
インターンのグループワークで評価されるポイント

グループワークでは、ただ参加するだけでは十分とはいえません。企業は参加者がどのように行動し、どのように貢献したかを細かく見ています。ここでは、評価されやすい5つのポイントを紹介します。
事前に意識しておくことで、自分の強みをより効果的にアピールできるでしょう。
- 論理的思考力があるか
- 積極性があるか
- 協調性があるか
- 役割遂行力があるか
- 問題解決に向けた工夫力があるか
① 論理的思考力があるか
論理的思考力は、課題に対するアプローチを構造的に捉え、相手にわかりやすく説明する力です。
たとえば「この施策を選ぶ理由は、データからAが伸びており、Bのニーズが強まっているから」といったように、根拠を明確に示しながら意見を伝えると説得力が増します。
論理が明快な人は、議論を混乱させずに建設的な方向へ導けるため、チームからも信頼されやすくなるでしょう。内容そのものの正確さだけでなく、順序立てて話せるかどうかも評価の鍵となるはずです。
論理的思考力を伝えるために、「情報を整理して根拠をもとに結論を導けるか」が求められています。その構成の仕方や、聞き手に伝わるかどうかまでを私たちは見ています。
また、論理的に話せる人は議論の流れを俯瞰できるため、周囲が感情的になったときでも冷静に軌道修正できる力があります。これは入社後のチーム業務でも非常に重宝される力ですよ。
② 積極性があるか
積極性は、単に発言の回数が多ければよいというものではありません。大切なのは、チームを前に進めるための行動ができているかどうかです。
たとえば、意見が出にくい場面で「ほかに思いつくことはありますか?」と話題を振ったり、誰かの意見に対して「それ面白いですね」と反応することも、積極的な姿勢として高く評価されます。
小さな一言や気配りが、場の空気を明るくし、全体の動きを滑らかにするのです。遠慮せず、自分から関わる意識を持ちましょう。
積極性の評価で見ているのは、場を動かそうとする意思や工夫があるかです。他の人の発言を促す姿勢や場に温度感を与える発言も、私たちはきちんと拾っています。
自分の意見に固執せず、周囲の雰囲気に配慮しながら場の流れを調整できたり、沈黙を打開する一言が自然に出せたりすると、「この人がいるとチームが前に進む」と感じますよね。
③ 協調性があるか
協調性とは、自分の考えをただ伝えるのではなく、相手の意見に耳を傾け、チーム全体のまとまりを意識して動ける力です。
議論で意見がぶつかっても、感情的にならず冷静に受け止める姿勢が信頼につながります。
また、自分の発言が強すぎると感じたら、「他に考えがあればぜひ聞きたいです」と一歩引いて周囲に配慮することも必要です。
チームとして一つの結論を導くには、個人の主張よりも全体のバランスが重要になります。協調的な行動は、確実に評価されやすい要素です。
協調性は「周囲に合わせる力」と誤解されがちですが、本質はチーム全体を前に進めるために必要な対話力です。意見が対立したときにこそ、その人の協調性が表れます。
私たちも選考の場では、会話の流れを自然につなげたり、沈黙をうまく補完したりといった場面に注目しています。最終的に「一緒に働きたい」と感じさせることが大切です。
④ 役割遂行力があるか
グループワークでは、それぞれに割り当てられた役割をきちんとこなす力も評価対象です。司会、書記、タイムキーパーなど、どのポジションでも責任を持って動ける人は、チームからの信頼を集めます。
特に、裏方の役割を黙々と支える姿勢は、見えにくくても企業側はしっかりチェックしています。
「発言が少ない=評価されない」と思いがちですが、与えられた役割を丁寧に遂行することこそ、信頼を得る近道です。見栄を張らず、地道な貢献を意識しましょう。
私たちは役割に対して自分なりの工夫を加えているかにも注目しており、例えばタイムキーパーが、残り時間を伝えるだけでなく、議論の進行ペースまで調整している場合、評価が高まります。
また、表に出づらい役割を担った場合でも、チーム全体がスムーズに動けた背景にはその人の貢献があるという構図が見えてくると、人事側はしっかりその努力を拾い上げます。
⑤ 問題解決に向けた工夫力があるか
議論が停滞したときや意見が割れたときに、どう打開するかを考える力も評価されるポイントです。
たとえば「視点を変えて考えてみませんか?」といった柔軟な発言や、「このアイデアを組み合わせてみては」といった工夫があると、問題解決力が高く評価される可能性があります。
決まった方法にとらわれず、課題に対して新しい角度からアプローチできる姿勢が求められるでしょう。論理性と同時に創造性も発揮しながら、現実的な提案に落とし込む力を意識してください。
グループワークでは、意見が平行線になった場面でどう動けるかが問われます。特に、既存の意見をうまく融合させて打開策を導ける人は、実際の業務でも応用力があると見なされやすいですね。
私たちも評価時には、「その場に合った打ち手を選べているか」まで見ています。大胆な発想だけでなく、現実的な落としどころまで考えられていると、一段評価が上がりますよ。
苦手なインターンのグループワークを乗り越えるコツ

グループワークが苦手な人は少なくありませんが、事前の準備とちょっとした意識の工夫で、不安は軽くなります。ここでは、実践しやすく効果的なコツを紹介します。
- 事前に業界や企業について調べる
- 自分ができそうな役割を把握する
- 自己紹介で相手と関係構築を意識する
- リーダーシップよりも協調性を重視する
- 常にメンターに見られていると意識する
- 繰り返し模擬練習をして慣れる
- 不安な点は素直に相談・質問をする
① 事前に業界や企業について調べる
事前に業界や企業の情報を調べておくことは、安心して議論に参加するための土台となります。
グループワークでは企業の実務に近いテーマが出されることもあるため、背景知識があるかどうかで発言の質が大きく変わるでしょう。
企業の公式サイトや採用ページを見るのはもちろん、業界レポートや最近のニュース、競合との違いなども確認してみてください。
自分なりの視点で課題をとらえられるようになれば、自信を持って意見を出しやすくなります。
企業や業界の情報を事前に調べることで、グループワークでの発言に深みが増します。業界特有の課題や企業の強み・弱みに触れた発言は、他の参加者との差を生む大きなポイントです。
また、情報を仕入れる際は、企業の公式サイトやIR情報などに加え、就活サイトやSNSでの外部評価も参考にすることで、多面的な理解につながりますよ。
② 自分ができそうな役割を把握する
自分の得意分野や性格をあらかじめ整理しておくことで、役割決めの際に迷いにくくなります。
話すのが得意な人はアイデア出しや司会、慎重な性格であればまとめ役や書記など、自分に合った形で無理なく貢献することが大切です。
特に初対面のチームでは、自分から「こういうことは得意です」と一言伝えるだけでもスムーズに役割が決まりやすくなります。
役割を持つことで自然と責任感も芽生えるため、不安の軽減にもつながるでしょう。
自分に合った役割を把握しておくことは、グループワークでの存在感を自然に高める一つの手段です。これは本番中に焦らず、思考や行動に余白を持たせる効果もありますよ。
私たちも「自分の強みを状況に応じてどう活かせるか」という視点を重視しています。その場でどう役立てるかを常に意識して参加すると高評価につながることが多いですね。
③ 自己紹介で相手と関係構築を意識する
自己紹介はただの形式的な挨拶ではなく、グループの雰囲気を決める重要な瞬間です。
名前や大学名だけで終わらせず、「今日は初めてですが、話すのは好きです」「緊張していますが頑張ります」といった一言を添えると、相手も安心しやすくなります。
表情やトーンにも気を配り、笑顔を意識するだけでも場の空気が柔らかくなります。短時間での信頼関係づくりがグループワークの成功に直結するため、第一印象を大切にしてください。
④ リーダーシップよりも協調性を重視する
「目立たなければいけない」と思い込むと空回りしてしまうことがあります。グループワークで重要なのは、全体のバランスを見ながら協力する姿勢です。
リーダーを務めることが必須ではなく、むしろ発言が多すぎて他者の意見をさえぎってしまうとマイナス評価になる可能性もあります。
相手の話に耳を傾け、必要に応じて助け舟を出したり、まとめ役に回ったりする柔軟な動きが、結果的に信頼される行動につながるのです。
私たちが注目するのは、チーム全体の成果を引き出そうとする姿勢です。他のメンバーの話を丁寧に聞いて要点を拾い、議論を整理してくれる人は、非常に好印象ですよ。
また、協調性を発揮しているかは、言葉だけでなく立ち位置にも現れます。一歩引いて場を俯瞰できるか、他人をフォローする気配りがあるかは、グループワークでこそよく見えるポイントなんです。
⑤ 常にメンターに見られていると意識する
グループワークでは、企業の担当者やメンターが常に参加者の様子を見ています。
発言内容だけでなく、うなずきやリアクション、メモを取る姿勢、相手の話をどれだけ真剣に聞いているかといった部分までチェックされていることを忘れてはいけません。
気を抜いた態度や無反応な表情はマイナスにつながりかねないのです。一貫して誠実な態度を意識し、目の前の人とのやり取りを大切にしましょう。
⑥ 繰り返し模擬練習をして慣れる
グループワークは経験値がものを言います。最初は誰でも緊張しますが、模擬練習を重ねることで、話すタイミングや役割の流れが自然と身についていくもの。
大学のキャリアセンター、民間の就活セミナー、オンラインワークショップなど、多くの練習の場があります。異なる人と組んでの練習は、初対面の人とのやり取りに慣れるうえでも効果的です。
少しずつで構いませんので、場数を踏んで自信につなげてください。
グループワークで見られているのは、「その場でどう動けるか」という瞬発力です。本番で落ち着いて行動できる人は、場慣れしていることが多く、それが評価の分かれ目にもなります。
また、模擬練習では自分の立ち回りを振り返る時間を設けるのがポイントです。第三者からのフィードバックで、自分の強みや課題に気づき、それが次回の行動に直結します。
⑦ 不安な点は素直に相談・質問をする
「分からないことがあっても聞きにくい」と感じる人は多いですが、そのまま黙っていることのほうが問題です。分からないことがあれば、遠慮なく「これはこういう意味ですか?」と確認してみましょう。
素直に質問する姿勢は、理解を深めるだけでなく、誠実さや向上心として好印象を与えます。
チーム内でもスタッフに対しても、迷ったときは言葉にして伝えることが、不安を減らし、スムーズな進行にもつながるでしょう。
インターンのグループワークは発言量より調整力?先輩の体験談から学ぼう
グループワークに参加すると、「積極的に発言しなきゃ」「目立たないと評価されないかも」と考えてしまう人は多いのではないでしょうか。でも、実際にはその姿勢が逆効果になることもあり、そんな気づきを得た先輩の体験談をご紹介します。
今回は、商社系のインターンで実際に出題されたお題に取り組んだ先輩が、初日の反省を経てどのように行動を変えたか、そして何を得たかを語ってくれました。「どれだけ発言したか」ではなく、「どうチームに貢献できたか」を重視する視点に行動していた部分に着目してみてください。
| 関西の私立大学 文学部 4年生(22歳)の体験談 |
|---|
| 商社系の3日間インターンに参加したとき、グループワークで「2030年に向けた新規事業を企画せよ」というお題が出されました。 初日はとにかく目立とうと、自分の意見をどんどん発言していたんですが、気づけば周りが発言しづらい雰囲気になってしまっていて…。 社員の方に「相手の意見を引き出すのも大事だよ」とアドバイスをもらって、2日目からはスタンスを切り替えました。発言するというより、チームの話し合いを整理したり、発言が少ない人に声をかけたりしてみたんです。 すると、それまで埋もれてた意見が出てくるようになって、全体の方向性が自然にまとまっていきました。最終日のプレゼンでは「チームの連携が良かった」とフィードバックももらえて。 発言量よりも、いかにチーム全体で成果を出せる空気をつくるかが大事だったんだと気づかされました。グループワークって、ただの自己アピールの場じゃないんですよね。 |
この体験談は、グループワークでありがちな「発言=評価」という誤解からの脱却を示しています。発言が多いこと自体は悪いことではありませんが、周囲が発言しづらくなるような空気を作ってしまっては、チームの輪を乱していると捉えられるケースもあり逆効果です。
むしろ、全体の議論を促進し、参加者それぞれの意見を引き出す姿勢こそが、選考でも高く評価されやすい行動です。チーム全体に目を向け、調整役として機能することが、信頼やリーダーシップのアピールにつながこともあります。
グループワークへの苦手意識は「うまく発言できない」不安や焦りからくるケースが多いですが、理想はチームの全員が「うまく発言できない」状態になっておらず、チームでゴールに到達できることです。
そのため、自身のアピールだけではなく、チームとしてどう評価されるのかという視点を意識してみましょう。その視点を持ってからインターンでのグループワークに参加することで、やるべきことと自分ができることが明確になりうまく立ち回ることができますよ。
「インターンの選考対策がよくわからない…」「何度も選考に落ちてしまう…」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるインターン選考対策ガイドを確認して必勝法を知っておきましょう。LINE登録だけで無料でダウンロードできますよ。
インターンのグループワークを成功に導くコツと立ち回りを理解しておこう!

インターンにおけるグループワークでは、目的や種類、評価基準、進め方まで幅広い視点からの理解が求められます。
成功するためには、ただ場に臨むだけでなく、事前に業界知識や役割理解、テーマへの対応力を身につけておくことが大切です。
特に、グループディスカッションとの違いや、作業型・討論型など各形式の特性を知っておくことで、求められる行動が明確になります。
苦手意識がある人でも、模擬練習や役割の把握を通して自信が持てるでしょう。インターンのグループワークは評価にも直結する重要な機会です。
対策を怠らず、自分らしさを発揮することで、確実に成果につなげてください。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













