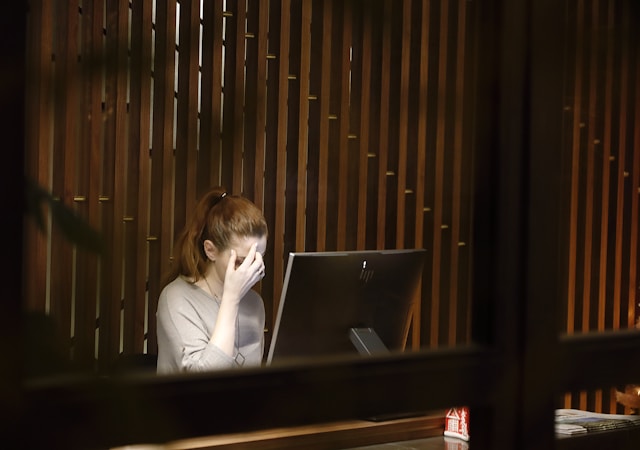就活倍率をどう活用する?企業選びと内定獲得につなげる方法
就活倍率は単なる「競争率」ではなく、企業選びや戦略的なエントリー計画を立てるうえでの指標のひとつです。
この記事では、就活倍率の基礎知識から業界別・企業別の傾向、そして倍率をどう読み解き、自分のキャリア形成に生かすかまでを詳しく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
就活倍率とは?

就活倍率とは、ある企業や業界に対して応募する学生数と採用予定人数の比率を示す指標です。
就活生にとってこの数字は、単に「難しい」や「人気がある」という感覚を裏づけるものではなく、自分の立ち位置を知るための客観的な目安になります。
有名企業や大手総合商社、テレビ局、食品メーカーなどは、毎年多くの学生から注目を集め、数十倍から100倍を超える倍率になることも少なくありません。
一方で、地方企業や専門分野に特化した企業では応募者数が限られるため倍率が低めとなり、意外な「穴場」となる場合があります。
つまり就活倍率は、学生が現実的に勝ち抜くための戦略を立てるための出発点であり、自分の努力の方向性を整理する羅針盤のような役割を果たすのです。
「就活でまずは何をすれば良いかわからない…」「自分でやるべきことを調べるのが大変」と悩んでいる場合は、これだけやっておけば就活の対策ができる「内定サポートBOX」を無料でダウンロードしてみましょう!
・自己分析シート
・志望動機作成シート
・自己PR作成シート
・ガクチカ作成シート
・ビジネスメール作成シート
・インターン選考対策ガイド
・面接の想定質問集100選….etc
など、就活で「自分1人で全て行うには大変な部分」を手助けできる中身になっていて、ダウンロードしておいて損がない特典になっていますよ。
就活で使用する他の倍率

就活において「倍率」という言葉はよく耳にしますが、その意味は一つではありません。就職活動では就職倍率、内定倍率、求人倍率といった複数の種類があり、それぞれに役割や使い方が異なります。
これらを正しく理解することで、自分が受けようとしている業界や企業の状況を冷静に分析できるようになります。ここでは各倍率の特徴を整理し、就活で活用する際の視点を紹介します。
- 就職倍率
- 内定倍率
- 求人倍率
①就職倍率
就職倍率とは、就職希望者の人数を求人の人数で割った数値です。例えば倍率が3倍なら、1人の求人に対して3人が希望していることを意味します。
倍率が高ければ「難関」という印象を持ちやすいですが、実際には必ずしもそうとは限りません。
なぜなら、就職倍率は人気業界や大手企業が数値を押し上げている場合も多く、全体の就活状況を一律に表しているわけではないからです。
また、就活倍率と比べると、就職倍率は「業界や全体」を示す指標であるのに対し、就活倍率は「企業や学生の体感難易度」と結びつきやすい傾向があります。
数字に振り回されず、自分の強みとマッチする領域を見極める視点が重要でしょう。
②内定倍率
内定倍率は、実際に応募した学生数に対して企業が出した内定者数の割合を示します。
例えば応募者1,000人に対して内定が100人なら、倍率は10倍となり、平均すると10人に1人しか内定を得られない計算になります。
この数値は「内定がどのくらい取りやすいか」を表しているため、学生にとって非常に実感しやすい指標といえるでしょう。
倍率が高ければ厳しい選考を突破しなければなりませんが、その分企業の求める人物像が明確で、適性が合う学生にとっては意外とチャンスが大きいこともあります。
単に数字を見て諦めるのではなく、エントリー数や準備の深さを調整し、自分の強みを生かせる環境を探すことが成功の鍵になるでしょう。
③求人倍率
求人倍率は、企業が出している求人の数を求職者の数で割った数値であり、労働市場における需給バランスを示します。
就職倍率が「学生から見た競争率」であるのに対し、求人倍率は「企業が人材をどの程度必要としているか」を表す指標です。
特に業界ごとの差が大きく、ITや建設業界では慢性的な人材不足の影響で高倍率が続く一方、マスコミや広告業界では求人が少なく倍率が低く出やすい傾向があります。
ここで就活倍率との違いを意識すると、求人倍率はあくまで「採用市場全体の需給」を反映している数値であるのに対し、就活倍率は「学生が体感する企業難易度」に近い意味合いを持ちます。
数字を自分の立ち位置を知るツールとして活用し、準備や志望先選びに反映させることが成功につながるでしょう。
近年の就活倍率の傾向

近年の就活倍率は、景気や採用数の増減に大きく左右されています。全体としては売り手市場と呼ばれる状況が続いていますが、実際には業界や企業規模、専攻や地域によって大きな差があるのが現実です。
ここでは全体的な推移から個別の傾向までを解説し、就活生が自分に合った戦略を立てられるよう整理していきます。
- 全体の就活倍率の傾向
- 業界別の就活倍率の傾向
- 企業規模別の就活倍率の傾向
- 専攻別(文系・理系)の就活倍率の傾向
- 地域別の就活倍率の傾向
「有名企業でなくてもまずは内定を目指したい…」「隠れホワイト企業を見つけたい」方には、穴場求人も紹介しています。第一志望はすでに決まっているけど、他の業界や企業でも選考に参加したい方は非公開の穴場求人を確認してみてくださいね。キャリアアドバイザーがあなたに合う求人を紹介してくれますよ。
①全体の就活倍率の傾向
就活全体の倍率は景気の状況や企業の採用数に大きく影響されます。近年は人手不足の背景もあり、全体の平均倍率は下がり、学生にとって有利な売り手市場といえるでしょう。
しかし、この数字だけを見て安心するのは危険です。例えば、人気業界や知名度のある大手企業に応募が集中し、数十倍から100倍を超えるような高倍率になる場合もあります。
つまり「全体的に倍率が低い=簡単に内定が取れる」というわけではありません。
就活生が意識すべきなのは、全体の数値を一つの目安にしつつ、実際に自分が志望する業界や企業の倍率をしっかり確認することです。
そのうえで、必要な準備量や対策を現実的に計画することが大切でしょう。倍率の裏にある意味を理解できれば、不必要な不安に振り回されることなく、正しく努力を積み重ねられるはずです。
②業界別の就活倍率の傾向
業界ごとに倍率の特徴は大きく異なります。商社やマスコミといった華やかで人気のある業界は、現在でも高倍率が続いており、時には100倍を超えるケースも存在します。
これらの業界を第一志望とするなら、相当な準備と覚悟が求められるでしょう。一方で、インフラ業界や製造業の一部は採用数が安定して多く、比較的倍率が落ち着いている傾向にあります。
倍率の差を理解せずに志望先を限定すると、必要以上に厳しい競争に飛び込むことになりかねません。
就活生が意識すべきなのは、自分の興味や適性を大切にしつつ、倍率の情報を参考にして選択肢を広げる姿勢です。
倍率は志望業界を狭めるための基準ではなく、自分がどこに挑むべきかを見極めるための指標として活用してください。
③企業規模別の就活倍率の傾向
企業規模も倍率に大きな影響を与えます。大手企業は安定した経営基盤や待遇の良さから学生に人気が集まり、倍率が非常に高くなる傾向があります。
就活生の多くは「大手志向」を持つため、その競争率は自然と厳しくなってしまうのです。
逆に、中小企業やベンチャー企業は採用数自体は少なくても、応募する学生が限定されるため、倍率は比較的落ち着くことが多いでしょう。
また、中堅規模の企業は知名度こそ劣りますが、独自の強みや成長性を持っているケースも少なくありません。
倍率を理解しながら企業規模ごとの特徴を踏まえて戦略を練ることで、現実的に内定に近づく道を描けるでしょう。
④専攻別(文系・理系)の就活倍率の傾向
文系と理系では倍率の傾向が異なります。文系学生は応募できる業界が幅広いため選択肢が多い一方で、金融や商社、マスコミといった人気業界に応募が集中し、高倍率に直面しやすいのが特徴です。
理系学生は技術職や研究職を中心に採用ニーズが安定しており、文系に比べると全体的には倍率が低い傾向があります。
ただし、理系でも大手メーカーやIT系の人気企業では競争が激しくなり、決して簡単に内定が得られるわけではありません。就活生は専攻ごとの傾向を理解したうえで戦略を立てることが大切です。
文系なら応募先をある程度分散させる、理系なら自分の専門性を前面に出して評価されるポジションを狙うといった工夫が有効でしょう。
単に「文系は厳しい」「理系は有利」と一括りにするのではなく、自分の専攻に沿った倍率の背景を踏まえた対策が、内定への近道になるはずです。
⑤地域別の就活倍率の傾向
地域ごとに就活倍率の傾向も大きく異なります。東京や大阪などの大都市圏は企業数が多く選択肢が豊富ですが、全国から学生が集まるため倍率は高くなる傾向があります。
特に有名企業の本社が集中する都市部では、競争が一層激しくなるでしょう。一方で地方は企業数が限られるものの、応募者が地元志向の学生に偏るため、倍率は比較的低くなるケースも見られます。
ただし、地方企業の中には安定した経営基盤や独自技術を持つ優良企業が数多く存在し、就職先として大きなチャンスになる場合もあります。
就活生は倍率と合わせて、自分のキャリアやライフプランとの適合性を見極めることが必要でしょう。
倍率を正しく理解すれば、都市部か地方かを問わず、自分に合った選択を自信を持って行えるはずです。
就活倍率が高い企業

就活倍率が高い企業は、多くの学生から人気を集める一方で、内定獲得の難易度も大きく高まります。理由はブランド力や給与水準、キャリアの広がりなど幅広く、業界ごとの特性も影響しています。
ここでは、食品や商社、広告など就活生から特に注目を集める業界ごとに、高倍率企業の傾向を詳しく見ていきます。
- 食品・飲料業界の高倍率企業
- 商社業界の高倍率企業
- 広告・マスコミ業界の高倍率企業
- 金融業界の高倍率企業
- メーカー業界の高倍率企業
- IT業界の高倍率企業
- コンサルティング業界の高倍率企業
- 航空・旅行業界の高倍率企業
- インフラ業界の高倍率企業
- 官公庁・公務員の高倍率職種
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
①食品・飲料業界の高倍率企業
食品・飲料業界は生活に直結する商品を扱うため、多くの学生にとって親しみやすく志望しやすい分野です。特に大手メーカーは消費者として日常的に接していることから知名度が高く、志望者が集中します。
たとえばサントリーやキリン、明治などは毎年多くの応募があり、倍率は数十倍に達することも少なくありません。
人気の背景には「社会に影響を与えられる実感」や「長期的に安定したブランドのもとで働ける魅力」があります。ただし採用人数が限られており、志望理由が漠然としたものでは突破は困難です。
学生時代の経験をどう活かし、ブランド価値向上につなげるかを明確に伝えることが評価につながるでしょう。
主な高倍率企業:サントリー、キリン、アサヒ、明治、森永乳業、雪印メグミルク、カゴメ、日清食品、味の素、ロッテ
②商社業界の高倍率企業
商社業界は就活倍率が突出して高い業界です。特に総合商社は、年収の高さやスケールの大きな仕事に憧れる学生が殺到し、倍率が100倍を超えることも珍しくありません。
伊藤忠商事や三菱商事、住友商事といった大手は、世界を舞台にビジネスを展開できる点が魅力です。就活生にとって、語学力や主体性をアピールできる理想的なフィールドでしょう。
しかし採用では将来のリーダー候補としての素養が重視されるため、学歴や語学力だけでは不十分です。
論理的思考や調整力、周囲を巻き込む力など、多面的な資質を持っていることを示す必要があります。早期のインターン参加や業界理解の深さも評価に直結するため、入念な準備が欠かせません。
主な高倍率企業:伊藤忠商事、三菱商事、三井物産、住友商事、丸紅、双日、豊田通商、兼松、阪和興業、長瀬産業
③広告・マスコミ業界の高倍率企業
広告・マスコミ業界は華やかなイメージや社会的影響力の大きさから、学生の憧れを集めています。電通や博報堂といった大手広告代理店、NHKや在京キー局は常に高倍率です。
ここで働くことで、自らのアイデアや企画が世の中に広がる体験を得られる点が大きな魅力でしょう。
一方で、成果主義や長時間労働といった厳しさもあり、現実を理解せずに応募するとギャップに直面します。
就活生には「なぜ広告を通じて世の中に影響を与えたいのか」を自分の経験と結びつけて伝える力が求められます。
倍率が高い分、企業研究や志望動機の深さがそのまま評価につながるため、十分な準備が必要です。
主な高倍率企業:電通、博報堂、ADK、東急エージェンシー、読売新聞社、朝日新聞社、NHK、日本テレビ、フジテレビ、TBS
④金融業界の高倍率企業
金融業界は銀行、証券、保険など多様ですが、特に外資系投資銀行や大手証券会社は高倍率です。年収水準の高さや専門性のある業務への憧れから、志望者が集中します。
ゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレー、日本の大和証券や野村證券などは数十倍の競争率になることがあります。
金融業界で重視されるのは、数字への強さや分析力だけではなく、顧客対応力や組織で成果を出す力です。
学生時代の経験を通じて「粘り強く成果を出した実績」や「人との信頼関係を築いたエピソード」を具体的に伝えることが合格につながります。
倍率は高いですが、それを乗り越える価値のある業界といえるでしょう。
主な高倍率企業:ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、JPモルガン、シティグループ、UBS、野村證券、大和証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券
⑤メーカー業界の高倍率企業
メーカー業界は幅広い分野を持ち、特に自動車や電機メーカーは高倍率になりやすいです。
トヨタやソニー、パナソニックなど世界的ブランドを持つ企業は、社会的影響力の大きさから学生に強い人気を集めます。
製品を通じて社会に貢献できるやりがいや、グローバルに挑戦できる環境が魅力でしょう。一方で職種や採用枠が多岐にわたるため、研究開発や営業など希望分野を明確にしないと説得力に欠けます。
就活生には「自分がその企業のどの商品や技術に魅力を感じているのか」を掘り下げて語る力が重要です。
倍率は高いですが、入社後の安定性や長期的キャリア形成を考えると挑戦する価値は十分にあります。
主な高倍率企業:トヨタ自動車、ソニー、パナソニック、日立製作所、三菱電機、ホンダ、マツダ、任天堂、資生堂、花王
⑥IT業界の高倍率企業
IT業界は成長性が高く、特にGAFAなどの外資系や楽天、サイバーエージェントなど国内大手は倍率が高いです。自由な働き方やイノベーションに携われる点が学生を惹きつけています。
就活生にとっては、新しいサービスを作り出す場でチャレンジできることが魅力でしょう。ただし、人気企業ほどプログラミングスキルやデータ分析力など具体的な能力が重視されます。
単なる憧れだけでは通用せず、成果物や実績を提示できるかが選考突破の分かれ目です。スキルを磨きながら、自分がどの領域で価値を発揮できるかを整理することが重要でしょう。
倍率は高いですが、成長産業であるため挑戦する意義は大きいです。
主な高倍率企業:Google、Apple、Amazon、Meta、Microsoft、楽天、サイバーエージェント、LINEヤフー、リクルート、DeNA
⑦コンサルティング業界の高倍率企業
コンサルティング業界は課題解決力や論理的思考力を活かしたい学生にとって理想的な舞台です。
マッキンゼーやBCG、アクセンチュアなどは国内外で高い人気を誇り、倍率は数十倍から100倍に迫ることもあります。
高収入や成長機会が豊富な点に魅力を感じる学生が多い一方、激務で離職率が高い実態もあります。選考ではケース面接や論理力を試す課題が多く、徹底的な準備が不可欠です。
就活生は「自分がどんな課題に向き合い、どう解決してきたか」を整理し、自信を持って伝える必要があります。倍率の高さを乗り越えれば、大きな成長を得られる環境が待っているでしょう。
主な高倍率企業:マッキンゼー、ボストン・コンサルティング・グループ、ベイン&カンパニー、アクセンチュア、デロイト、PwC、EY、KPMG、ローランド・ベルガー、アーサー・D・リトル
⑧航空・旅行業界の高倍率企業
航空・旅行業界は「憧れの職業」として人気が高く、倍率は常に高水準です。ANAやJALの客室乗務員や総合職は、数十倍の競争率になる場合も珍しくありません。
人々の移動を支え、国際的に活躍できる点が大きな魅力です。ただし業界は景気変動の影響を受けやすく、近年はコロナ禍で採用状況が大きく変動しました。
そのため志望者は柔軟性や対応力を備えていることを示す必要があります。単に「憧れている」だけではなく、自分の経験をサービス精神や国際感覚に結びつけることが突破につながります。
倍率は高いですが、熱意と準備次第で夢を実現できる業界です。
主な高倍率企業:ANA、JAL、スカイマーク、エアドゥ、スターフライヤー、HIS、JTB、近畿日本ツーリスト、楽天トラベル、日本旅行
⑨インフラ業界の高倍率企業
インフラ業界は生活基盤を支える役割を担うため、安定性の高さから志望者が多く倍率が上がりやすいです。JR東日本や東京電力、関西電力などは安定志向の学生に選ばれる代表例です。
景気に左右されにくく長期的に働ける点、社会に貢献できる点が人気の理由でしょう。ただし勤務地や働き方に制約がある場合もあり、実際の働き方を理解せずに入社するとギャップを感じやすいです。
就活生は「なぜインフラで働きたいのか」を社会や地域とのつながりを意識して説明することが大切です。倍率は高いですが、志望理由が具体的であれば十分突破できる可能性があります。
主な高倍率企業:JR東日本、JR西日本、JR東海、東京電力、関西電力、中部電力、東京ガス、大阪ガス、東急電鉄、小田急電鉄
⑩官公庁・公務員の高倍率職種
官公庁や公務員は安定性と社会的意義の高さから、多くの学生に人気があり倍率が高くなります。国家総合職や外務省などは採用人数が少ないため、志望者が集中しやすいです。
国の政策に関わり、社会に影響を与える責任の大きさが魅力ですが、筆記試験や論文、面接など選考過程は多段階です。
そのため他業界以上に長期的な準備が必要になります。就活生にとっては、安定志向と社会貢献を両立できるキャリアとして魅力的でしょう。
倍率は高いですが、努力を重ねることで突破できる可能性は十分にあります。
主な高倍率企業:外務省、財務省、経済産業省、国土交通省、総務省、厚生労働省、農林水産省、警察庁、裁判所事務官、国家総合職
参考:業界別・就職偏差値ランキング | 日本企業格付センター作成 / 「入社が難しい有名企業ランキング」(東洋経済新報社)
就活倍率が高い企業の特徴

就活倍率が高い企業には共通する傾向があります。これを理解することで、なぜ競争率が上がるのかを把握でき、志望先を選ぶ際の判断材料にもなるでしょう。
また、倍率を正しく理解すれば、単に人気企業を狙うのではなく、自分の就活戦略に活かすこともできます。ここでは主な5つの特徴を整理しました。
- 知名度やブランド力が高い
- 採用人数が限られている
- 給与や福利厚生が充実している
- 人気業界に属している
- 社会的影響力が大きい
「有名企業でなくてもまずは内定を目指したい…」「隠れホワイト企業を見つけたい」方には、穴場求人も紹介しています。第一志望はすでに決まっているけど、他の業界や企業でも選考に参加したい方は非公開の穴場求人を確認してみてくださいね。キャリアアドバイザーがあなたに合う求人を紹介してくれますよ。
①知名度やブランド力が高い
就活倍率が高い企業の典型例として、知名度やブランド力の高さが挙げられます。
誰もが知っている大企業や商品を展開する企業は「安定して働ける」「社会的に信頼できる」という安心感が強く、エントリー数が自然と増えるのです。
例えば大手自動車メーカーや食品会社は、世代を問わず認知度が高いため、多くの学生が志望します。ただし有名企業に応募が集中することで、倍率は一気に跳ね上がります。
そのため、単に「知っているから」「有名だから」ではなく、自分がその企業で何を実現したいかを言語化しておくことが必要です。
倍率の高さを逆に利用して「厳しい環境で挑戦する意志」をアピールできれば、面接官に強い印象を与えられるでしょう。
②採用人数が限られている
就活倍率を押し上げる大きな要因の1つが採用人数の少なさです。
知名度が高くても採用枠が広ければ倍率はある程度抑えられますが、外資系やベンチャー企業のように「少人数精鋭」を掲げる会社は、一気に狭き門となります。
特に外資系コンサルや投資銀行は数十人程度しか採らない年もあり、倍率は数十倍に及ぶことも珍しくありません。
こうした企業では「即戦力として活躍できる人材」を求める傾向があるため、事前準備の質が結果を大きく左右します。
就活生にとっては厳しい競争に挑む覚悟が求められますが、その分「少人数で裁量の大きな環境に身を置ける」という魅力もあります。
倍率が高い企業だからと敬遠せず、挑戦を通じて自分の市場価値を試す機会にするのも戦略のひとつでしょう。
③給与や福利厚生が充実している
待遇の良さは、就活倍率を高める大きな理由です。給与水準が高く、住宅手当・社宅・研修制度などの福利厚生が整った企業には、多くの学生が安心感を覚えます。
特に都市部で働くことを前提にしている学生にとって、経済的な支援制度は志望動機の大きな要素になるでしょう。
例えば総合商社や大手インフラ企業は、給与面や福利厚生の手厚さで群を抜いており、その結果として高倍率になります。
ここで大切なのは「待遇はあくまで入口」であり、「自分のキャリアビジョンとマッチしているか」を見極めることです。
倍率が高い理由を理解し、待遇以外の軸も整理することで、より納得感のある企業選びができるでしょう。
④人気業界に属している
広告・マスコミ・総合商社・航空などの人気業界に属する企業は、学生からの志望が集中しやすく、倍率が高くなります。
華やかなイメージや国際的に活躍できる機会などがアピールされやすいため、説明会やインターンの段階から参加希望者が殺到します。
しかし、人気業界だからといって必ずしも自分に適した環境とは限りません。実際には激しい競争や長時間労働といった厳しい現実も存在するのです。
就活生にとっては「業界の表の顔」と「裏の実態」を正しく理解することが欠かせません。倍率の高い業界に挑戦する経験は、自分の可能性を広げる意味でも有益です。
⑤社会的影響力が大きい
社会的影響力の大きさも就活倍率に直結します。人々の生活を支える事業を展開している企業や、時代を動かすサービスを提供している企業は「社会に貢献できる」という点で学生の憧れを集めます。
インフラ企業や大手ITプラットフォーム企業はその代表例で、安定性と社会的意義を兼ね備えているため、志望者が後を絶ちません。
倍率が高い企業では、応募理由が似通いやすいという落とし穴があります。
多くの学生が「社会に貢献したい」と語るため、差別化が難しくなるのです。重要なのは、自分自身の経験や価値観と結びつけて具体的に語ることです。
就活倍率が低い企業の特徴

就活倍率が低い企業にはいくつかの共通点があります。倍率が低いからといって魅力が劣るわけではなく、見方を変えれば自分に合った働き方や成長の機会を見つけられることも多いでしょう。
特に就活倍率は企業選びの判断材料の一つに過ぎず、それをどう活用するかが重要です。
倍率だけにとらわれず、自分の価値観や将来像と照らし合わせながら考えることが、納得できるキャリア形成につながります。ここでは主な特徴を整理し、就活生が理解しておきたいポイントを解説します。
- 知名度があまり高くない
- 地方や特定地域に根ざしている
- 業界が成熟しており成長が緩やかである
- 募集職種の専門性が低い
- 離職率や人手不足の課題を抱えている
①知名度があまり高くない
知名度が低い企業は、大手や有名企業に比べて応募者が少ないため倍率が低くなる傾向があります。
学生の多くは「名前を知っている安心感」を求めるため、どうしてもブランド力のある企業に志望が集中しやすいのです。
その一方で、知名度が高くない企業は選考で一人ひとりを丁寧に評価してくれる可能性が高く、自分の強みを正当に見てもらえるチャンスがあります。
また、中小規模ながら業界内で確かなシェアを持つ隠れた優良企業も存在します。
倍率が低いからこそ内定の可能性が高まりやすいという側面もあるため、表面的な知名度に左右されず、事業内容や社風まで踏み込んで調べてみると、自分に合った企業に出会えるかもしれません。
②地方や特定地域に根ざしている
地方に拠点を構える企業は、就活倍率が低くなりやすい特徴があります。都市部に比べて応募者数が少なくなるため、競争が激化しにくいのです。
また、勤務地が地域に限定されるため、就職後に転勤の可能性が低い一方、「都市部で働きたい」と考える学生から敬遠されることもあります。
しかし地域密着型の企業は、地元の人々や行政と強い信頼関係を築いているケースが多く、安定的に経営を続けられる点が大きな強みです。
さらに、地域の産業や文化を支えるやりがいを得られるのも魅力でしょう。UターンやIターンを検討している学生にとっては、就活倍率が低いからこそ地元で働ける可能性が広がることになります。
倍率を活用する際には、「競争率が低い=選択肢を広げるチャンス」と捉え、自分のキャリアと勤務地の希望を照らし合わせながら検討するとよいでしょう。
③業界が成熟しており成長が緩やかである
成熟産業に属する企業も、倍率が低くなる傾向があります。最新のテクノロジーや急成長市場に比べると華やかさに欠け、学生からは「将来性が乏しいのでは」と思われやすいからです。
ただし、成熟している業界は市場が安定しており、需要が継続的に存在するという強みがあります。
例えばインフラや生活必需品を扱う業界は、景気変動の影響を受けにくく、安定して働ける環境が整っています。
また、制度や教育体制が整備されていることが多いため、安心してキャリアをスタートできる点も魅力です。
就活倍率を活用する視点として、「派手さよりも安定」を重視する学生にとっては大きなヒントになるでしょう。
④募集職種の専門性が低い
専門性が低い職種は応募できる学生の幅が広がる一方で、「特別なスキルがいらない」と見られがちで、人気が集まりにくい傾向があります。そのため結果的に就活倍率が低くなるのです。
しかし、これは裏を返せば入社後に基礎から育成してもらえる可能性が高いということでもあります。
新卒の時点で専門的な知識を持たない学生にとって、成長の土台をつくれる環境は非常にありがたいものです。
また、営業職や総合職など専門性が低いとされる職種でも、対人スキルや課題解決力といった普遍的な能力を培うことができます。
倍率が低いからこそ「入りやすい」ではなく、「成長できる機会を得やすい」と捉えるのが就活生にとって賢い活用法でしょう。
⑤離職率や人手不足の課題を抱えている
離職率が高い、または人手不足の企業は敬遠されがちで、その結果倍率が低くなります。もちろん、過酷な労働環境や待遇への不満といった要因も存在しますが、それだけで判断するのは早計です。
人手不足の企業では若いうちから責任のある仕事を任されやすく、短期間で多くの経験を積める可能性があります。
また、離職率の高さも「成長意欲の高い社員が次のステージに挑戦している」という背景がある場合もあるでしょう。
就活生にとっては厳しい環境に見えるかもしれませんが、実際には成長スピードを高められるチャンスともなり得ます。就活倍率を活用する際は、数字の裏にある「理由」を見抜くことが成功の近道です。
就職先の倍率を調べる方法
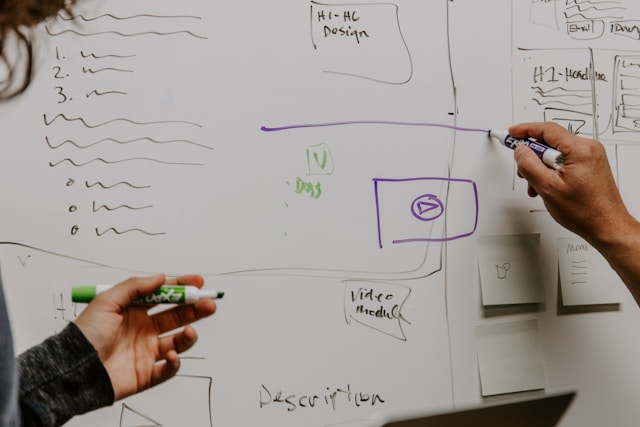
就活を進めるうえで、志望企業や業界の倍率を把握することは欠かせません。倍率を知れば競争の厳しさを理解でき、自分に合った戦略を立てやすくなるでしょう。
調べ方にはいくつかの手段があり、それぞれ特徴や注意点があります。複数の情報を組み合わせると、より正確な判断につながります。ここでは代表的な4つの方法を紹介します。
- 就職四季報や統計資料を確認する
- 求人サイトや逆求人サイトを活用する
- 会社説明会や合同説明会で情報を得る
- OB・OG訪問や先輩からの情報を参考にする
「自分らしく働ける会社が、実はあなたのすぐそばにあるかもしれない」
就活を続ける中で、求人票を見て「これ、ちょっと興味あるかも」と思うことはあっても、なかなかピンとくる企業は少ないものです。そんなときに知ってほしいのが、一般のサイトには載っていない「非公開求人」。
①あなたの強みを見極め企業をマッチング
②ES添削から面接対策まですべて支援
③限定求人なので、競争率が低い
「ただ応募するだけじゃなく、自分にフィットする会社でスタートを切りたい」そんなあなたにぴったりのサービスです。まずは非公開求人に登録して、あなたらしい一歩を踏み出しましょう!
①就職四季報や統計資料を確認する
就職四季報や厚生労働省が発表している統計資料は、倍率を調べるうえで最も基礎となる情報源です。企業ごとの応募者数や採用人数が明確に示されているため、数字をもとに客観的に倍率を把握できます。
特に大手企業では倍率が数十倍に達することもあり、人気度の高さが如実に反映されます。
ただし、こうした資料は年度ごとに発行されるため、最新の動向を確認するには発行年を必ずチェックする必要があります。
さらに、複数年のデータを見比べることで、その企業が長期的に人気を集めているのか、一時的に注目されているのかといった傾向も見極められます。
信頼できる基礎データを把握することは、就活全体の方針を考えるうえで大きな助けになります。
②求人サイトや逆求人サイトを活用する
求人サイトや逆求人サイトも倍率を推測するのに役立ちます。求人サイトではエントリー数や応募締め切りまでのスピード感から、どの企業に学生が集中しているのかが読み取れるでしょう。
また、逆求人型サービスでは企業からのスカウト件数や面談打診の頻度によって、採用側がどれほど積極的かを知ることができます。
特にベンチャーや中堅企業は公式な倍率が公表されないことも多いため、こうしたサービスを利用することで相対的な難易度を判断できるのです。
ただし、サイトによっては掲載企業に偏りがあり、必ずしも市場全体を反映していない点に注意が必要です。
自分の専攻やスキルが企業にどれくらい求められているのかを把握する意味でも、有効な手段といえるでしょう。
③会社説明会や合同説明会で情報を得る
会社説明会や合同説明会は倍率を数値で知る場ではありませんが、実際の人気度を肌で感じられる絶好の機会です。
会場がすぐに満席になる企業や、事前予約が取れないほどの混雑ぶりは、その企業が高倍率である可能性を示しています。
また、採用担当者の話の中に「採用予定人数」や「過去の応募数」が出ることもあり、倍率を推測するヒントになるでしょう。
さらに、説明会では他の学生の質問や雰囲気からも志望度の高さを読み取れます。参加者が多い企業ほど、自分がアピールできる強みや差別化ポイントをしっかり準備する必要があります。
資料やネットの数値では得られない臨場感を体験できる点は大きな価値があるといえるでしょう。
④OB・OG訪問や先輩からの情報を参考にする
OB・OG訪問や大学の先輩からの情報は、就活生にとって最もリアルで具体的な情報源です。
実際にその企業の選考を経験した人からは、エントリー数や各面接での通過率など、統計資料には載らない細かな情報を聞くことができます。
たとえば「一次面接で半分に絞られた」「最終面接は10人に1人しか通らなかった」といった実感のこもった話は、倍率を肌で理解する上で非常に有益です。
ただし、体験談はあくまで個人の経験であるため、そのまま鵜呑みにしてしまうと誤解につながる場合があります。
現場のリアルな雰囲気を知ることは、就活に向けた心構えを整える意味でも大きな価値があります。
就活倍率が低い企業を見つける方法

就活倍率が低い企業を探すことは、効率的に内定に近づくための有効な戦略です。人気企業に集中すると競争率が高まり、努力しても結果につながらない場合があります。
しかし、就活倍率が低めの企業を狙えば、可能性を広げながら自分に合った環境を見つけやすいでしょう。ここでは倍率が低い企業を見つける具体的な方法を解説します。
- 地方企業や地域密着型の企業を探す
- 中小企業やベンチャーに注目する
- 人材不足の業界を検討する
- 就活エージェントに相談する
①地方企業や地域密着型の企業を探す
地方に本社を置く企業や、地域で長年事業を続けている会社は、首都圏の大手企業と比べて倍率が低くなる傾向があります。
就活生の多くが都市部の有名企業に応募するため、地方企業は競争が緩和されやすいのです。
例えば地方銀行、地元の鉄道会社、インフラ関連の企業は、安定性を備えつつ地域に密着しており、社会貢献度も高いでしょう。
さらに地方で働くと生活コストを抑えやすく、ゆとりある暮らしを実現できます。
就活倍率を活用する視点で考えると、都市部で高倍率となる人気企業ばかりに集中するのではなく、地方で堅実に経営を続ける企業に目を向けることで、選考を有利に進められるでしょう。
②中小企業やベンチャーに注目する
中小企業やベンチャーは、大手企業に比べて就活倍率が低めです。大手ほどの知名度はないものの、専門分野で強みを持つ会社や新しいビジネスモデルで成長している企業は数多く存在します。
特にベンチャーでは若手にも積極的に責任ある仕事を任せる傾向が強く、早くから実力を試せる環境が整っています。中小企業でも経営層との距離が近く、挑戦を歓迎する文化がある場合が多いです。
就活倍率を意識するなら、大手の高倍率を避けてこれらの企業を狙うことで内定獲得のチャンスを増やせるでしょう。加えて、若いうちから幅広い業務に携われるため、将来的なスキル形成にも直結します。
安定性を求める人には慎重さも必要ですが、自分の成長を優先する学生には魅力的な選択肢となるはずです。
③人材不足の業界を検討する
人材不足が深刻な業界は、就活倍率が低くなる傾向があります。
介護や福祉、建設業界、ITエンジニア職などは慢性的に人材が不足しており、採用枠が多いにもかかわらず応募者数が限られているのが現状です。
そのため、他業界と比べて内定を得やすい可能性が高いでしょう。もちろん業務の負担や専門スキル習得の大変さはありますが、社会に必要とされる役割を果たせる点は大きなやりがいです。
さらに、スキルを身につければ長期的に安定して働き続けられる強みもあります。人材不足業界を候補に入れることで、内定の可能性を広げながら社会的価値の高い仕事に就けるでしょう。
④就活エージェントに相談する
就活倍率の低い企業を探す際には、自分だけで調べるよりも就活エージェントを活用する方法が効果的です。
エージェントは企業から直接求人情報を得ており、一般には公開されていない非公開求人や、就活サイトに掲載されない優良企業を紹介してくれる場合があります。
これらの企業は応募者が少なく、倍率が低いケースも多いのが特徴です。
倍率だけで判断するのではなく、エージェントを通して効率的に情報を得ながら戦略的に動くことで、内定獲得に一歩近づけるはずです。
「有名企業でなくてもまずは内定を目指したい…」「隠れホワイト企業を見つけたい」方には、穴場求人も紹介しています。第一志望はすでに決まっているけど、他の業界や企業でも選考に参加したい方は非公開の穴場求人を確認してみてくださいね。キャリアアドバイザーがあなたに合う求人を紹介してくれますよ。
就活倍率を参考にする際の注意点

就活倍率は企業の人気や採用難易度を示す目安として役立ちますが、その数値だけを頼りにすると誤解を招くことがあります。
倍率の高さや低さには必ず理由があり、単純に「高倍率=優良企業」「低倍率=狙い目」とは言えません。ここでは、倍率を見るときに気をつけたい観点を整理し、冷静に判断できるように説明します。
- 倍率が高い企業=良い企業とは限らない
- 倍率が低いからといって必ず受かるわけではない
- 業界や企業研究を並行して行う
- インターンシップ参加の有無も考慮する
- エントリー数と採用数のバランスを確認する
- 複数の情報源を照合する
- 倍率よりも自分の適性を重視する
①倍率が高い企業=良い企業とは限らない
倍率が高い企業は知名度やブランド力が高く、多くの学生が憧れを持って志望します。しかし、高倍率だからといって自分に適した職場とは限りません。
実際に入社後に業務内容や社風に違和感を覚え、早期離職につながるケースもあります。
倍率を活用する際には「人気の理由」を分析し、自分がその環境でやりがいを感じられるかを確認することが重要です。倍率の高さは就活の参考情報であり、判断の一部にとどめると安心できるでしょう。
②倍率が低いからといって必ず受かるわけではない
倍率が低い企業は一見チャンスが大きいように思えますが、必ず内定が得られるわけではありません。
例えば採用地域が限定されていたり、専門的なスキルを求められていたりと、応募者の裾野が狭いケースもあります。
そのため競争相手が少なくても、自分が条件に合っていなければ不採用になるでしょう。倍率を活用する場合には「なぜ低いのか」を見極め、応募条件や仕事内容を丁寧に確認することが欠かせません。
油断せず準備を進めることが大切です。
③業界や企業研究を並行して行う
倍率の数字だけを追いかけると、自分の希望や将来像から外れる危険があります。
業界の動向や企業の特徴を調べながら倍率を見ることで、単なる数字ではなく「自分にとって意味のある指標」に変わります。
例えば、同じ高倍率でも成長産業の企業なのか、ブランドイメージが先行しているだけなのかで評価は違ってきます。就活倍率を活用するには、業界研究と組み合わせて情報を整理することが不可欠です。
研究を深めることで志望理由の説得力も増し、選考突破につながります。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
④インターンシップ参加の有無も考慮する
インターンシップは倍率に大きな影響を与える要因の1つです。特に大手企業では、インターン参加者を優遇して選考を進める仕組みを導入している場合が少なくありません。
そのため表面的な倍率だけを見て応募すると、実際にはインターン参加組に比べて不利になる可能性があります。
就活生にとっては、倍率を見る際に「インターン経験者がどの程度含まれているか」を考慮することが有効です。早い段階からインターンに参加しておけば、選考を優位に進められるでしょう。
⑤エントリー数と採用数のバランスを確認する
倍率は「エントリー数÷採用数」で算出されますが、実際には採用人数の少なさが数字を大きく見せているケースもあります。
例えば、採用枠が数人しかない企業では、数十人の応募があるだけで倍率が一気に跳ね上がります。就活倍率を活用するには、このような数字の背景を理解することが大切です。
単なる倍率に振り回されず、採用予定人数や応募者の層といった要素を合わせて確認することで、より正確に企業の選考状況を把握できます。
⑥複数の情報源を照合する
倍率に関するデータは調査方法や発表元によって異なることがあります。1つの情報だけを信じると、実際の状況とずれて判断を誤るかもしれません。
大学のキャリアセンターや就活サイト、OB・OG訪問など、多方面から情報を収集することが望ましいです。倍率を活用する際は「複数の情報を見比べる」意識を持つことで信頼性が高まります。
照合した結果をもとに戦略を立てれば、選考に向けてより現実的な準備ができるでしょう。
⑦倍率よりも自分の適性を重視する
最も重要なのは倍率そのものではなく、自分の適性や将来像に合った企業を見つけることです。高倍率の企業にこだわると視野が狭まり、自分に合った選択肢を逃してしまう可能性があります。
逆に倍率が低くても、自分の強みを活かせる職場であればキャリアの満足度は高まるでしょう。
倍率を活用する際には「参考情報」としてとどめ、最終判断は自己分析やキャリアビジョンを軸にすることが大切です。数字よりも自分の成長とやりがいを重視してください。
企業選びで意識すべきポイント

就活で企業を選ぶ際には、倍率の高さや人気度だけで判断するのは危険です。むしろ、自分に合った環境かどうかを見極めることが、内定獲得後の満足度や成長スピードに直結します。
ここでは、就活生が企業選びで重視すべき観点を整理しました。
これらを理解することで「倍率が高いから魅力的」「低いから狙いやすい」という単純な考えにとどまらず、より納得感のある選択につなげられるでしょう。
- 自分の適性や強みとの一致
- 将来のキャリア形成の可能性
- 働き方やワークライフバランス
- 企業文化や社風の理解
- 勤務地や転勤の有無
- 待遇や福利厚生の確認
- 成長性や安定性のある業界選び
①自分の適性や強みとの一致
企業を選ぶ上で最も大切なのは、自分の適性や強みがその企業の仕事内容と噛み合っているかどうかです。
なぜなら、得意分野を活かせる環境では成果を出しやすく、自信やモチベーションを長期的に維持できるからです。たとえば、論理的思考が得意ならコンサルや企画職で力を発揮できる可能性が高いでしょう。
逆に、人と話すことが好きなのに分析職を選ぶと、日々の仕事に違和感を覚えるかもしれません。就活倍率の高さにとらわれず、自己分析で得た強みを具体的に職務内容と照らし合わせることが重要です。
適性を意識して選んだ企業は、結果として早期離職の防止にもつながるでしょう。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
②将来のキャリア形成の可能性
就職先はゴールではなく、キャリアのスタート地点にすぎません。そのため、入社後にどんな成長機会を得られるのかを見極めることが欠かせません。
研修制度やジョブローテーション制度がある企業は、幅広い経験を積みながら自分の方向性を見極められます。
逆に、担当業務が限定的な企業では早く専門性を深められる反面、キャリアの幅が狭まる可能性もあるでしょう。さらに、挑戦を歓迎する社風かどうかも、若手にとっては大きな判断材料です。
倍率が高い企業ほど教育制度が整っている一方、競争も激しくなる傾向があります。倍率の数値に惑わされず、成長環境として自分に合うかを重視してください。
長期的なキャリア形成を意識して企業を選ぶことが、数年後の自分にとって最良の投資になるはずです。
③働き方やワークライフバランス
どれだけ人気企業で倍率が高くても、働き方が自分に合わなければ入社後に不満を抱くことになりかねません。残業時間や休日の取りやすさは生活の質に直結します。
最近ではリモートワークやフレックスタイムを導入している企業も増えており、柔軟な働き方を希望する学生にとって魅力的な条件でしょう。
特に就活生にとって見落としがちなのが「長期的に持続可能な働き方かどうか」です。ワークライフバランスが整っていれば、趣味や学びの時間を確保でき、心身の健康を維持できます。
就活倍率を確認する際も、数字の高低より「この企業でどんな働き方を実現できるのか」という視点を優先してください。
ライフスタイルに合った働き方を選ぶことが、長期的なパフォーマンス向上につながります。
④企業文化や社風の理解
社風の相性を見誤ると、どんなに倍率が低く内定を得やすい企業でも、早期離職につながる可能性があります。成果主義を掲げる企業では、自ら挑戦して成果を出す姿勢が求められます。
一方、協調性を重んじる企業では、チームワークを大切にする人が評価されやすいでしょう。
こうした違いは求人票や数値データからは見えにくく、OB・OG訪問やインターンシップで実際に社員と触れ合うことで理解できます。
就活倍率を参考にする際も「倍率が高い=人気があるから良い」ではなく、「なぜ人気があるのか」「その人気は自分に合う理由なのか」を考えることが大切です。
社風を理解して選ぶことで、入社後のギャップを減らし、自分にとって居心地の良い職場を見つけやすくなります。
⑤勤務地や転勤の有無
勤務地や転勤の条件は、就活生にとって見落とされがちですが、実際の生活に直結する重要な要素です。
希望勤務地で働けない場合、生活コストの増加や家族・友人との距離の変化がストレスにつながることもあります。
逆に、転勤を通じて幅広い経験を積むことを成長の機会と考える人にとっては、プラスに働く場合もあるでしょう。
近年は地域限定職を設ける企業も増えており、勤務地条件を事前に確認しておくことが安心につながります。
単なる数字ではなく、自分のライフプランに合った働き方と結び付けて倍率を読み解くことが大切です。
⑥待遇や福利厚生の確認
給与や福利厚生は、多くの就活生が最初に気にする要素でしょう。
初任給や賞与の金額だけでなく、昇給制度や住宅手当、健康保険、退職金制度まで確認することで、入社後の生活の安定度を判断できます。
さらに、近年では育児休暇や介護休暇、在宅勤務支援など、働きやすさを支える制度も企業の魅力の一部になっています。
福利厚生が整った企業は倍率が高くなる傾向がありますが、それだけ人気がある理由が明確とも言えます。ただし待遇面だけを基準に選ぶと、やりがいを感じられない可能性もあります。
就活倍率を参考にする際には「待遇が良いから倍率が高い」という事実を押さえつつ、自分の価値観や将来設計に合致しているかどうかを冷静に見極めてください。
⑦成長性や安定性のある業界選び
個別の企業だけでなく、業界全体の将来性を見極めることも欠かせません。需要が高まる業界は人材育成にも積極的で、挑戦できる機会が豊富です。
反対に、人口減少や景気変動に左右されやすい業界は倍率が低くても将来の安定性に不安を抱えるケースもあるでしょう。
就活倍率を「今の人気度」として理解しつつ、業界の成長性や安定性を軸に選ぶことが大切です。
倍率が高いから挑戦を避けるのではなく、未来のキャリアを考えたうえで挑戦する判断ができると、入社後に納得感のあるキャリアを築きやすくなります。
就活倍率を理解して活用するために

就活倍率は、就活の難易度や企業人気を示す重要な指標ですが、単に倍率が高い・低いという数値だけで判断するのは危険です。
実際には、就職倍率・内定倍率・求人倍率といった複数の指標を組み合わせ、近年の傾向や業界ごとの違いを把握することが求められます。
特に、食品・商社・広告など高倍率企業は魅力が大きい一方で狭き門であり、地方企業や中小企業など低倍率の企業には思わぬキャリアチャンスが隠れています。
したがって、就活倍率を調べる際には統計や説明会、OB・OG訪問など多角的な情報源を活用し、自分の適性や将来のキャリアとの一致を優先すべきです。
倍率はあくまで判断材料の一つであり、自分に合う企業を見極めて選択する姿勢こそが、最終的な内定獲得と納得感ある就職につながります。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。