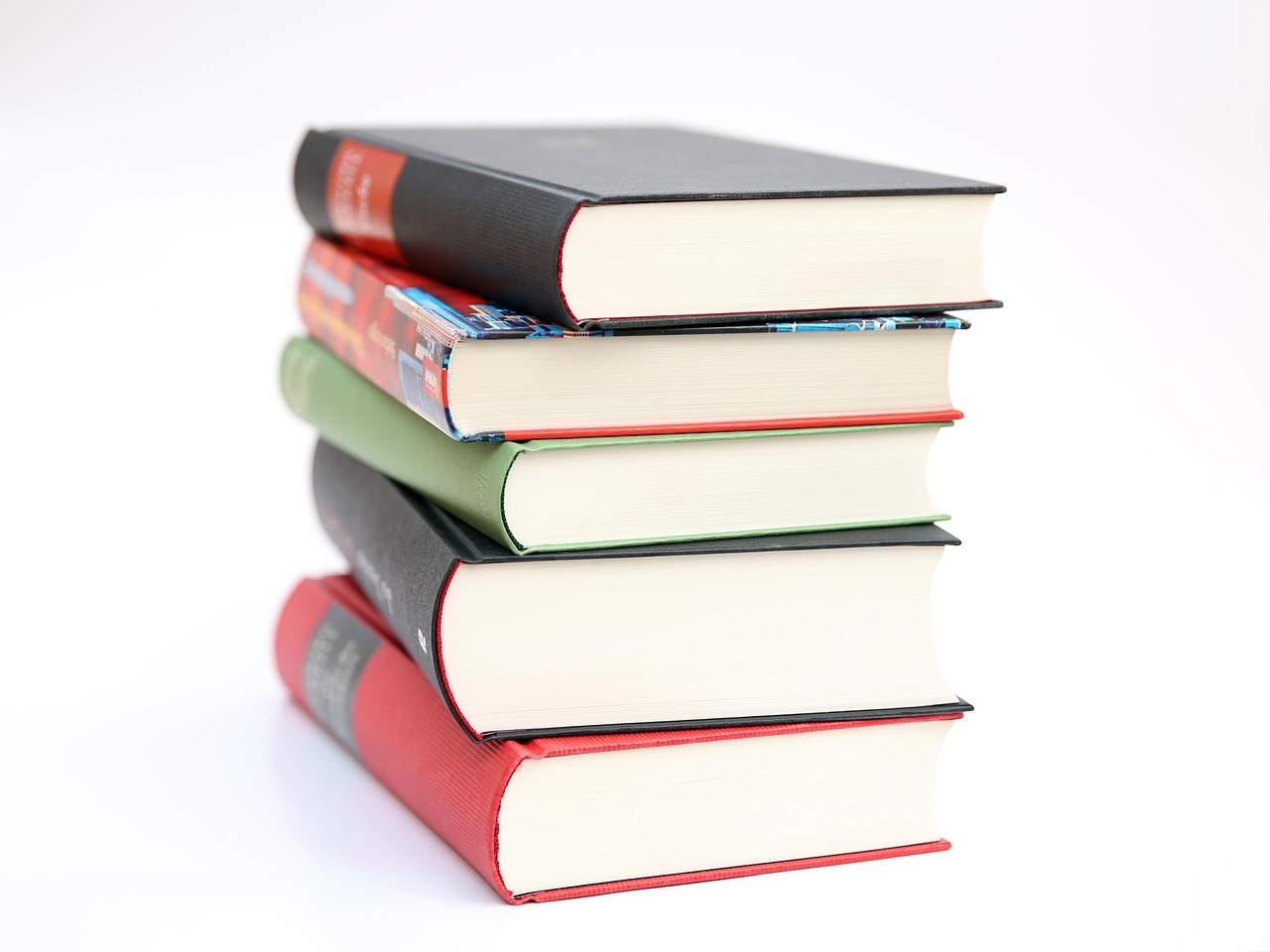編集者の平均年収はいくら?仕事内容・将来性・やりがいを徹底解説
「本づくりに関わりたい」「文章やコンテンツを通して人に伝えたい」そんな思いから、編集者という仕事に憧れる人も多いのではないでしょうか。
編集者は、書籍・雑誌・Webメディア・広告など、さまざまな情報発信の現場で企画から完成までを支える役割を担っています。
本記事では、編集者の仕事内容・年収・必要なスキル・向いている人の特徴・将来性までをわかりやすく解説します。
未経験から編集の道を目指したい方や、今後にキャリアについて考えている方は、ぜひ参考にしてください。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
編集者とは?

編集者とは、書籍や雑誌、Web記事などのコンテンツを企画し、読者に伝わる形に仕上げる仕事です。
情報を整理して「どうすれば面白く、正確に伝わるか」を考えるクリエイティブな役割を担っています。
就活生の中には「編集者は文章を書く人」と思っている方も多いかもしれませんが、実際には多くの人と関わりながら作品をつくるプロデューサー的な存在です。
編集者は、自分が考えた企画が形になり、多くの人に読まれる喜びを味わえる一方で、締め切りや責任の重さといったプレッシャーも大きいでしょう。
それでも、編集者として培った経験は他業界でも応用が利く貴重な力です。物事を構成し、人に伝える力を伸ばしたい方にとって、編集者は大きなやりがいを感じられる仕事ですよ。
編集者の平均年収

編集者の平均年収は、働く業界や企業の規模、経験年数によって大きく異なります。厚生労働省が公表しているデータによると、「記者・編集者等」に分類される職種の所定内給与は月額およそ24万7,000円です。
これを年収に換算すると、賞与を含めておよそ300〜400万円台が新卒から中堅レベルの相場と考えられます。初任給からの昇給幅は企業によって異なりますが、経験を重ねることで徐々に収入は上がっていく傾向にあります。
一方、大手出版社では高水準の給与が見られます。講談社では編集職の平均年収が約1,474万円とされ、編集長クラスや管理職では非常に高い収入が得られるようです。
集英社でも入社10年目で800〜1,200万円という水準が報告されており、成果とポジション次第で収入が大きく変わることがわかります。
一方で、中堅出版社や中小企業の編集職では平均年収が400〜500万円台となるケースも少なくありません。たとえば、枻出版社の編集職では平均年収が431万円、産業編集センターでは474万円と報告されています。
これらの数値を踏まえると、編集者全体の平均年収はおおむね400〜700万円前後が目安といえるでしょう。ただし、担当するジャンルやメディアの種類によっても年収差は生まれますよ。
引用:
- 雑誌編集者 – 職業情報提供サイト(job tag)
- 講談社 編集職・年収データ(OpenWork)
- 集英社 編集職・年収事例(OpenWork)
- 枻出版社 編集年収データ(OpenWork)
- 産業編集センター 年収事例(OpenWork)
編集者の仕事内容

編集者の仕事は、コンテンツを生み出すための全体の流れを管理することです。単に原稿をまとめるだけでなく、企画から取材、編集、デザイン、公開後の分析まで、制作のあらゆる工程に関わります。
ここでは、編集者がどのようにして企画を立て、完成まで導くのかを具体的に見ていきましょう。
- 企画立案とコンテンツ企画の流れ
- 取材・原稿依頼・ライターとのやり取り
- 校正・校閲・クオリティチェック
- デザイン・レイアウトのディレクション
- 進行管理とスケジュール調整
- 出版後・公開後の効果分析と改善提案
①企画立案とコンテンツ企画の流れ
企画立案は編集者の仕事の中でも、最もクリエイティブであり責任の重い工程です。編集者はまず、読者が求める情報をリサーチし、社会の動きや季節のトレンドを分析します。
そのうえで「誰に」「どんなテーマで」「どう伝えるか」を明確にし、全体の方向性を設計します。特に出版・Webメディアでは、時期や読者層に合ったテーマ選定が成果を左右します。
企画段階では、アイデア出しのほか、競合メディアの調査やSEOキーワード分析なども行います。さらに、記事構成の大枠を作り、取材対象者や執筆者の選定も進めます。
この時点でどれだけ丁寧に設計できるかが、後の編集工程をスムーズに進められるかを決める鍵になるでしょう。
②取材・原稿依頼・ライターとのやり取り
取材や原稿依頼は、編集者が最も現場で活躍する実践的な仕事です。まずは取材の目的や構成を整理し、ライターやカメラマンに明確な指示を出します。
どんな切り口で伝えるのか、どのような雰囲気の写真が必要なのかなど、細部までイメージを共有することが重要です。また、ライターとの信頼関係づくりも大切な役割です。
良い編集者は、ライターの個性や得意分野を理解し、その力を最大限に引き出すディレクションを行います。納品された原稿を確認し、内容が読者に分かりやすく、構成が整っているかをチェックします。
予定外のトラブルが起きたときも、冷静に方向性を再調整し、最良の結果へ導くのが編集者の腕の見せどころです。コミュニケーション能力と柔軟性が、質の高いコンテンツを支える基盤となります。
③校正・校閲・クオリティチェック
原稿が出そろったら、次は「校正・校閲」の工程に入ります。ここでは文章の誤字脱字だけでなく、事実確認やデータの整合性、表現の適切さなどを徹底的に確認します。
単なるチェック作業ではなく、読者の信頼を守るための重要なプロセスです。校閲では、引用や統計データの出典確認、人物名・企業名など固有名詞の正確性も検証します。
誤りを放置すれば、媒体全体の信頼を損なう可能性があります。そのため、複数人でのダブルチェック体制を取ることも多いです。また、文章のリズムや構成を整えるのも編集者の仕事ですよ。
④デザイン・レイアウトのディレクション
デザインやレイアウトは、コンテンツの印象を決める大切な要素です。どんなに良い内容でも、見づらい誌面やWebページでは読まれません。
編集者はデザイナーと協力し、読者の視線の流れや興味を考慮しながらページ構成を調整します。雑誌なら、タイトルのフォントや写真の配置、色使いなどを細かく指示します。
Webの場合は、スマートフォンでの見やすさやクリック率を考えたデザイン設計が必要です。特に若年層向けの媒体では、ビジュアルの魅力がアクセス数を左右することもあります。
編集者はデザインの専門家ではありませんが、「どうすれば読者が読み進めたくなるか」を考え、全体をコントロールします。
デザインの段階で情報の整理やメリハリを意識することで、記事の完成度をさらに高められるでしょう。
⑤進行管理とスケジュール調整
進行管理は、編集者の段取り力が問われる重要な仕事です。複数の関係者が関わる中で、納期を守りながら制作を進めるには、細かなスケジュール設計と調整力が必要です。
特に出版やWeb更新は期限が厳しく、遅れが他の工程に連鎖することもあります。編集者は全体の進行を把握し、関係者との連絡を密に取りながらプロジェクトを管理します。
タスク管理ツールやスプレッドシートを活用し、進捗を可視化することも多いです。また、トラブルが発生した場合には迅速に判断し、スケジュールの再構築を行います。
優れた進行管理ができる編集者は、信頼を得やすく次の仕事にもつながります。単に予定を守るだけでなく、チーム全体が気持ちよく働ける環境をつくることも、編集者の大切な役割です。
⑥出版後・公開後の効果分析と改善提案
編集者の仕事は、コンテンツを公開した時点で終わりではありません。むしろ本当の勝負はここからです。公開後の反応を数値やデータで分析し、次の企画に反映させることが、継続的な成長につながります。
Webメディアであれば、PV(閲覧数)や読者の滞在時間、SNSでのシェア数などを確認します。紙媒体では、売上や読者アンケートの結果から反響を分析します。
こうしたデータをもとに、どの部分が読者の興味を引いたのか、改善すべき点はどこかを見極めます。そして、結果を踏まえて次の企画で新たな施策を試すことで、より効果的な編集方針を作り上げます。
分析から改善までのサイクルを回せる編集者は、長期的に信頼される存在となるでしょう。コンテンツ制作を継続的に育てる視点が、プロフェッショナルとしての成長を支えるのです。
編集者のやりがい

編集者の仕事には、他の職種では味わえないやりがいが数多くあります。自分の企画が世に出て多くの人に届く喜びや、読者の反応を直接感じられる瞬間は、この仕事ならではの魅力です。
ここでは、編集者が感じる代表的なやりがいを具体的に紹介します。
- 自分の企画が形になる達成感
- 読者の反応を直接感じられる喜び
- 多様な人と関われる魅力
- 社会的影響力のある仕事である点
- スキルアップ・成長を実感できる環境
- クリエイティブな発想を活かせる場面
①自分の企画が形になる達成感
編集者にとって最大のやりがいは、自分の考えた企画が実際に形になることです。
ゼロからテーマを考え、取材を重ね、原稿を磨き上げたコンテンツが読者に届いたときの達成感は、何にも代えがたいものがあります。
自分の発想や切り口が記事や本として形になると、「自分の仕事が社会に影響を与えている」と実感できるでしょう。
特に初めて担当した企画が多くの人に読まれたり、SNSで話題になったりしたときは、努力が報われる瞬間でしょう。
②読者の反応を直接感じられる喜び
編集者は、自分が手がけたコンテンツに対する読者の反応を直接見れます。書籍であればレビューや感想、WebメディアならSNSでのコメントやアクセス数などがすぐに目に入ります。
読者の「この企画を読んでよかった」「ためになった」といった声は、何よりの励みです。自分の仕事が人の行動や考え方を変えるきっかけになったとき、編集者としての使命感を感じるでしょう。
もちろん、時には厳しい意見をもらうことも。しかし、その声を次の改善に活かすことで、より良い企画を生み出せるようになりますよ。
③多様な人と関われる魅力
編集者の仕事は、さまざまな職業の人と協力して進めることが特徴です。ライター、カメラマン、デザイナー、取材対象者など、毎回違う人と出会い、新しい知識や考え方に触れられます。
この多様な人脈こそが、編集者としての財産になります。異なる分野の専門家と関わることで、自分の視野が広がり、企画の発想も豊かになります。
また、取材を通して普段接することのない業界や文化に触れるのも、この仕事の魅力です。人と関わる機会が多い分、コミュニケーション力や調整力も自然に身につきます。
人との出会いを楽しめる人にとって、編集者という職業は非常に刺激的な環境といえるでしょう。
④社会的影響力のある仕事である点
編集者は情報を発信する立場として、社会に影響を与える存在です。メディアを通して多くの人に新しい価値観や知識を届けることで、世の中の流れを変えることもあります。
たとえば、環境問題や働き方改革など、社会課題を扱う企画では、読者の意識を変えるきっかけをつくれます。言葉や構成の工夫ひとつで、読者の行動や感情を動かせるのです。
この責任の重さが、同時にやりがいにもなります。単なる情報伝達者ではなく、社会にメッセージを届ける職業としての誇りを持てるのが、編集者という仕事の本質でしょう。
⑤スキルアップ・成長を実感できる環境
編集者は日々新しい情報に触れ、常に学び続ける仕事です。記事や書籍の企画を通じて、自然とマーケティング・リサーチ・ライティング・ディレクションなど多様なスキルを身につけられます。
1つのテーマを深掘りするたびに、新しい分野の知識が増え、自分の成長を実感できるでしょう。また、企画から制作、発信までを一貫して担当するため、プロジェクトマネジメント能力も磨かれます。
このように、編集者は常に変化の中で成長できる環境にいます。努力が結果として可視化されやすく、自分の成長が作品として世に残る点も大きな魅力です。
⑥クリエイティブな発想を活かせる場面
編集者の仕事は、常に「新しいものを生み出す」ことと向き合う創造的な仕事です。企画を立てるときも、タイトルを考えるときも、どんな伝え方なら読者の心を動かせるかを考え抜きます。
柔軟な発想や独自の視点が求められるため、アイデアを形にすることが好きな人には理想的な環境です。編集者は単なる裏方ではなく、企画の立案者であり、チームを導くクリエイターでもあります。
自分の発想が作品として社会に影響を与える瞬間には、大きな達成感があるでしょう。創造的な挑戦を続けたい人にとって、編集という仕事は最高の舞台です。
編集者の大変なこと

編集者はやりがいの大きい仕事である一方、非常にハードな一面もあります。
締め切りに追われる日々や、ミスの許されない責任、複数案件を同時にこなす負荷など、現場では常に緊張感を持って働く必要があります。
ここでは、編集者が直面する主な大変さについて具体的に見ていきましょう。
- スケジュール管理と納期プレッシャー
- ミスが許されない責任の重さ
- 複数案件を同時に進行する忙しさ
- コミュニケーション調整の難しさ
- トレンド変化への継続的なキャッチアップ
- 精神的ストレスと長時間労働の現実
①スケジュール管理と納期プレッシャー
編集者の仕事では、常に複数の締め切りを同時に管理する必要があります。企画や取材、原稿の確認、校正、デザイン指示など、すべての工程を計画的に進めなければ、最終的な納期に間に合いません。
1つの遅れが全体に影響するため、綿密なスケジュール設計が欠かせません。納期前は特にプレッシャーが強く、徹夜作業になることも珍しくありません。
予期せぬ修正依頼やトラブルが発生した場合でも、冷静に対応しながら全体の進行を調整する必要があります。この緊張感の中で結果を出す力こそが、編集者の真価です。
計画的に物事を進めるスキルと、突発的な問題に柔軟に対応するバランス感覚が求められます。
②ミスが許されない責任の重さ
編集者は、媒体の最終責任を担う存在です。記事や書籍に誤字や事実誤認があると、信頼を失うだけでなく、企業や著者に迷惑をかけてしまう可能性もあります。
そのため、どんな小さなミスも見逃さない注意力が必要です。特に情報の正確性が重視される分野では、確認作業に多くの時間を費やします。
引用や統計データ、人物名などを何度も確認する地道な作業が続くでしょう。一見地味な作業に思えるかもしれませんが、この積み重ねが媒体の品質を支えています。
編集者にとって「責任を持つ」ということは、信頼を守ることそのものなのです。
③複数案件を同時に進行する忙しさ
多くの編集者は、複数の企画を同時に担当しています。1本の記事を仕上げながら次の企画を立ち上げたり、他の案件の校正を進めたりと、常に並行作業が発生します。
スケジュールが重なる時期は、頭の切り替えが重要になります。異なるテーマやトーンの記事を同時に扱うため、集中力と判断力を維持することが求められます。
このような環境は忙しい反面、マルチタスク能力を鍛える絶好の機会でもあります。限られた時間の中で成果を出すスキルを身につければ、どの業界でも通用する実践的な力を得られるでしょう。
④コミュニケーション調整の難しさ
編集者は、ライター・カメラマン・デザイナー・クライアントなど、多くの関係者の間に立って仕事を進めます。各方面の意見をまとめ、全体の方向性を調整するのは簡単ではありません。
時には、意見の食い違いや納期のズレに悩まされることもあります。しかし、ここで大切なのは「相手の立場を理解すること」です。
誰かを優先するのではなく、全体の目的を見据えて最適な判断を下すことが編集者の役割です。難しい調整を乗り越えるたびに、対人スキルが磨かれ、人間的な成長を実感できるでしょう。
円滑なコミュニケーションは、編集者にとって最大の武器です。
⑤トレンド変化への継続的なキャッチアップ
メディア業界は変化のスピードが非常に速く、常に新しい情報やトレンドを追いかけなければなりません。特にWeb編集では、SEO対策やSNSの動向など、数か月単位でルールやアルゴリズムが変わります。
最新の情報をキャッチアップし続けるには、日々の学習が欠かせません。ニュースや他媒体の分析、読者の反応チェックなどを習慣化することが大切です。
変化を面倒に感じる人もいるかもしれませんが、トレンドを追うことは編集者にとって刺激であり、成長のチャンスです。
常に新しい視点を持ち続けることで、より魅力的なコンテンツを生み出せるようになります。
⑥精神的ストレスと長時間労働の現実
締め切りやトラブル対応に追われる編集者の仕事は、精神的にも肉体的にも負担が大きい職種です。特に繁忙期には、休日出勤や夜遅くまでの作業が続くこともあります。
納期に間に合わせるためにプレッシャーを抱えながら作業を進めるため、ストレス管理が非常に重要になります。短期間で高品質な成果を求められる環境では、自分のペースを保つ工夫が必要です。
一方で、最近は働き方改革が進み、リモート編集やフレックスタイム制を導入する企業も増えています。
適切に休息を取り、チームで助け合うことで、より持続的に働ける編集スタイルを築けるでしょう。
編集者に必要なスキル

編集者として活躍するためには、幅広いスキルが求められます。単に文章を扱うだけでなく、企画を立て、関係者をまとめ、情報を的確に発信する総合的な力が必要です。
ここでは、編集者が身につけるべき代表的なスキルを詳しく紹介します。
- 企画力・構成力
- 文章力・校正力
- リサーチ力・情報収集力
- コミュニケーション能力
- スケジュール管理・ディレクション力
- マーケティング・データ分析力
①企画力・構成力
編集者の仕事の根幹となるのが企画力と構成力です。どんなに文章が上手でも、読者の心を動かすテーマを選べなければ良いコンテンツは生まれません。
読者のニーズを正確に把握し、「今、何を求めているか」を見極める洞察力が求められます。また、企画を形にするには全体の構成を考える力が欠かせません。
情報をどの順番で、どのように提示すれば最も効果的に伝わるのかを設計する必要があります。特にWeb編集では、見出し構成やSEOを意識した文章設計も重要です。
優れた編集者は、発想力だけでなく論理的思考力を兼ね備えています。企画と構成、この2つの力がバランスよく磨かれてこそ、読まれるコンテンツを生み出せるのです。
②文章力・校正力
編集者は文章を扱うプロフェッショナルである以上、文章力と校正力は必須スキルです。ライターが書いた原稿をそのまま掲載するのではなく、読者に伝わりやすいように修正・調整するのが編集者の役割です。
文章力とは、単に文法が正しいことではありません。読者が「読みやすい」「理解しやすい」と感じるように構成や語彙を調整する力のことです。
一方、校正力はミスを防ぎ、表現の正確さを保つための重要な技術です。また、最近ではWebメディア特有のライティングルールも増えています。
文字装飾や改行のタイミングなど、読者の閲覧環境を考えた表現を意識することで、より信頼される記事を仕上げられるでしょう。
③リサーチ力・情報収集力
良いコンテンツを作るためには、正確で深い情報収集が欠かせません。編集者は取材対象を選ぶ段階から、信頼できる情報源を見極め、事実を裏付けるデータを集める必要があります。
リサーチ力とは、単に調べるだけでなく「情報の真偽を見抜く力」でもあります。インターネット上の情報には誤りも多いため、複数の信頼できるソースを照合する姿勢が求められます。
さらに、情報を整理・分析し、分かりやすく構成する力も重要です。最新のトレンドを素早くキャッチできる編集者ほど、タイムリーで価値のある記事を生み出せます。
④コミュニケーション能力
編集者は一人で仕事を完結できる職業ではありません。ライター、カメラマン、デザイナー、クライアントなど、多くの人と連携しながらコンテンツを作り上げます。
そのため、明確に意図を伝え、相手の意見を引き出すコミュニケーション能力が求められます。特に取材や打ち合わせの場では、相手との信頼関係づくりが大切です。
柔らかい言葉選びや丁寧な対応を意識することで、良い情報を引き出せることもあります。また、複数の関係者の意見を調整するバランス感覚も重要です。
人をまとめる力を磨くことで、よりスムーズにチームを動かせる編集者になれるでしょう。
⑤スケジュール管理・ディレクション力
編集者は、複数の企画や制作工程を同時に進めるため、スケジュール管理とディレクション力が欠かせません。
取材日程の調整、原稿の締め切り、デザイン入稿の確認など、細かい段取りを正確に把握する必要があります。
進行が滞ると全体の納期に影響するため、トラブルを防ぐための事前準備と柔軟な対応力が求められます。また、チームメンバーの作業状況を把握し、必要に応じてフォローすることも編集者の役割です。
プロジェクトを「俯瞰して見る力」があれば、無理のないスケジュールで高品質な成果を出せます。ディレクション力は経験を重ねるほど磨かれるスキルです。
⑥マーケティング・データ分析力
現代の編集者には、マーケティング思考とデータ分析力も不可欠です。どんなに良い記事でも、読まれなければ意味がありません。
読者層を分析し、ニーズに合ったテーマやキーワードを設定する力が求められます。
Webメディアの場合、アクセス解析ツールやSNSのデータを活用し、どんな記事が読まれているのか、どの部分で離脱しているのかを分析します。
こうした数値をもとに改善を重ねることで、より効果的なコンテンツを制作できるようになります。
マーケティング視点を持つことで、単なる「情報発信者」ではなく、「結果を出せる編集者」へと成長できます。データに基づく判断ができる編集者は、企業や読者から高く評価されるでしょう。
編集者に向いている人の特徴

編集者はクリエイティブでやりがいのある仕事ですが、誰にでも向いているわけではありません。常に多方面の知識や人との関わりが求められるため、向き不向きがはっきりと出る職種です。
ここでは、編集者に向いている人の特徴を6つの視点から紹介します。
- 好奇心が強く学び続けられる人
- 責任感があり細部にこだわれる人
- チームワークと協調性を大切にできる人
- 柔軟に対応できる思考を持つ人
- 情報発信や表現が好きな人
- 読者視点で考えられる人
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①好奇心が強く学び続けられる人
編集者に最も大切なのは、常に新しいことに興味を持ち、学び続ける姿勢です。社会の変化やトレンドを敏感にキャッチできる人ほど、読者の関心を引く企画を生み出せます。
たとえば、日常のニュースや流行から「なぜ話題になっているのか」を掘り下げる力がある人は、自然と企画のアイデアが浮かびやすいでしょう。編集者の仕事は常に情報との戦いです。
新しいテーマに挑戦することを楽しめる好奇心旺盛な人は、変化の多い編集業界でも柔軟に成長し続けられます。
②責任感があり細部にこだわれる人
編集者は、コンテンツの最終責任を負う仕事です。誤字脱字ひとつでも信頼を損ねる可能性があるため、細部にまで目を配る注意力が求められます。
また、制作過程では多くの人が関わるため、スケジュールの遅延や内容の修正など、責任を持って最後までやり遂げる姿勢が不可欠です。
細かい部分に気づける人ほど、記事や書籍の完成度を高められます。責任感と丁寧さを持つ人は、編集者として確実に評価されるでしょう。
③チームワークと協調性を大切にできる人
編集者は一人で仕事を完結させることがほとんどありません。ライターやデザイナー、カメラマン、印刷会社など、多くの人と協力してコンテンツを作ります。
チームの意見を尊重しながら、自分の考えも適切に伝えられる人は、スムーズにプロジェクトを進められます。相手の立場を理解し、感謝を忘れずに働けることが大切です。
人との関わりを楽しめる人は、編集現場で信頼を得やすく、長く活躍できる傾向があります。協調性とコミュニケーション力は、編集者にとって欠かせない資質です。
④柔軟に対応できる思考を持つ人
編集の現場では、予定通りに進まないことが日常茶飯事です。取材の延期、デザインの修正、掲載中止など、突発的な変更が頻繁に起こります。
そんな時に冷静に判断し、最善策を見つけられる人が編集者に向いています。完璧主義よりも「今できる最良の形を作る」柔軟な思考が求められます。
状況に応じて臨機応変に対応できる人は、どんな現場でも重宝されます。変化を前向きに受け止める姿勢が、成長と信頼を生むでしょう。
⑤情報発信や表現が好きな人
「誰かに伝えたい」という思いを持つ人は、編集者にぴったりです。文章やビジュアルを通じて自分の考えを形にする楽しさを感じられる人は、この仕事を長く続けられます。
編集者は表舞台に立つわけではありませんが、裏方として作品を支える誇りがあります。読者に届く瞬間の喜びは、他の職種では味わえない特別なものです。
情報を発信することにやりがいを感じる人は、編集という仕事で大きな満足感を得られるでしょう。
⑥読者視点で考えられる人
編集者に求められる最も重要な素質の1つが、「読者目線で考える力」です。自分の好みではなく、読者が本当に求めている情報を見極めることが成功の鍵になります。
読者の悩みや関心を理解し、「どんな内容なら心に響くか」を想像できる人は、質の高い企画を作り出せます。アンケートやアクセスデータを分析し、読者ニーズを把握することも大切です。
常に相手の立場に立って考えられる人こそ、読まれるコンテンツを作れる編集者といえるでしょう。
編集者におすすめの資格

編集者になるために必ず資格が必要というわけではありませんが、スキルを客観的に証明できる資格を持っていると、採用や転職で有利に働きます。
特に未経験から編集者を目指す場合、基礎知識や実務スキルを補う手段として資格は効果的です。ここでは、編集者におすすめの代表的な資格を紹介します。
- 校正技能検定
- マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)
- アドビ認定プロフェッショナル(Adobe Certified Professional)
- Webライティング能力検定
- 知的財産管理技能検定 3級
- 出版編集技能検定
①校正技能検定
「校正技能検定」は、文章の誤りを正確に見抜く力を証明できる資格です。日本エディタースクールが実施しており、出版・広告業界では認知度が高い検定です。
編集者は日常的に原稿を確認するため、誤字脱字や表記揺れを見逃さない力が求められます。この検定では、校正記号や文法、表記ルールなどを体系的に学べます。
正確性を重視する出版系の職場では評価されやすく、編集アシスタントや校閲職を目指す人にもおすすめです。
②マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)
「MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)」は、WordやExcel、PowerPointといったOfficeソフトの操作スキルを証明する資格です。
編集業務では、原稿整理やスケジュール管理、資料作成などにOfficeソフトを使う機会が多くあります。
特にExcelでの進行管理やWordでの体裁調整、PowerPointでの企画書作成など、効率的に作業を進めるために役立ちます。
基本操作をスムーズにこなせることは、チーム内の信頼にもつながります。未経験者が職場に馴染むための「即戦力スキル」として取得しておくと良いでしょう。
③アドビ認定プロフェッショナル(Adobe Certified Professional)
「アドビ認定プロフェッショナル(旧Adobe Certified Associate)」は、PhotoshopやIllustratorなど、デザイン系ソフトの操作スキルを認定する資格です。
編集者がデザインデータを扱う場面では、基本的な操作を理解しておくとコミュニケーションがスムーズになります。デザイナーに修正を依頼するときや、サンプルを自分で作成する際にも役立ちます。
特にWeb編集者や雑誌編集者にとっては、ビジュアルの理解度を高める大きな武器になります。編集とデザインの両方に精通している人は、職場で重宝されやすい存在です。
④Webライティング能力検定
「Webライティング能力検定」は、インターネット上での文章作成に特化した資格です。SEOや構成力、著作権の知識など、Webメディアに必要なスキルを幅広く学べます。
Web編集者として活躍したい人に特におすすめで、検定を通じて「読まれる文章」の書き方を体系的に理解できるのが特徴です。
資格取得によって、ライターとのやり取りや構成提案の質も向上します。Web業界を目指す就活生や転職希望者にとって、実践的な一歩となるでしょう。
⑤知的財産管理技能検定 3級
「知的財産管理技能検定」は、著作権や商標権など、コンテンツを扱ううえで欠かせない知識を学べる国家資格です。特に3級は基礎的な内容で、編集者を目指す人にも挑戦しやすいレベルです。
編集者は日々、写真や文章、イラストなど多様な素材を扱うため、権利関係の理解が不可欠です。この資格を持っていると、著作権侵害などのトラブルを未然に防ぐ判断力が身につきます。
法的リスクを理解している編集者は、クライアントや上司からの信頼も得やすくなります。
⑥出版編集技能検定
「出版編集技能検定」は、出版業界における編集実務の知識を評価する検定で、公益社団法人日本書籍出版協会が実施しています。編集の基礎から実践的な流れまで、体系的に学べる点が特徴です。
この検定では、企画立案、原稿整理、校正、装丁、印刷まで、編集者に必要な一連の知識を幅広くカバーしています。
業界全体の理解を深めたい人や、出版社・編集プロダクションへの就職を目指す人に最適です。
資格取得を通じて、実務で役立つ知識を身につけられるだけでなく、「出版の専門家」としての信頼性を高められます。
編集者になるには?未経験からのなり方とステップ

編集者は経験や専門知識が重視される職業ですが、未経験からでも挑戦できます。大切なのは、編集という仕事の流れを理解し、必要なスキルを積み重ねていくことです。
ここでは、未経験から編集者を目指すための具体的なステップを紹介します。
- 編集者の仕事を理解する
- 業界研究をして自分に合う分野を見つける
- 必要なスキルを身につける
- ポートフォリオを作成する
- 未経験可の求人やアシスタント職に応募する
- 実務経験を積んでスキルを磨く
- 編集実績を活かしてキャリアアップする
①編集者の仕事を理解する
まずは、編集者がどんな役割を担っているかを知ることから始めましょう。編集者は、文章を書く人ではなく、企画・取材・構成・校正・発信までを統括する「コンテンツのプロデューサー」です。
出版社やWebメディア、広告代理店など、働く業界によって仕事内容は異なります。本や記事だけでなく、SNS投稿や企業のオウンドメディア運営を行う編集者も増えています。
未経験者は、まず編集者の業務フローを理解し、自分がどの分野に興味を持てるかを明確にすることが大切です。これが次のキャリア選択の基盤になります。
②業界研究をして自分に合う分野を見つける
編集と一口にいっても、出版・Web・広告・映像など活躍の場は多岐にわたります。自分がどのジャンルに関わりたいかを明確にすることが、キャリア形成の第一歩です。
たとえば、活字が好きなら書籍編集、流行を発信したいならWeb編集、クリエイティブな制作現場に興味があるなら雑誌編集が向いています。
業界研究を通じて、企業の特徴や求められるスキルを把握しておきましょう。興味のある分野が見つかれば、企業説明会やインターンに参加し、現場の空気感を掴むのがおすすめです。
自分に合った環境を選ぶことで、モチベーションを維持しやすくなります。
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
③必要なスキルを身につける
未経験者が編集者を目指すうえで、まず身につけたいのは「文章力」「情報収集力」「構成力」です。読者が理解しやすい文章を書く練習を重ね、正確で魅力的な情報発信ができるようにしましょう。
また、取材や打ち合わせなどで関係者とやり取りするため、コミュニケーション能力も重要です。加えて、基本的なPCスキル(Word・Excel・Photoshopなど)を習得しておくと即戦力として評価されます。
資格を取得したい場合は、校正技能検定やWebライティング検定なども有効です。スキルの証明になるだけでなく、実務の理解にもつながります。
④ポートフォリオを作成する
採用担当者に自分の実力を示すためには、ポートフォリオ(制作実績集)が効果的です。過去に執筆した記事、ブログ投稿、学校で作成した企画書などをまとめて、自分の「編集力」を見せましょう。
特にWeb業界では、ポートフォリオサイトやnoteなどを活用してオンラインで公開するのがおすすめです。内容はテーマごとに整理し、見やすく構成することを意識してください。
ポートフォリオは単なる作品集ではなく、「自分が何を考え、どう伝えたいか」を表現する場です。継続的に更新し、自分の成長をアピールできる形にしましょう。
⑤未経験可の求人やアシスタント職に応募する
未経験から編集者を目指す場合、まずはアシスタント職や制作進行など、編集に近いポジションから経験を積むのが現実的です。
出版プロダクションやWebメディア運営会社では、初心者を歓迎する求人も少なくありません。アシスタントとして働くことで、実際の編集現場を学び、プロの仕事を間近で見れます。
最初は地味な作業が多いかもしれませんが、基礎を身につける大切な期間です。経験を積むうちに、取材や校正などの実務も任されるようになり、ステップアップの道が開けます。
「自分らしく働ける会社が、実はあなたのすぐそばにあるかもしれない」
就活を続ける中で、求人票を見て「これ、ちょっと興味あるかも」と思うことはあっても、なかなかピンとくる企業は少ないものです。そんなときに知ってほしいのが、一般のサイトには載っていない「非公開求人」。
①あなたの強みを見極め企業をマッチング
②ES添削から面接対策まですべて支援
③限定求人なので、競争率が低い
「ただ応募するだけじゃなく、自分にフィットする会社でスタートを切りたい」そんなあなたにぴったりのサービスです。まずは非公開求人に登録して、あなたらしい一歩を踏み出しましょう!
⑥実務経験を積んでスキルを磨く
実務経験は、編集者としての信頼を築く最大の武器です。現場での経験を通して、文章の構成力や企画力、スケジュール管理力などが自然と身につきます。
また、さまざまなジャンルの案件に携わることで、自分の得意分野や強みが見えてきます。経験を積んだ後は、フリーランスとして独立したり、大手出版社や制作会社への転職を目指すことも可能です。
1つひとつの仕事を丁寧にこなす姿勢が、次のチャンスを呼び込みます。経験の積み重ねが、プロフェッショナルへの最短ルートといえるでしょう。
⑦編集実績を活かしてキャリアアップする
一定の経験を積んだら、自分の得意領域を活かしてキャリアアップを目指しましょう。雑誌編集者からWeb編集者への転身や、ディレクター職への昇進など、スキルを広げる道は多岐にわたります。
近年では、マーケティングやSNS運用の知識を活かして、企業の広報やコンテンツプランナーに転職するケースも増えています。
フリーランスとして活動する人も多く、自分のライフスタイルに合った働き方を選べます。キャリアアップの鍵は「学び続ける姿勢」と「成果の見える実績」です。
自分の経験を積極的に発信し、業界内での信頼を築いていきましょう。
編集者の将来性と今後の需要
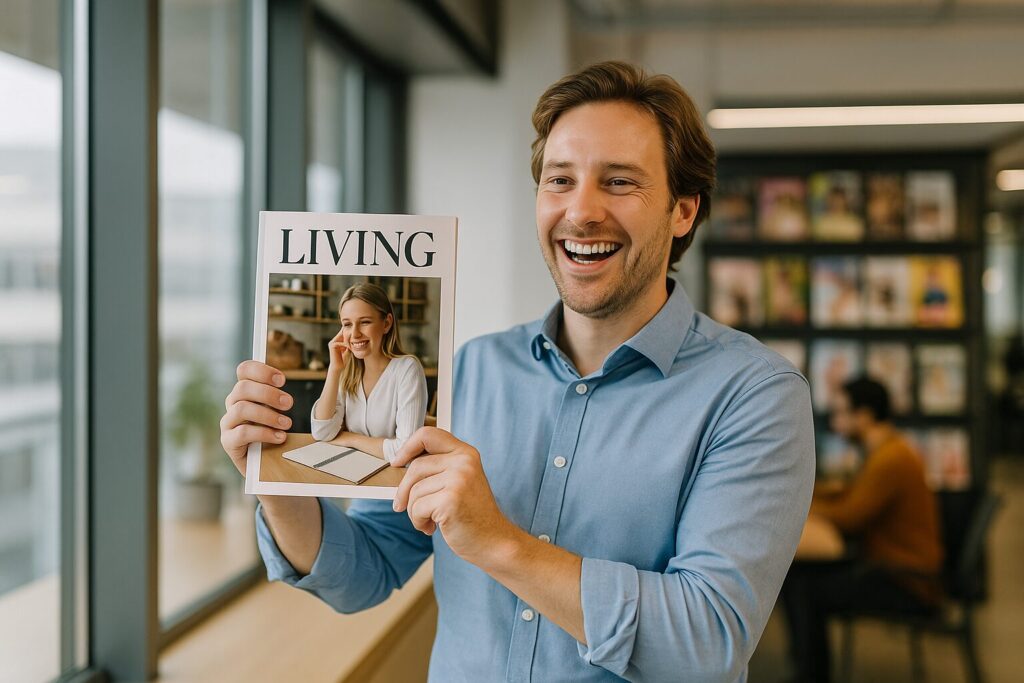
編集者という職業は、時代の変化とともに役割や働き方が大きく変化しています。
紙媒体の減少が叫ばれる一方で、WebメディアやSNS、動画プラットフォームの拡大により、編集スキルの需要はむしろ高まっています。ここでは、編集者の将来性を多角的に見ていきましょう。
- 出版業界の現状とデジタルシフトの影響
- Webメディア・SNSコンテンツの拡大
- AI・自動生成時代における編集者の役割
- 専門分野・ニッチ領域での需要増加
- スキルアップとキャリアの多様化
- 将来の編集者に求められる人材像
①出版業界の現状とデジタルシフトの影響
出版業界はここ数年、紙媒体の売上減少が続いていますが、電子書籍やオンライン出版の需要は急速に拡大しています。
読者がスマートフォンやタブレットでコンテンツを楽しむ時代となり、編集者にもデジタル対応力が求められるようになりました。
紙媒体の衰退を悲観する声もありますが、実際には編集者の役割が「紙からデジタルへ」広がっただけともいえます。
従来の編集スキルに加え、SEOやSNS運用、データ分析などを取り入れることで、新しい市場での価値を発揮できるでしょう。
編集者はこれからも「情報を整理し、伝える力」で活躍の場を広げていく職種です。
②Webメディア・SNSコンテンツの拡大
WebメディアやSNSの台頭により、コンテンツ制作の主戦場はオンラインへと移行しました。企業のオウンドメディア、ニュースサイト、YouTubeやTikTokなど、情報発信の場は多様化しています。
この変化に伴い、編集者の仕事も「記事を作る」だけではなく、「デジタルコンテンツ全体を企画・設計する」方向に進化しています。
SNSの反応やアクセスデータを分析し、どんなテーマが読者の心を動かすかを見極める力が求められます。
今後、Web編集者やSNSディレクターといった新たな職種も増え、デジタル分野の編集スキルを持つ人材の需要はますます高まるでしょう。
③AI・自動生成時代における編集者の役割
AI技術の発展により、文章生成やデータ整理などの作業は自動化が進んでいます。
これにより「編集者の仕事がなくなるのでは」と懸念する声もありますが、実際にはAI時代こそ編集者の価値が問われる時代です。
AIが生み出す文章には「人の感情」や「文脈の深み」が欠けることが多いため、最終的に読者に響くコンテンツに仕上げるのは人間の役割です。
AIが生産した情報を取捨選択し、正確かつ魅力的に整える能力が求められます。つまり、AIは編集者のライバルではなく、優秀なアシスタントです。
AIをうまく活用できる編集者こそ、今後の時代に最も重宝される存在になるでしょう。
④専門分野・ニッチ領域での需要増加
情報が氾濫する現代では、「誰が発信するか」「どの分野に精通しているか」がますます重要になっています。そのため、医療・教育・IT・金融など、特定分野に強い編集者の需要が急上昇しています。
専門的な知識を持つ編集者は、記事の正確性と信頼性を高める役割を果たします。読者にとって「専門家が編集した情報」という信頼感は大きな価値です。
ニッチな領域でも、深い知見と読者理解を持つ編集者は、メディア運営に欠かせない存在となっています。特化型スキルを磨くことで、他と差別化されたキャリアを築けます。
⑤スキルアップとキャリアの多様化
現代の編集者は、1つのスキルだけでは通用しません。ライティング・デザイン・マーケティング・動画編集など、幅広い知識を組み合わせて総合的なコンテンツ制作を行う力が求められます。
この傾向はキャリアの選択肢を広げるチャンスでもあります。出版やWebメディアにとどまらず、企業の広報、コンテンツマーケター、SNSプランナーなどへの転職も可能です。
新しい技術やツールを積極的に取り入れることで、変化の激しい業界でも安定した価値を提供できるようになります。
⑥将来の編集者に求められる人材像
これからの時代に求められる編集者像は、「情報編集者」から「価値創造者」へと変化しています。単に文章を整えるだけでなく、企画・戦略・発信までをトータルに考えられる人材が重視されます。
読者の行動データを分析し、どのように届けるかを設計できるマーケティング視点を持つことが重要です。また、AIや新しいツールを柔軟に取り入れるデジタル感度の高さも欠かせません。
今後、編集者は「コンテンツを作る人」ではなく、「情報をデザインし、価値を生み出す人」へと進化していくでしょう。
編集者が年収を上げるためのポイント

編集者として働く中で、「どのように収入を上げていくか」を考えることはキャリア形成において非常に重要です。
単に勤続年数を重ねるだけでは昇給が難しい業界だからこそ、戦略的にスキルを磨き、ポジションや働き方を見直すことが求められます。ここでは、年収アップにつながる具体的なポイントを紹介します。
- キャリアアップと昇進による収入増
- 高単価案件を獲得するスキルと実績づくり
- ジャンル選定による年収差の活用
- 副業・兼業で収入を増やす方法
- 資格取得・専門知識による市場価値向上
- フリーランスや独立で高収入を目指す戦略
①キャリアアップと昇進による収入増
編集者の年収を上げる最も王道の方法は、社内でのキャリアアップと昇進です。
アシスタントや一般編集者から、チーフ編集者、編集長、マネージャー職へとステップアップすることで、役職手当や裁量の拡大に伴い収入も上がります。
また、成果を出すためには「担当した媒体の成績」や「売上貢献度」を可視化して上司にアピールすることも大切です。近年では編集部門でも評価制度が整備され、個人の成果が報酬に直結する傾向があります。
地道に経験を積みながら、自分の強みを発揮できるポジションを目指すことが、安定的な収入アップへの近道です。
②高単価案件を獲得するスキルと実績づくり
編集者としてフリーランスや外注契約で働く場合、単価を上げる鍵は「専門性と信頼性」です。得意な分野を明確にし、そのジャンルで実績を積み重ねることで、高単価の案件を獲得しやすくなります。
特に、企業のオウンドメディアや大手出版社との仕事は、品質と納期の安定が評価基準となります。クライアントからの信頼を得るために、納品スピード・提案力・編集方針の一貫性を磨きましょう。
また、自分のポートフォリオを整え、SNSや制作プラットフォームで発信することも重要です。自分をブランド化する意識が、継続的な収入増につながります。
③ジャンル選定による年収差の活用
編集者の年収は、扱うジャンルによって大きく異なります。たとえば、エンタメやファッション誌よりも、医療・金融・ITといった専門性の高い分野では、編集単価や給与水準が高い傾向にあります。
そのため、自分の興味関心に加えて「市場価値の高い分野」を選ぶことが戦略的に重要です。専門的な知識を身につけることで、企画の質やクライアントとの信頼関係も深まり、高収入を得やすくなります。
得意分野を作ることは、単なるスキルアップではなく年収の底上げに直結する要素です。
④副業・兼業で収入を増やす方法
近年では、副業として編集やライティングを行う人も増えています。出版社や制作会社に勤めながら、Web記事の編集や企業ブログの監修を請け負うことで、安定収入に加えて副収入を得ることが可能です。
クラウドソーシングサイトやSNSを通じて、案件を受注するケースも一般的です。特に自分の専門分野に関連する仕事を選ぶと、効率よくスキルと収入を両立できます。
ただし、副業を行う際は勤務先の就業規則を確認し、無理のない範囲で行うことが大切です。継続できるスタイルを確立することで、将来的な独立への準備にもなります。
⑤資格取得・専門知識による市場価値向上
資格や専門知識は、編集者としての信頼度を高める武器になります。たとえば「校正技能検定」や「知的財産管理技能検定」などは、品質管理や著作権対応の力を客観的に示せる資格です。
また、SEOやマーケティング分析、SNS運用に関する資格を取得すれば、Web業界でも高単価の仕事を受けやすくなります。
資格そのものよりも、「資格を通じて得た知識をどう活かすか」が評価のポイントです。常に学びを続ける姿勢が、長期的に市場価値を高め、収入アップにつながります。
⑥フリーランスや独立で高収入を目指す戦略
最も大きく収入を伸ばしたい場合、フリーランスとして独立するという選択肢もあります。独立後は仕事の単価を自分で設定でき、受注案件の内容も自由に選べます。
ただし、収入の安定性は会社員に比べて低くなるため、信頼できるクライアントを確保し、安定した契約を結ぶことが鍵となります。また、確定申告や経費管理などの基本知識も必要です。
実績を積み重ねれば、月収100万円を超える編集者も珍しくありません。自分のスキルとネットワークを活かして、独立という形で年収を飛躍的に伸ばすことも可能です。
編集者という仕事で年収を高めるために大切なこと

編集者は、情報を企画・構成し、読者に価値あるコンテンツを届ける重要な職業です。平均年収はおおよそ400〜700万円といわれますが、スキルや経験、所属する業界によって収入は大きく変わります。
特に、出版やWebメディア、広告など多様な分野で活躍できる点は、この職業の魅力といえるでしょう。結論として、編集者として年収を上げるには「スキルを磨き、実績を積むこと」が不可欠です。
企画力や文章力、情報分析力などのスキルを高めることで、より高単価の案件やポジションを得やすくなります。また、資格取得や専門分野の知識を深めることで、市場価値をさらに向上させることも可能です。
これから編集者を目指す方は、やりがいや大変さを理解した上で、自分の強みを活かせる分野を見つけてください。
将来性のある業界で着実にスキルを磨くことが、安定した収入と長期的なキャリアの両立につながるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。