MRの給料は本当に高い?平均年収とやりがいを徹底解説
「MRって本当にそんなに給料が高いの?」と気になっている人も多いのではないでしょうか。
医薬品メーカーの営業職として知られるMR(医薬情報担当者)は、一般的な営業職と比べても平均年収が高いといわれています。しかし一方で、厳しいノルマや出張の多さなど、大変な面も少なくありません。
この記事では、MRの平均年収やボーナス事情、やりがいと大変さ、さらに薬剤師やMSとの違いまでを詳しく解説します。
高収入の理由や向いている人の特徴を知り、自分に合ったキャリアを見極める参考にしてみてください。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
MRとは?仕事内容と役割をわかりやすく解説

医療業界で働く「MR(医薬情報担当者)」という仕事は、名前を聞いたことがあっても、実際の業務内容を詳しく知っている学生は多くありません。
ここでは、まずMRの定義を明確にし、どんな仕事をしているのか、そして医療現場でどのような役割を担っているのかをわかりやすく紹介します。
- MRの定義
- MRの主な仕事内容
- 医療現場でのMRの役割
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①MRの定義
MR(Medical Representative)は、製薬会社に所属し、医師や薬剤師などの医療従事者に自社の医薬品情報を提供する専門職です。
目的は、医薬品をより安全かつ効果的に使ってもらうために、正確で新しい情報を伝えることにあります。
一般的に営業職と混同されがちですが、MRは医療知識と情報提供力を兼ね備えた専門職であり、医療の質を支える重要な存在です。文系・理系を問わず活躍できる点も特徴でしょう。
医薬品の知識がなくても、入社後にしっかり学べる研修体制が整っている企業が多く、努力次第で成長できる環境です。
②MRの主な仕事内容
MRの主な仕事は、病院やクリニックなどを訪問し、自社製品の効果や副作用、適正な使用方法を医療従事者に伝えることです。
単に薬を販売するのではなく、医師の治療方針や患者の状況を理解したうえで、必要な情報を的確に届ける役割を担っています。
さらに、医療現場で得た意見を製薬会社に報告し、製品改良や新薬開発に活かすことも重要な任務です。
また、勉強会や講演会の資料作成、医師への説明活動など、知識と信頼が問われる場面も多いでしょう。常に最新の医薬情報をアップデートし続ける姿勢が求められます。
③医療現場でのMRの役割
MRは、医師と製薬企業をつなぐ「情報の橋渡し」として、医療現場で欠かせない存在です。
医師が新しい薬を安心して使用できるよう、エビデンスに基づくデータを提供し、患者の治療を間接的に支えています。
また、薬剤師や看護師と連携して治療を最適化する機会も多く、チーム医療の一員として活躍します。
近年ではオンライン面談などデジタルツールを使った活動も増えており、情報共有の効率化が進んでいます。MRは、正確な情報提供を通じて医療の質を高める、社会的にも意義の大きい職業といえるでしょう。
MRと薬剤師・MSの違い

MR(医薬情報担当者)は医療業界で欠かせない存在ですが、薬剤師やMS(医薬品卸担当)と混同されることが多い職種でもあります。
ここでは、それぞれの役割や業務内容の違いをわかりやすく整理し、就活生が自分に合ったキャリアを考えるうえでの参考になる情報を紹介します。
- 薬剤師との違い
- MS(医薬品卸担当)との違い
①薬剤師との違い
MRと薬剤師はどちらも医薬品に関わる仕事ですが、役割や働く環境は大きく異なります。薬剤師は、患者に直接薬を渡したり、処方箋を確認して安全に服用できるよう管理する「医療提供者」です。
一方、MRは医療機関を訪問し、医師や薬剤師に医薬品の情報を提供する「情報伝達者」としての立場にあります。
つまり、薬剤師は現場で患者と関わるのに対し、MRはその前段階で正確な情報を届け、医療の質を高めるサポートをするのが役目です。
また、MRは営業要素も含むため、コミュニケーション力や提案力が求められる点も特徴でしょう。直接医療行為は行いませんが、医療現場を支える重要なパートナーとして機能しています。
②MS(医薬品卸担当)との違い
MRと混同されやすい職種にMS(Marketing Specialist、医薬品卸担当)があります。MSは医薬品卸会社に所属し、病院や薬局に医薬品を安定供給することが主な仕事です。
価格交渉や在庫管理を行い、必要な薬を途切れなく届ける「流通の専門家」といえます。
一方、MRは製薬会社の立場から、医薬品の特性や効果、副作用、使用方法などの情報を医師へ提供します。したがって、同じ医薬品業界に関わりながらも、目的は「販売」ではなく「適正使用の促進」です。
MRは医師との信頼関係を築くことが成果に直結するため、専門知識に加えて誠実な姿勢や聞く力が重視されます。両者は協力関係にあり、医療を支える役割を分担しているのです。
MRの給料は高い?MRの平均年収について

MR(医薬情報担当者)は医療業界の中でも高収入な職種として有名です。ここでは、その理由とMR平均年収の実態について解説します。
MRの年収は、おおよそ620万程度といわれています。これは日本の平均年収478万円を大きく上回る数字です。大手の外資系製薬企業では、年収1,000万円を超えるケースも見られます。
高収入の理由は、MRが担う仕事の専門性と責任の重さにあります。医師や薬剤師と対等に話せるだけの医薬品知識を持ち、正確な情報を提供する必要があるため、専門性が評価されやすいのです。
また、医療の質向上に直結する仕事であることから、成果が社会的にも高く評価される傾向にあります。
とはいえ、高額な水準にはそれだけの努力と責任が伴います。最新の医療情報を常に学び続ける姿勢や、医師との信頼関係を築くコミュニケーションを欠かさない、挑戦意欲のある人に向いているでしょう。
引用:openwork「MRの年収情報・企業年収ランキング」
MRの仕事のやりがいと魅力

MR(医薬情報担当者)は、医療業界の中でも「人の健康を支える実感」と「成果が収入に反映される充実感」が得られる仕事です。
ここでは、MRという職種ならではのやりがいや魅力を3つの観点から詳しく紹介します。医療に関心のある就活生にとって、将来のキャリアを考える上で重要なヒントになるでしょう。
- 医療貢献を実感できる
- 成果が給与に反映されやすい
- 専門知識と営業力の両方が磨かれる
①医療貢献を実感できる
MRの最大のやりがいは、医療を通じて社会に貢献できる点にあります。医師に最新の医薬品情報を提供することで、患者さんの治療に役立つ可能性が高まります。
自分が提供した情報が医師の処方判断に影響し、患者の回復に結びついたとき、大きな達成感を得られるでしょう。
また、医薬品の正しい使用を支えることで、医療全体の安全性向上にも貢献できます。MRは直接患者に接する機会は少ないものの、裏方として医療を支える重要な存在です。
自分の仕事が誰かの健康を守っているという実感が、仕事を続けるモチベーションにつながります。
②成果が給与に反映されやすい
MRの魅力のひとつは、努力や成果が給与に反映されやすい点です。多くの企業では、実績に応じた評価制度が導入されており、数字として成果が見える仕事といえます。
担当医療機関との信頼関係を築き、医薬品の認知度や使用率を高めることができれば、その分評価が上がる傾向があります。
自分の行動が目に見える形で報われるため、モチベーションを維持しやすい職種です。一方で、成果が出るまでの過程では地道な努力も必要です。
医療従事者との信頼関係は一朝一夕に築けないため、誠実に向き合う姿勢が求められます。成果主義の環境で自分を成長させたい人にとって、大きなやりがいを感じられる仕事でしょう。
③専門知識と営業力の両方が磨かれる
MRは、医薬品や疾患に関する知識を深めながら、営業力やコミュニケーション能力も高められる職種です。医師に情報提供を行うためには、医薬品の効果や副作用、臨床データを理解する必要があります。
勉強を重ねることで、医療の専門知識を持つ社会人として成長できます。
同時に、医師や薬剤師との対話を通して、傾聴力や提案力も磨かれます。理系の知識だけでなく、人との関係構築力が求められるため、文系出身者でも活躍しやすい仕事です。
知識と人間力の両面がバランスよく成長できる点は、他の職種にはない魅力といえるでしょう。
MRはやめとけ?MRの仕事の大変さ・きついと感じる瞬間

MRは高収入でやりがいのある仕事として注目される一方で、「MRはやめとけ」と言われることもあります。その理由には、仕事の厳しさや精神的なプレッシャーが関係しています。
ここでは、MRがきついと感じる代表的な場面を3つに分けて解説します。現実を知ったうえで、自分に合うかを見極めていきましょう。
- 営業ノルマや目標達成のプレッシャー
- 医療関係者との関係構築の難しさ
- 長時間労働・出張の多さ
①営業ノルマや目標達成のプレッシャー
MRは営業職の一面も持つため、ノルマや目標に追われるプレッシャーを感じることがあります。
製薬会社では売上やシェア率などの数値目標が設定されており、それを達成するための戦略立案と行動が求められます。
とくに新薬発売時はプレッシャーが強く、医師に情報を届けるスピードや交渉力が成果を左右します。
結果が数字で明確に示されるため、やりがいと同時に精神的な負担を感じやすい面もあります。努力がすぐに結果に結びつかないことも多く、継続的な忍耐力が必要です。
ただし、この経験を通して営業力や計画力を磨けるため、社会人としての成長にもつながります。
②医療関係者との関係構築の難しさ
MRの業務は医師や薬剤師など医療従事者との信頼関係が前提になりますが、その関係を築くのは簡単ではありません。医師は非常に忙しく、MRに割ける時間が限られています。
短い面談の中で信頼を得るには、医薬品の知識だけでなく、相手のニーズを的確に把握する力が求められます。
また、同業他社のMRとの競合も多く、自社製品を選んでもらうためには誠実さと専門性の両方が必要です。
すぐに成果が出ない場面も多いですが、地道な訪問や適切な情報提供を重ねることで信頼は積み上がっていきます。人間関係構築に時間をかけることをいとわない人に向いている仕事といえるでしょう。
③長時間労働・出張の多さ
MRの仕事は行動量が多く、スケジュールも変動しやすいのが特徴です。日中は病院やクリニックへの訪問を行い、夜は学会資料や報告書をまとめることもあります。
また、担当エリアが広い場合は地方出張が多く、長時間の移動や不規則な勤務時間になることも珍しくありません。
特に新薬説明会や学会シーズンは多忙になり、プライベートの時間を確保しにくい時期もあります。効率的な時間管理が求められるため、自己管理が苦手な人には負担に感じるかもしれません。
ただし、近年は働き方改革の影響で、リモート面談や直行直帰の導入が進み、以前よりも働きやすい環境づくりが整いつつあります。
MRに向いている人の特徴

MR(医薬情報担当者)は、医療の専門知識と営業力の両方が求められる職種です。そのため、どんな人がMRに向いているのか気になる就活生も多いでしょう。
ここでは、MRとして活躍できる人の特徴を4つの観点から紹介します。自分の性格や強みと照らし合わせながら、適性を確認してみてください。
- コミュニケーション能力が高い人
- 学び続ける姿勢がある人
- 成果志向・行動力のある人
- ストレス耐性・自己管理力がある人
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
①コミュニケーション能力が高い人
MRは医師や薬剤師と信頼関係を築く仕事であるため、人と関わる力が非常に重要です。医療従事者は多忙な中で限られた時間しか取れないため、短時間で要点をわかりやすく伝えるスキルが求められます。
単に話が上手なだけでなく、相手の立場を理解し、的確な提案を行えることが大切です。
また、医療現場では専門用語が多く、相手によって求める情報も異なります。相手の知識レベルや状況に合わせて伝え方を工夫できる人は、より信頼を得やすいでしょう。
誠実で丁寧なコミュニケーションを意識できる人は、MRとして成長できる素質を持っています。
②学び続ける姿勢がある人
医薬品の知識は日々進化しており、MRは常に最新情報を学び続ける必要があります。新薬の開発や制度変更など、医療業界は変化が速いため、知識を更新し続ける姿勢が欠かせません。
学びを楽しめる人や、情報を整理し他人にわかりやすく伝えられる人は、MRに向いています。
また、社内研修や学会など、学ぶ機会は多くあります。自発的に知識を吸収するだけでなく、日々の経験から学びを得ようとする姿勢が成長の鍵です。
受け身ではなく、自ら課題を見つけて改善できる人は、どんな環境でも活躍できるでしょう。
③成果志向・行動力のある人
MRの仕事は成果が明確に数字で表れるため、結果に対して前向きに取り組める人が向いています。売上や処方数などの目標を達成するためには、粘り強く行動することが欠かせません。
失敗を恐れずに試行錯誤を重ねる行動力が、成果につながります。
さらに、結果を出すためには効率的なスケジュール管理も重要です。限られた時間で訪問や資料作成をこなす必要があるため、計画的に動ける人は評価されやすいでしょう。
数字への意識が高く、挑戦を楽しめるタイプの人は、MRとして高いパフォーマンスを発揮できます。
④ストレス耐性・自己管理力がある人
MRはプレッシャーの多い仕事です。営業ノルマや医師対応、出張などが重なると、精神的にも体力的にも負担がかかります。
そんな環境の中で安定した成果を出すためには、ストレスに柔軟に対応できる力が必要です。
また、忙しい日々の中でも体調を崩さないよう、自己管理が欠かせません。生活リズムを整え、仕事とプライベートのバランスをとる意識が大切です。
ストレスを前向きに捉え、改善策を考えられる人は、長く活躍できるMRになれるでしょう。
MRに必要なスキルと能力

MR(医薬情報担当者)は、医療知識だけでなく営業的なスキルや思考力も求められる職種です。医師や薬剤師に正確な情報を伝えるための専門知識と、人間関係を築くための対話力が欠かせません。
ここでは、MRとして活躍するために必要な3つのスキルと能力を紹介します。
- 医薬品や疾患に関する専門知識
- プレゼンテーション・交渉スキル
- 問題解決力と提案力
①医薬品や疾患に関する専門知識
MRの基礎となるのは、医薬品と疾患に関する深い知識です。医師に製品情報を正確に伝えるためには、薬の作用機序、副作用、臨床データなどを理解しておく必要があります。
また、病気の仕組みや治療法を体系的に学ぶことで、医師との会話もスムーズに進みます。
この知識は大学での専攻だけでなく、入社後の研修や自己学習を通して身につけることが可能です。特に医療業界では情報の更新が早いため、継続的に勉強する姿勢が求められます。
専門性を高めることで信頼を得られ、医療従事者から相談を受けるような存在を目指せるでしょう。
②プレゼンテーション・交渉スキル
MRは医師や病院関係者に医薬品情報をわかりやすく説明する役割を担っています。そのため、聞き手に合わせたプレゼンテーション能力が不可欠です。
短い時間で重要な情報を伝える力や、相手の関心を引く話し方が成果に直結します。
また、医師の要望や意見を引き出すためには、交渉力も必要です。自社製品をただ紹介するだけではなく、医療現場の課題を理解し、それに合った提案を行うことが大切です。
誠実な対応を続けることで信頼を築き、長期的な関係を維持できるようになります。
③問題解決力と提案力
MRは単に情報を伝えるだけでなく、医療機関の課題を解決する役割も担っています。たとえば、処方データを分析し、医師が抱える疑問や課題を明確化して、より適切な医薬品の使い方を提案します。
このように、課題を発見して解決策を提示する力が求められます。
また、患者さんの安全や治療効果を考慮した提案を行うことも重要です。医師にとって有益な情報を届けるには、柔軟な思考力と客観的な視点が欠かせません。
問題解決力と提案力を磨くことで、医療従事者から信頼される「頼られるMR」へと成長できます。
新卒からMRを目指すには?就職ルートと必要資格を解説
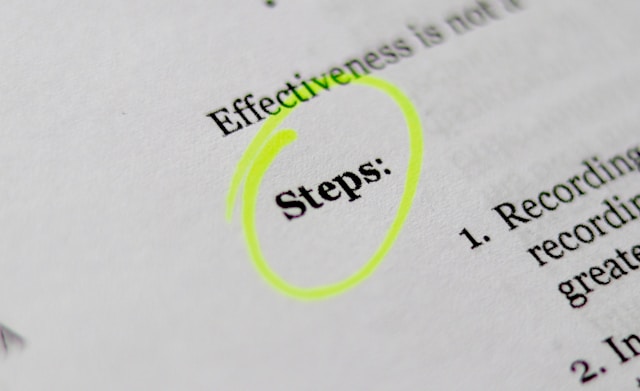
MRは高い専門性と営業力が求められる職種ですが、新卒からでも十分に目指せます。新卒でMRを目指す場合、主な就職先は製薬会社になるでしょう。
理系学生が多いですが、文系学生であっても営業力やコミュニケーション能力を評価されて採用されるケースも少なくありません。入社後は企業の実習を受け、MRとして必要な知識とスキルを身につけます。
また、就活時に必須となる資格はありませんが、実際に医療機関を訪問して情報提供を行う場合、「MR認定証」が必要になります。これは、入社後に企業が用意した研修と試験を通じて取得するのが一般的です。
そのため、薬学や生物学、医療制度などの基礎知識を学んでおくと有利です。また、就活時は志望動機を明確に伝えることも重要です。MRは医師との信頼関係が重要なので、誠実さが強みになります。
新卒でも専門的な医療知識を深めながらキャリアを築ける点が、MR職の大きな魅力といえるでしょう。
MR認定証とは?取得方法と新制度の変更点

MR(医薬情報担当者)として働くには、専門的な知識と倫理観を証明する「MR認定証」の取得が実務上重要になります。
ただし、新卒で製薬会社に就職する際には、この資格を持っていなくても問題ありません。多くの企業では入社後の研修を通じて取得を目指す形が一般的です。
ここでは、認定証の概要から試験内容、新制度の変更点、更新の流れまでをわかりやすく解説します。
- MR認定証の概要と目的
- MR基礎試験の受験資格・科目・難易度
- 2026年度以降の新制度と主な変更点
- MR認定証更新の手続きと有効期限
①MR認定証の概要と目的
MR認定証とは、一般社団法人MR認定センターが発行する「医薬情報担当者」としての専門資格です。
MRとして採用される際に特別な資格は必要ありませんが、実際に医療機関を訪問して医師へ情報提供を行うには、この認定証がほぼ必須とされています。
製薬会社の多くでは、入社後の研修を通じてMR認定証の取得を義務づけています。これは、医薬品に関する科学的知識と高い倫理観を備えていることを第三者機関が保証する仕組みです。
1997年に制度が開始されて以来、医療現場で信頼されるMRの証として定着しています。医師や薬剤師と信頼関係を築くためにも、取得を目指すことが望ましいでしょう。
②MR基礎試験の受験資格・科目・難易度
MR認定試験を受けるには、MR認定センターが指定する教育課程を修了している必要があります。
一般的には、製薬会社に入社後、通信教育や集合研修などを通じて基礎教育を修了し、その後に受験資格が得られます。大学生のうちに受験できる試験ではなく、社会人になってから挑戦する形式です。
ただし2026年度以降はこの受験資格が撤廃され、誰でも「MR基礎試験」を受験できるようになります。
試験科目は、薬学・生物学・医学・倫理など多岐にわたります。出題範囲は広いものの、製薬企業の研修カリキュラムをしっかり学べば十分合格可能です。
例年の合格率は80%前後と高く、継続的に学ぶ姿勢があれば取得は難しくありません。合格後は、製薬企業のMRとして医療現場での活動が認められるようになります。
③2026年度以降の新制度と主な変更点
MR認定制度は、2026年度から新たな仕組みに移行する予定です。従来の「MR認定試験」は「MR基礎試験」として再編され、実務に直結する教育内容がより重視される方針です。
これにより、単なる知識試験ではなく、医療現場での対応力や倫理観を問う実践型の評価へと変化します。
また、新制度では教育体制の柔軟化も進められ、オンライン学習の導入や地方会場の拡充などが検討されています。
背景には、医療環境や働き方の多様化に合わせて、MRの質を高める狙いがあります。変化に対応できる学びの仕組みが整うことで、より多くの人が専門性を高めやすくなるでしょう。
④MR認定証更新の手続きと有効期限
MR認定証には有効期限があり、定期的な更新が必要です。一般的には5年ごとに更新手続きを行い、再教育プログラムを受講することで資格の継続が認められます。
医薬品や医療制度は常に進化しているため、知識のアップデートを怠ると最新情報に対応できなくなるおそれがあります。
更新時には、法規制や医薬倫理、最新の薬剤情報などの再学習が求められます。多くの製薬会社では、社員が確実に更新できるよう社内サポート体制を整えています。
定期的に知識を更新することは、自身の専門性を保つだけでなく、医療従事者から信頼され続けるための重要なプロセスといえるでしょう。
MRの給料とキャリアを理解して後悔しない選択をしよう

MR(医薬情報担当者)は、医療業界において重要な役割を担う専門職です。仕事内容は医師への医薬品情報の提供や安全性の説明など多岐にわたり、医療に直接貢献できる点が大きな魅力です。
平均年収はおよそ600万円と高水準で、成果が給与に反映されやすい特徴もあります。一方で、営業ノルマのプレッシャーや長時間労働といった厳しさも存在します。
とはいえ、コミュニケーション能力や学ぶ姿勢を持つ人にとっては大きく成長できる職種です。新卒であっても特別な資格は不要で、入社後にMR認定証を取得することで専門性を高められます。
高収入を目指しつつ医療に貢献したい人にとって、MRは挑戦する価値のあるキャリアでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













