図書館司書の年収事情|仕事内容・雇用形態・資格で差は出る?
本や知識に関わる仕事として人気の高い司書ですが、実際の給与水準や働き方はあまり知られていません。勤務先によって待遇も異なり、正規職員と非正規職員では年収に大きな差が出ることもあります。
この記事では、図書館司書の仕事内容や雇用形態、資格の違いによる収入格差までを徹底解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
司書とは?

図書館司書という仕事は「本が好きだから」という気持ちだけでは務まりません。専門的な知識と責任を持って情報を扱う、知の専門職です。
ここでは、司書の定義や役割、司書教諭との違い、資格取得の方法について分かりやすく解説します。大学生や就職を考える人が「司書を目指すには何が必要か」を理解できる内容です。
- 司書の定義と役割
- 図書館司書と司書教諭の違い
- 司書資格の種類と取得方法
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①司書の定義と役割
司書は、図書館で資料の収集や整理、利用者への提供を担う専門職です。本を貸し出すだけでなく、利用者が求める情報を正確かつ迅速に見つけ出し、知識を活用できるよう支援します。
図書館を「知の拠点」として機能させるための中心的な存在であり、学びや文化を支える役割を持っています。
また、地域住民の調査活動を助けたり、教育機関と連携して学習支援を行ったりすることもあります。
近年では、デジタル資料の管理や電子図書館の構築、情報リテラシー教育にも携わるなど、活躍の場が広がっています。地道な業務が多い仕事ですが、人々の成長を支えるやりがいの大きい職業です。
②図書館司書と司書教諭の違い
図書館司書と司書教諭は、どちらも本や情報に関わる仕事ですが、役割と職務内容には明確な違いがあります。
図書館司書は主に、公共図書館・大学図書館・専門図書館などで働き、資料の収集や貸出、利用者への案内、情報提供を行う「専門職」です。
一方の司書教諭は学校に勤務し、子どもたちの読書活動や調べ学習を支援する「教育職」であり、教員免許が必要になります。
司書教諭は、授業の一環として読書指導を行うこともありますが、図書館司書は地域全体の学びや文化活動をサポートする立場です。
どちらも重要な役割を担っていますが、求められるスキルやキャリアパスが異なるため、自分の目指す働き方を早めに明確にしておくことが大切でしょう。
③司書資格の種類と取得方法
司書として働くためには、文部科学省が定める「司書資格」を取得する必要があります。これは、国家資格に位置づけられており、大学や通信制大学で指定の科目を修了すると取得可能です。
資格には「司書」「司書補」「司書教諭」の3種類があり、求められる学歴や履修条件がそれぞれ異なります。特に、司書資格は大学卒業を前提とする場合が多く、社会人でも通信課程で学び直す人が増加中です。
近年は、オンライン授業にも対応する大学が増え、働きながらでも取得しやすくなっています。
なお、資格を取っただけで、自動的に就職できるわけではありませんが、採用試験や応募時に大きなアピールポイントになります。
図書館司書の種類

図書館司書といっても、勤務先や役割によって仕事内容や求められるスキルは大きく異なります。ここでは、代表的な5つの司書の種類を紹介しています。
どの職場を選ぶかによって、年収や働き方にも違いが出てくるため、将来の方向性を考えるうえでの参考にしてください。
- 公共図書館司書
- 大学図書館司書
- 学校図書館司書
- 専門図書館司書
- 司書教諭(学校教員を兼ねる司書)
①公共図書館司書
公共図書館司書は、地域住民にとって最も身近で親しみやすい存在です。市町村や都道府県が運営する図書館に勤務し、資料の貸出や返却、蔵書の整理・管理、利用者への案内など幅広い業務を担っています。
利用者の年齢層が幼児から高齢者まで幅広いため、子ども向けの読み聞かせイベントや高齢者向け講座、地域交流の場づくりなど、多様な活動を行うこともあります。
また、地域の課題解決を支援する情報提供や、学習・研究活動のサポートも重要な役割です。人と接する機会が多く、利用者一人ひとりに寄り添う姿勢が求められます。
コミュニケーション能力や企画力、地域貢献への意欲が高い人に向いた職種でしょう。市民の知的活動を支え、地域社会の発展に貢献できるやりがいのある仕事です。
②大学図書館司書
大学図書館司書は、学生や研究者の学びと研究を支える専門職です。一般書に加え、専門書・学術雑誌・論文・電子ジャーナルなど、学問分野ごとの高度な資料を扱っています。
主な業務は、資料の整理・管理だけでなく、文献検索の支援や研究データの提供、情報リテラシー教育など多岐にわたります。
学術情報のデジタル化が進む現在では、電子資料やデータベースを扱う機会も増え、ITスキルや英語文献を読み解く力も重視されるでしょう。
研究者とやり取りする機会も多く、正確な情報処理能力と専門的な知識が求められます。学問への関心が強く、知的好奇心を持って仕事に向き合える人に向いているでしょう。
③学校図書館司書
学校図書館司書は、小学校から高校までの教育現場で、児童や生徒に読書の楽しさを伝える役割を担います。読書支援や資料の整備に加え、授業に役立つ図書の選定や学習支援も行っています。
教員と連携して調べ学習をサポートすることも多く、教育的な視点や子どもへの理解が欠かせません。
また、読書週間に合わせたイベントの企画や、図書委員活動の運営支援など、学校全体の読書文化を育てる活動も重要です。子どもたちが本を通して学び、成長する姿を間近で見られるのが大きな魅力でしょう。
教育への情熱と柔軟な対応力、そして子どもに寄り添う温かさが求められます。子どもと関わることが好きで、教育に貢献したい人に最適な職種です。
④専門図書館司書
専門図書館司書は、企業・病院・研究機関・官公庁など、特定分野に特化した情報を扱う司書です。
取り扱う資料は、法律・医療・経済・工学・環境など専門的な内容が多く、利用者の業務や研究を支えるための正確かつ迅速な情報提供が求められます。
英語論文や専門データベースを扱うこともあり、語学力や専門知識を活かせる環境です。また、社内報の編集やデジタルアーカイブの整備など、組織の知識資産を管理する仕事を担当する場合もあるでしょう。
利用者が限られる分、より深く専門性を追求でき、自分の得意分野を伸ばすことが可能です。研究者や技術者のパートナーとして働くため、正確性・分析力・情報整理能力が重視されます。
専門分野で長くキャリアを築きたい人にとって、理想的な職場でしょう。
⑤司書教諭(学校教員を兼ねる司書)
司書教諭は、学校で教員として授業を担当しながら、図書館運営や読書活動の推進も行う職種です。教員免許と司書教諭資格の両方を持ち、教育現場で本を通じた学習支援を行います。
子どもたちが主体的に学ぶ力を育てるため、授業の中で図書を活用した調べ学習や読書指導を実施しています。
また、授業に必要な教材や資料を整備したり、学校全体の読書活動を企画したりするなど、教育支援の幅が広いのも特徴です。
生徒の成長を間近で感じられる点が大きな魅力で、教育と読書の両方に情熱を持てる人に向いています。
図書館司書の仕事内容

図書館司書の仕事は「本を貸すだけ」と思われがちですが、実際はとても幅広いです。ここでは、司書が日々どのような業務を行っているのかをわかりやすく紹介します。
仕事内容を知ることで、図書館司書という仕事の専門性とやりがいがより明確に理解できるでしょう。
- 資料の選定・収集・整理
- 図書館資料の管理・貸出業務
- 利用者への案内・レファレンスサービス
- 読書推進・イベント企画運営
- 館外活動・地域連携業務
①資料の選定・収集・整理
図書館司書の基本的な業務の1つが、資料の選定と整理です。図書館に置く本や雑誌、新聞、DVD、電子書籍など、多様な資料を選定し、利用者の関心や地域の特色に合わせてコレクションを充実させます。
そのためには、出版動向を常に把握し、利用者アンケートや貸出データを分析する力も求められるでしょう。
収集した資料は、日本十進分類法(NDC)などの分類法に基づいて整理し、誰でも探しやすいように配置します。また、除籍や保存処理など、蔵書のライフサイクルを管理するのも司書の重要な役割です。
見た目は地味ですが、図書館の質と利便性を左右する、縁の下の力持ちといえる仕事でしょう。
②図書館資料の管理・貸出業務
図書館の中心的な業務といえば、資料の貸出・返却対応です。利用者と直接接するカウンター業務に加え、資料の所在確認、破損や汚損本の修理、定期的な蔵書点検など、裏方の管理作業も欠かせません。
資料が正しく管理・循環されることで、利用者が快適に本を利用できる環境が維持されます。
近年では、自動貸出機やICタグ、蔵書管理システムなどの導入が進み、デジタル技術への対応力も求められています。
単純な作業に見えて、正確性・効率性・利用者対応力のすべてが必要とされる奥深い仕事です。利用者の「また来たい」という気持ちを生む、大切な役割を担っています。
③利用者への案内・レファレンスサービス
レファレンスサービスとは、利用者が求める情報や資料を見つけ出すための専門的な支援業務です。
「特定のテーマを調べたい」「この分野の最新資料を知りたい」といった相談に対し、最適な資料や情報源を案内します。そのため、幅広い分野の知識や情報検索スキル、的確な質問力が欠かせません。
インターネットやデータベースを活用しながら情報を整理し、信頼性の高い回答を導き出す能力が求められます。質問の背景を読み取り、利用者の意図を理解する力も重要です。
レファレンス対応の質は、図書館全体の評価にも関わるため、責任とやりがいを感じられる業務といえるでしょう。
④読書推進・イベント企画運営
図書館は単なる本の貸出施設ではなく、地域の文化を育む「交流の場」でもあります。そのため司書は、読書会やおはなし会、ブックトーク、文学展示など、多彩なイベントを企画・運営もしています。
子どもから大人まで幅広い層に読書の魅力を伝えるため、季節や社会的テーマに合わせた工夫が求められます。また、地域作家とのコラボレーションや、地元学校との共同企画を行うこともあるでしょう。
こうした活動を通じて、図書館が地域の文化拠点としての役割を果たすことができます。人との関わりが多く、企画力・発信力・調整力など多面的なスキルが磨かれる仕事です。
⑤館外活動・地域連携業務
図書館司書は、館内業務にとどまらず、地域社会とのつながりを築く重要な役割も担っています。
学校や地域団体と協力して、移動図書館を運営したり、子どもや高齢者を対象とした読書指導や講座を開いたりします。
さらに、病院や福祉施設、子育て支援センターなどへ出張して本を届ける活動も行われています。
こうした取り組みは「本を届ける」だけでなく、読書を通じた心の支援や社会的つながりの促進にもつながります。地域課題の解決に関わることもあり、図書館の枠を超えた活動の幅が広がっています。
図書館司書の平均年収
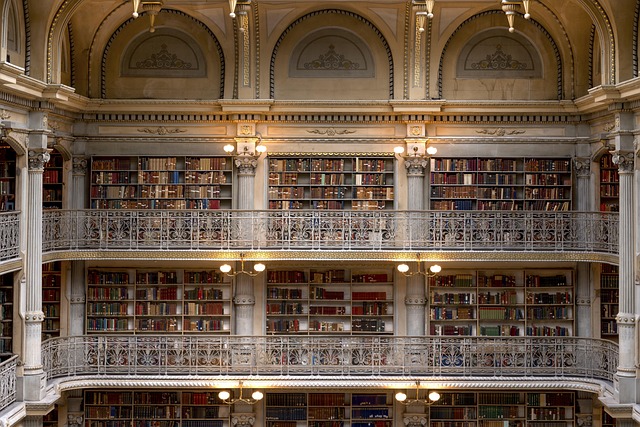
図書館司書の年収は、勤務先の種類や地域、雇用形態によって大きく変わります。
ここでは、厚生労働省の最新統計データをもとに、図書館司書の平均年収や月収、地域や年齢による違いをわかりやすく解説しています。就職を考える前に、収入の現実を正しく理解しておくことが大切です。
- 最新統計データで見る平均年収
- 平均月収・時給換算ベースの目安
- 年齢・経験年数別で見る年収推移
- 地域別・都道府県別で見る年収の違い
- 雇用形態別で見る年収比較
①最新統計データで見る平均年収
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」によると、図書館司書(「図書館司書等」に分類)の平均年収は約591万円です。
これは、賞与などを含めた推定年収で、全国平均よりやや高い水準といえます。基本給の平均は約32万円、年間賞与はおよそ200万円前後とされており、職場の規模や雇用条件によって大きく変動します。
大学や専門図書館を含むデータであるため、公共図書館の司書では400〜500万円台にとどまる場合も多いでしょう。
実際の給与水準は自治体の財政力や職員の勤続年数によっても異なり、同じ「司書」でも勤務先によって年収差が生まれやすい職種です。
②平均月収・時給換算ベースの目安
図書館司書の平均月収は、およそ19.7万円とされています。これを時給に換算すると、概ね1,200〜1,300円前後です。
正規職員の場合は賞与や諸手当、退職金制度があり、年間を通して安定した収入を得られます。一方、非正規職員は時給制や日給制のことが多く、勤務日数によって収入が変動する傾向があるようです。
特に、非常勤職員はボーナスが支給されない場合も多いため、見た目の月給だけでは実際の年収を判断しにくい点に注意が必要でしょう。
求人票を見る際は、勤務時間や休日数、各種手当の有無まで確認してください。職場によっては、交通費や時間外手当などが含まれないケースもあるため、総支給額と手取り額の差も意識することが大切です。
③年齢・経験年数別で見る年収推移
図書館司書の年収は、年齢や経験年数によって緩やかに上昇する傾向があります。若手の20代前半では、年収250万円前後からスタートし、30代〜40代の中堅層になると300〜350万円程度が一般的です。
勤続年数が長いベテラン司書では、400万円を超えるケースもありますが、これは主に正規職員や管理職クラスに限られます。
非正規雇用では昇給の機会が限られ、長年働いても年収が大きく変わらないことも珍しくありません。
安定した収入を得たい人は、正規職員採用を目指すほか、資格の取得やキャリアアップを意識することが重要です。
専門知識を高め、電子資料管理やイベント企画など幅広いスキルを身につけることで、年収アップの可能性も高まるでしょう。
④地域別・都道府県別で見る年収の違い
地域によっても、司書の年収水準には大きな差があります。大都市圏(東京都・大阪府・神奈川県など)では、図書館の規模が大きく業務内容も多岐にわたるため、平均年収が300〜350万円前後とやや高めです。
反対に地方自治体では、財政規模や人件費削減の影響を受けやすく、250万円前後にとどまるケースが多く見られます。特に、小規模自治体では非常勤や契約職員が中心で、勤務日数が限られることもあるでしょう。
その一方で、地方では生活コストが低いため、実質的な生活水準は大都市圏と大きく変わらない場合もあります。
勤務地を選ぶ際は、単に給与額だけでなく、通勤時間・生活費・福利厚生などを総合的に考慮することが大切です。
⑤雇用形態別で見る年収比較
図書館司書の年収差を最も左右するのが、雇用形態の違いです。正規職員(地方公務員)として働く場合の年収は、おおよそ350〜400万円前後が目安で、賞与や昇給制度も整っています。
一方、契約職員や非常勤職員は200〜280万円程度とされ、年間勤務日数や雇用期間によってさらに変動します。
厚生労働省の調査によると、正規職員の割合は約33%、パートタイマーが55%、契約社員・期間従業員が40%と、非正規雇用が多い現状が浮き彫りになっています。
安定した収入を目指すなら、地方自治体や大学の正規採用枠を狙うのが現実的です。
また、司書資格に加えて関連資格を取得することや、長期勤務による信頼を築くことで、契約更新や昇給につながるチャンスも増えるでしょう。
司書の年収が低いと言われる理由
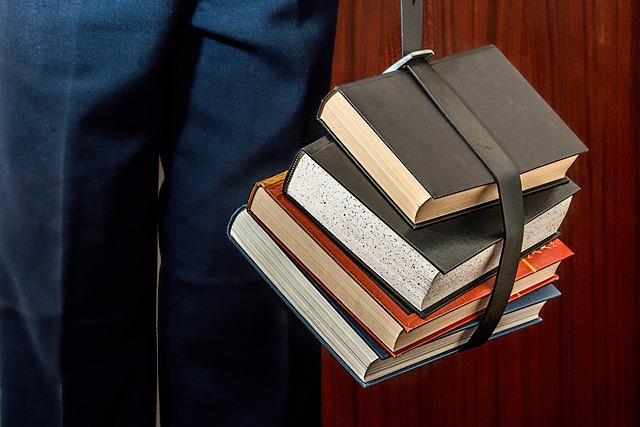
図書館司書は「安定しているが収入が低い」と言われる職業のひとつです。ここでは、なぜ司書の年収が上がりにくいのか、その背景を6つの観点から整理して解説します。
理由を理解しておくことで、将来の働き方やキャリア設計をより現実的に考えられるでしょう。
- 非正規雇用の割合が高いため
- 求人の少なさと競争率の高さが影響しているため
- 給与が自治体予算に左右されるため
- 司書職の昇進・昇給機会が限られているため
- 専門職でありながら資格手当が少ないため
- 図書館運営の外部委託・民間委託が進んでいるため
①非正規雇用の割合が高いため
図書館司書の多くは、非正規雇用で働いており、正規職員として働く人は全体の約3割にとどまるというデータもあります。
残りの大半は契約職員や非常勤職員、パートタイマーとして勤務しており、雇用が不安定な場合が多いのが現状です。
非正規雇用では、賞与や昇給がほとんどなく、時給制・日給制で働くことが一般的。そのため、フルタイム勤務であっても、年収200万円台にとどまることが珍しくありません。
契約更新のたびに職を失う不安を抱える人も多く、生活基盤を安定させるのが難しい一面もあります。
安定した収入を得るには、地方自治体の正規採用試験を受けて公務員として勤務するか、長期雇用を前提とした大学図書館・研究機関などを目指すのが現実的な方法です。
②求人の少なさと競争率の高さが影響しているため
図書館司書の求人は全国的に少なく、採用の機会が限られています。多くの図書館では定員が固定されており、新規採用よりも退職者の補充が中心です。
募集人数が1〜2名ということも多く、司書資格を持つ人が多いため競争率は非常に高くなります。特に、人気の高い自治体や大学では数十倍になることもあるようです。
こうした状況から、採用までに数年かかるケースも珍しくありません。就職を目指す場合は、公共図書館だけでなく、大学・専門図書館・企業図書室など幅広い選択肢を検討することが重要です。
また、ボランティア活動や実務経験を積んでおくことで、採用時に有利になる可能性もあります。視野を広く持ち、長期的なキャリア形成を意識することが大切です。
③給与が自治体予算に左右されるため
公共図書館の多くは、地方自治体が運営しており、司書の給与は自治体の財政状況に大きく左右されます。
財政が厳しい自治体では人件費削減の一環として、非常勤職員の増加や時給制への切り替えが進んでいます。
これにより、給与水準が全国的に低下する傾向が見られます。一方で、財政に余裕のある自治体では、手当や賞与が充実していることもあり、待遇面での格差が生まれやすい職種です。
さらに、図書館の運営方針が変わるたびに予算が見直されるため、雇用の安定性にも影響が出やすい点が課題になっています。
応募前に、自治体の財政健全度や職員給与水準を調べておくと、働き始めてからのギャップを防げるでしょう。
④司書職の昇進・昇給機会が限られているため
図書館司書は専門職でありながら、組織内での昇進や昇給のチャンスが限られています。図書館は職員数が少なく、上位職にあたる館長・副館長・主任司書などのポストがごくわずかしか存在しません。
そのため、どれだけ経験を積んでも、役職や給与が大きく変わらないケースが多いのです。特に公共図書館では、昇給幅が小さく、勤続年数に応じてゆるやかに上がる程度にとどまります。
給与アップを望むなら、管理職を目指すだけでなく、大学図書館や企業の情報センターなど専門性を活かせる職場への転職を検討するのも一つの方法です。
資格や実務経験を生かし、キャリアの幅を広げることが、収入向上につながるでしょう。
⑤専門職でありながら資格手当が少ないため
図書館司書は、専門的な知識とスキルを必要とする職業ですが、その専門性が給与に反映されにくい現状があります。
司書資格は、国家資格ではなく「任用資格」に分類されるため、資格手当がつかない、または数千円程度しか支給されないケースが一般的です。
同じ専門職である看護師や薬剤師と比べると、資格の評価が低く設定されています。その結果、専門職でありながら年収が伸びにくい状況が生まれているようです。
ただし、情報整理やデジタルアーカイブ、教育支援などの分野でスキルを磨けば、より専門的な職場で評価される可能性もあります。
資格だけに依存せず、実務的な能力を高めることで、待遇改善のチャンスをつかむことができるでしょう。
⑥図書館運営の外部委託・民間委託が進んでいるため
近年、自治体が経費削減を目的に、図書館運営を民間企業へ委託する「指定管理者制度」を導入するケースが増えています。
これにより、公務員として働く司書が減少し、民間委託会社に雇用される契約職員やパート職員が増加しているのが実情です。
民間委託では雇用期間が短く、賞与や昇給制度が整っていない場合も多いため、結果として年収が低く抑えられる傾向があります。
また、契約更新のたびに条件が変わる可能性もあり、長期的なキャリア形成が難しいという課題もあるでしょう。
安定した働き方を希望するなら、自治体直営の図書館や大学附属図書館など、正規雇用のチャンスがある職場を選ぶことが大切です。
図書館司書になるには
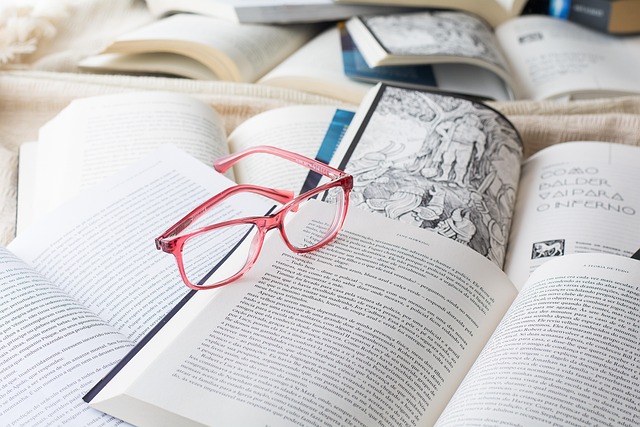
図書館司書になるためには、まず「司書資格」の取得が欠かせません。そのうえで、公立図書館や大学図書館などの採用試験に合格する必要があります。
ここでは、資格の取得条件から学び方、採用の流れまでをわかりやすく紹介しています。就活を意識している学生にとって、現実的なステップを理解しておくことが大切です。
- 司書資格を取得するための条件
- 通信大学・通学課程での取得方法
- 司書として就職・採用されるまでの流れ
- 採用試験や面接で重視されるポイント
①司書資格を取得するための条件
図書館司書として働くためには、文部科学省が定める「司書資格」の取得が必要不可欠です。この資格は、大学や短期大学で指定された科目を履修・修了することで得られます。
たとえば、「図書館概論」「図書館サービス論」「情報資源組織論」など、図書館運営に関する専門的な知識を学ぶ科目が含まれています。
大学在学中に履修すれば、卒業と同時に資格を得ることができるほか、すでに社会人の人でも通信制大学を利用して取得できます。
なお、司書資格は国家資格ではなく任用資格に分類されますが、図書館職に就く際には必須条件として求められることが多いです。
司書を目指す場合は、大学進学時から司書課程の有無を確認しておくと安心でしょう。
②通信大学・通学課程での取得方法
司書資格は、通学制・通信制のどちらでも取得できます。通学課程では、大学の講義や演習を通じて、実際の図書館運営や情報整理技術を体系的に学ぶことが可能です。
現場で働く司書による授業や、実際の図書館での実習を取り入れている学校もあり、実践的なスキルを磨けるのが強みでしょう。
一方、通信制大学では、教材やオンライン講義を活用して自宅で学習できるため、社会人や子育て中の人にも人気があります。
大学によってはスクーリング(面接授業)やレポート提出が必要で、半年から1年程度で修了するケースが多いです。費用は、10〜30万円ほどが一般的ですが、在籍期間や履修科目数によって変動します。
自分の生活リズムや学習スタイルに合わせて、通学・通信のどちらが適しているか検討してみてください。
③司書として就職・採用されるまでの流れ
司書資格を取得した後は、希望する職場の採用試験を受けることになります。公共図書館で働く場合は、地方公務員試験(一般事務職または司書職)を受験し、合格後に配属される流れです。
大学図書館や企業の情報センターでは、独自の採用試験や面接が実施される場合もあります。
正規職員の採用枠は限られているため、まずは非常勤職員や契約職員として経験を積み、実績を重ねてから正規採用を目指す人も少なくありません。
採用後は、資料の整理や貸出管理、レファレンス対応などを担当しながら、実務を通じて知識とスキルを深めていきます。
また、経験を重ねることで企画や教育支援など、より幅広い業務に関わる機会も増えていくでしょう。
④採用試験や面接で重視されるポイント
司書採用試験では、一般教養や時事問題に加え、自治体によっては専門試験が行われます。
筆記試験に加えて、面接では「なぜ司書を志望したのか」「図書館を通じてどんな貢献をしたいか」といった質問が多く、志望動機の明確さが評価のポイントとなるでしょう。
さらに、図書館は地域の利用者と直接関わる場であるため、利用者対応力や協調性、柔軟な対応力も重視されます。
最近では、デジタル資料の管理やイベント企画など多様な業務が求められるため、発想力や提案力をアピールできると有利です。
司書が年収を上げる方法

司書の年収は決して高いとは言えませんが、工夫次第で収入を上げることは十分に可能です。ここでは、キャリア形成やスキルアップを通じて、年収を伸ばすための具体的な方法を紹介します。
自分の適性や目標に合わせて働き方を見直すことで、将来のキャリアに新たな可能性を見いだせるでしょう。
- 専門分野に強みを持つ
- 大学院進学や研究職へのステップアップを目指す
- 司書教諭など関連資格を取得して活躍の場を広げる
- 副業・兼業で収入源を増やす
- 管理職・マネジメント職を目指すことで昇給を狙う
①専門分野に強みを持つ
図書館司書として年収を上げたい場合、特定の専門分野に強みを持つことが非常に効果的です。
たとえば医療、法律、工学、経済など、専門性の高い情報を扱う分野に詳しい司書は、大学図書館や企業図書館、研究機関などで重宝されます。
また、データベース検索や情報アーカイブ管理、電子書籍の運用などIT関連のスキルを身につければ、電子図書館の運営や情報システム構築にも関わることが可能です。
こうしたスキルは市場価値が高く、より待遇の良い職場への転職にもつながります。自分の関心のある分野を深掘りし、専門性を高めることで、他の司書との差別化を図りましょう。
②大学院進学や研究職へのステップアップを目指す
大学院に進学して図書館情報学や教育学、情報科学などを研究することで、より高度な専門知識を得られます。
大学図書館や研究機関では、修士号や博士号を持つ人が優遇される傾向があり、採用時の給与水準も高めに設定されている場合があるでしょう。
特に研究支援、学術情報管理、データベース構築などの分野では、大学院修了者が求められることが多いです。
学位を取得することで、図書館の専門職だけでなく研究員や教育職といったキャリアにもつながり、安定した収入を得られる可能性が高まります。
学術的な探究心があり、専門職として長期的にキャリアを築きたい人にとって、大学院進学は大きなステップアップの手段といえるでしょう。
③司書教諭など関連資格を取得して活躍の場を広げる
司書教諭の資格を取得すれば、学校図書館で教育活動に直接関わることができます。教員免許を持っている場合は授業支援や読書教育を担当でき、児童や生徒の学習意欲を高める活動にも携われるでしょう。
教育現場での経験を積むことで、教育委員会や学校運営に関わるキャリアへ発展する可能性もあります。
また、司書教諭以外にも学芸員、情報処理技術者、出版・編集関連資格など、図書館業務と親和性の高い資格を取得することで、博物館、企業、行政機関など活躍の場を広げることが可能です。
複数の資格を持つことは専門性の証明になり、より高い報酬やポジションを得やすくなるでしょう。学び続ける姿勢が、年収アップのカギとなります。
④副業・兼業で収入源を増やす
近年では、副業を解禁する自治体や企業が増えており、司書としての知識やスキルを生かした副業に挑戦する人も多くなっています。
たとえば、読書や図書館運営に関するコラム執筆、書籍レビュー、オンライン講座の講師、資料整理の在宅ワークなどが代表的です。
専門分野を活かした情報発信や教育支援を行うことで、信頼性の高い副収入源を確保できます。また、電子書籍の編集やデータアーカイブ関連の仕事など、リモートでできる業務も増えています。
ただし、公務員として働く場合は副業が原則禁止されているため、勤務先の就業規則を必ず確認しましょう。時間の使い方を工夫すれば、無理なく安定的に収入を増やすことができます。
⑤管理職・マネジメント職を目指すことで昇給を狙う
司書として安定した高収入を得たい場合、管理職やマネジメント職への昇進を目指すのも効果的です。
館長、課長、主任司書といったポジションに就くことで、基本給だけでなく管理手当や役職手当も支給され、年収が大幅に上がるケースがあります。
特に自治体の図書館では、公務員給与体系に基づく明確な昇給制度が設けられているため、キャリアを積み重ねるほど収入が安定していくでしょう。
管理職になるためには、チーム運営力や人材育成力、予算・企画のマネジメントスキルが求められます。
司書のキャリアと年収の実態を知り、将来の働き方を考えよう
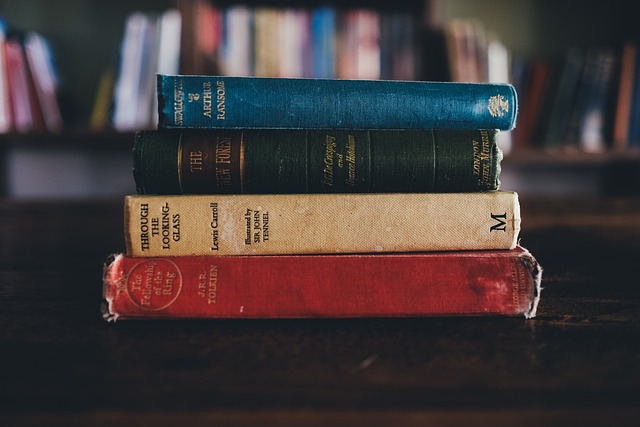
司書は本を扱うだけでなく、情報を整理し、人と知識をつなぐ専門職です。図書館司書や司書教諭など働く場所や役割によって業務内容が異なり、年収も大きく変わります。
平均年収は、約300万円前後とされていますが、雇用形態や勤務先によって格差が生じるのが現実です。非正規雇用の割合が高く、昇給機会が限られている点が課題といえるでしょう。
しかし、専門分野を極めたり、関連資格を取得したり、管理職を目指すことで年収アップを狙うことも可能です。
司書を目指すなら、資格取得からキャリア形成までの道筋を理解し、自分に合った働き方を計画的に考えることが大切でしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














