教師の平均年収を徹底解説|年代・地域・学校別に詳しく紹介
教師の年収は小学校・中学校・高校、さらに私立や公立によっても給与水準は大きく異なります。また、年齢や経験年数、地域によっても年収に差が出るのが実情です。
この記事では、教師の平均年収を年代・地域・学校別に徹底解説。さらに、教師になるために必要な資格や採用までの流れ、キャリアアップで年収を上げる方法まで詳しく紹介します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
教師の仕事内容
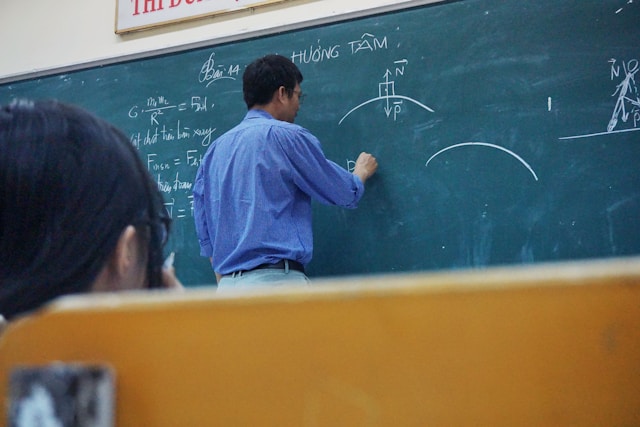
教師の仕事は、子どもたちの成長を支えることが中心ですが、実際には授業以外にも多くの役割があります。
ここでは、公立と私立の違いや担当業務の種類をわかりやすく紹介しましょう。教師を目指す就活生が、働く姿を具体的にイメージできる内容です。
- 教師の主な仕事内容
- 公立と私立の教師の違い
- 担任・教科担当・学年主任などの役割の違い
①教師の主な仕事内容
教師の主な仕事は、授業を通して生徒に学びを提供することです。ただし、実際にはそれだけではありません。生活指導や学校行事の準備、保護者対応など、学校生活を総合的に支える役割も担っています。
特に、担任を持つ場合は、生徒一人ひとりの変化に目を配り、学習面と生活面の両方をサポートします。
放課後には、授業準備や会議があり忙しい日々ですが、生徒の成長を近くで感じられるやりがいがあるでしょう。
最初は、仕事量の多さに驚くかもしれませんが、経験を積むほど効率的に進められるようになります。教師はまさに、子どもの可能性を引き出す専門職といえるでしょう。
②公立と私立の教師の違い
公立と私立の教師では、雇用形態や待遇に違いがあります。公立の教師は地方公務員として働くため、安定した収入や充実した福利厚生が特徴です。
配属先は教育委員会が決めるため、異動の機会が多いこともあります。一方、私立の教師は学校法人に雇われるため、給与や評価制度は学校ごとに異なります。
成果や実績が直接評価に反映されることが多く、頑張り次第で高収入も目指せるでしょう。安定性を重視するなら公立、成果を重視したいなら私立が向いています。
どちらを選んでも、教育の質を高める姿勢が大切です。自分の性格や理想の働き方に合った選択をすることが、長く続けるためのポイントといえます。
③担任・教科担当・学年主任などの役割の違い
学校には、それぞれ異なる役割を持つ教師がいます。担任はクラス運営の中心で、生徒の生活全般を支えます。授業や行事の進行だけでなく、家庭との連携も重要な仕事です。
教科担当は特定の教科を専門的に教え、生徒の理解を深める役割を担います。さらに、学年主任は学年全体をまとめる立場として、担任同士の調整や学校行事の運営を指揮します。
これらの役割は、経験や実績に応じて任命され、責任とともに手当や評価も上がるでしょう。どのポジションも学校運営に欠かせない存在であり、チームで協力しながら教育を支える仕組みになっています。
将来的にどの役割を目指すのかを考えておくと、キャリア形成に役立ちます。
【学校別】教師の平均年収

教師といっても、勤務する学校の種類によって年収は異なります。ここでは、厚生労働省「職業情報提供サイト(jobtag)」の最新データをもとに、小学校から大学までの平均年収をわかりやすく紹介しています。
- 小学校教師の平均年収
- 中学校教師の平均年収
- 高校教師の平均年収
- 特別支援学校教師の平均年収
- 専門学校教師の平均年収
- 大学・短期大学教師の平均年収
①小学校教師の平均年収
小学校教師の平均年収は、約726.5万円です。地方公務員として働く公立小学校の教員は、経験年数に応じて段階的に昇給する安定した給与制度が特徴。
学年が上がるほど責任が増す分、役職手当なども加算される仕組みです。地域によっては、都市手当や通勤手当などが支給されることもあり、総支給額は勤務先によって差が生じます。
子どもの成長を支えながら、安定した収入を得たい人に向いた職業でしょう。
②中学校教師の平均年収
中学校教師の平均年収は、約726.5万円です。中学校では教科担任制が導入されており、特定科目を専門的に教える能力が求められます。
教職調整額や部活動手当など、業務量に応じた報酬制度も整っています。長期的に勤続することで管理職に昇進し、年収が800万円前後に達するケースもあります。
教育の専門性を磨きたい人にとって安定と成長の両方が得られる環境といえるでしょう。
③高校教師の平均年収
高校教師の平均年収は、約678.8万円です。高校は学習内容が専門的になるため、大学での専攻や専門知識を生かして授業を行うのが特徴でしょう。
進路指導や受験対策など責任の重い業務も多いですが、成果が給与に反映されやすい傾向があります。
私立高校では公立校よりも給与水準が高いこともあり、実績次第で年収800万円を超える場合もあるでしょう。専門性と教育力の両方が評価される職種です。
④特別支援学校教師の平均年収
特別支援学校教師の平均年収は、約491万円です。障がいのある児童・生徒に対して個別の支援計画を立て、学習と生活の両面でサポートします。
特別支援教育手当が支給されるため、実際の支給額は平均より高くなることもあります。教育内容は、一人ひとりに合わせた指導が中心で、根気と専門知識が求められる仕事です。
子どもたちの小さな成長を積み重ねて見届けたい人には、非常にやりがいのある職業でしょう。
⑤専門学校教師の平均年収
専門学校教師の平均年収は、約491万円です。ただし、実際の給与は学校法人の規模や、担当する授業数によって変動します。
専門学校では、社会人経験を持つ人が多く、業界で培ったスキルを学生に教える実践的な授業が中心です。年功よりも、実績や担当数で評価される傾向があり、成果に応じて報酬が増えるケースもあります。
教育と実務の両面で、スキルを発揮したい人に向いています。
⑥大学・短期大学教師の平均年収
大学・短期大学教師の平均年収は約1093.3万円です。教授・准教授・講師など職階によって収入差が大きく、教授クラスでは年収900万円を超えることもあります。
国公立大学では安定性が高く、私立大学では研究業績や社会貢献度によって給与が変わります。研究と教育の両立が求められるため、自身の専門分野を深めたい人には理想的な職種でしょう。
学生とともに、学び続けられる環境も魅力のひとつです。
引用:
- 小学校教師 — 職業情報提供サイト(job tag) 小学校教員
- 中学校教師 — 職業情報提供サイト(job tag) 中学校教員
- 高校教師 — 職業情報提供サイト(job tag) 高等学校教員
- 特別支援学校教師 — 職業情報提供サイト(job tag) 特別支援学校教員、特別支援学級教員
- 専門学校教師 — 職業情報提供サイト(job tag) 専門学校教員
- 大学・短期大学教師 — 職業情報提供サイト(job tag) 大学・短期大学教員
【年齢・経験年数別】教師の平均年収

教師の年収は、勤務校種だけでなく年齢や経験年数によっても大きく変わります。
ここでは、厚生労働省のデータや教育業界の実情をもとに、年齢ごとの平均年収の目安を紹介しています。就職後のキャリア形成や、収入の見通しを立てる参考にしてください。
- 小学校教師の年齢・経験年数別平均年収
- 中学校教師の年齢・経験年数別平均年収
- 高校教師の年齢・経験年数別平均年収
- 特別支援学校教師の年齢・経験年数別平均年収
- 専門学校教師の年齢・経験年数別平均年収
- 大学・短期大学教師の年齢・経験年数別平均年収
①小学校教師の年齢・経験年数別平均年収
小学校教師の平均年収は、20代で約400万円前後、30代で約550万円、40代で約650万円、50代では700万円を超えるケースが一般的です。
若手のうちは基本給が少ないものの、毎年の昇給やボーナスで着実に収入が増えていきます。経験年数が長くなるほど管理職への昇進機会も増え、校長クラスになると年収900万円を超えることもあるでしょう。
安定した昇給制度と福利厚生が整っており、長期的なキャリア形成がしやすい職種といえます。
②中学校教師の年齢・経験年数別平均年収
中学校教師の平均年収は、20代で約420万円、30代で約560万円、40代で約670万円、50代で700万円台に達します。
教科担任制を採用しているため、専門知識を深めながらキャリアアップできるのが特徴です。部活動顧問などの担当業務によっては手当も支給され、年齢が上がるごとに収入の幅も広がります。
経験豊富な教師ほど、進路指導や教員育成にも携わる機会が多くなり、収入とやりがいの両立を実感しやすい職業でしょう。
③高校教師の年齢・経験年数別平均年収
高校教師の平均年収は、20代で約430万円、30代で約580万円、40代で約680万円、50代では750万円を超える傾向があります。
高校は、進路指導や大学入試対応など責任の重い業務が多く、経験年数に比例して給与も上がる仕組みです。特に、教頭や校長などの管理職に昇進すれば、年収900万円を超えるケースもあります。
専門性が評価される職場であり、授業力や進学実績に応じて賞与額が増える学校も少なくありません。安定とやりがいを兼ね備えた職種といえるでしょう。
④特別支援学校教師の年齢・経験年数別平均年収
特別支援学校教師の平均年収は、20代で約400万円、30代で約540万円、40代で約650万円、50代で700万円台となっています。
一般校に比べて専門的な対応が求められるため、特別支援教育手当などが支給され、経験年数に応じた加算もあります。
児童・生徒一人ひとりの支援に長期的に携わるため、勤務年数を重ねるほどスキルと信頼が評価されやすい職場です。安定した収入のもとで専門性を深めたい人に向いています。
⑤専門学校教師の年齢・経験年数別平均年収
専門学校教師の平均年収は、20代で約380万円、30代で約480万円、40代で約550万円、50代で600万円前後です。
学校法人の規模や担当コマ数によって収入は変わりますが、実務経験があるほど高い給与が提示される傾向があります。
成果報酬型を採用している学校では、業界経験を生かして、独自の授業を展開することで年収アップも可能です。若手のうちから評価されやすく、スキル次第でキャリアの幅を広げられる仕事といえるでしょう。
⑥大学・短期大学教師の年齢・経験年数別平均年収
大学・短期大学教師の平均年収は、20代で約450万円、30代で約600万円、40代で約750万円、50代では850万円を超えることもあります。
教授・准教授・講師などの職階によって給与が大きく変わるため、経験を重ねるほど年収差が広がる傾向です。
研究業績や学会活動の実績が、昇給や賞与に反映されるケースもあり、努力が直接報われやすい環境といえます。安定した給与と研究の自由度の両方を求める人にとって、魅力的な職業でしょう。
引用:
- 小学校教師 — 職業情報提供サイト(job tag) 小学校教員
- 中学校教師 — 職業情報提供サイト(job tag) 中学校教員
- 高校教師 — 職業情報提供サイト(job tag) 高等学校教員
- 特別支援学校教師 — 職業情報提供サイト(job tag) 特別支援学校教員、特別支援学級教員
- 専門学校教師 — 職業情報提供サイト(job tag) 専門学校教員
- 大学・短期大学教師 — 職業情報提供サイト(job tag) 大学・短期大学教員
【地域別・都道府県別】教師の平均年収

教師の平均年収は、勤務する地域や自治体の財政状況によって大きく変わります。ここでは、小学校から大学まで、それぞれの校種ごとの全国平均年収を基に、地域ごとの傾向を見ていきましょう。
- 小学校教師の地域別・都道府県別平均年収
- 中学校教師の地域別・都道府県別平均年収
- 高校教師の地域別・都道府県別平均年収
- 特別支援学校教師の地域別・都道府県別平均年収
- 専門学校教師の地域別・都道府県別平均年収
- 大学・短期大学教師の地域別・都道府県別平均年収
①小学校教師の地域別・都道府県別平均年収
東京都や神奈川県などの都市部は、地域手当が上乗せされ、平均750万円前後になることもあります。一方で地方では、680万円前後が多く、自治体によって支給額に差が生じています。
生活コストとのバランスを考え、勤務エリアを選ぶことが大切でしょう。
加えて、地域によっては寒冷地手当や住宅補助などの支援制度が整っている場合もあり、実際の手取り額は単純な年収額以上に違いが出ることもあります。
特に、都市圏では交通費や物価が高いため、支給される手当が生活を支える大きな要素となります。
公立と私立の学校間でも待遇に差があり、私立校では独自の給与制度を導入しているケースも少なくありません。
どの地域で働くかを検討する際には、給与水準だけでなく生活のしやすさも重要な視点になるでしょう。
②中学校教師の地域別・都道府県別平均年収
中学校は部活動や進路指導など時間外業務が多く、地域によって手当の支給基準が異なります。
都市部では、年間760万円近くになるケースもあり、勤務先の自治体の給与体系を把握しておくことが重要です。また、
政令指定都市や県庁所在地では教職員の配置数が多く、職務内容が細分化されている傾向があります。そのため、管理職や主任としての役割を担う機会が増えれば、給与水準も上がることが期待できるでしょう。
一方、地方自治体では人員が限られるため、一人の教師が複数の業務を兼任する場合もあり、時間外勤務の割合が高くなりやすい傾向にあります。
こうした労働環境の違いも、地域による年収差を生む要因となっています。勤務を希望する自治体の教育委員会が公開している、給与データを事前に確認しておくと安心です。
③高校教師の地域別・都道府県別平均年収
東京都や愛知県などの都市部では、720万円を超える傾向があり、地方では650万円前後が一般的です。地域手当や通勤補助などの制度も異なるため、応募前に確認しておくと安心でしょう。
さらに、高校は大学進学を意識した指導や、専門教科の授業が中心になるため、教員の専門性が給与に反映されやすい特徴があります。
理系や外国語など、専門性の高い教科を担当する教師は、教員採用の際にも需要が高く、キャリアを積むことで昇給スピードが上がることも。
また、私立高校の場合は、学校ごとの経営方針により給与水準が大きく異なり、学費が高い進学校ほど年収が高い傾向です。地域だけでなく、学校の教育方針や進学実績も年収に影響する要素といえるでしょう。
④特別支援学校教師の地域別・都道府県別平均年収
都市部では、特別手当や加配制度が充実しており、待遇がやや高めになる傾向があります。地方では平均に近い水準ですが、生活費の負担が少ないため実質的な生活水準は大きく変わらないでしょう。
さらに、特別支援学校では教員1人あたりの生徒数が少なく、きめ細やかな指導が求められるため、勤務環境に応じた手当が支給されるケースがあります。
地域によっては、専門資格の取得支援制度や、障がい支援に特化した研修制度が整っており、スキルアップがそのまま収入に反映されやすい職場環境です。
地方自治体の中には、支援教育を推進するために独自の加算制度を設けている例もあります。給与水準だけでなく、働きやすさやサポート体制にも地域差が出やすい職種といえるでしょう。
⑤専門学校教師の地域別・都道府県別平均年収
私立学校が中心のため、地域よりも学校法人の規模や経営状況によって差が出やすい職種です。東京や大阪などでは550万円前後、地方では450万円前後が一般的でしょう。
実務経験や資格を活かせば、収入アップも期待できます。また、専門学校は分野ごとに求められるスキルが異なるため、たとえば医療・IT・デザインなど人気分野では高い給与が提示されることも。
地方でも、地域の産業に直結した学科を持つ学校では待遇が良く、教員が企業研修や外部講師として活動することで収入を補うケースも増えています。
授業以外の活動や社会連携プロジェクトに積極的に参加することが、キャリアアップや年収向上につながるでしょう。
⑥大学・短期大学教師の地域別・都道府県別平均年収
都市部の私立大学では、1,200万円を超える例もあり、地方の国立大学では900万円台が中心です。職位(教授・准教授・講師)によって差が大きく、研究実績や教育経験が評価のカギになります。
大学教員は、教育だけでなく研究活動や論文発表、学会活動なども重要な職務に含まれるため、研究費の配分や外部資金の獲得実績が年収に影響することがあるでしょう。
特に、首都圏や関西圏の有名私立大学では、研究実績が給与査定に直結し、教授クラスになると1,500万円を超えるケースもあります。
一方で、地方大学では学生数の減少や予算削減の影響を受け、給与水準が抑えられる傾向です。教育・研究の両面で成果を上げることが、安定した収入と昇進につながるといえるでしょう。
引用:
- 小学校教師 — 職業情報提供サイト(job tag) 小学校教員
- 中学校教師 — 職業情報提供サイト(job tag) 中学校教員
- 高校教師 — 職業情報提供サイト(job tag) 高等学校教員
- 特別支援学校教師 — 職業情報提供サイト(job tag) 特別支援学校教員、特別支援学級教員
- 専門学校教師 — 職業情報提供サイト(job tag) 専門学校教員
- 大学・短期大学教師 — 職業情報提供サイト(job tag) 大学・短期大学教員
教師になるためのステップ

教師になるには、資格の取得から採用試験、現場でのキャリア形成までいくつかの段階を踏む必要があります。
ここでは、大学進学から免許取得、採用試験、そして実際に教壇に立つまでの流れをわかりやすく解説しています。将来の進路を考えている方は、自分に合った道をイメージしながら確認してみてください。
- 教師になるために必要な資格と免許状の種類
- 教員免許を取得するための大学・学部選び
- 教職課程で学ぶ内容と単位取得の流れ
- 教員採用試験の概要と合格までのスケジュール
- 採用後の研修と教師としてのキャリアスタート
①教師になるために必要な資格と免許状の種類
教師を目指すには、まず「教員免許状」を取得する必要があります。免許には「幼稚園」「小学校」「中学校」「高等学校」「特別支援学校」などの種類があり、それぞれ担当できる教育段階が異なります。
また、免許状には「一種」「二種」「専修」の3種類があり、大学卒業で取得できるのは主に「一種免許状」です。さらに、大学院を修了すれば「専修免許状」を取得できます。
教員免許は、各都道府県の教育委員会が発行し、指定された課程を修了すれば申請できます。自分が目指す学校の種別に応じて、どの免許が必要かを早めに確認しておくことが大切でしょう。
②教員免許を取得するための大学・学部選び
教員免許を取得するには、文部科学省が認定する「教職課程」が設置された大学・学部に進学する必要があります。教育学部はもちろん、文学部や理学部などでも教職課程を履修すれば免許の取得が可能です。
たとえば、小学校教員を目指すなら、教育学部の初等教育課程が一般的で、中学校や高校教員を目指す場合は、専門科目を学べる学部を選ぶのが良いでしょう。
大学によって取得に必要な単位数や実習内容が異なるため、入学前にカリキュラムを確認しておくと安心です。興味や得意分野に合った学部を選ぶことで、教員としての学びがより実りあるものになるでしょう。
③教職課程で学ぶ内容と単位取得の流れ
教職課程では、教育の専門知識や指導法、児童生徒理解などを体系的に学びます。主な科目には「教育原理」「教育心理学」「教育方法論」などがあり、加えて教育実習も必修です。
多くの大学では、2〜3年次に教育実習を実施し、実際の授業運営や子どもとの関わりを体験します。単位取得には計画性が求められるため、早い段階から履修計画を立てることが大切です。
また、教職課程以外にも専門科目や一般教養科目が必要なため、学業全体のバランスを意識しましょう。教育実習を通して得られる実践的な経験は、教師としての成長に欠かせません。
④教員採用試験の概要と合格までのスケジュール
公立学校で働くには、各都道府県や政令指定都市が実施する「教員採用試験」の合格が必須です。試験内容は筆記試験(専門・一般教養)に加え、面接、論作文、実技試験など多岐にわたります。
一般的に試験は大学4年生の夏頃に実施されるため、3年生の秋ごろから本格的な勉強を始めるのが理想です。合格後は採用候補者名簿に登録され、翌年4月に正式採用となります。
私立学校を希望する場合は、各学校や法人が独自に実施する採用試験を受験します。自治体によって出題傾向や日程が異なるため、早めに情報を調べて計画的に準備を進めてください。
⑤採用後の研修と教師としてのキャリアスタート
採用後は、1年間の「新任研修」を通して教育現場での実践力を磨きます。授業づくりや学級運営、保護者対応などを学びながら、先輩教員からの指導を受ける形です。
研修中も正規教員として給与が支給されるため、安心して現場経験を積めます。その後も3年目・10年目といった節目ごとに研修があり、長期的にスキルアップを図れるのが特徴です。
経験を重ねることで、学年主任や教務主任、さらには管理職へのキャリアパスも開けます。教師は学び続ける姿勢が求められる職業であり、努力が確実に成長とやりがいにつながる仕事といえるでしょう。
教師に向いている人の特徴

教師は、知識を教えるだけでなく、子どもたちの成長を支え、人として導く重要な役割を担います。
ここでは、教師に向いている人の特徴を具体的に紹介します。自分の性格や考え方と照らし合わせながら、教育現場で活躍できるタイプかどうかを確認してみてください。
- 子どもに愛情を持って関われる人
- コミュニケーション能力が高い人
- 授業づくり・教えることが好きな人
- ストレス耐性・ポジティブ思考を持つ人
- 変化に柔軟に対応できる人
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①子どもに愛情を持って関われる人
教師に最も求められるのは、子どもに対する深い愛情と理解です。子どもは日々成長する中で失敗や葛藤を経験します。その過程を支えるには、結果だけでなく努力を認め、温かく見守る姿勢が大切です。
たとえ問題行動があっても、叱るだけで終わらず、なぜそうなったのかを一緒に考える姿勢が必要でしょう。信頼関係を築くことで、子どもは安心して学びに向かえるようになります。
教育現場では、知識以上に「人を思いやる心」が重要な資質といえます。
②コミュニケーション能力が高い人
教師は、生徒だけでなく保護者や同僚、地域の人々など多くの人と関わります。そのため、相手の立場を理解し、わかりやすく伝える力が必要です。
特に保護者とのやりとりでは、家庭と学校をつなぐ役割を果たすため、丁寧で誠実な対応が求められます。また、同僚との協力や情報共有も、円滑な学校運営には欠かせません。
相手の話をしっかり聞き、自分の意見を適切に伝えられる人は、職場でも信頼を得やすいでしょう。コミュニケーション力は、教育の質を高めるうえで欠かせないスキルです。
③授業づくり・教えることが好きな人
「教えることが好き」という気持ちは、教師としての大きな原動力になります。授業の内容を工夫し、子どもたちの反応を見ながら改善を重ねていくことに喜びを感じられる人は、この仕事に向いています。
また、教科書の内容をただ伝えるのではなく、「どうすれば理解しやすいか」「どうすれば興味を持ってもらえるか」を考える工夫も欠かせません。
授業づくりは試行錯誤の連続ですが、生徒が理解して笑顔を見せた瞬間の喜びは格別です。教育に情熱を持てる人ほど、長く続けられる仕事といえるでしょう。
④ストレス耐性・ポジティブ思考を持つ人
教師の仕事は、授業だけでなく、行事や保護者対応、学級運営など多岐にわたります。その中で思い通りに進まないことや、プレッシャーを感じる場面も少なくありません。
そんなときこそ、ストレスを前向きに受け止め、気持ちを切り替えられる力が大切です。落ち込んでも次にどう活かすかを考えられる人は、現場でも長く活躍できるでしょう。
また、失敗を恐れず挑戦する姿勢は、子どもたちの手本にもなります。ポジティブな考え方を持ち続けることで、毎日の仕事にやりがいを感じられるはずです。
⑤変化に柔軟に対応できる人
教育現場は、常に変化しています。ICT教育の導入や学習指導要領の改訂、子どもたちの多様化など、時代とともに求められる力も変わってきました。
こうした変化に柔軟に対応し、自ら学び続ける姿勢を持つことが重要です。また、子どもの個性や成長スピードもさまざまであるため、一律の指導ではうまくいかないこともあります。
状況に応じて柔軟に対応し、新しい方法を取り入れられる人は、教育の現場で大きな力を発揮できるでしょう。学びを楽しみながら成長できる人にこそ、教師という仕事は向いています。
教師の魅力・やりがい

教師という仕事には、他の職業では得られない魅力ややりがいがあります。安定した待遇だけでなく、人の成長に関われる喜びや社会への貢献など、人生を通して誇りを持てる職業といえるでしょう。
ここでは、教師という仕事の魅力を5つの視点から紹介します。
- 人の成長を支える喜びがある
- 安定した収入と福利厚生が充実している
- 家庭や子育てと両立しやすい働き方ができる
- 社会に貢献できる誇りと使命感を感じられる
- 自分自身も成長し続けられる環境がある
①人の成長を支える喜びがある
教師の一番のやりがいは、子どもたちの成長を身近で感じられることです。できなかったことができるようになる瞬間や、生徒が自信を持ちはじめる姿を見ると、大きな喜びと達成感を得られます。
学習面だけでなく、挨拶や思いやりといった日常の成長も感じられるでしょう。また、卒業後に「先生のおかげで頑張れました」と感謝されることもあります。
人の人生に関われる喜びを実感できるのは、教師という仕事ならではの魅力です。
②安定した収入と福利厚生が充実している
教師は公務員として働くケースが多く、安定した収入と充実した福利厚生が魅力です。年齢や勤続年数に応じて昇給があり、ボーナスも年2回支給されます。
住居手当や扶養手当、通勤手当などの各種手当も整っており、経済面での安心感が得られるでしょう。また、有給休暇や育児休業などの制度も利用しやすく、ライフステージが変わっても働きやすい環境です。
安定した基盤のもと、安心してキャリアを築ける点も教師の大きな魅力といえます。
③家庭や子育てと両立しやすい働き方ができる
教師の仕事は、家庭や子育てとの両立がしやすい働き方といえます。授業や行事のスケジュールが年間で決まっているため、生活リズムを整えやすいことが特徴です。
さらに、夏休みや冬休みなどの長期休暇もあり、家族と過ごす時間を確保しやすいでしょう。育児休業や時短勤務制度も整備されているため、子育て中の教員も安心して働けます。
仕事とプライベートのバランスを重視したい人にとって、教師という職業は理想的な選択肢の1つです。
④社会に貢献できる誇りと使命感を感じられる
教師は、社会の未来を担う人材を育てるという重要な役割を担っています。日々の授業や指導を通して、子どもたちに学ぶ楽しさや生きる力を伝えることができます。
自分の働きが生徒の成長につながり、ひいては社会の発展にも貢献していると感じられるのは、教師ならではのやりがいでしょう。
また、教育を通して地域社会と深く関わることで、「自分の仕事が誰かのためになっている」という誇りを持てます。使命感を持って働きたい人にとって、教師は大きなやりがいを感じられる職業です。
⑤自分自身も成長し続けられる環境がある
教師は教える立場でありながら、自分自身も常に学び続ける職業です。社会の変化に合わせて新しい知識や教育方法を身につける必要があり、学びを重ねるほど授業の質も高まります。
また、子どもたちとの関わりを通じて新しい価値観を得たり、自分の人間性を磨いたりできるのも教師の魅力です。さらに、研修や自己啓発の機会も多く、学び続ける姿勢が自然と身につきます。
自分の成長を実感しながら働きたい人にとって、教師は長く続ける価値のある仕事といえるでしょう。
教師が年収を上げる方法

教師は安定した職業というイメージがありますが、工夫や努力次第で年収を上げることも可能です。
ここでは、キャリアを積みながら収入を増やすための具体的な方法を紹介します。自分の将来像を描くうえで、どのようなステップがあるのかを理解しておきましょう。
- 勤続年数を重ねて昇給・昇進を目指す
- 主任・管理職ポジションにキャリアアップする
- 私立学校や高給与エリアへの転職を検討する
- 副業や資格取得でスキルを活かす
①勤続年数を重ねて昇給・昇進を目指す
教師の年収を上げる基本的な方法は、勤続年数を重ねて昇給・昇進を目指すことです。公立学校の教員は地方公務員として勤務しており、経験年数に応じて基本給が自動的に上がる仕組みになっています。
さらに、昇任試験に合格すれば役職が上がり、年収も大きく増えます。たとえば、教諭から主幹教諭、副校長、校長へと昇進すると、年収が数百万円単位で変わる場合もあるでしょう。
日々の業務に真摯に取り組みながら、長期的な視点でキャリア形成を意識することが大切です。
②主任・管理職ポジションにキャリアアップする
学校内で、主任や管理職などのポジションに就くと、役職手当が支給されるため年収アップにつながります。主任は学年や教科をまとめる立場として、教育現場の中心的な役割を担っています。
責任は重くなりますが、教育現場をリードするやりがいも大きいです。さらに、副校長や校長といった管理職になると、年収は700万円〜900万円前後に達することもあります。
管理職を目指すには、リーダーシップやマネジメント力が求められますが、挑戦する価値のあるキャリアパスといえるでしょう。
③私立学校や高給与エリアへの転職を検討する
公立校だけでなく、私立学校や都市部の学校への転職を考えるのも、年収アップの方法です。私立学校は、経営母体によって給与体系が異なり、公立よりも高い給与水準が設定されている場合があります。
特に、進学校や有名私立校では、専門性や指導力が評価され、年収600万円以上を得ることも可能です。
また、首都圏など物価の高い地域では、地域手当や住宅手当が充実していることもあり、実質的な手取り額が増えるケースもあります。
転職の際は、給与だけでなく働き方や教育方針との相性も確認しておくとよいでしょう。
④副業や資格取得でスキルを活かす
近年は、自治体によっては、教員の副業が一部認められるようになってきました。教育関連のライティングやオンライン家庭教師、教材制作など、自身のスキルを活かした副業で収入を得ることができます。
また、資格を取得して新たな分野に挑戦するのも有効です。たとえば、心理学やキャリアコンサルタント、ICT教育関連の資格を取得すれば、教育現場以外の場でも活躍の幅を広げられるでしょう。
本業に支障をきたさない範囲で、スキルアップを目指すことが収入向上への第一歩になります。
教師という仕事で安定と成長を手に入れるために

教師の年収は、勤務先の種類や経験年数、地域によって大きく異なりますが、安定した収入と社会的意義のある仕事として高い人気を誇ります。
結論から言うと、教師は「安定性」と「やりがい」を両立できる職業です。公立・私立の違いや、小・中・高校、大学など勤務先ごとの平均年収を理解することで、自分に合った働き方を見極めやすくなります。
また、資格取得や採用試験を経てキャリアを積む過程では、努力に応じて昇給や昇進のチャンスも得られるはずです。
さらに、教師に向いている人の特徴や魅力を知ることで、仕事への理解が深まり、長く続けるためのモチベーションにつながるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














