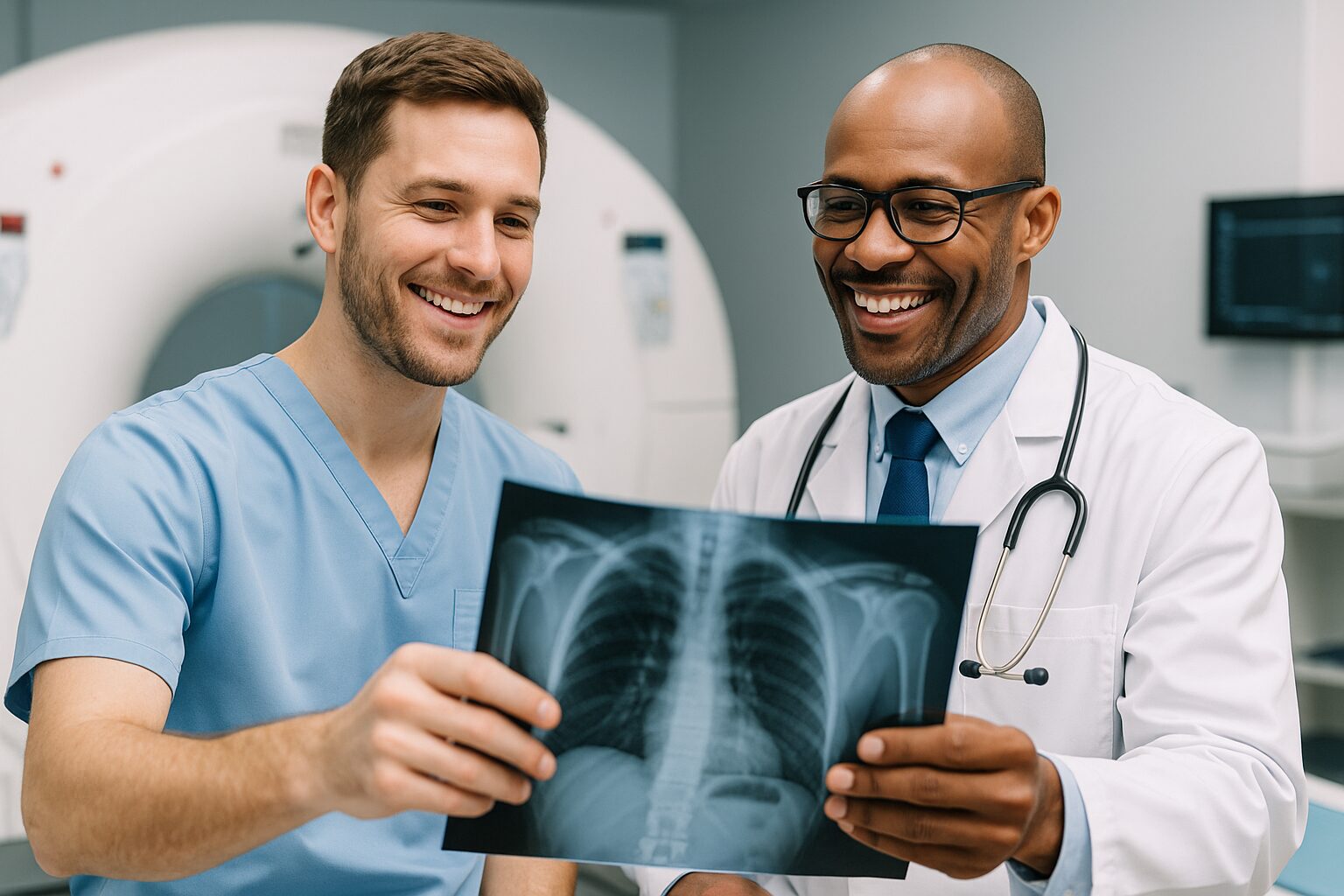言語聴覚士の平均年収はいくら?年代・職場別の相場を徹底解説
医療・福祉・教育など幅広い分野で活躍する国家資格でありながら、言語聴覚士の実態は意外と知られていません。
本記事では、年代別・職場別の平均年収や収入を上げるためのポイントを詳しく解説し、将来性やキャリアアップの道筋、国家資格取得までのステップも紹介します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
言語聴覚士とは?

言語聴覚士とは、ことばや聞こえ、食べることなど、コミュニケーションや摂食に関する困りごとを専門的に支援する国家資格の専門職です。
人が社会で生活するうえで欠かせない「話す」「聞く」「食べる」という基本的な働きを支える役割を担っています。
具体的には、発達の過程でことばの遅れが見られる子どもや、病気やけがで話す力を失った大人などに対して、専門的な訓練や助言を行います。
単なるリハビリ職ではなく、心理面や社会的な側面にも配慮しながら、本人の生活の質を高めることが求められる仕事です。また、医療・福祉・教育など幅広い分野で活躍できる点も特徴といえます。
言語聴覚士とは、人の声と想いをつなぎ、日常の中で「伝える喜び」を支える専門家なのです。
言語聴覚士の仕事内容

言語聴覚士(ST)は、ことば・聞こえ・聞く・食べるといった人の基本的な生活機能に深く関わる専門職です。医療・福祉・教育など幅広い分野で活躍し、年齢や症状に合わせたサポートを行います。
ここでは、分野ごとの仕事内容を具体的に紹介します。
- 発達障害児への言語訓練支援
- 高齢者の嚥下障害リハビリ
- 失語症患者へのコミュニケーション訓練
- 発声・発音障害への指導と訓練
- 小児の言語発達支援と家族指導
- 医療チーム・多職種連携の役割
- 訪問リハビリ・地域支援活動
- 教育・研究・講師としての活動
①発達障害児への言語訓練支援
発達障害のある子どもは、ことばの理解や発音、会話のやりとりに課題を抱えることが多いです。言語聴覚士は、子どもの個性や成長段階に合わせて、無理なく楽しめる訓練を行います。
発音練習や語彙の増加、会話の流れを学ぶトレーニングなどを通じ、自然なコミュニケーション力を育てていきます。
また、家庭での関わり方も非常に重要です。保護者には、家庭でできる声かけ方法や遊びを通じた学び方をアドバイスし、訓練の効果を日常生活へつなげます。
さらに、保育園や学校との連携を図り、生活全体で成長をサポートするのも大切な役割です。こうした支援により、子どもがことばに自信を持ち、他者と関わる力を伸ばしていけるでしょう。
②高齢者の嚥下障害リハビリ
高齢になると、加齢や脳血管疾患などの影響で飲み込みにくさを感じる方が増えます。言語聴覚士は、嚥下機能の低下を評価し、個人に合った訓練を行う専門家です。
たとえば、舌やのどの筋肉を動かす体操、呼吸と飲み込みのタイミングを合わせる練習などがあります。これにより、食事中のむせや誤嚥を防ぎ、安全に食べられるよう支援します。
加えて、栄養士や看護師、介護士と協力し、食事内容や姿勢、食器の工夫なども提案します。食べる行為は生きる意欲に直結するため、再び自分の口で食事を楽しめることは大きな喜びです。
言語聴覚士は、食べる力を取り戻すことで、心身両面の健康を支えています。
③失語症患者へのコミュニケーション訓練
脳卒中や頭部外傷などで失語症になると、言葉を理解したり発したりする力が低下します。言語聴覚士は、患者一人ひとりの症状に合わせ、ことばの再獲得を目指して訓練を行います。
具体的には、単語を思い出す練習、文を構成する訓練、音読や書字のトレーニングなどを段階的に実施します。
さらに、言葉以外の伝達手段として、ジェスチャーや絵カード、電子機器を用いたコミュニケーション支援も行います。
家族や周囲の人に対しては、患者が伝えやすい方法を理解してもらうための指導を行い、社会とのつながりを保てるようにサポートします。
失語症のリハビリは長期にわたることもありますが、少しずつ話せるようになる喜びは、本人にとってかけがえのない希望となるでしょう。
④発声・発音障害への指導と訓練
声が出にくい、発音が不明瞭などの悩みは、日常生活だけでなく職場でのコミュニケーションにも影響します。
言語聴覚士は、発声に関わる筋肉や呼吸の使い方を整えることで、自然で明瞭な話し方を身につけるサポートを行います。
具体的には、腹式呼吸の訓練、声帯のバランス調整、音の響きの改善などを行い、無理なく話せる声を育てていきます。
教師やアナウンサー、接客業など、声を使う職業の方が相談するケースも多く、声の専門家として信頼されています。
発声訓練を続けることで、発音の改善だけでなく自分の声への意識が変わり、より自信を持って人と話せるようになるでしょう。
⑤小児の言語発達支援と家族指導
言葉の発達に遅れが見られる子どもには、成長に合わせた段階的な支援が必要です。言語聴覚士は、単語の理解・文の構成・会話のキャッチボールなどを、子どものペースに合わせて丁寧に訓練します。
遊びや絵本、音楽などを活用しながら、自然な形でことばを学べる環境をつくるのも特徴です。
また、家庭での関わり方が訓練の効果を大きく左右します。
そのため、保護者には声かけや遊び方の工夫、家庭でできる練習方法を具体的に伝えます。
言語発達の支援は、単に「話せるようにする」ことが目的ではなく、自己表現の力や他者との信頼関係を育むことでもあります。
家族が一体となって子どもの成長を見守ることで、より豊かな発達が促されるでしょう。
⑥医療チーム・多職種連携の役割
言語聴覚士は、医師・看護師・理学療法士・作業療法士などと連携し、患者の回復を総合的に支援します。
嚥下や発声だけでなく、呼吸・栄養・生活動作などの情報を共有し、最適なリハビリ計画を立てるのです。多職種が協力することで、患者の身体面・精神面の両方をきめ細かく支えることができます。
また、チーム内では言語や嚥下の専門家として意見を発信し、医療現場の質向上にも貢献します。こうした連携を通じて、言語聴覚士は「チーム医療の要」として重要な役割を担っているといえるでしょう。
患者一人ひとりの生活を支えるためには、専門知識だけでなく柔軟な対応力も欠かせません。
⑦訪問リハビリ・地域支援活動
退院後も、ことばや食事に不自由を感じる人は少なくありません。言語聴覚士は、自宅や介護施設に出向き、実際の生活環境に合わせた支援を行います。
たとえば、食卓やベッドでの嚥下訓練、家族への介助指導などを行い、生活に直結するサポートを提供します。
また、地域の保健センターや学校などで講座を開き、言語発達や嚥下障害に関する正しい知識を広める活動も行っています。
地域の人々が困りごとを早期に相談できる体制を整えることで、予防や早期改善にもつながります。訪問リハビリは、医療の枠を超えた「地域の支え」としての役割を果たしているのです。
⑧教育・研究・講師としての活動
言語聴覚士は、臨床だけでなく教育や研究の分野でも大きな活躍をしています。大学や専門学校では、将来の言語聴覚士を育てる教育者として、実践的な知識や技術を伝えます。
研究分野では、臨床データをもとに新しいリハビリ方法や支援技術の開発に取り組み、専門領域の発展に貢献しています。
また、講演や研修を通じて現場のスタッフや地域住民に最新の情報を伝えることもあります。臨床で培った経験を教育・研究へ還元することで、医療福祉全体の質を高めることができるのです。
言語聴覚士のキャリアは幅広く、長く続けるほど社会的価値が増していく職業といえるでしょう。
言語聴覚士の平均年収はどのくらい?

言語聴覚士(ST)の平均年収は、おおむね約432万円前後とされています。厚生労働省の令和5年度賃金構造基本統計調査によると、月給は30万円前後、年間賞与を含めると400万円台前半となる傾向です。
この数字は同じリハビリ職である理学療法士や作業療法士と近い水準であり、医療系国家資格の中では中間的な位置にあります。
初任給はおおよそ20万円前後からスタートし、経験を重ねることで徐々に昇給していきます。また、勤務先の規模や地域によっても年収には差があります。
大都市圏では比較的高く、地方ではやや低い傾向です。総合病院や医療法人などでは安定した収入が期待できますが、個人クリニックや介護施設では給与水準が抑えられる場合もあります。
今後は高齢化の進行により需要がさらに高まることが予想され、将来的にも安定した働き方ができる職種です。
引用:
【年代別】言語聴覚士の年収相場

言語聴覚士(ST)は、年齢や経験に応じて年収に幅が出やすい職種です。勤務先、勤務地、役職などの条件も強く影響するため、年代別相場を知っておくことはキャリア設計において極めて大切でしょう。
ここでは、20代〜50代を中心に平均年収傾向を紹介します。
- 20代の平均年収
- 30代の平均年収
- 40代の平均年収
- 50代の平均年収
①20代の平均年収
20代の言語聴覚士の平均年収は、おおよそ300万〜380万円あたりと見られています。初任給は月収約22万円〜25万円程度という調査もあり、ボーナスを合わせても年収300万円台後半が多いようです。
経験が浅いうちは業務の幅は限られがちで、昇給ペースも緩やかでしょう。ただし、現場を積極的に経験し、高頻度な症例や研修機会を獲得すれば、3〜5年目以降に年収アップの可能性が高まります。
勤務先を病院からリハビリ施設・訪問リハビリへ転じる選択も、働き方の柔軟性や収入を考えるうえで有力な戦略です。
②30代の平均年収
30代では、平均年収は約380万〜460万円程度まで上昇する傾向があります。この年代になると、医療機関や施設での責任ある業務を任されることが増え、役職手当の付与も見られるようになります。
また家庭を持つ方も多いため、収入の安定性を重視する動きも強くなります。収入をさらに上げたいなら、認定言語聴覚士などの専門資格取得や、管理職昇格を目指すのが有効です。
転職や夜勤なしの勤務形態への切り替えも検討に値します。
③40代の平均年収
40代では、平均年収はおよそ450万〜550万円のレンジに達することが多いようです。
この年代になると、主任・リーダーやチームマネジメントなどを担当することが多くなり、手当の上乗せ要素が強くなります。
加えて、在宅医療や訪問リハビリ需要の高まりによって報酬が高めに設定されるケースもあります。ただし、勤続年数が多くなると昇給の伸びが鈍化しやすく、転職や副業も有効な選択肢になるかもしれません。
④50代の平均年収
50代になると、平均年収は約480万〜600万円台になる可能性があります。この年代では、管理職や教育・指導役としての責務を担うことが多いため、経験・貢献度による評価が反映されやすくなります。
ただし、年功序列型の給与体系が残る職場では昇給が緩やかになりやすく、実質的年収が横ばいになるケースも散見されます。
こうした中で、地域包括ケアや学校・教育分野などでの役割を広げることで、収入の多角化を図る人もいます。
引用:
【経験年数別】言語聴覚士の年収相場

言語聴覚士の年収は、経験を重ねるほど上昇する傾向があります。ただし、伸び幅には限度があり、勤務先や地域、役割によって大きく変わります。ここでは、経験年数ごとの年収相場を見ていきましょう。
- 新人・1〜3年目の平均年収
- 5〜10年目の中堅期の平均年収
- 10年以上のベテラン層の平均年収
①新人・1〜3年目の平均年収
最初の数年は、年収よりも経験を積むことが優先されます。
言語聴覚士を含むリハビリ職種の平均年収はおよそ430万円前後とされますが、これは全体の平均であり、新人期ではこの水準に届かないことが一般的です。
初任給は月22万円〜26万円ほどが多く、ボーナスを含めても年収300万円前後にとどまるケースが多いでしょう。新人期は、症例経験や対応力、評価技術を身につける時間です。
焦らず学びを重ねることが、将来的な年収アップにつながります。経験を積むことで患者との信頼関係が深まり、数年後には昇給のチャンスも期待できます。
②5〜10年目の中堅期の平均年収
5年から10年ほど経験を重ねた中堅層では、役割や責任が増えることで年収の上昇が見込めます。
年収は400〜500万円程度が目安で、後輩指導やリハビリ計画の作成など、リーダー的な立場を担うことも増えます。この時期は専門分野を磨くことが重要です。
摂食嚥下、高次脳機能障害、発音障害など、特定の領域で専門性を高めることで、職場での評価が上がり、より待遇のよい職場への転職も現実的になります
資格の追加取得や学会参加を通じてキャリアを広げることも、安定した収入を得るうえで有効です。
③10年以上のベテラン層の平均年収
10年以上のキャリアを持つベテラン層では、年収は500〜600万円前後が相場とされています。経験豊富な人材は管理職としてチームをまとめたり、教育機関で講師として活躍したりすることもあります。
臨床経験の深さから、患者や家族からの信頼も厚く、職場の中心的な存在となることが多いでしょう。ただし、ある程度の年数を超えると年収の伸びが緩やかになる傾向もあります。
さらに収入を増やすためには、転職や独立といった選択も考えられます。特に訪問リハビリやフリーランスとして働く形は、経験を活かしつつ働き方を自由に選べる方法として注目されています。
これまで培った知識と技術を生かし、キャリアの幅を広げることが高年収への近道です。
引用:
- 厚生労働省「令和5年度 賃金構造基本統計調査」
- 厚生労働省「労働経済の分析(労働白書)」
- 独立行政法人 国立病院機構 横浜医療センター 言語聴覚士採用情報
- 日本福祉大学 言語聴覚士の仕事内容・給与紹介ページ
- OpenWork「医療・福祉業界 言語聴覚士の年収・評価情報」
【職場別】言語聴覚士年収相場(病院・施設・クリニックなど)

言語聴覚士の年収は、勤務する職場によって大きく変わります。
病院やクリニック、福祉施設、在宅支援、さらには企業や研究職など、多様な働き方があるため、自分に合った環境を選ぶうえで「どこがどのくらいの年収か」を知ることは重要です。
ここでは職場別に平均年収とその特徴をわかりやすく紹介します。
- 総合病院・大学病院での平均年収
- リハビリ専門病院・クリニックの平均年収
- 介護老人保健施設・福祉施設の平均年収
- 訪問リハビリ・在宅支援での平均年収
- 企業・教育機関・研究職での平均年収
- フリーランス・開業STの平均年収
①総合病院・大学病院での平均年収
総合病院や大学病院で働く言語聴覚士の平均年収は、約380万〜450万円ほどです。大規模な病院では症例数が多く、医師や他職種との連携も活発なため、臨床経験を積むには最適な環境でしょう。
ただし、給与は公的機関の給与体系に基づくことが多く、昇給は勤続年数に応じて段階的に上がる仕組みです。キャリア初期は収入より経験を重視する人が多く、安定を求める傾向にあります。
大学病院では研究協力手当などがつく場合もあり、安定した収入と専門的なスキルを磨ける職場といえます。安定・専門性・経験値を重視したい人に適しています。
②リハビリ専門病院・クリニックの平均年収
リハビリ専門病院やクリニックでの平均年収は、およそ350万〜420万円ほどです。総合病院に比べ規模は小さいですが、リハビリに特化しており、患者と密に関わることができます。
脳血管障害や高次脳機能障害など、特定の分野に集中してスキルを磨ける点が強みです。多くが民間運営のため、経営状況によって給与に差が出やすいのが実情です。
ただし、主任や管理職に昇進すれば年収500万円を超えることもあります。専門性を生かして患者とじっくり向き合いたい人に向いた環境でしょう。
③介護老人保健施設・福祉施設の平均年収
介護老人保健施設や福祉施設で働く言語聴覚士の平均年収は、330万〜400万円前後です。
高齢者を対象に、嚥下や発声訓練を中心に支援することが多く、医療よりも「生活の質」を支える側面が強い仕事です。夜勤が少なく、勤務時間が安定している点は大きな魅力といえます。
一方で、介護保険制度の影響を受けるため、報酬水準はやや低めです。収入よりもワークライフバランスを大切にしたい人や、利用者と長く関わりたい人には働きやすい職場でしょう。
④訪問リハビリ・在宅支援での平均年収
訪問リハビリや在宅支援で働く言語聴覚士の平均年収は、400万〜500万円程度と比較的高めです。訪問リハでは1件あたりの報酬単価が高く、件数に応じて収入が変動する歩合制の事業所もあります。
利用者の自宅を訪問し、直接支援を行うため、コミュニケーション力や自己管理力が求められます。経験を積むことで独立を目指す人も多く、自分の裁量で働きたい人にとって魅力的な分野です。
ただし、移動やスケジュール管理の負担があるため、効率的な働き方を意識することが必要でしょう。
⑤企業・教育機関・研究職での平均年収
企業や教育機関、研究職に就く言語聴覚士の平均年収は、450万〜550万円ほどです。現場よりも研究や教育、製品開発などに関わるケースが多く、知識や分析力が重視されます。
大学や研究機関では、学位や論文発表が求められる場合もありますが、その分安定した給与体系で、知的好奇心を満たせる職場です。
臨床現場とは違う形で専門性を発揮したい人には、やりがいを感じられる分野でしょう。
⑥フリーランス・開業STの平均年収
フリーランスや開業した言語聴覚士の年収は、300万〜700万円以上と幅があります。完全歩合制のため、スキルや集客力によって収入は大きく変わるのが特徴です。
訪問リハやセミナー講師、オンラインレッスンなど複数の仕事を組み合わせることで、年収1000万円を超える人もいます。ただし、安定した収入を得るまでには営業や経営努力が欠かせません。
働く時間や場所を自由に決めたい人、挑戦心のある人に向いた働き方です。職場によって年収だけでなく、働き方やキャリアの方向性も大きく異なります。
自分の価値観や目標に合ったフィールドを選ぶことが、長く満足して働くための大切なポイントでしょう。
引用:
言語聴覚士の年収を上げる方法

言語聴覚士として働くうえで「収入をどう上げるか」は多くの人が抱える課題です。経験を重ねるだけでなく、専門性や働き方を工夫することで収入アップは十分可能でしょう。
ここでは、キャリアアップやスキル向上、転職や副業など、年収を上げるための現実的な方法を紹介します。
- 経験を積んで専門スキルを高める
- 認定資格や専門資格を取得する
- 管理職や主任職に昇進する
- 給与の高い職場へ転職する
- 副業や講師活動で収入源を増やす
- フリーランスや独立開業に挑戦する
①経験を積んで専門スキルを高める
言語聴覚士の年収を上げるための基本は、日々の臨床を通じて経験を積み、専門スキルを磨くことです。経験を重ねることで対応できる症例が増え、職場での信頼や評価が向上します。
とくに嚥下障害、小児発達、失語症など特定分野に強みを持つことで「この分野なら任せたい」と思われる存在になれるでしょう。
こうした専門性の高さは昇給や役職登用につながりやすく、転職市場でも高く評価されます。
また、学会や研修に積極的に参加して最新の治療知識を取り入れることで、実践力と理論の両面からスキルを磨くことが可能です。地道な努力の積み重ねが、将来的に安定した収入アップへとつながります。
さらに後輩や学生の指導を通じて知識を整理することも、自身のスキル向上に効果的です。
②認定資格や専門資格を取得する
資格の取得は、年収アップを目指す上で極めて有効な手段です。
「摂食嚥下リハビリテーション認定士」や「認定言語聴覚士(発達障害・高次脳機能障害など)」といった資格を取得すると、専門性の証明となり、昇給や手当の対象になるケースが多く見られます。
これらの資格は学会認定であり、取得までに一定の臨床経験や研修参加が必要ですが、その分評価も高まります。
資格を持つことで病院や施設内での指導的立場を任されることもあり、キャリアの幅が広がるでしょう。さらに、専門資格を通じて学会発表や研究活動に参加すれば、業界内での知名度や信頼性も上がります。
こうした実績は転職時の交渉でも大きな強みになります。資格取得の過程で得た知識や人脈も、将来的に別のチャンスを呼び込む可能性があります。
③管理職や主任職に昇進する
管理職や主任職への昇進は、収入アップを実現する大きなチャンスです。役職に就くと基本給が上がるだけでなく、役職手当や責任手当が支給される場合もあります。
組織をまとめるリーダーシップやスタッフ育成、スケジュール管理など、臨床以外のスキルが求められますが、それらを身につけることで総合的な人材として評価されやすくなります。
また、管理職になると施設運営や会議への参加など、経営的な視点を学べる機会も増えるでしょう。これは将来的に独立やキャリア転換を考える際にも大きな財産になります。
責任は増えますが、それ以上にスキルと収入を両立できるやりがいあるステップです。
④給与の高い職場へ転職する
年収を上げるための最も直接的な方法は、給与の高い職場に転職することです。一般的に、総合病院よりも訪問リハビリや介護施設、民間クリニックのほうが給与水準が高めです。
特に訪問リハでは1件ごとの報酬体系が設定されており、努力次第で月収が大きく変わることもあります。
また、都市部や大手医療法人では昇給制度や賞与が整備されているケースも多く、安定した収入を得やすいでしょう。
ただし、給与だけでなく職場の雰囲気や働きやすさ、福利厚生、残業の有無なども慎重に確認する必要があります。
さらに年収アップを狙うなら、面接時に自己PRで専門スキルを明確に示し、交渉に臨むことが重要です。
⑤副業や講師活動で収入源を増やす
本業以外の収入源を確保することは、リスク分散と収入安定の両方に効果的です。
言語聴覚士の場合、セミナー講師や研修講座の登壇、専門誌やWebメディアへの執筆、さらにはオンライン講座の開設など、自分の知識を活かせる副業が多く存在します。
これらの活動は時間の使い方次第で収入を積み上げられ、将来的には独立やフリーランスへの足がかりにもなります。
また、副業を通じて同業者とのネットワークが広がり、新しい仕事のチャンスを得ることも少なくありません。ただし、勤務先の副業規定を確認し、無理のない範囲で始めることが大切です。
SNSやブログで情報発信を行えば、自分の専門性をアピールでき、仕事依頼を受けるきっかけにもなります。得意分野を軸に継続することで、安定した副収入を築けるでしょう。
⑥フリーランスや独立開業に挑戦する
将来的に大幅な収入アップを狙うなら、フリーランスや独立開業という選択肢もあります。独立すれば働く時間や場所を自由に決められ、努力がそのまま収益に反映されます。
特に在宅リハビリやオンライン相談、企業との契約業務など、今後需要が高まる分野ではチャンスが広がっています。
とはいえ、経営・集客・税務など臨床以外の知識も必要になるため、すぐに始めるのではなく、まずは準備期間を設けて計画的に進めることが重要です。
開業前には、顧客獲得の仕組みや広告戦略、資金計画をしっかり整えておきましょう。また、フリーランスとして働く場合は信頼が何よりも重要です。
前職で築いた人脈や実績を生かし、少しずつ案件を増やすことで、安定した収入基盤を作ることができます。独立はリスクも伴いますが、その分やりがいと自由度の高い働き方を実現できるでしょう。
言語聴覚士の将来性

言語聴覚士は、言葉や聞こえ、飲み込みなど、人の生活に深く関わる支援を行う専門職です。高齢化や医療技術の発展により、その重要性は年々高まっています。
ここでは、将来性が高い理由をわかりやすく紹介します。
- 高齢化社会による需要拡大
- 医療・介護分野での活躍領域の拡大
- 発達支援・教育分野での需要増加
- 在宅リハビリ・地域連携の重要性
- AI・ICT技術導入による新たな働き方
- 安定した資格職としてのキャリア価値
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
①高齢化社会による需要拡大
高齢化の進行に伴い、言語聴覚士のニーズは年々増え続けています。特に脳卒中後の失語症や嚥下障害を抱える高齢者が多く、医療現場では専門的な訓練を行える人材が求められています。
言語聴覚士は「話す」「聞く」「食べる」といった人間の基本的な機能を取り戻す支援を通して、患者の生活の質を大きく改善します。
また、入院期間の短縮化により、在宅でのリハビリ支援が増えていることも、需要拡大の要因です。高齢者が安心して暮らすには、言葉や飲み込み機能の維持が欠かせません。
こうした社会的背景から、今後も専門知識を持つ言語聴覚士の存在は欠かせないでしょう。医療・介護双方で必要とされるため、長期的に安定して働ける職業といえます。
②医療・介護分野での活躍領域の拡大
言語聴覚士は、これまで主に病院で活躍してきましたが、近年は介護施設、デイサービス、訪問リハビリなど、働く場が大きく広がっています。
特に介護現場では、食事中の誤嚥を防ぐための嚥下訓練や、認知症の進行を遅らせるためのコミュニケーション支援など、幅広い役割を担います。
さらに、チーム医療が重視される今、理学療法士や作業療法士、栄養士、看護師などと協力しながら包括的な支援を行う力が求められています。
患者の回復を支えるだけでなく、介護スタッフや家族に対するアドバイスも重要な仕事のひとつです。
今後は在宅医療や地域密着型サービスが進むことで、医療と生活をつなぐ専門家としての価値が一層高まるでしょう。
③発達支援・教育分野での需要増加
発達障害や言葉の遅れに関する理解が進み、教育や福祉の現場で言語聴覚士の役割が広がっています。
保育園や幼稚園、小学校、特別支援学校などでは、子どもの発音や言語理解をサポートし、学習や社会生活への適応を助けています。
また、療育施設や発達支援センターでは、早期に問題を発見し、個々の成長に合わせた支援を行うことが求められます。
保護者との面談を通じて、家庭でできる練習方法を提案するなど、家庭と教育機関をつなぐ役割も担っています。
さらに、発達障害の早期発見を目的とした行政の取り組みも進んでおり、今後この分野での専門職需要はさらに増すでしょう。子どもの未来を支えるやりがいのある分野です。
④在宅リハビリ・地域連携の重要性
病院中心の医療から、地域全体で支える「地域包括ケア」へと移行する中で、言語聴覚士の働き方も多様化しています。
退院後の在宅リハビリや、介護施設・地域センターでの健康支援活動など、生活に寄り添った支援が増えています。自宅で暮らす高齢者にとって、食事や会話は生きがいそのものです。
その機能を維持するために、言語聴覚士は家族や介護スタッフに指導し、安心して生活を送れるようサポートします。
また、地域の医師、看護師、介護士との連携が重要で、情報共有やケア会議への参加を通じてチーム医療の一員として貢献します。
今後は「地域に根ざしたリハビリ専門職」としての活躍がより期待されるでしょう。
⑤AI・ICT技術導入による新たな働き方
AIやICTの進化は、言語聴覚士の働き方にも大きな変化をもたらしています。音声解析技術を使った発音の定量評価や、オンラインリハビリを活用した遠隔支援など、新しいサービスが広がっています。
これにより、通院が難しい高齢者や地方在住者にもリハビリの機会を提供できるようになりました。さらに、AIが訓練データを分析することで、個々に最適なプログラムを設計することも可能です。
これらの技術は専門職の判断を補助するものであり、人間の温かみのある支援と組み合わせることで効果を高めます。今後は、デジタル技術を使いこなすスキルが、言語聴覚士の新たな強みとなるでしょう。
技術と人の心をつなぐ存在として、働き方の幅がますます広がっています。
⑥安定した資格職としてのキャリア価値
言語聴覚士は国家資格を持つ専門職であり、景気や社会情勢の変化に左右されにくい安定した職業です。
医療・介護・教育など多様な分野で必要とされるため、自分のライフステージに合わせて働く場所を選べます。
また、経験を積むことで、教育機関での講師やリーダー職、病院での管理職など、キャリアアップの道も広がります。
独立して訪問リハビリや研修講師として活動する人も増えており、働き方の自由度が高いのも特徴です。
専門知識を磨くことで、生涯にわたって社会に貢献できる職種といえるでしょう。
柔軟な働き方と安定性を両立できる点で、言語聴覚士は今後も魅力あるキャリアの選択肢として注目されます。
言語聴覚士になるためのステップ

言語聴覚士になるには、専門的な知識と実践的な経験を段階的に積み重ねることが欠かせません。
ここでは、学校選びから国家試験、現場経験、そしてスキルアップまで、言語聴覚士として着実に成長するための具体的なステップをわかりやすく紹介します。
- 言語聴覚士養成課程のある学校を選ぶ
- 国家試験受験資格を取得する
- 国家試験に合格する
- 医療機関や施設で実務経験を積む
- 専門分野を選んでスキルを磨く
- 学会や研修に参加して最新知識を学ぶ
①言語聴覚士養成課程のある学校を選ぶ
言語聴覚士を目指す最初のステップは、厚生労働省が指定する養成課程を持つ大学や専門学校を選ぶことです。国家試験の受験資格を得るためには、これらの学校で必要な単位を修得する必要があります。
学校選びでは、授業内容の深さや臨床実習の充実度、国家試験の合格率を丁寧に比較することが大切です。また、就職支援体制や卒業後の進路実績も見逃せません。
医療機関との連携が強い学校では、現場を意識した実践的な教育が受けられます。臨床実習の機会が多ければ、患者さんへの接し方や症例への対応力も早く身につくでしょう。
さらに、学びやすい環境や指導体制、講師の経験なども学校選びの重要な要素です。
自分がどのような言語聴覚士を目指すのかを明確にし、その目標に合った教育環境を選ぶことが、後のキャリア形成に大きく影響します。
②国家試験受験資格を取得する
必要な単位を修得し、課程を修了することで国家試験の受験資格を得られます。この期間は、言語聴覚士としての基礎を築く重要な段階です。
授業で理論を学ぶだけでなく、臨床実習を通じて実際の現場で判断力や応用力を身につけましょう。
机上の学びだけでは見えない、患者さんとのコミュニケーションの難しさや、症状に応じたリハビリ計画の立て方を体感できる貴重な機会です。また、国家試験対策は早めに始めることをおすすめします。
学内で行われる模試やグループ勉強会を活用すると、他の学生と刺激を与え合いながらモチベーションを保てるでしょう。
学習を進める中で、自分の得意分野や興味を見つけることも、将来の進路選択に役立ちます。
③国家試験に合格する
国家試験の合格は、言語聴覚士として働くための最終関門です。出題範囲は広く、聴覚・言語・心理・発達・医学・福祉など多岐にわたります。
そのため、単なる暗記ではなく、科目間のつながりを理解して整理することが合格への鍵となります。過去問を繰り返し解くことで傾向を把握し、実践的な問題対応力を鍛えてください。
特に、苦手分野を早期に洗い出し、重点的に学習することが重要です。友人や先輩と一緒に勉強することで、独学では気づけない視点を得ることもできます。
さらに、試験直前は焦らず体調管理を徹底し、集中できる環境を整えてください。国家資格取得はゴールではなく、専門職としてのスタートラインです。
④医療機関や施設で実務経験を積む
国家資格を取得したあとは、病院やリハビリ施設、福祉機関などで実務経験を積みます。現場では、患者さん一人ひとりの症状や生活背景が異なるため、教科書どおりの対応では通用しない場面も多いでしょう。
そのため、柔軟な思考と臨機応変な対応力が求められます。特に、言語障害や嚥下障害など、ケースによって治療内容やリハビリ方法が大きく異なるため、現場で学ぶことは非常に多いです。
また、チーム医療においては、医師・看護師・理学療法士・作業療法士など、多職種と連携して治療を進めることが欠かせません。
円滑なコミュニケーション力は、患者さんだけでなくチーム全体の信頼関係を築くうえでも大切です。
⑤専門分野を選んでスキルを磨く
言語聴覚士の活躍の場は、医療・教育・福祉と幅広く、分野ごとに求められるスキルが異なります。実務経験を積んだあとは、自分の興味や適性に合わせて専門分野を選び、知識と技術を深めましょう。
たとえば医療分野では、摂食嚥下障害、高次脳機能障害、発声障害などがあり、より専門的な対応力が必要です。一方、教育分野では発達障害や構音障害を持つ子どもへの支援が中心となります。
特定の分野を深掘りすることで、より的確で質の高いリハビリを提供できるようになります。また、専門性を高めることで、キャリアアップや転職の選択肢も広がります。
自分が「どのような形で人の力になりたいか」を意識しながら、学びと経験を重ねていくことが大切です。
⑥学会や研修に参加して最新知識を学ぶ
言語聴覚士として長く活躍するためには、学び続ける姿勢が不可欠です。医療や教育の分野では、研究や技術が日々進化しています。
学会や専門研修に参加することで、最新の治療法や支援技術を学び、現場での実践に活かすことができます。また、他の専門家との交流を通して、異なる視点や新しい発想を得られることも魅力です。
さらに、自身の経験をもとに研究発表や論文執筆に挑戦することで、専門家としての知見を社会に還元することもできます。
学びを重ねることで、自信と責任感が育ち、患者さんにより良い支援を提供できるようになるでしょう。
言語聴覚士のキャリアと年収を理解しよう!

言語聴覚士は、言語や聴覚、発声、嚥下などのリハビリを専門とする国家資格職です。子どもから高齢者まで幅広い対象に支援を行い、医療・福祉・教育の現場で重要な役割を担っています。
近年では、高齢化や発達支援需要の増加により、言語聴覚士の活躍領域は拡大しています。平均年収は約350万円〜450万円前後ですが、経験年数や勤務先、資格、職位によって差があります。
中堅期以降はスキルやマネジメント力を高めることで年収アップも可能です。さらに、認定資格取得や副業、独立開業といった選択肢で年収を上げる道もあります。
今後も需要拡大が見込まれる安定した専門職として、成長とやりがいを両立できる職種といえるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。