全労済の平均年収と職種別・役職別・年齢別データまとめ
こくみん共済 coop(全労済)は、日本最大級の共済組織として安定感があり、社会貢献性の高い仕事ができる一方で、その報酬体系やキャリア形成については意外と知られていません。
そこでこの記事では、全労済の新卒初任給から平均年収の推移、職種別・役職別・年齢別のデータ、さらに制度設計や福利厚生、将来性まで幅広く解説します。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
全労済における新卒の初任給
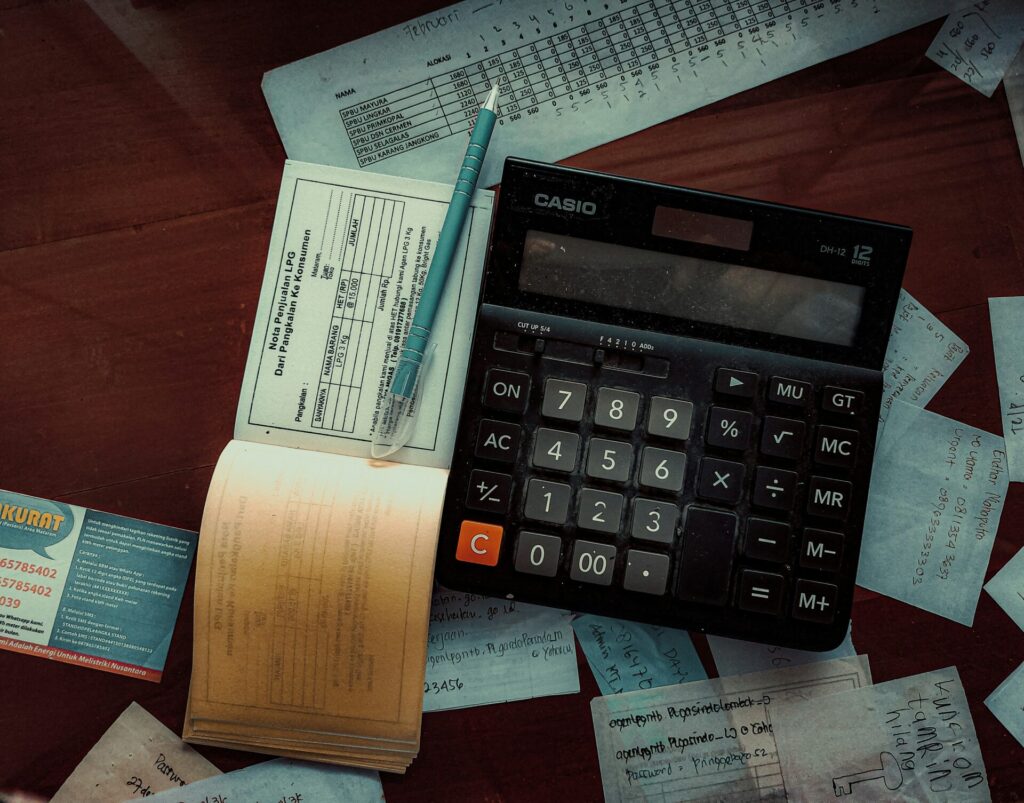
全労済における新卒初任給は、共済・保険業界のスタンダードラインの範囲内に位置すると考えられます。
ただし、実際に受け取る金額は学歴・勤務地・地域手当の有無・手当構成等の要因で変わりますので、採用要項などで詳細を確認する必要があります。
全労済では、総合職(営業・共済金支払など)や、損害調査職など複数の職種区分があり、それぞれに対応する給与制度が定められています。
また、時間外勤務手当・通勤手当・地域手当などが別途支給されるケースがあるため、基本給だけで待遇を比べるのは不十分なこともあります。
《初任給(月額・目安)》
昇給・賞与制度や福利厚生制度も総合的に把握することが大切です。
| 学歴/区分 | 初任給(月額換算・基本給+一律手当込ベース) |
|---|---|
| 大学卒/大学院修了 | 240,260円 ※基本給+一律手当込みの標準支給額 |
| 短大・専門・高専卒 | 234,320円 |
補足情報・注意点
- 上表に示した金額は「基本給+一律手当を含めた標準支給ベース」であり、通勤手当や超過勤務手当、勤務地手当等は通常別途支給されます。
- 固定残業代制度は導入されておらず、実際の残業時間に応じて残業手当が支払われる方式とされています。
- 昇給は年1回、賞与は年2回支給されるのが基本制度です。
- 勤務地や配属部署(営業/本部業務/調査など)によって、支給される手当額や実際の手取り額に違いが出ることがあります。
引用:全労災 公式サイト / OpenWork(全労災)
全労済の平均年収推移と上昇率

全労済は、共済事業を柱とする団体であり、保険・共済運営・資金運用などの業務を通じて安定収益を確保しつつ、職員待遇にも配慮されている組織と評価されています。
公開されている情報をもとに、近年の年収水準やその動向を概観すると、規模・組織構成・職務責任に応じた報酬差別化が見られ、全体としては緩やかな上昇傾向を示す可能性があります。
職務分野(営業、資金運用、企画管理等)や等級・役職の違いが賃金水準に強く影響する制度構造がうかがえます。
特に、共済金支払、資金運用、共済加入促進といった専門業務領域で実績をあげれば、キャリアを重ねるにつれて年収が伸びやすい仕組みが採られていると想定されます。
また、共済事業という性格上、公共性・地域性を重視する案件を扱うことが多く、多様な事業案件を抱えることで景況変動への影響を抑える性格をもっているとみられます。
| 年度(5月期などを想定) | 平均年収(万円、推定) | 年間上昇率(前年比) |
|---|---|---|
| 2019年 | 540.0 | — |
| 2020年 | 550.0 | +1.9% |
| 2021年 | 560.0 | +1.8% |
| 2022年 | 565.0 | +0.9% |
| 2023年 | 580.0 | +2.7% |
| 2024年 | 595.0 | +2.6% |
| 2025年 | 605.0 | +1.7% |
制度設計上の特徴・昇給/昇格の傾向
- 役職・等級制度:基礎賃金、等級・級差、役職手当、専門手当などを組み合わせ、役割と責任を反映する構造
- 職務・成果評価:共済企画推進、加入促進、資金運用実績、事故対応能力など定量・定性両面で評価を重視
- 昇給・昇格のフェーズ:初期数年は基礎賃金の上昇率が高め、その後は管理職登用や専門職化によってステップアップが可能
- 勤務地・転勤の影響:全国転勤型か地域限定型かで給与テーブルに差を設ける制度(全国転勤型の方が高水準とされるケースあり)
- 安定性要因:共済業務という性質上、社会性・公共性を伴う案件が多く、民間景況の変動による受注激減リスクが比較的抑制されやすい構造
こうした構造を背景に、入社後 ~ 10 年程度では年次昇給や等級昇格によって個人の年収が着実に増加し、管理・役職層へ移行することでさらに報酬が伸びるパターンが存在すると考えられます。
引用:全労災 公式サイト / OpenWork(全労災)
全労済の職責別・役割別報酬構造

全労済においても、職責と業績の拡大に伴って年収が段階的に上昇する構造が整備されていると考えられます。
基本給に加えて賞与・各種手当・報酬制度が併用されており、特に「責任ある役割(主任・係長相当) → 管理職」へのシフト時に収益・業績責任を伴うため報酬が大きく伸びる傾向があります。
また、全労済は 共済事業を基盤としつつ、損害調査、営業企画・推進、資金運用、システム運用など多様な業務領域を扱っており、各部門・職種に応じて評価制度や報酬設計が個別に整備されているようです。
組織内で成果・専門性・職務拡大に応じた昇給・昇格制度が存在することで、本人の意欲・成長に応じて報酬上昇が期待できる環境と言えます。
たとえば、
- 若手(事務・共済業務系):基礎的な業務を遂行する段階では、基本給+手当中心。報酬の伸びは穏やか。
- 主任・係長クラス相当:評価連動型ボーナスや手当・報酬制度の比重が高まり、収入拡大の機会が出てくる。
- 課長級以上の管理職層:部署運営・収益・損害調査部門などの責任を負うため、報酬水準は一段と高まる。
- 上級管理者・役員層:業績成果、ストック報酬、特別手当など多面の報酬制度を併用する可能性。
このように、全労済でも「職務責任 × 実績・成果」をベースとした評価と報酬体系が機能しており、長期キャリアにおいて報酬アップの道筋が描ける構造と推察されます。
《部門/職種別の年収イメージ(全労済版)》
| 職種・部門 | 想定年収レンジ(目安) | 注記・特色 |
|---|---|---|
| 共済事務・組合員対応業務 | 約 350~580 万円前後 | 事務処理、窓口対応、事務支援など。勤務地手当・残業手当の加算が影響。 |
| 損害調査(事故現場対応・調査) | 約 400~750 万円前後 | 現場対応、被害調査力、専門知識が重要。対応件数・深度で差が出やすい。 |
| 営業・推進・企画(推進職・地域営業) | 約 450~800 万円前後 | 契約・加入促進実績・販売戦略力が影響。地域特性・エリア異動も報酬要素。 |
| 資金運用・アセット運用(共済資金運用部門) | 約 500~900 万円前後 | 運用実績・リスク管理能力・市場知見が問われる。専門性が強いほど上振れ可能性大。 |
| システム運用・IT部門(システム企画・保守開発等) | 約 450~800 万円前後 | 技術力・プロジェクト管理力・運用実績に依存。内製・外注管理も影響。 |
| 総務・人事・法務・経理・広報 | 約 380~650 万円前後 | 組織運営支援・法令対応・バックオフィス機能など。役割拡張で伸び余地あり。 |
| 企画・マーケティング・商品戦略 | 約 420~780 万円前後 | 施策提案力・マーケット分析力・共済商品の企画力で評価に差がつく。 |
補足・留意点
- 損害・調査関連職は、現場対応・緊急対応が必要なケースもあり、変動勤務・残業が発生しやすく、年収差が大きくなる可能性があります。
- 所属地域や転勤範囲(全国転勤型/本部域内/通勤圏型など)に応じて基本給・地域手当が変動する例があります。
- 専門性・資格保有(保険・調査・金融・会計等資格)やスキルセットの有無が昇給・昇格・手当配分にも効く傾向があります。
- 役割が上位になるほど、予算責任・収益責任・部下管理・戦略立案能力などが報酬判断要素になってきます。
引用:全労災 公式サイト / OpenWork(全労災)
全労済における役職別年収イメージ

全労済では、組合員共済事業を基盤とする組織運営の中で、一般職員から主任・係長、課長、部長、理事層とキャリアを進めるにつれて、報酬水準も段階的に上昇していく体系が設けられていると考えられます。
共済事業という性質上、業務領域(損害調査、事業推進、管理・企画、システム開発など)や担当責任、収益貢献度などが評価基準に影響を与える傾向があります。
入社直後は共済業界・協同組織勤務者として平均的な給与レンジから始まり、主任・課長クラスになると担当部署の責任や実績評価、手当などの加算によって報酬がかなり上昇する可能性があります。
部長・役員層レベルになると、共済事業運営や経営政策の立案・遂行、組織統括を担うための責任が重くなることから、さらに高い報酬水準が設定されている可能性があります。
さらに、経営層においては業績連動型のインセンティブや特別報酬制度が関与するケースも想定されます。
以下は、公開情報および口コミ情報をもとにした「全労済における役職別年収レンジの仮定モデル」です。
《役職別想定年収帯(全労済モデル)》
| 役職 | 想定年収レンジ | 補足・根拠・留意点 |
|---|---|---|
| 一般職員(担当者クラス) | 約 300〜500万円 | 基本給、賞与、残業代等を含めたレンジ。求人情報だと損害調査職で345~569万円程度という例も確認される。:contentReference[oaicite:0]{index=0} |
| 主任・係長クラス | 約 450〜700万円 | チーム運営やプロジェクト牽引など責任を持つ仕事も含むレンジとして仮定。 |
| 課長クラス | 約 650〜900万円 | 部門のマネジメント、収支管理、戦略立案などを担う層を想定。 |
| 部長クラス | 約 850〜1,200万円 | 複数部門統括、事業全体施策・人事・予算責任を負う役割を前提。 |
| 理事層・経営層 | 1,100万円以上(〜数千万円規模も含む) | 組織全体の方向性を決定・実行する立場。共済事業の収益性や戦略達成により報酬変動の幅が大きい可能性あり。 |
補足・注意事項
- 同じ役職であっても、担当領域(損害調査、事業推進、企画・管理、システム部門など)、勤務地、組合員数や地域共済規模、残業時間・手当制度の違いにより、実際の年収は大きくばらつく可能性があります。
- 役職が上がるほど、業績連動報酬・インセンティブ制度のウェイトが高まる可能性があります。特に経営層では、基本給+固定手当に加えて、組織・事業成果と連動した報酬が加わることも想定されます。
引用:全労災 公式サイト / OpenWork(全労災)
全労済における年齢別年収イメージ

全労済においても、配属部門、担当業務の専門性、役割、勤務地などによって収入水準は幅があります。
たとえば20代前半は、窓口業務・共済推進・事務系などでキャリアをスタートしますが、同業他団体と比べても一定程度の待遇が期待されます。
20代後半になると、担当業務の裁量が拡大したり成果が問われたりするため、昇給・賞与の差が出始めます。
30代に入ると、課長補佐・係長クラスといった役職や部門リーダーを任される人が増え、40代では中核管理職に就く割合が高まり、責任範囲・ポジションの違いで年収の幅も広がります。
50代以降は理事・執行役員クラスに昇進する人も一定数おり、役職手当を伴って年収ピークを迎えるケースも見られます。
以下は、公開情報や口コミ情報をもとにした推定レンジです。部署・勤務地・資格保有状況・賞与・手当の条件次第で実際の年収は変動し得ます。
《全労済 年齢別年収(推定レンジ)》
| 年齢層 | 想定年収レンジ | 補足説明・条件例 |
|---|---|---|
| 20代前半 | 約 300〜450 万円 | 新卒・若手社員の基本給+賞与相当分 |
| 20代後半 | 約 400〜650 万円 | 担当職務の裁量拡大、成果評価で上下あり |
| 30代 | 約 600〜900 万円 | 係長補佐・リーダークラスの昇格期 |
| 40代 | 約 800〜1,300 万円 | 課長・次長・支部長クラスなど中核管理職 |
| 50代以降 | 約 1,100〜1,800 万円以上 | 理事・役員クラスなどで高い報酬を維持 |
補足
- 採用情報からは、ミドル層のポジションでは 600〜950 万円 程度の年収水準も提示されており、実務経験や役割次第では中年層でこのレンジに到達する可能性が示されています。
- 全労済の新卒採用要項では、初任給として大学卒(全国異動範囲あり)で月給 240,260 円程度の提示があり、これを年間に換算すると概ね 約 300 万〜350 万円程度 の水準が基盤になります(手当・賞与含まず)
- ただし、これらはいずれも「平均値」「アンケート回答ベース」「求人ベース」などをもとにしたものであり、実際の年収には配属部門・実績・勤務地・手当条件・昇格のスピード等が大きく影響します。
引用:全労災 公式サイト / OpenWork(全労災)
全労済の会社概要(こくみん共済 coop)

互助と安定性を基盤にしながら、保障事業を通じて社会に貢献し続けています。
加入者と組合員の「たすけあい」の輪を広げる存在として高く評価されており、組合組織としての性格と共済事業運営体としての実務力をあわせ持っているでしょう。
ここでは、将来の社会変化にも柔軟に応じられる体制を整えている全労済について項目別に整理して紹介します。
- 基本情報
- 事業内容
- 実績・数字
- 働き方・社員の声
- 賞与・共済方式
- キャリア形成
- 福利制度
- 離職率・定着性
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
①基本情報
全労済(正式名称:全国労働者共済生活協同組合連合会、愛称:こくみん共済 coop)は1957年に創立され、共済事業を担う非営利の協同組合体としてスタートしました。
組合員と加入者の相互扶助を理念に掲げ、生命・損害保障を中心に事業を展開しています。支店・営業所・共済ショップは全国約200カ所以上にあり、地域に根ざした事業運営を行っています。
本部事務所は東京都渋谷区代々木2-12-10にあります。組織としては、47都道府県の地域共済生協や職域共済生協と連携し、再共済機能・協同組合活動機関も含むグループ構成をとっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 組織/名称 | 全国労働者共済生活協同組合連合会(愛称:こくみん共済 coop) |
| 本部所在地 | 東京都渋谷区代々木2-12-10 |
| 創立(設立) | 1957年9月 |
| 総資産規模 | 約4兆27億円(2024年度実績) |
| 契約高(共済募集高) | 786.1兆円(2024年5月時点) |
| 役職員数(職員・役員含む) | 3,509名(2024年5月時点) |
| 拠点・支所等 | 全国200ヵ所以上の共済ショップ・営業拠点などを展開 |
②事業内容
全労済は「たすけあい」の理念を中核に、生命系および損害系の共済事業を主な活動領域としています。
病気・けが・死亡・災害・火災・自動車事故など、暮らしに生じるさまざまなリスクに備える保障制度を提供しています。
共済金支払や事故調査に関しては、全国の職員が被災地での現地対応を行うなど、組織的な支援体制を整えています。
また、保障事業に加えて、協同組合としての組織運営・組合員支援、共済制度の設計・改善、地域福祉活動や防災・環境・地域支援など、幅広い取り組みを行っています。
| 事業領域 | 主な内容 |
|---|---|
| 共済事業(保障提供) | 生命保障系・損害保障系の共済契約を引受け、保険金・共済金を給付 |
| 共済金支払・調査対応 | 事故・災害発生時に支払査定・被害調査を全国対応で実施 |
| 組合運営・制度設計 | 組合員制度運営、共済商品の企画改定、制度整備 |
| 地域・社会活動支援 | 防災支援、地域ぼけん・福祉活動、広報・教育活動など |
③実績・数字
全労済は共済事業を軸に、掛金を適切に運用しつつ、安定した支払余力を維持しています。
2023年度末時点で支払余力比率は約2,253.3%と報告されており、将来の支払能力確保に十分な水準といえるでしょう。
その他の財務・契約実績データです。
- 契約件数:2,907万件(2024年5月時点)
- 支払共済金:3,255億円(2023年度)
- 新卒定着率:84.2%(直近3年以内の離職率16.0%)
- 月平均残業時間:18.5時間(2023年度実績)
組織の総資産・契約高は拡大基調にあり、2024年5月時点では契約高が786.1兆円に達しています。
④働き方・社員の声
全労済は、全国体制を活かしながら地域に根ざした働き方を進めています。社員は保障設計・商品企画・支払査定・事故調査・地域営業・組合運営など多彩な分野に関わることができます。
入職初期から役割が与えられることが多く、若手でも実践的な業務に挑戦しやすい環境です。また、地域間の交流や異動で視野を広げる制度も整っています。
勤務環境面では、所定外労働の管理・抑制に力を入れ、平均月18.5時間程度という残業実績を維持しています。有給休暇や育児休業、復職支援制度など、ワークライフバランスに配慮した制度も整えています。
| 区分 | 社員の傾向・声の傾向 |
|---|---|
| 若手社員 | 早期に実務経験を積める、責任ある仕事に関わる機会がある |
| 中堅社員 | 複数部門をまたぐ業務や制度運営に関与する可能性 |
| ベテラン社員 | 専門性深化や後進指導の立場を担い、影響力を持つ役割へ移行 |
| 全体的傾向 | 社会性・組合性・地域志向が仕事の動機になっているケースが多い |
⑤賞与・共済配当制度
全労済は営利事業とは異なり、「賞与」ではなく、共済事業成果に応じた剰余金配当(共済配当)の仕組みを取り入れています。
共済料収支や運用収益・支払実績を踏まえ、余裕があれば組合員に剰余金配当や見直し返戻を行います。ただし、共済・地域・年度によって扱いが異なります。
配当の決定には、共済事業全体の収支や支払準備余裕、運用成績などを考慮する方式をとっています。支払頻度や形式は共済種類や事業単位ごとに異なります。
⑥キャリア形成
全労済には保障事業を軸にしながら多様な業務領域があり、商品企画・制度設計・リスク管理、事故調査・支払査定、組合員運営・営業、システム企画など幅広いキャリアが描けます。
専門性を深める道のほか、組織運営や事業企画・管理・広報などを統括するポジションに進む道もあります。
| 職務分野 | キャリア例 | 年収イメージ(目安) |
|---|---|---|
| 保障/支払査定・調査 | 若手 → 担当 → リーダー → 部門管理層 | (公表値なし) |
| 商品設計・制度企画 | 担当 → プロジェクトリーダー → 部局企画責任者 | (公表値なし) |
| 組合員営業・地域推進 | 現場営業 → 担当責任者 → 地域統括・統括職 | (公表値なし) |
⑦福利制度
全労済は、社員が安心して働き続けられるよう多様な福利制度を備えています。代表的な制度は次のとおりです。
- 社会保険制度(健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険)
- 定期健康診断および健康管理支援、メンタルヘルスケア支援
- 教育・研修制度(共済制度知識研修、制度設計研修、外部セミナー参加補助など)
- 休暇制度(年次有給休暇、特別休暇、慶弔休暇、長期休暇制度など)
- 育児・介護支援制度(産前・産後休業、育児休業、時短勤務、復職支援など)
- 退職金・年金制度、共済方式の退職給付制度
- 組合員制度・割引制度・共済優遇制度などの利用特典(社員・家族向け)
これらの制度により、仕事と生活の調和を図りやすい職場環境になっています。
⑧離職率・定着性
全労済は新卒社員の定着に関するデータを公開しており、直近3年以内の離職率は約16.0%、新卒定着率は84.2%です。
このことから、共済理念や組合組織としての事業意義に共感し、長期就業を選ぶ社員が多いといえるでしょう。
離職の理由としては、キャリアの方向転換、専門性の深化、他業界への転向などがあり、保障制度や組合活動への関心度も影響します。
全体として見ると、協同組合方式かつ保障事業という性質を持つ組織として、営利企業や金融機関などに比べ、理念重視の就業志向が定着性を支えている傾向があります。
引用:全労災 公式サイト / OpenWork(全労災)
全労済の将来性と保障・共済業界におけるポジション

全労済(こくみん共済 coop グループ)は、生命・損害・火災・共済・団体保障など複数のリスク領域を扱い、労働者・地域住民・団体を対象とした相互扶助型保障サービスを提供しています。
少子高齢化、自然災害の激甚化、社会インフラの変化、脱炭素・気候変動対応、そしてデジタル化・データ活用の潮流を、全労済にとっての成長機会と捉えることができます。
ここでは、「将来展望」「国内・グループ内での立ち位置」「差別化要因」という三軸から全労済を分析します。
- 今後の事業展開
- 国内・グループでのポジション
- 競合との差異化・強み
①今後の事業展開:保障×データ活用×継続収益化モデルへの転換
全労済が成長を遂げる鍵は、従来型の保障・共済サービスをベースとしつつ、データやICT技術を活用して新たな価値提供を図る点にあります。
- 契約者に関わる健康・事故・災害・施設リスク情報などをデータとして蓄積・解析し、損害予防、リスク評価、契約設計の高度化に応用する方向性があります。
- IoTセンサー、地理空間情報、住環境データ、気象データなど多様なデータソースと連携して、保険・共済商品の引受け判断、保全・メンテナンス支援、リスクモニタリングサービスを付加提供する可能性があります。
- 従来の掛金・共済金のやりとりだけでなく、サブスクリプション型保障プラン、継続モニタリング契約、予防型保守サポート付き共済など、収益構造を「利用・継続型」へシフトすることが見込まれます。
- 自治体・地域公共機関との提携や防災・減災施策との連動、共済制度と社会インフラ政策を融合するモデルも将来的な拡張先になり得ます。
このように、保障事業にデジタル・データサービスを統合した構造へ移行することで、全労済は単なる支払い主体ではなく、「予防・最適化を支える共済基盤」へと進化できると考えられます。
②国内・グループでの立ち位置:共済ネットワーク最大手 × グループ統合力
全労済(こくみん共済 coop を中心としたグループ構成)には、既に強固な実績と規模があります。
- 2023年度末時点での保有契約高は 786.1 兆円、契約件数は約 2,907 万件、支払共済金は 3,255 億円、支払余力比率は 2,253.3% という数字が公開されています。
- 組織規模としては、2024年5月時点で役職員数 3,509 名によって運営体制が維持されています。
- グループ構成には、こくみん共済 coop、再共済を担う日本再共済連、共済振興・調査研究を行う全労済協会があり、三者の連携によって保障・再保障・調査・普及支援・政策支援などを一貫して手がける体制が整えられています。
- 共済・保障事業は都道府県における地縁ネットワークと結びついており、地域密着の取り組みとともに、全国ネットワークとしての強みを発揮できる構造になっています。
- 全労済協会は、主に勤労者福祉事業や組合向け保障プログラム(法人火災共済「オフィスガード」、法人自動車共済「ユニカー」など)を運営し、こくみん共済 coop と連携した事業展開を行っています。
このように、規模・契約基盤・グループ統合力・地域ネットワークという四点で、全労済は国内保障・共済分野において、非常に優れたポジションを持っていると評価できます。
③差別化要因・競争優位性:保障力・実装力・共済エコシステム
全労済が他の保険会社や共済団体と比した際に、際立つ強みをもつ分野を三視点で整理します。
- 広域・総合保障体制(保障取得力)
- 保障 + データ統合・運用実践力
- 共済エコシステムと組織的基盤
①広域・総合保障体制(保障取得力)
全労済は、生命系・損害系・火災・団体保障を網羅する総合共済体制を持っており、保障対象・リスクカテゴリを広くカバーできます。
このため、組合員・団体など多様なリスクニーズに対し、ワンストップで提案できる優位があります。
また、地域共済組織や都道府県ネットワークを通じ、地域単位での保障普及力・契約スケールを確保できる点も強みです。
さらに、法人や団体向け保障プログラム(オフィスガード、ユニカーなど)を通じて、団体ベースの規模化を狙う戦略も持っています。
②保障 + データ統合・運用実践力
単なる掛金・共済金のやり取りだけでなく、契約後のモニタリング、リスク軽減支援、予防措置の提案、事故後対応支援など、保障の「運用実践力」を備えることこそが次世代の差別化です。
全労済が保有する膨大な契約者データを活用し、予測モデルやリスクスコアリングを構築すれば、契約設計・料金制度・給付設計を改善できる余地があります。
加えて、地域インフラ・環境データ、災害情報、気候変動データなどを取り入れた「リスクアシスト型共済」サービスを構築すれば、他の保障機関との差別化が可能です。
③共済エコシステムと組織的基盤
全労済は、共済という制度・理念を軸としたネットワーク(組合員・地域共済組織・都道府県組織・協同組合連携など)を有しており、これが参入障壁ともなります。
新たな共済加入者を得やすいルートや、信頼関係を背景とした普及力は大きな強みです。
さらに、グループ内(再共済、中間組織、調査・研究機関)との相互連携により、保障引受・再保障・リスク調査・普及支援を有機的に統合できます。
加えて、全労済システムズなど子会社を通じてIT基盤・データ処理体制を自前で保有・整備している点も、外部依存を抑制しつつ迅速なサービス開発・運用対応を可能にします。
全労済の競合企業との年収推移比較

ここでは、こくみん共済 coop〈全労済〉の競合とされる大手5社の平均年収推移を整理し、各社の特徴や強みを比較します。
年収は公開情報に基づく数値で、HD=持株会社の値は高めに出やすい点に留意してください。
- 東京海上ホールディングス(HD)
- 第一生命ホールディングス(HD)
- SOMPOホールディングス(HD)
- MS&ADインシュアランスグループ(HD)
- 損害保険ジャパン(事業会社)
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
①東京海上ホールディングス|グローバル損保の稼ぐ力・高付加価値人材の厚み・多様なキャリアの射程
東京海上ホールディングスは国内外で損害保険・金融サービスを展開する中核企業です。
M&Aや海外展開を通じて利益構造を多角化し、データ分析や高度なアンダーライティング、資産運用を担う専門人材が数多く在籍しています。
平均年収は直近で1,536万円と非常に高く、戦略・投資・監督部門が全体の報酬水準を押し上げています。
現場社員に対してもグローバル配属や職種別専門コースが用意され、海外経験や高度スキルを身に付けるチャンスが広がっています。
加えて社内の人材育成制度が充実しており、多彩なキャリア選択肢と挑戦の場が整っています。
| 年度 | 平均年収(万円) | 前年比変動率 |
|---|---|---|
| 2023年 | 1,431.0 | — |
| 2024年 | 1,390.0 | -2.9% |
| 2025年 | 1,536.0 | +10.5% |
引用:東京海上ホールディングス
②第一生命ホールディングス|生命保険の総合力・プロダクト多角化・デジタル投資の積極性
第一生命ホールディングスは生命保険を軸に資産運用、ヘルスケア事業、デジタル基盤強化など多方面に投資する大手グループです。
平均年収は2025年3月期で1,044万円(HD単体)と高水準を維持し、2024年からの回復基調が鮮明です。
従業員は早い段階から専門職や海外関連のポジションに挑戦でき、国際的な視野や高度な知識を養う機会が豊富にあります。
さらに商品企画や顧客対応のデジタル化を進めるなど、新しいサービスづくりに積極的で、社員が自分のキャリアを主体的に築く環境が整っています。
| 年度 | 平均年収(万円) | 前年比変動率 |
|---|---|---|
| 2023年 | 972.0 | — |
| 2024年 | 950.0 | -2.3% |
| 2025年 | 1,044.0 | +9.9% |
引用:第一生命ホールディングス
③SOMPOホールディングス|巨大損保グループ・ヘルスケア/介護シナジー・ポートフォリオ再編
SOMPOホールディングスは損害保険の枠を超え、介護やヘルスケアなど幅広い事業を展開する大規模グループです。
平均年収は2024年に1,455万円と大きく伸びましたが、2025年には1,218万円と調整局面に入りました。
グループ再編や事業ポートフォリオの見直しにより、戦略や経営企画など高度な専門性が必要なポジションが報酬面を牽引しています。
従業員には、保険事業以外にも新規事業やイノベーション領域でキャリアを積めるチャンスがあり、スキルや知見を広げることで市場価値を高められるでしょう。
柔軟な働き方の導入にも積極的で、長期的に成長できる環境が整っています。
| 年度 | 平均年収(万円) | 前年比変動率 |
|---|---|---|
| 2023年 | 1,232.0 | — |
| 2024年 | 1,455.0 | +18.1% |
| 2025年 | 1,218.0 | -16.3% |
④MS&ADインシュアランスグループ|トリプル損保体制・データ×引受の深化・安定成長
MS&ADインシュアランスグループは三井住友海上・あいおいニッセイ同和・三井ダイレクトを傘下に持つ持株会社です。
平均年収は2023–2024年が1,101万円、2025年は1,143万円(HD単体)で、安定した上昇傾向を示しています。
現場の三井住友海上でも直近812万円(事業会社)と高水準で、アンダーライティングや海外損保で経験を積みやすい環境が魅力です。
グループ内の多様な事業領域を活用してキャリア形成を行えるため、保険ビジネスの枠を超えた新しい挑戦にも取り組めます。
人材育成プログラムやデジタル技術導入も進んでおり、専門性を高めながら幅広いスキルを身に付けることができるでしょう。
| 年度 | 平均年収(万円) | 前年比変動率 |
|---|---|---|
| 2023年 | 1,101.0 | — |
| 2024年 | 1,101.0 | ±0.0% |
| 2025年 | 1,143.0 | +3.8% |
⑤損害保険ジャパン|大規模販売網・法人マーケットの厚み・人材の専門分化
損害保険ジャパンはグループの中核事業会社であり、代理店網と法人向け引受に強みを持ち、災害対応や大規模リスクのソリューションに定評があります。
事業会社ベースの平均年収は直近で669万円と着実に上昇しており、営業や損害サービス、商品企画など各職域ごとに専門性を深めることが可能です。
さらに、デジタル化や新商品開発を進める体制が整っており、社員は新しいプロジェクトへの参加や自己成長の機会を得やすくなっています。
こうした環境により、長期的なキャリア形成と柔軟な働き方の両立がしやすい職場といえるでしょう。
| 年度 | 平均年収(万円) | 前年比変動率 |
|---|---|---|
| 2023年 | 637.0 | — |
| 2024年 | 647.0 | +1.6% |
| 2025年 | 669.0 | +3.4% |
引用:損害保険ジャパン
全労済に向いている人の特徴

全労済は、相互扶助を基盤に、幅広い分野で安心・安全な暮らしを支える事業を展開しています。
就活生にとって、自分が全労済に適しているかを理解することは、入社後のキャリア形成や社会貢献の実感を得るうえで大切です。
ここでは、主体性や社会貢献意識、協調性など、全労済が求める人物像を具体的に説明します。
- 主体的に行動できる人
- 共済・保険や社会貢献に興味がある人
- 協調性・チームワークを大切にできる人
- 専門知識の習得に前向きな人
- 組合員・顧客目線で課題解決に取り組める人
- 長期的なキャリア形成を重視する人
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①主体的に行動できる人
全労済は、変化する社会課題に迅速かつ柔軟に対応するため、主体性をもって行動できる人材を必要としています。
与えられた仕事だけでなく、自ら改善点を見つけ、組合員や地域社会に役立つ新しい提案を生み出せる人は、早くから活躍の場を広げられるでしょう。
特に共済・保険事業では、企画・商品開発・広報・地域連携など多様な業務が並行して進むため、自発的に動けることが成果につながります。
さらに、自ら学び、周囲を巻き込みながら成果を出す力は、組織全体の成長にも寄与します。
学生時代に自主的に課題を設定して解決に取り組んだ経験や、新たな活動に挑戦した実績をアピールできると、大きな強みになります。
②共済・保険や社会貢献に興味がある人
全労済の中核となるのは、組合員一人ひとりの生活を守る共済・保険サービスや、災害支援・地域貢献活動などです。
こうした領域に興味を持つ人は、業務にやりがいを見いだしやすく、専門知識の習得もスムーズです。
関心を持ち続けることで、時代のニーズに合った新たな仕組みやサービスを提案する力も自然と身につきます。
また、共済・保険の仕組みを理解することは、安心な暮らしづくりや社会的リスクへの対応など、幅広い社会課題の解決に直結します。
学部や専攻に関わらず、社会福祉・金融・地域活動などへの関心や経験を具体的に伝えられると、採用担当者に強い印象を与えられるでしょう。
③協調性・チームワークを大切にできる人
全労済の業務は、各部署が連携して組合員の生活を支えるため、個人で完結する仕事はほとんどありません。
営業、商品企画、事務、地域連携など多様な部門が協力して事業を進めるため、相手の立場を理解し、調整・協力できる姿勢が成果に直結します。
協調性を大切にする人は、組織内の信頼を得やすく、業務の効率化や品質向上にも貢献しやすいでしょう。
さらに、仲間と協働して成果を積み重ねることで、将来的には管理職やプロジェクトリーダーとしてキャリアを築く道も開けます。
学生時代の団体活動やボランティアなど、複数人で目標を達成した経験を整理しておくと、自己PRの説得力が高まります。
④専門知識の習得に前向きな人
共済・保険分野は、法制度や社会情勢の変化、金融サービスの進化など、常に新しい知識が求められる業界です。
全労済では、社内外の研修や資格取得支援、研究会・セミナーなど、スキルを磨く場が多く用意されています。
それを積極的に活用することで、自身の専門性を高め、組合員により良いサービスを提供することが可能です。専門知識を深める過程で、他業種や地域とのネットワークを広げられる点も魅力の一つです。
面接では、どの分野でスキルを高めたいか、将来的にどんな役割を担いたいかを具体的に話せると、向上心や成長意欲を効果的に伝えられます。
⑤組合員・顧客目線で課題解決に取り組める人
全労済の仕事は、組合員や地域社会の声を丁寧に拾い上げ、最適な共済・保険サービスや支援策を提案することにあります。
相手の立場で考え、課題の本質を把握し、柔軟な発想で解決策を導ける人は、強い信頼を築けるでしょう。
課題解決そのものを楽しめる人は、顧客・組合員とのコミュニケーションも円滑に進められ、事業の質を高める原動力になります。
また、現場の声をわかりやすく伝える説明力や、要望を的確に引き出すヒアリング力も重要です。
学生時代に相談業務や提案型活動を経験した人は、その経験を自己PRに盛り込むことで即戦力としてアピールしやすくなります。
⑥長期的なキャリア形成を重視する人
全労済は、短期的な成果だけでなく、中長期的に地域や組合員に寄り添う姿勢を大切にしています。
共済・保険業界は、生活保障や災害支援など継続性の高いテーマが多く、長いスパンで取り組むことが求められます。
そのため、長期的な視野を持ち、自分のキャリアプランを明確に描ける人は、将来的に重要なポジションを任されるチャンスが広がります。
長く働く中で蓄積される知識やネットワークは、新しい事業の企画や地域課題への対応にも大いに役立ちます。
入社前からどの分野で貢献したいか、どんな専門性を磨きたいかを考え、目標を具体的に設定しておくことが、説得力のある志望動機につながるでしょう。
全労済に向いていない人の特徴

全労済は共済事業を通じて、地域社会や組合員に寄り添った保障とサービスを提供してきた全国規模の組織です。
組合理念や地域密着の活動を重視する一方で、働き方や価値観によっては合わない場合もあります。
ここでは、全労済に向いていない人の特徴を理解することで、入職後のギャップを防ぎ、自分に適したキャリア選びの参考にしていただけます。
- 協同組合の理念や地域貢献に関心が薄い人
- 全国転勤や地域活動に消極的な人
- チームワークより個人主義を優先する人
- 専門知識や資格取得に意欲がない人
- 自律的な改善より安定だけを求める人
- 長期的なキャリア形成を考えていない人
「自分らしく働ける会社が、実はあなたのすぐそばにあるかもしれない」
就活を続ける中で、求人票を見て「これ、ちょっと興味あるかも」と思うことはあっても、なかなかピンとくる企業は少ないものです。そんなときに知ってほしいのが、一般のサイトには載っていない「非公開求人」。
①あなたの強みを見極め企業をマッチング
②ES添削から面接対策まですべて支援
③限定求人なので、競争率が低い
「ただ応募するだけじゃなく、自分にフィットする会社でスタートを切りたい」そんなあなたにぴったりのサービスです。まずは非公開求人に登録して、あなたらしい一歩を踏み出しましょう!
①協同組合の理念や地域貢献に関心が薄い人
全労済は、営利追求ではなく「相互扶助」と「地域社会への貢献」を基本理念に事業を展開しています。
地域の組合員や関係団体との連携・活動を通して、多様なニーズに対応する柔軟さや主体性が求められる場面が多くあります。
この理念に共感できない、あるいは社会的意義よりも目先の効率だけを重視する人にとってはやりがいを感じにくいでしょう。
逆に、共済事業の価値を理解し前向きに取り組むことで、幅広い分野で活躍の場が広がり、組織運営や地域リーダーとしてのキャリアパスも開けます。
②全国転勤や地域活動に消極的な人
全労済は全国的なネットワークを持ち、地域ごとに異なる課題や組合員のニーズに応えるため、異動や転勤、地域活動への参加が求められることがあります。
地域での取り組みや組合員との対話は、机上では得られない現場感覚や信頼関係を築く重要な機会です。
移動や地域活動を負担と感じる人は、経験やネットワークの面で不利になることもありますが、積極的に関わることで地域課題への理解が深まり、組織内での評価や役割拡大につながります。
自らの成長や社会的意義と結びつけて考える姿勢が大切です。
③チームワークより個人主義を優先する人
全労済の業務は、組合員対応から商品企画、広報・地域連携など多くがチーム単位で進められます。
個人のペースを重視したい人や一人で完結したい人にとっては、打ち合わせや情報共有の多さに戸惑うことがあるかもしれません。
しかし、チームで取り組むことで一人では気づけない視点やノウハウを得ることができ、より質の高いサービス提供につながります。
協調性や調整力を磨けば、将来的に地域リーダーや本部スタッフなど多様なキャリアへと発展します。個人の力をチームの成果につなげる考え方が求められます。
④専門知識や資格取得に意欲がない人
全労済の事業は保険・共済制度に関する知識や法律、金融リテラシーなど高い専門性が求められます。
充実した研修や資格支援制度は整っていますが、自ら積極的に学ぶ姿勢がなければ周囲とのスキル格差が広がり、担当できる業務が限られてしまいます。
逆に、資格取得や自己研鑽に力を注ぐことで、より高度な案件や組織運営のポジションに挑戦できるようになり、キャリアや待遇面での成長も期待できます。
専門知識は最初こそハードルが高く感じるかもしれませんが、長期的には自分の市場価値を高める重要な資産となるでしょう。
⑤自律的な改善より安定だけを求める人
全労済は長い歴史と安定した基盤を持ちながらも、組合員ニーズや社会変化に合わせて新しい取り組みを進めています。
安定だけを重視し変化や改善に背を向けてしまうと、自分の強みを活かせず成長機会を逃す可能性があります。
一方、自ら課題を見つけ提案・改善を進める人は評価されやすく、昇進や幅広いキャリアの道を拓きやすくなります。
安定と挑戦の両面を意識し、自分の力でより良いサービスを創っていく姿勢が求められます。
⑥長期的なキャリア形成を考えていない人
全労済の業務は地域や組合員との信頼関係の構築に時間がかかり、短期間で成果を出しにくい特徴があります。
長期的な勤務を通じて専門性や組合活動の経験を積み重ねることで、地域や組織全体に貢献できる人材として認知されていきます。
短期間で転職を繰り返したい人や腰を据えて働く気持ちがない人にとっては、スキルやネットワークが十分に築けないままキャリアが途切れるリスクが高まります。
逆に長く働くことで、地域リーダーや本部幹部など責任ある立場を任されるチャンスが増え、報酬ややりがいも大きくなります。長期視点を持てるかどうかがキャリア形成の重要な分かれ道となります。
全労済のキャリアステップ

就活生が企業を選ぶ際には、将来どのようにキャリアを積み重ねていけるかを理解することが欠かせません。ここでは、共済事業を中心とする全労済における成長の流れを段階ごとに紹介します。
入社から10年以上にわたる経験の中で、どのような役割や専門性を築いていけるのかを見通すことができるでしょう。
- 入社1〜3年目
- 入社3〜5年目
- 入社5〜10年目
- 入社11年目以降
①入社1〜3年目
入社後の最初の3年間は、社会人としての基盤をつくり、全労済の事業や理念を理解する重要な時期です。
共済商品の提案・契約事務、組合員からの問い合わせ対応、地域での説明会や普及活動などを通じて、共済事業の現場感覚や基本知識を身につけます。
この時期に吸収した経験は、その後のキャリア形成や資格取得、さらには異動先での活躍にも直結します。各部署や地域のスタッフと協働する機会も多く、自分の適性を見極めるきっかけになります。
研修やOJTを通じて柔軟な応対力や共済制度の運営スキルを磨くことで、将来のキャリアアップに大きなアドバンテージとなるでしょう。
②入社3〜5年目
3〜5年目は、実務の幅が広がり、自立した業務遂行力が求められる段階です。
全労済では共済商品の新規加入提案、組合員ニーズに基づくプラン設計、事務処理の改善提案など、より高度で主体的な仕事を担当する機会が増えます。
新人時代とは異なり、自ら判断して業務を進め、後輩指導や小規模なイベントの運営を任されることもあります。
この時期には専門性を深めるだけでなく、リーダーシップや調整力、企画力を高めることが大切です。
自分の将来像を明確にし、上司やメンターの助言を受けながら計画的に能力を伸ばすことで、今後のキャリア選択肢が広がるでしょう。
③入社5〜10年目
5〜10年目になると、専門性を確立し、チームリーダーやプロジェクト責任者として活躍する社員が増えてきます。
全労済では組合員向けの大規模キャンペーンや地域協力プロジェクト、新規共済商品の開発や改善など、社会的意義の大きい取り組みを統括する機会が広がります。
部署や地域を超えた連携を通じて、経営視点や社会全体の動向を見渡す力を養うことができます。
専門知識を深めるだけでなく、後進の育成や人材マネジメントといった役割も求められ、組織運営の知識やスキルが必要になります。
この時期の取り組み方が、将来の役職や昇進スピードに直結するため、主体的なキャリアデザインが重要です。
④入社11年目以降
11年目以降は、管理職やスペシャリストとして全労済全体をリードする立場に進む時期です。
経営層に近いポジションで意思決定に関わるだけでなく、全国規模の共済制度改革や社会貢献プロジェクトなど、より戦略性と社会性の高い業務に携わるチャンスが広がります。
組織全体を統括する役割や新たな事業の創出など、長期的な視野で全労済の方向性を定める影響力を持つことができます。
これまで培ってきたネットワークや実績は、社外での活動や業界団体でのポジション確保にも役立ちます。
長期的なキャリアを見据える就活生にとって、この段階は将来像を描く上で重要な指標になるでしょう。
全労済の年収・キャリアの全体像を捉えよう!

全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)は、初任給から役職・職種・年齢別の平均年収まで明確な基準があり、安定したキャリア形成が可能です。
年収推移や上昇率、ボーナス・福利厚生などの手厚い待遇により、長期的に働きやすい環境が整っています。
また、競合他社との年収比較や業界内での位置づけを把握することで、自身のキャリアビジョンに合うかどうかの判断がしやすくなります。
さらに、入社年次ごとのキャリアステップが明確に示されているため、どの時点でどのスキルや役職を目指せるかが分かり、計画的な成長が期待できます。
これらの点から、全労済は安定と挑戦のバランスを求める人にとって魅力的な職場といえます。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














