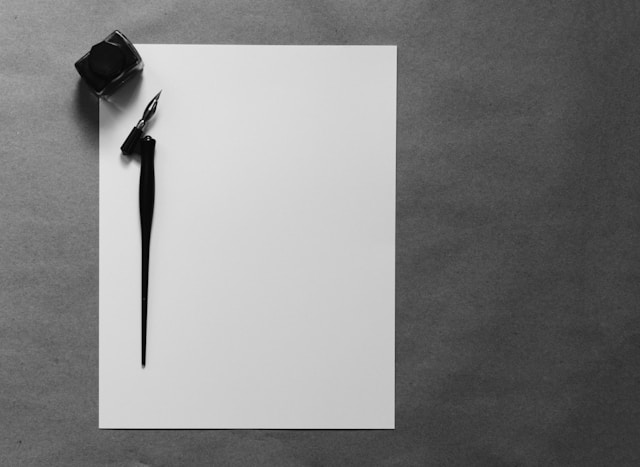就活で聞かれる「どんな保育士になりたいか」回答例と考え方
「将来どんな保育士になりたいかを教えてほしい」と問われたとき、何をどう伝えれば良いのか迷ってしまう…
面接や書類で将来のことについて問われることは多いですが、表現の仕方に悩む人も少なくありません。
そこで本記事では、考え方を整理するステップと答え方の例をわかりやすく紹介します。自分なりの将来像を描き、面接官にしっかりと想いを伝えられるよう準備していきましょう。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
「どんな保育士になりたいか」を聞かれる理由は?

就活の面接やエントリーシートでは、「どんな保育士になりたいか」という質問がよく出てきます。この質問は志望動機の確認だけでなく、あなたの価値観や働き方を多面的に見極める重要なポイントでしょう。
ここでは、面接官がどんな意図でこの質問をしているのか整理し、その背景を理解することで自分自身の強みや目指す姿をより明確にし、自信を持って話せるようになるはずです。
さらに、質問の意味を知ることで面接全体の流れや雰囲気をつかみやすくなります。質問の意味を理解して自己分析にもつなげていきましょう。
- 応募者の人柄や保育観を知るため
- 園の保育理念や方針との相性を確認するため
- 長期的に働けるかどうかを見極めるため
- 応募者の熱意を把握するため
- 子どもや保護者との関わり方を推測するため
- 保育士としての成長意欲を確認するため
①応募者の人柄や保育観を知るため
面接官が「どんな保育士になりたいか」を聞く最大の理由は、応募者の人柄や保育観を知ることにあります。
例えば、子ども一人ひとりの個性を尊重したいのか、集団生活の中で協調性を育みたいのかなど、価値観を把握することで園の理念との整合性を確認できるでしょう。
ここで伝えられる内容は、応募者の考え方や日々の姿勢に直結するため、相手が人物像をつかみやすくなります。
また、自分がなぜそのような考えに至ったのかや、その価値観をどのように形にしていきたいかまで触れることで、より深みのある印象を持たれるでしょう。
さらに、こうした背景を具体的に語ることで、応募者の人生観や信念まで垣間見せることができ、面接官がより多面的に理解しやすくなります。
②園の保育理念や方針との相性を確認するため
どんなに能力が高くても、園の理念や方針と合わなければミスマッチが生じてしまいます。そのため面接官は、応募者の理想像と園の方針がどれだけ一致しているかを重視しているのです。
園の教育方針や特色を理解することで、相手が自園でどのように働く姿を想像できるかが決まってきます。
園の理念を知ったうえで自分の考えを照らし合わせる姿勢は、職場選びに慎重で誠実な人物であるという印象も与えやすいです。また、その相性を見て応募者の適応力や柔軟さを判断する指標にもなります。
さらに、こうした姿勢は「園と応募者がともに成長できるかどうか」を測るうえでの大切なポイントともいえるでしょう。
③長期的に働けるかどうかを見極めるため
園側が採用で重視するポイントの1つが、長く働き続けられるかどうかです。
「どんな保育士になりたいか」という問いには、将来のキャリアビジョンや成長意欲が表れやすく、そこから安定的な勤務の可能性を見極められます。
園は長期的な人材確保を望んでいるため、応募者がどのような姿勢で仕事に向き合い、どれだけ継続性を持って働けそうかを慎重に見ているのです。
さらに、その人がどのように仕事の変化に対応していくかや、安定した環境でどのように経験を積んでいくかなども読み取ろうとしています。
応募者の回答には、職業観や将来的な展望だけでなく、日常の取り組み方や考え方まで反映されやすいので、園側にとって貴重な判断材料となるのです。
④応募者の熱意を把握するため
どれだけ志望動機が明確でも、熱意が伝わらなければ採用担当者の心には響きません。「どんな保育士になりたいか」という質問は、応募者の本気度や働く姿勢を知るためのものです。
相手はその人がどれほど積極的に仕事に取り組むか、またどれだけ強い思いを持っているかをこの質問から感じ取ります。
言葉の内容だけでなく、話し方や表情などからも意欲の強さを判断している場合があります。熱意があるかどうかは園全体の雰囲気に影響するため、採用時の重要な判断材料となるのです。
さらに、その熱意は「この人と一緒に働きたい」と思わせる力にもなり、園に活力を与える存在になるかどうかを見極める大きな要素にもなります。
⑤子どもや保護者との関わり方を推測するため
保育士は子どもだけでなく、その保護者や地域社会との連携も欠かせません。
面接官は「どんな保育士になりたいか」という答えから、応募者が保護者との関わりや協力体制をどのように考えているかを推測しています。
子どもと向き合うだけでなく、保護者との信頼関係づくりや同僚とのチーム保育にも関心があるかどうかがわかる質問です。
さらに、応募者がどれだけ幅広い視点を持ち、さまざまな立場の人と協調できるかを判断する材料にもなります。こうした要素は現場での安定感や柔軟な対応力にもつながるでしょう。
また、地域や家庭との橋渡し役としての姿勢をどのように考えているかも、この質問からうかがえることが多いです。
⑥保育士としての成長意欲を確認するため
保育士という仕事は資格を取って終わりではなく、常に新しい知識や技術を学び続ける姿勢が求められます。
面接官は「どんな保育士になりたいか」という質問を通じて、応募者が自分の成長にどれだけ積極的かを見ているのです。
園にとって成長意欲のある人材は長期的な戦力となるため、応募者の姿勢を知る大きなきっかけになるでしょう。また、周囲から学び取る柔軟性や新しい環境への順応力の高さも同時に評価されます。
さらに、どんな形で園に貢献し、現場の質を高めていくかを考える姿勢があるかどうかも重要な判断ポイントとなります。
どんな保育士になりたいかを考えるためのポイント
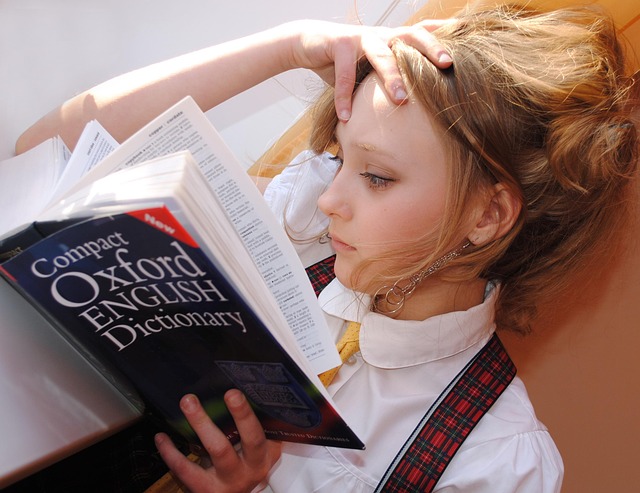
「どんな保育士になりたいか」を考える際には、いきなり答えを作ろうとせず、まず自分の考えや経験を整理することがとても大切です。
焦って結論を出すよりも、段階を踏んでじっくり考えるほうが、自分の軸が自然に見えてきます。あらかじめ準備を進めておけば、自分の価値観がより明確になり、将来的に選択肢の幅も広がるでしょう。
ここでは、理想像を深めるための考え方や視点をまとめました。視野を広げることで、自分らしい方向性を見つけやすくなり、面接や作文の準備にもつながります。
- 保育士を志したきっかけを振り返る
- 実習やアルバイトで得た学びを整理する
- 尊敬する先輩保育士やモデル像から理想像を見つける
- 子ども・保護者・同僚など多方面の視点で考える
- 自分の強みや得意分野をベースに理想像を描く
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
①保育士を志したきっかけを振り返る
自分が保育士を志した理由を思い出すことは、軸となる価値観を把握するうえでとても有効です。ここでは、過去の体験や動機を整理する視点を紹介します。
まず、幼少期や学生時代の出来事、身近な人の影響などを丁寧に書き出してみましょう。
「なぜその経験が印象に残っているのか」「どのような価値観につながったのか」を掘り下げると、自分の中にある優先順位や強みが見えてきます。
さらに、こうした出来事が現在の考え方や行動にどのように結びついているかまで考えると、将来像の土台としての説得力が増します。エピソードは大小問わず構いません。
こうした自己理解のプロセスは、他の誰かと比べるのではなく、「自分ならではの理由や価値観」を整理するための手段として役立ちます。
②実習やアルバイトで得た学びを整理する
保育実習やアルバイト経験は、自分の考えや得意分野を浮き彫りにする大切な材料です。ここでは、経験を整理し今後に活かす視点を説明することが大切です。
実習やアルバイトで感じたことを「出来事」「気づき」「成長」の3つに分けて整理すると、自分がどのような場面で力を発揮できるかがわかります。
たとえば、子どもとの関わりで工夫した点や、現場で印象に残った先輩の行動などを書き留めてみてください。成功だけでなく失敗からの学びを含めることで、より立体的な自己像が見えてきます。
さらに、経験を自分の価値観や強みと照らし合わせると、単なる記録ではなく「将来へのヒント」に変わります。
ここでの棚卸しがしっかりできていると、後々の面接や作文でも根拠を持って語れるようになります。
③尊敬する先輩保育士やモデル像から理想像を見つける
身近な先輩や専門書・記事などから理想の保育士像を探すことは、自分の視野を広げるのに役立ちます。
まず、尊敬する先輩やロールモデルの「行動」や「考え方」に注目してみてください。「自分ならどこを学びたいか」「どの要素を取り入れたいか」を具体的に書き出すと、自分の方向性が明確になります。
複数のモデル像を比較することで、偏りのない視点を持てるようにもなりますし、異なるタイプの人物からヒントを得ることもできます。
さらに、その人がどのようにキャリアを積んできたのか、その過程を調べることで、自分の成長プランを描く手がかりにもなるでしょう。
他者の良い部分をヒントに、自分自身の強みや価値観と照らし合わせることで、唯一無二の理想像を形づくれるようになります。
④子ども・保護者・同僚など多方面の視点で考える
保育士の仕事は多様な立場の人々と関わるため、幅広い視点で自分の役割を考えることが求められます。
子ども・保護者・同僚の立場それぞれで、どんな存在でありたいかを書き出してみてください。保護者との信頼、同僚との協働、子どもへのサポートなど、関わる相手によって求められる役割は異なります。
さらに、園全体や地域社会とのつながりまで視野を広げると、自分が貢献できる可能性が見えてきます。
たとえば「子どもたちに安心を与えたい」「チームの一員として周囲をサポートしたい」など具体的にイメージすることがポイントです。
このような多方面の視点を持つことで、自分の理想像がより現実的かつ具体的になり、日常の小さな行動目標にも落とし込みやすくなるでしょう。
⑤自分の強みや得意分野をベースに理想像を描く
最後に、自分の強みを軸に理想像を描く方法を紹介します。ここでは「自己分析」と「将来像のすり合わせ」を意識することがポイントです。
まず、自分の性格・得意なこと・周囲からよく褒められることなどを書き出し、それがどのような場面で活かせるかを考えましょう。
さらに、強みを「どんな保育士像に発展させたいか」という視点に変換することで、目指す方向が明確になります。
「自分の強みをどう広げていくか」「どの分野で特に活かしていきたいか」を具体的に描くと、より実践的な未来像になるでしょう。
強みを起点に理想像を描くことで、他人と比較しない自分らしい将来像をつくることができますし、これにより面接や作文においても一貫したストーリーを語りやすくなるはずです。
なりたい保育士像別「どんな保育士になりたいか」回答例文

「どんな保育士になりたいか」を考えるとき、自分の目指す姿を明確にするのは難しいものです。ここでは、具体的な例文を通して、自分の理想像をイメージしやすくするためのヒントをまとめました。
- 子どもの成長をサポートする保育士の例文
- 子どもの個性を尊重する保育士の例文
- 子どもの安全を最優先にする保育士の例文
- 保護者との信頼関係を築く保育士の例文
- チームワークを重視する保育士の例文
- 自然や遊びを大切にする保育士の例文
- 笑顔と明るさを大切にする保育士の例文
①子どもの成長をサポートする保育士の例文
子どもが日々成長していく過程を見守り、その一歩一歩を支えることは保育士にとって大切な役割のひとつです。ここでは、子どもの成長に寄り添う保育士像をイメージできる例文をご紹介します。
| 私は、子どもに寄り添い、成長をサポートできる保育士になりたいと考えています。 私は大学時代に地域の子ども向けイベントでボランティアをしたことがあり、その中で一人ひとりの成長に寄り添う大切さを学びました。 絵本の読み聞かせや簡単な工作を通して、子どもたちが新しいことに挑戦する笑顔に触れ、サポートする喜びを実感しました。 この経験から、子どもの気持ちに寄り添い、自分らしく成長できる環境を整える保育士になりたいと考えるようになりました。 |
エピソードは、自分が子どもと接した具体的な場面を思い出しながら書くとリアリティが増します。
また、活動内容とそこから学んだことをセットで入れると、読者があなたの目指す保育士像をイメージしやすくなりますよ。
②子どもの個性を尊重する保育士の例文
子ども一人ひとりが持つ個性を認め、その違いを大切にすることは保育士に欠かせない姿勢です。ここでは、子どもの個性を尊重する保育士像をイメージできる例文をご紹介します。
| 私は、子どもが持つ個性を引き出せる保育士になりたいと考えています。 私は、大学のボランティア活動で地域の子どもたちと関わった経験から、子どもの個性を大切にする保育士になりたいと思うようになりました。 ある日、工作が苦手な子が「絵を描くのは好き」と話してくれたことがあり、そのときに一人ひとりの得意なことや好きなことに寄り添う大切さを学びました。 将来は、子どもたちが自分らしさを発揮できる環境をつくり、それぞれの可能性を伸ばせる保育士として成長していきたいです。 |
例文では、大学での身近な経験から「子どもの個性を尊重する姿勢」に結びつけています。書くときは、自分が実際に体験した小さな出来事や感情を交えながら、将来のビジョンにつなげると説得力が高まりますのでおすすめです。
③子どもの安全を最優先にする保育士の例文
子どもたちが安心して生活・遊び・学びに取り組めるように安全を守ることは、保育士にとって基本かつ重要な役割です。ここでは、子どもの安全を第一に考える保育士像をイメージできる例文をご紹介します。
| 私は、子どもの環境を整え、安全を第一に考える保育士になりたいと考えています。 私は大学時代に地域の子ども向けボランティア活動に参加し、小さな事故が起きそうな場面に直面したことがありました。その時に、周囲の大人が冷静に子どもを守る姿を見て、強く心を動かされました。 将来は、子どもたちが安心して遊べる環境を整え、危険を未然に防ぐために細かな点まで目を配れる保育士になりたいと考えています。 子どもの安全を第一に考え、保護者からも信頼される存在を目指して努力していきます。 |
大学生活でのボランティアやアルバイトなど、身近な体験を通して安全への意識が芽生えたエピソードを書くと説得力が高まります。
また「子どもを守る」「安心できる環境」などの具体的な言葉を盛り込むと、読み手にイメージが伝わりやすくなるでしょう。
④保護者との信頼関係を築く保育士の例文
保育士は子どもだけでなく、保護者との信頼関係を築くことも大切な役割のひとつです。ここでは、保護者とのコミュニケーションを大切にする保育士像をイメージできる例文をご紹介します。
| 私は、子どもに寄り添うだけでなく、保護者の方にも信頼してもらえる保育士になりたいと考えています。 大学でボランティアとして保育園のお手伝いをした際、毎朝の挨拶やちょっとした声かけが保護者の安心につながることを実感しました。 子どもの成長やその日の様子をていねいに伝えると、保護者の方の笑顔が増え、私自身も信頼されているという自信を持てました。 この経験から、保護者の気持ちに寄り添い、安心感を与えられる保育士になりたいと思うようになりました。 今後はもっと多くの現場経験を重ね、子どもと保護者の両方に信頼される存在を目指して努力していきたいです。 |
例文では、大学生でも体験しやすいボランティア活動を取り上げ、保護者との関係づくりを自然に描いています。
書くときは「どんな行動が保護者の安心や信頼につながったのか」を具体的に示すと、より読者に伝わりやすくなりますよ。
⑤チームワークを重視する保育士の例文
子どもたち一人ひとりに丁寧に向き合うためには、同僚や保護者とのチームワークが欠かせません。ここでは、協力し合いながら保育に取り組む保育士像をイメージできる例文をご紹介します。
| 私は、子どもたちに丁寧に向き合うため、同僚や保護者の方とも積極的にコミュニケーションをとる保育士になりたいと考えています。 私は大学のサークル活動で後輩の指導を任された経験があります。当初は自分のやり方にこだわってしまい、チーム全体の意見を取り入れられずに悩んだこともありました。 しかし、仲間の考えを尊重し、一緒に企画を進めるうちに、より良い成果を生み出せることに気づきました。 この経験から、保育の現場でも同僚や保護者と積極的に意見交換を行い、子どもたちにとって安心で楽しい環境づくりに貢献したいと考えています。 |
この例文では、大学生活での身近な経験を通して協調性や柔軟性をアピールしています。
同じようなテーマを書く場合は、結果よりも過程に焦点を当て、どのようにチームで成長できたかを具体的に表現すると効果的です。
⑥自然や遊びを大切にする保育士の例文
子どもが自然や遊びを通してさまざまな経験を積み、その中で学びや成長を深めることはとても大切です。ここでは、自然や遊びを通して子どもを育む保育士像をイメージできる例文をご紹介します。
| 私は、子どもたちの学びをサポートできるよう、環境や遊びを大切にする保育士になりたいと考えています。 私は大学時代に地域の公園で子どもたちと一緒に遊ぶボランティア活動に参加し、自然の中で自由に遊ぶ時間が子どもの成長に大きな影響を与えることを実感しました。 この経験から、子どもたちが自然に触れながら好奇心や探究心を育める環境づくりを大切にしたいと考えるようになりました。 保育士としては、遊びの中で学びや発見をサポートし、子ども一人ひとりの個性や興味を尊重しながら、のびのびと過ごせる時間を提供できる存在になりたいです。 |
ボランティアや実習など具体的なエピソードを入れることで、読者に自分ごととしてイメージさせやすくなります。
同じテーマで書く場合も「どこで・どんな体験をして・何を学んだか」を意識して書くと説得力が増しますよ。
⑦笑顔と明るさを大切にする保育士の例文
子どもたちに安心感と楽しさを届けるためには、笑顔や明るい雰囲気がとても大切です。ここでは、笑顔と明るさをもって子どもたちを支える保育士像をイメージできる例文をご紹介します。
| 私は、子どもたちに安心を届けるためにも、常に笑顔と明るさを大切にする保育士になりたいと考えています。 大学時代、地域の子ども会でボランティアとしてイベントの企画やお手伝いをした経験があります。 最初は緊張していましたが、子どもたちと一緒に遊んだり歌ったりするうちに、笑顔で接することが安心感や信頼につながることを実感しました。 この体験を通して、子どもたちが楽しく過ごせる環境を作るには、明るく元気な態度が欠かせないと強く感じました。 将来は、どんなときも子ども一人ひとりの気持ちに寄り添い、笑顔と明るさで保育の現場を支える保育士になりたいと思っています。 |
この例文では、自分の体験から「笑顔と明るさ」の重要性を学んだ過程を具体的に書くことで説得力を高めています。
似たテーマを書くときは、自分の経験した小さな出来事や心の変化を入れることで、オリジナリティのある文章に仕上げやすくなるはずです。
「どんな保育士になりたいか」面接での答え方

就活の面接で「どんな保育士になりたいか」と聞かれるのは、あなたの価値観や仕事観を確かめる大切な機会です。ここでは、面接官に好印象を与えつつ自分らしさをしっかり伝える方法を紹介します。
準備の段階で方向性を決めておくと、自分の強みや目標がより鮮明になり、選考にも自信を持てるでしょう。
- 志望先の保育理念を軸に自分の考えを伝える
- 自分の経験を具体的に語って理解を深めてもらう
- 子どもへの思いや将来像を明確に示す
- 面接全体で一貫したメッセージを保つ
- 限られた時間で印象に残る話し方を工夫する
①志望先の保育理念を軸に自分の考えを伝える
面接で印象を高めるには、志望する園や施設の保育理念を深く理解し、それに沿った自分の方向性を語ることが欠かせません。単に「やさしい保育士になりたい」と述べるだけでは抽象的になりがちです。
「子どもの主体性を大切にする園の理念に共感し、一人ひとりの個性を伸ばす保育士を目指したい」といった形にすると、説得力が大きく増します。
ホームページや説明会、園見学などで園の特徴を把握し、自分の価値観との共通点を探しておくと安心です。
理念に沿った発言は、志望動機や自己PRの一貫性を示せるだけでなく、採用後のイメージも具体的に持ってもらいやすくなります。
さらに、自分の経験と結びつけて語ると、現実味のある自己紹介として印象づけられるでしょう。
②自分の経験を具体的に語って理解を深めてもらう
面接官に自分の姿勢を伝えるには、経験に基づいたエピソードを添えることが効果的です。
大学での保育実習や地域のボランティア活動、子どもと接した際に工夫したことなど、あなたらしい体験を選びましょう。エピソードは1つに絞り、短くても内容を鮮明に伝えることが大事です。
その際、「何を学び」「どのように活かしたいか」を添えると成長意欲や分析力が伝わります。
例えば「子どもの自己表現を支援する取り組みで自信がついた」など具体的な成果を含めると、言葉に重みが出ます。
単なる思い出話にせず、今後の目標や志望する園の特徴につなげることで、より一貫性のあるメッセージが完成します。結果として「働く姿」を自然に想像してもらえるでしょう。
③子どもへの思いや将来像を明確に示す
どんな保育士を目指すかを伝えるには、子どもに対する思いや将来像をはっきり示すことが欠かせません。
「子どもの気持ちに寄り添う」などの抽象的な言葉ではなく、「子どもが自分で挑戦する機会を尊重したい」「保護者とも連携して子どもの成長を支えたい」といった具体的な姿勢を語ると、印象が大きく変わります。
また、その考えに至った背景やきっかけを補足すると、自分らしさが強調されます。実習やアルバイトで得た小さな気づきや成功体験でも十分です。
園の方針や教育観と重なる部分を示せば、採用後のビジョンをイメージしてもらいやすくなり、選考全体を通じて一貫した印象を残せるでしょう。
こうした具体性は、面接官の記憶に残る大きな要因となります。
④面接全体で一貫したメッセージを保つ
面接では「志望動機」「学生時代に頑張ったこと」など複数の質問が続くため、答えがぶれてしまうと説得力が落ちます。
「子どもの主体性を大切にする」と話したなら、自己PRや志望動機でも同じテーマを盛り込むようにすることが大切です。
また、複数の質問に対応できるエピソードを準備しておくと、落ち着いて話せるだけでなく印象の統一感も高まります。
練習の際には録音や模擬面接を活用し、自分の回答にどんな癖があるか、どこで強調が足りないかを確認してください。
一貫したメッセージを保つことができれば、採用担当者に安定感や信頼感を示せるでしょう。
⑤限られた時間で印象に残る話し方を工夫する
面接の持ち時間は限られているため、短い時間で印象を残す工夫が重要です。長い説明よりも、結論→理由→具体例→まとめという流れを意識するとわかりやすくなります。
落ち着いた声や表情、姿勢など非言語の要素にも気を配ると、より好印象を持たれやすいでしょう。
事前に自分の回答を200字程度にまとめて練習したり、友人やキャリアセンターのスタッフに聞いてもらって改善点を見つけたりするのも効果的です。
また、強調したい言葉やジェスチャーをあらかじめ決めておくと、本番で自然に伝えられます。
こうした準備を積み重ねることで、自信を持って簡潔に話せるようになり、結果的に熱意や将来像がより鮮明に伝わるでしょう。
「どんな保育士になりたいか」面接での注意点

就活生が保育士面接で「どんな保育士になりたいか」と聞かれるのは、自分の価値観や仕事観を確認するためです。しかし、内容によっては面接官に誤解を与えることもあります。
ここでは、注意すべきポイントを具体的に解説し、失敗を防ぐコツを知ることで自信を持って答えられるように導きます。
さらに、面接全体の流れを理解することで、自分らしい強みを引き出しやすくなります。
- 過剰な理想像にならないようにする
- 強すぎるこだわりを避ける
- 面接官に好印象を与える態度を意識する
- 園ごとの特色に合わせて答えを調整する
①過剰な理想像にならないようにする
多くの就活生が面接で好印象を与えようとして、理想的すぎる保育士像を語りがちです。しかし、過剰な理想は「現実との乖離が大きい」と受け止められる恐れがあります。
まず、子どもたち一人ひとりに寄り添いたいという基本姿勢を軸に置き、自分なりの得意分野や実習経験に基づいたエピソードを交えて伝えてください。
現実的かつ熱意のある言葉は、採用側に誠実さを印象づけるでしょう。
理想を語る際は「努力して身につけたいスキル」や「先輩から学びたい姿勢」など未来への成長意欲を含めると、バランスのとれた人物像を示せます。
また、理想と現実のどちらも理解していることを表現することで、採用側に安心感や信頼感を与える効果も期待できますよ。
②強すぎるこだわりを避ける
「絶対にこうでなければならない」という強いこだわりは、協調性の欠如や柔軟性不足と見られることがあります。
特に園にはそれぞれ独自の方針やカリキュラムがあり、それに適応できる姿勢が求められるでしょう。
回答時には、自分の考えや理想を述べつつも「園の方針に合わせて柔軟に取り組む意欲があります」と補足することが大切です。
さらに、こだわりを語る際には「これは自分が大切にしている考えだが、園の取り組みを理解し尊重していく」という姿勢をセットで示すと、柔軟性を強く印象づけられます。
自分の想いを一方的に押し出すのではなく、相手のニーズに寄り添うことで、信頼を得られる面接回答につながるでしょう。
③面接官に好印象を与える態度を意識する
「どんな保育士になりたいか」という内容だけでなく、その伝え方や態度も重要です。表情や声のトーン、姿勢など、非言語の要素が評価に大きく影響します。
例えば、落ち着いた笑顔や相手の目を見る姿勢は、自信と誠実さを示す手段となります。また、過去の経験や学びを具体的に示しながら語ると、言葉に説得力が増すでしょう。
さらに「子どもや保護者の立場を尊重する姿勢」や「学び続ける意欲」を言及すると、仕事に対する前向きな気持ちを伝えられます。ここで大切なのは、言葉と態度を一致させることです。
緊張している場合でも、深呼吸をして話すスピードをゆっくりにするだけで印象が変わります。態度と内容を一貫させることが、面接官に安心感と信頼感を与える決め手になるでしょう。
④園ごとの特色に合わせて答えを調整する
保育園や幼稚園には、それぞれ異なる教育方針や保育スタイルがあります。そのため、応募先の特色に応じて回答内容をカスタマイズすることが欠かせません。
事前に園のホームページや説明会で得た情報を踏まえ、「この園では○○な取り組みが特徴的なので、私もその一員として力を発揮したいです」といった形で具体的に言及すると効果的でしょう。
こうした回答は「調査力」や「準備力」をアピールすることにつながり、志望度の高さを裏付けることにつながります。
さらに、自分の経験や価値観と園の特徴がどのように重なるのかを整理し、具体例を交えて話すと説得力が増すはずです。
「どんな保育士になりたいか」作文での答え方
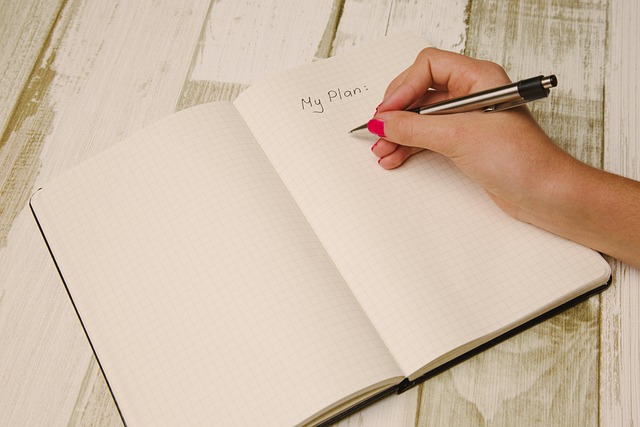
就活における作文は、自分の考えや姿勢を的確に伝える大切な機会です。特に「どんな保育士になりたいか」というテーマは、面接官が志望者の価値観や将来像を知る重要な手がかりになります。
ここでは、説得力と個性を兼ね備えた作文の書き方を段階的に解説します。自分らしさをしっかり伝えることで、他の応募者との差別化も期待できるでしょう。
- 結論から書いて読みやすくする
- 印象に残るエピソードを盛り込む
- 志望動機や経験とのつながりを示す
- 自分らしさを具体的に書いて強調する
- 他の応募書類との整合性を意識する
①結論から書いて読みやすくする
作文の冒頭で結論を提示すると、読み手に強い印象を与えやすくなります。まず、自分が「どんな保育士になりたいか」を一文で示し、その後に理由や背景を説明してください。
例えば「子どもの個性を尊重し、のびのびと育てる保育士になりたい」と先に書き、その動機や体験を補足する形です。結論先行の文章は説得力を高め、面接官にも記憶されやすいでしょう。
さらに、文章全体の骨組みが明確になり、推敲もしやすくなります。初めに結論を置くことで、限られた文字数の中でも伝えたいことがしっかり伝わり、他の応募者との差別化にもつながりますよ。
②印象に残るエピソードを盛り込む
作文にエピソードを入れると、言葉にリアリティが生まれ、人物像が浮かびやすくなります。特にアルバイトやボランティア、サークル活動など、子どもや教育に関わる経験がある場合は有効です。
具体的な行動や感情を交えて書くと、読み手が共感しやすく、単なる理想論ではない姿勢を示せます。短いエピソードでも一貫した価値観を伝えれば、作文全体に深みが増しますよ。
さらに、保育に対する自分の考え方や姿勢を自然に表現できるため、採用担当者が「この人はどんな価値観を持っているか」を理解しやすくなるでしょう。
自分ならではの視点を持ち込むことが、印象を強めるポイントです。
③志望動機や経験とのつながりを示す
「どんな保育士になりたいか」を語るときは、志望動機や過去の経験と自然に結びつけることが重要です。
例えば保育園実習で学んだことや子どもと接した経験を文章に組み込むことで、考えに根拠があると伝わります。過去の経験→学び→将来像という流れを意識すれば、文章に一貫性が出てきます。
また、自分が感じた課題や成長ポイントも正直に書くと、向上心や誠実さが伝わるでしょう。
さらに、経験を通じて見つけた強みや得意分野を盛り込むことで、保育士としての将来像をより具体的に示せます。面接官に「実体験を通して保育を考えている」と感じてもらうことが大切です。
④自分らしさを具体的に書いて強調する
作文では、自分らしさを曖昧にせず、具体的に表現することが鍵です。
「やさしい保育士」「明るい保育士」といった抽象的な言葉だけでなく、「子どもの話を一人ひとり丁寧に聴き、日々の変化に寄り添える保育士」のように具体像に落とし込むとよいでしょう。
さらに、自分の性格や価値観を示す事例を添えると、企業側にイメージが伝わりやすくなります。
加えて、自分がどんな工夫をしながら子どもと関わってきたか、どんな考え方を持っているかを書き添えると、文章に説得力が増します。
オリジナリティを意識して、自分ならではの強みや視点を盛り込むことが差別化につながりますよ。
⑤他の応募書類との整合性を意識する
作文は、履歴書やエントリーシートなど他の応募書類と一貫性があることが大切です。内容や表現にずれがあると、面接官に準備不足と見られかねません。
自己PRや志望動機と同じ軸を持たせることで、キャリアビジョンがより鮮明になるでしょう。文章のトーンやキーワードをそろえると統一感が増し、信頼感も高まります。
さらに、文章全体の表現やエピソードも他の書類と重複しないように調整しながら整合性を確保すると、より印象が良くなります。
事前に他の書類を見直し、共通するテーマを確認してから作文に取り組んでください。説得力のある自己表現ができ、結果として自分の強みを最大限に引き出せるでしょう。
「どんな保育士になりたいか」どうしても思いつかないときの対処法

就活で「どんな保育士になりたいか」を聞かれても、うまく答えられず悩む学生は少なくありません。これは自己理解や情報収集がまだ不十分な場合に多く見られる課題です。
そんなときは一度立ち止まり、具体的な行動を通じて自分の理想像を見つけることが有効でしょう。
ここでは、発想を広げるための書き出しワークから情報収集、相談や模擬面接、園見学まで、段階的にできる対処法を紹介します。
自分らしい保育士像を確立することで、選考時の回答にも自信が持てるようになります。
- 書き出しワークでアイデアを広げる
- 就職サイトやSNSで他人の例を調べてヒントを得る
- 友人や先輩に相談してフィードバックをもらう
- 模擬面接や自己分析ツールを活用して整理する
- 気になる園の説明会やインターンに参加してイメージを膨らませる
①書き出しワークでアイデアを広げる
「どんな保育士になりたいか」を考えるとき、まずは頭の中だけで悩まず、紙に書き出すことが効果的です。
例えば自分が得意なこと、子どもにどのような影響を与えたいか、尊敬する先生の特徴などを書き出すと、漠然としていたイメージを具体的にできます。
さらに「なぜそう思うのか」を掘り下げながら書くと、自分の価値観や強みが整理され、面接でも自信を持って答えられるでしょう。
また、思考がまとまらないときは「理想の1日」や「やりがいを感じる瞬間」などテーマを決めて書くと、イメージがより広がるはずです。
時間を決めて短時間で一気に書くと、思わぬアイデアが浮かびやすくなり、自己分析の質も高まりますよ。
②就職サイトやSNSで他人の例を調べてヒントを得る
自分一人で考えていると視野が狭くなりがちです。そんなときは就職サイトやSNSを活用し、他の就活生や現役保育士の声に触れるとヒントが得られます。
先輩たちがどのように「なりたい保育士像」を表現しているかを調べることで、自分の考えとの共通点や違いが見えてきますよ。
また、具体的な事例を知ることで、自分が共感するポイントや避けたい方向性も明確にできるはずです。特にブログや動画など、インタビュー形式の記事を見ると、現場のリアルな声や体験談を学べるでしょう。
注意点としては、あくまで参考にとどめ、オリジナリティを持った回答につなげる意識が大切です。情報を取りすぎて迷ってしまう前に、自分なりの基準を決めて整理してください。
③友人や先輩に相談してフィードバックをもらう
自己分析を進めるうえで、第三者の視点を取り入れることは大きな助けになります。友人や先輩に相談することで、自分では気づいていなかった強みや印象を教えてもらえるからです。
特に保育実習やボランティアを経験した人からの具体的なアドバイスは、自分の考えを深めるヒントになります。
さらに相談の場では、自分の考えを言葉にして話すことで整理が進み、思わぬ気づきが得られることもあります。
相談する際は、単に「どんな保育士がいいと思うか」ではなく、自分が考えている方向性を伝えたうえで意見を求めると、より実践的なフィードバックが得られるはずです。
相談相手を変えることで、異なる視点を集めやすくなる点にも注目してください。
④模擬面接や自己分析ツールを活用して整理する
模擬面接や自己分析ツールは、自分の考えを客観的に確認するために役立ちます。模擬面接を通じて話してみると、自分の表現がどこで曖昧になっているかが明確になり、改善点が見えてくるでしょう。
また、性格診断や価値観診断などのツールを使うと、自分でも気づかなかった特徴が浮かび上がり、志望動機や将来像を補強する根拠にできます。
さらにツールの結果を参考にして、自分の過去の経験とつなげると、説得力のあるストーリーを組み立てやすくなりますよ。
こうした方法を組み合わせることで、回答の説得力が高まり、面接官に印象づける話ができるようになるはずです。特に自分の軸をはっきり示せるようになると、面接や作文での緊張もやわらぐでしょう。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
⑤気になる園の説明会やインターンに参加してイメージを膨らませる
最終的に「どんな保育士になりたいか」をより鮮明にするには、現場を知ることが欠かせません。
気になる園の説明会やインターンに参加することで、園の方針や先輩職員の働き方を直接見ることができ、自分の理想像と照らし合わせる材料になります。
また、現場で感じたことや印象に残ったエピソードは、そのまま面接や作文の具体例として活用できます。
さらに現場での経験は、自分がどんな環境で力を発揮できるかを知る手がかりにもなり、長く働ける職場選びにも役立つでしょう。
自分に合う環境を知ることは、面接対策だけでなく、入職後のミスマッチ防止にもつながります。興味がある園が複数ある場合は、比較してみることも新しい発見につながるかもしれません。
「どんな保育士になりたいか」に関するよくある質問

就活の面接や作文で「どんな保育士になりたいか」と聞かれると、どう答えればよいか迷う人は多いでしょう。ここでは、よくある質問に対して就活生が安心して準備できるような視点をまとめています。
ポイントを押さえた回答や考え方を知ることで、自己PRの質が高まり、自信を持って面接に臨めるはずです。
さらに、ここで紹介する考え方をもとに自己分析を深めることで、説得力のある志望動機や自己PRがより具体的に作れるでしょう。
- 子どもが好きなだけで志望してもいいですか?
- 「まだ決まっていない」と正直に言ってもいいですか?
- 園の理念と少し違っても正直に話していいですか?
- 保育士以外のキャリアの話をしてもいいですか?
①子どもが好きなだけで志望してもいいですか?
「子どもが好きだから」という動機は、保育士を志す上で自然な出発点です。
しかし、それだけでは「なぜ保育士なのか」「どんな働き方をしたいのか」という深い部分が伝わりにくく、印象が弱まる可能性があります。
そこで「子どもが好き」という気持ちに加え、自分がどのようなサポートをしたいか、どんな場面で力を発揮できるかを具体的に話してください。
例えば「子どもの自立を促す保育を実践したい」「保護者との信頼関係を大切にしたい」など、自身の経験やエピソードを交えて話すと説得力が増します。
さらに、自分が保育士としてどのような姿勢で仕事に取り組むのか、将来的にどんな成長を目指しているのかも一緒に伝えるとより好印象につながるはずです。
感情を土台にしつつ、ビジョンや行動に結びつけることで、印象に残る志望動機になるでしょう。
②「まだ決まっていない」と正直に言ってもいいですか?
「まだ決まっていない」という回答は正直ですが、そのまま伝えると消極的な印象を与えかねません。
面接官は明確なビジョンを求めているのではなく、あなたが保育士としてどんな価値を提供したいかを知りたいのです。
そのため、「まだ模索中です」という表現に留めず、「いくつかの保育観を学びながら、自分に合うスタイルを探しています」など成長意欲や主体性を示すと評価が高まります。
また、過去のアルバイトや実習経験から得た学びを引用し、「今後も研修や現場を通じて理想像を深めていきたい」と添えると、より具体性が増します。
まだ決まっていないことをマイナス要素にせず、柔軟さと学び続ける姿勢として打ち出すのが効果的ですよ。
③園の理念と少し違っても正直に話していいですか?
園の理念と自分の考えが完全に一致しないことは珍しくありません。むしろ、理念を理解したうえで自分の価値観を整理し、その違いをどう受け止めるかが重要です。
正直に話す場合でも、否定的な表現を避け、「御園の〇〇な取り組みに共感しつつ、私は〇〇という視点も大切にしたいと思っています」といった前向きな言い回しにしましょう。
理念に対する理解と、自分なりの保育観を両立させることで、柔軟かつ主体性のある人材として評価されます。
さらに、異なる視点を持つことで園に新しい価値をもたらせる可能性があることや、自分の考えをアップデートしながら園の方針に合わせていく柔軟性があることも伝えるとよいでしょう。
自分の考えを無理に合わせる必要はなく、園ごとの特色を尊重しながら成長していく意欲を示すことが大切です。違いを恐れるより、対話を通じて互いの理解を深める姿勢をアピールしてください。
④保育士以外のキャリアの話をしてもいいですか?
面接で保育士以外のキャリアに触れることは、慎重な配慮が必要です。なぜなら、保育士として長く働く意欲が疑われる可能性があるからです。
ただし「将来の幅広い視野の一環として考えている」と伝える形であれば、逆に多様な経験を持つ強みとして受け取られることもあります。
例えば「今は保育士として経験を積み、将来的には子どもや家庭を支える別の領域にも関心があります」といった形です。重要なのは「まずは保育士として全力で取り組む意欲」を明確に示すことです。
さらに、なぜ保育士からキャリアをスタートさせたいのか、その理由を添えることで、意欲や誠実さが一層伝わります。
選考側が知りたいのはあなたの現在の軸なので、未来像を語る際は「今やりたいこと」とのバランスに注意してください。
自分だけの理想の保育士像を描いてみよう

「どんな保育士になりたいか」という質問は、面接や作文で必ず聞かれる大切なテーマです。これは、あなたの人柄や保育観、園との相性、長く働く意欲などを総合的に判断するためにあります。
だからこそ、保育士を志したきっかけや実習経験、尊敬する先輩などを振り返り、子ども・保護者・同僚への関わり方や自分の強みを整理してみましょう。
そして志望先の保育理念や具体的なエピソードを踏まえて、自分の言葉で伝えることが大切です。
こうして準備を重ねれば、自分らしい「どんな保育士になりたいか」の答えが自然と見つかり、面接や作文でも一貫性と説得力を持って表現できるようになりますよ。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。