就活で名刺をもらったら?受け取り方から保管方法まで徹底解説
「就活で企業から名刺をもらったけれど、正しい対応方法が分からない…」と戸惑う人も多いのではないでしょうか。
実は名刺の受け取り方や扱い方には細かなマナーがあり、社会人としての基本が試される場面でもあります。
また、名刺はただ受け取るだけでなく、整理・活用することで就活やその後の人脈づくりにもつながります。
本記事では、就活で名刺をもらった際の正しい受け取り方から保管・活用法、さらには学生自身の名刺準備の必要性まで徹底解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
就活で名刺をもらったらどうする?

就活の場では、面接官やOB訪問で社会人から名刺をもらうことがあります。どう受け取るべきか迷う学生は多くいますが、適切な行動をとれば好印象を与えられ、今後のつながりを広げるきっかけにもなります。
名刺を受け取るときは、相手に敬意を示すことを意識することが大切です。椅子に座ったままではなく立ち上がり、両手で丁寧に受け取って一礼すると、礼儀正しい印象を与えられます。
その後、すぐにしまうのではなく一度目を通し、相手の氏名や役職を確認してから「よろしくお願いいたします」と言葉を添えるとより丁寧です。
きちんとしたマナーで対応できないと、社会人としての準備不足と受け取られてしまうこともあります。小さな動作ですが、誠意が伝わるかどうかを左右する重要な場面といえるでしょう。
このように、名刺はただ受け取るだけでなく、感謝を伝え、丁寧に扱い、その後の連絡に活用することが大切です。小さな所作の積み重ねが、信頼を得る第一歩になるでしょう。
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
就活の面接や説明会で名刺を渡す企業側の意図

就活の場では、学生が企業から名刺を受け取る機会が多くあります。名刺交換は単なる連絡先の提示ではなく、複数の意味を持っています。
企業側の狙いを知っておけば、正しい対応ができるだけでなく、自分の印象を良くするきっかけにもなるでしょう。ここでは、企業が名刺を渡す背景について解説します。
- 採用担当者の氏名と役職を明確に伝えるため
- 学生に安心感を与えるため
- 企業の存在やブランドを印象づけるため
- 学生に「社会人マナーを試す」狙いがあるため
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
①採用担当者の氏名と役職を明確に伝えるため
企業が名刺を渡す基本的な理由は、担当者の氏名や役職を正しく知ってもらうためです。
就活では短時間で多くの学生と接するため、口頭だけの紹介では名前を忘れてしまったり、役職を聞き間違えたりする可能性があります。
名刺があれば、面接後にお礼のメールを送る際も名前や肩書きを正確に記載でき、失礼を避けられるのです。
さらに、名刺を確認しながら会話を進めれば相手への意識が高まり、親近感や信頼感も生まれやすくなります。
名刺は単なる情報カードではなく、学生と企業をつなぐ大切なコミュニケーションの橋渡しといえるでしょう。
②学生に安心感を与えるため
初対面の場では緊張する学生が多く、企業が名刺を渡すのは安心感を与える狙いもあります。
名刺には会社名や住所、電話番号、担当者の役職などが記載されているため、「この人は確かに会社を代表している」と実感できるのです。
特に、合同説明会のように複数の企業担当者と会う場面では、顔と名前を一致させるのが難しい場合がありますが、名刺があれば後で振り返りやすく混乱を防げます。
学生に信頼できる環境を整えることは、円滑なコミュニケーションを進めるうえで大切な意味を持つのです。
③企業の存在やブランドを印象づけるため
名刺は単なる連絡先ではなく、会社の顔としての役割も担っています。
社名ロゴやフォント、色使い、紙質などのデザインには、それぞれの企業が大切にしている姿勢やブランドイメージが反映されているものです。
名刺を通じて「この会社は堅実そう」「新しいことに挑戦していそう」といった印象を学生に残すことができます。さらに、多くの企業担当者と会ったあとでも、名刺が手元にあれば記憶を呼び起こす助けになるでしょう。
小さな紙片であっても、学生に企業の存在を伝え、自社を思い出してもらう「広告」の役割を果たしているのです。
④学生に「社会人マナーを試す」狙いがあるため
就活の現場では、名刺交換を通じて学生の礼儀や所作を確認する意図も含まれています。名刺をどう受け取るかで、相手に対する敬意や細やかな気配りが表れるものです。
両手で丁寧に受け取り、一度しっかり目を通してから大切に扱う姿勢を見せれば、好印象につながります。
反対に、片手で雑に受け取ったり、すぐにカバンへしまったりすると、マナーを理解していないと判断されるおそれも。
名刺交換自体が合否を決めるわけではありませんが、社会人としての素養を測る「小さな試験」として見られる場面もあるでしょう。
名刺をもらったときの正しい受け取り方

就活中に名刺をもらう場面では、受け取り方ひとつで印象が変わります。正しいマナーを身につけることは、社会人としての第一歩です。
形式的に見える所作も、相手への敬意を示す大切な要素になります。ここでは、名刺をもらったときの正しい受け取り方を順に説明しています。
- 椅子から立ち上がって受け取る
- 両手で受け取り一礼する
- 名刺に目を通して氏名と役職を確認する
- 名刺は名刺入れの上やテーブルの左側に置く
- 複数の名刺をもらった場合は並べて置く
①椅子から立ち上がって受け取る
名刺を受け取るときは、着席したままではなく立ち上がることが基本です。座ったままでは、横柄な印象を与えてしまうでしょう。
立ち上がることで相手への敬意が伝わり、礼儀正しい学生だと感じてもらえます。特に、面接や説明会では第一印象が大切です。姿勢を正して立ち、相手の目を見て受け取れば、誠実さが自然と伝わります。
また、相手が立って差し出している場合には、必ず同じ高さで応じることが求められます。相手に合わせる意識を持つことが、社会人としてふさわしい振る舞いにつながるでしょう。
②両手で受け取り一礼する
名刺は単なる紙ではなく、相手の分身と考えられるため、片手で受け取るのは失礼にあたります。必ず両手で受け取り、胸の高さで丁寧に受け取ったうえで軽く一礼しましょう。
形式的に思える所作であっても、敬意を示す重要な動作です。ここで「いただきます。よろしくお願いいたします」と感謝の言葉を添えれば、さらに良い印象を与えられます。
ほんの数秒の違いですが、その心がけが相手の記憶に残るものです。社会人はこうした小さな所作の積み重ねを重視しているため、気を抜かないよう注意してください。
③名刺に目を通して氏名と役職を確認する
名刺を受け取ったら、そのまましまわず必ず目を通しましょう。氏名や役職を確認することで、相手の顔と名前を結び付けることができます。
会話の中で名前を呼びかければ、相手は「覚えてもらえている」と感じ、自然に親近感を持つはずです。さらに、後日お礼のメールを送る際に誤字や役職の間違いを防げるという、実務的なメリットもあります。
名刺を見ながら「○○様ですね」と口にすることで確認にもなり、好印象を与えられるでしょう。このひと手間が、その後のやり取りをスムーズにする大切なポイントになります。
④名刺は名刺入れの上やテーブルの左側に置く
受け取った名刺はすぐにカバンやポケットにしまわず、自分の正面に置くのが礼儀です。名刺入れの上やテーブルの左側に置くことで、相手を敬う気持ちが伝わります。
会話の途中で視線を落とすと、名前や役職を確認できるため、話の流れを自然にサポートする効果もあるでしょう。机の上に直接置かず、必ず名刺入れを下に添えると一層丁寧な印象になります。
これはちょっとした工夫ですが、細やかな所作として相手の評価を高める要因になりやすい点です。
⑤複数の名刺をもらった場合は並べて置く
合同説明会や座談会では、複数の担当者から名刺をいただくケースも珍しくありません。その際は、座っている位置に合わせて名刺を横並びに置くことが基本です。
こうすることで、誰がどの役職なのかを一目で把握でき、会話をスムーズに進められるでしょう。名刺を重ねたり、無造作に扱ったりすると相手への配慮が欠けて見えてしまいます。
整理整頓された並べ方を意識することで、几帳面さや丁寧さが伝わり、信頼感を得られるでしょう。ちょっとした心配りが「気配りのできる学生」として評価されるきっかけになります。
名刺を受け取る際の注意点
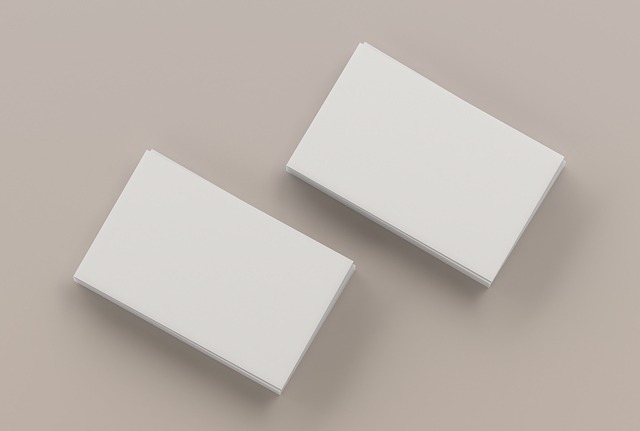
名刺を受け取る場面では、基本的なマナーだけでなく細かな注意点も意識することが大切です。小さな所作や扱い方の違いで、相手に与える印象は大きく変わります。
ここでは、名刺を受け取るときに気をつけたい具体的なポイントを整理しました。
- 相手の目を見て丁寧に受け取る
- 机越しに名刺を受け取らないようにする
- 受け取った名刺を置き忘れを避ける
- カバンや財布に直接しまわないようにする
①相手の目を見て丁寧に受け取る
名刺を受け取る際には、相手の目をしっかり見て対応することが基本です。視線を合わせることで「あなたを大切に思っています」という気持ちが伝わり、信頼感が生まれやすくなります。
うつむいたままや無表情で受け取ると、形式的で冷たい印象を与えてしまうでしょう。特に、就活の場では、第一印象が評価に直結するため注意が必要です。
また、両手で丁寧に受け取りながら「ありがとうございます」「よろしくお願いいたします」と一言添えると、相手に安心感を与えられるでしょう。
こうした言葉は短くても心に残りやすく、好印象につながります。動作と表情、言葉がそろうことで誠実さが強調され、礼儀正しい学生だと感じてもらえるでしょう。
②机越しに名刺を受け取らないようにする
名刺交換のときにやってしまいがちなのが、机を挟んだままの受け取りです。しかし、これは失礼にあたり、社会人としてのマナーを欠いていると判断される恐れがあります。
机越しに手を伸ばすのではなく、必ず立ち上がって相手の正面に移動し、同じ目線の高さで受け取ることが大切です。
この一手間をかけることで、相手に「きちんと礼を尽くしている」と伝わります。動作を省略してしまうと「手間を惜しむ学生」という印象を与えかねません。
就活の場では些細なことも評価対象になるため、立ち位置や動作に気を配りましょう。名刺を渡す相手も自分の振る舞いをよく見ていると意識しておくと安心です。
③受け取った名刺を置き忘れを避ける
名刺をいただいた後、机の上に置きっぱなしにして、そのまま退席するのは非常に失礼です。置き忘れは「相手の存在を軽んじている」と受け取られる可能性があり、せっかくの好印象を損なう原因になります。
名刺は相手そのものを象徴する大切なものなので、最後まで責任を持って扱わなければなりません。話が終わったら、相手に見える形できちんと名刺入れにしまいましょう。
その際も雑にしまうのではなく、姿勢を正して落ち着いて行動することが重要です。整理整頓を心がける姿勢は「この学生は信頼できる」と感じてもらうきっかけになります。
ちょっとした気配りの積み重ねが、社会人としての評価を高めるのです。
④カバンや財布に直接しまわないようにする
受け取った名刺を、そのままカバンや財布に入れてしまうのは大きなマナー違反です。名刺は相手の分身とされるため、乱雑に扱うと「軽んじられた」と不快に思われてしまいます。
名刺をいただいた直後は必ず名刺入れを使い、丁寧に保管してください。もし、名刺入れを持っていない場合は、ノートの間やファイルのポケットなどで一時的に保護すると良いでしょう。
ただし、就活を続けるうえでは名刺入れは必需品です。落ち着いたデザインのものを準備しておくと安心ですし、社会人としての意識を示すことにもつながります。
こうした準備の有無は、相手からの印象を左右する重要な要素になるでしょう。
名刺をもらった後の保管方法と活用方法

就活でいただいた名刺は、単なる連絡先ではなく今後の活動や社会人生活に役立つ大切な情報です。正しく整理し、必要な場面で活用すれば信頼を築けたり次の機会につなげたりできます。
ここでは、名刺をもらった後の保管と活用の方法を紹介しましょう。
- 名刺ファイルやケースで整理する
- データ化して名刺管理アプリに保存する
- 就活が終わるまで大切に保管する
- お礼メールや次回面接に活用する
- 就活後も人脈づくりに活用する
①名刺ファイルやケースで整理する
名刺はそのまま持ち歩いていると、折れたり汚れたり、最悪の場合は紛失するリスクがあります。そこで、専用の名刺ファイルやケースを使って整理することが大切です。
アルバムのように1枚ずつ収納できるファイルなら、企業ごとや日付ごとに分けて管理しやすく、後で振り返るときにも役立ちます。
また、面接や説明会が続くと名刺の枚数はどんどん増えていきます。きちんと整理しておくと、誰といつ会ったかが一目で確認でき、情報の抜け漏れを防げるでしょう。
整理整頓の習慣は、社会人としての基本姿勢を示す要素でもあります。信頼を得る第一歩として、早めに専用のケースを準備しておくと安心です。
②データ化して名刺管理アプリに保存する
名刺をスマホで撮影してデータ化すると、検索や管理が非常に効率的になります。氏名や会社名を入力すればすぐに探し出せるため、出先で急に必要になった場合でもすぐ確認できるでしょう。
さらに、クラウド上に保存できるアプリを使えば、端末が変わってもデータを失わず安心です。
紙の名刺はかさばりやすく、長期間の保管には限界がありますが、データ化しておけばスペースを取らず整理が簡単です。
共有機能を活用すれば、就活仲間やOB訪問で得た情報を効率的に活用することもできます。こうした工夫は、就活をスムーズに進める大きな助けになるでしょう。
③就活が終わるまで大切に保管する
就活中にいただいた名刺は、選考が進むにつれて思わぬ場面で役立つことがあります。
たとえば、一次面接で出会った担当者と再度やり取りするケースや、別の部署の採用担当者と接点を持つときに、以前の名刺情報が必要になることもあるでしょう。
そのため、内定が出るまでの間は、すべての名刺をまとめて大切に保管しておくことが重要です。たとえ一度きりの面談であっても、連絡先や役職は後々の参考資料になります。
短期間しか使わないと思って軽く扱ってしまうと、大事なつながりを失う原因になりかねません。社会人の意識を持って、最後まで丁寧に扱う習慣をつけておきましょう。
④お礼メールや次回面接に活用する
名刺に記載された情報は、お礼のメールを送るときや次回の面接準備に直接役立ちます。正しい氏名や役職を確認してメールに反映させれば、誤字脱字による失礼を防ぐことも可能です。
加えて、いただいた名刺を見ながら会話の内容を振り返り、具体的な話題に触れることで誠実さが伝わりやすくなるでしょう。
また、次の面接に進んだときには、担当者の情報をしっかり記憶している学生の方が印象が良くなります。
「前回は貴重なお話をいただきありがとうございました」といった言葉を添えるだけでも信頼感は高まるでしょう。名刺は単なる連絡先ではなく、次の機会へつなげるための重要な道具だと意識してください。
⑤就活後も人脈づくりに活用する
就活が終わってからも、いただいた名刺は大切な人脈の証として役立ちます。社会人になってから、OBや企業担当者と再び接点を持つことは少なくありません。
そのとき、以前の名刺をきっかけにスムーズに関係を再構築できるでしょう。
さらに、キャリアを積んで転職を考える場面や、新しい仕事に挑戦するときにも、過去の人脈が思わぬ形で助けになることがあります。
人とのつながりは長期的に価値を持つため、就活が終わっても名刺を整理し続けることが大切です。将来の可能性を広げる投資と考え、しっかり活用していきましょう。
就活で学生も名刺を用意すべき?

就活中に学生自身が名刺を持つべきかどうか悩む人は多いです。社会人と同じように名刺を準備するべきか、それとも不要なのか判断が難しいでしょう。
ここでは、学生が名刺を持つメリットとデメリット、役立つ場面や注意点について整理します。
- 学生が名刺を持つメリット
- 学生が名刺を持つデメリット
- 名刺があると役立つ場面
- 名刺を持つときに注意すべき点
- 学生名刺を持たない場合の対応
①学生が名刺を持つメリット
学生が名刺を持つことで、初対面の場面で自己紹介が格段にスムーズになります。口頭で伝えるよりも確実に名前や大学名、連絡先を残せるため、相手の記憶にも残りやすいでしょう。
特に、OB訪問やインターンの懇親会のように短い時間で多くの社会人と交流する場では、名刺があるだけで印象がぐっと強まります。
さらに、名刺があれば後日お礼の連絡をする際にも便利です。メールやSNSに比べ、名刺を介して情報を伝える行為は「社会人らしい姿勢」として評価されやすいでしょう。
小さな一歩ですが、プロ意識や準備の丁寧さを伝えられるため、信頼獲得のきっかけになります。
②学生が名刺を持つデメリット
一方で、名刺を持つことには注意点もあります。たとえば、記載内容に誤りがあると相手に誤解を与え、信頼を損なう恐れがあります。
また、電話番号や住所など不必要な情報を盛り込みすぎると、個人情報が流出するリスクにつながりかねません。
さらに、場面を選ばず名刺を配ってしまうと「形式ばかりにこだわる学生」という印象を与える可能性があります。
社会人にとって名刺は当たり前のツールですが、学生の場合はあくまで補助的な立場であることを意識することが重要です。
適切に活用すればメリットになりますが、扱いを誤ると逆効果になる点を理解しておきましょう。
③名刺があると役立つ場面
学生名刺は、特にOB・OG訪問や企業のキャリアイベントなどで力を発揮します。相手が一日に多くの学生と接する場面では、名刺があることで「誰だったか」を思い出す助けになるでしょう。
面接本番では必須ではないものの、説明会終了後や座談会などで個別に会話をする場面では非常に便利です。
また、名刺を通じて自分の存在を形として残すことで、お礼のメールを送るときもスムーズになります。
「名刺をいただいた○○大学の△△です」と伝えるだけで相手もすぐに思い出してくれるため、印象を強める効果が期待できるでしょう。
特に、人脈づくりを意識する人にとっては、有効なコミュニケーションツールとなるはずです。
④名刺を持つときに注意すべき点
学生が名刺を作成する際には、デザインや情報量に注意が必要です。記載すべき内容は、名前、大学名・学部、連絡が取れるメールアドレス程度にとどめるのが望ましいでしょう。
派手すぎる色や装飾はかえって不自然に映り、ビジネスの場にふさわしくありません。
また、名刺を持つ以上は扱い方も重要です。名刺入れを用意せず、カバンや財布にそのまましまうのはマナー違反と見なされるため、必ず専用のケースを使ってください。
さらに、名刺を渡すときや受け取るときの所作も丁寧に行うことで、単なる情報のやり取りではなく「礼儀をわきまえた行動」として評価されるでしょう。
⑤学生名刺を持たない場合の対応
名刺を持っていないからといって、必ずしもマイナスになるわけではありません。就活の面接や説明会では、名刺を持たない学生の方が一般的です。
その場合は、自己紹介をしっかり行い、必要に応じてメールアドレスや大学の情報を伝えれば十分に対応できます。
重要なのは、名刺の有無ではなく、誠実さや礼儀を意識した振る舞いです。たとえば「学生のため名刺は持っておりませんが、連絡先をお伝えいたします」と一言添えるだけで、真摯な姿勢は十分に伝わります。
名刺を持つかどうかはあくまで補助的な選択肢であり、自分のスタイルや状況に応じて柔軟に判断することが大切です。
就活生向け名刺の作り方

学生が名刺を準備するときは、自作するか外部サービスを利用するかで迷う人が多いです。名刺は自己紹介のツールであり、作り方によって相手に与える印象も変わります。
ここでは、就活生が利用しやすい名刺作成の方法を紹介しています。
- テンプレートを活用して時短で作成する
- 名刺作成アプリやソフトを利用する
- オンラインサービスに依頼する
- 印刷所や専門店に依頼して高品質に仕上げる
- 大学生協で作成する
①テンプレートを活用して時短で作成する
名刺を作るときに最も手軽なのが、既存のテンプレートを利用する方法です。WordやPowerPointには名刺用のフォーマットが用意されており、名前や大学名、連絡先を入力するだけで形が整います。
特別なスキルがなくても作れるため、パソコンがあれば誰でもすぐに取り組める点がメリットです。短時間で完成できるため、面接やOB訪問の予定が急に決まったときにも便利でしょう。
ただし、デザインの自由度は高くありません。同じテンプレートを利用する学生も多いため、人によっては似たような仕上がりになりがちです。
オリジナリティを強く出したい人にはやや物足りないかもしれませんが、無難さと実用性を重視する場面では十分役立つ方法だといえるでしょう。
②名刺作成アプリやソフトを利用する
スマホやPCの名刺作成アプリを使えば、直感的な操作でデザインを編集できます。フォントや文字サイズ、背景色などを自由に調整でき、自分らしい名刺を作れるのが魅力です。
テンプレートも豊富に用意されているため、デザインに自信がなくても安心して利用できるでしょう。
また、作成したデータをそのまま印刷所やネットサービスに送信できるケースも多く、効率よく仕上げられる点も強みです。
ただし、慣れるまで操作に少し時間がかかることがあり、機能を使いこなすには工夫が必要でしょう。
とはいえ、工夫次第でシンプルかつ個性を感じさせる名刺を作れるため、就活で差をつけたい学生にはおすすめの方法です。
③オンラインサービスに依頼する
オンラインの名刺作成サービスを利用すれば、注文から印刷、発送までを一括で行えます。
パソコンやスマホからデザインを選び、必要事項を入力するだけで簡単に注文できるため、デザインが苦手な人でも安心です。
豊富なテンプレートやカラーバリエーションから選べるので、自分の希望に合った仕上がりにしやすい点も魅力でしょう。
料金は比較的安く、数日で届くスピード感も就活生にとって大きなメリットです。ただし、サービスによっては50枚や100枚単位など、まとまった枚数での発注が必要になる場合があります。
そのため、実際の利用頻度や活動量を考え、自分に合った発注枚数を検討することが重要です。コストと利便性のバランスを取りたい人に適した方法といえるでしょう。
④印刷所や専門店に依頼して高品質に仕上げる
本格的な名刺を作りたい場合は、印刷所や専門店に依頼するのが適しています。紙質や厚み、特殊加工などを選べるため、見た目だけでなく手触りからも高品質さを伝えられます。
名刺は「小さなビジネスツール」でもあるため、質感にこだわることで強い印象を残せるのは大きな利点でしょう。
特に、合同説明会やインターンで多くの人と会う場面では、少しの差が記憶に残るきっかけになります。ただし、他の方法に比べてコストや納期がかかりやすく、急ぎの場合には不向きです。
利用するときは「どんな場面で渡すのか」「どれだけの枚数が必要か」を考えたうえで選ぶと効果的でしょう。特別な機会に備えて用意しておくと安心できます。
⑤大学生協で作成する
大学生協は、学生向けにリーズナブルかつ簡単に名刺を作れるサービスを提供しています。必要事項を記入して申し込むだけで、数日以内に完成することが多く、初めてでも安心して利用できるでしょう。
価格も他の方法に比べて安く抑えられるため、コスト面を重視する学生にとっては大きな魅力です。また、デザインはシンプルで無難なものが多いため、どの場面でも安心して使える実用性があります。
奇抜さはないものの、就活においては「失礼にならない名刺」であることが最も重要です。身近な場所で簡単に依頼できる点も便利で、急ぎの場合にも対応しやすいでしょう。
信頼性と手軽さを両立した方法として、多くの学生に適しています。
名刺に載せる基本項目

学生が名刺を作るときは、必要な情報をシンプルにまとめることが大切です。情報が多すぎると見づらくなり、逆に少なすぎると実用性が下がったりします。
ここでは、最低限入れておきたい基本項目を紹介しましょう。
- 大学名や学部・学科
- 氏名と読み仮名
- 電話番号
- メールアドレス
①大学名や学部・学科
大学名や学部・学科を記載することで、相手に自分の所属を正確に伝えられます。企業の担当者は、就活の時期に数多くの学生と出会うため、どの大学の誰だったかを思い出す際に大きな助けになるでしょう。
特に、合同説明会やインターンの交流会などでは、複数の学生の中から印象を整理する必要があるため、大学名の情報は必須です。
また、略称や省略表記を使うと相手が誤解する可能性があるため、必ず正式名称で載せてください。
たとえば「東大」や「慶大」と書くよりも、「東京大学」「慶應義塾大学」と記載するほうが丁寧で信頼感を持たれやすいです。
さらに、同じ大学出身の担当者であれば、自然と会話が盛り上がり、共通点をきっかけに関係性を深めやすくなるでしょう。
②氏名と読み仮名
名刺において、最も重要なのが氏名です。名前は第一印象を形作る要素でもあるため、誤読されないようにする工夫が欠かせません。
日本語の名前には珍しい読み方や複数の読み方がある場合が多く、担当者が迷わないように読み仮名を添えておきましょう。
読み仮名を記載することで、相手に正しく呼んでもらえるだけでなく、会話がスムーズになり親近感も生まれやすくなります。
また、文字の大きさは少し大きめに設定すると目に留まりやすく、覚えてもらいやすくなるでしょう。フォントは、奇抜なものよりも読みやすさを優先してください。
見やすく整理された氏名は、相手に誠実で丁寧な印象を残す効果があります。
③電話番号
電話番号は必須項目ではありませんが、掲載しておくと便利です。特に、インターンや説明会の場面で、当日の急な連絡や確認が必要になったときに役立ちます。
担当者が直接連絡を取りたい場合にスムーズに対応できるため、安心感を与えられるでしょう。ただし、電話番号は個人情報でもあるため、慎重に扱う必要があります。
不安であれば、携帯番号ではなく大学の代表番号や、ゼミの研究室番号を記載しましょう。相手に確実に連絡手段を提示しつつ、自分のプライバシーを守ることが大切です。
就活でどのような場面に利用するかを想定し、記載するかどうかを判断してください。
④メールアドレス
メールアドレスは、名刺に必ず載せるべき項目です。就活におけるやり取りの多くはメールで行われるため、連絡手段として欠かせません。
大学で発行されるメールアドレスを使っても問題ありませんが、卒業後も利用できるGmailやYahoo!メールなどのフリーメールを記載しておくと長期的に安心です。
また、メールアドレスはできるだけシンプルでわかりやすいものを選びましょう。長すぎるアドレスや特殊な記号を多用すると誤入力の原因になりやすく、担当者に不便をかけてしまいます。
名前やイニシャルを組み合わせた、誰にでも覚えやすい形式がおすすめです。きちんと整理されたメールアドレスは、ビジネスにふさわしい信頼感を相手に与えることができます。
名刺交換の基本マナー

名刺交換は、第一印象を左右する重要な場面です。就活生にとっては慣れない行為かもしれませんが、基本を理解しておけば安心できるでしょう。
ここでは、就活生が押さえておくべき名刺交換のマナーを紹介します。
- 目下である学生側が先に名刺を出す
- 複数人と交換した場合は席順に並べて置く
- 交換後はすぐにしまわず会話中は手元に置いておく
- 名刺交換後のお礼や挨拶を伝える
①目下である学生側が先に名刺を出す
名刺交換では、立場が下の人から先に差し出すのが一般的なルールです。就活生の場合は、必ず自分から名刺を渡すようにしましょう。
両手で名刺を持ち、胸の高さよりも少し低い位置で相手に向けて差し出すと、丁寧で礼儀正しい印象を与えられます。もし、複数人が同席している場合は、役職が高い人から順番に渡すのが望ましいです。
先に差し出す姿勢は、相手を敬う気持ちを行動で示すことにつながります。渡す際には「よろしくお願いいたします」と一言添えるとさらに印象が良くなるでしょう。
形式的に見えても、この基本を守るかどうかで第一印象が大きく変わるため注意が必要です。
②複数人と交換した場合は席順に並べて置く
合同説明会や座談会などでは、複数の担当者と名刺交換を行う場面が多くあります。そのとき、いただいた名刺を机の上に順序よく並べることが重要です。
相手の座っている位置に合わせて名刺を置くことで、誰がどの役職なのかを一目で確認でき、会話もスムーズになります。
名刺を重ねて置いてしまうと失礼に見えるうえ、後で誰のものか混乱しやすいので避けてください。席順に沿って並べる配慮を示すことで、相手に対する敬意や細やかな気配りを伝えられます。
こうした小さな工夫が、落ち着いた学生だという印象につながるのです。
③交換後はすぐにしまわず会話中は手元に置いておく
名刺を受け取った直後に名刺入れにしまうのは、相手を軽視しているように見えてしまいます。
会話中は机の左側や名刺入れの上に置き、視線を落としながら相手の名前や役職を確認できるようにしてください。名刺を見ながら話を進めれば、自然と敬意が伝わり、会話も円滑になります。
また、相手の名前を会話の中で繰り返し呼ぶことで、親しみやすさや信頼感も高まります。話が一段落してから改めて丁寧に名刺入れへしまうのが正しい流れです。
名刺を扱う姿勢ひとつで社会人としてのマナーが伝わるため、注意深く行動しましょう。
④名刺交換後のお礼や挨拶を伝える
名刺交換が済んだら、そのまま会話に入るのではなく、必ず一言お礼を伝えることが大切です。
「本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます」「どうぞよろしくお願いいたします」といった短い言葉で十分ですが、こうした挨拶を添えるだけで相手に好印象を与えられます。
名刺交換は単なる形式ではなく、信頼関係を築く入り口です。感謝の気持ちを込めて挨拶することで、その後の会話がスムーズに運びやすくなります。
逆に、無言で終えてしまうと印象が悪くなるため、言葉を添える習慣を身につけておきましょう。名刺交換後の一言が、就活生としての礼儀や人柄をしっかりと示す機会になるのです。
就活生におすすめの名刺入れの選び方

名刺入れは、就活で欠かせないアイテムです。名刺交換の場面で相手の目に入るため、選ぶものによって印象が大きく変わります。ここでは、就活生に適した名刺入れの選び方を紹介しましょう。
- 落ち着いた色合いの名刺入れを選ぶ
- シンプルで清潔感のあるデザインを選ぶ
- 革製や金属製など素材で選ぶ
- 安すぎず高すぎない価格帯を選ぶ
- 収納力やポケット数を確認して選ぶ
- 就活後も長く使える耐久性を重視して選ぶ
①落ち着いた色合いの名刺入れを選ぶ
名刺入れの色は、学生が思う以上に第一印象に直結します。赤や黄色、明るいグリーンといった派手な色合いは、元気さを伝える一方で軽く見えてしまうおそれがあります。
そのため、黒や紺、茶、ダークグレーといった落ち着いた色を選ぶのが無難です。これらの色は誠実さや落ち着きを感じさせ、信頼感を与えることができます。
特に、就活の場ではシンプルさと安心感が重視されるため、派手さよりも控えめな色を選ぶのが基本です。男女を問わず好印象を得られるため、迷ったら黒か紺を選ぶと安心でしょう。
②シンプルで清潔感のあるデザインを選ぶ
名刺入れのデザインは、就活において重要な評価ポイントです。ラインストーンや派手なロゴ、柄物など装飾が多いデザインは、学生らしさを欠き、ビジネスの場には不向きです。
シンプルで清潔感のあるものを選ぶことで、相手に落ち着いた印象を与えられます。また、装飾が少ない名刺入れは長く使える点でも優れています。
シンプルさは流行に左右されず、社会人になってからも違和感なく使い続けられるでしょう。余計な飾りを排除し、清潔感を重視したデザインを選ぶことが大切です。
③革製や金属製など素材で選ぶ
素材によって、名刺入れが持つ印象は大きく変わります。革製は柔らかい雰囲気を持ち、上品で落ち着いた印象を与えるでしょう。
使い込むほど手になじみ、風合いが増していくため、長く使うほど魅力が出る素材です。
一方で、金属製は耐久性が高く、シャープでスタイリッシュな印象を持たせられます。ビジネスの場で、スマートに見せたい学生にはおすすめです。
どちらを選ぶかは、自分の性格や就活後の利用シーンを考えて決めるとよいでしょう。
たとえば、金融業界や堅実さを求められる場では、革製が安心感を与えますし、IT業界やデザイン業界では、金属製のスタイリッシュさがマッチする場合もあります。
④安すぎず高すぎない価格帯を選ぶ
名刺入れは、価格帯によって品質が大きく変わります。あまりに安いものは素材が薄く、すぐに劣化してしまうことがあるでしょう。
その一方で、高級すぎるものは学生らしさを欠き、かえって背伸びしている印象を与えかねません。就活生には、3,000〜10,000円程度の価格帯がバランスの良い目安です。
この範囲であれば、素材やデザインも一定の品質があり、相手にも好印象を与えやすいでしょう。安さや高級感にとらわれすぎず、見た目と実用性の両方を兼ね備えたものを選ぶことが大切です。
⑤収納力やポケット数を確認して選ぶ
就活では、説明会や面接などで複数の担当者と名刺交換をすることがよくあります。そのため、ある程度の収納力を持った名刺入れが必要です。目安としては、20〜30枚程度入るものを選ぶと安心でしょう。
また、ポケットが複数あるタイプを選べば、自分の名刺と相手の名刺を分けて整理でき、場面ごとの対応がスムーズになります。
名刺を探して慌てるようなことがなくなり、落ち着いた対応につながるため、ポケット数も忘れず確認しておくとよいでしょう。
⑥就活後も長く使える耐久性を重視して選ぶ
名刺入れは就活期間だけでなく、社会人になってからも継続して必要になるアイテムです。すぐに壊れてしまうようなものではなく、長く使える耐久性を重視して選ぶことが重要。
縫製や金具の強度、素材の厚みなどをチェックして、信頼できる作りのものを選びましょう。
少し価格が高くても耐久性のある名刺入れを選べば、社会人になってからも使い続けられるため、長期的に見てコストパフォーマンスが良くなります。
就活という短期的な視点だけでなく、将来を見据えて選ぶ姿勢が大切です。
就活の名刺に関するよくある質問

名刺交換は社会人にとって当たり前ですが、就活生にとっては慣れない場面も多く、不安を感じる人も少なくありません。ここでは、名刺に関する疑問に答え、安心して行動できるように整理します。
- 学生が名刺を持っていなくても失礼にならない?
- 名刺にSNSやポートフォリオURLを載せても大丈夫?
- 名刺交換のタイミングを逃した場合はどうすればいい?
- 名刺をもらった後にお礼メールを送るべき?
①学生が名刺を持っていなくても失礼にならない?
学生が名刺を持っていなくても、失礼にはあたりません。採用担当者も「学生は名刺を持っていないことが多い」と理解しているため、名刺を提示できなくてもマナー違反にはならないのです。
とはいえ、名刺を準備しておくと初対面での自己紹介がスムーズになり、名前や連絡先を正確に伝えられるという利点があります。
特に、OB・OG訪問やインターンの場面では、名刺を持参しているだけで積極性や準備の丁寧さを示せるため、プラスの評価につながりやすいでしょう。
必須ではありませんが、「あると便利で印象も良くなるツール」として考えておくのがおすすめです。
②名刺にSNSやポートフォリオURLを載せても大丈夫?
デザイン系やIT系など、自分のスキルや成果物を見てもらいたい業界では、名刺にSNSやポートフォリオURLを載せることは効果的です。
実際の作品や活動実績を確認してもらえるため、短時間で自分を印象づけられます。ただし、プライベートなアカウントをそのまま記載するのは避けるべきです。
採用担当者が安心して閲覧できるように、就活専用に整えたSNSやポートフォリオを用意し、内容も整理してから記載してください。
URLを記載する場合は、短縮URLではなく公式のドメインを使い、信頼性を高めることも大切です。
③名刺交換のタイミングを逃した場合はどうすればいい?
名刺交換のタイミングを逃してしまっても、心配する必要はありません。
会話の流れが落ち着いたときや、退席する前に「先ほど交換の機会を逃してしまいましたが、もし可能であればいただけますか」と丁寧に申し出れば問題ありません。
むしろ、焦らず落ち着いて対応する姿勢が評価されることもあります。大事なのは、タイミングを誤ったことを引きずらず、自然にリカバリーすることです。
また、自分の名刺を持っている場合は、同じタイミングで差し出すとよりスマートに見えるでしょう。
④名刺をもらった後にお礼メールを送るべき?
名刺をいただいた後に、お礼メールを送るのは非常に有効です。特に、面接や説明会で丁寧に対応してもらった場合、翌日までに感謝を伝えることで誠実さを示せます。
内容は長文である必要はなく、「本日は貴重なお時間をいただきありがとうございました」といった一文と、当日の会話に触れる短いコメントを加える程度で十分です。
名刺に記載された氏名や役職を正しく用いることで、相手に対する敬意も伝わります。こうした行動は、社会人としてのマナーを理解している証拠となり、今後の選考や関係構築にも良い影響を与えるでしょう。
就活における名刺対応の結論

就活で名刺をもらったら、正しい受け取り方とマナーを守ることが第一です。企業が名刺を渡すのは安心感や信頼を伝えるためであり、学生側の姿勢も見られています。
そのため、受け取る際は丁寧さを意識し、名刺入れを使って大切に保管することが欠かせません。さらに、お礼メールで感謝を伝えることで良い印象を残せます。
自分用の学生名刺を持つかどうかは自由ですが、準備しておくと自己紹介や人脈づくりに役立つでしょう。
名刺交換や管理は面倒に感じるかもしれませんが、将来の社会人生活に直結する練習の場でもあります。就活の中で積極的に実践することが、確かな成長につながるはずです。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













