【航空業界研究】JALとANAの比較|強み・年収・求める人物像を解説
「JALとANAって結局どう違うの?」
航空業界を志望する就活生の多くが、一度は抱く疑問ではないでしょうか。どちらも日本を代表する航空会社ですが、路線展開・経営戦略・社風・求める人物像には明確な違いがあります。
これらを理解しておくことは、志望動機を練る上でも、面接での回答を具体化する上でも非常に重要です。
そこで本記事では、「JALとANAの比較」を強み・年収・社風・採用ポイントといった観点から徹底解説します。航空業界研究や企業選びの参考に、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
ANAとJALを比較して違いを知ろう

航空業界を目指す就活生にとって、ANAとJALの違いを理解することは企業研究の出発点になります。
ANAはLCC事業や国際線拡大に積極的で、新しい挑戦を重視する傾向が強いでしょう。一方でJALは安定した国内線網と品質を強みとし、信頼性を大切にした経営姿勢が際立っています。
両社の売上や規模は拮抗していますが、ANAは成長性、JALは安定性で評価されやすいといえるのです。また、社風や働き方にも違いがあります。
ANAは若手の意見を取り入れる柔軟な風土があり、挑戦心を持つ人を求めているでしょう。それに対してJALはチームワークを重視し、規律を守りながら堅実に働く文化が浸透しています。
そのため、自分から新しいことに挑みたい人にはANAが、協調性を発揮しながら組織で成長したい人にはJALが向いているかもしれません。ANAとJALは同じ航空会社でも異なる魅力を持っています。
どちらが優れているかではなく、自分の価値観や将来の方向性に照らし合わせて考えることが、企業選びを成功させる一歩になるでしょう。
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
航空業界の現状

航空業界はコロナ禍による大幅な需要減から少しずつ回復を見せています。しかしその裏には、燃料費高騰や人手不足など解決すべき課題もあります。
就活生にとって業界の現状を正しく把握することは、志望理由を説得力あるものにするために欠かせません。ここでは国内需要や国際線の利用状況、LCCの影響、採用の現実などを多角的に解説します。
- 国内航空需要の回復状況
- 国際線の運航本数と利用者数の現状
- LCC(格安航空会社)の市場シェアと影響
- 航空業界における人手不足と採用の現状
- 燃料費高騰や環境対応が与える影響
- 新型コロナからの業績回復の進捗
①国内航空需要の回復状況
国内の航空需要はコロナ禍で大きく落ち込みましたが、観光需要の回復や出張の復活で徐々に改善しています。
結論として、JALとANAは国内線を軸に業績を支えており、この回復が採用活動の再開にもつながっているのです。特に観光需要の増加は地方空港の便数回復に直結し、学生が働くチャンスを広げています。
ただし、出張需要はオンライン会議の普及により完全には戻っていません。つまり航空会社は観光需要への依存度を高め、柔軟なサービス展開が必要になっているのです。
就活生は「回復=安定」と短絡的に考えるのではなく、需要の質が変化している点に注目し、志望理由を組み立てることが重要でしょう。
②国際線の運航本数と利用者数の現状
国際線は回復しつつありますが、地域ごとに差が大きいのが実情です。欧米路線は需要が戻りやすいのに対し、アジア方面は渡航制限や経済動向の影響を受けやすく、各社は慎重に便数を調整しています。
ANAは国際線の強みを活かし、新路線展開を模索しているでしょう。JALは効率的な運航計画でリスクを抑えている点が特徴。
学生にとって大切なのは、国際線の華やかさだけに目を向けるのではなく、収益バランスやリスク管理も理解することです。
結果として、グローバル志向を持つ人はANA、安定性を重視する人はJALに適性があると考えると比較がしやすくなるでしょう。
③LCC(格安航空会社)の市場シェアと影響
LCCは国内外で存在感を増し、大手航空会社に影響を与えています。安価な運賃で学生や観光客の利用を集め、市場の競争構造を変えているのが実情です。
そのため、JALやANAも座席の快適性やマイレージプログラムの充実など、サービスで差別化を図っています。LCCの拡大は脅威であると同時に、利用者層を広げる役割も担っているのです。
その結果、大手はブランド価値や付加価値を高める必要に迫られています。就活生が見落としがちなのは、この変化が面接での業界理解の深さを示す格好の題材になる点です。
LCCの存在が「価格」ではなく「価値」を重視する流れを生み出していることを理解してください。
④航空業界における人手不足と採用の現状
航空業界は人手不足が深刻化し、採用活動を強化しています。コロナ禍で縮小した雇用を再び拡大させる必要があり、パイロットや客室乗務員だけでなく、地上職でも人材需要が高まっているのです。
その背景には需要回復があり、特にサービス品質を保つための人材育成が急務。学生にとっては新卒採用の増加がチャンスとなりますが、競争が緩いわけではありません。
求められる人物像は「柔軟性」「ホスピタリティ」「語学力」と具体的であり、背景を理解せず応募するとミスマッチを招きやすいです。
採用の現状を踏まえて、自分の強みと結びつけて志望動機を準備してください。
⑤燃料費高騰や環境対応が与える影響
燃料費の高騰と環境規制の強化は業界に大きな影響を与えています。コスト増は業績の圧迫要因ですが、持続可能な経営への転換を促すきっかけでもあるのです。
ANAやJALは燃費効率の高い機材やSAF(持続可能な航空燃料)の導入を進めており、これは単なるコスト削減ではなくブランド強化にもつながります。
学生が注目すべきは、環境対応が採用基準にも影響を与えている点です。環境課題に関心を持ち、社会に貢献できる人材は今後さらに評価されるでしょう。
この視点を持つことで、長期的に活躍できる人材と見なされやすくなります。
⑥新型コロナからの業績回復の進捗
新型コロナの影響で航空業界は大きな打撃を受けましたが、現在は回復基調にあります。ANAもJALも赤字から脱却し、需要回復に伴って売上を伸ばしてきました。
観光需要の増加や国際線の復活が大きな理由です。業績の改善は採用再開にもつながっていますが、感染症リスクや世界情勢の変化によって再び影響を受ける可能性も否定できません。
就活生が学ぶべきは、両社が危機をどう乗り越えたかという姿勢です。JALは効率性を重視し、ANAは積極的に投資を進めました。この違いを理解して伝えると、企業比較の深さをアピールできるでしょう。
航空業界の動向

航空業界はコロナ禍を経て大きな変化を迎えています。訪日外国人の回復や国際線需要の増加、環境問題への対応など、各社が戦略を問われる状況です。
ここでは就活生が理解しておきたい最新の動きを整理し、企業研究や比較の参考にしてください。
- 訪日外国人需要の拡大予測
- 長距離国際線ネットワークの拡充計画
- LCCとフルサービスキャリアの今後の競争構図
- 航空業界におけるデジタル化・自動化の進展
- 持続可能な航空燃料(SAF)導入の加速
①訪日外国人需要の拡大予測
訪日外国人の増加は、航空業界の成長を大きく左右します。観光庁の発表でも、アジアや欧米からの訪日客は今後も増加が見込まれているのです。
特に2025年の大阪・関西万博や国際イベントは需要を押し上げるきっかけになるでしょう。需要の拡大は収益基盤の強化につながりますが、受け入れ体制や競争の激化といった課題もあります。
ANAは羽田や成田を拠点に国際線を増やし、多様な顧客層を取り込もうとしているのです。JALは北米やハワイ路線に強みを持ち、観光需要に合わせた展開を進めています。
両社の戦略の違いを知ることで、企業が何を重視しているかが見えてくるでしょう。また訪日客の増加に伴い、機内サービスや多言語対応も求められます。
語学力や異文化理解に強みを持つ人材は高く評価される可能性があるのです。訪日需要の拡大は業界にとって大きなチャンスであり、就活生にとってもアピールポイントを考える材料になるでしょう。
②長距離国際線ネットワークの拡充計画
長距離国際線は航空会社の収益やブランド力を高める重要な分野です。北米やヨーロッパ、中東への直行便が増え、日本からの利便性が高まっています。
ANAは北米とアジアをつなぐハブ戦略を強化し、乗り継ぎ需要を取り込む方針です。JALは効率を重視し、少数精鋭で質の高いサービスを提供しています。
この違いは企業研究に欠かせない比較材料です。ANAは挑戦的で柔軟な人材を求めやすく、JALは安定性や協調性を重んじる傾向があります。
どちらに共感できるかを考えることが、企業選びを進める上で重要でしょう。ただし長距離路線は燃料費や国際情勢の影響を受けやすいリスクがあります。
そのため、変化に対応できる柔軟さも社員に求められるでしょう。結論として、長距離国際線の拡充は単なる路線拡大ではなく、企業の将来性や働き方に直結する課題だといえます。
③LCCとフルサービスキャリアの今後の競争構図
LCCの台頭は業界全体の競争構図を変えています。低価格で支持を集めるLCCと、快適さやブランド力で差別化を図るフルサービスキャリア。それぞれの戦略を理解することが就活生にとって大切です。
ANAはPeachをグループに持ち、LCC市場で積極的に事業を展開しています。JALはZIPAIRを中心にLCCを拡大しつつ、サービス品質の高さを維持する方向で進めているのです。
両社の取り組みの違いは企業文化の差を表しています。一方でLCCは収益面の課題もあり、低価格が必ずしも安定につながるわけではありません。
サービスを簡略化しながらも安全性や運航品質を確保できるかが焦点です。結論として、LCCとフルサービスの競争は単なる価格差ではなく、企業の方向性を理解する上で重要な要素になるでしょう。
④航空業界におけるデジタル化・自動化の進展
デジタル化や自動化は急速に進んでいます。予約システムの高度化やAIによる需要予測、空港での自動チェックインなどが広がってきました。
業務効率は上がりますが、従来の仕事の一部が機械に置き換わる可能性もあります。就活生は自分がデジタルをどう活用できるかを意識することが必要でしょう。
ANAはデジタル人材を積極的に採用し、AIやデータ解析で運航最適化を進めています。JALも自動化を推進しつつ、安全性や顧客体験を重視し、人とデジタルを組み合わせる方向を目指しているのです。
似ているようで微妙に異なる方針が社風の差につながっています。さらに、自動化の進展は新しい職種を生み出しています。データサイエンスやシステム開発の知識を持つ人材は今後さらに求められるでしょう。
結論として、デジタル化は効率化にとどまらず、働き方そのものを変える要因であり、理解して備えることがキャリア形成に直結するはずです。
⑤持続可能な航空燃料(SAF)導入の加速
環境問題は業界全体の課題です。二酸化炭素削減のための持続可能な航空燃料(SAF)の導入は今後の競争力を大きく左右します。国際的な規制も強まっており、各社は導入を加速。
ANAは国内外の企業と連携し、SAFの安定供給網を整えようとしています。JALも調達ルートの確保や実証実験を進め、将来に備えているのです。
こうした取り組みは環境意識の高い利用者からの信頼向上にもつながるでしょう。ただし、SAFは価格が高く供給量も限られているのが現実です。経済性と環境対応をどう両立させるかが課題。
就活生にとっては、環境意識や持続可能性をどう考えるかが、企業選びや自己PRに役立つかもしれません。SAFの導入は単なる環境対策にとどまらず、航空会社の未来を映す大きなテーマといえるでしょう。
航空業界の主な職種

航空業界には多様な職種があり、それぞれの役割が連携することで安全で快適な空の旅が実現します。就活生にとって仕事内容を理解することは、将来のキャリア選択や自己PRに直結するでしょう。
ここでは代表的な5つの職種を紹介し、特徴や求められる資質を解説します。
- パイロット
- 客室乗務員(CA)
- グランドスタッフ
- 航空整備士
- ディスパッチャー
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①パイロット
パイロットは航空会社の顔であり、安全運航の最前線を担います。結論として、操縦技術だけでなく冷静な判断力や強い責任感が必須です。
飛行中に予想外の事態が発生しても、乗客と乗員の安全を守るために決断しなければなりません。さらに最新の航空機は高度にシステム化されているため、機材知識や国際規制の理解も重要です。
学生が知っておくべきなのは、パイロットが単なる操縦者ではなく「安全を統括するリーダー」であるという点。採用試験は難関ですが、体力や語学力、協調性が重視されます。
日々の学習や自己管理が成果に直結するでしょう。志望理由を語る際は「高度な専門職」というより「チームの中心で安全を守る役割」という視点を意識してください。
②客室乗務員(CA)
客室乗務員はサービス提供だけでなく、安全確保の責任を持つ職種です。結論として、CAは「接客業」であると同時に「保安要員」であることを理解すべきでしょう。
乗客が快適に過ごせるように対応する一方、緊急時には冷静に避難誘導を行う必要があります。求められる力はホスピタリティに加えて柔軟な対応力や語学力です。
さらに長時間勤務や時差に対応する体力も欠かせません。就活生が注意すべきは「華やかな接客業」というイメージに偏りすぎることです。
実際には安全を守るプロとしての冷静さや協調性が評価されます。こうした点を理解して自己PRに取り入れると、説得力のある志望動機につながるでしょう。
③グランドスタッフ
グランドスタッフは空港で乗客をサポートし、航空会社の第一印象を決める存在です。結論として、正確さとスピードの両立が求められます。
搭乗手続きや手荷物対応は限られた時間で多数の乗客をさばかなければならず、少しの遅れが運航全体に影響。また外国人客の対応も多く、語学力や異文化理解も欠かせません。
就活生が意識すべきは「接客スキルだけでは足りない」という点です。グランドスタッフは運航を支える裏方であり、判断力や調整力が必要。さらに不測の事態に直面しても冷静に動ける力が求められます。
表に見える華やかさではなく、縁の下の力持ちとして空の安全を支える意識を持つことが自己アピールにつながるでしょう。
④航空整備士
航空整備士は航空機の安全性を技術面から守る職種であり、高い専門性が求められます。結論として、整備士は「陰の主役」として乗客の安心を支える存在です。
もし整備が不十分であれば安全運航は成り立ちません。必要なスキルは機械や電気に関する知識とチームでの連携力です。また国家資格が必要で、入社後も学び続ける姿勢が欠かせません。
学生が見落としがちなのは、整備士が「現場作業者」ではなく「判断を担う専門職」である点です。実際にはわずかな不具合を見抜く観察力や強い責任感が問われます。
技術力だけでなく人命を守る使命感を持つことで、選考での差別化につながるでしょう。
⑤ディスパッチャー
ディスパッチャーは「運航管理者」とも呼ばれ、フライトの安全を地上から支える職種です。結論として、パイロットと同じくらい重い責任を負います。
気象情報や航空路の状況をもとに飛行計画を作成し、最終的に機長へ運航の可否を伝える立場にあるため、判断を誤れば大きなリスクにつながるのです。
必要な力は分析力と冷静な意思決定能力で、緊急時には迅速に最適な指示を出さなければなりません。就活生にはあまり知られていない職種ですが、航空会社の安全運航を裏側から支える重要な存在です。
ここに関心を持ち志望理由に取り入れることで、他の候補者との差別化が可能になるでしょう。空を飛ぶだけでなく地上からも安全を守る役割があることを理解してください。
航空業界で働く魅力

航空業界は日常を超えた舞台で活躍できることが大きな特徴です。就活生にとって働く魅力を理解することは、企業選びや自己PRに役立ちます。
ここでは具体的なメリットを整理し、将来像を描く参考にしてください。
- 国内外の多様な人々と出会える
- 国際的な舞台で働ける
- 人々の生活を支える重要な役割を実感できる
- 社員割引や社内制度で旅行を楽しめる
- 専門的なスキルや知識を日々の業務で磨ける
①国内外の多様な人々と出会える
航空業界の魅力のひとつは、国内外の幅広い人々と関わる機会があることです。空港や機内では文化や背景の異なるお客さまや仲間と接するため、常に新しい刺激を受けられます。
こうした環境で柔軟な対応力やコミュニケーション力が自然と育まれるでしょう。ANAは羽田や成田を中心に世界各地へ路線を展開し、多国籍の乗客と接する場面が豊富です。
JALは北米やハワイをはじめ観光路線に強く、外国人観光客との接点が多くあります。両社とも国際色豊かですが、路線網や客層に違いがあるため、得られる経験も異なるでしょう。
また、多様な人々と接する中では文化を尊重する姿勢や臨機応変な行動が不可欠。これは将来どんな業界でも役立つ力になるはずです。
結論として、航空業界での出会いは成長のきっかけとなり、大きな魅力といえるでしょう。
②国際的な舞台で働ける
航空業界は世界と日本を結ぶ役割を担っており、国際的な舞台で働ける点が大きな特徴です。国際線業務や海外拠点を通じて語学力や異文化理解を活かせる場が広がります。
自分の力を世界でどう生かすかを考えるきっかけになるでしょう。ANAは国際線拡大に積極的で、海外勤務や出張の機会が豊富です。
JALも国際線に強みがあり、北米や欧州路線でグローバルなキャリアを積むことが可能。両社の違いを知ることで、自分に合う舞台を見極めやすくなります。
ただし国際環境では語学力や文化の違いへの柔軟な対応が欠かせません。厳しい場面に直面することもありますが、乗り越えたときの成長は大きいです。
結論として、国際的な舞台で働けることは航空業界ならではの魅力であり、挑戦の価値があるでしょう。
③人々の生活を支える重要な役割を実感できる
航空業界で働く魅力のひとつは、人々の生活を支えていると日々実感できる点です。ビジネス、観光、留学や家族の再会など、飛行機は多くの人生に欠かせない存在です。
その運航を支える立場には社会的な意義があります。ANAは国内外を幅広く結び、多様な移動を支えているのです。JALは地方路線を重視し、地域社会や暮らしに寄り添った運航を続けてきました。
路線網の違いはありますが、共通して「人の暮らしを支える」という使命を担っています。また、お客さまから感謝の言葉をいただける瞬間は大きなやりがいになります。
社会に必要とされる実感が日々の原動力となるでしょう。結論として、人々の生活に直結する役割を果たせることは航空業界で働く大きな魅力です。
④社員割引や社内制度で旅行を楽しめる
航空業界で働く魅力のひとつに、社員割引や社内制度を活用して旅行を楽しめる点があります。
社員向けの航空券制度を使えば、普段よりも手軽に国内外へ出かけられ、旅行好きな人にとって大きな利点でしょう。
ANAもJALも社員向けの航空券制度を整えており、休日を利用して気軽に旅を満喫できます。さらに福利厚生としてホテルや観光施設と提携していることも多く、リフレッシュしやすい環境が整っているのです。
勤務は不規則なこともあり、計画的に休暇を取る工夫が必要。しかしその点をうまく調整できれば、仕事と趣味を両立する豊かな生活が可能です。
結論として、社員割引や社内制度を活用できることは、航空業界ならではの楽しみといえるでしょう。
⑤専門的なスキルや知識を日々の業務で磨ける
航空業界で働くことは、専門的なスキルや知識を日々磨ける機会につながります。安全運航に関わる技術、接客スキル、語学力や異文化対応力など、多様な力が自然と身につくでしょう。
ANAはデジタル化やAI活用を進め、データ解析やシステム分野の人材育成に注力しています。JALは安全や品質を重視し、チームワークを基盤とした教育体制を整えているのです。
両社の取り組みは異なりますが、専門性を高められる環境が共通してあります。こうしたスキルは業界内にとどまらず、将来のキャリアにも活用できます。異業種への転職時にも強みとなるでしょう。
結論として、専門性を高めながら働けることは航空業界ならではの大きな魅力です。
ANA(全日本空輸)の特徴

ANAは日本を代表する航空会社の1つであり、国際線と国内線の両方で強い存在感を発揮しています。世界的なネットワークやサービスの質、安定した経営など多角的な強みがあることが特徴です。
ここではANAの主な5つのポイントを整理し、就活生が理解を深められるように解説します。
- 国際線路線を幅広く展開している
- スターアライアンス加盟で世界各国と連携できる
- 接客やサービス品質が世界的に高く評価されている
- LCCを含む複数ブランドを運営している
- 安定した経営基盤で将来性も期待できる
①国際線路線を幅広く展開している
ANAはアジアや欧米を中心に国際線ネットワークを拡大しています。結論として、グローバルに働きたい学生にとって大きなチャンスとなるでしょう。
理由は、国際線の拡充が海外勤務や国際業務の経験につながるからです。ニューヨークやロンドン、シンガポールなどの主要都市に直行便を運航しており、文化や価値観の違いに触れながら働けます。
さらに国際線は観光需要だけでなくビジネス需要とも結びついており、今後も安定した成長が見込めるでしょう。就活生が意識すべきは、国際線で働くには語学力や異文化理解が強く求められるという点。
華やかさの裏には適応力や判断力が不可欠であり、そこに自分の強みをどう活かせるかを考えることが大切です。
②スターアライアンス加盟で世界各国と連携できる
ANAは世界最大規模の航空連合「スターアライアンス」に加盟しています。結論として、この加盟によりANAは単独では届かない地域へもネットワークを広げられ、利用者に大きな利便性を提供。
加盟航空会社同士でコードシェアやマイレージ提携を行うため、ANAの顧客は190以上の国と地域にアクセス可能です。学生にとって重要なのは、こうした提携が社員にも成長の機会を与えている点でしょう。
海外の航空会社と協力する業務や共同プロジェクトに参加できる可能性があり、グローバルな舞台で力を試せます。
ただし提携先の状況に左右されることもあるため、柔軟に対応する力や協調性が必要となるでしょう。
③接客やサービス品質が世界的に高く評価されている
ANAは世界的に高いサービス評価を受けており、Skytrax社の格付けで5スターを継続的に獲得しています。結論からいえば、顧客対応の質や細やかな気配りが背景にあるのです。
和食の提供や清潔な機内、丁寧な接客などが国内外の利用者に支持されてきました。学生が注目すべきは、この評価を支えているのが一人ひとりの社員の努力だという点です。
マニュアルに従うだけでなく、状況に応じて柔軟に判断し行動できる力が不可欠。そのためANAが求める人物像は、ホスピタリティ精神と主体性を持つ人材といえます。
世界的評価の裏には日々の改善と挑戦があることを理解しておくと、面接で説得力ある話ができるでしょう。
④LCCを含む複数ブランドを運営している
ANAはフルサービスキャリア(FSC)だけでなく、LCCのPeach Aviationなど複数ブランドを展開しています。結論として、幅広い顧客層に対応し、市場変化に柔軟に適応できる体制を築いているのです。
LCCでは安価な運賃で若年層や観光客を取り込み、FSCではビジネス層や国際線利用者に質の高いサービスを提供しています。
就活生が見落としやすいのは、この2つのブランド運営が社員のキャリアに多様な選択肢を与えている点でしょう。コスト意識を学べる場から、付加価値を追求するサービスの現場まで幅広い経験が可能です。
ブランドごとの役割を理解することで、具体的かつ現実的な志望動機を組み立てられるでしょう。
⑤安定した経営基盤で将来性も期待できる
ANAは国内航空業界でトップクラスの売上を誇り、安定した経営基盤を築いています。結論として、この安定性は就職先を選ぶ学生に安心感を与えるでしょう。
新型コロナ後は需要の回復も進み、収益力が改善しています。その背景には国際線と国内線のバランスが取れており、リスクを分散できる点があるのです。
さらに燃費効率の高い機材や持続可能な航空燃料の導入など、環境対応に力を入れることで長期的な競争力も高めています。就活生にとっては「安定しているからこそ挑戦できる」という視点が重要です。
基盤の安定に甘んじるのではなく、新しい事業展開や成長機会を積極的に活かせる環境が整っていると考えてください。
JAL(日本航空)の特徴

JALは日本を代表する航空会社として、伝統と信頼を守りながら進化を続けています。就活生にとっては、サービスの質や国際展開、経営戦略を理解することが企業研究の参考になるでしょう。
ここではJALの特徴を整理し、自分の適性や志望動機を考える手がかりにしてください。
- 丁寧なおもてなしを重視した接客サービスである
- ワンワールドアライアンス加盟で海外路線に強い
- 地方空港への路線網が充実している
- 経営再建を経て効率的な運営体制を確立している
- 海外路線や新規事業の拡大に積極的である
①丁寧なおもてなしを重視した接客サービスである
JALの大きな特徴は「丁寧なおもてなし」を重視した接客です。客室乗務員や地上スタッフは細やかな心配りを徹底し、安心感を与えることを第一にしています。
その結果、利用者からの信頼が厚く、リピーターも多くなってきました。例えば、言葉の使い方や表情にまで気を配り、快適な空間を作り出しています。
これは単なる接客ではなく、日本の「おもてなし文化」を企業理念に反映させたものといえるでしょう。一方で、丁寧な対応には時間や人員が必要で、効率性との両立が課題になります。
そのためJALはマニュアル化やデジタル化を進めつつ、心のこもった接客を保つ工夫をしているのです。結論として、JALのサービスは質の高さで際立ち、顧客満足を支える大きな強みになっています。
②ワンワールドアライアンス加盟で海外路線に強い
JALは国際的な航空連合「ワンワールドアライアンス」に加盟し、世界に広がるネットワークを活用しています。
これにより、乗客はスムーズな乗り継ぎや共通マイレージの利用ができ、利便性が高まってきました。
アメリカン航空やブリティッシュ・エアウェイズとの提携を通じ、北米やヨーロッパへの路線を強化しています。その結果、ビジネス客から観光客まで幅広いニーズに応えられる体制が整っているのです。
ただし、アライアンスに依存しすぎると独自性が薄れる可能性もあります。そこでJALは「日本品質のサービス」を前面に打ち出し、差別化を図っているのです。
結論として、ワンワールド加盟は国際競争力を高める強みであり、海外志向を持つ就活生にとって魅力的な環境といえるでしょう。
③地方空港への路線網が充実している
JALは地方空港への路線網が充実している点も強み。地域の足として全国を結び、ビジネスや観光、暮らしを支えているのです。ANAと比べても地方路線に注力している姿勢が目立ちます。
離島や人口の少ない地域にも便を維持し、地域とのつながりを大切にしています。これにより「なくてはならない存在」として地域社会から信頼を得ているでしょう。
利益追求だけでなく、社会的使命を重視している姿勢が特徴です。ただし、地方路線は採算が厳しい場合も多く、効率化が求められます。
JALは小型機材の導入や運航スケジュールの工夫により、採算性と地域貢献の両立を目指しているのです。地方路線の充実はJALの社会的責任を象徴し、就活生が共感しやすい要素だといえるでしょう。
④経営再建を経て効率的な運営体制を確立している
JALは2010年に経営破綻を経験しましたが、その後の再建で効率的な運営体制を築きました。無駄を省き、限られた資源を有効に使う経営姿勢は、安定した業績につながっています。
再建の過程では人員削減や路線整理といった厳しい改革が行われました。その経験が「効率性を重んじる文化」として根づき、財務基盤を強化して再上場を果たしたのです。
企業にとって大きな転換点になったといえます。ただし、効率を優先しすぎると柔軟性を失う恐れがあります。そのため近年は挑戦的な事業にも力を入れ、成長と安定の両立を目指しているでしょう。
結論として、経営再建を経たJALは効率性と挑戦心を併せ持つ企業へと変化しました。
⑤海外路線や新規事業の拡大に積極的である
近年のJALは海外路線や新規事業の拡大に積極的です。北米や欧州路線だけでなく、新興国市場の開拓やLCC事業への参入も進めています。これにより新しい収益源を確保しようとしているのです。
JALグループのZIPAIRは中長距離のLCCとして注目され、若い世代や観光需要を取り込んでいるのです。また、航空以外でも旅行サービスやライフスタイル事業に取り組み、収益構造の多様化を進めています。
一方で、新規事業はリスクが大きく、必ず成功するとは限りません。そのため既存の強みを活かしながら成長を目指しています。JALは伝統を持ちながらも新しい挑戦を続ける柔軟な企業といえるでしょう。
ANA(全日本空輸)の社風

ANAは大手航空会社の中でも「挑戦」と「協調」を両立させた社風を持ち、社員一人ひとりが安心して力を発揮できる環境を整えています。
就活生にとっては、どのような文化の中で働けるのかを知ることが志望動機に直結するでしょう。ここではANAの社風を示す5つの特徴を紹介し、働く姿を具体的にイメージできるよう解説します。
- 個性を尊重し自由な発想を歓迎する文化
- 挑戦を後押しする風土
- 若手にも活躍のチャンスがある
- チームワークを大切にする社風
- 働き方の柔軟性を重視する制度
①個性を尊重し自由な発想を歓迎する文化
ANAは社員一人ひとりの個性を大切にし、自由な発想を歓迎する文化があります。結論として、この風土が新しいサービスや改善策を生み出す力となっているのです。
理由は、変化の大きい航空業界では従来のやり方にとらわれない柔軟さが求められるから。例えば、機内サービスの工夫やデジタル技術の導入など、社員の意見が実際に形になることも珍しくありません。
就活生にとって覚えておきたいのは、大企業だからといって画一的な働き方を強いられるわけではないという点です。
むしろ多様な価値観を持つ社員が集まるからこそ、新しい挑戦ができる環境になっています。自分の考えを仕事に活かしたい人には魅力的な職場といえるでしょう。
②挑戦を後押しする風土
ANAには挑戦を評価し、失敗を恐れず取り組む姿勢を支える風土があります。結論として、自ら積極的に行動する人ほど成長の機会を得やすいでしょう。
航空業界は環境変化が大きく、柔軟な発想や新しい取り組みが欠かせません。だからこそ挑戦を歓迎する文化が定着しています。
たとえば新規路線の開設やサービス改革はリスクも伴いますが、社員が主体的に動くことで成果につながった事例も。
就活生が勘違いしやすいのは「常に挑戦し続けなければならない」というプレッシャーがあるという点です。実際には挑戦する意思を尊重し、それを支える体制があることが特徴。
前向きに成長したい学生にとって、力を伸ばせる環境といえるでしょう。
③若手にも活躍のチャンスがある
ANAでは若手社員にも責任ある仕事が与えられ、早い段階から挑戦できる環境があります。結論として、自ら行動できる人には大きな成長の機会が用意されているでしょう。
理由は、国際線の展開や多様な事業領域を持つANAでは新しいプロジェクトが常に動いており、若手の力も必要とされているからです。実際に入社数年で海外勤務や新規事業に携わる社員もいます。
就活生が知っておくべきは、大手だからといって年功序列に縛られるわけではないということです。成果や意欲次第で早くからチャンスをつかめます。
もちろん責任は伴いますが、研修制度や上司の支援も整っているので安心です。自分の力を早く試したい人には向いている環境でしょう。
④チームワークを大切にする社風
ANAの社風で特に重視されるのが、チームワークです。結論として、航空業界は多職種が協力し合うことで安全とサービスが成り立ちます。
パイロット、客室乗務員、整備士、グランドスタッフなど幅広い職種が連携し、1つのフライトを支えているのです。そのためANAでは協調性や相互理解を大事にする文化が自然と根付いています。
就活生が意識すべきは、成果を出すにはチームの一員として役割を果たす姿勢が欠かせないということです。個人の能力が高くても連携が不足すれば結果は出ません。
ANAが求める人物像に「チームで成果を出す力」が含まれるのはそのためです。協力し合いながら成果を積み重ねたい人にとって、安心して働ける職場といえるでしょう。
⑤働き方の柔軟性を重視する制度
ANAは社員が安心して働き続けられるよう、柔軟な働き方を支える制度を整えています。結論として、多様なライフスタイルに合わせて仕事と生活を両立できる環境です。
航空業界は勤務が不規則になりやすいため、社員の負担を減らす仕組みが導入されています。例えば在宅勤務や育児・介護を支援する制度は男女問わず利用され、定着。
就活生が注目すべきは、こうした制度が単なる福利厚生ではなく、社員の力を最大限に引き出すための仕組みとして活用されている点です。
柔軟な働き方が可能であることは、長期的にキャリアを続ける上での安心材料となります。成長と生活を両立させたい人にとって、ANAの環境は大きな魅力になるでしょう。
JAL(日本航空)の社風
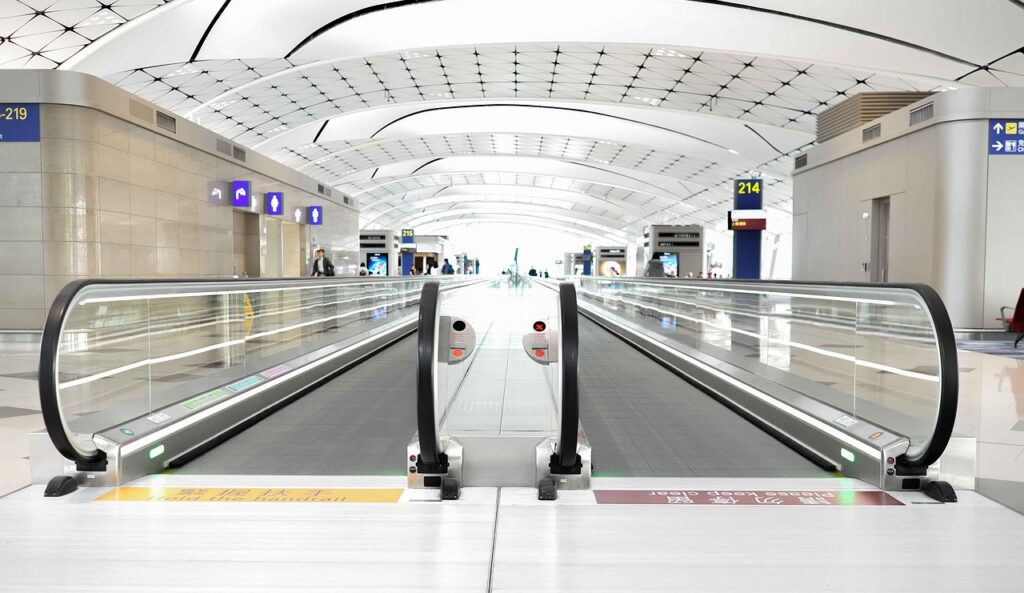
JALは日本を代表する航空会社として、伝統を守りながら現代に合わせて進化してきました。社風を理解することは、就活生にとって企業との相性を見極める重要な手がかりです。
ここではJALならではの価値観や働き方を整理し、自分に合うかどうかを考える参考にしてください。
- 協調性を重視し一体感を大切にする文化
- 伝統を重んじる安定志向の風土
- 社員教育や研修制度が充実
- リーダーシップと気配り力を重視
- 安全運航を最優先する姿勢
①協調性を重視し一体感を大切にする文化
JALの社風は協調性を重んじ、一体感を大切にしている点が特徴です。航空業界の仕事は運航や整備、接客など多くの部署が連携して初めて成り立ちます。
そのため、社員同士のチームワークが非常に重要とされているのです。実際に、日常的な声かけやサポートを欠かさず、互いに助け合う姿勢が根づいています。
困っている人を放置せず、組織全体で成果を目指す雰囲気があるでしょう。こうした協調性はお客さまへのサービスにも表れ、安心感や信頼につながっているのです。
ただし協調性が強調されすぎると、個人の意見が前に出にくい場合もあります。そのため、自分の考えを伝えるバランス感覚が必要です。
結論として、協調性を重んじる文化はJALの強みであり、チームワークを重視したい人にとって魅力的だといえるでしょう。
②伝統を重んじる安定志向の風土
JALは長い歴史の中で築いた伝統を大切にし、安定を求める風土があります。経営再建を経て慎重さが加わり、堅実な判断を行う傾向が強いです。
そのため落ち着いた雰囲気があり、安心して働ける環境が整っています。具体的には、既存のルールや仕組みを大切にし、前例を重視する文化があるのです。
大きな変化は少ないため、長期的に安定したキャリアを築きたい人に適しています。一方で、新しい挑戦を望む人には物足りなさを感じる場面もあるかもしれません。
ただし、安定志向の背景には「安全第一」という使命感が根づいています。そのためリスクを抑えながら成長を続けられる土台があるのです。
結論として、伝統と安定を重んじる風土は安心感を与える一方で、自分の挑戦意欲との相性を見極めることが大切でしょう。
③社員教育や研修制度が充実
JALは社員教育や研修制度が整っている点でも知られています。航空業界は専門性が高く、入社後の教育環境が充実しているかどうかが成長に直結。
その点でJALは多様な研修を用意し、社員を育てる体制を築いています。新入社員向けの基礎研修だけでなく、接客や安全に関する実践的な教育が徹底されているのです。
さらにキャリア段階に応じた研修や海外派遣の機会もあり、社員一人ひとりが強みを伸ばしながら成長できる環境が整っています。ただし制度が整っていても、学びを活かすかどうかは本人の意欲次第です。
積極的に挑戦する姿勢を持つことで研修の価値を最大限に引き出せます。結論として、教育体制の充実はJALの大きな魅力であり、学び続けたい人に向いている企業といえるでしょう。
④リーダーシップと気配り力を重視
JALの社風ではリーダーシップと気配り力の両立が求められます。航空業務はチームで進めるため、状況に応じて周囲を導く力が必要です。しかし同時に、相手を思いやる姿勢が信頼関係を築く上で不可欠。
例えば、客室乗務員はチームの中心として業務を回しつつ、お客さま一人ひとりに寄り添った対応をしています。整備や運航部門でも、仲間を尊重しながら適切な判断を下すことが重要です。
このようにリーダーシップと気配りを両立させることが、JALらしい働き方につながっています。ただし、どちらかに偏ると信頼を得られない可能性も。そのため状況を見極めて行動できる力が必要です。
結論として、リーダーシップと気配り力を兼ね備えた人材はJALで高く評価され、活躍の幅が広がるでしょう。
⑤安全運航を最優先する姿勢
JALの社風で最も重要なのが、安全運航を最優先する姿勢です。航空会社にとって安全は最大の使命であり、JALはその意識を組織全体で共有しています。
社員一人ひとりが責任を持ち、常に安全を守る文化が浸透しているのです。過去の経験を踏まえ、リスク管理や訓練を徹底し、どのような状況でも安全を優先する判断が下されます。
これは利用者に安心を与えるだけでなく、社員にとっても誇りとなっているでしょう。ただし、安全を守るためには規律を徹底する必要があり、柔軟さが制限される場面もあります。
しかし、それこそが航空業界における責任の重さを示しているのです。結論として、安全を最優先する姿勢はJALの根幹であり、利用者からの信頼を支える最大の要因でしょう。
ANAとJALの業績比較(売上高)

ANAとJALの売上高を比べると、近年はANAが国内首位を維持しています。規模の大きさと国際線展開の広さがANAの強みであり、就活生にとって成長性や安定性を感じやすいポイントになるでしょう。
ANAは国内線に加えて国際線も積極的に拡大し、多角的に収益を上げています。一方でJALは再建後、効率的な経営を重視しており、売上規模はANAに及ばないものの収益率の高さが特徴です。
つまり、単純に売上の大きさだけで判断するのではなく、それぞれの企業戦略や強みを理解することが重要でしょう。
売上が大きいANAでは挑戦の幅が広がり、JALでは効率性や堅実さを学べる環境があります。
どちらを志望する場合でも、この違いを自分の適性や価値観と結びつければ、説得力のある志望動機を作れるはずです。
| 企業 | 連結売上(年度) | ポイント | 引用元 |
|---|---|---|---|
| ANA(ANAホールディングス) | 売上高 2兆2,618億円(2025年3月期) | 国際線の拡大により過去最高を更新。 | ANA 2025年3月期 決算IR |
| JAL(日本航空) | 売上収益 1兆8,440億円(2025年3月期) | 再上場後で最高水準を記録。効率的な経営体制。 | JAL 2025年3月期 決算IR |
ANAとJALが求める人物像

航空業界を目指す就活生にとって、企業が求める人物像を理解することは非常に重要です。ANAとJALは共に日本を代表する航空会社ですが、重視する資質には共通点と違いがあります。
ここでは両社が求める人材像を整理し、自己分析や志望動機づくりに役立ててください。
- 挑戦心とチームワークを持つ人材
- 協調性と柔軟性を備えた人材
- グローバル志向を持ち多様性を尊重できる人材
- 責任感を持ち安全意識を徹底できる人材
- 顧客志向で高いコミュニケーション力を持つ人材
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
①挑戦心とチームワークを持つ人材
ANAとJALが共通して求めるのは、挑戦心とチームワークを兼ね備えた人材です。航空業界は変化が激しく、常に新しい挑戦が必要とされます。
その一方で業務はチームで行われるため、協力し合う姿勢も欠かせません。ANAは新規事業や国際線拡大に積極的で、前例のない取り組みに挑戦する人を評価します。
JALも再建を経て効率化を進めつつ、新規路線やサービス改革を行っており、挑戦できる人材を必要としているのです。ただし一人で成果を出すのではなく、仲間と力を合わせる姿勢が大切です。
挑戦心だけが強すぎても協調性を欠けば組織に溶け込みにくくなります。逆に協調性ばかりで新しい提案をしないと成長の機会を逃すでしょう。
結論として、自ら挑戦しながらもチームで成果を追求できるバランス感覚が求められています。
②協調性と柔軟性を備えた人材
ANAとJALは、ともに協調性と柔軟性を重視しています。航空業界は天候やシステムの不具合など、予測できない状況が多く、その場に応じて対応できる力が必要だからです。
さらに、部署ごとの連携が欠かせないため、協調性も大切になります。ANAは若手の意見を積極的に取り入れる文化があり、柔軟な発想と協調的な姿勢を持つ人材を評価します。
JALは伝統的にチームワークを重んじる社風が強く、周囲と調和を図りながら柔軟に動ける人を求めているでしょう。
どちらも「一人で完結しない仕事」であることを理解し、仲間と協力できる人を求めているのです。ただし、協調性を意識しすぎて自分の意見を出せないと、主体性に欠けると見なされる場合があります。
結論として、協調性と柔軟性を持ちつつ、自分の考えを適切に発信できる人材が評価されるでしょう。
③グローバル志向を持ち多様性を尊重できる人材
ANAとJALが共通して重視するもう一つの資質は、グローバル志向と多様性への理解。両社とも国際線を広く展開しており、多国籍の顧客や社員と接する機会が多いからです。
ANAは海外事業を積極的に拡大しており、異文化を尊重しながら行動できる人材を必要としています。
JALもワンワールドアライアンス加盟を通じて海外航空会社と連携しており、国際的な感覚を持つ人が評価されるでしょう。語学力はもちろんですが、それ以上に異なる価値観を受け入れる姿勢が重要です。
ただし、グローバル志向という言葉だけでは説得力に欠けます。留学や外国人との協働経験など、具体的なエピソードを示すことが効果的です。
結論として、多様性を尊重し国際的に活躍できる意欲を持つことが、両社で評価される資質でしょう。
④責任感を持ち安全意識を徹底できる人材
航空業界で最も大切なのは、安全を守る責任感です。ANAとJALの双方が共通して強調しているのは、どんな状況でも安全を優先する意識を持つ人材。
航空機の運航は小さなミスが重大な事故につながるため、高い責任感が欠かせません。ANAはデジタル技術を取り入れながらも、安全最優先の姿勢を徹底しています。
JALも経営再建後、安全意識を組織文化の中心に据え直し、社員全員で支える体制を築きました。両社の共通点は「安全なくして成長なし」という考えです。
ただし、安全を守るためには規律を徹底するだけでなく、現場では迅速な判断も必要です。結論として、責任感を持ちながら安全を守りつつ、臨機応変に動ける人材が求められています。
⑤顧客志向で高いコミュニケーション力を持つ人材
ANAとJALが最後に重視するのは、顧客志向と高いコミュニケーション力です。航空業界は人との関わりが中心であり、乗客に安心と満足を届けることが求められます。
そのため、顧客の立場で考え、円滑に意思疎通できる力が不可欠です。ANAは若手にも発言の機会を与える文化があり、自分の考えを分かりやすく伝える力を重視します。
JALは「丁寧なおもてなし」を大切にしており、細やかな気配りを持って接する人を評価。両社に共通するのは、相手の状況を理解し最適な対応を取れることです。
ただし、コミュニケーション力は話す力だけではありません。聞く力や相手の気持ちをくみ取る力も含まれます。
結論として、顧客志向を持ち、信頼関係を築けるコミュニケーション力こそが、ANAとJALで高く評価される資質です。
ANAとJALの比較から見える就活のヒント

ANAとJALを比較すると、それぞれの特徴や社風、業績に明確な違いがあり、自分に合った企業選びの参考になります。
理由は、航空業界全体の現状や動向を理解することで、企業の強みや方向性がより具体的に見えてくるからです。
ANAは国際線の幅広い展開やスターアライアンス加盟を強みに成長を続け、挑戦や自由な発想を歓迎する社風を築いています。
一方でJALは丁寧なおもてなしや地方空港網の充実に力を入れ、協調性や伝統を大切にする風土を持っているのです。実際に売上規模はANAが大きいですが、効率性や安定感ではJALも強みを発揮しています。
JALとANAの比較を通して両社の違いを理解し、自分の価値観やキャリアの方向性に照らし合わせて選択してくださいね。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。











