就活と卒論は両立できる?面接での答え方とスケジュール管理法
大学生活の集大成である卒論と、人生を左右する就活を同時進行させるのは大きな負担ですよね。特に面接では卒論のテーマや取り組み姿勢を問われることがあり、答え方次第で好印象を与えられます。
この記事では、卒論と就活という就活生が直面する課題について、面接での答え方のポイントやスケジュール管理のコツを、例文や具体的な対処法とともにわかりやすく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
就活で面接官が卒論について質問する理由

就活の面接では、自己PRや志望動機に加えて「卒論」について聞かれることがよくあります。
これは研究テーマを知りたいからだけではなく、学生がどのように課題へ取り組み、考えをまとめるのかを確認する意図があるのです。
ここでは面接官が卒論を質問する理由を整理し、理解を深めていきましょう。
- 学生の興味・関心を把握するため
- 卒論テーマと企業との親和性を確認するため
- 論理的に説明する力を測るため
- 問題解決能力や思考力を評価するため
- 研究への取り組み姿勢や粘り強さを見極めるため
①学生の興味・関心を把握するため
卒論に関する質問は、学生がどの分野に関心を持ち、なぜそのテーマを選んだのかを知る手がかりとなります。
面接官は研究の内容自体の優劣を見ているわけではなく、選んだ理由や背景をしっかり説明できるかを確認しているのです。
自分がどんな思いで取り組んだのかを加えることで、相手に人柄や価値観が伝わります。また、体験やエピソードを交えて話せば、聞き手にとってイメージしやすくなるでしょう。
研究内容を説明するだけでなく、自分らしさや行動の軸を表現することが評価につながるのです。
②卒論テーマと企業との親和性を確認するため
面接官は学生が研究してきたテーマが、企業の事業や業務にどの程度関係しているのかを確かめています。
たとえばマーケティングを研究してきた学生が消費財メーカーを志望する場合、学んだ分析方法をどう実務に活かせるかを語れば、説得力が増すでしょう。
一方で、テーマが直接関係していなくても問題はありません。研究を通じて得た分析力や継続力、課題を整理する力を業務に応用できると伝えることが大切です。
自分の研究と仕事を結びつける姿勢を示すことで、入社後の成長を期待させる答えにつながるのです。
③論理的に説明する力を測るため
卒論は大量の情報を収集・整理し、最終的に結論へまとめる作業です。そのため、面接で説明する場面は学生の論理的思考力を示す良い機会になります。
専門的な研究であっても、そのまま話すと伝わりにくいため、相手に理解できる形に噛み砕く必要があるのです。話すときは「結論→理由→根拠→成果や学び」という順序を意識するとわかりやすいでしょう。
例えば「○○をテーマに研究し、△△という方法で分析した結果、□□がわかりました。この過程で課題を整理する力が身につきました」といった流れです。
研究を伝える力そのものが社会人に求められるコミュニケーション力と直結しており、その点を評価されやすいのです。
④問題解決能力や思考力を評価するため
卒論はテーマ設定から調査、分析、結論に至るまで長い過程をたどるため、必ず困難や課題に直面します。面接官はそのときにどう対処したのか、失敗をどう乗り越えたのかに注目しています。
失敗を隠す必要はありません。むしろ「一度は壁にぶつかったが、工夫や努力で改善できた」という経験は高く評価されます。
困難に直面しても粘り強く取り組んだ姿勢は、社会で求められる問題解決力を示すものです。研究内容そのものよりも、過程を通じて身につけた力が重要視されます。
自分なりの課題解決プロセスを語れるように準備しておくと、面接官に強い印象を残せるでしょう。
⑤研究への取り組み姿勢や粘り強さを見極めるため
卒論は半年から1年以上をかけて取り組む長期的な課題です。そのため面接官は、最後まで努力を続けられるかどうかを確認しています。
答える際には、特に苦労した場面や工夫した取り組みを具体的に話してください。
例えば「資料が見つからず困ったが、図書館や専門家に相談して解決した」「途中で方向性がぶれたが、指導教員に相談しながら修正した」などです。
こうした話は真剣に取り組んだ姿勢を裏付ける証拠になります。
研究をやり遂げた経験は、社会に出てから困難に立ち向かう力の証明になります。自分の粘り強さを誠実に語ることが、就職後の可能性を伝える最良の方法となるでしょう。
就活で卒論について回答する際のポイント

就活の面接で卒論について聞かれるのは珍しくありません。面接官は研究の専門性よりも、学生がどのように課題へ取り組み、そこから何を学んだのかを知りたいのです。
そのため答え方次第で印象は大きく変わるでしょう。ここでは卒論を質問されたときに意識すべき答え方のポイントを整理しました。
- テーマ選定の理由を簡潔に伝える
- 卒論で学んだことや成果をアピールする
- 応募先企業との関連性を意識して答える
- 今後の研究計画や展望を交えて話す
- 卒論がない場合は正直に伝える
①テーマ選定の理由を簡潔に伝える
面接官が知りたいのは研究テーマそのものではなく、なぜそのテーマを選んだのかという思考の背景です。理由を簡潔に伝えることで、論理的な判断力や主体性を示せます。
例えば「関心を持った社会問題を研究したかった」や「これまでの学びを深めたいと考えた」と説明すれば十分に伝わるでしょう。
ただし専門用語を多用すると理解されにくく逆効果になりやすいため注意してください。結論を先に述べ、その後で背景を添えると整理された印象を与えられます。
個人的な興味と社会的な意義を組み合わせて話せば説得力が増し、意欲と視野の広さを同時に示せるはずです。自分なりの選択基準や考え方を言葉にできれば、より強い自己PRにつながるでしょう。
②卒論で学んだことや成果をアピールする
卒論の過程では調査力や計画性、課題解決力など多様なスキルを身につけています。面接ではそのスキルを社会でどう生かせるかを伝えることが大切です。
例えば「困難に直面しても試行錯誤を重ねたことで粘り強さを得た」や「大量の資料を整理して要点をまとめる力を磨いた」と説明すれば評価されやすいでしょう。
成果を伝えるときは「経験を通じてどう成長したのか」を強調すると伝わりやすいです。
さらに、研究で得たスキルを業務に応用する具体例を加えると説得力が高まります。学業の成果を社会的な価値に置き換えて伝えることが、面接で評価を得る大きなポイントになるでしょう。
③応募先企業との関連性を意識して答える
卒論の内容が直接企業の事業に結びつかなくても、工夫して関連づけることは可能。面接官は「学んだことをどう応用できるか」を重視しているからです。
例えば「データ分析を通じて論理的に課題を整理する力を培ったので、営業活動の戦略立案に活かせる」と答えると説得力があります。
あるいは「共同研究で協働力を学んだので、チームでの業務に役立てたい」と伝えるのも効果的です。ただし無理なこじつけは不自然に映るため避けましょう。
卒論とキャリアを関連づけることは、自分を採用するメリットを具体的に示すことでもあるのです。
④今後の研究計画や展望を交えて話す
卒論の説明を印象づけるために、今後の展望を語ることも効果的です。
例えば「研究を通じて課題発見の重要性を知ったので、社会人になっても改善点を探し続けたい」と答えれば前向きな印象を与えられるでしょう。
ただし研究を続けたい思いを強調しすぎると「就職より研究を優先するのでは」と誤解される場合があります。そのためキャリア形成や社会での活用を意識して話すことが大切です。
研究で得た知識や姿勢を「業務にどのように役立てたいか」と結びつけると、より現実的で効果的なアピールになります。
将来への意欲を示せば、学びを実務に結びつけられる人物として好印象を残せるでしょう。
⑤卒論がない場合は正直に伝える
学部や学科によっては卒論が必須でないこともあります。その場合は無理に作り話をせず、正直に伝える方が良いでしょう。大切なのは卒論そのものではなく、学びをどう活かしたかです。
例えば「ゼミ活動で発表を重ねて分かりやすく伝える力を培った」や「長期課題で計画性と粘り強さを身につけた」と具体的に話せば信頼を得られます。
隠すよりも誠実に現状を説明する姿勢の方が評価されやすいです。さらに卒論以外の活動を通じて得た成果を面接で示すことで、むしろプラスの評価につながる場合もあります。
卒論がなくても他の経験を魅力的に語ることは可能であり、むしろ自分の成長や可能性を示す絶好の機会になるのです。
就活で卒論について聞かれたときの回答例文
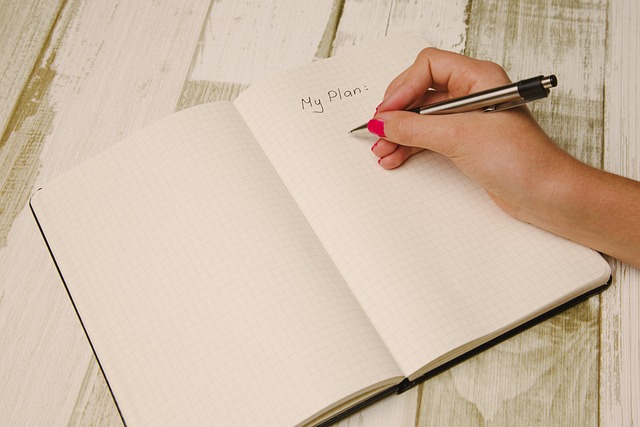
面接で卒論について聞かれたとき、どのように答えればよいか迷う人は少なくありません。ここでは、実際に使える例文を紹介しながら、自分の状況に合った答え方のイメージをつかめるように解説します。
文系の卒論テーマを伝える例文
文系の学生が面接で卒論について答えるときは、研究テーマの背景やきっかけを簡潔に伝えることが大切です。ここでは文学や社会学など、幅広い文系分野に応用できる例文を紹介します。
《例文》
| 私は卒論で「若者の読書離れとSNS利用の関係性」について研究しています。高校時代に友人と読書習慣の差を感じたことがきっかけで、大学入学後にさらに興味を持ちました。 調査ではSNSの使用時間が長いほど紙の本を読む頻度が下がる傾向が見られましたが、一方で電子書籍の利用が増えるという新しい発見もあったのです。 この研究を通して、データを整理しながら人の行動を分析する力を養うことができました。今後はこうした分析力を活かし、御社でのマーケティング業務に貢献したいと考えています。 |
《解説》
研究のテーマを選んだきっかけと、そこから得た学びをセットで伝えると説得力が増します。特に「学んだ力を企業でどう活かすか」を一言加えると、評価につながりやすいでしょう。
理系の卒論テーマを伝える例文
理系の学生が卒論について面接で答えるときは、研究内容を難しく語るのではなく、研究のきっかけや工夫した点を伝えることが効果的です。ここでは理系分野に応用できる例文を紹介します。
《例文》
| 私は卒論で「再生可能エネルギーを効率的に利用するための小型風力発電の改良」に取り組んでいます。 大学2年生のとき、ゼミでエネルギー問題に関する発表を聞いたことがきっかけで興味を持ちました。研究では模型を作り、風向きや風速の条件を変えて効率を測定しました。 その中で羽の形を工夫することで、従来よりも発電量が上がることを確認できました。実験を通じて計画的にデータを集め、課題を改善する力を身につけられたと考えています。 今後はその経験を活かし、御社の技術開発に貢献したいです。 |
《解説》
研究の内容を専門用語で説明しすぎると伝わりにくいため、工夫した点や成果を簡潔にまとめることが重要です。学んだ力を企業の仕事にどう活かすかを明確にすると説得力が高まります。
卒論テーマが未定の場合の例文
卒論のテーマがまだ決まっていない状態で面接を迎える学生も少なくありません。そのような場合でも、正直に伝えながら前向きな姿勢を示すことで十分評価につながります。
《例文》
| 現在、卒論のテーマは最終的に決定していませんが、環境問題に関する研究を候補として考えています。 高校時代に地元の清掃活動に参加した経験がきっかけで、社会に役立つ研究をしたいと思うようになりました。 大学では環境政策に関する授業を多く履修し、学んだ知識を卒論でも活かしたいと考えています。具体的なテーマはゼミの先生と相談しながら今後数か月で絞り込む予定です。 テーマが未定ではありますが、自分の興味関心を深めると同時に、研究を通じて問題解決力を高めたいと考えています。 |
《解説》
テーマが決まっていなくても、興味を持つ分野や今後の計画を伝えると前向きさを示せます。具体的な行動予定を添えることで信頼性が高まり、面接官に誠実な印象を与えられるでしょう。
卒論を執筆していない場合の例文
大学によっては卒論が必須でない場合もあり、そのことで不安を抱える学生は多いです。ただし面接では正直に説明し、代わりに力を入れてきた活動を具体的に伝えることで十分に評価されます。
《例文》
| 私の学部では卒論が必修ではないため執筆はしていませんが、その分ゼミ活動と課外活動に力を注いできました。 ゼミでは少人数のグループで企業の経営戦略について研究し、最終発表では発表内容をまとめる役割を担当しました。 また、アルバイト先では新人教育を任され、相手の理解度に合わせた説明の工夫を意識。 こうした経験を通じて、情報を整理して分かりやすく伝える力や、周囲と協力して目標を達成する姿勢を培うことができました。 卒論の代わりに得たこれらの経験を、御社での業務にしっかり活かしたいと考えています。 |
《解説》
卒論がない場合でも、ゼミやアルバイトなどで学んだ経験を具体的に語ると強みになります。大切なのは「そこで得た力を仕事にどう活かせるか」を必ず結びつけて説明することです。
企業との関連性を意識した例文
面接で卒論について話すときは、研究内容をそのまま説明するだけでは不十分です。志望する企業や業務とのつながりを意識して答えると、自分の強みをより効果的に伝えられます。
《例文》
| 私は卒論で「地域の観光振興とSNS活用の関係」について研究しました。大学近くの観光地が訪問者数減少に悩んでいることを知り、SNSでの発信が来訪者数にどのように影響するのかを調べました。 調査の結果、写真や動画を活用した投稿は閲覧数や来訪意欲の向上につながる傾向が見られました。この研究を通してデータを整理し、効果的な発信方法を考える力を身につけられたと思います。 御社の広報活動や地域との連携施策でも、培った分析力や発信力を活かし、より多くの人に魅力を伝えることに貢献したいと考えています。 |
《解説》
企業との関連性を意識する際は、研究内容を業務にどう活かせるかを具体的に示すことが重要です。「得た力」→「企業での活用方法」という流れを意識すると伝わりやすくなります。
就活で卒論について回答する際の注意点

就活の面接では卒論について聞かれることが多く、答え方によって印象が大きく変わります。正直さやわかりやすさはもちろんですが、伝え方を誤ると熱意や能力が伝わりにくくなる場合もあるでしょう。
ここでは、回答時に特に気をつけたいポイントを具体的に紹介します。
- 「好きだから」だけの理由は避ける
- 専門用語を使いすぎない
- 嘘や誇張をせず正直に答える
- 自分の研究だけを一方的に語らない
①「好きだから」だけの理由は避ける
卒論のテーマ選びを聞かれた際に「好きだから」「興味があったから」とだけ答えると、印象が浅くなり説得力も弱まります。
面接官はその先にある思考や学びを知りたいと考えているため、理由を補足することが必要です。
例えば「興味があったから取り組んだ」ではなく、「調べていく中で課題を見つけ、解決に向けて研究した」と話すと主体性が伝わります。
単なる感情の表現ではなく、研究の過程や成果につながる背景を添えることで、学びの姿勢を示せるでしょう。自分らしさを表現するためにも、選んだ理由に一歩踏み込んだ説明を加えてください。
②専門用語を使いすぎない
研究内容を正確に伝えようとして専門用語を多用すると、相手に伝わらないことがあります。面接官は必ずしも同じ分野の知識を持っているわけではないので、難しい言葉だけでは理解が難しいのです。
専門用語を使う場合には、誰でも理解できる言葉に置き換えたり補足したりする工夫をしてください。
例えば「回帰分析」という言葉をそのまま使うのではなく、「データの傾向を数値で確かめる方法」と加えるだけで相手の理解度は大きく変わります。
研究の専門性を強調するよりも、平易な説明で伝える方が評価につながるでしょう。分かりやすさを優先することで、結果的に論理性や説明力も示せます。
③嘘や誇張をせず正直に答える
面接で好印象を得たいと考え、実際以上に成果を大きく話したり、研究の進み具合を誤魔化したりする人もいます。しかし、そのような答えはすぐに見抜かれることが多く、信頼を失う原因になりかねません。
研究が未完成であれば「まだ分析途中ですが、こうした傾向が見えてきました」と答える方が誠実さを示せます。面接官が知りたいのは完璧な成果ではなく、研究への姿勢や取り組み方です。
誇張せず事実を正直に伝え、その中で工夫や学びを強調すれば信頼感を得られるでしょう。正直さは長期的に見ても大きな評価につながるため、ありのままを誠実に話してください。
④自分の研究だけを一方的に語らない
卒論の説明に集中しすぎると、自分の研究を長く語りすぎてしまうことがあります。しかし面接は発表の場ではなく対話であり、相手に伝わることが重要です。
研究の細部まで説明するよりも、要点を整理して簡潔にまとめましょう。そのうえで、企業や職種と関連づけて話すと効果的です。
例えば「この研究で得た分析力を御社の業務改善に活かせると思います」と加えれば、単なる研究紹介ではなく自己PRへと自然につながります。
研究の詳細を一方的に話すのではなく、面接官が意味を見いだせるよう工夫して説明してください。伝える内容を整理し、理解されやすい形に変えることが評価につながるでしょう。
就活で卒論のテーマがない場合の対処法
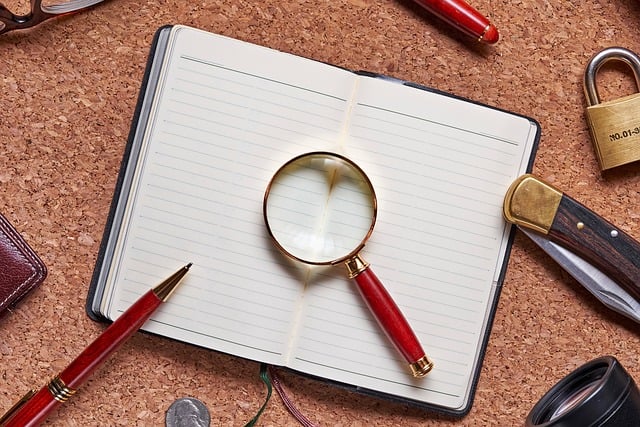
就活の面接では「卒論のテーマ」について質問されることがよくあります。ただ、全員が明確なテーマを持っているわけではありません。
研究計画がまだ進んでいない学生も多く、そのときの答え方で印象は大きく変わるでしょう。ここではテーマが未定のときの具体的な対処法を紹介します。
- テーマが未定であることを正直に話す
- 今後の卒論計画を説明する
- ゼミや授業で力を入れたことを伝える
- 学業以外で力を入れた活動をアピールする
①テーマが未定であることを正直に話す
面接で卒論のテーマを聞かれたとき、まだ決まっていないなら無理に答えを作る必要はありません。正直に「現在は検討中」と伝える方が誠実に映ります。
そのうえで「どの分野に関心を持っているか」や「今どの段階まで考えているか」を補足すると、主体性を感じてもらえるでしょう。逆に曖昧な説明をすると、信頼性を損ねてしまいかねません。
面接官が知りたいのはテーマ自体の専門性ではなく、考え方や取り組む姿勢です。ですから正直さと今後の意欲を示すことが大切。自分の現状を整理して前向きに伝えてください。
②今後の卒論計画を説明する
テーマがまだ決まっていなくても、今後の計画を話すことで前向きな印象を与えられます。例えば「夏までに分野を絞り、秋に具体的なテーマを決める予定です」と時期を示すと計画性が伝わるのです。
また「社会問題に関心があるので、その中から研究テーマを見つけたい」と方向性を添えると、自分の興味や視点をアピールできるでしょう。
大切なのは「未定だから何もしていない」のではなく「考えを深めている途中」であることを示すことです。計画を説明すれば、主体的に取り組む姿勢が伝わり、面接官も安心できるはず。
③ゼミや授業で力を入れたことを伝える
卒論テーマが未定でも、ゼミ活動や授業での取り組みを伝えれば十分にアピールできます。]
例えば「ゼミでのディスカッションを通じて論理的思考力を磨いた」や「課題レポートでデータ分析を行い問題解決力を高めた」と具体的に話すと効果的です。
面接官は研究そのものだけでなく、その過程で得た力を知りたいと考えています。そのため、授業やゼミでの経験を通じて培ったスキルや姿勢を示せば評価材料になるでしょう。
重要なのは、ただ活動内容を述べるだけではなく「そこから何を学び、どう成長したか」を明確にすることです。これによりテーマ未定であっても前向きな評価につながります。
④学業以外で力を入れた活動をアピールする
卒論のテーマがない場合は、学業以外の経験をアピールするのも効果的です。アルバイトや部活動、インターンシップで得た力は社会人として必要な能力と直結しています。
例えば「アルバイトで培った接客力や調整力」「部活動でのリーダー経験によるマネジメント力」などを具体的に伝えると説得力が増すでしょう。
卒論の有無は一要素に過ぎず、他の活動から得た学びや成果を示すことで十分に評価されます。面接官が知りたいのは「どのように課題に向き合い成長してきたか」です。
学業以外の経験も堂々と伝えて構いません。結果として、卒論テーマがなくても前向きな印象を残すことができるでしょう。
就活と卒論を両立させるためのコツ

大学生活の後半は就活と卒論が重なるため、どちらも手が回らず悩む学生が多いです。計画的に取り組まなければ、就活で十分な準備ができず、卒論の完成度も下がってしまうでしょう。
ここでは両立を進めるための具体的な工夫を紹介します。
- 就活と卒論のスケジュールを把握する
- 早めに卒論に取りかかる
- 月ごとに目標を設定する
- 状況に応じて優先順位を決める
- 就活準備を早めに始めておく
①就活と卒論のスケジュールを把握する
両立の第一歩は全体のスケジュールを正しく把握することです。就活は説明会やエントリー、面接など段階ごとに忙しい時期があり、卒論も調査や執筆に時間がかかります。
この2つが重なると負担が大きくなり、結果的にどちらも中途半端になりかねません。大学の卒論提出時期や就活サイトの予定を確認し、カレンダーにまとめて見える化しておくと安心です。
そのうえで忙しくなる月を前もって予測し、準備を前倒しに進めてください。全体像を把握するだけで余裕が生まれ、焦らず計画的に動けるようになります。
②早めに卒論に取りかかる
卒論を短期間で仕上げようとすると、思った以上に時間を奪われます。調査や分析に予想以上の労力が必要になることも珍しくありません。そのため、就活が本格化する前から着手することが重要です。
例えば3年生のうちにテーマを固めておけば、4年生では分析や執筆に集中できます。早めに進めておくと、就活が忙しい時期でも最低限の作業だけで済ませられるでしょう。
加えて予想外のトラブルがあっても柔軟に対応できます。つまり、早期の取りかかりは時間の自由度を確保するための基本であり、両立を成功させる最も確実な方法なのです。
③月ごとに目標を設定する
大まかな計画だけでは実行につながりません。就活と卒論を同時に進めるには、月単位で目標を決めると効果的です。
例えば「今月は研究資料を集める」「来月は調査結果をまとめる」と区切ると、進捗を確認しながら着実に進められます。
就活でも「今月は説明会に5社参加」「来月はエントリーシートを3社分仕上げる」など、具体的に設定してください。細かく分けておくことで達成感が積み重なり、モチベーションも維持しやすいです。
無理のない計画を立てることが両立の支えとなり、小さな目標設定が大きな成果につながるでしょう。
④状況に応じて優先順位を決める
常に両方を完璧に進めようとすると無理が生じ、逆にどちらも進まなくなることがあります。
面接が集中する週は就活を優先し、就活が落ち着いた時期には卒論に比重を置くなど、柔軟に切り替えることが大切です。
「今はどちらを優先すべきか」を定期的に確認すると迷いが減り、効率的に取り組めます。優先順位を明確にすればストレスも少なく、最終的に成果を残しやすくなるでしょう。
両立は均等に分けることではなく、その時々の状況に合わせて調整する姿勢が鍵です。
⑤就活準備を早めに始めておく
就活の準備を直前から始めると、自己分析や企業研究に追われて卒論の時間を削ることになります。だからこそ、早い段階から少しずつ進める必要があります。
例えば履歴書の下書きやガクチカの整理を3年生のうちに進めておけば、エントリーが始まった時に慌てず対応できるでしょう。面接対策も早めに練習しておくと安心です。
土台を整えておけば、4年生になってから卒論と並行しても混乱せず進められます。結局のところ「準備が早ければ早いほど両立はしやすい」ということです。
時間を分散させて進める工夫が負担を減らす最大のポイントになります。
卒論との両立に役立つ就活方法

就活と卒論を同時に進めるのは、多くの学生にとって大きな負担になります。ただし工夫を取り入れれば無理なく両立できるでしょう。
ここでは限られた時間を有効に使い、卒論と就活を並行して進めるための実践的な方法を紹介します。
- 就活エージェントを活用する
- スカウト型求人サイトを利用する
- 短期・長期インターンシップに参加する
- 大学のキャリアセンターを活用する
- 選考直結イベントや合同説明会に参加する
①就活エージェントを活用する
卒論と就活を両立させたいとき、就活エージェントは大きな助けになります。エージェントは企業情報を整理して紹介してくれるため、効率よく企業と出会えるのです。
さらに応募書類の添削や面接対策も受けられるので、準備にかける時間を短縮できるでしょう。特に卒論で忙しい時期は、自分で一から情報を探すと負担が大きくなりがちです。
その点、エージェントを使えば必要な情報がすぐに手に入り、時間を研究に充てられます。ただし担当者によってサポートの質が異なるため、複数のサービスを比較して選んでください。
信頼できる担当者に出会えれば、両立の心強い味方になるはずです。
面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?
一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。
②スカウト型求人サイトを利用する
効率的に企業とつながりたいなら、スカウト型求人サイトの利用が効果的です。プロフィールを登録しておくだけで企業からオファーが届くため、自分から探す手間を減らせます。
卒論に集中したいときでも届いたスカウトから選んで応募でき、時間の節約になるでしょう。さらに想定外の企業や業界から声がかかることもあり、選択肢を広げる機会にもなります。
ただしプロフィールが不十分だとスカウトは届きにくいです。学業や課外活動で得た経験を具体的に記載し、内容を充実させてください。
効率と可能性を両立できる方法として、卒論との並行に役立つでしょう。
③短期・長期インターンシップに参加する
インターンシップは就活対策だけでなく、卒論との両立にもつながります。短期インターンは数日から数週間で参加でき、複数の企業を効率よく体験できるのです。
一方で長期インターンは実務を継続的に経験でき、自分の強みや課題を明確にするきっかけになるでしょう。
卒論に集中したい時期には短期インターンを選び、研究の合間に社会経験を積むと負担が少なくなります。逆に就活を先取りしたい場合は長期インターンが有効です。
いずれの経験も卒論に結びつけることで、自己分析や面接でのアピール材料になります。自分の状況に合わせてインターンを選ぶことが、両立のコツといえるでしょう。
「インターンの選考対策がよくわからない…」「何度も選考に落ちてしまう…」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるインターン選考対策ガイドを確認して必勝法を知っておきましょう。LINE登録だけで無料でダウンロードできますよ。
④大学のキャリアセンターを活用する
大学のキャリアセンターは就活と卒論を両立したい学生にとって利用価値が高い場所です。求人情報や企業データがまとまっているだけでなく、エントリーシートの添削や模擬面接も受けられます。
自分で調べるより効率的に情報を得られるので、卒論にかける時間を確保しやすくなるでしょう。
さらにキャリアアドバイザーは多くの学生を支援しているため、就活と学業を両立するための実践的な助言を受けられます。
利用を後回しにする学生もいますが、積極的に相談すれば早めに課題を発見できるでしょう。大学の支援を上手に活用することが、両立を進めるうえで重要です。
⑤選考直結イベントや合同説明会に参加する
効率的に複数の企業と接触できるのが、選考直結イベントや合同説明会です。短時間で多くの情報を得られるため、卒論で忙しい学生にとって有効な手段になります。
イベントによっては、その場で一次選考に進める場合もあり、就活を早く進められるのが魅力です。さらに一度に複数社の担当者と話せるので、企業研究や比較も行いやすくなります。
ただし情報量が多いため、参加前に業界や企業をある程度絞っておくことが必要です。準備をせずに参加すると、せっかくの機会を活かせません。
計画的に臨めば、卒論と就活を効率よく両立させる大きな支えになるでしょう。
卒論と就活を両立させるために大切なこと

就活で卒論について聞かれるのは、学生の興味や思考力、姿勢を確認するためです。そのため、答える際にはテーマ選定の理由や学びを簡潔に伝え、企業との関連性を意識することが重要でしょう。
具体例を参考に準備すれば、自分の強みを分かりやすく表現できます。また、専門用語の使いすぎや誇張を避け、正直さを大切にしてください。
もしテーマが未定でも、計画や他の活動を伝えることで評価は得られます。さらに両立のためには早めの準備や優先順位の調整が欠かせません。
エージェントや大学のサポートを活用すれば効率も高まります。結論として、卒論と就活は工夫次第で相乗効果を生み出し、自信を持って挑めるはずです。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












