企業研究ノート完全ガイド|項目一覧から作成ポイントまで紹介
「企業研究ノートって本当に必要なの?」と疑問に思っている就活生も多いのではないでしょうか。
エントリーシートや面接でしっかりアピールするためには、企業理解を深めて言語化できる準備が欠かせません。
その際に役立つのが、自分だけの情報を整理できる「企業研究ノート」です。どのような項目をまとめ、どんな形で作成すると効果的なのかを知っておくことで、就活全体の質が大きく変わります。
本記事では、企業研究ノートの意味や役割から、必要な項目一覧、作成のコツまで徹底的に解説します。効率よく活用して、納得のいく内定獲得につなげましょう。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
「企業研究ノート」とは?

就活では、企業の情報を正しく整理することが合否を左右します。そのために役立つのが「企業研究ノート」です。
企業ごとの特徴をまとめることで、比較や自己分析に活かせるだけでなく、選考準備の効率化にもつながるでしょう。ここでは、意味や役割、業界研究との違い、作成を始める時期について解説します。
- 企業研究ノートの意味と役割
- 企業研究と業界研究の違い
- 企業研究ノートを作るべき時期
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
①企業研究ノートの意味と役割
企業研究ノートとは、志望企業の情報を1冊にまとめた就活専用のノートです。目的は、単に情報を記録することではなく、自分の考えを整理して就活をスムーズに進める点にあります。
就活生は複数の企業を同時に調べるため、情報が混乱しやすいものです。そこでノートにまとめておけば比較がしやすく、志望動機の作成にも役立ちます。
さらに、見返すことで理解が深まり、面接直前の確認にも活用できます。ノートはただのメモではなく、自分の就活を支える戦略的なツールです。
結果として「何を基準に企業を選ぶか」が明確になり、納得感のあるキャリア選択につながるでしょう。
②企業研究と業界研究の違い
就活では「企業研究」と「業界研究」を混同してしまう学生が少なくありません。しかし、目的と範囲は異なります。業界研究は、自分に合う分野を知るために業界全体の特徴や動向を把握するものです。
一方で企業研究は、特定の会社を深く理解し、自分に合っているかを確認する作業をいいます。業界研究が地図だとすれば、企業研究は目的地に向かうルートの確認に近いです。
業界研究だけで満足してしまうと、面接で志望度を伝える際に説得力が不足することもあるでしょう。
だからこそ両者を区別し、業界研究で全体像を把握したうえで、企業研究ノートで詳細を整理していくことが大切です。
③企業研究ノートを作るべき時期
企業研究ノートは、できるだけ早く取り組むのがおすすめです。特に大学3年の夏インターンの前から始めておくと、本選考で大きな強みになります。
早い段階で特徴を記録しておけば、自己分析や他社との比較にも役立つでしょう。逆に、直前になって作ろうとすると情報が不足し、志望動機に深みを出せません。
早めに作成しておけば、説明会やインターンで得た内容をその場で反映でき、自然と充実したノートになります。ありがちな落とし穴は「本選考直前でいい」と先延ばししてしまうことです。
その結果、面接で具体的な根拠を示せず後悔するケースも多いものです。準備は早ければ早いほど安心につながります。
就活で企業研究ノートを作るメリット

就活において情報を整理しないまま進めると、自分に合う企業を見失いやすくなります。そこで役立つのが企業研究ノートです。ここでは、ノートを作ることで得られる具体的なメリットを紹介します。
理解や比較のしやすさ、志望動機の作成への応用などを記入し、就活を有利に進めるための視点をまとめましょう。
- 企業理解を深められる
- 企業を比較しやすくなる
- 志望動機や自己PRに活かせる
- 就活の軸を明確にできる
- 選考対策に役立つ
①企業理解を深められる
企業研究ノートを作る最大の利点は、企業理解を自然に深められる点です。企業のホームページを読むだけでは情報が流れてしまい、頭に残りにくいことも多いでしょう。
しかし、ノートにまとめると自分の言葉に置き換えるため、理解が進みます。書き出す過程で気づきや疑問が浮かぶこともあります。
さらに繰り返し見返すことで記憶に定着しやすくなり、面接でも具体的に語れるようになるのです。その結果、「なぜこの企業を選んだのか」を説得力を持って話せるでしょう。
②企業を比較しやすくなる
就活では、複数の企業を受けるのが一般的ですが、情報が混ざり混乱することも少なくありません。企業研究ノートを使えば、共通のフォーマットで情報を整理でき、比較が格段にしやすくなるでしょう。
同じ項目で企業を並べれば、強みや弱み、将来性の違いが一目でわかります。比較を通して自分に合う条件がはっきりし、納得できる意思決定が可能になるでしょう。
選択に迷ったときもノートを見返せば冷静に判断でき、後悔のない選択につながります。
③志望動機や自己PRに活かせる
エントリーシートや面接では、企業に合わせた志望動機や自己PRを問われます。ここで効果を発揮するのが、企業研究ノートです。
ノートに蓄積した情報を基にすれば、その企業だからこそ語れる具体的な理由やエピソードを盛り込みやすくなります。
たとえば「理念に共感した」「成長分野で強みを活かせる」といった根拠を示せば説得力が増すでしょう。準備不足だと回答が表面的になりがちですが、ノートがあれば深みのある発言ができます。
その結果、企業に「本気で志望している」と伝わるでしょう。
④就活の軸を明確にできる
就活では「どんな基準で企業を選ぶのか」という軸がないと、受ける企業が増えるにつれて迷走しやすくなります。企業研究ノートを作れば、自分の判断基準が自然に見えてくるでしょう。
たとえば「福利厚生を重視するのか」「成長できる環境を優先するのか」など、比較を通じて自分の軸が浮かび上がります。
この軸が明確になれば志望動機やキャリアプランに一貫性が生まれ、採用担当者にも信頼感を与えられるでしょう。軸を持つことで、不合格が続いても迷わず前進できる強さも得られます。
⑤選考対策に役立つ
企業研究ノートは、選考直前の強力なサポートになります。面接では「なぜこの会社なのか」「他社との違いは何か」といった質問が多く出ますが、ノートを見ればすぐに確認が可能です。
整理した情報を基に答えれば自信を持って話せますし、説得力も増します。エントリーシート作成の際にも、特徴を整理した内容があると文章化がスムーズです。
効率的に準備が進むことで、安心感も生まれます。こうした積み重ねが選考通過率を高め、就活を有利に進める結果につながるでしょう。
企業研究ノートに必要な項目一覧

企業研究ノートを作るときに大切なのは、情報を整理して抜け漏れを防ぐことです。必要な項目をそろえておけば、比較検討や志望動機作成にも役立つでしょう。
ここでは、基本情報から自分の考察まで、押さえるべき項目を順番に解説します。
- 基本情報(会社名・所在地・設立年など)
- 経営理念・ビジョン
- 業績や財務状況
- 事業内容と特徴
- 企業の強みと弱み
- 競合他社との違い
- 求める人物像と社風
- 将来性と成長性
- 給与・福利厚生・勤務地
- 選考フローと採用情報
- 自分の所感・疑問点
①基本情報(会社名・所在地・設立年など)
まず押さえるべきは、会社の基本情報です。会社名や所在地、設立年、従業員数といった情報は、応募書類や面接で正確に答える必要があります。
ここが曖昧だと「志望度が低い」と受け取られるかもしれません。基本情報は調べやすい反面、誤りがあると大きなマイナスになります。
信頼できる公式サイトや有価証券報告書などから確認し、必ず最新の内容を記録しておきましょう。小さなポイントですが、就活全体の信頼感を高める基盤となります。
②経営理念・ビジョン
経営理念やビジョンは、企業が大切にする価値観や将来像を示しています。ここを理解しておくと、志望動機を語るときに一貫性を持たせられるでしょう。
逆に理念を無視した自己PRは、的外れに感じられてしまいます。企業研究ノートには、公式サイトにある理念の文言だけでなく、自分なりの解釈も添えてください。
その理念に共感できるか、また自分の価値観と合うかを考えることで、志望度の整理につながります。
③業績や財務状況
業績や財務状況を知ることは、企業の安定性や将来性を判断する上で欠かせません。売上高や利益率、過去数年の推移を確認すれば、成長しているのか停滞しているのかが見えてきます。
数字は難しく感じるかもしれませんが、グラフや簡単な表にまとめれば理解しやすくなるはずです。
財務状況を把握することで「安心して働けるか」「今後事業拡大が見込めるか」といった視点で企業を選べます。名前だけで判断せず、根拠のある選択につなげてください。
④事業内容と特徴
事業内容を理解することは、その企業が社会にどう貢献しているかを知る出発点です。事業の柱や主力製品・サービスを整理すると、他社との違いや強みが見えてくるでしょう。
同じ業界でも、BtoB中心かBtoC中心かで仕事内容は大きく異なります。企業研究ノートには具体的な事例も記録しておくと、面接で会話が深まりやすいでしょう。
単に「大きな会社だから」ではなく、自分がその事業にどう関わりたいかを考える助けになります。
⑤企業の強みと弱み
企業の強みと弱みを整理することは、志望動機を説得力あるものにするカギです。強みを理解すれば「だから惹かれる」と説明でき、弱みを把握すれば「自分が補える部分」と結びつけられます。
ただし弱みをそのまま伝えると印象が悪くなるため、改善点や可能性として言い換えるのが効果的です。ノートにまとめておくことで、企業を見る目が一方的にならず、バランスの取れた理解につながるでしょう。
⑥競合他社との違い
競合他社との違いを理解することは、志望動機の差別化に直結します。似た業界の企業を複数受けるとき、「なぜこの会社なのか」を語れなければ選考を突破できません。
競合と比較する際は、商品ラインナップやシェア、海外展開の有無など具体的な視点で整理するとわかりやすいです。
こうした比較をノートに残しておけば、面接でも自信を持って「この企業を選んだ理由」を伝えられるでしょう。
⑦求める人物像と社風
企業は採用ページや説明会を通じて、求める人物像を示しています。これを理解せずに応募すると、ミスマッチが起きやすくなります。
企業研究ノートには「挑戦心がある人」「チームワークを重視する人」など具体的に書き留めてください。さらに社員インタビューや口コミを参考にすると、実際の社風も見えてきます。
求める人物像と自分の性格が近いかどうかを見極めることで、安心して選考に臨めるはずです。
⑧将来性と成長性
将来性と成長性を考えることは、入社後のキャリアを見通すうえで重要です。新規事業への投資や海外進出、業界の流れに乗れているかを調べると、その企業の未来像が見えてきます。
短期的な業績だけでなく、中長期的にどのように成長するかを意識してください。企業研究ノートに「この事業に期待できる」「将来リスクがある」といった自分の評価を残しておくと、意思決定の参考になります。
⑨給与・福利厚生・勤務地
給与や福利厚生、勤務地などの条件は、長く働く上で欠かせない要素です。ただし待遇だけで決めると、入社後にミスマッチを感じることもあります。
重要なのは、他の項目と照らし合わせて「自分に合っているか」を判断することです。たとえば給与は平均的でも、勤務地が希望に合えば働きやすい場合もあるでしょう。
ノートに具体的な条件を書き出し、自分の優先順位を整理してください。
⑩選考フローと採用情報
選考フローや採用情報を把握することは、効率的な準備に直結します。エントリー開始時期や選考ステップを知らなければ、チャンスを逃す恐れも。
企業研究ノートに説明会やエントリーシートの締切日、面接回数などを記録しておけば、スケジュール管理が容易になるでしょう。採用情報は変わることがあるため、定期的に更新することも忘れないでください。
⑪自分の所感・疑問点
最後に、自分の所感や疑問点を必ず残しましょう。情報を並べるだけでは、自分にとっての意味が見えにくくなります。
調べた内容に対して「共感した点」「気になる部分」「もっと知りたいこと」を書き添えることで、企業研究が自分ごととして深まるはずです。
この記録は、面接で逆質問を考えるときのヒントにもなります。所感や疑問を積極的に残すことで、より主体的な就活につながるでしょう。
企業研究ノートの情報収集方法

企業研究ノートの質は、集める情報の質で決まります。信頼できる一次情報を軸にしつつ、第三者の評価で補強するのが近道です。
ここでは、入手先ごとの使い分けと注意点を整理します。精度と更新性を意識してノートに反映しましょう。
- 企業の公式サイト・採用ページ
- 就活サイトやナビサイト
- IR情報・決算資料
- ニュースや業界誌
- OB・OG訪問
- 会社説明会・セミナー
- インターンシップ
- SNSや口コミサイト
①企業の公式サイト・採用ページ
最初に確認すべき情報源は、公式サイトです。理念や事業、採用フローなどの基礎情報が最新かつ正確だからです。沿革やトピックスを見れば直近の動きや重点領域がつかめます。
職種紹介や求める人物像からは、面接で問われやすい観点も見えてくるでしょう。内容はそのまま写すのではなく、自分の言葉で要点をまとめてください。
ページURLと更新日をノートに残しておけば、見直すときに迷いません。
②就活サイトやナビサイト
強みは、俯瞰と比較ができること。公式だけでは拾えない締切日やイベント情報、先輩の体験談が集まりやすいからです。
検索条件を保存して新着を追い、エントリー要件や選考ステップを一覧化すると効率が上がるでしょう。口コミは主観が混ざるため、複数の投稿で傾向を確認してください。
公式情報と照らし合わせて一致点と相違点を書き分けると精度が増します。一次情報の補助として活用するのが安全です。
③IR情報・決算資料
数字で裏づけると、理解が深まります。売上や利益、事業別の内訳が事実ベースで示されるためです。過去3〜5年の推移や中期計画の重点投資領域、KPIの達成状況を簡単な表やメモで整理しましょう。
専門用語は、自分の言葉に言い換えると理解しやすくなります。単年だけで判断せず、流れを追うことが大切です。最後に、数字から得た示唆と自分の関心領域との接点を一行で残しておくと役立ちます。
④ニュースや業界誌
時事を把握すると、選考の説得力が増します。最新の提携や不祥事、規制変更は志望理由や逆質問の切り口になるからです。
企業名と主力事業のキーワードでニュースアラートを設定し、週1回まとめてノートに反映すると効率的でしょう。見出しだけで終わらせず、要点と影響を二行でまとめてください。
業界誌は潮流や競合の動きを知るのに有効です。事実と自分の見立てを分けて書けば、思い込みを避けられます。
⑤OB・OG訪問
現場の温度感は、会話で得るのが最短でしょう。公式には出ない業務の実態や評価軸、入社後のギャップが分かるからです。
訪問前に「1日の仕事の流れ」「評価で重視される行動」「入社前後のギャップ」の3点を質問として準備してください。
面談中は事実と感想を分けてメモし、終了後24時間以内にノートへ整理すると記憶が鮮明です。お礼の連絡も忘れずに行いましょう。個人の意見である前提を書き添え、鵜呑みにはしないことが大切です。
⑥会社説明会・セミナー
会社説明会・セミナーは、公式メッセージを声で確認できる貴重な場です。登壇者の言葉や反応から、文化や優先課題が見えてきます。参加前に基礎を押さえて質問を2〜3個準備してください。
配布資料は写すのではなく、強調点と自分の解釈を並べて記録すると有効です。終了後は、選考日程や必要書類をすぐにノートへ反映しましょう。
印象に残ったキーワードを抜き出し、志望動機のフレーズ候補として保存するのも効果的です。
⑦インターンシップ
体験を通じた理解は、最も強い学びになります。業務プロセスやコミュニケーションを、自分の感覚で把握できるからです。
参加前に「学びたいこと」と「評価してほしい行動」を1枚にまとめ、終了後に成果と課題を振り返ってください。担当者からのフィードバックは原文でメモし、次の行動につなげましょう。
雰囲気だけで判断せず、配属や働き方の条件も確認するとズレを減らせます。その企業で働く理由を一文で言語化すると芯が固まるでしょう。
「インターンの選考対策がよくわからない…」「何度も選考に落ちてしまう…」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるインターン選考対策ガイドを確認して必勝法を知っておきましょう。LINE登録だけで無料でダウンロードできますよ。
⑧SNSや口コミサイト
SNSや口コミサイトは、現場の空気感をつかむ補助になります。発信の頻度や内容から採用の温度や、社内の関心事が分かるからです。
公式アカウントは狙いを推測しながら読み、事実ベースでノートにまとめましょう。個人の口コミは有益ですが感情が強く出やすいため、同様の声が複数あるかで重みづけしてください。
出典と日時を明記し、真偽不明は保留にするのが安全です。公式情報と矛盾する点は再確認すると安心でしょう。
企業研究ノートの作り方

企業研究ノートは、就活の合否に直結する重要なツールです。効率的に情報を集めて整理すれば、面接やエントリーシートで説得力ある回答ができるでしょう。
ここでは、準備から整理までの流れを具体的に紹介します。
- インターンや説明会前に準備する
- テンプレートやレイアウトを決める
- わかる部分から情報を埋める
- 収集した情報を整理して書き込む
①インターンや説明会前に準備する
インターンや説明会に参加する前に、ノートを整えることが成果を高める第一歩です。情報を受け取る枠を作っておけば、気づきを逃さずに整理できます。
たとえば、企業概要や業界動向をあらかじめ書いておくと、当日に聞いた内容との差分がすぐに分かるでしょう。
準備不足だと重要な情報を聞き流してしまいがちですが、基本的な欄を作るだけでメモの精度は高まります。
事前準備には時間がかかると思うかもしれませんが、後の分析や志望動機づくりが楽になるため結果的に効率的です。
②テンプレートやレイアウトを決める
企業研究ノートを作るときに、迷いやすいのがレイアウトです。形式を決めないまま始めると、企業ごとにバラバラな記録になり、比較が難しくなってしまいます。
そのため、最初に基本のテンプレートを統一するのが効果的です。「企業概要」「事業内容」「強みと弱み」「選考情報」という4つの枠を設ければ、どの会社も同じ基準で整理できるでしょう。
統一した型でまとめることで見直しやすくなり、志望動機の作成にも役立ちます。完全に固定する必要はありませんが、自分に合った形式を最初に整えておくことが継続のカギです。
③わかる部分から情報を埋める
企業研究では「全部を完璧に調べないといけない」と考えがちですが、それは大きな負担になります。大事なのは、分かる部分から少しずつ埋めていくことです。
まずは、公式サイトや就活サイトから得られる基本情報を書き込み、空欄が残っても気にする必要はありません。むしろ、空欄があることで説明会や、OB訪問で質問すべき点が自然と見えてきます。
最初から完全を目指すと途中で挫折しやすいですが、段階的にノートを育てる意識を持てば長く活用が可能です。わかることを記録する習慣を続けることで、やがて企業同士の比較や自己分析にもつながるでしょう。
④収集した情報を整理して書き込む
情報を集めるだけでは、使えるノートになりません。大切なのは、自分の視点でまとめ直すことです。たとえば決算資料の数字を見たら「売上が伸びているが課題もある」と簡潔に整理します。
ニュース記事を読んだ場合は、事実と自分の考えを分けて記録してください。そうすることで理解が深まり、面接で自分の意見として話せるようになるでしょう。
また、色分けやマーカーを活用すれば要点が一目で分かります。情報量に圧倒されても、自分の言葉に置き換えて記録すれば知識は実践に活かせる知恵へと変わるのです。
企業研究ノートの作成ポイント

企業研究ノートは就活に欠かせない道具ですが、作ること自体が目的になると効果は半減します。ここでは、使いやすいノートを仕上げるための4つのポイントを紹介しましょう。
- 目的化せずに作成する
- 随時追記して更新する
- 表や図を活用し、視覚的に見やすい工夫をする
- 感想や気づきを書き残す
①目的化せずに作成する
企業研究ノートを作るときに注意したいのは、ノート作り自体に満足してしまうことです。本来の目的は選考で役立つ情報を整理することなのに、体裁ばかり整えてしまう学生は少なくありません。
大切なのは、見た目や情報量ではなく、自分が必要なときにすぐ取り出せる内容かどうかです。事業内容を簡潔にまとめ、自分の関心とどうつながるかを一言添えるだけで、十分活用できます。
時間をかけすぎると他の準備が遅れるため、完璧さより「使える状態」を目指してください。
②随時追記して更新する
企業研究ノートは作って終わりではなく、進めながら育てていくものです。説明会や面接で得た新しい情報をその都度書き加えると、鮮度の高い内容を維持できます。
最初から全てを埋める必要はなく、空欄があることで質問のきっかけにもなるでしょう。たとえば、社員の言葉や説明会での印象を記録すると、志望動機をより具体的にできます。
情報が古いままだと面接で食い違いが出るおそれもあるため、更新を習慣にしてください。こまめな追記が実践的な企業研究につながります。
③表や図を活用し、視覚的に見やすい工夫をする
企業研究ノートを見直す場面では、短い時間で情報を把握することが多いものです。文字だけを並べるより、表や図を取り入れることでぐっと理解がしやすくなります。
たとえば、給与や福利厚生などを比較するときは表にすると、違いが一目でわかるようになるでしょう。事業の特徴や強みをまとめるときには、図解やマトリクスを活用すると整理しやすいです。
視覚的にわかりやすい形にすれば、確認の負担も減り、効率的に準備ができます。結果として、企業研究ノートは単なる記録ではなく、戦略的に活用できるツールへと変わるのです。
④感想や気づきを書き残す
事実だけを並べたノートは、読み返しても自分の言葉で話しにくくなります。そこで重要なのが、感想や気づきを加えることです。
たとえば「社員の雰囲気が自分に合っていた」「将来性に少し不安を感じた」など主観的な記録を残すと、志望動機や逆質問の材料に変わります。
また、感想を書き添えることで記憶に残りやすくなり、面接でも自然に話せるようになるでしょう。情報のまとめだけでなく、自分の思考を反映させることが、説得力を持った企業研究ノートにつながるのです。
企業研究ノートに使えるおすすめのツール

企業研究を効率よく進めるには、自分に合ったツールを選ぶことが大切です。
ここでは、大学ノートやPCソフト、クラウドサービスといった代表的な方法を取り上げ、それぞれの特徴や使い方を解説します。学習スタイルや管理のしやすさを考えて選んでください。
- 大学ノートやルーズリーフ
- PCツール(ExcelやWordなど)
- クラウドツール(Googleドキュメント・スプレッドシート)
①大学ノートやルーズリーフ
手書きでまとめる方法は、記憶に残りやすい点が大きな利点です。志望企業ごとに1冊用意して、説明会や面接対策の情報を整理すれば見返しやすくなります。
ただし、検索や比較のしやすさではデジタルに劣るという点も。そのため、ページの端にインデックスを付けたり、色で要点を区切ったりすると便利です。
手を動かして書く作業は、思考の整理にも役立ちます。紙に残る安心感がほしい人や、自分の考えを深めながら記録したい人に適した方法といえるでしょう。
②PCツール(ExcelやWordなど)
ExcelやWordを使うと、情報を体系的にまとめられます。Excelでは企業名や業界、特徴を列ごとに整理でき、条件を絞り込んで比較するのも簡単です。
Wordは文章形式でまとめるのに適していて、企業理念の要約や自分の意見を記録しておけば面接の答えにも活かせます。効率的に作業したい人や、複数の企業を比較しながら分析したい人におすすめです。
情報の見やすさと編集のしやすさを両立できる点は、大きな魅力でしょう。
③クラウドツール(Googleドキュメント・スプレッドシート)
クラウドツールは、インターネット環境があればどこからでもアクセスできるのが最大の特徴。PCやスマートフォンから同じデータに触れられるので、外出先での更新も可能です。
自動保存されるためデータを失う心配がなく、安心して使えます。さらに、共有機能を使えば友人やキャリアセンターと共同でノートを活用できるのも利点です。
ただし、オフラインでは使いにくいこともあるため、事前準備は必要となります。柔軟に情報を整理したい人や、仲間と一緒に就活を進めたい人に向いています。
企業研究ノートの活用方法

企業研究ノートは、作って終わりではありません。自己分析や選考準備に結びつけることで、情報が成果へと変わります。
ここでは、強みの言語化から面接・ES・内定先の比較まで、実際に使える具体的な方法を紹介。日々の更新と振り返りを心がけてください。
- 自己分析と結びつけて強みを言語化する
- 面接でよく聞かれる質問への回答を準備する
- エントリーシート作成の材料にする
- 内定先の比較検討に使う
①自己分析と結びつけて強みを言語化する
企業研究ノートを自己分析とつなげ、自分の強みを具体的に表現するのに活用してみてください。企業の価値観や求める人物像と自分の経験を照らし合わせることで、説得力のある言葉に変わります。
たとえば「挑戦」を重視する会社なら、学業やサークルで工夫して成果を出した体験を数値や役割と一緒にまとめてみましょう。
企業のキーワードを左、自分の経験を右に並べるだけでも整理が進みます。最終的に「結論→根拠→成果」という流れで一文にすると、他社でも応用しやすいでしょう。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
②面接でよく聞かれる質問への回答を準備する
面接での想定問答を、企業ごとに調整しておくのもおすすめです。同じ質問でも、評価の基準は会社ごとに異なります。
「志望理由」「学生時代に力を入れたこと」「入社後に挑戦したいこと」などを見出しにして、ノートに企業情報を根拠として組み込みましょう。
新規事業に力を入れる会社なら、学内での企画立ち上げ経験を成果と学びと合わせて語ると伝わりやすいです。直前には、要点だけを色やマーカーで強調しておくと覚えやすくなります。
結論として、同じ骨子を持ちながら企業ごとに根拠を最適化することが有効でしょう。
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
③エントリーシート作成の材料にする
おすすめなのは、企業研究ノートをESの素材集として活用することです。企業の強みや事業計画と、自分の経験を線でつなぐと、独自性のある内容ができます。
たとえば海外展開を進める会社なら、留学や語学学習での成果を数字や行動と一緒に示し、どう貢献できるかを描くと効果的です。
文章は「主張→根拠→企業との接点→再主張」の流れでまとめると読みやすくなります。仕上げには固有名詞や数字を確認し、表現を簡潔に整えてください。これで説得力が高まるでしょう。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
④内定先の比較検討に使う
最終的な意思決定は、ノートを基準に比較すると納得感が生まれます。条件や印象が混ざると判断がぶれるため、同じ指標で比較することが大切です。
「ミッションへの共感度」「成長機会」「配属の現実」「報酬や勤務地」「働き方」などを5段階で採点し、短いコメントを添えておきましょう。
説明会やOB訪問で得た情報を参考に重みづけすると、判断の精度が上がります。最終的には合計点ではなく、自分が譲れない2つの項目で決めると後悔が少ないでしょう。
企業研究ノートに関するよくある質問

ここでは、就活生が企業研究ノートについてよく抱く疑問を取り上げ、役立つ知識や考え方を解説します。就活を効率よく進めたい方に向けて、具体的な答えをまとめました。
- 企業研究ノートは必ず作るべき?
- 紙とデジタルどちらがおすすめ?
- 途中で作成をやめてしまったらどうすればいい?
①企業研究ノートは必ず作るべき?
企業研究ノートは全員に必須ではありませんが、就活を計画的に進めたい方にとって大きな支えになります。理由は、企業理解を深め、志望動機や自己PRに説得力を加える材料を一つにまとめられるからです。
もし、ノートを作らずに選考へ進むと、話が表面的になり、根拠に乏しい印象を与えてしまう恐れがあります。
逆に、情報を一元化して整理しておくと、面接での受け答えやエントリーシートに自然な厚みが出るでしょう。もちろん、時間が限られている場合は簡単なメモでも構いません。
ただし、準備の質を高めたい方にとってノート作成は大きな武器になるはずです。つまり「必須ではないが、作った方が確実に有利」と考えるのが妥当でしょう。
②紙とデジタルどちらがおすすめ?
紙とデジタルには、それぞれ利点があります。紙のノートは手で書くことで記憶に残りやすく、持ち歩いてすぐに見返せるのが強みです。ただし、情報が増えると書き直しや整理が難しくなります。
一方デジタルは、検索やコピー、レイアウト変更が簡単で効率的に管理できるのが魅力です。しかし、画面越しでは定着しにくいと感じる人も少なくありません。
結論としては「覚える段階では紙」「整理や比較を重視する段階ではデジタル」と使い分けると良いでしょう。
状況に応じて切り替えることで、双方のメリットを活かせます。無理にどちらか一方に絞らず、柔軟に選んでください。
④途中で作成をやめてしまったらどうすればいい?
企業研究ノートを途中でやめてしまっても、問題はありません。重要なのは「就活に使える情報を残すこと」であり、完璧に仕上げることではないからです。
まずは中断した時点で残っている情報を見直し、不要な部分は整理しましょう。そのうえで志望度の高い企業に絞り込み、そこに集中して情報を追加すれば十分に活用できます。
むしろ全企業を網羅しようとして、負担を抱える方が効率が悪いといえるでしょう。再開するときは「選考直前に必要な答えが書かれているか」という視点で確認してください。
絞り込みと整理を行えば、止まっていたノートもすぐに実用的な形に戻せるでしょう。
就活で企業研究ノートを活かすために大切なこと
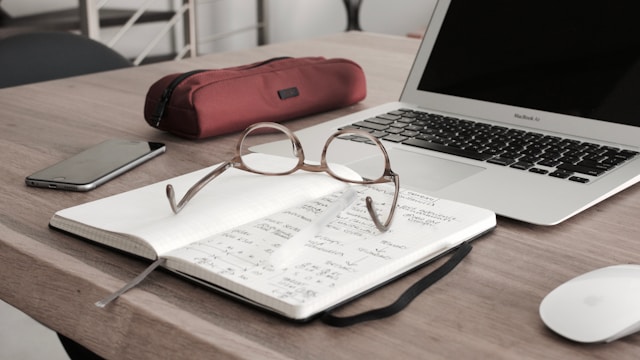
就活において企業研究ノートは、自分の理解を深め、選考を有利に進めるための重要なツールです。理由は、企業情報を整理することで志望動機や自己PRが一貫性を持ち、比較検討や面接対策に直結するから。
企業理解・業界理解・採用情報を体系的にまとめることで、自分の就活の軸を明確にでき、説得力のある回答が可能になります。
企業研究ノートの作り方は、テンプレートを決めて基本情報や所感を書き込み、随時更新することが効果的でしょう。
また、Excelやクラウドツールを活用すれば管理も容易です。結論として、企業研究ノートは就活の指針となり、自信を持って選考に臨むための基盤になるといえます。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










