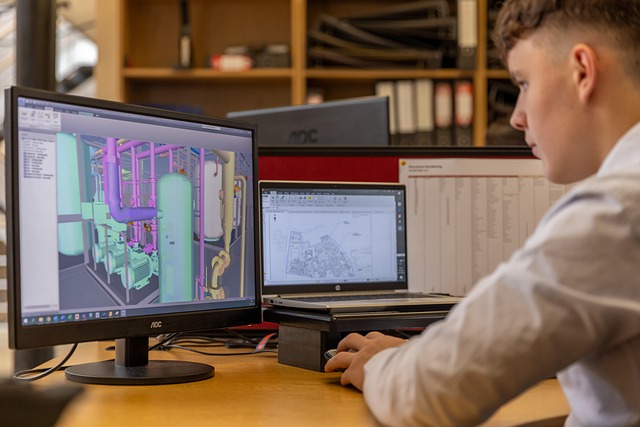ボランティア経験を就活で活かす方法|伝え方のコツと具体例を紹介
「ボランティア活動を就活でどう伝えれば評価されるのか分からない…」そんな悩みを持つ学生は少なくありません。社会貢献の一環として取り組んだ経験があっても、それを企業がどのように見ているのか、どこまでアピールになるのか気になるところですよね。
そこで本記事では、就活におけるボランティア経験の評価ポイントや、種類別の効果的な伝え方、具体的なアピール例文まで詳しく解説します。
自己PRをすぐに作れる便利アイテム
- 1自己PR自動作成ツール
- 最短3分!受かる自己PRを、AIが自動で作成
- 2ES自動作成ツール
- AIが【自己PR・志望動機・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 3強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みがわかります。
就活におけるボランティア経験は評価されるのか

就活でボランティア経験が評価されるかどうかは、多くの学生が気になる点でしょう。ここでは「経験があるだけでは不十分」という事実を踏まえ、どのように伝えると評価につながるのかを解説します。
就活でのボランティア経験は、評価されるか否かが最大の不安かもしれません。結論を言えば、経験そのものより「学びをどう得て、それを仕事でどう生かせるか」が重要でしょう。
なぜなら企業は活動の規模や種類ではなく、そこから見える人柄や強みを重視しているからです。
たとえば、地域清掃や学習支援といった身近な活動でも、主体的に取り組み工夫した姿勢を伝えれば十分評価されます。逆に、「ただ参加しただけ」と受け取られる伝え方では、印象が弱まってしまうでしょう。
つまり大事なのは活動内容ではなく、自分の言葉で学びを整理して話せるかどうかです。
準備段階で経験を振り返り、仕事との接点を意識してください。そうすれば、ボランティア経験は就活において確かなアピール材料となるはずです。
「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。
企業がボランティア経験から評価するポイント

就活でボランティア経験を伝えるとき、企業が注目しているのは活動の種類や規模ではありません。ここでは評価の視点を整理し、どんな点を意識して話せば効果的に伝わるのかを解説します。
- 主体性を発揮しているか
- コミュニケーション能力を培っているか
- 社会貢献や課題解決への姿勢を持っているか
- 協調性やリーダーシップを発揮できているか
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
①主体性を発揮しているか
ボランティア経験で、企業がまず見るのは主体性です。社会人には自ら考えて動く力が求められるため、受け身では評価が低くなってしまいます。
活動の中で自分から、工夫したことや改善した点を伝えると効果的です。たとえば清掃活動で人が足りない日に仲間を誘ったり、効率を上げる方法を提案した経験は良い例でしょう。
こうした行動があれば「自分から動ける人」と評価されます。つまり、どんな小さな活動でも主体性を示せれば強いアピール材料になるということです。
②コミュニケーション能力を培っているか
ボランティアは年代や背景の違う人と関わる機会が多く、そこで得られるのがコミュニケーション能力です。相手に合わせて話し方を変えることや、聞き役に回る柔軟さは社会に出ても役立ちます。
たとえば、高齢者施設で相手に伝わるように工夫した経験や、子ども支援で気持ちを引き出す工夫をした例は強いアピールになるでしょう。
重要なのは「どう関わり、相手からどんな反応を得たか」を具体的に語ることです。その点が伝われば、人と関わる力を持つ学生だと評価されます。
③社会貢献や課題解決への姿勢を持っているか
ボランティアを通じて、社会や地域の課題に関心を持ったかどうかも重要です。企業は責任感を持ち、改善に向けて動ける人材を求めています。
活動の中で課題に気づき、工夫して改善した経験があれば強みになるでしょう。例をあげるなら、フードバンクで仕分け作業を効率化したり、災害支援で現地の人に合わせたサポートを工夫した行動は良い例です。
こうした経験を語ることで「入社後も課題を見つけて解決できる人」と印象づけられます。
④協調性やリーダーシップを発揮できているか
ボランティア活動では、仲間と協力しながら進めることが多いため、協調性やリーダーシップをどう発揮したかも評価の対象となります。
仕事でも一人で成果を出すことは少なく、周囲を動かしながら結果を出す力が必要だからです。
たとえばイベント運営で意見がまとまらないときに調整役を務めたり、困難な場面でチームを支えたりした経験は有効でしょう。
大切なのは「自分だけで頑張った」ではなく「周囲と協力して成果を出した」と伝えることです。これにより、協力しながら結果を出せる人材として評価されます。
【種類別】アピールにつながるボランティア経験

ボランティア経験は、種類によって強調できるポイントが異なるものです。ここでは活動ごとの特徴を整理し、就活で効果的に伝える方法を紹介します。経験を自分の強みにどう結びつけるかを意識して見ていきましょう。
- 地域活動のボランティア経験
- 福祉・介護系のボランティア経験
- 災害支援ボランティア経験
- 海外ボランティア経験
- 教育・子ども支援系のボランティア経験
①地域活動のボランティア経験
地域活動のボランティアは身近で取り組みやすく、多くの学生が経験しています。だからこそ、どう差別化するかが大切です。
清掃活動や祭りの運営は一見単純に思われますが、そこで工夫した点や周囲と協力した姿勢を具体的に伝えると評価されます。
たとえば、人手不足のときに参加者を集めたり、効率的な進め方を提案したりしたエピソードは主体性を示せるでしょう。
地域活動は規模が小さくても、誠実に取り組んだ姿勢を示せれば十分にアピール可能です。結局のところ、活動の大小よりも学びや行動力をどう表現するかが評価の分かれ目になります。
②福祉・介護系のボランティア経験
福祉や介護に関わる活動は、思いやりや粘り強さを伝えられる経験です。高齢者施設での補助や障がいのある方への支援では、相手に合わせた工夫が欠かせません。
その姿勢は、企業からも高く評価されるでしょう。耳の遠い方に丁寧に話す工夫や、子どもの安心感を引き出す対応は、相手を尊重する力を示せます。
活動の中で感じた苦労や学んだことを、自分の言葉で整理することが大切です。特別な成果を示す必要はなく、相手の立場を理解して根気強く行動した経験こそが評価につながるでしょう。
③災害支援ボランティア経験
災害支援は、困難な状況で力を発揮した経験として注目されます。被災地での片付けや物資運搬は体力的にも厳しいですが、仲間と協力してやり抜いた姿勢は強いアピールになるでしょう。
企業は困難に直面した際の行動を重視するため、その体験を具体的に語ると効果的です。
もし、「不安を感じながらも仲間と協力して最後までやり遂げた」といったエピソードがあれば、粘り強さや協調性を示せます。
大切なのは規模を誇ることではなく、困難な場面で諦めずに行動した事実です。その姿勢こそが評価される要素でしょう。
④海外ボランティア経験
海外での活動は異文化に触れることで、柔軟性や対応力を示せる経験です。言葉や習慣の違いがある中で工夫して取り組んだことは、企業にとって魅力的に映ります。
たとえば、教育支援で言葉が通じにくい場面で、ジェスチャーや図を使って伝えた工夫は、適応力を示す好例でしょう。
重要なのは「特別な経験をした」と強調することではなく、「相手に合わせて工夫した」姿勢を伝えることです。
海外活動は珍しさよりも、異文化の中で培った対応力や協調性を具体的に語ることで評価されるでしょう。
⑤教育・子ども支援系のボランティア経験
子ども支援の活動は、責任感や根気強さを示せる機会です。学習支援や遊びを通して関わる中で、相手に合わせて対応を考える力が養われます。
理解度に応じて説明を変えたり、集中力が途切れないよう声をかけたりした経験は、柔軟な対応力を示せるでしょう。成果がすぐに出なくても、継続して取り組む姿勢が伝われば十分評価されます。
企業が求める「相手の立場に立ち、粘り強く支える力」を示すことができるため、この経験は大きなアピールポイントになるでしょう。
就活でボランティア経験を伝える場面とタイミング

ボランティア経験は就活でさまざまな場面に活かせます。うまく伝えるには、それぞれの場面に合わせて強調する内容を工夫することが大切です。ここでは、代表的な3つの場面を取り上げます。
- エントリーシートや履歴書の自己PR欄で伝える
- 面接での「学生時代に力を入れたこと」への回答に使う
- 志望動機や将来のビジョンと関連づけて伝える
①エントリーシートや履歴書の自己PR欄で伝える
エントリーシートや履歴書では、自分の強みを簡潔に示すことが求められます。ボランティア経験を記載する際は、活動の内容だけでなく、そこから得た成長や工夫を盛り込むと効果的でしょう。
単に「清掃活動に参加した」と書くだけでは印象に残りません。「清掃活動で参加者をまとめ、効率的に進める方法を提案した結果、予定より早く作業を終えられた」と具体的に記せば主体性が伝わります。
経験の大きさよりも、自分が果たした役割や工夫をどう発揮したかを強調してください。そうすることで、企業には「業務においても改善を進められる人材」と受け止めてもらえるはずです。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
②面接での「学生時代に力を入れたこと」への回答に使う
面接でよく問われるのが「学生時代に力を入れたこと」です。ここでボランティア経験を伝える場合は、取り組みの過程や困難をどう克服したかを示すことが大事でしょう。
たとえば、災害支援で体力的に厳しい作業を続けたとき、仲間と励まし合ってやり抜いた経験は粘り強さを裏付けます。面接官は成果よりも、そこに至る思考や行動を重視しているのです。
そのため「課題に直面したが工夫して解決した」という流れで話すと説得力が増すでしょう。活動を通じて学んだ価値観や姿勢を、自分の言葉で語れるかどうかが評価を左右します。
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
③志望動機や将来のビジョンと関連づけて伝える
志望動機や将来のビジョンに結びつけて語ると、ボランティア経験はより説得力を持ちます。
もし、教育系の企業を志望する場合なら「子ども支援の活動を通じて一人ひとりの成長を支える喜びを知り、教育の分野で力を発揮したいと考えた」と述べれば自然でしょう。
ここで重要なのは、経験そのものを語るのではなく、学びをどう志望先に活かせるかを示すことです。経験を動機の根拠として結びつければ、思いつきではなく実感に基づいた選択であると伝わります。
結果として、企業に「将来像が明確である」という印象を持ってもらえるでしょう。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
就活でボランティア経験を伝える際の書き方

ボランティア経験を就活で効果的に伝えるには、活動内容を並べるだけでは十分ではありません。採用担当者が知りたいのは「経験を通じて何を学び、それをどう仕事に活かすのか」という点です。
ここでは、具体的な伝え方のポイントを5つ紹介します。
- どのようなボランティア活動をしたのかを伝える
- 活動に参加した理由を伝える
- 具体的なエピソードを交えて伝える
- 活動を通じて得た学びを伝える
- 学んだことを仕事でどう活かすかを伝える
①どのようなボランティア活動をしたのかを伝える
最初に大切なのは、どのような活動をしたのかを具体的に示すことです。採用担当者は活動内容そのものよりも、そこから表れる姿勢や力を見ています。
そのため「地域の清掃活動に参加しました」ではなく、「毎週2時間、地域の清掃活動を継続して行い、仲間と協力しながら環境改善に取り組みました」と伝えると良いでしょう。
頻度や継続期間を示すことで、責任感や粘り強さを自然に表せます。曖昧な説明では伝わりにくいため、具体的に表現してください。
②活動に参加した理由を伝える
活動を始めた理由を話すと、あなたの価値観や行動の背景が見えてきます。「地域に貢献したいと思った」や「福祉分野の仕事に興味があった」など、率直で構いません。
さらに「自分の強みを試す場にしたかった」といった自己成長への意識を加えれば、主体性が際立つでしょう。逆に「誘われたから」という言い方は避け、ポジティブに言い換えることが大切です。
理由を丁寧に伝えることで、面接官に「目的を持って行動する人」という印象を残せます。
③具体的なエピソードを交えて伝える
説得力を持たせるには、実際に印象に残った出来事を交えて話すことが効果的です。「イベント運営で参加者が混乱した際に声をかけて誘導し、無事に進行できた」といったエピソードは行動力を伝えます。
成果や工夫も含めて語れば、採用担当者は強みをイメージしやすくなるでしょう。エピソードは1つに絞り、結論を明確にするのがポイントです。
複数を詰め込むと、焦点がぼやけてしまうため注意してください。具体的な経験を語ることが、自己PRの信頼性を高めます。
④活動を通じて得た学びを伝える
経験から得た学びを整理して伝えると、成長の証明になります。
「限られた時間で成果を出すには、事前準備と役割分担が大事だと気づいた」や「困っている人に寄り添う姿勢の大切さを実感した」といった形が良いでしょう。
学びは抽象的にせず、具体的な気づきとして表現することが重要です。そうすることで「経験を振り返り、自分の成長につなげられる人物」という評価につながります。
自分の言葉でまとめることは、面接で深掘りされたときにも役立つでしょう。
⑤学んだことを仕事でどう活かすかを伝える
最後に必要なのは、経験から得た学びを仕事にどう活かすかを結びつけることです。
「役割分担の大切さを学んだ経験を、チームで成果を上げる行動に活かしたい」と伝えれば、将来の働く姿を面接官が想像しやすくなります。
経験と仕事を関連づけることで、単なる思い出話ではなく、志望動機やキャリアの展望と一貫性が生まれるでしょう。自分の経験が社会でどう役立つかを示すことこそが、評価を高める最大のポイントです。
就活でボランティア経験をアピールする際の注意点

就活でボランティア経験を話すとき、単に「社会貢献をしました」と伝えるだけでは十分ではありません。採用担当者が知りたいのは、その経験をどう理解し、自分の成長につなげたかです。
ここでは、特に気をつけたい3つのポイントを紹介します。
- ビジネスとボランティアの違いを理解して伝える
- 専門用語や団体の理念ばかりに頼らないで伝える
- 団体ではなく自分自身の成長や考えを中心に伝える
①ビジネスとボランティアの違いを理解して伝える
ボランティアは社会貢献を目的としますが、企業は利益を追求する存在です。この違いを意識せずに語ると、現実的な感覚が欠けていると見られるかもしれません。
たとえば「誰かのためになればよい」という姿勢だけでは説得力が弱いでしょう。そこで「効率や成果を意識して行動した経験が、仕事でも役立つ」と結びつけると評価されやすくなります。
活動の価値観と企業の目的を区別しつつ、自分の経験を橋渡しとして語ることが大切です。違いを理解している姿勢は、柔軟で実践的な思考の証として信頼を得られるでしょう。
②専門用語や団体の理念ばかりに頼らないで伝える
ボランティア団体の理念や専門用語を強調しすぎると、聞き手に伝わりにくくなります。採用担当者は必ずしも同じ分野に詳しいわけではないため、専門的な説明が続くと理解が追いつきません。
大切なのは「誰にでもわかる言葉で、自分の行動や学びを説明すること」です。
そのため、「SDGsの目標に貢献しました」と言うよりも、「地域の子どもたちに学習支援を行い、勉強に前向きになる姿を見て自分も成長できた」と具体的に話すほうが効果的でしょう。
団体の理念を補足として触れるのは有効ですが、中心は自分の体験であることを忘れないでください。わかりやすい言葉は共感を生み、選考でも好印象を与えます。
③団体ではなく自分自身の成長や考えを中心に伝える
就活で評価されるのは団体の知名度や実績ではなく、そこで得た自分自身の成長です。「有名な団体に参加しました」と伝えるだけでは強みになりません。
むしろ「自分がどんな役割を担い、どのように工夫して成果を出したか」を話すことが求められます。
たとえば「募金活動をしました」ではなく、「通行人への声かけ方法を工夫し、最終的に寄付額を伸ばせた」と具体的に伝えると効果的でしょう。
採用担当者が知りたいのは、あなたの考え方や行動力です。団体を背景として示しつつ、自分の成長を中心に語ることで、独自性のある自己PRとなり、他の応募者との差別化につながるでしょう。
就活で使えるボランティア経験のアピール例文

就活で、ボランティア経験をどう伝えればいいのか悩む人は多いはずです。ここでは実際に使える例文を紹介し、活動ごとにどのようにアピールすれば効果的かをまとめています。
具体的な表現方法を参考にして、自分の経験に置き換えて活用してみましょう。
- 地域活動のボランティア経験を活かした例文
- 福祉・介護系のボランティア経験を活かした例文
- 災害支援ボランティア経験を活かした例文
- 海外ボランティア経験を活かした例文
- 教育・子ども支援系のボランティア経験を活かした例文
- ボランティアでリーダーシップを発揮した経験を活かした例文
- ボランティアを通じて社会問題への関心を示す例文
また、自己PRがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
自己PRが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。
【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
①地域活動のボランティア経験を活かした例文
地域活動に関するボランティア経験は、身近で取り組みやすい一方で多くの学生が経験しているため、差別化が重要になります。
ここでは、地域清掃活動を題材に、就活に活かせる形でまとめた例文を紹介しましょう。
《例文》
| 私には大学時代、地域の清掃活動に定期的に参加した経験があります。 最初は友人に誘われて軽い気持ちで始めましたが、続ける中で地域の方々と交流する機会が増え、自分の行動が周囲の環境や人の気持ちに良い影響を与えることを実感しました。 活動の中では、参加者が少ない日もありましたが、仲間を積極的に誘い、協力しながら取り組むことで継続的に活動を続けることができました。 この経験から、自ら動いて人を巻き込み、チームとして成果を出す大切さを学べたと思います。今後はこの行動力と協調性を活かし、社会に貢献できる仕事に取り組みたいと考えています。 |
《解説》
地域活動のエピソードは誰にでも身近だからこそ、行動の中で工夫した点や成長を示すことが差別化のカギです。具体的な行動と学びを結びつけて書くようにしましょう。
「自己PRの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己PRテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みを効果的にアピールする自己PRが作成できますよ。
②福祉・介護系のボランティア経験を活かした例文
福祉や介護のボランティア経験は、相手の立場を思いやる姿勢や粘り強さを示すことができるため、就活において高く評価されやすいテーマです。
ここでは、高齢者施設でのサポート活動を題材に、就活向けの表現に整えた例文を紹介します。
《例文》
| 私は、大学時代に高齢者施設で食事や移動の補助を行うボランティアに参加していました。 初めは思うように声かけができず戸惑いましたが、利用者の方の立場に立って耳を傾けることで、少しずつ信頼を得ることができました。 特に、耳の遠い方に対しては、相手の目を見ながらゆっくり話す工夫を続けた結果、感謝の言葉をいただいたときに、人との関わりの大切さを強く感じたことを覚えています。 この経験から、相手の状況に応じて柔軟に対応する力や、粘り強く関係を築く姿勢を身につけることができました。今後はこの学びを活かし、周囲との信頼関係を大切にしながら成果を出していきたいと考えています。 |
《解説》
福祉や介護の経験を書く際は、ただ活動内容を並べるのではなく、そこから得た人との関わり方や気づきを強調することが大切です。学んだ姿勢を将来の仕事にどう結びつけるかを意識してまとめましょう。
③災害支援ボランティア経験を活かした例文
災害支援のボランティア経験は、困難な状況における行動力や柔軟性を伝えることができる貴重なテーマです。
ここでは、大学生が参加しやすい被災地での片付け支援を題材に、就活で活かせる形にまとめた例文を紹介します。
《例文》
| 私は、大学時代に豪雨災害の被災地で片付け支援のボランティアに参加したことがあります。 初めて現地を訪れたときは被害の大きさに圧倒され、自分に何ができるのか不安でしたが、先輩方と協力しながら家屋の泥かきや物資運搬を行う中で、目の前の課題に全力で取り組む姿勢を学びました。 体力的に厳しい場面もありましたが、住民の方から「ありがとう」と声をかけていただいたとき、自分の小さな行動が人の役に立つことを実感しました。 この経験を通して、困難な状況でも諦めずに行動し続ける力や、仲間と協力して成果を出す重要性を身につけられたと思います。 今後はこの姿勢を仕事にも活かし、社会に貢献できる人材として成長したいと考えています。 |
《解説》
災害支援の経験はインパクトが強い分、事実を並べるだけではなく自分の学びをしっかり結びつけることが大切です。困難にどう向き合ったかを軸にまとめると説得力が高まります。
④海外ボランティア経験を活かした例文
海外でのボランティア活動は、異文化の中での挑戦や柔軟な対応力を示せる強いアピール材料です。ここでは、途上国での教育支援をテーマに、就活で活かせる表現をまとめた例文を紹介します。
《例文》
| 私には、大学2年の夏に東南アジアで教育支援のボランティアに参加した経験があります。 現地の子どもたちに簡単な英語や算数を教える活動でしたが、言語や文化の違いから思うように伝わらないことも多く、最初は戸惑いました。 そこで身ぶりや絵を活用したり、現地の先生に協力をお願いするなど工夫を重ねることで、子どもたちの笑顔や理解が広がっていくのを実感したのです。 この経験を通じて、相手の立場を考えながら柔軟に工夫する力や、多様な価値観を受け入れる姿勢を学びました。 今後はこの学びを活かし、チームやお客様との信頼関係を築きながら成果を出せる社会人になりたいと考えています。 |
《解説》
海外ボランティアの経験を書くときは、特別感を強調するよりも「工夫した行動」や「学んだ姿勢」を中心に伝えるのが効果的です。異文化対応の学びを仕事に結びつける視点を意識しましょう。
⑤教育・子ども支援系のボランティア経験を活かした例文
教育や子ども支援のボランティア経験は、責任感や相手に合わせた対応力を示せるテーマとして有効です。ここでは、学習支援を通じて学んだことを就活に活かせる形で紹介します。
《例文》
| 私は大学時代、地域の小学生を対象にした学習支援ボランティアに参加していました。 宿題を一緒に進める中で、最初は子どもたちの集中が続かず、指導に苦労しました。しかし一人ひとりの性格や理解度を観察し、声かけや教材を工夫することで、少しずつ成果が見えるようになったのです。 ある生徒が「先生のおかげで算数がわかるようになった」と言ってくれたとき、自分の関わりが相手の成長につながる喜びを実感しました。 この経験から、相手の状況に合わせた柔軟な対応力や、根気強くサポートを続ける姿勢の大切さを学びました。今後はこの経験を社会人生活でも活かし、チームやお客様に寄り添いながら成果を出していきたいと考えています。 |
《解説》
教育支援の経験を書くときは、子どもとの関わり方の工夫や成長の瞬間を具体的に示すことが大切です。学びを自分の強みとしてどう活かすかを意識してまとめましょう。
⑥ボランティアでリーダーシップを発揮した経験を活かした例文
リーダーシップを発揮したボランティア経験は、チームをまとめる力や課題解決への姿勢をアピールできます。ここでは、大学生がよく経験するイベント運営のボランティアを題材に例文を紹介しています。
《例文》
| 私は大学時代、地域イベントの運営ボランティアで10人のチームをまとめる役割を担いました。 初めはメンバー同士の意見がまとまらず、準備が停滞してしまいました。そこで全員の意見を聞いた上で、優先順位を整理して役割を分担し、進捗を共有する場を設けることにしたのです。 その結果、各自が責任を持って行動できるようになり、イベント当日も大きなトラブルなく運営を成功させることができました。 この経験を通して、チーム全体を見渡しながら調整し、メンバーの力を引き出すリーダーシップを学びました。今後はこの力を活かし、仕事においても周囲を巻き込みながら成果を出していきたいと考えています。 |
《解説》
リーダーシップをテーマにする場合は、「どのような課題があり、どう解決したのか」を明確に示すことが重要です。役割分担や調整力など、具体的な行動に焦点を当てて書きましょう。
⑦ボランティアを通じて社会問題への関心を示す例文
社会問題に関わるボランティア経験は、自分の関心の広がりや社会に対する姿勢を示せます。ここではフードバンク活動を例に、就活で活かせる形に整えた例文を紹介しましょう。
《例文》
| 私は大学時代、地域のフードバンク活動に参加し、余った食品を集めて生活に困っている家庭へ届ける活動を行いました。 最初は軽い気持ちで参加しましたが、支援を受けた方から直接「助かります」と言われたとき、食の問題が身近にあることを強く実感したのを覚えています。 その後は活動に積極的に関わり、食品を効率的に仕分ける方法を提案するなど、自分なりの工夫を意識しました。 この経験を通じて、社会問題に対して関心を持ち、解決に向けて小さな行動を積み重ねる姿勢を学びました。今後はこの姿勢を大切にし、社会の課題解決に貢献できる人材を目指したいと考えています。 |
《解説》
社会問題に関する経験を書くときは、活動を通じて気づいた課題と自分の行動を結びつけることが重要です。大げさに語るのではなく、身近な気づきや工夫を具体的に示すと伝わりやすくなります。
就活で避けたいボランティア経験のNG例
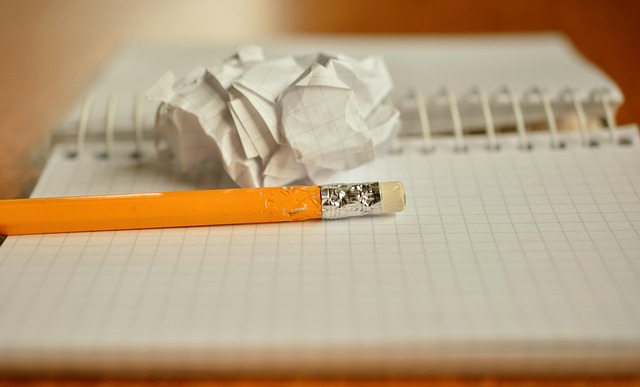
就活でボランティア経験を話すとき、伝え方を誤ると逆効果になることがあります。せっかくの経験も、面接官に誤解を与えてしまってはもったいないでしょう。ここでは、代表的なNG例を4つ紹介します。
- アピールのためだけに参加したと感じられる例
- 具体的な学びや成果が伝わらない例
- 活動内容の説明だけで終わってしまう例
- ボランティア経験を自慢しているように聞こえる例
①アピールのためだけに参加したと感じられる例
活動の目的が「就活のため」と受け取られてしまうと、誠実さに欠ける印象になります。企業が見ているのは経験そのものではなく、取り組む姿勢です。
「自己PRのネタ作りでした」と思われる伝え方は避けた方がよいでしょう。たとえば「就活に役立つと思い参加しました」と言うと、社会貢献の気持ちが薄れてしまいます。
その代わりに「地域の子どもたちの力になりたいと思い参加し、協調性を磨けました」と伝えると自然です。動機を話すときは、就活目線に偏らない工夫が必要になります。
②具体的な学びや成果が伝わらない例
参加した事実だけを強調しても、説得力が弱くなります。面接官が知りたいのは「何を学び、どのように成長したか」です。そこが伝わらなければ、経験の価値は半減してしまうでしょう。
「清掃活動をしました」だけでは報告にすぎません。これを「多くの人と協力し、役割分担の大切さを実感しました」と言い換えれば、学びを示せます。
活動自体よりも、そこから得た気づきを語ることが評価につながると覚えておきましょう。
③活動内容の説明だけで終わってしまう例
活動の概要説明で終わると、自分自身の印象が残りません。面接で評価されるのは「どんな経験をしたか」ではなく、「その経験でどう成長したか」です。
たとえば、「施設でお年寄りの話し相手になりました」と話すだけでは説明で終わってしまいます。
しかし「高齢者と接する中で相手の気持ちを尊重する大切さを学び、傾聴力が養われました」と伝えると、自分の強みに結びつけられるでしょう。活動内容は背景にとどめ、成長や考えを中心に話してください。
④ボランティア経験を自慢しているように聞こえる例
「立派な活動をしました」と強調しすぎると、自慢話に聞こえてしまいます。ボランティアは謙虚さが前提にあるため、過度な誇張は逆効果です。
たとえば「自分がいなければ活動は成り立たなかった」と話してしまうと、協調性を疑われるでしょう。
その代わりに「仲間と協力する中で、自分の役割を果たすことの大切さを学びました」と伝えると好印象を与えられます。大切なのは成果を誇示することではなく、そこから得た気づきを丁寧に語ることです。
就活でボランティア経験を効果的に伝えるために

就活においてボランティア経験は、主体性や協調性を示せる重要な材料です。企業は活動内容そのものではなく、そこで培った力や姿勢を評価します。
地域活動や福祉、災害支援、海外など、種類ごとに学びの切り口は異なるでしょう。大切なのは「なぜ参加したのか」「どんな経験を得たのか」「それを仕事でどう活かすのか」を具体的に語ることです。
自己PRや面接の回答で活用すれば説得力が増します。反対に、自慢や表面的な説明だけでは逆効果になりかねません。
就活でボランティア経験を効果的に伝えるには、経験をエピソードに落とし込み、自分自身の成長と未来への意欲を結びつけることがカギとなるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。