就職試験作文の書き方と構成|テーマ別例文と対策ポイント
「就職試験の作文って、どんなテーマが出るのか不安……」
そう感じる学生は多いものです。限られた時間と文字数の中で、自分の考えや経験を的確に表現するのは決して簡単ではありません。
特に「就職 試験 作文 テーマ」は、企業が応募者の人柄や価値観を見極める大事な要素です。
そこで本記事では、就職試験の作文でよく出題されるテーマや基本構成、効果的な書き方のポイントを、例文とともにわかりやすく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
就職試験の作文とは

就職試験の作文は、採用試験の一環として行われる文章作成課題のことです。企業はこの作文を通じて、応募者の思考力や文章構成力、表現力、さらに価値観や人柄を判断します。
テーマは社会問題や自己分析、志望動機などさまざまで、制限時間内に論理的で分かりやすい文章を書く必要があるのです。
そのため、あらかじめ多様なテーマで練習し、構成の型を身につけておくことが大切です。また、就職試験の作文は一発勝負の場面が多く、短時間で思考をまとめる力も求められます。
日頃から新聞やニュースをもとに、自分の意見を短時間でまとめる練習をしておくと、本番でも落ち着いて対応できるはずです。準備と意識次第で、作文は強力なアピールの場になります。
企業が就職試験の作文で評価するポイント

就職試験の作文は、単に文章力だけでなく、応募者の人柄や価値観、さらに将来への意欲までを知る大切な機会です。
企業は限られた文字数の中から、その人がどんな人物で、どのように働くのかを推測します。ここでは、企業が特に注目している評価ポイントを整理し、それぞれの特徴や対策を解説しました。
- 応募者の人柄や価値観を読み取る
- 文章力や構成力を評価する
- 仕事への意欲や将来のビジョンを確認する
- 論理性や説得力を見極める
- コミュニケーション力や協調性を判断する
①応募者の人柄や価値観を読み取る
企業は作文を通じて、応募者の考え方や人柄を探ります。成績や資格では分からない部分を知るため、エピソードや経験談から価値観を判断するのです。
困難をどう乗り越えたかや、他者との関わり方は、その人の姿勢をよく表します。読み手に共感を与える内容を盛り込み、誠実さと自己理解の深さを示すことが重要でしょう。
事実を盛りすぎると不自然になり、かえって評価を下げかねません。一貫した価値観が文章全体から伝わる構成にしてください。
②文章力や構成力を評価する
作文では、文法や語彙の正確さだけでなく、論理的な展開や読みやすさも重視されます。企業は、仕事での報告書や提案書作成にも通じるスキルとして文章力を見るのです。
冒頭でテーマを明確に提示し、根拠や具体例を挙げながら結論へ導く構成は説得力を高めます。段落ごとに役割を持たせると理解しやすくなるでしょう。
長文でも同じ語尾や表現を繰り返さない工夫が必要です。最後まで集中して読んでもらえる文章こそ、高評価につながります。
③仕事への意欲や将来のビジョンを確認する
作文は志望動機や将来像を具体的に伝える場でもあります。企業は、応募者がどれほど仕事に前向きで、長期的な成長を見据えているかを見ているのです。
将来どんな役割を果たしたいか、入社後にどんなスキルを磨きたいかを明確に述べると効果的。抽象的な夢だけでは説得力が弱くなるため、過去の経験と結びつけて説明してください。
例えば、学生時代のプロジェクト経験から得た学びを、入社後にどう活かすかを具体的に示すと、現実味のある将来像として評価されやすくなります。
④論理性や説得力を見極める
企業は作文から、物事を論理的に説明できるかを確認します。論理性は、結論を支える根拠や事例の適切さによって判断されるでしょう。
主張と理由がずれていると説得力を失うので、常に「なぜそう考えるのか」を明確にすることが大切です。反対意見や異なる視点を意識的に取り入れると、バランスの取れた文章になります。
これは実務でのプレゼンや交渉にも直結するスキルです。短時間で書く試験では、書き始める前に構成メモを作る習慣をつけておきましょう。
⑤コミュニケーション力や協調性を判断する
作文からは、相手に配慮した表現や協調性の姿勢も見えてきます。自分の意見を述べつつ、他者の立場を尊重する書き方は、円滑な人間関係を築ける人物像として好印象です。
仕事はチームで進める場面が多いため、この視点は特に重要といえます。協調性を示すには、仲間と課題を解決した事例や、相手の意見を受け入れて成果につなげた経験を盛り込むと効果的です。
読み手が「この人と働きたい」と感じる文章は、採用へのプラス材料になります。
就職試験の作文の基本構成
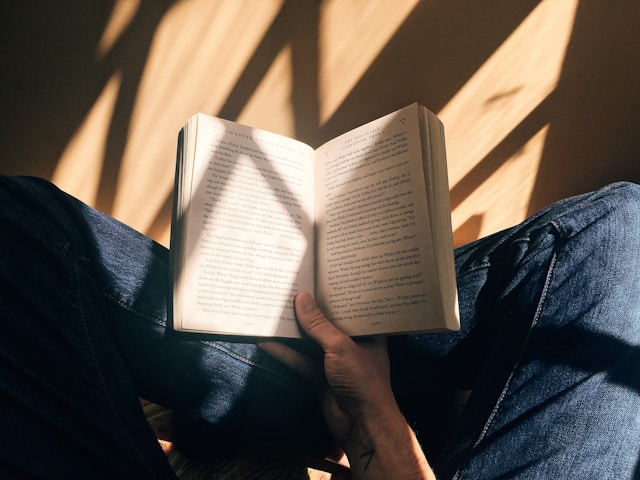
就職試験の作文は、限られた時間内で自分の考えをわかりやすく伝える力が求められます。そのため、序論・本論・結論の流れを押さえ、読み手が理解しやすい形にまとめることが大切です。
ここでは、それぞれのパートで意識すべきポイントを整理します。
- 序論:テーマや背景を明確にする
- 本論:具体的な事例や経験を示す
- 結論:主張や学びをまとめる
①序論:テーマや背景を明確にする
序論は作文全体の入口で、読み手にテーマの方向性を伝える重要な役割を持ちます。最初にテーマの概要や背景を簡潔に示すことで、読み手は内容をすぐに理解できるでしょう。
たとえば「私が成長を感じた経験」というテーマなら、その経験がいつ・どこで・どんな状況で起きたのかを冒頭で示すと効果的です。
注意点として、序論が長くなりすぎると本題に入る前に集中力が切れるおそれがあります。文章量は全体の1〜2割にとどめ、要点を押さえてください。
また、テーマと関係の薄い情報を入れると焦点がぼやけるため、本論につながる内容だけを選びましょう。序論をしっかり整えることで、文章全体の印象がぐっと良くなります。
②本論:具体的な事例や経験を示す
本論は作文の中心で、テーマに沿った事例や経験を具体的に描く部分です。事実を並べるだけでなく、「なぜその出来事が重要だったのか」という理由や、自分がそこでどんな行動を取ったのかまで書きましょう。
たとえば、アルバイトの接客経験を取り上げる場合、「混雑時の対応で顧客満足度を高めた」という事実に加え、そのときの判断や工夫、得られた学びを示すと説得力が増します。
話の順序が前後すると読み手が混乱するため、時系列や因果関係に沿って整理することが大切です。数字や固有名詞を適度に使うと、文章に具体性と信頼感が生まれます。
本論が薄いと全体の評価が下がるため、この部分には十分な時間と工夫をかけるべきです。
③結論:主張や学びをまとめる
結論は作文を締めくくる部分で、読み手に「この人は何を伝えたかったのか」を明確に残す役割があります。本論で述べた内容を踏まえ、自分の考えや成長した点を簡潔にまとめてください。
ここでは、単に事実を繰り返すのではなく、「この経験を通じて〜を学び、今後は〜に生かしたい」というように、未来への意欲を盛り込むと良いでしょう。
結論が長すぎると要点があいまいになるため、全体の1〜2割程度に収めることを意識してください。
読み終えたときに「なるほど、この人はこういう価値観を持っている」と理解してもらえる結論を目指すと、採用担当者の印象に残る作文になります。
就職試験の作文を書く際のポイント

就職試験の作文では、文章力だけでなく、テーマ理解や論理構成、表現の正確さまで幅広く見られます。
限られた時間で読み手に伝わる文章を書くためには、基本的な書き方のルールと実践的な工夫が必要です。ここでは、特に重要な5つのポイントを解説します。
- テーマや設問の意図を正しく理解する
- PREP法や双括型で論理的に展開する
- タイトルと内容を一致させる
- 一文一義で簡潔に表現する
- 指定文字数の範囲内で書く
①テーマや設問の意図を正しく理解する
作文で最も重要なのは、テーマや設問が何を求めているのかを正しく把握することです。意図を誤解したまま書くと、内容がずれて評価が下がってしまいます。
設問に含まれるキーワードや条件をしっかり読み取り、自分が答えるべき範囲を明確にしましょう。
例えば「学生時代に頑張ったこと」というテーマでも、「結果」より「過程」に重点を置く設問があります。
こうした違いを見抜くために、書き始める前に設問を要約し、自分の理解が正しいかを確認してください。
②PREP法や双括型で論理的に展開する
分かりやすく説得力のある文章にするには構成が欠かせません。PREP法(結論→理由→具体例→結論)や双括型(結論で始め結論で終わる構成)を使えば、論理の流れが明確になるのでオススメです。
例えば「協調性が強み」という結論を冒頭で述べ、その理由や具体的なエピソードを展開し、最後に再び結論を示すと一貫性が生まれます。
本番では緊張から内容が散漫になりがちですが、あらかじめ構成の型を覚えておけば落ち着いて書けるでしょう。
③タイトルと内容を一致させる
タイトルは内容の方向性を示す看板のような役割を持ちます。本文とずれていると、何を伝えたいのか分からない印象を与えてしまうでしょう。
例えばタイトルが「挑戦から学んだこと」なのに、本文の大半が失敗談で終われば整合性がなくなります。
タイトルを決めるときは、本文の主張やエピソードと一致しているかを意識し、読み終えたあとに納得できる構成にしてください。
④一文一義で簡潔に表現する
試験の作文では、長く複雑な文章は理解を妨げます。一文には1つの意味だけを盛り込み、短くまとめることが基本です。接続詞を多用して情報を詰め込みすぎると、文が冗長になり説得力も下がります。
短い文でも必要な情報と感情をしっかり盛り込めば十分に印象を与えられるでしょう。同じ語尾や表現を続けないよう、語尾のバリエーションにも注意してください。
⑤指定文字数の範囲内で書く
文字数制限を守ることは、与えられた条件の中で適切に対応できるかを判断する材料になります。オーバーや不足は減点されやすく、大幅な超過は「指示を守れない」と見なされるでしょう。
書く前に全体の配分を決め、結論・理由・具体例のそれぞれにおおよその文字数を割り振ると安定します。書き終えたら必ず文字数を確認し、必要なら調整してください。
無理に削ったり足したりせず、質を保ちながら範囲に収めることが大切です。
就職試験の作文でよく出題されるテーマ

就職試験の作文では、企業が応募者の価値観や考え方を知るために幅広いテーマを設定します。
大きく分けると、未来・過去・社会・仕事・自己PRに関する内容が多く、それぞれに適した書き方や注意点があるのです。ここでは、出題の傾向と対策のヒントを紹介します。
- 未来に関するテーマ
- 過去に関するテーマ
- 社会に関するテーマ
- 仕事に関するテーマ
- 自己PRに関連するテーマ
①未来に関するテーマ
未来に関するテーマは、将来の目標や理想像、社会や業界の展望などが問われます。企業は、応募者がどのようなビジョンを持ち、成長意欲や計画性を備えているかを見ているのです。
書くときは、まず自分の理想や目標を明確にし、その理由や背景を具体的に説明してください。さらに、それを実現するための行動計画を示すと説得力が高まります。
抽象的な理想だけでは評価が下がるため、必ず事例や経験と結びつけましょう。将来像は現実味と挑戦性の両方を意識すると、読み手に好印象を与えられるはずです。
②過去に関するテーマ
過去に関するテーマでは、これまでの経験から得た学びや成長の過程が問われます。企業は、困難をどう乗り越え、どのように行動して改善したかに注目しているのです。
出来事の背景や状況を簡潔に示し、その経験から得た学びを具体的に伝えてください。感情的な表現だけに偏らず、事実と行動を明確に記すことで説得力が増します。
また、過去の話をする際は、その経験が今後どのように活かせるのかまで結びつけることが重要です。そうすることで、成長意欲や適応力もアピールできます。
③社会に関するテーマ
社会に関するテーマは、時事問題や社会課題について意見を述べる形式が多く見られます。企業は、応募者が社会の動きを理解し、物事を多角的に考えられるかを確認しているのです。
主張を述べる際は、現状の説明、課題の指摘、解決策の提示という順序でまとめると読みやすくなります。意見は一方的にならないよう、反対意見や別の視点にも触れると論理性が高まるでしょう。
普段からニュースや社会情勢に目を向け、自分の意見を整理する習慣をつけておくと、本番でも落ち着いて書けるはずです。
④仕事に関するテーマ
仕事に関するテーマは、働く姿勢や職業観、理想の職場環境などについて問われます。企業は、応募者がどのように仕事へ向き合い、組織にどう貢献できるかを知りたいと考えているでしょう。
自分の考えを述べる際は、抽象的な表現だけでなく、過去の経験や身近な事例を交えてください。また、応募先の企業研究を行い、方針や文化に沿った内容にすることも大切です。
働く姿勢を語る中で、自分の強みや価値観が自然と伝わるよう意識しましょう。
⑤自己PRに関連するテーマ
自己PRに関連するテーマは、自分の強みや特性を具体的に伝える内容です。企業は、その強みがどのように組織で活かせるのかを知ろうとします。
単なる自己評価ではなく、根拠となる経験や成果を提示してください。たとえば、チームでの成功や課題解決の事例など、行動と結果を結びつけると効果的です。
さらに、強みの裏にある努力や改善の過程を加えることで、より人間味のある文章になります。読む人が「この人と一緒に働きたい」と感じる内容を目指しましょう。
就職試験の作文例文
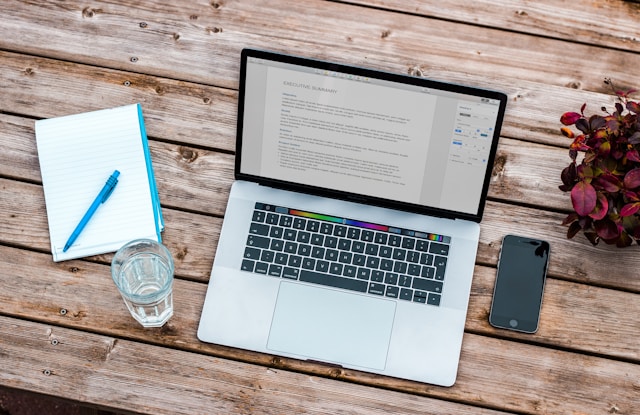
就職試験の作文では、テーマごとにどのような書き方をすればよいのか具体的に知りたい方も多いでしょう。
ここでは、実際の試験を想定した例文をテーマ別に紹介し、構成や表現の参考になるポイントを示します。
①未来に関するテーマの例文
ここでは、将来の目標や進みたい道をテーマにした作文例を紹介します。企業が知りたいのは、あなたがどのようなビジョンを持ち、その実現に向けてどのような行動を考えているかです。
| 私の将来の目標は、地域の人々に役立つ企画をつくる仕事に携わることです。大学2年のとき、地元商店街のイベント運営を手伝った経験があります。 そのとき、参加者の笑顔を間近で見て、人が集まる場を作ることの魅力を感じました。さらに、SNSを活用して告知を行い、前年より来場者数を増やせたことは大きな達成感があったのです。 将来はこの経験を活かし、地域活性化に貢献できる企画を提案できる人材になりたいと考えています。 そのために、残りの学生生活ではマーケティングや広報の知識を学び、インターンシップにも積極的に参加するつもりです。 |
このテーマでは、将来の目標を明確にし、そのきっかけや根拠を具体的に示すことが重要です。経験と結びつけることで、説得力が増し、読み手の印象に残りやすくなります。
②過去に関するテーマの例文
ここでは、自分の過去の経験から学んだことをテーマにした作文例を紹介します。企業は、その経験を通じてどのように成長し、今後にどう活かすかを知りたいと考えています。
| 私は大学1年のとき、飲食店でのアルバイトを始めました。最初は接客のスピードが遅く、先輩やお客様に迷惑をかけることも多くあったのです。 しかし、改善のために先輩の動きを観察し、注文を覚えるコツや効率的な動線を工夫したことで、徐々に業務をスムーズにこなせるようになりました。 3か月後には新人スタッフの指導を任されるまでになり、自分の成長を実感。この経験を通じて、課題に対して行動を重ねれば必ず改善できることを学びました。 今後もこの姿勢を忘れず、仕事に取り組んでいきたいです。 |
過去のテーマでは、状況・課題・行動・結果の順でまとめるとわかりやすくなります。成長の過程を具体的に描くことで、企業に努力と向上心を印象づけられるでしょう。
③社会に関するテーマの例文
ここでは、社会問題や身近な出来事を通して感じたことをテーマにした作文例を紹介します。企業は、あなたが社会をどのように捉え、そこから何を考え行動できる人なのかを見ています。
| 私は大学の授業で、食品ロス問題について調べる機会がありました。スーパーや飲食店で大量に廃棄される食材の現状を知り、身近な生活にも関わる深刻な課題だと感じたのです。 そこで、まず自分にできることとして、アルバイト先のカフェで賞味期限が近い食材を使ったメニューを提案しました。その結果、廃棄量を減らすだけでなく、お客様からも新メニューが好評。 この経験から、社会課題は小さな行動からでも解決に近づけることを学びました。将来はこの意識を持ち続け、仕事の中でも社会に貢献できる取り組みを実践していきたいです。 |
社会テーマでは、課題を知ったきっかけから具体的な行動、得られた成果までを明確に書くことが大切です。小さな行動でも成果を示すと、主体性と問題意識が伝わります。
④仕事に関するテーマの例文
ここでは、働く姿勢や職業観に関する作文例を紹介します。企業は、あなたがどのような考え方で仕事に取り組むのか、組織でどのように貢献できるのかを知りたいと考えているでしょう。
| 私はアルバイトで学んだ「責任感」を仕事にも活かしたいと考えています。大学2年のとき、レストランでアルバイトをしていた際、開店前の仕込みを任されたことがありました。 最初は時間内に作業を終えられず、他のスタッフに負担をかけてしまったのです。そこで、前日のうちに作業手順をメモし、効率的に動けるように工夫しました。 その結果、時間内に準備を終えられるようになり、店長からも信頼される存在になれたと思っています。 この経験を通して、任された仕事は最後までやり遂げる責任感と、改善のための工夫が大切だと学びました。将来もこの姿勢を持ち続け、職場に貢献していきたいです。 |
仕事に関するテーマでは、経験から得た価値観や学びを明確に示すことが重要です。行動の工夫や成果を具体的に書くことで、実行力と信頼性が伝わります。
⑤自己PRに関するテーマの例文
ここでは、自分の強みや長所を活かした経験をテーマにした作文例を紹介します。企業は、あなたの性格や行動特性が仕事でどのように活かせるかを知ろうとしているのです。
| 私は行動力の高さを強みとしています。大学でのゼミ活動では、地域活性化イベントの企画を担当。初めは参加者集めが思うように進まず、計画通りの人数に届かない可能性がありました。 そこで、地域の商店街やカフェに直接出向き、ポスター掲示をお願いするなど積極的に行動したのです。その結果、予定を上回る来場者が集まり、イベントは大成功に終わりました。 この経験から、課題に直面したときこそ行動を起こすことで状況を変えられると学べたと思っています。今後もこの行動力を活かし、職場で新しい価値を生み出せる人材になりたいです。 |
自己PRのテーマでは、自分の強みを裏付ける具体的なエピソードを書くことが重要です。課題解決の過程を明確にすることで、説得力が高まります。
就職試験の作文を書く際の注意点
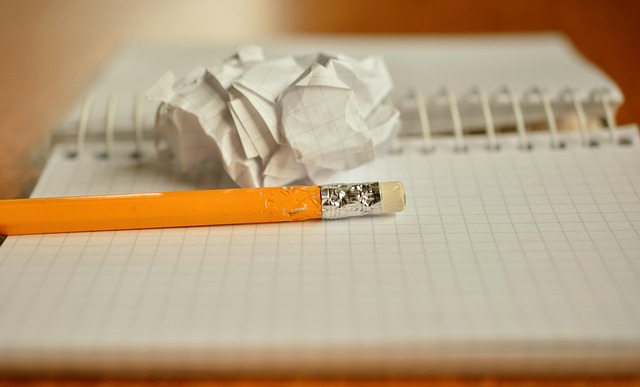
就職試験の作文は、内容の質だけでなく、書き方や形式面も評価されます。丁寧で読みやすい字、正しい文字数、誤字脱字のない文章は、社会人としての基本姿勢を示す要素です。
ここでは、見落としやすい5つの注意点について解説します。
- 丁寧な字で読みやすく書く
- 文字数の上限・下限を守る
- 文体や語尾を統一する
- 誤字脱字やねじれ文をなくす
- 段落分けやレイアウトを整える
①丁寧な字で読みやすく書く
どれほど内容が良くても、字が乱れていると読み手に負担を与え、印象を損ねます。試験官は短時間で多くの作文を読むため、丁寧で見やすい字はそれだけで評価を高める要素です。
文字の大きさや間隔をそろえ、乱雑にならないよう心がけてください。普段からノートやメモをきれいに書く習慣を持てば、本番でも安定した字が書けるでしょう。
急いで書くと字形が崩れやすいため、時間配分を工夫して丁寧さを保つことが大切です。
②文字数の上限・下限を守る
文字数制限は、与えられた条件でまとめる力を測る基準です。大幅な超過や不足は減点対象になりやすく、「指示を守れない人」という印象を与えるおそれがあります。
書く前に全体の配分を決め、序論・本論・結論のバランスを意識しましょう。書き終えたら必ず文字数を確認し、必要に応じて調整してください。
ただし、無理な加筆や削除で内容が不自然にならないよう注意が必要です。
③文体や語尾を統一する
文章全体の読みやすさや一貫性は、文体と語尾の統一で大きく変わります。敬体(です・ます調)と常体(だ・である調)が混ざると、文章が不安定になり説得力も弱まるでしょう。
試験では基本的に敬体で統一するのが無難です。また、語尾が同じ形で続くと単調に感じられるため、「〜です」「〜ます」だけでなく、「〜でしょう」「〜ません」など自然なバリエーションを使ってください。
こうすることで、文章にリズムが生まれます。
④誤字脱字やねじれ文をなくす
誤字脱字や文の構造が不自然な「ねじれ文」は、読み手にストレスを与えます。こうしたミスは注意力の欠如と受け取られ、評価を下げる原因になりやすいです。
特に漢字の誤用や送り仮名の間違いは目立つため、普段から正しい表記を意識しましょう。
試験の最後に見直し時間を確保し、一度声に出して読んでみると、不自然な部分に気づきやすくなります。
⑤段落分けやレイアウトを整える
適切な段落分けと整ったレイアウトだと、文章がとても読みやすいです。内容が変わるタイミングで段落を切ると、話の展開が分かりやすくなります。
段落の冒頭は1字下げを守り、行間や字間も詰まりすぎないようにしてください。整った見た目の文章は丁寧な印象を与え、内容の説得力を高める効果があります。
日頃から見た目の整った文章を書く習慣をつけておくと、本番での完成度が上がるでしょう。
作文が苦手な人のための対策方法

就職試験の作文は、日ごろ文章を書く機会が少ない人にとって難しく感じられることがあります。
しかし、いくつかの方法を継続して実践すれば、語彙力や構成力が高まり、本番でも落ち着いて書けるようになるでしょう。ここでは、効果的な対策を5つ紹介します。
- 新聞や本を読んで語彙力と表現力を養う
- 過去の出題テーマで繰り返し練習する
- 書いた作文を第三者に添削してもらう
- 制限時間を設定して書く練習をする
- キャリアセンターや就活サービスを活用する
①新聞や本を読んで語彙力と表現力を養う
語彙力や表現力を伸ばすには、新聞や本を日常的に読む習慣が有効です。新聞では社会問題や時事情報に触れられ、作文で時事テーマが出たときに役立ちます。
本では多様な文章表現や構造を学べるため、書き方の幅が広がるでしょう。読みながら気になった言葉や表現をメモし、自分の文章に取り入れてください。
また、読むだけでなく要約や意見を書く練習をすると、理解と定着がより深まります。続けることで自然に文章力が高まっていきます。
②過去の出題テーマで繰り返し練習する
実際の試験形式に慣れるためには、過去の出題テーマを使った練習が効果的です。本番と同じ条件で書くことで、時間配分や構成の作り方を身につけられます。
テーマはインターネットや就活本、大学の資料などで入手可能です。同じテーマを複数回書くと、表現の改善や内容の深まりが実感できます。
最初から完璧を目指さず、まずは書く回数を重ねることが上達への近道です。
③書いた作文を第三者に添削してもらう
自分だけで書いていると、誤字や文章の癖に気づきにくいものです。信頼できる友人や先生、家族などに読んでもらい、率直な意見を聞いてください。
第三者の視点からの指摘は、改善点を明確にしてくれます。特に論理の飛躍や説明不足といった課題は、自分では見落としがちです。添削後は指摘を反映させ、同じミスを繰り返さないよう注意しましょう。
④制限時間を設定して書く練習をする
就職試験では限られた時間内で書き上げる必要があります。普段から時間を計って練習すると、本番でも焦らず対応できるでしょう。
30分や40分などの制限時間を決め、テーマ決定から完成までを通して練習してください。時間が足りなくなる場合は、構想段階で要点を絞る練習が有効です。
制限時間を意識した訓練は、集中力や判断力の向上にもつながります。
⑤キャリアセンターや就活サービスを活用する
大学のキャリアセンターやオンラインの就活サービスでは、作文対策の支援を受けられることがあります。模擬試験や添削、講座などを利用すれば、独学より効率的に力を伸ばせるのです。
他の就活生と比較することで、自分の課題や強みも客観的に把握できるでしょう。無料で使えるサービスも多いため、積極的に活用することをおすすめします。
就職試験の作文対策の最終指針

就職試験の作文は、テーマの意図を正しく理解し、論理的で読みやすい文章にまとめることが重要です。企業は文章の中から人柄や価値観、将来への意欲を見極めます。
そのため、序論・本論・結論の基本構成を押さえ、PREP法や双括型を活用すると説得力が高まるでしょう。また、よく出題されるテーマを事前に把握し、例文や過去問で練習することが実力向上の近道です。
さらに、丁寧な字や文字数の遵守、誤字脱字の防止など形式面の配慮も欠かせません。苦手意識がある場合は、語彙力の強化や添削指導の活用で改善できます。
計画的な準備と実践練習こそが、就職試験の作文で高評価を得るために大切でしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。









