インテリア業界に就職するには?向いている人や企業の選び方
「インテリアが好きだから将来はこの業界で働きたい!」そんな思いを抱いている就活生は多いでしょう。
しかし一口にインテリア業界といっても、家具メーカーや雑貨メーカー、住宅設備メーカーなど多くの分野に分かれ、企業ごとに求められるスキルや人材像も異なります。
さらに、トレンドや生活様式の変化、サステナブルな商品への注目など、市場環境も常に動いています。
本記事では、インテリア業界の仕組みや主な分類、最新動向から就職に向いている人の特徴、志望動機や自己PRの書き方、選考で有利になるコツまでをわかりやすく解説します。
インテリア業界を目指す就活生が、理想の企業と出会い、納得のいく就活ができるようサポートしていきます。
インテリア業界とは

インテリア業界とは、住宅やオフィス、商業施設などの空間を美しく整え、快適に過ごせるようにする商品やサービスを提供する分野です。
たとえば、家具や照明、カーテン、壁紙といった製品を作ったり売ったりする会社のほか、空間の設計やコーディネートを行うデザイン会社、実際に施工を行う企業など、さまざまな業種が関わっています。
この業界の大きな特徴は、「暮らす人・使う人の心地よさ」を最優先に考える点にあるのです。
就活生にとっては、デザインに関心がある方や、人の暮らしに寄り添う仕事がしたい方にぴったりの業界です。
とはいえ、一般消費者向けだけでなく企業向けの取引も多く、業界内での役割も多岐にわたるため、仕組みや関係性を事前に理解しておかないと、自分に合った職種が見つけづらくなるかもしれません。
就職活動でスムーズに志望先を見つけるためにも、インテリア業界全体の構造をつかんでおくことが大切です。
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
インテリア業界の仕組み

インテリア業界は、家具・照明・ファブリック・住宅設備など、幅広い商品やサービスが関係する分野です。
ここでは、就職活動を始めた学生にも理解しやすいように、業界の基本的な仕組みをわかりやすく解説します。まず理解しておきたいのは、製品がつくられてから消費者の手に届くまでの流れです。
たとえば家具であれば、メーカーが企画・設計・製造を行い、その商品は問屋や商社を通じて小売店やインテリアショップに運ばれます。
また、インテリア業界には、一般消費者を対象とした「BtoC」と、法人や事業者を相手にする「BtoB」のビジネスがあります。
家庭用ソファを販売する会社と、オフィス空間全体をデザイン・施工する会社では、業務の内容や必要なスキルがまったく異なるでしょう。
なんとなくのイメージだけで選ぶのではなく、業務の流れや関わる人々の役割を具体的にイメージしておくと、納得のいく就活につながるはずです。
適職診断であなたにぴったりな職種を見つけよう!
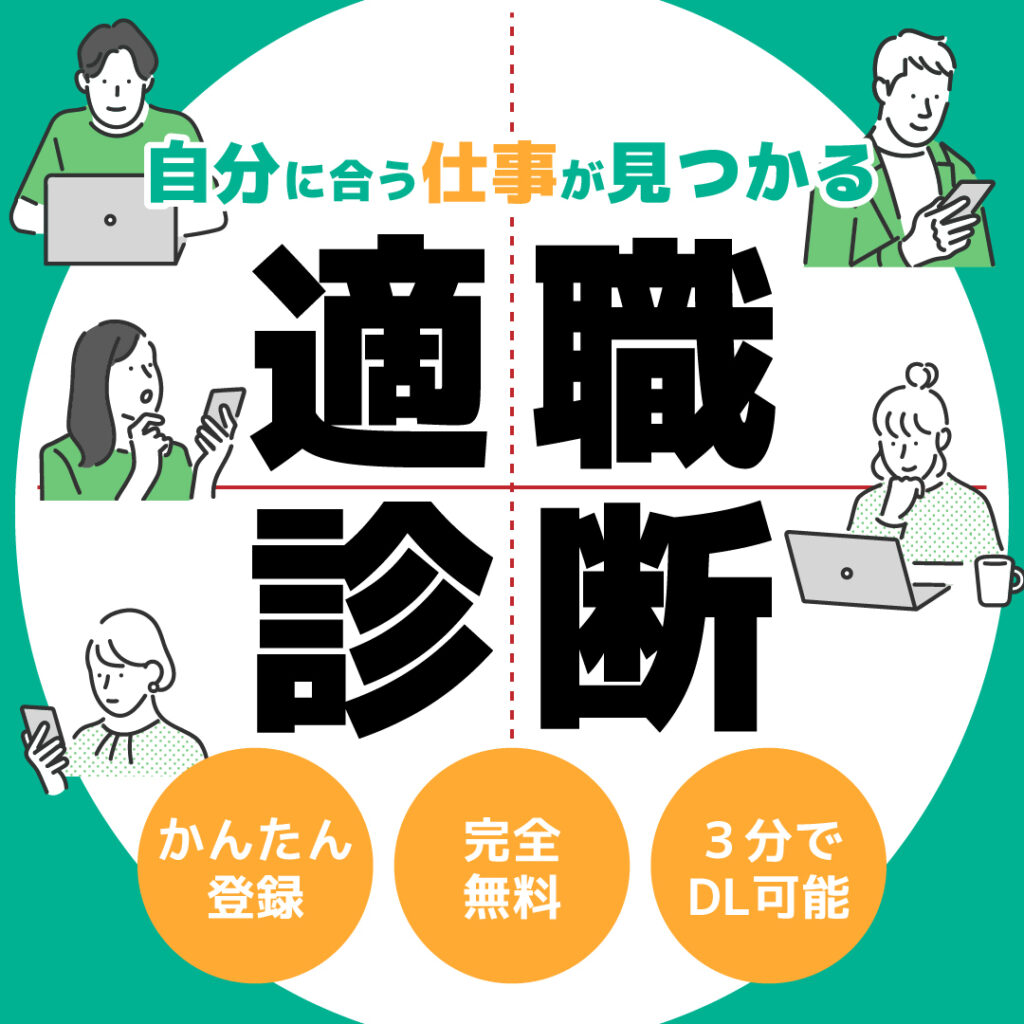
「なんとなく就活してるけど、自分に合う仕事が分からない…」
「選考に応募はしているけど、しっくりこない…」
そんな人にぴったりなのが、就活マガジンが用意している、LINEでできる適職診断です!1
0個の質問にスマホで答えるだけで、あなたの性格や価値観、向いている業界・職種が明確になります。
診断系のツールはパソコンで時間も取られる印象があると思いますが、すべてLINE上で完結するので、移動中やスキマ時間にもサクッと診断ができますよ!
就活に少しでも不安がある人は、まずは気軽に診断してみてください。
インテリア業界の主な分類

インテリア業界は一見するとひとつの業種に見えますが、実際にはさまざまな分野に分かれており、それぞれに特徴や役割があります。
分類を理解しておくことで、自分に合った企業や職種を選びやすくなるでしょう。ここでは代表的な5つの分類を紹介します。
- 家具メーカー
- 雑貨メーカー
- 住宅設備メーカー
- 日系メーカー
- 外資系メーカー
①家具メーカー
家具メーカーは、ソファやベッド、テーブルなど生活に必要な家具をつくって販売する企業です。国内外で多くのブランドがあり、見た目の美しさと使いやすさの両方が重視されます。
家具は部屋の印象を大きく左右するため、空間全体のバランスを考える力が求められるでしょう。家具の流行はファッションと同じように変化します。市場のニーズを読み取る力が必要です。
また、最近ではネット販売やショールームを活用した販売方法も広がっており、デジタルに強い人材も歓迎されやすい傾向にあります。
大手企業では企画から製造、販売までをすべて自社で行うこともあるのです。そのため、自分がどの工程に関わりたいのかを考えておくと、就職活動でも方向性がはっきりするでしょう。
②雑貨メーカー
雑貨メーカーは、クッションやライト、収納グッズなど、部屋の雰囲気を彩る小物類を扱っています。家具に比べて価格が手ごろな分、消費者の動きが売上に直結しやすいのが特徴。
この分野で大切なのは、商品の魅力だけでなく、売り場づくりやディスプレイの工夫です。見た目の印象が購入を左右する場面も多いため、感性や提案力が活かせます。
とくに女性向けブランドでは、細やかな気配りやトレンドへの理解が求められるでしょう。また、海外の工場とやりとりをする企業も多く、語学力や国際的な感覚が活かせる場面もあります。
アイデアをかたちにできる人や、さまざまなテイストに興味を持てる人には、向いている業界かもしれません。
③住宅設備メーカー
住宅設備メーカーは、キッチン、バスルーム、トイレなど、暮らしの基盤となる設備を提供しています。見た目よりも機能性や安全性が重視されるため、製品の専門性が高くなりがちです。
この業界ではBtoBの取引が中心で、住宅会社や建設会社と連携して仕事を進めます。そのため、営業職であっても基本的な設計知識や建築の流れを理解しておくと役立つでしょう。
文系出身者にはハードルが高そうに思えるかもしれませんが、研修制度が整っている企業も多く、入社後に学べる環境がある場合もあります。
最近では、省エネ性能や環境配慮が注目されており、サステナビリティに関心のある方にもおすすめの分野です。社会的な貢献を意識した仕事をしたい方には、やりがいを感じやすい業界でしょう。
④日系メーカー
日系メーカーとは、日本国内で商品開発から販売までを行っている企業を指します。地域ごとに細やかな対応ができる点や、品質の高さを強みとしているのです。
日本人の暮らしに合った製品が多く、安定したニーズがあります。社内文化としては、丁寧な指導やチームでの協力を大切にする企業が多く、新人教育にも力を入れているのです。
そのため、初めて社会に出る就活生にとっても安心できる環境だといえるでしょう。転勤があっても国内が中心で、海外勤務は少なめです。
ただし、グローバル展開や先端技術への挑戦には慎重な場合もあります。堅実にキャリアを積んでいきたい方には、向いている選択肢といえるでしょう。
⑤外資系メーカー
外資系メーカーは、海外に本社を持ち、日本でも展開しているインテリア企業です。業務の多くは本国主導で進められ、スピードや成果を重視する文化があります。
採用では専門性や実力が重視されやすく、結果を出せば年齢に関係なくチャンスが得られる風土です。
英語を使ったやりとりや、異文化との調整力が問われる場面も多いため、語学や柔軟性に自信のある方には向いています。
企業によって福利厚生や働き方に差はありますが、実力主義の環境で成長したい方にとっては、魅力のある選択肢になるはずです。
グローバルな視点を持ってキャリアを築きたい方には、最適な環境といえるでしょう。
インテリア業界の主な職種

インテリア業界では、商品の企画から販売、広報まで、さまざまな職種が連携して業務を進めています。自分に合った仕事を見つけるには、それぞれの役割を理解することが欠かせません。
ここでは、代表的な5つの職種について紹介します。
- 営業職
- 販売職
- 企画制作職
- 商品開発職
- 広報・マーケティング職
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①営業職
営業職は、顧客に商品やサービスを提案し、契約から納品、アフターフォローまで一貫して担当する仕事です。
法人営業では、オフィスや店舗など空間全体の提案を行うこともあり、ヒアリング力と提案力が求められます。営業のやりがいは、提案が形になり空間として完成するところです。
ただし、顧客の要望を正確に把握し、スケジュールや予算に応じて柔軟に対応する必要があります。専門的な知識や調整力が求められる場面も多いでしょう。
単なる販売ではなく信頼構築が重要なため、人と話すことが好きで、相手のニーズに応えるのが得意な人には向いている職種といえます。
②販売職
販売職は、インテリアショップやショールームで来店客に商品を提案し、購入へと導く仕事です。
お客さまの希望を聞きながら最適な商品を案内するため、商品知識だけでなく接客力やセンスも必要になります。接客を通じて直接感謝される場面も多く、やりがいを感じやすい職種でしょう。
一方で、売上目標がある場合もあり、数字への意識も欠かせません。流行やシーズンによって人気商品が変わるため、常に最新情報をチェックしておくことが大切です。
人と接することが好きで、トレンドに興味がある方におすすめです。
③企画制作職
企画制作職は、広告や販促物、Webコンテンツなどを通じて商品の魅力を発信する仕事です。社内外のスタッフと協力しながら、企画立案から制作進行まで幅広く関わります。
この職種では、見せ方や伝え方の工夫が成果に直結。そのため、創造力だけでなく、ターゲット理解や情報収集のスキルも求められるでしょう。
見た目の華やかさとは裏腹に、細かな作業や調整が多く、地道な努力が必要です。ただ、自分のアイデアが形になり、多くの人に届くという達成感は格別でしょう。
④商品開発職
商品開発職は、新しいインテリア商品の企画から製造までを担当する仕事です。市場調査をもとにニーズを分析し、魅力ある商品をつくり出す役割を担います。
デザイン性だけでなく、使いやすさやコスト、製造のしやすさなども考慮する必要があり、バランス感覚が重要です。CADなどの設計スキルが求められる場合もあります。
完成までには時間がかかるため、粘り強く試行錯誤を重ねる力が求められるでしょう。ものづくりに情熱を持ち、細部にこだわりたい方には適した仕事です。
⑤広報・マーケティング職
広報・マーケティング職は、自社や商品の魅力を効果的に発信し、認知度を高める仕事です。SNSやイベント、プレスリリースなどを通じて企業の情報を社外に届けます。
誰に何をどう伝えるかを戦略的に考える力が必要です。特にデジタル領域では、トレンドの移り変わりが早いため、常に最新情報に触れておくことが欠かせません。
表に立つ仕事に見えますが、実際には裏での準備や調整が多く、地道な努力が結果につながります。ブランドづくりに関心がある方にとっては、やりがいのある職種といえるでしょう。
インテリア業界の最新動向

インテリア業界は、社会の変化や人々の価値観に合わせて日々進化しています。特に近年はライフスタイルの多様化やテクノロジーの進歩により、従来のビジネスモデルが見直されるようになりました。
ここでは、注目されている最新の動向を5つ紹介します。
- 巣ごもり需要による家具・雑貨の売上変化
- ユニバーサルデザインの普及と新ニーズ
- デジタル化の進展とECサイトの影響
- 海外展開とグローバル戦略の方向性
- 環境意識の高まりとサステナブル商品
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
①巣ごもり需要による家具・雑貨の売上変化
巣ごもり生活の影響で、家具や雑貨の売上が大きく伸びました。家で過ごす時間が増えたことで、自宅を快適にしたいというニーズが高まったためです。
これを受けて、多くの企業が新商品を打ち出し、通販事業の強化に乗り出しました。この流れは一過性ではなく、「家の中での豊かさ」を求める考えが定着しつつあります。
たとえば、リモートワーク用のデスクや癒しを意識した照明、観葉植物などが人気を集めているのです。企業はこの変化に柔軟に対応し、売り場や商品開発の方針を見直しています。
就職活動では、こうした変化をふまえて「自分ならどんな暮らしを提案したいか」を考えることが、企業への関心や熱意を伝えるうえで効果的です。
②ユニバーサルデザインの普及と新ニーズ
ユニバーサルデザインとは、年齢や性別、障がいの有無を問わず、誰もが使いやすいように設計された商品や空間のことを指します。
高齢化が進むなか、インテリア業界でもこの考え方が重視されるようになってきました。たとえば、段差のない床や、開閉しやすい収納、目に優しい色使いなどが挙げられます。
個人住宅だけでなく、病院や公共施設、商業空間でも広がっており、社会全体に求められる視点です。企業は、使いやすさと美しさの両立を図るため、より高いデザイン力と観察力を求めています。
就活では、「誰のどんな課題を解決したいか」を具体的に伝えられると、自分の意欲をしっかりとアピールできるでしょう。
③デジタル化の進展とECサイトの影響
インテリア業界でもデジタル化が急速に進んでいます。特にECサイトの利用拡大により、店舗に行かなくても商品を購入できるようになりました。
これにより、販売やマーケティングの方法が大きく変わっています。最近では、スマートフォンから簡単に注文できるだけでなく、ARやVRを使って家具の「試し置き」ができるサービスも登場しました。
自宅にいながら空間イメージを確認できるようになり、消費者の購入行動にも変化が出ています。
このような背景から、デジタルに強い人材や、Webマーケティングに関心がある人の活躍が期待されているのです。最新の技術に目を向ける姿勢は、企業からも高く評価されるでしょう。
④海外展開とグローバル戦略の方向性
インテリア業界でもグローバル化が進み、日本企業が海外市場を視野に入れる動きが活発になっています。とくにアジアや欧米では、日本製品の品質やデザインが高く評価されてきました。
企業によっては現地法人を立ち上げ、海外のニーズに合わせた商品開発を進めているケースもあります。こうした動きに対応するためには、語学力や異文化への理解が重要です。
また、柔軟に考え、現地の価値観に寄り添える姿勢も求められます。
就活においては、「海外でこんな暮らしを支えたい」「国を超えて価値を届けたい」といった思いを伝えると、グローバルな視野を持つ人材として評価されやすくなるでしょう。
⑤環境意識の高まりとサステナブル商品
環境問題への意識が高まる中、インテリア業界でもサステナブルな商品が注目されています。たとえば、リサイクル素材を使った家具や、長く使えるシンプルなデザインの商品などが増えてきました。
企業は、製品そのものだけでなく、製造方法や流通にも配慮するようになっています。さらに、商品の修理や回収などのサービスも広がり、持続可能な取り組みが業界全体で進んでいるのです。
こうした流れを理解したうえで、「環境と共に暮らすデザインを考えたい」といった意欲を伝えられると、企業の姿勢ともマッチしやすくなります。
社会課題に対して前向きに取り組む姿勢は、就活でも大きな強みになるでしょう。
インテリア業界の企業売上ランキング

インテリア業界への就職を目指すなら、企業ごとの売上規模を知っておくことが大切です。売上は企業の安定性や将来性を判断するうえでの目安となり、就職先を選ぶ際の参考になります。
たとえば、ニトリは業界トップクラスの売上を誇っており、自社で製造から販売、物流までを一貫して行うことでコストを抑え、安定した成長を続けています。
カインズや無印良品、大塚家具といった企業も広く知られており、各社それぞれ異なる強みを持っているのです。ただし、売上が高い企業だけが魅力的とは限りません。
中堅や小規模な企業の中にも、独自のデザインや高い専門性で評価されている会社があります。
数値にとらわれすぎず、自分の価値観や興味と合うかどうかを重視することが、後悔のない企業選びにつながるでしょう。
| 順位 | 企業名 | 売上高(2024年度) | 出典元 |
|---|---|---|---|
| 1 | ニトリホールディングス | 約8,954億円(2024年3月期) | 公式IR資料 |
| 2 | 無印良品(良品計画) | 約6,617億円(2024年8月期) | FASHIONSNAP |
| 3 | ナフコ | 約1,818.5億円(2025年3月期) | ダイヤモンド・チェーンストア |
| 4 | イケア・ジャパン | 約953億円(2024年8月期) | PR TIMES |
| 5 | 東京インテリア家具 | 約525億円(2024年5月期) | リクナビ |
インテリア業界の就職に向いている人の特徴

インテリア業界で働くには、単にデザインが好きなだけでなく、求められる特性や考え方を理解しておくことが大切です。
自分に合った仕事かどうかを見極めることで、就職活動でも自信を持ってアピールしやすくなるでしょう。ここでは、業界で活躍しやすい人の特徴を5つ紹介します。
- インテリアが好きでこだわりがある人
- ものづくり・デザインに興味がある人
- 人と接することが得意な人
- チームでの仕事を楽しめる人
- 流行やトレンドに敏感な人
①インテリアが好きでこだわりがある人
インテリアに対して強い関心やこだわりを持っている人は、仕事に対する情熱を自然と発揮できます。
「部屋をもっと心地よくしたい」「使いやすく美しい空間を作りたい」といった思いは、日々の業務に前向きに取り組む原動力になるでしょう。
企業側も、インテリアへの興味や熱意を、具体的な経験や行動として伝えてほしいと考えています。
たとえば、自分の部屋を工夫して模様替えしたエピソードや、お気に入りのブランドについて語れると、面接で印象に残りやすくなるのです。
漠然とした「インテリアが好き」という気持ちだけではなく、自分の言葉でこだわりを説明できるように準備しておくと良いでしょう。そうした積み重ねが、就職後の成長にもつながっていきます。
②ものづくり・デザインに興味がある人
インテリア業界は、家具や雑貨などのモノをつくり、人の暮らしに新たな価値を提供する仕事です。
ものづくりやデザインが好きな人にとっては、アイデアを形にする楽しさを日々感じられる環境といえるでしょう。
特に企画やデザインの職種では、細かな部分にまで目を配る力や、使う人の視点で考える姿勢が求められます。
完璧なセンスは必要ありませんが、自分なりに工夫しようとする意欲や、新しい視点を取り入れる柔軟さがあると評価されやすくなるのです。
デザインに触れる機会を増やしたり、展示会やインテリアショップを訪れて感性を磨いたりすることが、就活の準備としても役立ちます。
自分が好きなデザインや考え方を、言葉で表現できるようにしておいてください。
③人と接することが得意な人
インテリア業界では、人と接する力も大切な資質のひとつです。営業や販売はもちろん、設計や施工の現場でも、顧客や他の担当者とやり取りする機会が多くあります。
相手の希望を正しくくみ取り、それを提案につなげていく力が求められるでしょう。住空間に関する商品は、生活そのものに深く関わるため、お客様の気持ちを理解し、信頼関係を築くことが重要です。
質問をしながら相手の本音を引き出したり、専門的な内容をわかりやすく説明したりするスキルが、結果につながります。
人と関わることが好きな方は、コミュニケーション力を強みとしてアピールしてください。チームのなかでも信頼される存在になれる可能性があります。
④チームでの仕事を楽しめる人
インテリアの仕事は、複数の専門職が協力しながら進めていくことが一般的です。営業、デザイナー、施工管理など、さまざまな立場の人と連携しながらプロジェクトを完成させていきます。
チームでの仕事を楽しめる人には、やりがいを感じやすい環境でしょう。チームワークでは、自分の役割を理解し、他の人をサポートする意識も必要になります。
また、考え方の違いがあったときにも、冷静に意見を交わす姿勢が求められるのです。
学生時代にグループで活動した経験や、アルバイトでの協力体験を振り返り、「どうチームに貢献したか」を整理しておくと、面接でも効果的にアピールできます。
人と協力しながら成果を出すのが好きな人にとっては、向いている業界だといえるでしょう。
⑤流行やトレンドに敏感な人
インテリアの世界でも、流行やスタイルは年ごとに変化しています。
北欧風、韓国風、ナチュラルテイストなど、人気のテイストは次々と入れ替わっていくため、トレンドに敏感であることが大きな武器になるのです。
新しい情報をキャッチし、自分の感性で取り入れていける人は、企画や販売の場面で活躍しやすいでしょう。
SNSや雑誌、展示会などから日常的に情報を集める習慣を持っていれば、そのまま強みとして伝えることができます。
ただ流行を追うだけでなく、「なぜそのスタイルが注目されているのか」を考える力も求められます。背景を理解し、自分の考察として言語化できれば、選考でも説得力を持ったアピールができるでしょう。
インテリア業界の志望動機の書き方

インテリア業界への志望動機を書くには、「インテリアが好き」という気持ちだけでは不十分です。
企業ごとの特性や業界の仕組み、自分の経験などを踏まえて、具体的で説得力のある内容に仕上げる必要があるでしょう。
ここでは、就活で評価されやすい志望動機をつくるための5つのポイントを紹介します。
- インテリア業界を志望する理由を明確に言語化する
- 企業を選んだ理由を事業内容や理念と結びつけて書く
- 自分の経験や強みを業界・企業と関連づける
- 入社後にどう貢献できるかを具体的に示す
- 職種に応じて内容と言葉選びを調整する
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
①インテリア業界を志望する理由を明確に言語化する
まず大切なのは、なぜ数ある業界の中でインテリア業界を選んだのかを明確に伝えることです。「興味があるから」「おしゃれだから」といった曖昧な理由では、面接官の心には響きません。
関心を持ったきっかけや、その業界で働きたいと思うようになった具体的なエピソードを交えて書くことで、説得力が生まれます。
たとえば、「引っ越しの際、家具選びに夢中になり、空間の雰囲気が自分の手で変えられることに感動した」という経験があるなら、それを志望理由として言語化してください。
さらに、「この業界で誰かの暮らしを支える空間をつくりたい」といった思いも加えると、より意欲が伝わるでしょう。
自分の経験や価値観を深掘りし、「なぜインテリア業界なのか」をはっきりさせておくことが重要です。
②企業を選んだ理由を事業内容や理念と結びつけて書く
志望動機では業界だけでなく、「なぜこの会社なのか」も必ず問われます。単に「有名だから」「デザインが好みだから」といった理由では、他社との違いが伝わりません。
企業が掲げている理念やサービスの特徴を自分の価値観と結びつけて説明することが大切です。
たとえば、「貴社が取り組んでいる空間全体のトータル提案に共感し、自分も暮らしの質を高めるお手伝いがしたいと感じました」といったように、
具体的な事業内容と自身の想いをリンクさせて表現してください。
また、「環境配慮型の素材を取り入れている姿勢に共鳴しました」「地域密着でサービス展開している点が、自分の理想に合っていました」なども効果的です。
企業研究が浅いと説得力に欠けるため、ホームページや説明会、社員インタビューなどで事前に情報を集めておきましょう。
③自分の経験や強みを業界・企業と関連づける
良い志望動機には、自分の強みやこれまでの経験が必ず含まれています。重要なのは、その経験が企業や職種でどう活かせるのかを具体的に伝えることです。
ただの自慢話ではなく、「だからこそ活躍できる」という未来像を示してください。
たとえば、接客のアルバイトで培ったコミュニケーション力を「お客さまの要望を引き出し、最適な空間を提案する力」としてアピールすると、業務との関連性が明確になります。
また、「イベント運営で空間演出を担当した」「建築や美術の授業で空間設計を学んだ」といった実体験があれば、それも志望理由の裏付けになるでしょう。
自分の経験が企業の求める人材像と重なるポイントを探し、自然に結びつけて書いてみてください。
④入社後にどう貢献できるかを具体的に示す
志望動機の最後は、入社後に自分がどう貢献できるかを伝える場面です。「働きたい」だけではなく、「入社後に何をしたいか」「どう役立てるか」まで言及することで、前向きな印象を与えることができます。
たとえば、「顧客の暮らしに寄り添ったインテリア提案で満足度を高めたい」や、「新しいトレンドを取り入れた商品開発でブランド力を高めたい」といった表現が考えられるのです。
さらに、「自分の強みである分析力を活かして、マーケティング施策にも貢献したい」など、具体的なスキルと紐づけて書くと説得力が増すでしょう。
現実味のある目標を掲げることで、企業側に「この人と一緒に働きたい」と思わせることができるはずです。
⑤職種に応じて内容と言葉選びを調整する
インテリア業界には、営業・販売・企画・デザインなど、さまざまな職種があります。それぞれ求められる能力や視点が異なるため、志望動機の書き方も職種に合わせて変える必要があるでしょう。
たとえば、営業職を志望するなら「人との信頼関係を築くことが得意で、最適な提案を通じて顧客の課題を解決したい」といった内容が適しています。
一方、商品企画職であれば「トレンドを先読みし、ニーズに合った新商品を形にしたい」という視点が必要でしょう。すべての職種に共通するような表現では印象が薄くなってしまいます。
希望する職種の特徴をよく理解し、担当者に伝わる言葉を選んでください。
インテリア業界の自己PRの書き方

インテリア業界での自己PRは、自分の強みを明確にしつつ、業界とのつながりを意識して伝えることが大切です。
経験をただ並べるのではなく、企業が求める人物像と重ねて構成することで、説得力が増すでしょう。ここでは、印象に残る自己PRを作るための4つのポイントを紹介します。
- 構成は結論→エピソード→学び→活かし方にする
- 成果よりも工夫や姿勢を重視する
- 入社後にどう貢献できるかを示す
- インテリアや人との関わりを強みに絡める
「自己PRの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己PRテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みを効果的にアピールする自己PRが作成できますよ。
①構成は結論→エピソード→学び→活かし方にする
自己PRは、結論から始めることで伝わりやすくなります。最初に「私は〇〇が強みです」と述べ、その裏付けとなる具体的なエピソードを続けてください。
その後に得た学びを紹介し、最後に「その経験を活かしてどのように貢献したいか」を述べると、自然な流れになります。
たとえば、「私は状況に応じた提案が得意です」と伝えたうえで、アルバイトやゼミ活動などで工夫した経験を紹介します。
その結果、どのように成長できたかを整理し、「顧客に合った空間づくりに活かしていきたい」とつなげると、具体性のある自己PRになるでしょう。
順序立てて話すことで、読み手や聞き手にも理解されやすくなります。面接での受け答えにも応用できる構成です。
②成果よりも工夫や姿勢を重視する
インテリア業界では、目立った成果よりも「どのように工夫したか」「どんな姿勢で取り組んだか」が重視されます。なぜなら、商品開発や提案の多くが長期的で、チームで進めることが多いためです。
たとえば、「売上を伸ばした」という実績だけではなく、その背景にある工夫や行動を丁寧に説明するほうが印象に残ります。
たとえ大きな成果がなくても、どんな工夫をし、どんな気づきを得たかを伝えることで、主体性や考える力をアピールできるでしょう。企業は即戦力よりも、将来伸びる素質を見ています。
努力の過程を素直に伝えることが、自己PRをより魅力的にしてくれるのです。
③入社後にどう貢献できるかを示す
自己PRでは、自分の強みを語るだけでなく、「その強みをどう活かして会社に貢献したいか」まで伝えることが重要です。企業は「入社後に何をしてくれそうか」を知りたがっています。
たとえば、「チーム内で調整役を担った経験がある」なら、「その経験を活かし、部門をつなぐ存在としてプロジェクトを円滑に進めたい」といった形で、具体的な貢献イメージにつなげましょう。
こうした視点を持つためには、企業研究も欠かせません。志望先の事業内容や理念、強みなどを理解し、それに沿う形で自分の特性を結びつけてください。
相手の立場に立った自己PRは、面接官の心に届きやすくなります。
④インテリアや人との関わりを強みに絡める
インテリア業界では、モノづくりだけでなく、人との関わりも重視されます。
そのため、自己PRでは「人への思いやり」や「空間へのこだわり」など、自分の強みが業界とどう結びつくかを意識して伝えてください。
たとえば、「相手の気持ちをくみ取るのが得意」といった強みがあれば、「その力を活かして、顧客のライフスタイルに合った提案を行いたい」といった形で結びつけると、具体的なイメージが伝わります。
また、インテリアへの関心を自分なりの行動として語れると説得力が増すでしょう。
「店舗のディスプレイを見るのが好き」「空間の色使いに注目している」といった日常の行動も、立派なアピール材料になります。
業界に対する関心と、自分の強みの接点を意識した自己PRを作成してみてください。
インテリア業界の就職選考で有利になるコツ
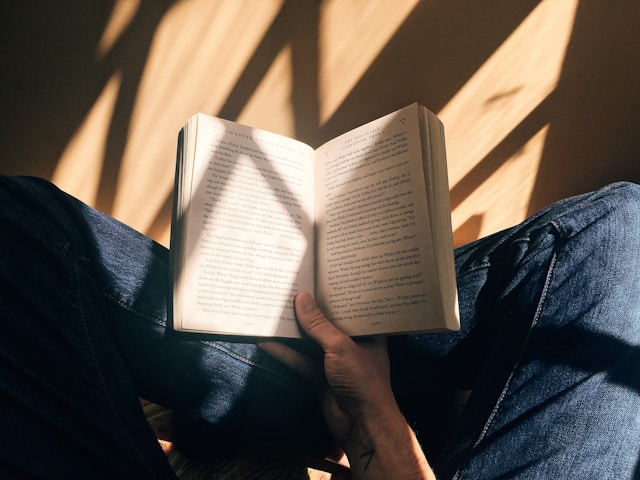
インテリア業界は人気が高く、志望者が多い分だけ、選考で他の学生と差をつけるには準備が欠かせません。ここでは、就活で有利になるために意識しておきたい5つの行動ポイントを紹介します。
- 業界理解・経験・自己分析を早めに行う
- 企業研究は商品・顧客・競合を見る
- 接客や販売経験をしておく
- インターンやイベントに参加する
- デザイン系の職種はポートフォリオを作る
①業界理解・経験・自己分析を早めに行う
インテリア業界は職種が多様で、企業ごとに働き方や扱う商品も異なります。そのため、業界の仕組みを早めに理解し、自分の適性と重なる部分を明確にしておくことが大切です。
たとえば営業や販売、企画、デザインなど、それぞれの職種がどんな役割を担っているのかを知ると、自分に合う方向性を見つけやすくなります。
あわせて、自分の過去の経験や強みを振り返り、それがどのように仕事に活かせそうかも考えてみてください。この段階で深く自己分析をしておけば、エントリーシートや面接での説得力も増します。
早い段階から準備を始めることで、選択肢の幅が広がり、納得のいく就活につながるでしょう。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
②企業研究は商品・顧客・競合を見る
企業研究は、企業理念や沿革を確認するだけで終わらせないことが重要です。特にインテリア業界では、「誰に、何を、どう届けているか」を丁寧に見る必要があります。
たとえば、取り扱っている商品が法人向けか個人向けかによって、求められる対応力も変わってくるでしょう。
競合と比較しながら、自社の強みや特徴を分析しておくと、自分がなぜその企業に合っているのかを具体的に語れるようになります。
実店舗やオンラインショップを見て、商品や接客の違いを感じてみるのもおすすめです。実感をもとに話ができれば、企業研究の深さが自然に伝わるでしょう。
③接客や販売経験をしておく
インテリア業界では、営業や販売など顧客と接する仕事が多くあります。実際の現場では、言葉づかいや気配り、ニーズを汲み取る力が求められるのです。
そのため、接客や販売のアルバイト経験は非常に役立ちます。このような経験を通して得られる力は、面接でのエピソードとしても活用しやすいです。
ただ働くだけでなく、「どんな工夫をしたか」「どんな成果があったか」を意識して振り返っておきましょう。実務に近い環境で得た経験は、自信を持って自分をアピールするための大きな材料になります。
時間に余裕があるうちに、ぜひ挑戦してみてください。
④インターンやイベントに参加する
業界への理解を深めるには、インターンや合同説明会、企業主催のイベントなどへの参加が非常に効果的です。仕事の実態や社風を体感することで、自分に合った企業を見つけやすくなります。
また、選考過程で「インターンに参加しました」と伝えることで、企業への関心や本気度も伝えられるでしょう。
社員との会話から得られる生の声や、職場の雰囲気は、ウェブ情報では得られない貴重なヒントになります。複数の企業を比較することで、自分が本当に働きたいと思える会社が見えてくるはずです。
機会があれば積極的に参加してみてください。
「インターンの選考対策がよくわからない…」「何度も選考に落ちてしまう…」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるインターン選考対策ガイドを確認して必勝法を知っておきましょう。LINE登録だけで無料でダウンロードできますよ。
⑤デザイン系の職種はポートフォリオを作る
デザイン系の職種を希望する場合、ポートフォリオは必須といってよいでしょう。自分の制作実績を伝えるための資料であり、スキルや感性、考え方を伝える重要な手段です。
作品だけでなく、制作意図や工夫した点もあわせて記載することで、より評価されやすくなります。学校の課題だけでなく、自主的に取り組んだ作品も含めると、より意欲が伝わるでしょう。
早めに準備を始めて、何度も見直しながら完成度を高めておくことが大切です。見せ方や構成にも工夫を加えて、他の応募者と差をつけてください。
インテリア業界の就職で役立つ資格

インテリア業界を目指すうえで、専門性や意欲を示す手段として資格を取得しておくと強みになります。必須ではありませんが、業界に対する理解や関心の深さを伝える材料として効果的です。
ここでは、就職活動で特に評価されやすい代表的な資格を4つ紹介します。
- インテリアコーディネーター
- インテリアプランナー
- カラーコーディネーター
- 商業施設士・建築士
①インテリアコーディネーター
インテリアコーディネーターは、家具や照明、カーテン、壁紙などの内装アイテムをトータルで提案する専門家です。主に一般住宅を対象とし、暮らしを快適に整えるアドバイザーとして活躍します。
この資格を持っていると、空間全体を考えた提案力や基礎的なインテリア知識があると認められやすくなるのです。
試験では建築、設備、色彩、家具など幅広い知識が求められるため、勉強を通して業界理解も深まるでしょう。学歴や学部に関係なく誰でも受験できるため、文系の学生にも取り組みやすいのが特徴です。
実務経験がなくてもアピール材料になるため、選考で話題にしやすい資格といえます。業界への関心を行動で示す方法として、取得を検討してみてください。
②インテリアプランナー
インテリアプランナーは、空間そのものの設計やデザインに関わる専門資格です。住宅だけでなく、オフィスや公共施設など大規模な空間を対象とすることが多く、より高度なスキルが求められます。
この資格は国土交通省の登録制度に基づくため、公的な信頼性が高いといえるでしょう。取得には建築士資格や実務経験が必要になるため、学生のうちに取得するのは難しいかもしれません。
それでも、「将来インテリアプランナーを目指している」と明確に伝えることで、長期的な視野と意欲を評価されやすくなります。
設計や空間デザインに関心がある方は、今のうちから学習計画を立てておくと良いでしょう。
③カラーコーディネーター
カラーコーディネーターは、色彩の知識を活かして空間や商品にふさわしい配色を提案できる力を証明する資格です。
インテリア業界では、色の組み合わせひとつで空間の印象が大きく変わるため、色に強い人材は重宝されやすい傾向にあります。
この資格を持っていると、「色彩感覚に優れている」「全体のバランスを考えられる」といった評価につながりやすくなるでしょう。筆記中心の試験であるため、就活準備と並行して学びやすい点も魅力です。
住宅や店舗のコーディネート職を目指す場合には、特に実践的な知識として役立つでしょう。パーソナルカラーや照明との関係性など、応用範囲も広いため、自己PRにも活かしやすい資格です。
④商業施設士・建築士
商業施設士は、ショッピングモールや飲食店などの商業空間の設計や計画に関わる資格です。利用者の導線や集客性、雰囲気づくりなど、多くの視点から空間を設計する能力が求められます。
一方、建築士は建物の構造や安全性に関する専門知識を証明する国家資格です。設計職や施工管理職を希望する場合には、将来的に必要になることもあるため、早い段階から意識しておくと安心でしょう。
どちらも難易度は高めですが、「将来この資格を取得して空間づくりに貢献したい」という意欲を伝えられれば、ポテンシャルとして高く評価される可能性があります。
設計や技術分野に強い関心を持つ方は、長期的な目標として視野に入れておくと良いでしょう。
インテリア業界の就職面接でよく聞かれる質問

インテリア業界を目指す就活生にとって、面接対策は欠かせない準備の一つです。質問の傾向をあらかじめ把握しておけば、焦らず自信を持って答えられるでしょう。
ここでは、実際によく問われる5つの質問と、その答え方のコツを紹介します。
- インテリア業界を志望した理由
- インテリアに興味を持ったきっかけ
- インテリア業界で実現したいこと
- 学生時代に頑張ったこと
- 自分の強みを活かす方法
①インテリア業界を志望した理由
志望理由は面接で高確率で聞かれる質問です。「インテリアが好きだから」だけでは漠然としていて印象に残りません。
業界のどこに魅力を感じ、自分のどのような体験とつながっているかを伝えることが大切です。
たとえば「引っ越しの際に家具選びを通じて、空間づくりが暮らしに与える影響の大きさを実感した」など、具体的な経験を含めて話すと説得力が増します。
そのうえで、「人々の暮らしに寄り添う空間を提案したい」といった将来への意欲も示せると良いでしょう。ポイントは、業界研究と自己理解の両方を深めて、自分だけの言葉で話すことです。
②インテリアに興味を持ったきっかけ
この質問では、インテリアへの関心がどのように芽生えたかが問われます。個人的な体験と現在の志望理由とが自然につながっていることが重要です。
たとえば「アルバイト先で家具のレイアウトを変更したところ、売れ行きが上がった。それが空間づくりの力に気づくきっかけとなった」など、実体験を交えて説明するとリアリティが出ます。
ほかにも、「家族の模様替えを手伝った際に、照明や配置によって居心地が変化することに感動した」といった話もよく伝わるでしょう。
大切なのは、抽象的な表現を避けて、自分にしか語れない出来事を伝えることです。
③インテリア業界で実現したいこと
企業は、応募者がどんな思いを持って業界に入ろうとしているかを知りたがっています。「何をしたいか」だけでなく、「なぜそれを実現したいのか」まで掘り下げて伝えることが大切です。
たとえば「誰もが安心して過ごせるユニバーサルデザインの空間をつくりたい」といった目標を語ると、ビジョンが伝わりやすくなります。
それに加えて、「大学で学んだ建築の知識を活かして提案したい」など、自分の経験と結びつけると説得力が増すでしょう。意欲だけでなく、実現性や準備の有無も評価対象になります。
目指す姿を現実的に語ってみてください。
④学生時代に頑張ったこと
「学生時代に力を入れたこと」は、自己理解や行動力を測る定番の質問です。インテリア業界では、チームでの協働や顧客対応の経験が活かせるため、それに関連するエピソードが有効でしょう。
たとえば「文化祭の装飾を担当し、空間全体の統一感を意識したデザインを提案した結果、来場者から高評価を得た」という経験があれば、考え方や工夫の過程を丁寧に説明すると良いでしょう。
結果よりも、どう考えて動いたかのプロセスを伝えることが重視されます。自分の強みや価値観がにじむようなストーリーを選び、印象に残るエピソードに仕上げてください。
⑤自分の強みを活かす方法
自分の強みを聞かれたときは、「それをどのように活かせるか」まで言及することで実践力が伝わります。
「協調性がある」と答えるなら、「チームでの業務が多い営業職で、相手の立場を考えながら調整できる」など、具体的な場面を想定してください。
また、「発想力がある」場合でも、「企画職で、新しい空間づくりのアイデアを提案することに活かせる」など、職種との結びつきを示すと納得感が高まるでしょう。
漠然とした強みだけでは差がつきにくいため、具体性がカギとなります。実際のエピソードや成果を盛り込みながら、自分ならではの強みをわかりやすく伝えてください。
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
就職を目指すなら知っておきたいインテリア業界の全体像

インテリア業界への就職を考えているなら、まず業界全体の構造や主な職種、そして最新動向を押さえておくことが重要です。
特に、家具や雑貨を扱うメーカーの違いや、営業・企画・開発など多様な職種の特徴を理解することは、自分に合ったキャリアを描くうえで大きな手助けになります。
さらに、ユニバーサルデザインやECサイトの進化など、時代とともに変化する業界動向にも注目すべきでしょう。
そのうえで、志望動機や自己PRの書き方、面接対策、役立つ資格まで準備しておけば、インテリア業界への就職成功に一歩近づけるはずです。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












