国家公務員の職種一覧と仕事内容|試験区分や年収も解説
就職先として安定性が魅力の国家公務員ですが、実際には多種多様な職種や試験区分が存在し、それぞれ求められる資質や仕事内容が異なります。
この記事では、国家総合職・一般職・専門職の違いから裁判所職員・国会職員まで、各職種の特徴や年収、向いている人の傾向までを徹底解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
国家公務員とは何か

国家公務員とは、内閣府や各省庁、裁判所、国会などの国家機関に所属し、国の行政・立法・司法に関わる業務を担う職員のことです。
「安定していて福利厚生が手厚い」といったイメージを持つ就活生も多いかもしれませんが、実際は日本社会の土台を支える重要な仕事であり、責任感と専門性のある人材が求められます。
国家公務員の仕事は、法律の施行や制度の設計、政策の立案と実行、そして国民サービスの運営など多岐にわたります。
勤務先は本省だけでなく、全国にある出先機関も含まれるため、勤務地が幅広い点も特徴です。
将来、自分の仕事を通じて社会にどう貢献したいかを考えるとき、国家公務員という選択肢は非常に意義深いものになるはずです。
国家公務員の職種一覧

国家公務員と聞くと一括りにされがちですが、実際にはさまざまな職種が存在し、役割や働く現場、求められる資質も大きく異なります。
志望先を考えるうえで、それぞれの職種の違いを正しく理解しておくことはとても重要です。以下では、代表的な職種を5つに分類し、それぞれの特徴についてわかりやすく解説していきます。
- 国家総合職
- 国家一般職
- 国家専門職
- 裁判所職員(司法府)
- 国会職員・法制局職員(立法府)
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①国家総合職
国家総合職は、中央省庁で政策の企画や立案を行う“幹部候補”として採用される職種です。
例えば「経済の活性化」「エネルギー政策の推進」「外交戦略の構築」といった、日本全体に影響する大きなテーマに関わる機会があります。
一方で、高い学力や政策への理解、論理的思考力は必須です。採用後も本省での激務や全国転勤があるなど、ハードな側面も覚悟する必要があります。
「国を動かしたい」「グローバルな仕事をしたい」「課題を制度で解決したい」そんな志を持つ人にとっては、他にはないやりがいを感じられる道でしょう。
②国家一般職
国家一般職は、出先機関や地方支分部局で国の制度を現場で動かす“実務のプロ”です。中央省庁ではなく、各地の税務署、労働局、地方整備局などでの勤務が中心となります。
例えば、災害対応で住民支援をしたり、国の補助金の運用を担当したりと、地域密着の業務が多く、国民生活と直結した現場で活躍できます。
住民からの感謝の声を直接受け取れることもあり、「人の役に立っている実感」が得られやすい点も特徴です。
派手さはなくても、堅実にキャリアを築きたい方、公務の原点である“国民のための行政”を地道に支えたい方にとって、非常に意義のある選択肢といえるでしょう。
③国家専門職
国家専門職は、特定の分野に特化して専門知識を活かして働く国家公務員です。「国税専門官」「労働基準監督官」「出入国在留管理官」などが該当します。実務の専門性が高く、採用段階で担当分野が決まっているのが特徴です。
例えば、国税専門官なら企業や個人の税務調査、徴収業務を通じて公正な課税を実現します。労働基準監督官であれば、違法な労働環境を取り締まり、労働者の安全と権利を守ります。
また、専門性を高めていくことで“その道のプロ”として信頼される存在になれる点は、将来的な安定やキャリア設計にもつながります。
「得意分野を活かして貢献したい」「制度の最前線で働きたい」という方には、とても魅力的な進路です。
④裁判所職員(司法府)
ここから紹介する2つの職種は、いわゆる行政官とは異なり、「司法」や「立法」の現場で活躍する国家公務員です。
その一つが裁判所職員です。裁判所職員は、裁判の円滑な進行を支える裏方の存在です。
例えば裁判所事務官は、裁判資料の作成・管理・手続きの補助を行い、書記官は法廷での記録や訴訟手続きの管理を担います。
また、家庭裁判所調査官は、福祉や心理学の知見を活かして子どもや家庭の実情を調査し、裁判の判断材料を提供します。
法律に興味があり、人に寄り添う支援をしたい方には、裁判所職員という選択肢は非常に有意義でしょう。
⑤国会職員・法制局職員(立法府)
もう一つ、行政機関とは異なるのが、立法府に属する国会職員や法制局職員です。国会職員は衆議院や参議院に配属され、議会の運営や議員のサポート、会議資料の作成、秘書的業務などを幅広く担当します。
一方、法制局職員は、法案の内容が憲法に合致しているか、法体系として整合性があるかをチェックする専門的な役割を果たします。いずれも、政治の最前線を内側から支える存在です。
ただし、採用人数が限られているため競争は激しく、法学や政治学などの素養が求められる傾向があります。志望する場合は、早めの情報収集と対策が欠かせません。
表には出にくい仕事ではありますが、議会の運営や立法の品質を支える、非常に重要なポジションです。
国家総合職の仕事内容

国家総合職は「中央省庁で働く幹部候補」として、政策の企画立案や法制度の構築に携わる役割を担います。
業務内容は幅広く、所属先や専門分野によっても大きく異なります。ここでは代表的な5つの職種に絞って、その仕事内容や特徴を紹介します。
- 本省係長級職員
- 外交官
- 経済官僚
- 技術系キャリア官僚
- 法務系キャリア
①本省係長級職員
本省係長級職員は、いわば中央官庁における“現場の司令塔”です。課や室と呼ばれるチーム単位で業務を動かし、政策の具体化や法令の整備、関係省庁との調整業務などを担います。
この職種のやりがいは、国の方針を自分の手で形にできる点にあります。一方で、答弁資料の作成や国会対応、突発的な社会課題への緊急対応など、繁忙期は深夜まで働くケースも珍しくありません。
政策に直接関わりたい、行政の中枢で働きたいという志を持つ方には、非常に魅力のあるフィールドといえるでしょう。
②外交官
外交官は、外務省に所属し、日本の国益を国際社会で守るというミッションを担っています。海外の大使館や国際機関での勤務も多く、グローバルに活躍したい学生にとって非常に人気の高い職種です。
具体的には、条約交渉・ODA(政府開発援助)・日本文化の発信・災害時の邦人保護など、多様な外交実務を通じて国と国との橋渡しを行います。
日々の業務は英語や現地語で行うこともあり、高い語学力と対人交渉力が求められます。
「世界を舞台に働きたい」「国際問題に関わりたい」という強い志がある方にとって、外交官は唯一無二のキャリアです。
③経済官僚
経済官僚は、経済産業省・財務省・内閣府などで経済政策の企画や調整を行う職種です。マクロ経済から産業振興まで、広範なテーマを扱い、企業活動や市場の健全な発展を支えます。
財務省では予算編成や税制改革を担当し、経産省ではスタートアップ支援やエネルギー政策を所管します。日本銀行やIMFなどと連携することもあり、金融・経済の知識に加え、分析力・調整力も重要です。
近年ではデジタル経済、カーボンニュートラル、新興国との経済連携など、新しい課題にも柔軟に対応していく必要があります。
数字や制度に強く、経済を通じて社会を動かしたいという学生には、非常にやりがいのある職種でしょう。
④技術系キャリア官僚
技術系キャリア官僚は、理系の専門知識を活かしてインフラ整備、災害対策、環境保護などの技術的行政を担う職種です。国土交通省・農林水産省・環境省・防衛省など、幅広い官庁で活躍の場があります。
例えば、国土交通省でダムや道路の整備計画を策定したり、環境省で再生可能エネルギー政策を推進したりと、理系的視点から公共インフラの安全と発展を支えます。
大学では土木・機械・電気・農学・建築などを専攻した学生が多く、採用後も“技術職”として専門スキルを発揮できるのが魅力です。
各分野の研究機関や自治体と連携する場面も多く、現場志向の強い職種といえます。理系の知識を活かして、国民生活に密着した社会課題に取り組みたい方にぴったりの選択肢です。
⑤法務系キャリア
法務系キャリアは、法務省や出入国在留管理庁などで、司法制度や人権擁護、外国人政策などを担当する職種です。法律を扱う場面が多く、行政手続や制度設計において法的観点からの判断が求められます。
例えば、刑事政策の見直しや矯正施設の運営支援、外国人の在留管理や難民認定など、国民の権利と安全を守るための施策に関与します。
国内外の人権問題への対応や、法改正に向けた国会対応も重要な業務の一つです。
法律を通じて人と社会を守りたい。そんな思いを抱く学生にとって、法務系キャリアは大きな意義のある道となるでしょう。
国家一般職の仕事内容

国家一般職は、地方の出先機関や支分部局で、国の制度や政策を現場で運用・実務に携わる公務員です。
地域に密着し、国民生活に直接関わるため、行政の「現場力」として欠かせない存在です。仕事内容は幅広く多様で、地域特有の課題に対応しながら日々の行政サービスを提供します。
ここでは代表的な5つの職種について、その役割や魅力を詳しく解説します。
- 税務署事務官
- 労働局事務官
- 地方整備局職員
- 入国管理局職員
- 法務局事務官
①税務署事務官
税務署事務官は、国税庁の出先機関である税務署に勤務し、納税者の申告内容の処理や納税相談、税務調査のサポートなどを担当します。
税金は国の根幹を支える重要な財源ですから、その公平かつ適正な徴収に寄与する役割は大変責任が重いものです。
就活生にとっては「法律や会計に詳しくないと務まらないのでは」と不安に感じるかもしれません。しかし、未経験でも研修が充実しており、基礎から学べる環境が整っています。
実務を通じて税の仕組みや法律を深く理解できるため、専門知識を着実に身に付けられます。
数字が苦手でも、コツコツと丁寧に仕事に取り組みたい方や、社会のルールを守ることにやりがいを感じたい学生には特に向いています。
②労働局事務官
労働局事務官は厚生労働省の地方機関に所属し、労働環境の改善や雇用促進、労働者の権利保護を目的としたさまざまな施策を実施しています。
労働条件の監督や相談対応など、地域の働く人々の生活を支えるための仕事です。
現場では多様な相談に耳を傾け、法律の枠組みを駆使して問題解決を図ります。
具体的には、長時間労働の是正指導や職場の安全管理の指導、職業訓練の支援、失業対策の企画・運営など、多岐にわたる活動を行います。
社会正義を重んじ、人々の働く環境をより良くしたい方にはぴったりの職種です。
③地方整備局職員
地方整備局職員は国土交通省の地方支分部局で、道路・河川・港湾などの公共インフラの整備や維持管理を担います。地域の安全と生活の基盤を守るため、技術的な知識と調整能力が必要な仕事です。
理系・文系を問わず活躍の場があり、技術的な業務に関わりたい学生はもちろん、プロジェクトマネジメントや地域連携に興味がある人にも魅力的です。
実際には、自治体や建設会社、住民との調整が多く、現場に出る機会も多いため、地域の課題解決に貢献できます。
地域社会に根差し、地元のために役立ちたいという思いを持つ学生にとって、非常に魅力ある職種でしょう。
④入国管理局職員
入国管理局職員は法務省の出先機関で、外国人の入国・在留管理や不法滞在者の取り締まりを行います。
多文化共生社会の推進と安全な社会の維持という難しいバランスを取りながら、行政サービスを実施しています。
初めて接する学生にはハードルが高く感じるかもしれませんが、研修が充実しており、語学や法律の知識を段階的に身に付けられます。実際、外国語スキルを活かす場面も多く、国際感覚を磨く絶好の職場です。
国際社会に興味があり、安全と共生を両立させる仕事に携わりたい学生におすすめします。
⑤法務局事務官
法務局事務官は法務省の地域機関に勤務し、不動産登記や商業登記、戸籍事務など、市民生活に深く関わる行政サービスを提供します。
これらの手続きは、個人の財産権や身分関係を守るために欠かせないものであり、正確さと迅速さが強く求められます。
仕事に必要な法律知識は入庁後にしっかり学べるため、法律初心者でも挑戦しやすい職種です。
例えば、土地の所有権を正確に登記したり、会社設立のための登記手続きを行うほか、出生や結婚などの戸籍記録を適切に管理することで、トラブル防止や法的安全性の確保に貢献します。
安定した環境で着実にキャリアを築きたい人、社会の基盤を支える実感を得たい学生に向いています。
国家専門職の仕事内容

国家専門職は高度な専門性を持ち、特定分野の実務を通じて国の施策を推進する職種です。
法律、経済、農業など多様な分野で専門知識を活かし、社会のルールを守りながら国民生活の安定と発展に貢献します。ここでは代表的な5つの職種について仕事内容を詳しく紹介します。
- 国税専門官
- 労働基準監督官
- 出入国在留管理官
- 財務専門官
- 食料農業行政職
①国税専門官
国税専門官は国税庁の中核として、税務調査や納税指導を通じて適正な税収確保に努めます。税務の専門知識に加え、調査対象者との折衝能力やコミュニケーション力も問われます。
就活生の中には「調査の仕事は怖そう」「専門的な知識が必要そう」と感じる方もいるでしょうが、充実した研修が用意され、未経験から着実に成長可能です。
現場では企業の帳簿を精査したり、納税者に制度を説明したりと、実務を通じて税務のスペシャリストになります。
例えば、架空経費の指摘や脱税防止のための指導を行い、正しい納税を促すことが社会全体の公正を守ることにつながります。
数字や法律に強い方はもちろん、人と話すことが好きな学生にも適しています。
②労働基準監督官
労働基準監督官は労働基準監督署に勤務し、労働法令の遵守を監督し、労働者の安全と健康を守ります。違法な労働条件の是正や労働災害の防止に向けた指導、調査が中心です。
「社会正義に関心がある」「労働者の権利を守りたい」という学生に強くおすすめできる仕事です。業務では労働現場の実態調査を行い、企業に対して法令遵守の指導を行うことも多いです。
例えば、長時間労働が常態化している企業に対して是正指導を行ったり、労働災害の原因調査に赴くなど、働く人の安全確保に直接貢献します。
責任感が強く、人のために動きたい人にはやりがいを感じやすい職種です。
③出入国在留管理官
出入国在留管理官は入国管理局に所属し、外国人の入国や在留の管理、適法な在留資格の審査、難民認定などを担当します。多文化共生と安全の両立を図る重要な役割です。
語学力や異文化理解が求められ、国際社会に関心が高い学生にとって魅力的な仕事です。実務では、外国人の入国審査や不法滞在者の摘発、国際的な人権問題への対応も含まれます。
例えば、正規のビザを持たない不法滞在者を発見し、法に基づく対応を行いながら、必要に応じて支援も実施します。緊張感のある現場での判断力が問われますが、その分やりがいも大きい職種です。
④財務専門官
財務専門官は財務省に所属し、国の財政運営や予算編成、歳出の監視などを専門的に担当します。経済・財政の専門知識を活かし、持続可能な財政運営に貢献します。
経済や数字に強い学生に特に向いています。業務は政策分析や財政計画の立案が中心で、国の予算配分を決定づける責任あるポジションです。
例えば、社会保障費の適正管理や公共事業の予算配分の最適化など、国民生活に直結する政策の財政面を支えます。緻密な分析力と判断力が求められる高度専門職と言えるでしょう。
⑤食料農業行政職
食料農業行政職は農林水産省に所属し、農業政策の立案・実施や食料安全保障の確保に携わります。農業の振興や品質管理、環境保全など幅広い分野で活躍します。
農業や環境問題に興味を持つ学生におすすめです。地域の農業者と密接に連携しながら政策を実行し、現場の課題解決に取り組みます。
例えば、持続可能な農業技術の普及や食料輸入の監視を行い、国民の安全な食生活を支えます。理系・文系問わず活躍の場が広い、社会的意義の大きい職種です。
国家公務員になるには
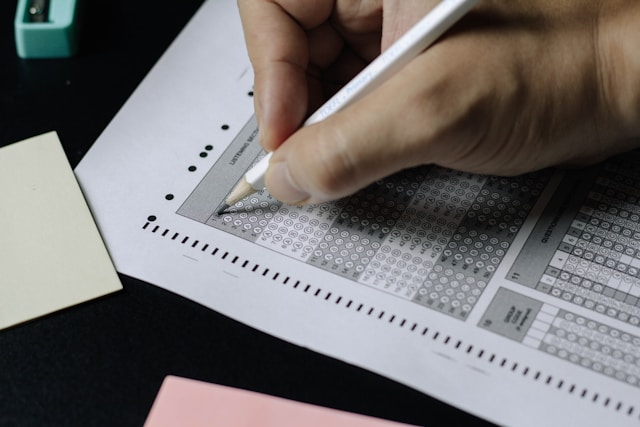
国家公務員を目指すには、単に試験を受けるだけではなく、段階的かつ計画的な準備が欠かせません。
まずは、自分に合った試験区分を見極めたうえで、受験資格の確認、筆記試験対策、人物評価の準備、そして志望動機の言語化などを行う必要があります。
特に、民間企業の就活と並行する学生にとっては、スケジュールや対策の進め方が大きな鍵となります。以下では、国家公務員を目指すうえで必要なステップを順を追って詳しく解説します。
- 試験区分を選択する
- 受験資格と日程を確認する
- 筆記試験に向けて準備する
- 人物評価対策を行う
- 志望動機やESを準備する
①試験区分を選択する
国家公務員試験には複数の試験区分が存在し、それぞれ役割やキャリアの方向性が異なります。そのため、自分の将来像や関心分野と照らし合わせながら、最適な区分を選ぶことが極めて重要です。
国家総合職は、中央省庁で政策立案に関わるエリートコースで、社会課題に制度や法律でアプローチしたい人に向いています。
一方で国家一般職は、実際の現場で国民に近い立場で行政を支えるポジションが多く、堅実かつ安定志向の学生に人気があります。
国家専門職は、税務・労働・公安・外交などの分野で専門性を活かす働き方が特徴で、自分の得意分野を活かしたい人には魅力的でしょう。
就活が本格化する時期に焦って決めるのではなく、情報収集を通じて違いを正しく理解し、後悔のない選択をすることが大切です。
②受験資格と日程を確認する
国家公務員試験は、年度ごとに受験資格やスケジュールが公表されます。大学3年生のうちから志望区分ごとの要項を把握しておくことで、後から慌てることなく計画的に動くことができます。
国家総合職では「大学院卒業程度」などの受験区分もあり、同じ学年でも受験できる区分に違いが出てきます。
さらに申込期間は早ければ3月中旬ごろから始まり、筆記試験は4〜6月に集中するため、民間のエントリーシートや面接と重なってしまうこともあります。
そうした事態を防ぐには、各試験の公式ホームページを定期的に確認しておくのが賢明です。
試験区分や年齢制限の見落としは取り返しがつかないため、「いつ・どの区分に・どうやって」挑むのか、早期に方針を立てておくと安心です。
③筆記試験に向けて準備する
国家公務員試験の最初の大きな関門が筆記試験です。教養試験や専門試験、さらに論文など、多様な試験形式に対応する必要があり、対策には時間がかかります。
特に大学の授業や民間就活と並行する場合は、効率的な勉強法が求められます。
教養試験では、数的処理や文章理解、時事問題など幅広い分野が出題され、基礎学力とバランスのよい知識が問われます。
専門試験は、法学・経済・行政学など各自の区分に応じた深い理解が必要であり、出題範囲も広いため早めの取り組みが鍵です。
公務員試験用の参考書や過去問に加え、模試やアプリの活用も有効です。自分の苦手分野を早期に把握し、計画的に克服することが合格への近道になります。
大学生のうちにこれだけの量をこなすのは大変ですが、早めに始めることで負担を分散しやすくなります。
④人物評価対策を行う
筆記試験に合格しても、人物評価で不合格になるケースは少なくありません。それほど国家公務員にとって面接は重要であり、事前の準備が結果を左右します。
人物評価では、志望動機の一貫性、政策への理解、課題への意識、対話力などが問われます。
特に国家総合職では、政策課題に対して自分なりの見解を持っているかが重視され、時事問題の把握や論理的な構成力も求められます。
模擬面接を繰り返すことで、表現力や受け答えのクセにも気づけるはずです。表面的な対策だけでなく、行政への思いを自分の言葉で伝える準備が、面接官の心に響く材料になります。
⑤志望動機やESを準備する
国家公務員試験では、エントリーシート(ES)や志望動機の提出が求められることがあり、人物評価の材料としても重要な位置づけとなっています。
書き方ひとつで、あなたが本当に行政に関心を持っているかが伝わってしまうため、丁寧な準備が必要です。
志望動機を書く際には、「なぜ民間ではなく国家公務員なのか」「どのような分野で活躍したいか」「大学生活や課外活動で得たものをどう活かせるか」といった問いに答えられるようにしておきましょう。
また、ESの記載内容は面接時にも参照されるため、一貫性があることが求められます。
大学生のうちに、業務理解や職員のインタビューを通じて、自分なりの視点を持っておくと、他の就活生との差別化にもつながるでしょう。
「ESの書き方が分からない…多すぎるESの提出期限に追われている…」と悩んでいませんか?
就活で初めてエントリーシート(ES)を作成し、分からないことも多いし、提出すべきESも多くて困りますよね。その場合は、就活マガジンが提供しているES自動作成サービスである「AI ES」を使って就活を効率化!
ES作成に困りやすい【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】の作成がLINE登録で何度でも作成できます。1つのテーマに約3~5分ほどで作成が完了するので、気になる方はまずはLINE登録してみてくださいね。
受験区分ごとの仕事内容

国家公務員の仕事は、受験区分によって内容や求められるスキルが大きく異なります。行政事務系や技術系、公安系、さらに専門資格が必要な免許職など、選べる進路は多岐にわたります。
どの区分を目指すかによって、勉強の方向性や今後のキャリアビジョンも変わってきます。
自分に合った道を見つけるためには、それぞれの仕事内容を知り、興味や強みと照らし合わせて検討することが大切です。ここでは、代表的な4つの受験区分の内容を詳しく紹介します。
- 行政事務系の仕事内容
- 技術系の仕事内容
- 公安系の仕事内容
- 資格免許職の仕事内容
①行政事務系の仕事内容
行政事務系の国家公務員は、国の法律や制度を実際に動かすための“事務の専門家”です。
例えば、文部科学省では教育制度の調整や補助金の配分、厚生労働省では雇用対策や年金制度の運用など、多様な業務に携わります。
特に国会対応に向けた準備では、限られた時間で正確な情報を整理しなければならず、粘り強さと論理的な思考が試される場面も少なくありません。
自分の意見が政策の一部として形になったときの達成感は大きく、「社会全体に貢献している」と実感できる瞬間もあります。
人の話を丁寧に聞き、誰かの役に立ちたいという気持ちを持つ方に向いている仕事といえるでしょう。
②技術系の仕事内容
技術系の国家公務員は、大学などで学んできた理系分野の専門知識を活かして、国のインフラ整備や環境保全、科学技術振興などに貢献します。
例えば、国土交通省では道路やダムの設計・施工監督を、気象庁ではデータ分析をもとに気象予報や災害対策を担うなど、分野は多岐にわたります。
理系学生は、大学で学んだ内容が抽象的なままで終わってしまうこともありますが、技術系公務員なら“社会に使える技術”として現場で活かすことができます。
現場調査の実施や地域の自治体との連携も多く、専門性と実務能力のバランスが問われます。
また、法律や予算など文系的な知識も必要になるため、理系の視点に加え、広い視野を持って柔軟に動ける方に適しているといえるでしょう。
地道な努力を社会のかたちに変えたい方に、ぴったりの進路です。
③公安系の仕事内容
公安系国家公務員は、国の安全や秩序を守るという極めて重要な任務を担っています。
配属先は警察庁、出入国在留管理庁、皇宮警察などで、サイバー攻撃の防止やテロ対策、外国人の在留管理、皇室の護衛など、現場での対応も多く含まれます。
「現場志向が強い」「人の安全を守りたい」と考える方にとって、公安系は非常にやりがいのある職種です。
例えば、出入国在留管理庁では、不法滞在や在留資格の審査を行いながら、国際情勢にも目を配らなければなりません。
責任感の強い方や、変化のある現場に身を置きたい方には、非常に相性のよいフィールドです。
④資格免許職の仕事内容
資格免許職とは、医師、薬剤師、看護師、獣医師、保健師、航空管制官など、国家資格を有する人が就ける国家公務員の職種です。
所属機関は厚生労働省、防衛省、国土交通省などで、医療・防疫・航空管理など、国民生活を守る最前線で活躍します。
例えば、保健所での感染症対策や、空港での検疫業務、災害派遣の医療対応など、現場と行政の両面に関与できるのが特徴です。
国全体の健康や安全を支えるという視点で働けることに、誇りと使命を感じる方も少なくありません。
既に資格を取得している方、将来の取得を目指している方にとって、資格免許職はキャリアの幅を広げる可能性を秘めた進路といえるでしょう。
国家公務員の平均年収

国家公務員の平均年収は、配属先や職種、昇進スピードなどによって大きく変わります。
志望区分ごとに給与体系や手当の付き方が異なるため、具体的なキャリアパスとあわせて年収面を知っておくことは、職業選択のうえで非常に重要です。
ここでは、学生が特に気になる5つの主要職種について、平均年収の目安や収入の特徴を解説します。
- 国家総合職の年収水準
- 国家一般職の年収水準
- 国家専門職の年収水準
- 裁判所職員の年収水準
- 国会職員・法制局職員の年収水準
①国家総合職の年収水準
国家総合職は「官僚の花形」とも呼ばれ、中央省庁で政策立案などを担う中枢的な存在です。
そのため、他職種と比べて年収水準は高く、20代後半で500〜600万円、30代前半で700万円台に届くことも珍しくありません。
若手でも課長補佐や企画官など重要なポストに就きやすく、職責に応じた手当も加算され、収入はさらに伸びていきます。
人事院公式「国家公務員給与制度の概要」によれば、係長級で月額約47万円(年収約730万円)、課長補佐級で月額約59万円(年収約930万円)とのモデル例が掲載されています。
学生のうちから将来の収入や役割を意識することで、志望動機にも深みが出るでしょう。
②国家一般職の年収水準
国家一般職は各省庁の出先機関や本省で実務を担う職種です。
新卒初任給は約21万円程度で、地域手当・住居手当・扶養手当などが加わるため、生活基盤は安定します。昇給制度も整っており、30代になると年収400万円後半〜500万円台に達するケースが多いです。
人事院「令和5年 国家公務員給与等実態調査」によると、国家公務員全体の平均給与月額は約40.4万円、年収で約666万円と報告されています。
一般職ではやや下回る可能性がありますが、無理なく安定的に働きたい学生には安心の働き方が可能でしょう。
③国家専門職の年収水準
国家専門職は税務・労働・外交・入国管理などの専門分野に特化した職種です。
統一された公的統計は不足していますが、国税専門官のモデル年収は、国税庁公式「国税専門官 採用案内(PDF)」において、30歳で約625万円、40歳で約740万円、50歳で約900万円近い金額と示されています。
外交等の専門職は地域・危険地手当が加算されるため600〜800万円台のレンジになることもあります。
専門性を活かしつつ着実に収入を伸ばしたい学生におすすめです。
④裁判所職員の年収水準
裁判所職員は事務官や書記官として司法手続きを支える役割であり、高い正確性が求められます。
令和4年度の裁判所公式データによれば、平均年収は約628万円とされています(裁判所職員採用ガイド参照)。
書記官へ昇任すると500~600万円台へアップすることもあり、専門性と安定が両立しやすい職場です。
⑤国会職員・法制局職員の年収水準
国会職員(参議院事務局)や法制局職員は、深夜勤務・休日勤務が多く、超過勤務手当が充実しています。
参議院公式「採用Q&A」では、令和7年初任給(短大卒・地域手当含む)が241,200円とあり、通勤・扶養・超過勤務手当が加わることで、30代で600〜800万円台になる可能性が高いと考えられます。
また参議院法制局の案内「初任給284,800円モデル」もあり、法学志望の学生には給与面でも魅力的です。
国家公務員と地方公務員の違い

国家公務員と地方公務員は、どちらも社会の基盤を支える重要な存在です。しかし、採用制度や勤務地、仕事の内容、キャリアの築き方にははっきりとした違いがあります。
特に就活中の学生にとっては、「将来の働き方」や「どこで、誰のために働くか」を見極める上で、両者の違いを知ることは不可欠です。
ここでは、代表的な5つのポイントに沿って、学生目線でも理解しやすいように解説します。
- 採用方法の違い
- 勤務エリアの違い
- 業務内容の違い
- 人事制度の違い
- キャリアパスの違い
①採用方法の違い
国家公務員と地方公務員では、まず採用の入口からして大きく異なります。
国家公務員は総務省の管轄する「国家公務員試験」に合格することが必要で、試験区分も総合職・一般職・専門職と分かれており、それぞれに応じた対策が求められます。
全国で一斉に実施されるため、倍率も高く、学力だけでなく計画的な準備が必要です。
一方で、地方公務員は都道府県や市区町村などの自治体ごとに独自の採用試験を実施しており、試験日程や内容も自治体によって大きく異なります。
試験制度の違いをしっかり理解して、志望先に合わせた準備を進めてください。
②勤務エリアの違い
働く場所の違いは、将来のライフスタイルに大きく影響します。国家公務員はその名の通り“国全体”を対象にするため、中央省庁を中心に、全国各地への異動が基本となります。
特に総合職の場合は、幹部候補として様々な地域で経験を積む必要があるため、転勤が前提となる働き方です。
一方、地方公務員は原則として採用された自治体の範囲内で勤務します。地元に残って働きたい人や、家庭の事情で引越しが難しい人にとっては、安心感のある働き方といえるでしょう。
就活生としては、自分の将来像と働く地域の関係を真剣に考えることが大切です。
③業務内容の違い
仕事内容についても、両者には明確な違いがあります。国家公務員の仕事は「国全体の制度やルールをつくる」ことが中心です。
中央省庁の職員として、他国の担当者と交渉する場に立つこともあれば、法令改正のための調査・企画といったスケールの大きな課題に取り組むことが出来ます。
一方で、地方公務員は「住民一人ひとりの生活に密着した支援」を行います。市役所での窓口業務、福祉サービス、防災対策、教育支援など、地域に根差した課題解決が主な役割です。
就活生の目線で考えると、「広く国の仕組みに関わりたいか」「地域社会に直接貢献したいか」で、自分に合った方向性を見極める必要があります。
どちらもやりがいのある仕事ですが、求められる視点や関わる相手が大きく異なる点に注目してください。
④人事制度の違い
働き始めてからのキャリア形成にも、制度面で差があります。
国家公務員は人事制度が非常に体系化されており、職員の能力や成果に応じた評価や昇進が行われます。
総合職の場合は、「幹部候補」としてのルートが明確であり、若手のうちから様々なポジションを経験する中で成長していくことが期待されます。
一方で、地方公務員の人事制度は自治体ごとに異なり、比較的柔軟な運用がされることが多いです。
学生としては、「決められた階段を上がっていきたいのか」「その地域に合った柔軟なキャリアを歩みたいのか」といった視点で考えると、自分に合った環境が見えてくるはずです。
⑤キャリアパスの違い
国家公務員と地方公務員では、将来のキャリアの広がり方にも違いがあります。
国家公務員の総合職は、20代のうちから政策形成の中心を担うこともあり、将来的には課長級・局長級といった幹部ポストに就くルートが期待されます。
また、海外出張や国際会議への参加、他省庁との連携など、視野の広い経験を積めることも大きな魅力です。
一方、地方公務員は長く同じ自治体で働くことを前提としながら、地域の課題解決に一貫して取り組むスタイルです。
地元の人と信頼関係を築きながら行政サービスを向上させていく中で、自治体の中核人材として育っていくことが求められます。
自分の価値観や将来の理想像を明確にすることで、後悔のない進路選択につながります。
公務員試験の難易度別区分
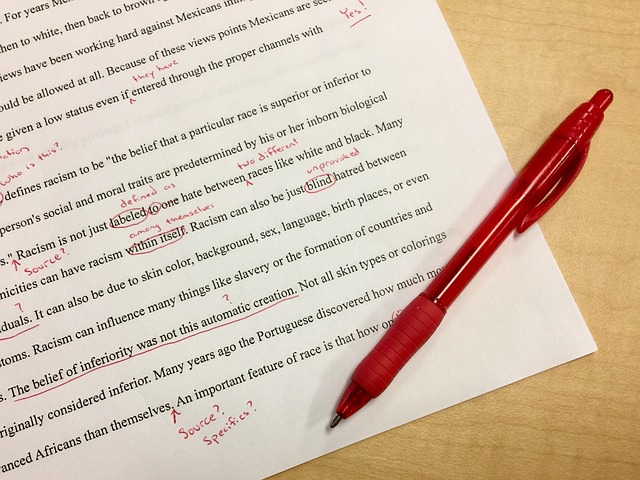
公務員試験には複数の区分があり、それぞれ難易度に大きな差があります。
漠然と「安定しているから公務員を目指す」と考える学生も多いかもしれませんが、実際には求められる準備期間や専門知識、倍率などが職種によって異なります。
ここでは、主に倍率の高さ、専門知識の有無、初学者向けかどうかの観点から、試験区分ごとの難しさを具体的に解説します。
- 倍率の高い試験区分
- 専門知識が求められる試験区分
- 初学者向けとされる試験区分
①倍率の高い試験区分
もっとも競争が激しいのは「国家総合職」や「裁判所職員総合職」などのハイレベルな区分です。
人気の理由は、政策形成や法律運用といった高度な業務に若いうちから関われる点や、将来の昇進スピード、待遇面の安定感が挙げられます。
特に総合職は「官僚の登竜門」とも呼ばれ、東大や京大をはじめとする難関大の学生が数多く挑戦することから、1年〜1年半以上かけて専門科目・論文・面接まで綿密に準備する必要があります。
成績上位層が集まりやすいため、「とりあえず受ける」という姿勢では太刀打ちできません。本気で目指すなら、大学3年の夏頃には対策を始めるべきでしょう。
②専門知識が求められる試験区分
専門職系の区分では、大学で学んできた内容や取得済みの資格が問われることが多くなります。
技術職(土木・建築・情報など)や、資格職(税務職員、労働基準監督官など)は、一般教養に加えて理系・法律・経済といった専門分野の理解が合否を大きく左右します。
これらの試験は出題範囲が明確で、事前に学習計画を立てやすい反面、「苦手分野がそのまま致命傷になる」構造でもあります。
文系出身であっても経済原論や憲法・民法を独学で学ぶ必要がある場合があり、理系なら大学の実験・研究と並行しての勉強になるため、時間管理力も問われます。
自分の専門性を活かせる職種を選ぶことで効率的な準備ができますが、早めに問題傾向を把握しておいたほうがよいでしょう。
③初学者向けとされる試験区分
「公務員に興味はあるけど、何から始めればいいかわからない」という学生には、国家一般職や地方初級・中級といった比較的入り口の広い区分がおすすめです。
これらは基礎的な教養科目が中心で、独学でも対策しやすい点が魅力です。
実際、国家一般職では文章理解・数的処理・人文科学などが出題の中心を占めており、大学の一般教養と重なる内容も多く、コツコツと取り組めば着実に力がついてきます。
他区分に比べて学習のハードルが低めなため、「まずは挑戦してみたい」という学生にとっては非常に現実的な選択肢です。
国家公務員に向いている人の特徴

国家公務員は、国の根幹を支える制度や仕組みを企画・運用し、広く社会全体に影響を与える職業です。
そのため、自分自身の性格や価値観が国家公務員に向いているのかを理解しておくことが、志望動機や面接対策でも重要になります。
ここでは、国家公務員に向いているとされる人物像を5つの観点から詳しく解説します。自己分析やES作成の参考として、自分の特性と照らし合わせながら読んでみてください。
- 使命感と公共意識を持つ人
- 論理的思考力に優れた人
- 柔軟性と協調性がある人
- 専門分野に強みを持つ人
- 全国異動に前向きな人
①使命感と公共意識を持つ人
国家公務員に必要とされるもっとも基本的な資質は、「誰かの役に立ちたい」「社会を良くしたい」という強い使命感と公共意識です。
国家公務員は民間企業とは異なり、利益を追求するのではなく、国民全体の幸福や社会の安定を目的として働きます。
例えば、災害対策、教育支援、少子化対応といった社会課題に取り組む中で、自分の仕事が多くの人の暮らしに直接影響する場面が数多くあります。
学生のうちからボランティア活動に関心がある人や、自治体の仕組みに興味を持ったことがある人は、この資質に近いかもしれません。
自己PRでも「公共の利益を大切にしている」姿勢を具体的な経験を交えて伝えることで、志望理由の説得力が増すでしょう。
②論理的思考力に優れた人
国家公務員の業務では、政策の立案や制度設計など、複雑な社会課題に向き合う機会が多くあります。そのため、物事を論理的に整理し、筋道を立てて考えられる力が欠かせません。
複数の要因が絡む問題に対して、感情ではなく事実と根拠に基づいて冷静に判断する力が重要になります。
例えば、ゼミ活動でデータ分析を行った経験や、ディベートサークルで立論の構成にこだわった経験がある学生は、この力をアピールしやすいでしょう。
また、面接でケーススタディのような課題が出された際にも、論理的に答えを導けるかが評価されます。理系・文系を問わず、日頃から「なぜそうなるのか」を意識して考える習慣をつけることが大切です。
③柔軟性と協調性がある人
国家公務員の仕事は、省庁内のチームだけでなく、他の官公庁、地方自治体、さらには民間企業や住民との協働によって成り立っています。
多様な立場の人々と関係を築きながら、調整・合意形成を進めるには、高い協調性と状況に応じた柔軟な対応力が必要です。
例えば、大学のグループワークやサークル運営で意見が分かれた際、メンバー間の調整役を担った経験がある場合、それは国家公務員に求められる力と重なります。
「自分の意見を押し通すのではなく、周囲の意見を尊重しながら最善策を導ける人」は、行政の現場で活躍できる可能性が高いでしょう。
社会人になればより多様な人と関わるようになるため、学生のうちから対人関係のスキルを磨いておくと安心です。
④専門分野に強みを持つ人
国家公務員には、一般的な行政職のほかにも、法律、経済、建築、情報、農業、科学技術など、さまざまな専門職があります。
特定の分野に対して強い関心や専門性がある人は、その力を公的な場で活かすことができます。
例えば、法学部で法律知識を深めてきた学生は、立法支援や法制度の運用に関わる仕事で活躍が見込めますし、理系学生であれば技術系の職種として、災害対策やインフラ整備などの現場で自らの知見を活かせます。
自分の専門が国家のどの業務に結びつくかを考えておくことで、エントリーシートや面接でより具体的な志望理由を述べることができるでしょう。
⑤全国異動に前向きな人
国家公務員の多くは、3~5年おきに全国各地へ異動するのが一般的です。そのため、特定の地域にこだわらず、さまざまな場所での勤務を前向きに受け入れられる人が向いています。
異動は大変そうに感じるかもしれませんが、様々な地域の課題や文化に触れることで、視野が広がり、より実効性の高い政策提案ができるようになります。
地方の現場で得た経験が、中央省庁での政策立案に生きることもあり、「現場を知ること」が大きな強みになります。
自己PRでも、「変化を成長のチャンスと捉える姿勢」を伝えると好印象です。
国家公務員の職種を理解し、自分に合った進路を見つけよう

国家公務員を目指すうえで重要なのは、各職種や試験区分の違いを正しく理解し、自分に合った選択をすることです。
国家総合職・一般職・専門職に加え、司法・立法府の職員など、国家公務員の職種は多岐にわたります。
それぞれ仕事内容や求められるスキル、年収水準も異なるため、志望先を検討する際には事前の情報収集が欠かせません。
さらに、公務員試験の難易度や地方公務員との違いも踏まえることで、より納得感のある進路選択ができるでしょう。
公共に貢献したいという強い思いを持ち、自己理解と職種理解を深めていくことが、国家公務員への第一歩となります。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










