面接でのグループディスカッションの書記の役割を解説|求められているスキルも紹介
「グループディスカッションでうまく発言できるか不安…」
そう感じている就活生は少なくありません。
しかし、発言以外にも評価される役割があるのをご存じですか?それが「書記」です。
書記は、議論を整理し、結論を導くまでの土台をつくる存在です。
実は、書記をうまくこなすことで、構造的思考力やチーム貢献力といったポイントをしっかりアピールできるのです。
本記事では、グループディスカッションにおける書記の役割や、選考で評価される力、成功のコツまでをわかりやすく解説します。
発言に自信がない人も、自分の強みを活かすチャンスとして、ぜひ参考にしてくださいね。
面接前に役立つアイテム集
- 1実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- あなたの志望動機を面接官に響く形へブラッシュアップできるテンプレート
- 3自己PRテンプレシート
- 面接官視点で伝わる構成に落とし込み、自分の強みをブレずに説明できるようにします。
- 4適職診断
- 60秒で診断!あなたが面接を受けるべき職種がわかる
- 5面接前に差がつく!ビジネスマナーBOOK
- 面接前に一度確認しておきたい、減点されやすいマナーポイントをまとめています。
グループディスカッションでの発言が苦手なら書記をやろう

就職活動で避けて通れないグループディスカッション(GD)に、苦手意識を持つ人も多いのではないでしょうか。
そんなときに検討してほしいのが、「書記」という立場です。発言が少なくても、議論の中で自分の強みを活かして貢献できるポジションとして注目されています。
実際に、書記をうまくこなすことで選考で高く評価された例もあるのです。
発言に不安がある方こそ、自分に合った方法で選考に臨むヒントを見つけてみてくださいね。
グループディスカッションにおける書記とは

グループディスカッション(GD)で書記を担当することは、貢献するための選択肢のひとつです。
特に発言が得意ではない人にとっては、自分らしいアプローチで参加できるきっかけになるでしょう。
たとえ目立つポジションでなくても、議事録への丁寧な取り組み方や冷静な視点はしっかりと見られています。
議事録をまとめる中で考えが浮かんだら発言したり、周囲と連携したりして、場への関わり方を工夫することがポイントになるでしょう。
グループディスカッションでの書記の役割

グループディスカッションにおける「書記」は、単なるメモ係ではありません。議論をまとめ、チームの理解を深める重要なポジションです。
ここでは、就活で評価される書記の具体的な役割を5つの視点から紹介します。
- 発言内容を記録して議論を整理する
- 全体の意見を把握して要点をまとめる
- 議論の進行をサポートする
- 対立点や合意点を明確にする
- 最終的な結論や発表内容を記録する
① 発言内容を記録して議論を整理する
書記の基本的な役割は、発言内容を正確に記録し、それを通じて議論を整理することです。ディスカッションが活発になると、意見が交錯し、話題があちこちに飛ぶことも少なくありません。
そんなとき、記録によって「誰が何を話したのか」「どんな意見が出ているのか」が整理されていれば、メンバーの頭の中も自然と整理され、話し合いがスムーズに進行します。
記録はすべて書き起こす必要はありません。大切なのは、発言の要点を簡潔に抜き出し、全体の流れがわかるようにまとめることです。
記録があることで、議論の振り返りや発表準備もスムーズになり、結果的にチーム全体の完成度が高まるでしょう。
② 全体の意見を把握して要点をまとめる
書記は、ただ目の前の発言を記録するだけではなく、チーム全体の意見を俯瞰する視点が求められます。
複数人の意見が出揃う中で、何が本質的な論点なのか、どこに話の焦点が集まっているのかを見極める力が必要です。
書記が要点を整理できていれば、メンバー全員の頭の中もクリアになり、発言が活性化する効果も期待できます。
話が混乱しがちな場面でも、まとめ役として機能できる書記は、まさに縁の下の力持ちです。
③ 議論の進行をサポートする
書記はファシリテーターではないものの、議論の流れに影響を与える場面は多くあります。
たとえば、話が堂々巡りになったときや、意見が出尽くして停滞したときに、「ここまでの意見を整理するとこうですね」と一言添えるだけでも、議論が前進するきっかけになります。
このような場面で適切に動ける書記は、非常に評価されやすい存在です。
書記の視点を活かして、議論を滑らかに進めるサポート役として動けると、チーム内での信頼感も増し、結果として自分の評価にもつながっていくでしょう。
④ 対立点や合意点を明確にする
ディスカッションでは、意見が対立するのはむしろ自然なことです。重要なのは、対立を恐れずに「どこがズレているのか」「どこに共通点があるのか」を客観的に示すことです。
書記がこの役割を担えると、議論は建設的に進みやすくなります。
議論が混乱しているときでも、対立軸や論点が可視化されれば、メンバー全体が冷静に次の判断を下せるようになります。
記録を通じて論点の構造を明確にする書記の存在は、まさに議論の「舵取り」を間接的に担っていると言えるでしょう。
⑤ 最終的な結論や発表内容を記録する
グループディスカッションの終盤では、これまでの話し合いをもとに結論を導き出し、全体で発表に向けた準備を進めていきます。このとき、書記が記録したメモがチームの「道しるべ」となるのです。
発表者が迷わずに話せるのは、書記の記録が明確にまとめられているからにほかなりません。
結論部分だけでなく、その背景や理由、対立から合意に至ったプロセスも簡潔に記録しておくと、発表内容に説得力が生まれます。
最終的に「伝わるまとめ」ができているかどうかが、書記としての評価に大きく関わるポイントとなるでしょう。
グループディスカッションの書記は選考に不利なの?

書記を務めたからといって評価が下がることはありません。むしろ、役割を通じてアピールできる点も多く、評価されるケースも十分にあります。
要所で発言しながら、全体の意見を整理し、議論の流れを見ながら的確に記録できれば、企業側から高い評価を受ける可能性もあるでしょう。
企業が重視しているのは「チームにどのように貢献したか」です。目立つことや発言数の多さだけが評価の対象ではありません。
書記としての役割を果たしつつ、自分の考えも簡潔に伝えられれば、選考において十分にアピールにつながります。
グループディスカッションで書記に向いている人の特徴

書記はグループディスカッションの中でも、やや特殊なポジションです。自分に合っているかを見極めれば、より自然に、かつ高く評価される動きができるようになるでしょう。
ここでは、書記に向いている人の特徴を5つ紹介します。
- マルチタスクが得意な人
- 高い集中力を維持できる人
- 要点を素早く捉えるのが得意な人
- 他者の意見を冷静に受け止められる人
- 客観的な視点で記録できる人
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
① マルチタスクが得意な人
書記は、発言を聞きながら記録を取るという複数の作業を同時にこなす必要があります。
話の流れを理解しつつ、誰が何を言ったのか、どういう意味合いかを瞬時に捉え、それを簡潔にまとめていく作業が求められます。これは想像以上に頭を使う仕事です。
加えて、ディスカッション中にメンバーから「いまの意見をまとめてくれる?」と頼まれたり、議論が煮詰まった際に整理役としての補助を求められたりすることもあるでしょう。
そうした瞬間にも、パニックにならず複数のタスクを冷静に処理できる人は、非常に重宝されます。書記は目立たなくても重要な立場。マルチタスク力がある人ほど、その価値を発揮できるでしょう。
② 高い集中力を維持できる人
グループディスカッションは20〜30分という限られた時間で進行しますが、その間にさまざまな意見や視点が飛び交います。
書記はその全体を把握し、正確に記録し続ける必要があるため、常に高い集中力を維持することが求められるのです。
集中力を切らさず、議論の軌道を見失わずに記録し続けられる人は、全体の流れを整理する役割としても信頼を得やすいでしょう。
地味なようでいて、集中力の高さは書記における大きな武器です。
③ 要点を素早く捉えるのが得意な人
書記には、会話の中から重要な情報を瞬時に見抜く力が欠かせません。すべての発言をそのまま書き留めていては、時間も紙面も足りませんし、あとで見返したときに肝心なポイントが埋もれてしまいます。
そのため、話の「核」になる部分をいかに素早く、的確に切り取れるかが問われるのです。また、発言の背景や意図を考えながら整理するスキルも求められます。
ときには抽象的な意見をかみ砕いてメモする力、論点がブレているときに要点だけを抜き出す判断力も必要です。要約のスキルが高ければ、議論の流れも整い、他のメンバーの理解にもつながります。
情報処理に強い人にとって、書記はその力をアピールする絶好のポジションです。
④ 他者の意見を冷静に受け止められる人
ディスカッションでは、さまざまな考え方や視点が交わります。なかには自分とは異なる意見に出会い、驚いたり戸惑ったりすることもあるでしょう。
しかし、書記に求められるのは、個人的な好みや立場を離れて、あくまで中立的な立場で発言を受け止める姿勢です。
自分の考えに引きずられてしまうと、記録が偏ったり、特定の意見だけを重視したりする原因になります。どんな意見にも敬意を払い、公平に記録できる人は、議論を支える存在として信頼されます。
また、意見がぶつかったときにも、感情に流されず冷静な態度を保てる人は、グループ全体の安定感にも貢献できるでしょう。人の話を一歩引いて受け止める冷静さは、書記に欠かせない資質です。
⑤ 客観的な視点で記録できる人
書記には、ただ言われたことを写すだけでなく、「いまグループ全体がどういう状況にあるのか」を見渡す視点が必要です。
特定の発言にばかり注目してしまうと、議論のバランスが崩れたり、チームの合意形成が妨げられるおそれもあります。そこで大切になるのが、常に一歩引いた視点を持ち続ける姿勢です。
全体の構造を把握しながら、要点や流れを整理する力がある人は、書記としても安心して任されるでしょう。
主観を抑え、常に全体を見ながら冷静に対応できる人に最適なポジションです。
グループディスカッションの書記に求められる力

書記は単なる記録係ではなく、チーム全体の議論を支える役割です。正しく貢献できれば、企業からの評価にもつながるのです。
ここでは、書記として期待される具体的なスキルを紹介します。
- リスニングスキル
- 情報を簡潔にまとめる力
- 議論を構造化する力
- 読みやすく伝える文章力
- 議論の流れを把握する理解力
① リスニングスキル
書記にとって最も重要なのが、相手の話を正確に聴き取る力です。発言の聞き漏れや誤解があると、記録が不正確になり、チーム全体に混乱を招くおそれがあります。
ただ言葉をそのまま書き残すのではなく、「何を伝えようとしていたのか」という意図をくみ取る姿勢が求められます。
話し手の表現が曖昧なときにも、背景や前後の流れから意味を補いながら理解しようとする姿勢が大切です。
書記としてのリスニング力は、単なる記録を超えて、グループ全体の理解を支える核になります。
② 情報を簡潔にまとめる力
グループディスカッションでは、限られた時間内に多くの情報が飛び交います。そうした中で、すべてを記録するのではなく、要点を見極めて簡潔にまとめる力が求められるのです。
たとえば「結論」「理由」「具体例」など、情報の型を意識してまとめることで、誰にとってもわかりやすい記録が作成できるでしょう。
また、記録の目的は「あとから見返したときに、すぐに内容が理解できること」です。簡潔で的確な記録は、最終的にチームの成果物として提出されることもあるため、評価の対象にもなります。
シンプルで無駄のないまとめ方を意識できる人は、書記において非常に重宝されるのです。
③ 議論を構造化する力
ただ意見を並べて記録するだけでは、議論の進行や結論が分かりづらくなってしまいます。書記には、議論の流れを俯瞰しながら、論理的に整理して記録する「構造化」の力が求められるでしょう。
たとえば、「課題 → 原因 → 解決策」といったロジックの型を用いて意見をまとめると、メンバーの頭の中も整理されやすくなります。
この力があると、議論が脱線したときに「いまどこにいて、次に何を考えるべきか」がわかるようになるため、ファシリテーターのような視点でも貢献できます。
議論を単なる記録で終わらせず、全体の構造を整えることで、チームの生産性を大きく高められる存在になれるでしょう。
④ 読みやすく伝える文章力
議論の内容をどれだけ正確に記録しても、それが他のメンバーにとって読みづらい内容であれば意味がありません。書記には、記録を「他者に伝える手段」として意識できる文章力が必要です。
わかりやすい言葉で、簡潔に、かつ視認性の高い形で記録する力が問われます。
また、オンラインディスカッションではGoogle Docsやチャット機能などを通じて記録がリアルタイムで共有されるため、読みやすさはより一層重要になるでしょう。
全員が同じ情報を同じ理解で把握できるよう、見やすく伝わる文章を意識してください。
⑤ 議論の流れを把握する理解力
書記には、今グループがどこにいて、これから何を話すべきかを理解する力が欠かせません。
単に話を聞くだけでなく、全体の文脈を把握しながら記録する「議論の地図を描くような視点」が求められます。
理解力に優れている人ほど、議論の流れをつかみやすく、記録の中でも適切に表現できるのです。
単なる記録にとどまらず、「議論の道しるべ」として機能する書記になれれば、チームからの信頼も厚くなるでしょう。
グループディスカッションで書記をする際のコツ

書記としての働きがうまくいけば、議論の流れを整理し、チーム全体のパフォーマンスを高められます。正確かつ効率的に記録をとるためには、事前の準備といくつかの工夫が大切です。
ここでは、実践に活かせる5つのコツを紹介します。
- 発言者・内容・要点を分類して記録する
- 重要な意見と補足情報を分けて書く
- テンプレートを事前に準備しておく
- ロジックツリーやマトリクスを活用する
- 発表者も兼任して全体をまとめる
① 発言者・内容・要点を分類して記録する
書記が記録を取るとき、単に発言をそのまま書き留めるだけでは、後で見返した際に情報の整理が難しくなります。
そこで効果的なのが、「誰が」「何を」「なぜ」といった要素を明確に分類して記録することです。
この形式に慣れておけば、記録のスピードも上がり、同時に情報の抜けや偏りも防げます。また、発言者を明記しておくと、発表や質疑応答の場面で「この意見は誰が言っていたか」が明確になります。
誰がどの視点で話していたかを把握することは、議論全体の構成を理解するうえでも非常に有効です。整理された記録は、発表者や他のメンバーにとっても心強い支えになります。
② 重要な意見と補足情報を分けて書く
議論が進むと、メンバーの発言は増えていき、重要な意見とそうでない情報が入り混じっていきます。
たとえば、メモ内で強調表示や記号(「★」「→」など)を使って、意見の重要度に段差をつけておくと良いでしょう。
また、補足情報は文末に「補足:~」と付け加えるなどの工夫で、主要な論点が埋もれるのを防げます。
時間に追われる場面でも、あらかじめ整った情報があることで、冷静にまとめ作業を進められるようになります。
③ テンプレートを事前に準備しておく
書記の記録作業をスムーズに行うためには、事前にテンプレートを用意しておくことが効果的です。白紙の状態から即興で枠を作るのは非効率ですし、焦りが出てしまうと記録の精度も落ちてしまいます。
テンプレートには、発言者欄・発言内容欄・要点欄を設けたり、話題ごとに区切れるスペースを確保したりするなど、目的に合わせた設計が必要です。
特にオンラインでのGDでは、Google Docsなどで作成したテンプレートをリアルタイムで共有すれば、他のメンバーとの連携も取りやすくなります。
準備の段階で差が出るのが、書記という役割の大きな特徴です。
④ ロジックツリーやマトリクスを活用する
議論を記録していく中で、情報が複雑になってきたときに便利なのが、図解を用いた整理方法です。例として、「ロジックツリー」や「マトリクス」が挙げられます。
ロジックツリーは、ある結論に至るまでの原因や要素を枝分かれで示す形式で、因果関係や理由の深掘りを明確にするのに役立ちます。
一方、マトリクスは、複数の案を比較する際に「コスト」「効果」「スピード」などの軸で整理するのに適しているのです。
こうした図を議論の途中で取り入れると、メンバー全員の理解が深まり、議論が可視化されることで認識のズレも減ります。
⑤ 発表者も兼任して全体をまとめる
書記がそのまま発表も兼任することで、議論の内容を一貫して把握し、的確に伝えられます。
記録を取っていた本人だからこそ、話の流れや重要ポイントを自然に整理して伝えられ、説得力のある発表につながるでしょう。
発言を聞きながら、「これは発表で使えそう」「ここはまとめに入れよう」と意識しながらメモを取る習慣をつけておくと、後の作業がスムーズになります。
役割が重なる分、責任も大きくなりますが、それを前向きに引き受ける姿勢は、選考でも好印象を与えるはずです。
グループディスカッションで書記をするときの注意点
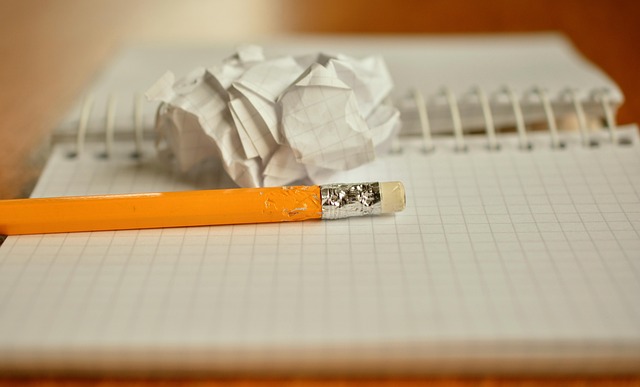
書記はチームの議論を支える重要な役割ですが、やり方を誤ると評価を下げてしまうおそれもあります。
ここでは、書記として円滑に役割を果たすために意識すべきポイントを紹介します。
- 発言量が少なくならないよう意識する
- 下を向きすぎて表情が硬くならないようにする
- 字を丁寧に書き、誤字脱字を避ける
- 結論と意見を混同しないようにメモを取る
- チーム内で役割を共有して負担を分散する
① 発言量が少なくならないよう意識する
書記の作業に集中しすぎると、どうしても発言の機会が減ってしまいがちです。
就職活動の選考では「どれだけ積極的に関われたか」も重視されるため、記録に徹しているだけでは評価につながりにくいでしょう。
自分の意見を述べるタイミングを逃さず、適切な場面で発言する姿勢が大切です。たとえば、議論の流れが一段落したときや意見が分かれた場面で、自分の考えを一言加えるだけでも存在感を示せます。
記録と発言を両立するのは簡単ではありませんが、「短くても的を射た発言」ができれば、役割を果たしながら主体性もアピールできるはずです。意識的にチャンスを見つけて話すことを心がけてください。
② 下を向きすぎて表情が硬くならないようにする
メモを取るためにずっとうつむいていると、表情が相手に見えにくくなり、話を聞いていないような印象を与えてしまうことがあります。
面接官や他の参加者に対して「反応が薄い」「会話が通じにくい」と思われると、評価が下がる可能性もあるでしょう。
そうならないように、ときどき顔を上げてうなずいたり、話している相手の目を見るなどの工夫が必要です。
たとえ言葉を発していなくても、相づちや視線を送るだけで「きちんと聞いている」という印象を与えられます。表情や態度でのリアクションも、コミュニケーションの一部ととらえて意識しましょう。
③ 字を丁寧に書き、誤字脱字を避ける
書記が作成するメモは、チームの議論内容をまとめた重要な情報源になります。そのため、読みづらい文字や誤字脱字があると、内容が正確に伝わらなくなり、メンバー全員の理解にも影響が出てしまいます。
記録するスピードも大切ですが、誰が読んでも分かるような丁寧さが求められるのです。
とくに画面共有やホワイトボードで他の人と情報を共有する場合、文字の大きさやバランス、改行のタイミングなどにも気を配ってください。
見やすさを意識した書き方ができれば、それだけでチームからの信頼感も高まります。急いでいるときほど、基本的な丁寧さを忘れないようにしましょう。
④ 結論と意見を混同しないようにメモを取る
個人の発言と、グループとしてまとまった結論がごちゃまぜになっていると、発表時に混乱が生じます。書記としては、誰の意見かをしっかり区別しながらメモを取ることが求められるでしょう。
「〜さんの意見」「全体の合意点」といった見出しを設けて分類しておくと、あとから見返しても整理しやすくなります。
また、メモの構成を段階的に分けて記録することで、議論の流れも見えやすくなるのです。
情報を正しく分類し、伝える意識を常に持っておいてください。
⑤ チーム内で役割を共有して負担を分散する
書記の仕事をすべて一人で抱え込むと、記録に集中しすぎて発言や全体の流れを見失ってしまうリスクがあります。そこで重要なのが、あらかじめ他のメンバーと役割分担をしておくことです。
たとえば「書記がメモを取り、進行役が時間配分と要点整理を担う」といった形にすると、負担が分散されてスムーズに議論が進みます。
役割を共有することで、メンバー同士の連携も強まり、チームとしての一体感も生まれやすくなるでしょう。
書記だからといって一人で抱え込まず、チーム全体でサポートし合える関係を築いていきましょう。
オンラインでグループディスカッションの書記を担当する場合のポイント

対面と違い、オンラインでのグループディスカッションでは進行や情報共有にひと工夫が必要です。特に書記の役割は、ツールの使い方やネット環境への理解が結果に直結するでしょう。
ここでは、オンラインならではのポイントを5つに分けて紹介します。
- Google Docsなどでリアルタイムにメモを共有する
- 音声の聞き取りミスを防ぐために録音の可否を確認する
- ZoomやMeetのチャット・画面共有を活用する
- 紙ではなくデジタルで素早く記録する
- 通信環境とデバイスの操作に慣れておく
① Google Docsなどでリアルタイムにメモを共有する
オンラインでのグループディスカッションでは、対面と比べて参加者の反応や発言の流れを把握するのが難しくなる場面があります。
そうした課題を補うために効果的なのが、Google Docsなどのクラウド型ドキュメントツールを使ったリアルタイム共有です。
書記が記録した内容を同時に全員で閲覧できれば、誰が何を言ったかを即座に確認でき、議論の方向性を常に一致させやすくなります。
リンクがうまく機能しなかったり、編集権限がなかったりすると混乱を招くおそれもあるため、事前に設定の確認をしておくと安心でしょう。
② 音声の聞き取りミスを防ぐために録音の可否を確認する
オンライン環境では、Wi-Fiの不安定さやマイクのノイズなどで音声が途切れてしまうことがあります。
そのため、大切な発言を聞き逃さないために、あらかじめ録音を検討しておくと安心です。
ただし、録音には必ず事前の許可が必要で、全員の同意を得ることが大前提となります。
録音は便利な反面、プライバシーの配慮が欠かせないため、活用には慎重さが求められます。
③ ZoomやMeetのチャット・画面共有を活用する
オンラインのグループディスカッションでは、音声だけのやりとりに頼っていると情報が抜けやすく、参加者間での認識に差が生まれがちです。
そこで役立つのが、ZoomやGoogle Meetに搭載されているチャット機能や画面共有機能です。
書記がメモの要点をチャットに記載すれば、参加者全員が即座に確認でき、議論の途中で方向性を再確認する際にも便利です。
こうした機能は「見える化」の補助ツールとして活用できるため、積極的に取り入れていくと良いでしょう。
④ 紙ではなくデジタルで素早く記録する
オンラインでの書記作業では、紙に手書きするよりも、パソコンやタブレットを使ったタイピングが圧倒的に有利です。
キーボード入力なら、素早くかつ正確に記録ができ、内容の整理や修正も柔軟に対応できます。
また、デジタルメモはそのまま議事録や発表資料としても使えるため、書き直す手間を省けます。
自分が使いやすいツールを事前に選んでおき、操作に慣れておくことで、当日のパフォーマンスにも大きく差が出てくるでしょう。
⑤ 通信環境とデバイスの操作に慣れておく
オンラインで書記を務めるうえで、通信環境の安定性と使用ツールの操作スキルは不可欠です。
音声が途切れたり、ツールの使い方がわからなかったりすると、記録どころではなくなってしまいます。
本番前には、必ずインターネットの接続状況を確認し、できるだけ安定したWi-Fiや有線接続を選ぶようにしてください。
ZoomやGoogle Meetなどで模擬的に接続テストをしておくと、当日の不安も軽減できます。
書記としての役割を十分に果たすためにも、ツールと環境の両方を整えておくことが大切でしょう。
発言が苦手でもグループディスカッションの書記でチームに貢献しよう!

グループディスカッションで発言に不安を感じるなら、書記という役割を選ぶのも1つの手です。
書記は、単なるメモ係ではなく、議論を整理しチームの意見をまとめる重要なポジションです。
役割を通じてリスニング力や要約力をアピールできるため、選考で不利になることはありません。むしろ、マルチタスクや論理的思考、冷静な観察力などを発揮できる絶好の機会です。
書記は、自分の強みを活かし、チーム全体に貢献できる重要な役割だと言えるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。









