【例付き】業界研究ノートのやり方|就活に効くまとめ方とは?
「業界研究ってどうやって進めればいいの?」「調べてもすぐに忘れてしまう…」就活を始めた多くの学生が直面するのが、業界研究の情報整理と活用の難しさでしょう。
そんなときにおすすめなのが、自分だけの業界研究ノートを作ること。情報をまとめて可視化することで、志望動機や企業選びの軸がグッと明確になります。
本記事では、業界研究ノートのやり方をゼロから丁寧に解説。作成の目的やメリット、具体的な書き方、活用のコツに加え、実際の記入例まで紹介します。
初めて業界研究に取り組む方や、情報整理が苦手な方にも役立つ内容になっていますので、ぜひ参考にしてください。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
業界研究ノートのやり方を理解しよう!
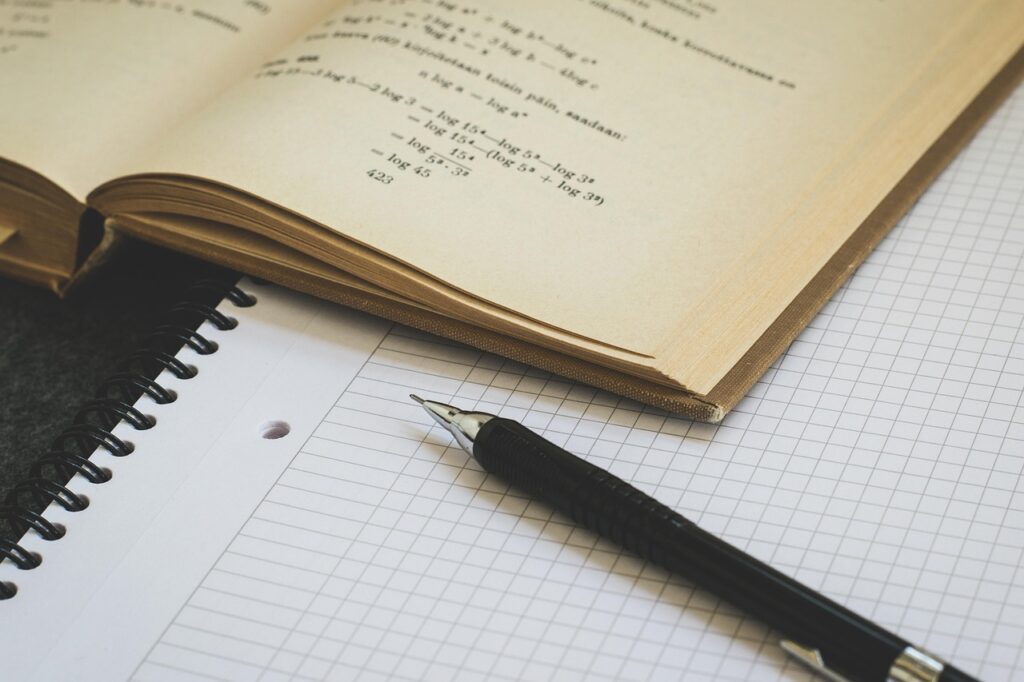
業界研究を進めるとき、情報を整理して理解を深めるにはノートの活用が効果的です。単に調べた内容を読むだけでは、記憶に残りにくく、他人に説明できるほどの理解にもつながりません。
しかし、ノートにまとめることで、自分の言葉として落とし込む力が育つでしょう。特に就活に不安を感じている人にとっては、情報を「見える形」にすることが安心材料になります。
志望動機を考えるうえでも、思考の過程を記録しておくと、後から振り返って説得力のある理由が導き出せるでしょう。
スマートフォンやパソコンでも情報管理は可能ですが、ノートを使うと自然に手を動かすことになり、考えを整理しやすくなります。さらに、自分が本当に大切にしたいことにも気づけるかもしれません。
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
業界研究ノートとは
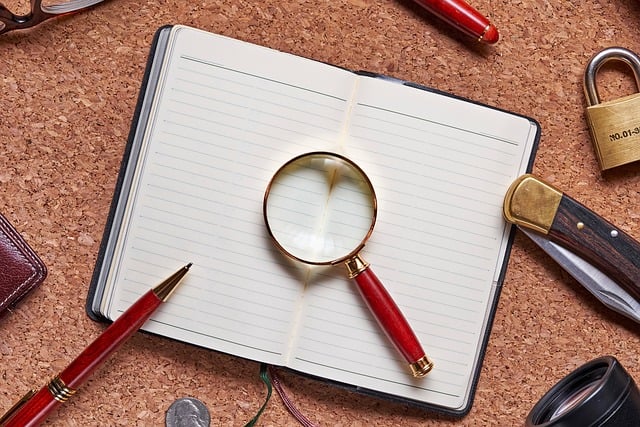
業界研究ノートとは、就職活動で自分が興味のある業界や企業についての情報をまとめるためのノートです。
企業選びや面接対策に役立つ大事な準備のひとつで、単なる情報のメモではなく、自分なりの視点や考えも書き込むことで、志望動機や自己分析にもつなげられます。
また、面接で「なぜこの業界を選んだのか」と聞かれたときに、具体的なデータや気づきをもとに話すことができるため、説得力もぐっと増すでしょう。
就活が本格化する前から少しずつ作っておけば、自己分析やエントリーシート作成にも活用でき、準備に余裕が持てるはずです。
いきなり情報収集を始める前に、まずは業界研究ノートの目的や役割をしっかり理解しておくことが、就職活動成功への近道と言えるでしょう。
業界研究ノートを作る目的

業界研究ノートは、就活を成功させるための重要なツールです。単に情報を整理するだけでなく、自分の考えや志望理由を深めるきっかけにもなるのです。
ここでは、ノートを作る目的を以下の4つに分けて紹介します。
- 志望動機の材料を整理するため
- 自分に合う業界を見極めるため
- 企業選びの軸を明確にするため
- 面接対策として活用するため
① 志望動機の材料を整理するため
志望動機は、就活で最も重視されるポイントのひとつです。そこで役立つのが業界研究ノート。
ノートに、自分がなぜその業界に惹かれたのか、どのような点に魅力を感じたのかを具体的に書き出してみてください。そうすることで、考えが整理され、言語化しやすくなります。
自分の視点で情報をまとめると、説得力のある志望動機を作る助けにもなるのです。志望理由に自信が持てない人ほど、ノートを使って思考を可視化することで方向性が明確になるでしょう。
② 自分に合う業界を見極めるため
「自分に向いている業界がわからない」と感じている人は少なくありません。そんなときこそ、業界研究ノートを活用してください。
さまざまな業界について調べ、それぞれの特徴や仕事内容を記録することで、自分の価値観や適性に気づけます。
また、ただ情報を書き写すのではなく、自分なりの感想や気づきも添えることで、どの業界に魅力を感じたのかが明確になるでしょう。
情報を受け取るだけでなく、考えを加えることが、業界選びの精度を高めるコツです。
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
③ 企業選びの軸を明確にするため
就活では、自分の中にある「企業を選ぶ基準」を持っていることが重要です。給与や知名度など、表面的な条件だけで決めてしまうと、入社後のミスマッチにもつながりかねません。
業界研究ノートに情報をまとめることで、何を大切にしたいのか、どんな職場環境を望んでいるのかといった軸がはっきりしてきます。
たとえば「働き方の自由度」「社会貢献性」「成長性」など、自分が納得できる軸を明文化することで、企業選びにも一貫性が出てくるはずです。
④ 面接対策として活用するため
業界研究ノートは、面接前の準備としてもとても有効です。自分でまとめた情報を見返すことで、質問に対する答えを整理しやすくなります。
「なぜその業界なのか」「この企業にどんな魅力を感じたのか」といった問いにも、ブレずに答えられるでしょう。
また、ノートに書いた言葉は自分自身の思考の結果ですから、面接でも自然に話しやすくなります。緊張しやすい人ほど、事前にノートで準備をしておくことで安心感が得られるはずです。
「業界分析」はこれ1冊だけ!業界分析大全を受け取ろう!
就活で志望業界を説得力高く語るには、「なぜこの業界なのか」をデータやトレンドで裏づける業界分析が欠かせません。とはいえ、IR資料やニュースを一から読み解くのは時間も手間もかかり、表面的な理解で面接に臨んでしまう学生も少なくありません。
そこで就活マガジン編集部では、主要20業界を網羅し「市場規模・最新トレンド・主要企業比較」まで1冊で整理した『業界分析大全』を無料提供しています。業界研究に迷ったら、まずはLINEを登録で特典をダウンロードして「面接で差がつく業界知識」を最短で手に入れてみましょう。
業界知識の深さは選考官が必ずチェックするポイントです。志望度の高さもアピールできるのでおすすめですよ。
業界研究ノートを作るメリット

業界研究ノートには、情報を整理するだけでなく、就活全体をスムーズに進めるための多くのメリットがあるのです。ここでは、ノートを作成することで得られる具体的な効果を紹介します。
- 就活でのアウトプット力が高まる
- 比較検討がしやすくなる
- 情報の見返しがしやすくなる
- 自信を持って就活を進められる
① 就活でのアウトプット力が高まる
業界研究ノートを作ることで、自分の考えを言葉にする力が鍛えられます。就活では、自己PRや志望動機を面接で伝える場面が多く、自分の言葉で分かりやすく話す力が求められるのです。
ノートに気づきや分析を書き留めておくと、情報が整理され、自然と言葉にしやすくなるでしょう。特に、業界への理解を具体的な内容で説明できると、面接官への印象も良くなります。
書くことを通じて頭の中が整理されるため、日々の積み重ねがアウトプット力の向上につながるのです。
② 比較検討がしやすくなる
業界研究ノートは、複数の業界を比べるうえで非常に便利です。
1つの業界に絞ってしまうと、選択肢が狭くなりがちですが、さまざまな業界の特徴や違いを並べて見ることで、自分に合った方向性が見つけやすくなります。
たとえば、「働き方」「将来性」「収益モデル」など、いくつかの視点から整理していくと、それぞれの業界の良し悪しが見えてくるでしょう。気づかなかった興味の対象にも出会えるかもしれません。
この比較が、後悔のない進路選びを後押ししてくれるはずです。
③ 情報の見返しがしやすくなる
就活では、数多くの企業を受ける中で情報が混在しがちです。そんなとき、自分でまとめた業界研究ノートがあると、必要な情報をすぐに見返せます。
ネット検索では情報が散らばりやすく、時間がかかることも多いですが、ノートに整理してあれば準備がスムーズに進みます。特にエントリーシートや面接前の確認では、その効果を実感するでしょう。
最新の情報と過去に調べた内容を比較しながら、理解を深めていくことも可能です。見返せる環境を整えておくことが、安心感にもつながります。
④ 自信を持って就活を進められる
業界研究ノートを丁寧に作っていくことで、自分の進路に対する不安を減らせます。情報を集めるだけでなく、自分の言葉で理解をまとめる作業は、知識の定着とともに自信にもつながっていきます。
他の就活生との差をつけたいなら、自分なりに掘り下げた内容が重要です。しっかり調べてノートにまとめた情報は、どんな場面でも説得力のある受け答えを支えてくれるでしょう。
迷ったときや不安なときに見返せるノートがあると、それだけで心強いはずです。
業界研究ノートを作成すべき人の特徴
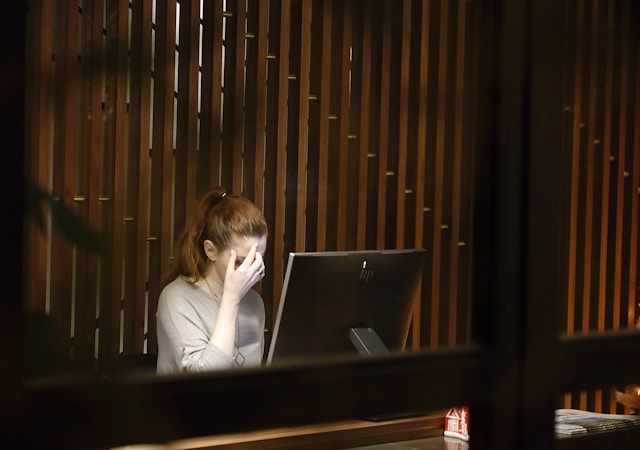
業界研究ノートは、就活を進めるうえで心強いサポートになります。ただし、すべての人に必要というわけではありません。どんな人にとって特に効果的か、ここで具体的に紹介します。
- 志望業界をある程度絞っている人
- 自己分析だけでは不安な人
- 就活の進め方に不安を感じている人
- 情報整理が苦手な人
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
① 志望業界をある程度絞っている人
すでに興味のある業界がいくつかあるなら、業界研究ノートがとても役立ちます。
たとえば「商社とメーカー」「金融とIT」など、選択肢の中で迷っているときには、特徴を比較しながらノートにまとめることで、自分にとって本当に合う業界が見えてくるでしょう。
ただ頭の中で考えるのではなく、情報を言葉にして整理すると、イメージだけでは気づけなかった違いにも気づけます。志望業界を絞る途中で迷っている人には、ノートの活用がおすすめです。
② 自己分析だけでは不安な人
自己分析をして「なんとなく自分の強みはわかったけれど、それをどう活かせばいいのか迷う」と感じていませんか?そんな人にこそ、業界研究ノートが効果的です。
業界ごとの特徴や働き方をまとめながら、自分の価値観と照らし合わせていくと、「自分に合う業界像」が少しずつはっきりしてくるはず。
情報をノートに書き出すことで頭の中も整理され、判断しやすくなるでしょう。
③ 就活の進め方に不安を感じている人
「何から始めればいいのかわからない」「自己分析ばかりで前に進めていない」といった不安を抱えている場合も、ノートを使うことで方向性が見えるでしょう
調べた内容を記録していくと、今の自分に足りない情報や次にすべき行動がはっきりします。また、手を動かすことで自然と就活に対する意識も高まるでしょう。
漠然とした不安を感じているなら、まずはノートを開いてみてください。
④ 情報整理が苦手な人
情報収集はしているけれど、あとで見返せなかったり頭に残らなかったりする場合は、ノートを活用してみましょう。情報を自分の言葉で書いていくことで、記憶に定着しやすくなります。
また、視覚的にまとまっていると、どこに何を書いたかもすぐに把握できます。調べっぱなしにならず、実際に使える情報として残しておける点が大きなメリットです。
整理が苦手な人ほど、ノートが頼れるツールになるでしょう。
業界研究ノートを作るために準備しておくもの

業界研究ノートをしっかり作るためには、事前に必要なアイテムをそろえておくことが大切です。ここでは、準備しておきたい具体的な道具を5つ紹介します。
- ノートやルーズリーフ
- 付箋
- ペンやマーカー
- 業界地図や就職四季報
- インターネット接続ができるデバイス
① ノートやルーズリーフ
業界ごとの情報を整理しやすくするには、ノートやルーズリーフの準備が欠かせません。特にルーズリーフは、ページの追加や入れ替えができるため便利です。
たとえば、業界別にページを分けたり、同じ形式で内容を書き進めると、あとから見返しやすくなります。
「業界の概要」「主な企業」「市場の動き」「自分の気づき」といった項目を決めておくと、情報が整理されやすいでしょう。
手書きにすることで頭に残りやすくなり、思考の整理にもつながります。自分にとって使いやすいスタイルを選んでください。
② 付箋
付箋は、情報の分類や目印づけに役立つ便利なアイテムです。特に、「あとで調べたいこと」「重要なポイント」などをメモするのに最適。
色を使い分けて貼っておけば、ノートの中から目的のページをすぐに見つけやすくなります。あとで貼り替えたり、内容を追加したいときにも、簡単に対応できるのが付箋の魅力です。
視覚的に整理しやすくなるため、情報が多くなってきたときほど、その効果を実感できるでしょう。
③ ペンやマーカー
複数の色を使えるペンやマーカーは、ノートの見やすさを大きく左右します。色を分けて書くだけで、重要な情報や分類が一目でわかるようになります。
たとえば、企業データは黒、業界の特徴は青、自分の考えは赤というように使い分けてみてください。色にルールを持たせることで、あとから内容を読み返すときの理解もスムーズになるでしょう。
図やフローチャートを描くときにも、カラーペンがあると表現の幅が広がります。
④ 業界地図や就職四季報
「業界地図」や「就職四季報」は、信頼性の高い情報がまとまった資料としておすすめです。業界ごとの構造や主要企業の特徴、市場規模などが一覧で確認できます。
たとえば、IT業界の中でも通信とソフトウェアでは内容が異なるため、それぞれの違いを比較するのに役立つでしょう。
図解やデータが充実しているので、ノートに貼ったり抜き出したりしながら使うと、理解が深まります。ネットには載っていない一次情報が得られるのも大きな利点です。
⑤ インターネット接続ができるデバイス
パソコンやスマートフォンなど、インターネットが使えるデバイスも必須です。企業の最新情報やニュース、説明会の動画など、日々更新される情報をリアルタイムで収集できます。
紙の資料だけでは補えない部分を、ネット情報で補完するとより効果的です。調べた内容は、すぐノートにまとめるクセをつけておくと、情報が定着しやすくなります。
デジタルとアナログの両方をバランスよく使い分けてください。
業界研究ノートに役立つ情報源

業界研究ノートをしっかり作るためには、信頼できる情報を集めることが欠かせません。ここでは、就活生にとって活用しやすく、正確な情報が得られる代表的な情報源を5つ紹介します。
- 企業の採用ページ
- 就職情報サイト
- 業界研究関連の書籍・雑誌
- OB・OG訪問やキャリア面談
- 業界に関するニュース・新聞記事
① 企業の採用ページ
企業の採用ページでは、その会社が発信する最新かつ正確な情報を確認できます。事業内容や社風、募集要項などが詳しく載っており、志望動機の根拠としても有効です。
とくに社員インタビューやキャリアパスに関する情報は、働くイメージをつかむうえで役立つでしょう。
企業ごとに情報量や内容の深さが異なるため、気になる会社のページはこまめにチェックしておくことをおすすめします。
② 就職情報サイト
リクナビやマイナビなどの就職情報サイトは、数多くの企業情報が一度に見られる便利なツールです。業界別の特集や就活コラム、選考体験談なども豊富で、さまざまな角度から情報を得られます。
ただし、掲載情報が多い分、自分に必要な情報を選ぶ力も求められるのです。テーマを決めて調べると、効率よく情報を整理しやすくなるでしょう。
③ 業界研究関連の書籍・雑誌
『就職四季報』や『日経業界地図』などの書籍は、業界全体の構造や主要企業の位置づけを把握するのに役立ちます。
客観的で網羅的な情報がコンパクトにまとめられており、信頼性も高いため、基礎理解を深めたい人に向いているでしょう。図表やランキングも多く、視覚的にわかりやすい点も魅力。
ネット検索では得られない情報が得られる可能性もあります。
④ OB・OG訪問やキャリア面談
実際にその業界で働く先輩から話を聞けるOB・OG訪問は、リアルな業務内容や働く環境を知る貴重な機会です。ネットや書籍ではわからない、職場の雰囲気ややりがい・苦労などの生の声が得られます。
また、大学のキャリアセンターでの面談も、自分の考えを言語化するきっかけになるでしょう。事前に質問を用意しておくと、会話が深まりやすくなります。
⑤ 業界に関するニュース・新聞記事
業界の動向をタイムリーに知るには、日経新聞や業界専門紙のチェックが欠かせません。新規事業の立ち上げ、企業間の提携、法改正の影響など、時事的な話題はESや面接でもよく聞かれます。
自分の志望業界に関する記事を定期的に読んでおくと、知識の幅が広がるだけでなく、志望動機にも説得力が増すでしょう。気になる記事はノートにメモしておくことをおすすめします。
業界研究ノートに書くべき項目

業界研究ノートを有効に活用するには、あらかじめ書く内容を決めておくことが大切です。ここでは、就活で役立つ記入項目を7つに分けて紹介します。
- 業界名と注目している企業名
- 業界の市場規模や動向
- 業務内容とビジネスモデルの特徴
- 業界の課題や将来性
- 平均年収・年齢・福利厚生などの待遇情報
- 関連業種・職種との比較
- 自分なりの気づき・考察
① 業界名と注目している企業名
まずは、どの業界を調べているのかをはっきりさせ、注目している企業名も一緒に書いてください。これを最初に記録しておくことで、情報の整理がしやすくなり、方向性もぶれにくくなります。
企業名まで記載すれば、業界研究だけでなく企業研究への入り口としても活用できます。複数の業界を並行して調べる場合でも、こうした工夫で混乱を防げるでしょう。
業界全体と企業個別の視点を意識してまとめてみてください。
② 業界の市場規模や動向
市場の大きさや成長傾向は、業界を知るうえで欠かせない情報です。拡大中の業界なら将来性に期待ができますし、縮小傾向にある場合は慎重な判断が求められるでしょう。
データや最新ニュースを参考にして、業界全体の流れを押さえておくと安心です。この内容は、志望動機を語るときの裏づけにもなります。
成長している分野を見極める視点を持つことで、就活の軸がより明確になるはずです。
③ 業務内容とビジネスモデルの特徴
その業界では、どんな仕事が行われ、どのように利益を生み出しているのかを理解することが重要です。たとえば、製造業では開発から販売までの流れ、小売業では仕入れと販売の仕組みなどがあります。
職種ごとの関わり方や役割にも注目してください。ノートには図やフロー図で簡単にまとめておくと、後から見返すときにも便利です。
仕組みを理解できれば、自分がどの役割に適しているかも見えてきます。
④ 業界の課題や将来性
どの業界にも課題やリスクはあります。たとえば、労働力不足、国際競争、環境対応などが代表的です。これらを知っておくことで、志望理由に深みが出てくるのです。
同時に、業界の今後の見通しや成長の可能性も確認しましょう。将来性を意識した視点を持っていると、企業側からも前向きに受け取られやすくなります。
良い面と課題の両方を押さえておくと、より説得力のある話ができるでしょう。
⑤ 平均年収・年齢・福利厚生などの待遇情報
給与や働き方に関する情報は、キャリアを考えるうえで無視できません。平均年収や勤務年数、福利厚生の内容なども整理しておきましょう。
ただし、数字だけで判断するのではなく、その背景や働き方とのバランスも見てください。たとえば、高収入でも残業が多い業界があれば、それが自分に合っているかも考える必要があります。
複数の情報源を比較して、偏りのない判断を意識してください。
⑥ 関連業種・職種との比較
興味のある業界だけを見るのではなく、似た業界や職種と比較することで、自分に合う選択肢を見つけやすくなるでしょう。
たとえば、広告業界とWebマーケティングは似ているようで、仕事内容や求められるスキルが異なっています。こうした違いを明確にすることで、自信を持って進路を選べるようになるのです。
比較することで思いがけない気づきを得られることもあるため、視野を広く持つことが大切。
⑦ 自分なりの気づき・考察
調べた情報を並べるだけでは、他の就活生との差別化は難しいかもしれません。自分なりの視点で気づいたことや感じたことを、積極的に書き加えてください。
たとえば、「この業界は新技術に対して積極的」「自分の性格に合っていそう」など、主観的でも構いません。そうした考察が、面接での深みある回答につながっていきます。
情報を自分の言葉に落とし込む習慣をつけることが、業界理解を深める近道です。
業界研究ノートの作り方

業界研究ノートは、単なる情報の整理ではなく、自分の考えを深めて就活に活かすためのツールです。ここでは、ノートを効果的に活用するための5つのステップを紹介します。
- ステップ①:業界全体の概要を調べる
- ステップ②:気になる企業の情報をまとめる
- ステップ③:業界内の他社と比較検討する
- ステップ④:自分の視点で整理・分析する
- ステップ⑤:ESや面接に活かせるようにまとめ直す
① 業界全体の概要を調べる
はじめに、興味のある業界の全体像を把握しておくことが大切です。市場規模や成長性、主要なプレーヤーや業界の歴史的背景など、全体の枠組みをつかむことで、理解の土台ができます。
業界がどういった社会的役割を果たしているかも重要な観点です。
たとえば、自分が日常的に関わっているサービスや製品の裏側にあるビジネス構造に気づくことができれば、企業理解の精度も高まるでしょう。
また、過去の変化や現在のトレンド、今後の予測なども一緒に押さえておくと、志望動機に説得力を持たせる根拠にもなります。
業界地図や日経新聞、経済誌の特集などを活用して、広い視野で調査を進めてください。業界の特徴やポジションがわかると、企業選びや面接でも芯の通った回答ができるでしょう。
② 気になる企業の情報をまとめる
業界全体を俯瞰できたら、次はその中でも特に関心のある企業を深掘りしましょう。
会社の基本情報(売上高、従業員数、事業所の所在地など)に加えて、経営理念や今後のビジョン、展開している事業の特徴なども調べて記録しておくとよいです。
たとえば、同じ業界でも顧客ターゲットや強みが全く異なるケースも多いため、企業ごとの「らしさ」を明確に言語化することが求められます。
さらに、企業の採用情報ページや社員インタビュー記事、就職四季報なども活用し、働き方や人材に求められる価値観をつかみましょう。
ここで重要なのは、単に情報を写すのではなく、自分が「なぜこの会社に惹かれたのか」をノートに書き添えることです。
感じたことを言語化することで、自己理解が進み、面接やESの記述にも直結していきます。
③ 業界内の他社と比較検討する
気になる企業だけを見ていると、その魅力に偏った認識になってしまうことがあります。そこでおすすめなのが、同業他社との比較です。
複数社を並べてみると、会社ごとの事業領域の違いやビジネスモデルの独自性、社風やカルチャーの差が浮かび上がってきます。
たとえば、同じ食品メーカーでもBtoCとBtoBでは戦略や仕事の内容が大きく異なるのです。
比較する際は、企業規模・業績・理念・教育制度・海外展開の有無など、いくつかの軸を設定しておくと分析しやすくなります。また、自分がどのポイントに魅力を感じるのかを明確にする材料にもなるでしょう。
結果的に、「この会社じゃないとダメな理由」が言語化しやすくなるので、ESや面接対策にもつながります。主観と客観のバランスを意識しながら整理することが大切です。
④ 自分の視点で整理・分析する
情報を集めるだけでは、印象が薄くなったり、選考の場面で活かしづらくなったりします。大事なのは、集めた情報に対して自分なりの考察を加えることです。
「この企業の戦略は時代に合っていると思う」「この事業は今後伸びそう」など、気づいたことを素直に書き出してみてください。
また、違和感や疑問を感じた点もあえて記録しておくと、自分に合う・合わないの判断材料になります。
たとえば、「ワークライフバランスより成果主義を重視しているようだ」といった気づきは、将来的なミスマッチを防ぐヒントにもなるでしょう。
この段階では、きれいにまとめる必要はありません。むしろ、自分の言葉でラフに書いておくことで、考えが深まるのです。
⑤ ESや面接に活かせるようにまとめ直す
最後の仕上げとして、ここまで調べた内容をもとに、選考に直結する形でノートを再構成しましょう。
重要なのは、単なる情報の羅列ではなく、「だからこの業界を志望する」「この企業で働きたい」といったストーリーに落とし込むことです。
実際のESでは、企業理解と自己理解を結びつける論理性が求められます。そのためには、ノートを構造化して、要点を1ページにまとめておくのが効果的です。
たとえば、「企業名・魅力に感じたポイント・自分の価値観との共通点・将来やってみたいこと」のように整理すれば、見直しやすくなります。
時間が経っても使えるようにしておくと、他社の選考や志望動機作成にも使い回せる場面が増えるでしょう。自分の言葉で語れるようになるまで繰り返し練習することが大切です。
業界研究ノートの作成例

業界研究ノートをどう書けばよいか分からないと感じている方もいるかもしれません。ここでは3つの異なる業界について、実際の記入例を紹介します。
形式や内容の参考にしながら、自分なりのノートづくりに活かしてください。
例①:総合商社業界
総合商社業界は、多種多様な事業領域をグローバルに展開しており、就活生から非常に人気の高い業界です。
ここでは、注目企業やビジネスモデル、将来性などを総合的に整理し、業界への理解を深めるための情報をまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業界名と注目している企業名 | 総合商社/三菱商事、伊藤忠商事、住友商事など |
| 業界の市場規模や動向 | 多角的なビジネスを展開する巨大産業。近年は非資源分野へのシフトや脱炭素投資が進んでいる。 |
| 業務内容とビジネスモデルの特徴 | モノの仲介にとどまらず、事業投資や子会社経営なども担う。グローバル展開が進む。 |
| 業界の課題や将来性 | 資源依存からの脱却とESG対応が課題。変化対応力が企業成長の鍵を握る。 |
| 待遇情報(年収・年齢・福利厚生) | 平均年収1,200〜1,400万円。住宅手当や海外赴任手当が充実。平均年齢は40歳前後。 |
| 関連業種・職種との比較 | メーカーや専門商社よりも戦略性と事業多様性が強い。金融よりも実行フェーズが多い。 |
| 自分なりの気づき・考察 | 幅広い事業で経済変動に強いが、海外勤務に柔軟に対応する覚悟も必要だと感じた。 |
例②:金融業界(銀行)
銀行業界は、経済インフラを支える重要な役割を担っており、安定志向の学生を中心に根強い人気があります。フィンテックなどの新技術の影響も含めて、今後の展望や課題を具体的に整理しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業界名と注目している企業名 | 銀行/三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行など |
| 業界の市場規模や動向 | 成熟市場で低金利が継続。フィンテック台頭で競争環境が激化している。 |
| 業務内容とビジネスモデルの特徴 | 融資・預金業務が中心。近年は法人支援やデジタル対応への転換が進んでいる。 |
| 業界の課題や将来性 | 収益源の多様化とデジタル化対応が重要。安定性はあるが変革も求められる。 |
| 待遇情報(年収・年齢・福利厚生) | 平均年収600〜900万円。福利厚生や研修制度が手厚いが、昇進は年功傾向が残る。 |
| 関連業種・職種との比較 | 証券業界よりも安定志向。IT業界との連携が進み、金融×テックの可能性が広がる。 |
| 自分なりの気づき・考察 | 安定感と社会的意義が魅力。対人スキルと誠実さが強く求められると感じた。 |
例③:コンサルティング業界
コンサルティング業界は、企業の課題解決を通じて社会に大きな影響を与えるやりがいのある仕事です。
業務の特徴や待遇、他業界との違いについて深く考察しながら、業界研究ノートとしてまとめています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業界名と注目している企業名 | コンサルティング/アクセンチュア、デロイト、野村総合研究所など |
| 業界の市場規模や動向 | 市場拡大中。デジタル戦略や業務改善などのニーズが増加している。 |
| 業務内容とビジネスモデルの特徴 | 企業の課題解決を支援する提案型ビジネス。プロジェクト単位で変化に富む。 |
| 業界の課題や将来性 | 人材流動性が高く、働き方や育成制度の改善が必要。AI活用も鍵を握る。 |
| 待遇情報(年収・年齢・福利厚生) | 平均年収800〜1,200万円。成果次第で昇進も早く、柔軟な働き方も可能。 |
| 関連業種・職種との比較 | 提案だけでなく実行支援まで担う点が、シンクタンクや広告業界と異なる。 |
| 自分なりの気づき・考察 | 変化の激しい環境にやりがいを感じる。成長志向の人に適していると考えた。 |
業界研究ノート作成時の注意点

業界研究ノートは、ただ情報を書き留めるだけでは意味がありません。実際の就職活動に役立てるには、視点や記述方法に注意する必要があるでしょう。
ここでは、ノートを作成するうえで押さえておきたい5つのポイントを紹介します。
- インターネットの情報に偏らないようにする
- 情報を写すだけでなく自分の考察も書くようにする
- 事実と主観を明確に分けて記述する
- 業界研究を目的にせず、就活に活かす意識を持つ
- 一度作ったら終わりにせず継続的に更新する
① インターネットの情報に偏らないようにする
ネット上の情報は便利ですが、信ぴょう性に欠ける内容や個人の主観が強いものも多くあります。それだけに頼ると、偏った理解につながってしまう恐れも。
書籍、新聞、業界誌、企業説明会など、多様な情報源を取り入れることが大切です。特に、公式データや一次情報を意識的に選ぶと、より信頼できるノートになるでしょう。
幅広い視点から情報を集めることで、理解が深まり、就活にも安心して臨めます。
② 情報を写すだけでなく自分の考察も書くようにする
ノートに情報を書き写すだけでは、自分の中に定着しません。重要なのは、調べた内容に対して自分の意見や気づきを書き添えることです。
たとえば、「この業界は新しい技術導入が活発」と感じたら、「なぜそうなのか」「自分はそれをどう感じたか」まで掘り下げてみてください。
そうした考察は、志望動機を話すときにも役立ちます。受け身の記録にとどまらず、能動的に思考を深めていくことを意識しましょう。
③ 事実と主観を明確に分けて記述する
業界研究では、事実と感想が混在しやすいですが、それぞれを区別して書くことが大切です。情報の正確さを保つためにも、事実には出典やデータを添え、主観は自分の視点であることを明示してください。
たとえば、「売上高は前年比10%増加」というのは事実ですが、「成長が魅力的に感じた」というのは主観です。このように表現を分けておけば、読み返したときにも混乱しません。
面接で話す際にも、自信を持って説明できる内容になります。
④ 業界研究を目的にせず、就活に活かす意識を持つ
ノートを作ること自体が目的になってしまうと、本来の意味が薄れてしまいます。業界研究は、志望動機を明確にしたり、企業選びの判断材料にしたりするための手段です。
「この情報はどんな場面で使えるか」「自分の軸とどう関係しているか」といった観点でまとめるようにしてください。実際の面接やESにも活かせるノートになります。
常に就活全体の流れを意識しながら作成を進めましょう。
⑤ 一度作ったら終わりにせず継続的に更新する
業界や企業の情報は日々変わります。ノートも一度作って終わりではなく、こまめに更新することが大切です。
たとえば、新しい業界ニュースや決算発表があれば、それをもとに記録を追加したり修正したりしてください。情報が最新であれば、面接でも説得力のある話ができるようになるでしょう。
ノートを育てる感覚で、就活期間中は定期的に見直していくことをおすすめします。
就活で差がつく「業界研究ノート」のやり方を理解しよう!

業界研究のやり方に悩む就活生にとって、ノートを活用することは非常に効果的。なぜなら、業界研究ノートを使うことで情報を整理しやすくなり、志望動機や自己PRの材料が明確になるからです。
特に、自分に合った業界を見極めたり、企業を比較検討したりするうえで、ノートは重要なツールといえるでしょう。また、書きながら考えることでアウトプット力も養われ、面接対策にも活かせます。
情報源や書くべき項目、作り方の手順まで意識して作成すれば、業界研究の精度が大きく変わるでしょう。ノートを活用した業界研究こそが、内定への近道です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。











