就活でのエントリー数はどれくらい?平均エントリー数や企業選びのポイントも紹介
この記事では、就活でエントリーするべき企業や選考の数を解説しています。
就活における平均エントリー数や最新の傾向を紹介しつつ、エントリー社数が多い・少ない場合のメリットとデメリットも整理しています。
自分に合った適切な社数を見極めるための考え方や注意点も紹介しているので、エントリー数で迷っている場合は参考にしてみてくださいね。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
就活における「エントリー」とは

就活を始めたばかりの学生にとって、「エントリー」という言葉の意味が曖昧なまま進めてしまうケースは少なくありません。
しかし、就職活動を円滑に進めるには、この「エントリー」の役割を正しく理解することが非常に重要です。
エントリーとは、企業の採用活動に対し「興味があります」「情報が欲しいです」という意思を表明する最初のステップを指します。単なる申し込みではなく、企業と接点を持つ第一歩です。
具体的には、企業の採用ページやナビサイトで「エントリーする」ボタンを押し、マイページを作成したり、エントリーシートを提出したりする行為が含まれます。
これにより、説明会やインターン、選考情報の案内が届くようになります。エントリー時点では選考が始まるわけではないため、比較的気軽に行えるという特徴があります。
ただし、気になる企業すべてに無計画にエントリーしてしまうと、スケジュール管理が難しくなり、本当に志望度の高い企業への対策が疎かになりかねません。
エントリーの数にばかり目を向けるのではなく、自分がきちんとフォローできる社数に絞り、情報管理や企業研究に時間をかけることが重要です。
エントリーは就活の出発点であり、自分の関心や志向性を見極める手がかりにもなります。まずは仕組みを理解し、目的をもって企業選びを進めていくことで、後悔のない就職活動へとつながるでしょう。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
就活生の平均エントリー社数

就職活動を進めるうえで、エントリー社数は計画の軸となる重要な要素です。平均的な数を知ることで、自分の活動が多すぎるのか少なすぎるのかを判断する材料になります。
また、文系と理系では活動のスタイルや市場の特性に違いがあるため、それぞれの傾向を知っておくことが大切です。
ここでは、文系・理系の平均エントリー社数と、そこから見えてくる注意点や背景について詳しく解説します。
- 文系学生の平均エントリー社数
- 理系学生の平均エントリー社数
① 文系学生の平均エントリー社数
文系学生の平均エントリー社数は、おおむね30〜40社といわれています。
文系は志望業界が広く、将来の方向性が明確でない学生も多いため、複数の企業にエントリーする傾向があります。
特に人気業界や大手企業は選考倍率が高く、通過率を補う意味でも数を出す人が多くなりがちです。ただし、数だけに注目すると、1社ごとの企業研究や書類の質が下がるリスクがあります。
エントリーシートが浅い内容になったり、面接での発言に一貫性がなくなったりすると、通過率にも悪影響を及ぼすでしょう。
エントリー数が多いことは悪いことではありませんが、目的があいまいなまま増やすのではなく、優先順位をつけて対策の精度を上げていく必要があります。
エントリー数を抑えることで選考の質を高めるという考え方もあります。自分にとって本当に必要な企業を見極め、無理なく継続できる社数に絞ることが成功の鍵となるでしょう。
② 理系学生の平均エントリー社数
理系学生の平均エントリー社数は、20〜30社程度とされており、文系に比べるとやや少なめです。
これは、研究室活動や卒業論文といった学業の負担が大きく、就職活動に使える時間が限られていることが主な要因です。
また、理系の学生は専攻を活かせる技術職など、比較的志望職種が明確になっているケースが多く、企業選びも絞り込みやすい傾向があります。
一方で、1社あたりにかける準備の手間は少なくありません。
企業側も応募者の専門性や研究内容を重視するため、志望動機や自己PRでは内容の深さや一貫性が求められます。そのため、少ない社数でも高い精度で臨む必要があります。
しかし、エントリー数が少なすぎると不採用時のリスクが大きくなるのも事実です。万が一に備えてある程度の選択肢を確保しつつ、スケジュール管理と情報収集を徹底することが求められます。
焦らず着実に進める姿勢が、結果として内定につながる可能性を高めてくれるでしょう。
就活でのエントリー数に関する最新傾向

就活でのエントリー数の傾向を正しく理解しておくことで、計画的に企業選びがしやすくなります。
ここでは、最近の就活で見られる代表的な傾向を3つに分けて紹介します。
- エントリー数は減少傾向
- エントリー数はプレエントリー後に伸びにくい傾向
- エントリー数は3〜4月に集中する傾向
① エントリー数は減少傾向
エントリー数は全体的に減少傾向にあります。以前は「できるだけ多くの企業にエントリーすること」が一般的でしたが、最近では自分に合った企業を見極めて選ぶスタイルが主流となっています。
就活情報の取得が簡単になったことや、企業研究の重要性が広まったことが背景にあります。
また、エントリー数が多すぎるとスケジュール管理が難しくなり、提出漏れや志望度の低さが企業に伝わるリスクもあるため注意が必要です。
そのため、数にとらわれず、質を重視してエントリーする姿勢が求められます。
② エントリー数はプレエントリー後に伸びにくい傾向
プレエントリーをしたあとに追加でエントリーする人は減る傾向があります。多くの就活生が3月初旬に一斉に動き出し、複数社へプレエントリーしますが、その後は説明会や提出物に追われて余裕がなくなってしまいます。
このような状態を避けるためには、早い段階から企業研究を進めておき、3月以降の多忙な時期に慌てないよう備えておくことが大切です。
選考の進み具合に合わせて、定期的にエントリーの見直しを行うことも効果的でしょう。
③ エントリー数は3〜4月に集中する傾向
エントリー数は3月から4月にかけて大きく伸びる傾向があります。これは、広報活動の解禁が3月であることが影響しています。
企業もこの時期に集中してエントリー受付を開始するため、就活生の行動が一斉に活発になります。ただし、短期間に多数の企業へエントリーすると、準備が追いつかず、ESの質が下がってしまう可能性があります。
エントリーが集中する前の1月や2月のうちに企業をリストアップし、余裕を持って準備を進めておくことが成功のポイントです。
就活でエントリー社数が多い場合のメリット

就活で複数の企業にエントリーすることには、戦略的にも心理的にも多くの利点があります。
視野の拡大や選考力の向上、そして精神的な余裕の確保といった恩恵は、結果的に自分に合った進路選びをサポートしてくれます。ここでは、それぞれのメリットを詳しく解説します。
- 視野が広がりやすい
- 選考経験を積みやすい
- 精神的な安心感を得やすい
① 視野が広がりやすい
エントリー社数を多めに設定すると、さまざまな業界や職種の情報に自然と触れられるようになり、就活全体の視野が大きく広がります。
たとえば、当初はメーカー志望だった人が、IT業界やコンサル業界の業務内容に興味を持つことがあります。企業説明会や面接を通じて、新たな選択肢に気づけることは少なくありません。
これは、自分の適性や価値観を再確認する大きなきっかけにもなります。
また、エントリーを通じて異なる企業文化や理念に触れることで、志望動機をより深めることも可能です。選考の過程で企業研究を重ねる中で、自分に合った働き方やキャリアの方向性が見えてくるでしょう。
② 選考経験を積みやすい
企業へのエントリー数を増やすことで、エントリーシートの提出や面接、グループディスカッションなど、実際の選考に触れる機会が増えていきます。
最初は緊張してしまう場面もあるかもしれませんが、回数を重ねるごとに話し方がこなれてきたり、伝えたい内容がより整理されたりと、着実にスキルが高まっていきます。
とくに、企業によって評価されるポイントが異なるため、複数社を経験することで自分の強みや改善点にも気づきやすくなります。
また、よく聞かれる質問や選考形式に事前に慣れておくことは、本命企業の選考時に大きな安心材料になります。こうした積み重ねが、自信を持って臨める姿勢につながるのです。
③ 精神的な安心感を得やすい
エントリー数が多いと、ひとつの選考結果に気持ちが左右されにくくなり、冷静に次のステップへ進みやすくなります。
就活初期は不合格が続いて落ち込みやすい時期ですが、候補が複数あることで「まだ他がある」という前向きな気持ちを持ち続けやすくなります。この余裕は、就活全体のパフォーマンス向上にもつながります。
また、複数の企業の選考結果を比較することで、自分がどう評価されやすいか、どのような職種に適性があるかなどのヒントを得られる場合もあります。
精神的な安定を保ちながら、自分に合った企業を見極めるためにも、ある程度のエントリー数を確保しておくとよいでしょう。
就活でエントリー社数が多い場合のデメリット

就活において多くの企業にエントリーすることは、選択肢を増やすという意味では一定の合理性があります。しかし、数を重視しすぎた結果、思わぬ落とし穴に陥るリスクもあるため注意が必要です。
とくにスケジュールや対策面での負担が増えやすく、自分の実力を十分に発揮できないまま選考が進んでしまう可能性があります。
ここでは、エントリー数が多いことによって起こりやすい代表的なデメリットを3つ紹介します。
- スケジュール管理が難しい
- 企業ごとの対策が難しい
- 集中して選考に臨むのが難しい
① スケジュール管理が難しい
エントリー社数が増えると、説明会やWebテスト、面接などの予定が次々と入り、スケジュール管理が非常に複雑になります。
たとえば、ある企業の面接と別企業のグループディスカッションが同じ日に重なった場合、時間配分や準備の優先順位に頭を悩ませることになります。
さらに、オンラインと対面の選考が混在すると、移動時間や機材の準備といった物理的な制約も発生し、うっかりミスが起きやすくなります。
情報が煩雑になればなるほど、重要な企業の選考を見逃す、開始時間を間違えるといった致命的なトラブルに直結しかねません。
こうした事態を防ぐには、手帳や管理アプリなどを活用して常に全体の流れを俯瞰できるようにしておくことが求められます。
② 企業ごとの対策が難しい
多くの企業に同時にエントリーしていると、各社に合わせた情報収集や準備に割く時間がどうしても足りなくなります。
企業研究が浅くなれば、志望動機や自己PRに具体性が欠け、表面的なアピールに終始してしまう傾向が強まります。
また、業界によって重視されるポイントが異なるにもかかわらず、すべてに共通したフォーマットで対応してしまうと、企業側には「使い回し」だと見抜かれてしまうでしょう。
実際、ES(エントリーシート)の段階で落とされる原因の多くは、こうした“浅さ”に起因しています。
特に、第一志望群の企業への準備が手薄になってしまえば、本末転倒です。対策の質を確保するには、エントリー数を絞り込むと同時に、自分が本気で入りたい企業を見極める眼も必要になります。
③ 集中して選考に臨むのが難しい
複数の選考が同時並行で進行していると、ひとつひとつに集中することが難しくなります。
たとえば、今日がA社の一次面接で明日はB社の最終面接、週末にはC社のWebテストが控えている……といった状況が続くと、常に頭の中が情報であふれかえり、パフォーマンスにも悪影響が出てしまいます。
精神的な余裕が失われると、面接中に言葉が詰まったり、質問の意図を正確に汲み取れなかったりといった、思わぬ失敗にもつながりかねません。
こうした集中力の分散は、自信を失うきっかけにもなりやすく、結果的に選考全体の質を下げてしまう要因になります。
心身のコンディションを安定させ、最も力を発揮したい企業に全力を注ぐためにも、エントリー数を見直し、自分のペースで進められる環境を整えることが大切です。
就活でエントリー社数が少ない場合のメリット

就活においてエントリー社数を少なく抑えることには、大量エントリーとは異なる利点があります。数を追うより、自分に合った企業にじっくりと向き合いたい人にとっては、少数精鋭の進め方が有効です。
ここでは、エントリー社数が少ない場合に得られる主なメリットを紹介します。
- 一社ごとに準備しやすい
- 就活の軸が定まりやすい
- 志望度の高い企業に集中しやすい
① 一社ごとに準備しやすい
エントリー数を絞ると、各企業への対策にじっくりと時間をかけられるようになります。
自己分析や企業研究の精度を高めることができ、応募先企業の特徴や社風、事業内容に即したエントリーシートを仕上げることが可能です。
特に、設問の意図を丁寧に読み取り、自分の強みと企業の求める人物像を的確に結びつける作業には、一定の時間と思考の深さが求められます。
また、面接準備においても、想定質問の回答だけでなく、自分の経験をどのように語れば伝わりやすいかといった表現面にも気を配れるようになります。
さらに、選考段階で企業側から提示される課題や適性検査などに対しても、焦らず落ち着いて対応しやすくなります。量ではなく質を重視した就活を進めたい人にとって、大きなメリットといえるでしょう。
② 就活の軸が定まりやすい
応募する企業を厳選する過程では、自然と「自分が何を大事にして働きたいか」という価値観を見つめ直すことになります。
業界研究や職種の理解を深める中で、自分の適性や興味関心、理想の働き方を明確にできるようになり、それが「就活の軸」として形成されていきます。
軸がはっきりしていると、選考の一貫性が生まれ、エントリーシートや面接での受け答えにも説得力が増します。
企業からの質問に対しても、自分の考えに基づいて具体的かつブレのない回答ができるため、好印象を与えやすくなるでしょう。
さらに、選考の中で企業との相性や違和感を感じた際も、軸が定まっていれば判断に迷うことなく対応できます。結果として、後悔の少ないキャリア選択へとつながっていきます。
③ 志望度の高い企業に集中しやすい
応募する企業が少ないからこそ、1社ごとの志望度が高くなり、準備やアプローチに対する意欲も自然と高まります。
志望企業への理解を深めるために、説明会への積極的な参加、OB・OG訪問、インターンシップの活用など、自主的な行動がしやすくなります。そうした取り組みは、志望理由に具体性を持たせるうえで非常に効果的です。
さらに、選考の場面でも「本気度」や「熱意」が伝わりやすくなります。志望動機に企業独自のエピソードを盛り込んだり、社員の声を引用したりといった工夫が可能になるため、他の候補者との差別化にもつながります。
企業側も、その学生がどれだけ真剣に向き合っているかを見ており、熱意ある姿勢はプラスに働く要素です。限られた選択肢に集中することで、より深く、より濃い関係性を築くことができるでしょう。
就活でエントリー社数が少ない場合のデメリット
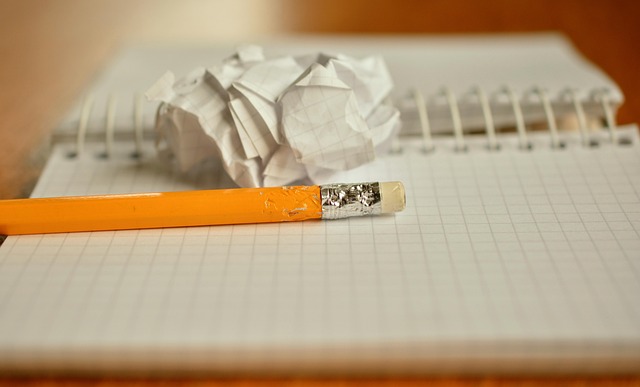
エントリー社数が極端に少ない状態では、内定獲得の確率が低下するだけでなく、選考が思うように進まなかった際の軌道修正も難しくなります。
また、情報源や比較対象が限られることで、志望動機や企業選びに説得力を持たせることが難しくなり、自分に合った進路選択がしづらくなるおそれがあります。
就活は想定外の連続でもあるため、数の少なさがリスクになることを理解しておく必要があります。
- 内定が出にくくなりやすい
- リカバリーが難しくなりやすい
- 情報収集が不足しやすい
① 内定が出にくくなりやすい
就活では、選考に進む前提としてエントリーが必要です。エントリー数が少ないということは、その時点で受けられる企業の母数が少ないということに直結します。
たとえば、5社のみのエントリーでは、どこかで書類不通過や面接落ちが続いた場合、一気に全滅の可能性が高まります。
また、企業側の都合で採用数が急遽減ったり、選考そのものが中止になったりすることもあり得ます。たとえ自信のあるESや面接対応であっても、タイミングや相性の問題で落ちてしまうケースは少なくありません。
そうした外的要因も含めて内定獲得の難易度は変動するため、ある程度の数を確保することでチャンスの幅を持たせることが現実的なリスク対策となります。
とくに新卒の就活は一発勝負であり、機会損失を最小限にするための保険として、エントリー数の確保は欠かせません。
② リカバリーが難しくなりやすい
就活は長期戦である一方、各フェーズには期限があるため、出遅れや選考不合格が続いた場合にすぐに次の手を打てる準備がないと挽回が困難になります。
エントリー社数が少ないと、1社1社に依存度が高まり、不合格になった際のショックが大きくなる傾向にあります。
特に本命企業の結果が悪かったときに、それに代わる選考が進んでいなければ、ゼロからの再スタートとなり、精神的・時間的コストの両方が発生します。
また、締切が過ぎてエントリーできる企業が限られていたり、人気企業では応募枠がすでに埋まっていることも多いため、再エントリーの選択肢すら残っていないケースもあります。
就活には「保険」としての併願が必要であり、万が一の事態に備えて、複数の選考を並行させておくことで、失敗してもすぐ次に切り替えられる精神的な余裕が生まれます。
③ 情報収集が不足しやすい
就活は単なる企業への応募作業ではなく、自己理解と企業理解の積み重ねです。
エントリーを通じて説明会や面談に参加する中で、自分の価値観や働き方に合う企業像を少しずつ明確にしていくプロセスでもあります。
しかし、エントリー数が少ないと接点のある企業が限られるため、業界ごとの風土や仕事内容の違いを比較検討する機会が大きく減ってしまいます。
結果として、企業を「知っているつもり」のまま選考に臨み、志望動機が浅くなったり、面接での回答に説得力を欠いたりすることがあります。
また、情報の幅が狭いことで「自分が何を重視したいのか」さえ見えてこないまま進んでしまい、最終的に納得感のない就職先を選ぶリスクも高まります。
より良い意思決定をするためには、多くの企業を見比べることが欠かせません。エントリー数の少なさは、自分にとって必要な選択肢を減らしているという点で、見えづらいデメリットなのです。
自分に合ったエントリー数の考え方

就活において「何社にエントリーすればよいか」は、多くの学生が不安を抱えるテーマです。
平均的な社数や他人の動きに流されず、自分の志望度やスケジュール、準備の進め方をふまえて、無理のない範囲で判断することが大切です。ここでは、自分に合った適切なエントリー数を見極めるための考え方を紹介します。
エントリー数が多すぎると、書類や面接の準備が追いつかなくなるおそれがあります。応募先が多ければチャンスは広がりますが、そのぶん一社ごとの対応が雑になり、結果として通過率が下がることも考えられます。
逆に、エントリー数が少なすぎると、不合格が続いた際のリスクが大きくなります。
選考が終わってから新たに企業を探しても、すでに募集が締め切られている場合もあるため、再スタートに時間がかかってしまう可能性があります。
こうしたバランスをふまえると、自分の体力や予定、企業への熱意などをもとにエントリー数を調整する必要があります。
文系であれば30〜40社、理系であれば20〜30社程度が一つの目安ですが、最終的には一人ひとりの状況に合わせて決めることが重要です。他人と比べるのではなく、自分が最後までやりきれる社数を意識してください。
エントリーする企業選びのポイント

企業選びは就活の第一歩であり、自分に合った企業を見極めることが納得のいく活動につながります。知名度や条件だけで判断すると、選考の途中でモチベーションが下がってしまうこともあります。
ここでは、企業選びで意識したい観点を3つ紹介します。
- 就活の軸に合致する企業
- 学んだ内容を活かせる企業
- 志望動機につなげやすい企業
① 就活の軸に合致する企業
自分の就活の軸と企業の方向性が一致しているかどうかは、企業選びにおいて非常に重要です。
たとえば「社会課題の解決に携わりたい」という軸を持つ学生であれば、地方創生や環境分野に力を入れている企業が候補になります。
実際に、自治体と連携して地域活性化を図る不動産会社や、脱炭素に向けた新規事業を推進しているメーカーなどが挙げられるでしょう。
このように軸と企業の取り組みが合致すれば、志望理由やエントリーシートにも一貫性が生まれ、選考時の発言に説得力が加わります。
一方で、「なんとなく安定していそう」「知っている企業だから」といった曖昧な理由で企業を選んでしまうと、深掘り質問に答えられず、面接で失速する可能性もあります。
まずは自己分析を通じて、働くうえで重視したい価値観を明らかにし、その軸に基づいて企業を絞ることが成功への近道といえるでしょう。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
② 学んだ内容を活かせる企業
大学で学んだ専門知識やスキルを活かせる企業を選ぶことで、就職後の適応もスムーズになります。
たとえば化学系の学部に所属している学生であれば、製薬メーカーや素材メーカーの研究開発職において、学びを直接活かすことができます。
また、経済学部でマーケティングを学んできた学生なら、広告代理店や消費財メーカーでの企画職が適しているでしょう。
こうした「活かせる接点」が明確な企業であればあるほど、ESや面接において具体的な志望動機が作りやすくなり、選考官にとっても評価しやすい材料になります。
もちろん、専攻と直接関係のない業界へ進むことも可能ですが、その場合でも「なぜその業界に興味を持ったのか」「どのように自分の経験を転用できるか」といった論理的な説明が求められます。
自分の強みと企業の求めるスキルが交差するポイントを見つけることが、選考突破への鍵となります。
③ 志望動機につなげやすい企業
企業理念やビジョン、事業内容に強く共感できる企業を選ぶことは、自然で説得力のある志望動機を構築するうえで大きなアドバンテージになります。
たとえば「子どもの教育格差をなくしたい」という想いを持っている学生が、教育系のベンチャー企業やEdTech(教育×テクノロジー)に力を入れている企業を選べば、個人的な原体験と企業の事業とが結びつき、明確な志望理由を伝えることができます。
また、理念に共感していると、企業研究や説明会参加時のモチベーションも高まり、質問の質や選考での受け答えにも良い影響を与えるでしょう。
反対に、収益モデルやビジネス構造にピンとこないまま応募すると、業務内容の理解も浅くなり、選考対策が進まない原因になります。
企業のコーポレートサイトや採用ページだけでなく、社員インタビュー記事やIR資料なども活用しながら、自分の価値観と重なる部分を探してみてください。
エントリーの際に気をつけたい注意点

就活で複数の企業にエントリーするのは一般的ですが、進行管理を怠ると重要な機会を逃すおそれがあります。
とくに、エントリーの時期や手続きの見落としは、志望度の高い企業との接点を失う原因になりかねません。
ここでは、エントリーを円滑に進めるために押さえておきたい基本的な注意点を紹介します。
- エントリーのタイミングを逃さないようにする
- 処理できる社数を超えないようにする
- エントリーシートの提出期限や説明会への参加を見落とさないようにする
① エントリーのタイミングを逃さないようにする
就活において、企業へのエントリーは早い者勝ちともいえる重要な一手です。
企業ごとにエントリー開始日や締切日は異なり、人気企業や外資系企業などは募集が突然終了することもあります。
これに気づかず出遅れてしまうと、応募すらできない事態になりかねません。特に就活解禁直後の2月から3月は、多くの企業が一斉に動き出すため、情報の整理と把握に追われる時期です。
対策としては、就活サイトの通知機能やエントリー予定企業のリスト化が有効です。カレンダーアプリなどで企業別のエントリー期日を登録しておくと、視覚的に把握できてスムーズに管理できます。
また、大学のキャリアセンターが配信する情報にも目を通すことで、見落としのリスクを減らせるでしょう。
「気づいたら締切が過ぎていた」とならないためには、スケジュールを先手で組み立て、日々の確認を習慣化することが欠かせません。エントリーの機会を確実に掴む姿勢が、選考突破への第一歩につながります。
② 処理できる社数を超えないようにする
「数撃てば当たる」と考えて大量にエントリーしてしまうと、思わぬ落とし穴にはまりかねません。
たしかに応募先を増やすことでチャンスは広がりますが、実際にはエントリー後に必要なタスクが一気に発生します。
エントリーシートの作成、企業研究、説明会や面接の日程調整など、1社ごとに時間と労力がかかるのです。
自分の処理能力を超えてしまうと、どの企業にも中途半端な対応しかできず、結果的にどこからも評価されにくくなるおそれがあります。本命企業の準備まで手が回らず、悔いを残すことにもなりかねません。
対処法としては、事前に「1週間で対応できる企業数」を試算して、無理のない範囲でエントリー数を調整することです。
また、企業の選考スケジュールを把握し、期間が重なりすぎないように分散させることも有効です。就活では「がんばりすぎない工夫」も大切です。
質の高い選考対策を行うためには、応募企業を絞り込む勇気も必要になります。見かけの数よりも中身で勝負する姿勢が、結果につながりやすい就活をつくるはずです。
③ エントリーシートの提出期限や説明会への参加を見落とさないようにする
エントリー後の対応を怠ると、せっかくの努力が水の泡になりかねません。
「エントリーはしたのに、ESの提出を忘れて不通過になった」「説明会の予約を忘れて参加できなかった」といったミスは、実際に多くの就活生が経験しています。
こうした見落としは、単なる不注意では済まされず、選考対象から外れる決定打となってしまいます。
このような事態を防ぐためには、エントリー時点で「何がいつまでに必要か」を即座に確認し、タスクを整理する習慣が不可欠です。
企業によっては、エントリー後にマイページ登録やES提出、説明会予約といったアクションが立て続けに求められる場合もあります。
複数の企業に応募していると情報が混在しやすいため、一覧表やスケジュールアプリなどを使って可視化することが効果的です。
また、企業から届くメールを見落とさないようにすることも重要です。迷惑メールフォルダに振り分けられることもあるため、受信設定の見直しやフィルター管理も行っておくと安心です。
通知に気づかず機会を逃すのは非常にもったいないことです。就活では「うっかり」が命取りになります。エントリー後こそ丁寧な対応を心がけ、提出・参加の抜け漏れを防ぐ体制を整えておきましょう。
確実に選考を進めるためにも、最初のアクションで気を抜かないことが成功への一歩です。
自分に合うエントリー数で効率的に就活を進めよう!

就活におけるエントリー数は、ただの数字ではなく、戦略そのものです。平均社数や最新の傾向を把握することで、自分に合ったエントリー数を見極めやすくなります。
たとえば、多くの企業にエントリーすれば選択肢は広がる一方で、対策やスケジュール管理が難しくなる傾向があります。
一方、少ない社数に絞れば準備に集中できますが、内定のチャンスを逃しやすくなるリスクもあります。そのため、就活の軸や自分の処理能力をもとに、無理のない範囲で計画を立てることが重要です。
エントリー数は多ければ良い、少なければ安心という単純な話ではありません。情報や目的を整理し、納得のいく就活を進めていきましょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










