面接で「最近読んだ本」を聞かれた時の答え方と例文10選
「最近読んだ本は何ですか?」面接で突然こう聞かれたら、どう答えればいいか悩んでしまいますよね。
就職活動の面接では、志望動機や自己PRだけでなく、こうした日常的な質問で人柄を見られることがあります。
準備していないと焦ってしまいがちですが、適切に答えることで思考力や学習意欲を効果的にアピールできますよ。
この記事では、面接官が最近読んだ本を尋ねる理由や答えるときのポイント、実際の回答例をジャンル別に紹介しながら、印象の良い伝え方をわかりやすく解説します。
面接の準備の際に、ぜひ参考にしてください。
面接前に役立つアイテム集
- 1実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- あなたの志望動機を面接官に響く形へブラッシュアップできるテンプレート
- 3自己PRテンプレシート
- 面接官視点で伝わる構成に落とし込み、自分の強みをブレずに説明できるようにします。
- 4適職診断
- 60秒で診断!あなたが面接を受けるべき職種がわかる
- 5面接前に差がつく!ビジネスマナーBOOK
- 面接前に一度確認しておきたい、減点されやすいマナーポイントをまとめています。

記事の監修者
記事の監修者
人事担当役員 小林
1989年新潟県生まれ。大学在学中に人材系ベンチャー企業でインターンを経験し、ビジネスのやりがいに魅力を感じて大学を1年で中退。その後、同社で採用や人材マネジメントなどを経験し、2011年に株式会社C-mindの創業期に参画。訪問営業やコールセンター事業の責任者を務めたのち、2016年に人事部の立ち上げ、2018年にはリクルートスーツの無料レンタルサービスでもある「カリクル」の立ち上げにも携わる。現在は人事担当役員として、グループ全体の採用、人事評価制度の設計、人事戦略に従事している。
詳しく見る
記事の監修者
記事の監修者
吉田
新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細
詳しく見る面接官が最近読んだ本を聞く理由とは?
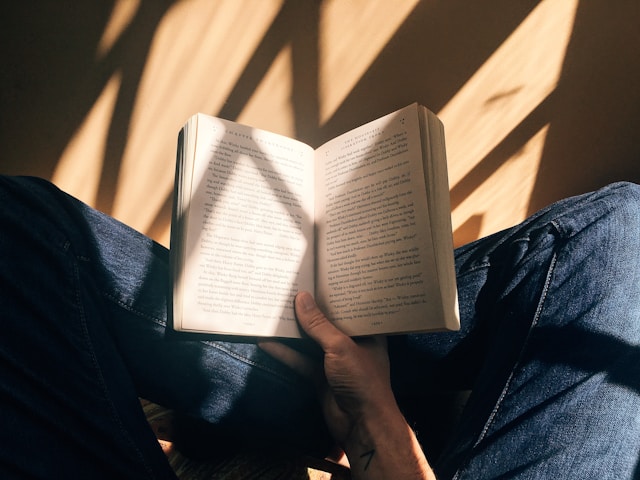
最近で読んだ本についての質問ですが、実は面接官には明確な意図があります。
ここでは、この質問を通じて面接官がどのようなポイントを見ているのかを解説しましょう。
- 応募者のひととなりを把握するため
- 日頃の読書週間を把握するため
- 表現力・プレゼン力を見るため
①応募者のひととなりを把握するため
この質問の背景には、本の選び方や感想から応募者の内面や価値観を知りたいという意図があります。
どのジャンルを選び、どんな理由でその本を手に取ったのか、そして読んでどう感じたのか――これらにはその人の興味・関心や考え方が色濃く表れるものです。
たとえば、実務的な本を選ぶ人には向上心や目標志向の強さが、物語性のある本を選ぶ人には感受性や共感力の高さが垣間見えることもあります。
読書体験は、その人の人となりを映し出す要素のひとつです。印象に残る受け答えをするには、「何をどう感じたのか」を、自分自身の言葉で丁寧に伝えることが大切です。
本の選び方は、あなたが大切にしている価値観や考え方が反映されやすいです。例えば、文学や哲学書など感受性を重視する本を選ぶと、柔軟な思考や共感力をアピールできますね。
もし最近読んだ本が面接と関連するテーマに近いものであれば、そのつながりを意識的に話すと、自分の話に一貫性と説得力を持たせられるのでおすすめですよ。
②日頃の読書週間を把握するため
面接官は、成長意欲があり、日々新しい知識を吸収する姿勢を持つ人材を求めています。そのため、読書習慣があるかどうかは、学ぶ意欲の象徴として評価されやすいポイントです。
必ずしも読書量が多い必要はありませんが、読んだ内容をもとに、自分の考えをしっかりと言葉にできることが重要でしょう。
大事なのは、どれだけ読んだかではなく、「なぜその1冊を選び、どう活かそうとしたか」という視点です。
もし、コミュニケーションを見直すために会話術の本を読んだと話せば、自己改善への取り組みとして伝わります。
選書の理由に加えて、その後の行動や変化まで一貫して話せると、面接官の信頼を得やすくなるでしょう。
③表現力・プレゼン力を見るため
この場面では、自分の考えを整理し、限られた時間で的確に伝える力が試されているのです。
どんなに内容が素晴らしくても、話が長くなったり、要点がぼやけてしまっては、相手には伝わりません。
面接で話す際には、PREP法(Point→Reason→Example→Point)を活用して構成するのがおすすめです。
最初に結論を述べ、その理由や具体例を挟んで、最後にもう一度要点をまとめることで、論理的かつわかりやすく伝えられます。
さらに、明るくはきはきと話す態度も加われば、内容と話し方の両面から高い評価につながるでしょう。練習を重ねて、自然に話せるようにしておくことが大切です。
とはいえ、「面接での受け答えは、どんな答え方が正解なのかわからない」「面接に苦手意識がある」と感じている方も少なくありません。以下の記事では、PREP法を活用した面接での答え方を紹介しているので、就活に向けて身につけたい方は参考にしてみてください。
最近読んだ本を聞かれた時のポイント
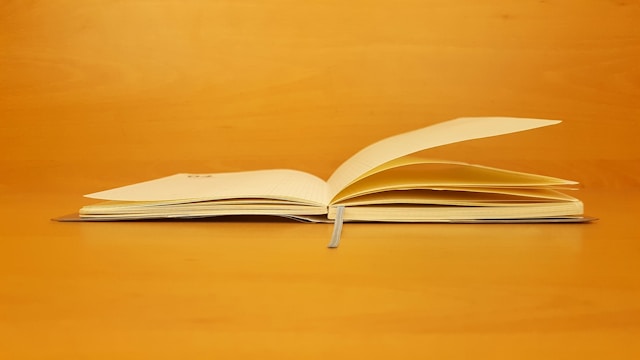
ここでは、より魅力的に伝えるために意識したい3つのポイントについて解説します。
- 本の内容より「なぜ読んだか」を伝える
- 実際に読んだ本を挙げる
- 本から得た知識をどう活かしているかを示す
①本の内容より「なぜ読んだか」を伝える
読書について質問されると、ストーリーの詳細を語ってしまう人が多いものです。
しかし、面接官が本当に知りたいのは、その本を手に取った背景や理由。選書の動機には、応募者の価値観や関心の向きが如実に現れるからです。
例えば、「専門知識を深めたかった」「自分の弱点を改善するヒントを求めた」などの具体的な目的があることで、回答に深みと納得感が生まれますよ。
実際に面接官が最も重視しているのは「なぜその本を選んだか」です。本を選んだ理由を話す際は、具体的な目的や背景を明確に示すことで話の内容に説得力を持たせられます。
また、本を読んだ上で学んだことや自分の行動がどう変わったのかも伝えると、自分の価値観や考え方がより明確になり、面接官に対して自分の人柄を印象付けられますよ。
「本を読んで、自分の行動はどう変わったのだろう……」と悩む方も多いでしょう。そんな方は、以下の記事を参考に自分史を作成して過去を振り返ることで、読書前後の心境の変化や自分の成長に気づけるかもしれません。
②実際に読んだ本を挙げる
読んでいない本を答えてしまうと、予想外の質問をされたときに答えられず、信頼を損ねるリスクがあります。
有名な書籍なら、面接官も内容を把握している可能性が高く、曖昧な説明ではマイナスの印象を与えてしまうかもしれません。
本の要約だけでなく、自分が特に印象に残った点や読んで感じたことを含めて話すと、より具体的で信頼感のある内容になります。
無理して難しい本を選ぶよりも、自分の言葉でちゃんと語れる1冊を選ぶほうが、結果として好印象につながるでしょう。
③本から得た知識をどう活かしているかを示す
どれほど感銘を受けた本でも、読んだだけで終わってしまってはアピールとしては弱くなってしまいます。
読書後に得たものを、日常生活や行動にどう反映させているかを語れると、「成長意欲のある人」として前向きな印象を与えられるでしょう。
「読書術の本を読んで以来、毎朝30分間の読書を習慣にした」といった実践エピソードを添えると効果的です。
本を読んで得た知識を、どのように自分の生活や考え方に取り入れているかを伝えることが大切です。読書をただの知識の吸収にとどめず、行動に移していることを示しましょう。
また、「実際にどう活かしているか」だけでなく、「業務にどう活かせそうか」「その学びを今後どう発揮するか」も話せると再現性のある学びとしてアピールできますよ。
面接が不安な人必見!振り返りシートで「受かる」答え方を知ろう

面接落ちを経験していくと、だんだんと「落ちたこと」へのショックが大きくなり、「どこを直せばもっとよくなるんだろう?」とは考えられなくなっていくものですよね。
最終的には、まだ面接結果が出ていなくても「落ちたかも……」と焦ってしまい、その後の就活が空回ってしまうことも。
「落ちた理由がわからない……」「次も面接落ちするんじゃ……」と不安でいっぱいの人にこそおすすめしたいのが、就活マガジンが無料で配布している面接振り返りシートです!
いくつかの質問に答えるだけで簡単に面接の振り返りができ、「直すべき箇所」「伸ばすべき箇所」がすぐに分かりますよ。また、実際に先輩就活生が直面した挫折経験と、その克服法も解説しています。
面接の通過率を上げる最大の近道は「過去の面接でどうして落ちた・受かったのか」を知ることです。面接の振り返りを次に活かせれば、確実に通過率は上がっていきます。
「最近読んだ本を聞かれたとき、どう答えたらよいのかわからない…」と思っている人も、まずは面接振り返りシートで、「次の面接への活かし方」を学んでいきましょう。
好印象を残す質問の答え方

面接での質問に備えて、答え方の流れをあらかじめ整理しておくと安心です。ここでは、好印象を残すために押さえておきたい4つのポイントを紹介します。
- 本のタイトルと著者名を伝える
- その本を選んだ理由を述べる
- その本から得た学びを説明する
- 得た学びをどう活かしているかを示す
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
①本のタイトルと著者名を伝える
最初に、読んだ本の正式なタイトルと著者の名前を間違いなく伝えることが基本です。
もし、面接官がその本を知っている可能性も考え、曖昧にせず、はっきりとした情報を伝えましょう。
あわせて、本のジャンルや簡潔な概要を添えると、会話の導入がスムーズになります。
冒頭できちんと概要を押さえておくことで、以降の説明にも説得力が生まれるでしょう。
②その本を選んだ理由を述べる
その本を手に取った背景や動機について話す際は、自分の関心や課題とどうつながっているかを伝えると効果的です。
「話題になっていたから」だけでは浅く受け取られる可能性があります。
たとえば、「チームでの役割に悩んでいたときに、リーダーシップを学べると思って選んだ」といったように、自分の思えや行動の背景が伝わると、面接官にも響きやすくなるでしょう。
目的が明確であれば、その後のエピソードにも一貫性が出ます。
答える際は、選んだ理由をまず一文で簡潔に伝え、そのあとに学びや行動の変化を伝えましょう。例えば「〇〇を高めたくこの本を選んだ。結果的に△△に繋がった」という流れで話すと簡潔でわかりやすいです。
また、業界や志望企業の課題と繋げられると、「目的を持って学べる人」という印象を与えられるのでおすすめですよ。本を選ぶ理由を話す際は意識してくださいね。
志望企業の課題と紹介する本を結び付けて答えるためにも、まずは企業研究を通して企業理解を深めることが大切です。以下の記事では、企業研究の進め方について詳しく紹介しています。
③その本から得た学びを説明する
面接官に感想を伝える際は、あらすじを追うのではなく、「自分にどんな気づきがあったか」「どの部分に心を動かされたか」に焦点を当てると印象的です。
「相手の立場を理解することの大切さを学んだ」や「自分の弱さを認める視点に気づかされた」といった、内面的な変化や気づきを交えて話すと、説得力が高まります。
他の候補者と差をつけるためにも、自分自身の視点で語ることを意識しましょう。
実は面接官は「学びの内容」だけでなく、その学びをどう行動に移したかまで見ています。書籍から得た気づきをサークル活動や学業などで実践したエピソードを伝えると行動力や実践力が伝わりやすいです。
さらに、学びを説明するときは企業が求める人物像と結び付けることが重要ですよ。チームワーク重視の企業なら本での学びから団結力を高めた経験を話すなど、活躍を想像できる内容にしましょう。
④得た学びをどう活かしているかを示す
本から得たことをこれからどう活かしていくかを伝えることで、実行力や前向きな姿勢がアピールできます。
ただ読んで終わりではなく、「実際にこう行動している」「これからこう活かしていきたい」といった具体的な例があると説得力が増すでしょう。
たとえば、「読書で学んだ時間管理方法を、毎日の予定の立て方に取り入れた」など、学びを行動に落とし込めていることを示すと、面接官にも前向きな姿勢が伝わりやすくなります。
就活生が読むのにおすすめの本のジャンル
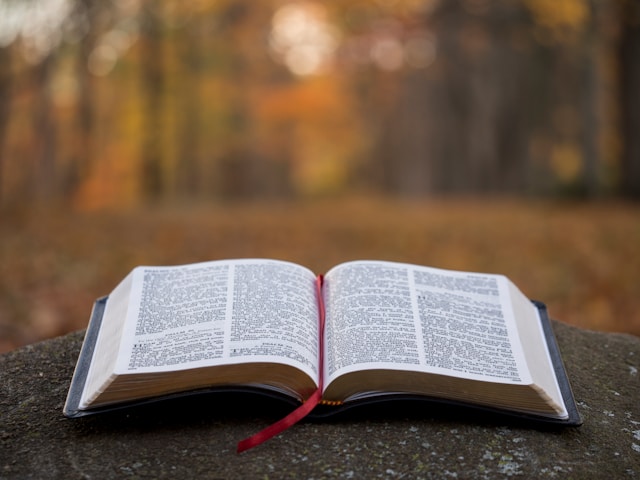
面接でどんな本を紹介すれば、印象に残るのか分からないと悩む就活生も多いのではないでしょうか?ここでは、面接官に好印象を与えやすい代表的な本のジャンルを紹介します。
- ビジネス書
- 自己啓発書
- 小説・エッセイ
①ビジネス書
ビジネス書は、就職後の実務や考え方に直結する知識が得られるため、就活生にとって非常に実用的なジャンルです。
このジャンルの本は、社会人として求められる論理的思考、プレゼンテーション力、時間管理、リーダーシップなど、ビジネスシーンで必要とされるスキルを幅広く学ぶ手助けとなります。
面接でこのジャンルの本を紹介することで、「仕事への関心がある」「入社後の成長をイメージできている」といった前向きな姿勢を示せるでしょう。
さらに、読書をきっかけに自分の話し方を見直した、スケジュールの立て方を工夫するようになったなど、具体的な変化を伝えると効果的です。
②自己啓発書
自己啓発書は、内面の成長や考え方の転換につながる要素が多く、自分自身の変化や行動のきっかけとして話しやすいジャンルです。
読んだ本によってどのように意識が変わったかを伝えることで、自己理解が深い人物として好印象を持たれることも。
このジャンルの魅力は、自分の価値観や人生観に影響を与えた具体的なエピソードと結びつけやすい点にあるでしょう。
たとえば、「他人と比較する癖を見直すようになった」「毎日の過ごし方に目的を持つようになった」といった内面的な気づきがあれば、それをどう実践しているかまで話すことで、説得力ある自己PRができます。
単に読んで良かったという感想にとどまらず、「自分の中で何が変わったか」「どう行動に反映されているか」を丁寧に言語化することがカギです。
自己啓発書は、ただ読んで終わりではなく、どのように実生活に活かしているかが重要です。学びを実践に移した過程やその結果を明確に伝えることで、自分の成長を証明できます。
また、自己啓発書を読んで得た気づきが日々の行動にどう影響を与えているかを説明する際には、できるだけ数値的な結果や具体例を挙げるとより説得力が増し、面接官側も信頼しやすいですよ。
③小説・エッセイ
小説やエッセイは、ビジネス書や自己啓発書とは違った角度から、自分の人間性や感受性を表現できるジャンルです。
特に、人との関わり方や価値観の多様性を描いた作品を通して、自分の人生観や社会に対する姿勢を語れます。
面接でこのジャンルを選ぶことで、思いやりや共感力といった「人柄」をアピールできるのが特徴です。
また、小説などのフィクション作品は、自分の経験に照らし合わせて共感した部分や、印象に残った登場人物の考え方を話すことで、独自の視点を伝えられます。
具体的には、「登場人物の決断が、自分の過去の選択と重なって印象に残った」「物語を通じて多様な生き方の価値に気づかされた」といった話し方が効果的です。
面接官は、あなたがどのような視点で物語を解釈し、そこから何を学んだかを知りたいのです。小説やエッセイを選ぶことで、思考力や他者の価値観への理解を伝えることができます。
伝える際のポイントとして、作品のテーマを就活の軸や志望動機に関連付けることを意識しましょう。自分の強みや今後の行動にもつなげて話すと、自分の価値観や人柄に一貫性を持たせられますよ。
そもそも就活の軸が定まっていないと、どのような小説やエッセイを選べばよいのか迷ってしまうでしょう。就活の軸の見つけ方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
「最近読んだ本」面接対策に役立つおすすめの10冊

面接で「最近読んだ本は?」と聞かれたとき、印象に残る回答をするには、本の内容そのものよりも、自分がどう感じたかや何を学んだかを言葉にして伝えることが大切です。
ここでは、就活生が答えやすく、かつ面接官の印象に残りやすい書籍を10冊紹介します。
- 『7つの習慣』
- 『嫌われる勇気』
- 『苦しかったときの話をしようか』
- 『夢をかなえるゾウ』
- 『エッセンシャル思考』
- 『1分で話せ』
- 『20代にしておきたい17のこと』
- 『ゼロ――なにもない自分に小さなイチを足していく』
- 『自分を操る超集中力』
- 『アウトプット大全』
①『7つの習慣』
多くの社会人に支持される定番の自己啓発書です。主体的に動く姿勢や信頼関係の築き方、長期的な目標の立て方など、社会に出たあとに役立つ考え方が数多く詰まっています。
読むことで、自分の行動や考え方を見つめ直す機会になり、自然と意識が変わってくるのを実感できるでしょう。
特に、就活で自己分析に悩んでいる方にとっては、自分の価値観を整理するヒントが得られるはず。就活の場面だけでなく、入社後も長く使える思考の土台をつくれる一冊です。
②『嫌われる勇気』
アドラー心理学をベースにした会話形式の書籍で、「他人と比べず、自分の人生を生きる」ことの大切さが学べます。
哲学的な要素を含みながらも、登場人物同士の対話で進んでいくため、心理学に詳しくない方でも読みやすい構成になっています。
就活を進めるなかで、自分の選択に迷いが生じたときや他人の目が気になるときに、考え方をリセットできる良いきっかけになります。自分の軸を見つめ直したいときに、ぜひ手に取ってみてください。
③『苦しかったときの話をしようか』
社会で働いてきた父親が、娘に向けて語るという形式で、仕事やお金、人生観といったテーマをわかりやすく、率直な言葉で伝えてくれるため、これから社会に出る学生にもすっと入り込んでくる内容です。
就活の不安や迷いに共感する場面も多く、自分の悩みが特別ではないと気づける安心感があります。
また、現実的で具体的なアドバイスが多く、自分自身の行動を見直すヒントにもなるでしょう。面接でも話しやすい実感のこもった本です。
④『夢をかなえるゾウ』
インドの神様「ガネーシャ」が主人公に課題を出しながら導いていく、物語形式の自己啓発書です。
ユーモアに富んだ語り口でありながら、「毎日の習慣が人生を変える」という本質的なメッセージが随所に込められています。
読みやすさと気づきのバランスが良く、自己成長に前向きな印象を与えやすい一冊です。
堅苦しい内容が苦手な方でも、自然に読み進められ、最後には前向きな気持ちになれる構成で、面接での話題にも適しています。
⑤『エッセンシャル思考』
「すべてをやろうとするのではなく、本当に重要なことに集中する」という思考法を紹介する本です。
情報過多な現代社会では、あれもこれもと手を出してしまいがちですが、この本は「やらないことを明確に決める」ことの価値を教えてくれますよ。
就活でも、数ある選択肢から自分に必要なものを選び取る判断力が問われています。
そのときに、この思考法は強い武器になります。効率よく動きたい方、時間の使い方を見直したい方にぴったりです。
⑥『1分で話せ』
「短く、わかりやすく伝える」ためのスキルが詰まった実践的なビジネス書です。就活では、面接やグループディスカッションなど、限られた時間内で自分の考えを伝える場面が多くあります。
この本では、結論から話すことの大切さや、PREP法などの基本的な話法を具体例を交えて学べるでしょう。話がまとまらない、伝わっている実感が持てないという方には特におすすめ。
面接対策だけでなく、社会人になってからも活かせる「伝える力」の基礎を身につけられる1冊です。
⑦『20代にしておきたい17のこと』
社会人になる前の若者に向けて、人生の土台づくりに役立つ行動や考え方が紹介されています。
内容は、仕事、人間関係、将来への向き合い方など、すぐに実践しやすいものが多く、漠然とした不安を抱える就活生にとっては心強い味方になるでしょう。
特に、「今のうちに意識しておくべきこと」が明確に書かれており、自分に足りない視点に気づかされる内容です。面接でも「この本を読んでから行動を変えた」と語れるような実用性の高さがあります。
⑧『ゼロ――なにもない自分に小さなイチを足していく』
著者の実体験をもとに、ゼロから一歩ずつ積み重ねる姿勢の大切さが綴られています。何も持っていない自分でも、少しずつ前に進むことで道が開ける、という前向きなメッセージが詰まった内容です。
就活中は「自分には何もない」と落ち込むこともありますが、この本を読むと、完璧でなくても踏み出す勇気を持つことが大切だと気づけるでしょう。
行動に迷っているときに読むと、自然と前を向けるようになる一冊です。
⑨『自分を操る超集中力』
現代の生活で失われがちな集中力を、科学的な視点から回復・維持する方法を紹介している本です。
スマホやSNSなど、多くの誘惑がある中で、どうすれば集中できる環境をつくれるかを、わかりやすく解説しています。
勉強や自己分析が続かない、自宅でなかなか集中できないという悩みを持つ方には特におすすめ。集中力を上げることで、限られた時間でも高い成果を出せるようになるヒントが得られるでしょう。
日々の行動にもすぐ活かせる実用性が魅力です。
⑩『アウトプット大全』
「学んだことは出すことで身につく」という考え方をベースに、アウトプットの重要性を解説した本です。
話す、書く、行動するなど、さまざまな方法を通じて知識を深めていく実践的なアイデアが詰まっています。
就活においても、学びを自分の言葉で伝える力は重要であり、この本の内容は面接やエントリーシートでの表現にも活かせます。
読み終えた後に、すぐ何かを「試したくなる」刺激にあふれた一冊。学びを成果に変えたい方に最適です。
どうせなら就活に役立つ本を読みたいと感じる方も多いでしょう。以下の記事では、就活生が読むべき本とその活用法を、自己分析や面接対策の視点から紹介しているので、本選びの参考にしてみてください。
ジャンル別に見る「最近読んだ本」面接回答例文
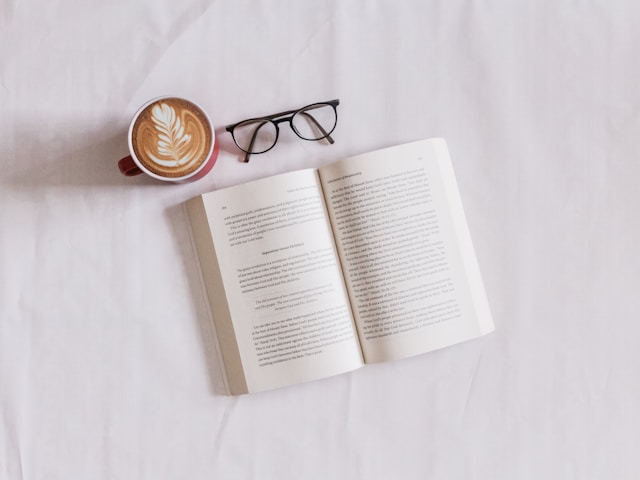
どんな本を紹介すれば面接官に良い印象を与えられるか悩んでいませんか?ここでは、ジャンル別に面接で好印象を与えやすい本と、それぞれの効果的な答え方の例文を紹介します。
自分に合ったジャンルを選び、説得力のある回答を準備しましょう。
- 自己啓発書『チーズはどこへ消えた?』を紹介する場合の例文
- ビジネス書『なぜUSJのジェットコースターは後ろ向きに走ったのか』を紹介する場合の例文
- 小説『コンビニ人間』を紹介する場合の例文
- 随筆『人間失格』を紹介する場合の例文
- エッセイ『生き方』を紹介する場合の例文
- ノンフィクション『FACTFULNESS(ファクトフルネス)』を紹介する場合の例文
- 歴史書『日本のいちばん長い日』を紹介する場合の例文
- 実用書『LIFE SHIFT』を紹介する場合の例文
志望先企業に合う本選びに悩む方は、OB・OG訪問も1つの手です。志望先企業への理解を深めたり、先輩社員から話を聞いたりすることで、何かヒントが得られるかもしれません。OB・OG訪問の進め方や基本マナーについては、こちらの記事で解説しています。
①自己啓発書『チーズはどこへ消えた?』を紹介する場合の例文
就職活動中に、変化への向き合い方や柔軟性をどのように伝えるかは非常に重要なポイントです。
ここでは、スペンサー・ジョンソンが著した自己啓発書『チーズはどこへ消えた?』を読んだことを通じて、前向きな姿勢をアピールする例文を紹介します。
《例文》
| 大学2年の頃、サークルの活動方針が急に変更され、戸惑った経験があります。それまでのやり方が通用しなくなり、最初はなかなか適応できませんでした。 そんな時に読んだのが『チーズはどこへ消えた?』です。登場人物たちの姿を通して、変化を恐れずに動き出すことの大切さを学びました。 それ以来、物事が変わったときに「どうしたら自分も前に進めるか」を考える習慣が身につきました。 この考え方は就職活動でも活かされていて、業界研究や自己分析でも自分の視点を柔軟に変えて取り組むよう意識しています。 これからも変化を前向きに捉え、学び続ける姿勢を大切にしていきたいです。 |
《解説》
この例文では、「変化にどう向き合ったか」を読書体験と実体験で結びつけています。読んだ本の影響が「行動の変化」として伝わると、説得力が増します。
②ビジネス書『なぜUSJのジェットコースターは後ろ向きに走ったのか』を紹介する場合の例文
発想力や課題解決力をアピールしたいときには、既成概念を打ち破る視点を学べる本を紹介するのが効果的です。
ここでは、森岡 毅さんのビジネス書『なぜUSJのジェットコースターは後ろ向きに走ったのか』を読んだことを通じて、ユニークなアイデアに触れ、自らの行動に活かしたエピソード例を紹介します。
《例文》
| 私は大学の学園祭実行委員として、来場者数の伸び悩みに直面した経験があります。 例年と同じ企画では目新しさがないと感じ、何か新しい工夫が必要だと思っていたときに読んだのが『なぜUSJのジェットコースターは後ろ向きに走ったのか』でした。 この本から、「常識を疑い、逆の発想で勝負すること」が時に大きな成果を生むということを学んだのです。 その考えをもとに、企画内容を逆転の発想で見直し、定番だった屋台の配置をあえて変更して動線を変えた結果、多くの来場者に新鮮さを感じてもらえました。 この経験は、課題に直面したときに柔軟な発想で対応する重要性を実感するきっかけとなったことを実感しています。 |
《解説》
この例文では、本から得た「逆転の発想」を行動にどう活かしたかが明確に語られています。抽象的な感想で終わらせず、変化した行動や結果を具体的に書くことが重要です。
③小説『コンビニ人間』を紹介する場合の例文
個性や他人との違いに悩んだ経験を持つ学生は少なくありません。
ここでは、村田 沙耶香さんの小説『コンビニ人間』を通じて「自分らしさ」や「他人との違いを認める姿勢」に気づいた体験をベースにした例文を紹介します。
《例文》
| 私は大学1年生の頃、周囲と価値観が合わず、サークル活動でもどこか浮いていると感じていました。そんなときに出会ったのが、小説『コンビニ人間』です。 主人公が「普通」に馴染もうと苦しみながらも、自分のペースで生きる姿に強く共感しました。 それをきっかけに、他人と違う自分を否定するのではなく、「何が得意か」「どこで力を発揮できるか」を考えるようになったのを覚えています。 その後、私はアルバイト先で接客リーダーを任されることになり、細かな気配りや観察力を評価されました。 自分にしかできないことに自信を持てたことで、以前よりも前向きに物事に取り組めるようになったのが良い経験となっています。 |
《解説》
この例文では、小説のテーマを自己理解につなげた点がポイントです。読書によって得た気づきを、行動の変化や成長エピソードとセットで語ると説得力が増します。
④随筆『人間失格』を紹介する場合の例文
人との関わりに悩んだ経験や、自分の弱さと向き合ったことがある人には、それを前向きに語れる本の紹介が効果的です。
ここでは太宰 治の『人間失格』を通して、自分自身を見つめ直した体験を伝える例文を紹介します。
《例文》
| 私は大学生活の初め、周囲の期待に応えようと無理をしていた時期があり、自分らしさを見失いかけていました。 そんなときに読んだのが太宰治の『人間失格』です。主人公が他人との関係の中で苦しみ、自分を否定しながらも生きようとする姿を通して、「弱さも自分の一部だ」と受け入れる大切さに気づきました。 それ以来、私は無理に理想の自分を演じるのではなく、できることからコツコツ努力する姿勢に切り替えるように。 その結果、人前で発言することへの苦手意識が少しずつ薄れ、ゼミではプレゼンを任されるまでになりました。弱さに向き合った経験が、自分にとっての強みに変わったと感じています。 |
《解説》
自己の弱さや苦手意識を、読書をきっかけに克服したことが伝わる好例です。感情的な本でも、読み終えた後の行動変化を具体的に語ることが面接では重要となるでしょう。
⑤エッセイ『生き方』を紹介する場合の例文
将来に対する不安や、社会に出ることへの迷いを抱えている就活生にとって、人生観を深める読書体験は自己理解の手助けになります。
ここでは、稲盛和夫さんの『生き方』を読んだことによって、自分の価値観に気づいた体験を伝える例文を紹介しましょう。
《例文》
| 就職活動を意識し始めた頃、私は「自分は何のために働くのか」という問いに悩んでいました。そんな時、稲盛和夫さんの著書『生き方』を手に取りました。 本書では、仕事とは単なる生計手段ではなく、「人としてどう生きるか」が大切だと説かれています。その言葉に強く心を打たれ、自分も誠実さや努力を大切にした働き方をしたいと考えるようになりました。 それからは、自分の価値観に合う企業を探すことを意識するようになり、説明会では企業理念や社員の働き方にも注目するようになりました。 この本を読んだことで、自分の判断基準を持って就活に臨めるようになったと感じています。 |
《解説》
この例文は、「働く意味」や「自分の価値観」を深く考えたことを示しています。人生観に関わる本を紹介する場合は、それが行動や判断にどう結びついたかまで書くと効果的です。
⑥ノンフィクション『FACTFULNESS(ファクトフルネス)』を紹介する場合の例文
情報に流されず、自分で物事を判断する力を持っていることは、社会人として大きな強みです。
ここでは、ハンス・ロスリングのノンフィクション『FACTFULNESS(ファクトフルネス)』を通じて、データや事実に基づく考え方を学んだ経験をもとにした例文を紹介します。
《例文》
| 大学のゼミで国際問題を扱うプレゼンを行った際、ネット上の印象的な話に頼ってしまい、指導教官から「根拠が薄い」と指摘を受けたことがあります。 その反省をきっかけに読んだのが『FACTFULNESS』でした。この本では、世界に対する私たちの思い込みがいかに間違っているかを、データに基づいて教えてくれます。 特に「ネガティブな情報ばかり信じてしまう傾向がある」と気づかされたことで、以後は報道や資料を見るときに「これは事実か?」と自分で考える習慣がつきました。 この姿勢は、課題に取り組む際の分析力にもつながっており、就職活動でも情報の見極めを意識して企業研究を行っています。 |
《解説》
この例文では、「本で得た知識」が思考の変化にどうつながったかが明確です。知的なテーマの本を紹介する場合は、自分の行動や姿勢にどう影響したかを具体的に示すと説得力が高まります。
⑦歴史書『日本のいちばん長い日』を紹介する場合の例文
責任感や冷静な判断力といった社会人としての資質をアピールしたいときは、歴史的な決断に触れた本を紹介すると効果的です。
ここでは、半藤一利さんの歴史書『日本のいちばん長い日』を通して得た学びをもとにした例文を紹介します。
《例文》
| 大学の授業で太平洋戦争を学んでいた際に手に取ったのが『日本のいちばん長い日』でした。 終戦間際の1日を克明に描いた内容で、国の未来を左右する重い決断が、どれほどの葛藤と責任の中で行われたかを知ることができ、衝撃を受けたのを覚えています。 特に、個人の信念と国全体の利益を天秤にかけながらも、最終的には国民の命を守るために下された判断に深く感動しました。 この読書体験は、自分がゼミのリーダーを任されたときの判断時にも活かせました。 メンバーの意見が分かれる中でも、全体の進行や完成度を最優先に考え、方向性を決定することの重さを意識できたのです。責任を持って決断することの大切さを学ぶきっかけになりました。 |
《解説》
歴史書を扱う際は「学術的な知識」に終わらせず、それを自分の経験にどう活かしたかを語ることがカギです。自分の判断力やリーダーシップに結びつけると面接官に伝わりやすくなります。
⑧実用書『LIFE SHIFT』を紹介する場合の例文
キャリア観や人生設計への意識をアピールしたい場面では、長期的な視点を持てるようになった読書体験が有効です。ここでは、実用書の『LIFE SHIFT』を読んで将来の考え方が変わった例を紹介します。
《例文》
| 就職活動を始めたばかりの頃は、「安定した企業に入ることがゴール」だと思っていました。しかし、大学のキャリア講座で紹介されて読んだ『LIFE SHIFT』によって、その考え方が大きく分かることに。 この本では、人生100年時代を見据えた柔軟なキャリア形成の必要性が説かれており、一つの仕事だけにこだわらず、自分の価値を高め続ける姿勢が重要だと気づかされました。 その後は、短期的な待遇よりも、長く成長できる環境かどうかを基準に企業を見るようになりました。 今では、自分の強みを磨き続けるために学びを継続する意識が芽生え、資格取得にも前向きに取り組んでいます。この本が私のキャリア観に大きな影響を与えてくれました。 |
《解説》
この例文では、読書によって価値観や行動がどう変わったかを就活の視点で具体的に示しています。将来志向の本を選んだ場合は、変化した考え方とその実践内容を明確に書くと効果的です。
「最近読んだ本」の質問で避けたいNG回答例
面接で「最近読んだ本」を尋ねられたとき、どのように答えるかで評価が大きく変わるでしょう。
内容が優れた本を選んでいたとしても、話し方や伝え方次第でマイナスに受け取られてしまうことも。ここでは、特に避けたいNG回答の例を紹介します。
- 「最近本を読んでいない」と答える
- 読んでいない本について語る
- ライトノベルや漫画を紹介する
- 内容を曖昧にして伝える
- 本のあらすじだけ話す
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
①「最近本を読んでいない」と答える
「忙しくて最近は本を読んでいません」と答えてしまうと、自己研鑽の意識が低いと思われかねません。企業は知的好奇心や自発的な学びの姿勢を重視しています。
仮に本当に最近読んでいなかった場合でも、過去に印象に残った本を紹介しましょう。その本から得た学びや影響を具体的に伝えることが大切です。
内容よりも、それをどう受け取り、行動に移したかが評価の分かれ目となるでしょう。
最近読んでいない理由を正直に話す場合は、学びへの姿勢を示すことが必要です。「読書ができていない分、別の方法で自分を成長させている」という姿勢を見せましょう。
例えば、オンライン講座や業界に関連するニュースをチェックしているなどは自己研鑽が感じられます。読書を最近していない人は、読書以外で自分を成長させている学びがないか振り返ってみてくださいね。
あまり読書をしない方も、自己研鑽をアピールするために新聞を読むのはおすすめです。以下の記事では、就活で新聞を読むべき理由や効率的な活用法、おすすめの新聞、習慣化のコツを徹底解説していますよ。
②読んでいない本について語る
よく見られたいという気持ちから、実際には読んでいない本について話すのは危険です。もし面接官に内容を深掘りされて答えに詰まれば、信頼を損なう恐れも。
表面的な受け答えではなく、その人の誠実さや本質を見ているからです。
本を紹介する際は、自分がきちんと読んで理解し、印象に残ったものを選んでください。そして何を感じ、どう考えたかを自分の言葉で伝えることが大切です。
正直に語る姿勢は、かえって好印象につながるでしょう。
面接官は、本人の学ぶ姿勢や物事への向き合い方を見ています。有名な本でなくても、自分の考えや行動に影響を与えた一冊の方が熱意や人柄が伝わりやすいですよ。
また、日ごろから読んだ本や記事のポイントをメモに簡単に残しておくのをおすすめします。面接前に見返せば内容や感想が整理され、自分の言葉で自然に話しやすいです。
③ライトノベルや漫画を紹介する
自分にとって感動的な内容であっても、ライトノベルや漫画を紹介するのは避けましょう。一般的にはビジネス書や教養書のほうが誠実で意欲的な印象を与えます。
ただし、どうしても紹介したい場合は、作品の中から得た気づきや考え方の変化を具体的に語りましょう。
選書ひとつであなたの価値観や考え方が伝わるため、慎重に判断してください。
④内容を曖昧にして伝える
「なんとなく良かった」「学びがあった気がする」といった曖昧な説明は、説得力に欠けてしまいます。
面接では、具体的にどんなことを学び、それがどんな変化につながったのかを伝えることが必要です。
たとえば「時間の使い方を見直すようになった」など、行動や意識の変化まで含めて話すことで、あなたの成長意欲を伝えられるでしょう。
抽象的な表現ではなく、はっきりと伝えることを意識してください。
⑤本のあらすじだけ話す
本の要約を話すだけでは、面接官にとっては情報として物足りないと感じられる可能性があります。
求められているのは、「その本から何を得て、どう変わったか」というあなた自身のエピソードです。
「この本を読んでから、人との接し方に意識的になった」といったように、自分の経験や行動と結びつけて話すと、説得力がぐっと増します。
あらすじは補足程度にとどめて、自分の考えを中心に話してください。
面接で聞かれる「最近読んだ本」に関する他の質問

「最近読んだ本」に関する質問は、本のタイトルを答えるだけでは終わりません。面接官は、あなたの考え方や人柄を知るために、関連する深掘り質問をしてくるでしょう。
ここでは、よく聞かれる質問を4つ取り上げ、その答え方のポイントを紹介します。
- 「好きなジャンルは?」
- 「最近読んだ本の印象的なシーンは?」
- 「自分がおすすめする本は?」
- 「最近読んだ本から得たスキルは?」
①「好きなジャンルは?」
この質問では、あなたの興味や価値観が見られています。たとえば、ビジネス書やエッセイが好きだと伝えると、自己成長に関心のある人物だと感じてもらえるでしょう。
反対に、なぜそのジャンルが好きなのかを説明できなければ、印象に残りにくくなってしまいます。
「考え方を広げてくれる内容が多いので、社会に出る前に学びたい」といったように、背景もあわせて伝えてください。自分らしさを出しつつ、目的をもって読書していることが伝わると好印象です。
とはいえ、そもそも「自分らしさって何だろう」と悩む方は、まず自己分析から始めてみましょう。以下の記事では、効果的な自己分析の方法や進め方について詳しく解説しています。
②「最近読んだ本の印象的なシーンは?」
この質問は、きちんと読んでいるかを確認する意図があります。印象に残った場面を具体的に挙げて、その理由を説明することで、読解力や感受性を伝えられるでしょう。
「主人公が失敗を乗り越えて再挑戦するシーンに共感した」といった具合に、自分の経験や価値観と結びつけて話してください。あらすじの紹介だけに終始せず、自分の言葉で語ることが重要です。
③「自分がおすすめする本は?」
この問いでは、あなたの判断力や他者への配慮が問われます。誰にどんな理由で勧めたいのかを具体的に語ることがポイントです。
「就活で悩んでいる友人に、自分の視野を広げてくれた一冊を伝えたい」といったように、相手を想定して話すと説得力が増します。
ただ「面白かった」ではなく、どのような気づきや変化があったかも合わせて話してください。
この質問では、自分が大切にしている考え方や行動指針を、その本を通じて相手にどう共有するかが見られています。本人の価値観や他者との関わり方を見ているのです。
質問に答える際は、すすめる相手の状況を踏まえた上で「その人の課題解決の手助けになると思うからすすめたい」というような理由を示すと他者への配慮も伝わるのでおすすめですよ。
④「最近読んだ本から得たスキルは?」
この質問では、読書を自分の成長につなげられているかが見られています。
「自己管理術を学んで、毎朝の予定を手帳に書くようになった」といったように、具体的な行動や習慣に落とし込めているかがポイントです。
抽象的な感想だけでなく、スキルとして何を得たか、それをどう活かしているかを伝えてください。読書を単なるインプットにとどめず、日常や行動に活かしている姿勢が評価されやすくなります。
面接で「最近読んだ本」を効果的に伝える方法を知ろう!

「最近読んだ本は」という質問が面接で出るのは、あなたの人柄や思考、そして読書から何を学び、どう活かしているかを知るためです。
そこで問われるのは、どんな本を読んだかよりも、「なぜそれを選んだのか」「何を学び、どう行動に移したのか」だったりします。
適切に伝えるためには、本の選び方や伝え方に加えて、好印象を与える答え「方を活用し、具体的に表現することが重要です。
また、ビジネス書や自己啓発書など、就活に適したジャンルを選ぶことも印象を大きく左右します。NG回答やよくある関連質問にも事前に対応しておくことで、面接本番での失敗を防げるでしょう。
読書経験を自己PRにつなげる準備が、面接突破のカギとなります。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












