インフラ業界とは?業務内容・年収・向いている人まで徹底解説!
「安定した仕事に就きたい」「社会の役に立つ仕事がしたい」そんな思いから、インフラ業界に興味を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、インフラ業界の基本から最新の動向、具体的な業務内容や平均年収、さらには向いている人の特徴や注意点まで、わかりやすく解説します。
就職・転職を考えている方が自分に合ったキャリアを描けるよう、準備のポイントや自己分析の方法も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
インフラ業界とは?

インフラ業界は、電気・ガス・水道・交通・通信といった、私たちの暮らしに欠かせない社会基盤を支える業界です。
ここでは、そんなインフラ業界の「現在の動向」と「直面している課題」について、わかりやすく解説していきます。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
①インフラ業界の動向
インフラ業界は、景気の影響を受けにくく安定した業界ですが、少子高齢化や環境問題、デジタル技術の進展により変革が求められています。
近年ではスマートインフラの開発が進み、都市部を中心にIoTやAIを活用した効率的な管理が導入されるようになりました。
さらに、脱炭素化の流れを受けて再生可能エネルギーの活用が重要視され、環境負荷の低減に向けた取り組みが加速しています。
こうした変化に対応するため、新しい発想や技術の導入が欠かせず、若い世代の活躍にも期待が寄せられています。
②インフラ業界の現状・課題
社会を支える重要な役割を担うインフラ業界は、現在さまざまな課題に直面しています。
そのひとつが、老朽化した設備の更新です。日本国内のインフラは建設から数十年を経ているものが多く、適切な維持管理や改修が求められています。
しかし、専門性の高い技術者の高齢化が進み、人材不足が深刻化しているため、若手の育成が急務となっています。
また、日本は自然災害が多い国であり、地震や台風などへの備えは不可欠です。既存のインフラを災害に強い構造へと改修する取り組みが進んでいますが、予算や人材の確保が十分とは言えません。
さらに、地方ではインフラを維持する事業者が減少し、後継者不足も深刻な問題となっています。持続可能な事業環境を整えるため、新たな施策や改革が求められている業界なのです。
インフラ業界8分野の業務内容

ここでは、インフラ業界を支える8つの主要分野の業務内容を紹介します。
自分の適性や関心に合った分野を見つけるための参考として活用してください。
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
①電力
電力インフラは、私たちの生活や産業に欠かせない電気の安定供給を担っています。
2016年には電力小売が自由化され、民間企業の参入が進みました。その結果、消費者は自分に合った電力会社を自由に選べるようになりました。
電力分野には、発電・送電に関わる「技術職」や、電気料金プランを提案する「営業職」のほか、「事務職」や「電気工事士」といった職種があります。
②水道
安全な飲料水を安定して供給し、人々の暮らしと健康を支える重要な役割を担うのが水道インフラです。
水道事業には厚生労働省や都道府県知事の認可が必要で、給水人口に応じて「簡易水道」や「上水道」に分類されます。
また、水道分野における代表的な職種は、水道設備の工事や新技術の導入に携わる「技術職」、人事・総務・法務などを担当する「事務職」などが挙げられます。
③ガス
ガス業界は、都市ガスやLPガスといったエネルギーを家庭や企業へ届ける役割を担っています。全国に多くのガス会社があり、それぞれが地域ごとに事業を展開している点が特徴です。
近年では、単にガスを届けるだけでなく「環境に配慮したエネルギー供給」も求められるようになりました。たとえば、家庭用燃料電池「エネファーム」のような発電技術がその1つです。
代表的な職種としては、設備の管理や点検を行う「技術職」、顧客対応を行う「営業職」、社内業務を支える「事務職」などがあります。
④鉄道運輸
鉄道運輸分野は、人や荷物を鉄道によって安全・確実に運ぶインフラとして、都市の発展や人々の移動を支えています。
近年では、鉄道の運行だけでなく、駅ビルの開発やショッピング施設・ホテルの運営にも力を入れる企業が増えてきました。そのため、職種の幅も非常に広いことが特徴です。
具体的には、鉄道の運行に直接関わる「運転士」「駅係員」「グリーンアテンダント」「技術職」のほか、駅周辺施設の開発や運営を担う「企画職」「営業職」「広報職」などの職種が挙げられます。
⑤航空
航空分野は、人や貨物を空路で運ぶ重要な交通インフラです。
理系・文系を問わず活躍の場があるのが魅力で、飛行機の運航、整備、空港施設の管理、空港内テナントの運営やイベントの企画・実施など、業務は多岐に渡ります。
就職先としても、ANAやJALといった国内の大手航空会社をはじめ、外資系の航空会社や航空機メーカーなど、幅広い選択肢が用意されています。
代表的な職種には「客室乗務員」「パイロット」「グランドスタッフ」「航空整備士」「営業職」「事務職」などがあり、機内食に関わる「製造職」や空港内店舗の「販売職」もありますよ。
⑥通信・IT
通信・IT分野は、インターネットや電話といった通信インフラを提供する業界で、私たちの生活に欠かせない役割を果たしています。
この分野では、電力や水道のような現場作業が中心の業界とは異なり、パソコンやシステムを使った業務が主軸となっていますよ。
とくに重要なポジションを占めているのが、ネットワークの構築やシステム開発に関わる「エンジニア職」です。
また、スマートフォンや通信サービスを個人や法人に提案する「営業職」や、利用者のニーズや市場動向を分析して新しいサービスを企画・立案する「マーケティング職」などの職種が存在します。
⑦道路・建設
道路・建設分野は、道路・橋、そしてトンネルなどの社会インフラを整備し、それらを維持・補修していく役割を担っています。
インフラ設備の老朽化が進む現在では、新たな建設だけでなく既存設備の保全業務の重要性も高まっており、将来的にも安定した需要が見込まれる分野です。
また、工事の多くは国や自治体から発注される公共事業として実施されるため、社会への貢献度が高い点も特徴です。
主な職種には、現場全体の進行を管理する「施工管理」や「現場監督」、専門技術を生かして作業を行う「職人(建設・電気・配管など)」があります。
そのほか、図面の作成や費用の積算を担当する「設計職」「専門職」、そして「営業職」や「事務職」といった職種も幅広く活躍しています。
⑧その他のインフラサービス
「インフラ=生活の基盤を支えるもの」と考えると、教育・福祉・観光・外食・冠婚葬祭のようなサービス業も、広義ではインフラに含まれる場合があります。
実際、インフラ業界に明確な定義があるわけではなく、生活に欠かせない要素を提供している分野であれば、インフラ的な側面があると言えるでしょう。
たとえば、食品業界は一般にはインフラとは分類されませんが、私たちの暮らしに欠かせない存在であり、社会の安定を支える重要な役割を担っています。
「業界分析」はこれ1冊だけ!業界分析大全を受け取ろう!
就活で志望業界を説得力高く語るには、「なぜこの業界なのか」をデータやトレンドで裏づける業界分析が欠かせません。とはいえ、IR資料やニュースを一から読み解くのは時間も手間もかかり、表面的な理解で面接に臨んでしまう学生も少なくありません。
そこで就活マガジン編集部では、主要20業界を網羅し「市場規模・最新トレンド・主要企業比較」まで1冊で整理した『業界分析大全』を無料提供しています。業界研究に迷ったら、まずはLINEを登録で特典をダウンロードして「面接で差がつく業界知識」を最短で手に入れてみましょう。
業界知識の深さは選考官が必ずチェックするポイントです。志望度の高さもアピールできるのでおすすめですよ。
インフラ業界の平均年収

インフラ業界の平均年収は、分野によって大きな違いがあります。令和5年の民間給与実態統計調査をもとに、具体的に見てみましょう。
| 分野 | 平均年収 |
| 電気・ガス・水道 | 775 万円 |
| 運輸業・郵便業 | 473万円 |
| 情報通信業 | 649万円 |
「電気・ガス・水道分野」は特に高水準で、全国平均の460万円を大きく上回っています。これは、インフラの中でもライフラインに直結し、高度な専門性や責任を伴う仕事が多いためです。
一方で、運輸業や郵便業は他分野と比べると年収は低めで、業務量や勤務形態の厳しさに対して給与面に課題を感じる声もあります。
就職活動では、「業界全体のイメージ」だけで判断せず、分野ごとの年収差や将来性、働き方の違いにも注目して業界研究を進めることが大切ですよ。
安定志向の人におすすめ!インフラ業界で働く5つのメリット

ここでは、インフラ業界で働く5つのメリットを紹介します。
インフラ業界の魅力を知って、ぜひ自分に合った業界選びに役立ててみてくださいね。
①需要が安定している
インフラ業界の最大の強みは、需要が安定していることにあります。
人々の暮らしに欠かせないライフラインを担っているため、社会の状況が変わっても需要が急激に落ち込むことは考えにくく、雇用や事業の安定性が保たれやすいのです。
この「需要がなくならない」という構造的な強みは、将来に不安を感じずに働き続けたい人にとって、大きな安心材料となるでしょう。
②福利厚生や待遇が整っている
インフラ業界のメリットに、福利厚生や待遇が良いことがあります。電気・ガス・水道業の平均年収は775万円(※令和5年の民間給与実態統計調査)と、他業種と比べても高水準です。
勤続年数や実績に応じて着実に収入が上がる企業が多いため、「長く働けば働くほど報われる」という実感も得やすいでしょう。
また、住宅手当や資格手当、退職金制度なども整っている場合が多く、働く人が安心して長く勤められる環境づくりが進められていることも特徴です。
③専門性のあるスキルが身につく
インフラの仕事では、日々の業務を通して専門的な知識やスキルを磨けます。たとえば、設備の運用管理やシステム保守、災害対応などは、現場でしか得られないノウハウが蓄積される領域といえるでしょう。
また、企業によっては資格取得の支援や研修制度も整っており、働きながら着実にスキルアップできる環境がが整っています。
こうして身につけたスキルは、将来的に社内外でのキャリアの幅を広げるための強みとなるでしょう。
④社会に貢献している実感を得られる
「自分の仕事が社会を支えている」という実感を得られることも、インフラ業界で働くメリットの1つでしょう。
目に見える形で人々の生活を支えられるので、日々の仕事に意味や誇りを感じられる機会が多いのです。
例えば、災害時の対応やインフラの復旧作業に携わったときなどは、特にその重要性を実感できるでしょう。
感謝の言葉を直接受け取る場面も多く、「人の役に立っている」という感覚を大切にしたい人にはぴったりの業界ですよ。
⑤文系・理系を問わず活躍できる
インフラ業界=理系の仕事というイメージがあるかもしれませんが、実際には文系出身者が活躍するフィールドも豊富にあります。
たとえば、営業、企画、人事、広報、経理などのバックオフィス系や、運行管理・サービス業務などの職種は文系出身者が多く活躍していますよ。
さらに近年では、ITやデジタル技術の導入が進み、学部を問わず多様な人材が求められています。インフラ業界は、専攻や得意分野にかかわらず活躍できるチャンスがある業界と言えるでしょう。
注意が必要?インフラ業界で働くうえでの4つの課題

ここでは、インフラ業界を志望するうえであらかじめ知っておきたい4つの注意点を紹介します。
インフラ業界は「安定していて、高収入も期待できる」といった魅力が語られる一方で、人によっては合わないと感じるポイントも少なくありません。
入社前にこうした実情を知らずに飛び込んでしまうと、後悔につながるリスクもあるため、しっかりと把握しておきましょう。
①転勤の頻度が高い場合がある
インフラ業界の多くの企業は、全国各地に事業所や拠点を持っているため、異動や転勤が発生しやすい傾向にあります。
「地元で働きたい」「家族と一緒に暮らしたい」といった想いが強い人にとっては、転勤の多さがストレスになるかもしれません。
ただし、企業によっては地域限定の働き方を選べるケースもあるため、募集要項や採用制度をしっかり確認することが重要です。
②昇進には年功序列の影響がある
インフラ業界では、いわゆる「年功序列」の文化が色濃く残っている企業も多くあるため、若手のうちは昇進やポジションアップが限定されがちです。
そのため、スピード感を持ってキャリアを積みたい人や、成果主義の環境を好む人にとっては、物足りなさを感じるかもしれません。
もちろん、最近では実力を正当に評価する企業も増えてきていますが、伝統的な企業文化が根付いた社風には注意が必要です。
③保守的な社風の企業が多い
安全性や信頼性が第一とされるインフラ業界では、ミスやリスクを最小限にするため、既存のやり方を守る傾向が強い企業も少なくありません。
その結果、「新しいアイデアを提案しても通りにくい」「変化を歓迎する風土ではない」と感じる場面に直面することもあります。
創造性を発揮したい人や、新しい技術・仕組みを導入して現場を変えていきたいと考える人にとっては、物足りなさを感じるかもしれません。
➃夜勤やシフト勤務の可能性がある
インフラの仕事は、夜勤やシフト勤務の可能性があります。生活を支える「止めてはならない」サービスを提供しているため、昼夜問わず稼働が必要な現場が多いからです。
夜勤やシフト勤務に対応することで、生活リズムを整えにくいと感じる人もいるでしょう。
すべての職種がそうではありませんが、夜間対応や交代制勤務がある可能性は頭に入れておいた方が安心です。
インフラ業界に向いている人の5つの特徴

ここでは、インフラ業界に向いている人の5つの特徴を紹介します。
自分に合った仕事を見つけるためには、業界ごとの特性や向いている人の傾向を知っておくことが大切ですよ。
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
①責任感を持って仕事に取り組める人
インフラ業界に向いているのは、強い責任感を持ち、使命感をもって自分の役割を全うできる人です。インフラの仕事は、日常生活だけでなく、人命や経済活動にも大きく関わっています。
たとえば、鉄道の運行管理や電力設備の保守では、1つの判断ミスが遅延や事故に直結するため、常に正確で冷静な対応が欠かせません。
さらに、災害時にはインフラ復旧のため、深夜や悪天候の中で作業にあたることもあります。
このように「誰かがやらなければ生活が成り立たない」という意識を持てるかが問われる場面が多い現場で信頼を集め、長く活躍できるのは、自分の仕事に責任と誇りを持てる人だと言えるのです。
②ルールや手順を守るのが得意な人
インフラ業界は、決められたルールや手順をきちんと守って作業できる人に向いています。
たとえば電力会社では、送電に関わる設備の点検を行う際に「マニュアル通りに進めること」が厳しく決められています。
また、鉄道会社では保守作業のスケジュールを秒単位で管理することもあり、時間の使い方や手順の正確さがとても重視されます。
そのため、ひらめきや自由な発想よりも、落ち着いて物事を進められる人や、こつこつと確実に作業を積み重ねられる人に向いている業界といえるでしょう。
③安定した働き方を重視する人
インフラ業界は景気や流行に左右されにくいため、将来にわたって安定した働き方を望む人に向いています。
また、公共性の高い事業であることから、会社が急激に経営破綻するリスクも比較的低く、安定した収入・職場環境を求める人にとっては理想的な業界です。
ライフプランを重視したい人、転職を何度も繰り返したくない人にとって、長期的なキャリアを描きやすい業界だと言えるでしょう。
④社会貢献にやりがいを感じる人
インフラ業界は、人や社会の役に立つことに喜びを感じる人が向いています。
たとえば、道路の維持管理に携われば「あの橋は自分が補修した」と実感でき、鉄道のダイヤ調整に関われば「毎日の安全で快適な移動を影で支えている」と実感できるでしょう。
このように、インフラは目に見える形で人々の生活を支えているため、自分の仕事が直接誰かの役に立っていることを実感しやすいのです。
また「この社会に貢献している」という自覚は、働くうえでのモチベーションになるでしょう。
⑤コミュニケーションスキルが高い人
インフラ業界は、コミュニケーションスキルが高い人が向いていますよ。たとえば、鉄道会社の駅員や電力会社のカスタマーサポートなどは、日々さまざまな利用者や関係者と接します。
また、設備保守や工事現場でも、チーム内の連携や報告・連絡・相談(ホウレンソウ)が非常に重要です。特に緊急時の対応では、現場全体が連携して動かなければ迅速な解決ができません。
また状況を正確に伝えたり、相手の意図をくみ取ったりするコミュニケーション能力は、技術職・事務職問わずどの職種でも重宝されますよ。
インフラ業界に就職・転職する人が今すぐ始めたい4つの準備
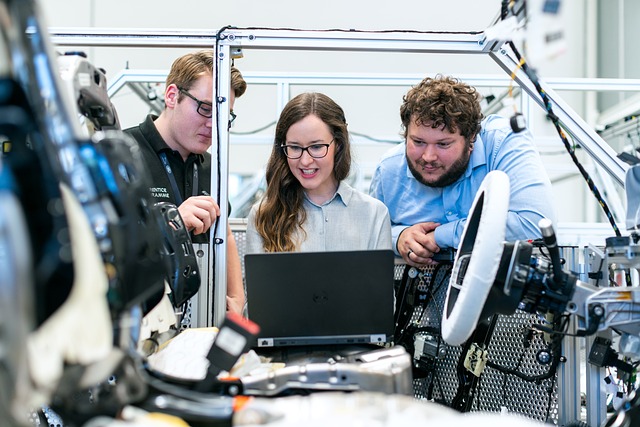
ここでは、インフラ業界に就職・転職を成功させるために、今すぐ始めたい4つの準備について紹介します。
インフラ業界を目指すうえで大切なのは、「なんとなく安定してそうだから」といったイメージだけで動かないことです。
この業界は、分野によって求められる適性やスキルが大きく異なるため、しっかりとした準備があるかどうかで内定の可能性が大きく変わりますよ。
- 自己分析で自分に向いているインフラ業界の分野を知る
- 業界研究を通して、技術革新や社会貢献性への理解を深める
- 就活でアピールできる語学・専門資格を取得する
- 志望企業の理解を深めるため、インターンや合同説明会に参加する
①自己分析で自分に向いているインフラ業界の分野を知る
インフラ業界は、電力、ガス、水道、交通、通信、建設など多岐にわたるため、自分の強みや価値観に合った分野を見極めることが大切です。
たとえば、「チームで動くのが好き」「現場で体を動かしたい」という人は、保守・施工・運輸系の仕事が向いているかもしれません。
一方、「計画を立てて物事を進めるのが得意」「社会に貢献する仕組みを考えたい」という人には、技術開発や設計、経営企画のような職種がフィットする可能性があります。
このように自分の価値観や性格を掘り下げることで、安易に「向いていないかも」と判断してしまうリスクを回避するだけでなく、志望動機の説得力も高まるでしょう。
自分1人での自己分析に不安がある方は、就活のプロと一緒に自己分析をしてみませんか?あなたらしい長所や強みが見つかり、就活がより楽になりますよ。
②業界研究を通して、技術革新や社会貢献性への理解を深める
インフラ業界を研究して、技術革新や社会貢献性への理解を深めることも大切です。
この業界は「変化が少ない」と思われがちですが、実際にはデジタル技術や再生可能エネルギー、災害対応などの最前線に立つ業界でもあります。
こうした特徴を深掘りして自分が関わりたい事業や社会課題を明確にすることで、志望企業の選定に役立つだけでなく面接対策にもなるでしょう。
③就活でアピールできる語学・専門資格を取得する
インフラ業界に就職する際、就活でアピールできる語学・専門資格を取得することは大きなアドバンテージになります。
外資系企業や海外事業を展開している企業では、TOEICスコアや英会話力が評価されるでしょう。
また、電気主任技術者、管工事施工管理技士、第二種電気工事士などの技術系資格は、早期に取得しておくと応募可能な職種が一気に広がります。
資格の取得は、単なるスキルの証明だけでなく、「インフラ業界に本気で挑もうとしている姿勢」をアピールする材料になるのです。
④志望企業の理解を深めるため、インターンや合同説明会に参加する
インフラ業界を目指すなら、志望企業の理解を深めるためにインターンや合同説明会へ積極的に参加しましょう。
現場の社員と直接話すことで、企業の風土や働き方、業務内容を具体的に知れるため、入社後のミスマッチを防ぐことにつながります。
たとえば、「デスクワーク中心だと思っていたが、実際はフィールドワークも多かった」といった予想外の発見を得られるかもしれません。
また、こうした体験はエントリーシートや面接の場でエピソードとして活用できるため、他の志望者との差別化にもつながる有力なアピールポイントになります。
インフラ業界の特徴を理解しよう
インフラ業界は、安定した需要と社会貢献性の高さを兼ね備えた、非常にやりがいのある業界です。
電気・水道・交通・通信といった生活に不可欠なサービスを支える責任感と使命感は、大きな達成感や自己成長につながります。
もちろん、転勤や夜勤、年功序列など、人によっては合わないと感じる部分もありますが、それを理解したうえで自分に合った分野や企業を見つければ、安心して働ける職場に出会えるでしょう。
今回紹介した業務内容や準備のポイント、向いている人の特徴などを参考に、ぜひあなた自身の価値観や目指すキャリアと照らし合わせて、インフラ業界を前向きに検討してみてください。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。











