「ご足労おかけいたしますが」の意味・使い方・注意点と例文を徹底解説
「『ご足労をおかけいたしますが』って、どんな場面で使えばいいの?」
就職活動のメールなどでよく目にする表現ですが、正しい使い方に迷う人も多いですよね。実はこの言葉、使う相手や状況を誤ると、かえって失礼になることもあります。
本記事では、「ご足労をおかけいたしますが」の正しい意味や使い方、就活での例文を分かりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
「ご足労をおかけいたしますが」の意味と読み方

就活を進める中で、説明会や面接の案内メールなどで「ご足労をおかけいたしますが」という表現を目にすることは少なくありません。
相手に来てもらうことをお願いする際に使われ、移動や労力をかけてもらうことに対する感謝や配慮の気持ちを伝える役割を持っています。
読み方は「ごそくろうをおかけいたしますが」となり、社会人として必須の敬語表現の一つです。この表現を適切に使えると、相手に対して誠実さや礼儀を示すことができ、良い印象を与えられます。
就活の場面では、企業の採用担当者や面接官といった自分よりも立場が上の人に向けて使うのが基本です。
「ご足労をおかけいたしますが」という言葉を理解し、適切に使いこなせるようになることは、第一印象を良くし、信頼を得る大きな一歩につながるでしょう。
「ビジネスメールの作成法がわからない…」「突然のメールに戸惑ってしまっている」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるビジネスメール自動作成シートをダウンロードしてみましょう!シーン別に必要なメールのテンプレを選択し、必要情報を入力するだけでメールが完成しますよ。
「ご足労をおかけいたしますが」の語源と由来
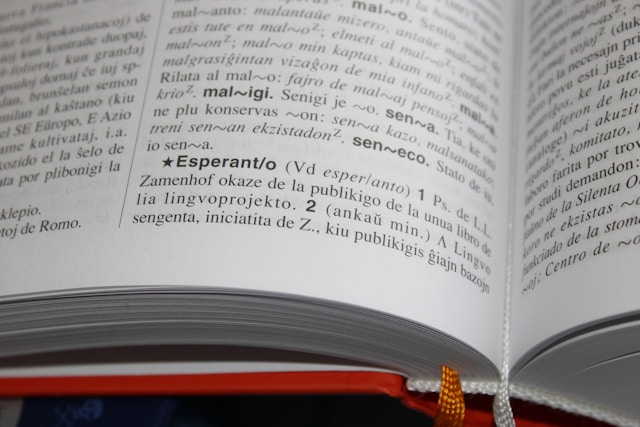
語源として、「足労」という語は、相手が自分のためにわざわざ足を運んでくれる労苦を意味し、その行為に対して感謝や敬意を表すものです。
単に訪問という事実を指すのではなく、そこにかかる時間や体力、さらには心理的な負担までも含めて気遣う姿勢を示しているのが特徴でしょう。
この表現が広まったのは江戸時代以降といわれており、商家や武家の往来において「わざわざ来てもらうのは申し訳ない」という思いを言葉で示すために用いられてきました。
その後、明治以降の近代社会でもビジネスや公式の場で重んじられ、現代では案内文や依頼メール、さらには面接や会議の案内状などでも使われています。
社会全体が効率化している今でもなお残っているのは、単なる慣用表現ではなく、相手を尊重する文化が根底にあるからです。語源と由来を理解し、失礼なく相手への敬意を示せるようにしましょう。
「ご足労をおかけいたしますが」を使うべき相手

就活の場面では、相手に敬意を払った適切な表現を選ぶことが欠かせません。「ご足労をおかけいたしますが」という言葉は、使い方を誤ると不自然さや違和感を与えてしまうこともあります。
だからこそ、状況や相手に合わせて正しく使い分けることが重要です。ここでは、使用すべきな代表的な相手や場面を解説します。
- 社外の取引先での利用
- 顧客や来訪者への利用
- 目上の立場にある人への利用
- 初対面や関係構築中の相手への利用
①社外の取引先での利用
取引先に訪問や来社をお願いする際には、「ご足労をおかけいたしますが」という表現が最適です。社外の相手に対して高い敬意を示しつつ、負担をかけることを自覚している姿勢を伝えられます。
例えば「ご足労をおかけいたしますが、弊社オフィスまでお越しください」と伝えると、相手の時間や労力に配慮していることを伝えられるのです。
逆に「お越しください」とだけ書くと、配慮に欠ける印象を持たれてしまうでしょう。就活のやり取りは一言の言葉遣いで印象が左右されるため、社外の人に依頼をするときほど表現に気を配るべきです。
取引先とのやり取りは信頼関係の基盤になるため、この表現を習慣として使いこなせるようにしましょう。
②顧客や来訪者への利用
顧客や来訪者に対しても「ご足労をおかけいたしますが」という表現が有効です。
たとえば合同説明会を自社で行う場合に、「ご足労をおかけいたしますが、当日は受付までお越しください」と添えると、移動の負担を理解していることが伝わります。
このような言葉が入るだけで、相手の受け取る印象は大きく変わるものです。ただし、同じ表現を社内の先輩や同期に使うと不自然なので注意が必要です。
顧客や来訪者といった外部の立場の人にこそ適切に使うことで、好印象を得られるようにしましょう。
③目上の立場にある人への利用
教授やゼミの先生、OB・OGといった目上の人に依頼する場合にも「ご足労をおかけいたしますが」は自然で丁寧な表現です。
例えばOB訪問のお願いメールに「ご足労をおかけいたしますが、指定のカフェにてお話を伺えますと幸いです」と書くと、移動の負担に気を配っていると伝わります。
一方で「お越しください」と書くと、礼儀を欠いていると感じられかねません。就活では、基本的なビジネスマナーも見られていることがあります。
そのため、目上の人と接するときほど丁寧で正しい言葉遣いを意識してください。正しい敬語を使えているだけで、誠実で信頼できる学生という印象につながりやすいです。
④初対面や関係構築中の相手への利用
初対面やまだ関係を築いている途中の相手には、特に丁寧な言葉遣いが求められます。「ご足労をおかけいたしますが」は、誠実さや配慮を伝えるのに効果的です。
例えば企業説明会で「ご足労をおかけいたしますが、受付にて資料をお受け取りください」と案内されると、就活生にとっても「丁寧な扱いをしてくれている」と感じますよね。
初対面だからこそ、誠実な気持ちを示す言葉遣いが大切です。
「ご足労をおかけいたしますが」の利用シーン

就活や社会人生活では、相手に来訪をお願いしたり感謝を伝えたりする場面で「ご足労をおかけいたしますが」を使うことがあります。
ただし、状況によって適切な言い回しが異なるため、誤用を避けることが大切です。ここでは就活生が出会いやすい利用シーンを整理し、安心して使えるように解説します。
- 来訪依頼メールでの利用
- 打ち合わせ依頼での利用
- イベントやセミナー招待での利用
- 面接や説明会案内での利用
- 訪問後のお礼での利用
- 上司や先輩への同行依頼での利用
① 来訪依頼メールでの利用
就活生が企業担当者に来てもらう依頼をする際には、相手の負担を意識した言葉選びが欠かせません。その際に「ご足労をおかけいたしますが」を使うと、敬意と感謝の気持ちを同時に伝えられます。
単に「お越しください」と記すと、どうしても命令的で柔らかさに欠けてしまいますが、この表現を添えることで配慮のある依頼に変わります。
例えばOB訪問などの機会で「ご足労をおかけいたしますが、当日〇〇までお越しください」と書けば、相手は気持ちよく応じやすくなるでしょう。
学生は立場上お願いする機会が多いため、相手への思いやりを言葉に込められるかどうかが信頼につながります。このフレーズを習慣的に取り入れることで、誠実さをアピールできるのです。
② 打ち合わせ依頼での利用
面接の準備やOB訪問の調整など、打ち合わせのお願いをする場面でも「ご足労をおかけいたしますが」という表現は効果的です。
就活中は社会人の方と時間や場所を合わせることが多く、移動や予定変更をお願いすることも少なくありません。
その際に「ご足労をおかけいたしますが」と添えることで、相手の時間を大切にしている姿勢を示せます。
例えば「ご足労をおかけいたしますが、〇〇駅近くのカフェにお越しいただけますでしょうか」と伝えると、単なる日程連絡ではなく誠意を込めた依頼になります。
社会人は学生以上に時間を重視しているため、この一言が信頼感につながります。就活生としては「配慮できる人材」と思ってもらえることが大きな評価につながるでしょう。
③ イベントやセミナー招待での利用
企業が開催する就活イベントや説明会の案内文でも頻繁に使われる表現ですが、学生が主催側になる場合にも応用できます。
例えばゼミ活動で企業担当者を呼ぶときに「ご足労をおかけいたしますが、ご参加いただければ幸いです」と書けば、ただの案内ではなく、相手の移動や時間に感謝していることが伝わります。
就活では相手に足を運んでもらう場面が多く、その一言で印象が大きく変わるものです。こうした丁寧な依頼をされると誠実さや真剣さが伝わります。
学生のうちから自然に使えるようにしておくことで、社会に出てからも信頼を得やすいです。ビジネスマナーを意識した言葉遣いを今のうちから身に着けておきましょう。
④ 面接や説明会案内での利用
面接や説明会の案内には、企業から学生へ向けて「ご足労をおかけいたしますが」という表現が多く使われます。
就活生側が案内を送る立場になることは少ないですが、ゼミや研究会で企業担当者を呼ぶときなどには活用可能です。
「ご足労をおかけいたしますが、当日は〇〇会場までお越しください」と添えれば、事務的な内容に温かみを加えられます。案内文は、簡潔でありながら相手への敬意を欠かさないことが大切です。
就活生にとって、こうした言葉を覚えておくことは社会人とのやり取りに自信を持つ助けとなり、周囲との差をつける要素にもなります。
⑤ 訪問後のお礼での利用
企業担当者やOBがわざわざ訪問してくれたときに「本日はご足労をおかけいたしました」と伝えると、丁寧な感謝の表現になります。
「ありがとうございました」だけでも感謝は伝わりますが、移動にかかった労力や時間を意識していない印象を与えてしまう可能性があります。
この言葉を添えることで、相手がしてくれた行動を具体的にねぎらっていることが伝わり、より誠実さが伝わるのです。
就活は人とのご縁や印象が非常に重要ですから、こうした細かい言葉が評価につながります。
例えば訪問後のメールで「本日はご足労をおかけいたしました。お忙しい中、貴重なお時間をいただき誠にありがとうございました」と記せば、相手に信頼感を持ってもらえるでしょう。
⑥ 上司や先輩への同行依頼での利用
インターンやアルバイトで、上司や先輩に同行をお願いすることは珍しくありません。就活中でも、企業訪問や学外イベントに先輩や先生に同席してもらう場合があります。
そうしたときに「ご足労をおかけいたしますが」と伝えると、相手への敬意を表しながらスムーズに依頼できます。
「ご足労をおかけいたしますが、〇〇にご一緒いただけますでしょうか」と頼めば、単なる同行依頼が丁寧なお願いに変わります。
学生の立場で目上の人にお願いする際は、失礼のない言い回しが欠かせません。就活生にとって、自然にこの表現を使えるかどうかは社会人としてのマナー意識を示す大きなポイントになります。
普段から意識して練習しておくことで、いざという時にも落ち着いて対応できるようになるでしょう。
「ご足労をおかけいたしますが」の正しい使い方

ビジネスの現場では「ご足労をおかけいたしますが」という表現を正しく使えるかどうかで、相手に与える印象が大きく変わります。
依頼や感謝、文書や会話など場面ごとに微妙なニュアンスの違いがあるため、理解が不十分だと配慮に欠ける人と思われる可能性もあります。
ここでは代表的な使い方を整理し、就活生が面接やメールで自信を持って使えるように解説します。
- 依頼表現としての使い方
- 感謝表現としての使い方
- メールやビジネス文書での使い方
- 電話や口頭での使い方
- 敬語を組み合わせた使い方
①依頼表現としての使い方
「ご足労をおかけいたしますが」は、相手にわざわざ出向いてもらう依頼をするときに欠かせない表現です。OB・OG訪問などの機会に使うことができます。
例えば「ご足労をおかけいたしますが、当日は○○へお越しください」と伝えれば、単なる「来てください」との依頼よりもずっと柔らかく、相手に配慮した言い方になります。
社会人は「相手の時間を奪うこと」への意識を重視するため、この一言があるかどうかで受け取る印象は大きく変わるのです。
就活生はまだ経験が浅いため、つい事務的な依頼になりがちですが、この表現を知っているだけで誠実さや気遣いが伝わり、印象を良くする武器になります。
②感謝表現としての使い方
「ご足労をおかけいたしますが」は依頼だけでなく、感謝を伝えるときにも役立ちます。
特に訪問や面談の後には「本日はご足労をおかけいたしました」と過去形で使うことで、相手がわざわざ時間を割いて足を運んでくれたことに敬意と感謝を表せます。
単純に「ありがとうございました」と述べるだけでは一般的ですが、「ご足労」という言葉を添えることで、移動の負担を理解している姿勢がより伝わるのです。
就活の場面では、説明会や面談が終わった後にこの表現をメールで送ると、細やかな配慮ができる学生として評価されやすいでしょう。
言葉選び一つで人柄が表れるため、感謝のシーンでは積極的に取り入れるのがおすすめです。社会人に近づく第一歩としてもぜひ使ってみてください。
③メールやビジネス文書での使い方
メールや文書で「ご足労をおかけいたしますが」を使うと、冷たい印象になりがちな文章に柔らかさと誠実さを加えられます。
就活性が使う機会は少ないですが、「ご足労をおかけいたしますが、当日は受付にてお名前をお伝えください」と書けば、案内の内容に相手を思いやる姿勢が加わります。
特に説明会や面接の案内メールでは、移動の負担を伴うことを踏まえた表現を意識すると、文面に誠実さが伝わってきますよね。
社会人になったときには、こうした細やかな気遣いをした言葉遣いを取り入れるようにしてください。
④電話や口頭での使い方
電話や口頭で「ご足労をおかけいたしますが」を使うときは、言葉のトーンや間の取り方で印象が大きく変わります。
例えば、企業の方に学校まで来てもらう際は「ご足労をおかけいたしますが、当日は正門までお越しください」と、やわらかい声でゆっくり話すと丁寧さがより伝わります。
表情が見えない電話では、言葉選びと声の雰囲気が特に重要です。企業とのやり取りに慣れていないと早口になりがちですが、このフレーズを落ち着いて使えるようにしましょう。
また、省略して「当日は正門までお越しください」とだけ言うと、相手の負担を考えていないように聞こえることもあります。
だからこそ、こうした一言を加えるかどうかが信頼につながります。
⑤敬語を組み合わせた使い方
「ご足労をおかけいたしますが」は単独でも丁寧ですが、他の敬語を添えることでさらに自然で温かみのある表現になります。
例えば「ご足労をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます」と結ぶと、相手への依頼の重みをやわらげながら敬意を示せます。
あるいは「ご足労をおかけいたしますが、ご確認いただけますと幸いです」とすれば、依頼のニュアンスに柔軟さが加わり、相手の判断を尊重する形になります。
就活の場面ではメールの最後にこのような組み合わせを入れると、文章が格段に洗練されます。
単に「ご足労をおかけいたしますが」で終えると堅苦しい印象になることもありますが、表現を工夫することで温かさを伝えることができるでしょう。
こうした一工夫は、ビジネスマナーを身につけた学生としての評価につながります。
「ご足労をおかけいたしますが」の例文集

実際の場面では、どのように「ご足労をおかけいたしますが」という言葉を使えばよいのか悩んでしまいますよね。ここでは就活の様々な状況で活用できる具体的な例文を紹介します。
依頼やお願いの場面だけでなく、感謝を伝える場面でも役立つので、ぜひ参考にしてください。
- 会議出席をお願いする例文
- 面談設定を依頼する例文
- 訪問後に感謝を伝える例文
① 会議出席をお願いする例文
会議の出席を依頼する場面では、相手の時間をいただくことになるため、丁寧で配慮ある表現が欠かせません。
ここでは、就活生がゼミ活動や学生団体の活動を通じて、打ち合わせへの参加をお願いする状況の例文を紹介します。
実際のビジネスシーンでも応用できる書き方なので、学生のうちから練習しておくと安心です。
| 先日は資料作成にご協力いただき、誠にありがとうございました。次回の活動に向けて、皆さまと意見を共有する場を設けたいと考えております。 つきましては、今週金曜日の15時より大学の会議室にて打ち合わせを予定しております。お忙しいところご足労をおかけいたしますが、ぜひご出席いただけますと幸いです。 当日は発表内容の確認と役割分担を中心に話し合う予定ですので、ご準備いただく必要はございません。短い時間ではありますが、今後の活動を円滑に進めるために重要な機会と考えております。 どうぞよろしくお願いいたします。 |
この例文では「ご足労をおかけいたしますが」を自然に盛り込みつつ、会議の目的や内容を簡潔に伝えています。
同じテーマで書く際は、依頼の理由を明確にし、相手が安心して参加できる情報を補足することが効果的です。
また、日時や場所を具体的に提示することで、相手がすぐに予定を確認できるように工夫するとさらに丁寧な印象を与えられます。
② 面談設定を依頼する例文
就職活動では、企業担当者に面談のお願いをする機会があります。その際に「ご足労おかけいたしますが」という表現を添えると、相手への配慮や敬意が伝わりやすくなります。
ここでは、大学生が実際に使いやすい面談依頼の例文を紹介します。丁寧な言葉を選ぶことで、第一印象を良くし信頼関係を築くきっかけにもつながります。
| このたびは、面談の機会を頂きたくご連絡いたしました。ご多用のところ恐れ入りますが、○月○日から○月○日のいずれかの日程でお時間を頂戴できますでしょうか。 ご足労おかけいたしますが、大学近くのカフェやオンラインなど、先方のご都合に合わせて設定できればと考えております。 私自身、ゼミ活動で培った企画力について具体的にお話しし、貴社で活かせる可能性を直接伺いたいと思っております。ご都合の良い日時や場所がございましたら、ご教示いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 |
依頼文では「ご足労おかけいたしますが」を自然に挟み込み、相手の時間と労力に配慮している点が重要です。
自分の希望だけでなく、相手の都合を尊重する文言を入れると、誠実さや丁寧さがより伝わりやすくなります。
③訪問後に感謝を伝える例文
相手に足を運んでいただいたことに対して感謝を示す際にも、「ご足労おかけいたしますが」という言葉が有効です。
ここでは、大学生が就活や研究活動などで相手に助けてもらった場面を想定した例文を紹介します。こうした表現を知っておくと、「社会人としての常識がある」と好印象につながりやすいですよ。
| このたびはお忙しい中、ご足労いただきありがとうございました。 貴重なお時間の中で研究発表にお越しいただき、心より感謝申し上げます。直接お会いしてご意見をいただけたことで、今後の研究につながる大きな学びとなりました。 これからも努力を重ねてまいりますので、引き続きご指導のほどよろしくお願い申し上げます。 |
相手に時間を割いてもらった感謝を表現すると、丁寧な印象につながります。同じテーマを書くときは、「どの場面で助けられたのか」を短く入れると、印象に残る文章になるのでオススメです。
また、最後に前向きな意欲や今後の姿勢を添えると、誠実さがより強調されるので参考にしてみてください。
「ご足労をおかけいたしますが」の類義語・言い換え表現

「ご足労をおかけいたしますが」は、相手に来訪や行動を依頼するときの敬語表現ですが、場面によっては別の表現に置き換える方が自然で丁寧に響きます。
ここでは、就活生が知っておくと役立つ類義語や言い換えの表現を紹介します。正しく使い分けられると、相手への配慮が伝わり、より信頼感のある印象を与えられるでしょう。
- 「お手数をおかけいたしますが」
- 「ご面倒をおかけいたしますが」
- 「お呼び立てして恐縮ですが」
- 「お時間をいただきますが」
- 「お力添えをお願いできますでしょうか」
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
①「お手数をおかけいたしますが」
「お手数をおかけいたしますが」は、相手に作業や確認をお願いするときに最も広く使われる表現です。就活では、企業担当者に面接日程の確認や提出書類の再確認を依頼する場面で用いられます。
例えば「お手数をおかけいたしますが、面接日程をご確認いただけますでしょうか」と記すことで、誠意をもって依頼している姿勢が相手に伝わります。
この言葉は、移動や大きな労力を伴う依頼ではなく、あくまで事務的な対応や少しの負担をお願いする場合に適しています。
学生のうちに習得しておくと、社会人になってからもあらゆるシーンで使えるため、早めに慣れておくと安心でしょう。
また「お手数ですが」と短縮しても丁寧さは損なわれず、ビジネスメールでも違和感なく使えます。
②「面倒をおかけいたしますが」
「面倒をおかけいたしますが」は、相手に心理的・時間的な負担を強いる場合に使う表現です。就活では、企業に追加の準備を依頼したり、複数回のやりとりをお願いする場面で有効です。
例えば「面倒をおかけいたしますが、再度ご確認いただけますでしょうか」と書けば、相手の労力に配慮していることをしっかりと伝えられます。
ただし「面倒」という言葉にはやや重い響きがあるため、多用すると相手に負担感を強調しすぎてしまうおそれもあります。
そのため、簡単な確認や依頼であれば「お手数」を、より手間がかかる依頼なら「面倒」といったように、ニュアンスの違いを理解して使い分けることが重要です。
場面ごとの使い分けができると、社会人としての言葉選びのセンスも評価されるでしょう。
③「お呼び立てして恐縮ですが」
「お呼び立てして恐縮ですが」は、相手を直接呼び出すときや時間を割いてもらう場面で使われる表現です。就活では、OB・OG訪問や説明会などで担当者に参加してもらう依頼に適しています。
「恐縮」という言葉を加えることで、相手に対して強い遠慮と感謝の気持ちを同時に伝えられるのが特徴です。
例えば「お呼び立てして恐縮ですが、当日の面談にご出席いただけますでしょうか」と記すと、丁寧で控えめな姿勢を表現できます。
この表現は、学生が使用すると謙虚さや誠実さを示すことにつながり、相手に好印象を与えやすいのも魅力です。
特に初対面の相手や年上の社会人に対しては、過剰にならない程度に「恐縮」を添えることで距離感を適切に保つ効果もあります。就活生にとって、信頼関係を築く上で有効な言い回しといえるでしょう。
④「お時間をいただきますが」
「お時間をいただきますが」は、相手に行動を求めるのではなく、単に時間を割いてもらうときに用いる表現です。
例えば面接や面談の案内メールで「お時間をいただきますが、ご参加いただけますと幸いです」と書くと、相手の時間を尊重している姿勢を自然に伝えられます。
就活の場では、企業の担当者が多忙なことが多いため、相手に負担を感じさせずに配慮を示せるこの言葉は非常に便利です。
単純な依頼であっても「時間をいただく」という意識を言葉にするだけで、誠意や感謝のニュアンスが強まり、より信頼を得やすくなります。
社会人になってからも、会議の招集や相談を持ちかける際など幅広い場面で活用できるため、学生のうちから積極的に使い慣れておくと良いでしょう。
⑤「お力添えをお願いできますでしょうか」
「お力添えをお願いできますでしょうか」は、相手に協力や支援を求めるときに使う柔らかい表現です。就活では、推薦状の依頼や選考に関する調整など、相手の力を借りたいときに適しています。
「ご足労」が移動や行動に焦点を当てているのに対し、「お力添え」は相手の協力そのものをお願いする点が大きな違いです。
例えば「今後の進路選択にあたり、お力添えをお願いできませんか」と伝えると、相手を尊重しながら支援を仰ぐ姿勢を示せます。
押しつけがましさを避けつつ、謙虚さと真剣さを伝えられるため、就活生にとって非常に使いやすい表現でしょう。
さらに社会人になってからも、プロジェクトの依頼やチームワークを必要とする場面で重宝するため、早めに習得しておくと将来にわたり役立ちます。
「ご足労をおかけいたしますが」を使う際の注意点

「ご足労をおかけいたしますが」は丁寧な表現である一方、使い方を誤ると相手に不快感を与えるおそれがあります。
就活生にとっては、面接や企業担当者へのメールで使用する可能性が高く、正しい場面や注意点を理解しておくことが重要です。
ここでは代表的な注意点を4つ取り上げ、それぞれの理由と具体的な使い方を解説します。
- 社内の人間には使わない
- 訪問が確定していない場合には避ける
- 「ご足労様です」と省略しない
- 相手の立場を考慮して使う
① 社内の人間には使わない
「ご足労をおかけいたしますが」は、基本的に社外の人へ敬意を示すための表現です。そのため、同じ社内の上司や同僚に使うと不自然に思われます。
例えば、上司に「ご足労をおかけいたしますが会議室までお願いします」と伝えると、過剰にかしこまりすぎて、違和感を与えてしまうでしょう。
社内では「お手数ですが」「恐れ入りますが」といった言い方の方が自然で適切です。就活生は、インターン先やアルバイトで誤用する可能性もあるため注意してください。
正しく使えば、社会人としてのマナーを理解していると評価されますが、誤った場面で使うと常識が欠けていると思われる危険もあります。正しい言葉遣いを意識してくださいね。
② 訪問が確定していない場合には避ける
「ご足労をおかけいたしますが」は、相手が訪問することが確定している状況でのみ使うのが適切です。
まだ日程が決まっていない段階や、相手が来られるか不明な段階で使うと、「もう来ることが決まっているのか」と受け取られてしまい、相手に負担や違和感を与える可能性があります。
例えば、面接日時の候補を提示するメールで「ご足労をおかけいたしますが」と書くと、相手に予定を強要しているような印象になりかねません。
そのような場面では「もしご来社いただけるようでしたら」や「ご都合がよろしければ」といった表現が無難です。就活では、採用担当者の多忙なスケジュールに配慮することが好印象につながります。
言葉の選び方ひとつで印象が変わるため、訪問が確定してから使用するよう心掛けてください。
③ 「ご足労様です」と省略しない
「ご足労をおかけいたしますが」を短くして「ご足労様です」と言うのは誤りです。「ご足労様」は訪問後のねぎらいとして使う言葉であり、依頼の場面には不向きだからです。
企業担当者にメールを送る際に「ご足労様ですが」と書いてしまうと、敬語の知識不足を露呈してしまい、マイナス評価につながる恐れがあります。
就活生にとって、言葉の誤用は面接の場での印象にも直結するため軽視できません。省略せず、正しい形で「ご足労をおかけいたしますが」と書くことが基本です。
たとえ文章がやや長くなっても、丁寧な表現を心がけることが社会人としての誠実さを示す結果につながります。
採用担当者は細かい言葉遣いから学生の配慮や姿勢を判断することもあるので、正確さを意識して使いましょう。
④ 相手の立場を考慮して使う
「ご足労をおかけいたしますが」は、自分より立場が上の人や、外部から訪問してもらう相手に対して使うのが基本です。
就活生が企業の採用担当者に対して使うのは適切ですが、同級生や後輩に用いるのは不自然に感じられます。
また、遠方からわざわざ来てもらう場合や、移動が大きな負担になる状況で使うと、相手に必要以上に恐縮させてしまうこともあります。
そのような場面では「ご来社いただけますと幸いです」や「お越しいただければありがたく存じます」といった柔らかい表現の方が望ましいでしょう。
就活では、相手の立場や状況に合わせて言葉を選べるかどうかが信頼関係を築くカギになります。
単に形式的に敬語を使うのではなく、相手に負担をかけない配慮ができることが社会人としての成熟度を示すのです。
言葉を正しく理解し適切に使うために
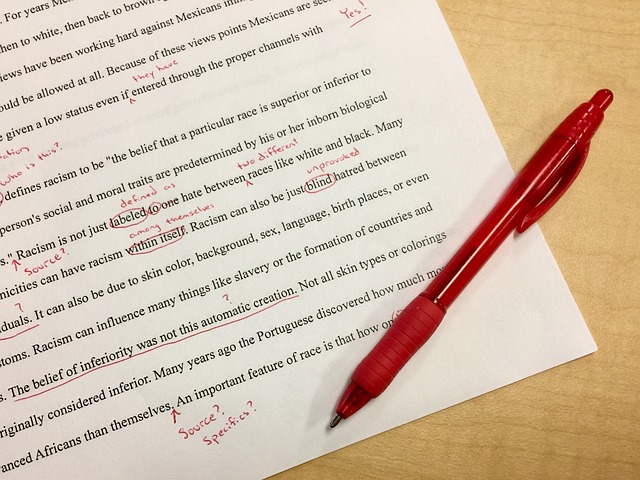
「ご足労をおかけいたしますが」という表現は、相手に移動の負担をお願いする場面で用いられる丁寧な言葉です。
実際の利用シーンとしては、来訪依頼メールや打ち合わせの案内、面接や説明会など多岐にわたり、依頼と感謝の両方を込めることができます。
また、社外の取引先や顧客、目上の立場にある人など、適切な相手を意識することが重要です。さらに、例文や類義語を参考にすることで、柔軟に言い換え表現を選べます。
この言葉を正しく理解し使いこなすことで、ビジネスシーンで信頼感や誠実さを示すことができるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














