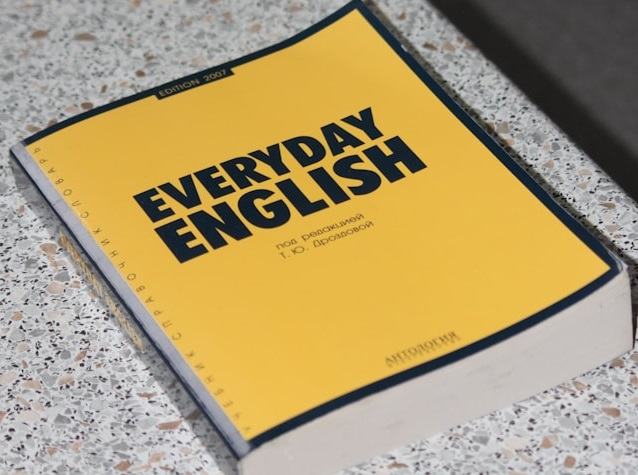就活ノートとは?情報のまとめ方から作るときのコツまで紹介
「就活の情報が多すぎて、何から整理すればいいのかわからない…」と感じている人も多いのではないでしょうか。
エントリーシートや面接日程、企業研究など、就活では管理すべき情報が次々と増えていきます。
そんなときに役立つのが「就活ノート」です。自分専用のノートを作ることで、スケジュールや企業情報、自己分析を一元管理でき、選考対策の質も格段に上がります。
この記事では、就活ノートの効果的な作り方やまとめ方のコツ、注意点までを詳しく紹介します。自分に合った方法で情報を整理し、効率的に就活を進めましょう。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
就活情報をまとめる就活ノートとは?

就活ノートとは、エントリー情報や自己分析、企業研究、面接対策など、就職活動に関する情報を整理してまとめるためのノートです。
就活の進行状況をひと目で把握できるだけでなく、考えを整理することで効率よく行動できるようになるでしょう。就活ノートを作る一番の目的は、自身の就活を確実に管理することです。
エントリー先が増えるにつれ応募状況や日程、選考結果などの情報が氾濫し、頭の中だけだとミスや抜け漏れが出てきてしまいます。
ノートにまとめておけば、いつでも確認できる状態を保てるため、スケジュール管理や情報整理がスムーズになります。また、就活ノートを使うことで、自分の成長を客観的に振り返ることもできるのです。
たとえば、面接での反省点や質問への回答を記録しておくと、次の面接に活かせます。さらに、自己分析を記録しておくことで、志望動機や自己PRの一貫性を保ちやすくなるでしょう。
「就活でまずは何をすれば良いかわからない…」「自分でやるべきことを調べるのが大変」と悩んでいる場合は、これだけやっておけば就活の対策ができる「内定サポートBOX」を無料でダウンロードしてみましょう!
・自己分析シート
・志望動機作成シート
・自己PR作成シート
・ガクチカ作成シート
・ビジネスメール作成シート
・インターン選考対策ガイド
・面接の想定質問集100選….etc
など、就活で「自分1人で全て行うには大変な部分」を手助けできる中身になっていて、ダウンロードしておいて損がない特典になっていますよ。
就活ノートを作るメリット

就活ノートは、就活中に感じる「情報の多さ」「整理の難しさ」「スケジュール管理の煩雑さ」を解消できる便利なツールといえるでしょう。
ここでは、就活ノートを作ることで得られる5つの主なメリットを紹介します。
- スケジュール管理がしやすくなる
- 就活全体を整理して効率的に進められる
- 企業研究や面接対策の質が向上する
- 自分の考えを可視化して自己分析が深まる
- モチベーションを維持しやすくなる
①スケジュール管理がしやすくなる
就活では、エントリーの締切や説明会、面接の日程など、複数の予定を同時に管理しなければなりません。就活ノートを活用すれば、スケジュールを一覧で確認でき、予定の抜け漏れを防げます。
特にカレンダー形式で記録しておくと、1週間単位で行動を把握しやすくなるでしょう。また、企業ごとの進行状況をまとめておくことで「次に何をすべきか」が明確になります。
スマホのアプリでも管理できますが、手書きで記録すると記憶に残りやすく、優先順位の整理もしやすいです。予定を見える化することで、時間を有効に使えるようになるでしょう。
②就活全体を整理して効率的に進められる
就職活動では、企業研究やエントリーシート作成、面接準備など多くの作業を同時に行う必要があります。就活ノートを使えば、就活に関する情報を一元的に管理でき、効率良く行動できるでしょう。
複数の企業を受ける場合、「どの企業で何を話したか」「どんな印象を持ったか」が混同しがちです。ノートに進捗や感想を記録しておけば、選考内容を比較でき、次回の面接にも活かせます。
振り返りがしやすい点も大きなメリットです。ノートに情報を整理しておくことで、焦らず冷静に就活を進められるでしょう。
③企業研究や面接対策の質が向上する
企業研究を就活ノートにまとめておくと、情報の抜け漏れが減り、面接での回答にも説得力が増します。企業理念や事業内容、担当者の印象などを項目ごとに整理しておくと、比較しやすくなるのです。
また、志望動機や自己PRを企業ごとに書き分けておくと、面接直前の確認にも便利でしょう。ノートに自分の言葉で書くことで理解が深まり、暗記ではなく「納得した状態」で話せるようになります。
ネットの情報だけでなく、自分が感じたことを記録すると、自分にとって価値のある企業研究ノートになるでしょう。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
④自分の考えを可視化して自己分析が深まる
自己分析は就活の出発点ですが、頭の中で考えるだけでは整理しきれません。就活ノートを使えば、自分の強みや弱み、価値観、経験を可視化でき、より客観的に理解できるようになります。
たとえば「なぜその企業を選びたいのか」「どんな働き方をしたいのか」を書き出すと、自分の軸が明確になるのです。
また、ノートに書く過程で新しい気づきが生まれることも多く、面接での受け答えに一貫性が出るでしょう。自分の言葉でまとめることが、自然な自己PRにつながるのでぜひノートを作ってみてください。
⑤モチベーションを維持しやすくなる
就活は長期間にわたるため、途中でやる気を失ってしまう人も少なくありません。そんなとき、就活ノートは気持ちを立て直す助けになります。
これまでの努力や成果、面接での手応えを記録しておくと、自分の成長を実感しやすくなるからです。
また、今後の目標や予定を書いておけば「次に何をすべきか」が明確になり、不安を感じにくくなります。
小さな成功体験を積み重ねて記録することが、前向きな気持ちを保つコツです。就活ノートは、自分の成長を支えるパートナーともいえるでしょう。
就活ノートにまとめるべき内容

就活ノートを有効に活用するためには、記録する内容を明確にしておくことが大切です。思いついたことをただ書き並べるだけでは、情報が散らかってしまい、必要なときに振り返りづらくなるでしょう。
ここでは、就活をスムーズに進めるためにまとめておきたい5つの項目を紹介します。
- 就活スケジュールと選考日程
- 業界・企業研究の情報
- 自己分析・他己分析の結果
- インターンやOB・OG訪問の記録
- 面接内容・選考結果の振り返り
①就活スケジュールと選考日程
就活ノートの基本はスケジュール管理です。エントリー開始日、説明会の日程、面接や適性検査の日などを整理しておくことで、予定の重複や見落としを防げます。
複数の企業を同時に受ける場合は、企業ごとの進行状況をひと目で確認できるようにまとめておくと便利です。カレンダー形式で整理すれば、全体の流れがつかみやすくなります。
また、面接準備や提出書類の締切などもあわせて記載しておくと、余裕を持って行動できるでしょう。
②業界・企業研究の情報
業界・企業研究は、就活ノートの中でも特に重要な項目です。業界の動きや主要企業の特徴、仕事内容、求める人物像などを整理しておくと、志望動機や自己PRに説得力が生まれます。
ノートには調べた情報だけでなく、自分が感じた印象や他社との違いも書き残しておくと理解が深まるでしょう。
説明会やインターンで得たリアルな情報を追記すれば、自分だけの「就活データブック」が完成します。情報をため込むだけでなく、定期的に見返して内容を更新していくことも大切です。
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
③自己分析・他己分析の結果
自己分析の結果は、就活の軸を定めるうえで欠かせません。自分の強み・弱み、価値観、将来像を整理しておくと、面接でも一貫した受け答えができるようになります。
他己分析の結果も合わせて記録しておくと、自分では気づかなかった長所や課題を客観的に把握できるでしょう。
また、どの経験がどの強みに結びついているのかを具体的に書き出しておくと、自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)の作成にも役立つでしょう。
書きながら自分を深く理解していくプロセスは、就活を成功に近づける鍵ですよ。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
④インターンやOB・OG訪問の記録
インターンシップやOB・OG訪問で得た情報も、就活ノートにしっかり残しておきましょう。実際に働く社員から聞いた仕事内容や職場の雰囲気、採用の流れなどは、公式サイトでは得られない貴重な情報です。
訪問日時や担当者の名前、印象に残った言葉なども記録しておくと、再度連絡を取りたいときにも役立ちます。
また、インターン中の学びや成果を整理しておけば、面接で具体的なエピソードとして話すことができます。体験を文字に残すことで、自分の成長を実感しやすくなるでしょう。
⑤面接内容・選考結果の振り返り
面接後は、できるだけ早く内容をノートに記録してください。質問内容や回答、面接官の反応などを具体的に書き残しておくことで、次の面接に向けて改善点を明確にできます。
選考結果が出た際には、成功した理由や失敗の要因も分析しておくとよいでしょう。同じミスを繰り返さないための「反省メモ」として役立ちます。
さらに、「面接で何を聞かれたか」をまとめておけば、他社での面接対策にも応用できますよ。こうした積み重ねが、面接力の向上につながるはずです。
就活ノートの効果的な作り方

就活ノートは、就職活動の流れを整理し、自分の考えや情報をまとめるための重要なツールです。ただ思いつくままに書き始めると、後で探したい情報を見つけにくくなり、時間を無駄にしてしまうことも。
ここでは、就活ノートを効果的に作るための5つのコツを紹介します。
- ノートの構成を決めてから書き始める
- スケジュール→企業研究→自己分析の順で整理する
- 項目ごとに色分けして見やすくまとめる
- 余白を残して情報を追加しやすくする
- インデックスや目次を活用して管理する
①ノートの構成を決めてから書き始める
就活ノートを作るときは、まず全体の構成を決めることが大切です。最初に考えずに書き始めてしまうと、後から情報を追加しづらくなったり、整理が難しくなったりします。
「スケジュール」「企業研究」「自己分析」「面接対策」など、あらかじめ大きな項目を決めてページを区切っておくと、情報の流れがスムーズになるでしょう。
さらに、最初のページに目次を作っておくと、どこに何が書いてあるか一目で分かるので便利です。最初のひと工夫が、使いやすいノート作りにつながります。
②スケジュール→企業研究→自己分析の順で整理する
就活ノートの内容は、書く順番にも工夫が必要です。
「スケジュール管理」から始め、「企業研究」「自己分析」という流れで整理する方法をおすすめします。この順番でまとめることで、情報が混ざらず、一貫した流れを保てるからです。
まず、就活全体のスケジュールを把握し、いつまでに何をするかを明確にしましょう。次に、志望企業の情報を調べ、自分の強みや価値観を整理していきます。
分かりやすい順番で整理されたノートは、面接前に見返したときにも理解しやすく、復習がしやすいでしょう。
③項目ごとに色分けして見やすくまとめる
色分けは、就活ノートを見やすくするための効果的な方法です。例えば、スケジュールは青、企業研究は赤、自己分析は緑など、テーマごとに色を統一すると情報が整理しやすくなります。
また、重要な部分や覚えておきたいキーワードはマーカーで強調すると、後から見直すときに目に入りやすいです。
ただし、色を使いすぎると見づらくなるので、3~4色程度に抑えると良いでしょう。最初に色のルールを決めておくと、統一感が生まれ、より使いやすいノートになります。
④余白を残して情報を追加しやすくする
就職活動が進むにつれて、新しい情報や気づきが増えていきます。そのため、最初からページを埋め尽くさず、余白を意識して残しておくことが大切です。
余白があると、後からメモやコメントを追加しやすく、情報を更新しながらノートを成長させていけます。ページの端や下部にスペースを設けるだけでも、メモの取りやすさが変わるのです。
完璧な形を目指すのではなく、「成長していくノート」という意識で書き進めていくと、より実用的で長く使える就活ノートになります。
⑤インデックスや目次を活用して管理する
情報が増えてくると、どこに何を書いたのか分からなくなりがちです。そのため、必要な情報をすぐに探せるようにインデックスや目次を作っておくことをおすすめします。
インデックスシールを使えば、ページを瞬時に開けるため、面接前の確認にも便利です。
また、ノートが複数冊に分かれる場合は、「企業研究用」「自己分析用」などとラベルを貼って区別すると管理しやすくなります。探す時間を減らせば、効率的に就活を進められるでしょう。
就活ノートを上手に管理することが、成功への近道です。
就活ノートをわかりやすく作成するコツ

就活ノートは、情報を整理して自分だけの「就活戦略書」として活用できる大切なツールです。しかし、書き方を工夫しないと内容がごちゃつき、あとで振り返りにくくなることも。
ここでは、就活ノートをより見やすく使いやすくするための5つのコツを紹介します。
- 情報の種類ごとにページを分ける
- ペンやマーカーで重要部分を強調する
- 箇条書きで簡潔にまとめる
- 自分の意見や感想も書き添える
- デジタルツールと併用して情報を整理する
①情報の種類ごとにページを分ける
就活ノートを作成するときは、まず情報の種類ごとにページを分けるのがおすすめです。
たとえば、「企業研究」「自己分析」「エントリー管理」「面接対策」といったように、目的別にセクションを設けるとよいでしょう。情報が整理され、必要なページをすぐに開けるようになります。
また、付箋やインデックスシールで区切ると、視覚的にも使いやすくなるのです。最初に目次ページを作っておくと、全体の構成が一目で分かるようになります。
②ペンやマーカーで重要部分を強調する
就活ノートは、ただ情報を記録するだけではなく、重要なポイントを目立たせる工夫が必要です。赤や青など色分けをして、優先度や注意点を区別しましょう。
たとえば、「面接でよく聞かれる質問」は赤、「改善点」は青のように自分なりのルールを決めると整理しやすくなります。
ただし、色を多用しすぎると逆に見づらくなってしまうため、1ページあたり2~3色に抑えるのがコツです。強調したい部分を絞ることで、重要な情報がより引き立ちます。
③箇条書きで簡潔にまとめる
就活ノートは「見返してすぐ理解できること」が大切です。そのため、長文で書くよりも箇条書きで簡潔に整理するようにしてくださいね。
たとえば、「社風→アットホーム」「強み→教育制度が充実」といった形で短くまとめると、復習がスムーズになります。特に、面接の質問や自己PRのポイントなどは要点を短く書くと頭に入りやすいでしょう。
ノートは「読むため」ではなく「使うため」のツールだと意識して、まとめてみてください。
④自分の意見や感想も書き添える
就活ノートには、企業情報だけでなく自分の感想や考えも書いておくと効果的です。説明会で感じた印象、社員の話から受けたイメージなどを記録しておくと、志望動機を作る際に役立ちます。
また、他社との比較や、自分が成長したと感じた出来事なども書いておくと、就活の軌跡を振り返るときに参考になるのです。
自分の考えを言語化する習慣を持つことで、面接での表現力アップにもつながるでしょう。
⑤デジタルツールと併用して情報を整理する
紙のノートだけでなく、デジタルツールを併用すると情報管理がより効率的になります。
Googleスプレッドシートで選考状況をまとめたり、NotionやEvernoteで企業研究を記録したりする方法もおすすめです。検索機能を使えば必要な情報をすぐ見つけられます。
一方で、手書きノートには記憶に残りやすいという利点があります。紙とデジタルの両方をうまく組み合わせ、自分に合った方法で整理していくことが大切です。
就活ノートを書くときの注意点

就活ノートは情報を整理し、効率的に活動を進めるための大切なツールです。しかし、作り方を誤ると、かえって混乱を招いてしまうこともあります。特に、情報の扱い方や記録方法には注意が必要です。
ここでは、就活ノートを書くときに気をつけたい5つのポイントを紹介します。
- 情報を詰め込みすぎず見やすく整理する
- 古い情報を定期的に更新する
- 企業情報は公式サイトや最新データを確認する
- 個人情報を適切に管理する
- 完璧を目指しすぎず要点をまとめる
①情報を詰め込みすぎず見やすく整理する
就活ノートは多くの情報をまとめる場ですが、詰め込みすぎると読みにくくなり、肝心な内容を見落とすおそれがあります。重要なのは、すべてを書こうとせず、自分に必要な情報を厳選することです。
たとえば、企業ごとの特徴や志望動機の要点だけを書き、詳細なデータは別資料にまとめると良いでしょう。
ページごとにテーマを決め、見出しや余白をうまく使うと、全体が整理されて見やすくなります。情報は量より質を意識して作ると、後からの確認もしやすくなるでしょう。
②古い情報を定期的に更新する
就職活動では、説明会の日時や選考スケジュールなどが頻繁に変わります。そのため、一度書いた情報を放置せず、定期的に更新することが大切です。
古い情報をそのまま残しておくと、誤った日程で行動してしまう可能性があります。ページの隅に「更新日」を記入しておけば、情報の鮮度がすぐに分かるでしょう。
また、不要になった内容は削除し、新しい情報に置き換える習慣をつけてください。常に最新の状態を保つことで、就活ノートが信頼できるツールになります。
③企業情報は公式サイトや最新データを確認する
企業研究をするときは、公式サイトや信頼できる情報源を必ず確認するようにしましょう。口コミやSNSだけを参考にすると、誤った情報を信じてしまう危険があります。
たとえば、企業の採用ページや最新のIR情報、会社説明会での担当者の話などは信頼性が高いです。これらをもとに整理すれば、事実に基づいた理解が深まります。
また、情報を書き写すときは引用元を明記しておくと、後から確認しやすく便利です。正確な情報をまとめたノートは、面接の準備にも自信を与えてくれるでしょう。
④個人情報を適切に管理する
就活ノートには、氏名や住所、メールアドレスなどの個人情報を記入することがあります。紛失や盗難のリスクを避けるために、取り扱いには十分注意してください。
外出時に持ち歩く場合は、必要なページだけコピーして持参すると安心です。また、パソコンやクラウドに保存する場合は、パスワードを設定したり、アクセス制限を設けたりしましょう。
就活に関する情報は個人データの集まりでもあるため、安全な管理を心がけてくださいね。
⑤完璧を目指しすぎず要点をまとめる
就活ノートを完璧に仕上げようとすると、時間がかかりすぎて本来の活動が進まなくなることがあります。
ノートは作品ではなく、実用的なメモです。まずは思いついたことを簡単に書き出し、あとから整理していくくらいの気持ちで構いません。
重要なのは、後から見返したときに自分がすぐ理解できる内容にすることです。見た目の美しさよりも、必要な情報を的確にまとめることを優先しましょう。
就活ノートの種類
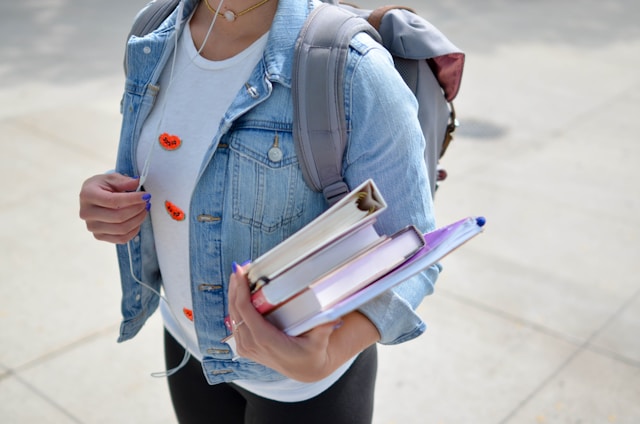
就活ノートには、目的や管理方法に合わせてさまざまなタイプがあります。自分のやり方に合った形式を選ぶことで、情報を整理しやすくなり、就職活動全体の効率も上がるでしょう。
ここでは代表的な5つのタイプを紹介します。
- ノートタイプ
- ルーズリーフタイプ
- バインダー式ノート
- 手帳タイプ
- デジタルタイプ
①ノートタイプ
最も一般的で扱いやすい形式がノートタイプです。時系列で書き進められるため、後から見返しても流れがわかりやすいのが特徴です。
スケジュール管理や面接の記録など、日ごとの動きをまとめるのに向いています。一方で、ページの追加や順番の変更ができない点は注意が必要です。
内容を追加したい場合は、新しいノートを用意する手間がかかります。シンプルにまとめたい人や、紙に手書きで整理したい人におすすめのタイプです。
②ルーズリーフタイプ
自由度の高さが魅力のルーズリーフタイプは、就活の進行に合わせてページを入れ替えられるのが大きな利点です。
自己分析や企業研究など、内容ごとにページを分けて管理できるため、整理がしやすいでしょう。ただし、紙が外れやすい点には注意が必要です。
外出先で使う場合は、ファイルやクリップでまとめて持ち歩くと安心。情報を項目ごとにしっかり整理したい人に向いています。
③バインダー式ノート
ルーズリーフの使いやすさに加え、しっかりしたカバーがあるのがバインダー式ノートです。見た目が整っており、外出時の持ち運びにも適しています。
ポケット付きタイプを選べば、企業資料や名刺なども一緒に管理できるため便利です。
少し重くなりますが、「資料を一括でまとめたい」「整理されたノートを作りたい」という人にはぴったりの形式でしょう。
ビジネスシーンにもなじむデザインのものを選ぶと、就活中もスマートな印象になりますよ。
④手帳タイプ
コンパクトで携帯性に優れているのが手帳タイプです。スケジュール管理を中心に、面接の予定や簡単なメモを書き込むのに最適でしょう。
予定と就活情報を一冊にまとめられるため、外出の多い人に向いています。
ただし、ページ数が限られているため、企業研究や面接内容の詳細な記録には不向きです。日々の予定をすぐ確認したい人や、持ち歩きのしやすさを重視する人におすすめします。
⑤デジタルタイプ
パソコンやスマートフォンを使うデジタルタイプは、検索のしやすさと編集の簡単さが魅力です。
GoogleドキュメントやNotion、Evernoteなどを活用すれば、どこからでもアクセスでき、データの保存や共有もスムーズにできます。ただし、手書きに比べて記憶に残りにくいという面に注意です。
面接練習のメモなど、覚えておきたい内容は紙に書くとよいでしょう。オンラインで効率的に情報を整理したい人におすすめの方法です。
就活ノート作成に役立つアイテム

就活ノートを効率よく作るためには、使うアイテムの選び方が重要です。便利な文房具やデジタルツールをうまく活用することで、整理しやすく見返しやすいノートに仕上がるでしょう。
ここでは、就活ノート作成に役立つアイテムを5つ紹介します。
- こすると消せるボールペン
- 蛍光ペンやカラーマーカー
- 付箋やインデックスシール
- バインダーやクリアファイル
- 就活管理に便利なスマホアプリ
①こすると消せるボールペン
就活ノートでは、説明会の日程変更や企業情報の更新など、書き直す場面が多くあります。そのため、フリクションなどのこすると消せるボールペンを使うと便利です。
誤字をきれいに修正できるので、ノートをすっきりと保てます。また、黒・青・赤の3色を使い分けると、情報の優先度を整理しやすくなるでしょう。
たとえば、締切日などの重要事項は赤、企業情報は黒、補足メモは青といった形です。ペン先は0.38〜0.5mmの細字を選ぶと、文字が詰まりすぎず読みやすいノートになります。
②蛍光ペンやカラーマーカー
ノートの中で特に目立たせたい部分を強調するには、蛍光ペンやカラーマーカーが役立ちます。
スケジュールや企業の特徴など、後で見返したい情報に色をつけておくと、必要な箇所をすぐに見つけやすくなるでしょう。ただし、色を多用しすぎると見づらくなるため、2〜3色に絞るのがおすすめです。
たとえば、スケジュールはオレンジ、企業データは緑、自己分析メモは黄色といったルールを決めておくと混乱しません。裏写りしにくいペンを選ぶと、ノートがよりきれいに保てるでしょう。
③付箋やインデックスシール
付箋やインデックスシールは、情報整理やページ管理に欠かせないアイテムです。企業ごとにページを分けたり、進行状況を見やすくしたりする際に使用します。
特に小さめの付箋は、後から新しい情報を追加するときに便利です。説明会で得た内容や面接メモを貼っておけば、ページを汚さずに整理できるでしょう。
インデックスシールでページを色分けしておくと、開きたいページをすぐに探せて効率的です。色や形を工夫すると、自分だけの使いやすいノートに仕上がります。
④バインダーやクリアファイル
バインダー式ノートやクリアファイルを使うと、ページを自由に入れ替えられるため、常に最新の情報を保てます。
就活では企業情報や選考記録を頻繁に更新することが多いため、固定ノートよりバインダー形式が向いているでしょう。
また、説明会資料や名刺、応募書類を一緒に保管できるクリアファイルを用意しておくと便利です。企業ごとにポケットを分けておけば、情報の取り違えを防げます。
外出時にも取り出しやすく、整理された印象を保てるのもメリットです。
⑤就活管理に便利なスマホアプリ
紙のノートと併用したいのが、就活管理用のスマホアプリです。スケジュールや企業情報、選考状況をデジタルでまとめておくと、外出先でもすぐに確認できるでしょう。
代表的なアプリには「Googleカレンダー」「マイナビアプリ」などがあります。これらを活用すれば、説明会の通知や企業情報の更新を自動で受け取ることが可能です。
アプリ内のメモ機能を使えば、紙のノートとの併用もスムーズになります。アナログとデジタルを組み合わせることで、より効率的に就活を進められるでしょう。
就活ノートを活用して効率的に就活を進めよう

就活を成功させるためには、情報を整理しながら計画的に行動することが欠かせません。そのための最適なツールが「就活ノート」です。
就活ノートを活用すれば、スケジュール管理や企業研究、自己分析などを一元化でき、行動の抜け漏れを防げます。
また、思考を可視化することで自分の強みや課題を客観的に把握でき、面接対策にも役立つでしょう。さらに、デジタルや手書きなど自分に合った形式を選ぶことで、無理なく継続できます。
重要なのは完璧を目指すことではなく、「自分が見返しやすい形」にすることです。就活ノートをうまく使いこなせば、情報整理だけでなく、自信を持って選考に臨むための強力な味方になるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。