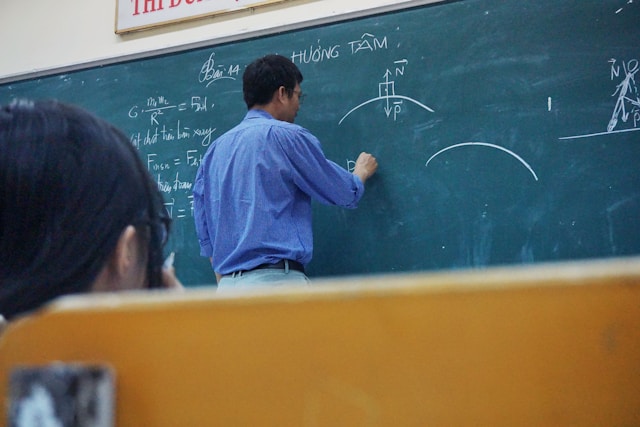士業の年収はいくら?人気8士業・10士業の難易度と将来性を詳しく紹介
弁護士や税理士などの士業は専門性の高い国家資格であり、独立開業や高年収を目指せる職業として人気があります。一方で、資格の難易度や将来性には大きな差があるのも事実です。
そこで本記事では、代表的な8士業・10士業の仕事内容や平均年収、難易度、そして今後の将来性まで詳しく紹介します。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
士業とは?

士業とは、特定の専門知識や国家資格をもとに、社会や企業の問題を解決する仕事の総称です。
ここでは、士業の基本的な定義から、一般職との違い、そして代表的な8士業・10士業について分かりやすく解説しています。
- 士業の定義
- 士業と一般職の違い
- 8士業・10士業
①士業の定義
士業とは、国家資格を取得し、特定の分野で専門的な業務を行う職業のことを指します。
代表的な例には、弁護士、税理士、司法書士などがあり、これらはいずれも法律・経済・労務などの専門知識を活かして、個人や企業が直面する問題を支えています。
就活生にとって重要なのは、「資格を取れば安定して働ける」という表面的な面だけでなく、「資格を通じて専門家として信頼される存在になれる」という本質を理解することでしょう。
特に、近年はAIやデジタル化の発展により、法律判断や倫理的判断など人の感性が問われる領域で、士業の重要性はさらに高まっています。
士業は単なる職業ではなく、一生を通して磨き続ける専門スキルを軸にキャリアを築く生き方ともいえます。
②士業と一般職の違い
士業と一般職の大きな違いは、「国家資格の有無」と「独占業務を行えるかどうか」にあります。
一般職は、企業ごとの業務範囲で働き、スキルや経験によって評価されますが、士業は法律で定められた資格を持つことで、特定の業務を独占的に行えます。
さらに、一般職が企業に所属して働くのに対し、士業は独立開業が可能で、自らの裁量で仕事量を調整できます。もちろん、資格を取った後も法律改正や制度変化に対応し、学び続ける姿勢が不可欠です。
その反面、努力や信頼を積み重ねることで顧客を獲得し、安定した収入と社会的信用を得られる魅力もあります。自分の力でキャリアを築ける働き方といえるでしょう。
③8士業・10士業
「8士業」や「10士業」とは、日本における主要な士業の分類を指します。
まず「8士業」には、弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士が含まれています。
さらに「10士業」と呼ばれる分類では、これらに加えて、公認会計士と中小企業診断士、不動産鑑定士が含まれます。
就活生にとって注目すべきなのは、各士業ごとに年収・独立のしやすさ・将来性が異なるという点です。たとえば、弁護士や公認会計士は高収入が期待できますが、資格取得の難易度も高い傾向にあります。
どの士業を選ぶかによってキャリアの形が大きく変わるため、自分の適性や興味をしっかり見極めることが、後悔しない選択につながります。
代表的な士業一覧(8士業・10士業)とその仕事内容

士業といっても、その内容や専門分野はさまざまです。ここでは、8士業・10士業に含まれる代表的な職種について、それぞれの仕事内容や役割を解説します。
どの士業を目指すかによって、働き方や将来のキャリアが大きく変わるため、就活生のうちから理解しておくことが大切です。
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
- 弁理士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 土地家屋調査士
- 海事代理士
- 公認会計士
- 不動産鑑定士
- 中小企業診断士
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①弁護士
弁護士は、法律に関するあらゆる問題を扱う法務の専門家です。個人のトラブルから企業法務、刑事事件まで幅広く対応します。
主な業務は法律相談、契約書作成、訴訟代理などで、社会正義の実現に貢献する職業といえるでしょう。資格試験の難易度は高いですが、専門性が高いため年収水準は士業の中でも上位に位置します。
社会的信頼も厚く、企業法務や国際法務など幅広い分野で活躍の場が広がっています。近年では、企業コンプライアンスやスタートアップの法務支援、知的財産関連など、新しい分野へのニーズも増加しています。
弁護士は法の知識だけでなく、論理的思考力や交渉力が重要であり、社会の公正を守る使命感を持つ人に向いた職業です。
②司法書士
司法書士は、不動産登記や商業登記、相続手続きなどを専門とする士業です。法律知識をもとに、登記に関する書類作成や申請を代行し、登記業務の円滑化を担います。
また、簡易裁判所での代理業務も行えるため、市民にとって身近な法務の専門家といえるでしょう。仕事には、正確さと信頼性が求められ、独立開業する人も多い職種です。
実績を積めば安定した年収を得られ、長く活躍できる職業でしょう。さらに、相続登記の義務化や空き家問題の増加により、今後も需要の高まりが期待されています。
法律知識を社会生活に密接に活かせる点が魅力であり、地域に根ざして働きたい人にも向いているでしょう。
③行政書士
行政書士は、官公庁への許認可申請や、契約書作成などの手続きを専門とする士業です。企業設立のサポート、建設業許可申請、外国人の在留資格申請など幅広い行政業務を担当します。
中小企業や個人事業主の支援役として、欠かせない存在です。独立開業しやすい反面、案件の獲得には営業力も必要となります。
資格取得後は、ネット集客や口コミなどを活用して、実績を積むことが成功のポイントです。加えて、近年では入管業務や補助金申請のサポートなど、新しい分野でも活躍の場が広がっています。
柔軟な対応力とコミュニケーション能力を磨くことで、信頼を積み重ね、安定した収入につなげられるでしょう。
④弁理士
弁理士は、特許や商標、意匠、実用新案などの知的財産を保護する専門家です。発明やアイデアを法的に守るための申請・手続きを行い、企業の技術やブランドを支えます。
理系出身者が多く、特許庁への申請業務や企業の知的財産戦略に関わる機会も多い職種です。国際的な案件では、英語力も重要になります。
専門性が高く、知識と経験を積めば高収入を狙える職業です。さらに、技術革新の進む現代では特許関連の需要が増えており、AI、医療、バイオ分野など最先端技術に触れる機会も多くあります。
技術への理解力と法的センスの両方が求められますが、その分やりがいのある職業といえるでしょう。
⑤税理士
税理士は、税務申告や会計処理を通じて、企業や個人の財務面を支える専門家です。税務の相談や節税対策を行い、経営者の良きパートナーとして信頼されています。
繁忙期は忙しいものの、景気に左右されにくく安定した需要があります。独立開業がしやすく、経験を積むほどに顧客も増えやすい傾向です。
会計知識を活かしてコンサルティングに進む道もあり、キャリアの選択肢が広い職業といえるでしょう。特に、中小企業支援や事業承継、相続税対策の分野では今後も高い需要が見込まれます。
数字に強く、経営の全体像を見通せる人に適した資格です。
⑥社会保険労務士
社会保険労務士(社労士)は、人事・労務・社会保険の分野を専門とする士業です。
労働保険や社会保険の手続きを代行し、企業の労務管理をサポートします。就業規則の作成や労務トラブルの防止にも携わり、働き方改革が進む今、特に需要が高まっている職種です。
企業内で働くことも可能ですが、独立して顧問契約を結ぶ人も多くいます。安定性と社会的意義の両方を兼ね備えた士業です。
近年では、メンタルヘルス対応やハラスメント防止支援など、従業員が安心して働ける職場づくりに貢献する場面も増えています。
人事分野に興味がある人や、人と企業をつなぐ役割を果たしたい人に適した資格です。
⑦土地家屋調査士
土地家屋調査士は、土地や建物の登記を扱う専門家です。測量や調査を行い、法務局への登記申請を代行します。不動産業界や建設業界との関わりが深く、正確な図面作成や境界確認などが主な業務です。
現場経験が重視される職業であり、地域密着型の働き方を選ぶ人も多く見られます。資格取得後も継続的にスキルを磨けば、信頼を得ながら安定した年収を維持できる職業です。
特に、都市開発や再開発事業の拡大により、専門知識を持つ人材の需要が増加しています。実務力と人間関係の構築力が成果に直結する職業といえるでしょう。
⑧海事代理士
海事代理士は、船舶や海運業に関する行政手続きを専門とする士業です。船舶の登記や登録、検査申請などを行い、船主や海運会社の事務をサポートします。
扱う業務が限られるため知名度は高くありませんが、専門性が高く、特定分野での信頼が厚い資格です。行政書士業務と兼ねて独立するケースも多く、少数ながら安定した需要があります。
海事に関心のある人にとって、魅力的な職業でしょう。さらに、港湾業務や海上物流のグローバル化が進む中で、国際的な手続きや法規に対応できる専門家としての価値も高まっています。
⑨公認会計士
公認会計士は、会計監査や財務分析を通じて、企業の経営を支える士業です。企業の財務状況を監査し、適正な会計処理が行われているかを確認します。
監査法人やコンサルティング会社で働く人が多く、転職市場でも高く評価されています。資格の難易度は非常に高いですが、合格すれば高年収と安定したキャリアが得られます。
独立して税理士業務を行うこともでき、将来の選択肢が豊富です。さらに、企業のM&Aや国際会計基準対応など、グローバルな舞台で活躍するチャンスもあります。
数字を扱うだけでなく、経営の健全性を支える社会的使命を担う職業です。
⑩不動産鑑定士
不動産鑑定士は、土地や建物の価値を評価する専門家です。売買や相続、融資の際に不動産の適正価格を算出します。法律、経済、建築の知識を活かして評価を行うため、幅広い専門知識が求められるでしょう。
不動産業界や金融機関、官公庁などで活躍できる職業です。資格の難易度は高いですが、社会的需要が安定しており、長期的に収入を維持しやすい士業といえるでしょう。
特に、地価公示や公共事業に関する評価など、社会インフラに関わる業務も多く、社会貢献度の高い職業でもあります。
⑪中小企業診断士
中小企業診断士は、企業経営を支援するコンサルティングの専門家です。経営戦略や人材育成、資金繰りなどの課題を分析し、改善策を提案します。
国家資格の中でも、実践的な経営知識を学べる点が特徴です。中小企業庁や自治体の支援事業に関わることもあり、社会貢献度の高い職業といえます。
会社員としてのキャリアアップにも有効で、独立して経営コンサルタントとして活躍する人も少なくありません。
さらに、企業のデジタル化や事業承継の課題が増える中で、診断士の役割はますます重要になっています。理論と実践の両方を磨くことで、信頼される経営アドバイザーとして長期的に活躍できるでしょう。
士業の平均年収

士業の平均年収は、資格の難易度や独立のしやすさ、業務内容によって大きく異なります。ここでは、主要な士業ごとの平均年収を紹介し、それぞれの特徴や働き方による違いを解説しています。
就活生にとっては将来のキャリアを考えるうえで、収入面の目安を知っておくことが重要です。
- 弁護士の平均年収
- 司法書士の平均年収
- 行政書士の平均年収
- 弁理士の平均年収
- 税理士の平均年収
- 社会保険労務士の平均年収
- 土地家屋調査士の平均年収
- 海事代理士の平均年収
- 公認会計士の平均年収
- 不動産鑑定士の平均年収
- 中小企業診断士の平均年収
①弁護士の平均年収
弁護士の平均年収は、約765.3万円です。この統計値を基に考えると、弁護士は高収入が期待できる職業といえます。
大手事務所や企業法務を担当すれば、これを上回る報酬を得る可能性があります。反対に、若手で独立したばかりの段階では、収入がこの統計を下回ることもあり得るでしょう。
実務経験を積み、クライアントを増やす努力が年収を底上げするカギになります。
弁護士 — 職業情報提供サイト(job tag) 弁護士
②司法書士の平均年収
司法書士の平均年収は、約765.3万円です。この数値をもとに考えると、司法書士は年収面で有利な可能性があります。企業や大都市部の事務所勤務者は、このレベルを上回るケースもあり得ます。
一方、若手や開業直後の司法書士はこれを下回ることも多く、収入は案件数や地域によって大きく左右されるでしょう。実績を積み上げて信頼を得ることで、高水準の年収を目指せる職業といえます。
司法書士 — 職業情報提供サイト(job tag) 司法書士
③行政書士の平均年収
行政書士の平均年収は、約591万円です。ただし、行政書士は業務範囲が非常に広いため、扱う分野や案件内容によって収入に大きな差が生じやすい職業でしょう。
始めたばかりの時期は、収入300万円台というケースもありますが、許認可申請や外国人関連業務といった専門性の高い分野に特化すれば、700万円以上の収入も目指せます。
重要なのは、専門分野を絞って実績を積むことと、営業や顧客獲得の努力を継続することです。
特に、都市部ではこの統計値を上回る収入例も報告されており、地域や活動範囲によって差が出やすい点に留意してください。
行政書士 — 職業情報提供サイト(job tag) 行政書士
④弁理士の平均年収
弁理士の平均年収は、約765.3万円です。この数字を参考にすれば、弁理士は高い年収を期待できる職業といえます。
特許事務所や企業の知財部門に勤める場合、この基準を超える報酬を得る可能性があるでしょう。逆に、若手や独立初期の段階では、この水準を下回ることも珍しくありません。
収入を伸ばすには、実績を積んで顧客を増やすこと、専門分野に特化してニッチを掴むことが不可欠です。特許・商標分野など知財業務全般で高い専門性を示せれば、さらなる年収アップも見えてくるでしょう。
弁理士 — 職業情報提供サイト(job tag) 弁理士
⑤税理士の平均年収
税理士の平均年収は、約856.3万円です。この統計を指標とすれば、税理士には高収入の可能性がある職業と言えます。
会計事務所勤務の税理士であれば、経験に応じて400〜600万円あたりの年収が多く見られますが、独立して顧問先を増やせば1,000万円超も十分に見込めるでしょう。
顧客層や業務内容によって収入の振れ幅が大きいため、信頼を得て案件を拡大していくことが収入アップのカギとなります。
税理士 — 職業情報提供サイト(job tag) 税理士
⑥社会保険労務士の平均年収
社会保険労務士の平均年収は、約903.2万円です。この数字から見ると、社労士という職業にも高収入の可能性があると判断できます。
企業勤務の社労士であれば、勤務先の規模や役職によって年収は大きく変動するでしょうし、独立して顧問契約を多く結べば、この統計値を超える職もあり得ます。
労務トラブル対応や人事制度設計など、付加価値の高い業務を担えるように専門性を磨けば、年収アップにつながるのは間違いありません。
社会保険労務士 — 職業情報提供サイト(job tag) 社会保険労務士
⑦土地家屋調査士の平均年収
土地家屋調査士の平均年収は、約765.3万円です。実際の年収は、案件数、地域、独立か勤務かなど、多くの要因で変動します。
土地家屋調査士は、測量や登記を行う専門家として、不動産取引や建設に欠かせない役割を担っています。独立して活動する人が多く、仕事を得る量や地域の信頼性が年収に直結します。
経験を重ねて地域での評価を高めれば、安定した依頼を確保しやすくなるでしょう。手に職をつけたい人には、長く続けられる可能性のある職業だといます。
土地家屋調査士 — 職業情報提供サイト(job tag) 土地家屋調査士
⑧海事代理士の平均年収
海事代理士の平均年収は明確な公的データがなく、概ね300~500万円程度とされています。船舶登記や海運関連の行政手続きを扱う専門職で、業務範囲が限られるため件数により収入差が出ます。
行政書士業務を兼ねることで、収益を安定させる人も多いです。海事分野はニッチながら専門性が高く、独自のポジションを築ける士業といえるでしょう。
⑨公認会計士の平均年収
公認会計士の平均年収は、約856.3万円です。それを踏まえると、公認会計士は十分に高い年収が見込める職業といえます。
監査法人勤務であれば、若手でも600万円前後から始める例が多く、経験を積んでマネジメント職やパートナーとなれば、1,200万円以上も十分可能です。
独立して顧問契約を多数持つことで、さらに高収入を目指せます。難易度の高い資格ですが、将来的なキャリアの幅や国際的な活躍も視野に入る点が魅力でしょう。
公認会計士 — 職業情報提供サイト(job tag) 公認会計士
⑩不動産鑑定士の平均年収
不動産鑑定士関連の平均年収は、約765.3万円です。不動産鑑定士は、不動産の価値を評価する専門家として、売買、相続、融資など多くの場面で用いられます。
経験を重ねて案件の質や量を高められれば、独立して1,000万円以上を目指すことも可能です。
ただし、不動産の市場変動や景気の影響を受けやすい性質もあるため、収入を安定させるには専門性を深め、顧客との信頼関係を築くことがカギとなります。
不動産鑑定士 — 職業情報提供サイト(job tag) 不動産鑑定士
⑪中小企業診断士の平均年収
中小企業診断士の平均年収は、約903.2万円です。それを踏まえると、中小企業診断士は高収入の可能性を秘めた職業といえます。
企業勤務であれば、経験やポジションによって年収アップが期待でき、独立して複数の顧問契約を確保すれば、さらなる高収入も視野に入るでしょう。
専門性と実績を強めることで、さまざまな業界で活躍できる資格といえます。
中小企業診断士 — 職業情報提供サイト(job tag) 中小企業診断士
士業資格の種類と特徴

士業資格にはさまざまな種類があり、それぞれに特徴や取得の難易度、活かし方が異なります。
ここでは、国家資格と民間資格の違い、独占業務の有無による違い、そして資格を取るメリットとデメリットについて解説しましょう。
- 国家資格と民間資格の違い
- 独占業務がある士業とない士業の違い
- 資格取得のメリット・デメリット
①国家資格と民間資格の違い
士業資格には、大きく分けて国家資格と民間資格があります。国家資格は法律に基づいて国が認めたもので、一定の業務を独占して行えるのが特徴です。
たとえば、弁護士や税理士などがこれに該当します。一方、民間資格は企業や団体が独自に設定した資格で、業務の独占権はありません。国家資格は社会的な信頼性が高く、就職や転職で有利になるでしょう。
ただし、取得には時間と費用がかかります。民間資格は比較的取得しやすい反面、社会的評価が限定的です。どちらを選ぶかは、自分のキャリア目標や働き方に合わせて考えるのが大切です。
②独占業務がある士業とない士業の違い
士業の中には「独占業務」が認められている資格と、そうでない資格があります。独占業務とは、特定の資格者だけが行える業務のことです。
たとえば、弁護士の訴訟代理や、税理士の税務申告が代表例です。反対に、独占業務のない士業は、資格がなくても一部の業務を行える場合があります。
ただし、資格を持つことで専門性や信頼性が高まり、依頼を得やすくなるのが実情です。独占業務がある士業は収入が安定しやすい一方、資格取得の難易度が高い傾向があります。
自分の得意分野や、将来の働き方を意識して選ぶことが重要です。
③資格取得のメリット・デメリット
士業資格を取得する最大のメリットは、専門職としての信頼を得られることです。国家資格の場合、独占業務によって安定した収入を確保できる可能性もあります。
さらに、独立開業できる資格も多く、自分の力でキャリアを築ける点も魅力でしょう。一方で、資格取得には多くの時間や費用がかかり、合格率も低めです。
働きながら学ぶ人にとっては、両立が難しい場合もあるでしょう。また、資格を取っただけでは高収入が保証されるわけではなく、実務経験や営業力が求められます。
資格はゴールではなく、キャリア形成のスタートと考える姿勢が大切です。
特に難易度が高い士業

士業の中には、試験の合格率や学習期間の長さから、特に難易度が高いとされる資格があります。ここでは、代表的な5つの難関士業を取り上げ、それぞれの特徴や難しさの理由を解説しています。
努力と計画的な学習が必要ですが、取得できれば高い専門性と社会的信頼を得られるでしょう。
- 弁護士(司法試験)
- 公認会計士
- 不動産鑑定士
- 弁理士
- 司法書士
①弁護士(司法試験)
士業の中でも、最難関といわれるのが弁護士資格です。司法試験の合格率は例年20%前後と低く、法科大学院を修了しても合格には多くの努力が必要でしょう。
試験範囲は、民法・刑法・憲法などに加えて、実務を想定した応用問題も含まれます。そのため、長期間の学習と論理的思考力が欠かせません。合格後は、高い社会的地位と収入を得られるのが大きな魅力です。
平均年収は約1,000万円といわれ、専門分野を持つことでさらにキャリアの幅を広げられるでしょう。
②公認会計士
公認会計士は「会計のプロフェッショナル」として、監査や財務分析を行う専門職です。試験の合格率は10%前後と難易度が高く、平均2〜3年の学習期間が必要とされています。
会計学や企業法、監査論など多くの専門分野を学ぶため、計画的な勉強が欠かせません。合格後は、監査法人や一般企業の財務部門などで活躍でき、平均年収は1,000万円を超える場合もあります。
数字に強く、論理的に考えることが得意な人に向いている資格といえるでしょう。
③不動産鑑定士
不動産鑑定士は、不動産の価値を公正に評価する専門家です。試験の合格率は10%前後で、法律・経済・会計の知識を幅広く求められる点が難しさの要因となっています。
合格までには、3年以上の学習期間を要することもあります。不動産業界、金融機関、官公庁など活躍の場が広く、平均年収は約700万円です。
景気の影響を受けやすい職業ですが、専門的な分析力を身につければ安定した収入を得られる士業といえるでしょう。
④弁理士
弁理士は、特許や商標などの知的財産を扱う専門家で、理系出身者にも人気の高い資格です。試験の合格率は6〜8%と低く、難関資格の一つに数えられます。
出題範囲が広く、特許法や実用新案法、英語による書面作成など実務的な能力も求められます。特許事務所や企業の知的財産部で活躍するケースが多く、平均年収は約700万円です。
技術と法律の知識を活かして働きたい人にとって、魅力的なキャリアパスとなるでしょう。
⑤司法書士
司法書士は、不動産登記や商業登記、相続関連の法的手続きを行う専門家です。試験の合格率は3〜5%ほどと非常に低く、合格までに長い学習期間が必要でしょう。
科目数が多く、法律の理解と記述力の両方が求められるため、独学での合格は容易ではありません。一方で、資格を取得すれば独立開業がしやすく、安定した仕事量を確保できます。
平均年収は約700万円前後で、経験を積むほど依頼が増える傾向にあるでしょう。地道に努力を続けたい人に向いた士業といえます。
士業の将来性

士業は専門知識を生かして長く働ける職業ですが、社会や技術の変化によって、求められるスキルや役割は変わりつつあります。
ここでは、今後需要が高まる士業やAI時代でも活躍できる分野を紹介し、将来性のある士業を目指すためのヒントを解説しています。
- 今後需要が高まる士業とは
- 人口減少・少子高齢化が士業に与える影響
- AI・自動化に代替されにくい士業の特徴
- 将来性のある士業になるために今からできる準備
- 若手士業が活躍できる新しい働き方
①今後需要が高まる士業とは
今後需要が高まる士業は、社会の変化や技術革新に柔軟に対応できる、専門性を持つ職業です。
たとえば、労務管理や年金制度を扱う社会保険労務士は、働き方改革の推進や雇用環境の改善に伴って注目度が上がっています。
さらに、経営再建や資金調達を支援する中小企業診断士も、経済の不安定化によりニーズが拡大しています。
また、国際取引の増加や知的財産の保護意識の高まりにより、弁理士や弁護士の国際案件対応も増えていくでしょう。
これからの時代は、単に資格を持つだけでなく、デジタル化やグローバル化への理解を深め、課題を解決できる実践的なスキルを備えた士業が求められるでしょう。
②人口減少・少子高齢化が士業に与える影響
人口減少や少子高齢化は、士業にとって避けられない社会的課題です。高齢化が進む中で、相続、遺言、成年後見制度などを扱う司法書士や行政書士への需要は着実に増加しています。
さらに、介護や医療、年金制度など社会保障関連の分野でも、社会保険労務士の役割が拡大中です。一方で、地方では企業数や人口の減少により、顧客の確保が難しくなる傾向もあります。
そのため、オンライン相談やリモート業務を導入し、全国の顧客に対応できる体制を整えることが重要です。
地域密着型の信頼関係とデジタル活用を両立させる士業が、今後の社会で安定した活躍を続けられるでしょう。社会構造の変化に対応し続ける姿勢が、将来の差を生むポイントです。
③AI・自動化に代替されにくい士業の特徴
AI技術の発展によって、単純な計算や文書作成などの定型業務は、自動化が進むと考えられます。しかし、士業の根幹にある「人との信頼関係構築」や「状況に応じた判断力」はAIには代替できません。
たとえば、弁護士がクライアントの感情に寄り添いながら法的戦略を立てたり、税理士が企業の状況を見極めた上で節税提案を行ったりする業務は、人の洞察力が欠かせません。
社会保険労務士や中小企業診断士のように、人事問題や経営課題を総合的に判断する仕事も同様です。
共感力、柔軟な思考、倫理的判断力といった「人間ならではのスキル」を磨くことで、AI時代でも必要とされる士業になれるでしょう。
④将来性のある士業になるために今からできる準備
将来性のある士業を目指すには、資格取得だけでなく、実務経験や最新スキルの習得が欠かせません。
AIやデジタル化によって業務効率が向上する一方、オンライン申請や電子契約の導入など、ITリテラシーが求められる場面も増えています。
そのため、Excelやクラウド会計ソフトの操作、電子署名などの基本スキルを身につけておくと有利です。
さらに、英語や中国語などの語学力を磨けば、海外との取引や国際業務にも対応でき、キャリアの幅が広がります。実務経験を重ねながら、継続的に勉強する姿勢を持つことが何より重要です。
また、他士業とのネットワークを築き、協業のチャンスを広げることも将来の強みになります。資格を取った瞬間がスタートであり、学び続ける姿勢こそが長く活躍するために重要となります。
⑤若手士業が活躍できる新しい働き方
近年では、若手士業を中心に柔軟で革新的な働き方が広がっています。
SNSを活用して自分の専門性を発信し、顧客を獲得する「パーソナルブランディング型士業」や、オンライン相談サービスを通じて全国のクライアントを支援するスタイルが注目されています。
また、弁護士・税理士・行政書士など複数の士業が連携し、企業の課題を総合的に解決する「ワンストップ型事務所」も増加中です。
こうした環境では、デジタルツールの習熟や柔軟な発想が大きな強みとなります。さらに、副業やフリーランスとしての働き方を取り入れる士業も増えており、専門性を武器に多様なキャリアを築けます。
若手のうちから新しい挑戦を恐れず、時代の変化に合わせて自分らしい働き方を選ぶことが、将来性の高い士業への第一歩といえるでしょう。
士業のキャリアと年収の展望

士業は専門的な知識と国家資格を武器に、高い専門性と安定した年収を得られる職業です。
弁護士や公認会計士などの難関資格から、行政書士や社会保険労務士といった身近な資格まで、その種類と働き方は多岐にわたります。
特に、平均年収は職種や経験によって大きく異なり、努力次第で年収1,000万円以上も目指せる点が魅力でしょう。
また、AIや自動化が進む中でも、人間の判断や信頼関係が求められる士業は代替されにくい存在です。今後はデジタルスキルや柔軟な働き方を取り入れることで、若手士業にもチャンスが広がるでしょう。
将来性と収入の両方を追求したい人にとって、士業は有力なキャリア選択肢の一つといえます。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。