小論文の構成を徹底解説!書き方と頻出テーマ・例文付き
「小論文って、どうやって構成を考えればいいの?」と悩む就活生は多いでしょう。企業によっては、面接やESだけでなく小論文試験を課すこともあり、論理的な構成力や思考力が合否を左右します。
そこで本記事では、「小論文の構成」をテーマに、基本の書き方から頻出テーマ、例文までわかりやすく解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
就活の選考で小論文が出ることもある

就職活動では、面接や筆記試験に加えて小論文を求める企業もあります。小論文は、応募者の思考力や文章力だけでなく、価値観や論理的な表現力を確認するための重要な選考手段です。
小論文は与えられたテーマについて、自分の考えを根拠をもとに整理し、論理的に展開する力が求められるでしょう。文章の構成や語彙よりも、「どう考え、どう説明するか」という論理性が評価の中心になります。
また、企業は小論文を通して応募者の人柄や考え方、そして自社との相性を見極めているのです。テーマから逸れた内容や論理の飛躍があると、どんなに表現が巧みでも評価は下がってしまいます。
与えられたテーマに対して、冷静かつ一貫した視点で考える姿勢を大切にしてください。日ごろからニュースや社会問題に目を向け、自分の意見をまとめる練習をしておくと安心です。
採用担当者は文章を通じてあなたの価値観や信念を読み取るため、全体の整合性を意識しましょう。小論文は単なる試験ではなく、あなたの思考力と人間性を表現できるチャンスです。
「就活でまずは何をすれば良いかわからない…」「自分でやるべきことを調べるのが大変」と悩んでいる場合は、これだけやっておけば就活の対策ができる「内定サポートBOX」を無料でダウンロードしてみましょう!
・自己分析シート
・志望動機作成シート
・自己PR作成シート
・ガクチカ作成シート
・ビジネスメール作成シート
・インターン選考対策ガイド
・面接の想定質問集100選….etc
など、就活で「自分1人で全て行うには大変な部分」を手助けできる中身になっていて、ダウンロードしておいて損がない特典になっていますよ。
小論文と作文の違い

小論文と作文はどちらも文章を書く試験ですが、目的や構成、評価の観点が大きく異なります。就職活動や入社試験で出題されるのは多くの場合「小論文」です。
小論文は「自分の意見を筋道立てて説明する文章」です。与えられたテーマに対して、根拠を示しながら自分の考えを整理し、論理的に展開していく必要があります。
たとえば「AIの普及は社会にどのような影響を与えるか」というテーマであれば、現状の課題を説明し、自分の立場を明確にしたうえで意見を述べることが大切です。
感情的な表現ではなく、論理性や一貫性、客観性が評価のポイントになります。一方、作文は「自分の経験や感情を中心に表現する文章」です。
普段からニュースや社会問題に関心を持ち、自分の考えを言葉にする練習を続けておくとよいでしょう。そうすることで、論理的で説得力のある小論文が書けるようになります。
企業が小論文で見ているポイント

小論文試験は、単に文章の上手さを問うものではなく、あなたの考え方や社会人としての資質を見極める大切な選考要素です。
企業は小論文を通して、応募者の論理的思考力、社会的関心、価値観、そして自社との相性を確認しているでしょう。ここでは、採用担当者が注目している5つの観点について詳しく解説します。
- 論理的な思考力があるか
- 自分の意見を根拠を持って説明できているか
- 文章構成力・表現力があるか
- 社会問題への関心や理解があるか
- 企業理念や業界理解との整合性があるか
①論理的な思考力があるか
企業が小論文でまず重視するのは、筋道を立てて物事を考える力です。主張と理由が明確で、矛盾のない構成になっているかを見られます。
「なぜそう考えるのか」「どんな根拠があるのか」を順を追って説明できれば、説得力のある文章になるのです。論理的な文章を書くためには、主張・根拠・具体例を意識して構成することが大切です。
感情的な表現や抽象的な言い回しが多いと、意図が伝わりにくくなってしまいます。
普段からニュース記事などを読むときに、「なぜ」「どうして」という視点を持つことで、自然と論理的に考える力が磨かれるでしょう。面接や社会人生活でも役立つスキルです。
②自分の意見を根拠を持って説明できているか
小論文では、自分の意見をただ述べるだけでは不十分です。その意見を裏づける根拠があるかどうかが重要になります。
根拠のない主張は信頼性が低く、読んでいる人に「説得力がない」と感じさせてしまうことがあるのです。
たとえば、「リーダーには柔軟性が必要」と書くなら、「多様な価値観を受け入れることでチームの意見をまとめやすくなる」など、具体的な理由を添えると説得力が増します。
さらに、自分の体験やニュースの事例を交えると、より現実味のある文章になるでしょう。根拠を丁寧に示すことで、思考の深さと誠実さを伝えられます。
③文章構成力・表現力があるか
小論文は、内容だけでなく構成力も評価の対象になります。主張が明確で、序論・本論・結論の流れが整理されていれば、読んでいて理解しやすい文章になるでしょう。
1文を短く区切り、リズムを意識して書くことで、読みやすさも向上します。また、語彙や表現の多様さも評価に影響するでしょう。
難しい言葉を使う必要はありませんが、同じ語尾や表現を繰り返すと単調な印象になるため注意が必要です。文末のバリエーションを意識したり、語彙を豊かにする努力を続けてください。
自分の文章を声に出して読んでみると、構成の不自然さや表現の偏りにも気づけます。
④社会問題への関心や理解があるか
小論文では、社会問題をテーマに出題されることが多くあります。そのため、日頃からニュースや時事問題に関心を持っておくことが大切です。
企業は、社会の出来事をどのように捉え、自分の考えとして整理できるかを見ています。
ただ情報を並べるのではなく、「なぜその問題が起きたのか」「自分ならどう解決するか」といった自分の視点を持って書くことが大切です。
多角的に考える姿勢は、社会人として求められる柔軟性にもつながります。普段から新聞やニュースアプリを活用し、関心を持って考える習慣をつけておきましょう。
⑤企業理念や業界理解との整合性があるか
小論文の内容は、企業の価値観や業界の方向性と矛盾しないようにすることが重要です。
たとえば、チームワークを重視する企業に対して「個人の成果が最優先」と書いてしまうと、理念とのずれが生じてしまいます。
そのため、事前に企業研究を行い、自社の理念や事業方針を理解したうえで、自分の意見を構築しましょう。
「自分の考えがどのようにその企業で活かせるか」を意識して書くことで、より一貫性のある内容になります。小論文は、あなたの価値観と企業の方向性が合っているかを確認する場でもあるのです。
しっかりと情報を整理して臨んでください。
就活小論文の事前準備

就職活動で出題される小論文は、事前の準備が合否を左右する重要な要素です。小論文では、知識や語彙力に加えて、論理的思考力や表現力も求められます。
限られた時間で説得力のある文章を書くためには、普段からのトレーニングが欠かせません。ここでは、就活小論文に向けた効果的な準備方法を5つ紹介します。
- 出題テーマの傾向を把握しておく
- 時事問題への理解を深めておく
- 自分の意見を言語化する練習をする
- 模擬小論文で時間配分を練習する
- 第三者に添削を依頼しフィードバックを得る
①出題テーマの傾向を把握しておく
まずは、企業や業界ごとの出題テーマの傾向を把握しておくことが大切です。小論文では「社会問題」「仕事観」「リーダーシップ」「コミュニケーション」などが頻出テーマ。
志望企業の過去の出題内容を調べると、対策の方向性が見えてきます。また、業界ごとに重視されるテーマが異なる点にも注意しましょう。
たとえば金融業界では「倫理観」や「責任感」、IT業界では「変化への柔軟性」などが問われやすい傾向があります。過去問を活用して、どのようなテーマにも対応できるよう準備を進めてください。
筋の通った主張を構築できるようにすることが、得点を伸ばすポイントになります。
②時事問題への理解を深めておく
時事問題は小論文で頻繁に出題されるでしょう。企業は学生の社会への関心度や視点の広さを見ています。
毎日新聞やニュースサイトをチェックして、政治・経済・環境・労働など幅広い分野に触れておくことが重要です。
情報をただ読むだけではなく、「なぜこの問題が起きたのか」「今後どんな影響があるのか」といった点を考える習慣をつけましょう。
気になるニュースは、要約と自分の意見をセットでノートにまとめておくとよいでしょう。こうした練習を続けることで、考えを整理して文章化する力が自然と養われます。
時事への理解を深めることは、社会人としての基礎力にもつながるのです。
③自分の意見を言語化する練習をする
小論文で最も重視されるのは、自分の意見をわかりやすく伝える力です。テーマに対して「自分は何を主張したいのか」「どんな理由でそう考えるのか」を明確にして書きましょう。
例えば「働くうえで大切なもの」というテーマなら、「責任感」と答えるだけでは不十分です。なぜ責任感が重要なのか、どんな経験からそう感じたのかを、具体的な根拠とともに説明することが必要。
普段から身の回りの出来事やニュースについて、自分の考えを短くまとめる練習を繰り返してください。自分の意見を言語化する習慣が身につけば、論理的で説得力のある小論文を書けるようになるでしょう。
④模擬小論文で時間配分を練習する
小論文試験では、限られた時間内で構成から清書まで行う必要があります。焦らず書き切るためには、時間配分の練習が欠かせません。
たとえば「構想5分・下書き20分・清書10分」といったように、段階ごとに時間を決めておくと効率的です。最初は時間内にまとまらなくても、繰り返すうちに要点を整理して書く力が身についていきます。
また、書き終えた後に自分の文章を見直し、「主張が一貫しているか」「根拠が適切か」を確認してください。何度も練習を重ねることで、限られた試験時間の中でも落ち着いて書けるようになります。
⑤第三者に添削を依頼しフィードバックを得る
自分だけで小論文を仕上げようとすると、誤りや弱点に気づけないことがあります。第三者の視点を取り入れることで、文章の質を大きく高めることができるでしょう。
大学のキャリアセンター、ゼミの先生、信頼できる先輩などに添削を依頼してみましょう。指摘を受けることで、「主張が弱い」「構成が不明確」「表現が伝わりづらい」といった課題が明確になります。
フィードバックを受けたあとは、その内容をもとに必ず自分で書き直すことが大切です。修正を繰り返すことで、構成力や表現力が確実に向上します。
実践を積むほど、自信をもって本番に臨めるようになるでしょう。
出題されやすい小論文テーマ
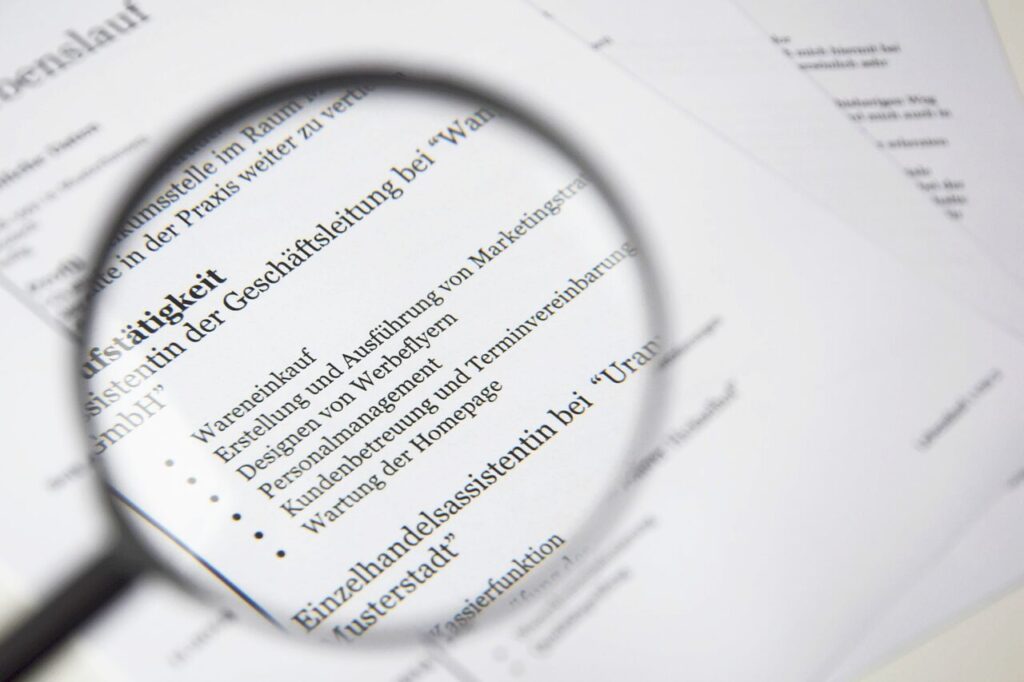
就職活動の小論文試験では、限られた時間で自分の考えを整理し、筋道を立てて伝える力が求められます。テーマの傾向を知っておくと、事前準備がしやすくなるのです。
ここでは、出題されやすい代表的な5つのテーマを紹介します。
- 社会問題・時事問題に関するテーマ
- 業界・企業に関連するテーマ
- 学生自身の価値観や経験に関するテーマ
- 働き方やキャリアに関するテーマ
- 環境・テクノロジーなど未来志向のテーマ
①社会問題・時事問題に関するテーマ
小論文でよく出題されるのは、社会で注目されているニュースや課題に関するテーマです。たとえば、少子高齢化、働き方改革、AIの導入、環境問題などが代表的。
これらのテーマでは、社会全体を広く捉え、自分の考えを明確に持っているかが見られます。日頃から新聞やニュースに触れ、自分の意見を言葉にする練習をしておくと良いでしょう。
例えば「テレワークの普及による働き方の変化」をテーマにするなら、「生産性の向上」と「人間関係の希薄化」という両面を踏まえて書くことが大切です。
どんなテーマでも、「問題点」「原因」「解決策」を整理して構成すると、論理的で説得力のある文章になります。
②業界・企業に関連するテーマ
志望業界や企業に関するテーマも頻出です。たとえば、「自動車業界の今後の展望」「食品業界の安全管理」「IT技術の発展による影響」などがあります。
このタイプのテーマでは、企業研究の深さや業界理解が問われるのです。効果的な準備として、企業の公式サイトや業界ニュースをこまめに確認しておきましょう。
そのうえで、「業界の課題に対して自分がどう関わりたいか」を明確にすることが重要です。単なる賛同や意見ではなく、「課題への具体的な姿勢」や「入社後にどう行動したいか」を書けると好印象。
自分の志望動機と結びつけると、より説得力が増すでしょう。
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
③学生自身の価値観や経験に関するテーマ
「学生時代に力を入れたこと」「困難を乗り越えた経験」「チームでの成果」など、自分の経験をもとに考えるテーマも多く出題されます。
企業はこのテーマを通じて、応募者の人間性や思考のプロセス、価値観を見ているのです。
このタイプでは、経験を並べるだけでなく、そこから「何を学んだか」「どう成長したか」を明確に伝えることが大切です。
たとえば、「アルバイトでのクレーム対応」なら、「お客様の視点に立つ大切さを学んだ」など、得た気づきを書きましょう。
さらに、その学びを社会人としてどう活かすかまで触れると、成長意欲が伝わります。過去の経験を未来の行動につなげることがポイントです。
④働き方やキャリアに関するテーマ
「理想の働き方」「キャリアアップ」「ワークライフバランス」など、働く姿勢を問うテーマも多く見られます。企業はこのテーマを通して、応募者がどのように仕事を捉えているかを知ろうとしているでしょう。
理想論だけでなく、現実的な視点を持つことが大切です。「残業を減らすべき」などの意見だけでなく、「生産性を高める工夫」や「チームでの協力の重要性」など、実践的な考えを盛り込みましょう。
また、自分のキャリアビジョンを踏まえて、「社会人としてどう成長したいか」を具体的に書くと印象が良くなります。将来を見据えた言葉選びを意識してください。
⑤環境・テクノロジーなど未来志向のテーマ
AIや再生可能エネルギー、IoTなど、テクノロジーや環境に関するテーマも人気です。これらは、変化の激しい社会の中で、未来をどう捉え行動できるかを見る意図があります。
このタイプでは、専門知識の多さよりも、自分なりの考え方が重視されるのです。たとえば「AIと人間の共存」をテーマにするなら、「効率化と人間らしさの両立」をどう実現するかを考えてみましょう。
社会の変化に対して自分がどう関わるのかを軸にまとめると、深みのある文章になります。柔軟な発想と現実的な視点を併せ持つことが評価につながるでしょう。
小論文の構成の基本

小論文を上手に書くためには、明確な構成を理解しておくことが欠かせません。多くの学生が内容ばかりに意識を向けがちですが、構成が整っていないと伝わりにくい文章になってしまいます。
ここでは、それぞれのパートの役割と書き方のコツをわかりやすく解説します。
- 序論:テーマと自分の立場を明確にする
- 本論:根拠・具体例を用いて主張を展開する
- 結論:主張を再確認し、全体をまとめる
①序論:テーマと自分の立場を明確にする
序論は小論文全体の方向性を決める重要な部分です。ここではテーマの意図を正確に把握し、自分の立場をはっきりと示すことが大切。
読み手が「この文章は何を主張しているのか」をすぐ理解できるよう、冒頭で問題提起を行いましょう。
たとえば、「現代社会における働き方の多様化についてどう考えるか」というテーマなら、「私は働き方の多様化は、個人の能力を最大限に生かす好ましい流れだと考えます」と書くとわかりやすいです。
また、序論ではテーマの背景や現状を簡潔に述べることで説得力が増します。ただし、書きすぎると冗長になるため、全体の2~3割ほどの分量に収めてください。
序論の目的は、読み手に「これから何を論じるのか」を明確に伝えることです。立場を早い段階で示すことで、文章全体に一貫性を持たせることができます。
②本論:根拠・具体例を用いて主張を展開する
本論は小論文の中心となる部分で、序論で述べた意見を具体的な根拠で支える構成が求められます。ここでは、データや事例、自分の体験などを交えて、主張の信頼性を高めましょう。
たとえば「働き方の多様化が生産性を向上させる」と主張する場合、「リモートワークの普及によって通勤時間が削減された」「個人の裁量が広がり、意欲が向上した」などの根拠を挙げると説得力が増します。
また、反対意見にも一度触れ、その上で自分の立場を強調することで、論理の厚みが出ます。段落ごとに1つの論点を整理するよう意識してください。
あれもこれも詰め込みすぎると、文章の焦点がぼやけてしまいます。「主張→根拠→具体例→まとめ」という流れを意識して構成すれば、読みやすく一貫した論文になるでしょう。
文章を展開するときは、「なぜそう考えるのか」を常に意識しながら書いてください。
③結論:主張を再確認し、全体をまとめる
結論は、序論と本論で述べた内容を整理し、読み手に強い印象を残す部分です。新しい情報を加えるのではなく、これまでの内容をまとめながら、自分の主張を再確認しましょう。
たとえば、「働き方の多様化は、個人がより自由で生産的に働く社会を実現するために必要な変化だと考えます」といった形でまとめると、全体の流れに一貫性が生まれます。
また、就職活動の小論文では、主張を自分の価値観や社会への貢献意識と結びつけるとより効果的です。
「私は多様な働き方を尊重し、自分の強みを生かして社会に貢献できる人材になりたい」といった形で未来への姿勢を示すと印象が良くなります。
結論の目的は、読み手に「この意見は納得できる」と感じてもらうことです。主張の要約と再提示をバランスよく組み合わせ、読み終わった後に説得力が残るよう意識してください。
小論文の書き方のポイント

小論文では、自分の考えを論理的に伝える力が求められます。限られた文字数の中で明確な主張と根拠を提示し、読み手に納得してもらうことが大切です。
ここでは、評価を高めるために意識したい5つの書き方のポイントを紹介します。
- 5W1Hを意識して一貫性のある文章にする
- 根拠や具体性を持たせて説得力を高める
- 語尾は断定的に書いて印象を強める
- 文体は「だ・である」調で統一する
- 誤字脱字・表現のゆれを見直す
①5W1Hを意識して一貫性のある文章にする
小論文では、主張に一貫性のある文章構成が求められます。そのためには、5W1H(When・Where・Who・What・Why・How)を意識することが効果的です。
これを意識して書くことで、読み手が内容を理解しやすくなり、全体の論理が明確になります。
たとえば「なぜその問題が起きたのか」「どのように解決できるのか」といった視点を持つと、論理の流れが整理されるのです。
また、主張→理由→具体例→結論という流れ(PREP法)を意識すると、読みやすい構成になるでしょう。段落ごとにテーマを明確にし、論点がぶれないようにすることが大切です。
一貫性のある文章は、読み手に信頼感を与える鍵になります。
②根拠や具体性を持たせて説得力を高める
小論文で高い評価を得るには、意見に裏づけとなる根拠を示すことが欠かせません。主張だけでは説得力が弱く、印象に残りにくいためです。
根拠には、客観的なデータや事例、自身の経験などを組み合わせると効果的。
たとえば「若者の政治参加を促すべきだ」と書く場合、「投票率の低下傾向」や「SNSを通じた意識変化」などの事実を挙げると説得力が増します。
自分の体験を交えることで、リアリティのある文章にもなるのです。データを用いる際は、出典を明記して正確性を保ちましょう。
根拠を具体的に示すことで、読み手の理解を助け、あなたの意見に重みを持たせることができます。
③語尾は断定的に書いて印象を強める
小論文では、「〜だと思う」「〜ではないでしょうか」といったあいまいな言葉を避け、断定的な語尾で書くことが重要。これは、自分の主張に自信を持っている印象を与えるためです。
たとえば、「〜すべきである」「〜が必要である」と書くと、文章全体に芯が通り、読み手に明確なメッセージを伝えられます。
ただし、根拠を示さずに断定しすぎると独りよがりな印象になるので注意が必要です。主張の裏づけを丁寧に説明しながら、語尾で意志を示すと良いでしょう。
文末を力強く締めることで、文章全体が引き締まり、印象に残る小論文になります。
④文体は「だ・である」調で統一する
小論文では、文体の統一が読みやすさと信頼性に直結します。基本的に「です・ます調」よりも、「だ・である調」を使うのが適しているでしょう。
こちらのほうが客観性が高く、論理的で落ち着いた印象を与えるためです。たとえば「私はそう思います」よりも「私はそう考える」と書くほうが、明確で力強い表現になります。
文体が混ざると、文章に一貫性がなくなり、読み手が違和感を覚える場合があるのです。執筆後には必ず全体を読み返し、文末表現を統一しているか確認してください。
「だ・である」調で書くことで、主張の説得力が高まり、より論理的な印象を与えられるでしょう。
⑤誤字脱字・表現のゆれを見直す
内容がどれほど良くても、誤字脱字や表現のゆれがあると評価が下がってしまいます。小論文試験は限られた時間で行われることが多いため、見直しを怠ってしまう人もいますが、最終確認は非常に重要です。
見直す際は、文章を声に出して読んでみてください。音読すると、不自然な言い回しや言葉の重複に気づきやすくなります。
また、「一文が長すぎないか」「同じ語尾が続いていないか」を確認するのも大切です。誤字や表現のゆれを丁寧に直すことで、完成度が大きく上がります。
小さな修正の積み重ねが、読み手への印象を良くし、あなたの誠実さや集中力を示すことにもつながるでしょう。
小論文を書く際の注意点

小論文では、論理的な構成だけでなく、設問の意図を正しく理解し、限られた時間内で一貫性のある文章を書く力が求められるでしょう。
ここでは、試験で失敗しないために意識すべき5つの注意点を解説します。
- 設問の意図を正確に読み取る
- 主張がブレないように一貫性を保つ
- 感情的・抽象的な表現を避ける
- 制限時間・文字数内で書き切る
- 清書前に内容と構成を必ず見直す
①設問の意図を正確に読み取る
小論文で最も多い失敗は、設問の主旨からずれた内容を書いてしまうことです。テーマを表面的に理解するだけでなく、出題者が何を問いたいのかを正確に把握することが大切。
たとえば「グローバル化についてあなたの意見を述べなさい」という設問でも、「企業のグローバル展開」か「個人の働き方」かで焦点は異なります。
まずは設問文のキーワードを丁寧に確認し、中心となる論点を定めてください。また、問いが複数ある場合は、それぞれにきちんと答える必要があります。
出題者は「読解力」と「論理的思考力」の両方を見ているのです。焦らずに設問の意図をつかむことが、良い小論文を書く第一歩になるでしょう。
②主張がブレないように一貫性を保つ
小論文では、一貫した主張を最後まで維持することが重要です。序論で述べた立場と本論・結論が矛盾していると、全体の説得力が弱まってしまいます。
主張がブレる原因は、根拠をいくつも並べようとして焦点がぼやけることにあるのです。書く前に「自分の意見を一言で表すなら何か」を明確にしておきましょう。
その軸に沿って根拠や事例を展開すれば、自然と文章にまとまりが生まれます。
また、反対意見を取り入れる際には、「確かに〜だが、私は〜と考える」といった形で自分の主張を補強する書き方を心がけてください。一貫性のある論理展開が、読み手の信頼を得る鍵となります。
③感情的・抽象的な表現を避ける
小論文は感情を表す作文ではなく、論理的に意見を述べる文章です。
そのため、「すごい」「ひどい」「かわいそう」といった感情的な言葉や、「大切だと思います」「いろいろな考えがある」などの曖昧な表現は避けましょう。
読み手に納得してもらうためには、具体的な事実やデータ、体験を根拠として示すことが効果的です。
たとえば「働き方改革が進んでいる」よりも、「テレワークを導入する企業が60%に増加した」というように、数字を使うと説得力が増します。
また、比喩や感覚的な表現も避け、誰が読んでも同じように理解できる言葉を選んでください。客観的かつ明確な表現を意識することで、論理的な文章に仕上がります。
④制限時間・文字数内で書き切る
小論文試験では、限られた時間内に指定された文字数を満たす必要があります。時間配分を誤ると、途中で書き終えられなかったり、文字数不足になったりすることも。
まずは、書く前に3〜5分ほどで構成を整理してください。序論・本論・結論の割合を「2:6:2」に設定すると、バランスよくまとめやすくなります。
また、1文を長くしすぎると読みづらくなり、推敲にも時間がかかるのです。1文はおおむね50〜60字を目安にまとめると良いでしょう。
練習の段階から時間を意識して書くことで、本番でも落ち着いて対応できるようになります。限られた時間内で的確に書く力も、企業が評価する大切なポイントです。
⑤清書前に内容と構成を必ず見直す
どんなに良い内容でも、誤字脱字や文の流れに不自然さがあると印象が悪くなります。清書する前に、必ず内容と構成を見直しましょう。まず、序論から結論までの流れが自然かを確認してください。
主張と根拠の関係が不明確な場合は、段落を整理するのも効果的です。次に、語尾のバランスや言い回しの重複をチェックしましょう。
「〜です」「〜ます」が続く場合は、「〜でしょう」「〜ください」などに言い換えると、読みやすさが増します。また、字の乱れや書き損じがある場合は、修正液を使わず新しい用紙に書き直してください。
最後まで丁寧に見直す姿勢が、誠実さを伝える重要な要素になります。細部への配慮が高評価につながるでしょう。
小論文の構成を理解して就活で自分を正しく伝える

就職活動における小論文は、企業が学生の思考力や価値観、そして文章構成力を判断する重要な要素です。
小論文と作文の違いを理解し、構成の基本である「序論・本論・結論」を押さえることが、説得力のある文章を書く第一歩になります。
効果的な小論文を作成するには、論理的な思考力を磨き、自分の意見を根拠とともに明確に伝えることが大切です。
また、時事問題や業界動向への理解を深め、出題テーマへの対応力を養う準備も欠かせません。最終的に、小論文は「自分がどのような考え方を持ち、社会や企業にどう貢献できるか」を伝える場です。
構成の基本と書き方のポイントを意識し、一貫性のある論理展開で自分の強みを表現できれば、選考で高い評価を得られるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














