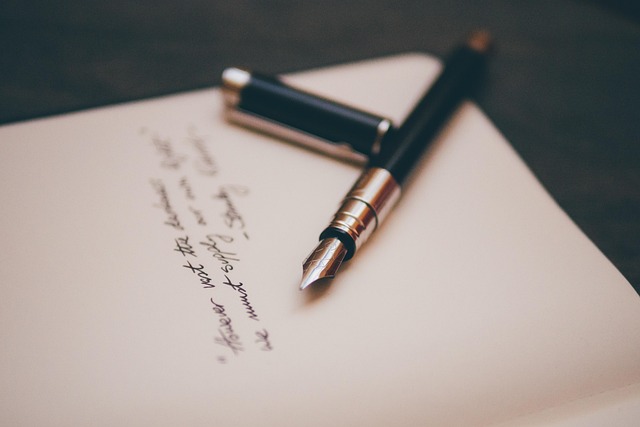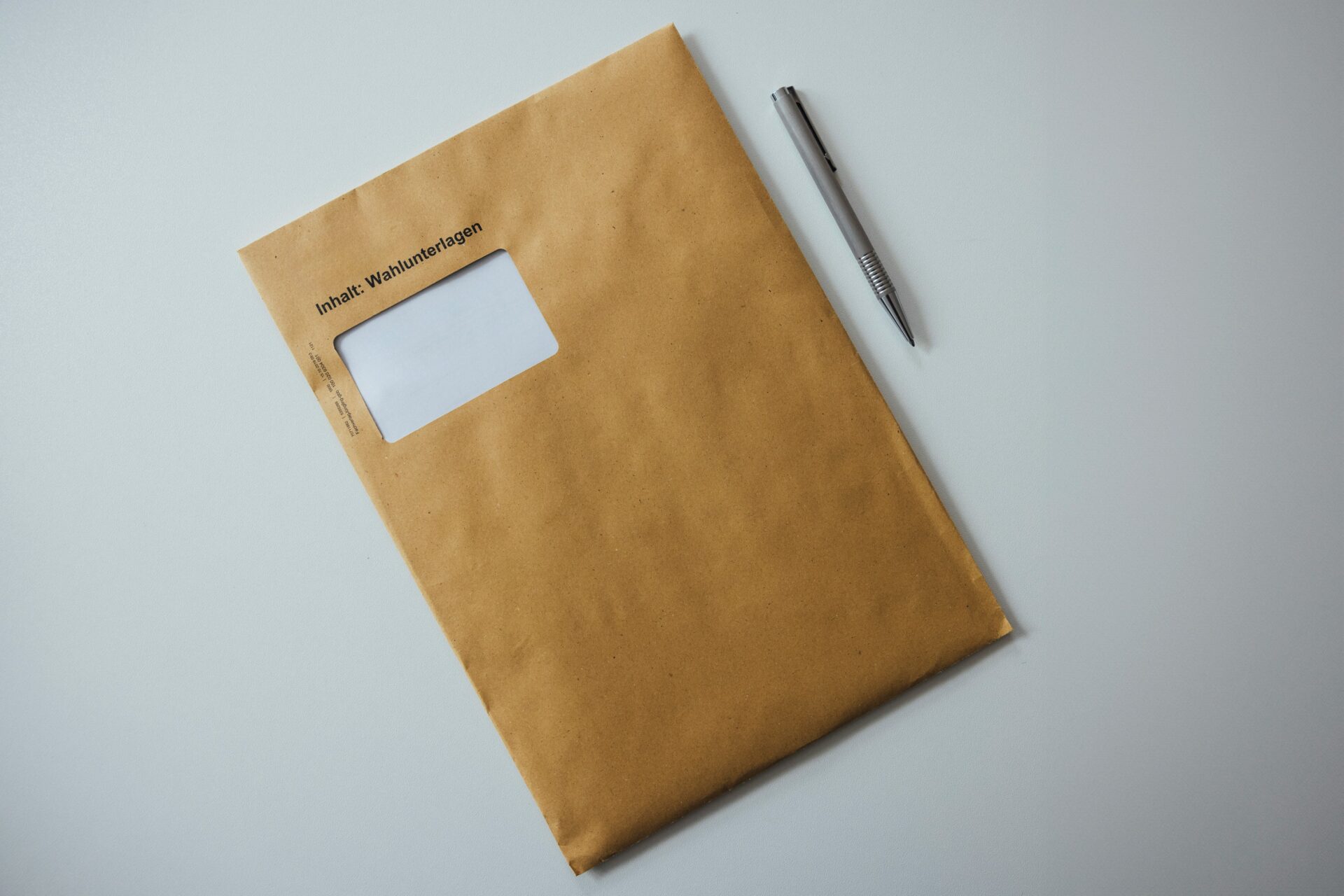会社訪問で好印象を与える!手土産の選び方と渡し方のマナー
「会社訪問で手土産って本当に必要なの?」と悩む人も多いのではないでしょうか。
企業訪問は採用活動の一環やOB・OG訪問など、社会人との初めての接点になる大切な場面です。感謝や誠意の気持ちを、手土産を通じて伝えたいと考えている人もいることでしょう。
しかし、状況によっては手土産が不要とされるケースもあり、選び方や渡し方を誤ると逆効果になってしまうこともあります。
この記事では、会社訪問での手土産マナーについて、相場・選び方・渡し方のポイントを詳しく解説し、好印象を与えるコツを紹介します。ぜひ訪問前の準備に役立ててください。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
会社訪問時の手土産とは?

会社訪問の手土産とは、相手企業への敬意や感謝を表すために送られるものです。
社会人のビジネスマナーとして、取引先を訪問する際に「お世話になっていることへのお礼」として手土産を用意することがあります。ただし、就職活動中の学生の場合は少し事情が異なります。
面接や説明会など、採用選考に関わる訪問では基本的に手土産を用意する必要はありません。賄賂的な使われ方を防止するために、そういったものの受け取りを完全に拒否する企業もあります。
とはいえ、例外的に長年お世話になったインターン先や指導担当の社員の方へ感謝を伝えたい場合には、可能かどうか確かめたうえであれば心のこもった控えめな手土産を検討しても良いでしょう。
このときは、高価なものではなく、気持ちが伝わる程度の小さな品物を選ぶのがポイントです。会社訪問時の手土産は、感謝の気持ちを丁寧に伝えるための手段のひとつとして考えるのが適切です。
会社訪問で手土産が不要とされる理由

会社訪問の際に手土産を持参することは、社会人としては礼儀や気配りの表れとされています。
しかし、就職活動中の学生が企業を訪問する場合には、手土産は基本的に不要です。
ここでは、会社訪問で手土産が不要とされる主な理由を3つの観点から紹介します。
- 採用活動の公平性を保つため
- 過度な印象や誤解を与える可能性があるため
- 言葉や態度で感謝を伝えられるため
①採用活動の公平性を保つため
企業の採用活動では、すべての学生を平等な条件で評価することが最も大切にされています。
そのため、一部の学生が手土産を持参してしまうと、「その学生だけが特別扱いを受けているのでは?」と公平性に疑問を持たれるリスクがあります。
採用担当者の立場から見ても、受け取る側が困ってしまうケースが多く、「他の応募者にも同じ対応をすべきか」と悩ませてしまうこともあります。
また、企業によっては社内規定で「学生からの贈答品は受け取らない」と明確に定めている場合もあります。
このように、企業が公平な選考を行うためには、学生が一律で手土産を持参しない方が望ましいのです。誠実さや礼儀は、手土産ではなく態度で示すことが何より大切だと考えましょう。
②過度な印象や誤解を与える可能性があるため
たとえ純粋に「お世話になったお礼を伝えたい」という気持ちであっても、企業によっては「賄賂のような行為」や「過剰なアピール」と受け取られてしまう可能性があります。
特に採用の場では、学生と企業が対等な関係であるべきため、贈り物をすること自体がそのバランスを崩す原因になりかねません。
また、手土産の内容や価格によっては、「他の学生より印象を良くしようとしている」といった意図しない誤解を招くこともあります。
こうした誤解が生じると、せっかくの誠意が逆効果になってしまいかねません。
そのため、採用担当者に良い印象を残したい場合こそ、贈り物ではなく丁寧な言動や立ち居振る舞いで誠意を伝えることが重要です。小さな行動が信頼につながることを意識してください。
③言葉や態度で感謝を伝えられるため
就職活動では、企業側も学生の「礼儀」や「人柄」をよく見ています。
手土産のような形式的なものよりも、言葉づかい・身だしなみ・立ち方・お辞儀の仕方など、態度から感じ取れる誠実さを重視する企業がほとんどです。
そのため、感謝の気持ちは「モノ」ではなく「コトバ」で伝える方が、より自然で印象的です。
たとえば、訪問時に「本日はお時間をいただきありがとうございます」や「貴重なお話を聞かせていただき感謝しています」と具体的にお礼を伝えることで、あなたの誠意は十分に伝わります。
また、こうした言葉を添えることで、形式に頼らずとも信頼関係の第一歩を築けるという点もポイントです。手土産がなくても、真摯な態度と感謝の言葉こそが最大の“お礼”になります。
会社訪問の手土産の相場

就職活動中に手土産を渡す機会はほとんどありませんが、長年お世話になったインターン先や担当者に感謝を伝えたい場合など、例外的に贈り物を用意することもあります。
そのような場合の相場は、1,000円から2,000円程度が目安です。高価すぎる品物はかえって相手に気を遣わせてしまうため、気持ちを添える程度の控えめな品を選ぶのがポイントです。
個包装の焼き菓子や日持ちのするお菓子、地元の特産品など、受け取る側が負担に感じないシンプルなものが好印象です。また、訪問先の規模や人数に合わせることも大切です。
小規模な企業であれば少人数でも分けやすいお菓子を、大人数の部署であれば配りやすい焼き菓子やティーバッグなどを選ぶと良いでしょう。
華やかさよりも誠実さや気遣いが感じられる品を選ぶことで、「丁寧で感じの良い人だな」という印象を残すことができます。値段よりも、感謝の気持ちがしっかり伝わるかどうかが一番大切です。
会社訪問にふさわしい手土産を選ぶポイント

会社訪問で手土産を用意する機会は少ないものの、お世話になった企業やインターン先へ感謝を伝える際は、その選び方が印象を左右します。
ここでは、訪問先で好印象を与えるための手土産選びのポイントを6つ紹介します。
- 日持ちする食品を選ぶ
- 個包装で配りやすい手土産を選ぶ
- 相手企業の業種や社員数に合わせた内容にする
- 高すぎず安すぎない価格帯を意識する
- 季節感や地域性を取り入れる
- のし・包装・紙袋など見た目の印象も大切にする
①日持ちする食品を選ぶ
会社訪問の手土産として最も多く選ばれるのは食品ですが、その中でも「日持ちするもの」を選ぶことが基本です。生菓子や要冷蔵の商品は、すぐに配れない場合に困らせてしまうおそれがあります。
焼き菓子やクッキー、せんべいなどの常温保存ができるものを選ぶと安心です。特に社員数の多い企業では、すぐに配られず数日間保管されることもあるため、賞味期限が長いものを選ぶと良いでしょう。
相手に余計な手間をかけさせない心配りこそが、ビジネスマナーの基本です。手土産は「贈る側の気持ち」だけでなく、「受け取る側の立場」を考えて選んでください。
②個包装で配りやすい手土産を選ぶ
会社訪問でどうしても手土産を渡す場合は、個包装のお菓子など配りやすいものを選ぶと好印象です。
複数の社員が同席する場面でも分けやすく、衛生的で受け取る側の負担になりにくいのがポイントです。また、包装が丁寧で統一感のあるお菓子は清潔感があり、気配りのある印象を与えます。
一人で食べきれるサイズのものを選ぶと、「さりげなく心遣いができる人」と感じてもらいやすいでしょう。人数分より少し多めに用意しておくと、想定外の場面でもスマートに対応できます。
あくまで「感謝を伝えるための小さな心づかい」として、控えめな品を選ぶことが大切です。
③相手企業の業種や社員数に合わせた内容にする
手土産を選ぶ際は、相手企業の業種や雰囲気に合った品を選ぶことが大切です。たとえば、金融機関や行政など落ち着いた雰囲気の企業には、上品な包装や味わいの和菓子が喜ばれます。
一方で、広告やITなど自由な社風の企業であれば、話題性のあるスイーツや地域限定のお菓子など、親しみを感じてもらえる品もよいでしょう。
社員数が多い企業では、配りやすい個包装の詰め合わせが便利です。少人数の企業を訪問する場合は、質の良い小箱入りのものを選ぶと気持ちが伝わりやすいでしょう。
事前に相手の雰囲気や職場の雰囲気を調べておくと、より印象に残るお礼になります。
④高すぎず安すぎない価格帯を意識する
手土産の価格相場は、1,000円〜2,000円程度が目安です。高すぎる品は相手に気を遣わせてしまい、安すぎるものはかえって気持ちが伝わりにくくなることがあります。
大切なのは、金額よりも「感謝の気持ちがきちんと伝わるかどうか」です。
たとえば、インターン先やお世話になった社員の方へお礼を伝える場合は、1,000円前後の控えめな焼き菓子や小箱入りの和菓子などを選ぶと良いでしょう。
高価なものを選ぶ必要はなく、心を込めて選んだことが伝われば十分です。
あくまで「お世話になったことへのお礼」として渡すことを意識すれば、金額よりも気持ちのこもった対応が印象に残ります。
⑤季節感や地域性を取り入れる
季節を感じられる手土産は、心のこもった印象を与えやすく、会話のきっかけにもなります。
お世話になった企業やインターン先などに感謝を伝える際は、季節感のある品を選ぶとより丁寧な印象になります。
春は桜を使ったお菓子、夏は涼しげなゼリーや水ようかん、秋は栗や芋の焼き菓子、冬はチョコレートなど、季節に合った品を選ぶと喜ばれるでしょう。
また、地元の名産品を選ぶのもおすすめです。地域らしさが伝わり、自然と話題が広がります。
こうした工夫は、「お礼の気持ちを込めて選んだ」という誠実な姿勢を感じさせ、相手に好印象を残すきっかけになります。
⑥のし・包装・紙袋など見た目の印象も大切にする
どんなに中身が良くても、包装が雑だと印象が下がってしまうことがあります。手土産は中身だけでなく、見た目の清潔感や丁寧さも大切なポイントです。
お世話になった企業やインターン先へお礼を伝える場合は、シンプルで落ち着いた包装を選ぶと好印象です。
「御礼」などののし紙を添えると丁寧ですが、就活生の場合は必ずしも必要ではありません。相手に堅苦しさを与えないよう、控えめで清潔感のあるデザインを意識しましょう。
渡す際は、紙袋から一度出して両手で丁寧に差し出すのが基本です。細かい部分まで心を配ることで、感謝の気持ちと誠実さが自然に伝わります。
取引先・シーン別のおすすめの手土産

会社訪問で手土産を用意する場合は、訪問の目的や季節、そして相手との関係性によってふさわしい品が変わります。
ここでは、お世話になった企業やインターン先などへお礼を伝える際におすすめの手土産をシーン別に紹介します。相手に気を遣わせず、感謝の気持ちが伝わる品選びの参考にしてください。
- インターン終了後やお礼訪問の場合
- OB・OG訪問の場合
- 暑い季節の場合
- 寒い季節の場合
①インターン終了後やお礼訪問の場合
インターンでお世話になった企業を訪問する際は、形式ばった贈り物ではなく、「お世話になりました」という気持ちを伝えるための控えめな手土産が適しています。
長期間関わった担当者や部署へのお礼であれば、1,000円〜2,000円程度の個包装のお菓子がちょうど良いでしょう。
たとえば、焼き菓子の詰め合わせや和菓子の小箱など、日持ちして配りやすいものが安心です。訪問当日は、包装や袋の色味を落ち着いたトーンで統一すると、誠実で丁寧な印象になります。
気をつけたいのは、高価すぎるものを選ばないことです。たとえ良い意味で選んだつもりでも、「学生なのに気を遣わせてしまう」と感じさせてしまう場合があります。
「少しだけ特別なお礼を伝える」程度に抑えるのがポイントです。
おすすめの手土産例:
| ・個包装のクッキーやフィナンシェなどの焼き菓子 ・小分けになった最中やどら焼きなどの和菓子 ・地元の名産を使った日持ちするスイーツ |
②OB・OG訪問の場合
OB・OG訪問は、現場の生の話を聞かせてもらう貴重な機会です。訪問先の先輩に感謝を伝えたい場合は、500円〜1,000円程度の気軽なお菓子を選ぶのが適しています。
高価なものを用意すると、かえって恐縮されてしまうため避けましょう。たとえば、ちょっとした焼き菓子やコーヒー・紅茶のセットなど、カフェ感覚で楽しめるようなものがぴったりです。
持ち運びやすく、かさばらないものを選ぶとスマートに見えます。渡すタイミングは、話を聞き終わったあとに「今日は本当にありがとうございました」と一言添えて手渡すのが自然です。
無理に形式を整えるよりも、素直な感謝の気持ちを伝えることが一番のマナーです。
おすすめの手土産例:
| ・小包装のバターサンドやマドレーヌ ・上品な包装の最中や羊羹などの伝統和菓子 ・白や淡い色の清潔感あるパッケージ菓子 |
③暑い季節の場合
夏場の会社訪問では、見た目にも涼しげな手土産が好まれます。ゼリーや水羊羹などの冷菓が定番で、さっぱりとした味わいが人気です。
ただし、冷蔵品を選ぶ場合は移動時間や保存方法にも注意が必要。常温保存できるタイプなら安心して持ち運べます。
包装やリボンに季節感を取り入れることで、さりげない気配りを印象づけることができます。特に暑い季節は食品の劣化が早いため、日持ちの良さや衛生面にも気を配りましょう。
涼を感じる手土産は、相手の気持ちを和らげる効果もあります。
おすすめの手土産例:
| ・フルーツゼリーや水羊羹などの冷菓 ・レモン風味の焼き菓子やサブレ ・常温保存できる涼感スイーツ(抹茶・柚子など) |
④寒い季節の場合
寒い季節の会社訪問では、温かみを感じられる手土産が喜ばれます。焼き菓子やチョコレート、ほうじ茶やコーヒーなど、ほっと一息つける品が最適です。
価格は2,000円前後を目安に、落ち着いたデザインのものを選ぶと良いでしょう。冬は年末年始の挨拶回りも多く、のし紙や包装のマナーにも気をつける必要があります。
クリスマスや新年の季節限定スイーツなども人気があるでしょう。寒い季節ならではの温もりを感じる贈り物で、相手への感謝と心遣いをしっかり伝えてください。
おすすめの手土産例:
| ・チョコレートや焼き菓子の詰め合わせ ・ほうじ茶、コーヒーなどのドリンクギフト ・冬季限定のスイーツ(ショコラ・ナッツ系など) |
会社訪問時の手土産の正しい渡し方

会社訪問の際に手土産を渡すタイミングや方法を誤ると、せっかくの気遣いが十分に伝わらないことがあります。正しいマナーを身につけることで、相手に誠実な印象を与えられるでしょう。
ここでは、ビジネスシーンで手土産をスマートに渡すための基本を紹介します。
- 挨拶を済ませたあとに渡す
- 会議室では着席前に渡す
- 受付ではなく担当者本人へ渡す
- 丁寧な言葉遣いで渡す
- 会食や外出先では自然なタイミングで渡す
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
①挨拶と名刺交換を終えてから渡す
訪問時にいきなり手土産を差し出すのは避けましょう。まずは「本日はお時間をいただきありがとうございます」と感謝の言葉を伝えたうえで、落ち着いたタイミングで渡すのが基本です。
タイミングとしては、最初の挨拶後や会話の区切りの良いところで、「ささやかですが、お礼の気持ちです」と一言添えると好印象です。
あくまで“感謝の気持ちを形にしたもの”という姿勢を忘れずに。落ち着いた声のトーンと丁寧な所作を心がけてください。
②着席する前に渡す
会議室などで着席を勧められた場合は、座る前に渡すのが基本です。椅子に座ってから渡すと、慌ただしく見えてしまうため、立った状態で渡すほうが丁寧に見えます。
その際、紙袋に入れたまま渡すのではなく、一度袋から出して両手で差し出すのがマナーです。
紙袋は持ち帰るつもりで折りたたむか、自分の足元に置いておきましょう。
学生でも「相手に負担をかけないスマートな渡し方」を意識するだけで、印象が大きく変わります。
③受付ではなく担当者本人へ渡す
手土産は必ず担当者本人へ直接渡すのがマナーです。受付で渡してしまうと「誰宛か分からない」「意図が伝わらない」といった誤解を招くおそれがあります。
もし担当者が不在の場合は、受付の方に「○○様へお渡しいただけますか」と伝え、名刺を添えてお願いしましょう。ただし、重要な面談や商談の場合は、次回の訪問時に直接渡すほうが丁寧です。
手土産は単なる贈り物ではなく、信頼関係を築くための大切な手段でしょう。
④丁寧な言葉遣いで渡す
手土産を渡す際の言葉遣いにも注意が必要です。「つまらないものですが」といった表現は、相手によっては失礼に聞こえる場合があります。
代わりに「ささやかですが感謝の気持ちです」「お気に召していただければ幸いです」といった柔らかい言葉を使うと良いでしょう。
また、相手の時間を取らないように簡潔に伝えるのもポイントです。言葉だけでなく、表情や声のトーンにも気を配りましょう。丁寧で温かみのある対応が、印象をより良くしてくれます。
会社訪問時の手土産に関する注意点

会社訪問の際に渡す手土産は、せっかくの感謝の気持ちも、マナーを誤ると意図が正しく伝わらないことがあります。ここでは、訪問時に気をつけたい5つの注意点を紹介します。
- 会社名入りや宣伝目的の品は避ける
- 日持ちしない食品や生ものは選ばない
- 相手先の近隣で購入したものは避ける
- のしは「紅白蝶結び」で「御挨拶」と表書きする
- 天候や持ち運びの状態に配慮する
①会社名入りや宣伝目的の品は避ける
会社訪問で手土産を用意する場合は、宣伝や営業を思わせるような品は避けるのがマナーです。
他社や大学のロゴ入りグッズなど、宣伝目的と受け取られるものは、せっかくの気持ちが誤解されてしまうおそれがあります。
特に就職活動中の学生の場合、企業との関係はまだこれから築いていく段階です。そのため、相手に気を遣わせたり、意図を勘ぐられたりしないよう控えめな品を選ぶことが大切です。
たとえば、季節感のあるお菓子やシンプルで上品な包装の食品など、誰が受け取っても気持ちよく感じられるものがおすすめです。
広告的な要素を含めず、純粋に「お世話になりました」という気持ちを形にすることで、自然と好印象を残すことができます。
②日持ちしない食品や生ものは選ばない
会社訪問時の手土産は、相手が保管しやすく、安心して受け取れるものを選ぶことが大切です。日持ちしない食品や生ものは、相手の負担になる可能性があります。
忙しい企業ではすぐに開封されないことも多く、保管場所や賞味期限に気を使わせてしまうかもしれません。おすすめは、常温で保存でき、数日から1週間程度は日持ちする焼き菓子や個包装のお菓子です。
中でもフィナンシェやクッキー、羊羹などは定番で、部署単位でも配りやすい利点があります。
冷蔵・冷凍品を持参する場合は、保冷材や移動時間を考慮し、品質が保たれる状態で渡せるよう工夫してください。渡す相手が受け取りやすいかどうかを常に意識することが、細やかな気配りにつながります。
③相手先の近隣で購入したものは避ける
会社訪問の際は、相手企業の近くで購入した手土産を避けるのが基本。理由は、相手が「なぜ地元のものをわざわざ持ってきたのか」と違和感を抱く可能性があるからです。
とくにその地域で有名な銘菓を現地で買って渡すと、「手抜き」と受け取られるおそれもあります。そのため、訪問側の地域にちなんだ特産品や、話題性のあるスイーツなどを選ぶのが望ましいでしょう。
遠方から訪問する場合は、「お土産として持参しました」と伝えると、自然な印象になります。
相手にとって珍しいものや、包装が上品で高級感のある品を選ぶことで、「わざわざ選んでくれた」という誠意が伝わりやすくなります。
相手への思いやりが伝わるよう、選ぶ過程にも心を配ることが大切です。
④のしは「紅白蝶結び」で「御挨拶」と表書きする
会社訪問時の手土産には、のしをつけるのが一般的です。格式を重んじる企業ほど、細かなマナーにも目を向けています。
「紅白蝶結び」は何度でも繰り返してよい慶事に使われるため、初訪問や商談など、あらゆるビジネスシーンに適しています。表書きは「御挨拶」と記すのが最も無難で、誰に対しても好印象を与えるでしょう。
また、すでに取引のある相手への訪問であれば「御礼」でも問題ありません。のしは外のしを選び、手渡しの際は相手に文字が正面を向くように差し出すのが基本です。
こうした所作ひとつで、礼儀正しさや細やかな配慮が伝わります。たとえ小さな贈り物でも、丁寧な扱いができる人は、信頼できる人物として印象に残りやすいでしょう。
⑤天候や持ち運びの状態に配慮する
手土産を準備する際は、当日の天候や持ち運び環境にも注意を払いましょう。夏場の高温多湿な時期には、チョコレートや生菓子など、溶けやすい品は避けるのが賢明です。
反対に冬場は、乾燥による品質劣化を防ぐため、しっかりと密閉された包装を選ぶと安心。雨の日は、紙袋が濡れないよう防水素材の袋を用意するか、別のカバーをかける配慮が必要です。
長距離の移動がある場合は、軽くて壊れにくい商品を選ぶと持ち運びの負担を減らせます。さらに、相手に渡す前までの保管場所や温度管理にも気をつけてください。
最後まで丁寧に扱う姿勢が、誠実さや信頼感を自然と伝えます。ビジネスの場では、こうした「見えない気遣い」こそが印象を左右する重要なポイントです。
ビジネスの印象を左右する会社訪問時の手土産の心得

会社訪問での手土産は、感謝や敬意を伝えるための小さな心づかいです。
就活生の場合は基本的に不要ですが、どうしてもお礼を伝えたい場面では、控えめで誠実な品を選ぶことで気持ちを丁寧に表すことができます。
大切なのは、品物そのものよりも相手を思いやる気持ちが伝わるかどうかです。心のこもった対応こそが、今後につながる良い印象を残すでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。