内定もらえない原因と特徴|今から始める改善策
就活を頑張っているのに「なぜか内定が出ない」と焦りや不安を感じる人は少なくありません。
周囲の友人が次々と決まっていく中、自分だけ取り残されたような気持ちになることもあるでしょう。しかし、内定がもらえない原因は決してひとつではなく、改善できるポイントが必ずあります。
本記事では、内定がもらえない人に共通する特徴や就活の落とし穴を整理し、改善のための具体的な方法を解説します。
今からでもできる工夫を取り入れれば、就活を前向きに進められるはずです。
面接前に役立つアイテム集
- 1実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
- 2志望動機テンプレシート
- あなたの志望動機を面接官に響く形へブラッシュアップできるテンプレート
- 3自己PRテンプレシート
- 面接官視点で伝わる構成に落とし込み、自分の強みをブレずに説明できるようにします。
- 4適職診断
- 60秒で診断!あなたが面接を受けるべき職種がわかる
- 5面接前に差がつく!ビジネスマナーBOOK
- 面接前に一度確認しておきたい、減点されやすいマナーポイントをまとめています。
内定もらえない人が増えている現状
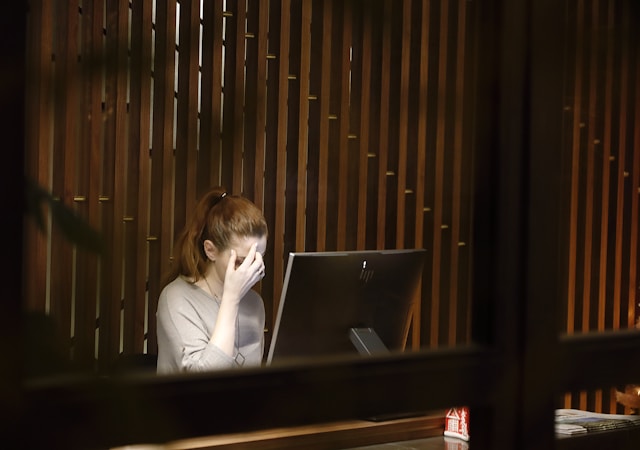
就活市場では、年々「内定がもらえない」という悩みを抱える学生が増えています。特に、大学3年生から4年生にかけて、就活のスケジュールが早期化・多様化していることが背景にあるようです。
ここでは「無い内定(NNT)」と呼ばれる現状や、内定がもらえない人の割合、さらに時期ごとの内定率の変化までを整理し、現状を正しく理解できるように解説します。
- 無い内定(NNT)と呼ばれる背景と実態
- 内定がもらえない人の割合
- 就活時期ごとの内定率の変化と傾向
①無い内定(NNT)と呼ばれる背景と実態
無い内定(NNT)とは、大学4年生や卒業直前になっても、企業から1つも内定をもらえていない状態を指します。
ここ数年、就活の早期化や採用方法の多様化が進むなかで、対策が後手に回ってしまう学生が増え、この言葉が広く使われるようになりました。
背景には、企業の採用スケジュールの変化や学生の情報不足・準備不足が重なっていることが多いです。
早期選考やインターンシップを経由しないと、選考に進めない場合もあるため、従来型のスケジュールだけでは内定に届かないことも珍しくありません。
ただ、現実を知って適切な情報収集や対策を行えば、今からでも十分に巻き返しが可能でしょう。焦らずに、状況を客観視することが第一歩です。
②内定がもらえない人の割合
毎年の調査では、卒業直前でも一定数の学生が「内定がない」状態であることが示されています。
特に、3年生後半から4年生前半にかけては、内定取得率が半分程度にとどまることも多く、焦りを感じる学生が増えているようです。
しかし統計上、夏以降に内定を得る学生も多く、時期の差があるだけで実力不足ではないケースも少なくありません。
採用活動が通年化しつつある現在では、従来の「春までに内定が出ないと危ない」という考え方は、必ずしも当てはまらないでしょう。
自分のペースで着実に準備と行動を続けることで、内定獲得のチャンスはまだ十分にあります。
③就活時期ごとの内定率の変化と傾向
就活の内定率は、時期によって大きく変動します。春先から夏にかけては、早期内定組が目立ちますが、秋以降にも追加採用や第二新卒採用を行う企業は多くあるでしょう。
特に、中小企業やベンチャー企業は秋冬採用に力を入れているケースが増えており、これを知らずに「もう遅い」と諦めてしまうのは大きな機会損失です。
一方で、早期に内定が出ないからといって焦って条件を妥協することも、長期的なキャリア形成にはマイナスになりかねません。
大切なのは、内定率の季節変動を理解し、自分の行動計画を立て直すことです。適切な時期に戦略を見直せば、まだまだ十分なチャンスがあるでしょう。
内定がもらえない主な原因

就活で内定がもらえない学生には、いくつか共通する理由があります。ここでは、特に多い4つのポイントに注目し、それぞれの問題点と改善のヒントを紹介しています。
- 自己分析不足のため
- 業界・企業研究が足りていないため
- 面接対策が行き届いていないため
- 応募企業数が少ないため
①自己分析不足のため
自己分析が不十分だと、自分の強みや価値観を整理できず、志望動機や自己PRが浅くなりがちです。
その結果、企業に「なぜうちで働きたいのか」が十分に伝わらず、内定に結びつかないことが多くなります。
改善するためには、自分史やモチベーショングラフを活用して過去の経験や行動を整理し、強みや弱みをしっかり言語化することが大切です。
さらに、具体的なエピソードを交えて説明できると説得力が増し、採用担当者の印象にも強く残りやすくなります。
自己分析を深めるほど、自分に合った企業や職種も見えやすくなり、選考でのアピールも自然に効果的になるでしょう。
「自己分析のやり方がよくわからない……」「やってみたけどうまく行かない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己分析シートを活用してみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強み、就活の軸が簡単に見つかりますよ。
②業界・企業研究が足りていないため
業界や企業研究が不足していると、選考時に質問にうまく答えられなかったり、志望動機が表面的で説得力に欠けたりすることがあります。
その結果、企業から「熱意や本気度が低い」と受け取られ、内定のチャンスを逃すことにつながりかねません。
改善のためには、企業の公式サイトやIR情報、就活サイトの口コミ、OB・OG訪問などを活用し、多角的に情報を収集することが重要です。
「なぜその業界なのか」「なぜこの企業なのか」を自分の言葉で説明できるようになると、採用担当者に熱意や適性をしっかりアピールでき、内定獲得の可能性が高まります。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
③面接対策が行き届いていないため
面接対策が不十分だと、緊張しすぎてしまったり、質問に的外れな回答をしてしまったりすることがあります。また、表情や声のトーンが暗く、第一印象が悪くなることも少なくありません。
改善するには、模擬面接や自己録画を活用して、自分の話し方や態度を客観的にチェックすることが効果的です。
さらに、よくある質問への回答を事前に用意し、結論から話す練習をすると説得力が増し、自然な受け答えができるようになります。
選考の場数を踏むことで緊張も和らぎ、自信がつくと同時に、内定につながる印象を残しやすくなるでしょう。
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
④応募企業数が少ないため
応募する企業の数が少ないと、単純にチャンスが減り、内定獲得までに時間がかかる可能性が高くなります。
特に、大手企業ばかりに絞ってしまうと、倍率が非常に高くなり、結果的に内定率が下がることも少なくありません。改善策としては、業界や企業の幅を広げて、柔軟に応募することが重要です。
まずは、興味のある業界を複数挙げ、その中から応募先を増やすなど戦略的に動きましょう。
応募先が増えることで、選考経験が自然に積めるため、自己PRや面接対応も段階的に改善され、より内定に近づきやすくなります。
内定がもらえない人の共通点とは

就活で内定がもらえない人には、いくつかの共通した特徴があります。ここでは、特に多い6つのポイントを取り上げ、それぞれの問題点と改善のヒントを紹介しましょう。
- 応募企業の選び方に偏りがある
- 応募書類や適性検査の対策が足りていない
- 自己PRや志望動機が弱い
- マナーや身だしなみが整っていない
- 面接時の態度や印象が悪い
- マインドや考え方に問題がある
①応募企業の選び方に偏りがある
応募企業の選び方に偏りがあると、自分に合う企業や隠れた優良企業に出会う機会を逃してしまいます。特に、大手企業ばかりに応募する場合、倍率が高くなり内定獲得が難しくなるでしょう。
改善するには、業界や規模にこだわらず幅広く企業研究を行い、選択肢を増やしてください。多様な企業に触れることで視野が広がり、自分に合った企業を見つけやすくなります。
②応募書類や適性検査の対策が足りていない
応募書類や適性検査の準備が不十分だと、書類選考で落ちる確率が高まります。誤字脱字や形式的な志望動機は、企業から「熱意が低い」と見られやすいです。
改善するには、応募前に第三者にチェックしてもらう、企業ごとに内容をカスタマイズする、WebテストやSPIなどの形式を把握しておくことが有効でしょう。
こうした対策を積み重ねることで、選考通過率が上がります。
③自己PRや志望動機が弱い
自己PRや志望動機が弱いと、自分の魅力や企業とのマッチ度が伝わらず、内定獲得につながりません。
改善するには、自分の経験を整理して強みを明確にし、企業が求める人物像に沿った内容に書き直してください。
エピソードを具体的に示し、結果だけでなく過程や学びも伝えると説得力が増します。志望動機も企業の特徴を取り入れて、オリジナル性を持たせましょう。
④マナーや身だしなみが整っていない
マナーや身だしなみが整っていないと、第一印象でマイナス評価を受ける可能性があります。清潔感のある服装や髪型、正しい敬語の使用は基本です。
改善するには、面接前に友人やキャリアセンターなどで確認してもらい、相手に不快感を与えない身だしなみを意識してください。こうした配慮が「社会人としての準備ができている」という印象につながります。
⑤面接時の態度や印象が悪い
面接で態度や印象が悪いと、どれだけ内容が良くても評価が下がる可能性があります。緊張しすぎて表情が硬くなる、声が小さい、相手の話を遮るなどは避けてください。
改善するには、模擬面接や録画で自分の話し方や表情を確認し、自然な笑顔と落ち着いたトーンを意識しましょう。事前準備と練習を重ねることで、自信がつき印象も良くなります。
⑥マインドや考え方に問題がある
就活への取り組み方や考え方に問題があると、行動が消極的になったり、失敗を引きずったりしがちです。
「どうせ無理だ」と決めつける気持ちは選考にも表れやすく、企業にネガティブな印象を与えることがあります。
改善するには、目標を小さく設定して達成感を積み重ねることや、信頼できる人に相談して新しい視点を得てください。前向きな姿勢は選考全体の雰囲気にも、良い影響を与えるでしょう。
企業選びが原因で内定もらえない人の特徴

就活で内定がもらえない理由のひとつに、企業選びの偏りがあります。ここでは、特に多い5つの特徴を挙げ、それぞれの問題点と改善のヒントを紹介しましょう。
- 企業選びの軸が曖昧である
- 自分に合わない企業ばかり選んでいる
- 大手企業ばかりを狙っている
- 勤務地や待遇など条件面だけで企業を選んでいる
- 将来のキャリアプランを考えずに企業を選んでいる
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
①企業選びの軸が曖昧である
企業選びの軸が曖昧だと、自分に合う企業を見極めにくくなり、志望動機も浅くなりがちです。
その結果、選考時に「なぜこの企業なのか」という質問にうまく答えられず、採用担当者に本気度や熱意が十分に伝わらなくなります。
改善策としては、仕事内容や社風、価値観、働く環境など、自分が重視するポイントを明確にし、優先順位をつけることが大切です。
軸がしっかり定まることで企業研究も深まり、説得力のある志望動機や自己PRを作りやすくなります。
また、軸を明確にすることで選考中の意思決定もスムーズになり、応募先企業の質を高められるでしょう。
②自分に合わない企業ばかり選んでいる
自分に合わない企業ばかりを選ぶと、書類選考や面接の段階でミスマッチが起こり、内定を得るのが難しくなります。
改善するためには、企業の理念や社風、仕事内容をしっかり調べ、自分の強みや価値観と照らし合わせて合致しているかを確認することが重要です。
さらに、OB・OG訪問やインターンシップを活用すると、実際の職場の雰囲気や業務内容を体感でき、より現実的な視点でミスマッチを減らせるでしょう。
自分に合う企業を選ぶことで、面接での自信や熱意も自然に伝わり、内定率向上につながります。
③大手企業ばかりを狙っている
大手企業だけに絞って応募すると、倍率が非常に高くなり、内定獲得が難しくなる傾向があります。さらに、選考期間が長くなり、他のチャンスを逃してしまうリスクが生じることも。
改善策としては、中小企業や成長企業、ベンチャー企業なども視野に入れて応募先を増やすことが有効です。
応募先の選択肢を広げることで、自分に合った企業を見つけやすくなり、選考経験も積めるため、自己PRや面接対応のスキルも自然に向上します。幅広く応募することで、内定への可能性が大きく高まるでしょう。
④勤務地や待遇など条件面だけで企業を選んでいる
勤務地や給与、福利厚生など条件面だけで企業を選ぶと、仕事内容や社風との相性を見落としやすくなります。その結果、志望動機が弱くなり、選考で熱意を伝えにくくなることがあるかもしれません。
改善策としては、条件面だけでなく、仕事内容、キャリア形成の可能性、企業文化や社風など多角的に判断することが重要です。
バランスの取れた視点で企業を選ぶことで、自分に合った企業に出会いやすくなり、選考でのアピール力も高まります。
⑤将来のキャリアプランを考えずに企業を選んでいる
将来のキャリアプランを考えずに企業を選ぶと、入社後のミスマッチや短期離職につながりやすく、選考時にも一貫性のない印象を与えてしまいます。
改善するには、5年後・10年後にどんな仕事をしていたいかを具体的にイメージし、それに合った企業を探すことが大切です。
キャリアビジョンが明確になると、志望動機に説得力が増し、企業からの評価も高まります。また、自分の成長プランを意識して企業を選ぶことで、入社後のモチベーション維持にもつながるでしょう。
応募書類・適性検査が原因で内定もらえない人の特徴

就活で内定がもらえない理由のひとつに、応募書類や適性検査の準備不足があります。ここでは、特に多い5つの特徴を挙げ、それぞれの問題点と改善のヒントを紹介しています。
- 応募書類に誤字脱字が多い
- 企業ごとに書類をカスタマイズしていない
- WebテストやSPIなどの形式を把握していない
- 適性検査の対策をしていない
- 提出前に第三者のチェックを受けていない
①応募書類に誤字脱字が多い
応募書類に誤字脱字が多いと、採用担当者に「準備不足」や「注意力が低い」という印象を与えてしまい、書類選考で不利になりやすくなります。
小さなミスでも印象は大きく変わるため、提出前には必ず複数回読み直し、文章チェックツールや校正ソフトも活用してください。
また、声に出して読むことで、文章の不自然さや言い回しの違和感にも気づけます。
さらに、日頃から文章を書く習慣をつけると、誤字脱字の防止にもつながり、より丁寧で説得力のある書類を作れるようになるでしょう。
正確で丁寧な応募書類は、それだけで選考担当者の印象を大きく改善し、他の応募者との差別化にもなります。
②企業ごとに書類をカスタマイズしていない
同じ内容の書類を複数企業に使い回すと、志望動機や自己PRが表面的に見え、採用担当者に熱意が伝わらない可能性が高まります。
改善策としては、企業ごとの特徴や募集職種、業界の動向などを踏まえて、内容を柔軟に調整することが重要です。特に志望動機には、その企業独自の魅力や自分の経験との関連性を盛り込むと効果的でしょう。
たとえば、企業の最近の取り組みやプロジェクトを自分の経験と結びつけるだけでも、オリジナリティのある文章になります。少しの工夫で書類の説得力は大きく変わり、選考通過率も向上するでしょう。
③WebテストやSPIなどの形式を把握していない
WebテストやSPIの形式を把握していないと、時間配分や出題傾向に対応できず、十分な点数を取れないことがあります。
対策として、まず参考書や過去問題集、模擬テストを活用して問題形式や出題傾向に慣れることが重要です。事前に形式を知るだけでも、当日の心構えができ、試験中に焦ることが少なくなります。
また、出題傾向を把握することで、自分の苦手分野を効率的に補強でき、スピードと正確さを意識した練習が可能になるでしょう。
形式を理解し、繰り返し練習しておくことは、点数を安定させるだけでなく、自信を持って試験に臨むためにも非常に有効です。
④適性検査の対策をしていない
適性検査を軽視すると、思わぬ失点につながり、選考に進めない可能性が高まります。よく出題される分野や問題パターンを分析し、問題集や模擬テストで繰り返し練習することが大切です。
特に、スピードと正確さを意識したトレーニングを行うと、得点力を安定させやすくなります。
さらに、適性検査は職種適性や性格傾向を見られることも多いため、自分の特性を理解しながら回答する練習をすると、結果の安定性や自己理解にもつながるでしょう。
適性検査をきちんと準備しておくことで、選考全体の印象も良くなり、次の面接に進むチャンスを高められます。
⑤提出前に第三者のチェックを受けていない
自分だけで書類を確認すると、誤字や構成の甘さに気づけないことがあります。改善策としては、友人やキャリアセンターのスタッフ、就活のプロに第三者チェックをお願いすることが重要です。
第三者からの客観的な指摘を受けることで、自分では見落としていたミスや文章のわかりにくさに気づき、書類の完成度を格段に高められます。
さらに、他人に内容を説明することで、自分の志望動機や自己PRの整理にもつながり、自信を持って提出できるようになるでしょう。
第三者の目を取り入れるだけで、書類の質が大きく向上し、選考通過率を高める効果があります。
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
自己PRが原因で内定もらえない人の特徴

自己PRは、就活で自分を売り込む重要な場面ですが、内容や伝え方に問題があると内定に届かないことがあります。ここでは特に多い5つの特徴と、その改善のヒントを紹介しましょう。
- エピソードに具体性や信頼性がない
- 企業が求める人物像と自己PRが合っていない
- 自分の強みを把握できていない
- 内容が他人と差別化できていない
- 自己PRが長すぎる・短すぎるなど適切な時間で伝えられていない
「自己PRの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己PRテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みを効果的にアピールする自己PRが作成できますよ。
①エピソードに具体性や信頼性がない
自己PRのエピソードが抽象的すぎると、面接官にあなたの行動や成果がしっかり伝わらず、印象が薄くなってしまいます。
「頑張りました」「努力しました」といった漠然とした表現だけでは、どの程度の成果を出したのかが伝わりません。改善策として、数字や実績、具体的な状況を盛り込むことが重要です。
たとえば「部活で頑張りました」というよりも、「部活の試合でキャプテンとしてチームをまとめ、勝率を前年より20%上げました」と表現すると、行動と結果が明確になり、説得力がぐっと増します。
また、困難な状況をどう乗り越えたか、工夫した方法を加えると、あなたの行動力や問題解決力も伝わりやすくなるでしょう。具体性と信頼性を意識することで、自己PRの印象は大きく向上します。
②企業が求める人物像と自己PRが合っていない
企業が重視する能力や人物像に合わない自己PRをすると、せっかくのアピールも半減してしまいます。企業が求める人物像は、採用ページや会社説明会、OB・OG訪問などから把握することが可能です。
その情報をもとに、自分の経験や強みをどのように企業の求める要素に結びつけるかを整理してください。
たとえば、チームワークを重視する企業には、自分がチームで成果を出した経験や、協調性を発揮したエピソードを中心に話すと効果的です。
企業の価値観やカルチャーと自己PRの内容が合致していると、面接官に「この人は当社で活躍できそうだ」と感じてもらいやすくなります。
方向性をしっかり合わせることが、内定につながる自己PR作りの第一歩です。
③自分の強みを把握できていない
自分の強みが明確でないと、自己PRはどうしても漠然とした内容になり、面接官に伝わりにくくなります。
まずは、過去の経験や周囲からのフィードバックを振り返り、自分の行動や成果のパターンを整理してみましょう。自己分析ツールや、キャリアセンターの相談を活用することも有効です。
自分の強みがはっきりすると、話す内容が一貫し、面接中も自信を持って話せるようになります。
さらに、強みを活かしてどのように企業に貢献できるかまで結びつけると、より説得力のある自己PRになるでしょう。自己理解を深めることは、自己PR作りの土台となる非常に重要なステップです。
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
④内容が他人と差別化できていない
他の就活生と同じような自己PRでは、面接官の印象に残りにくく、埋もれてしまいます。差別化のポイントは、ユニークな経験や数字などの具体性を取り入れることです。
成果だけでなく、その過程でどのような工夫をしたか、どんな困難をどう乗り越えたかを示すと、独自性がより際立ちます。
たとえば「チームで成果を出しました」だけでなく、「チーム内の意見対立を調整し、目標達成に向けてプロジェクトの進行方法を改善しました」と伝えると、問題解決力やリーダーシップもアピールできるでしょう。
他の応募者との差別化を意識することで、面接官に強く印象づけられる自己PRになります。
⑤自己PRが長すぎる・短すぎるなど適切な時間で伝えられていない
自己PRが長すぎると要点がぼやけてしまい、短すぎると魅力や成果が十分に伝わりません。面接での自己PRは、1分前後を目安に要点をまとめることが理想です。
練習の際は、録音や動画を使って自分の話すスピードや内容の密度を確認し、改善点を見つけて調整しましょう。
また、面接官に伝わりやすい構成(結論→具体例→成果→学び)を意識すると、短時間でも効果的にアピールできます。
適切な長さで的確に話すことで、面接官に好印象を与えやすくなり、内定につながる自己PRになるでしょう。
マナー・身だしなみが原因で内定もらえない人の特徴

面接や説明会では、第一印象が大きなポイントになります。どれだけ自己PRや志望動機が良くても、マナーや身だしなみに問題があると評価が下がってしまうでしょう。
ここでは、特に多い5つの特徴と改善のヒントを紹介します。
- 言葉遣いが正しくできていない
- 社会人マナーができていない
- 清潔感がない
- 服装や髪型が場に合っていない
- 表情や態度が硬すぎて印象が悪い
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
①言葉遣いが正しくできていない
敬語や言い回しが適切でないと、面接官から基本的なコミュニケーション能力や、社会人としての常識を疑われることがあります。
「です・ます」調の基本的な敬語ができていないだけで、印象は大きく下がるものです。改善策として、日常生活の中から正しい敬語や、丁寧な言い回しを意識して使うことが重要になるでしょう。
模擬面接や友人との練習でも、実際に声に出して使うことで自然に身につきます。
また、尊敬語・謙譲語の使い分けや、適切なタイミングでの言い換えも練習しておくと、面接時にスムーズに話せるようになるでしょう。
言葉遣いの正確さは、面接官に信頼感と落ち着きのある印象を与える大きな要素です。
②社会人マナーができていない
遅刻や提出期限の遅れ、メールの返信が遅いなど、社会人としての基本的なマナーができていないと、信頼を失う原因になります。
たとえ面接での受け答えが完璧でも、そうした小さな不手際が印象に残ってしまうことがあるかもしれません。
改善のためには、小さな約束でも必ず守ること、報連相(報告・連絡・相談)を徹底することが大切です。また、面接前の到着時間や準備を余裕をもって行う習慣をつけると、自然と印象も向上します。
日頃からの行動習慣が、面接や説明会での評価にも直結することを意識してください。
③清潔感がない
髪や服装が乱れている、靴が汚れているなど、清潔感が欠けていると、評価が下がる要因になります。
高価なスーツやブランド品は必要ありませんが、シワのない服、整った髪型、手入れされた靴や爪など、基本的な身だしなみを整えることが重要です。
清潔感は単なる外見の問題ではなく、自己管理能力や仕事への意欲を示す指標としても見られます。また、面接官は無意識のうちに清潔感を判断しており、第一印象の合否に大きく影響しています。
④服装や髪型が場に合っていない
場違いな服装や過度に派手な髪色は、ビジネスの場では不適切と見なされることがあります。説明会や面接では、シンプルで清潔感のある服装を心がけることが大切です。
TPO(Time, Place, Occasion)を考えた服装選びは、相手への配慮ができる人だと印象づける効果もあります。
そのため、面接ではジャケットを着用し、派手すぎないアクセサリーや髪型に整えることで、ビジネス環境での適応力を示せるでしょう。
服装や髪型は第一印象に直結するため、社会人としての常識や場の空気を意識して選ぶことが重要です。
⑤表情や態度が硬すぎて印象が悪い
表情が固い、姿勢が悪い、声が小さいなど、態度から暗い印象を与えると、面接官に不安を抱かせてしまいます。改善策として、自然な笑顔を意識し、ハキハキとした声で話すことが効果的です。
面接前に鏡や動画で自分の姿を確認すると、姿勢や表情、話すスピードの改善点を客観的に把握できます。
また、少し緊張していても、軽く深呼吸して落ち着くことで、柔らかい表情や自然な態度が作りやすくなるでしょう。
表情や態度は、面接官にあなたの人柄やコミュニケーション力を伝える重要な要素であり、第一印象の良し悪しに大きく影響します。
面接が原因で内定もらえない人の特徴

面接は、書類選考以上に人柄やコミュニケーション力が重視される場です。ここで評価を落としてしまうと、どれだけ書類が優秀でも内定にはつながりません。
ここでは、特に多く見られる5つの特徴と改善のヒントを紹介します。
- 面接で過度に緊張してしまう
- 質問に的外れな答えをしている
- 面接質問対策をしていない
- 表情や声が暗く印象が悪い
- 心がこもっていない受け答えをしている
①面接で過度に緊張してしまう
過度な緊張は声を小さくし、言葉が出にくくなるだけでなく、頭が真っ白になり冷静な対応ができなくなる原因になります。
緊張を完全になくすことは難しいですが、練習を重ねて面接の場数を踏むことで、自然と落ち着きを得られるようになるでしょう。
特に、模擬面接を何度も行うことで、質問への反応速度や話すリズムを身につけられます。また、面接前に深呼吸や腹式呼吸を取り入れると、心拍数を落ち着かせ、声に力を込めやすくなるでしょう。
軽いストレッチや体をほぐすことも、緊張緩和につながります。緊張は誰でもするものですが、準備や呼吸法でコントロールできることを覚えておきましょう。
②質問に的外れな答えをしている
面接官の質問の意図を正確にくみ取れず、的外れな答えをしてしまうと、理解力や論理的思考力が不足していると見なされてしまいます。
そのため日ごろから、質問の背景や意図を考える癖をつけることが重要です。質問を一度自分の言葉で復唱してから答えることで、相手の意図を確認しつつ、回答の精度を上げられます。
また、答えを結論から先に述べる「PREP法(Point→Reason→Example→Point)」を活用すると、簡潔かつ論理的に伝えられるため、面接官に理解されやすくなるでしょう。
質問に対する的確な答えは、理解力や思考力のアピールにもつながります。
③面接質問対策をしていない
準備不足のまま面接に臨むと、予想外の質問に対応できず、印象を大きく下げてしまいます。
自己分析を深め、自分の強みや過去の経験を整理することはもちろん、応募企業の事業内容や求める人物像を把握し、質問への回答例を準備しておくことが大切です。
過去の面接例や、他の就活生の体験談も参考になります。さらに、模擬面接を活用して第三者に質問してもらうことで、自分では気づきにくい回答の甘さや態度の癖を確認でき、改善点を具体的に把握できるでしょう。
事前対策を徹底することで、当日の落ち着きや自信に直結します。
「面接になぜか受からない…」「内定を早く取りたい…」と悩んでいる場合は、誰でも簡単に面接の振り返りができる、面接振り返りシートを無料ダウンロードしてみましょう!自分の課題が分かるだけでなく、実際に先輩就活生がどう課題を乗り越えたかも紹介していますよ。
④表情や声が暗く印象が悪い
笑顔がなく声が小さいと、自信がない、やる気が薄いと面接官に受け取られやすくなります。改善策として、話す内容だけでなく、表情や声のトーンも意識しましょう。
鏡の前で話す練習や、録音・動画で自分の話し方を確認することで、声の大きさや表情の硬さを客観的に把握できるでしょう。
オンライン面接の場合は、カメラ目線や照明にも注意し、明るい印象を意識するとより好印象になります。表情や声のトーンは、面接官にポジティブな印象を与え、質問への理解度や人柄を伝える重要な要素です。
⑤心がこもっていない受け答えをしている
話の内容が正しくても、熱意や誠意が伝わらなければ、面接官に「本気度が低い」と感じられ、説得力が大きく落ちます。
改善策として、志望理由や自己PRの根拠を自分で深く理解し、具体的な体験談やエピソードを交えて話すことが重要です。たとえば、数字や成果、工夫した点などを盛り込むと、より説得力が増します。
また、気持ちを込めて話すことで、自然な声のトーンや表情にも反映され、面接官に強い印象を与えられるでしょう。
心がこもった受け答えは、単なる言葉の説明ではなく、あなた自身の熱意や人柄を伝える最大のチャンスです。
内定がもらえない人の就活マインドセット

就活で結果が出ないと、自信をなくして動きが鈍ることがあります。しかし、考え方や行動を見直せば、状況を変えるきっかけをつかめるでしょう。
ここでは、就活マインドセットを整える5つのポイントを紹介します。
- 自己分析の見直しをする
- 企業研究・業界研究をやり直す
- 内定もらえない状況を前向きに乗り越える
- 周囲に相談して客観的なアドバイスを得る
- 小さな成功体験を積み重ねて自己効力感を高める
①自己分析の見直しをする
自己分析が浅いままだと、自分の強みや価値観を正確に把握できず、志望動機や自己PRが弱くなってしまいます。
過去の経験を深く掘り下げ、どんな環境で自分が力を発揮できるか、どんな場面でモチベーションが高まるかを確認してください。
また、友人や先輩、先生からのフィードバックを参考にすることで、自分では気づけなかった強みを見つけられます。
再確認することで新しい発見があり、面接やESで自信を持って話せるようになりますし、自分の方向性に迷いがある場合でも軌道修正がしやすくなるでしょう。
自分1人での自己分析に不安がある方は、就活のプロと一緒に自己分析をしてみませんか?あなたらしい長所や強みが見つかり、就活がより楽になりますよ。
②企業研究・業界研究をやり直す
視野が狭いと、受ける企業が偏り、内定のチャンスを逃してしまうことがあります。改めて、業界全体の動きや各企業の特徴、将来性を調べることで、自分に合った企業を見つけやすくなるでしょう。
複数の業界を比較検討することで、志望理由がより具体的になり、面接官に説得力を持って伝えることが可能です。
また、業界ニュースや企業の最新情報を把握しておくと、面接での質問への対応力や会話力も向上します。こうした準備は、応募先企業の選定にも自信を持たせ、戦略的に就活を進める助けになるでしょう。
③内定もらえない状況を前向きに乗り越える
選考で結果が出ないと、焦りや不安から行動が止まりがちです。しかし、失敗をただ悔やむのではなく、そこから学び、次の選考で改善していく姿勢が非常に重要になります。
たとえば、面接でうまく話せなかったポイントを振り返り、次回はどのように改善できるか具体策を考えるだけでも成長につながるでしょう。
前向きな気持ちを持つことで、新しい挑戦にも積極的に踏み出せるようになり、精神的な安定感も増します。
また、困難に直面しても学びとして捉えることで、就活全体を通して着実にスキルや自信を積み上げられるでしょう。
④周囲に相談して客観的なアドバイスを得る
一人で悩み続けるより、先輩、キャリアセンター、就活エージェントなどに相談することで、自分では気づけなかった改善点や強みを見つけられます。
第三者の視点を取り入れることで、自己分析や志望動機の精度が上がるだけでなく、面接練習の際には具体的な改善点ももらいやすくなるでしょう。
また、相談する過程で自分の考えを言語化する練習にもなり、話す力や自己理解も同時に向上します。信頼できる人に意見を聞くことで、心理的な支えも得られ、就活の孤独感を減らす効果も期待できるでしょう。
⑤小さな成功体験を積み重ねて自己効力感を高める
大きな目標ばかりを追いかけると、失敗したときに挫折感が強くなります。そのため、小さな行動目標を設定し、少しずつ達成していくことが自己効力感の向上につながるでしょう。
たとえば、1日1社の企業研究を行う、模擬面接を受ける、ESを1本完成させるなど、達成可能なタスクを積み重ねてください。
小さな成功体験の積み重ねは、自信や前向きな気持ちを育て、次の挑戦への原動力になります。また、自己効力感が高まることで、緊張や不安も軽減され、面接や説明会で自然体の自分を出せるようになるでしょう。
内定がもらえない人がやりがちなNG行動
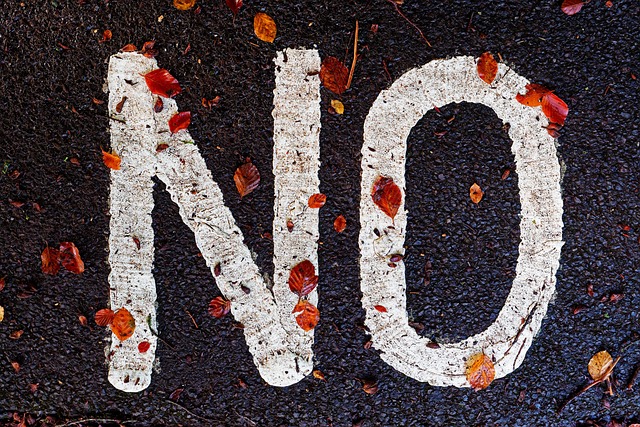
就活が長引く人には、共通するNG行動パターンがあります。これらを見直すことで改善策を見つけやすくなり、内定獲得に一歩近づけるでしょう。ここでは、代表的なNG行動を4つ紹介します。
- 不特定多数に応募する
- 準備不足のまま面接に挑む
- 就活を一人だけで進める
- 自己分析や企業研究を怠る
①不特定多数に応募する
数をこなせば内定が取れると考え、とにかく大量に応募する人がいます。しかし、自分に合わない企業まで無計画に応募すると、志望動機が弱まり、面接で熱意をうまく伝えられなくなります。
さらに、応募書類の作成や面接準備に時間を取られすぎると、一社一社に十分な時間をかけられず、全体の印象が薄くなってしまうことも。
そのため、応募先は自分の軸や価値観に合った企業に絞り込み、数より質を重視することが内定獲得の近道です。絞り込むことで、面接時に具体的な志望理由や自分の強みを熱意をもって伝えやすくなります。
②準備不足のまま面接に挑む
面接前に、自己PRや想定質問への回答を準備していないと、当日緊張して言葉に詰まったり、話がまとまらなくなったりします。
企業理解が浅いと、質問に的確に答えられず、印象を大きく下げる原因になることも。
そのため、面接前には企業の特徴や業界動向、求める人物像をしっかり調べ、模擬面接や友人との練習で回答の流れや表現を確認しておくことが重要です。
また、事前準備を丁寧に行うことで自信がつき、緊張をコントロールしやすくなる効果もあります。
③就活を一人だけで進める
孤独な就活は視野が狭くなり、間違った方向に進んでしまう危険があります。自分の考えだけで進めると、改善すべき点に気づかず、同じ失敗を繰り返すことも少なくありません。
キャリアセンターや就活エージェント、先輩や友人などに相談することで、自分では気づけなかった改善点や新しい視点を得られます。
さらに、相談を通じて模擬面接やES添削をしてもらうことで、具体的な改善策が見つかり、選考通過率も高まるでしょう。
周囲の力をうまく借りながら就活を進めることが、結果につながりやすくなるポイントです。
④自己分析や企業研究を怠る
自己分析や企業研究が浅いと、自分に合う企業が見つからず、志望理由も表面的になってしまいます。その結果、面接官に響かない答えになり、他の候補者との差が生まれてしまうのでしょう。
過去の経験や成功体験、失敗体験を丁寧に振り返り、自分の強みや価値観を整理することが大切です。
さらに、企業のビジョンや文化、事業内容を深く理解することで、志望理由を具体的に話せるようになり、面接官に「この学生は本当に企業を理解している」と思わせられます。
自己分析と企業研究の徹底は、内定獲得に直結する重要なステップです。
内定もらえないときの具体的な改善方法

就活が長引くと自信を失いやすいですが、行動や環境を変えることで内定につながる可能性が高まります。ここでは、実践的で効果的な改善方法を5つ紹介しましょう。
- 就活エージェントやキャリアセンターを活用する
- 応募企業数や業界の幅を増やしてチャンスを広げる
- メンタルケアや生活習慣を見直して就活に集中できる状態を整える
- インターンシップや短期就業体験に参加して実績を積む
- 資格取得やスキルアップに取り組み自分の強みを増やす
①就活エージェントやキャリアセンターを活用する
一人で就活を続けると視野が狭まり、誤った方向に進む危険があります。就活エージェントや大学のキャリアセンターを活用すれば、自分の強みや課題を客観的に把握しやすくなるでしょう。
また、非公開求人や企業の内部情報、選考のコツなども得られるため、より効率的な就活を進められます。
模擬面接やES添削などのサポートを受けることで、自分では気づきにくい改善点を発見でき、面接本番での自信にもつながるでしょう。
さらに、第三者の意見を取り入れることで、自己分析の精度も上がり、志望動機や自己PRの説得力が格段に高まります。
面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?
一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。
②応募企業数や業界の幅を増やしてチャンスを広げる
特定の業界や企業だけに絞りすぎると、内定獲得が難しくなる場合があります。自分の興味や適性を再確認し、まだ検討していなかった業界や職種にも視野を広げて応募してみてください。
新しい業界に挑戦することで、思わぬ適性や可能性に気づくことがあります。また、複数の業界を比較することで志望理由が深まり、面接での説得力も増すでしょう。
応募先を広げる際は、自分の強みや価値観と照らし合わせることで、闇雲に応募せず、効率よくチャンスを増やせます。
③メンタルケアや生活習慣を見直して就活に集中できる状態を整える
長期の就活はストレスが蓄積しやすく、集中力や判断力の低下を招くことがあります。規則正しい生活、十分な睡眠、適度な運動を意識するだけでも、心身のパフォーマンスは大きく向上するでしょう。
また、瞑想や軽いストレッチなどでリフレッシュする習慣を取り入れると、面接時の緊張や不安を和らげる効果もあります。
精神的な余裕を持つことで、面接官に自然な笑顔やハキハキした受け答えを見せられるため、自信を持って選考に臨めるようになるでしょう。
④インターンシップや短期就業体験に参加して実績を積む
実際の業務を体験することで、自分の適性や働くイメージをより具体的に理解できます。インターンシップは、単に職務経験を積むだけでなく、自己PRや志望動機に説得力を加える材料にもなるでしょう。
実務経験や業界理解がある学生は、面接官から見て即戦力としての評価も高くなります。
また、インターンで得た経験をESや面接で具体的に話すことで、「この学生は業界や職種に対する理解が深い」と印象づけられるため、内定に直結する可能性が高まるでしょう。
⑤資格取得やスキルアップに取り組み自分の強みを増やす
選考中に資格やスキルを持っていることは、他の候補者との差別化につながります。
短期間で取得できる資格やオンライン講座、プログラミングや語学など、自分のキャリアに直結するスキルを磨くことは非常に有効です。
また、新しい知識やスキルを得ることで自信も向上し、面接や自己PRでより積極的にアピールできるようになります。
資格やスキルは、企業に「努力して能力を高め続ける人材」という印象を与えるため、就活全体の印象を底上げする重要な要素です。
内定がもらえないことに関するよくある質問と回答

就活を進める中で、「なぜ自分だけ内定が出ないのか」と悩むことは珍しくありません。ここでは、大学3〜4年生の就活生が抱きやすい疑問に答え、不安を減らすためのポイントを解説します。
- 高学歴でも内定もらえないことはある?
- 内定がもらえないまま卒業した場合どうなる?
- 内定がもらえない状態から挽回する方法はある?
①高学歴でも内定もらえないことはある?
高学歴であっても、必ず内定がもらえるわけではありません。企業は学歴だけで判断せず、コミュニケーション能力やチームでの協働力、人柄、仕事への意欲なども重視します。
そのため、学歴に頼りすぎると、自分の強みや具体的な経験を面接で十分に伝えられず、評価が下がることもあるでしょう。
たとえば、勉強はできてもチームでの取り組みや問題解決の経験を話せない場合、面接官には「現場で活かせる力が不明確」と映ってしまうことも。
高学歴でも、自己分析をしっかり行い、自分の経験や考えを具体的に整理して話せる準備をすることが、内定獲得の大きなカギになるでしょう。
②内定がもらえないまま卒業した場合どうなる?
内定がないまま卒業しても、就職の道が完全に閉ざされるわけではありません。既卒採用や第二新卒枠、契約社員や派遣社員としての経験を積むなど、社会に出てから挑戦できる選択肢はいくつもあります。
ただし、新卒枠と比べると応募できる企業の幅が狭まる場合があるため、早めの行動が重要です。
アルバイトやインターン、ボランティアなどで経験やスキルを積んでおくと、履歴書や面接で具体的にアピールできる材料となります。
また、卒業後も自己分析や企業研究を続けておくことで、再挑戦の際にスムーズに応募できる準備が整うでしょう。
③内定がもらえない状態から挽回する方法はある?
内定が取れない状況は、就活の方法を見直す良い機会でもあります。まずは、キャリアセンターや就活エージェントに相談し、第三者の意見やフィードバックを取り入れることが有効です。
また、応募企業の幅を広げる、業界や職種を見直す、面接練習やES添削を重ねるなど、小さな改善を積み重ねることで状況を好転させやすくなるでしょう。
さらに、自己PRや志望動機に説得力を持たせるため、過去の経験を具体的に整理し、面接で自信を持って話せる準備をすることも大切です。焦らず、一つひとつ丁寧に取り組む姿勢が、内定獲得への近道となります。
内定もらえない人が陥りやすい課題と改善のポイント

内定がもらえない状況は、企業選びや応募書類、面接対応、マナー、自己PRなど、さまざまな要因が絡み合っています。
本記事では、現状の把握と原因の分析、共通する特徴、マインドセットや改善方法まで幅広く解説しました。多くの場合、自己分析不足や企業研究の甘さ、面接対策の不十分さが内定獲得を妨げます。
したがって、まずは自分の就活スタイルを客観的に見直し、応募書類や面接の質を高めることが重要でしょう。
さらに、就活エージェントやキャリアセンターを活用して第三者の意見を取り入れたり、インターンやスキルアップで実績を増やすことも効果的です。
これらを実践することで、内定がもらえない状況から挽回しやすくなります。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













