座談会の質問例75選!好印象を残す聞き方とNG質問を徹底解説
就活イベントでよく行われる座談会は、採用担当者や若手社員と直接話せる貴重な場です。しかし、いざ質問するとなると何を聞けばよいか迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、就活生が実際に使える座談会質問例75選を紹介します。基本的なルールから避けるべきNG質問、聞き方の工夫まで徹底解説。
これを読めば、座談会で自信を持って質問し、社員に好印象を残す準備が整います。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
就活における座談会とは?

就活における座談会とは、企業と学生がざっくばらんに話をする場であり、説明会や面接とは異なる特徴を持ちます。
多くの場合、現場社員や若手社員が参加し、学生が気になる働き方や社風について直接質問できるのが魅力でしょう。
たとえば、入社後の研修内容やキャリア形成の実例などは、社員の生の声からしか得られません。一方で、座談会を単なる情報収集の場と考えてしまうと、効果を十分に発揮できないこともあります。
座談会は情報を得るだけでなく、自分をさりげなくアピールする場でもあるので、事前に企業研究を進めたうえで具体的な質問を用意し、積極的に参加することが大切です。
そうすれば、他の学生との差別化につながり、選考過程でも有利に働く可能性が高まるでしょう。
座談会で質問するメリット

就活生が企業の座談会に参加するとき、質問をすることには大きな意味があります。単に疑問を解消するだけでなく、企業理解や自己アピールにもつながるからです。
ここでは、質問することで得られる代表的なメリットを整理しました。下記の小見出しごとに詳しく解説していきます。
- 採用担当者に覚えてもらえる可能性がある
- 企業の社風や雰囲気を知ることができる
- 社員のリアルな体験談を聞ける
- 志望度の高さをアピールできる
- 他の学生の質問から学べる
①採用担当者に覚えてもらえる可能性がある
座談会で積極的に質問することは、採用担当者にあなたの存在を強く印象づける有効な手段。
なぜなら、数多くの学生が参加する中で黙っていると埋もれてしまいますが、質問を通じて前向きな姿勢を見せられるからです。
具体的な質問や自分の考えを踏まえた問いかけをすれば「この学生はきちんと準備をしている」と感じてもらえるでしょう。
その結果、後日の面接やエントリーシートで名前を見たときに思い出してもらえる可能性が高まります。一方で、自己アピールばかりを狙った不自然な質問は逆効果になりかねません。
自然に企業への関心を示す質問を心がけると、座談会での発言は「選考への布石」として働きやすく、積極的に行動するほど有利に働くはずです。
②企業の社風や雰囲気を知ることができる
座談会に参加する大きな意義は、企業の社風や雰囲気を直接感じ取れる点です。ホームページや求人票だけでは、働き方や人間関係の空気感まで理解するのは難しいでしょう。
しかし、社員の話し方ややり取りから、その企業がどのような文化を大切にしているかを知ることができます。
たとえば、終始フランクに話しているなら風通しのよさを示すサインかもしれませんし、質問に丁寧に答えてくれる様子からは教育体制やサポートの手厚さが伝わるでしょう。
就活生にとって、こうした情報は入社後のミスマッチを防ぐ判断材料になり、感じ取った雰囲気を志望動機に盛り込めば、より説得力のあるアピールが可能です。
したがって、座談会は情報収集と自己分析の両方に役立つ貴重な機会といえるでしょう。
③社員のリアルな体験談を聞ける
座談会の大きな魅力は、社員のリアルな体験談を直接聞けることです。
企業説明会では制度や数字の説明が中心ですが、座談会では入社の決め手や失敗談、仕事のやりがいなど、実際に働く人の声がそのまま届きます。
また、同じ業界でも企業によって働き方や評価基準は異なるため、複数の社員の話を比較することで、自分に合うかどうかを判断できるでしょう。
さらに、体験談を通じて感じた疑問をその場で掘り下げれば、より深い情報を得られるだけでなく、関心の高さを示すことにもつながります。
社員の生の声を聞ける座談会は、就活に必要な情報を集め、進路を決めるうえで欠かせない場といえますよ。
④志望度の高さをアピールできる
質問をすること自体が、志望度の高さを伝える有効な手段です。企業に対して「積極的に知ろうとしている学生」という印象を与えられるからです。
特に、企業研究を踏まえて生まれた疑問を投げかければ「この学生は真剣に考えている」と感じてもらえるでしょう。反対に、調べれば分かるような基本的な質問ばかりでは準備不足と思われてしまいます。
志望度を効果的に示すには、自分のキャリアや将来像と企業の特徴を結び付けた質問が効果的です。
たとえば「御社の研修制度が将来的にどのようなスキルにつながるか」といった聞き方なら、志望意欲を自然に伝えられるでしょう。結果的に、座談会での質問は選考時の評価にも好影響を与えるはずですよ。
⑤他の学生の質問から学べる
座談会は自分が質問する場であると同時に、他の学生から学ぶ場でもあります。他人の視点を通じて、自分では思い付かなかった疑問や気付きを得られるからです。
たとえば「働き方の柔軟性」や「海外事業の展望」といった自分が調べていなかったテーマに触れると、企業理解の幅が広がるでしょう。
また、他の学生の質問に対する社員の回答を記録しておけば、面接やエントリーシートで活用できる貴重な情報源になります。
同じテーマでも質問の切り口が異なることで「自分ならどう聞くか」と考えるきっかけにもなるはずです。
座談会では自分の発言だけでなく、周囲のやり取りにも注意を向けることが成長や情報収集につながるので、他人の質問を自分の学びに変える姿勢を持ってください。
座談会で質問する際の基本的なルール

座談会は社員と直接やりとりできる貴重な場ですが、質問の仕方によって相手に与える印象は大きく変わるのです。
ここでは質問をするときに意識すべき基本的なルールを整理し、就活生が安心して参加できるよう具体的なポイントを紹介します。
- 質問は事前に準備しておく
- 一方的にならず双方向の会話を意識する
- 自分ばかり発言しすぎない
- 簡潔でわかりやすい質問を心がける
- 敬意を持った言葉遣いで質問する
①質問は事前に準備しておく
座談会で良い印象を持たれるには、質問を事前に準備しておくことが欠かせません。準備不足で場当たり的な質問をすると「企業研究をしていないのでは」と思われる可能性があります。
特にホームページに載っている基本情報をそのまま聞くと、熱意が伝わりにくいでしょう。一方で、あらかじめ考えておけば、聞きたいことを整理できるため座談会を有意義にできます。
具体的には、企業研究で感じた疑問や自分の将来像に関連した質問を用意するのが効果的です。
つまり、座談会をただの情報収集に終わらせないためには、質問を準備して臨むことが重要。質問の質が高ければ真剣さが伝わり、自然に好印象につながるでしょう。
②一方的にならず双方向の会話を意識する
座談会は面接とは違い、双方向のやりとりが求められる場です。学生が一方的に質問を続けると、尋問のようになってしまい、相手も答えにくくなります。その結果、得られる情報も限られてしまうでしょう。
効果的に会話を進めるには、社員の答えに共感やリアクションを返し、「その経験は自分のアルバイトにも共通していて参考になります」と一言添えるだけで、自然に話が広がります。
こうしたやりとりは「きちんと聞いている」という印象も与えるのです。さらに双方向を意識すれば、自分の関心を深掘りすることもできます。
答えだけでなく背景や考え方に触れられるため、理解がより深まるでしょう。つまり、座談会での質問は「会話のきっかけ」と考えると成功しやすいのです。
③自分ばかり発言しすぎない
座談会は複数の学生が同席することが多いため、発言のバランスも欠かせません。自分ばかり話すと、他の学生に質問の機会を与えられず、場の雰囲気を悪くする可能性も。
もし質問が重なった場合は「先ほどの内容に関連して」と補足すれば、自然に関心を示せるでしょう。さらに他の学生の質問を聞くことで、自分では気づかなかった疑問が解消されることもあります。
そのため座談会では「話す」と「聞く」をうまく両立させることが大切です。要するに、発言の量を調整することが有意義な座談会につながる基本マナーといえるでしょう。
④簡潔でわかりやすい質問を心がける
社員に質問するときは、できるだけ簡潔にまとめることが必要です。前置きが長すぎたり複雑な言い方をしたりすると、聞き手が混乱して答えがずれる可能性があります。
効果的に伝えるには、要点を押さえて短く言うことが大切。「入社後の研修制度について教えてください」とシンプルに聞けば相手も答えやすいでしょう。
その上で「特に若手社員に印象的な取り組みはありますか」と補足すれば、より具体的な情報を得られます。また、話を短くすることで他の学生の時間も確保できますよ。
結果として座談会全体がスムーズに進み、参加者全員にとって充実した時間になるはずです。「短く、わかりやすく」を意識することが、質問の質を高める基本でしょう。
⑤敬意を持った言葉遣いで質問する
座談会はフランクに進む場合が多いものの、最低限の敬意を持った言葉遣いは欠かせません。くだけすぎた話し方は礼儀を欠いている印象を与える可能性があります。
特に初対面の社員には、丁寧語を基本としましょう。その上で、相手の雰囲気に少し合わせると、自然で柔らかい会話になります。
「なるほど、そういう考え方もあるのですね」といった表現は、敬意と親しみの両方を伝えられるでしょう。敬語を正しく使うことは、社会人としての基本的な姿勢を示す行為でもあります。
社員に安心感を与えると同時に、自分自身の印象も良くなるため、敬意を持った言葉遣いは座談会で信頼を得る第一歩なのです。
「ビジネスマナーできた気になっていない?」
就活で意外と見られているのが、言葉遣いや挨拶、メールの書き方といった「ビジネスマナー」。自分ではできていると思っていても、間違っていたり、そもそもマナーを知らず、印象が下がっているケースが多いです。
ビジネスマナーに不安がある場合は、これだけ見ればビジネスマナーが網羅できる「ビジネスマナー攻略BOOK」を受け取って、サクッと確認しておきましょう。
座談会で聞くべき質問例

就活の場である座談会は、企業理解を深めるだけでなく、印象を残す貴重な機会でもあります。
適切な質問を選ぶことで、自分に合う企業かどうかを判断できるだけでなく、志望意欲を自然に示すことも可能です。ここでは、座談会で効果的に活用できる質問例をまとめました。
- 仕事内容や業務内容
- 社風や職場の雰囲気
- 求める人物像や評価されるスキル
- 社員が就活時に感じたこと
- 入社を決めた理由やキャリアパス
①仕事内容や業務内容
座談会で基本かつ重要な質問が、仕事内容や業務内容に関するもの。なぜなら、企業説明会や求人票では表面的な情報しか分からず、実際の業務や1日の流れまでは把握しにくいからです。
具体的な質問をすれば「自分がこの環境で働けるか」をイメージしやすくなります。こうした質問は仕事内容を知るだけでなく、成長のチャンスや働く姿勢についても理解を深められるでしょう。
表面的な理解にとどまることは就活の落とし穴ですが、座談会で掘り下げて聞くことでそのリスクを防げます。結果として、自分に合うかどうかを判断する材料を得られるはずです。
| ・入社1年目の社員はどんな業務を担当しますか ・1日のスケジュールの流れを教えてください ・新人が成長を実感しやすい業務は何ですか |
②社風や職場の雰囲気
企業の社風や職場の雰囲気は、求人票や公式サイトだけでは伝わりにくい情報です。座談会で質問することで、社員のリアルな声から雰囲気を感じ取れるでしょう。
大切なのは、自分が馴染めるかどうかを見極める視点です。働きやすいと感じる環境は人によって違います。にぎやかな職場を好む人もいれば、落ち着いた環境を望む人もいるでしょう。
自分の価値観に合うかを知るために、社風に関する質問は欠かせません。座談会を通じて企業文化を理解すれば、入社後のギャップを減らせるはずです。
| ・チームで働くときの雰囲気はどうですか ・若手社員が意見を出しやすい環境でしょうか ・職場でコミュニケーションを取る際に大切にしていることは何ですか |
③求める人物像や評価されるスキル
座談会では、企業が求める人物像や評価するスキルを聞くことも有益ですよ。理由は、自分の強みが企業に合っているかどうかを確認できるからです。
さらに、その情報を自己PRや志望動機に盛り込めば、説得力あるアピールができるでしょう。逆に、自分の価値観やスキルと合わないと気付く場合もありますが、それはミスマッチを避ける意味で大切。
座談会で得た情報を活用すれば、就活の軸づくりに役立つはずです。
| ・活躍している社員に共通する特徴はありますか ・評価されやすいスキルにはどのようなものがありますか ・新人に期待される行動や姿勢は何でしょうか |
④社員が就活時に感じたこと
社員が就活生だったころに感じたことを尋ねるのも効果的と言えます。なぜなら、自分と同じ立場を経験した人の視点からリアルなアドバイスを得られるからです。
こうしたやり取りは不安を和らげるだけでなく、自分の行動の参考にもなります。さらに、社員が企業を選んだ基準や決断の理由を聞けば、自分が進路を決める際の指針にもなるはずです。
ネットや説明資料だけでは分からない等身大の声を聞ける点で、座談会ならではの価値があります。迷いを感じるときこそ、このような質問で道しるべを得てください。
| ・就活中にどんなことで悩みましたか ・内定を得るまでに工夫したことはありますか ・企業を選ぶ際に重視したポイントは何ですか |
⑤入社を決めた理由やキャリアパス
最後に役立つのが、社員が入社を決めた理由や入社後のキャリアパスに関する質問です。「なぜこの企業を選んだのか」を知ることで、志望動機を深める手がかりになるからです。
企業が提供している成長の場を理解できます。さらに、実際のキャリアステップを知ることで、自分の将来像を描きやすくなるでしょう。
志望動機を作る際には「なぜこの会社なのか」を明確にすることが不可欠であり、そのヒントを得られるのが、この質問の大きな強み。
座談会で情報を集めれば、選考の場で説得力ある説明ができるようになるはずです。
| ・数ある企業の中で御社を選んだ決め手は何ですか ・入社後に挑戦できるキャリアパスの事例を教えてください ・長期的に活躍している社員のキャリア形成にはどんな特徴がありますか |
座談会で避けるべきNGな質問例
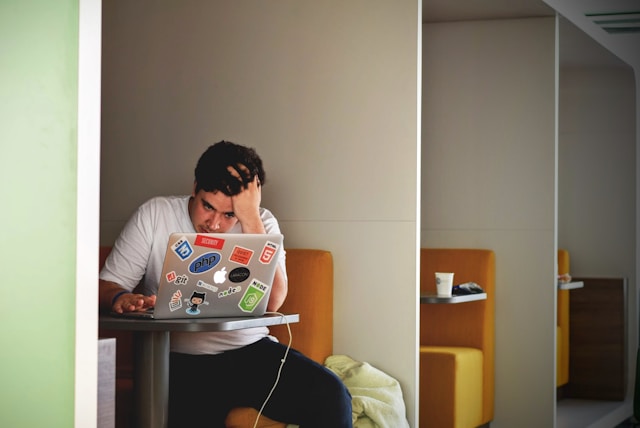
座談会は社員と直接交流できる場ですが、質問内容によっては印象を損ねる場合があります。良い評価を得るためには、聞かないほうがいい質問を把握することが大切です。
ここでは具体的な例と理由を整理しました。
- 待遇・福利厚生
- 給与・残業時間
- 社員のプライベート
- 批判的・ネガティブな内容
- 説明会やHPでわかる内容
①待遇・福利厚生
待遇や福利厚生は気になるテーマですが、座談会で直接聞いてしまうと「条件面にしか関心がない」と思われる恐れがあります。
とくに選考の序盤では熱意や理解度を重視されるため、質問の仕方には注意が必要です。それでも気になる場合は表現を変えてみてください。
「社員が長く働き続けられる理由は何だと思いますか」と聞けば、制度やサポートに関する情報を自然に引き出せます。前向きな形に工夫すれば印象を損なわずに知りたい内容を聞けるでしょう。
結論として、待遇や福利厚生は座談会で直接触れるより、選考が進んだ段階や公式資料で確認したほうが安心です。
- 福利厚生の詳細はいくらですか
- 有給休暇の取得率はどのくらいですか
- 住宅手当はありますか
②給与・残業時間
給与や残業時間も重要な関心事ですが、座談会で尋ねるのは避けたほうがいいでしょう。「働きやすさより条件を重視しているのでは」と誤解され、評価に影響する可能性があるためです。
ただし、働き方に関心を持つこと自体は問題ありません。質問を工夫すれば、相手も答えやすいでしょう。
「繁忙期はどのようにチームで対応していますか」と尋ねれば、働き方やサポート体制を具体的に知ることができます。
要するに、給与や残業時間は座談会で直接聞かず、人事や資料から確認するのが適切です。
| ・初任給はいくらですか ・残業は何時間ありますか ・ボーナスの金額を教えてください |
③社員のプライベート
社員の休日や趣味といったプライベートを聞くのは避けるべきです。軽い気持ちで聞いたつもりでも、相手にとって答えにくい場合があります。
就活はビジネスの場であるため、過度に個人的なことを尋ねるのはマナー違反と受け取られかねません。
ただし、生活と仕事のバランスに関心がある場合は、「仕事と生活の両立で意識していることはありますか」と聞けば、相手に負担をかけずに参考になる情報を得られるでしょう。
つまり、プライベートではなく働き方の工夫に焦点を当てれば、安心して話を聞けます。
| ・休日は何をしていますか ・趣味は何ですか ・家族構成を教えてください |
④批判的・ネガティブな内容
批判的な質問や否定的な言い方は相手を不快にさせやすいです。「離職率が高いと聞きましたが本当ですか」といった表現は挑発的に受け取られかねません。
座談会は信頼関係を築く場なので、ネガティブな切り口は避けたほうがいいでしょう。同じテーマでも聞き方を変えれば印象は大きく違います。
「社員が長く働き続けられるために工夫している点はありますか」と聞けば、前向きな情報を得ながら雰囲気も保てるでしょう。結論として、批判や否定は控え、前向きな質問に置き換えることが必要です。
| ・離職率は高いですか ・辞める人はどんな理由で辞めていますか ・ブラック企業ではありませんか |
⑤説明会やHPでわかる内容
説明会や企業HPで確認できる内容をそのまま聞くと「準備不足」と判断されるかもしれません。「会社の沿革を教えてください」といった質問は調べれば分かるため、座談会では不適切です。
代わりに、調べた情報を踏まえて深掘りするのがおすすめ。「HPで新規事業に注力していると拝見しましたが、現場での変化はありますか」と聞けば、事前に学んだ上での関心が伝わります。
表面的な質問ではなく、自分なりに調べた上で具体的な疑問を投げかけることが評価につながりますよ。
| ・会社の沿革を教えてください ・事業内容を教えてください ・採用情報の基本条件を説明してください |
聞き方に工夫が必要な質問例

座談会での質問は自由度が高い反面、聞き方によっては誤解を招いたり、印象を下げてしまう場合があります。特にデリケートな内容を扱うときは注意が必要です。
ここでは気を付けながら質問すべきテーマをまとめました。
- 残業や働き方
- 福利厚生や制度
- 研修や教育体制
- 仕事で大変なこと
- 評価や昇進
①残業や働き方
残業や働き方について尋ねるときは、表現の仕方に注意が必要。「残業が少ない会社に入りたい」という受け取り方をされると、働く意欲を疑われる恐れがあるからです。
言い方を工夫すると、働き方全体を理解したい姿勢が伝わりますし、働き方に関する質問は生活に直結するため情報を得ること自体は大切です。
ただし聞き方を間違えると逆効果になるので、前向きさが伝わる質問を意識してください。その結果、自分に合う環境かどうかを冷静に判断できるでしょう。
| ・繁忙期と通常期で勤務時間や業務配分にどんな違いがありますか ・1日のスケジュールの流れと、集中して取り組む時間帯はいつですか ・残業削減や柔軟な働き方に向けた取り組みはありますか |
②福利厚生や制度
福利厚生や制度は多くの就活生が関心を持つテーマですが、直接的すぎる質問は注意が必要です。「住宅手当はいくらですか」と聞くと待遇だけを重視している印象になりやすいでしょう。
言い方を気をつけることで社員の満足度や制度の実際の使われ方を知ることができます。福利厚生を確認するのは重要ですが、お金だけに注目すると逆効果です。
生活や働き方を支える仕組みに関心を示せば、理解を深めながらも好印象を残せるでしょう。
| ・社員から特に支持されている福利厚生や制度はどれですか ・どの制度が日々の業務や成長に役立っていると感じますか ・若手でも利用しやすい制度運用になっていますか |
③研修や教育体制
研修や教育体制は、成長意欲を示すテーマとして非常に有効です。ただし「研修はどのくらいありますか」と形式的に聞くだけでは意欲が伝わりにくいでしょう。
教育制度は企業ごとに差があるため、深掘りすることで比較しやすくなります。聞き方を工夫することで、成長への意欲を自然に伝えられるのも大きな強みです。
| ・新人研修の学びが現場で活きた具体的な場面はありますか ・OJTとOff-JTのバランスはどのようになっていますか ・書籍・資格・eラーニングなど学習支援の活用状況はいかがですか |
④仕事で大変なこと
仕事の大変さを質問するときも注意が必要です。「大変なことばかりですか」と聞いてしまうと、不安ばかりを抱いているように受け取られるかもしれません。
言い方を気をつけることでネガティブな印象を与えずに実情を知ることができます。さらに、社員の体験談を通じて大変さとやりがいの両方を理解できるでしょう。
入社後に直面する可能性のある課題を知ることは準備にもつながります。前向きに質問すれば、企業理解を深めると同時に自分の意欲も示せるはずです。
| ・業務で大変さを感じるのは具体的にどんな場面ですか ・難しい局面を乗り越えるためにチームで工夫していることはありますか ・乗り越えた後に得られるやりがいや学びは何でしょうか |
⑤評価や昇進
評価や昇進に関する質問は慎重に行うべきです。「昇進は何年でできますか」と尋ねると、地位や待遇だけを気にしているように思われかねません。言い方を気をつけることで前向きな姿勢を示せます。
こうした聞き方なら、努力の方向性や成長の道筋を知ることができるでしょう。評価制度を理解することは、キャリアを考えるうえで欠かせません。
聞き方を工夫することで、選考の場でも意欲的な印象を残せるはずです。最終的に、自分のキャリアプランと企業の仕組みが合うかどうかを見極められるでしょう。
| ・評価されやすい行動や成果の基準は何ですか ・昇進につながりやすい経験や役割にはどのようなものがありますか ・目標設定やフィードバックの頻度はどれくらいですか |
座談会で質問がない場合の対処法

座談会では必ず質問をしなければならないわけではありませんが、発言がないまま終わると消極的に見られる恐れがあるでしょう。
ここでは質問が浮かばないときでも積極性を示せる方法を紹介します。
- 事前に準備した質問例を活用する
- 他の学生の質問内容を参考にする
- 感想や学びを伝えて参加姿勢を示す
- 社員へのお礼や感謝を伝える
- 聞き役に徹して積極的にメモを取る
①事前に準備した質問例を活用する
座談会で質問が思い浮かばないときは、事前に用意しておいた質問が助けになります。準備不足だと沈黙してしまいがちですが、いくつか候補をメモしておけば安心できるでしょう。
たとえば「入社後に成長を実感したのはどのような場面ですか」といった質問なら答えやすく、自然に会話が広がりますよね。準備した質問を活用すれば、積極的に参加している姿勢が伝るでしょう。
また、当日の会話に合わせて少し表現を変えるだけでも違和感はありません。事前準備をしていない学生との差が出やすい場面でもあるため、大きな強みとなるでしょう。
つまり、質問が出てこなくて困らないように、あらかじめ準備しておくことが最も効果的な対策です。
②他の学生の質問内容を参考にする
他の学生が先に質問することも多くあります。そのときに内容をよく聞き、関連した質問をすると自然に会話に参加できるでしょう。
「先ほどの質問に関連して、もう少し具体的に伺ってもよろしいですか」と切り出せば違和感なく発言できます。この方法の良さは、自分で新しく考えなくても質問できる点です。
さらに、場全体の理解を深めるきっかけにもなり、社員には「しっかり話を聞いている」という姿勢も伝わるため印象も良くなるでしょう。
自分の質問が思いつかないときは、他の学生の質問を足掛かりにすることが効果的です。
③感想や学びを伝えて参加姿勢を示す
質問がどうしても思い浮かばないときは、感想や学んだことを伝えるのも有効です。「今のお話でキャリアのイメージが明確になりました」と一言添えるだけで、きちんと理解していることを示せます。
感想を伝える行為は社員へのフィードバックにもなるのです。話がどう受け止められたかがわかれば、社員にとっても意味のある時間になるでしょう。
また、自分自身も言葉にすることで理解が深まり整理しやすくなります。つまり、無理に質問を作らなくても、感想を述べるだけで積極性を表現できるのです。
④社員へのお礼や感謝を伝える
質問が浮かばない場合でも、社員への感謝を伝えることで積極性を示せます。「本日は貴重なお話をありがとうございました」と締めくくれば、それだけでも好印象です。
社員は多忙な中で時間を割いてくれているため、その点に触れて感謝を示すと礼儀正しさが伝わります。
「研修制度についての説明がとても参考になりました」と具体的に言葉を添えると、さらに伝わりやすいでしょう。結論として、質問がなくてもお礼を伝えること自体が評価につながる行動です。
⑤聞き役に徹して積極的にメモを取る
質問できないときは、聞き役に徹するのも一つの方法です。ただ黙っているのではなく、しっかりメモを取りながらうなずくことで「積極的に学んでいる」という印象を与えられます。
メモを残せば、後から振り返りやすくなり、志望動機や面接準備にも役立つでしょう。発言できなかったとしても情報を最大限に活かせるのです。
つまり、発言できないときでも受け身にならず、学ぶ姿勢を見せることが大切です。その姿勢そのものが好印象につながるでしょう。
座談会で良い質問をするための事前準備

座談会で良い質問をするには、当日の思いつきではなく事前準備が欠かせません。準備を怠ると印象を悪くしたり、有益な情報を得られなかったりする恐れがあるのです。
ここでは成果を高めるために行っておきたい具体的な準備を紹介します。
- 企業研究をして疑問点を整理する
- 質問リストを事前に作成する
- 質問の意図を簡潔に伝えられるようにする
- 話す練習をしてハキハキと質問できるようにする
- 社員へのリスペクトを持つ姿勢を準備する
①企業研究をして疑問点を整理する
座談会の前に企業研究を行い、疑問点を整理しておくことは必須。基本的な情報を調べていないと、準備不足と見なされる可能性があるからです。
公式サイトや説明会資料、ニュース記事を確認し、仕事内容や事業方針を理解したうえで深掘りしたい部分を明確にしましょう。
例えば「新規事業が社員のキャリア形成にどんな影響を与えていますか」といった質問なら、関心の高さを示せるだけでなく有益な情報も得られます。
反対に、調べれば分かる内容をそのまま聞くと印象を損ねかねません。疑問を整理する準備は、自信を持って発言するための土台作りでもありますよ。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
②質問リストを事前に作成する
その場で質問を考えるのは難しく、緊張すると言葉が出ないこともあります。事前に質問リストを作っておくと安心です。3〜5個ほどの質問を用意すれば、会話の流れに応じて柔軟に選べます。
例えば「入社1年目のやりがい」「チームでの協力体制」「キャリアパスの実例」といったテーマを考えておくと良いでしょう。
さらに、座談会中に他の学生の質問や社員の発言から気づいた点を加えていけば、理解がより深まります。質問リストの準備は意欲を形にする行動でもあり、あるかないかで発言の質が変わるでしょう。
③質問の意図を簡潔に伝えられるようにする
質問の中身だけでなく、伝え方も大事です。前置きが長すぎたり、自分の話ばかりをすると意図が伝わらず相手を困らせてしまいます。
そこで「背景」と「聞きたい点」を短くまとめる練習をしておきましょう。例えば「企業研究の中で○○を知り、さらに△△について伺いたいです」と伝えると、関心の深さと意図の明確さを両立できます。
シンプルに要点を話すことで社員も答えやすく、座談会の雰囲気も良くなるでしょう。意図を整理して伝える準備は、自分の思考を明確にする訓練にもなり、面接やグループディスカッションにも役立ちます。
④話す練習をしてハキハキと質問できるようにする
内容を準備していても、声が小さかったり言葉に詰まったりすると印象は弱くなります。座談会は人前で発言する場なので、自信を持って話せるかどうかが評価に直結することも。
事前に声に出して練習し、はっきりとした口調で話せるようにしておきましょう。鏡の前で練習したり、友人に聞いてもらうのも効果的です。
また、本番では深呼吸をして緊張を和らげてから話すと安心。発言の際に相手の目を見て話すと誠実さも伝わります。こうした準備を重ねれば、本番で落ち着いて堂々と質問できるでしょう。
⑤社員へのリスペクトを持つ姿勢を準備する
座談会では質問の内容だけでなく、態度からも人柄が伝わります。そのため社員へのリスペクトを意識しておくことが大切です。
「お忙しい中ありがとうございます」と一言添えるだけで印象は大きく変わります。さらに答えにうなずいたり、最後に「参考になりました」と伝えれば誠意が伝わるでしょう。
逆に、当然のように質問を投げかけたり答えを否定するような態度は悪印象につながります。敬意を持った姿勢で臨めば、座談会がより有意義な場となり、相手にも好印象を残せるでしょう。
リスペクトを持つ心構えは、就活全般でも役立つ大切な姿勢です。
座談会で質問を成功につなげるために

就活における座談会は、企業理解を深めながら自分を印象づける絶好の場です。特に座談会で質問することは、社風や仕事内容を知れるだけでなく、採用担当者に覚えてもらえる可能性を高めます。
さらに社員の体験談を通じてリアルな情報を得られ、志望度の高さを示すチャンスにもなるでしょう。一方で、待遇や給与などのNG質問は避け、双方向の会話や敬意ある姿勢を意識することが必要です。
事前に質問例を準備し、状況に応じて感想やお礼を伝えれば、発言が少なくても積極性を示せます。
座談会で良い質問ができれば、自分らしさを伝えつつ選考の大きな一歩となるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。











