自己紹介書の書き方と例文集|就活で差がつくコツと注意点を解説
自己紹介書は、自分の強みや人柄を効果的に伝える大切な書類です。だからこそ、書き方を工夫することで合否や印象に大きな差が生まれます。
本記事では、自己紹介書の役割や履歴書との違いから、書くべき定番項目、刺さる内容にするためのコツまで徹底解説します。
さらに、実際に使える【項目別の例文集】も紹介。これを読めば、あなたの自己紹介書を就活で有利に活かせるはずです。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
自己紹介書とは?

就職活動で自己紹介書は、多くの学生が不安を抱く書類の1つです。なぜ必要なのか、履歴書やエントリーシートとの違いを理解していないと、書き方に迷うかもしれません。
ここでは、自己紹介書の役割や、ほかの書類との違いを整理して説明します。
- 自己紹介書が就活で果たす役割
- 自己紹介書と履歴書の違い
- 自己紹介書とエントリーシートの違い
①自己紹介書が就活で果たす役割
自己紹介書は、採用担当者に人柄や価値観を伝える大切な資料です。履歴書のように決まった情報を書くだけではなく、自分の強みや経験を自由にアピールできます。
そのため、面接官が「どんな人物か」を理解する手がかりになり、会話のきっかけにもなるでしょう。たとえば、学生時代に頑張った活動や趣味を紹介すれば、協調性や主体性を示す要素になります。
書く内容に迷うときは、友人と協力した体験や、努力を続けた経験を思い出しましょう。つまり自己紹介書は、スキルだけでなく人物像を伝える役割を持つため、準備を丁寧にするほど選考で有利に働きます。
事実を並べるだけではなく、自分の考えや学びを盛り込んで、伝わる文章にすることが大切です。
②自己紹介書と履歴書の違い
履歴書は、学歴や資格などの基本情報を簡潔にまとめるための書類です。一方、自己紹介書は文章を通じて、人柄や強みを具体的に示す場となります。
つまり、履歴書が事実を確認するための資料なら、自己紹介書は自分を知ってもらう表現の場といえるでしょう。履歴書に書いた資格や活動を深掘りし、その背景や思いを説明できるのも特徴です。
採用担当者は、履歴書だけでは見えない部分を自己紹介書で判断しているため、他の就活生と差をつけるためにも自己紹介書での工夫が不可欠です。
履歴書と同じ内容を繰り返さず、エピソードや経験を交えて「なぜ取り組んだのか」「どんな力を得たのか」を伝えることが重要になりますよ。
③自己紹介書とエントリーシートの違い
エントリーシートは、企業ごとに設問や形式が決められており、その枠に沿って答える必要があります。これに対して自己紹介書は、比較的自由度が高く、自分で伝えたい内容を選べるのが大きな違いです。
エントリーシートは企業の質問に答えるテスト形式ですが、自己紹介書は自分の魅力をプレゼンする資料に近い役割を持っています。そのため、研究やアルバイト経験を、自分らしい視点で紹介できるでしょう。
この違いを理解せずに同じように書くと、自由記述の良さを活かせません。エントリーシートは「問いに答える場」、自己紹介書は「魅力を選んで伝える場」と整理するとわかりやすいですね。
両方を使い分ければ、就活全体でのアピール力を高めることにつながります。
自己紹介書を企業が求める意図

自己紹介書は単なる自己PRの場ではなく、企業が応募者を理解するために重視する書類です。なぜ必要とされるのかを知ると、何を意識して書けばよいかがわかりやすくなるでしょう。
ここでは、企業の視点からその意図を整理して説明します。
- 人物像や人柄を知るため
- 志望度や熱意を把握するため
- コミュニケーション能力を確認するため
- 応募者の差別化を確認するため
①人物像や人柄を知るため
企業が特に重視しているのは、応募者の人物像や人柄です。同じスキルを持つ人が複数いても、組織に合うかどうかは人柄で決まることが多いでしょう。
自己紹介書には、学生生活での経験や大切にしている考え方が表れます。たとえば、サークルで仲間をまとめた経験や、アルバイトで努力を続けた姿勢は協調性や責任感を示す材料になるでしょう。
ポイントは、性格を直接書くのではなく、日常のエピソードを通して人柄を示すことです。そうすれば「どんな場面で力を発揮できる人か」を理解してもらえるはずですよ。
②志望度や熱意を把握するため
企業は、自己紹介書から応募者の志望度や熱意を見ています。どれだけ企業研究をしているか、経験とどう結びつけているかで本気度が伝わるからです。
「貴社の理念に共感しました」だけでは説得力に欠けるので、大学での研究やアルバイト経験を踏まえて「この経験から〇〇に関心を持ち、御社で活かしたい」と書くと熱意が具体的に伝わるでしょう。
採用担当者は数多くの学生を見ているため、漠然とした志望理由では印象に残りません。自分の経験と志望先の特徴をつなげることが大切です。
③コミュニケーション能力を確認するため
自己紹介書は文章で自分を伝えるため、自然にコミュニケーション能力が表れます。企業は入社後に円滑にやりとりできるかを気にしており、その力を事前に見ているのです。
長すぎて読みづらい文章や筋が通っていない内容は、相手の立場を考えていない証拠と見なされます。逆に、結論を先に示し、そのあとに理由や具体的な体験を添えると、わかりやすく伝わるでしょう。
就活生は「何を書くか」だけではなく「どう伝えるか」にも注意する必要があります。
読みやすく端的にまとめられれば、採用担当者に好印象を持ってもらえて、文章力だけでなく対人スキルも高いと評価されるでしょう。
④応募者の差別化を確認するため
企業は多数の応募者から自社に合う人を選ぶため、自己紹介書で差別化を確認します。学歴や資格だけでは見えない強みや個性が、ここで表れるからです。
同じアルバイト経験でも「接客で工夫したこと」「困難をどう乗り越えたか」を具体的に書けば、他の学生との差が生まれます。
採用担当者は似た経歴を持つ学生を比較するとき、この細かな違いを参考にしています。ありきたりな内容ではなく、自分なりの視点や学びを盛り込むことが大切です。
自分の強みを裏づけるエピソードを加えると「この学生には独自の魅力がある」と受け取られやすくなります。その結果、他の応募者との差をつけやすくなり、選考を有利に進められるでしょう。
自己紹介書に書くべき定番の項目
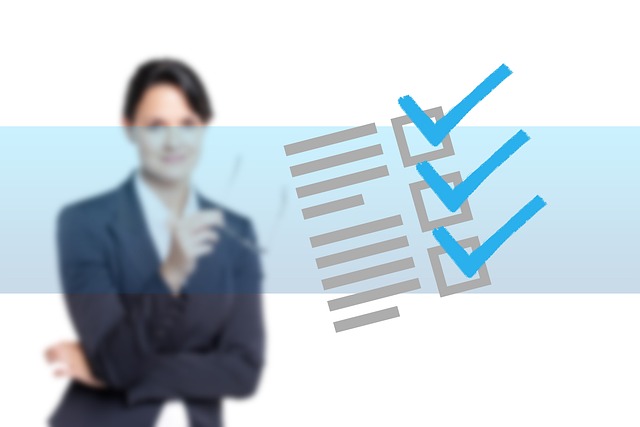
自己紹介書には、採用担当者が知りたい情報を的確に伝えるための定番項目があります。
これらを押さえておけば、書類選考で不利になる心配は少ないでしょう。ここでは、代表的な項目を整理して解説します。
- 志望動機
- 自己PR
- 資格や免許
- 趣味や特技
- 学生時代に力を入れたこと
- 研究課題や学業内容
①志望動機
志望動機は、採用担当者が特に重視する部分です。なぜなら、企業に対する理解度と応募者の熱意が明確に伝わるから。「成長したいから」といった抽象的な理由では印象に残りません。
そこで、自分の経験や価値観と企業の特徴を結びつけて書くことが大切になります。大学での活動から得た学びを具体的に示し、それを企業でどう活かすかを説明すると説得力が増すでしょう。
採用担当者は多くの学生を見ているため、漠然とした動機では埋もれてしまいます。経験と結びつけた志望動機を整理し、自分の言葉で表現してください。
それが「この学生は本気だ」と感じてもらえるきっかけになります。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
②自己PR
自己PRは、自分の強みを伝える場です。企業は、入社後にどのように力を発揮できるのかを知りたいと考えています。
そのため「強みをひと言で示す→背景やエピソードを紹介する→学んだことをまとめる」という流れで書くと効果的でしょう。
たとえば「継続力がある」と伝える場合は、アルバイトや部活動で続けた経験を紹介し、成果や学びを加えてください。強みを裏づける体験を具体的に示すことで、採用担当者はあなたの姿をイメージできます。
最後にその強みを社会でどう活かすかを添えれば、印象に残る自己PRになるでしょう。
「自己PRの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる自己PRテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みを効果的にアピールする自己PRが作成できますよ。
③資格や免許
資格や免許は、努力の証として有効です。採用担当者は資格そのものよりも、取得までの過程から見える継続力や主体性を評価します。
「数字が苦手だったが簿記に挑戦し、学習習慣を工夫して克服した」といった内容なら、粘り強さが伝わるでしょう。
もちろん、業務に直結する資格は強みになりますが、そうでなくても「努力を続けて結果を出せる人」という印象を与えられます。
書く際は「挑戦のきっかけ→努力の過程→合格までの流れ→学んだこと」を意識するとわかりやすいです。資格名を並べるだけではなく、その過程で得た姿勢や考え方を示してください。
④趣味や特技
趣味や特技は、一見選考に関係なさそうですが、人柄を伝える大切な要素です。採用担当者は、応募者の個性や価値観を知る材料にしています。
「ジョギングを3年間続けた経験」と書けば、継続力や自己管理能力を示せるでしょう。
また、例えば趣味を伝える際にただ「音楽が好きです」とだけ書くのでは弱く、どのように取り組んでいるのかや学びを添えると伝わりやすいです。
趣味や特技を通じて得た力を、社会でどう活かすかまで結びつければ、強いアピールにつながります。自分らしさを自然に表せる項目なので、工夫して活用してください。
⑤学生時代に力を入れたこと
学生時代に力を入れたことは、多くの企業が重視する定番テーマです。ここで重要なのは、単なる活動紹介ではなく「自分がどう動いたか、何を学んだか」を伝えることです。
たとえば「学園祭の実行委員を務めた」という経験なら、役割や課題、改善の工夫、成果までを順に説明しましょう。採用担当者は「主体性」「協調性」「課題解決力」といった資質を確認しています。
だからこそ「課題→行動→成果」の流れを意識すると伝わりやすいです。最後にその経験から得た学びを社会でどう活かすかに触れると、より効果的なアピールになります。
「ガクチカの作成法がよくわからない……」「やってみたけどうまく作成できない」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるガクチカテンプレシートをダウンロードしてみましょう!ステップごとに答えを記入していくだけで、あなたらしい長所や強みをアピールできるガクチカの作成ができますよ。
⑥研究課題や学業内容
研究課題や学業内容は、学びに対する姿勢や論理的思考を示す項目です。専門分野と企業の事業が関連している場合は、強いアピールにつながります。
「地域活性化をテーマに研究し、データ収集と分析を行い課題解決の提案を発表した」といった内容なら、分析力や問題解決力が伝わるでしょう。
注意点は、専門的すぎる表現を避けて誰にでもわかる言葉で説明することです。採用担当者の多くは、その分野の専門家ではありません。
研究のテーマや進め方、成果とそこからの学びを簡潔にまとめ、将来どう役立てたいかまで書けば、効果的に伝わります。
自己紹介書の書き方

自己紹介書は、自分の強みや考えを伝える大切な書類です。ただ思いついたことを書くのではなく、読み手にわかりやすく整理することが求められます。
ここでは、効果的にまとめるためのポイントを紹介しましょう。
- 結論ファーストで伝える
- A4用紙1枚に収める
- 手書きとパソコン作成から選ぶ
- 選考担当者を意識して書く
①結論ファーストで伝える
自己紹介書では、冒頭で結論を伝えると効果的です。採用担当者は限られた時間で多くの書類を読むため、最初に要点が示されると印象に残りやすいでしょう。
たとえば「私は継続力があります」と先に伝え、その後にエピソードや成果を添えると説得力が増します。逆に、結論を最後まで隠すと、何を言いたいのかが伝わりにくくなり、評価を下げる原因になりかねません。
短い時間で自分の強みを確実に届けるためには、結論を冒頭に示し、根拠を簡潔に補足する流れを意識してください。結論ファーストを徹底すれば、読み手に負担をかけず魅力を伝えられるはずです。
②A4用紙1枚に収める
自己紹介書は、長すぎても短すぎても逆効果です。A4用紙1枚にまとめるのが適切でしょう。採用担当者は短時間で多くの書類を確認するため、適切な分量で整理されているかどうかが大切になります。
情報を詰め込みすぎると読みにくく、少なすぎると熱意が伝わりにくいので、強みや経験を整理し、要点だけに絞って書いてください。
「アルバイトでの工夫」や「研究での成果」といった具体例を、1つか2つ選んで展開すると良いでしょう。A4用紙1枚という制約を意識すれば、内容が整理されて伝わりやすい文章になります。
適切な分量を守ることは、信頼感にもつながるものです。
③手書きとパソコン作成から選ぶ
自己紹介書を手書きにするか、パソコンで作成するか迷う人は多いでしょう。結論から言うと、どちらにも利点があります。
手書きは温かみや誠意が伝わりやすく、丁寧に仕上げれば好印象を与えられる一方、パソコン作成はレイアウトが整い、見やすい書類に仕上がるのが強みです。
企業側で形式が指定されている場合もあるため、まずは募集要項を確認しましょう。指定がないなら、自分が最も丁寧に仕上げられる方法を選んで問題ありません。
重要なのは「読みやすさ」と「誠意」です。誤字脱字や文字の見やすさに注意すれば、どちらを選んでも評価されるでしょう。応募先の雰囲気に合わせるのも有効です。
④選考担当者を意識して書く
自己紹介書を書くときは、常に選考担当者の視点を意識してください。採用側が知りたいのは「この学生と一緒に働きたいかどうか」です。
自分の言いたいことだけを書くのではなく、相手にとって有益な情報を意識しましょう。
たとえば「協調性を活かして周囲と成果を出した経験」や「主体的に行動して課題を解決した経験」は、どの職場でも評価されやすい内容です。
読み手が「一緒に働く姿」をイメージできるように書き、相手の立場を意識すれば、より効果的な自己紹介書につながります。
刺さる自己紹介書にするためのコツ

自己紹介書はただ書くだけでは十分ではなく、採用担当者の心に残る内容にすることが重要です。
ここでは、より効果的に伝わる工夫や意識すべきポイントを紹介します。
- 企業ごとに内容をカスタマイズする
- 一貫性のあるエピソードを選ぶ
- 数字や成果を入れて具体性を出す
- 読み手の印象に残る表現を工夫する
- 簡潔かつ分かりやすい文章にする
①企業ごとに内容をカスタマイズする
自己紹介書は同じ内容を使い回すと、採用担当者に熱意が伝わりません。志望先ごとに調整することが大切です。
もし、「地域に貢献したい」という思いがあるなら、地域事業に力を入れている企業ではその点を強調すると良いでしょう。一方で、グローバル展開を重視する企業であれば、留学や語学の経験を示すと効果的です。
自分の経験を、相手の強みや特徴に寄せて伝えることで「この人はうちに合う」と思ってもらえる可能性が高まります。大事なのは、自分の強みと企業の魅力を自然につなげることです。
②一貫性のあるエピソードを選ぶ
自己紹介書に複数のエピソードを詰め込むと、結局何を伝えたいのか分からなくなります。そのため、一貫性のあるエピソードを選ぶことが大切でしょう。
「協調性」をアピールしたいなら、部活動やゼミ活動など人と協力した経験を中心に書くと説得力が増します。逆に、異なる強みを並べてしまうと印象が薄れてしまうでしょう。
読み手に残るのは「この人はこういう強みがある」という一言で表せるイメージです。そのため、最も自分らしさを伝えられる経験を選び、筋の通った自己紹介書にしてください。
③数字や成果を入れて具体性を出す
自己紹介書で説得力を高めるには、数字や成果を取り入れることが効果的です。
例えば、「イベントの参加者を前年の2倍に増やした」「アルバイトで売上を10%改善した」といった具体的な数値は客観性を持ち、読み手の印象に残りやすいでしょう。
漠然と「努力した」と書くよりも、成果を数字で示せば評価は大きく変わります。小さな成果でも、問題ありません。
「半年間、毎日30分勉強して資格に合格した」という書き方でも十分に伝わります。数字を活用することで、自己紹介書の説得力が一段と高まるはずです。
④読み手の印象に残る表現を工夫する
自己紹介書は、多くの応募者と比較されるため、印象に残る工夫が必要です。ありふれた表現だけでは、記憶に残りません。
たとえば「努力家」ではなく「毎日30分の学習を3年間続けた」と書けば、具体性と個性が出ます。また、エピソードに情景を想像できる表現を取り入れるのも有効でしょう。
ただし、誇張しすぎると不自然になるため注意してください。大切なのは、読み手があなたをイメージできるかどうかです。表現を工夫することで、担当者の記憶に残る自己紹介書に変わります。
⑤簡潔かつ分かりやすい文章にする
自己紹介書は、長く書きすぎると読み手の負担になり、短すぎると熱意が伝わりません。そのため、簡潔で分かりやすい文章を意識しましょう。
たとえば「私は責任感があります。その力を生かしてアルバイトで新人の指導を任されました」と区切れば読みやすさが増し、情報を詰め込みすぎると読みにくくなります。
誰が読んでもすぐ理解できるように整理することで、誠実さや配慮も伝わるでしょう。読みやすさを意識した文章は、選考を有利に進める力になるはずです。
【項目別】自己紹介書の例文

自己紹介書を書こうと思っても「具体的にどう書けばいいのか」と迷う方は多いでしょう。ここでは、代表的な項目ごとの例文を紹介します。実際のイメージをつかむことができるでしょう。
また、志望動機がそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの志望動機テンプレを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
志望動機が既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。
【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
①志望動機の例文
志望動機は、自己紹介書の中でも特に重要な項目です。
ここでは、大学生が就活で使いやすい志望動機の例文を紹介します。企業への関心や学びを、どのように自分の言葉で表現するかをイメージしてください。
| 私は、貴社で地域社会に貢献しながら、自分自身も成長していきたいと考えています。大学時代、ゼミ活動を通じて地域の課題解決に取り組み、仲間と協力して成果を形にする喜びを実感しました。 その経験から、チームで課題を解決していく働き方に強く魅力を感じました。御社のインターンに参加した際にも、社員の方々が一丸となって課題に挑む姿勢に感銘を受けました。 特に、地域に根ざした事業展開に共感しており、これまでの経験を活かして貴社の一員として貢献したいと強く志望しています。 |
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
結論ファーストで志望の意思を冒頭に伝えると、読み手に強い印象を与えられます。その後に具体的な経験や企業への共感点を補足すると説得力が高まるでしょう。
②自己PRの例文
自己PRは、自分の強みや特長を相手に伝えるための重要なパートです。ここでは、大学生活での身近な経験を通じて、自分の強みを自然に表現する例文を紹介します。
| 私の強みは、状況を分析して改善につなげる行動力と、仲間と協力して目標を達成する姿勢です。大学時代、サークル活動でイベント企画を担当した際、当初は参加者が集まらず悩みました。 そこで、先輩や仲間と相談しながらSNSを活用した告知方法を工夫した結果、当日の参加者は前年の倍以上となりました。 この経験から、自ら課題を見つけて解決策を考え、実行する力を磨くことができました。社会人になってからも、この力を活かしてチームに貢献していきたいと考えています。 |
自己PRは冒頭で「自分の強み」をはっきり示すと印象が強まります。その後に具体的なエピソードで補足すれば、説得力が格段に高まるでしょう。
③資格や免許の例文
資格や免許は、自分の努力や継続力をアピールする有効な材料です。ここでは、学業と並行して資格取得に挑戦したエピソードを紹介します。
| 私は、大学在学中に簿記の資格を取得しました。もともと数字に苦手意識があり、学習を始めた当初は理解が進まず挫折しそうになったこともありました。 しかし、毎日決まった時間を学習に充て、友人と問題を解き合うことで少しずつ理解を深めるていったのです。 努力を積み重ねた結果、試験本番では自信を持って臨むことができ、合格につなげることができました。この経験から、苦手分野にも粘り強く挑戦し、継続して学ぶ姿勢を身につけました。 今後も、新しい知識やスキルの習得に取り組み、社会に出てからも成果を出せるよう努めていきたいと考えています。 |
取得した資格を冒頭に示すと、成果が明確になり印象に残ります。その後に努力の過程や学びを補足すると、説得力とストーリー性が増すでしょう。
④趣味や特技の例文
趣味や特技は、人柄や個性を伝える重要な要素です。ここでは、大学生活で培った趣味を通じて、自分の強みを自然にアピールする例文を紹介します。
| 私の趣味はジョギングであり、それを通じて粘り強さと集中力を培いました。大学入学後に体力づくりの一環として始めましたが、毎日続けることで忍耐力も身につけることができました。 雨の日や忙しい時期でも工夫して時間を確保し、3年間継続して取り組んだ結果、地域のマラソン大会を完走するまでに成長できたのです。 この経験から、一つのことを長く続ける習慣と、日々の小さな努力が成果につながることを実感しました。今後もこの姿勢を活かし、社会に出てからも粘り強く取り組み成果を上げていきたいと考えています。 |
趣味や特技は、最初に結論として示すと伝わりやすくなるでしょう。その上で「継続→成果→学び」の流れを補足すれば、説得力が一層高まります。
⑤学生時代に力を入れたことの例文
学生時代に力を入れたことは、自分の主体性や学びの姿勢を示す絶好のテーマです。ここでは、大学生がよく経験する活動を題材にした例文を紹介します。
| 私は学生時代、学園祭の実行委員として企画運営に力を入れました。特に、初めて参加した1年目は、意見がまとまらず準備が遅れることが多く、チーム全体が不安を抱えていました。 そこで私は、進捗状況を共有できる表を作成し、役割ごとの責任を明確にする仕組みを提案。その結果、各自が自分の役割を把握できるようになり、準備がスムーズに進みました。 当日のイベントは大きなトラブルもなく成功し、多くの来場者に楽しんでいただくことができました。この経験を通じて、主体的に課題を解決し、仲間と協力しながら一つの目標を達成する大切さを学びました。 社会人になってからもこの姿勢を忘れず、周囲と協力して成果を出していきたいと考えています。 |
「課題→行動→成果」の流れを意識すると、取り組みの過程が伝わりやすくなるでしょう。組織の中でどう貢献したかを具体的に書くと評価が高まります。
⑥研究課題に関する例文
研究課題は、学びに対する姿勢や問題解決力をアピールできるテーマです。ここでは、大学での研究活動を通じて得た経験を例文として紹介します。
| 私は、大学で地域活性化をテーマとした研究に取り組んだ経験があります。少子高齢化による商店街の衰退を調査する中で、地元住民や店舗の方々への聞き取り調査を行い、課題の整理を進めました。 当初は、意見が多岐にわたり整理に苦労しましたが、データを分類し直すことで共通点を見つけることができたのです。 その結果、若年層向けのイベントを増やすことが効果的だと結論づけ、研究発表会では具体的な提案として発表しました。 この経験を通して、課題を発見し分析する力や、データを基に論理的に考える姿勢を養うことができました。社会に出てからも、この力を活かして現場の課題解決に取り組み、成果に結びつけていきたいと考えています。 |
研究課題を題材にする際は「研究テーマ→困難→工夫→成果」の順で整理すると読みやすくなります。取り組みから得た力を将来の仕事と結びつけると効果的です。
自己紹介書を書くときの注意点
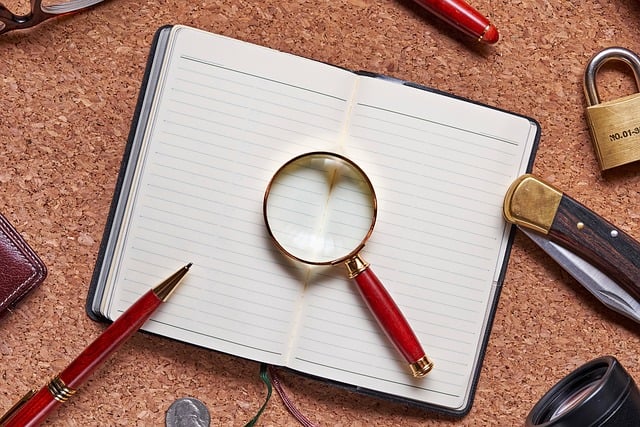
自己紹介書は、自分を伝える大切な書類ですが、内容だけでなく形式や表現方法にも注意が必要です。小さなミスや誤った書き方は、せっかくの努力を無駄にしてしまうかもしれません。
ここでは、作成時に押さえておきたい基本的な注意点を整理しました。
- 誤字脱字や形式の不備を避ける
- 手書きの場合は黒のボールペンを使用する
- 盛りすぎず簡潔にまとめる
- 事実と異なる内容を書くのは控える
①誤字脱字や形式の不備を避ける
誤字脱字は、読み手に「細かい部分まで配慮できない人」という印象を与えかねません。たとえ文章の内容が優れていても、誤りが一つあるだけで信頼性は一気に下がってしまいます。
特に、氏名や住所、日付などの基本情報に不備があると、応募書類全体の評価に直結するため致命的です。
完成後は必ず時間をかけて見直しを行い、可能であれば家族や友人など第三者の目で確認してもらうと安心でしょう。読みやすさや誠実さは、小さな配慮の積み重ねで伝わるものです。
細部まで注意を払う姿勢が、結果として好印象につながります。
②手書きの場合は黒のボールペンを使用する
自己紹介書を手書きで提出する場合、黒のボールペンを使用するのが基本的なマナーです。
鉛筆やシャープペンシルは、消しやすいため正式な書類には不向きであり、青や赤などのインクはビジネス文書としては避けられることが一般的でしょう。
黒は安定感があり、誰にとっても見やすく落ち着いた印象を与える色です。さらに、丁寧に書かれた文字そのものが応募者の誠実さや姿勢を表すため、急がず落ち着いて記入することが大切でしょう。
インクのかすれやにじみを防ぐために、使い慣れたペンを選ぶこともおすすめです。
③盛りすぎず簡潔にまとめる
自分を良く見せようとするあまり、事実以上に盛った内容を書くのは避けたほうが無難です。大げさな表現や不自然な経歴は、読み手に違和感や不信感を与えてしまいます。
限られた文字数の中で伝えるには、余計な修飾よりも「事実を端的に整理すること」が重要です。たとえば、経験の経緯や行動、成果をできるだけ具体的に示すことで、文章が短くても説得力を持たせられます。
また、情報を整理して簡潔に伝える力そのものが、社会人に求められるスキルでもあります。読み手が短時間で理解できる文章を意識し、シンプルながらも的確に自分を表現してください。
④事実と異なる内容を書くのは控える
事実と異なることを書けば、面接で質問された際にすぐに矛盾が浮き彫りになります。一度信用を失えば、その印象を挽回するのは非常に難しいでしょう。
たとえ小さな経験や成果でも、正直に伝えることが大切です。自分が感じた成長や学びを具体的に示すだけで、読み手には十分な魅力として伝わります。
採用担当者は派手なエピソードよりも、誠実で一貫性のある人物像を重視する傾向があるでしょう。そのため、等身大の姿を丁寧に言葉にすることが信頼を築く近道です。
自分らしさを大切にしながら、真実に基づいた表現で自信を持ってアピールしてください。
自己紹介書に関するよくある質問

自己紹介書を用意する際、多くの学生が同じような悩みを持っています。履歴書との違いに戸惑ったり、書く内容に迷ったりすることもあるでしょう。
ここでは、よくある疑問を整理し、安心して準備を進められるように解説します。
- 自己紹介書と履歴書はどちらを優先すべき?
- 自己紹介書に書くことが思いつかないときはどうすればいい?
- アルバイト経験は自己紹介書に書いていい?
- 自己紹介書の文字数はどれくらいが必要?
- 自己紹介書を提出する際に注意することは?
①自己紹介書と履歴書はどちらを優先すべき?
履歴書は、必須の応募書類であり、企業に提出しないと選考が始まりません。そのため、まず履歴書を優先的に整えることが大前提です。
一方で、自己紹介書は企業によって扱いが異なり、採用基準の中心として評価される場合もあれば、参考資料程度に目を通すだけというケースもあります。
自己紹介書は、履歴書に書ききれない自分の人物像を補足できる貴重な場でもあるので、履歴書と自己紹介書の内容に一貫性を持たせつつ、自分らしさを加えましょう。
結果的に、両方をそろえることで応募書類全体の完成度が高まり、選考突破の可能性が広がります。
②自己紹介書に書くことが思いつかないときはどうすればいい?
書く内容が浮かばないと感じる学生は少なくありません。そんなときは、まず大学生活を幅広く振り返ることが有効です。
授業での発表やゼミでの研究、サークル活動や部活動、アルバイトでの経験、さらにはボランティアや趣味で得た学びなども立派な材料になります。
重要なのは、出来事そのものの大きさではなく、そこからどんな姿勢や価値観を得たかを掘り下げて表現することです。小さな体験でも、自分の強みや人柄がにじみ出るエピソードに変えることができます。
また、「人に語りたくなる体験は何か」「困難を乗り越えた場面はあったか」と問いかけてみると、具体的なネタを見つけやすいでしょう。
書けないと悩むときは、まず箇条書きで思いつく経験を洗い出し、その中から選んで膨らませる方法もおすすめですよ。
③アルバイト経験は自己紹介書に書いていい?
アルバイト経験は、自己紹介書に盛り込んで問題ありません。むしろ、社会経験が少ない学生にとって、アルバイトは働く姿勢や責任感を示すための貴重な題材になります。
特に、接客業で培った対応力やコミュニケーション力、長期間勤務する中で身につけた継続力や責任感などは、高く評価されやすいポイントです。
ただし、仕事内容そのものを羅列するだけではアピールになりにくいため、「その経験から何を学んだか」「自分の成長にどうつながったか」を具体的に示すことが重要でしょう。
たとえば「繁忙期に仲間と協力して仕事をやり遂げた経験」「お客様の声を受けて改善した工夫」など、行動と成果を結びつけて書くと説得力が増します。
アルバイト経験を通じて得た学びを、社会人としてどう活かせるかまで言及すると、より強い印象を残せるでしょう。
④自己紹介書の文字数はどれくらいが必要?
自己紹介書の分量は一般的にA4用紙1枚に収めるのが理想的とされ、文字数の指定はありません。
短すぎると自分の人柄や強みを十分に伝えられず、内容が薄く見えてしまいます。一方で、長すぎると要点がぼやけ、読み手に負担をかけてしまう可能性も。
選考担当者は多くの書類を限られた時間で目を通すため、シンプルで理解しやすい文章が好まれます。そのため、段落分けを工夫して読みやすさを意識し、適度な余白を確保すると全体の印象が整うでしょう。
また、文字数はあくまで目安であり、最終的には「短時間で内容が伝わるかどうか」を基準に仕上げることが大切です。無理に長くせず、端的で具体的なエピソードを選んでまとめることを心がけてください。
⑤自己紹介書を提出する際に注意することは?
自己紹介書を提出する際には、仕上がりを入念に確認することが不可欠です。誤字脱字や日付、氏名など基本的な部分の記入漏れがあると、それだけで信頼を損なう恐れがあります。
手書きで作成する場合は、黒のボールペンを使用し、丁寧で読みやすい文字を心がけてください。字の乱れや修正の跡は、印象を悪くする可能性があるので見直しを行いましょう。
また、オンラインで提出する場合は、企業が指定するファイル形式(PDFなど)やファイル名のルールを守ることが必要です。
細かい提出マナーや形式を守れるかどうかも評価の対象になるため、注意を怠らないでください。さらに、提出直前にもう一度全体を見直す余裕を持つことが、最後の信頼確保につながります。
形式と内容の両面で整った書類を仕上げることが、選考を突破する第一歩となるでしょう。
自己紹介書を活かして就活を有利に進めるために

自己紹介書は、履歴書やエントリーシートと並び、自分を深く理解してもらうための大切な書類です。企業は人物像や熱意、コミュニケーション力を見極めるために自己紹介書を求めます。
そのため、志望動機や自己PR、資格や学生生活での経験を盛り込み、一貫性を持たせて書くことが必要です。また、結論ファーストで伝え、数字を活用して具体性を高める工夫も効果的でしょう。
誤字脱字を避け、盛りすぎない姿勢を意識することも重要です。自己紹介書は、就活を成功に導く大きな武器になります。ここで学んだポイントを押さえて作成すれば、自分の魅力を最大限に伝えられるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














