大学生向け公務員試験完全ガイド|出題範囲・勉強法・予備校の選び方
「公務員試験っていつから勉強を始めればいいの?」「科目が多すぎて手がつけられない…」そんな悩みを抱える大学生は少なくありません。
公務員の試験科目は教養から専門、面接や論文まで幅広く、正しい準備が欠かせません。
そこで本記事では、大学生が公務員になるために知っておきたい試験の出題範囲や学年別の勉強法、さらに予備校や通信講座の選び方までを徹底解説。
初めて挑戦する方でも合格までの道筋がイメージできるよう、完全ガイドとしてまとめました。ぜひ、参考にしてください。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
大学生が公務員になるには

大学生が公務員になるためには、まず志望する職種と試験区分を決定する必要があります。国家公務員と地方公務員では求められる能力や仕事内容が異なり、採用試験の難易度も変わるからです。
国家公務員総合職は高度な専門知識と政策立案能力が求められる一方、地方公務員は地域貢献や行政サービスに携わる業務が中心。
そのため、自分の将来像に合った職種を早めに見極めることが重要でしょう。
さらに、公務員試験は筆記・面接・論文・適性検査など複数のステップを経て行われるため、学業と両立しながら計画的に学習を進めなければなりません。
大学3年生からの本格的な勉強が一般的ですが、競争率を考慮すると大学1~2年生からの準備も有利です。
採用後のキャリアや勤務地の選択肢も職種によって異なるため、早い段階から情報収集を徹底し、効率的な対策を始めることが合格への近道ですよ。
公務員試験の出題範囲

公務員試験は出題範囲が広く、効率的な学習計画が不可欠です。教養試験から専門試験、論文や面接試験まで多様な科目と形式があります。
ここでは、各試験の特徴や傾向を整理し、何から着手すべきかを分かりやすく解説します。
- 教養試験の出題範囲
- 専門試験の出題範囲
- 論文・作文の出題範囲
- 面接試験で問われる項目の範囲
- 適性検査・体力試験の実施範囲
①教養試験の出題範囲
教養試験はすべての受験者が共通して受ける試験で、基礎学力と一般常識を幅広く確認します。
文章理解や判断推理、数的推理、資料解釈などの知能分野と、政治・経済・社会・地理・歴史などの知識分野が中心です。
出題範囲が広いため、暗記量が多くなりやすいですが、頻出分野から学習を始めると効率的。特に文章理解や判断推理は得点源になりやすく、全体の得点を安定させる鍵となります。
暗記が必要な科目は早めに取り掛かり、スキマ時間を活用する工夫も効果的でしょう。
教養試験の得点はすべての公務員試験における基礎力を示す重要な指標であり、まずはこの分野で安定して点を取れる実力をつけることが合格への近道です。
②専門試験の出題範囲
専門試験は職種や区分によって内容が変わり、大学で学んだ知識を問う問題が多いです。国家公務員総合職では法律や経済、行政職では憲法・民法・行政法などが中心になります。
地方公務員試験でも専門試験を課す自治体は多く、範囲の広さから計画的な学習が欠かせません。まずは志望先の職種と出題科目を把握し、出題数が多い科目から優先的に対策を進めてください。
大学の授業内容を早期に復習しておくと理解が深まります。参考書や過去問で出題傾向を分析すれば、効率よく学習が進められるでしょう。
専門試験は配点も高く、合否を大きく左右するため、早めの準備が必要です。
③論文・作文の出題範囲
論文や作文は、社会問題への理解や文章力、論理的思考を評価される試験です。時事問題や公共政策に関するテーマが多く、単なる知識ではなく意見を根拠を示して述べる力が求められます。
序論・本論・結論の型を習得し、過去問を活用した練習を積むことが重要です。普段からニュースに触れて社会情勢を把握し、具体例やデータを引用できるように知識を整理してください。
論理性や具体性のある文章を意識すれば高評価につながりますよ。作文や論文のスキルは面接や社会人としての基礎力にも直結するため、早めの練習が将来の自信になります。
④面接試験で問われる項目の範囲
面接試験は人物評価が中心で、受験者の人柄や志望理由、価値観が見られます。自己PRや学生時代の経験、地域や政策への理解が問われることも多いです。
短い時間で自分を効果的に伝えるためには、自己分析と企業研究が欠かせません。特に公務員試験では公共性や使命感の有無が評価されやすいです。
模擬面接を受けて表情や話し方を確認するとよいでしょう。話の一貫性や具体性を意識すれば、信頼感を与えられます。筆記試験だけに集中せず、面接準備も並行して進めておくことで合格に近づけます。
⑤適性検査・体力試験の実施範囲
警察官や消防士、自衛官などで行われる適性検査や体力試験は、基礎体力や心理的適性を評価します。
体力試験は走力や腕立て伏せなどの基本的な動作が多く、日常的な運動習慣の積み重ねが結果に直結します。
適性検査ではストレス耐性や判断力が測られ、特別な知識は必要ありませんが、自己理解を深めておくと役立つでしょう。
受験先の体力基準を早めに確認し、必要に応じたトレーニングを始めれば余裕を持って臨めます。実務を意識した試験内容であるため、早期準備が安心につながります。
大学生が公務員試験の勉強を始めるタイミング
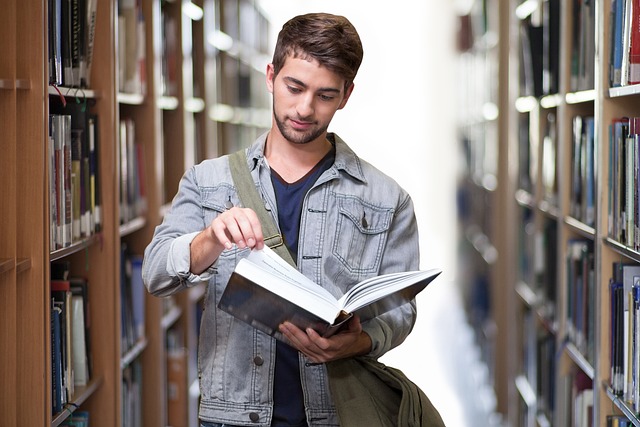
公務員試験は出題範囲が広く、計画的な準備が必要な試験です。勉強を始める時期によって対策の仕方や重点分野が変わるため、早めの情報収集が欠かせません。
ここでは学年ごとの学習開始時期と特徴を解説します。
- 大学1年生からの学習開始
- 大学2年生からの学習開始
- 大学3年生からの学習開始
- 試験1年前からの集中的準備
①大学1年生からの学習開始
大学1年から勉強を始めると基礎を丁寧に固められ、長期的な学習計画を立てやすくなります。教養試験や論文対策など幅広い知識が求められる科目は、早期対策が有利です。
時間に余裕がある時期に勉強習慣を作ることで、部活動やアルバイトとも無理なく両立できるでしょう。
さらに、興味のある分野や志望先の研究を早めに始めることで、面接対策や志望動機の質も高まります。まずは基礎力の習得を最優先にし、勉強に向き合う時間を確保することが大切です。
②大学2年生からの学習開始
大学2年から学習を始めるのは一般的で、効率的な計画を立てやすい時期です。早めに勉強を始めれば、3年の夏までに模試やインターンなどの実践的な経験を積む余裕もできます。
2年の後半には専門試験の科目を絞り、自分に合った勉強法を見つけるとよいでしょう。授業や部活動と両立しながら、少しずつ学習習慣を身につけることが重要です。
参考書選びや過去問演習を並行して進めると、3年以降の本格的な試験対策にスムーズに移れます。
③大学3年生からの学習開始
大学3年からの学習は限られた時間の中で成果を出す必要があるため、計画性と集中力が求められます。この時期は部活動や就職活動などと重なることが多く、効率よく対策することが不可欠です。
まず出題範囲を確認し、頻出分野を優先的に学習しましょう。模試や過去問で弱点を明らかにし、重点的に復習することが重要です。
試験制度や選考スケジュールの把握も早めに行えば、時間を有効に使えるでしょう。短期集中型で基礎から応用まで一気に仕上げる意識が必要です。
④試験1年前からの集中的準備
試験の1年前から勉強を始める場合は、限られた期間で成果を出すための戦略が欠かせません。集中学習は短期間での得点力向上に向いていますが、基礎力が不足していると伸び悩む可能性もあります。
出題傾向を把握し、優先度の高い科目から取り組むことが大切です。過去問演習を中心に据え、理解が浅い分野を重点的に復習しましょう。
予備校や通信講座を活用すれば、短期間でも効率的な学習が可能です。強い集中力を維持し、限られた時間で仕上げる意識を持ちましょう。
大学1・2年生から始める公務員試験対策
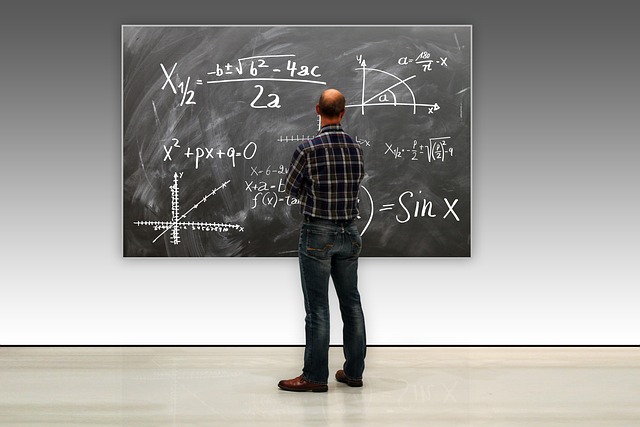
大学1・2年生のうちから計画的に試験対策を始めることで、試験直前に慌てず安定した成果を出せます。早期スタートは基礎固めや時間の余裕を確保し、大学生活と勉強の両立にも役立つでしょう。
ここでは、低学年から実践できる効果的な対策のポイントを解説します。
- 基礎学力の養成
- 教養試験対策の早期着手
- 大学講義の活用
- 時事問題の知識習得
- 学業と活動の両立計画
①基礎学力の養成
公務員試験に必要な土台は、中学・高校レベルの基礎知識です。特に数的処理や文章理解は頻出分野であり、早めに復習しておくと有利になります。
大学1・2年生は授業や活動で忙しいですが、1日30分でも英単語や数学を継続的に学ぶ習慣を作ってください。基礎が定着すれば、専門分野の勉強も効率的に進められるでしょう。
無理のない学習計画を立て、得意科目を少しずつ増やすことが安定した得点につながります。
②教養試験対策の早期着手
教養試験はすべての受験者に課されるため、早めの準備が合否を左右します。文章理解・判断推理・数的推理など頻出分野の問題に触れ、形式に慣れることが大切です。
大学1・2年生の段階で市販問題集に取り組めば、3年生以降の勉強がスムーズになります。基礎学力が強化されると、大学の授業や資格試験にも好影響を与えるでしょう。
毎日の勉強をルーティン化して、無理なく続けられる仕組みを整えてください。
③大学講義の活用
大学の授業には公務員試験に直結する内容が多くあります。憲法や政治学、経済学などは専門科目対策としても役立ちますので、意識的に履修しましょう。
講義を通じて学んだ内容をそのまま試験勉強に生かすことで、効率よく知識を習得できます。
課題や試験勉強を通じて論理的思考力や文章力も養われるため、一石二鳥です。授業を試験対策と切り離さず、日常の学びを最大限活用することが負担を減らすコツです。
④時事問題の知識習得
公務員試験では時事問題が頻繁に出題されるため、社会情勢や政策を理解しておくことが重要です。大学1・2年生からニュースや新聞を定期的にチェックし、背景まで整理する習慣をつけてください。
経済や政治、国際情勢など複数の分野を関連づけて考える力が得点力を高めます。SNSやニュースアプリを活用すると効率よく情報を得られますが、信頼性の判断も必要です。
日常的に時事問題に触れることで、本番の問題にも落ち着いて対応できるでしょう。
⑤学業と活動の両立計画
大学生活ではサークルやアルバイトなど活動の幅が広がりますが、試験対策との両立が合格の鍵です。早い段階から時間管理を意識し、試験までの計画を逆算して行動してください。
低学年のうちは資格取得やボランティアなど幅広い経験を積むことも評価されます。計画的な生活を心がければ、3年生からの本格的な勉強にも余裕を持てます。
大学生活を楽しみながら将来を見据え、学業・課外活動・試験準備のバランスを整えることが重要です。
大学3年生から始める公務員試験対策

大学3年生から公務員試験の対策を始めると、試験の全体像を把握しつつ効率よく学習を進められます。
ここでは志望先の選定や試験日程の確認から、専門試験や面接対策、模擬試験の活用まで合格を目指すための具体的な流れを解説します。
- 試験日程の確認と志望先選定
- 専門試験の重点対策
- 過去問演習による実力強化
- 面接・集団討論の準備
- 模擬試験の活用
- 試験直前期の総仕上げ
①試験日程の確認と志望先選定
大学3年生の秋から冬にかけて志望先を決め、試験日程を把握しておくことが重要です。公務員試験は職種や自治体によって実施時期や形式が異なり、試験日が重なる場合もあります。
まずは志望先の情報を集め、受験計画を立てましょう。早期に志望先を決めることで、必要な専門分野の勉強や面接対策の方向性を定めやすくなります。
情報収集には自治体や人事院の公式サイト、予備校の資料を活用してください。出願条件や採用人数の傾向も確認すると計画がより立てやすくなるでしょう。
②専門試験の重点対策
大学3年生の段階で専門試験対策を始めると、知識の定着度が大きく変わります。行政職では法律や経済、理系職では技術分野の出題が中心で、大学の授業と重なる部分も多いです。
効率的に学習するためには、出題頻度の高い科目を優先して取り組むことが重要です。過去問や参考書で出題傾向を確認し、得点源になる分野を強化しましょう。
苦手分野は早めに克服を目指し、予備校や通信講座を利用するのも効果的です。大学の授業と組み合わせれば学習効率も上がります。計画的な取り組みを継続すれば、本番での得点力が高まるはずです。
③過去問演習による実力強化
過去問演習は公務員試験対策の中でも最重要の学習法です。実際に過去問を解くことで出題傾向や問題形式を理解でき、効率的な解答スキルを養えます。
まずは3年分程度の過去問を解き、頻出分野と苦手分野を把握してください。その後、復習を徹底し知識を定着させましょう。演習を通じて試験時間の配分や解答順の工夫も身につきます。
本番の緊張を和らげるためにも、過去問演習は欠かせません。過去問は出題レベルを測る指標にもなり、参考書の選定や学習計画の立案にも役立つでしょう。
日々の学習に組み込み、着実に力をつけてください。
④面接・集団討論の準備
筆記試験だけでなく、面接や集団討論の準備も早期に始める必要があります。大学3年生の段階から自己分析を行い、強みや志望動機を明確にしましょう。
面接では人物評価や公務員としての適性が問われるため、模擬面接で経験を積むことが有効です。集団討論では、論理的に意見を述べつつ相手の話を尊重する姿勢が求められます。
ゼミやサークルでの活動経験を活かして練習してください。また、社会問題への関心を持ち日頃から情報収集を行うと発言に深みが出ます。早めの対策で自信を持って臨めるよう準備を整えましょう。
面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?
一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。
⑤模擬試験の活用
模擬試験は実力を客観的に把握できる貴重な機会です。大学3年生から積極的に模試を受け、試験の時間配分や傾向に慣れておきましょう。
模試を受けることで弱点や課題が明確になり、学習計画の見直しに役立ちます。本番に近い環境で緊張感を体験することも、メンタル面の準備につながりますよ。
模試後には間違えた問題を分析し、次回以降の改善点を見つけてください。予備校や大学キャリアセンターで実施される模試も積極的に活用し、複数の模試で実力の推移を確認することがおすすめです。
⑥試験直前期の総仕上げ
試験直前期は知識を整理し、確実に得点につながる内容を定着させる時期です。新しい知識を詰め込むのではなく、過去に間違えた問題や頻出分野を重点的に確認してください。
まとめノートやチェックリストを作り、効率的に復習を進めましょう。また、直前期は体調管理も欠かせません。睡眠や食事のリズムを整え、試験当日に集中できる状態を作ることが大切です。
さらに、試験会場や持ち物を事前に確認すれば不安を軽減できます。計画的な仕上げを行うことで、自信を持って本番に挑めるでしょう。
公務員試験合格までのスケジュール

公務員試験合格までの流れを理解することで、計画的な学習や準備が可能になります。大学生にとって公務員試験は長期間の対策が必要なため、早めに全体像を把握することが合格への第一歩です。
ここでは試験1年以上前から合格後までの各段階で取り組むべき内容を解説します。
- 試験1年以上前:志望先の情報収集
- 試験1年前:学習計画と試験科目の確認
- 半年前:重点分野の強化と過去問演習
- 試験直前期:模擬試験と総仕上げ
- 出願〜試験当日:手続きと当日の準備
- 合格後:面接対策と研修スケジュール確認
①試験1年以上前:志望先の情報収集
この時期は志望職種や自治体の特徴を把握し、自分の適性やキャリアの方向性を考える大切な段階です。
早い段階で情報を集めることで、受験科目や求められる人物像を理解でき、勉強の方針を定めやすくなります。説明会やインターン、自治体のホームページを活用して最新情報を得ましょう。
収集した内容をもとに計画を立てれば、効率的な学習を始めやすいでしょう。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
②試験1年前:学習計画と試験科目の確認
試験1年前には本格的な学習を開始しましょう。志望先ごとの試験科目を調べ、自分の得意不得意を分析して優先順位を決めることが大切です。
週単位で目標を設定し、進捗を振り返る習慣をつけると効果的。市販の問題集や過去問を使って出題傾向を把握し、必要に応じて予備校や通信講座の利用も検討しましょう。
早い段階での準備が後の安心につながります。
③半年前:重点分野の強化と過去問演習
試験まで半年となると、基礎固めから実践的な演習に学習の重点を移しましょう。特に頻出分野や苦手分野を徹底的に強化すると、点数の底上げが期待できます。
過去問を繰り返し解き、出題パターンや時間配分のコツをつかむことが重要です。本番を意識した時間内での演習を繰り返せば、当日の緊張にも対応しやすくなります。
今までの学習を振り返り、弱点を早めに補強してください。
④試験直前期:模擬試験と総仕上げ
直前期は知識の詰め込みよりも実践力の確認に重点を置きましょう。模擬試験を受験して、本番に近い環境で問題を解く練習を重ねるとよいです。
間違えた問題は必ず解説を確認し、理解を深めることで弱点を克服できます。生活リズムを整え、体調管理にも気を配ると試験当日に最高のパフォーマンスを発揮できるでしょう。
気分転換の時間も意識的に取り入れてください。
⑤出願〜試験当日:手続きと当日の準備
出願から試験当日までの期間は、細かな準備が合否に直結します。提出書類の締切や内容を必ず確認し、余裕を持って手続きを進めましょう。
受験票や会場の場所、持ち物の確認も忘れずに行ってください。移動手段や食事の準備など、当日を想定したシミュレーションをしておくと安心です。
前日までに準備を終えることで落ち着いて試験に臨めます。
⑥合格後:面接対策と研修スケジュール確認
筆記試験合格後は、人物評価を中心とした面接や討論への準備が重要になります。志望動機や自己PRを整理し、模擬面接などを通して自信をつけましょう。
配属先や研修スケジュールの確認も欠かせません。就職後の業務や職場の雰囲気を事前に把握しておくことで、スムーズに新しい環境に適応しやすくなります。合格後も計画的に行動していきましょう。
面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?
一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。
大学生におすすめな公務員試験の勉強法

大学生が公務員試験に合格するためには、生活スタイルや学習習慣に合った方法を選ぶことが重要です。
ここでは、独学や予備校、通信講座などの代表的な勉強法を比較し、それぞれの特徴や取り入れ方を解説します。
- 独学での勉強法
- 予備校での勉強法
- 通信講座での勉強法
- 大学講座での勉強法
- グループでの勉強法
- デジタルツールでの勉強法
①独学での勉強法
独学は費用を抑え、自分のペースで学習できるのが魅力です。市販の教材や過去問題集を活用し、出題傾向を分析しながら計画的に進めると効果的でしょう。
まず試験日から逆算して週ごとの学習計画を立てると、無理なく進められます。さらに、苦手科目の把握や定期的な模試の受験で実力を確認することが大切です。
独学は主体性を高める学習法でもあるため、自ら計画を立てて実行できる人に向いています。学習進度を可視化したりアプリで管理すると、継続のモチベーションも保ちやすいでしょう。
②予備校での勉強法
予備校は専門講師の授業を受けながら効率的に学べる手段です。体系的なカリキュラムが整っており、論文や面接対策なども一貫して学べます。
同じ目標を持つ仲間と学習できる環境は刺激になり、やる気を維持しやすいでしょう。費用はかかりますが、疑問をすぐ解決できるサポートや試験日から逆算した学習計画の提案は大きな利点です。
模擬試験や進捗確認も行えるため、最短ルートで合格を目指す人には有効な方法といえます。
③通信講座での勉強法
通信講座は自宅で学習を進められる柔軟な方法です。映像授業や教材で体系的に学び、通学時間を省けるのが魅力でしょう。スマホやタブレットを使えば、移動時間や隙間時間の活用も可能です。
質問対応や進捗管理機能が整った講座を選ぶと独学の不安を軽減できます。特に、アルバイトやゼミ活動と並行して勉強したい人には適した選択肢です。
自分のペースで学べるため、計画性を持って取り組むことが成功のポイントになります。
④大学講座での勉強法
大学内の公務員講座は費用が比較的安く、学内施設やキャリアセンターの支援も受けられます。講師が試験傾向を熟知しており、初めて試験勉強を始める学生でも基礎を固めやすいのが特徴です。
友人と一緒に学べるため、やる気を維持しやすいでしょう。ただし、講座数や開講時期は限られているため、早めに情報収集することをおすすめします。
大学生活の一環として無理なく学びたい人には適した選択肢です。
⑤グループでの勉強法
グループ学習は仲間と協力しながら知識を深められるのが利点です。お互いの得意分野を教え合うことで理解が定着しやすくなります。
定期的に勉強会を開くことで計画的に進められ、モチベーションも維持しやすいでしょう。ただし、周囲の進度に影響を受けやすい面もあるため、事前に目標やルールを決めることが大切です。
特に面接対策の練習相手としても有効で、実践的な力を磨けます。
⑥デジタルツールでの勉強法
デジタルツールを使った学習は効率性の高さが魅力です。過去問アプリや暗記アプリを活用すれば、移動時間やちょっとした隙間時間でも学習が進められます。
AIによる弱点分析や学習計画機能を備えたサービスもあり、自分に合った勉強法を見つけやすいでしょう。紙の教材と併用して理解を深めることで、より効果的な学習が可能です。
積極的にデジタルツールを取り入れることで、忙しい大学生活でも効率的に試験対策が行えます。
大学生向け公務員予備校・通信講座

公務員試験対策を効率よく進めるためには、自分に合った予備校や通信講座を選ぶことが大切です。
大学生は学業やアルバイトと両立する必要があるため、柔軟な学習スタイルや充実したサポート体制が合否を左右します。ここでは通学型予備校と通信講座の人気の選択肢を紹介します。
- 資格の大原
- TAC
- 東京アカデミー
- ユーキャン
- 実務教育出版
- 資格スクール大栄
①資格の大原
資格の大原は長年の指導実績を誇り、体系的なカリキュラムや豊富な模試で人気があります。基礎から応用まで段階的に学べるため、初めて公務員試験を受ける学生でも安心です。
個別相談や質問対応も充実しており、学習のつまずきを解消しやすいでしょう。全国各地に校舎があるため、通学のしやすさも魅力です。
②TAC
TACは資格取得の総合スクールとして知られ、公務員試験にも多彩なコースを展開しています。出題傾向を反映した講義や科目別の丁寧な指導が強みで、効率的な学習が可能です。
試験直前期には模試や論文対策が充実しており、合格を目指す受験生に安心感を与えます。講義の質の高さを重視する学生に向いているでしょう。
③東京アカデミー
東京アカデミーは初学者向けのわかりやすい授業が評価されています。基礎を徹底的に固めるカリキュラムが特徴で、着実な学力向上を目指す学生に最適です。
少人数制の授業や個別相談を取り入れ、学習ペースを維持しやすい体制を整えています。全国各地に教室があり、地方在住の学生にも利用しやすい環境です。
④ユーキャン
ユーキャンは初心者でも取り組みやすい教材と動画講義で知られています。短時間でも効率的に学べる工夫がされており、スマホやタブレットを使った学習も可能です。
質問サービスや添削指導などのサポートも手厚く、独学が不安な学生でも安心して学習を進められるでしょう。
⑤実務教育出版
実務教育出版は公務員試験の専門書籍でも有名で、通信講座でもそのノウハウを活かした教材を提供しています。出題傾向に沿った解説や模擬問題が豊富で、基礎から応用まで対応可能です。
教材の質の高さと長年の実績が信頼を集め、幅広い受験生に選ばれています。
⑥資格スクール大栄
資格スクール大栄の通信講座は、個別の学習計画や定期的なサポート体制が魅力です。オンラインでも講師に相談でき、自分のペースを尊重しながら学習を進められます。
通学型と併用できるハイブリッド型サービスもあり、状況に応じて柔軟に学び方を変えられる点も特徴です。
公務員試験に関するよくある質問

就活中の大学生が気になる公務員試験の疑問をまとめました。試験の難易度や合格率、学歴の有利不利、併願の可否、合格後の待遇やキャリアなど、進路選択の参考になる情報を詳しく解説します。
- 公務員試験の難易度や合格率は?
- 公務員試験と民間企業の併願はできる?
- 学歴や学部は公務員試験に有利?
- 公務員試験に落ちたらどうする?
- 公務員の給与や福利厚生はどうなっている?
- 公務員採用後のキャリアパスは?
①公務員試験の難易度や合格率は?
公務員試験は幅広い知識が求められるため、対策の有無で難易度の感じ方が大きく異なるでしょう。
国家公務員や地方公務員試験は採用人数が限られ、筆記や面接、適性検査など総合的な評価が行われるため、全体の合格率は20%前後とされています。
国家総合職はさらに難関で、大学1年や2年から計画的に勉強を始める人も少なくありません。
ただし出題範囲や試験形式は大きく変わらないため、正しい勉強方法を早期に取り入れれば十分合格を狙えます。
過去問や模試を積極的に活用し、効率的な学習スケジュールを立てることが合格への近道でしょう。
②公務員試験と民間企業の併願はできる?
公務員試験を受験しながら民間企業への就職活動を並行することは可能です。多くの学生が併願しており、進路の幅を広げる方法として一般的でしょう。
ただし公務員試験は筆記対策に時間がかかるため、企業説明会や面接との両立が課題になることもあります。
併願を成功させるためには、試験日程や企業の選考スケジュールを事前に確認し、優先順位を明確に決めておくことが重要です。
また、企業面接では志望動機を柔軟に調整し、公務員志望を必要以上に強調しない工夫も必要でしょう。計画的なスケジュール管理で過密な日程を乗り切る力が求められます。
就活では、多くの企業にエントリーしますが、その際の自分がエントリーした選考管理に苦戦する就活生が非常に多いです。大学の授業もあるので、スケジュール管理が大変になりますよね。
そこで就活マガジン編集部では、忙しくても簡単にできる「選考管理シート」を無料配布しています!多くの企業選考の管理を楽に行い、内定獲得を目指しましょう!
③学歴や学部は公務員試験に有利?
公務員試験は学歴や学部で出題範囲や評価基準が変わらず、誰でも公平に挑戦できます。
難関大学や特定学部出身だからといって直接有利になることはほとんどありませんが、法学や経済学など関連分野を学んでいる人は一部科目で理解が早まることも。
採用後はポテンシャルや適性が重視されるため、昇進や異動も学歴に左右されにくい傾向があります。重要なのは、自分の専攻に関係なく計画的に試験対策を行う姿勢です。
面接では大学時代の学びや経験をどのように公務員として活かせるかを明確に語れるよう準備しておくことが大切でしょう。
④公務員試験に落ちたらどうする?
公務員試験は倍率が高いため、一度の挑戦で合格できない人も珍しくありません。しかし、不合格でも進路は多く、柔軟な選択が可能。
大学生であれば、民間企業への就職活動を進めて新卒枠でキャリアを積む道がありますし、卒業後に社会人経験を経て再挑戦するケースも多いです。
非常勤職員や契約職員として役所で働き、現場経験を積んで次回試験に挑む人もいます。早期に自分の方向性を整理し、目標を持って行動することが重要です。
落ちた経験を次に活かすためにも、模試や過去問で弱点を分析し、効率的な再挑戦を計画してください。
⑤公務員の給与や福利厚生はどうなっている?
公務員は安定した給与体系と手厚い福利厚生が魅力です。基本給は人事院勧告に基づき決定され、勤続年数や年齢に応じて昇給します。賞与も年2回支給され、長期的に安定した収入を得られるでしょう。
福利厚生は共済組合制度を中心に医療費補助や住宅手当、育児・介護休暇などが整っており、ライフイベントに対応しやすい職場環境です。
一方で、初任給は大企業と比較するとやや低めのこともありますが、安定や長期的な働きやすさを重視する人にとっては魅力的な選択肢でしょう。
そのため、計画的なキャリア形成を考える学生に向いているといえますよ。
⑥公務員採用後のキャリアパスは?
公務員は採用後も幅広いキャリアパスを選べる点が特徴です。行政職や技術職など職種ごとに専門性を高める道や、管理職を目指すマネジメントの道があります。
国家公務員の場合は中央省庁勤務の後に地方出向を経験するなど、幅広い知識やスキルを磨けるでしょう。地方公務員も異動や部署ローテーションを通じてさまざまな分野で活躍できます。
昇進は年功序列ではなく成果評価が中心であり、近年は研修制度や留学支援制度も整備されていますよ。長期的なキャリア形成を見据え、自分で道を切り開いていける点が魅力です。
大学生の公務員試験完全ガイドの総括

大学生が公務員を目指すなら、早期から計画的な対策を取ることが合格への近道です。本記事では、公務員試験の出題範囲や難易度、学習開始の適切なタイミング、学年別の勉強法を整理しました。
さらに、予備校・通信講座の活用やスケジュールの立て方、よくある疑問も網羅しています。情報収集から面接準備まで一貫して取り組むことで、自信を持って試験に臨めるでしょう。
自分に合った勉強法を見極め、大学生活との両立を意識した戦略を立てれば、公務員試験の合格は十分可能です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













