銀行員の仕事内容とは?三大業務や職種ごとの特徴を詳しく解説
「銀行員って実際にはどんな仕事をしているんだろう?」
就職活動で人気の高い職業の一つである銀行員ですが、日々の業務内容や求められる役割について詳しく知っている人は意外と少ないかもしれません。
銀行には「預金」「融資」「為替」という三大業務があり、さらに総合職・一般職・専門職などの職種によっても仕事内容は大きく異なります。
本記事では、銀行員の基本的な役割から三大業務の仕組み、職種ごとの仕事内容、さらには1日の流れやキャリアパスまでを徹底解説します。
資格や適性についても紹介するので、「銀行員として働くイメージをつかみたい」「金融業界を目指したい」という方はぜひ参考にしてくださいね。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ESをAIに丸投げ|LINEで完結
- 完全無料でESを簡単作成
- 2赤ペンESで添削依頼|無料
- 就活のプロが丁寧に添削してくれる
- 3志望動機テンプレシート|簡単作成
- カンタンに志望動機が書ける!
- 4自己PR自動作成|テンプレ
- あなたの自己PRを代わりに作成
- 5企業・業界分析シート|徹底分析
- 企業比較や選考管理もできる
銀行員とは?

銀行員とは、預金・融資・為替といった三大業務を軸に、個人や企業の経済活動を支える職業です。社会インフラを担う役割も大きく、安定性と責任感が求められます。
就活生にとっては安定したキャリアの選択肢でありながらも、社会の信頼を背負う職業である点を理解することが大切でしょう。
ここでは銀行員の基本的な役割や社会的責任、さらに銀行の種類や特徴について詳しく解説します。
- 銀行員の基本的な役割
- 銀行員の社会的責任
- 銀行の種類と特徴
①銀行員の基本的な役割
銀行員の基本的な役割は、人や企業から資金を預かり、それを必要とする相手に適切に融資することです。お金の流れを円滑にする仲介者として機能し、社会や経済を支える基盤となっています。
例えば、学生が将来のために学費を貯金する一方で、企業は新しい事業を展開するために融資を受ける場面があります。このように、異なるニーズを結び付けて循環させるのが銀行員の仕事でしょう。
預金の安全を守りつつ、融資先の信用を慎重に見極める力が求められるため、単なる事務作業にとどまらない責任の重い仕事といえます。
地域経済を支えることにもつながり、結果的に人々の生活を守る役割を果たします。
就活を考える学生にとっては、金融知識の習得だけでなく「人の暮らしを支える使命を担えるかどうか」を意識して取り組むことが大切です。
②銀行員の社会的責任
銀行員には、社会全体の信頼を守るという極めて大きな責任があります。銀行は顧客から資産を預かり、安全に管理する立場にあるため、判断の誤りや不正は社会に甚大な影響を及ぼしかねません。
例えば、融資を安易に決定してしまえば、資金が回収できず預金者に不安を与える可能性もあります。だからこそ銀行員は常にリスクを分析し、慎重かつ誠実に対応することが欠かせません。
また災害や不況といった非常時には、地域へ資金を供給して人々の生活を支える役割を担います。こうした責任の重さは、他の職業には見られない特徴でしょう。
就職を考える学生にとって、銀行員は安定した職業であると同時に「人々の生活基盤を守る使命を果たす存在」であることを理解する必要があります。
責任感をやりがいとして受け止め、信頼される人材を目指す姿勢が重要です。
③銀行の種類と特徴
銀行には大きく分けて都市銀行・地方銀行・信用金庫があり、それぞれの役割や特徴に違いがあります。都市銀行は全国規模で展開し、大企業や国際的な取引を多く扱うのが特徴です。
一方で地方銀行は地域密着型で、中小企業や地元の人々に寄り添う金融サービスを展開しています。さらに信用金庫は営利を目的とせず、地域社会の発展を支える使命を持つ点で特異な存在です。
例えば、都市銀行では世界経済の動向を学びながらスケールの大きな業務に携われる一方、地方銀行では地域と深く関わりながら生活に密着したサポートを実感できるでしょう。
就職活動を進める学生は「安定しているかどうか」だけでなく、自分がどのような環境で力を発揮したいのかを考える必要があります。
銀行の種類ごとに求められるスキルやキャリアパスは異なるため、志望動機を考える際には特徴をしっかり理解することが大切です。
銀行員になるには?

銀行員を目指すためには、学業から実務経験まで段階的に準備を重ねることが欠かせません。大学や専門学校での学びを基盤に、インターンシップや採用試験を通じて実力を確かめる流れが一般的です。
さらに、面接では自らの適性を示し、資格を取得することで信頼性を高められるでしょう。就職活動の一歩一歩を意識的に進めることで、内定獲得に近づけます。
ここでは、それぞれのステップを具体的に解説します。
- 大学や専門学校で学ぶ
- インターンシップに参加する
- 就職試験や筆記試験を受ける
- 面接で適性を示す
- 必要な資格を取得する
①大学や専門学校で学ぶ
銀行員を目指す最初の段階は、大学や専門学校で基礎知識をしっかりと身につけることです。特に経済学や経営学、会計学は金融業務に直結するため大きな強みになります。
数字に強い人材は融資や為替業務で重宝されやすく、知識の積み重ねは将来の判断力に直結します。
また、金融以外の幅広い分野を学んでおくと、お客様との会話の中で話題の引き出しが増え、信頼関係を築きやすくなるでしょう。
就職活動においては、専攻内容を単に説明するだけでなく「学んだことをどう銀行業務に結びつけられるか」を語れるかどうかが重要です。
自分の学びを実践的に説明できる学生は、採用担当者からの評価も高まります。
②インターンシップに参加する
インターンシップは、銀行業務を実際に体験できる数少ないチャンスです。現場の雰囲気や接客スキルを直接学べるだけでなく、職場の空気感や求められる姿勢を知ることもできます。
参加することで「自分が銀行員に向いているかどうか」を確かめられるのは大きなメリットです。
さらに、そこで得た学びや気づきをエントリーシートや面接で具体的に語れば、採用担当者に鮮明な印象を与えられるでしょう。
銀行側もインターン参加者を将来の採用候補として見ている場合が多く、真剣に取り組むことで就活全体を有利に進められます。実際に現場を体験した経験は、他の学生との差を生む武器になります。
③就職試験や筆記試験を受ける
銀行の採用試験では、筆記試験も合格のために重要です。一般常識や数的処理に加えて、SPIなどの適性検査を通じて基礎学力や論理的思考力が確認されます。
これらは単なる知識の暗記ではなく、業務を遂行するうえでの柔軟な判断力や計算力を見極める目的があります。
準備不足のまま臨むと、本来の実力を発揮できずに面接へ進めない可能性もあるでしょう。だからこそ、過去問題や模擬試験を繰り返し解き、時間配分や回答の精度を高めることが欠かせません。
特に就活本番の時期は忙しくなるため、早めに計画を立てて学習を進めることがポイントです。筆記試験を突破できれば、面接でアピールするチャンスを得られます。
④面接で適性を示す
面接は、銀行員としての適性や人柄を見極める大切な場です。銀行はお客様の大切なお金を扱うため、誠実さや信頼性が何よりも重視されます。
また、業務はチームで進めることが多いため、協調性やコミュニケーション力も欠かせません。ここでは、自分の経験を具体的なエピソードとして話し、銀行業務にどう活かせるかを示すことが求められます。
例えば、ゼミ活動で培った分析力やアルバイトで磨いた接客スキルを紹介すると説得力が増すでしょう。
さらに「なぜ自分が銀行に適しているのか」を論理的に語れると、採用担当者の納得感も高まります。自分の強みを業務内容と結びつける意識を持つことが、選考突破の鍵になります。
⑤必要な資格を取得する
銀行員に必須の資格はありませんが、持っていると有利に働く資格は多いです。
特に日商簿記やファイナンシャル・プランナー(FP)は、金融や会計の基礎知識を証明できるため、就活で高く評価されやすいです。
さらに、入社後には証券外務員資格が必要になることが多く、あらかじめ学習を進めておけば研修をスムーズに乗り切れます。
資格は単なる勉強の成果ではなく「努力を継続できる姿勢」を示す証でもあり、即戦力として期待されるアピール材料にもなります。
学生のうちに計画的に資格取得を目指すことで、自信を持って選考に臨めるでしょう。努力を形として残す資格は、就活の大きな武器となります。
銀行の三大業務

銀行の三大業務は「預金」「融資」「為替」に大きく分けられ、それぞれが金融機関の信頼を支える柱です。
就活生にとっては、この3つが社会や経済にどのように役立ち、銀行員としての役割をどう形作っているのかを理解することが大切です。
ここでは三大業務の特徴や意義を紹介し、働く姿をイメージできるように整理しました。
- 預金業務
- 融資業務
- 為替業務
①預金業務
預金業務は銀行の出発点であり、顧客から資金を預かることで他の業務が成立します。銀行にとっては資金を安定的に調達する手段であり、顧客にとっては資産を安全に保管する安心の仕組みです。
もし十分な預金が集められなければ、融資や為替といった業務は成り立たないため、預金は銀行経営の基盤といえるでしょう。
就活生として注目すべきは、預金業務が単なる資産の保管にとどまらず、地域や経済の安定を支える社会的な役割を果たしている点です。
銀行員はお客様の信頼を直接預かり、その信頼をもとに資金を次の活動へと循環させます。
そのためには正確な処理や細やかな気配りが不可欠であり、一つひとつの対応が銀行全体の信用力を左右することもあります。
預金業務は地味に見えても、すべての金融活動を支える土台であり、就活生が銀行員の使命感を理解する入り口になるでしょう。
②融資業務
融資業務は、銀行が預かった資金を企業や個人に貸し出し、経済の発展や人々の生活を後押しする仕事です。
住宅ローンや教育ローン、企業の設備投資資金など、多様な場面で利用され、利用者の人生や事業に大きな影響を与えます。
銀行員が融資を担当する際に重要なのは、単に資金を提供するだけでなく、返済能力や事業計画を冷静に判断することです。就活生が見落としがちな点は、融資はリスク管理の要素が強いということです。
貸し出した資金が回収できなければ銀行の経営に直結するため、顧客の夢や挑戦を応援しつつも、慎重で的確な判断力が求められます。
そのため銀行員には、金融知識に加えてデータを分析する力、将来の展望を読み取る力、さらに顧客の話を丁寧に聞き取るコミュニケーション力が欠かせません。
社会全体の成長や地域経済の活性化に貢献する仕事であることを意識すると、銀行員としての役割の大きさを実感できるでしょう。
③為替業務
為替業務は、資金のやり取りをスムーズに行うための仕組みを提供し、国内外での資金移動を支えています。
代表的な例として振込や送金、小切手や手形の決済があり、さらに国際取引では外貨の両替や外国送金なども含まれます。
これらは個人の生活に欠かせないだけでなく、企業活動や貿易においても極めて重要です。為替業務の価値は、資金移動を安全かつ迅速に実現することで、経済全体の流れを止めないことにあります。
就活生が意識したいのは、グローバル化の進展により為替の役割が急速に拡大している点です。国際貿易や海外進出が進む中、為替の正確さとスピードは銀行の信用そのものを左右します。
銀行員は日常的な取引を正確に処理する一方で、不正やリスクを防ぐ役割も担い、細心の注意が必要です。表舞台では目立ちにくいものの、為替業務は社会や経済の基盤を裏から支える存在です。
就活生にとっては、銀行員が直接目に見えない形で社会を支えている点を理解する良いきっかけになるでしょう。為替業務を深く学ぶことは、金融全体の仕組みを理解するうえで大きな助けになります。
銀行の一般職の仕事内容

銀行の一般職は、お客さまと直接やり取りしながら、日々の業務を正確に支える役割を担っています。派手さはないものの、確実に仕事を積み重ねる力が求められ、社会人としての基礎を固める場でもあります。
ここでは一般職の代表的な業務内容を詳しく解説し、就活生が自分に合うかどうかを判断できるようにまとめました。
- 窓口業務
- 入出金や口座管理
- 金融商品の案内
- 書類作成や事務処理
- 顧客対応
①窓口業務
窓口業務は銀行の「顔」として来店したお客さまに最初に対応する仕事です。口座開設や各種手続きの案内を担当し、誤りなく処理することが何よりも大切になります。
なぜなら手続きの誤りは信頼を失うだけでなく、場合によっては大きな損害につながるからです。新人であっても責任を持って業務にあたることが多く、最初から大きな緊張感を伴います。
例えば高齢のお客さまには時間をかけて丁寧に説明する一方、混雑時には効率的に対応しなければなりません。このように状況に応じて対応を変える柔軟さが欠かせません。
就活生にとっては、対人スキルや気配りの力を伸ばせる業務であり、自分が人と向き合うことにやりがいを持てるかを考えるきっかけにもなるでしょう。
②入出金や口座管理
入出金や口座管理は銀行の基本であり、日常的に最も多く行われる業務の一つです。現金や残高を正確に扱う力が求められ、数字に強いだけでなく、小さなミスも見逃さない集中力が不可欠です。
金額の誤りは顧客とのトラブルや大きな損害につながりかねず、責任は非常に大きくなります。その一方で、日々正確な処理を積み重ねることで「安心して任せられる人材」として信頼を得られるでしょう。
例えばATMの障害対応や、不明な入金の調査を担当する際には、迅速に状況を整理し、最適な対応を取る必要があります。
このような経験は金融機関に限らず社会で通用する基礎力を養うものです。几帳面さや誠実さに自信のある学生は、自分の長所を活かせる業務だと感じられるでしょう。
③金融商品の案内
金融商品の案内では、お客さまに保険や投資信託などのサービスを紹介し、ライフスタイルや将来設計に合った選択を後押しします。
一般職の場合、直接の販売ノルマは少ないですが、商品の基本説明や資料の手渡しを任されることが多く、信頼関係を築く第一歩となります。
銀行は単にお金を預かる場所ではなく、お客さまの資産形成や生活の安定を支える存在でもあるため、こうした案内業務は重要な意味を持ちます。
例えば退職金の運用を検討している高齢者にはリスクを抑えた商品を、教育資金を準備する家庭には長期的な積立商品を案内するなど、状況に応じた柔軟な説明力が必要です。
この経験を通じて、傾聴力や提案力を磨くことができます。人と関わることが好きな学生にとっては、自分の強みを発揮できるやりがいの大きい分野でしょう。
④書類作成や事務処理
書類作成や事務処理は一見地味に見えますが、銀行業務を滞りなく進めるための欠かせない役割です。契約書や報告書を正確に仕上げる力が求められ、少しの誤字や数字の誤りも許されません。
なぜなら書類は監査や法的効力に直結する場合があり、間違いが大きなリスクになるからです。例えば融資契約の書類を不備なく完成させることは、顧客と銀行双方の安心を守る行為そのものです。
こうした業務を通じて、細部に目を配る力や、期限内に正確に仕事を終える時間管理力が鍛えられます。
学生時代にレポートや課題を誤字なく仕上げる習慣や、締切を守る姿勢を持っている人は特に適性が高いといえるでしょう。地道な作業が苦にならない学生にとっては、強みを発揮できる大切な分野です。
⑤顧客対応
顧客対応は電話やメールを通じて問い合わせや相談に答える業務で、銀行全体の信頼を左右する重要な役割を担います。
ときにはクレームを受けることもありますが、冷静に耳を傾け、誠実に対応する姿勢が欠かせません。顧客の不安を放置すると信頼を失い、銀行全体の評価に悪影響を及ぼすでしょう。
例えば引き落としの遅延やカード紛失の相談を受けた際には、その場で即答できない場合でも、迅速に上司や専門部署に引き継ぐ判断力が必要です。
このような経験を積むことで、柔軟に対応する力や、人と信頼関係を築くコミュニケーション力が自然と身についていきます。
人と誠実に向き合うことに喜びを感じられる学生にとっては、大きな成長を実感できる業務になるはずです。
銀行の総合職の仕事内容

銀行員の総合職は、銀行の中核を担う存在として幅広い業務を担当します。預金や融資にとどまらず、法人や個人への提案営業、経営戦略の立案、さらには海外拠点や専門分野に携わる機会もあります。
就活生にとっては「幅広すぎて自分に合うのか不安」と感じることもあるでしょうが、仕事内容を理解すればキャリアの見通しを立てやすくなります。
加えて、具体的な業務のイメージを持っておくことで、面接やエントリーシートでも説得力のある自己PRにつながるはずです。ここでは、代表的な5つの業務を紹介します。
- 法人営業
- 個人営業
- 融資審査
- 経営戦略や企画を立案
- 海外や専門分野の業務
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①法人営業
法人営業は、企業を相手に資金調達や資産運用を支援する役割です。難しそうに思うかもしれませんが、実際は企業の課題解決を金融面から後押しする仕事といえます。
たとえば新工場建設のための融資提案や、為替リスクに備えた商品紹介などが具体例です。企業の成長に直結するため、やりがいを得やすい業務でしょう。
その一方で、担当企業の経営状況を深く理解する力や責任を引き受ける覚悟も求められます。学生のうちから経済ニュースや企業分析に触れておくと、入社後に大きな強みになります。
また、インターンで企業訪問の経験を積むことで、法人営業の現場を実感でき、入社後の仕事理解も一層深まるでしょう。
②個人営業
個人営業は、個人顧客に向けて預金・投資信託・住宅ローンなどを提案する業務です。窓口対応と異なり、顧客のライフプランに沿ったコンサルティングが中心となります。
たとえば「子どもの教育費を準備したい」「老後資金を運用したい」といった相談に応じる場面が多いでしょう。信頼関係の構築が成果につながるため、人と話すことが好きな学生には向いています。
ただし、生活に関わる大切なお金を扱うため、提案には責任感と慎重さが必要です。自分の提案で顧客の将来を支えられるという達成感を得られるのが魅力です。
さらに、営業目標を達成するために粘り強さや提案力も磨かれるので、将来的にどの職種に進んでも役立つスキルが身につきます。
就活の段階で、アルバイトやサークル活動で培った「信頼を築く力」をアピールできれば、評価にもつながるでしょう。
③融資審査
融資審査は、融資申請に対して返済可能性を見極める重要な業務です。数字を扱うだけでなく、経営計画や収支の妥当性を読み取る力が問われます。
就活生の多くは「堅い仕事」という印象を持つかもしれませんが、銀行のリスクを管理する要の役割を担っています。
慎重すぎると融資が滞り、甘すぎると不良債権の原因となるため、バランス感覚が欠かせません。論理的思考やデータ分析の経験を持つ学生は特に力を発揮できるでしょう。
金融知識が自然に身につくと同時に、銀行の信頼を守る責任を実感できる仕事です。
さらに、融資審査を通じて業界全体の動向や企業の経営状況を学べるため、視野が広がり、将来のキャリア形成にも直結します。
ゼミや研究でデータ分析を行った経験がある学生にとっては、その成果を活かせる具体的な舞台になるはずです。
④経営戦略や企画を立案
経営戦略や企画を立案する業務は、銀行の未来を方向づける大きな役割です。新サービスの開発、デジタル化の推進、店舗網の見直しなど、変化に応じた施策を考える必要があります。
学生にとっては遠い存在のように思えるかもしれませんが、総合職として経験を積んだ後に挑戦できる分野です。
ここでは金融知識だけでなく、市場動向や顧客ニーズを把握するマーケティング力も求められます。成果が銀行全体の成長につながるため、挑戦しがいのある舞台といえるでしょう。
学生のうちから幅広い業界や社会の動きを意識することが第一歩になります。
加えて、アイデアを形にする力や新しいことに挑戦する姿勢が評価されるため、就活時点で「企画や改善に挑戦した経験」を整理しておくと強みになります。
⑤海外や専門分野の業務
海外や専門分野の業務は、グローバル化の中で注目される分野です。海外拠点での勤務や、国際金融・証券業務といった高度な専門性が求められることもあります。
語学力や異文化理解に加えて、国際情勢への関心を高く持つことが欠かせません。就活生には「ハードルが高い」と感じられやすいですが、キャリアの幅を大きく広げられるチャンスでもあります。
海外案件に携わることで視野が広がり、国内では得られない経験を積めるのが魅力です。留学や資格取得などを通じて学生時代から準備を進めれば、専門分野での活躍が現実味を帯びてくるでしょう。
また、海外での経験は将来グローバル人材としての評価にも直結し、企業の成長に貢献できる強力な武器になります。国際社会で挑戦したい学生にとっては、大きなやりがいを感じられる業務だといえます。
銀行でのその他の仕事内容

銀行員には預金・融資・為替といった三大業務以外にも、銀行の安定性や成長を支える重要な仕事が数多くあります。表に出にくい業務ですが、これらが整っていなければ日常の銀行サービスは成り立ちません。
ここでは、システム部門やリスク管理部門、資産運用、調査・企画部門といった専門領域に触れ、就活生が見落としがちな役割を解説します。
これらを知ることで、銀行員の仕事の幅広さを理解し、自分に合うキャリアを見つけやすくなるでしょう。
- システム部門の業務
- リスク管理部門の業務
- 資産運用関連の業務
- 調査・企画部門の業務
①システム部門の業務
銀行のシステム部門は、日常の取引やATM、インターネットバンキングを安全に稼働させる要の存在です。
近年はサイバー攻撃やフィンテックの普及により、強固なセキュリティや新サービスの素早い導入が不可欠でしょう。
もし障害が起これば顧客の信頼を失うため、迅速な対応やバックアップ体制も求められます。就活生にとっては金融知識だけでなく、情報技術やセキュリティの理解があると大きな強みになります。
さらにAIやブロックチェーンといった先端技術の活用も進んでおり、学んできた専門分野を生かせるチャンスが広がっています。
表には出にくい仕事ですが、利用者に安心感を提供し、銀行の基盤を支える極めて重要な役割です。
理系学生やITスキルを活かしたい人にとって、専門性を発揮しながら社会に貢献できる魅力的な分野といえるでしょう。
②リスク管理部門の業務
リスク管理部門は、銀行が直面するさまざまなリスクを数値化・分析し、健全な経営を支える部門です。市場リスクや信用リスク、流動性リスクなどは多岐にわたり、国際基準に基づく管理も必須となります。
見落としがあれば巨額の損失や経営危機につながるため、日々の監視と改善提案が欠かせません。
就活生は経済の動きや金融商品の仕組みを理解し、論理的に物事を考える力が求められることに気づいておくと安心です。
特に統計や数理分析を得意とする学生にとっては活躍の場が多く、将来的には専門的な資格取得を目指す道も開けます。
金融システム全体の安定性を守ることは社会的責任も大きく、知識を武器に信頼を築くことができます。
縁の下の力持ちとして銀行を支えるだけでなく、国際金融の安定にも関わることができるやりがいある仕事です。
③資産運用関連の業務
資産運用関連の業務は、銀行が保有する資金を有効に使い、利益を確保するための重要な分野です。国債や株式、債券など幅広い金融商品に投資し、ポートフォリオを組んで収益とリスクのバランスを取ります。
市場は常に変化するため、世界経済や金融政策の動向を敏感に察知し、素早く判断する力が欠かせません。就活生にとっては、金融市場への関心や日常的に経済ニュースを追う習慣が強みになります。
さらに外国為替や国際金融にも関わる可能性があるため、語学力や国際感覚を磨くことも大切です。単なる利益追求だけでなく、安定的な運用を通じて顧客や地域経済を支える意義があるのも特徴でしょう。
分析力や判断力に加えて責任感が必要となるため、挑戦意欲を持つ人には大きな成長の場となります。数字を使って成果を実感できる点も魅力で、結果を重視したい学生にとってはやりがいの大きい分野です。
④調査・企画部門の業務
調査・企画部門は、銀行の将来を見据えた戦略立案や新しい事業モデルの開発を担当します。市場動向や顧客ニーズを調べ、データに基づいて新サービスや業務改善を提案するのが主な役割です。
ここでは発想力と分析力の両方が試され、金融知識に加えてマーケティングや経営戦略の視点も必要になります。
就活生が理解しておきたいのは、調査だけで終わらせず、実際の施策へと結び付ける力が重視されることです。革新的な企画は競合との差別化を生み、顧客の利便性を高めるきっかけとなります。
さらに、デジタル化やサステナビリティを踏まえた新しい銀行の姿を考える場面も増えており、社会課題の解決にもつながります。
変化の大きい金融業界で、調査・企画部門は未来を切り拓く存在といえるでしょう。
挑戦的な姿勢を持ち、広い視野で物事を考えたい学生にとって、自分のアイデアを形にできる可能性を秘めたやりがいのある職種です。
銀行員の1日の流れ

銀行員の仕事は時間ごとに役割が変わり、規則正しい一日を通じて顧客対応と事務処理を両立しています。
ここでは、出勤から退勤までの流れを確認し、就活生が働く姿を具体的にイメージできるように解説します。
実際の一日を理解することで、入社後のギャップを減らし、自分に合っているかどうかを判断する手助けになるでしょう。
- 出勤しての朝礼実施
- 午前中の窓口対応
- 外回り営業
- 昼休憩
- 午後の事務処理や分析
- 夕方の会議や打ち合わせ
- 退勤前に整理や翌日の準備
①出勤しての朝礼実施
銀行員の一日は朝礼から始まります。朝礼では支店全体で当日の目標や重要事項を共有し、連帯感を強めます。新人にとっては、組織全体の流れを理解できる貴重な場です。
内容には前日の振り返りや注意点も含まれ、知識や姿勢を日々蓄積することにつながります。形式的な時間に見えますが、実際には効率やモチベーションを高める重要なプロセスです。
就活生の中には「どんな場面で自分が成長できるのか」と不安を抱える人もいますが、朝礼は社会人としての意識を養う第一歩になります。
自分の役割を意識しながら参加することで、学びの幅が広がるでしょう。
②午前中の窓口対応
午前中は窓口での顧客対応が中心です。入出金や口座開設など、生活に直結する金融サービスを取り扱うため、正確さとスピードが同時に求められます。
さらに、顧客との最初の接点となるため、信頼関係を築く大切な機会でもあります。一見すると単純な作業に感じるかもしれませんが、銀行全体の信用を支える責任のある業務です。
学生が気づきにくい点として、窓口での対応態度や言葉遣いが銀行のイメージを決定づけることが挙げられます。
細やかな心配りや臨機応変な判断力を磨ける場であり、将来のキャリアに直結する力を養えます。就活生にとって、窓口業務は「接客の基本を学ぶ研修の場」と考えると理解しやすいでしょう。
③外回り営業
法人や個人顧客を訪問する外回り営業も重要です。融資や投資商品の提案を通じて顧客の課題解決を支援するのが主な役割です。
」営業というと「売り込み」の印象を持つ学生が多いですが、銀行員の場合は顧客の課題を丁寧に聞き取り、最適な解決策を提示することが求められます。
確かに成果が数字に表れるためプレッシャーを感じやすい場面もありますが、その分やりがいも大きいです。地域の企業や個人と信頼関係を築き、長期的に伴走できる点は銀行ならではの特徴といえます。
外回りを通じて得られる傾聴力や提案力は、学生が将来どの職種に進んでも役立つスキルです。挑戦の場と捉えることで、自分を大きく成長させられるでしょう。
④昼休憩
昼休憩は午前中の業務で集中した頭と体をリフレッシュする大切な時間です。単なる休み時間と思われがちですが、実際には同僚と交流したり情報交換を行ったりする場としての役割も果たします。
雑談を通じて先輩から仕事のコツを学んだり、相談をすることで悩みを解決できることもあります。さらに午後の仕事へ切り替えるための準備時間としても機能し、効率を高めるためには欠かせません。
学生が意識すべきなのは「ただ休む」のではなく「次の仕事に備える」姿勢です。昼休憩の使い方次第で、一日のパフォーマンスに差が出るでしょう。
働き方の工夫を学べる場として、就活生にも参考になる部分が多いはずです。
⑤午後の事務処理や分析
午後は午前中に発生した取引や顧客対応に関する事務処理を行います。伝票整理やデータ入力はもちろん、数字の分析によって翌日の戦略を立てるための材料を整えることも大切な役割です。
事務処理というと裏方の単純作業のように思われがちですが、銀行の信頼を根本から支える基盤であり、正確さが何より重要です。
わずかな入力ミスでも大きなトラブルにつながるため、責任感と集中力が不可欠です。また、分析業務を通じて得られる情報は、営業活動や顧客提案の質を高める貴重な資源となります。
就活生にとっては「目立たない業務ほど組織全体を動かす要」と理解すると、銀行員の仕事の奥深さを実感できるでしょう。
⑥夕方の会議や打ち合わせ
夕方には支店内で会議や打ち合わせが開かれます。ここで当日の成果や課題を共有し、翌日の方針を確認します。
会議は「時間がかかるだけ」と思う人もいますが、実際には全員の意識を統一し、組織としての方向性を明確にするための欠かせない場です。
新人にとっては先輩の発言や報告から実務の進め方や課題解決の方法を学べる大きなチャンスになります。また、自分の小さな行動が全体の成果にどうつながっているかを実感できるのもこの時間です。
会議を通じて協働意識を強めることで、自分の役割を理解しやすくなり、仕事に対するやりがいも増すでしょう。就活生にとっては「組織全体で成果を生み出す仕組み」を知る場と捉えることが大切です。
⑦退勤前に整理や翌日の準備
一日の終わりにはデスク周りの整理や翌日の準備を行います。これは単なる片付けではなく、翌日の業務をスムーズに始めるための仕込みです。
勤務が終わればすぐ帰れると思う人もいますが、実際にはスケジュールや資料を整える時間が欠かせません。こうした段取りを整えることで、翌日のミスを防ぎ、余裕を持ったスタートが切れるのです。
習慣的に準備を行うことは、社会人としての信頼を高める行動でもあります。さらに「次の日の自分を助ける」という意識を持つことで、長期的に効率の良い働き方を実現できます。
就活生にとっては、退勤前のひと手間が自己管理力を育てる重要な習慣だと理解すると良いでしょう。
銀行員のキャリアパス

銀行員として働いた後にどのような道が開けるのかは、就活生にとって将来を考えるうえで大きな関心ごとです。
キャリアパスは個人の適性や希望によって多様に分かれ、営業から本部、管理職、専門職、国際業務、さらには転職市場での活躍まで選択肢は広がっています。
自分の強みをどの方向に伸ばせるかを理解することは、就活での志望動機づくりにも直結します。ここでは代表的な進路を整理して紹介します。
- 営業職から本部へキャリアアップする
- 管理職へ昇進する
- 専門職としてキャリアを形成する
- 海外勤務や国際業務に挑戦する
- 転職市場で活躍する
①営業職から本部へキャリアアップする
営業から本部へ移る道は、多くの銀行員が目指すキャリアの1つです。営業で培った顧客対応力や数字に向き合う姿勢は、本部での商品企画やリスク管理に直結します。
特に現場経験を持つ人は支店の実情を理解した施策を立案できるため、本部で即戦力として重宝されます。また、顧客目線を反映させた施策は説得力を持ち、現場と本部の橋渡し役としての価値も高まります。
ただし、営業のように成果が数字で明確に表れにくいため、自ら積極的に取り組みを発信し、成果をアピールする姿勢が欠かせません。
就活生にとっては「営業経験を活かして次の舞台で組織に貢献できる人材」になれることが、本部キャリアの魅力と言えるでしょう。
②管理職へ昇進する
銀行員としての典型的な進路は、支店や部署での管理職への昇進です。プレイヤーとして成果を上げ続けた人は、部下の育成や店舗全体の運営を任されます。
管理職に求められるのは、数字の達成だけでなく人を動かす力です。部下のモチベーションを高め、チーム全体の成果につなげられるかが評価の鍵となります。
銀行は組織規模が大きく、人材の多様性も豊かです。その中で信頼関係を築きながら組織をまとめる力が重要になります。
一方で、プレイヤー時代のように自分の努力だけで結果を出せるわけではなく、視点を「自分」から「組織」へ切り替える必要があります。
就活生が管理職を目指すなら、早い段階からリーダーシップや協調性を磨いておくと将来役立つでしょう。
③専門職としてキャリアを形成する
営業や管理職以外に、専門職としてキャリアを築く道もあります。たとえば、証券アナリストやファイナンシャルプランナー、ITシステム担当など、専門知識を武器にするポジションです。
こうした職種では資格取得や学習の継続が必須であり、常に最新の知識を身につける努力が求められます。専門職はスペシャリストとして社内外から信頼を得やすく、キャリアの安定につながりやすいでしょう。
加えて、特定分野を深く極めることで、組織内での存在感が増し、自分にしかできない仕事を任されることも増えていきます。
ただし、ゼネラリストのように幅広い異動は期待しにくいため、進路を選ぶ際は「専門性を高めることで将来どう成長したいか」を考えておくことが大切です。
学生のうちに関心分野を意識しておけば、キャリア形成の選択肢が広がります。
④海外勤務や国際業務に挑戦する
グローバル化の進展に伴い、海外勤務や国際業務に挑戦する道も魅力的です。現地法人や海外支店での勤務では、国際金融や現地企業との取引に携わり、幅広い視野とスキルを身につけられます。
語学力はもちろん、異文化への柔軟な対応力が欠かせません。若いうちから英語学習や国際業務への関心を示しておくと、チャンスを得やすくなります。
海外経験を積んだ人は、その後国内でもグローバルな案件を任されることが多く、キャリア全体の価値が大きく高まります。ただし、文化や生活習慣の違いに適応する力も必要です。
就活生の立場からすれば、国際的な舞台で働く経験は大きなやりがいとなり、自分のキャリアの幅を大きく広げる可能性を秘めているでしょう。
⑤転職市場で活躍する
銀行員として培った経験は、転職市場においても高く評価されます。金融知識や数値管理力、リスクマネジメント力は、証券会社や保険会社だけでなく、一般企業の財務部門でも求められています。
さらに、顧客との信頼関係を築いた経験は異業種でも応用しやすいでしょう。ただし、転職を考える際には「なぜ銀行から次の業界へ進むのか」を明確にする必要があります。
志望理由を整理し、転職先企業の課題やニーズと結びつけて説明できれば、強みとしてアピール可能です。転職は新しい挑戦であると同時に、自分のキャリアを再構築する機会でもあります。
就活生にとっては「銀行員としての経験が将来どのように他業界に生きるか」をイメージしておくと、進路選びの参考になるでしょう。
銀行員に向いている人

銀行員の仕事は幅広く、社会的責任も大きいため、適性のある人材が求められます。金融や経済に関心を持ち、責任感や協調性を兼ね備えている人は特に向いているでしょう。
加えて、自分の強みをどのように銀行員の仕事に活かせるかを考えることが、就活において差をつけるポイントになります。ここでは、銀行員に向いている人物像を具体的に紹介します。
- 金融や経済に興味を持つ人
- 責任感が強い人
- チームワークを重視できる人
- 数字に強い人
- 柔軟に対応できる人
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
①金融や経済に興味を持つ人
銀行員に向いている人の特徴として、まず金融や経済に関心を持つ姿勢が大切です。銀行の業務は単なる預金や融資だけではなく、景気動向や為替の変化、企業の経営状況などと常に結びついています。
興味があれば新しい知識を積極的に学び、社会の変化に合わせた判断力も養えるでしょう。反対に関心が薄いと知識が表面的になり、顧客との会話や提案に深みが欠けてしまいます。
日頃から経済ニュースに触れたり、投資の仕組みに挑戦したりすることは自己成長につながり、面接でも好印象を与えられます。
興味を持って学び続ける姿勢は、長期的に銀行員として活躍するための大きな武器になるでしょう。
②責任感が強い人
銀行員の仕事はお客様の大切なお金を預かるため、非常に高い責任感が求められます。少しの不注意でも信用を失う可能性があり、細かい確認を怠らない姿勢が必要です。
責任感が強い人は与えられた業務を着実にこなし、突発的なトラブルが起きても誠実に対応できるため、上司や顧客から信頼を集めやすいでしょう。
一方で、責任を重く捉えすぎると自分を追い込み、疲弊してしまうこともあります。冷静に物事を判断し、周囲と相談しながら責任を果たすバランス感覚が大切です。
就活の場面では「自分の責任でやり遂げた経験」を具体的に話すと、面接官に誠実さや信頼性を伝えられるでしょう。責任感を前向きに活かせる人は、銀行員として大きな成長を遂げやすいといえます。
③チームワークを重視できる人
銀行の業務は窓口対応や事務処理だけでなく、融資や営業など多くの人と連携して進める場面が多いです。そのため、チームワークを大切にし、周囲と協力して成果を出せる人が強く求められます。
協調性を持ち、上司や同僚に積極的に相談や報告ができる人は、組織の中で信頼されやすいでしょう。
逆に、成果を独り占めしようとしたり、一人で抱え込んだりすると、業務効率が下がり、周囲との関係が悪化する恐れがあります。
特に若手のうちは、先輩や上司のサポートを受けながら仕事を覚えることが多いため、素直に意見を取り入れる姿勢が重要です。
面接では「チームで成果を上げた経験」を話すと、自分の協調性を効果的に伝えられるでしょう。チームで動ける力は、銀行員として長くキャリアを築くうえで不可欠な要素です。
④数字に強い人
銀行員にとって数字に強いことは大きな武器です。融資審査やローンの提案、資産運用の相談など、あらゆる業務で数字を正確に扱う力が求められます。
数字に自信がある人は業務のスピードと正確性を両立でき、顧客からの信頼も得やすいでしょう。ただし、難しい数式を理解することよりも、数字を丁寧に扱い、間違いなく処理する姿勢が大切です。
経済学や会計学を学んだ経験や、簿記やFPといった資格を通じて養った知識は、就活でも有利に働きます。面接の際には「数字を扱って工夫した経験」を具体的に伝えると説得力が増します。
数字に強い人は銀行員の現場で即戦力となり、キャリアアップのスピードも速いでしょう。
⑤柔軟に対応できる人
銀行員は毎日多様な顧客と接するため、柔軟に対応できる人が向いています。顧客の要望やトラブルは必ずしもマニュアル通りに解決できるものではなく、その場に応じた判断力が必要です。
柔軟に動ける人は顧客満足度を高められるだけでなく、職場でも「頼れる人」として信頼を集めやすいでしょう。
逆に、考え方が固く状況に合わせられないと、顧客対応で不満を招いたり、職場で孤立する恐れがあります。面接では「想定外の状況に工夫して対応した経験」を話すと、柔軟性を効果的に示せます。
銀行員は日々変化する市場環境や顧客ニーズに直面するため、臨機応変に対応できる力を持つ人が、長期的に安定して成果を上げやすいのです。
銀行員に役立つ資格
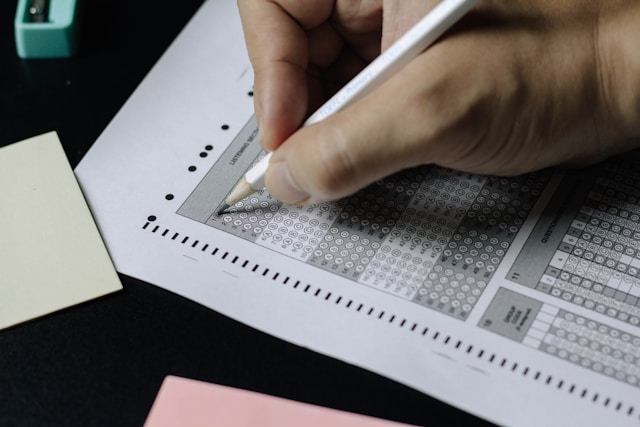
銀行員としてキャリアを築くうえで資格は大きな武器になります。金融知識を体系的に学べるだけでなく、顧客からの信頼や社内での評価にもつながるためです。
また、資格を通じて得た知識や姿勢は、就活の面接やエントリーシートでも説得力を増す要素となります。ここでは、銀行員に特に役立つ資格を5つ取り上げ、それぞれの特徴や就活でのアピール方法を解説します。
- 銀行業務検定
- 証券外務員資格
- 日商簿記検定
- ファイナンシャルプランナー(FP)
- TOEICなどの英語資格
①銀行業務検定
銀行業務検定は、銀行員の登竜門とも呼ばれる資格です。預金・融資・為替といった三大業務を中心に金融の基本を幅広く学べるため、取得しておけば業務理解の深さを示せます。
特に入社後に受験を推奨する銀行も多いため、学生時代に挑戦しておけば「学習意欲が高い人材」と評価される可能性が大きいでしょう。
また、学習を通じて金融の全体像を把握できるため、入社直後の研修やOJTで知識が結びつきやすく、業務習得のスピードも上がります。
さらに、資格を通じて身につけた知識は、顧客対応に自信を持てる基盤となります。
就活の場では「早期から銀行員に必要な知識を学んでいる」という姿勢を示せるため、他の学生との差別化につながるでしょう。
②証券外務員資格
証券外務員資格は、株式や投資信託などの販売に必須の資格で、銀行員が投資商品を顧客に提案する際に欠かせません。
この資格を取得していないと金融商品の販売に関われないため、早めに取得しておくことで「即戦力」としての評価が高まります。
特に営業やリテール部門を志望する学生にとっては、顧客対応の幅を広げる大きな強みとなるでしょう。
さらに、学習を通じて資産運用の仕組みを理解できるため、顧客の目的に合った提案力を磨くことができます。
例えば、リスクを抑えたい顧客には投資信託を、積極的に運用したい顧客には株式を紹介するなど、状況に応じた説明が可能になります。
資格取得の努力自体も「勉強を継続できる人材」として面接官に好印象を与える要素になります。
③日商簿記検定
日商簿記検定は、企業の財務状況を理解する力を養える資格で、銀行員にとって不可欠なスキルです。
融資判断を行う際には、決算書を読み解いて企業の経営状態を把握する必要があるため、簿記の知識は実務に直結します。
特に2級以上を取得していれば、財務諸表を正しく理解できる力を示せるため、法人営業や融資担当を志望する学生にとって大きな強みになるでしょう。
さらに簿記の勉強を通じて数字に強くなれるため、日々の業務における正確性やスピードも自然と向上します。
面接では「数字を扱うことに抵抗がない」と具体的にアピールできるため、説得力ある自己PRにつながります。金融業界を目指す学生にとって、簿記は土台を固める資格として非常に価値が高いといえます。
④ファイナンシャルプランナー(FP)
ファイナンシャルプランナー(FP)は、顧客の人生設計に沿った提案を行うための資格です。
銀行員は融資や投資だけでなく、保険や年金、相続といったライフプラン全般に関する相談を受けることが多く、FP資格があると幅広い提案が可能になります。
取得しておけば、顧客の将来を見据えたアドバイスができるため、「信頼できるパートナー」として評価されやすくなるでしょう。
就活の場でも、FP資格は「顧客の立場に立って考えられる人材」という印象を与えるため、コミュニケーション力や誠実さの裏付けになります。
また、FPの勉強を通じて培った知識は自分自身の資産管理にも活かせる点もメリットです。キャリアの初期から取得しておくことで、長期的な成長の基盤を築ける資格といえるでしょう。
⑤TOEICなどの英語資格
グローバル化の進展により、銀行員にも英語力がますます求められるようになっています。メガバンクや海外拠点を持つ銀行では、TOEICスコアが配属や昇進に影響するケースも少なくありません。
学生のうちに高得点を取得しておけば「国際業務に対応できる人材」と評価され、キャリアの選択肢が一気に広がります。
例えば、海外企業との取引や外資系企業の融資案件などに関わるチャンスが生まれやすくなるでしょう。国内業務であっても、英語力を持つ人材は希少性が高く、差別化につながります。
さらに、勉強を通じて得た語学力は、将来的に海外研修や駐在といった貴重な経験をつかむきっかけにもなります。
就活においても「将来を見据えて努力している」という姿勢を伝えられるため、強いアピールポイントになるでしょう。
銀行員という職業の理解を未来に活かす

銀行員の仕事内容は、預金や融資、為替といった三大業務に加え、一般職や総合職、さらにはシステムやリスク管理など多岐にわたります。
こうした幅広い業務を担う銀行員は、社会的な責任も大きく、専門性や適性が求められる職業です。そのため、大学やインターンを通じて学び、就職試験や資格取得で実力を示すことが重要となります。
キャリアパスも営業から本部、管理職、専門職、さらには国際業務へと発展でき、多様な将来像を描ける点が大きな魅力です。
金融や経済に関心がある人にとって、銀行員はやりがいと成長の両方を得られる職業だと言えるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














