高卒でも公務員になれる!試験と合格のコツ
「高卒だと公務員になるのは難しいのでは…」と不安に思っている人も多いのではないでしょうか。
実は、高卒でも国家公務員や地方公務員として働く道はしっかり用意されています。高卒程度の採用試験を突破すれば、安定した収入や社会的信用を得ながら、若いうちから実務経験を積むことが可能です。
しかし、大卒区分との違いやキャリアアップの制限など、知っておくべき注意点もあります。
この記事では、高卒で公務員を目指すための基本情報から試験対策、合格のコツまでを詳しく解説していきます。ぜひ参考にして、自分に合った進路を見極めてください。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
高卒でも公務員になれる?基本情報と現状

高卒向けの公務員試験については「高卒程度」として区分されており、大学に進学していなくても受験できる制度が整っています。そのため、計画的に学習すれば合格するチャンスは十分にあります。
ただし、自治体や職種によって倍率や競争率は異なるため、事前の情報収集は欠かせません。高卒で公務員を目指す場合、初任給や昇進スピードが大卒と異なることも理解しておく必要があります。
給与やキャリアの差を把握したうえで、自分に合った職種を選ぶことが大切です。
結論として、高卒でも公務員になることは可能ですが、試験対策と情報収集をしっかり行うことが合格への近道と言えるでしょう。
「就活でまずは何をすれば良いかわからない…」「自分でやるべきことを調べるのが大変」と悩んでいる場合は、これだけやっておけば就活の対策ができる「内定サポートBOX」を無料でダウンロードしてみましょう!
・自己分析シート
・志望動機作成シート
・自己PR作成シート
・ガクチカ作成シート
・ビジネスメール作成シート
・インターン選考対策ガイド
・面接の想定質問集100選….etc
など、就活で「自分1人で全て行うには大変な部分」を手助けできる中身になっていて、ダウンロードしておいて損がない特典になっていますよ。
高卒者がなれる公務員の種類【国家公務員・地方公務員】

高卒で公務員を目指す場合、どの職種や試験区分があるかを知っておくことは非常に重要です。自分の学歴や希望に合った選択肢を明確にできれば、進路を決める際に迷いにくくなります。
ここでは、国家公務員と地方公務員に分けて、高卒者が挑戦可能な職種や試験区分を整理します。これにより、「高卒でも公務員になれるのか」という不安を減らし、働くイメージを具体的に持てるでしょう。
- 国家公務員の職種と試験区分
- 地方公務員の職種と試験区分
①国家公務員の職種と試験区分
国家公務員には、高卒者向けの「一般職(高卒程度)」があります。事務職や技術職など幅広い職種を選ぶことができ、自分の適性や希望に合わせて働けます。
事務系は省庁で行政業務に携わる安定した仕事で、書類作成や予算管理、住民対応などさまざまな業務を経験できます。
技術系は電気・土木・機械など専門知識を活かせる職種が中心で、現場での実務経験を積みながらスキルを伸ばせます。
高卒で挑戦できる職種は限定されますが、安定性や将来設計のしやすさが大きな魅力です。給与や福利厚生も充実しており、長期的に安心して働ける職場環境が整っています。
また、国家公務員として働くことで幅広い業務経験を積めるため、キャリアアップや転職時にも役立つ知識やスキルを得られるでしょう。
②地方公務員の職種と試験区分
地方公務員には市役所や県庁などの行政職と、警察や消防などの専門職があります。高卒者は「高卒程度」の試験で受験でき、事務や窓口対応、地域サービスに携わるのが主な仕事です。
一般行政職では、地域の住民対応や手続きのサポート、予算管理などさまざまな業務を経験できるため、幅広いスキルが身につきます。
専門職は警察や消防の現場で、地域の安全や安心を守る重要な役割を担います。また、地方によって募集人数や仕事内容に違いがあるため、希望する地域や職種に合った働き方を確認しておくことが大切です。
地方公務員は地域社会に直接貢献できる点が大きな特徴で、地域への関心や意欲が高い人ほど適性があります。
勤務時間や福利厚生も安定しており、プライベートと仕事を両立しながら長期的にキャリアを形成できる点も魅力です。地域に根差して働きたい高卒者にとって、有力な選択肢といえるでしょう。
公務員における「高卒程度」と「大卒程度」の違い

就職活動を控える学生にとって、「高卒程度」と「大卒程度」という区分は大きな関心ごとです。
この違いを理解していないと、自分がどの試験を受けられるのかや、採用後の待遇について誤解してしまうおそれがあります。
ここでは、試験の区分や内容、初任給や待遇の差を整理し、安心して判断できるように解説します。
- 高卒程度と大卒程度の区分と意味
- 試験内容の違い
- 初任給の違い
- 待遇の違い
①高卒程度と大卒程度の区分と意味
公務員試験では、受験資格として「高卒程度」や「大卒程度」という表現が使われています。これは学歴そのものを示すのではなく、試験の難易度や求められる学力水準を表しています。
「高卒程度」は高校卒業レベルの学力を基準とした試験であり、必ずしも受験者が高校卒業直後でなければならないわけではありません。
逆に「大卒程度」は大学で学ぶ内容を前提とする問題が出題され、難易度は高くなります。この区分を誤解すると、自分が挑戦できる試験を見逃すことになりかねません。
実際には高卒でも「大卒程度」の試験を受験できる場合があり、その逆もあります。大切なのは学歴に縛られず、自分の学力と目的に合った試験を選ぶことです。
また自治体や職種によって募集区分は異なるため、募集要項を細かく確認しておく必要があります。こうした理解を持って準備すれば、より戦略的に進路を選べるでしょう。
②試験内容の違い
高卒程度と大卒程度の試験は、出題範囲や深さが大きく異なります。
高卒程度では一般知能や基礎的な教養が中心で、難易度も基礎から標準レベルに収まっています。数学や国語、社会など幅広い分野から出題されるため、バランスよく勉強することが重要です。
一方で大卒程度では法律や経済学など専門知識を問う試験や論文試験が多く、行政職や技術職では大学での学習が役立ちます。この違いを理解せずに準備すると、学習が偏り不十分になる恐れがあります。
また高卒程度は受験できる層が広いため競争率が高くなる傾向があり、効率的な学習法を取り入れなければ合格は難しいでしょう。
逆に大卒程度は科目数や難易度が高いため、長期的に計画を立てて学習を進める必要があります。自分の強みと弱みを見極め、受験区分に合わせた勉強法を選ぶことが合格の近道です。
③初任給の違い
採用後の初任給にも「高卒程度」と「大卒程度」では明確な差があります。高卒程度での初任給は15万円台後半から17万円台が多く、大卒程度では20万円前後が目安です。
差は数万円程度に見えても、昇給や昇進の速さに影響し、長期的には大きな差になります。同じ勤務年数でも大卒は役職に就くのが早く、責任ある仕事を任されやすいでしょう。
ただし高卒程度で採用された場合でも、経験を積み努力を重ねれば昇進や昇給は可能です。近年は成果や実績を重視する職場も増えているため、高卒だからといってキャリアの上限が決まるわけではありません。
さらに福利厚生や賞与などは大卒採用と大きな差がないため、生活の安定性は十分に確保されています。
初任給の差をどう捉えるかは人それぞれですが、将来設計を考える上で重要な判断材料です。早く安定を得たいのか、長期的なキャリアアップを重視するのかを見極め、自分に合った選択をしましょう。
④待遇の違い
待遇面でも「高卒程度」と「大卒程度」には違いがあります。
大卒程度は管理職候補として採用されることが多いため、昇進や昇格のスピードが比較的早い傾向にあります。早い段階で課長や係長などの役職に就き、組織運営に関わるケースも少なくありません。
一方で高卒程度は現場業務を中心に経験を積み、実務を通じて基礎力を養いながら徐々に昇格していきます。昇進が遅いと感じることもありますが、長く勤めれば安定した給与や待遇を得られるでしょう。
福利厚生や住宅手当、ボーナスは大卒とほぼ同じで安定した環境が魅力です。高卒でも待遇は大きく不利になることはなく、現場経験が評価される場合もあります。大切なのは望む働き方を理解することです。
将来的に管理職を目指すか、あるいは現場で専門性を高めていくか、自分の志向に合わせて進路を選ぶとよいでしょう。
高卒で公務員になれる確率(倍率)とは?

就職活動を控える学生にとって「高卒でも公務員になれるのか」という疑問は大きな関心ごとです。
実際に高卒程度区分の試験は毎年実施されており、国家・地方ともに受験機会がありますが、その倍率や難易度を正しく理解しておくことが大切でしょう。
ここでは、国家公務員と地方公務員それぞれの倍率について解説します。
- 国家公務員(高卒程度区分)の倍率
- 地方公務員(高卒程度区分)の倍率
①国家公務員(高卒程度区分)の倍率
国家公務員の高卒程度試験は、事務系や技術系など幅広い職種で実施されています。倍率は年度や職種によって差があり、平均すると数倍程度です。
大学入試の人気学部と同じくらいの競争率と考えると、決して不可能な数字ではありません。特に事務職は志望者が多く採用人数も限られるため倍率が高めになります。
一方で専門職や勤務地に条件がある職種は倍率が低い場合もあります。志望先を広く持てば合格の可能性が高まり、年齢制限もあるため早めの挑戦が将来の選択肢を広げる鍵となるでしょう。
また、国家公務員の高卒程度試験では学力だけでなく人物評価も重視されます。面接や適性検査で協調性や責任感が見られるため、勉強だけでなく普段の生活習慣や態度も評価の対象となります。
倍率が高いからといって不安になるのではなく、自分に合った職種を選びつつ、学力と人物面の両方を磨くことが合格を引き寄せる方法です。
②地方公務員(高卒程度区分)の倍率
地方公務員の高卒区分も人気が高く、自治体によって倍率は大きく異なります。大都市圏では応募者数が多いため10倍近いケースも見られますが、地方の小規模自治体では数倍程度にとどまることもあります。
この違いは勤務地の魅力や安定性を求める人の多さに直結しています。「倍率が高いから難しいのでは」と心配する学生も多いですが、倍率が低めの自治体を狙うことで可能性は広がるでしょう。
地方公務員試験は地域ごとに特色があり、教養試験や作文、面接の比重も異なります。地域の課題や特色を理解しているかが重視されるため、地元ニュースや行政の取り組みを把握しておくことが有利です。
特に面接では「なぜこの地域で働きたいのか」と問われるため、自分の考えを明確に整理しておくことが重要です。
倍率の数字だけを気にするのではなく、地域との結びつきや自分の適性を意識して準備することが、合格への大きな一歩になるでしょう。
高卒の公務員の給料目安【年代別・種類別】

公務員を目指す就活生にとって、実際にどれくらいの収入が見込めるのかは大きな関心事です。特に高卒で公務員になる場合、初任給や昇給のスピード、年代ごとの年収の変化は進路選びに直結します。
ここでは、国家公務員と地方公務員に分けて、それぞれの給料目安を解説します。給与水準を知ることで、自分の将来設計やライフプランを描きやすくなるでしょう。
- 国家公務員の初任給と平均年収
- 地方公務員の初任給と平均年収
①国家公務員の初任給と平均年収
国家公務員の給与は区分で異なりますが、高卒程度の一般職は初任給約16万円前後です。民間との差は小さいものの昇給制度が整っており、勤続年数に応じて着実に年収が増えていきます。
20代後半になると300万円台に届き、30代に入ると400万円台へ乗ることも多く、40代以降は役職や手当に応じて500万円を超えることも珍しくありません。
さらに地域手当や扶養手当、住居手当などの支給があり、実際の手取りは単純な基本給よりも厚くなる傾向です。こうした制度により、民間企業で働く同世代と比べても総合的な収入水準は高い位置にあります。
また、給与改定や賞与も人事院の勧告に基づいて透明性高く決定されるため、将来の見通しを立てやすいのも安心材料といえるでしょう。
短期的な収入だけでは判断せず、長期的な安定性を重視する人にとって、国家公務員は非常に魅力的な選択肢になります。
②地方公務員の初任給と平均年収
地方公務員の初任給は高卒採用で約15万円前後が相場です。地域によって差はありますが、国家公務員よりやや低めの水準に設定されている場合が多いです。
ただし住宅手当や地域手当、通勤手当など生活を支える制度が整っているのも魅力です。特に地元の市役所や町役場では家賃相場が低く、実質的な生活水準を保ちやすくなります。
地方公務員の年収は上昇が緩やかですが、30代半ばで400万円台、40代以降で500万円台に達する人も多いです。地域社会と密接に働けることは経済面だけでなく精神的な安定にもつながります。
特に長期的なライフプランを考えると、収入だけでなく働きやすさや住環境まで含めたトータルバランスでのメリットが大きい職業です。
安定した年収を確保しつつ地域に根ざした仕事をしたい人にとって、地方公務員は大変有力な進路の一つになるといえます。
高卒で公務員を目指すメリット

高校を卒業してすぐに公務員を目指すことには、大学進学とは違った魅力があります。早い段階から安定した職場で働けるため経済的に安心しやすく、社会経験も同年代より早く積めるでしょう。
また大学に進学せず試験合格を目指せるので、学費や時間をかけずに将来を築ける点も大きな利点です。ここでは、代表的な2つのメリットを解説します。
- 早くから現場で経験が積める
- 大学進学の必要が無い
①早くから現場で経験が積める
高卒で公務員になると、20歳前後という若さで現場に立つことができます。大学に通っている同年代が勉強を続けている時期に、すでに収入を得ながら社会人として成長できるのは大きな強みでしょう。
実務を通じて先輩から直接学ぶことで、机上の学びでは得られないスキルや人間関係の築き方を身につけられます。
さらにキャリアを早く始められる分、昇進や異動のチャンスも早く訪れ、経験の幅も広がります。また、仕事を通じて早くから責任ある立場を任されることもあり、自信や自己成長につながります。
地方公務員の年収は上昇が緩やかですが、30代半ばで400万円台、40代以降で500万円台に達する人も多いです。地域社会と密接に働けることは経済面だけでなく精神的な安定にもつながります。
もちろん慣れるまでに努力は欠かせませんが、その分得られる学びや成果は非常に大きな財産となります。
②大学進学の必要が無い
高卒で公務員を目指す大きなメリットは、大学に進学する時間や費用を節約できることです。大学に通えば授業料や生活費がかかり、卒業後に奨学金の返済を抱える人も少なくありません。
その一方で、公務員試験に合格すれば収入を得ながら働けるため、経済的に早く自立できます。しかも「高卒程度試験」に向けての勉強で十分に合格を狙えるので、努力次第で安定した職を得られるのです。
大学進学をしない分、就活準備やインターンが不要で目標に集中できます。合格後は給与を得ながら働けるため、早くから貯蓄や将来設計を始められます。
もちろん大学での学びを得られない点はデメリットに映るかもしれませんが、公務員の現場は人と関わる場面が多く、実務経験を重ねる中で知識やスキルを伸ばせます。
自ら勉強を続ければ、働きながら資格取得や専門知識の習得も実現できるでしょう。結果的に、大学に行かずとも十分に自己成長の機会を得られるのです。
高卒で公務員を目指すデメリット

高卒で公務員を目指す場合、安定した職場で長く働けるという魅力がある一方で、注意すべき点もあります。
特に、キャリア形成や将来的なスキル習得の幅に制限が出やすいことは大きな課題といえるでしょう。ここでは、高卒から公務員を目指す際に知っておきたい代表的なデメリットを解説します。
- キャリアアップの制限がある
- 公務員以外のスキルが身につきにくい
①キャリアアップの制限がある
高卒の公務員は安定や信用は得られますが、昇進や役職で差が出る傾向があります。自治体や官庁では「大卒程度」と「高卒程度」に区分され、学歴が昇進試験や昇格要件に影響する場合があるためです。
努力次第で昇進は可能ですが、大卒採用に比べると不利になりやすいです。昇進試験の受験時期や役職の上限が決まっている場合もあり、同じ努力でも評価が同等にならないことがあります。
政策立案や企画など裁量の大きな仕事は大卒資格が条件となることがあり、職務の幅が限られやすいです。そのため採用後に通信制大学や夜間大学で学び直す、資格取得で専門性を高めるなどの工夫が有効です。
高卒で入庁すること自体は十分に価値があります。若いうちから安定した環境で経験を積めることは大きな強みだからです。
しかし将来の昇進やキャリアアップを見据えるなら、入職後の学習や自己研鑽を続ける姿勢が欠かせません。学び続ける姿勢を持つことで、学歴の差を埋めながら自分のキャリアをより広く切り開けるでしょう。
②公務員以外のスキルが身につきにくい
もうひとつの懸念は、民間企業で通用するスキルを得にくい点です。
公務員は法律や規則に沿って業務を行うため専門性が組織内にとどまりやすく、転職時に他業界で役立つ力が不足しがちです。特に営業力や企画力、マーケ知識は得にくく、不利になる恐れがあります。
意識次第で改善可能です。事務処理力や調整力は民間でも評価され、ITや語学、資格取得に挑戦すれば将来の選択肢が広がります。これらは公務員としての効率化や円滑な業務遂行にもつながります。
一方で、公務員の安定性に甘えてしまうと「学ばなくても大丈夫」と考えてしまう人もいます。その姿勢が後々のキャリアの幅を狭める大きな落とし穴になりかねません。
高卒からでも早く安定した環境でキャリアを築ける利点があります。その上で学び続ける意識を持ち、汎用的なスキルを磨けば、転職時の不安も軽減できるでしょう。
高卒で公務員に向いている人の特徴
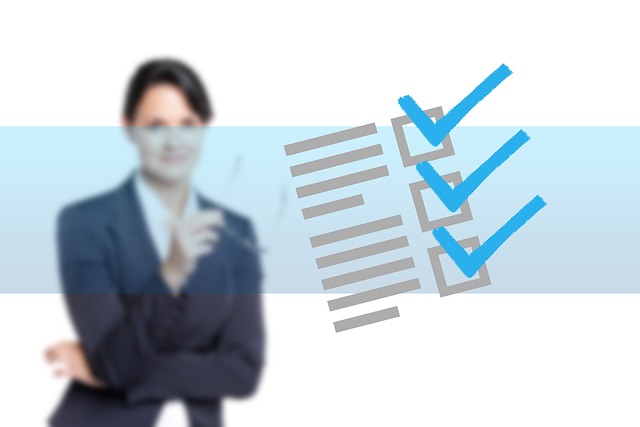
高卒で公務員を目指すとき、自分の性格や価値観が仕事に合っているかどうかを知ることは大切です。合わないまま進むと、就職後にギャップを感じてしまう恐れがあります。
ここでは、高卒で公務員に向いている人の特徴を整理しました。
- 若いうちから国や地域に貢献したい人
- 安定した職場で早く社会経験を積みたい人
- ルールや規律を守ることが得意な人
- 人と協力して仕事を進めるのが得意な人
- 経済的な安定を重視する人
- 専門知識より実務経験を重視する人
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①若いうちから国や地域に貢献したい人
地域社会や国のために早くから働きたい人には、公務員の仕事が合っています。高校卒業後すぐに試験を受ければ、20代前半から行政や住民サービスに関わることが可能です。
若いうちから多くの人と接し、住民の声を聞きながら業務に取り組むことで社会人としての視野も広がります。さらに、早い段階で実務経験を積むことは、自分のキャリアにとって大きな財産となるでしょう。
責任のある仕事を任される機会も増え、努力次第で昇進や異動のチャンスを得られるのも特徴です。社会的信用を得やすい環境に早くから身を置けることは、人生設計を安定させる大きな強みといえます。
②安定した職場で早く社会経験を積みたい人
公務員は雇用が安定しているため、早く社会で活躍したい人には理想的です。高卒での採用は若さを生かして現場で学べるため、経験値を積むスピードが速いのが特徴です。
大学進学を選んだ同年代よりも先に社会人としてのキャリアを始められるので、生活の安定や将来の選択肢にも余裕を持てます。
例えば、早くから収入を得ることで貯金やライフプランを考えやすく、家族や周囲に安心感を与えることもできるでしょう。また、現場で学ぶ経験は教科書では得られない実践力を育てます。
安定と成長を両立できる環境は、公務員という仕事ならではの魅力といえるでしょう。
③ルールや規律を守ることが得意な人
公務員の仕事は法律や規則に基づいて進みます。そのため、ルールをきちんと守れる人は向いているでしょう。規律を守る姿勢は信頼にもつながり、住民や上司からの評価を高めます。
さらに、ルールを正しく理解し守ることは、行政の公平性や透明性を維持するうえで欠かせません。公務員は「国民全体の奉仕者」であるため、個人の判断や感情よりもルールを優先する姿勢が求められます。
逆に、自分のやり方に強くこだわる人には息苦しさを感じる場面もあるかもしれません。自分がルールに従って行動できる性格かどうかを、あらかじめ確認しておくことが必要です。
④人と協力して仕事を進めるのが得意な人
公務員の業務は一人で完結するものではなく、多くの場合はチームで取り組みます。特に高卒で採用された場合は、経験豊富な先輩や上司の指導を受けながら成長する場面が多くあります。
そのため、協調性を持って周囲と連携できる人は働きやすいでしょう。自分の意見を伝えるだけでなく、相手の考えを尊重する姿勢も求められます。
信頼関係を築ける人ほど、上司や同僚からサポートを得やすく、結果として仕事の効率も高まります。さらに、課題をチームで解決する過程でリーダーシップを磨けるのも大きなメリットです。
協力する姿勢は評価されやすく、昇進や異動の機会にも直結するでしょう。
⑤経済的な安定を重視する人
安定した収入を求める人にとって、公務員は魅力的な選択です。高卒採用でも基本給がしっかりと保証され、昇給制度や福利厚生も整っています。
ボーナスや退職金の制度も充実しているため、長期的に見ても安心感があります。景気や業界の動きに左右されにくいため、安定した生活を望む人には特に向いているでしょう。
また、安定した収入は結婚や出産など将来のライフイベントを考える際の大きな支えになります。家庭を持ちたいと考える人にとっては、生活設計がしやすい点も強みといえます。
経済的な安心を重視するなら、公務員という道は非常に有力な選択肢です。
⑥専門知識より実務経験を重視する人
高卒枠の採用では、専門知識よりも実務での取り組み姿勢が重視されます。仕事の現場で経験を積みながら知識を吸収していくことで、自然にスキルを伸ばせるのが特徴です。
学歴よりも積極性や責任感が求められるため、若いうちから挑戦しながら成長したい人に向いているでしょう。
実際の業務では、住民対応や書類作成、チームでの業務調整など幅広い仕事に携わるため、知識より行動力が評価されます。
さらに、経験を重ねることで専門的な知識も身につき、仕事の幅が広がっていくのも魅力です。机上の学びよりも実践を通して力を発揮したい人には、非常に適した職業といえるでしょう。
高卒で公務員になるには?受験対策のしかた

高校を卒業してすぐに公務員を目指す場合、準備の段階で押さえるべきポイントが多くあります。
特に受験資格や年齢制限の確認から始まり、筆記試験と面接試験の対策、さらに独学か予備校かという学習方法の選択まで、事前に計画を立てることが成功への近道でしょう。
ここでは、高卒で公務員を目指すために必要な受験対策の流れを整理しながら、それぞれのステップで注意すべき点を解説します。
- 受験資格と年齢制限の確認
- 試験日程とスケジュール管理
- 筆記試験対策の方法
- 面接試験対策のポイント
- 独学と予備校の活用比較
①受験資格と年齢制限の確認
高卒で公務員を目指す際に、最初に確認すべきなのは受験資格と年齢制限です。これを見落とすと、勉強をどれだけ重ねても受験自体ができない可能性があります。
公務員試験における「高卒程度試験」については、一般的に18歳から20代前半にかけて受験可能と定められています。
ただし自治体や職種によって異なる場合もあり、警察官や消防士など体力を重視する職種では別の条件が課されることも少なくありません。
こうした細かな違いを確認せずに準備を進めてしまうと、条件を満たせずに受験を諦める事態にもつながります。募集要項は毎年変更されることがあるため、必ず最新情報をチェックしましょう。
自分が対象かどうかを早い段階で明確にすれば、不安なく学習に取り組めます。
②試験日程とスケジュール管理
公務員試験は年度ごとに日程が変わり、申込から試験本番までの流れも職種によって差があります。例えば、国家公務員の試験は春先に集中しますが、地方公務員は夏や秋にかけて複数の試験が行われます。
そのため志望先を複数考えている人は、日程が重なって受験できないケースも出てくるでしょう。
こうしたトラブルを避けるには、まず受験可能な試験を一覧化し、締切や本番日をカレンダーに書き出すことが効果的です。
さらに、試験日から逆算して「この月までに筆記の基礎を固める」「この時期から面接練習を開始する」といった学習計画を立ててください。
スケジュールを守ること自体がモチベーション維持にもつながります。逆に、行き当たりばったりで取り組むと、準備不足で本番に挑むことになり、後悔する可能性が高まります。
③筆記試験対策の方法
高卒程度の公務員試験では、幅広い分野から問題が出題されます。一般教養は国語・数学・社会など高校で学んだ基礎知識が中心ですが、特に数的処理や判断推理は多くの受験生が苦戦する分野です。
これらは慣れとスピードが重要であり、短期間で得点を伸ばすには繰り返し演習が欠かせません。市販の問題集を解くだけでなく、過去問を通して出題傾向を把握すると効率的に学習できます。
また、暗記科目については単純に覚えるのではなく、関連づけて理解することが得点力を高めるポイントです。
例えば、歴史の流れを年号と出来事で結び付けて覚えるなど、体系的に整理すると忘れにくくなります。
さらに、本番は限られた時間で解答するため、模試や過去問演習で時間配分の感覚を磨くことも重要です。勉強を「量」だけでなく「質」にもこだわることで、合格に近づくでしょう。
④面接試験対策のポイント
面接試験は、公務員としての適性や人柄を判断する大切な場です。筆記で高得点を取っても、面接で印象が悪ければ合格できません。
特に高卒の受験生は社会経験が浅いため、どうして公務員を志望するのか、その理由を明確に伝えることが求められます。
志望動機を作る際は「安定しているから」といった漠然とした理由ではなく、「地域の安全を守りたい」「住民サービスを支えたい」など、具体的に説明できるようにしてください。
また、面接ではアルバイトや部活動など学生時代の経験も評価対象になります。自分がどのように役割を果たし、そこから何を学んだのかを整理しておくと説得力が増します。
さらに、声の大きさや表情、姿勢といった非言語的な要素も大切です。模擬面接を重ねて改善点を客観的に把握すると、本番でも落ち着いて対応できるでしょう。
⑤独学と予備校の活用比較
公務員試験の学習方法は、独学か予備校かで悩む人が多いです。独学の最大の利点は費用を抑えられる点で、参考書や過去問を中心に取り組めば数万円程度で済みます。
しかし、自分で学習計画を立て、進捗を管理する必要があるため、途中で挫折する人も少なくありません。一方、予備校はカリキュラムや模擬試験、最新の出題傾向を踏まえた指導を受けられるのが強みです。
特に初めて受験する人や一人で勉強するのが苦手な人には心強い選択肢でしょう。ただし、費用が高くなることや、授業に依存して自主学習が不足するリスクもあります。
結局のところ、どちらが良いかは自分の性格や環境次第です。例えば、自己管理が得意で費用を抑えたい人は独学が向いていますし、体系的に学びたい人や仲間と切磋琢磨したい人は予備校を選ぶと効果的です。
いずれにしても、最終的には自分の努力次第で結果が決まるため、早めに方針を固めることが大切です。
高卒公務員を目指す人のQ&A【よくある疑問】

高卒で公務員を目指す人は、受験資格や試験の難易度、学習時間など多くの疑問を抱えやすいものです。ここでは、受験生が不安に思うポイントを整理し、知っておくべき基礎情報をわかりやすく解説します。
- 高卒と大卒で受験資格はどう違う?
- 高卒公務員の試験難易度は?
- 受験に必要な学習時間は?
- 国家・地方どちらを選ぶべき?
- 試験の申し込み方法は?
- 併願は可能か?
- 面接対策はどうすればいい?
- 試験直前に確認すべきポイントは?
①高卒と大卒で受験資格はどう違う?
公務員試験は「高卒程度」と「大卒程度」に分かれており、学歴によって受験できる試験区分が異なります。
高卒程度は高校卒業見込みや卒業後間もない人を対象とし、18歳前後から20代前半までが主な受験資格です。一方、大卒程度は大学卒業見込みの人や社会人経験者を対象とし、より多様な職種に挑戦できます。
誤解しやすいのは「大卒程度しか受験できない」と思い込んでしまうことです。高卒の人は、まず自分が受験資格を満たしているかどうかを確認することが不可欠でしょう。
無駄なく受験準備を進めるためには、区分をしっかり理解することが第一歩です。
②高卒公務員の試験難易度は?
高卒程度の試験は簡単に突破できるものではありません。倍率は自治体や職種によって異なりますが、事務職では数十倍になることもあります。
出題は国語や数学、社会など高校レベルの基礎分野が中心ですが、幅広い知識を求められるのが特徴です。ありがちな誤りは「基礎だから大丈夫」と軽視してしまうことです。
基礎的な内容であっても、過去問や模試を活用し、出題傾向に慣れることが必要になります。難易度の本質は学力の高さよりも、限られた範囲をどれだけ徹底的に押さえられるかにあるといえるでしょう。
正しい学習法を取れば突破できる試験ですので、早めに準備を進めてください。
③受験に必要な学習時間は?
合格に必要な学習時間はおおよそ300〜500時間です。1日2〜3時間の勉強を半年から1年続けるイメージでしょう。
もちろん学力や得意不得意によって調整は必要ですが、共通していえるのは「早めに始めるほど余裕を持てる」という点です。
直前に詰め込みをしようとすると、思考力を問う問題に対応できなくなり失敗につながります。効果的な方法は、過去問演習を定期的に取り入れ、短いサイクルで復習することです。
受験勉強はマラソンのようなもので、毎日の積み重ねが最終的な得点に直結します。学習習慣を整え、計画的に取り組むことが合格への近道です。
④国家・地方どちらを選ぶべき?
国家公務員と地方公務員では、仕事内容や勤務地に大きな違いがあります。国家公務員は全国規模での異動があり、中央省庁や出先機関で幅広い業務に携わります。
地方公務員は地域密着型で、採用された自治体に長く勤務するケースが一般的です。落とし穴は「どちらでも安定しているから同じ」と考えてしまうことです。
実際には勤務地や働き方が将来の生活設計に直結します。地方で暮らし続けたい人は地方公務員、全国を舞台に広い政策に関わりたい人は国家公務員が向いているでしょう。
仕事内容よりも、自分のライフスタイルに合うかどうかを基準に選ぶことが大切です。
⑤試験の申し込み方法は?
公務員試験の申し込みは、各自治体や人事院の公式サイトから行います。ほとんどはインターネットでの手続きで、必要事項を入力すれば完了です。
ただし、顔写真のアップロードや受験票の印刷など細かい条件があるため注意が必要です。よくある失敗は締め切り直前のアクセス集中によるエラーや、入力内容の誤りによる受験資格の無効化です。
安心して受験するためには、余裕を持って早めに手続きを済ませることが望ましいでしょう。募集要項を細かく確認してから申し込んでください。
⑥併願は可能か?
公務員試験は基本的に併願が可能です。国家公務員と地方公務員を同時に受ける人も多く、選択肢を広げる有効な手段といえます。ただし、試験日程の重複には注意が必要です。
地方自治体によっては同日に実施されることがあり、その場合はどちらかを選ばなければなりません。また、面接の時期が重なるとスケジュール調整が難しくなるリスクもあります。
さらに、複数の試験対策を並行すると勉強の焦点がぼやけ、成果が出にくくなることもあるでしょう。併願を考える際は、優先度の高い試験を決めておき、他は補助的に受ける戦略が賢明です。
⑦面接対策はどうすればいい?
面接は合否を左右する大きな要素です。志望動機や自己PRに加え、地域貢献への思いや将来像についても問われることが多いでしょう。失敗しやすいのは暗記した答えをそのまま話してしまうことです。
緊張で言葉が不自然になり、評価が下がる原因となります。対策としては、想定問答を繰り返し練習し、自分の言葉で自然に話せるように準備することが大切です。
さらに、身だしなみや姿勢など第一印象も大きく影響します。特に地方公務員では、地域に長く貢献する意欲が評価のポイントになります。面接は事前準備の積み重ねが成功の鍵になるでしょう。
⑧試験直前に確認すべきポイントは?
試験直前は新しい知識を詰め込むよりも、学習してきた内容を整理して自信を持つことが大切です。持ち物の確認や会場までのアクセスを前日にシミュレーションしておくと安心でしょう。
勉強は頻出分野を軽く復習し、基礎を固めることが効果的です。注意すべきは、前日に夜遅くまで勉強して睡眠不足になることです。本番で集中力を欠けば努力が水の泡になりかねません。
直前に意識すべきは「新しい知識」ではなく「積み重ねを確実に出す準備」です。冷静さを保つことが合格への最後の勝因になります。
高卒から目指す公務員への道筋を見極めよう!

高卒で公務員を目指すことは決して珍しい選択ではなく、国家公務員や地方公務員など幅広い職種が存在します。
大卒程度区分と比べて試験内容や待遇に違いはあるものの、若いうちから安定した環境で経験を積めることは大きな強みです。
実際、高卒程度の試験倍率は大卒と比べて必ずしも高いわけではなく、しっかりと対策すれば十分に合格を狙えます。
さらに年代別や職種別の給与水準も安定しており、経済的な安心を早期に得られる点は魅力です。一方で、キャリアアップの制限や専門スキルの習得機会が限られるデメリットも理解しておく必要があります。
総じて「安定した職場で早く社会経験を積みたい」「地域や国に貢献したい」と考える高卒者に、公務員は大きな可能性を持つ選択肢といえるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












