ドラッグストア就職の魅力とやりがいを徹底解説
「ドラッグストアに就職したいけど、具体的にどんな仕事ができるの?」
そんな疑問を持つ就活生も多いのではないでしょうか。
ドラッグストアは、医薬品や日用品の販売にとどまらず、地域住民の健康と生活を支える身近な存在として大きな役割を果たしています。
近年は調剤併設型店舗や美容・健康サービスの強化など、仕事内容の幅も広がっており、やりがいやキャリアの選択肢も豊富です。
そこで本記事では、ドラッグストア業界の特徴や課題、主要企業一覧、仕事内容の魅力ややりがいをわかりやすく解説します。
就活でドラッグストアを志望する方は、ぜひ参考にしてくださいね。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
ドラッグストア業界とは?業態や店舗の特徴を解説

ドラッグストア業界は、医薬品だけでなく日用品や食品まで取り扱うことで、年々存在感を高めています。
調剤薬局としての専門性に加えて、生活に密着した総合小売業としての側面もあり、医薬品だけでなく化粧品や食料品まで一度に購入できる便利さが魅力といえるでしょう。
また、医薬品を販売するには資格が必要な場合があり、登録販売者の資格などがキャリアアップにおいて有利になることもあります。
一見すると病院や調剤薬局と似ているように感じるかもしれませんが、実際の働き方や求められるスキルは大きく異なります。
こうした視点を持つことで、他の就活生と差をつけられる可能性も高まるでしょう。
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
ドラッグストア業界の課題

ドラッグストア業界は拡大を続けていますが、同時にさまざまな課題にも直面しています。就活生にとっては、業界の成長性だけでなく、現場で起きている問題を正しく理解しておくことが大切です。
ここでは代表的な4つの課題について詳しく解説します。
- 人手不足と労働環境の問題
- 価格競争の激化と利益率の低下
- 医薬品販売における規制対応
- 地域密着型サービスへの対応
①人手不足と労働環境の問題
近年、ドラッグストア業界では店舗数の急増と営業時間の拡大により、深刻な人手不足が続いています。
とくに登録販売者や薬剤師といった専門職の確保が難しく、店舗ごとに人材の偏りが起きやすい状況です。このことが、現場の業務過多や運営上の不安定さにつながっています。
加えて、シフト制による変則的な勤務や、長時間労働の常態化といった問題も見逃せません。
従業員が働きやすい環境を整備しない限り、離職率の高さが慢性化し、採用・教育にかかるコストも増えてしまいます。ワークライフバランスをどう確保するかは、業界全体の課題といえるでしょう。
就職先として検討する際は、給与や福利厚生だけでなく、現場のサポート体制や勤務実態まで把握しておくことが、入社後のギャップを減らすポイントになるでしょう。
②価格競争の激化と利益率の低下
ドラッグストア業界は、今やスーパーやコンビニ、ECサイトといった異業種とも激しく競合する市場に変わりました。
その結果、商品の価格を下げることで集客を図る店舗が増え、どの企業も利益率の確保に苦しむ状況に直面しています。
利益を出しづらい構造が続けば、社員の待遇や店舗のサービスレベルにも悪影響が及ぶおそれがあります。
このような状況では、単に安さを武器にするのではなく、他にはない価値をどのように提供できるかが重要です。
就職活動の際には、その企業がどのように収益構造を維持しているか、自社の強みをどう活かしているかを見極めることが、長期的なキャリア形成にもつながります。
③医薬品販売における規制対応
医薬品を取り扱う以上、法令遵守はドラッグストア業界にとって極めて重要な責任です。
第1類医薬品の販売には薬剤師の常駐が義務づけられており、登録販売者が取り扱える医薬品にも明確な範囲が定められています。こうした規制を正確に理解し、現場で適切に対応できる体制が必要です。
特に注意すべきなのは、医薬品の誤販売や不適切な説明によるトラブルです。
誤った服用による健康被害を防ぐためにも、販売スタッフには専門知識の習得だけでなく、コミュニケーション能力や責任感も求められます。
就職を考える際は、その企業が法令遵守にどう取り組んでいるか、また社内研修や資格支援制度が整っているかを確認するとよいでしょう。安心して働ける環境を選ぶことが、キャリアの土台となります。
④地域密着型サービスへの対応
ドラッグストアは、単なる商品を売る場所から、地域社会の健康を支える生活拠点へと役割が変化しつつあります。
とくに高齢化が進む地域では、処方箋の受付や在宅医療、健康相談イベントといったサービスを通じて、地域住民の生活に密着した支援を行うことが期待されています。
企業にとってはこれらの取り組みが新たな事業機会になる一方で、人員の確保や店舗運営の柔軟性といった課題も発生しています。
たとえば、地域ごとに異なる医療・福祉ニーズに対応するためには、現場スタッフの判断力や柔軟なサービス提供が求められます。
企業研究を行う際は、CSR活動や地域貢献の実績、社員の地域活動への関与状況などを確認しておくと、ミスマッチの防止につながります。
ドラッグストア業界の今後の動向

ドラッグストア業界は、消費者のライフスタイルや社会情勢の変化により、大きな転換期を迎えています。健康志向の高まりやデジタル技術の進展により、業界全体の方向性も変わってきました。
就職を検討する就活生にとって、業界の将来性や求められる役割を理解することは非常に重要です。ここでは、今後の動向に関わる注目すべき4つのテーマを紹介します。
- セルフメディケーション推進による需要拡大
- 高齢化社会におけるヘルスケアの重要性
- 海外展開・インバウンド需要の取り込み
- デジタル化とオンラインサービスの強化
①セルフメディケーション推進による需要拡大
セルフメディケーションとは、軽い体調不良を自分で判断して市販薬などで対処する健康管理の方法です。
国の方針により、この考え方は広く推進されており、OTC医薬品(一般用医薬品)の需要が増加しています。
これにより、ドラッグストアは単なる商品の販売店ではなく、健康を支える存在としての役割を担うようになりました。
そのため、薬剤師や登録販売者はより一層重要な存在となり、日々の業務を通じて専門性とホスピタリティの両方を磨けるでしょう。
また、ドラッグストアは地域に密着した営業スタイルが多いため、常連客との信頼関係も深まりやすく、人とのつながりを感じながら働ける環境です。
健康意識の高まりとともに、社会のニーズに応えるやりがいを実感しやすい職場といえるのではないでしょうか。
②高齢化社会におけるヘルスケアの重要性
急速に進む日本の高齢化により、ドラッグストアには従来以上にヘルスケア分野での対応力が求められるようになりました。
高齢者の増加に伴い、生活習慣病の予防や健康管理、さらには介護用品の提供など、店舗の役割が多様化しています。
たとえば、栄養相談を受けられるスペースを設けたり、血圧計や体組成計などの健康測定機器を常設したりする店舗も増えてきました。
これらの取り組みは、医療機関に頼らずとも日常的に健康を意識できる環境づくりにつながります。
高齢者本人だけでなく、その家族や介護者の支えにもなっている点で、社会的価値は非常に高いといえるでしょう。
今後ますます求められるのは、商品だけではなく「健康を支える拠点」としての機能です。その一端を担う仕事には、高い使命感と充実感があるはずです。
③海外展開・インバウンド需要の取り込み
近年のドラッグストア業界は、国内市場の成熟を背景に、積極的な海外展開とインバウンド対応を進めています。
特にアジア諸国では「メイド・イン・ジャパン」の医薬品やコスメの信頼性が高く、多くの企業が現地出店や提携を強化しています。
このような海外進出は、グローバル市場でのブランド認知や売上拡大につながる一方で、語学力や異文化理解を持つ人材の活躍の場を広げてもいます。
また、訪日観光客の増加によるインバウンド需要も重要です。人気商品を多言語で紹介するポップや、翻訳対応スタッフの配置、免税対応の強化など、多様な施策が取られてきました。
文化やニーズに応じた対応力が必要となるため、語学力やコミュニケーション力に自信がある人にとっては、大いに力を発揮できる分野でしょう。
今後は、海外事業部門やインバウンド戦略チームといった部門もさらに重要性を増すと考えられ、グローバルなキャリア形成を望む人にとって魅力的な選択肢となるはずです。
④デジタル化とオンラインサービスの強化
ドラッグストア業界では、近年急速にデジタル化が進んでいます。オンラインでの医薬品販売、健康管理アプリの提供、無人レジの導入、ポイント連携といった取り組みが各社で進行中です。
これにより、顧客の利便性は大きく向上し、従業員の業務効率も改善されています。たとえば、ECサイトを通じて24時間いつでも購入できる仕組みは、忙しい現代人にとって大きなメリットです。
また、アプリを使って体調を記録したり、過去の購入履歴から商品を提案したりといったサービスも注目されています。
これらは単なる販売にとどまらず、生活に寄り添うサービスとしての価値を提供しています。一方で、すべてが機械化されるわけではなく、接客の質を維持・向上させる工夫も欠かせません。
テクノロジーを活かしながら、人の力で補うことができる場として、ドラッグストアは次世代の働き方を体現するフィールドと言えるかもしれません。
ドラッグストア業界の主な職種

ドラッグストア業界では、接客や医薬品の販売にとどまらず、さまざまな職種が連携してサービスを支えています。
それぞれの職種には特徴や求められるスキルが異なるため、自分に合った働き方を見つけることが大切です。ここでは、業界で代表的な職種とその役割について詳しく紹介します。
- 販売スタッフ
- 薬剤師
- 登録販売者
- バイヤー・本部スタッフ
- エリアマネージャー
- ビューティーアドバイザー
- 物流・在庫管理スタッフ
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①販売スタッフ
販売スタッフは、お客さまとの最前線で接する業務を担当し、店舗全体の印象を左右する重要な存在です。
レジでの会計対応だけでなく、商品の陳列や在庫補充、清掃、POPの作成、売り場づくりなど、その仕事は多岐にわたります。
また、商品についての問い合わせに即座に対応したり、高齢者のお客さまの手助けをしたりと、ホスピタリティも求められます。
特に、売り場のレイアウト変更や季節ごとの販促イベントの実施などは、店舗ごとに独自性が出る部分です。そのため、創意工夫を楽しめる人にとってやりがいの大きい仕事でしょう。
さらに、こうした日常業務を通じて、売上やお客さま満足度に直接貢献できるのが特徴です。未経験からスタートしやすく、接客を通じて自己成長したい人にとって、第一歩として最適な職種といえます。
②薬剤師
薬剤師は、ドラッグストアにおいて専門性を活かし、医薬品の安全な提供と健康支援を担う役割があります。
第一類医薬品の販売に関する助言や、処方箋が必要ないOTC医薬品についてのアドバイスなど、幅広い健康ニーズに対応します。
ドラッグストアでは、医療知識を活かした接客スキルが重要で、患者ではなく「お客さま」に向き合う点が調剤薬局との大きな違いです。
また、最近は健康相談やサプリメント提案など、予防医療の担い手としての期待も高まっています。
知識だけにとどまらず、人として信頼される対応ができるかどうかが、成長と活躍のカギとなるでしょう。
③登録販売者
登録販売者は、薬剤師不在の時間帯でも医薬品販売を可能にする存在として、多くのドラッグストアで活躍しています。
第二類・第三類医薬品の販売ができる国家資格であり、取得後は比較的早い段階で専門的な業務に関わることができます。
お客さまからの症状や状況を聞き取り、適切な医薬品を提案する能力が問われるため、観察力や傾聴力も必要です。医薬品の知識だけでなく、法規制や副作用に関する理解も欠かせません。
間違った提案を避けるために、学び続ける姿勢が強く求められる職種です。また、医薬品以外の商品に関する問い合わせを受けることも多く、接客力の高さも活躍の要素となります。
資格を取得すればキャリアの選択肢が広がり、管理職や教育担当などへ進む道もあります。薬学部出身でなくても挑戦できる点が魅力で、学生時代から勉強を始める人も増えています。
④バイヤー・本部スタッフ
バイヤーや本部スタッフは、ドラッグストアの店舗運営を支える戦略的な役割を担っています。バイヤーは商品の仕入れや価格交渉、販促企画などを通じて、売上を伸ばすための全体戦略を構築します。
店舗ごとの売上データや市場動向をもとに、どのタイミングで何を仕入れるべきかを判断する力が重要です。一方、本部スタッフには、商品開発、システム導入、人材育成、店舗支援など多様な役割があります。
現場を経験したうえで本部に配属されることが多く、現場理解の深さが意思決定に活かされます。
特に、バイヤー業務は「目利き」が問われる場面も多く、新商品がヒットすれば自らの企画が大きな売上につながる喜びも味わえるでしょう。
現場とは異なる環境でのデスクワークやデータ分析が中心ですが、より広い視点で店舗や会社の成長に関われる点が特徴です。
⑤エリアマネージャー
エリアマネージャーは、複数の店舗を統括し、現場の状況を把握しながら経営的視点での判断を下すマネジメント職です。
各店舗の売上や課題を分析し、改善策を提案・実行する役割があるため、経営感覚と現場感覚の両方が求められます。
また、店長やスタッフとのコミュニケーションを通じて、指導やモチベーション管理にも深く関わります。具体的には、シフトの最適化や人材育成、クレーム対応など、実務面での支援も行います。
ときには人員不足の店舗へ応援に入ることもあり、柔軟な対応力が必要です。担当エリアの状況に応じて、販促の方向性を変えたり、本部と現場をつなぐパイプ役としての調整を行ったりすることも求められます。
単なる管理職ではなく、現場と同じ目線に立ちつつ、高い視座でマネジメントができる人材が評価されます。店舗業務を一通り経験した後のキャリアステップとして、将来性のあるポジションといえるでしょう。
⑥ビューティーアドバイザー
ビューティーアドバイザーは、スキンケアやメイクアップ、ヘアケアなどの美容全般に関する知識を活かして、お客さま一人ひとりに合った商品を提案します。
単に販売するのではなく、肌質や悩み、生活スタイルに応じて最適なケア方法をアドバイスすることが求められます。接客の中で信頼関係を築き、リピーターを増やすことが売上にもつながります。
メーカー主導の研修を受けながら知識を更新していく機会も多く、最新トレンドへの感度も重要です。化粧品の効果を自ら体験したうえで説明する機会もあり、商品の良さをリアルに伝える力が求められます。
美容が好きという気持ちはもちろん、「人の役に立ちたい」「外見だけでなく内面からの美をサポートしたい」という思いを持つ人に適した職種でしょう。
接客と専門性のバランスをとれる職場で、美容分野に携わりながらキャリアアップを目指せる点が魅力です。
⑦物流・在庫管理スタッフ
物流・在庫管理スタッフは、商品がスムーズに店舗に届くよう、倉庫での仕分けや在庫量の調整などを行う「裏方の要」です。
日々数千点の商品が動くドラッグストアにおいて、遅配や過不足を防ぐことは店舗運営の安定に直結します。特に、チラシ掲載商品や季節商材の入荷は時期が限られているため、時間管理の意識も非常に重要です。
また、近年ではシステムを活用した在庫管理やデータ分析も業務に含まれており、正確さに加えてITリテラシーも求められるようになっています。
業務は地味に見えるかもしれませんが、在庫のズレを防ぐことで廃棄ロスを減らし、収益向上に貢献するやりがいのある仕事です。
自分の仕事が全体の流れを支えているという責任感と達成感を得やすく、コツコツと地道な作業に向き合える人にとっては非常にやりがいを感じられるでしょう。
主要ドラッグストア企業一覧

主要なドラッグストア企業の特徴を把握しておくと、業界全体の動向や、自分に合った企業を見つけやすくなります。
ここでは、全国に展開している大手企業から、地域に根ざした企業まで、それぞれの強みをわかりやすく紹介します。
- マツモトキヨシ・ココカラ&カンパニー|業界最大級の店舗網とブランド力
- ウエルシアホールディングス|調剤併設型店舗と地域密着戦略
- ツルハホールディングス|積極的なM&Aと地方展開に強み
- スギ薬局|医療・介護連携を重視した多角的サービス
- サンドラッグ|ディスカウント型で低価格戦略を徹底
- クスリのアオキ|北陸中心に食品と医薬品の複合店舗を展開
- コスモス薬品|EDLP(毎日低価格)と郊外型大型店舗に強み
- カワチ薬品|調剤・セルフメディケーション重視の運営体制
- クリエイトSDホールディングス|神奈川中心に展開、調剤強化中
- ビー・アンド・ディー(B&D)ドラッグストア|愛知県を中心に展開する地域密着型店舗
就活では、多くの企業にエントリーしますが、その際の自分がエントリーした選考管理に苦戦する就活生が非常に多いです。大学の授業もあるので、スケジュール管理が大変になりますよね。
そこで就活マガジン編集部では、忙しくても簡単にできる「選考管理シート」を無料配布しています!多くの企業選考の管理を楽に行い、内定獲得を目指しましょう!
①マツモトキヨシ・ココカラ&カンパニー|業界最大級の店舗網とブランド力
マツモトキヨシとココカラファインの統合によって誕生したこのグループは、業界最大級の規模を誇ります。全国にわたる店舗展開に加え、強いブランド力が顧客からの信頼を集めています。
ドラッグストアの枠を超えて、日用品や化粧品の販売、さらにはアジア圏を中心とした海外展開も積極的に進めているのが特徴です。
このようなスケール感を持つ企業では、多様な働き方が可能となっており、キャリアアップの選択肢も豊富です。
大都市から地方、海外まで勤務地が選べることで、ライフステージの変化にも柔軟に対応できます。
安定性を求める一方で、将来的にはマネジメントや海外勤務など高い目標を持ちたい人にも向いているでしょう。
就職先として選ぶ際には、「どこでも通用する接客・販売スキル」を身につけることができる点も、大きな魅力といえるでしょう。
②ウエルシアホールディングス|調剤併設型店舗と地域密着戦略
ウエルシアホールディングスは、調剤併設型店舗を多く展開していることが大きな特徴です。
処方箋を扱う調剤部門と、日常的な買い物に対応するドラッグストア部門が同じ店舗にあることで、医療と生活の双方を支える存在として地域に根づいています。
特に注目すべきは「ウエルシアモデル」と呼ばれる店舗運営方針で、調剤・OTC医薬品・日用品・食品などをバランスよく取り扱い、地域のニーズに応じた品ぞろえを実現しています。
顧客第一を掲げたこのスタイルは、従業員の提案力や判断力を求めるため、成長意欲のある学生には最適です。
また、「お客様との対話を大切にする」ことが企業文化として根づいており、ただモノを売るのではなく、健康相談や生活提案など、コミュニケーションを通じて信頼を築く姿勢が評価されています。
将来的には店長、SV、本部職などのキャリアパスも明確で、長期的にキャリアを築きたい方にとって安心感のある企業です。
③ツルハホールディングス|積極的なM&Aと地方展開に強み
ツルハホールディングスは、北海道を基盤に全国へと店舗展開を拡大してきた企業で、特に地方への進出に力を入れてきました。
新規出店に加えて、M&A(企業買収)を通じてグループ傘下に入った企業と連携し、急成長を続けています。地方経済や地域住民との関係構築を重視しており、地域密着型の運営が信頼を集めています。
ツルハの魅力のひとつは、地域に根ざしながらもスケールの大きい挑戦ができる点にあります。
例えば、地元に貢献したいという思いを持ちつつ、大手の経営資源や教育体制を活用して、幅広い業務に取り組むことが可能です。
地方で働きたいと考えている人にとっては、安定と成長を両立できる環境だといえるでしょう。現場主導の店舗運営を大切にしているため、自ら考えて動ける人材が求められます。
多様な価値観の中で、自分らしく働きたいと考える方におすすめです。
④スギ薬局|医療・介護連携を重視した多角的サービス
スギ薬局は、ドラッグストア業界の中でも特に「医療・介護との連携」に注力している企業です。
調剤薬局の機能を持つ店舗が多く、さらに在宅医療や訪問看護、介護サービスまで展開しており、トータルヘルスケア企業としての存在感を高めています。
こうした幅広いサービスの提供は、地域の高齢化や健康志向の高まりといった社会的ニーズにもマッチしており、今後も成長が期待される分野です。
このような医療・介護と連携した事業モデルでは、専門知識やコミュニケーション能力が求められます。特に薬学部生にとっては、調剤や服薬指導だけでなく、在宅医療の現場にも関われる点が大きな魅力です。
また、文系の学生であっても、健康相談や地域イベントの運営などを通じて、地域の人々と密接に関わる機会があります。
医療・介護との多角的な連携が、ほかのドラッグストアとは異なるキャリアを描く道を提供してくれます。
⑤サンドラッグ|ディスカウント型で低価格戦略を徹底
サンドラッグは、徹底した低価格戦略と効率的な店舗運営によって、業界内でも高い利益率を維持している企業です。
特にディスカウント型のスタイルが特徴で、自社ブランド(PB)商品の開発や物流網の効率化を通じて、消費者にとって魅力的な価格を実現しています。
「質の高い商品を安く届ける」という方針は、コストパフォーマンスを重視する現代のニーズに合致しています。就職先として見ると、サンドラッグは「数字に強い」学生に向いている企業といえます。
単なる接客販売にとどまらず、商品配置や価格設定、販促活動など、店舗全体を俯瞰して動ける人材が重宝されます。
また、サンドラッグは教育制度にも力を入れており、「キャリアパス面談」や「能力評価制度」などを通じて、個人の成長をしっかりと支援しています。
ビジネス感覚を磨きながら、現場力とマネジメント力の両方を高めていける環境が整っています。
⑥クスリのアオキ|北陸中心に食品と医薬品の複合店舗を展開
クスリのアオキは、北陸地方を中心に、食品と医薬品の複合型店舗を展開している企業です。
ドラッグストアでありながら、スーパーマーケットのような食品売り場を併設しているのが特徴で、日常生活のあらゆるニーズに応える「ワンストップ型サービス」を提供しています。
この業態は、地域の生活者にとって非常に便利であり、同時に他社との差別化にもつながっています。
こうした店舗運営では、薬の知識だけでなく、食材や日用品に関する知見も求められます。幅広い商品カテゴリーを扱うことにより、接客力や売場づくりのスキルが自然と身についていきます。
特に、買い物ついでに健康相談をするお客さまも多く、接客の中で信頼関係を築く力が重要になります。
生活密着型のビジネスを通じて、多くの人の暮らしを支えるやりがいを感じることができるでしょう。
⑦コスモス薬品|EDLP(毎日低価格)と郊外型大型店舗に強み
コスモス薬品は、EDLP(Every Day Low Price)戦略を掲げ、日常的に安定した価格で商品を提供するスタイルを徹底しています。
この価格戦略は、特売に頼らず毎日安く買えるという安心感をお客様に提供するもので、価格変動に左右されない購買体験を重視しています。
また、郊外型の大型店舗を中心に展開し、駐車場完備の店舗設計など、地方のライフスタイルに合わせた経営を行っているのが特徴です。
このようなビジネスモデルでは、効率性と合理性が重視されます。商品の在庫管理や陳列方法においても、標準化されたオペレーションを徹底し、無駄を省くことでコストを削減しています。
そのため、現場で働く社員にも、常に「どうすればもっと効率的か」と考える習慣が求められます。論理的思考や改善意識を持った学生には、とてもやりがいを感じられる環境でしょう。
勤務地の希望も通りやすく、ライフスタイルに合わせた働き方がしやすい点も魅力です。価格と信頼の両立を図るコスモス薬品では、ビジネスの基礎力と人間力の両方を磨くことができるでしょう。
⑧カワチ薬品|調剤・セルフメディケーション重視の運営体制
カワチ薬品は、医薬品販売と調剤業務の両立を通じて、地域の人々の健康をトータルに支える運営方針を持っています。
中でもセルフメディケーション(自らの健康は自ら管理するという考え方)の推進に力を入れており、お客様一人ひとりの主体的な健康管理を支援する姿勢が評価されています。
このスタイルでは、販売スタッフにも医薬品や健康に関する一定の知識が求められます。入社後には登録販売者の資格取得を目指す制度もあり、文系出身でも医療分野にチャレンジすることが可能です。
また、店頭ではお客様の相談に対応する機会が多く、丁寧なヒアリング力と的確な商品提案が求められます。
人と関わることが好きで、困っている人の役に立ちたいという思いがある方には、とても向いている職場です。
薬の知識と接客力の両立を図りながら、信頼される存在を目指して成長していけます。
⑨クリエイトSDホールディングス|神奈川中心に展開、調剤強化中
クリエイトSDホールディングスは、神奈川県を中心とした関東圏で展開している企業で、近年は調剤部門の強化に力を入れています。
特に都市部における医療需要の高まりを受け、調剤併設店舗の比率を増やしているのが特徴です。
こうした流れの中で、薬剤師だけでなく、登録販売者や一般スタッフにも医療に対する知識や対応力が求められるようになっています。
クリエイトSDの魅力は、都市型店舗ならではの多様な顧客層に対応する力が身につく点にあります。
臨機応変な対応や情報提供を通じて、お客様からの信頼を積み重ねていくことが重要です。
また、都心部ならではのライフスタイルに合わせた勤務体系も整っており、時短勤務や休日制度など、ワークライフバランスを大切にしたい方にも適した環境が用意されています。
地域に根差しつつ、医療人としての視点を養いたいと考える学生にとって、クリエイトSDは非常に魅力的な選択肢です。
⑩ビー・アンド・ディー(B&D)ドラッグストア|愛知県を中心に展開する地域密着型店舗
B&Dドラッグストアは、愛知県を中心に展開している地域密着型のドラッグストアです。地域の健康と暮らしを支える存在として、地元住民との距離が近く、きめ細やかなサービスを提供している点が特徴です。
大手企業のような全国展開ではなく、あえてエリアを絞ることで地域のニーズを的確にとらえた運営が行われています。
こうした企業では、転勤が少なく、慣れ親しんだ土地で長く働くことができる点が大きな魅力です。
家庭との両立を考える学生や、地元で安定した生活を送りたいと考えている方にとって、非常に働きやすい環境といえるでしょう。
地域を大切にしながら、お客様の健康を支える役割を果たしたい学生には、B&Dドラッグストアは非常におすすめの企業といえるでしょう。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
ドラッグストアで働く魅力とやりがい

ドラッグストア業界は、身近な存在として多くの人の暮らしを支える役割を担っています。就活生にとっては、安定性や社会貢献性、スキルの幅広さなど、他業種にはない魅力が数多くあります。
ここでは、ドラッグストアで働くことで得られるやりがいや魅力について詳しく紹介します。
- 地域住民の健康を支える社会貢献性がある
- キャリアアップと資格取得支援制度がある
- 多様な業務によってスキルを習得できる
- 店舗運営を通じてマネジメント経験を積むことができる
- 安定した雇用と全国展開によって勤務地を選べる環境がある
- 異業種でも活かせる実践的な接客スキルが身につけられる
①地域住民の健康を支える社会貢献性がある
ドラッグストアは、単に薬や日用品を売る場所ではなく、地域の健康インフラの一部として機能しています。
特に医療機関の少ないエリアでは、体調の変化を気軽に相談できる窓口としての役割も大きくなっています。地域密着型の接客を通じて住民の健康維持に貢献できることは、大きなやりがいの源になるでしょう。
また、感染症対策や災害時の物資供給など、緊急時に地域の生活を支える重要な拠点としての責任も求められます。
こうした日々の積み重ねにより、単なる販売員ではなく「信頼される存在」へと成長していける点も見逃せません。
人の役に立ちたいという思いがある人にとって、心から納得できる仕事環境がここにはあります。
②キャリアアップと資格取得支援制度がある
ドラッグストアでは、社員の成長をサポートする体制が充実しています。中でも代表的なのが、登録販売者資格の取得支援です。
この資格を持つことで、医薬品の販売や説明が可能になり、業務の幅が大きく広がります。取得後は専門性が認められ、評価や昇進にも良い影響を与えるでしょう。
さらに、企業によってはビューティーケアや栄養学に関する研修制度もあり、美容部門やヘルスケア部門でのキャリア形成も可能です。
店舗の運営だけでなく、専門職や本部職への道も開かれており、多様な働き方が選べます。
ただ長く働くだけでなく、「成長し続けたい」という意欲を持つ人にとって、大きな可能性を秘めた業界といえるのではないでしょうか。
③多様な業務によってスキルを習得できる
ドラッグストアでの日々の業務は、想像以上に多岐にわたります。接客やレジ対応だけでなく、品出しや棚割り、発注業務、さらには売上分析や販促企画など、幅広い分野に関わることができます。
こうした経験を通じて、自然とビジネスに必要な「気づく力」や「考える力」が養われていきます。
また、店舗によっては地域イベントへの協力や商品提案会への参加など、外部との連携も求められる場面があります。
こうした実践的な業務の積み重ねが、自分の市場価値を高める大きな武器となってくれるでしょう。
限られた業務だけでなく、多様な経験を積んで視野を広げたいと考えている人にとっては、まさに成長の宝庫といえます。
④店舗運営を通じてマネジメント経験を積むことができる
多くのドラッグストアでは、入社後数年以内に副店長や店長として店舗運営に携わるチャンスが与えられます。
シフト作成や売上管理、発注量の調整、スタッフの育成など、マネジメントの実務をリアルに学べる点が大きな特長です。
特に、チーム全体をまとめながら成果を出す経験は、他業界でも通用するリーダーシップや問題解決能力の土台になります。
さらに、部門間の調整や本部との連携といった、より高度なコミュニケーション力も鍛えられていくでしょう。
若いうちから責任ある立場で結果を出す経験ができるのは、早期に実力を発揮したいと考える人にとって、非常に魅力的な環境です。
⑤安定した雇用と全国展開によって勤務地を選べる環境がある
大手チェーンが多いドラッグストア業界では、雇用の安定性が高く、安心して長く働ける職場が整っています。
全国展開をしている企業がほとんどなので、地元志向の学生や将来的なUターン・Iターン就職を希望する人にも適した環境といえます。
また、家庭の事情やライフステージの変化に合わせて勤務地を変更できる制度がある会社も多く、自分らしい働き方を実現しやすい点も大きな魅力です。
新店舗の立ち上げや異動先での新たな挑戦も、キャリア形成においてプラスに働くでしょう。「安定」と「柔軟性」の両方を大切にしたい方にとって、理想的な就職先といえるのではないでしょうか。
⑥異業種でも活かせる実践的な接客スキルが身につけられる
ドラッグストアでは、ただの接客ではなく、お客様の状況に応じて最適な提案を行うスキルが求められます。
日々の会話の中でニーズを読み取り、信頼関係を築いていく力は、あらゆる業種で活きる汎用性の高い能力といえるでしょう。
とくに、表情や言葉のニュアンスを敏感に読み取る観察力や、初対面の相手と円滑にやり取りを進める柔軟さは、営業・販売・サービスといった職種でも高く評価されます。
また、クレーム対応や多様な年齢層への対応力も自然と身につき、どこでも通用する実践力が養われていきます。
どの業界でも通用する「人と関わる力」を伸ばしたい方には、非常に価値ある経験となるはずです。
ドラッグストアに向いている人の特徴

ドラッグストア業界に興味はあるけれど、自分に向いているか不安を感じている就活生も多いのではないでしょうか。
ここでは、ドラッグストアで働くうえで求められる代表的な人物像を具体的に紹介します。自己分析や企業研究のヒントにしてください。
- 接客・コミュニケーションが得意な人
- 医薬品・健康・美容に関心がある人
- 臨機応変な対応力がある人
- チームワークを大切にできる人
- 責任感を持って仕事に取り組める人
- コツコツと継続して努力できる人
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
①接客・コミュニケーションが得意な人
ドラッグストアでは毎日さまざまな年齢層・立場のお客様が来店されるため、接客や会話力に自信がある人は非常に向いているといえます。
とくに、声のトーンや表情、聞き取りやすい話し方など、ちょっとした配慮が信頼感につながる場面も多くあります。
また、接客は単に商品を案内するだけではありません。体調不良や薬に関する相談を受けることもあり、お客様の気持ちをくみ取りながら対応する力が必要です。
たとえば「何を買えばよいかわからない」という不安を抱えた方に対して、丁寧に話を聞き、的確に選択肢を示すことで、安心感を与えられるでしょう。
最初は緊張してしまっても、経験を重ねるごとに自然と自信がついてくるものです。接客を楽しめる人、誰かの役に立ちたいと思える人にとって、ドラッグストアはやりがいのある職場といえるでしょう。
②医薬品・健康・美容に関心がある人
ドラッグストアでは、医薬品・サプリメント・スキンケア・ヘアケアなどの専門商品が多数並んでいます。そのため、これらに日頃から関心がある人は、仕事にも自然と熱意が向きやすいでしょう。
知識があるだけでなく、「もっと知りたい」「新しい商品を試してみたい」と思える姿勢は、接客の質にも大きく関係してきます。
お客様は「どの薬が自分に合うのか」「どの化粧品が効果的か」など、日常の悩みを相談に来ることも多くあります。その際、商品の違いや効果について、正しくわかりやすく伝えることが求められます。
情報収集や商品への興味が「強み」として活かされる環境なので、美容や健康のトレンドに敏感な人、SNSや口コミをチェックするのが好きな人にも適性がある職場といえるでしょう。
③臨機応変な対応力がある人
ドラッグストアでは、日々の業務において予測不能な出来事が起こることも珍しくありません。たとえば、突然のレジ渋滞、問い合わせの多発、シフト外のスタッフの欠勤など、状況は常に変化しています。
こうした場面で求められるのが、臨機応変な判断力と行動力です。マニュアル通りにいかないときに「どうすれば今ベストか」を考え、自分なりに動ける人は職場にとって貴重な存在になります。
また、自分だけでなく、周囲の動きを観察しながらフォローに回れる力も大切です。店全体を意識する視点があると、業務全体のスムーズさに貢献できます。
先輩の動きを観察したり、自ら改善策を探る努力を続けることで、少しずつ身につけていけます。ルーティンだけでなく変化にも柔軟に対応したい人には、非常に合っている職場といえるでしょう。
④チームワークを大切にできる人
ドラッグストアは、ひとりで完結する仕事ではありません。店内のさまざまな業務は、スタッフ同士が協力し合って初めて成り立つものです。
レジ、品出し、接客、発注、清掃、売場づくりなど、役割分担と連携が欠かせません。
たとえば、自分の業務がひと段落しても、まわりが忙しそうであればサポートに回る、声をかけて手伝いを申し出るといった気配りが、現場ではとても喜ばれます。
逆に、自己中心的な行動や、他人を無視するような言動があると、チーム全体の雰囲気が悪化してしまうおそれもあるでしょう。
仲間とともに成長していきたい人には、非常に向いている環境といえるでしょう。
⑤責任感を持って仕事に取り組める人
ドラッグストアの現場では、一見小さく見える業務ひとつひとつにも大きな責任が伴います。特に医薬品の案内や販売に関しては、お客様の健康に関わるため、誤情報や軽率な対応は許されません。
さらに、レジ業務では金銭の扱い、品出しでは期限管理や陳列ルールの順守、発注業務では在庫とのバランス確認など、正確性と慎重さが常に求められます。
こうした業務に対して、ミスを軽視せず真剣に向き合える人こそが信頼される存在になれるでしょう。もちろん、ミスをゼロにすることは現実的ではありません。
ただし、ミスをした際の報告・相談・改善の姿勢にこそ、その人の責任感が表れます。状況を他人任せにせず、自分ごととして受け止められるかがポイントです。
自分の行動に自覚を持ち、最後までやり抜く姿勢が、キャリアの広がりを生み出す原動力になるでしょう。
⑥コツコツと継続して努力できる人
華やかな仕事に見えにくいかもしれませんが、ドラッグストアの業務は、地道な積み重ねが大部分を占めています。
商品の補充、棚の清掃、在庫チェック、伝票確認など、日々のルーティンをしっかりこなすことが、お客様にとって快適な店舗づくりの基本になります。
また、業務以外にも継続的な学習が求められる場面は多くあります。とくに登録販売者の資格取得を目指す場合は、日々の勉強をコツコツ続ける力が不可欠です。
一度やると決めたことを投げ出さず、目標に向けて着実に進んでいける人は、必ず評価されます。
一方で、こうした努力が目立ちにくい職場でもあるため、結果を急ぎすぎず、自分自身でモチベーションを保てる工夫が必要になる場面もあるでしょう。
毎日の積み重ねを楽しめる人や、自分のペースで着実に力をつけたい人にとって、ドラッグストアは成長の機会にあふれた職場といえます。
ドラッグストア就職に有利な資格
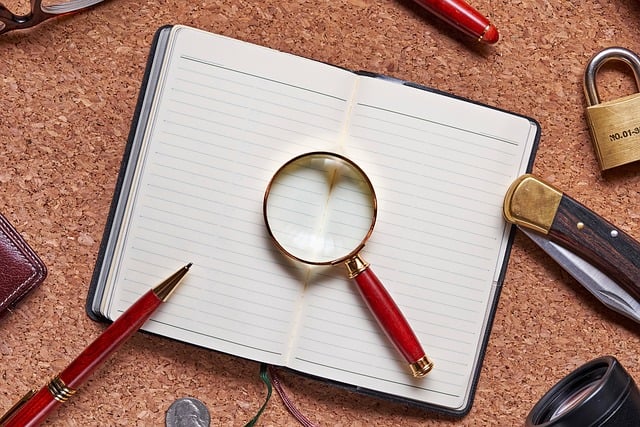
ドラッグストア業界はさまざまな職種があるため、資格の有無が採用に影響することも少なくありません。ここでは、学生のうちに取得しておくと就職活動で有利になる資格を紹介します。
- 登録販売者
- 薬剤師
- 衛生管理者
- 化粧品検定
- 調剤事務管理士
- 医療事務技能審査(メディカルクラーク)
①登録販売者
登録販売者は、一般用医薬品を販売できる国家資格です。
薬剤師がいない時間帯でも第2類・第3類医薬品の販売が可能となるため、ドラッグストアの営業時間を柔軟に運営するうえで不可欠な存在といえるでしょう。
多くの企業では、この資格を持っている人を積極的に採用しており、採用試験での評価も高くなりやすいです。
さらに、登録販売者の有資格者がいると、店舗の売り上げや信頼性にも好影響を与えることがあります。医薬品の専門的な知識を持つスタッフがいることで、お客様の不安や疑問にしっかり対応できるためです。
大学生でも独学や通信講座を活用すれば十分に合格を狙える内容なので、就活前にチャレンジしておいて損はありません。アルバイト経験があれば、出題内容との関連性も高く、より理解が深まります。
②薬剤師
薬剤師は、医療用医薬品の調剤や服薬指導、在宅医療支援など、多岐にわたる業務を担う国家資格です。
ドラッグストアでは、医薬品販売の専門家としての立場だけでなく、地域の健康相談役としても期待されています。
最近ではセルフメディケーションの浸透により、薬剤師の役割はますます重要になっているといえるでしょう。薬剤師として就職する場合、専門職採用枠となり、初任給や待遇が一般職とは異なります。
キャリアパスとしても、店舗の薬局長からエリアマネージャー、さらには本部勤務など多彩な可能性が広がります。
調剤薬局とは異なり、OTC販売の機会が多いことから、対人コミュニケーション力に自信がある人には非常に向いているでしょう。
③衛生管理者
衛生管理者は、労働者が50人以上いる職場で選任が義務付けられている国家資格です。
ドラッグストアの店舗や物流センター、調剤施設などでは、スタッフの安全や衛生環境の維持が重要課題となっているため、この資格を持つ人材は企業から高く評価されます。
とくに複数店舗を統括するポジションや、本部の安全衛生部門を目指す場合には有利になるでしょう。この資格は「第一種」と「第二種」に分かれており、対象業種が異なります。
ドラッグストア業界の場合、第一種のほうが幅広く対応できるためおすすめです。ただし、受験資格には実務経験が求められるため、学生のうちに取得するのは難しいこともあります。
これにより、現場での信頼を得やすくなるうえに、マネジメント側に進むチャンスも広がります。
④化粧品検定
化粧品検定(日本化粧品検定)は、美容やスキンケア、成分分析、正しい使用法など、化粧品に関する総合的な知識を身につけられる民間資格です。
ドラッグストアでは、化粧品売り場が大きな売上を占めることも多く、この資格を持っていることで即戦力として活躍しやすくなります。
検定は3級から1級まであり、3級は自己学習でWebから無料受験が可能な点も魅力です。2級以上では成分知識や肌トラブルへの理解が求められるため、カウンセリング重視の接客をしたい人には最適です。
近年では男性の受験者も増えており、美容部門を目指すなら性別に関係なく取得を検討してよい資格といえるでしょう。
また、資格を持っていることで「美容に興味がある」「最新の情報をキャッチアップしている」という印象を与えられるため、面接での印象もアップします。
店舗によっては、販促イベントやメイクアドバイスを担当する機会もあり、接客以外でのスキル発揮にもつながるでしょう。
⑤調剤事務管理士
調剤事務管理士は、調剤薬局で必要とされる事務処理能力を証明する資格です。
ドラッグストアの中には調剤部門を併設している店舗が増えており、そうした環境で働く場合、この資格を持っていることで大きな強みとなります。
主にレセプト作成、保険請求、患者対応などの業務が対象です。この資格は在学中でも取得可能であり、試験の難易度も比較的やさしいため、文系学生や医療未経験の人にも向いています。
資格を持っていることで、実務に入った際の習熟が早くなり、企業としても研修コストを抑えられるメリットがあります。
また、近年では電子カルテやレセプトソフトなど、IT系の知識も併せて求められる傾向にあります。資格取得の際にこうした点にも目を向けておけば、より実践的なスキルとして評価されやすくなるでしょう。
⑥医療事務技能審査(メディカルクラーク)
メディカルクラークは、医療事務に必要な知識と技能を測る全国統一の認定資格です。
病院だけでなく、調剤薬局やドラッグストアの医療関連部門でも活用されており、受付・会計・レセプト作成・患者応対などの基本スキルが身につきます。
資格の取得には、専門学校や通信講座を通じた学習が一般的ですが、在学中に受験できる点もメリットです。
とくに医療業界を志望するものの、薬剤師などの専門職までは目指していない学生にとって、現実的で有効な選択肢となるでしょう。
また、クレーム対応や電話応対など、実際の接客力も問われる内容が含まれており、接遇マナーを身につける良い機会にもなります。
医療・調剤部門に配属された際の即戦力として期待されることが多く、選考時の自己PRにもしっかりつなげられるでしょう。
ドラッグストア就活を成功させるポイント

ドラッグストア業界を目指す就活生にとって、しっかりとした準備は内定への第一歩です。業界研究から志望動機、インターン活用法まで、就活のあらゆる場面で役立つ情報を解説します。
ここでは、就活を成功させるための具体的なポイントをご紹介します。
- 業界研究の徹底をする
- 志望動機の準備と自己分析をする
- インターンシップや店舗見学を活用する
- 選考スケジュール管理と準備をする
- 企業説明会やOB訪問で情報収集をする
- 就職サイトやエージェントを活用する
①業界研究の徹底をする
ドラッグストア業界への就職を目指すうえで、まず取り組むべきなのが業界研究の徹底です。企業によって事業の柱や戦略が異なるため、それぞれの特徴を理解しておくことが欠かせません。
たとえば、調剤業務を中心とした医療寄りの企業、化粧品の販売に注力するビューティー重視の企業、そして生活用品を安価に提供するディスカウント型店舗など、多様なスタイルが存在しています。
さらに、業界全体の動向としては、セルフメディケーションの普及、少子高齢化によるヘルスケア需要の拡大、店舗統合によるチェーン化の進展などが挙げられます。
これらの背景を理解したうえで志望企業の方向性と照らし合わせると、自分が目指すキャリアとの接点が見えてくるでしょう。
また、IR資料や業界紙、経済ニュースなど一次情報を積極的に確認することで、他の就活生と差をつけることが可能です。
漠然とした知識で就活に臨むと、企業理解の浅さが面接で露呈する可能性もあるため、時間をかけて質の高い情報収集を行ってください。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
②志望動機の準備と自己分析をする
自分に合った企業を見つけるためには、自己分析と志望動機の準備が必要不可欠です。
自分がどのような価値観を持ち、どんな場面でやりがいを感じるのかを言語化できなければ、志望先との相性を判断することは難しいでしょう。
ドラッグストア業界では、顧客対応力、地域貢献意識、チームでの協調性などが評価されやすい要素とされています。
たとえば、「人と接することが好き」という曖昧な表現にとどまらず、「高齢者のお客さまと日常的に会話するなかで、信頼関係を築くことに喜びを感じた」といった具体的な体験談を交えることがポイントです。
このように、自己理解に基づいた志望動機は面接官にも伝わりやすく、説得力のあるアピールにつながります。また、志望動機は企業ごとにカスタマイズする必要があります。
自分の軸と企業の特徴が一致していることを明確にするには、自己分析と企業研究の両輪をしっかり回すことが大切です。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
③インターンシップや店舗見学を活用する
インターンシップや店舗見学は、就活の中でも特に実践的な情報を得られる貴重な機会です。
企業説明会やウェブサイトではわからない、店舗の雰囲気や従業員の働き方を自分の目で確認することで、理解が深まります。
たとえば、店舗見学ではレジ対応、商品補充、薬剤師や登録販売者の接客の様子などを観察でき、仕事内容のリアルがつかめるでしょう。
また、インターンでは、実際に業務を体験できるケースもあり、自分がその仕事に向いているかを判断する材料になります。
働くうえで何を大切にしたいか、自分にとって心地よい職場環境とは何かといった軸を明確にする手助けにもなるのです。
自ら行動し、現場を体感する姿勢は、主体性のある学生として印象づけることができるため、積極的に参加することをおすすめします。
「インターンの選考対策がよくわからない…」「何度も選考に落ちてしまう…」と悩んでいる場合は、無料で受け取れるインターン選考対策ガイドを確認して必勝法を知っておきましょう。LINE登録だけで無料でダウンロードできますよ。
④選考スケジュール管理と準備をする
ドラッグストア業界は業態が多様な分、企業数も多く、就活スケジュールが重なりやすい傾向にあります。そのため、早期からスケジュールを管理しておくことが非常に重要です。
エントリーシートの提出締切、会社説明会の日程、面接の予定などが次々に入り、対応が追いつかなくなるリスクもあるでしょう。
そのような事態を防ぐためにも、就活専用のカレンダーやアプリを使って一元管理することをおすすめします。企業ごとの状況を可視化しておけば、準備期間を逆算しながら行動できるようになります。
例えば、「説明会から面接まで2週間空いているから、この間に志望動機をブラッシュアップしよう」といった具合に、計画的な準備が可能になるのです。
また、就活には自己PRやガクチカ(学生時代に力を入れたこと)といった汎用的な質問に備える準備も必要です。
これらの準備が後手に回ると、短期間で大量の対策を求められることになり、内容が薄くなってしまいがちです。余裕のあるスケジューリングは、精神的にも余裕を持たせてくれるでしょう。
就活では、多くの企業にエントリーしますが、その際の自分がエントリーした選考管理に苦戦する就活生が非常に多いです。大学の授業もあるので、スケジュール管理が大変になりますよね。
そこで就活マガジン編集部では、忙しくても簡単にできる「選考管理シート」を無料配布しています!多くの企業選考の管理を楽に行い、内定獲得を目指しましょう!
⑤企業説明会やOB訪問で情報収集をする
企業説明会やOB訪問は、公式サイトでは得られないリアルな情報を集める絶好のチャンスです。
特にドラッグストア業界のように、企業によって運営方針や風土が大きく異なる場合、実際に働く人の声を聞くことは非常に参考になります。
現場の雰囲気や人間関係、キャリアステップの実情など、自分に合った職場かどうかを判断する重要な手がかりになるでしょう。
たとえば、説明会で人事担当者が語る企業理念や人材育成方針を聞くことで、その企業の大切にしている価値観が伝わってきます。
また、OB訪問では年齢の近い先輩社員から、就活時の実体験や入社後のギャップ、働いてみてわかった企業の魅力など、よりパーソナルで具体的な情報を得られる場合もあります。
情報は受け身ではなく、自ら取りにいく姿勢が評価されやすい点も意識してください。
⑥就職サイトやエージェントを活用する
就職サイトや就活エージェントは、自力では得にくい情報や支援を提供してくれる便利なツールです。
特にドラッグストア業界に詳しいエージェントであれば、企業の選考フローや過去の質問例、内定者の傾向など、実践的で具体的なアドバイスが受けられます。
これらは一般公開されていない情報であることが多く、情報の非対称性を埋める助けとなるでしょう。
また、エージェントによる模擬面接やエントリーシートの添削を通じて、自分では気づかなかった改善点を発見できることもあります。
ツールは活かすものであり、任せるものではありません。上手に活用することで、効率的かつ戦略的な就活が実現できるでしょう。
面接の深掘り質問に回答できるのか不安、間違った回答になっていないか確認したい方は、メンターと面接練習してみませんか?
一人で不安な方はまずはLINE登録でオンライン面談を予約してみましょう。
ドラッグストア就活で志望動機の書く際のコツ

就活でドラッグストア業界を志望する際、説得力のある志望動機を書くことが内定へのカギです。ありきたりな動機では印象が薄くなるため、企業の特徴や自分の経験をうまく盛り込む工夫が求められます。
ここでは、志望動機を魅力的に仕上げるための具体的なコツをご紹介します。
- 企業ごとの理念や特徴を理解する
- 具体的なエピソードを交えて自己PRをする
- 職種ごとの貢献意欲を明確にする
- NG例に学び注意点と改善をする
- 店舗での体験や観察を活かして書く
- 将来のキャリアビジョンと結びつける
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
①企業ごとの理念や特徴を理解する
ドラッグストア業界には、各企業が大切にしている理念や方向性があります。
表面的な事業内容だけでなく、その企業が何を社会に提供し、どのような価値観で運営されているのかを理解することで、深みのある志望動機を作ることが可能です。
たとえば、ある企業が「地域密着で健康を支える」ことを掲げている場合、ただ「人の役に立ちたいから」と書くのでは不十分です。
「地域での健康サポートを軸とした取り組みに共感し、自分も一員として携わりたい」といった視点が求められます。
また、企業理念と自分の経験がどうつながるのかを伝えることで、単なる共感では終わらない説得力が生まれるでしょう。
自分の過去の体験や考え方と照らし合わせながら、「なぜその企業でなければならないのか」を明確にすると、面接官の印象にも残りやすくなります。
企業が目指す方向性や今後の展望を把握でき、それが動機づけに深みを与えてくれるはずです。
②具体的なエピソードを交えて自己PRをする
志望動機においては、抽象的な表現にとどまらず、具体的なエピソードを用いて自分の強みを伝えることが欠かせません。
なぜなら、採用担当者は多くのエントリーシートを読む中で、「どの学生が現場で活躍できるか」を判断しているからです。
たとえば、「接客が得意」と伝える場合は、「アルバイト先でクレーム対応を任された経験があり、丁寧な説明でお客様の不満を解消した」といった具体的な場面を添えて言葉にリアリティを生みましょう。
また、数字や評価などの客観的な指標があれば、より印象が強くなるでしょう。たとえば「売上を前年比120%に伸ばした」「指名接客で常連のお客様が増えた」といった形で成果を伝えることも効果的です。
エピソードは、就職後の業務内容に直結していると説得力が増します。
単なる成功体験の羅列ではなく、そこから得た気づきや成長意欲を伝えることが重要です。
③職種ごとの貢献意欲を明確にする
ドラッグストアの仕事には、販売職だけでなく、登録販売者や医薬品の管理、マネジメント職など多様な職種が存在します。
それぞれ求められるスキルや視点が異なるため、志望する職種に応じた貢献意欲を明確に打ち出すことが必要です。
たとえば、販売職であれば「丁寧な接客でリピーターを増やし、売上に貢献したい」という視点が大切です。
登録販売者を志望する場合は、「正確な知識でお客様の健康相談に対応し、安心感を提供したい」といった動機が考えられます。
職種ごとの役割をしっかりと理解し、それに自分の経験や適性をどう結びつけるかがカギになります。
職種の理解が不十分だと、意欲があっても空回りしてしまうリスクがあります。事前のリサーチを怠らず、自分の志望職種に対する姿勢を明確にしておくと良いでしょう。
④NG例に学び注意点と改善をする
よくあるNG志望動機として、「どの会社にも通用するような汎用的な内容」や、「勤務地や勤務条件だけに焦点を当てた動機」が挙げられます。
たとえば、「家から近くて通いやすいから」といった理由では、企業への熱意や将来性が感じられません。
また、「人と話すのが好きです」といった曖昧な表現も、多くの学生が使っており差別化にはなりにくいです。
このようなミスを避けるには、「企業が自分に何を求めているのか」「自分が企業に何を提供できるのか」という両面の視点が欠かせません。
さらに、志望動機を作成したあとに第三者に読んでもらい、フィードバックを受けることで、独りよがりな内容や曖昧な部分に気づけるでしょう。
自分視点だけでなく、相手視点も意識しながら動機を書くことで、伝わる内容に変わっていきます。NG例は反面教師として、失敗しない志望動機づくりの参考にしましょう。
⑤店舗での体験や観察を活かして書く
実際に店舗に足を運んで得た体験や気づきは、志望動機に強い説得力を与える要素になります。ただ企業情報をネットで集めただけの内容と比べて、具体的な観察に基づく志望動機は説得力が段違いです。
たとえば、「来店時にスタッフが商品棚の整理と声かけを同時にこなしていて、接客と業務の両立に感心した」といった視点は、観察していないと得られないものです。
また、「お客様との距離感が近く、相談しやすい雰囲気があった」という印象も、志望理由にうまく活かせます。
観察から得た学びや、それを通じて「自分がどう貢献できるか」にまで言及することで、動機が単なる印象文にならず、志望の理由として機能するようになります。
体験は他人と被りにくく、オリジナリティのある志望動機が書けるチャンスです。時間が許す限り、実際に複数の店舗を訪れてみることをおすすめします。
⑥将来のキャリアビジョンと結びつける
志望動機には、目先のやる気だけでなく、将来のビジョンを盛り込むことで長期的な働く意欲を伝えられます。
企業としても、すぐに辞めてしまう可能性が低く、継続的に活躍してくれそうな人材を求めています。
たとえば、「入社後は登録販売者の資格を取得し、5年後には店舗マネジメントを任されるようになりたい」のようにキャリアプランを伝えましょう。
また、「将来的にはエリアマネージャーとして複数店舗の運営に携わりたい」といった具体的な目標を持って働ける人物として評価されやすくなるでしょう。
もちろん、希望が企業のキャリアパスとあまりにもずれていると逆効果になるため、事前に研修制度や昇進制度についての情報を確認しておく必要があります。
志望動機の中に盛り込むことで、より前向きな姿勢を伝えられるでしょう。
ドラッグストア業界における志望動機例文

ドラッグストアへの就職を考える際、自分の強みや希望する職種に合わせた志望動機の書き方に悩む方は多いでしょう。
ここでは、具体的な職種ごとの例文を紹介しながら、採用担当者に伝わりやすい志望動機のヒントをまとめています。ぜひ参考にしてください。
- 販売スタッフ志望の例文
- 薬剤師志望の例文
- バイヤー志望の例文
- ビューティーアドバイザー志望の例文
- 登録販売者志望の例文
- 店舗マネージャー志望の例文
- 商品企画・開発職志望の例文
- 本部スタッフ志望の例文
- 物流・在庫管理職志望の例文
また、志望動機がそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの志望動機テンプレを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
志望動機が既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。
【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
①販売スタッフ志望の例文
販売スタッフは、接客や商品管理を通じてお客様と直接関わる重要な仕事です。ここでは、大学生活での経験を活かした志望動機の例文をご紹介します。
| 私は大学時代、アルバイトで飲食店の接客を経験し、お客様から「ありがとう」と言っていただけることに大きなやりがいを感じました。 その中で、より多くの方の日常生活を支える仕事に携わりたいと考えるようになりました。ドラッグストアは生活に欠かせない商品を扱い、幅広い世代のお客様に必要とされる場です。 私は笑顔で丁寧な接客を心掛け、お客様が安心して買い物できる環境づくりに貢献したいと思います。 また、商品の特徴を分かりやすく伝える力を磨き、地域のお客様に信頼されるスタッフを目指して努力していきたいです。 |
この例文では「アルバイト経験」から「人の役に立ちたい」という動機につなげています。接客経験や日常での気づきをもとに書くと、志望理由に説得力が増します。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
②薬剤師志望の例文
薬剤師は専門的な知識を活かしながら、お客様の健康を支える役割を担います。ここでは、大学での学びを志望動機に結び付けた例文をご紹介します。
| 私は大学で薬学を学ぶ中で、薬が人々の生活を支える大切な存在であることを強く感じました。特に、家族が体調を崩した際に薬剤師の方に丁寧に説明していただいた経験が、私に安心を与えてくれました。 その経験から、私もお客様に信頼していただける薬剤師を目指したいと考えています。ドラッグストアは地域の方々にとって身近な存在であり、健康相談や服薬指導を通じて貢献できる場です。 私は学んだ知識を活かし、一人ひとりに寄り添った対応を行い、地域社会に必要とされる薬剤師になりたいと考えています。 |
この例文では「学業」と「身近な体験」を結び付けています。薬学の知識や信頼体験をもとに書くことで、説得力が生まれやすくなります。
③バイヤー志望の例文
バイヤーは商品を選定し、お客様の生活に直結する品ぞろえを担う重要な仕事です。ここでは、大学での関心や経験を活かした例文をご紹介します。
| 私は大学でマーケティングを学ぶ中で、消費者のニーズに合わせた商品選びの大切さを学びました。 特にゼミ活動で市場調査を行った際に、実際に消費者の声を反映させることで売上が伸びた経験が印象に残っています。 ドラッグストアでは、日用品から健康食品、化粧品まで幅広い商品を扱い、生活に直結した選定が求められます。私は常にお客様の視点を持ち、安心して選べる商品を提供できるよう努力したいです。 そして、地域のお客様に喜んでいただける売り場づくりに貢献したいと考えています。 |
この例文では「学び」と「実践経験」を強調しています。市場調査やアルバイト経験など、具体的な活動に触れると説得力が増します。
④ビューティーアドバイザー志望の例文
ビューティーアドバイザーは、美容や化粧品を通じてお客様の魅力を引き出す役割を持ちます。ここでは、化粧品への関心を活かした例文をご紹介します。
| 私は大学時代、友人からメイクの相談を受ける機会が多く、「自信が持てた」と言ってもらえたことがとても嬉しかった経験があります。 そこから、美容の力で人を前向きにできる仕事に就きたいと思うようになりました。ドラッグストアは幅広い化粧品を扱い、気軽に相談できる場所です。 私は丁寧にお客様の悩みを聞き、一人ひとりに合った商品を提案できるよう努力したいです。美容の知識を磨き続け、お客様の毎日を明るくするお手伝いができる存在になりたいです。 |
この例文では「身近な経験」から動機を導いています。美容や人を笑顔にするエピソードを具体的に入れると効果的です。
⑤登録販売者志望の例文
登録販売者は一般用医薬品を扱い、お客様の健康相談に対応する役割があります。ここでは、資格取得への思いや経験を結び付けた例文をご紹介します。
| 私は大学時代、家族が風邪をひいた際に市販薬を選ぶことに迷った経験から、正しい知識を持って薬を選ぶ大切さを実感しました。 その経験をきっかけに登録販売者の資格取得を目指し、勉強を進めています。ドラッグストアでは、お客様が安心して薬を選べるようにサポートすることが重要です。 私は学んだ知識を活かして丁寧に対応し、一人でも多くのお客様の健康を支えたいと考えています。地域の方々に信頼される存在となれるよう努力していきたいです。 |
この例文では「資格取得への思い」と「身近な経験」を結び付けています。学習中であっても意欲を示すことがポイントです。
⑥店舗マネージャー志望の例文
店舗マネージャーはスタッフをまとめ、売り場全体を管理する責任ある仕事です。ここでは、学生時代の経験をリーダーシップにつなげた例文をご紹介します。
| 私は大学時代、サークル活動で代表を務め、メンバーの意見をまとめてイベントを成功させた経験があります。その中で、人をまとめる難しさと同時に、全員で達成感を共有できる喜びを知りました。 ドラッグストアの店舗マネージャーは、売り場の管理だけでなくスタッフを導く役割も担います。 私はその経験を活かし、スタッフ全員が働きやすい環境を整えながら、お客様に喜ばれる店舗運営を実現したいと考えています。 |
この例文では「リーダー経験」から志望動機を展開しています。部活やサークルでの体験を交えると自然に書けます。
⑦商品企画・開発職志望の例文
商品企画・開発は、お客様のニーズに応じた新しい商品を生み出す仕事です。ここでは、大学での学びやアイデアを生かした例文をご紹介します。
| 私は大学でゼミ活動として商品開発の課題に取り組み、実際にアンケートをもとに新しいアイデアを形にする楽しさを学びました。 特に、消費者の声を取り入れて商品が完成したときの達成感が強く印象に残っています。ドラッグストアは生活に密着した商品を扱い、日常的にお客様の声を聞ける場です。 私はその経験を活かし、お客様の生活をより快適にできる商品企画に携わりたいと考えています。そして、多くの方に喜んでいただける商品づくりに挑戦していきたいです。 |
この例文では「ゼミ活動」から発展させています。研究や学びを具体的に結びつけると説得力が高まります。
⑧本部スタッフ志望の例文
本部スタッフは店舗運営を支え、全体の方針を決める重要な役割です。ここでは、組織の支援経験を志望動機に結び付けた例文をご紹介します。
| 私は大学時代、アルバイトで新人教育を任された経験があり、人をサポートすることで職場全体の雰囲気が良くなったことを実感しました。 その経験を通して、前線で働く人を支える役割に魅力を感じました。ドラッグストアの本部スタッフは、店舗の働きやすさや売上に直結する業務を担います。 私は現場スタッフが安心して働ける環境をつくり、店舗全体が活気づくような仕組みづくりに携わりたいと考えています。 |
この例文では「人を支える経験」から動機を展開しています。教育やサポートの経験をアピールすると一貫性が出ます。
⑨物流・在庫管理職志望の例文
物流・在庫管理は商品を安定的に届け、店舗運営を支える重要な仕事です。ここでは、計画性や裏方での努力を活かした例文をご紹介します。
| 私は大学時代、学園祭の運営で物品の調達と管理を担当し、期限までに必要なものを揃える難しさとやりがいを経験しました。 その中で、計画的に準備を進めることで全体が円滑に進むことに達成感を覚えました。ドラッグストアにおける物流や在庫管理は、店舗がスムーズに運営されるために欠かせない役割です。 私は責任感を持って正確に業務を進め、店舗やお客様に安心を届けられるよう努力したいと考えています。 |
この例文では「学園祭の運営経験」を活かしています。裏方の経験を具体的に書くことで信頼性のある志望動機になります。
ドラッグストア就職で描けるキャリアの可能性を見つけよう!

ドラッグストア業界は人手不足や価格競争といった課題を抱えつつも、セルフメディケーションの推進や高齢化社会への対応などによって需要が拡大し、今後も成長が見込まれる分野です。
就職先としては販売スタッフや薬剤師、登録販売者など幅広い職種があり、キャリアアップや資格取得を通じて専門性を高めることが可能です。
また、地域密着型のサービスを展開する企業も多く、社会貢献性と安定した雇用の両立が期待できます。
ドラッグストアに就職することで、医療・健康・美容の知識を活かしながら地域住民の生活を支えるやりがいを実感できるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













