ドラッグストア業界の今後の動向を徹底解説|業界が抱える課題や向いている人も紹介
「ドラッグストア業界って、今後どう変化していくんだろう?」
少子高齢化やセルフメディケーションの推進、さらにはデジタル化の加速など、社会の流れとともにドラッグストア業界は大きな転換期を迎えています。
将来性を見極めながら志望動機を考えることは、就職活動において欠かせないポイントです。
そこで本記事では、ドラッグストア業界の今後の動向をわかりやすく整理し、志望動機の例文とあわせて詳しく解説します。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
ドラッグストア業界とは?

ドラッグストア業界とは、医薬品や日用品、食品などを販売しながら、地域の健康支援も担う多機能型の小売業界です。
店舗には医薬品以外にも化粧品や食品、介護用品など幅広い商品が並び、地域の生活を総合的にサポートしています。
特に高齢化が進む日本では、セルフメディケーションの普及や医療費の抑制に貢献できる存在として注目されています。
一方で「誰でも働ける職場」という誤解を持たれがちですが、実際には登録販売者や薬剤師といった専門資格や、売り場管理・接客スキルなど多くの知識と実務力が求められます。
ドラッグストア業界は、医療×小売の融合で進化を続けており、地域社会に貢献しながらやりがいある仕事をしたい就活生には非常に魅力的な業界でしょう。
「業界分析…正直めんどくさい…」「サクッと業界分析を済ませたい」と悩んでいる場合は、無料で受け取れる業界分析大全をダウンロードしてみましょう!全19の業界を徹底分析しているので、サクッと様々な業界分析をしたい方におすすめですよ。
ドラッグストア業界の市場規模

現在、ドラッグストア業界の市場規模は年間で約8兆円に達しています。これはコンビニ業界に匹敵するほどの規模で、日々の買い物を担う重要なインフラといえるでしょう。
少子高齢化や健康意識の高まりを背景に、医薬品だけでなく食品や日用品などの販売も拡大しており、市場全体が拡大し続けているのが特徴です。
特に地方においては、コンビニの代わりとして使われるケースも増えており、高齢者にとっては身近で便利な店舗としての役割を果たしています。
さらに、健康食品や化粧品、ベビー用品など幅広い商品を取り扱うことで、「一か所で何でも揃う」利便性が高まっています。これにより、買い物客の滞在時間や購買単価も上昇傾向にあるのが現状です。
こうした背景から、ドラッグストア業界は今後も安定した成長を続けると見込まれるでしょう。
「業界分析」はこれ1冊だけ!業界分析大全を受け取ろう!
就活で志望業界を説得力高く語るには、「なぜこの業界なのか」をデータやトレンドで裏づける業界分析が欠かせません。とはいえ、IR資料やニュースを一から読み解くのは時間も手間もかかり、表面的な理解で面接に臨んでしまう学生も少なくありません。
そこで就活マガジン編集部では、主要20業界を網羅し「市場規模・最新トレンド・主要企業比較」まで1冊で整理した『業界分析大全』を無料提供しています。業界研究に迷ったら、まずはLINEを登録で特典をダウンロードして「面接で差がつく業界知識」を最短で手に入れてみましょう。
業界知識の深さは選考官が必ずチェックするポイントです。志望度の高さもアピールできるのでおすすめですよ。
ドラッグストア業界の主要企業

ドラッグストア業界には全国展開の大手企業が多数あり、それぞれ異なる戦略や強みを持っています。
業界研究を進める際には、こうした企業の特徴を知っておくと、志望動機や自己PRにも具体性が出せるでしょう。ここでは、主要企業ごとの強みを解説します。
- ウエルシアホールディングスの強み
- ツルハホールディングスの強み
- マツキヨココカラ&カンパニーの強み
- コスモス薬品の強み
- スギホールディングスの強み
①ウエルシアホールディングスの強み
ウエルシアホールディングスは、業界トップクラスの売上を誇る企業です。最大の特徴は、調剤薬局を併設した店舗を多く展開している点にあります。
これは高齢化が進む中、地域の医療ニーズに応える取り組みとして大きな価値を持っています。
さらに、24時間営業や地域密着型の運営体制を取り入れることで、住民のかかりつけ薬局としての信頼も築いています。このような柔軟なサービス提供は、他社との差別化に直結しています。
売上規模だけでなく、社会的な役割への意識が高い点も、企業選びの際に注目すべきポイントでしょう。
②ツルハホールディングスの強み
ツルハホールディングスは、全国に約2,000店舗を展開しており、国内でも有数の規模を誇ります。特筆すべきは、多ブランド戦略を採用していることです。
ツルハドラッグをはじめ、くすりの福太郎やウォンツなど、複数のブランドを地域特性に合わせて使い分けており、それぞれの地域で求められるサービスを提供しています。
また、従業員の教育体制も整っており、キャリアアップ支援が充実している点も魅力です。地元での就職を希望する学生や、安定したキャリア形成を重視する方にとって、有力な選択肢でしょう。
③マツキヨココカラ&カンパニーの強み
マツキヨココカラ&カンパニーは、マツモトキヨシとココカラファインの経営統合により誕生した企業で、業界の再編を象徴する存在です。
統合によって得られたスケールメリットは大きく、商品開発力の強化や仕入れコストの削減など、経営効率の向上が進んでいます。
また、調剤薬局との連携も強化されており、健康支援に特化したサービス体制が整っています。
業界最大級の企業で、幅広い業務に携わりながらキャリアを築きたい方にとって、学ぶ機会の多い環境といえるでしょう。
④コスモス薬品の強み
コスモス薬品の特徴は、徹底したディスカウント戦略にあります。「エブリデイ・ロープライス(EDLP)」を掲げ、常に低価格で商品を提供していることが顧客の支持を集めています。
ポイント制度や派手なキャンペーンを行わず、いつでも同じ価格で買えるという安心感が、リピーターの獲得につながっているのです。
郊外型の大型店舗で品揃えも豊富なため、生活必需品をまとめて購入したい消費者からの評価も高めです。コスト意識や効率性に関心がある方には、非常に魅力的な企業でしょう。
⑤スギホールディングスの強み
スギホールディングスは、医療分野への取り組みが強みとなっています。調剤薬局を併設した店舗だけでなく、在宅医療や訪問服薬指導にも力を入れており、地域医療への貢献度が高い企業です。
さらに、女性の活躍推進や育児支援制度など、働きやすい職場環境づくりにも積極的です。こうした取り組みにより、ライフステージに合わせて長く働ける点が大きな魅力といえるでしょう。
医療・福祉との接点を持ちながら、社会に貢献するキャリアを築きたい方に向いています。
ドラッグストア業界の今後の動向

近年、ドラッグストア業界は医薬品販売だけでなく、さまざまな方向に進化しています。
少子高齢化や健康志向の高まり、ネットショッピングの普及などを背景に、新しいビジネスモデルを模索する動きが活発になっています。
そこで、ドラッグストア業界の今後の動向について詳しく解説していきます。
- オンライン販売の拡大戦略とは
- 店舗の健康サポート機能とは
- 地域密着型店舗の増加とは
- セルフメディケーション推進とは
- グローバル展開の可能性とは
①オンライン販売の拡大戦略とは
オンライン販売は、今やドラッグストア業界にとって欠かせない成長分野といえるでしょう。
消費者が自宅から気軽に商品を注文できることから、企業はECサイトやスマホアプリの機能強化に力を入れています。
一方で、対面でのアドバイスができないことによる不安もあり、チャット相談や動画による解説などで安心感のある購買体験を提供する工夫が進んでいます。
こうした対応により、オンラインでも信頼されるサービスが提供されるようになってきました。
就職活動中の学生にとっては、ITやデジタルマーケティングの知識が活かせる場面も多く、薬剤師に限らない職種の広がりがある点に注目しておくとよいでしょう。
②店舗の健康サポート機能とは
最近のドラッグストアでは、商品を売るだけでなく、地域の健康支援拠点としての役割を担うようになっています。
店内では血圧測定や健康相談、栄養指導などを行い、来店者が気軽に健康チェックをできる仕組みが増えています。こうしたサービスの背景には、高齢化社会や生活習慣病の増加といった社会的課題があるでしょう。
ドラッグストアは、身近な場所で日常的に健康に関する情報やサービスを提供できる存在として期待されています。
このような動きにより、薬剤師だけでなく管理栄養士や登録販売者など多様な専門職が連携して活躍しています。
学生の皆さんも、「売る」だけでなく「支える」役割を意識して企業研究をしてみてください。
③地域密着型店舗の増加とは
ドラッグストア業界では、地域に密着した小型店舗の展開が広がっています。
大型の郊外店よりも、住宅街や駅前など人々の生活圏に近い場所に出店し、日用品や医薬品を気軽に購入できる環境を整えています。
この戦略により、地域ごとのニーズに柔軟に対応できるようになりました。その一方で、スタッフの人数が限られるため、接客・品出し・発注など幅広い業務をこなす必要がある点が特徴です。
マルチタスクで動ける柔軟性や、親しみのある接客が求められるため、人とのつながりを大切にしたい方には向いている職場といえるでしょう。
④セルフメディケーション推進とは
セルフメディケーションとは、自分の健康を自分で管理する考え方で、ドラッグストアがそのサポート役を担っています。
風邪薬や胃薬などの一般用医薬品を、専門家のアドバイスを受けながら自分で選べる環境づくりが進んでいます。
この取り組みは、医療機関の負担軽減や医療費の抑制にもつながる重要な施策です。そのため、登録販売者による丁寧な接客や、わかりやすい商品説明がますます求められています。
将来、医薬品の販売やカウンセリングに関わりたいと考えている人にとっては、専門知識と接客スキルの両方が必要となるため、早めに準備を始めるのがよいかもしれません。
⑤グローバル展開の可能性とは
国内市場の成長が鈍化する中、ドラッグストア業界は海外市場への進出にも力を入れ始めています。
特に日本製の医薬品や化粧品が信頼されているアジア地域では、現地店舗やECサイトの展開が進んでいます。このような流れの中で、語学力や異文化理解に優れた人材が求められるようになっています。
海外の法制度や生活習慣を踏まえたうえで、現地ニーズに合ったサービスや商品の提案ができる柔軟性も重要です。
グローバルに働きたいと考えている学生にとって、ドラッグストア業界は新しい可能性を秘めた就職先になるかもしれません。
ドラッグストア業界の主な職種

ドラッグストア業界にはさまざまな職種があり、それぞれが店舗運営や顧客満足に深く関わっています。
ここでは代表的な職種について仕事内容や特徴を紹介します。自分に合った働き方を見つけるための参考にしてください。
- 販売職の仕事内容とは
- 薬剤師の仕事内容とは
- 登録販売者の仕事内容とは
- バイヤーの仕事内容とは
- 店舗マネージャーの仕事内容とは
①販売職の仕事内容とは
販売職は、ドラッグストアの現場でお客さまと直接関わる役割を担っています。主な業務には、レジ対応、商品陳列、在庫管理、季節ごとの売り場づくりなどがあります。
一見すると単純な仕事に見えるかもしれませんが、実際には商品知識や接客スキルが求められるため、やりがいも大きいでしょう。
特に、来店されるお客さまのニーズは日々変化するため、柔軟に対応する力が大切です。
現場で経験を積むことで、販売リーダーや店舗マネージャーなど、キャリアアップの道も広がります。人と接することが好きで、チームで働くことにやりがいを感じる方に向いている仕事です。
②薬剤師の仕事内容とは
薬剤師は、医薬品の専門家としてドラッグストアで重要な役割を果たします。第1類医薬品の販売をはじめ、健康相談や服薬指導、在庫管理や商品の発注業務にも関わることが多いです。
OTC医薬品だけでなく、サプリメントや介護用品の知識も求められるため、幅広い知識と対応力が必要になります。来店するお客さまにとっては、気軽に相談できる存在であることも期待されています。
正確な情報をわかりやすく伝える力や、親しみやすさも大切です。地域の健康を支えたい方、専門性を生かして働きたい方にぴったりでしょう。
③登録販売者の仕事内容とは
登録販売者は、第2類・第3類の一般用医薬品を販売できる資格を持つ職種です。医薬品の効果や使用方法を理解したうえで、お客さまに適切にアドバイスすることが主な仕事になります。
そのほか、レジ業務や商品補充など、店舗業務全般に関わる場面も多くあります。薬剤師と違って取得のハードルが比較的低いため、学生のうちから資格を目指す人も多いようです。
ただし、販売業務を行うには一定の実務経験が必要になるため、早めの準備がポイントです。医療や健康に関心があり、人と話すことが好きな方に向いています。
④バイヤーの仕事内容とは
バイヤーは、商品の仕入れや選定を通じて店舗の売上を左右する重要な仕事を担っています。市場の動向を把握し、地域性や季節性に合わせた商品ラインナップを整える力が求められます。
たとえば、売れ筋商品を見極めたり、メーカーと交渉して価格を調整したりすることで、他店との差別化につなげます。さらに、販売戦略を立てるなど経営目線の思考も必要です。
数字に強く、情報収集や分析が得意な方には向いている職種です。目立つ仕事ではないかもしれませんが、店舗の魅力づくりに欠かせない存在といえるでしょう。
⑤店舗マネージャーの仕事内容とは
店舗マネージャーは、店舗全体の運営やスタッフ管理を任される責任ある役職です。売上管理やシフト作成、接客対応、人材育成など、多岐にわたる業務に携わります。
スタッフ一人ひとりの特徴を把握し、チームの力を最大限に引き出すことが求められるため、高いコミュニケーション力が欠かせません。経営層と現場をつなぐ役割も重要です。
自らの判断で店舗を動かすことができるため、やりがいや達成感を感じられるでしょう。プレイヤーからマネジメントへと成長したい方におすすめの職種です。
ドラッグストア業界で必要な資格

ドラッグストア業界で働くには、専門的な知識やスキルが求められるため、いくつかの資格がキャリアアップの鍵になります。
ここでは、就活生が知っておくべき代表的な資格について、それぞれの特徴や活かし方を紹介していきます。
- 登録販売者資格とは
- 薬剤師国家試験とは
- 管理薬剤師とは
- 衛生管理者資格とは
- 化粧品検定とは
①登録販売者資格とは
登録販売者資格は、一般用医薬品の第2類・第3類を販売するために必要な国家資格です。
この資格を持っていれば、薬剤師がいない時間帯でも医薬品を販売できるため、店舗の運営において重要な役割を担います。
ドラッグストアでは登録販売者の人数がシフトや売上に大きく影響することから、就職活動の場でも有利になるでしょう。
試験内容は医薬品の成分や効能、安全な使い方などで構成されており、独学でも合格を目指せます。ただし範囲が広いため、計画的な学習が欠かせません。
入社後に取得を支援する企業もありますが、学生のうちに取っておけば採用面接で強みとしてアピールしやすくなります。
②薬剤師国家試験とは
薬剤師として働くには、6年制の薬学部を卒業し、薬剤師国家試験に合格する必要があります。医療用医薬品の取り扱いや調剤業務を担うため、ドラッグストアでも中心的な役割を果たす職種です。
国家試験は難易度が高めで、合格率は70%前後です。ただし、大学のカリキュラムや実習がそのまま試験対策になるため、真面目に学べば十分に対応できます。
薬剤師免許を持っていると年収や役職の面で優遇されることが多く、特に調剤併設型の店舗では重宝されるでしょう。将来性の高さから、就活でも高く評価されやすい資格です。
③管理薬剤師とは
管理薬剤師とは、店舗における薬事関連の業務を総合的に管理する責任ある役職です。薬剤師資格を持つ人が就任でき、医薬品の在庫や品質の管理、法令順守の監督などを行います。
この職は1つの施設に1人しか配置できないため、信頼性と責任感が特に求められます。新卒でいきなり目指すことはできませんが、現場経験を積んだ上で目指せるポジションです。
キャリアアップを視野に入れているなら、早い段階から管理薬剤師という目標を意識することが将来の成長につながるはずです。
④衛生管理者資格とは
衛生管理者資格は、一定規模以上の職場で働く人たちの安全と健康を守るために必要な国家資格です。ドラッグストアでもスタッフの労働環境を整える目的で配置が求められる場合があります。
特にチェーン展開している企業では、法律で衛生管理者の配置が義務づけられるケースもあるため、資格保有者は重宝されるでしょう。
資格取得には実務経験が必要なため、就職後すぐに目指せるものではありません。ただし、将来的に人事や管理職を目指すなら、知識として持っておくことが役立ちます。
⑤化粧品検定とは
化粧品検定(日本化粧品検定)は、化粧品の成分や美容に関する知識を問う民間資格です。スキンケアやメイク用品の取り扱いが増える中で、こうした知識は接客力の向上にもつながります。
検定は1級から3級まであり、誰でも受験可能です。学生のうちに取得すれば、面接で美容や接客への関心を具体的に伝えられる材料になります。
特に美容部門への配属を希望している人やコスメ関連の仕事に就きたい人にとっては、有利な資格といえるでしょう。
ドラッグストア業界が抱える課題

ドラッグストア業界は一見すると順調に見えますが、実際には多くの課題を抱えています。市場の変化や社会的ニーズの多様化により、これまでの成長モデルでは通用しない場面も増えています。
ここでは、ドラッグストア業界が抱えている課題について解説します。今後この業界で働くことを考えている就活生にとっては、現状を正しく把握することが大切です。
- コンビニやECとの競合激化
- 専門人材不足による人材枯渇
- 医薬品販売における規制強化
- 店舗の過剰出店による市場飽和
- 高齢化社会に伴うサービス多様化
①コンビニやECとの競合激化
近年、ドラッグストア業界はコンビニやECサイトとの競争が一段と激しくなっています。とくに日用品や食品においては、コンビニの立地や利便性が強みとなり、差別化が難しくなっているのが現状です。
また、ネット通販ではAmazonや楽天をはじめとする大手サイトが医薬部外品まで取り扱っており、自宅にいながら購入できる環境が整っています。
こうした便利さが広がる中、リアル店舗ならではの価値をどう提供するかが課題です。
たとえば、店舗スタッフによる健康相談や、地域住民への寄り添ったサービスなど、人だからこそできる対応に力を入れることが、差別化のカギを握るでしょう。
②専門人材不足による人材枯渇
ドラッグストア業界では、薬剤師や登録販売者といった専門人材の確保が難しくなっています。店舗の増加により必要な人員は増える一方ですが、それに見合う採用が追いついていません。
とくに地方では人材が集まりにくく、都市部とのバランスの偏りも課題です。このままではサービスの質に影響が出る恐れがあるでしょう。
そのため、企業は待遇や働きやすさを見直し、研修制度の強化なども進めています。これから業界を目指す学生にとっては、専門資格の取得が大きな強みとなるはずです。
③医薬品販売における規制強化
医薬品の販売に関する法律や規制が強化されていることも、業界にとって無視できない課題です。
とくに一般用医薬品の販売については、登録販売者の常駐が求められるなど、以前に比べて厳しい条件が設けられています。
この影響で、登録販売者がいない時間帯には一部商品を販売できないケースもあり、売上に直結する問題となっています。
消費者の安全を守るためには必要な措置ですが、現場運営の柔軟性が損なわれるという側面もあります。
今後は、AIによるサポートやシフト体制の見直しなど、規制に対応しつつ業務効率を保つ工夫が必要です。
④店舗の過剰出店による市場飽和
ここ数年、ドラッグストア各社が積極的に出店を進めた結果、市場は飽和状態に近づいています。
とくに同じエリア内に複数の店舗が並ぶ状況では、顧客の取り合いが激しくなり、売上や利益率の低下を招いています。
新しい店舗が増えることで、既存店舗の売上が分散し、スタッフの士気にも影響が出ることがあるでしょう。無理な拡大路線は、かえって企業全体の安定性を損なうリスクもあります。
これからは、新規出店よりも既存店舗の強化や地域ニーズに合わせたサービス展開が求められます。就活生にとっても、企業の出店戦略に注目してみてください。
⑤高齢化社会に伴うサービス多様化
高齢化が進む日本では、ドラッグストアの役割も変化しています。単なる「商品を売る店」ではなく、地域の健康を支える存在としての期待が高まっているのです。
たとえば、介護用品の販売や在宅医療のサポート、健康チェックイベントの開催など、提供するサービスの幅は年々広がっています。
こうした取り組みには、医療や介護に関する知識だけでなく、丁寧な接客や柔軟な対応力も求められるでしょう。
そのため、薬剤師や理系出身者だけでなく、文系の学生にも活躍のチャンスが広がっています。社会に貢献したいという気持ちを持つ方にとっては、やりがいのある職場になるはずです。
ドラッグストア業界に向いている人物像
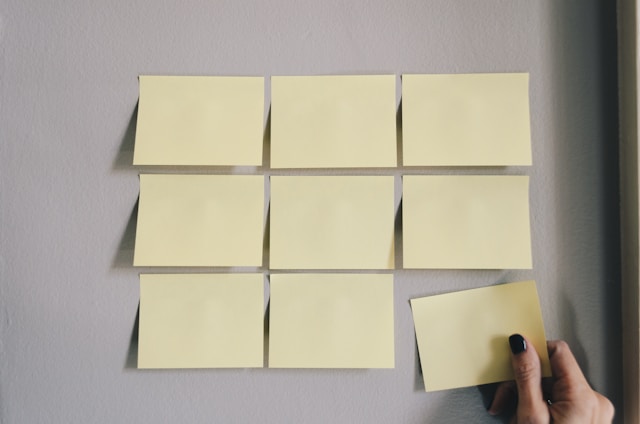
ドラッグストア業界は、単なる物販ではなく、地域の健康や美容を支える生活インフラとしての役割を果たしています。そのため、業界に適した人物像にはいくつかの共通点があります。
ここでは、業界への適性を判断するうえで重要な5つの特性について詳しく紹介します。
- 人と接することが好きな人
- 医薬品や美容に関心がある人
- 臨機応変な対応ができる人
- チームで協力できる協調性のある人
- 地域社会に貢献したい意欲のある人
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①人と接することが好きな人
ドラッグストアでは接客の機会が多く、人と関わることを楽しめる人に向いています。薬の説明や商品案内など、来店者との会話を通じて信頼を築くことが求められる場面が日常的にあります。
相手の立場に立った丁寧な対応ができるかどうかが重要なポイントです。反対に、人とのやり取りを煩わしく感じる場合は、業務そのものが負担になりやすいかもしれません。
接客の質は売上やリピーターの獲得にも直結します。人との会話を前向きに楽しめることは、業界で働くうえで大きな強みとなるでしょう。
②医薬品や美容に関心がある人
ドラッグストアでは、医薬品や化粧品、サプリメントなど幅広い商品を扱います。そのため、日頃から健康や美容に興味を持っている人には働きやすい環境といえます。
特に登録販売者などの資格を取得すれば、より専門的なアドバイスができるようになり、キャリアアップにもつながるでしょう。
知識は入社後に習得可能ですが、そもそも関心がなければ継続的な学習が難しくなります。お客さまからの質問に自信を持って対応するには、日々の情報収集や学ぶ姿勢が不可欠です。
③臨機応変な対応ができる人
マニュアルだけに頼らず、その場に合った判断ができる柔軟性が求められます。状況を読み取り、周囲と連携しながら行動できる人は、現場での信頼を集めやすいでしょう。
現場では、予定通りに進まないことがよくあります。たとえば、急な混雑で複数の接客を同時に行ったり、体調不良のお客さまに迅速に対応したりする場面もあります。
予測不能な出来事にもうまく対応できる人ほど、業界での適応力は高いといえます。
④チームで協力できる協調性のある人
ドラッグストアでは、薬剤師や登録販売者、パート・アルバイトなど多様な立場のスタッフが協力して業務を進めています。1人で完結する作業は少なく、チームワークが欠かせません。
たとえば、在庫管理や品出し、レジ対応など、それぞれの役割を理解して支え合う姿勢が求められます。協調性が不足していると連携が乱れ、業務全体の効率が落ちてしまいます。
周囲に気を配り、必要なときに声をかけられる人は、職場で信頼されやすくなるでしょう。
⑤地域社会に貢献したい意欲のある人
ドラッグストアは、地域住民の健康を支える存在としての役割も持っています。そのため、地域に根ざしたサービスを提供したいという思いがある人には、やりがいを感じられる職場です。
たとえば、高齢者への健康相談や子育て世代への商品提案など、地域のニーズに応じた対応が求められます。こうした姿勢はお客さまからの信頼にもつながるでしょう。
「人々の生活を支えたい」という気持ちを持つことで、仕事へのモチベーションも自然と高まります。
ドラッグストア業界で評価される自己PRのポイント

ドラッグストア業界は、接客対応だけでなく専門知識や地域貢献への姿勢など、さまざまな力が求められます。
どのような自己PRが評価されやすいのかを知ることは、就職活動を有利に進めるうえで欠かせません。ここでは、特に評価されやすい5つのポイントを紹介します。
- 接客スキルの高さをアピールする
- 医薬品や商品知識の習得意欲を伝える
- チームワークを重視した経験を伝える
- 困難を乗り越えたエピソードを伝える
- 地域貢献活動の経験を伝える
①接客スキルの高さをアピールする
接客スキルは、ドラッグストアで特に重視される要素の一つです。店頭業務の多くは顧客対応が中心となるため、商品知識よりもまず「感じの良さ」が求められます。
たとえば、アルバイトで「ありがとう」と感謝された経験がある場合、そのエピソードを用いて、相手の立場に立った対応ができることを伝えてみてください。
接客は単なる作業ではなく、感情のコントロールや臨機応変な判断力も求められる奥深いものです。
ありふれた話に聞こえるかもしれませんが、「どう対応し、どのような工夫をしたのか」まで具体的に説明することで、自分の強みとしてしっかり伝わります。
現場で活躍できる人材であることをアピールしましょう。
②医薬品や商品知識の習得意欲を伝える
医薬品を取り扱う業界として、学ぶ姿勢は非常に重要視されています。たとえば、「登録販売者の資格を目指して勉強している」といった努力があると好印象です。
大学の授業外で健康関連のニュースをチェックしているなど、日頃から興味を持って情報を収集していることを伝えるのも効果的でしょう。
企業側は、知識をすでに持っているかどうかよりも、学ぶ意欲があるかを重視します。学びを楽しむ姿勢がある学生は、成長の可能性が高いと判断されます。
知らないことに対して前向きに取り組めることをしっかり伝えてください。
③チームワークを重視した経験を伝える
ドラッグストアでは、スタッフ同士が協力し合いながら業務を進めるため、チームワークは欠かせません。
サークル活動やゼミ、アルバイトなどで「他人と協力して成果を出した経験」がある場合、それをアピールしましょう。
自分がリーダーでなくても問題ありません。たとえば、仲間のフォローをしたり、周囲に気を配って行動したりした経験は、十分に評価されます。
どのように信頼関係を築き、課題に向き合ったのかを具体的に示すことが大切です。協調性のある人材であることを自然に伝えることができるでしょう。
④困難を乗り越えたエピソードを伝える
現場では、予想外の出来事やプレッシャーにどう対処するかが問われます。そのため、困難に直面した経験と、それをどう乗り越えたかを語ることは非常に有効です。
たとえば、シフトが回らなくなった際に調整役を担った経験や、失敗を糧にプレゼンを成功させた経験などがあれば、それを具体的に伝えてみてください。
大事なのは失敗を隠すことではなく、そこから何を学び、どう成長につなげたかです。前向きに課題を乗り越えようとする姿勢は、企業が重視するポイントのひとつです。
実体験を交えて、自分の粘り強さや行動力を自然に示しましょう。
⑤地域貢献活動の経験を伝える
ドラッグストアは地域に密着した存在であり、地域社会への関心や貢献の姿勢は強く評価されます。
たとえば、地元でのボランティア活動や、地域イベントの運営に携わった経験があれば、それは大きなアピールポイントになります。
企業は、単に商品を販売するだけでなく、地域の健康や暮らしを支える役割も担っています。その価値観に共感していることを自己PRに盛り込むことで、自社との相性の良さをアピールできます。
地域とのつながりにやりがいを感じている気持ちを、率直に伝えてください。
ドラッグストア業界に刺さる志望動機例文

ドラッグストア業界への就職を検討している方にとって、どのような志望動機が評価されるのかは気になるところです。
このセクションでは、職種ごとに実際に使える志望動機の例文を紹介し、応募書類の作成に役立てていただけます。
また、志望動機がそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの志望動機テンプレを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
志望動機が既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。
【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
例文①販売職
就職活動においてドラッグストア業界を志望する大学生にとって、「なぜこの業界なのか」「なぜ販売職なのか」を明確にすることが大切です。
ここでは、日常の経験をきっかけにドラッグストア業界に興味を持った大学生の志望動機例を紹介します。
| 大学時代、一人暮らしを始めてから近所のドラッグストアを頻繁に利用するようになり、生活に密着した存在であることを実感しました。 特に風邪をひいた際、薬の選び方に迷っていた私に、スタッフの方が丁寧に相談に乗ってくださり、安心して購入できた経験が印象に残っています。 商品を売るだけでなく、生活を支える役割があることに感動し、私もそんな存在になりたいと感じました。 人と接することが好きで、誰かの役に立つ仕事に就きたいという思いから、販売職を志望しています。 お客様の不安や疑問を一つひとつ丁寧に解消し、信頼されるスタッフを目指して努力したいと考えています |
「日常の利用経験から業界への関心が生まれた」という流れは自然で共感を得やすいです。
志望動機を書く際は、自分の体験を具体的に描きながら、なぜ販売職を選んだのかを丁寧に伝えることがポイントです。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
例文②薬剤師
ドラッグストア業界の今後を考えるうえで、薬剤師としての志望動機を示す例文を紹介します。大学生活での身近な経験をもとに、将来のキャリアにどのようにつなげられるかを意識して書かれています。
| 大学時代、サークル活動が忙しくて体調を崩したとき、近くのドラッグストアで薬を購入した経験があります。 薬剤師の方が症状を丁寧に聞いてくれ、生活習慣の改善方法までアドバイスしてくれたことがとても心強く、安心できました。 この体験から、薬を販売するだけでなく、地域の人々の健康を支える存在として薬剤師の役割を実感しました。 今後のドラッグストア業界は高齢化やセルフメディケーションの浸透によって、より身近な健康相談の場としての重要性が高まると思います。 私はその一員として、地域に根ざした信頼される薬剤師になりたいと考えています。 |
大学生らしい日常的なエピソードを具体的に入れることで、読者に共感を持たせながら志望動機を自然に展開できます。
業界の今後について触れつつ、自分の役割をどう重ねるかを意識して書くと説得力が高まります。
例文③登録販売者
登録販売者を志す理由について、大学生活での実体験を交えながら伝える例文を紹介します。読者が共感しやすく、現場で働く姿が想像できるような内容を意識しましょう。
| 大学1年生のとき、実家の近くにあるドラッグストアでアルバイトを始めました。 最初はレジ業務だけでしたが、次第にお客様に商品の説明を求められることが増え、薬の知識がない自分に歯がゆさを感じるようになりました。 そんなとき、登録販売者という資格があることを知り、薬の正しい知識で人を支える仕事に魅力を感じました。 高齢のお客様が多い地域だったため、体調に合わせた商品の提案ができる登録販売者になりたいと考えるようになりました。 今後、セルフメディケーションの重要性が高まる中で、地域に密着した信頼される存在として働けるよう努力していきたいです。 |
アルバイト経験をきっかけにした動機は説得力があります。地域性や今後の社会的ニーズに触れることで、より現実的で志のある印象を与えましょう。
例文④バイヤー
今回は、大学時代の経験をもとに、バイヤー職に対する興味が芽生えたきっかけを語る例文を紹介します。
ドラッグストア業界で今後求められる「提案力」や「消費者視点」をアピールするには、身近な体験をうまく活かすことがポイントです。
| 大学時代、ゼミ活動の一環で地域密着型の小売店を訪問し、商品の仕入れや売れ筋の傾向についてヒアリングする機会がありました。 その際、担当の方が「お客様の声を聞いて商品を選ぶ」と話していたのが印象的で、仕入れには戦略だけでなく感覚や地域性も必要だと感じました。 また、普段からドラッグストアで新商品をチェックするのが習慣で、実際にSNSで話題の商品が棚に並んでいるのを見るたびに、どのような流れで店頭に並ぶのか気になっていました。 こうした体験を通じて、バイヤーとして消費者のニーズをいち早くキャッチし、それを店舗に反映させる仕事に魅力を感じ、志望しました。 |
大学での活動や日常の買い物体験を通して、バイヤーの仕事に興味を持った過程を自然に伝えた例文です。
難しい言葉を使わず、身近な体験から志望動機をつなげることが、読み手に共感されやすい文章につながります。
例文⑤店舗マネージャー
大学生活の中でリーダーシップを発揮した経験や、人と関わることの楽しさを感じたエピソードを活かした志望動機の例文を紹介します。
| 大学2年生のとき、学園祭実行委員として模擬店エリアの運営リーダーを担当しました。20名以上のメンバーと協力しながら、企画から当日の運営、トラブル対応まで経験しました。 このとき、スムーズに業務を進めるためには、メンバー一人ひとりの個性を活かした役割分担や、相手の立場に立った声かけが必要だと学びました。 この経験から、人と関わる中でチーム全体を動かしていくことにやりがいを感じ、将来は人をまとめる立場で働きたいと考えるようになりました。 貴社では多くの店舗スタッフと連携しながら、売場づくりやマネジメントを行うことに魅力を感じており、地域のお客様に信頼される店舗づくりに貢献したいと考え、志望いたしました。 |
リーダー経験を通して学んだことと、店舗マネージャーという職種へのつながりを明確に示すことで、説得力のある志望動機になります。
エピソードには人数や役割など具体性を持たせると、印象が強まります。
ドラッグストア業界の展望と将来性を理解しておこう!

ドラッグストア業界は、医薬品・日用品・化粧品など幅広い商品を提供し、地域の生活インフラとして重要な役割を果たしています。
現在、市場規模は拡大傾向にある一方で、ECやコンビニとの競争激化、人材不足、規制強化といった課題にも直面しています。
しかし、オンライン販売の拡大や健康サポート機能の強化、地域密着型サービスの充実など、今後の成長余地は依然大きいと言えるでしょう。
ドラッグストア業界で活躍するには、医薬品や美容への関心、人と接することが好きな姿勢、地域社会への貢献意欲が求められます。
志望動機や自己PRでは、これらの強みを具体的に伝えることが重要です。今後もこの業界は、生活者の健康と暮らしを支える存在として進化し続けるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













