【就活SPI対策】言語・非言語の頻出問題と解き方
「就活でSPIって、どこまで対策すればいいのか分からない…」
多くの企業で選考に導入されているSPI試験。特に総合職を志望する就活生にとっては、避けて通れない関門です。
しかし、「言語」「非言語」「英語」「性格検査」など幅広い出題内容に、何から手をつければよいか悩む人も多いはず。
そこで本記事では、SPIの全体像から分野別の頻出問題、効果的な学習法、さらにはおすすめの参考書や練習問題まで、対策方法を徹底解説していきます。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
SPIとは?

就職活動でよく見かける「SPI」とは、リクルートが開発した総合適性検査のことです。企業が新卒採用で応募者の能力や性格を判断するために用いるもので、選考の合否に直結するものがほとんどです。
SPIには、言語分野や非言語分野などの学力を測る問題に加えて、性格適性検査や英語検査なども含まれます。つまり、単に知識を問うだけではなく、物事の考え方や性格傾向まで評価される試験です。
就活成功の第一歩として、SPIへの理解を深めておきましょう。
SPIの出題内容

SPIは、就職活動で多くの企業が実施している適性検査です。学力だけでなく、論理的思考力や性格傾向など、さまざまな視点から就活生を評価します。
ここでは、SPIで出題される主な分野を紹介します。
- 言語分野
- 非言語分野
- 英語
- 構造的把握力
- 性格検査
① 言語分野
言語分野では、語彙力や読解力、文法の知識を活用しながら設問を読み解く力が求められます。出題される問題は短文や長文を中心とし、論理的に文章を理解できるかどうかが問われます。
また、限られた時間内に多くの設問を処理するため、内容を要点ごとに素早く把握するスキルも重要です。問題文の語句や構文に惑わされず、全体の文脈や論理展開に注目する視点が求められます。
対策の際は問題の形式に慣れることはもちろん、読解スピードと理解力のバランスを意識した練習を重ねることが効果的でしょう。
② 非言語分野
非言語分野では、計算や論理、条件整理といった、いわゆる数的推理の力が問われます。
内容は中学レベルの数学をベースとしていますが、単に数字を扱うだけではなく、状況を読み解きながら合理的に答えを導く力が必要です。
出題形式には一定の傾向があり、問題のパターンを把握することで効率的に解答できるようになります。
全問正解を目指すのではなく、解ける問題を確実に拾う姿勢が得点に直結するでしょう。
③ 英語
英語の出題は企業によって異なりますが、主に語彙や英文法、英文の読解が中心となります。
英語の実務的な読解力を測る目的で導入されていることが多く、基本的な知識に加え、文章を正確に理解する力が必要です。
英語が得意な人でも、SPI特有の出題形式に慣れていないと苦戦することがあるため注意が必要です。
読み飛ばしや読み間違いを防ぐためにも、問題演習を通して一定のリズムを身につけることが重要です。
④ 構造的把握力
構造的把握力の分野では、情報の並びや図形の配置などから、規則性や関連性を見出す力が試されます。表面的な情報だけでなく、その背後にある構造を素早く認識できるかどうかが重要です。
この分野は出題される企業が限られているものの、試験に含まれる場合は他の分野と比べても難易度が高い傾向があります。
問題自体は図形や表の並び替えなど視覚的なものが多く、読解よりも空間的な理解力が試されます。
慣れていないと戸惑う可能性が高いため、事前に出題の有無を確認したうえで、必要な場合は重点的に対策を行いましょう。
⑤ 性格検査
性格検査では、就活生の価値観や行動パターン、対人姿勢などが測定されます。自分の意見や性格に関する選択肢に答える形式で、論理的な正解がないため、戸惑う人もいるかもしれません。
ただし、この検査では一貫した回答が求められるため、自分自身の性格をよく理解しておくことが大切です。
面接やエントリーシートとの整合性を考慮しながら、無理のない形で一貫性のある回答を心がけてください。
SPIの受検方法

SPIの受検方法には複数の形式があります。それぞれに特徴があるため、企業ごとの選考方法を事前に確認しておくことが大切です。
また、受検形式によって求められるスキルや準備のポイントが異なるため、自分にとっての適応力も含めて見極めることが重要ですよ。ここでは、代表的な4つの受検方式について詳しく説明します。
- テストセンター方式
- Webテスティング方式
- ペーパーテスティング方式
- インハウスCBT方式
① テストセンター方式
テストセンター方式は、専用の試験会場に出向いて、備え付けのパソコンを使用して受験するスタイルです。全国各地に会場が設置されており、多くの大手企業がこの方式を導入しています。
予約制となっており、応募者は企業からの案内をもとに希望日時を選択して受験します。
この方式では、事前に問題が配布されたりすることはなく、毎回ランダムに出題されるため、他の受験者と問題内容が異なる可能性があります。
受験日が複数ある場合もあるため、体調管理も含めてスケジュールを組み立てることがポイントです。
② Webテスティング方式
Webテスティング方式は、自宅や学校のパソコンからインターネットを通じてSPIを受験できるスタイルです。
現在では多くの企業がこの方式を採用しており、時間と場所に柔軟性があるのが大きなメリットです。
試験は決められた期間内であれば、好きなタイミングで受験できることが多く、移動の手間がないため非常に便利です。
実際の環境に近い状態で模擬試験を繰り返すことで、本番でのミスを防ぐことができるでしょう。
③ ペーパーテスティング方式
ペーパーテスティング方式は、紙に印刷された問題用紙とマークシート形式の解答用紙を使って受験する、従来型のスタイルです。
現在では少なくなってきていますが、一部の中小企業や専門職志望の採用選考などで採用され続けています。
紙ベースの模擬問題集や過去問を使って本番に近い環境で練習しておくと、自然と対策が身につきますよ。
④ インハウスCBT方式
インハウスCBT方式は、企業が自社のオフィスや指定施設に試験設備を設け、受験者がそこでSPIをパソコンで受けるスタイルです。
CBTは「Computer Based Testing」の略で、パソコンを使った試験という点ではテストセンター方式と類似していますが、会場が企業内という点が異なります。
この方式の特徴は、企業によって試験の運用方法や出題内容にばらつきがあることです。
オフィスでの受験のため、リクルーターや社員の目がある環境下での受験になる場合もあります。態度やマナーまで見られている可能性もあるため、試験に集中するだけでなく、全体的な印象も意識して行動しましょう。
SPIの対策スケジュール
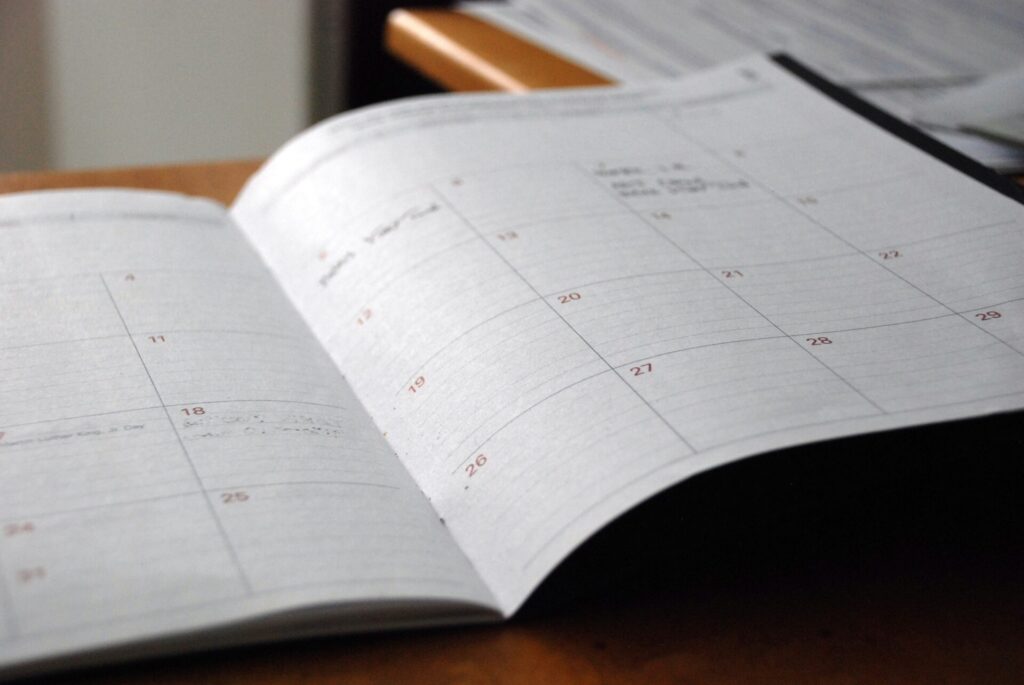
SPIの対策は、就職活動を成功させるうえで早めのスタートがカギになります。というのも、SPIの実施時期や内容は企業ごとに異なるため、直前になって慌てる学生も少なくないからです。
ここでは、SPI対策を始めるタイミングと、必要な学習時間の目安について解説します。
- 対策開始のタイミング
- 必要な学習時間
① 対策開始のタイミング
SPIの対策は、大学3年生の夏休みごろから始めるのが理想的です。
なぜなら、夏以降のインターン選考や早期選考でSPI試験が課されることが多く、早めに対策を進めておけば、その場で慌てずに済むからです。
特に大手企業を志望する場合、応募者数が多いため、SPIでのふるい落としが厳しくなる傾向があります。
焦らず確実に力をつけたいのであれば、早めに行動を始めることが何よりも大切です。
② 必要な学習時間
SPIの対策に必要な学習時間は、一般的に30〜50時間程度が目安とされていますが、それはあくまで平均的なケースにすぎません。
学力の個人差や得意・不得意分野によって、必要な時間は大きく異なります。
まずは模擬問題を解いてみて、自分の弱点を明確にしましょう。そのうえで、優先順位をつけて学習時間を配分することが効率的な進め方です。
忙しい就活期間中でも取り組めるよう、無理のないスケジュールを立てることが成功への近道といえるでしょう。
SPIを突破するための効果的な対策方法

SPI試験は、就職活動において多くの企業が導入しているため、対策の有無が選考結果に直結します。効率よく得点を伸ばすには、出題傾向の把握から苦手克服、時間管理まで段階的な準備が求められます。
ここでは、SPIを突破するための具体的な方法について6つの観点から紹介します。
- 出題傾向を把握する
- 問題集を繰り返し解く
- 公式や解法を暗記する
- 苦手分野を重点的に対策する
- 時間配分を意識して解く
- 模擬試験で本番に慣れる
① 出題傾向を把握する
SPIは「言語分野」「非言語分野」「英語分野」「構造的把握力」「性格検査」の5領域で構成されています。出題範囲が広く見えるかもしれませんが、企業や業界によって出題される内容や比重は異なります。
そのため、志望企業がどの形式を採用しているのかを早めに確認することが重要です。
出題傾向を知ることは、不安の軽減にもつながるはずです。
② 問題集を繰り返し解く
SPI対策では、実践形式の問題集を使って演習を重ねることが非常に重要です。初めは解くスピードが遅くても、繰り返し同じ問題を解くことで自然と正答率が向上していきます。
特に1冊の問題集をやり込むことで、問題の傾向や解法のパターンが頭に入りやすくなります。
問題集を何周もこなすことは地道な作業ではありますが、確実に力がつく最も基本的で効果的な方法といえるでしょう。
③ 公式や解法を暗記する
非言語分野では、公式や解法の暗記が得点アップのカギになります。
たとえば、割合・損益算・仕事算・速度算などは、出題される形式がある程度決まっており、定番の公式を覚えておけばスムーズに解けるようになります。
こうした問題を素早く解くには、計算そのものよりも手順や考え方を理解しておく必要があります。
苦手意識のある人ほど、早い段階で基礎固めをしておくことが必要です。知識を武器に変えて、得点源を増やしましょう。
④ 苦手分野を重点的に対策する
SPIの得点力を上げるには、得意な分野を伸ばすことも大切ですが、苦手分野の克服がより効果的です。
特に非言語分野は、算数や数学の応用問題が中心で、苦手と感じる学生も少なくありません。ですが、実際の出題パターンは一定しているため、繰り返し練習すれば誰でも克服できる範囲です。
まずは模擬試験や問題集を使って、自分がどの分野でつまずいているのかを明確にしましょう。そして、そこに集中して取り組むことで、弱点を強みに変えられますよ。
⑤ 時間配分を意識して解く
SPI試験は制限時間内でいかに正確に解答できるかが問われます。いくら知識があっても、時間配分が適切でなければ、途中で終わってしまい本来の実力を出し切れません。
そこで、普段の練習から時間を測って取り組むことが効果的です。1問にかける時間の目安を決め、全体のペース配分を意識することで、焦らずに試験に臨めます。
試験対策の一環として、時間配分にも意識を向けてください。
⑥ 模擬試験で本番に慣れる
SPIに向けた学習を積み重ねても、本番に緊張してしまっては実力を発揮できません。そのため、模擬試験を活用して本番に近い環境での演習を行うことが非常に効果的です。
時間配分や問題構成、解答の感覚を体で覚えておけば、本番でも落ち着いて取り組めるようになります。
最終的な仕上げとして、模擬試験を有効に活用してください。
SPI対策におすすめの参考書

SPI対策を始めようとしたとき、「どの参考書を選べばいいのか分からない」と感じる人は少なくありません。
実際、書店にはたくさんのSPI関連本が並んでいて、どれが自分に合っているのか判断しにくいものです。ここでは、SPIの出題傾向に対応しやすく、選考本番でも役立つ参考書を紹介します。
目的に合った1冊を選ぶことで、効率よく対策を進めることができるでしょう。
- 総合対策に使える王道の参考書
- 非言語に特化した対策書
- 初学者でも取り組みやすい入門書
① 総合対策に使える王道の参考書
『最新!これが本当のSPI3テストセンターだ!2026年度版』(著:SPIノートの会)
Amazonで見る
SPI全体の出題範囲をカバーしたい人には、この一冊が非常に心強い味方になります。
言語・非言語に加え、性格検査や構造的把握力検査、さらにはテストセンター形式にも対応しており、あらゆる企業のSPIに幅広く対応できる点が魅力です。
また、模擬試験形式の章もあり、自分の実力を測ることも可能です。全体像をつかみながら苦手な分野もピンポイントで補強できるため、時間のない就活生にとって、効率的な1冊といえるでしょう。
② 非言語に特化した対策書
『これが本当のSPI3だ![非言語分野]2026年度版』(著:SPIノートの会)
Amazonで見る
数的処理や資料解釈など、非言語問題に対する苦手意識を持っているなら、この本が有力な選択肢になります。
非言語に特化しているため、出題されるテーマを細かく分類しており、1つひとつ段階的に学べるよう設計されています。
本番を想定した練習問題が豊富にあり、試験の時間配分やスピード感を身につける練習にもなります。非言語がネックとなっている人にとって、苦手克服のきっかけになる1冊といえるでしょう。
③ 初学者でも取り組みやすい入門書
『SPI3完全版 2026年度版』(著:成美堂出版編集部)
Amazonで見る
SPIに対してまだ本格的に勉強していない場合、まず何から始めればいいのか分からないという悩みを抱えがちです。
そんなときにぴったりなのが、この『SPI3完全版』です。内容は基礎中心に構成されており、はじめてのSPI対策に最適といえます。
基本を固めたい人、SPIの全体像をまず掴みたい人は、まずこの1冊から始めることをおすすめします。
SPI言語分野の練習問題

SPIの言語分野では、主に文章の読解力や語彙力が問われます。ここでは、それぞれの問題形式について詳しく解説し、効果的な練習方法や注意点を紹介します。
言語分野で安定して得点を取れるようになると、SPI全体の結果にも良い影響が出るでしょう。
- 二語関係問題
- 熟語問題
- 語句の用法問題
- 文の並べ替え問題
- 空欄補充問題
- 長文読解問題
① 二語関係問題
二語関係問題では、語彙の意味や言葉同士の論理的なつながりを理解する力が求められます。例えば「医者:患者」のように、職業とその対象といった関係性を見抜けるかが問われます。
この問題に苦手意識を持つ人の多くは、言葉のつながりを直感だけで判断してしまいがちです。まずは「同義語」「対義語」「道具と使用者」などのパターンを意識すると、関係性の整理がしやすくなります。
また、普段の会話や読書の中でも、言葉同士の関係を意識してみてください。類似問題を繰り返し解くことで、自然と感覚が身についていくはずです。
例題
「鍵:扉」に対して、最も近い関係にあるものを選びなさい。
ア:包丁:肉
イ:医者:患者
ウ:スイッチ:電気
エ:ハサミ:紙
回答
正解は「ア:包丁:肉」
理由:どちらも「道具とその対象物」の関係にあります。
② 熟語問題
熟語問題では、四字熟語や二字熟語の意味、使い方を問われることが多くなっています。空欄にふさわしい熟語を選ぶ力や、意味の近い語の違いを見分ける力が必要です。
つまずきやすいポイントは、意味だけを暗記してしまい、使い方まで理解していないケースです。対策として、構成されている漢字の意味から熟語全体のイメージをつかむ練習が効果的でしょう。
また、例文とあわせて覚えることで、実際の使い方をより深く理解できます。日常的に新聞やニュース記事を読むことも、語彙力向上につながります。
例題
次の空欄に当てはまる適切な四字熟語を選びなさい。
「困難にも負けず、〇〇〇〇の精神で挑戦し続けた。」
ア:一期一会
イ:七転八起
ウ:晴耕雨読
エ:起死回生
回答
正解は「イ:七転八起」
理由:何度失敗しても立ち上がる精神を表しています。
③ 語句の用法問題
語句の用法問題では、ある語句が文中で正しく使われているかを判断します。語彙の知識だけでなく、文脈を読む力も試される問題です。
ありがちなミスとして、語の意味は知っているけれど正確な使い方が分からず、誤った選択肢を選んでしまうことが挙げられます。辞書を引くときには、意味だけでなく例文も確認しましょう。
さらに、自分でその語句を使った文を作ってみると、理解がより深まります。こうした練習を積み重ねれば、自然と正しい使い方が身につくはずです。
例題
次のうち、語句の使い方として正しいものを選びなさい。
ア:彼の意見は雰囲気を壊さずに「水を差した」。
イ:大事な会議で「青天の霹靂」のような失敗をしてしまった。
ウ:試合は互角だったが、最後は「満を持して」勝利をつかんだ。
エ:彼は思い切って「背水の陣」を敷いて転職活動に挑んだ。
回答
正解は「エ:背水の陣」
理由:逃げ道を断って全力で物事に挑むという意味で、使い方が適切です。
④ 文の並べ替え問題
文の並べ替え問題では、文や文節を意味の通る順番に並べ替える力が必要です。簡単そうに見えて意外とミスが多いため、油断は禁物です。
「だから」「しかし」などの接続語から流れをつかむと、論理的に自然な順序が見えてきます。読解力の土台を築くうえでも有効な問題形式といえます。
例題
次の文を意味の通る順番に並べ替えなさい。
ア:彼は諦めずに勉強を続けた。
イ:模試の結果は思わしくなかった。
ウ:努力の成果が試験当日に出た。
エ:その結果、第一志望に合格した。
回答
正解は「イ → ア → ウ → エ」
理由:模試の結果 → 勉強継続 → 努力の成果 → 合格、という時系列の流れです。
⑤ 空欄補充問題
空欄補充問題では、文章中の空欄に合う語句を選ぶことが求められます。読解力と語彙力の両方が問われるため、練習を重ねることが重要です。
選択肢を1つずつ文に当てはめて確認してみてください。こうした慎重な読み方を繰り返すことで、自然と正答率も上がっていくでしょう。
例題
次の空欄に最も適切な語句を選びなさい。
「彼女は新しい職場にもすぐに〇〇し、チームに欠かせない存在となった。」
ア:適応
イ:順応
ウ:参入
エ:定着
回答
正解は「イ:順応」
理由:新しい環境に自然となじむ様子を表す言葉として適切です。
⑥ 長文読解問題
長文読解問題では、情報を正確に読み取り、設問に答える力が求められます。文章量が多く、時間が足りなくなることも少なくありません。
効率よく解くには、設問と選択肢を先に確認してから本文を読む「設問先読み」がおすすめです。必要な情報に集中できるため、読み飛ばしや無駄読みを防げますよ。
例題
以下の文章を読み、問いに答えなさい。
「現代の若者は、かつてよりもSNSやスマートフォンを通じて多くの情報を瞬時に得られるようになった。その一方で、情報の真偽を見極める能力が追いついていないという課題もある。メディアリテラシーの重要性は今後ますます高まるだろう。」
問い:筆者が最も言いたいことは何か。
ア:SNSの利用は避けるべきである
イ:スマートフォンの普及には問題が多い
ウ:情報の真偽を見抜く力が必要である
エ:若者は情報を使いこなしている
回答
正解は「ウ:情報の真偽を見抜く力が必要である」
理由:全体を通じて筆者が訴えているのは、情報を正しく扱う力の重要性です。
SPI非言語分野の練習問題

SPIの非言語分野は、企業が受験者の論理的思考力や数量処理能力を確認するために出題される重要な分野です。
内容は高校レベルの数学ですが、就活生にとっては慣れない出題形式や時間制限が負担になることもあるでしょう。
ここでは、頻出の問題パターンごとに、押さえておきたいポイントや注意点をわかりやすく紹介します。
- 推論
- 順列・組み合わせ
- 割合と比
- 損益算
- 料金割引
- 仕事算
- 代金精算
- 速度算
- 集合
① 推論
推論問題では、与えられた情報から妥当な結論を導く力が求められます。単純な文章のように見えても、前提と結論のつながりを正しく把握しなければ正解にはたどり着けません。
条件を図や表で整理し、論理的に考える練習を積むと効果的です。焦らず冷静に情報を読み取り、必要な判断を積み重ねていくことが正答率アップのポイントでしょう。
例題
「すべてのAはBである」「すべてのBはCである」とき、次のうち必ず正しいものはどれか。
A. すべてのAはCである
B. すべてのCはAである
C. 一部のAはCである
D. 一部のCはBである
回答
Aが正解。三段論法を用いて「すべてのAはCである」と論理的に導けます。
② 順列・組み合わせ
順列と組み合わせの問題では、「順番が関係するかどうか」の見極めが非常に重要です。この違いを理解していないと、問題に合わない公式を使ってしまう可能性があります。
まずは、条件を丁寧に読み取り、順列(P)なのか組み合わせ(C)なのかを判断してください。具体的な物や人数を使って考えると、イメージしやすくなります。
例題
5人の中から3人を選んで、順番に席に座らせる場合、何通りの並べ方があるか。
回答
5P3 = 5×4×3 = 60通り。
③ 割合と比
割合や比の問題では、計算の正確さと比率の感覚が求められます。「〇%増加」と「〇倍」のような表現の違いを曖昧にしてしまうと、答えが大きくずれてしまいます。
問題を解く際は、まず「もとになる数」を意識し、図やイメージで比を整理してみてください。
例題
1000円の商品が20%引きで販売されています。販売価格はいくらか。
回答
1000円 × (1 − 0.2) = 800円。
④ 損益算
損益算は、商品を仕入れて販売する流れの中で、利益や損失を計算する問題です。混乱しやすいのは、「原価」「定価」「利益」などの用語の違いを曖昧に覚えてしまうケースです。
「利益率」や「割引価格」などの要素が絡む場合は、条件を一つずつ整理して順を追って計算するとよいでしょう。
例題
原価800円の商品を20%の利益で販売しました。販売価格はいくらか。
回答
800円 × (1 + 0.2) = 960円。
⑤ 料金割引
料金割引の問題では、割引額・割引率・支払金額といった複数の要素を正しく計算する必要があります。つまずきやすいのは、税金の扱いと割引率の計算です。
「税込」と「税抜」の違いに注意しながら、割引前の価格を明確にし、そこから段階的に割り引いていくとミスを防ぎやすくなります。繰り返し練習すれば、複雑な条件にも対応できるでしょう。
例題
定価2000円の商品が10%引きで、さらに消費税10%がかかります。支払額はいくらか。
回答
2000円 × 0.9 × 1.1 = 1980円。
⑥ 仕事算
仕事算では、複数人が協力して作業する際の進み具合を計算します。「Aさんは1時間に〇個作業する」「Bさんはその2倍のスピード」といった形で出題されることが多いです。
作業スピードを「1時間あたりの作業量」としてとらえると、正しく式を立てやすくなります。図や線分図を活用すると理解が進みます。
例題
Aさんは1時間で仕事を1/3進める。Bさんは1時間で1/6進める。2人で一緒に作業すると、何時間で終わるか。
回答
1時間あたりの進捗:1/3 + 1/6 = 1/2 → 完了まで2時間。
⑦ 代金精算
代金精算問題では、複数人でお金を出し合って支払いや割り勘を行うパターンが出題されます。「誰がいくら多く払ったのか」「どのように差額を清算するか」といった判断が求められます。
まずは全体の支出額と各人の支払額を明確にし、その平均額との差を考えれば、誰が多く払ったかが一目でわかるでしょう。シンプルに見えても、正確な計算力が問われる分野です。
例題
3人で6000円の食事代を支払った。Aは2000円、Bは2500円、Cは1500円払った。公平に分担するには、誰が誰にいくら渡すか。
回答
1人あたり2000円。Bは500円、Cは500円をAに渡す。
⑧ 速度算
速度算では、「距離」「速さ」「時間」の関係を理解することが基本です。公式自体は単純でも、「すれ違う」「追いかける」といった場面で混乱しやすくなります。
こうした問題に対応するには、まず状況を図で整理し、相対速度の考え方を身につけることが重要です。「誰と誰の差に注目するか」を明確にして式を立てると、正答にたどり着きやすくなります。
例題
2人が10km離れた地点から互いに向かって歩く。Aは時速4km、Bは時速6km。出発から何時間後に出会うか。
回答
相対速度10km/h → 10km ÷ 10km/h = 1時間後。
⑨ 集合
集合問題は、「Aに属する人」「AとBの両方に属する人」など、複数の条件を満たす要素を整理する力が必要です。間違いやすいのは、人数の重複や全体数との関係を見落としてしまうことです。
問題文の条件をベン図に書き出し、視覚的に情報を整理することで、複雑な関係性も明確になります。慣れてくれば、図を描かなくても頭の中でイメージできるようになるでしょう。
例題
30人のクラスで、英語を学ぶのは18人、数学を学ぶのは15人。両方を学ぶのは10人。どちらも学ばないのは何人か。
回答
18 + 15 − 10 = 23人がどちらかを学んでいる → 30 − 23 = 7人が学んでいない。
SPI英語検査の練習問題

SPIの英語検査は、企業によっては必須となる場合もあり、対策の有無が選考の結果に大きく影響することがあります。
ここでは、代表的な5種類の問題形式を取り上げ、それぞれの特徴や対策方法について分かりやすく解説します。
- 同意語問題
- 反意語問題
- 英英辞典形式問題
- 空欄補充問題
- 長文読解問題
① 同意語問題
SPI英語の同意語問題は、単語の意味をどれだけ深く理解しているかを問われる形式です。たとえば、「precise」に対して「accurate」を選ぶといった出題がされます。
効果的な対策としては、例文を用いて単語を覚えることが挙げられます。意味だけでなく、使われ方も一緒に理解すると記憶に残りやすくなるでしょう。
例題
Choose the word that is closest in meaning to “rapid.”
A. slow
B. steady
C. quick
D. rare
回答
C. quick
和訳
「rapid(速い)」ともっとも近い意味を持つ語を選びなさい。
A. 遅い
B. 安定した
C. 速い
D. 珍しい
解説
「rapid」は「速い」「迅速な」という意味で、「quick」とほぼ同義です。他の選択肢はいずれも意味が異なります。
② 反意語問題
反意語問題では、ある単語に対して正しい反対語を選びます。たとえば、「optimistic」の反意語として「pessimistic」を選ぶような形式です。
意味を曖昧に覚えていると、選択肢の中のひっかけに惑わされやすいため注意が必要です。この形式では、語彙力に加えて、意味を正確に理解しているかどうかが重要になりますよ。
例題
Choose the word that is opposite in meaning to “generous.”
A. selfish
B. kind
C. polite
D. friendly
回答
A. selfish
和訳
「generous(気前の良い)」の反対の意味を持つ語を選びなさい。
A. 自分勝手な
B. 親切な
C. 礼儀正しい
D. 友好的な
解説
「generous」は「惜しみなく与える・寛大な」ことを意味します。これに対して「selfish(自分本位な)」が反意語として正しい選択肢です。
③ 英英辞典形式問題
英英辞典形式の問題では、英語で書かれた定義文を読んで、その説明に合う単語を選ぶ必要があります。
英語の定義に触れる習慣をつけることで、自然と語彙力も向上します。
例題
Choose the best word that matches the following definition:
“a place where people go to see movies”
A. theater
B. museum
C. school
D. restaurant
回答
A. theater
和訳
「人々が映画を観に行く場所」と一致する語を選びなさい。
A. 劇場(映画館)
B. 博物館
C. 学校
D. レストラン
解説
定義文「a place where people go to see movies(人々が映画を観に行く場所)」は「theater」が最も適切です。他の選択肢はこの説明に該当しません。
④ 空欄補充問題
空欄補充問題では、英文の一部が空欄になっており、その文脈に合う語句を選ぶ形式です。たとえば、「She _ the piano very well.」という文に「plays」などを選ぶような出題がされます。
長文の中で出てくる空欄補充に備えて、実戦形式での練習もおすすめです。
例題
She _ to the office every morning.
A. go
B. went
C. goes
D. going
回答
C. goes
和訳
彼女は毎朝会社に_。
A. 行く(原形)
B. 行った(過去形)
C. 行きます(三人称単数現在)
D. 行っている(現在分詞)
解説
主語が「She」で、現在習慣的な動作を示すため、「go」の三人称単数形「goes」が正解です。他の選択肢は文法的に合いません。
⑤ 長文読解問題
長文読解問題では、2~4段落程度の英文を読み、その内容についての設問に答えます。テーマはビジネスや日常生活に関する内容が多く、難解な語彙よりも「スピードと正確な理解力」が重要です。
焦らず、コツコツと継続することが成功への近道です。
例題
Read the following passage and answer the question.
“Tom enjoys hiking on weekends. He usually goes to the mountains near his house. Last Saturday, he saw a deer while hiking.”
Question: What did Tom see while hiking last Saturday?
A. A bear
B. A bird
C. A deer
D. A rabbit
回答
C. A deer
和訳
以下の文章を読み、質問に答えなさい。
「トムは週末にハイキングを楽しんでいます。彼はたいてい家の近くの山に行きます。先週の土曜日、ハイキング中に鹿を見ました。」
質問:トムは先週の土曜日にハイキング中、何を見ましたか?
A. クマ
B. 鳥
C. 鹿
D. ウサギ
解説
文中に「he saw a deer while hiking(ハイキング中に鹿を見た)」とあるため、正解は「C. A deer」です。他の選択肢は記述と一致しません。
SPI構造的把握力の練習問題

SPIの構造的把握力とは、与えられた情報を論理的に整理し、全体の関係性を見抜く力を測る問題です。言語分野や非言語分野とは異なり、図や文の構造を正確に読み取る力が求められます。
対策には独自の練習が必要です。ここでは、構造的把握力の実際の練習問題を通して対策ポイントを紹介します。
- 非言語系
- 言語系
① 非言語系
構造的把握力の非言語系問題では、図や表、フローチャートなどを読み取ってルールや傾向を把握する力が求められます。
市販の問題集や無料のWebツールを使えば、毎日短時間でも練習できます。継続して取り組むことで、少しずつ感覚をつかめるようになります。
例題
以下の図形は、ある法則にしたがって左から右へと変化しています。
【図1】■→【図2】▲→【図3】◇→【図4】?
このとき、【図4】に入る図形はどれか。選択肢:A. ■ B. ▲ C. ◆ D. ◯
回答
正解はAの■です。図形は「■→▲→◇」と順番に変化しており、3種類の図形が循環していることがわかります。そのため、次に来るのは最初の■となります。
② 言語系
構造的把握力の言語系では、複数の段落や文を論理的につなげて、文章全体の構成を理解する力が求められます。
「文章の並び替え」や「前後の流れを予測する問題」が多く出題される傾向にあります。
文章の構造を意識する読書習慣が、SPI対策に直結します。毎日の中で少しずつでも続けることが、得点アップへの近道です。
例題
次の4つの文を、もっとも自然な流れになるように並び替えなさい。
ア:私は読書が好きだ。
イ:特に推理小説をよく読む。
ウ:読むと頭がすっきりする。
エ:だから本屋に行くと必ず新作をチェックする。
回答
正解は「ア→イ→ウ→エ」の順です。自分の好み(ア)を述べた後、その具体例(イ)を出し、読書の効果(ウ)に触れたうえで、行動の結果(エ)につなげると自然な流れになります。
SPI性格適性検査の対策ポイント

SPI性格適性検査では、個人の性格傾向や組織との相性が評価されます。数値化された正解がないため、どのように対策すればよいのか不安に感じる就活生も多いでしょう。
ここでは、企業が重視している観点や、実際に回答するときに注意したいポイントについて解説します。
- 評価ポイント
- 回答時に気をつけるべき点
① 評価ポイント
SPIの性格適性検査では、受験者の思考傾向や行動パターンを通じて、企業文化とのマッチ度や業務への適応性が評価されます。
とくに注目されるのは、協調性や責任感、ストレス耐性、主体性などの社会的特性です。
たとえば、チームで行動する際にどのような役割を担うか、指示に従う姿勢があるか、プレッシャーの中で冷静に行動できるかといった点が見られています。
事前に自己分析を行い、自分がどんな性格かを客観的に理解しておくことが大切です。
② 回答時に気をつけるべき点
性格検査では、「企業に好かれそうな答えを選びたい」という気持ちが先行してしまうことがあります。しかし、こうした意識が強くなりすぎると、不自然な回答や矛盾した内容になりがちです。
企業は、あくまであなたの人物像と社風の相性を確認したいと考えているため、取り繕った答えではかえってマイナス評価につながるおそれがあります。
過去の経験や判断の傾向を振り返り、「自分ならこう考える、こう動く」という軸を持っておくことで、さまざまな質問に対してもブレのない回答ができるようになりますよ。
就活におけるSPI対策の全体像を把握して成功させよう!

就活で多くの企業が導入しているSPIは、選考通過のために避けて通れない試験です。
SPIには言語・非言語・英語・構造的把握力・性格検査といった幅広い出題分野があり、それぞれに対策が必要です。
SPIを突破するためには、適切な参考書を活用し、地道な努力を継続することが成功のカギです。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。










