建設コンサルタントの志望動機|仕事内容ややりがいを徹底解説
「建設コンサルタントの志望動機って、どう書けば良いのだろう…」 就職活動を控える学生の中には、そう悩む人も多いのではないでしょうか。
専門性が高く社会貢献度も大きい建設コンサルタントの志望動機では、仕事内容ややりがいを理解したうえで、自分のキャリアビジョンと結びつけた志望動機の作成が重要です。
本記事では、建設コンサルタントの仕事内容やビジネスモデル、やりがいを解説するとともに、採用担当者の心に響く志望動機の書き方を例文付きで紹介します。あなた自身の経験や強みを活かし、説得力ある志望動機を作るための参考にしてください。
受かる志望動機のためのお助けアイテム
- 1志望動機作成ツール
- 最短3分で、AIが『志望動機』を自動で作成します。
- 2志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、選考通過率が高い志望動機が作れます。
- 3赤ペンESで志望動機を無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削し、選考通過率が上がる志望動機に
▼志望動機がまだない人はまずこれ▼
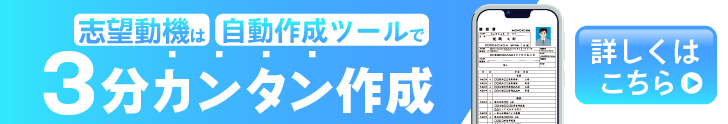

記事の監修者
記事の監修者
人事 鈴木
新卒でベンチャー企業で求人広告の新規営業を経験 入社半年でテレアポ獲得数社内1位。新卒売り上げ1位を獲得。 その後Cmind groupの人事部に入社し、新卒採用を担当。 現在は学生の面談だけではなく採用戦略や広報にも携わっている。
詳しく見る
記事の監修者
記事の監修者
吉田
新卒で株式会社C-mindに入社後、キャリアアドバイザーとして累計1000人以上の就活生との面談を経験。就活時代も大手からベンチャーまで様々な業界・職種を見てきた経験から、幅広い視点でのサポートを得意とする。プロフィール詳細
詳しく見る建設コンサルタントは志望動機が重要

建設コンサルタントを目指すとき、志望動機は合否を左右する大切な要素です。なぜなら、専門知識や技術だけでなく、公共性の高い仕事に挑む姿勢や社会的意義への理解が重視されるからです。
面接官は「なぜこの業界を選んだのか」「どのように貢献できるのか」といった点を特に見ています。そのため、漠然とした興味や安定志向だけでは十分とはいえません。
自分の経験や価値観をどう建設コンサルタントの役割と結び付けるのかが大事でしょう。
たとえば、インフラ整備を通じた地域貢献への思いを、大学での研究やアルバイトで得た課題解決の経験と関連付ければ、説得力はぐっと高まります。
採用担当者が本当に求めているのは「この人なら現場で信頼して任せられる」と感じられる動機です。だからこそ、業界研究と自己分析を重ねて、自分らしさを活かした理由をしっかり伝えてください。
また、「そもそも業界研究のやり方が分からない……」という人は、こちらの記事も参考にしてみてください。初めて業界分析をする人におすすめの「業界研究ノート」について詳しく解説していますよ。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
建設コンサルタントの仕事内容

建設コンサルタントの仕事内容は幅広く、都市計画や社会基盤を支える大切な役割を担います。就活生にとって具体的な業務を理解することは、志望動機の説得力を高める第一歩でしょう。
ここでは代表的な4つの業務について解説します。
- 事前調査業務
- 建設計画の立案業務
- 設計・計画の支援業務
- 発注者との調整業務
また、仕事内容に加えて「建設コンサルタントの年収はどれくらいなの?」と気になる方も多いですよね。以下の記事では、平均年収から企業別の年収まで解説しているのでぜひ参考にしてください。
① 事前調査業務
建設プロジェクトにおいて事前調査は欠かせない業務です。この調査は安全で効率的な計画を立てる基盤となります。
地形や地質、交通量や環境への影響を把握しなければ、後の設計で大きな修正が必要となり、コストや工期に悪影響を及ぼすかもしれません。
調査の精度が低ければ、災害リスクや住民トラブルといった問題も発生します。反対に、丁寧な調査によって課題を早期に見つければ、設計や施工で柔軟に対応でき、信頼性の高い成果物につながるでしょう。
事前調査は表立って目立たないものの、プロジェクト全体の成否を左右する役割を持ちます。志望動機を考える際は、調査の正確さや分析力に関心がある姿勢を示すことが強みになるはずです。
② 建設計画の立案業務
建設計画の立案は、プロジェクト全体の方向性を決める重要な段階です。計画の質が完成度や利用者満足度を大きく左右します。
計画では予算、工期、安全性、環境負荷への配慮など、複数の要素をバランスよく組み合わせる必要があります。
もし一つの観点に偏れば、後工程で調整が難航し、発注者や地域住民との信頼を損なう恐れがあるでしょう。そのため建設コンサルタントには、全体を俯瞰して合理的に判断する力が求められます。
法規制を踏まえつつ社会的ニーズに応えるプランを提示できれば、プロジェクトは円滑に進みます。
この計画力は就活時に「課題解決や調整を得意とする姿勢」として示すと、志望動機の具体性を高める要素になるはずです。
③ 設計・計画の支援業務
建設コンサルタントは設計会社やゼネコンと異なり、直接設計を担うよりも支援に重きを置きます。この支援業務は計画の実現性を高めるために欠かせない業務です。
支援業務では、構造の安全性やコスト効率を検討し、設計者のアイデアを現実的に落とし込むことが重要となります。
もし十分な検証が行われなければ、施工段階で設計変更が頻発し、無駄な費用や遅延につながってしまうでしょう。
支援を通じて問題を事前に防ぐことは、プロジェクト全体をスムーズに進める工夫でもあります。さらに、地域住民の安全や環境への配慮も不可欠です。
このような支援の役割を理解し、「計画の実現性に貢献したい」という意識を志望動機に盛り込むことで、説得力を強められるでしょう。
④ 発注者との調整業務
建設コンサルタントの特徴の一つが、発注者である官公庁や自治体との調整業務です。この調整力がプロジェクトを円滑に進める決め手となります。
発注者は地域のニーズや予算、政策上の制約を抱えており、技術的な提案だけでは合意形成が難しい場合があります。
そのため、専門知識をかみ砕いて分かりやすく伝え、関係者を納得させるスキルが必要です。調整がうまくいかなければ計画は停滞し、住民からの反対運動に発展する可能性もあるでしょう。
逆に、発注者の立場を理解した提案を行えば信頼が築かれ、長期的な受注にもつながります。
調整業務は「技術力とコミュニケーション力の両立」が試される場であり、志望動機に盛り込めば具体性を高められるはずです。
最短3分で建設コンサルタントに特化した志望動機を自動作成!面倒な手間はゼロ
「志望動機の完成形がわからない」
「志望動機を考えることすらめんどくさい」
「志望動機で何を書くべきかわからない」
など、志望動機を作成する際には様々な悩みがありますよね。
この『ES自動作成ツール』なら、スマホで5つの簡単な質問に答えるだけで、最短3分でそのまま使える志望動機を作成することができます。
文章を一から考えたり、構成に悩んだりする必要はありません。まずは完成した志望動機をベースにして、必要に応じて言い回しを調整するだけでもOKです。
完全無料で何度でも利用できるため、複数企業の志望動機づくりにも対応できます。「時間をかけずに、評価される志望動機を用意したい」という方は、ぜひ一度試してみてください。
▼考える時間ゼロ!志望動機を自動作成▼
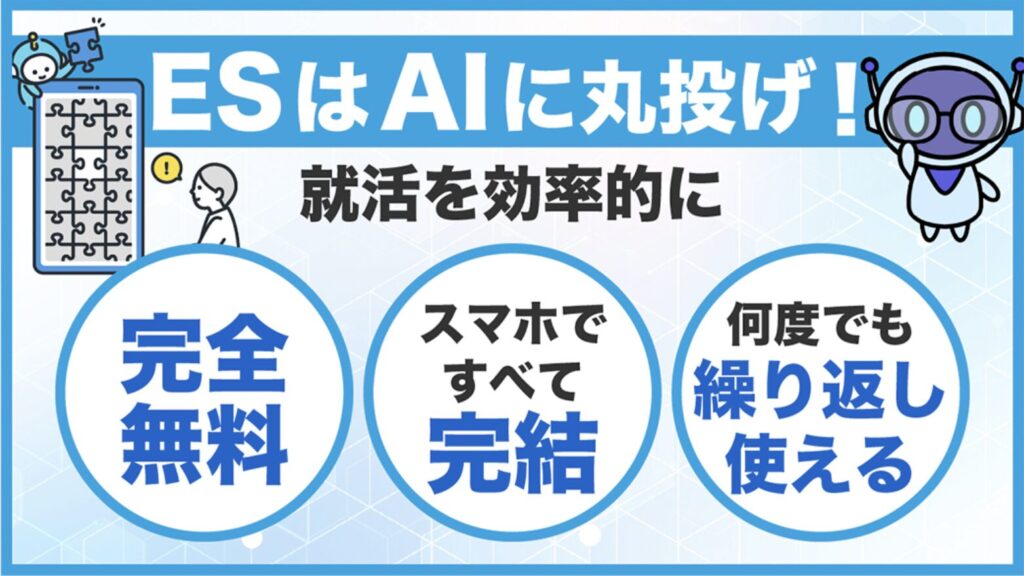
建設コンサルタントのビジネスモデル

建設コンサルタントのビジネスモデルは、公共性の高い事業と深く結びついています。事前調査から計画立案、設計支援までを担うため、安定性と社会的意義がある点が特徴です。
ここでは、公共事業や官公庁との契約、ゼネコンとの連携、収益構造の仕組みを理解することで、志望動機に具体性を持たせるヒントを解説します。
- 公共事業との関わり
- 官公庁との契約形態
- ゼネコンとの連携体制
- プロジェクトごとの収益構造
① 公共事業との関わり
建設コンサルタントは公共事業と密接に関係しています。道路や橋、上下水道など社会基盤を支える案件が多く、国や自治体からの発注で動くのが一般的です。
こうした仕事は景気の影響を受けにくく、安定した需要がある点が魅力でしょう。ただし、公共事業は入札制度による競争が激しく、コスト管理や技術力の差が受注の可否を左右します。
志望動機では「公共性に貢献したい」という表現にとどまらず、どの分野で力を発揮できるのかを具体的に述べる必要があります。
公共事業の特性を理解すれば、志望動機に説得力を加えることができるはずです。
② 官公庁との契約形態
建設コンサルタントの契約は、官公庁とのやり取りが中心です。入札方式が多く、価格だけではなく技術力や実績も重視されます。
この仕組みを理解していないと、なぜ特定の企業が安定して強いのかを見誤りかねません。大手は長年の実績と信頼から安定した受注を得やすく、中堅や新興企業は独自技術で競争力を発揮しています。
志望動機においては「入札環境で競われるからこそ技術を高めたい」といった姿勢を示すと有効です。契約形態を把握しておけば、企業研究の深みが増し、志望動機もより具体的に表現できるでしょう。
③ ゼネコンとの連携体制
建設コンサルタントはゼネコンと連携してプロジェクトを進めます。設計段階では技術的な助言を行い、施工段階では現場の課題解決を支援することもあります。
この役割を理解しないまま志望動機を書くと、仕事内容の捉え方がずれてしまう可能性があります。連携の本質は「施工と計画を結び付ける橋渡し」であり、双方の視点を理解する姿勢が求められます。
そのため「ゼネコンとの協働を通じて現場と計画を結び付けたい」と表現すると強いアピールにつながります。立ち位置を理解したうえで志望動機に盛り込むことが差別化の鍵になるでしょう。
④ プロジェクトごとの収益構造
建設コンサルタントの収益は案件ごとの契約金で構成されています。長期的にメンテナンス収入が見込める場合もありますが、基本はプロジェクト単位の収益です。
就活生が見落としがちなのは、景気や政策によって案件数が左右される点です。大規模なインフラ投資があれば収益は安定しますが、縮小期には競争が激しくなります。
この特徴を踏まえて志望動機を作ると「変化する環境でも柔軟に対応したい」という意欲を示せます。
単に「社会に貢献したい」と述べるよりも、収益モデルを理解して語ることで企業研究の深さを示せるでしょう。
また、「変化に柔軟に対応する姿勢」は志望動機だけでなく自己PRにも活かせますよ。以下の記事では、企業が求める「柔軟な対応」について解説しているので、気になった方はチェックしてみてください。
建設コンサルタントと近い建設関連業界

建設コンサルタントを目指す就活生にとって、業界全体の位置づけを理解することは志望動機を明確にするうえで欠かせません。
特に国土交通省やゼネコン、施工管理などの関連領域は密接に関わっており、それぞれの役割を正しく把握することで、建設コンサルならではの強みや価値を整理できます。
ここでは、それぞれの関連性について解説します。
- 国土交通省
- ゼネコン
- 施工管理
① 国土交通省
建設コンサルタントにとって国土交通省は最も重要な取引先の1つであり、公共事業の発注者として大きな影響を持ちます。志望動機を考える際には、この関わりを理解しておくことが欠かせません。
国交省は道路や河川、都市計画などの国家規模のインフラ整備を担っており、その調査や計画を委託する先として建設コンサルが選ばれることが多いです。
つまり、成果物が社会基盤の整備や地域の発展に直結します。この点を踏まえ、自分が社会課題の解決や地域への貢献を目指したいと語れば説得力のある志望動機につながるでしょう。
さらに、国交省との仕事は社会的意義が大きく、長期的な視点でキャリアを積める点も魅力です。
こうした背景を理解すれば、単に企業を志望するのではなく「社会インフラを支える一員になりたい」という熱意を示せます。
② ゼネコン
ゼネコンは実際に建物やインフラを施工する主体であり、建設コンサルと補完的な関係を築いています。就活生が混同しやすいのは両者の役割の違いです。
ゼネコンは現場での工事を総合的に管理するのに対し、建設コンサルは調査や設計といった上流工程を担います。
このため、建設コンサルは施工が始まる前の段階から関わり、プロジェクト全体の成否を左右する存在といえるでしょう。
ゼネコンは「形をつくる」役割ですが、建設コンサルは「形になる前の価値をつくる」役割です。
志望動機としては「社会基盤を計画する段階から関わりたい」「未来の地域像を描く役割に魅力を感じた」といった表現が効果的です。
ゼネコンとの違いを理解し、あえて建設コンサルを志望する理由を明確に伝えることが、面接での説得力につながります。
また、「ゼネコンの業務も面白そう」と興味をもった方は以下の記事もおすすめです。ゼネコンの種類や職種、求められるスキルまでを徹底解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
③ 施工管理
施工管理はゼネコンの現場に属する職種で、品質・工程・安全の管理を行います。両者の関係を理解すると、自分の志望先の位置づけがより明確になります。
施工管理は現場での判断力や統率力が求められる一方で、建設コンサルは調査や計画を通して現場が円滑に進むよう支える立場です。
役割が異なるため、志望動機では「現場をまとめるよりも、計画段階から社会基盤を支えたい」といった比較が有効でしょう。
また、施工管理が短期的な課題解決を中心とするのに対し、建設コンサルは地域や都市の将来を見据えた長期的な提案を行います。
こうした違いを理解したうえで自分のキャリアビジョンを説明できれば、業界研究を深く行っていると伝わり、志望度の高さも面接官に印象づけられます。
建設コンサルタントのやりがい

建設コンサルタントの魅力は、社会全体に長く残る成果を形にできる点にあります。ここでは具体的なやりがいを知ることで、志望動機に説得力を持たせるヒントをつかんでください。
- 地域のまちづくりへの貢献
- 大規模プロジェクトへの参画
- 社会インフラを支える責任感
- 長期的な成果が残る魅力
① 地域のまちづくりへの貢献
建設コンサルタントのやりがいの1つは、地域社会のまちづくりに直接貢献できることです。道路や橋、上下水道など生活に密着したインフラを計画や設計する業務は、住民の暮らしを支える基盤を整える役割を果たします。
例えば老朽化した施設の改修や新しい公共施設の計画は、地域の安全や利便性を高める効果があります。就活生にとっても「人の役に立ちたい」という思いを具体的に形にできる点は大きな動機になるでしょう。
さらに、住民や行政との意見交換を通じてニーズを把握し、計画に反映する過程では調整力や提案力も身につきます。
自分の専門性を活かしながら地域の発展に関われることは、建設コンサルを志望する理由として強い説得力を持つはずです。
② 大規模プロジェクトへの参画
建設コンサルタントは、都市再開発や高速道路整備といった大規模プロジェクトに携わる機会が多いです。
これらは数年から10年以上かけて進むこともあり、規模が大きい分だけ社会に与える影響も大きくなります。
若いうちから多様な専門家や大手ゼネコンと協力できるため、幅広い視野を育むことができます。
また、自分が関わった一部分が巨大な構造物として完成し、多くの人に利用される瞬間は強い達成感と誇りを得られるでしょう。
就活生にとって「スケールの大きな挑戦をしたい」という思いを実現できる場であり、志望動機にも直結します。課題は複雑ですが、それを乗り越える経験が確かな成長につながるのです。
③ 社会インフラを支える責任感
建設コンサルタントの業務は、社会インフラを安全に維持する責任を伴います。
災害時に道路や河川がどう機能するかを考え、防災や減災に結びつける役割も担うため、仕事の1つひとつが生活や命に直結しています。
責任の重さは大きなプレッシャーですが、その分やりがいも強く感じられるでしょう。就活生にとっては「社会を守る使命感」を根拠に志望理由を作れることが強みになります。
また、環境保全や持続可能な開発の視点も求められるため、社会課題の解決に貢献したい人にとって理想的な舞台です。専門知識を活かして責任を背負う姿勢は、建設コンサルに求められる大切な要素です。
また、志望動機に加えて自己PRでも「責任感がやりがいにつながる」と伝えると印象に残りやすいです。以下の記事では、責任感を効果的にアピールするポイントを解説しているので参考にしてくださいね。
④ 長期的な成果が残る魅力
建設コンサルタントの成果は、一時的ではなく長期的に社会に残り続ける点に大きな価値があります。完成した道路や橋は数十年にわたって生活を支え、次の世代にも影響を与えます。
自分の仕事が歴史の一部として残り続ける実感を得られるのは特別な魅力でしょう。就活生にとっても「社会に足跡を残す」という意義を持てることは大きなモチベーションになります。
また、完成した構造物を見るたびに新しい達成感を得られるため、長期的なキャリア形成でも誇りを持ちやすいです。
短期的な成果だけでなく未来を見据えた仕事に関わりたい人にとって、建設コンサルは最適な選択肢といえるでしょう。
建設コンサルタントで活かせるスキル

建設コンサルタントの仕事は専門性が高く幅広いため、志望動機でどのようなスキルを示すかが評価に直結します。
就活生にとっては、自分の経験や強みをどのように結びつければよいか迷う場面も多いでしょう。ここでは、建設コンサルタントで評価されやすい主要なスキルを解説します。
- 論理的思考力
- 協調性とチームワーク
- 責任感とタフさ
- 情報収集力と分析力
- コミュニケーション能力
また、このようなスキルは志望動機だけでなく自己PRでもアピールできますよ。「そもそも自己PRの書き方が分からない……」という方はぜひ以下の記事も参考にしてみてください。
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
① 論理的思考力
建設コンサルタントは複雑な課題を整理し、解決策を導き出す役割を担います。そのため論理的思考力が欠かせません。
課題を分解して順序立てて説明できる力は、行政や発注者との信頼構築につながるでしょう。たとえば現場の課題をデータで整理し、改善案を提案するときに筋道立てた思考は重要です。
就活生はゼミ研究や発表の経験を例に挙げれば説得力が高まります。論理的に考えられる姿勢を示せば、入社後も一貫して課題解決型の人材と見てもらえるでしょう。
② 協調性とチームワーク
建設コンサルタントの業務は行政、ゼネコン、住民など多様な関係者と進めます。そのため協調性とチームワークは必須です。
異なる立場の人々の意見をまとめるには、相手を尊重しつつ調整できる力が必要でしょう。学生時代のグループ研究や部活動での役割分担を例にすれば効果的です。
協調性を志望動機に盛り込むことで、全体最適を意識できる人物像を描けます。実務での調整力に直結するため、採用担当者に安心感を与えられるでしょう。
③ 責任感とタフさ
建設コンサルタントは社会的責任を伴う提案や大規模プロジェクトに関わります。そのため責任感とタフさは強い武器です。困難な状況でもやり抜く姿勢が求められるでしょう。
たとえば課題が多い案件で期限を守るために粘り強く取り組む姿勢は不可欠です。学生時代のアルバイトや部活動で困難を克服した経験を示せば説得力が増します。
責任感を強調することで、信頼して任せられる人材と評価されやすくなるでしょう。
④ 情報収集力と分析力
建設コンサルタントは地形データ、交通量調査、住民の意見など多様な情報を基に計画を立てます。そのため情報収集力と分析力が重要です。
正確なデータを集め、整理し、合理的な判断を下す力は高く評価されるでしょう。学生時代の研究活動や市場調査の経験を例に挙げれば、データに基づいた判断ができる人材であることを示せます。
この力を強調すれば、業務でも客観性を持って貢献できる姿勢が伝わります。
⑤ コミュニケーション能力
建設コンサルタントにとって、信頼を得るには円滑なやり取りが欠かせません。コミュニケーション能力は話す力だけでなく、相手の意図を理解し適切に伝える力も含まれます。
この能力はプロジェクト成功の鍵といえるでしょう。たとえば行政担当者への提案や住民説明会では、専門的な内容をわかりやすく伝える必要があります。
就活生はゼミ発表や接客経験を例に挙げれば効果的です。円滑なやり取りを示すことで、利害関係者と信頼関係を築ける人材だと印象づけられます。
建設コンサルタント志望動機の書き方の手順

建設コンサルタントを志望する際には、熱意だけでなく、筋道を立てた志望動機が求められます。
なぜなら、企業は応募者がどの程度業界や自社を理解しているか、また将来どのようなキャリアを描いているかを重視するからです。
ここでは、就活生が迷わずに志望動機を組み立てられるよう、手順ごとに具体的なポイントを解説します。
- 業界研究と企業研究を行う
- 自己分析でキャリアビジョンを明確にする
- 志望動機の構成要素を整理する
- 具体的なエピソードを盛り込む
- 企業への貢献意欲を表現する
また、「そもそも志望動機の書き方が分からない」「書き方のコツが知りたい」という方は以下の記事もおすすめです。志望動機の基本的な書き方やNG例を紹介しているので、ぜひ参考にしてくださいね。
「上手く志望動機が書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは無料で受け取れる志望動機のテンプレシートを使ってみましょう!1分でダウンロードでき、テンプレシートの質問に答えるだけで、好印象な志望動機を作成できますよ。
① 業界研究と企業研究を行う
志望動機を考える第一歩は、業界全体の動きと志望先企業の特徴を理解することです。
建設コンサルは公共インフラに関わり、社会貢献性が高い一方で、案件ごとに異なる課題へ柔軟に対応する力も求められます。
業界の現状や将来性を把握していなければ、説得力のある動機は作れないでしょう。さらに企業研究では、案件の実績や専門分野、組織文化を調べることで「なぜその企業を選ぶのか」を明確にできます。
たとえば「災害復興案件に強みがある企業に魅力を感じた」といった具体的な理由を添えると、選考担当者に伝わりやすいです。
ここを省略すると表面的な志望動機になりやすいため、十分なリサーチが必要になります。
② 自己分析でキャリアビジョンを明確にする
次に取り組むべきは自己分析です。自分がこれまで培ってきた強みや価値観を振り返り、将来どのようなキャリアを築きたいかを整理することが大切です。
建設コンサルは社会のインフラ整備に携わるため、長期的な視点で仕事を続ける姿勢が求められます。
そのため「地域社会に貢献するプロジェクトに携わりたい」「専門知識を活かして持続可能な都市づくりを支えたい」といった明確なビジョンを示すと、採用担当者は成長意欲を評価するでしょう。
単に「安定しているから」という理由では弱く、キャリアの方向性と仕事内容のつながりを示すことが欠かせません。自己理解を深めるほど、説得力のある志望動機が生まれます。
③ 志望動機の構成要素を整理する
効果的な志望動機にするには、要素を整理することが重要です。基本の流れは「業界への関心」「企業への共感」「自分の強みと結び付け」「将来の貢献意欲」という4段階です。
まず業界研究で得た知識をもとに、なぜ建設コンサルに魅力を感じるのかを伝えます。次に、その企業の特色や事例に共感した理由を具体的に示してください。
そのうえで、自分の経験や能力をどう活かせるのかを説明すると説得力が増します。最後に、将来どのように企業や社会に貢献したいのかを描くと、全体の流れが自然につながります。
この構成を意識することで、わかりやすく印象的な志望動機を仕上げられるでしょう。
④ 具体的なエピソードを盛り込む
説得力を高めるには、抽象的な表現より具体的な経験を取り入れることが効果的です。
たとえば「ゼミで都市計画の調査を行い、データ分析から課題解決策を提案した経験」や「インターンで道路設計に携わり、公共性の高さを実感した体験」を加えると、強みが明確になります。
エピソードは単なる出来事を語るのではなく、その経験で得た学びやスキルを建設コンサルの仕事にどう活かすかまでつなげることが必要です。
これにより、面接官は実際に業務で成果を出せる人物かをイメージしやすくなります。記憶に残る志望動機にするには、抽象論より具体的な事実を根拠にすることが有効です。
⑤ 企業への貢献意欲を表現する
最後に欠かせないのは、応募先企業でどのように貢献したいかを示すことです。企業は自社の将来を担う人材を求めているため、「自分の力を伸ばしたい」だけでは弱い印象を与えてしまいます。
「培った調整力を活かし、多様な関係者と円滑に連携しながらプロジェクトを進めたい」など、具体的な姿を描くとよいでしょう。
また、企業が取り組む重点分野や将来構想と結び付けると、熱意がより伝わりやすくなります。単なる志望理由を超えて「共に未来をつくる仲間」としての姿勢を示せれば、評価を高められるはずです。
志望動機に苦手意識ありませんか?
「時間をかけても、良い志望動機にならない」
「基本的な書き方がわからず、手が止まる」
「どこでも当てはまる志望動機になってしまう」
こうした悩みを抱えたまま、納得のいく志望動機が書けず、本来は志望度が高いにもかかわらず、その熱意が企業に伝わっていない就活生は少なくありません。
ES自動作成ツールでは、就活生が陥りがちな「どの企業にも当てはまる志望動機」から脱却し、企業が評価するポイントを押さえた『選考に通過する志望動機』を、5つの質問に答えるだけで作成できます。
考えるべき要素が整理されているため、文章作成に不慣れな方でも、無理なく自分の言葉で志望動機を完成させることが可能です。
建設コンサルタント志望動機を書く際の注意点

建設コンサルタントの志望動機は、応募者の熱意や業界理解の深さを見極める大切な要素です。形式的な言葉や他業界でも通じる表現では、専門性や適性が伝わりにくくなります。
ここでは、特に注意しておきたいポイントを整理し、就活生が説得力ある志望動機を書くための考え方を解説します。
- 建設業界全般で通じる理由は避ける
- 「成長したい」だけの理由にしない
- 抽象的な表現を使わない
- 企業ごとの特徴を反映させる
① 建設業界全般で通じる理由は避ける
「社会に貢献したい」「インフラ整備に携わりたい」といった理由をそのまま書くと、業界全体に共通する内容となり、特定の企業への志望度が伝わりません。
採用担当者が知りたいのは「なぜ当社なのか」という点です。企業ごとのプロジェクトや得意分野を調べ、共感した点や学びたいことを理由に結び付けてください。
例えば「地域防災に力を入れる〇〇社の取り組みに共感し、自身の研究で培った知識を活かしたい」とすれば、具体性が増して差別化につながるでしょう。
② 「成長したい」だけの理由にしない
「成長したい」「学びたい」という意欲は前向きですが、それだけでは受け身の印象を与えやすいです。企業が重視するのは、成長を通じてどのように貢献できるかという点でしょう。
「地域インフラ整備の経験を通じて専門性を高め、将来的には大規模プロジェクトを主導できる人材として貢献したい」と伝えると、主体性を示せます。
成長の先にある具体的な行動まで表現することが効果的です。
③ 抽象的な表現を使わない
「やりがいを感じたい」「幅広い分野に挑戦したい」といった抽象的な言葉は、どの業界でも使えてしまうため説得力が弱まります。経験や学びと関連付けて話すと納得感が高まります。
例えば「ゼミで都市計画を学ぶ中で、災害リスクを考慮した街づくりに強い関心を持った」とすれば、自分の背景と結び付き具体的に伝えられます。
採用担当者に適性をイメージさせやすくなる点もメリットです。
④ 企業ごとの特徴を反映させる
建設コンサルタントの企業は、防災や環境、都市開発など得意分野に違いがあります。そのため、どこにでも当てはまる志望動機では熱意が伝わりません。
企業の実績や事例を調べ、自分が特に興味を持った部分を理由に盛り込むことが重要です。
例えば「環境アセスメントに強みを持つ御社で、大学で学んだ環境工学の知識を活かしたい」と述べれば、志望度と適性を具体的に示せるでしょう。
企業ごとの特徴を知るには、会社説明会に参加するのがオススメです。以下の記事では、会社説明会で聞いておきたい質問を紹介しているのでぜひ参考にしてください。
【3選】建設コンサルタントの志望動機例文

ではここで、建設コンサルタントの志望動機例文を3つ紹介します。活かせそうな例文を探して、自分なりの志望動機を作成するヒントを見つけてみてください。
- 地域に貢献したい
- 強みを入社後に活かしたい
- 影響力が大きい仕事に携わりたい
さらに今回は、現在も就活生を内定に導いている現役のキャリアアドバイザーが、3つの例文を本気で添削!どんなポイントに注目して書くべきか知りたい人は、ぜひ参考にしてくださいね。
志望動機を早く完成させたいと考えている場合は、ES自動作成ツールがおすすめです。
最短3分で受かる志望動機を、AIが自動作成してくれます。志望動機の他にも、自己PRやガクチカなども完全無料で作成できるので、まずは以下のボタンから利用登録をしてみましょう。
▼最短3分で志望動機を作成する▼
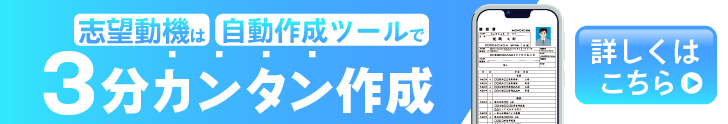
例文①地域に貢献したい
今回は、「地域に貢献したい思い」を軸とした建設コンサルタントの志望動機例文を添削しています。
地域に貢献したいだけでなく、どう貢献したいのかを明確に示すことが大切ですよ。
| 【結論】 私は、地域の課題解決を通じて人々の暮らしをより良くしたいという思いから、 |
| 添削コメント|「魅力を感じた」だけでは何に惹かれたのかが不明瞭なため、「地域に根差したまちづくりに技術面から関われる」というキーワードを加えて、役割と関心の対象を明確にしました。 |
| 【根拠となるエピソード】 きっかけは、通学路にあった老朽化した歩道橋の改修工事を見た経験です。 |
| 添削コメント|「進められる様子を目にし」だけでは根拠が曖昧で伝わりにくいため、「説明会や掲示物を通じて知った」と実際の情報源を示すことで、実体験としての説得力が増しました。 |
| 【エピソード詳細】 大学では土木工学を学び、特に地域インフラの計画立案に興味を持ってゼミ活動に取り組みました。ゼミでは地元駅周辺の混雑緩和をテーマに、 |
| 添削コメント|「実際に調査し、改善案を提案した」だけでは具体的な取り組み内容や得た学びが見えづらいです。ヒートマップでの分析や配置案の作成など、何を行い、学んだ知識をどう活かしたかを示すことで、取り組みの深さや工学的な視点が伝わりやすくなりました。 |
| 【企業を選んだ理由】 貴社は地域住民や行政との連携に力を入れており、技術と対話の両方を重視する姿勢に共感しています。 |
| 添削コメント|「長期的視点で提案できる」は曖昧な表現であり、選社理由として弱いです。「災害復旧」「老朽化対策」といった実際の事業を記すことで、志望度の高さが伝わるよう修正しました。 |
| 【入社後】 入社後は、 |
| 添削コメント|「安心して暮らせるまちづくり」はありきたりな表現で、入社後に何をしたいのかが不明確です。将来的な目標を明確に示すことで、成長意欲と業務への理解度の高さが伝わりやすくなりました。 |
【NGポイント】
歩道橋の工事やゼミでの活動などの経験が書かれている一方で、その中で何を感じ、どう取り組み、最終的に志望につながったのかが曖昧で、説得力がありませんでした。
【添削内容】
歩道橋改修の情報源やゼミでの取り組み内容を丁寧に示し、「なぜ関心を持ったのか」「どのように学びを活かしたのか」をはっきりさせました。
【どう変わった?】
工事現場の観察やヒートマップ分析といった経験が、建設コンサルタントの仕事への理解や意欲につながっていることが明確に伝わる構成になりました。
| ・実体験から関心の芽生えを示す ・「地域に貢献したい」で終わらせない ・学びを仕事につなげて示す |
| 私は、地域の課題解決を通じて人々の暮らしをより良くしたいという思いから、建設コンサルタントの仕事に魅力を感じ「地域に根差したまちづくりに技術面から関われる」という建設コンサルタントの役割に強く惹かれ、志望いたしました。きっかけは、通学路にあった老朽化した歩道橋の改修工事を見た経験です。地域住民の意見を反映しながら進められる様子を目にし工事の説明会や掲示物で、地域住民の声をもとに設計が変更されていく様子を知り、「まちづくり」に主体的に関われる仕事に関心を持ちました。大学では土木工学を学び、特に地域インフラの計画立案に興味を持ってゼミ活動に取り組みました。ゼミでは地元駅周辺の混雑緩和をテーマに、実際に利用者調査を行い改善策を提案する活動を経験し通行量のピーク時間帯を調べる調査や、ヒートマップを用いた通行経路の可視化を行い、動線改善の配置案をまとめる活動に取り組み、机上の理論を現場に活かす面白さを実感しました。貴社は地域住民や行政との連携に力を入れており、技術と対話の両方を重視する姿勢に共感しています。課題に寄り添いながら長期的な視点で提案できる点にも惹かれました。特に、災害復旧や老朽化対策といった地域密着の課題に対し、中長期の視点から提案を行う姿勢に魅力を感じました。入社後は、住民が安心して暮らせるまちづくりに貢献していきたいと考えております。地域特性をふまえ、利用者目線を大切にした調査・提案を行い、将来的には地元の持続可能なインフラづくりをリードできる技術者を目指したいと考えております。 |
例文②強みを入社後に活かしたい
今回は、自身の強みを入社後に活かしたい人向けの建設コンサルタントの志望動機例文を添削しています。
自身の強みがどのように建設コンサルタントの業務に活かせるのかをアピールしましょう。
| 【結論】 私は、まちづくりの根幹を支える建設コンサルタントの仕事を通じて、 |
| 添削コメント|「生活の安全性や利便性を高める」は他業種でも通用する表現です。そのため、建設コンサルタントの特徴である「地域課題に応じた最適なインフラの提案」を加え、志望理由を明示しました。 |
| 【根拠となるエピソード】 幼い頃に住んでいた地域で、 |
| 添削コメント|元の文章は説明が足りず、「なぜ建設コンサルタントを目指すのか」が伝わりにくい印象でした。出来事の具体的な内容と自身が感じたことを補うことで、動機に納得感が生まれました。 |
| 【エピソード詳細】 大学では土木工学を専攻し、研究では地域の交通網における渋滞緩和策の分析を行いました。 |
| 添削コメント|研究の工夫や成果が見えにくかったため、実際の現場での取り組みや提案内容を加えました。また、建設コンサルタントに求められる実践力が伝わるように修正しました。 |
| 【企業を選んだ理由】 中でも貴社は、 |
| 添削コメント|元の文章では、自身の価値観と企業の価値観との繋がりが弱く、企業を選んだ理由に説得力がありませんでした。そこで、企業の特徴にただ共感するだけでなく、自分の経験との接点を述べることで「なぜ他社ではなくこの企業なのか」が明確になりました。 |
| 【入社後】 入社後は、大学で培った分析力や論理的思考を活かし、 |
| 添削コメント|元の文は「地域課題に即した実行可能な提案を行う」だけで、強みとのつながりが見えにくくなっていました。そこで、強みを活かした入社後の目標を加えることで、働く姿が明確に伝わるようになりました。 |
【NGポイント】
災害経験や研究内容が書かれていても、志望動機や自身の強みとの関係がはっきりせず、読み手に伝わりにくい構成になっていました。
【添削内容】
災害時の道路寸断と復旧の体験、研究での聞き取りやバス停再配置の提案内容を詳しく説明し、志望理由と強みを明確に結びつけました。
【どう変わった?】
暮らしを支える基盤に関わりたいという思いが、経験と強みに裏付けられ、建設コンサルタントとして活躍する姿が読み手に伝わるようになっています。
| ・原体験を「仕事への関心」に変換する ・経験で得た力と仕事内容を結びつける ・強みをどう活かすか明確に示す |
| 私は、まちづくりの根幹を支える建設コンサルタントの仕事を通じて、生活の安全性や利便性を高める地域課題に応じた最適なインフラのあり方を考え、住民の暮らしをより良くする提案を行いたいと考えています。幼い頃に住んでいた地域で、災害による道路寸断を経験し、インフラ整備の重要性を実感しました。台風による土砂崩れで通学路が遮断され、生活に大きな影響が出たことを経験しました。数週間にわたり不便な生活を強いられた中で、道路復旧によって地域の安心が戻っていく様子を目にし、インフラ整備が生活基盤を支えていることを実感しました。この経験から、人々の暮らしを支える基盤に関わる仕事に興味を持つようになりました。大学では土木工学を専攻し、研究では地域の交通網における渋滞緩和策の分析を行いました。数値データだけでなく、利用者目線での改善策を提案することの意義を感じ、社会的視点を持った技術提案の大切さを学びました。現場の声を踏まえた改善策の必要性を実感し、学外での聞き取り調査も実施しました。分析結果をもとにした提案では、バス停の再配置案をまとめ、実践的な視点として教員から評価を受けました。中でも貴社は、上流工程からプロジェクトに関わり、地域住民との合意形成や多様なステークホルダーとの調整に力を入れている点に魅力を感じました。調査・計画段階から一貫して携わる体制に加え、住民参加型のまちづくりを推進している点に共感しました。私も研究を通じて利用者視点の提案に力を入れてきたため、貴社の姿勢に強く惹かれました。入社後は、大学で培った分析力や論理的思考を活かし、地域課題に即した実行可能な提案を行える建設コンサルタントを目指してまいります。現地調査による課題の発見から、関係者との調整、住民への説明に至るまで、丁寧なプロセスを経て実行可能な提案を行えるコンサルタントを目指します。 |
「そもそも自分の強みが分からない……」という方は、以下の記事もおすすめです。強みの見つけ方や伝え方のポイントを分かりやすく解説しているので、気になる人は参考にしてみてくださいね。
例文③影響力が大きい仕事に携わりたい
今回は、影響力が大きい仕事に携わりたい人向けの建設コンサルタントの志望動機例文を添削しています。
影響力の大きさだけでなく、どう影響を及ぼしたいかまで伝えましょう。
| 【結論】 私は、地域社会に長く残るインフラ整備に提案段階から関わることで、 |
| 添削コメント|「多くの人に影響を与える」という言葉では、仕事内容との結びつきが弱く見えてしまいます。「多様な立場の人々の生活基盤を支える」と言い換えることで、志望理由が職種の特徴につながるようになりました。 |
| 【根拠となるエピソード】 きっかけは、小学生の頃に参加した地域のまちづくりイベントで、自分のアイデアが図面に反映され、 |
| 添削コメント|「街の姿が変わっていく様子に感動した」という表現だけでは、建設コンサルタントの仕事で大切な提案の意義や形にしていく面白さが伝わっていませんでした。修正後は、提案段階から関わりたいという思いが明確に伝わるようになりました。 |
| 【エピソード詳細】 大学では都市環境工学を専攻し、道路や上下水道の整備に関する研究に取り組みました。特に、住民の生活と直結するインフラを、 |
| 添削コメント|元の文章でも研究への取り組みは伝わっていましたが、「住民ニーズ」や「地域特性」といった視点を加えたことで、建設コンサルタントとしての考え方がよりはっきり伝わる内容になりました。 |
| 【企業を選んだ理由】 なかでも貴社は、地域密着型の課題解決に強みを持ち、 |
| 添削コメント|元の文章は、競合他社にも言えるようなありきたりな表現で、企業選びの理由としては弱い印象でした。修正後は、企業の特徴である「住民参加型の取り組み」などに言及することで、選社理由としての納得感が向上しました。 |
| 【入社後】 入社後は、 |
| 添削コメント|元の文章はどのように貢献するのかが曖昧でした。修正後は「計画段階から地域と向き合う」「住民目線を重視した提案をする」といった行動を明記し、建設コンサルタントとしての姿勢が伝わる内容になりました。 |
【NGポイント】
「多くの人に影響を与えたい」などの理由が、建設コンサルタントでなければいけない根拠として弱く、志望理由が浅く見えていました。
【添削内容】
まちづくりイベントでの体験や住民ニーズを踏まえた大学での研究経験の内容をより具体的に説明し、提案段階から関わりたいという意欲を明確にしました。
【どう変わった?】
自分の経験と「暮らしを支える提案業務」がつながり、仕事への理解と適性が伝わる内容になりました。また企業との接点も強まりました。
| ・「影響を与えたい」だけで終わらせない ・自分の経験から関心の原点を示す ・提案段階から関わる意欲を示す |
| 私は、地域社会に長く残るインフラ整備に提案段階から関わることで、多くの人に影響を与えられる多様な立場の人々の生活基盤を支えられる建設コンサルタントの仕事に魅力を感じ、志望いたしました。きっかけは、小学生の頃に参加した地域のまちづくりイベントで、自分のアイデアが図面に反映され、形になる過程を見たことです。街の姿が変わっていく様子に感動し、まちの未来像が少しずつ形になる様子を目にしたことです。この経験を通じて、計画や提案が人の暮らしを形作っていくことに面白さを感じ、将来は人々の暮らしを支える仕事がしたいと考えるようになりました。大学では都市環境工学を専攻し、道路や上下水道の整備に関する研究に取り組みました。特に、住民の生活と直結するインフラを、コストや環境への影響も踏まえて計画することの重要性を学び、住民ニーズや地域特性に応じて設計方針を柔軟に検討する必要性を実感し、設計だけでなく「どう作るか」「なぜその案か」といった提案の視点を持つようになりました。なかでも貴社は、地域密着型の課題解決に強みを持ち、住民説明や合意形成にも力を入れている点に共感しました。技術だけでなく、信頼の上に成り立つ提案力を磨ける環境に魅力を感じています。特に住民参加型の合意形成プロセスを重視し、丁寧な説明や関係者の意見を取り入れた計画提案を実践されている点に惹かれました。人との対話を重ねながらまちづくりを進めていく貴社の姿勢に強く共感しています。入社後は、人々の安心と利便性の向上に貢献していきたいです。計画段階から地域と向き合い、住民目線を重視した提案を通じて、より良い暮らしの基盤づくりに貢献していきたいです。 |
ここまで、志望動機の例文を紹介してきましたが、例文のように自身の志望動機を仕上げたい方はES自動作成ツールがおすすめです。
人事に評価されやすい構成を意識した志望動機を最短3分で、AIが自動作成してくれます。志望動機の他にも、自己PRやガクチカなども完全無料で作成できるので、まずは以下のボタンから利用登録をしてみましょう。
▼最短3分で志望動機を作成する▼
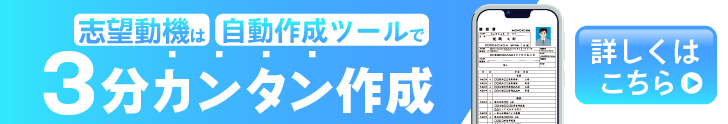
志望動機を磨いて建設コンサルタントの夢を実現しよう

建設コンサルタントを目指す上で、志望動機は採用担当者に熱意や適性を伝える重要な要素です。
なぜなら、仕事内容には調査・計画から発注者との調整まで幅広い業務が含まれ、ビジネスモデルも公共事業や官公庁との契約に基づくため、社会的責任が大きいからです。
実際、地域のまちづくりや大規模プロジェクトに関わるやりがいは大きく、論理的思考力や協調性など多様なスキルを活かす場面も豊富にあります。
したがって志望動機を作成する際は、業界研究や自己分析を通じてキャリアビジョンを明確にし、具体的なエピソードや企業への貢献意欲を盛り込むことが必要です。
さらに「成長したい」だけの表現を避け、抽象的でない理由を示すことで説得力が高まるでしょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













