自己PRで分析力を伝えたい!アピールするコツ・例文まで紹介
「長所である分析力をアピールしたいけど、どうやって自己PRを作ればいいかわからない……」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
そんな方に向けて、本記事では自己PRで分析力をアピールする方法・コツ・例文などを紹介します。分析力の種類も解説しているので、自分なりの強みをぜひ見つけてくださいね。
自己PRをすぐに作れる便利アイテム

記事の監修者
記事の監修者
人事 鈴木
新卒でベンチャー企業で求人広告の新規営業を経験 入社半年でテレアポ獲得数社内1位。新卒売り上げ1位を獲得。 その後Cmind groupの人事部に入社し、新卒採用を担当。 現在は学生の面談だけではなく採用戦略や広報にも携わっている。
詳しく見る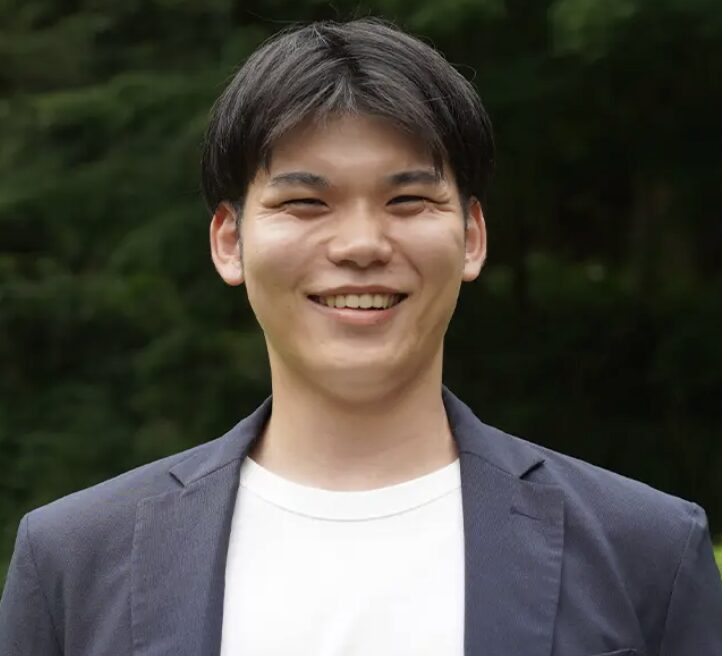
記事の監修者
記事の監修者
永井
2021年シーマインドグループにセールススタッフとして入社。営業を学び2022年にチームリーダーに昇格。その実績から2023年に株式会社シーマインドキャリアへ転籍。現在はキャリアアドバイザーとして就活サポートをおこなう。
詳しく見る企業が求めている分析力は大きく2つに分かれる!

「分析力」とは、高度なアイデアや解決策を提案するために、特定の分野に着目し、それを調査、理解するために必要な特性や能力を指します。
実際に、企業からは仕事の中で活かせる「課題解決のための分析力」と「情報やデータを読み解く分析力」の2つが求められています。
ここでは、この2つに関して詳しく解説していくので、分析力を強みとして効果的にアピールするために、しっかりと確認しておきましょう!
- 課題解決のための分析力
- 情報やデータを読み解く分析力
「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。
①課題解決のための分析力
社会人には、状況や課題を的確に把握し、改善点を特定して問題解決に取り組む力が求められます。分析力の高い人材であれば、収集した情報を整理し、現実的で効果的な解決策を見つけ出せますよ。
近年はビッグデータの活用が進み、分析結果を基に新しいビジネスモデルを生み出すケースも増えています。幅広い視野から情報を分析しながら、積極的に行動できる人材が期待されているのです。
つまり、課題解決に向けては、分析による深い理解と具体的な行動が重要となります。状況を多角的に捉え、原因を特定し、適切な対策を立案・実行できる力が必要不可欠なのです。
「分析力の中でも特に課題を特定するのが得意だ」という方は、こちらの記事も参考になるはずです。分析力の具体例として課題発見力を表現することで、面接官もイメージしやすくより評価につながる自己PRを作成することが出来ますよ。
②情報やデータを読み解く分析力
感情に流されがちな人間にとって、的確な判断を下すためには客観的なデータを最優先する論理的思考力が重要。仕事の重要な場面では、感情だけで簡単に決めてはいけません。
分析力のある人材は、収集したデータに基づいて論理的に考える力に長けています。感情を排除し、客観性を保ちながら状況を冷静に分析できる資質が求められるのです。
つまり企業が求める分析力とは、単に情報を集めるだけでなく、そこから論理的な思考を展開し、最適な結論を導き出す能力を指します。データを根拠としながら物事を多角的に捉え、合理的に判断できるスキルこそが重要なのです。
プロの目で変わる!赤ペンESで企業を惹きつける自己PRを作ろう
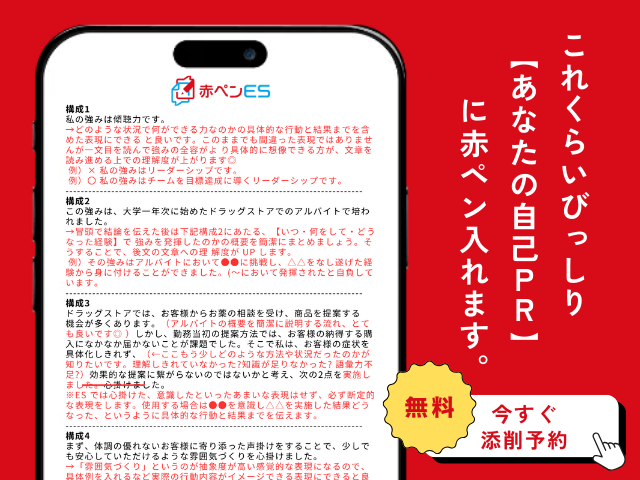
「自己PRが書けない……」「強みってどうやってアピールしたらいい?」など、就活において自己PRの悩みは尽きないものですよね。
そんな人には、就活のプロがじっくりESを添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
赤ペンESとは、年間2000人以上の就活生を合格に導くアドバイザーが、あなたのESをみっちり添削してくれるサービス。1つの回答にびっしり赤ペンが入るため、あなたの自己PRの良い点も改善点もまるごと分かりますよ。
さらに、本記事の後半では実際に「分析力」を長所とする自己PR例文を添削しています!
「赤ペンESってどこまで添削してくれるの?」「まずは実際の添削例文を見たい」という方は、下のボタンをタップして添削内容を確認してみてくださいね。
分析力が高い人の特徴を3つ紹介
分析力の自己PRが上手く書けない人の中には自分の分析力のタイプがわかっていない人も多くいます。
分析力といっても色々あり、本質的に自分がどの分析力を持っているかわからなければ、うまく自己PRに落とし込めません。
そこでここでは、分析力が高い人の特徴を3つ紹介します。自分の分析力がどのタイプなのかを知ることで、自己PRをより魅力的に作りましょう。
- 本質を見抜く力がある
- 必要な情報を取捨選択できる
- データをもとに解決策を導き出せる
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
①本質を見抜く力がある
分析力が高い人の特徴の1つは、本質を見抜く力があることです。
トラブルや予想外の出来事が起こると、焦りから視野が狭まってしまうこともありますよね。しかし分析力が高い人は、表面的な情報に惑わされず、多角的な情報から原因を見極められるのです。
たとえば商品の売上が低下した際、単純な売り上げ数値の変化に加えて、顧客の購買行動や市場のトレンドなど、様々な情報を分析して根本的な原因を明らかにできる人が当てはまりますね。
問題に対してその都度、的確な対策を立てられる力なので、企業でも重宝されがちです。
高度な力に見えますが「課題の本質を捉え、具体的な施策を考えた経験」があれば大丈夫。自己PRのエピソードとして使ってみましょう。
②必要な情報を取捨選択できる
分析力が高い人の特徴として、必要な情報を取捨選択できることもあてはまります。
現代では情報が溢れており、いちいち関連情報を全て集めるのは非効率的ですよね。そのため、限られた時間の中で最適な判断を下すためにも、重要な情報を見極める力が求められます。
たとえば、女性向けの商品開発をする場合、あらゆるリサーチをするのではなく、「必然的に女性しか使わない商品」の売上や女性の購買動向を探るなど、焦点を絞れる力があてはまるでしょう。
大学生活の中でも「レポートのための資料探し」や「アルバイト先でトラブルが起きた際の対処」など、短時間で正しく情報を取捨選択し、問題の解決を目指した経験がある人にはぴったりですよ。
上記の経験がある人はぜひ自己PRに盛り込み、業務の効率化や、正しい判断決定ができることをアピールしてくださいね。
とはいえ、「自己PRに盛り込めそうなエピソードがない……」という方も多いはずです。そんな方に向けて、こちらの記事でエピソードの探し方について解説しています。気になる方は参考にしてください。
③データをもとに解決策を導き出せる
データをもとに解決策を導き出せることも、分析力の高い人の特徴です。
企業では、業績を向上させる提案や意思決定のために、データを適切に活用する必要があります。そこで、集めたデータを駆使して具体的な施策を考えられる人が重宝されるのです。
何かしらのトラブルに対してアンケートや過去のデータを比較し、原因と解決策を出した経験がある人なら、特に好印象なアピールができるでしょう。
たとえば、アルバイト先の顧客満足度を上げるため、アンケート結果や購買履歴を分析し、ニーズに合った改善策を提案した経験などが当てはまりますよ。
企業は、自己分析力が高い人材を求めているため、論理的かつ戦略的に自分の強みを伝えましょう。
実際に分析力が評価されやすい職種を6つ紹介
仕事内容によっては、分析力がある人を強く求めている職種も多くあります。モチベーション高く仕事をするために、より自分の強みを活かしやすい職種を選ぶのも、就活の戦略の1つです。
そこでここでは、分析力が重視される6つの職種を紹介します。仕事とのマッチ度の高さも示せるため、これらの職種では積極的に分析力をアピールしていきましょう。
- マーケティング職
- コンサルタント職
- データサイエンティスト
- ビジネスアナリスト
- 経理職
- 研究開発職
自分に合っている職業が分からず不安な方は、LINE登録をしてまずは適職診断を行いましょう!完全無料で利用でき、LINEですべて完結するので、3分でサクッとあなたに合う仕事が見つかりますよ。
①マーケティング職
マーケティング職とは、商品を売り出すための各作業を行なう仕事です。現状のニーズに合った商品を提案し、上手く売れる販促方法を考え、販売後の商品の売上改善に取り組む必要があります。
そのため、市場調査や販促方法の考察、売り上げ解析からの改善策提案など、さまざまなところで分析力を活かす必要が出てくるのです。
市場の動向は常に流動し、年単位、月単位で流行も変化します。それらのデータを適切に加味しなければ売れる商品は作れないため、マーケティング職では分析力は必須といえますね。
とはいえ、マーケティング職は分析結果をクライアントに適切に伝え、提案に納得してもらうためのコミュニケーション力も必要です。地道な分析だけでなく、伝える力があるかも考えてみてくださいね。
マーケティング職に関心を抱いた方は、以下の記事を参照してみてください。具体的な業務と自分の強みを結びつけて、「入社したら○○の強みを△△の業務に活かせる」と伝えると高評価につながりますよ。
②コンサルタント職
コンサルタント職は、クライアント企業の課題を見つけ、最適な解決策を提案する仕事で、分析力が必須とされています。
なぜなら、特定の分野に詳しくないクライアントのために、その分野の情報を逐一集めて最適な案を考察する必要があるからです。データ収集・考察のどちらにも分析力が欠かせません。
論理的思考とデータに基づいた判断ができる人は、この職種で高く評価されます。
また、ここではただ分析をするだけでなく、それを用いて最適な提案をする提案力も必要とされます。データを分析して改善策を提案できるかどうか、検討してみてくださいね。
③データサイエンティスト
データサイエンティストは、膨大なデータを分析し、そこから統計的な手法や機械学習を活用して、課題解決をはかる職業です。
適切なデータを集める情報収集能力や、データを使って解決策を導き出す力が求められるため、分析力は必須ですね。単に数字を扱うだけでなく、複雑なデータの関係性を読み解けないといけません。
特に、業界や市場の動向を予測する場面では、正確なデータ分析が大きな武器になります。
また、分析結果を適切に伝える力も必要です。せっかく有益なデータ分析ができても、それを理解しやすい形で説明できなければ、組織内で活用されにくいでしょう。
データサイエンティストを志望するときは、分析力だけでなく、論理的思考力やコミュニケーション能力も備えているかを考えてみてくださいね。
④ビジネスアナリスト
ビジネスアナリストは、企業が行なっている業務の現状を詳しく分析し、効率化や改善策を提案する仕事で、分析力が非常に重宝されます。
何故なら、膨大なデータから正しい情報を読み取り、本質的な課題を見つける必要があるからです。
たとえば売上が低下している商品があったら、売上の変化に加え、市場の動向変化や商品のコンセプト、流通具合など、さまざまなデータから要因を分析し、具体的な改善策を導き出す必要があります。
さらに、関係者への説明や資料作成の機会も多いため、相手に伝わる説明力が必要不可欠。分析力に加えて、正確に情報を整理して伝える力があるかどうかも確認しましょう。
⑤経理職
分析力がある人は、会社の財務データを正確に分析し、適切な管理を行う必要がある経理職にも向いているでしょう。
特に、経理職では今までの業績を数字で管理しつつ、一見問題なさそうな箇所からも課題を素早く見つけ、改善策を提案する必要があります。
たとえば、過去の支出データからコスト削減の可能性を見つけて改善策を提案し、企業の利益をよりアップさせるなど、分析力が役立つ場面の多い仕事といえますね。
また、細かい数字のチェックだけでなく、法規制への理解や関係部門との調整も欠かせません。細部まで注意を払いつつ、臨機応変に対応できる力があるかどうかも判断軸にするのがおすすめですよ。
⑥研究開発職
研究開発職では、新しい製品や技術を生み出すために調査・実験を行う必要があり、データを分析する力は必須といえます。
特に、膨大な実験結果の中から必要な情報を正確に抽出し、仮説を検証してさらにより良い製品を生み出す作業では、細かい観察力と論理的な思考が不可欠です。
煩雑なデータから本質的な課題や改善点を見つけられる、分析力の高い人には、研究開発職が特に向いているでしょう。
とはいえ、研究開発においてはチーム内での意見共有や成果説明の場も多く、協調性も必要になってきます。一人で黙々と分析だけをする仕事ではないので、注意してくださいね。
自己PRで分析力を効果的にアピールする基本構成
自己PRでは採用担当に分かりやすくアピールポイントを伝える必要があり、そのためには論理的な構成が欠かせません。まとまった文章を書くときは、相手に伝わりやすい構成のセオリーを使いましょう。
特にPREP法(結論⇒理由⇒具体例⇒結論)の流れを活用すると、分かりやすく説得力のある文章になりますよ。ここでは、PREP法を元にした、効果的な自己PRの流れを解説します。
- 結論ファーストで強みを伝える
- 強みが発揮された具体的なエピソード
- エピソードでの課題や問題の乗り越え方
- 強みを発揮して出た成果
- 入社後の強みの活かし方
「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。
①結論ファーストで強みを伝える
自己PRを作るときは、最初に「分析力が強みであること」を明確に伝えましょう。
最初に結論を提示することで、何の文章なのかが分かりやすくなり、自然と頭を整理しながら次の文章を読み進められます。結果的に、自己PRの内容が正しく伝わりやすくなるのです。
実際に作るときは「私はトラブルが起きても冷静に情報を整理し、最適な解決策を導き出す力を強みとしています」のように、「自分の強みは何か」「その強みで何ができるか」の二点を伝えましょう。
「私の強みは分析力です」だけでは印象に残りづらいため、合わせてどんな成果が出せるかを伝えるのがポイントです。
自己PRを作成上では内容も大事ですが、伝わりやすい構成で書くことも重要です。時系列順に長々と話してしまうと、「結局この子の強みは何なんだ……?」と面接官に疑問を抱かせてしまうことも。ぜひこちらの記事を参考にしてくださいね。
②強みが発揮された具体的なエピソード
次に、分析力が発揮できた過去の経験を具体的に述べましょう。
ここでは「当時の状況」「出来事の具体的な流れ」だけでなく、「自分がそのときに考えたことと取った行動」も具体的に伝えるのがポイントです。
たとえば「ゼミで企業のマーケティング戦略を分析し、売上向上の提案を行った」というエピソードなら「どのように分析し、どんな提案を行ったのか」まで具体的に示せると好印象になります。
企業はエピソードの規模や成果の大きさに注目しているのではありません。応募者が過去にどんな努力をして、どんな行動を取ったかを最も知りたがっています。
自身がどのような行動を取って、結果、どのように強みを発揮したのかを詳しく伝えてくださいね。
③エピソードでの課題や問題の乗り越え方
自己PRをより質高く作るためには、エピソード内で当時直面した課題や問題を示し、それをどう乗り越えたかを詳しく伝えると効果的です。
仕事で一度もトラブルに遭遇しないことはありえないため、企業は「トラブルを起こさない人」よりも「トラブルに的確に対処できる人」を求めています。
そのため、どんな強みをアピールするときも「直面した課題に対処した」という流れを入れると非常に効果的ですよ。
例えば、まず「ゼミ活動でマーケティング戦略を行なったものの、市場データが不足しており、正確な分析が難しい状況だった」といった課題を挙げます。
その上で、「自らアンケートを実施し、データを補完することで分析の精度を高めた」と課題解決のプロセスを説明すると、トラブルに適切な対処ができる人材だとアピールできるでしょう。
④強みを発揮して出た成果
エピソードの最後に、分析力を発揮した結果、どのような成果が得られたのかを具体的に入れてください。成果を示すことで、努力の方向性が正しかったことが分かり、より評価が上がります。
またここでは「マーケティング戦略を提案した結果、クライアント企業の売上が10%向上しました」のように、具体的な数値を示すとなお良いです。
たとえば上記の例では、採用担当がマーケティングに詳しいとは限りませんよね。しかし、数値で成果を出すことで、専門的な知識がない人にも成果の規模や質が伝わりやすくなるのです。
また、数値が出しにくい場合は「比較」を意識しましょう。「分析結果が評価され、ゼミ内の発表で最優秀賞を獲得しました」のように、比較対象を加えることで、実績が伝わりやすくなります。
⑤入社後の強みの活かし方
最後に、入社後にどのように分析力を活かすつもりか、努力目標を述べましょう。
エピソードで強みの説得力を提示しても、「企業でも同じように強みを発揮できるか」が曖昧なままだと、採用担当も決め手に欠けてしまいます。
そこで、分析力をどう企業の仕事に活かすか、企業目線で目標を伝えてください。ここでは、志望企業の業務理解が必要になります。
たとえば「市場データを活用し、顧客ニーズに合ったマーケティング施策を提案したい」といった形で、企業の業務に関連付けると効果的です。
企業の求める人物像とマッチしていることを示せれば、採用担当者に強い印象を残せるでしょう。
自己PRで分析力を伝える際の注意点を4つ紹介

自己PRで分析力をアピールする際には、伝え方に工夫が必要です。内容が曖昧だと説得力に欠け、採用担当者に魅力が伝わりにくくなります。ここでは、自己PRの質を高めるための注意点を4つ紹介します。
- 専門的な言葉は控える
- 自己PR内容と面接時の態度がズレないように
- 分析をしただけのアピールにとどまっていないか
- 分析対象を分かりやすく伝える
①専門的な言葉は控える
自己PRを書く際には、専門用語を避け、わかりやすい言葉を使うことが大切です。専門用語が多いと、読む人に理解されにくく、印象が悪くなることがあります。
特に、異なる業界への応募の場合は、前職の専門用語を控えめにしましょう。もし専門用語を使う場合は、一般的な言葉での説明を加えてください。
これにより、あなたの経験やスキルが、どの業界の人にも伝わりやすくなりますよ。
②自己PR内容と面接時の態度がズレないように
自己PRを作成する際には、面接時の態度と矛盾しないよう留意することが大切です。分析力をアピールする場合、その能力が実際に備わっていることが求められます。
なぜなら、分析力は論理的思考を要するため、感情や推測で話すことがないためです。面接で質問に対して適切な答えが出せなければ、面接官に疑念を抱かれる可能性があります。
そのため、面接に臨むまでには、実際にそのスキルを身につけ、面接中も論理的に話すことを心掛けましょう。
面接時に自己PRを効果的に伝えられるためにはどうしたらよいか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。エントリーシートなどの書類とはまた別の注意点があるので、面接を控えている人はぜひこちらの記事も見てみてください。
「面接で想定外の質問がきて、答えられなかったらどうしよう」
面接は企業によって質問内容が違うので、想定外の質問や深掘りがあるのではないかと不安になりますよね。
その不安を解消するために、就活マガジン編集部は「400社の面接を調査」した面接の頻出質問集100選を無料配布しています。事前に質問を知っておき、面接対策に生かしてみてくださいね。
③分析をしただけのアピールにとどまっていないか
自己PRでは、分析した事実だけでなく、その結果をどう活用したかまで伝えましょう。単に「データを分析しました」では、実際の業務に活かせるスキルかどうか判断できません。
例えば、ゼミで市場調査を行い、競合との差別化ポイントを提案した経験がある場合、「用いたデータと分析方法」だけでなく、「分析結果をもとに具体的にどんな提案を行ったのか」まで伝えましょう。
また、提案結果が具体的な成果に繋がったことも示してください。
例えば「分析をもとにSNSの投稿内容を改善し、閲覧率が20%向上した」といった具体例を示すと、分析力を実務で活かせることが伝わります。
企業は、分析を通じて適切に行動し、成果を出せる人材を求めています。自己PRでは、分析の過程だけでなく、その結果をどのように活用し、どんな成果を出したのかまで意識して伝えましょう。
④分析対象を分かりやすく伝える
自己PRで分析力を伝える際には、何を分析したのかを明確にしましょう。分析対象が曖昧だと、採用担当者が具体的なイメージを持ちづらく、評価につながりにくくなります。
例として「データを分析して課題を発見した」は「大学の学祭で来場者数のデータを分析し、混雑を減らすための施策を提案した」のように言い換えましょう。分析対象を具体的に示すのがポイントです。
また、専門的なデータや指標を用いた場合、誰にでも伝わる表現に言い換えて説明してくださいね。
たとえば「アンケート結果をクロス分析した」だと分かりづらいので「アンケート結果から、来場者の満足度と滞在時間の関係を調査した」と、理解しやすい表現に変更してみましょう。
差別化!「分析力」を効果的に言い換える4つの表現
自己PRで分析力をアピールする際に重要なのが差別化です。「分析力」という言葉自体は便利ですが、抽象的な印象を与えやすく、具体的な強みや成果が伝わりにくくなる可能性があります。
他の就活生と差をつけるためにも、単純に「分析力」と伝えるのではなく、別の表現に言い換えていきましょう。
本章では「分析力」をより魅力的に伝えるための言い換え表現を4つ紹介します。自分の経験や強みに合わせて適切な表現を選んでくださいね。
- 問題解決力
- 洞察力
- 観察量
- 課題発見力
①問題解決能力
分析した結果をもとに課題を解決した経験がある場合、「問題解決能力」と表現すると効果的です。企業は単にデータを分析できる人ではなく、分析を活かして課題を解決できる人材を求めています。
たとえば「問題発生時にさまざまな情報を分析し、問題点を抽出・解決できる問題解決力があります」のように、「分析の力で問題を解決した」と示しましょう。
その際はエピソードで「アルバイト先の売上の低下の要因を分析し、ターゲット層の見直しを提案して売上を回復させた経験があります」と、分析力を問題解決に活かしたことを伝えるのがポイントです。
似たような経験がある人は過去を振り返り、分析の結果としてどんな解決策を生み出したのかを整理してくださいね。
②洞察力
物事の本質を見抜く力が強みなら、「洞察力」と言い換えましょう。単に数値を処理するだけでなく、隠れた課題や将来の可能性を見出す視点を持っていることをアピールできます。
特に、何かトラブルがあった際に論理的に原因を分析・推測し、解決に導いた経験がある人にはお勧めです。
たとえば、アルバイトで商品の売れ行きが悪い理由を分析した結果、「顧客層の変化に着目し、新たなターゲット層へのアプローチを提案して解決した」経験などは、エピソードとして使えますね。
このとき、分析内容だけでなく「どんな情報に着目し、どう考えてどんな解決策を提案したのか」が分かるようにエピソードを説明するのがポイントです。
③観察力
分析力の中でも、細かい変化やパターンを見逃さず、適切な判断ができる力があると伝えたい場合は、「観察力」を使うとよいでしょう。
データだけでなく、人の動きや市場のトレンドなど、流動的で曖昧なものを分析した経験がある人には特におすすめ。
たとえば、サークルメンバーの行動をよく観察し、得意分野を把握して適切な役割分担を行なった経験などがそれにあたります。いわゆる、数字だけでは測り切れない情報を分析するエピソードですね。
また、観察力を強みとする場合は、「どんな変化や違和感に気づいたのか」「それをもとにどんなアクションを取ったのか」を明確に伝えることがポイントです。
④課題発見力
過去の結果や数値を分析することで、まだ顕在化していない問題に気づく力をアピールする場合は、「課題発見力」という表現が適しています。
これまでの経験を分析して事前に問題に気づける人や、組織のセーフティーネットとして活動したことのある人にオススメの言い換え表現ですね。
たとえば、「特定の作業でつまづく人が多かったため、似た作業を任されたとき最初にマニュアルを作った」など、起こりうるリスクを予測して対策を打ち出した経験があるとぴったりでしょう。
このように、分析力を「先を見通す力」として伝えることで、企業にとって貴重なスキルであることが伝わりますよ。
ここで紹介した以外にも、「分析力」を言い換えられる強みはありますよ。以下の記事では、自己PRで用いられる強みを一覧で紹介しているので、「分析力以外の強みを見つけたい」という方もぜひ参考にしてみてください。
「分析力」を伝える自己PRの例文を9つ紹介
ここでは「分析力」を強みとして伝える自己PRの例文を9つ紹介します。就活生が使いやすいエピソードをもとに例文を作成したので、気になるものから読んでみてくださいね。
- 分析力×アルバイト
- 分析力×研究
- 分析力×サークル
- 分析力×ゼミ
- 分析力×部活動
- 分析力×塾講師
- 分析力×学業
- 分析力×マーケティング系インターン
- 分析力×営業系インターン
さらに今回は、現在も就活生を内定に導いている現役のキャリアアドバイザーが、9つの例文を本気で添削!分析力をどうアピールしたらいいか気になる人は、ぜひ読んでみてくださいね。
また、自己PRがそもそも書けずに困っている人は、就活マガジンの自動作成ツールを試してみてください!まずはサクッと作成して、悩む時間を減らしましょう。
自己PRが既に書けている人には、添削サービスである赤ペンESがオススメ!今回のように詳細な解説付きで、あなたの回答を添削します。
「赤ペンES」は就活相談実績のあるエージェントが無料でESを添削してくれるサービスです。以下の記事で赤ペンESを実際に使用してみた感想や添削の実例なども紹介しているので、登録に迷っている方はぜひ記事を参考にしてみてくださいね。
【関連記事】赤ペンESを徹底解説!エントリーシート無料添削サービスとは
①分析力×アルバイト
分析力を活かし、状況を客観的に捉えて行動した自己PR例文です。
自己PRで「分析力」をアピールする際は、曖昧な言い回しを避け、根拠のある行動や成果につなげることがポイントですよ。
| 【結論】 私の強みは、状況を客観的に捉え、課題の原因を見極める「分析力」です。 |
| 添削コメント|結論部分は非常に明快で、読み手が冒頭で強みを明確に把握できる良い構成です。特に「課題の原因を見極める」という表現が、分析力の本質に触れており、他の長所と差別化できています。 |
| 【エピソード】 大学時代に飲食店のホールスタッフとして働いていた際、週末のピークタイムにオーダーミスが頻発していました。 |
| 添削コメント|「忙しさのせいだと思われていましたが」の部分は周囲の印象を述べるだけなので削除し、代わりに自分の気づきを強調しました。自ら違和感に気づき行動する姿勢は、まさに分析力の出発点として重要です。 |
| 【エピソード詳細】 3週間にわたり共通点を分析しました。 |
| 添削コメント|削除した分析結果の表現は曖昧で、なぜその状況でミスが起きるかの因果が見えにくくなっていました。改善後は条件を明確に絞り、より論理的かつ定量的な分析の形に仕上げることで、強みとしての説得力が増しています。 |
| 【成果】 改善策を導入した翌月から、ミスの件数は約40%減少し、 |
| 添削コメント|成果の表現を抽象的な「店舗の月間評価」から、実際の指標である「接客満足度」へ変更しました。定量的な結果を示すことで、読み手にとって納得感と実績の大きさがより伝わりやすくなっています。 |
| 【入社後】 入社後も、根本原因を見極める分析力を活かして、 |
| 添削コメント|入社後の活かし方が抽象的だったため、分析力を活かす「具体的な対象(業務プロセス)」と「結果(生産性向上)」を明示することで、読み手に職場での再現性を想像してもらいやすくしました。 |
【NGポイント】
分析力の自己PRであるにもかかわらず、「何をどのように分析したのか」が見えにくい状態でした。また、「忙しさのせい」や「店舗評価が上昇」といった表現も主観的または抽象的です。
【添削内容】
成果部分では客観的な数値指標である「接客満足度」を提示し、結果の具体性と信頼性を強化しています。入社後の活用イメージも明確になりました。
【どう変わった?】
全体を通して、「自ら疑問を持ち、分析し、行動し、成果を出す」という一貫した流れが明確になりました。企業側から見ても、職場でも活かせる再現性のあるスキルであることが伝わります。
| ・原因特定の過程を具体化する ・成果に客観的な数値を使う ・入社後の活用方法も明示する |
「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
②分析力×研究
「研究室での分析活動」を通して、課題の本質を見抜いた上で改善へ導く力をアピールする自己PR例文です。
| 【結論】 私の強みは、課題の本質を見抜き、改善に導く分析力です。状況を客観的に捉えて整理し、 |
| 添削コメント|「アクションに落とし込む」は抽象的すぎて、分析力の具体的な強みが伝わりません。そこで、課題を分解し、改善策を導くというプロセスに言い換えて効果的に伝えています。 |
| 【エピソード】 この力を発揮したのは、大学の研究室で行った実験データの整理・分析に関する取り組みです。 |
| 添削コメント|「任された」という表現は、主体性や能動性が伝わりにくく、受け身な印象を与えがちです。自ら課題を発見し分析に取り組む姿勢を示すことで、「分析力」を行動の中で発揮したことが明確になります。 |
| 【エピソード詳細】 当初は、結果に一貫性が見られない状態が続いており、私は過去のデータを整理し直しました。 |
| 添削コメント|実際にどのような分析を行い、どのような視点で因果関係を見出したのかを「比較・可視化」などの言葉で補足することで、分析力を発揮したプロセスの説得力を高めています。 |
| 【成果】 この分析をもとに実験条件を再調整したことで、データの再現性が大幅に向上しました。 |
| 添削コメント|「高く評価されました」は主観的かつ曖昧です。誰がどのように評価したのかを具体的に示すことで、成果の信ぴょう性と客観性を高めることができ、企業側にも再現性が伝わる内容になります。 |
| 【入社後】 入社後も、丁寧な情報整理と客観的な視点を武器に、業務の中で発生する課題に対しても、データや事実をもとに原因を分析することで改善策を提案できる人材を目指します。 |
| 添削コメント|元の表現でも意欲は伝わりますが、実際の業務を想定した表現を追記することで、「分析力」が企業でどのように活かされるかをより明確に伝えました。 |
【NGポイント】
受け身表現を使っていたり、分析した過程の説明が不十分だったりと、「分析力」の強みをアピールしきれていない印象でした。成果の内容もぼかして書かれており、説得力や具体性を欠いていました。
【添削内容】
分析の具体的なプロセスを明示することで説得力を高め、評価や成果に関しても「誰がどう評価したか」を明確にしました。さらに、主体的な行動を示す言葉に置き換えることで、積極性を伝えています。
【どう変わった?】
分析力が「行動・思考・成果」に紐づき、再現性を感じやすい構成に改善されました。加えて、研究での経験が実務にどう応用されるかが明確になり、企業視点でも評価しやすくなっています。
| ・抽象表現は具体化して伝える ・評価は誰からいつ受けたか明記する ・受け身表現は能動に直す |
③分析力×サークル
バレーボールサークルでの活動を通じて、課題の原因を見極め、データをもとに改善策を提案した経験をもとにした自己PR例文です。
| 【結論】 私の強みは、物事を冷静に捉え、課題の原因を分析して最適な解決策を導く「分析力」です。 |
| 添削コメント|結論部分では「分析力」というキーワードを明確に示し、簡潔に自己PRの主軸を提示できているため、読者がすぐにテーマを把握できます。 |
| 【エピソード】 大学ではバレーボールサークルに所属し、試合での勝率向上を目指す中で、 |
| 添削コメント|「戦略面の課題解決に取り組んだ」という表現だけでは何をどうしたのかが伝わらないため、より具体的かつ簡潔な説明に置き換えています。 |
| 【エピソード詳細】 私は過去10試合のミスの発生タイミングやパターンを記録しました。その結果、「連続失点後にミスが集中する」傾向が明らかになったのです。そこで、失点後にプレーを一度止め、攻撃パターンを切り替えることを提案しました。 |
| 添削コメント|元の文章では、その後の【成果】の文章との繋がりが不自然になっていました。修正後は「データの記録→傾向分析→戦術提案」と行動のプロセスが分かりやすくなり、企業が重視する「ロジカルに動ける人物像」に近づいています。 |
| 【成果】 その結果、接戦での勝率が3割から7割へと向上しました。 |
| 添削コメント|信頼されたという感想ベースの表現では客観性が弱く、成果としては不十分です。代わりに、周囲の反応や行動の変化を具体的に描写することで、企業が重視する「周囲に影響を与える分析力」としての再現性が伝わる構成にしました。 |
| 【入社後】 入社後も、客観的な視点で現状を見極め、課題の本質を捉えた上で具体的な解決策を提示し、組織の成果に貢献していきたいと考えています。 |
| 添削コメント|自分の強みを企業でどう活かすかが明確で、ビジネスシーンを意識した表現になっています。 |
【NGポイント】
「戦略面の課題解決」など、分析力との関連が不明確な表現が見られました。具体的な分析行動や結果も曖昧で、企業が求める「再現性のある行動力」が伝わりにくくなっていました。
【添削内容】
抽象的だった表現を「データの記録」「パターン分析」など、行動の描写に書き換えました。論理的な戦術変更をアピールすることで、強みとの一貫性を強調しています。
【どう変わった?】
行動プロセスが明確になり、企業が重視する「問題発見から改善提案までの思考力・実行力」がより伝わる内容に仕上がりました。
| ・抽象表現は具体的な行動に変換する ・分析力を発揮した過程を示す ・成果は第三者の視点で表現する |
④分析力×ゼミ
ゼミ活動の中で、要因を整理して解決策を導いた自己PR例文です。
一般的な大学生活の中でも、課題の本質を見抜く姿勢や、客観的に状況を整理する力をどうアピールするかが重要ですよ。
| 【結論】 私の強みは、状況を客観的に把握し、要因を整理して最適な解決策を導き出す「分析力」です。 |
| 添削コメント|「分析力」をストレートに提示し、評価されやすい構成です。強みの定義と具体性のバランスが取れていて、企業が知りたい「再現性」のある力として伝わります。 |
| 【エピソード】 大学のゼミ活動で、地域の課題を解決するための提案プレゼンを行う機会がありました。 |
| 添削コメント|元の表現は状況描写が漠然としており、「分析力をどう発揮したか」が読み取りにくくなっていました。改善後は「停滞の要因分析」という視点を加えることで、分析的なアプローチが示されています。 |
| 【エピソード詳細】 まずは地域のアンケート結果や過去の取り組みを整理し、 |
| 添削コメント|改善後は“ホワイトボードへの記述”など具体的な行動を示し、「どのように分析したか」が視覚的に伝わる表現になりました。これにより、企業は実務での応用可能性をイメージしやすくなります。 |
| 【成果】 その提案はゼミ内でも高く評価され、 |
| 添削コメント|「最終選考進出」は成果として曖昧で、客観性や評価の具体性に欠けていました。改善後は「特別賞受賞」という具体的成果を示し、外部からの評価によって信頼性が格段に上がっています。 |
| 【入社後】 入社後も、複数の意見やデータが入り乱れる中でも冷静に整理し、 |
| 添削コメント|「課題解決や業務改善」は抽象的であり、どのような場面で分析力を使うのかが不明確でした。改善後は企業側が「職場での活かし方」をリアルにイメージしやすくなっています。 |
【NGポイント】
エピソードや成果の一部において、「分析力」がどのように発揮されたかの記述が抽象的すぎた点が課題でした。また、説明が簡潔すぎた結果、「成果」のインパクトが弱くなっていました。
【添削内容】
特にエピソード部分の状況描写を明確にする文章を追記しました。成果部分は第三者の評価に基づいた明確な実績に言い換えることで、エピソード全体に説得力を持たせています。
【どう変わった?】
読み手に「この人は実際に職場で分析力をどう発揮するのか」が伝わる自己PRになりました。結果として、再現性の高いスキルとして評価される内容へと改善されています。
| ・状況をできるだけ詳細に伝える ・どの部分で評価されたのかまでアピールする ・職場での再現性を意識する |
ゼミで頑張っていることを自己PRに用いたい方は多いのではないでしょうか。ゼミは多くの人が経験するので、書きやすい反面ほかの就活生との差別化が重要となってきます。書き方のポイントが知りたい方はぜひこちらもチェックしてみてください。
⑤分析力×部活動
部活動を通して、課題の本質を見極めて対策を立てたことを伝える例文です。
企業が求める「根拠に基づく行動力」を意識して構成することを意識しましょう。
| 【結論】 私の強みは、 |
| 添削コメント|「課題から改善策を見出す」は漠然としており、分析力の深さが伝わりにくい表現です。代わりに「課題の本質を見極める」と言い換えることで、採用担当により響く表現に修正しました。 |
| 【エピソード】 大学ではバレーボール部に所属し、週に5回の練習に取り組んでいました。 |
| 添削コメント|「勝率が下がる」「士気が落ちる」は抽象的で読み手に状況が伝わりづらいため、試合の連敗という具体的な事実に置き換えました。数字を含めた定量表現は分析の前提として説得力を持ちやすくなります。 |
| 【エピソード詳細】 私は原因を探るため、試合動画を複数見直しました。 |
| 添削コメント|「分析の結果〜と分かった」と書くことで、行動のプロセスと結論がつながり、分析力がどのように発揮されたかが明確になります。 |
| 【成果】 その結果、ミスが減り、チーム全体の連携がスムーズになりました。 |
| 添削コメント|「準優勝」という成果だけでは、本当に分析力による改善効果なのか分かりにくくなっていました。そのため、成功率や失点の改善といった具体的な数値を入れることで、行動と成果の因果関係を明確にしています。 |
| 【入社後】 入社後も、現状に疑問を持ち、 |
| 添削コメント|「丁寧に分析する姿勢」は抽象的で再現性に欠ける表現です。「構造的に捉え」「数値や事実に基づく」といった表現で、入社後の活躍を具体的にイメージさせています。 |
【NGポイント】
元の例文では主観的で曖昧な表現が多く、分析力をどう発揮したのかが伝わりにくい状態でした。また、成果部分も「準優勝」という結果だけに留まり、どのような数値的改善があったかが不明確です。
【添削内容】
抽象的な表現を「課題の本質を見極める」「分析の結果〜と分かった」など、具体性のある言い回しに変更しました。また成果に関しても「サーブ成功率85%」「失点の半減」など客観的な数字を加えています。
【どう変わった?】
分析の着眼点から行動、成果へのつながりが筋道立てて示されたことで、一貫性のある自己PRになりました。「この人物は業務上の課題も同様に見抜いて改善できるだろう」と期待できる内容です。
| ・分析結果は数字で裏付ける ・主観的な表現より客観的な事実を語る ・企業での再現性を意識する |
⑥分析力×塾講師
塾講師の経験を通して分析力を自己PRする例文です。
分析力をPRするには、課題の具体的な特定方法や取り組みを数値とともに示し、説得力を高めましょう。
| 【結論】 私の強みは、塾講師として生徒一人ひとりの課題を正確に把握し、改善策を導き出す分析力です。 |
| 添削コメント|結論部分は「分析力」という強みを明確かつ簡潔に示せており、読み手がその後のエピソードにも関心を持ちやすいように書けています。 |
| 【エピソード】 大学時代にアルバイトで高校生向けの学習塾講師を務めました。 |
| 添削コメント|「伸び悩んでいました」という曖昧な表現を具体的な人数や成績の状況で明確にしました。具体性が高まり、分析力を発揮した背景がより明確になっています。 |
| 【エピソード詳細】私はその原因を明確にするため、生徒一人ひとりの家庭学習の様子を記録したところ、多くの生徒が「復習不足」であると特定しました。そこで、 |
| 添削コメント|「目標設定を明確化」も行動として良い印象を与えますが、具体性をさらに高めるため、「小テストを実施して進度を可視化した」と詳細を示しました。 |
| 【成果】 その結果、定期テスト |
| 添削コメント|成果を客観的かつ具体的な数値や科目で表現し、曖昧な内容を修正しました。分析力の結果が客観的事実として示されており、説得力が格段に向上しています。 |
| 【入社後】 貴社に入社後もこの分析力を活かし、 |
| 添削コメント|入社後の目標をより具体的な業務内容に関連づけて明確にしたことで、企業側が採用後の活躍をイメージしやすくなり、評価されやすくなりました。 |
【NGポイント】
「成績に伸び悩んだ」など曖昧な表現が多く、分析力を具体的にどう発揮したのか、読み手に伝わりませんでした。また成果も漠然とした数値で表されていたため、説得力が弱いのが課題です。
【添削内容】
当時の状況が不明瞭だった箇所を、具体的な数値や状況説明に置き換えました。例えば、「半数以上が平均点以下」という具体的な状況説明や、「平均15点以上の向上」など詳細な成果を追記しました。
【どう変わった?】
結果的に、読み手が状況をイメージしやすい具体的な内容に改善されました。課題発見から対策、成果までの流れが明確になり、分析力が説得力を持って伝わる内容になっています。
| ・状況の説明を省略しすぎない ・数値で成果を客観的に示す ・入社後の業務に関連付ける |
⑦分析力×学業
分析力をTOEICの勉強に活かした自己PR例文です。
学業に関するエピソードでは、客観的な成果とプロセスを通じて、どれだけ論理的に取り組んだかを示すことが大切ですよ。
| 【結論】 私の強みは、目標達成に向けて課題を細かく分析し、最適な対策を実行する分析力です。 |
| 添削コメント|強みを「分析力」と明示し、かつその説明が「課題分解→対策実行」という採用担当が期待するビジネススキルと重なります。簡潔ながら本質が伝わる結論です。 |
| 【エピソード】 大学2年時、就職活動を見据えてTOEICのスコアを大幅に上げたいと考え、 |
| 添削コメント|「600→800点」は一般的に短期間では困難であり、誇張と受け取られる恐れがあります。ここでは、根拠ある目標設定(模試や期間)に言い換え、分析力に基づいた実行可能な計画であることを強調しています。 |
| 【エピソード詳細】 模試を通じて苦手分野を把握し |
| 添削コメント|苦手分野を把握してどうしたのかの説明が不十分になっていたため、追記しつつ、「誤答傾向の分析→構造化→戦略的対応」というプロセスを同時に伝えることで分析力が行動に直結していることを示しました。 |
| 【成果】 3ヶ月の対策期間で、TOEICのスコアを |
| 添削コメント|「大きく伸ばした」はインパクトはあるものの説得力に欠けると感じられる可能性があります。修正後はどの点からどの点まで伸びたのかを明記し、信頼性が向上しています。 |
| 【入社後】 入社後も目標に対して現状を正確に把握し、課題を細分化・分析した上で改善策を講じる姿勢を |
| 添削コメント|「貫き」は曖昧かつ精神論的な表現であり、ビジネスでの再現性をイメージしづらくなります。「徹底して実行する」という表現に置き換えることで、分析力の活用方法が明確になります。 |
【NGポイント】
TOEICスコアを600点から800点へ伸ばすという記述は、短期間では非現実的で、誇張と捉えられる恐れがあります。また、分析力をアピールするには具体的な分析行動が弱く、努力型の印象になってしまっていました。
【添削内容】
目標設定を修正し、行動の背景にある分析思考を明確にしました。リスニングの改善では誤答傾向を踏まえて施策を打ち出す流れに変更し、分析型のアプローチへと再構成しました。
【どう変わった?】
採用担当者が納得できる再現性ある分析力が伝わる構成に変わりました。実際の問題発見から改善までのプロセスが明確になったことで、「課題解決能力」や「論理的思考力」も伝わる内容になっています。
| ・目標設定には根拠を示す ・課題の分析過程を可視化する ・数字を用いて信頼性を示す |
⑧分析力×マーケティング系インターン
この例文では、マーケティング系インターンでの経験をもとに、データ分析力をどのように発揮したかを伝えています。
| 【結論】 私の強みは、情報を整理し、課題の本質を見極める分析力です。マーケティングインターンを通じて、データを基に仮説を立てて行動に移す力を磨いてきました。 |
| 添削コメント|「仮説をもとに行動に移す力を磨いてきた」という一文は良いですが、どんな分析力なのかを先に示すことで、より読み手に強みを印象付けるようにしています。 |
| 【エピソード】 大学3年次に参加したマーケティングのインターンでは、SNS広告の効果測定と改善提案を担当しました。担当企業の広告は |
| 添削コメント|「伸び悩んでいました」という表現では、課題の深刻度が伝わりません。数値を使って具体的な状況を示すことで、読者が「この課題にどうアプローチしたのか」に関心を持ちやすくなり、分析力の必要性が自然に伝わります。 |
| 【エピソード詳細】 私は過去の広告と購入率を分析し、 |
| 添削コメント|行動に至るまでの「根拠」が不足していたため、データを活用して仮説を立証した過程を明記しました。単なる思いつきではなく、論理に基づいた分析行動であることが明確になっています。 |
| 【成果】その結果、広告クリック後の購入率が2週間で1.4倍に改善しました。社内報にも成果が掲載され、 |
| 添削コメント|「高評価をいただいた」だけでは、成果の信頼性が弱いため、誰から・どのように評価されたかを具体的に記載しました。 |
| 【入社後】入社後も、この分析力を活かして市場や顧客の動きを数値から読み解き、 |
| 添削コメント|「戦略を立てられる人材」では抽象的な表現で、活躍の具体像が見えづらくなっていました。企業における再現性を示すため、「チームで提案し、売上向上に貢献する」という実務的な行動に落とし込みました。 |
【NGポイント】
元の文章では「分析力」という強みが抽象的に語られており、エピソードの具体性も薄かったため、企業側が再現性やエピソードの信頼性を感じにくい構成になっていました。
【添削内容】
インターンの時期や業務内容を明記し、取り組んだ課題に数値的な背景を与えました。加えて、仮説立証のプロセスや改善策の提案内容に対し、データの根拠をしっかりと示しました。
【どう変わった?】
「この人なら自社でも分析を任せられる」と感じられる自己PRになりました。曖昧だった内容が数値や根拠によって裏付けられたことで、分析力という強みが職場で活きる実践的な能力として伝わっています。
| ・分析の根拠は数値で示す ・強みが職場で再現可能なことをアピールする ・成果は評価者の声で裏付けする |
⑨分析力×営業系インターン
営業系の長期インターンで得た実体験をもとに、「分析力」を強みとしてニーズに合わせた提案ができることをアピールする自己PR例文です。
| 【結論】 私の強みは、状況を客観的に捉え、最適な行動を導き出す「分析力」です。 |
| 添削コメント|この結論は非常に端的かつ分かりやすく、読む人が一文で「分析力が強みなのだ」と理解できます。 |
| 【エピソード】 大学3年時に参加した営業系の長期インターンで、アポイントの獲得件数が伸び悩む課題に直面しました。 |
| 添削コメント|「自分のやり方に原因があると考えた」の一文では文章の流れが不自然になるため、「課題に気づいて主体的に動いた姿勢」に焦点を当てて追記し、問題解決型の人材として印象付けるようにしています。 |
| 【エピソード詳細】 自分のトークを録音して聞き直し、成果を出している先輩のやり方と照らし合わせました。その結果、 |
| 添削コメント|元例文は何が問題だったのかまでは伝わりますが、肝心の改善部分の説明が不十分で、「分析を活かして行動できる」強みを伝えきれていなかったため、実際どのように行動したのかを追記しました。 |
| 【成果】 その結果、アポイント率が月末には2倍に向上し、最終的にはチーム内で上位の成績を残すことができました。 |
| 添削コメント|「信頼を得た」という抽象的表現ではなく、行動と成果の関係性にフォーカスした言葉に置き換えることで、アピールの信頼性と説得力が向上します。再現性を強調することで、企業での活躍がイメージしやすくなります。 |
| 【入社後】 入社後もこの分析力を活かし、業務の中で成果が出にくい要因を自ら探り、常に改善と工夫を重ねる営業職として貢献したいと考えています。 |
| 添削コメント|この入社後の展望は具体的かつ企業目線に立っており、即戦力としての将来像を描けています。「分析力」を単にアピールするだけでなく、どう企業の利益や成長に還元できるかを語っている点が高評価です。 |
【NGポイント】
文章の繋がりが不自然になっている箇所がありました。また、課題に対する行動の部分や「信頼を得た」という成果の部分でも説明が少なく、強みをアピールしきれていない印象でした。
【添削内容】
課題発見と改善行動を軸に文章を再構成しました。また、曖昧なフレーズを削り、自身の行動・分析・成果を明確に伝える文に変更しています。再現性や数値的成果など、客観的評価に結びつく表現へと調整しました。
【どう変わった?】
問題意識を起点に「分析→行動→成果」という一貫したロジックが強調され、企業側が評価しやすい内容へと改善されました。営業職としての成長性・貢献意欲も明確にアピールできています。
| ・再現性のある成果を示す ・文章の自然な流れを意識する ・主体的に改善したことを述べる |
「エントリーシート(ES)がうまく作れているか不安……誰かに見てもらえないかな……」
就活にはさまざまな不安がつきものですが、特に、自分のESに不安があるパターンは多いですよね。そんな人には、無料でESを丁寧に添削してくれる「赤ペンES」がおすすめです!
就活のプロがESの項目を一つひとつじっくり添削してくれるほか、ES作成のアドバイスも伝授しますよ。気になる方は下のボタンから、ESの添削依頼をエントリーしてみてくださいね。
分析力を自己PRでより好印象にアピールする方法
自己PRで分析力を伝える際、単に「分析力があります」と述べるだけでは、企業に強みとして伝わりにくい場合があります。
企業は「その分析力を活かしてどんな努力ができて、どう成果に繋げられるか」を気にしているため、これらを明確に伝えることが重要です。
本章では、分析力をより効果的にアピールするための方法を3つ紹介します。これらを意識して、説得力のある自己PRを作成しましょう。
- 分析力と別の強みを組み合わせて伝える
- 具体的な数字やデータも一緒に伝える
- 分析内容を誰にでも分かりやすい表現にする
①分析力と別の強みを組み合わせて伝える
分析力をアピールする際は、別の強みと組み合わせて伝えましょう。
分析力はそれのみだと抽象的な印象ですが、「行動力」「コミュニケーション力」「創造力」などと組み合わせることで、より具体的な強みとして伝えられるのです。
実際に「データを分析して課題を発見したうえで、その改善策を周囲に提案し、実行しました」と伝えれば、「分析力」に加えて「提案力」や「実行力」も強みとしてアピールできます。
また、「チームの意見を聞きながら分析を進め、最適な解決策を見出しました」といった形で伝えれば、「協調性」や「調整力」も伝わるでしょう。
このように、分析した情報を活用する能力まで示せると、より高評価につながるでしょう。意識してみてくださいね。
②具体的な数字やデータも一緒に伝える
自己PRでは、具体的な数値やデータを示すことで、説得力が高まります。
「売上を向上させました」よりも、「分析したデータを基に改善策を提案し、売上を10%向上させました」と伝えるほうが、成果が明確になります。
例えば、インターンシップで顧客の購買データを分析し、購入頻度を高める施策を提案した経験がある場合、「施策導入後、リピート率が15%向上しました」と数値を交えることで、より具体的な実績として評価されるでしょう。
③分析内容を誰にでも分かりやすい表現にする
分析力をアピールする際、専門的な言葉を多用すると、かえって伝わりにくくなることがあるため、なるべく誰にでも伝わる表現になるよう工夫しましょう。
たとえば、「回帰分析を用いてトレンドを予測しました」といった表現は、面接官が理解しづらい可能性があります。
この場合は、「過去の売上データを比較し、次の月に売れる商品を予測しました」と言い換えることで、より伝わりやすくなります。
特に、就活では幅広い年代の人が評価するため、専門知識に頼らず、誰にでも分かる言葉で説明することが重要です。
以上のポイントを押さえた上で、自己添削をするとより質の高い自己PRに仕上がりますよ。以下の記事では、実際に自己添削する際のチェックポイントや、誰かに添削を依頼するときの方法についても紹介しているのでぜひ参考にしてください。
自己PRで「分析力」をアピールするポイントを理解して選考通過を目指そう!
自己PRで分析力をアピールする際は、自分自身の言葉で分析力を定義しましょう。分析力とは、現状を正確に把握し、未来を予測する能力です。
具体的な例を挙げて、自分の分析力をどのように活かしてきたかを説明します。そして、それがどのように将来の職場で役立つかを伝えることが重要です。この記事を参考に、充実した準備をして、就職活動に臨んでください。頑張ってくださいね。

まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













