【完全攻略】TG-WEB対策マニュアル|試験内容と高得点の秘訣を徹底解説
「TG-WEBって聞いたことはあるけれど、実際にどんな問題が出るのか分からない……」
そんな悩みを抱える就活生は多いのではないでしょうか。TG-WEBは、多くの大手企業が採用しているWebテスト形式の一つで、対策の有無が結果を大きく左右します。
SPIとは出題傾向が異なり、思考力やスピードも問われるため、事前準備が必須です。そこで本記事では、TG-WEB対策の基本から高得点を狙うための秘訣まで、初心者にも分かりやすく徹底解説します。
エントリーシートのお助けアイテム!
- 1ES自動作成ツール
- まずは通過レベルのESを一気に作成できる
- 2赤ペンESでESを無料添削
- プロが人事に評価されやすい観点で赤ペン添削して、選考通過率が上がるESに
- 3志望動機テンプレシート
- ESの中でもつまづきやすい志望動機を、評価される志望動機に仕上げられる
- 4強み診断
- 60秒で診断!あなたの本当の強みを知り、ESで一貫性のある自己PRができる
TG-WEBとは?基本の概要と特徴
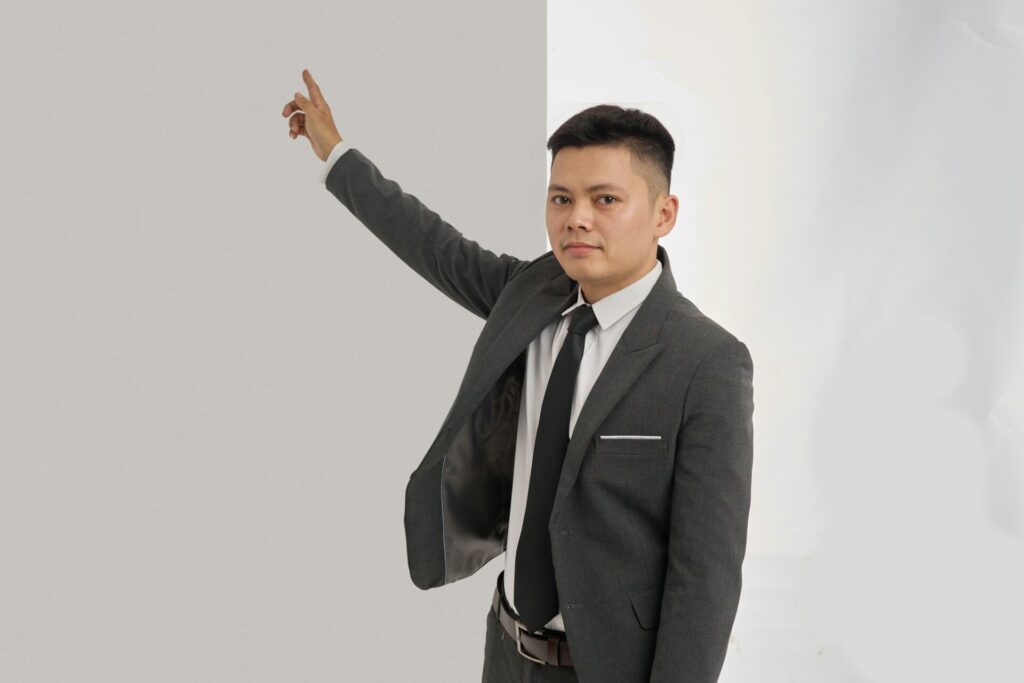
TG-WEBは、企業の採用選考で広く利用されているWeb適性検査のひとつです。多くの大手企業が導入しており、応募者の論理的思考力や読解力、英語力、性格傾向などをオンラインで多面的に評価します。
テスト結果は採用判断の参考になるだけでなく、応募者自身の強みや課題を客観的に把握する機会にもなるでしょう。
ここではTG-WEBの基本構成から特徴、他のWebテストとの違いまでを詳しく解説します。
- TG-WEBの全体構成
- 計数・言語・英語・性格の4分野
- 従来型と新型の違い
- 試験時間・問題数の目安
- 他のWebテスト(SPI・玉手箱)との違い
「就活でまずは何をすれば良いかわからない…」「自分でやるべきことを調べるのが大変」と悩んでいる場合は、これだけやっておけば就活の対策ができる「内定サポートBOX」を無料でダウンロードしてみましょう!
・自己分析シート
・志望動機作成シート
・自己PR作成シート
・ガクチカ作成シート
・ビジネスメール作成シート
・インターン選考対策ガイド
・面接の想定質問集100選….etc
など、就活で「自分1人で全て行うには大変な部分」を手助けできる中身になっていて、ダウンロードしておいて損がない特典になっていますよ。
①TG-WEBの全体構成
TG-WEBは「能力検査」と「性格検査」の2つで構成されています。能力検査では、数的処理や読解力、英語理解などの基礎スキルを測定し、職務に必要な論理的思考力や情報処理力を評価します。
一方、性格検査は協調性や主体性、忍耐力、ストレス耐性といった行動特性を分析する内容です。この2種類を組み合わせることで、企業は応募者を「スキル面」と「性格」の両面から判断できます。
単なる知識テストではなく、仕事に取り組む姿勢や思考の一貫性まで見抜くことが可能です。自分らしい回答を意識することで、より信頼性の高い結果が得られるでしょう。
②計数・言語・英語・性格の4分野
TG-WEBの能力検査は、「計数」「言語」「英語」「性格」の4分野に分かれています。計数分野では、グラフや表から数値を読み解く問題や、割合・確率・論理的推論などが出題され、分析力と判断力が必要です。
言語分野は文章読解や語句の意味理解、論理関係を把握する問題が多く、普段からニュースや本を読む習慣が対策になります。
英語分野は短文読解や文法理解、語彙問題などが中心で、TOEIC600点前後のレベルを意識して学習すると効果的です。
性格分野は一見簡単に思えますが、回答の一貫性がカギを握ります。正直に答えながら、自分の思考や行動パターンを見つめ直す機会にしてください。
③従来型と新型の違い
TG-WEBには「従来型」と「新型」があり、内容や出題傾向が異なります。
従来型は紙ベースや簡易Web形式で、問題数が少なく、短時間で終了する傾向があります。新型は完全Web化され、出題形式が多様化し、より実務に近い判断力や応用力を求められる設計です。
グラフの読解や長文処理など、複合的な問題が増えています。企業はより精度の高い人材評価を目指して新型を採用するケースが増加しています。
そのため、過去問題集や模擬テストを活用して形式に慣れておくことが大切です。テスト形式を把握するだけでも、当日の緊張を和らげ、落ち着いて実力を発揮できるでしょう。
④試験時間・問題数の目安
TG-WEBの試験時間は全体で約60〜90分程度、問題数は10~50問ほどです。計数・言語・英語の各分野が20〜30分、性格検査が15〜20分とされています。
制限時間に対して問題数が多いため、効率的に解答を進めることが求められます。焦って誤答を増やすより、確実に解ける問題を優先する方が得点率を上げやすいでしょう。
特に序盤の問題は比較的解きやすいため、落ち着いて取り組むことが重要です。また、時間配分を意識して解く練習を重ねると、本番でも焦らず実力を発揮できます。
数値処理問題などは、暗算や簡単な計算練習を日常的に取り入れておくと本番でも焦らずに解けるでしょう。
⑤他のWebテスト(SPI・玉手箱)との違い
TG-WEBはSPIや玉手箱と並ぶ代表的なWeb適性検査ですが、それぞれの目的や特徴が異なります。SPIは基礎的な思考力と性格のバランス重視、玉手箱はスピードと処理能力を測定します。
一方でTG-WEBは、論理的思考や読解力の「深さ」を重視しており、より応用的な判断が必要です。
さらにTG-WEBには英語問題が含まれている点も特徴です。企業がTG-WEBを導入する背景には、単に学力を見るのではなく、「実務で活かせる思考力」を評価したいという狙いがあります。
暗記よりも理解・分析を意識した学習を行いましょう。特に外資系やグローバル志向の企業では、TG-WEBでの得点が選考通過の鍵を握ることもありますよ。
TG-WEBを導入する企業の狙いと背景

就活でTG-WEBを実施する企業が増えていますが、その背景を理解しておくと効果的な対策につながります。ここでは、企業がTG-WEBを導入する5つの目的を詳しく解説します。
- 応募者の能力を見極めるため
- 企業文化や価値観とのマッチ度を判断するため
- 入社後の活躍度・ストレス耐性を測るため
- 採用コスト削減と効率化を実現するため
- ミスマッチ防止と定着率向上のため
①応募者の能力を見極めるため
企業がTG-WEBを導入する最大の目的は、応募者の基礎的な能力を正確に測定することです。言語・計数・英語などの分野を通して、論理的思考力や読解力、数的処理力を多面的に評価します。
これにより、面接だけでは判断しにくい知的な基盤や思考の癖を可視化できるのです。たとえば、限られた時間内に大量の情報を整理し、正確に対策を導き出す力は、ビジネスで欠かせないスキルです。
企業は単なる学力よりも、スピーディーに考え、状況に応じて柔軟に判断できる力を求めています。TG-WEBはそうした力を測定するツールとして非常に有効です。
受験者は、出題形式を理解し、過去問題などを使って反復練習することで得点アップが期待できます。特に制限時間の感覚をつかむ練習をしておくと、本番で実力を発揮しやすくなるでしょう。
②企業文化や価値観とのマッチ度を判断するため
TG-WEBの性格検査は、企業と応募者の価値観がどの程度一致しているかを判断する目的で実施されます。近年はスキルや学歴だけでなく、組織文化との相性を重視する企業が増えています。
どんなに能力が高くても、会社の考え方に共感できなければ、長期的な活躍は難しいと考えられているためです。
この性格検査では、応募者がどんな環境でモチベーションを発揮できるのか、チームでの関わり方やリーダーシップ傾向などを分析します。
回答内容から「主体的に動けるタイプ」「協調を重視するタイプ」などが見えてくるため、採用担当者は組織とのマッチ度を見極めることができます。
大切なのは、良く見せようとするのではなく、自然体で回答することです。無理に理想的な人物になろうとすると、一貫性がなくなりかえって評価を下げてしまうこともあるので注意しましょう。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
③入社後の活躍度・ストレス耐性を測るため
TG-WEBは、「入社後にどの分野で活躍できるか」「ストレスの多い状況でどんな反応を示すか」を見極める目的でも活用されています。
たとえば、思い通りにいかない場面で冷静に対応できるか、困難に直面した際に粘り強く行動できるかなど、問題解決力や精神的耐久力を推定するのです。
企業は採用段階で、将来的に安定して成果を出せる人材を選びたいと考えているため、こうした心理的な側面の分析はとても重要なのです。また、採用後の早期退職のリスクも防げます。
受験者にとっては、単なる適性テストではなく「自分の強みや弱点を知る機会」として捉えるのが大切です。
回答を通して、自分がどんな状況で力を発揮できるのかを理解すれば、今後の自己分析や面接対策にも役立つでしょう。
④採用コスト削減と効率化を実現するため
TG-WEBの導入は、企業の採用活動を効率化し、コストを抑えるうえで大きな効果を発揮します。オンラインで一斉に試験を実施できるため、会場準備や人件費などの運営コストを大幅に削減できます。
また、短期間で多くの応募者を選別できるため、採用までのプロセスを迅速に進められるのです。この効率化によって、企業はこれまでよりも幅広い学生層にアプローチできるようになりました。
地方や海外の学生も、移動せず自宅で受験できるため、選考機会の公平性が高まっています。就活生にとっても、移動の手間が省けることや、自分のペースで受けられる安心感は大きなメリットです。
TG-WEBは、企業にとっても学生にとっても「時間・費用・手間を最小化できる合理的な選考ツール」といえるでしょう。結果として、より多くの人材と出会う機会を生み出し、採用の質を高めています。
⑤ミスマッチ防止と定着率向上のため
TG-WEBは、採用後のミスマッチを防ぐためにも欠かせないツールです。応募者の志向性や性格傾向を事前に把握することで、入社後に「思っていた仕事と違った」と感じるケースを減らせます。
こうした分析を行うことで、入社後のギャップを最小限に抑え、社員の定着率を高めることができるのです。TG-WEBの結果からは、社員との相性や職務への適性が客観的に見えてきます。
これにより、企業は配属や育成方針を考える際の参考データとしても活用できます。応募者にとっても、自分に合う職場環境を見つけやすくなり、入社後のストレスを減らす効果が期待できるでしょう。
つまり、TG-WEBは「入社後の幸福度を高める指標」としても機能しているのです。自分の特性を理解し、それに合った企業を選ぶことで、長期的に充実したキャリアを築けるでしょう。
TG-WEBの試験内容の解説
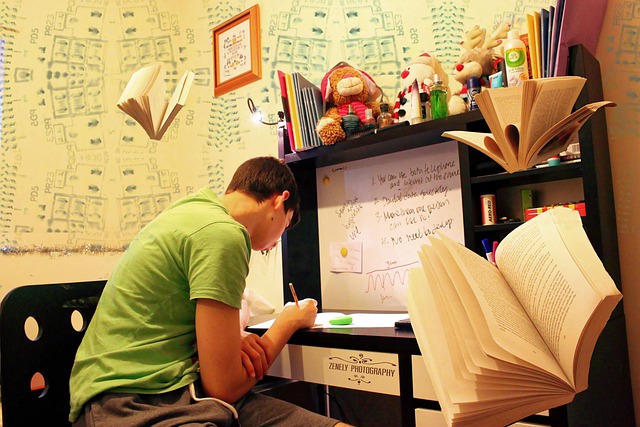
就職活動で多くの企業が採用選考に導入しているのが「TG-WEB」と呼ばれるWeb適性検査です。SPIや玉手箱と並び、応募者の基礎能力や性格傾向を測る重要なテストとされています。
ここでは、TG-WEBの主な試験内容を分野ごとに整理し、出題の全体像だけを簡潔にまとめます。ぜひ参考にしてください。
- 計数(計算・図表分野)の概要
- 言語(読解・語彙分野)の概要
- 英語(英文法・長文分野)の概要
- 性格検査(パーソナリティ)の概要
①計数(計算・図表分野)の概要
計数は、数的処理と論理的整理の力を幅広く測る問題です。割合・損益・比・確率といった基本概念に加えて、表やグラフから情報を読み取り、関係性を筋道立てて把握できるかが見られます。
設問は短時間での判断を想定しており、条件の読み落としを避けながら、必要な数値だけを素早く抽出できるかどうかが評価の焦点になります。ここでは、計算力だけでは不十分です。
数量データを適切に扱い、優先的に扱う情報を選ぶ力が問われます。新旧形式の違いで文章量や図表構造の内容は変化しますが、どちらも「定義に基づく整然とした思考」が重要です。
②言語(読解・語彙分野)の概要
言語は、「文章を正確に読み取る力」と「語の意味を適切に理解しているか」を確かめる分野です。設問は内容一致、言い換え、長文読解などが中心で、文中での根拠を見つける力が求められます。
主張・根拠・具体例の関係をたどり、段落同士のつながりや指示語の参照先を自然にたどれるかがポイントです。
語彙では日常語からやや専門寄りの表現まで幅があり、近い意味の語の差や文脈上のニュアンスに注意が必要でしょう。加えて、設問文の指示に沿って必要部分だけを素早く特定できる力も大切です。
③英語(英文法・長文分野)の概要
英語は、基礎的な文法知識と読解力を確認する問題です。文法では品詞、時制、前置詞、関係詞、語法など基本項目が幅広く扱われ、文全体として自然かどうかが見られます。
長文では、段落の役割や要旨の把握、指示語を短時間で押さえられるかがポイントです。題材はビジネス、社会、科学など多岐にわたるため、一般的な背景知識が理解の助けになります。
時間が限られるため、全文を細かく読むのではなく、設問に沿って情報を絞る姿勢も重要です。語彙レベルは基礎から中級にまたがり、文脈による意味の揺れを捉えられると安心でしょう。
④性格検査(パーソナリティ)の概要
性格検査は、価値観・行動の傾向などを多面的に把握する分野です。ここでは能力の優劣を競うのではなく、企業や職務とのマッチ度を見極める意図があります。
ただ、同じ内容を言い換えた設問もあるため、回答に矛盾が生じないようにすることが大切です。
自己像と行動のギャップが生まれにくい選択が望ましいため、無理に理想に合わせず自分らしい回答を心がけてください。
自分1人での自己分析に不安がある方は、就活のプロと一緒に自己分析をしてみませんか?あなたらしい長所や強みが見つかり、就活がより楽になりますよ。
TG-WEB計数問題の出題傾向

TG-WEBの計数問題は、就活生の中でも特に苦手意識を持つ人が多い分野です。出題形式や内容を理解しておくことで、得点力を安定させやすくなります。
ここでは、代表的な3つの出題カテゴリを紹介します。事前に傾向を押さえておくことで、効率的に勉強を進められるだけでなく、本番でも焦らず落ち着いて対応できるようになるでしょう。
- 図形・表・グラフ問題の傾向
- 四則演算・割合・比率問題の傾向
- 推論・確率・場合の数の傾向
①図形・表・グラフ問題の傾向
図形・表・グラフ問題では、情報整理力と論理的な読み取り力が問われます。単なる計算力ではなく、複数の条件を整理しながら正確に図表を読む力が求められているのです。
出題形式は、折れ線グラフ・円グラフ・表形式などが中心で、1つのデータを正確に把握するよりも、複数の情報を比較・分析する問題が多い傾向にあります。
たとえば、グラフ内の数値変化を読み取り、最も効率的な選択肢を選ぶ問題や、面積・角度・比率を求める応用問題などがよく出題されます。解くときは、まず設問を確認するのがオススメです。
また、日頃からニュース記事や統計データなどのグラフを見て、数字の動きを読む練習をしておくと、本番でも動じずに対応できるでしょう。
②四則演算・割合・比率問題の傾向
四則演算・割合・比率問題では、計算の正確さとスピードを両立できるかどうかが合否を分けます。出題は単純な計算ではなく、複数の条件を組み合わせた応用型が中心です。
利益率や人口比、時間あたりの作業量など、現実的な数値を扱う問題も増えています。このタイプの問題では、単位変換などのひっかけ要素が多く、焦って計算に入ると誤答しやすいのが特徴です。
条件を一度紙に整理してから解くと、見落としが減り、計算過程も明確になります。特に新型TG-WEBでは、問題文が長くなる傾向にあるため、「計算式に入る前の思考整理」がより重要です。
また、スピードを重視するあまり暗算に頼りすぎると、ケアレスミスが増える原因になります。自分で簡単な図や表を描き、情報をわかりやすく整理することで、正確さを高められるでしょう。
暗算力よりも、「計算手順を導く力」を鍛えることがおすすめです。練習時には、「なぜこの式を使うのか」「他の方法はなかったか」を意識しながら解き進めてください。
③推論・確率・場合の数の傾向
推論・確率・場合の数で求められるのは、「パターン化された思考」と「条件を見落とさない力」です。条件が入り組んでいるため、1つでも誤解すると答えが大きくずれてしまいます。
確率問題では、条件付き確率や順列・組み合わせが中心で、直感で答えると誤答になりやすい構造です。推論問題では、複数の条件を同時に処理しながら、最も妥当な結論を導く必要があります。
たとえば、「少なくとも1人が当たる確率」や「異なる結果が出る確率」など、否定の考え方を利用する設問も多いです。対策としては、「なぜその式を使うのか」を理解することが欠かせません。
サイコロ・カード・くじ引きなど身近な例を題材に、自分でルールを説明できるようになると、複雑な問題にも対応しやすくなります。
さらに、図や樹形図を使って状況を整理する練習をすると、問題を俯瞰して理解できるようになるでしょう。考える過程を丁寧に行うことが、得点アップにつながります。
④従来型と新型計数問題の違い
結論として、新型では「グラフや表が複雑化し、問題文も長め」従来型は「四則演算中心で比較的シンプルな構成」です。
新型では、計算力だけでなく「情報の取捨選択力」も求められます。問題文の中に余分な情報が含まれていることが多く、限られた時間の中で「解く必要のある部分」を瞬時に判断しなければなりません。
さらに、新型を導入する企業は年々増加しており、単なる暗記よりも「思考過程を理解する勉強法」が求められます。
対策としては、模擬テスト形式の演習を繰り返すのがおすすめです。形式の違いを意識し、問題を読むスピードと分析力を磨くことで、本番でも高得点を狙えるでしょう。
TG-WEB言語問題の出題傾向
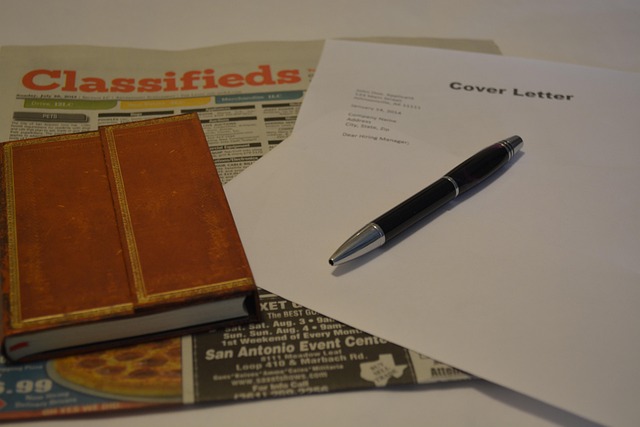
就活生が受ける適性検査の中でも、TG-WEBの言語問題は特に差が出やすい分野です。試験の形式をしっかり理解しておくことで、出題パターンに惑わされず安定した得点を取ることができるでしょう。
ここでは出題傾向と効果的な対策法を整理し、わかりやすく解説します。主な出題形式は次のとおりです。
- 空欄補充・並べ替え問題の傾向
- 語彙・慣用句・ことわざの出題傾向
- 長文読解問題の傾向と解法
- 従来型と新型言語問題の違い
①空欄補充・並べ替え問題の傾向
空欄補充や並べ替え問題は、文法力と語彙力の両方が問われる形式です。先に文全体の意味をつかみ、そのあと前後の文脈から文構造を正確に読み取ることが重要です。
特定の単語にだけ注目してしまうと、全体の論理を見誤り、文意がずれて誤答を選びやすくなります。特に「主語と述語の対応」「接続語の使い方」「修飾語の位置関係」などは注意すべきポイントです。
正答だけを見るのではなく、なぜ誤った選択肢が不正解なのかを分析すると、理解の深さが変わります。演習を通して、文の流れを直感的につかむ力を養ってください。
また、制限時間内で解く訓練を重ねることで、試験本番でも焦らず対応できるようになります。文を素早く読み取りながらも意味を見失わない練習を繰り返すと、安定した得点が取れるようになるでしょう。
②語彙・慣用句・ことわざの出題傾向
TG-WEBの語彙問題は、慣用句やことわざ、さらには四字熟語まで問われることもあり、日常ではあまり使わない表現に戸惑う人も少なくありません。
対策のポイントは、「どういう場面で使われるのか」というイメージをつかむことです。たとえば「一石二鳥」という言葉を覚える際には、その背景や使い方まで理解しておくと応用が利きます。
語彙力を伸ばすには、ニュース記事やエッセイ、ビジネス書などを通じて、自然な文脈の中で表現に触れるのが効果的です。
語彙問題では似た意味を持つ言葉が並ぶことも多いため、微妙なニュアンスの違いを意識して学ぶとよいでしょう。コツコツと積み重ねることで得点アップにつながります。
③長文読解問題の傾向と解法
長文読解は文章構成をすばやく把握する力と、筆者の意図を読み取る力が問われます。出題テーマはビジネス・社会問題・心理学など多岐にわたり、論理展開を理解しながら要点をつかむことが重要です。
設問の多くは「筆者の主張」「段落の関係」「具体例の意図」などを問う形式であり、単なる読解ではなく論理的思考も求められます。対策としては、段落ごとに要点をまとめる練習が効果的です。
これにより、全体の構成を読み取れるようになります。また、読むスピードを上げるだけでなく、内容を的確に把握する精読力も欠かせません。
1問ごとに目安時間を設定し、一定のスピードで解答を進める練習を重ねてください。読書量を増やし、さまざまな文体に慣れておくことで、初見の文章にも柔軟に対応できるようになるでしょう。
④従来型と新型言語問題の違い
従来型は文法や語彙を中心とした設問が多く、知識量で勝負できる内容でした。一方、新型は文脈理解や論理的思考力を重視しており、文章全体を読まなければ解けない問題が増えています。
そのため、選択肢のすべてが正しそうに見える問題では、文全体の整合性を見抜く力が必要です。
つまり、暗記だけでは対応しきれず、考えながら読む姿勢が求められます。さらに新型ではAIによる自動出題システムが導入されることもあり、同じ企業でも年によって形式が変わることがあります。
そのため、過去問に頼りすぎず、最新の模試や予想問題集で新傾向に慣れておくと安心です。試験本番では焦らず、まず全体を俯瞰してから問題を解くよう意識してください。
変化に対応できる柔軟な思考力を磨くことが、高得点への近道になります。
TG-WEB英語問題の出題傾向

TG-WEBの英語問題は、読解力と語彙力の両方をバランスよく問う内容です。
英文法・語彙・長文読解と幅広い分野から出題されるため、出題形式を理解し、効率的に学習することが得点アップの鍵となります。ここでは、各問題タイプの傾向と効果的な対策を紹介します。
試験本番で慌てないためにも、問題構成や難易度の特徴を事前に把握しておくことが重要です。
- 英文法・語彙問題の傾向
- 英語長文読解問題の傾向
- 出題テーマ別の語彙分野と頻出トピック
①英文法・語彙問題の傾向
TG-WEBの英文法・語彙問題は、文法の基礎を正確に理解しているかを確認する内容が中心です。品詞の使い分けやイディオム、動詞の語法、さらには前置詞の使い方など細かい文法知識も問われます。
単純に単語の意味を知っているだけではなく、文の構造や語句のニュアンスまで理解することが求められます。代表的な形式は「文中の空欄に最も適切な単語を選ぶ」というものです。
この形式では、単語の意味だけでなく前後の文脈を読み取る力が欠かせません。文の主語・動詞・目的語の関係を把握しながら、全体の流れを意識して解くことが大切です。
対策としては、過去問や模試を通して慣れることがあげられます。特に間違えた問題はそのままにせず、「なぜ誤ったのか」「正しい選択肢はどう使われるのか」を丁寧に分析しましょう。
この繰り返しによって文法感覚が鍛えられ、自然とスピードと正確さが身につきます。また、英文を声に出して読むことで、リズムと言語感覚を養うのもおすすめです。
②英語長文読解問題の傾向
TG-WEBの長文読解問題は、英語セクションの中でも特に得点差が出やすい分野です。出題されるテーマはビジネス、科学、社会問題など多岐にわたり、文章の内容を論理的に読み解く力が求められます。
設問形式は内容一致、空欄補充、要旨把握が中心です。文章の展開を追ううえで、接続詞や代名詞の指す内容に注意を払うと理解がスムーズになります。
段落ごとに筆者の主張を整理して読むと、要点をつかみやすくなるでしょう。また、文章全体のテーマを意識しながら読むことで、設問の意図も把握しやすくなります。
効率よく解くためには、まず設問を先に読んでから本文に目を通すのがおすすめです。問題文を読むことで、探すべき情報が明確になり、時間のロスを防げます。
限られた試験時間の中では、すべてを完璧に理解するよりも「必要な情報を素早く見抜く力」を意識することが重要です。英語を「読むスピード」よりも「理解の深さ」で勝負しましょう。
③出題テーマ別の語彙分野と頻出トピック
TG-WEBの英語問題には、出題テーマに一貫した傾向があります。特にビジネス、経済、テクノロジー、環境、社会問題などの分野が多く取り上げられます。
これらのテーマは就職活動や企業活動にも関わる内容が多く、文章の背景知識を持っていると理解が格段に深まります。
頻出語には「innovation(革新)」「productivity(生産性)」「sustainability(持続可能性)」などがあり、社会的文脈を理解しながら語彙を習得することが大切です。
単語帳で意味を覚えるだけでなく、例文で用法を確認し、実際にどのような状況で使われるかを理解しておくと記憶が定着します。また、同義語や反意語の関係を意識して整理するのもおすすめです。
さらに、時事ニュースや英字記事を読むと、頻出テーマに関連した語彙や表現が自然に身につき、理解がスムーズになります。語彙を広げることで、TG-WEBの読解問題への対応力も向上するでしょう。
TG-WEB性格検査の出題傾向

TG-WEBの性格検査は、企業が学生の適性や価値観を客観的に把握する意図が多いです。質問の内容は幅広く、仕事に対する姿勢やチームでの行動パターン、意思決定の傾向など、多岐にわたります。
多くの場合、複数の選択肢の中から自分に最も近いものを選ぶ形式ですが、注意したいのは「正解が存在しない」という点です。そのため、無理に理想の人物像を演じる必要はありません。
日常の自分の行動や考え方に沿って回答することが最も適切で、企業もその一貫性から学生の人物像を判断します。事前に出題傾向や質問パターンを理解しておくと、回答に迷う場面を大幅に減らせます。
具体的には、自己分析を深めて自分の強みや弱みを整理しておくこと、質問の意図をよく読みながら回答することが、ポイントです。
無理に理想の人物に合わせて回答すると矛盾が生まれ、信頼を失いやすいので注意しましょう。
TG-WEB対策方法/効率的な勉強の進め方

就活で多くの企業が導入しているTG-WEB。特徴を理解し、効率的に対策を進めることが内定への近道です。
ここでは、実践的な学習手順をステップごとに紹介します。自分のペースに合った方法で計画的に取り組みましょう。適切な手順で勉強を進めることで、短期間でも得点アップを実現できるはずです。
- 志望企業がTG-WEBを導入しているか確認する
- 出題傾向を把握する
- 学習スケジュールと計画を立てる
- 問題集・参考書の選び方
- Web模試・スマホアプリでの実践練習
- 苦手分野を克服する学習サイクルの構築
①志望企業がTG-WEBを導入しているか確認する
まず確認すべきは、志望企業がTG-WEBを採用しているかどうかです。企業によって適性検査の種類は異なり、TG-WEB以外にもSPIや玉手箱などが使われることがあります。
採用ページや口コミサイト、就活系の掲示板を活用して最新情報を調べ、自分が受ける形式を早めに特定しておきましょう。誤った形式を勉強してしまうと、努力が無駄になってしまいます。
特に同じ企業でも年度によって検査形式を変えるケースもあるため、最新年度の受験情報を確認する習慣をつけておくことが大切です。
また、OB・OG訪問や説明会などで実際の受験形式を聞くのも効果的です。正しい情報をもとに準備を進めることで、学習の方向性が明確になり、効率的に成果を上げられるでしょう。
準備の早い段階で確認しておくことが、後の安心感にもつながります。
②出題傾向を把握する
まずTG-WEB全体の出題傾向を理解し、どの分野に重点を置くかを決めましょう。
TG-WEBは、言語・計数・英語・性格検査の4分野で構成されています。計数分野ではスピードと正確さ、言語分野では読解力や語彙力、英語分野では基礎的な文法と読解のバランスが求められます。
過去問題や模擬問題を通して頻出パターンを分析することで、勉強すべき範囲を絞り込めます。
特にTG-WEBは「制限時間の短さ」が特徴なので、内容理解だけでなく時間感覚をつかむ練習も必要です。自分の苦手を分析し、優先順位をつけて学習を進めると効率よく得点を挙げられるでしょう。
③学習スケジュールと計画を立てる
TG-WEBの勉強では、明確なスケジュールを立てて継続することが非常に重要です。まず試験日から逆算し、1週間ごとの学習テーマを設定しましょう。
「今週は計数問題を中心に」「来週は言語と英語を並行して」など、細かく区切ると進捗を可視化しやすくなります。
さらに、勉強計画には「復習日」と「模擬練習日」を組み込むことが欠かせません。人は3日後には学んだことの大半を忘れてしまうといわれています。
復習のタイミングを意識することで記憶が定着し、安定した得点力につながります。勉強時間を長く確保できない人は、1日30分でも構いません。
短時間でも集中して取り組むことが重要です。無理のないペースで続ければ、試験直前の焦りを減らし、安定して力を発揮できるようになるでしょう。
④問題集・参考書の選び方
問題集選びを誤ると、せっかくの努力が無駄になってしまうことがあります。TG-WEBには公式問題集が存在しないため、「TG-WEB対応」や「Webテスト形式別」と明記された市販教材を選ぶのが基本です。
購入時には必ず最新版を選びましょう。出題傾向は年度によって変化するため、古い教材では現行の問題形式に対応できない場合があります。
また、複数の問題集に手を出すより、1冊を徹底的にやり込む方が効果的です。特に解説が丁寧で、間違えた理由が理解できる構成の教材を選ぶと学習効率が高まります。
自分のレベルに合った問題集を選ぶことも大切です。基礎力が足りないと感じる人は、やや易しめの入門書から始めるのがおすすめ。参考書を活用して理解を深め得点アップを狙いましょう。
⑤Web模試・スマホアプリでの実践練習
TG-WEBの本番は制限時間が非常に短く、時間配分が結果を左右します。そのため、Web模試やスマホアプリを活用した実践練習が効果的です。
オンライン模試は本番に近い環境で問題に取り組めるため、緊張感を持って時間感覚を磨けます。スマホアプリなら通学時間や待ち時間など、スキマ時間を活用して継続的に練習することが可能です。
模試を受けた後は、必ず結果を分析しましょう。間違えた問題の原因を探り、理解不足なのかケアレスミスなのかを区別します。これを繰り返すと、次同じミスをしなくなるはずです。
また、定期的に模試を受けることで成長を実感しやすくなり、モチベーションの維持にもつながります。実践を重ねるほど本番の焦りが減り、落ち着いて力を発揮できるようになるでしょう。
⑥苦手分野を克服する学習サイクルの構築
苦手分野を克服するための学習が大切です。TG-WEBでは分野ごとの得点が総合評価に影響するため、苦手を放置するのは避けましょう。
まず「間違いノート」を作り、解けなかった問題や迷った問題を記録します。間違いの原因を可視化すると、次に同じミスを防ぎやすくなります。
同じタイプの問題を何度も解くことで、解法パターンが自然に身につきます。苦手分野こそ、繰り返しの演習が必要です。また、週単位で成果を振り返り、成長を確認するのも効果的です。
スマホアプリや模試の履歴を使えば、得点の推移が見える化され、モチベーション維持にもつながります。焦らずコツコツと練習することで、確実に得点力を底上げできるでしょう。
TG-WEBで高得点を狙うコツとテクニック

就活で多くの企業が導入する「TG-WEB」は、短時間で正確な判断力を問うWeb適性検査です。高得点を取るには、やみくもに問題集を解くだけでは不十分でしょう。
ここでは本番で実力を最大限に発揮するための具体的なテクニックを紹介します。しっかりと準備を整え、自分の強みを活かしながら効率的にスコアを伸ばしていきましょう。
- 制限時間を意識して解答順序を工夫する
- ひっかけ問題を見抜く読解テクニック
- 計算スピードを上げる
- 本番でのメンタルコントロール術
- 試験後の振り返りを行う
①制限時間を意識して解答順序を工夫する
TG-WEBの特徴は「時間の短さ」と「問題の難易度の高さ」にあります。まずは「得意な問題から解く」ことを徹底し、瞬時に判断して切り替える練習が大切です。
制限時間を意識せず全問を順に解こうとすると、終盤で焦ってミスをしやすくなるでしょう。特に、最初の数問で時間を使いすぎると、後半の得点源を逃してしまうことがあります。
過去問題を解くときはタイマーを使い、時間配分を意識しながら本番と同じ環境で取り組むと良いでしょう。また、問題全体を一度ざっと見渡してから解くことで、難易度の感覚をつかみやすくなります。
取れる問題を確実に取り、難問は潔く飛ばす勇気も必要です。こうした戦略的な姿勢を持つことで、焦りを抑えながらも安定した得点を維持できるようになります。
②ひっかけ問題を見抜く読解テクニック
TG-WEBの言語問題は、選択肢の文面が似ていたり、本文の一部を切り取っただけの内容が正解のように見えたりと、注意して読まないと引っかかってしまう問題が多いのです。
これを防ぐには、「設問文→選択肢→本文」の順で読むことを習慣にすると良いでしょう。最初に問われている内容を把握しておけば、本文中のどこに注目すべきかが明確になり、効率よく正答を導けます。
さらに、設問ごとに「根拠のある選択肢」を意識して選ぶ癖をつけることが大切です。直感だけに頼らず、本文中に答えの裏づけを求めることで、読み間違いを防げます。
日頃の練習では、間違えた問題を分析し、自分がどのようなパターンでミスをしやすいかを把握しておきましょう。弱点を理解しておくと、同じ失敗を繰り返さず、読解力全体の底上げにもつながります。
③計算スピードを上げる
TG-WEBの計数問題では、正確さとスピードの両方が求められます。時間内に解き切るためには、ただの暗記ではなく「瞬時に処理できる計算力」を身につけることが重要です。
まずは、計算過程を省きすぎず、メモに残すことを意識しましょう。すべてを紙に書くと時間が足りませんが、暗算だけに頼ると正確性が落ちます。
練習を重ねて、自分に合ったバランスを見つけることが大切です。また、比率・割合・表の読み取りなど、頻出パターンを事前に把握しておくと本番での迷いが減ります。
普段から四則演算や端数の処理を意識的に行うことで、自然とスピードが上がるでしょう。さらに、数字を「かたまり」で認識するトレーニングも効果的です。
桁数の多い計算もパターン化して考えられるようになると、時間が大きく短縮されます。地道な練習が結果に直結する分野なので、日々の継続が最も重要です。
④本番でのメンタルコントロール術
TG-WEBは制限時間が厳しいため、焦りや緊張で実力を発揮できないケースが多く見られます。どれだけ準備しても、当日の心の状態次第で結果が変わることも珍しくありません。
まずは深呼吸をして心拍数を整え、目線を画面中央に戻してから問題に取り組んでください。焦りを感じたら一度視線を離し、呼吸を整えるだけでも思考がクリアになります。
また、前日は遅くまで勉強せず、しっかり睡眠をとることが重要です。睡眠不足は集中力の低下を招き、ミスを誘発しやすくなります。
軽いストレッチや深呼吸など、リラックスできるルーティンを作るのもおすすめです。
「完璧に解こう」と意気込みすぎるより、「取れる問題を確実に取る」と意識する方が安定した結果につながります。心の余裕がある状態こそが、本当の実力を発揮するための最良の環境です。
⑤試験後の振り返りを行う
TG-WEBは受けっぱなしでは成長できません。試験後の振り返りを行うことで、自分の弱点を見つけ、次に向けて確実な改善が可能になります。
まずは時間配分のミスや、手こずった問題を具体的に書き出しましょう。どの問題に時間を使いすぎたか、どんな思考のクセがあったかを記録することが大切です。
さらに、正解した問題の中にも「たまたま合っていたもの」がないか確認しておくと良いでしょう。勘で選んだ問題を放置すると、本当の実力がつかないままになります。
次に向けての改善計画を立てる際は、「何を」「どれくらい」「いつまでに」取り組むかを明確にすると効果的です。定期的に振り返りを行い、改善することで大きくスコアを伸ばせるようになるでしょう。
TG-WEBのボーダーラインはどれくらい?
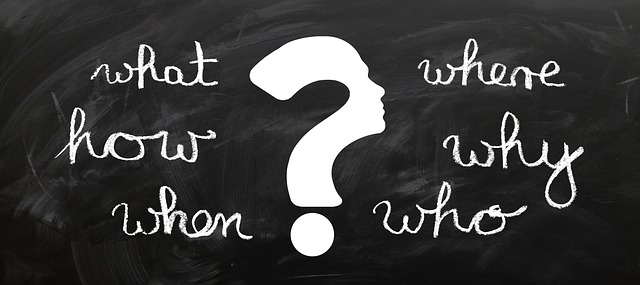
結論から言うと、TG-WEBのボーダーラインはおおむね正答率70〜80%が目安です。ただし、企業や業界によって大きな差があり、人気企業ほど高い基準を設定している傾向があります。
特に総合商社や外資系コンサルのように、受験者のレベルが高い業界では、8割以上の正答率が求められることも珍しくありません。
こうした企業では、スコアだけでなくスピードや安定した正答率も重視されるため、短時間で正確に解答する力が必要です。一方で、IT企業やメーカーなどでは6割台でも通過できるケースがあります。
同じTG-WEBでも重要度が企業ごとに異なるため、「平均的なボーダー」だけで判断するのは危険です。実戦形式での練習を重ね、自分の得点がどのレベルにあるか把握するようにしましょう。
TG-WEBによくある質問(FAQ)

ここでは「対策期間」「電卓の使用可否」「不正検出」「同時受験」「外部ツールの発覚」など、特に注意しておきたいポイントを分かりやすく解説します。
正しい知識を持っておくことで、安心して本番に臨めるでしょう。また、ここで紹介する内容を事前に理解しておくことで、焦りや不安を減らし、実力を最大限に発揮しやすくなります。
- TG-WEBの対策期間の目安はどれくらい?
- 電卓やメモの使用は認められるか?
- 替え玉受験や不正行為の検出方法は?
- 他人と同時に受験しても問題ないか?
- 解答集や外部ツールの利用は発覚するか?
①TG-WEBの対策期間の目安はどれくらい?
TG-WEB対策に必要な期間は、一般的に2〜4週間が目安といわれています。短期間でも集中して取り組めば得点力を高められますが、問題形式に慣れていない人ほど、計画的な学習が必要です。
TG-WEBはSPIよりも難易度が高く、論理的思考やスピードが求められるため、初めて解くと戸惑う人も多いでしょう。特に計数分野は出題形式が多様で、反復練習の有無が結果を大きく左右します。
最初の1週間は出題傾向を分析し、次の2週間で問題演習を繰り返し、残りの期間で弱点補強を行うのが効果的です。問題を「速く・正確に」解く練習を意識すると、本番での焦りも減ります。
早めに準備を始めておくことで、心の余裕を持って試験に臨めるでしょう。
②電卓やメモの使用は認められるか?
TG-WEBでは、基本的に電卓の使用は禁止されています。問題は暗算や筆算で解けるように設計されており、公平性を保つためでもあります。
オンライン試験の場合、操作履歴が細かく記録されているため、不自然な入力があると不正行為とみなされることがあります。
一方で、メモの使用に関しては企業ごとに対応が異なり、許可されているケースもあります。ただし、試験案内に「完全禁止」と記載されている場合は必ず従ってください。
仮にメモを使う場合でも、解法を整理する程度にとどめるのが無難です。最も重要なのは、何も使わなくても正確に解ける力をつけることです。
本番環境に近い形で練習を重ねることで、落ち着いて試験を進められるようにしましょう。
③替え玉受験や不正行為の検出方法は?
TG-WEBでは、不正を防ぐための監視体制が非常に厳しく設計されています。カメラやマイク、操作履歴などのデータが常に記録されており、不正受験の多くは検出されます。
AIによる顔認識システムが導入されているため、受験者の動作や表情、画面操作のタイミングまで監視されているのです。
また、回答パターンの分析も行われ、極端に速い回答や、特定分野だけ異常に正答率が高い場合などは、自動的に不正疑惑として判定されます。
企業側には不正履歴が共有されることもあり、発覚すれば信頼を大きく損なう結果につながります。正しい方法で努力することこそ、確実な成功への道です。
④他人と同時に受験しても問題ないか?
複数人で同時にTG-WEBを受けることは、大きなリスクがあります。そもそも試験問題はランダムで構成されているため、協力しても正確な答えを共有することは難しいのが現実です。
一緒に受験したことがきっかけで、不正の疑いをかけられる可能性もあります。集中力を欠いたり、他人のペースに引きずられたりするリスクもあるため、個人で受験する方が安全で効果的です。
落ち着いた環境で自分のペースを保つことが、最終的に高得点につながります。正々堂々と挑戦する姿勢が、結果的に一番信頼されるでしょう。
⑤解答集や外部ツールの利用は発覚するか?
最近のTG-WEBでは、AIによる解答パターン検知が進化しており、不自然な回答は多くの場合ばれます。
特に、解答集や外部ツールを利用して短時間で高得点を取った場合や、極度に高い正答率が続いた場合などは、自動的にシステムで不正疑いとして記録されます。
企業は受験者の真の実力を見たいと考えているため、不正と判断された時点で評価が下がるのは避けられません。
結局のところ、誠実に練習し、出題傾向を理解したうえで効率的に学習するのが最も効果的なのです。
出題傾向をつかんで、TG-WEBを制して就活を成功させよう

TG-WEBは、多くの企業が導入する代表的なWebテストであり、論理的思考力・言語理解力・英語力・性格特性を総合的に評価する重要な試験です。
だからこそ、出題傾向をしっかりつかみ、効率的に対策を進めることが合格への第一歩となります。
計数・言語・英語・性格の4分野を理解し、制限時間を意識した練習を重ねることで、自信を持って本番に臨めるようになります。
志望企業がTG-WEBを採用しているかを確認し、自分に合った問題集やアプリを活用するのも効果的です。戦略的に学び、得点力を磨けば、あなたの就活は必ず前進します。
積み重ねた努力が結果につながるよう、一歩ずつ着実に対策を進めていきましょう。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。












