ケアマネージャーの年収相場と将来性|収入アップの秘訣も紹介
「ケアマネージャーってどれくらい稼げるの?」「資格を取れば本当に収入アップできる?」
介護や福祉の現場で中心的な役割を担うケアマネージャー(介護支援専門員)。高齢化が進む日本において、需要が増える一方で、年収や待遇について気になる人も多いのではないでしょうか。
本記事では、平均年収や地域・経験年数による違い、さらに主任ケアマネージャーや管理職への昇格による収入アップのポイントまでを徹底解説します。
「これからケアマネージャーを目指したい」「資格を活かしてキャリアアップしたい」そんな方に向けて、年収のリアルと今後のキャリア戦略をわかりやすくまとめました。
ぜひ最後までご覧ください。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
ケアマネージャー(介護支援専門員)とは?

介護職の中でも「ケアマネージャー」は、利用者の生活を支える重要な専門職です。ここでは、仕事内容や働く場所、そして求められるスキルについて紹介します。
将来のキャリアを考えるうえで、まずは職種の全体像をしっかり理解しておきましょう。
- ケアマネージャーの仕事内容と役割
- ケアマネージャーの主な勤務先
- ケアマネージャーに求められるスキルと適性
①ケアマネージャーの仕事内容と役割
ケアマネージャー(介護支援専門員)は、介護を必要とする高齢者やその家族に対して、最適な介護サービスを受けられるよう支援する専門職です。
主な仕事は、利用者の心身の状態や生活環境を丁寧に把握し、どのような支援が必要かを総合的に判断したうえで「ケアプラン(介護サービス計画)」を作成すること。
また、作成したプランを実現するために、訪問介護やデイサービス、リハビリ、医療機関など複数の関係機関と連携・調整を行います。
さらに、介護保険の申請や更新のサポート、利用者や家族からの相談対応も大切な役割です。現場で直接介助を行うわけではありませんが、幅広い知識と的確な判断力が求められます。
利用者の「その人らしい生活」を支えるコーディネーターとして、社会的意義の高い仕事といえるでしょう。
②ケアマネージャーの主な勤務先
ケアマネージャーの勤務先は、主に「居宅介護支援事業所」と「介護施設」の2つに大別されています。
居宅介護支援事業所では、自宅で生活する高齢者を対象にケアプランを作成し、訪問介護・デイサービス・福祉用具貸与などの利用を支援します。
一方、介護老人保健施設(老健)や特別養護老人ホーム(特養)などの施設では、入所者の生活全体を見据えて介護計画を立て、職員間での情報共有や調整を行います。
さらに、地域包括支援センターで地域高齢者の総合相談に応じるケアマネージャーもいます。
勤務先によって担当業務や労働時間、休日体制などが異なるため、自身のキャリア目標やワークライフバランスを考慮して選択することが大切です。
③ケアマネージャーに求められるスキルと適性
ケアマネージャーに必要とされるスキルは多岐にわたりますが、特に重要なのは「傾聴力」と「調整力」です。
利用者や家族の希望を丁寧に聞き取り、その思いを反映させた支援プランを立てる力が求められます。
また、医師・看護師・介護職員・行政担当者など、さまざまな立場の人と関わるため、対話を通じて最適な解決策を導き出すコミュニケーション能力も欠かせません。
さらに、介護保険制度や福祉行政、医療知識など幅広い専門知識を理解し、変化する制度に合わせて最新情報を学び続ける姿勢が必要です。
利用者一人ひとりの生活背景を理解し、寄り添うことができる思いやりと責任感も大切になります。
ケアマネージャーになるには

ケアマネージャーになるには、国家資格である「介護支援専門員」の資格を取得する必要があります。ここでは、資格取得までの流れをわかりやすく紹介しています。
就活生が将来を見据えてキャリアを考えるうえで、ステップをしっかり理解しておくことが大切です。
- ケアマネージャーになるための基本ステップを理解する
- ケアマネージャー資格(介護支援専門員)の受験条件を満たす
- 介護支援専門員実務研修受講試験の内容を把握する
- 介護福祉士や看護師などの資格からキャリアアップする
- 試験合格後に実務研修と登録手続きを完了する
①ケアマネージャーになるための基本ステップを理解する
ケアマネージャーを目指すには、まず介護や医療の現場で一定期間の実務経験を積むことが必要です。
介護福祉士や看護師、社会福祉士などの資格を取得し、専門職として経験を重ねることで受験資格を得られます。
そのうえで「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格し、さらに実務研修を修了して登録を行うことで、ようやく正式なケアマネージャーとして認定されます。
このプロセスは決して短い道のりではありませんが、現場経験を通して身につけたスキルや人間理解は、ケアマネージャーとしての大きな財産になるでしょう。
計画的に資格取得と経験を積み重ねる姿勢が、信頼される専門職への第一歩です。
②ケアマネージャー資格(介護支援専門員)の受験条件を満たす
介護支援専門員試験を受けるためには、介護・医療・福祉の分野で通算5年以上、かつ900日以上の実務経験が求められます。
対象となる職種は介護福祉士、看護師、准看護師、社会福祉士、精神保健福祉士など多岐にわたっています。この条件を満たしていないと受験資格が得られないため、早期にキャリア設計を行うことが大切です。
たとえば、大学在学中から介護職に関心がある人は、まずは介護福祉士を目指して実務経験を積むルートを選ぶのが現実的でしょう。
どの職種で経験を積むか、どの資格を起点にするかを明確にしておくことで、スムーズに次のステップへ進むことができます。
③介護支援専門員実務研修受講試験の内容を把握する
介護支援専門員実務研修受講試験は、介護保険制度や福祉・医療サービスに関する総合的な知識を問う国家試験です。
試験範囲は「介護支援分野」「保健医療サービス分野」「福祉サービス分野」の3領域に分かれており、幅広い分野から出題されます。
難易度は比較的高いですが、過去問題や模擬試験を繰り返し学ぶことで理解を深められるでしょう。また、単なる暗記ではなく、実務での経験と知識を結びつけながら学ぶことがポイントです。
実際の介護現場を思い浮かべながら学習することで、制度の背景やサービスの仕組みをより深く理解できるでしょう。
④介護福祉士や看護師などの資格からキャリアアップする
介護福祉士や看護師、社会福祉士などの資格を持つ人は、ケアマネージャーへのキャリアアップがしやすい立場にあります。
これらの資格を通して培った専門知識や実務経験は、ケアプラン作成や利用者支援の際に強みとして活かせるでしょう。
現場で培った観察力や判断力、利用者との信頼関係を築く力は、ケアマネ業務において非常に重要なスキルです。
また、医療・福祉両面から支援できる視点を持つことで、より質の高いサービスを提供できるようになります。
自らの専門分野を広げ、長期的なキャリア形成を目指したい人にとって、ケアマネージャーは成長のチャンスを与えてくれる職種といえるでしょう。
⑤試験合格後に実務研修と登録手続きを完了する
試験合格後は、都道府県が実施する「介護支援専門員実務研修」の受講が必要です。この研修では、ケアプラン作成の実践的な知識や介護保険制度の運用方法、法的責任に関する内容などを学びます。
研修は数十時間にわたるカリキュラムで構成され、現場で即戦力として活躍できる力を養うことが目的です。
研修を修了した後、都道府県への登録申請を経て、正式にケアマネージャーとして業務に就くことが可能になります。
試験に合格した段階で終わりではなく、登録手続きまでをスムーズに進めることが大切です。ここまでの流れをしっかり理解しておけば、自信を持ってキャリアをスタートできるでしょう。
ケアマネージャーの平均年収

ケアマネージャー(介護支援専門員)の全国平均年収の目安は、約429万円前後であるとされており、これは他の介護職と比較するとやや高めの水準です。
ただし、勤務先や雇用形態によってはこの平均から乖離が生じます。
居宅介護支援事業所勤務だと、利用者数や担当ケアプラン数に応じた手当がつく場合があり、年収がさらに上振れすることもあり得るでしょう。
反対に、非常勤・パート勤務の場合は年収は大きく下がり、時給制で働く人も多くなります。経験を重ね、資格や役職を得られれば年収アップの余地は十分あるでしょう。
全体としては、ケアマネージャーは「安定性と成長性を兼ね備えた職種」と言えます。主任ケアマネージャーや管理職へのステップを意識すれば、さらなる収入も目指せるでしょう。
ケアマネージャーの年収に影響する要因
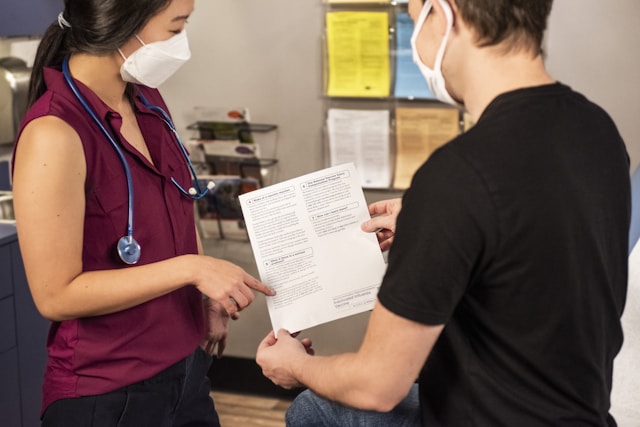
ケアマネージャー(介護支援専門員)の年収は、勤務する地域や経験、勤務形態、事業所の種類などによって大きく左右されます。ここでは、収入に関係する主なポイントを詳しく解説しています。
就職先やキャリア設計を考えるうえで、年収に影響する要素を理解しておくことが重要です。
- 地域・都道府県による年収差
- 経験年数・勤続年数が年収に与える影響
- 勤務形態(常勤・非常勤・パート)の違い
- 勤務先の事業所形態・規模による影響
- 資格・他資格保有が与える効果
- 役職・管理職ポジションの効果
- 勤務時間・シフト・残業による年収増減
①地域・都道府県による年収差
全国平均で見ると、ケアマネージャーの平均年収(賃金構造基本統計調査による所定内給与+賞与を含む水準)は約429.6万円です。ただし、都道府県によって賃金には大きな違いがあります。
東京・神奈川・大阪などの都市部では人材需要が高く、求人も多いため給与が上がりやすい傾向に。
一方で、地方では事業所の数が少なく、地域経済や介護報酬の影響から年収が低く抑えられることもあります。また、生活コストの違いも考慮する必要があるでしょう。
都市部は給与が高くても家賃や物価も高いことが多く、実質的な可処分所得は地方と大きく変わらない場合もあります。
勤務地を選ぶ際は、収入面だけでなく生活環境も含めてバランスよく判断することが大切です。
②経験年数・勤続年数が年収に与える影響
経験年数や勤続年数は、ケアマネージャーの年収を大きく左右する重要な要因です。キャリアを重ねることで専門性が高まり、基本給や役職手当が上がる傾向にあります。
特に、経験10年を超える中堅層では、平均より50万〜100万円ほど高い年収を得ているケースも少なくありません。また、同じ職場で長く勤めることで評価が安定し、賞与や昇給の機会も増えやすくなります。
主任ケアマネージャーなどの上位資格を取得すれば、さらに昇給幅が広がる可能性があるでしょう。短期間で転職を繰り返すよりも、着実に経験を積み重ねることで、年収面でも大きな差が生まれています。
③勤務形態(常勤・非常勤・パート)の違い
勤務形態も、年収に直結する要素のひとつです。常勤(正社員)で働く場合は、月給制や年俸制で安定した収入が得られ、賞与や各種手当も支給されるケースが多いです。
一方、非常勤やパート勤務は時給制が中心で、勤務時間によって収入が変動します。全体の約82.7%が正規雇用であり、残りはパートや契約社員です。
非常勤の場合、子育てや家庭の事情に合わせて柔軟に働ける利点がありますが、ボーナスや退職金がない場合も多く、長期的な収入安定にはやや不利でしょう。
働き方を選ぶ際は、収入の安定性とライフスタイルの両面から検討することが望ましいです。
④勤務先の事業所形態・規模による影響
勤務先の事業所形態や規模によっても、年収には差があります。
たとえば、居宅介護支援事業所では、利用者数や作成したケアプラン数に応じて手当が支給される場合があり、成果が収入に反映されやすい環境といえるでしょう。
一方で、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設勤務では、業務が安定している反面、昇給や歩合の幅は比較的狭い傾向にあります。
また、医療法人や社会福祉法人など大規模法人に勤める場合は、福利厚生や賞与制度が充実しており、トータルでみると年収が高くなるケースもあるでしょう。
事業所の規模や運営母体は、働く前にしっかり確認しておきたいポイントです。
⑤資格・他資格保有が与える効果
ケアマネージャーの仕事では、他の専門資格を併せ持つことで、収入アップにつながる可能性が高まります。
介護福祉士や看護師、社会福祉士などをすでに取得している場合、それらの知識やスキルを活かして利用者支援の質を高められるため、職場での評価が上がりやすいです。
また、事業所によっては資格手当が支給されることもあり、1つの資格にとどまらず複数の資格を組み合わせることで、基本給や手当額の上昇が見込めます。
スキルアップを目的に資格取得を続けることは、自身の市場価値を高める有効な方法でしょう。
⑥役職・管理職ポジションの効果
主任ケアマネージャーや管理職などの役職に就くことで、年収が大幅に上がることがあります。
主任介護支援専門員の資格は、ケアマネージャーとして5年以上の実務経験を積んだ人が取得できる上位資格です。この資格を持つことで、教育や指導の役割を担い、役職手当が加わるケースが一般的でしょう。
また、管理職クラスになると、スタッフ育成や事業所運営に携わることもあり、責任の大きさに見合う報酬が得られます。
キャリアアップを意識してスキルを磨き、実務経験を重ねることで、年収600万円以上を目指すことも可能です。
⑦勤務時間・シフト・残業による年収増減
ケアマネージャーは、基本的に日勤勤務が中心ですが、施設によっては夜間や休日の対応を求められる場合もあります。夜勤手当や残業手当がつくことで、年収が増えるケースも多いです。
特に、繁忙期や人員不足の時期には時間外勤務が発生しやすく、その分収入が上積みされます。ただし、残業が多すぎると心身の負担が大きくなり、ワークライフバランスを損なうおそれもあるでしょう。
収入だけでなく、働きやすさや健康面も重視することが大切です。自分に合った勤務時間と働き方を選ぶことで、長く続けられる職場環境を整えましょう。
ケアマネージャーに必要な資格

ケアマネージャー(介護支援専門員)として働くには、一定の資格と実務経験が欠かせません。ここでは、資格取得に関わる主要な国家資格を紹介します。
それぞれの資格の特徴を理解することで、自分に合ったキャリアパスを描きやすくなるでしょう。
- 介護支援専門員
- 介護福祉士
- 看護師
- 社会福祉士
- 保健師
①介護支援専門員
ケアマネージャーとして働くために、必ず必要なのが「介護支援専門員」の資格です。
都道府県が実施する国家資格であり、介護・医療・福祉分野で5年以上、かつ900日以上の実務経験を積んだ人が受験できます。
試験は「介護支援分野」「保健医療サービス分野」「福祉サービス分野」の3科目で構成され、合格後には「実務研修」を受講することが必須です。
研修を修了し、都道府県に登録することで、正式にケアマネージャーとして活動できるようになります。この資格がなければケアプランを作成できないため、まさにケアマネの中心的な資格といえるでしょう。
②介護福祉士
介護福祉士は、介護現場で利用者の生活を支援する国家資格です。介護支援専門員の受験資格を得るための代表的なルートとして、多くの人が取得しています。
現場での実務経験を積むことで、利用者の生活背景や介護の実情を深く理解できるため、ケアプラン作成においても現実的で実行可能な提案ができるようになります。
介護福祉士としての経験は信頼につながり、キャリアアップや年収向上にもプラスに働くでしょう。
③看護師
看護師資格を持つ人も、医療の知識と経験を生かしてケアマネージャーを目指せます。医療ニーズの高い利用者に対して、より的確な支援を提供できる点が強みです。
また、医師や多職種との連携も円滑に進められるため、医療と介護の架け橋として重要な存在になります。特に、医療系の事業所では看護師出身のケアマネが高く評価され、待遇面でも優遇される傾向があるでしょう。
④社会福祉士
社会福祉士は、福祉制度の知識を活かして利用者の生活を支援する国家資格です。福祉分野での実務経験があれば、介護支援専門員の受験資格を得ることができます。
社会福祉士は、制度や法律に精通しているため、行政や地域と連携した支援に強みがあるでしょう。特に、地域包括支援センターなどでの活躍が期待され、利用者や家族の幅広い相談に応えられる点が特徴です。
⑤保健師
保健師は、地域や職域で健康指導や予防医療に携わる専門職です。介護支援専門員の受験資格を持っており、地域包括支援センターなどでの配置も多く見られます。
医療知識と健康管理のスキルを活かし、介護予防や健康維持を支援できるのが強みです。利用者の身体面だけでなく、生活全体を見渡した支援ができるため、チームケアの中でも重要な役割を果たします。
ケアマネージャーが年収をアップさせる方法

ケアマネージャーとして働くなかで、「もっと収入を上げたい」「将来的に安定した生活を送りたい」と考える人は少なくありません。
ここでは、キャリアアップや資格取得、職場選びの工夫など、実際に年収を高めるために効果的な方法を紹介します。
自分の強みを活かし、着実にスキルを磨くことで、長期的なキャリアの安定と収入向上の両立が可能になるでしょう。
- 主任ケアマネージャーや管理職を目指す
- 介護福祉士や看護師などの資格を併用する
- 高待遇の職場・転職先を選ぶ
- 事業所を独立開業して収入を増やす
①主任ケアマネージャーや管理職を目指す
主任ケアマネージャーは、通常のケアマネージャーよりも高度な専門知識とマネジメント能力が求められるため、基本給や役職手当が高めに設定されています。
資格を取得するには、介護支援専門員として5年以上、かつ900日以上の実務経験を積む必要があります。
主任として認定されると、後輩ケアマネの育成や会議での助言など、リーダー的な役割を担うようになり、業務範囲が広がるでしょう。
また、管理職に昇進すれば、事業所運営や人材育成、経営的視点が求められる分、報酬も一段と高くなります。信頼と経験を積み重ね、責任ある立場を目指すことが、年収アップへの最短ルートといえるでしょう。
②介護福祉士や看護師などの資格を併用する
介護福祉士や看護師、社会福祉士などの資格を併せ持つと、担当できる業務の幅が広がり、職場での専門的な評価も高まります。
特に、看護師資格を持つケアマネージャーは、医療ケアを要する利用者の支援にも対応でき、医療機関や訪問看護ステーションなどで高待遇を得やすいです。
また、介護福祉士として現場の介助業務を兼任する場合、夜勤手当や処遇改善加算などの収入増加が見込めます。複数資格を持つことで、介護・医療・福祉の各分野を横断的に理解できる点も大きな強みです。
専門性を高めながらキャリアを多方面に展開することで、将来的に安定した収入基盤を築くことができるでしょう。
③高待遇の職場・転職先を選ぶ
同じケアマネージャーの資格を持っていても、勤務先によって年収には大きな違いが生じます。医療法人や社会福祉法人、または大手民間事業所では、給与や賞与の水準が比較的高い傾向があるでしょう。
特に、都市部では人材の需要が高く、地方よりも年収水準が上がるケースが多いです。
転職を検討する際は、基本給だけでなく、昇給制度・賞与実績・福利厚生・残業時間など、総合的な条件を確認することが大切でしょう。
また、企業の安定性や経営方針も、収入の継続性に関わる要素です。複数の求人を比較し、自分の価値を正しく評価してくれる職場を選ぶことが、結果的にキャリアアップと年収アップの両方につながります。
④事業所を独立開業して収入を増やす
ケアマネージャーは、一定の経験を積むことで自ら居宅介護支援事業所を設立し、独立開業することも可能です。
独立すれば、報酬体系や働き方を自分で設計できるため、利用者数や契約件数によって年収が大きく伸びる可能性があります。
ただし、開業には初期投資や人件費、事務手続きなどのリスクが伴うことも考えられるでしょう。安定的に運営するためには、地域のニーズ把握や介護事業者との連携、行政手続きへの理解が不可欠です。
さらに、利用者や家族との信頼関係を築くことが成功のカギとなります。経営知識を身につけ、事業計画を丁寧に立てたうえで挑戦すれば、自立した働き方と高収入の両立を実現できるでしょう。
ケアマネージャーの将来性と需要

ケアマネージャー(介護支援専門員)は、今後も高い需要が見込まれる安定した職業です。
日本の高齢化が進む中で、介護サービスを必要とする人が増え、専門的な支援を行うケアマネージャーの存在は、ますます欠かせなくなっています。
ここでは、将来性を支える3つの要素を具体的に紹介します。
- 高齢化社会の進展による需要拡大
- 介護報酬改定や処遇改善による影響
- AI・ICT導入による業務変化と今後の展望
①高齢化社会の進展による需要拡大
日本の高齢化率は上昇を続けており、2035年には人口の約3分の1が65歳以上になると予測されています。高齢化が進むほど介護サービスの需要が増し、それに伴ってケアマネージャーの必要性も高まります。
ケアマネージャーは、利用者一人ひとりに最適なケアプランを立て、医療機関や介護施設などと連携を取る重要な役割を担っています。
こうした専門職がいなければ介護サービスは成り立たないため、今後も安定した雇用が期待できるでしょう。
また、人材不足が続く介護業界では、資格を持つケアマネージャーの価値がさらに高まることが予想されます。
②介護報酬改定や処遇改善による影響
介護報酬は3年ごとに見直され、業界全体の待遇改善に影響を与えます。近年は、介護職員の給与を引き上げる「処遇改善加算」の導入が進み、ケアマネージャーもその恩恵を受けています。
主任ケアマネージャーなど、経験やスキルの高い人材に対しては報酬が上がる傾向にあり、今後も待遇改善は続くと考えられます。
一方で、制度改定によって一時的に事務負担が増えることもあるため、制度の流れを理解し、柔軟に対応できる力が求められています。社会の動向を意識して行動することが、キャリアアップの近道になるでしょう。
③AI・ICT導入による業務変化と今後の展望
AIやICTの活用が進み、ケアマネージャーの業務効率は大きく向上しています。
たとえば、ケアプラン作成支援ソフトや電子記録システムを活用することで、煩雑な事務作業が減り、利用者との面談や支援の質により多くの時間を割けるようになりました。
ただし、どれだけ技術が発展しても、利用者の気持ちに寄り添う力や、家族・医療職との調整能力は人にしかできません。
AIを補助的に使いながら、人間らしい判断と関係構築を行えるケアマネージャーこそ、今後さらに求められる存在になるでしょう。
技術を味方にしながら「人の心を理解できる専門職」として成長することが、将来性を高めるカギです。
ケアマネージャーの年収に関するよくある質問

ケアマネージャーの収入は、就職を考える学生や資格取得を目指す人にとって特に関心の高いテーマです。
ここでは、実際に現場で働く人やこれから目指す人から多く寄せられる3つの質問を取り上げ、収入アップの可能性や業界のリアルを具体的に紹介します。キャリアの方向性を考える際の参考にしてください。
- ケアマネージャーが年収1000万円を目指すことは可能?
- ケアマネージャーの昇給・ボーナス事情は?
- 男性と女性とで年収に差はある?
①ケアマネージャーが年収1,000万円を目指すことは可能?
一般的なケアマネージャーの平均年収は、およそ400万〜450万円程度ですが、条件や環境次第では年収1,000万円を目指すことも不可能ではありません。
そのためには、主任ケアマネージャーや施設管理者、事業所の運営責任者など、より高い責任と専門性を伴う立場にステップアップすることが求められます。
また、独立して居宅介護支援事業所を開業し、経営者として成功を収めるケースもあるでしょう。
自分の事業を持つことで、報酬の上限を大きく広げることが可能になりますが、経営スキルや地域とのネットワーク構築など、多面的な能力が必要です。
実際には、全体のごく一部がこの水準に到達しているのが現状で、まずは年収600万円前後を目指して、段階的にキャリアを積むことが現実的で着実な方法といえるでしょう。
②ケアマネージャーの昇給・ボーナス事情は?
ケアマネージャーの給与は、勤続年数、勤務先の規模、担当する業務内容などによって大きく左右されます。介護報酬の改定や処遇改善加算の影響もあり、ここ数年は賃金水準が徐々に上がる傾向にあるでしょう。
昇給は多くの事業所で年1回実施され、主任ケアマネージャーやリーダー職に昇格すると月給が数万円単位で上がることもあります。
また、ボーナス(賞与)は公務員系や社会福祉法人、大規模法人などでは年2回支給されるケースが多く、安定した年収を得やすいのが特徴です。
一方で、民間の小規模事業所では経営状況によって、支給額が変動する場合もあります。転職や就職を検討する際には、基本給だけでなく賞与実績・昇給制度・福利厚生などを事前に確認しておくと安心です。
こうした情報をしっかり比較することで、長期的に安定した収入アップを実現できるでしょう。
③男性と女性とで年収に差はある?
ケアマネージャーの仕事は、性別に関係なく専門性と成果で評価される職種です。しかし統計上では、わずかに男性の平均年収が高い傾向にあります。
これは、男性が管理職や施設運営など、責任の大きい役職に就く割合が比較的高いためと考えられています。
一方で、女性のケアマネージャーも、主任ケアマネージャー資格の取得やマネジメントスキルの向上によって、収入を大きく伸ばすことが可能です。
特に、女性はコミュニケーション力や調整力を強みに評価されることが多く、職場によってはリーダー職として活躍する例も増えています。
大切なのは、性別ではなく「経験」「実績」「資格」による評価が中心である点です。地道にスキルを積み重ねていけば、男女問わず安定した高収入を得られるでしょう。
ケアマネージャーのキャリアと年収を総合的に理解しよう

ケアマネージャー(介護支援専門員)は、介護現場の中心的な役割を担う専門職です。
仕事内容や勤務先、必要な資格、そして気になる年収事情を理解することは、将来のキャリアを考えるうえで欠かせません。
結論として、ケアマネージャーの年収は勤務先や経験年数、資格の有無によって大きく変動しますが、主任ケアマネージャーや管理職への昇進、または独立開業などで収入アップを実現できる可能性があります。
ケアマネージャーを目指すなら、まず資格取得を目標にしながら、経験を重ねてステップアップを図ることが安定した高収入への近道です。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。














