学童保育の仕事内容を徹底解説!給料・資格・働く魅力とは
「学童保育って、具体的にどんな仕事をするの?」
子どもの放課後を安心して過ごせるよう支える学童保育は、保護者からも地域からも必要とされる存在です。しかし、仕事内容や給料、資格などについては意外と知られていません。
そこで本記事では、学童保育の仕事内容を中心に、役割や給料、必要な資格から働く魅力までを徹底解説します。
業界研究のお助けツール
- 1自分に合う業界がわかる分析大全
- 主要な業界の特徴と働き方を一目でつかみ、あなたに合った業界選びをスムーズに進められます。
- 2適職診断
- 60秒で診断!あなたの特性に合った職種がわかり、業界選びに納得感が増します
- 3志望動機テンプレシート
- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作れる
- 4ES自動作成ツール
- AIが【志望動機・自己PR・ガクチカ・長所・短所】を全てを自動で作成
- 5実際の面接で使われた質問集100選
- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。
学童保育とは?役割と目的をわかりやすく解説

学童保育は、小学校低学年の子どもを放課後に安全に預かる仕組みで、共働き世帯の増加により需要が高まっています。
就活生にとっては「具体的にどのような役割を担うのか」「どんな基準や料金で運営されているのか」が分からない点が不安になりやすい部分でしょう。
ここでは役割や対象年齢、運営基準や利用条件を整理し、学童保育という仕事の全体像を理解できるように解説します。
- 学童保育の役割
- 学童保育の対象年齢
- 学童保育の運営基準
- 学童保育の利用時間
- 学童保育の利用料金
①学童保育の役割
学童保育の大きな役割は、放課後の子どもを安全に見守りながら成長を支えることです。とくに共働きやひとり親家庭では、安心して預けられる居場所があるかどうかは生活の安定に直結します。
学習や遊びをただ管理するのではなく、子ども同士の関わりを通じて協調性や社会性を育てる場でもあります。
単に宿題を済ませる場所と考えるのは早計で、実際には地域の教育力を支える社会的な役割を担っているのです。指導員は安全管理だけでなく、子どもの心に寄り添う姿勢が求められるでしょう。
②学童保育の対象年齢
対象となるのは主に小学校1〜3年生ですが、自治体や施設によっては6年生まで利用可能な場合もあります。低学年の子どもは放課後を一人で過ごすのが難しく、学童保育の存在は特に重要です。
一方で、高学年まで受け入れる施設では、年齢差から生まれる人間関係や学習のサポートに工夫が必要となります。就活生が働く場を選ぶ際には、どの年齢層と関わることになるのかを確認することが大切です。
自分に合った対象年齢層を見極めることが、長く働くための手がかりになるでしょう。
③学童保育の運営基準
学童保育は厚生労働省が定める基準に沿って運営されています。子どもの人数に応じた指導員の配置や施設の広さ、安全確保のルールなどが決められています。
例えば、40人につき2人以上の指導員を配置するのが一般的です。こうした基準により、一人ひとりの子どもに適切なサポートを届けられる環境が守られています。
ただし実際には、自治体ごとの事情で人員不足や施設の狭さが課題になることも珍しくありません。就職先を考える際には、基準が守られているかを確認しておくと安心できるでしょう。
④学童保育の利用時間
一般的な利用時間は放課後から18時ごろまでですが、19時や20時まで延長される施設もあります。
さらに夏休みや冬休みなどの長期休暇には午前から開所し、1日を通して子どもを受け入れるケースも少なくありません。
利用時間が長くなると指導員にかかる負担も増えるため、体力や勤務環境の理解が必要です。
就活生のうちに「夕方以降や長期休暇の勤務に対応できるかどうか」を考えておくと、入職後にギャップを感じにくいでしょう。
⑤学童保育の利用料金
利用料金は自治体や運営形態によって異なります。公立では月額5,000〜10,000円程度が目安で、比較的安価に利用できる場合が多いです。
一方、私立では20,000円を超えることもあり、サービス内容や環境によって幅があります。料金にはおやつ代や教材費が含まれるケースもあり、家庭の経済状況に応じた選択が行われています。
料金設定は利用者層や施設の運営体制に直結するため、就活生にとっても働く環境を理解する重要な指標になるでしょう。
学童保育の種類|公立と私立の違い

学童保育には大きく分けて公立と私立の2種類があります。どちらも子どもを安全に預かるという目的は共通していますが、運営主体や料金、サービス内容に違いがあります。
就活生にとっては働く環境や待遇に直結するため、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。ここでは公立と私立の学童保育の特徴を紹介します。
- 公立学童保育の特徴
- 私立学童保育の特徴
①公立学童保育の特徴
公立学童保育は市区町村などの自治体が運営しています。特徴は利用料金が安めで、保護者の経済的な負担が少ないことです。
その一方で職員数や設備は最低限にとどまることが多く、指導員が担う日々の業務は幅広くなります。例えば、子どもの見守りや行事の準備、安全管理、保護者対応などです。
安定感があるとはいえ公務員としての待遇ではなく、繁忙感を覚える場面もあるでしょう。ただし自治体に雇用されるため、一定の労働条件は守られやすい環境といえます。
働きがいと同時に忙しさも理解したうえで選ぶことが必要です。
②私立学童保育の特徴
私立学童保育はNPO法人や企業、教育関連事業者などが運営していて、利用料金は公立より高めですが、サービスが充実しているケースが多く、学習支援や習い事、特色あるプログラムを提供している施設もあります。
職場環境は運営母体によって大きく異なり、給与や勤務時間にも幅があるため、応募前に条件を確認することが欠かせません。
民間ならではの柔軟さがあり、新しい取り組みに挑戦できる場面も多く、キャリア形成につながる可能性も広がります。
安定を重視するか、成長の機会を優先するかを考えることが、就活生にとって重要な判断材料となるでしょう。
学童保育指導員の給料・待遇

学童保育指導員の給料や待遇は、就職を考えるうえで多くの人が気になる点でしょう。月給はおおよそ15万〜20万円で、保育士や教員と比べると低めの水準です。
パートやアルバイトでは時給1,000円前後が多く、地域や運営形態によって違いが見られます。
数字だけを見ると生活が安定しにくいと感じるかもしれませんが、近年は共働き家庭の増加で需要が高まり、自治体によっては処遇改善手当や研修制度が導入される例もあります。
待遇面では社会保険や交通費の支給といった最低限の保障があり、私立では福利厚生がより手厚いケースも少なくありません。
求人を見る際には給与だけに注目せず、手当や勤務環境も含めて総合的に判断してください。
企業分析をやらなくては行けないのはわかっているけど、「やり方がわからない」「ちょっとめんどくさい」と感じている方は、企業・業界分析シートの活用がおすすめです。
やるべきことが明確になっており、シートの項目ごとに調査していけば企業分析が完了します!無料ダウンロードができるので、受け取っておいて損はありませんよ。
学童保育指導員の仕事内容

学童保育指導員の仕事は、子どもの安全を守りながら成長を支えることです。ただ実際の内容は幅広く、就活生には分かりにくいかもしれません。
ここでは代表的な業務を具体的に紹介します。
- 環境整備
- 子どもの迎え入れ
- 遊びや学習の見守り
- おやつの準備、提供
- 行事の準備と実施
- 保護者対応
- 記録業務
①環境整備
指導員の大切な役割は、子どもが安心して過ごせる環境を整えることです。机やいすの配置、安全点検、教材や遊具の準備などを行い、事故を防ぐ体制をつくります。
環境が整っていなければ子どもは落ち着いて活動できません。日々の地道な整備によって集中できる空間が生まれるのです。表には出にくい作業ですが、子どもを思う気持ちが欠かせない業務でしょう。
②子どもの迎え入れ
放課後に子どもを受け入れるとき、指導員は笑顔で迎えることが大切です。挨拶を通して安心感を与え、その日の体調や気分を確認します。
学校での出来事に耳を傾けることも信頼関係につながります。短い時間ですが、子どもが安心して過ごせるかを左右する重要な瞬間といえるでしょう。
③遊びや学習の見守り
学童保育では自由遊びや宿題の時間があるため、指導員は安全を見守り、必要に応じてアドバイスや仲裁を行います。ときには小さなトラブルを防ぐ役目も果たすでしょう。
遊びや学習を通じて子ども同士の関係が深まるため、観察力と臨機応変な対応力が求められる仕事です。
④おやつの準備、提供
おやつは子どもにとって楽しみのひとつです。指導員はアレルギーに配慮しながら準備し、衛生面にも注意して提供します。
ただ食べるだけの時間ではなく、マナーや集団での過ごし方を学ぶ機会にもなるのです。安心して過ごせる楽しい時間にすることで、子どもとの関係が一層深まるでしょう。
⑤行事の準備と実施
学童保育では季節ごとのイベントや特別活動が行われ、指導員は企画から準備、当日の運営までを担います。子どもが主体的に参加できるよう工夫し、達成感を得られる場をつくることが役割です。
準備には手間がかかりますが、行事を通じて見える子どもの成長は大きなやりがいにつながります。
⑥保護者対応
指導員にとって保護者との連携も欠かせない仕事です。日々の様子を伝えたり、相談に応じたりすることで信頼を築きます。
要望や不満を受けることもありますが、誠実に対応することで関係性が深まります。家庭と学童をつなぐ存在としての責任は大きいですが、やりがいのある業務でもあります。
⑦記録業務
指導員は毎日、子どもの出欠や体調、活動の様子を記録します。記録はトラブルが起きた際の証拠となり、保護者や学校、行政と連携するときにも役立ちます。
手間に感じることもありますが、正確な記録が信頼される学童保育を支えているのです。丁寧な積み重ねが重要といえるでしょう。
学童保育で活かせる資格

学童保育で働くとき、資格の有無は大きなポイントになります。必ずしも資格が必要なわけではありませんが、持っていると採用や待遇で有利になる場合があります。
ここでは代表的な資格を取り上げ、それぞれの特徴を説明します。
- 放課後児童支援員
- 保育士
- 社会福祉士
- 教員免許
①放課後児童支援員
学童保育にもっとも直結する資格が放課後児童支援員です。2015年に制度化され、学童に必要な専門人材を育てる目的で作られました。
所定の研修を受けることで取得でき、現場の中心的な役割を担います。資格があると採用で有利になり、処遇改善手当の対象になることもあります。
学童で働きたい就活生にとって、実践的で安心感のある資格といえるでしょう。
②保育士
保育士資格も学童で活かせます。本来は乳幼児を対象とした国家資格ですが、子どもの発達理解や生活支援の力が評価されるのです。。
学童は小学生が中心のため直接的に必要となる場面は少ないものの、安全管理や子どもへの対応で役立つ場面は多く、資格を持っていれば就職やキャリア形成でプラスになるでしょう。
③社会福祉士
社会福祉士は福祉分野の国家資格で、困難を抱える家庭や子どもの支援に強みを持ちます。学童では保護者との連携や家庭環境への配慮が必要になるため、福祉の視点は大きな力となります。
必須とされることは少ないですが、保護者対応や地域との協力で役立つでしょう。将来福祉分野で幅広く働きたい人にも有効な資格です。
④教員免許
教員免許は学校教育で使う資格ですが、学童でも子どもの学習支援や生活指導に活かせます。宿題の見守りや勉強のサポートで知識を発揮できるため、現場で重宝されるでしょう。
さらに、学校や塾など幅広い分野で働ける選択肢が広がる点も魅力です。資格の有無で差が出やすいため、取得しておくと心強いといえます。
学童保育で働くメリット
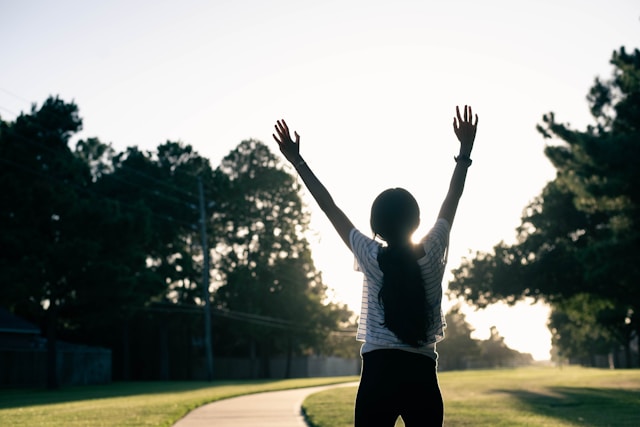
学童保育で働くことには、就活生にとって多くの魅力があります。やりがいを感じられるだけでなく、キャリア形成や安定性にもつながる点が特徴です。
ここでは代表的なメリットを4つ紹介します。
- 子どもの成長を支えられる
- 多様な経験やスキルを積める
- 地域社会に貢献できる
- 需要が高まり安定している
①子どもの成長を支えられる
学童保育の魅力は、子どもの成長を間近で見守れることです。宿題を手伝ったり遊びを通じて支えたりする中で、自信をつけていく姿に出会えます。
保護者から感謝の言葉をもらえる場面も多く、社会に役立っている実感を得られるでしょう。子どもと一緒に過ごすことで得られる喜びは、この仕事ならではです。
②多様な経験やスキルを積める
現場では遊びや学習の見守り、保護者対応、行事の企画など幅広い業務があります。そのため自然とコミュニケーション力や企画力、危機管理能力が身につきます。
これらの力は教育や福祉だけでなく、一般企業でも評価されやすいです。将来のキャリア形成に役立つ点は大きな魅力といえるでしょう。
③地域社会に貢献できる
学童保育は地域の子どもを支える存在であり、地域社会への貢献度が高い仕事です。保護者が安心して働ける環境をつくることで、地域全体の生活を支えることにもつながります。
自分の仕事が地域にとって必要とされていると実感できるのは、大きなやりがいになるでしょう。
④需要が高まり安定している
共働き家庭の増加により、学童保育の需要は年々高まっています。施設数は増え、人材確保の取り組みも進んでおり、今後も安定した働き口が期待できるでしょう。
長期的に働きたい人にとっても安心感があり、将来を見据えてキャリアを築きやすい仕事といえます。
学童保育で働くデメリット

学童保育はやりがいのある仕事ですが、実際にはデメリットも存在します。待遇や働き方に関する課題を知っておくことは、就職後のギャップを防ぐうえで大切です。
ここでは代表的なデメリットを4つ紹介します。
- 給料が低く生活が安定しにくい
- 勤務時間が不規則で長くなりやすい
- 体力的な負担が大きい
- 保護者対応で精神的に疲れる
①給料が低く生活が安定しにくい
学童保育の給与水準は、保育士や教員に比べて低めです。正社員でも月給15万〜20万円程度が多く、パートやアルバイトは時給1,000円前後にとどまることがあります。
そのため生活費や貯蓄を考えると不安を感じる人もいるでしょう。安定を重視するなら、福利厚生や手当が整った運営母体を選ぶことが必要です。
②勤務時間が不規則で長くなりやすい
学童保育は放課後や長期休暇に子どもを預かるため、勤務時間が不規則になりがちです。特に夏休みなどは朝から夕方まで勤務が続き、労働時間が長くなる場合があります。
働き方と生活リズムが合わず負担を感じることもあるでしょう。求人を探すときは勤務体制を必ず確認してください。
③体力的な負担が大きい
子どもと外で遊んだり安全を見守ったりする場面が多く、体力を使います。複数の子どもを相手にするため、常に注意を払う必要があり集中力も欠かせません。
若いうちは問題なくても、長期的に働くと負担を感じることもあります。日頃から体調管理に気を配ることが大切でしょう。
④保護者対応で精神的に疲れる
学童保育では子どもだけでなく保護者との関わりも重要です。しかし要望や相談の中には難しい内容もあり、精神的に疲れてしまうことがあります。
ときには意見が合わず板挟みになることもあるでしょう。こうした場面では冷静に対応できる力と気持ちの切り替えが求められます。
学童保育に向いている人の特徴

学童保育で働くには、子どもと接するだけでなく柔軟な対応力も欠かせません。
ここでは学童保育に向いている人の特徴を5つ紹介します。自分がこの仕事に合っているかを確認する参考にしてください。
- 子どもが好きで寄り添える人
- コミュニケーション能力がある人
- 体力と忍耐力に自信がある人
- 安全管理に気を配れる人
- 臨機応変に行動できる人
「自分の強みが分からない…本当にこの強みで良いのだろうか…」と、自分らしい強みが見つからず不安な方もいますよね。
そんな方はまず、就活マガジンが用意している強み診断をまずは受けてみましょう!3分であなたらしい強みが見つかり、就活にもっと自信を持って臨めるようになりますよ。
①子どもが好きで寄り添える人
子どもが好きで気持ちに寄り添える人は学童保育に向いています。宿題や遊びを通じて関わる中で、子どもが安心して過ごせる環境をつくることが重要です。
ただ「好き」という気持ちだけでなく、子どもの声に耳を傾け行動できる姿勢が求められるでしょう。
②コミュニケーション能力がある人
学童保育では子どもだけでなく保護者や同僚との連携も必要です。意見を伝えたり相談を受けたりする場面が多いため、相手に合わせて分かりやすく話せる力が役立ちます。
聞く姿勢を大切にし、信頼を築ける人が向いているでしょう。
③体力と忍耐力に自信がある人
体力と忍耐力に自信がある人は、長く安定して働けるでしょう。
子どもと外で遊んだり安全を見守ったりするには体力が欠かせません。さらに同じ注意を繰り返すなど根気強さも必要です。
④安全管理に気を配れる人
細やかな気配りができる人は大きな信頼を得られるでしょう。
学童保育ではケガや事故を防ぐため、常に安全に注意する必要があります。子どもの行動を予測して危険を回避し、環境を整える力が重要です。
⑤臨機応変に行動できる人
変化に前向きに取り組める人にとって、この仕事はやりがいにつながるでしょう。
学童保育では予定通りに進まないことも多く、柔軟な対応が求められるのです。急な体調不良や保護者からの要望など、予想外の事態でも落ち着いて行動できる人は現場で重宝されます。
学童保育で働くには

学童保育で働くには、自治体や民間団体が運営する施設へ応募するのが一般的です。求人はハローワークや自治体の募集ページ、民間の採用サイトなどで見つけられます。
資格が必要とされる場合もありますが、無資格で応募できる施設もあり、研修を受けながら学べる道もあるのです。
特に放課後児童支援員や保育士、教員免許を持っていると採用で有利になり、待遇の面でも良い影響があるでしょう。
一方で勤務時間は放課後や長期休暇が中心となるため、生活リズムとの相性を考える必要があります。学童保育は子どもと深く関わり、成長を支えるやりがいの大きな仕事です。
応募するときは給与や条件だけを重視せず、施設の方針や雰囲気も確認して、自分に合った環境を選んでください。
学童保育のキャリアパス

学童保育で働いた経験は、その後のキャリアにもつながります。指導員としてのスキルを高めるだけでなく、資格や経験を活かして進路を広げられるのが特徴です。
ここではキャリアアップや資格を生かした道、他職種への転職について紹介します。
- 学童保育指導員としてのキャリアアップ
- 保育士や教員免許などの関連資格を活かしたキャリア形成
- 学童保育から他職種への転職
①学童保育指導員としてのキャリアアップ
学童保育で経験を積むと、主任指導員や施設長などの役職に進めます。リーダーとして現場をまとめる力が求められ、待遇が改善されることもあるでしょう。
ただし、人材不足の施設では業務が増え、責任も重くなる可能性があります。キャリアアップを目指すなら、自分の得意分野を活かせる職場を選ぶことが大切でしょう。
②保育士や教員免許などの関連資格を活かしたキャリア形成
保育士や教員免許を持っていれば、学童での経験をもとに保育園や学校へ進む道も開けます。保育士資格は幼児への対応力が評価され、教員免許は学習支援で役立つのです。
学童での実務経験と資格を組み合わせることで、将来の選択肢は広がります。資格がない人も、働きながら取得を目指すことが有効です。
③学童保育から他職種への転職
学童保育で得られる力は教育や福祉にとどまりません。子どもを支える中で培ったコミュニケーション力や安全意識は、企業の人材育成や接客でも活かせます。
保護者対応を通じて磨かれる調整力や傾聴力も強みになるのです。学童での経験は転職活動でも評価されやすく、キャリアの幅を広げるきっかけになるでしょう。
学童保育の仕事を通じて得られる可能性

学童保育の仕事内容は、子どもの生活を支えながら成長を見守る大切な役割です。対象年齢や運営基準、利用時間や料金といった制度面の理解に加え、公立と私立の違いを知ることは働く場を選ぶうえで重要です。
さらに指導員としての仕事内容は環境整備から保護者対応まで幅広く、給料や待遇を含めて現実的な側面も把握する必要があります。
そのうえで資格取得やキャリアパスを考えることで、自分に合った働き方が見えてくるでしょう。
子どもの成長を支えるやりがいと、多様なスキルを積めるメリットがある一方で、給料や勤務環境に課題がある点も事実です。
だからこそ、自身の強みや適性を見極めることが長く活躍するための第一歩になります。
まずは志望動機を作ってみる

この記事を書いた人
編集部
「就活に苦しむ学生を減らしたい」をモットーに、志望動機やES、面接対策など、多種多様な就活の困りごとを解決するための記事を日々発信。700以上の記事で就活生の悩みに対処しつつ、就活の専門家であるキャリアアドバイザーの監修により、最後まで内定を狙える就活の方法を伝授し続けています。













